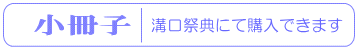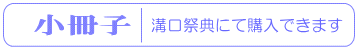【こすもすセミナー特別講演】
光に向かって歩む
ー いのちの真実を伝える希望のメッセージ ー
武 本 昌 三
人身受け難し今すでに受く
仏法聴き難し今すでに聴く
この身今生に向かって度せずんば
更にいずれの生に向かってかこの身を度せん
ー (仏教)礼拝文より ー
は じ め に
今年の三月十一日にNHKの教育テレビで「臨死体験・人は死ぬとき何を見るのか」という八十分の番組が放送されました。これは、臨死体験に興味をもっていた評論家の立花隆さんが、NHKの協力で一年もかけて、日本各地はもとより、アメリカ、カナダ、イタリア、インド等にいたるまで広く取材して作り上げた大型ドキュメンタリー番組の再放送です。
この番組が「NHKスペシャル」として初めて放送されたのは、一九九一年三月十七日のことでした。そのときには非常に好評で、その翌日から続けられた「臨死体験を探る」という番組とあわせますと、視聴率から計算して、二千万人を超える人々がこれらの番組を見たことになるのだそうです。
日本では長い間、臨死体験などというのは、オカルトめいた幻想のたぐいのように受け取られて、まともに取り上げられない傾向が続いてきました。しかし、アメリカやヨーロッパの国々では、一九七〇年代から心理学者、精神・神経医、脳生理学者、文化人類学者等の間で臨死体験の学問的研究が盛んになり、臨死体験研究国際会議まで開かれていることは、前回の小冊子のなかでも触れておきました。生と死に関する大切な問題であるだけに、日本でもこうして、NHKが大きく立花さんの取材をとりあげ、日本中の六人に一人がこういう番組を見るようになったということは大変意義のあることだと思われます。
私もこの「こすもすセミナー」で、このような欧米の学者の研究を紹介しながら、生と死の問題についてお話をしてきました。「人間のいのちというのは生きている間だけがいのちであって、死んでしまえば焼かれて灰になり、それですべてが終わってしまう」というのと、「実は人間のいのちというのは永遠で死んでも死なない、形を変えていつまでも生きていく」というのとでは、大変な違いです。本当に、どちらが真実なのでしょうか。「死んでも死なない」などというのは、荒唐無稽な絵空事でしょうか。たとえば、仏教では死後の世界に「極楽」というところがある、などと教えますが、それは本当でしょうか。
今年の三月の上旬に、前回の小冊子でご紹介しました大谷さんの一周忌法要が大田区の称名寺というところであって、私も出席させていただきました。そのお寺は浄土宗で、その日も『仏説阿弥陀経』というお経がよまれました。
「仏説」というのは、文字通り、仏様のお説きになった、という意味です。「如是我聞一時仏在舎衛国・・・」という書き出しで、「ある時尊き師である釈尊は、千二百五十人もの多くの修行者とともに舎衛国の祇園精舎に滞在しておられた。その時に釈尊は、長老の舎利弗に言われた」というふうにこのお経は始まります。それからが、釈尊御自身のことばです。その内容をいまのことばでごく簡単にわかりやすくまとめますと、だいたい次のようになると思います。
ここから西方に十万億の仏の国を過ぎたところに、極楽という名の世界がある。その世界には、限りない命と光をもった阿弥陀仏が住んでおり、いま現に教えを説いておられる。
その世界に住む者たちには、体の苦しみも心の悩みもなく、ただ幸せがあるだけだ。その世界には、七重の石垣、七重の並木があり、それらは、金、銀、水晶等の宝石で飾られている。また、宝石から出来ている池があり、池の底には一面の金の砂が敷き詰められている。階段の上には御殿があって、七種類の宝石で飾られ、池の中には、車の車輪ほどもある大きい蓮の花が美しく咲いている。
その世界では、常にすぐれた音楽が演奏されている。大地は黄金でできていて、昼、夜に三度ずつ、曼陀羅の花が降ってくる。白鳥、クジャク、オウム等、色とりどりの美しい鳥たちも、昼、夜に三度ずつ、優しい声で鳴く。そよ風が気持ちよく吹き渡り、宝石で飾られた並木を揺り動かして、美しい音が流れている。その美しい音は、あたかも百千種類の音楽を同時に演奏しているようである。
生きている者は、わたしの教えを聞くならば、この世界に生まれたいと願いをたてるべきである。わたしがいま、阿弥陀仏のすぐれた徳をたたえているように、東西南北上下の世界でも、数多くの仏たちがおられて、それぞれの国で、三千大千世界を長い舌で覆い、教えが真実であることを証明しながら、こういわれているのだ。「世の生ける者たちよ、そなたたちは今こそこの阿弥陀仏のすぐれた徳をたたえ、すべての仏によって護られているこのお経の教えを信じなさい」と。
このなかの「三千大千世界を長い舌で覆い」というのは、釈尊の説法が嘘ではないことを示す言い方です。釈尊の三十二ある身体的徳著の一つで、その舌の大きいことは、顔面を覆うほどであるといわれます。舌が鼻を覆えば、その説くことばに偽りがないと考える風習がインドではあったのです。
私たちは、葬儀や法事などで、しばしばこういうお経が読まれているのを聞いているわけですが、釈尊が「嘘ではない、嘘ではない」と繰り返し繰り返し言われている仏教の教えをどのように受け止めているでしょうか。夢物語のように聞き流していることはないでしょうか。これから、この小冊子でも、いろいろと霊界からのメッセージなどを取り上げますが、そのなかにも、 例えば、霊界とはどういうところか、つぎのように描いているものもあります。
こちらには、この上もない美の世界がある。光が隅々までゆきわたり、あらゆるものに光がみなぎっている。建物は、たいてい美しい大理石のような材料でできており、塵やほこりはないから、どこもきれいで新しい。自然のままの優雅な田園もある。土は独特の黄金色で燦然と七色にきらめき、あたり一面には神秘的で華麗な色彩がある。空は無数の虹がかかったようにほんのりと明るく、湖は生命力と美に輝いている。美しい樹木や灌木や藪や牧草地があり、花々は地球では想像できないほど美しい。①
私はまだ勉強も不十分ですし信仰も足りませんから、こういうメッセージを「嘘ではない、嘘ではない」と声高に皆さんにお伝えする資格はありませんが、それでも、ここではできるだけあやふやな資料や引用は避けるように心がけながら、改めて生と死の問題を取り上げ、皆さんと一緒に考えていくことにしたいと思います。
一 臨死体験のなかの体外離脱
ターミナル・ケアの世界的権威として知られているエリザベス・キュブラー・ロス博士は、かって、癌にかかって死んでいく子供に、つぎのように書き送ったことがありました。
地球に生まれてきて、あたえられた宿題をぜんぶすませたら、もう、からだをぬぎ捨ててもいいのよ。からだはそこから蝶が飛び立つさなぎみたいに、たましいをつつんでいる殻なの。ときがきたら、からだを手ばなしてもいいわ。そしたら、痛さからも、怖さや心配からも自由になるの。神さまのお家に帰っていく、とてもきれいな蝶のように自由に・・・・。②
これは、死んでいく子供に対する単なる慰めではないでしょう。博士の長年の医者としての研究と臨死体験や体外離脱を含むさまざまな経験から生み出された確固たる信念で、死とは何かを、わかりやすく、あたたかく伝えようとしているのだと思います。私たちの肉体というのは、実は、さなぎであるにすぎない。そのさなぎのなかにある本当の自分、すなわち「蝶」は不滅で、永遠の生命をもっている。だから、人間というのは死ぬとき、さなぎから抜け出た蝶のように、自由になれるのである、というのがロス博士の考え方です。
さなぎから抜け出た蝶が、自分の抜け殻であるさなぎを見ることができるであろうことは、誰も疑いません。それなら私たちも、肉体が単なるさなぎであって、本当の自分はそこから抜け出た蝶であるとすると、抜け出た瞬間、つまり死んだときに、私たちは、外から、私たち自身の肉体が見えなければならないことになります。つまり私たちは、「自由になったとき」に体外離脱するか、ということですが、これは、肉体と私たちのいのちとは別であることを考える重要なポイントになりますので、まず、そのことを「実例」について見ていくことにしましょう。
立花隆さんがアメリカのコネチカット州で直接インタビューしたアラン・サリバンという五十九歳の男性がいました。サリバンさんは、心筋梗塞の発作を起こしてハート・フォードの救急病院にかつぎ込まれ、緊急手術を受けたのですが、そのときに体外離脱して、自分が手術されているところを天井のほうから見ていたというのです。サリバンさんの手術をしたのは、日本人でもう二十年もその病院で外科医をしていた高田祐司博士でした。サリバンさんの体外離脱を確かめるために、立花さんは高田博士の了解を得たうえで、サリバンさんと一緒に病院へ会いに行きました。退院後はじめて高田博士に会ったサリバンさんは、手術のときの様子をつぎのように語り始めました。③
わたしがまず何よりびっくりしたのは、沢山の人がわたしの体を取りかこんでいたことです。五人くらいいたと思います。そして、そのうち二人が、熱心にわたしの脚を手術していました。わたしは、悪いところは心臓とばかり思っていたので、これにはびっくりしました。あの医者はいったい何をやっているのだろうと不思議に思いました。高田先生はわたしの頭の方にいました。その両脇に医者と看護婦が一人ずついて、それから、わたしの頭のところに大きな白い帽子をかぶった看護婦がいて、先生以外に全部で五人いました。
この場面はNHKテレビにも出ましたので、ごらんになった方もおられるかもしれません。サリバンさんの言ったことは正確でした。特に心臓の手術をするのだと思っていたら、熱心に自分の脚を手術しているのを見てサリバンさんは驚いたのですが、これも確かめてみるとその通りでした。
サリバンさんの心臓は冠動脈が動脈硬化を起こし心筋梗塞をもたらしていたので、冠動脈のバイパスを作る必要がありました。そのバイパス用の血管は普通、脚の血管を切って利用するのだそうです。ですから、心臓の手術にかかる前に、脚を切開して、その血管をいつでも切り取れるようにむき出しにしておく必要があります。脚のところにいた二人の医師は、その作業をやっていたのでした。こういうことは、かなり心臓手術に通じている人でなければわからないことです。「もしサリバンさんが本当に見ていなかったとすれば、なぜサリバンさんが二人の医師が自分の脚の手術をしていたことを知ったのか不思議です」と立花さんも述べています。サリバンさんの話はまだ続きます。
上から見ると、私の目のところが、何かよくわからないもので覆われていました。あれはいったい何だったのですか。それからもうひとつ驚いたのは、みんながブーツをはいていたことです。なんでブーツをはいているんだろうといぶかしく思いました。
高田博士の説明では、患者の目を万が一にも誤って傷つけることがないように、患者の目を閉じさせ、その上に卵形のアイパッチをのせ、それをテープで固定してしまうのだそうです。だから、たとえ患者が手術中に意識を取り戻して目を開いたとしても、患者は何も見えないことになります。体外離脱の解釈で、麻酔が途中で弱くなって、患者が薄く意識を取り戻した状態で、薄目を開けて外を見ていたのではないかという説もありますが、サリバンさんの場合は、目を覆われていますから、それも不可能な状態でした。
ブーツについても、確かにそのとき高田博士以外のスタッフはみんなブーツをはいていました。そのブーツは導電性の物質でできていて、衣服に生じた静電気などの電気をアースするためにはくのだそうです。昔は、麻酔薬のエーテルなど、電気火花で爆発の恐れがある物質が手術室にあったので、そういうブーツをはくようになりました。しかし、最近はそういう危険な物質がなくなったといいます。それでも、昔からの習慣でいまでもみんなブーツをはいているのだそうです。
それから高田先生は、手を胸の前に組んで、肘を左右に突きだすような格好をしていました。
その姿勢のまま、肘の先で何かを指し示しながらいろんな指示をくだすので、まるで、両肘が鳥の翼のように見えました。鳥が翼をバタバタ動かしているようでした。それで私は、おやおやこの人はこれからどこかに飛んでいこうとしているのだろうかと思いました。それから高田先生は、黒い重そうな眼鏡をしておられましたね。そのとき以外眼鏡をしておられるのを見たことがないので、変だなと思っているんですが。
手術中の医師が、「手を胸の前に組んで、肘を左右に突き出すような格好」をしていた、というような高田博士の姿は、その場に居合わせたものにしか見えないことで、高田博士自身も自分のことは覚えていなかったかもしれません。しかし、これも、その会見に立ち会っていた同僚の医師が、それは高田医師のクセだと証言してくれました。手術前には両手は必ず丹念に殺菌します。殺菌してある両手を、また何かにふれさせると、細菌がついてしまうおそれがあります。それを避けるために、高田博士は、何かを指図するようなときにも、肘を手の代わりに使っていたのだそうです。
「黒い重そうな眼鏡」もその通りでした。普段は眼鏡をかけていない高田博士も、手術のときだけは、特別の拡大鏡がついた眼鏡を着用していたのです。サリバンさんはさらに、こう言いました。
私の胸が切り開かれ、心臓が見えていました。こういう大手術のときに血が大量に流れるのかと思っていたら、ほとんど流れないのでビックリしました。そして、心臓は血で赤いのかと 思ったら、白っぽい紫色で血の気がぜんぜんないのにも驚かされました。
現場を見た人でなければわからない、手術の内部に深く立ち入った観察ですが、それまでは手術の経験がなかったサリバンさんにとっては、血が大量に流れなかったのが不思議であったのでしょう。しかし、高田博士の説明では、そのときのサリバンさんの血液の循環は、すべて人工心肺装置がおこなっていて、手術中の心臓にはまったく血液がきていなかったのだそうです。だから、心臓の色も、白っぽい紫色をしていたということでした。
かつて自分が手術をした患者から、患者の立場では決してわかるはずのない手術中のさまざまな事実をつぎつぎに告げられて、高田博士も明らかに当惑を隠せませんでした。「麻酔が手術中に弱くなって、医者の会話を聞いていたとか、そういう事例は、人からよく聞くし、自分でもこれまで何度か出会ったことがあります。だけど、手術中の患者が、その様子をこれだけ詳しく、まるで本当に見ていたかのように描写したというのははじめてですね。これにどういう解釈をつけ得るのか、正直いって、私にはわかりません」というのが、会見を終えた高田博士の感想でした。
博士は、さらに、つぎのようにつけ加えました。「ただ、事実として、こういうことがあったのだから、それは事実として受け入れざるを得ない。やはり我々は事実の前には謙虚でなければならないと思うんです。結局、人間の持っ能力というものが、科学ではまだ十分に解明できていないということだろうと思うんです。科学と数学ではとらえきれないものが、この世の中に存在するということです。そういうことすら受け入れようとしない人がいますが、それはやはり事実の前に謙虚じゃない態度だろうと思います」。
二 ある医師の体外離脱実験
もうひとつここで、信頼性の高い「証言」として、ある医師の臨死体験を取り上げてみることにいたします。医師だからといって、その証言が必ずしも正しいわけではありませんが、医師というのは、少なくとも、医学的科学的な訓練を受けており、自分の身体や意識の上に起きたことを、できるだけ客観的に把握することには慣れているであろうと思われるメリットは否定できないと思います。
立花さんが、直接インタビューして臨死体験を聞き出したのは、フィンランドのラウニ・キルデ博士からでした。キルデ博士は、社会的地位の高い医師として、また『死は存在しない』という本の著者としても有名で、一九九〇年にアメリカのワシントンで開かれた第一回臨死体験研究国際会議では、初日に自分の臨死体験をもとにした記念講演をおこないました。その彼女は、一九六九年に医学校を卒業して医者になったばかりの時に、急性腹膜炎で救急病院に担ぎ込まれたことがあります。その救急病院で、緊急手術を受けたときに臨死体験をしたのです。そして、やはり、自分で自分のからだが手術されているのを見るという、体外離脱を経験しました。④
そのとき私は、全身麻酔をかけられて意識喪失状態にあったわけです。しかし、突然気がついてみると、私は天井のあたりに浮かんでいて、自分が手術されるところを見ていました。そして不思議なことには、手術をしている医者の考えが読めたのです。これからメスを取って、切ろうとしているなというのがわかりました。彼が切ろうとしているところには小さな動脈がかくれているということもなぜか私にはわかりました。しかし彼はそれに気がついていない。だからその動脈が切られてしまうというのがわかったのです。私はそれを止めようとしてあわてて叫びました。「そこを切っちゃダメ!そこには動脈があるのよ!」。しかし、彼には私の声が聞こえません。私が予知した通り、彼は動脈を切ってしまいました。血がパアーと噴き上がり、天井近くまで達するのが見えました。その途端、私はトンネルの中に吸い込まれていきました。トンネルの中は真っ暗で何もありませんでした。その向こうに輝く光があり、そこに私は入っていきました。それは自由の女神像くらい巨大で強く光り輝いていました。光は暖かく、愛に満ちていました。輝き方があまりに強かったので、私は光を直接みることが出来ませんでした。私は思わずその前にひざまずいてしまいました。
このあと、意識を取り戻したキルデ博士は、自分の体に戻ります。気がついてみると、彼女は大量の輸血をされている最中でした。彼女は手術中全血液の四十パーセントに相当する二リットルもの血液を失っていたのです。そのあと、どうしたか。彼女自身のことばで、続けてみましょう。
私はすぐに医者に自分が体験したことを告げました。手術の失敗を見ていたことも告げました。しかし医者たちは、私のいうことを信用せず、大量出血が手術の失敗によるということも認めませんでした。そして、まあまあ、落ち着いて、気をしずめなさいと取りなすだけでした。大量出血で脳にいく血流量が不足して、脳の低酸素状態がもたらす幻覚を見たんだというような説明をして、私を納得させようとしました。しかし私は医者ですから、どうすればカルテが見られるかを知っていました。そして、自由に動けるようになってから自分のカルテを見ると、私が臨死体験中に見たとおりのことが手術中に起きていたことが記されていたのです。
キルデ博士によると、このような臨死体験をしているときの意識は「完全に鮮明であった」といいます。自分の手術を見ている様子も、どこかぼんやりしているとか、かすみがかかったようになっているということはなくて、視野はすみずみまでクリアであったと述べています。
彼女は、医者として、この自分の体験を科学的にどう説明できるかを、いろいろと考えました。手術中にミスを犯した医者が言った「脳の低酸素状態が生んだ幻覚」というのは、確かに一理があることも彼女は知っていました。ただ違うのは、低酸素状態の場合、意識レベルも低下して眠くなり、彼女が経験したような、明晰な意識を持ち続けることはできないということです。
精神分裂病や、アルコール中毒、薬物中毒のような場合にも、幻覚、幻聴はよくおこりますが、その内容は、臨死体験とは明白な違いがあると、博士は言います。精神病の場合は、幻覚の内容は狂気の産物であり、妄想的で、患者の精神症状をより一層悪化させるものであるのに対し、臨死体験の場合は、内容が美しくこころ休まるものであり、愛とよろこびに満ちたポジティブな体験だというのです。結局、臨死体験というのは、いろいろこじつけて無理な説明をつけるより、物理的な三次元の日常生活から離れて、四次元の霊的な世界へ入っていくこと、とするのが一番簡単で正しい説明だと彼女は述べています。
実は、このキルデ博士は、それから何年かたって、かっての自分の臨死体験を、もう一度意識的に体験してみて、その体験中の自分を十分に観察し、分析してみたいと思うようになりました。インタビューしている立花さんが、「でも、臨死体験の実験なんて、どうやってやるんですか。わざと死にかけるんですか?」と聞きますと、キルデ博士はこう答えました。⑤
いろいろ文献を集めて読んでいるうちに、体外離脱は、催眠術によって誘発される可能性があるとわかったのです。過去にそれを利用して実験が行われたこともあるとわかりました。その頃私は、催眠術に興味を持って、自己催眠がかけられるようになっていましたので、これなら自分で実験できるのではないかと考えたわけです。その頃私は、ラップランド地方のロヤニエミという北極圏の町に一人で住んでいたのですが、ある日、自宅のベッドの上に横になって、一人で実験を始めました。
大変な実験ですが、これはうまくいきました。手や足など、末梢神経系の血流をどんどん減少させて、血液が心臓と脳に集中するように自己催眠をかけていくと、本当に末梢の血流が減っていくのだそうです。そして、突然、足指の先から頭までふるえが走り、髪の毛が逆立って目の前が真っ暗になり、気がついたら、いつのまにか体外離脱していたというのです。「浮き上がった自分のほうはどうなっているのですか。何かこれが自分だといえるような実体があるんですか?」と立花さんが聞きますと、「ちゃんと私の体と同じような形があるんです。顔もあるんです。しかし、それは半透明のスキムミルクのようなものでできていました。これがエネルギー体というものかと思いました」とキルデ博士は返事しています。
ここでキルデ博士が、肉体を離れた実体(エネルギー体)について述べているのは、貴重な「証言」です。コナン・ドイルもかって、「個性の死後存続を具体的に理解する上で基本となるのは、死後も肉体に相当する何らかの身体をそなえているという事実である。材質は肉体よりはるかに柔軟であるが、細かい部分まで肉体と同じものをそなえている」と述べたあとで、こう続けています。
むろんそれは地上時代から肉体とともに成長していたもので、肉眼では見えないが、肉体と 同じ形態を持ち肉体と完全に融合して存在している。けれどもこの両者は、肉体の死に際してーーあるいは条件次第では生きている間でもーー離ればなれになり、両者を同時に見ることも できる。生前と死後の違いは、死後は両者を結びつけている生命の糸が切れて、それ以後は霊 的身体だけで生きていくという点である。肉体は、あたかもさなぎが出ていったあとの抜け殻のように、やがて分解して塵となって消える。これまでの人類は、その抜け殻を手厚く葬ることに不必要なほどの厳粛さを求め、肝心の「成虫」のその後の事情については、実にいい加減な関心しか示さなかった。⑥
キルデ博士の体験は、ここでいう「条件次第では生きている間でも」肉体と肉体に相当する身体(エネルギー体)の両者を離ればなれに見ている例にあたります。彼女は、このようにエネルギー体の自分の姿について観察しているばかりでなく、やがて、ベッドの上に横になっている自分の肉体のそばまでおりていってじっくり観察をはじめました。いわば、さなぎから抜け出た蝶が、いま抜け出たばかりのさなぎをくわしく観察する、というようなことを、現実に実行してみたのです。その様子を、彼女はこう述べています。
そばにいくと、自分の肉体がゆっくりゆっくり呼吸しているのがわかりました。それは異常なほどゆっくりでした。それで、呼吸数を数えてみようと思いました。私は麻酔医をしていたこともあるので、いつでも時計を見ずにきっかり六十秒の時間をとることができるように訓練されていました。だから、時計なしで呼吸量がはかれたのです。数えてみると、一分間にわずか十回でした。
正常値は二十回前後ですから、半分です。あまりにも少なすぎます。それでちょっと心配になり、今度は脈をとってみることにしました。数えてみたら、一分間に三十二回しかありませんでした。やはり正常値の半分です。低すぎます。ますます心配になって、顔のところに手をあててみました。すると、顔から暖かみが失せて、冷たくなっているのです。冷たいだけでなく、こわばっていました。
これは大変だと思いました。呼吸、心拍、体温などの生命徴候が明らかに低下しているのです。これは、死んでしまうことになるのかもしれないと思いました。肉体が死ぬとしたら、エネルギー体の自分のほうも死ぬことになるのだろうかと考えましたが、どうなるのかよくわかりませんでした。
その頃はまだ、死というものがあると思い、死を恐れていましたから、心理的にパニック状態に陥りました。そして、戦場の兵士が生命の危機にさらされたときに、思わず「お母さん!」と叫ぶように、私も、「お母さん、助けて!」と叫んでいました。するとどうでしょう。私は一瞬にして、千キロも離れたヘルシンキの両親が住む家の居間に飛んでいたのです。⑦
キルデ博士は、自己催眠により、こうして自分で自分の肉体から抜け出し、抜け出した自分が自分の肉体の呼吸量や心拍数を計るということまでしているわけですが、これは、たとえば、自動車を運転している人が、自動車を降りて車体を点検しているというような状況と比べて考えるとわかりやすいかもしれません。
自動車はあくまでも機械であってさなぎのようなものです。あるいは、蝉の抜け殻です。機械にも耐用年数はありますが、これはいのちではありません。本当のいのちをもっているのは、自動車のなかにいる人間、つまり運転手です。自動車は手入れを怠ったり、大事に扱ったりしないと、耐用年数がこなくても故障して動かなくなったりします。その場合、運転手はその自動車を放棄して、また新しい自動車に乗り換えます。自動車が故障して廃棄処分になったからといって、運転手が死ぬわけではありません。運転手は、つぎからつぎへと車を乗り換えて、そして永遠に生きていきます。これが本当のいのちの姿といっていいのかもしれません。
人間のいのちを包んでいる、あるいは、乗せている肉体の「耐用年数」はせいぜい百年ですが、普通は、いろいろな病気や事故などで、耐用年数を待たずに機能しなくなります。その肉体の死を私たちは、しばしば、いのちの死と勘違いして、乗り換えることを(つまり、生まれ変わることを)知らず、そのために、恐れたり、嘆き悲しんだりしているということはないでしょうか。一昨年の講演会でもご紹介しましたが、空海も「生まれ、生まれ、生まれ、生まれて、生の始めに暗く、死に、死に、死に、死んで、生の終わりに冥し」と書き残しました。これは、「いったい何度生まれ変わったら、あなたがたは、この生と死の真理が理解できるようになるのか」という私たちに対する戒めのことばだと思います。
ここに引用したキルデ博士も、自分の肉体が死にそうになっているのを見ると、さすがに怖くなり、パニック状態になります。そして、思わず「お母さん、助けて!」と叫びました。すると、その瞬間、キルデ博士は、千キロも離れたヘルシンキのお母さんの家に移っていました。一瞬のうちに千キロ移動する、というのはすごいですね。「常識」ではとても考えられないことです。この辺までくると、さすがにもうついていけない、と思われる方もおられるかもしれません。しかし、体外離脱は三次元の物理現象ではなくて、三次元を超えた超常現象です。体外離脱ができないにせよ、あるいは、しないにせよ、人間という生命体には本来そういう力をも潜在的に持っているのだと考えたほうがよいのかもしれません。
このような体外離脱体験とそれが示唆する人間の無限の潜在能力について、もうひとつの例を取り上げてみましょう。実は、あのキュブラー・ロス博士もこのような体外離脱の体験者なのです。
キューブラー・ロス博士は自分の二万例に及ぶ臨死体験の調査研究から、死後の生に対する確信を抱き、数多くの著作や講演、セミナーで永遠の生命を説き続けてきました。彼女自身も自分の臨死体験を著書などで述べています。そのキューブラー・ロス博士にも、立花氏はアメリカでインタビューしたのですが、その時に、立花氏は念のため、臨死体験のほかに、体外離脱をしたことがあるか、と彼女に聞いてみたのです。すると思いがけなく、彼女はつぎのように答えました。
あります。何度もあります。好きなときに好きなように離脱できるわけではありませんが、十五年ほど前に、宇宙意識セミナーに出て、人間は誰でも体外離脱能力を持っており、訓練によってその能力を引き出すことができるということを学び、それができるようになったのです。そういうことができる人が、何千人、何万人といるのです。
(体外離脱して)いろんなところへ行きます。その辺の屋根の上にとどまっていることもあれば、別の銀河まで行ってしまうこともあります。ついこの間は、プレヤデス星団(すばる)まで行って来ました。そこの人たちは、地球人よりずっと優れた文明を持っていて、「地球人は地球を破壊しすぎた。もう元に戻らないだろう。地球が再びきれいになる前に、何百万人もの人間が死ぬ必要がある」といっていました。⑧
これがたとえば、普通一般の人間の言ったことであれば、そんなことは単なる幻想や作り話にすぎないと一笑に付すこともできるかもしれません。しかし、これを言っているのがキュブラー・ロスであるとなると、おのずからその重みが違ってきます。このような例はまだいくつもあります。あのスイスの精神医学の巨人、C.G.ユングにも、彼が自ら書き記した体外離脱の証言があることを立花氏は紹介しています。
ユングは、一九四四年のはじめに、心筋梗塞で意識不明になり、そのときに千五百キロほどの高度から眺めた青い地球の姿を詳細に描いています。ソ連のガガーリンが世界初の有人宇宙飛行で、宇宙から地球を見て、「地球は青かった」と言ったのは、一九六一年四月十二日のことでした。それまでは誰も、宇宙から地球を見れば青く見えることは知らなかったはずでした。それをユングは、ガガーリン以前にそのことも書いていたからです。それでもなお、ユングのいう体外離脱を否定するというのは、客観的に見てもかなりの無理があるといわなければなりません。⑨
三 霊界からの導きの手
キルデ博士が『死は存在しない』という本を書いて、それがベストセラーになったことは先に述べましたが、この本が書かれた背景には興味深い事実があります。彼女の従兄にソルヴェーグという名の医科大学教授がいました。ソルヴェーグは、五十一歳のときに心筋梗塞で亡くなったのだそうです。ところが一九七九年に、その従兄が、瞑想中のキルデ博士に「一九八一年にお前は本を書くことになる。それはベストセラーになり、世界各国で翻訳されるようになるだろう」と伝えてきたのです。
キルデ博士は、初めはそのことをとても信じられませんでした。彼女は自分には文章を書く力はないと思っていたし、それに、フィンランドは人口五百万の国です。フィンランド語で書かれた本で、それまで、外国語にまで翻訳された本はなかったからでした。しかし、従兄の言ったことは現実になりました。本当にそれから二年後、彼女は本を書いて、ベストセラーになり、世界各国で翻訳されることになったのです。『死は存在しない』がその本です。「それは、本当に信じられないことでした。一九八一年のある日、突然、『書きなさい』という命令が下ったのです。そして、ペンを取ると、猛烈な勢いで自動書記がはじまり、二十四時間で本を一冊書いてしまったんです」と彼女は語っています。
自動書記というのは、書いている本人が意識しなくても、ペンを持っている手が勝手に動いて字が綴られていくことをいいます。通常、書いている人の手は、霊界からの力で統制され、自分のものとは違った筆跡や文体で、ものすごいスピードで書かれていくといわれます。キルデ博士の場合もそうでした。ある時は一時間、ある時は一時間半と、こまぎれにでしたが、積算しても二十四時間にしかならないくらいの猛スピードで、『死は存在しない』が書き上げられていったのです。彼女は言っています。
自分では何を書いているのかわからないんです。あるときは、真っ暗闇で書いたこともあります。そのときは、真夜中に「書きなさい」という命令がきて、眠いからいやだといったんですが「どうしても書きなさい」という。仕方がないので起きあがって、スタンドのスイッチをひねったら「そんなものは必要ない。どうせお前が書くのではないから消しなさい」というんです。それで本当に真っ暗闇で書いたんですが、翌朝起きて見たら、本当にきれいにかけてる んでびっくりしました。しかもその字体が、十九世紀に流行った古風なきれいな書体なんですね。正常なときに、その書体で書けといわれても書けないような書体でした。⑩
こうして、キルデ博士の本は、「予言」どおり、発売後直ちにベストセラーになったわけですが、このようにして書かれた本というのは、実は、欧米でもかなりの数に上っているようです。日本でも例外ではありません。たとえば「幸福の科学」を主宰している大川隆法さんの本などがそうで、彼は、千冊の本を書くのを目標としている、と聞いたことがあります。
彼は多くのベストセラーを出していますが、その代表作のひとつである『太陽の法』の初版本には、「本書は、単に地上に肉体をもっている私の小さな脳細胞から生み出されたものではありません。霊天上界、九次元世界にある私の潜在意識から啓示をうけつつ、これを文字として、また私自身の思想としてあらわしたものなのです」とあり、「ペンを握る筆者の手は、まるで生きもののごとく勝手に動き・・・わずか十日あまりで、一冊を書き上げたことになります」と結んでいます。
このような、いわば霊界から差しのばされた手によって書かれた本の中には、生と死についても貴重な示唆を与えてくれるものが少なくはありません。これから取り上げる、『輪廻を超えて』も、そのような本の一冊です。
この本は、「本書を手にする多くの人びとは、著者であるわたしの存在を信じようとはしないだろう。なぜならわたしが、この言葉を記録して整った原稿に仕上げるために毎日忠実にタイプを打ってくれる女性、ジュディー・ラドンではないからだ」と、この本には書かれています。「わたしは彼女のこころにことばを生じさせるが、そのことばは彼女のものではない」とも述べられています。ジュディー・ラドンが著者ということになっていますが、これを書かせているのは、実は、「アフ」と名乗る霊界の存在なのです。
前回の小冊子で、私はシルバー・バーチと仮に名乗る高位霊からの通信を紹介しました。地上時代の本名は、何度尋ねても答えませんでしたが、そのときにシルバー・バーチは、「前世で私が王様であろうと乞食であろうと、大富豪であろうと奴隷であろうと、そんなことはどうでもよいのです。私の言っていることに、なるほどと納得がいったら真理として信じて下さい。そんな馬鹿な、と思われたら、どうぞ信じないで下さい。それでいいのです」と述べていました。もし、この本の「アフ」と名乗る霊界の著者に本名を尋ねたとしても、多分同じ答えが返ってくることでしょう。私たちは、納得できれば信じればよいのです。そして、そんな馬鹿な、と思ったら、信じなければよいのです。
私たちは、生と死の真理を知るためにも、こうして一生懸命に霊界の実状に迫ろうとしていますが、この三次元の世界の制約のなかでは、いままで述べてきたような臨死体験などの研究に取り組んでも、どうも核心を掴み得ないもどかしさが残ります。それだけに、霊界の内部にいて、しかも私たちとコミュニケーションをとれる能力のある霊界の存在からの通信は、極めて貴重であるといわなければなりません。そのような例をみてみましょう。
まず、ある男性がある病気にかかり、自宅または病院で死亡したとします。その場合、霊界では霊界の存在がそれをどういうふうに捉えるでしょうか。つぎのように述べられています。
たったいま、彼の肉体は機能を停止し、周囲には親族や医者や看護婦らが何人か集まっている。ところが、(亡くなった)彼自身はすっかり元気で、久しく味わったことのない爽快さを感じている。いつもとひとつだけ違っているのは、自分が部屋の天井あたりに浮かんで、悲嘆にくれる家族を見下ろしていることだ。当然、彼は驚いているーーどうして自分はこんな奇妙なところにいるのだろう!すでに生命を失った自分の肉体と、自分のいまの姿を見ることので きない家族とを前にして、彼は後ろ髪を引かれる思いである。もし生前に霊魂の不滅を信じていなければ、彼はさらに動揺や混乱を感じるかもしれない。うまい具合にこの「死者」が広い心の持ち主であれば、肉体は死んだが自分は生きながらえているのだ、という事実をうけいれることになるだろう。⑪
臨死体験でも、一旦は自分の肉体から離れて、天井あたりから自分の肉体を見下ろす、ということがしばしば語られてきましたが、少なくともその部分は、この霊界内部からの観察でも裏付けられているといってよいでしょう。これは、しかし、きわめ重要な裏付けです。なぜなら、これは同時に、私たちは死んでも別の存在になって生き続けることが本当であることをも裏付けているからです。
私たちの肉体が死んでも、本当の私たちは生き続けます。しかも、この場合、私たちは肉体という制約から抜き出て自由になり、やがて私たち自身のいのちの本質をも理解し始めるようになるのです。つぎのようにです。
あなたの知っている「自己」とは、あなたの存在全体からみればほんのわずかな部分にすぎない。物質界で生活していく上でもっとも有利なように、自己はごく狭い範囲に限定される必 要があるのだ。だが死ぬと同時に、あなたがた一人ひとりの機能は飛躍的に拡大する。たとえてみれば、急に千里眼の持ち主となってテレパシーが通じるようなもので、他人の考えを簡単 に読みとったり、多くのことを直感的に理解できるようになるのだ。まさかと思うだろうが、一旦肉体というわずらわしいものを脱ぎ捨ててしまえば本当にそのような状態になる。⑫
このあとでは、「こころに想い描いたことはそのまま体験され、移動するのも足を使うのではなく、想念を用いて遠いところへでも、好きなところへ一瞬のうちに行くことができる」とも、述べられていますから、キルデ博士やキュブラー・ロス博士が体外離脱の時に見せた不思議な能力、たとえば、相手のしようとしていることが手に取るようにわかるとか、瞬時にして千キロを移動するというような能力も、「一旦肉体というわずらわしいものを脱ぎ捨ててしまえば」、不思議ではないのかもしれません。ここでいう、テレパシーも、そういう能力の一つを例示したものなのでしょう。
霊界に移ってからの「身体」にも触れています。「こちらにやってきても、身体を持たないわけではない。五体はもとどおり満足で、見慣れた服まで着ている。こちらでの身体は、地上のものに比べて、より繊細な素材でできており、痛みや病気、不快感、疲労、飢えなどの感覚はない」ということです。先に、キルデ博士が体外離脱したときに、肉体から離れた自分の体の様子について語っているところがありました。私はそれを「貴重な証言」と述べましたが、実は、霊界では当たり前のことで、「五体満足」の姿を伝える数多くの通信には矛盾はありません。
四 霊界からの訪問客
私たちは、生存中から「肉のからだ」と「霊のからだ」を併せ持っているといわれます。私たちが死ねば、「肉のからだ」は確かに死にます。しかし、「霊のからだ」は永遠に生き続けて滅びることがないのです。これが、生と死を考える場合のもっとも重要で根幹的な真理であるといってよいでしょう。そのことを示す貴重なエピソードを、ここでまた、キューブラー・ロス博士の体験に基づいて触れておきたいと思います。
かつて、シカゴ大学医学部教授として勤務中の博士には、シュワルツ夫人という患者がいました。その彼女が亡くなり埋葬されてから十か月ほど経った頃、博士はこのシュワルツ夫人の「来訪」を受けたのです。その証拠も残っているといいます。その来訪の模様を講演会で語っている部分を、少し長くなりますが、つぎに引用してみましょう。⑬
・・・ある日、私は一大決心をしました。「シカゴ大学を辞めよう。今日、死と死の準備のセミナーが終わったらすぐそれを打ち明けよう」。
新しい牧師と私は、セミナーのあと、いつもきまってエレベーターまで並んで歩き、エレベーターが来るのを待ちながら仕事の話を片づけると彼はエレベーターに乗り、私はオフィスにもどるのでした。私のオフィスはセミナーと同じ階の廊下の突き当たりにありました。・・・ その牧師は大男なのですが、エレベーターが来る前に私は彼の襟首をつかんで言いました。「ちょっと待ってください。私は恐ろしい決断をしたの。それを聞いてちょうだい」。
大男をひっつかまえてそう言ったことで、私は自分が英雄になったみたいな気分でした。でも彼は何も答えません。
そのとき、エレベーターの前に一人の女性があらわれ、私をみつめました。よく知っている人なのに、それが誰だかどうしても思い出せない、ということがあるでしょう。みなさんにも経験があると思います。私は牧師に、「まあ、あれ、誰だったかしら。知っている人だわ。私のことをじっと見ている。あなたがエレベーターに乗るのを待っているんだわ。きっと私に用 があるのよ」。
私は、彼女が誰かということに心を奪われて、牧師をつかまえようとしていたことをすっかり忘れていました。その女性が忘れさせたのです。彼女は透き通っているように見えましたが、後ろにあるものがはっきり見えるほどではありませんでした。私は牧師にもう一度「誰かしら」と聞きましたが、牧師は答えませんでした。それで私は牧師のことはあきらめました。私が最後に牧師に言ったのは、「私からじかに彼女に、あなたの名前が思い出せないって言うわ」という意味のことでした。先ほどからのことはすっかり忘れていたのです。
この大男の牧師には、多分エレベーターの前に現れた女性は見えていなかったのでしょう。ただ、キューブラー・ロス博士が二度繰り返してその女性のことを言っているのは聞いているはずですから、牧師は不審に思いながらも、答えようがなかったのかもしれません。そのままエレベーターに乗り込んでしまいました。彼女は、話を続けます。
牧師がエレベーターに乗るとすぐに、その女性が近づいてきて、「ロス先生、帰ってきました。オフィスにお寄りしてもよろしいですか。ほんの二、三分しかお時間はとりません」という意味のことを言いました。彼女が私の名前もオフィスの場所も知っていたので、彼女の名前を思い出せないということを、こちらから言わずにすみました。
エレベーターからオフィスまでの距離があんなに長く感じられたことはありません。・・・そのとき、私は自分に言い聞かせました。「あの人が見える、って言いたいんでしょ。でもそれはありえないことよ」。
私がそのとき何をしていたか、おわかりになりますか。私はエレベーターからオフィスに行くまで、自分に対して検証していたのです。「疲れているせいだろうか。これまで精神分裂病患者ばかり診てきたせいだろうか。いろいろなものが見えはじめたようだ。この女にさわって、現実かどうか確かめなくては」。
彼女の肌が温かいか冷たいかを知ろうと思い、あるいは触れたとたん消えてしまうのではないかと思い、実際に触れてみたりしましたが、オフィスに着くまで、自分がどうしてそんなことをしているのか、自分でもわかりませんでした。・・・私はそのとき、ひょっとしたら、この人は本当に何か月も前に死んで埋葬されたシュワルツ夫人かもしれないという考えを必死に押し殺そうとしました。
このように「霊のからだ」が目の前に現れるということはめったにあることではありません。さすがのキューブラー・ロス博士も、この時は半信半疑で状況がよくのみこめないでいたようです。しかし、科学者の自覚を取り戻して、この現象が事実であることを証明する証拠を掴もうとしました。そして彼女は、その証拠をも手に入れたのです。⑭
オフィスまでくると、彼女がドアを開けました。まるで私のほうが客みたいに。彼女は本当に信じられないくらいの優しさと思いやりと愛情を込めてドアを開け、こう言いました。「ロス先生、私が帰ってきたのには二つ理由があります。ひとつは先生とゲインズ牧師にお礼を申し上げるためです」。ゲインズ牧師というのは、私と理想的な協力関係にあった、素晴らしい黒人牧師です。「私にしてくださったことに対して、お二人にお礼を言いたくて。でも私が帰ってきた本当の理由は、先生にお願いするためです。死とその準備についてのお仕事をやめてはいけません。まだ、いまは」。
私は彼女の顔を見つめました。そのとき私が彼女のことをシュワルツ夫人かもしれないと思ったかどうかは覚えていません。何しろ彼女は何か月も前に埋葬されていましたし、私は死者のよみがえりとかそういったことはいっさい信じていませんでした。私はなんとか自分の机にたどり着くと、こうすれば彼女が消えるのではないかと期待して、そこに実在している机やペンにさわりました。でも彼女は消えませんでした。そこに立ったまま、優しく、でも同時に強い調子で言いました。「ロス先生、聞こえますか。先生の仕事は終わっていません。私たちがお手伝いします。時がくればわかります。でも、いまはまだやめないでください。そう約束してください」。
私は思いました。「やれやれ、こんなことを話しても、誰も信じてくれないだろう。いちばんの親友だって」。そのときは、何百人もの人にこの話をすることになろうとは夢にも思いませんでした。それから、私の中の科学者が首をもたげ、ひじょうに狡猾な、とんでもない大うそをつきました。「ゲインズ牧師はいまアーバナにいるの」。
そこまでは本当でした。ゲインズ牧師は実際にアーバナの教会に移ったのです。「あなたがひとこと何か書いてくれたら、きっと喜ぶと思うわ」。
私は彼女に紙と鉛筆を渡しました。おわかりでしょう。、私はその手紙を親友の牧師に送るつもりはなく、科学的な証拠にしたかったのです。埋葬された人間に手紙が書けるはずがありません。彼女はじつに人間的なーーいや、にんげんではありませんねーー優しい笑みを浮かべました。私のもくろみなど、お見通しだったのです。テレパシーというものがあるとしたら、私の考えていることが彼女に伝わった方法はテレパシーでした。それでも彼女は紙と鉛筆を受け取って、短い手紙を書いてくれました。もちろん私どもではそれをガラス張りの額縁に入れて大事に保管しています。書き終えると、彼女は言葉には出さずに言いました。「これで満足ですか?」。
私はそれを見て、思いました。「これは誰にでも話せるような話題じゃない。とにかくこれは大事にしておこう」。彼女は立ち上がって、繰り返しました。「ロス先生、約束してください」。私が「約束するわ」と答えた瞬間、彼女は出ていきました。
その手紙はいまもちゃんと持っています。
お わ り に
さる三月一日、劇作家の田中澄江さんが九十一歳で亡くなられました。ご存じの方も多いことと思いますが、田中さんは、舞台の戯曲だけではなく、映画「めし」やNHKの連続テレビ小説「うず潮」などのシナリオのほか、小説、エッセーなどの旺盛な文筆活動で知られた人です。死ぬ直前まで、童女のような天真らんまんさと盛んな好奇心は変わらず、人間だけではなく、山や野の草花、森羅万象にまで、あふれんばかりの愛情を注がれた人だといわれています。生前には、「ひっそりとシャボンのあぶくがひとつ消えたくらいの、しずかな形でこの世を去りたい」と書いていましたが、告別式は、七百人もの人々がカトリックの大聖堂を埋めて、盛大だったそうです。
私は、田中さんの本はあまり読んでいないのですが、むかし、朝日新聞に載った「神を知るために」という一文は、切り抜きにしていまも私の資料ファイルのなかにあります。彼女がこれを書いたのは、八十二歳の頃でした。彼女はその文を、「自分は、どこから来て、どこへゆくのか。自分は何をしに、この世に生まれて来たのか。物ごころついて以来、心に持ったはずの問いかけを、まだ、私は持ちつづけ、まだ、問いつづけている」と、書き出しています。そして、最後にはつぎのようなエピソードでこの文をむすんでいます。
二十三歳のとき、芝白金三光町の聖心女子学院の教師となり、マザー・ラムという英国人から、公教要理の講義を受けた。開口一番、ひとは何のために生まれましたか。神を知るためですねと言われたとき、大粒の涙が机の上にぽたぽた落ちて、そうだ、本当にそうだ、神を知る ために生まれたのだと、全身で叫びたい思いになった。以来半世紀を経て、いまだにその感激が胸の底に燃えているような気がする。⑮
私にとっても、これは忘れられない文章で、ときおり思い出しては、自分の不勉強と鈍い感受性を反省させられたりしています。「神を知るために生まれた」というのは、おそらく「自分を知るために生まれた」と同義で、ひとつの「真理」だと思いますが、こういう真理を知っていると、人間は強いですね。少々の困難に出会っても、あまり苦にもならず、明るく前向きに生きていく力が湧いてきます。逆に、知らないと私たちは本当に弱いと思います。ちょっとした障害にぶつかってもそれを乗り越えることができず、暗く落ち込んで、しばしば、自分の不運を嘆いたりひとを呪ったりするのではないでしょうか。
若き日の田中さんは、「神を知るために生まれた」と聞かされて、ぽたぽたと大粒の涙を落とし、全身で叫びたいようなあれほどの感動でふるえました。おそらくこれは、このことばが、田中さんの意識の奥深くに潜んでいた「生まれてきた目的」に激しく共鳴したからではないかと思われます。
私たちは、ひとりひとりが、目的をもってこの世に生まれてきました。そのことは、多くの霊界からのメッセージが伝えています。その目的を達成するのにふさわしい両親や環境を自ら選び取って、この世に生を受けたはずでした。誕生の瞬間に、その目的はこころの深層に封じ込まれてしまいましたが、それをまず、私たちは思い出す必要があるのかもしれません。そして、そのための第一歩は、多分、私たちが、「生きている」のではなくて、「生かされている」ことを知ることであろうと思います。コナン・ドイルも、自分が死んだあとで、霊界からつぎのように伝えてきたことがありました。
科学者たちは、自然の出来事は物質的存在の正常な営みの一部であると見なしがちです。そして、自然は一種の法則によって動かされていると考え、その法則に名前をつけるだけで、なぜそうなるのかについては理解しようとはしません。彼らはただ、種を土のなかに蒔き、一定の水分と太陽と温度があれば芽が出る、と主張するのです。そしてそれを聞く人は、その種蒔きの結果を奇跡として見るのではなく、言い換えれば、霊的な力の不可思議な現実化であるとは見なさず、ごく当たり前のこととして受け入れてしまうだけなのです。
霊界の真実を知らない多くの人々は、自分を支えてくれている自然のさまざまな営みをごく当たり前のことで、あたかも自分たちの権利でもあるかのように考えています。その結果、自然のあらゆる現象の根源にある精霊たちの限りない奉仕、忍耐、愛情に感謝することもしようとはしないのです。⑯
たしかに私たちは、霊界のこのような奉仕や尽力を意識することが少ないですから、毎日、朝になれば目覚めるのが当たり前で、手足が動くのも当たり前と考えがちです。しかし、それは本当に当たり前のことでしょうか。私たちが呼吸ひとつするのにも、それは決して当たり前ではなく、実は背後で大きな力に支えられていることに気がつかなければならないのかもしれません。そういうことに気がついて初めて、私たちはおのずから、感謝の気持ちがもてるようになるのではないでしょうか。感謝の気持は、さらなる感謝を呼び込み、それが、優しさや思いやりとなってまわりに広がっていくのでしょう。そのとき私たちは、「神を知るために」、そして「自分を知るために」、確実に光へ向かって歩んでいることになるのだと思います。
注
①ジュディ・ラドン『輪廻を超えて』(片桐すみ子訳)人文
書院、一九九七年、三九〜四〇ページ。
②E.キュブラー・ロス『人生は廻る輪のように』(上野圭一訳)
一九九八年、五ページ。全文は、『ダギーへの 手紙』
(アグネス・チャン訳)佼成出版社、一九九八年。
③立花隆『臨死体験・下』文芸春秋、一九九四年、
二二三〜二二七ページ。
④立花隆『臨死体験・上』文芸春秋、一九九四年、
一四九〜一五九ページ。
⑤立花隆、前掲書、『臨死体験・上』
一六七〜一六九ページ。
⑥コナン・ドイル『コナン・ドイルの心霊学』(近藤千雄訳)
新潮社、一九九二年、一七一ページ。
⑦立花隆、前掲書(上)、一七〇〜一七一ページ。
⑧立花隆、前掲書(上)、四三九〜四四〇ページ。
⑨立花隆、前掲書(上)、五一〜五四ページ。
⑩立花隆、前掲書(上)、一八〇ページ。
⑪ジュディ・ラドン、前掲書、二八ページ。
⑫ジュディ・ラドン、前掲書、三〇ページ。
⑬ E.キュブラー・ロス『死ぬ瞬間と臨死体験』(鈴木晶訳)
読売新聞社、一九九七年、一七七〜一八二ページ。
⑭ 同様の証拠としては、たとえば、イギリスでの物理霊媒
による交霊会で、美しい容貌の女性霊が現れて、列席し
ていた外科医がその手を取ってみたら脈拍まで打ってい
たという記録がある。「英国学士院のガリー博士がケーティ
・キング霊の脈を計っているシーン」として、その写真まで
残されている。コナン・ドイル、前掲書、一七五ページ
参照。
⑮「朝日新聞」一九九一年三月十一日。
⑯アイヴァン・クック『コナン・ドイル』(大内博訳)講談社、
一九九四年、二〇二ページ。
本稿は、来る五月十四日(二〇〇〇年)に、こすもす斎場三階大ホールで行う予定の「こすもすセミナー」特別講演のテキストとして書き上げました。小冊子としては、一昨年の「いのちを慈しみ明日に向かって生きる」と昨年の「生と死の実相について」に続く連作として書いておりますので、前二冊とも併せてご一読いただければ、たいへん有り難く存じます。
こすもす斎場の社会に対する貢献の一環として、今年もこのような小冊子の発行を企画してくださった溝口祭典・溝口勝巳社長のご高配に、こころから厚くお礼申しあげます。
謝 辞
今年は、武本昌三先生の特別講演を五月十四日にお願いすることになりました。その特別講演のためにまとめられたのがこの小冊子「光に向かって歩む」であります。当日は、この小冊子をテキストにして、ご講演いただく予定になっております。
生と死の問題は、私たちの身近なところにある切実な問題でありながら、正面から向き合って考えていくようなことは、ふだん、あまりないように思われます。「死を考えることは生を考えること」などとよくいわれますが、それでも、なんとなく扱いにくい、重すぎるテーマのように受け取られているからかもしれません。そのようななかで、武本先生の毎年のご講演は、人間のいのちの尊さを学ばせていただける、まことに貴重な学習の機会であるといわなければなりません。私たちが、皆さまに対する奉仕活動の一環として、毎年このような講演会を開催させていただいているゆえんであります。
私たち社員一同も、このような講演会での学習を通じて、私たちの真心を込めたご奉仕が、いのちの真理に裏付けられたものでなければならないことを、深く学んでまいりました。今回の先生の「光に向かって歩む」お話も、私たちは、肝に銘じてご奉仕に活かし、一層の精進に励みたい所存であります。
毎回、熱心にご参加くださっております皆様方に厚くお礼申し上げますと共に、この小冊子をまとめて下さった武本先生にも、改めて衷心より感謝の意を表したいと存じます。
二〇〇〇年四月二〇日
株式会社 溝口祭典 代表取締役 溝 口 勝 巳
|