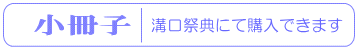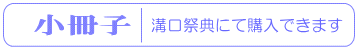【こすもすセミナー特別講演】
真実の自分を求めて
ー「生まれ変わり」から学ぶ悔いのない人生 ー
武 本 昌 三
一生を通じて、
あなたは身体が自分だと思っている。
ときには精神が自分だと思うこともある。
ほんとうの自分が何者かを知るのは、
死ぬときだ。
ー ニール・ウォルシュ『神との対話』より ー
は じ め に
いま、私たちはどのような世界に生きているのでしょうか。
世界の終末を午前零時と見立てた「核の時計」というのが、アメリカのシカゴ大学にあります。人類の滅亡をもたらす核戦争までの残り時間を象徴的に示したもので、この時計はアメリカの科学誌「原子力科学者会報」の委員会によって管理されています。第二次世界大戦後から間もない一九四七年にこの時計が初めて登場したときには、世界の終末は七分前にセットされていました。
もっとも危うかったのは、米ソが水素爆弾の実験をしていた一九六三年で、時計の針は、人類滅亡の二分前まで近づきました。その後、冷戦の終結で一九九一年には一七分前まで戻されましたが、九五年、九八年と時計の針は滅亡へ向かって進められ、本年(二〇〇二年)の二月二七日には、また元の、「残り七分」の振り出しに戻ってしまったようです。①
今回の判断でマイナス材料となったのは、核物質管理への懸念の増大、アメリカの弾道弾迎撃ミサイル(ABM)制限条約脱退、核兵器を持つインド・パキスタンの対立、核兵器取得を狙うテロリストの存在などがあげられています。毎年、核廃絶への進展を評価している世界的な反核運動「アボリッション(核廃絶)二〇〇〇」も、昨年初めて最悪の「0点」をつけるなど、核軍縮の行き詰まりとブッシュ大統領が主導するアメリカなどの核回帰への懸念は高まるばかりです。
人類の生存に脅威となっているのは、毎年深刻さを増している地球の環境破壊も同様ですが、地球温暖化問題一つをとってみても、温暖化ガス削減についての世界各国の足並みはなかなか揃わず、富裕な大国のエゴが目立つようです。京都議定書では、日本、アメリカ、ヨーロッパの削減義務は、一九九〇年に比べて、今後一〇年間に、それぞれマイナス六、七、八パーセントにする、となっていました。しかしアメリカ政府は、九〇年の水準より七パーセント減らすどころか、三五・五パーセントも増えることを公言したうえで、「アメリカは国益を考えて京都議定書は批准しない。しかし、他国の批准の妨害もしない」と言い切っています。②
その一方で、アメリカの価値基準を世界に押し進めているといわれている「グローバル化」は、世界の貧富の差をますます広めてきました。一握りの六パーセントの豊かな人間が世界の富の六〇パーセントをも独占するという極端なアンバランスのなかで、世界人口六〇億のうち八億三千万人もの貧者が飢えに苦しんでいるという深刻な事態も、なかなか改善されないようです。
問題は、八億三千万の人々が飢えているのは、世界の食糧が足りないからではないことです。現在の世界の穀物生産量は一八・七億トンですが、これに対して、世界の年間必要量は、推定で九億トンですから、世界には必要量の倍以上の食料があるのです。牛や豚、鶏などの家畜飼料用としての六・六億トンを加えても、まだ世界の食糧は余る計算になります。③
食料が余っているはずなのに八億人以上が飢えるのは、食料を捨てるほど買う人がいる一方で、まったく買えない人がいるという、富の極端な偏在がその原因です。おそらく、昨年の「9・11テロ事件」を直視する場合にも、その背景にあるこの飢餓と富の偏在の問題を無視することはできないでしょう。作家の辺見庸氏は、それを「朝日」('01・10・09)で、つぎのように述べていました。
オサマ・ビンラディン氏の背後にあるのは、数千の武装集団だけではなく、おそらく億を超えるであろう貧者たちの米国に対するすさまじい怨念である。一方で、ブッシュ大統領が背負っているのは、同時多発テロへの復讐心ばかりでなく、富者たちの途方もない傲慢である。
現在、世界で食料を大量に食べ残し、捨てているのは、アメリカと日本で、その量は、アメリカが年間で四三六〇万トン、日本が一六〇〇万トンにもなっているようです。日本も戦後の食糧難時代には、日本人の一千万人が餓死するのではないか、といわれたこともありました。しかし、半世紀の後、世界第二の経済大国になって飽食にも慣れきってしまいますと、私たちも、世界のそういう飢餓状態の人々のことには、つい無関心になってしまいがちです。アフガニスタンでは、人口一六〇〇万のうち、六〇〇万人もが飢餓にさらされているといわれていますが、日本の家庭で一年間に食べ残して捨てている量は、アフガニスタンの人々が食べる三年間の穀物の量と同じになる、というようなことも、時には考えてみる必要があるのかもしれません。
人間は、二十一世紀の現在に至る数千年の人類の歴史を経て、生活の向上を目指し、極めて高度の物質文明を築き上げてきました。しかし、そのようにして手に入れた物質的な豊かさに反比例するように、人間的な優しさや思いやりの精神的な豊かさからはむしろ遠ざかってきているように思えます。このまま、この人間のこころの歪みが増幅されていくならば、はじめに取り上げた「核の時計」の警告が示すまでもなく、そう遠くない将来、人類全体の存在自体が深刻な危機にさらされることになるのかもしれません。
実は、人類がこのような危機的な状況におかれているのは、いまが初めてではありません。有史以前の太古にも、同じようなことが起こっていました。あの水没する前のアトランティス時代がそうです。そしてまた、実は、これは思い切った言い方になるのかもしれませんが、私はかってアトランティスに生きていました。私だけではありません。皆さんの多くの方々もそこで生きていたはずです。ただ私たちはその記憶を、いまではこころの奥深くに閉じこめて、すっかり忘れてしまっているだけなのです。
一 アトランティスの消滅
私たちが世界史の中で理解している人類最初の文明は、五千年くらいまで遡れます。いわゆる四大文明としてのメソポタミア文明、中国文明、エジプト文明、それにインド文明などがあり、そこから始まったのが人類の歴史であると私たちは考えてきました。それ以前の歴史については、学問的に実証されていません。現段階で言えるのは、それ以前の歴史の一部が科学的にも証明されつつあるということぐらいでしょうか。しかし、現在までの学問の水準で実証されていないから、それまでの歴史がなかったとは言えないのです。
前回の講演で、私は霊能者浅野信さん(A氏として紹介)のリーディングについてお話しましたが、浅野さんは、アトランティスの存在は、「当然のことであり、事実であることが判明している」と述べています。浅野さんは、リーディング能力では世界でもトップクラスの一人といわれていて、霊界の情報・資料などもかなり自由に引き出して読めるようです。その浅野さんによれば、アトランティス時代は世界の四大文明よりもはるか前に、紀元前二〇万年頃から紀元前九六〇〇年頃まで、約一九万年も続いたということです。
アトランティスは、もともと、大西洋に位置するあたりに、ヨーロッパとロシアを含めたほど大きな広がりをもっていました。そのアトランティスが、一度目の紀元前五万年頃の大異変、二度目の紀元前二万八千年頃の天変地異などによって大きな打撃を受けます。そのために、だんだん大陸が小さくなっていったところへ第三の数百年も続いた大洪水が起こり、完全に消滅してしまったのだそうです。
アトランティス時代が一九万年も続いたとすると、その間に文明は相当な発達を遂げたであろうことは容易に想像できます。事実、水没当時のアトランティスは高度の文明をもっていました。浅野さんは、その科学技術力はむしろ現代のもの以上であったと、つぎのように書いています。
科学技術は、紀元前五万年以降、段々、発達を見、紀元前一万年頃にピークに達しました。
ファイアー・ストーンがポセイディアの都に置かれ、それが通信にも使われるようになり、医療、特に蘇生術でそれはふんだんに活用されました。しかし、逆に人体を破壊するということも起きたのです。
レーザー光線はアトランティスの特徴であり、また、電気がアトランティスのエネルギーの元になっています。それでアトランティスは電気の時代とも言われたのです。当然のことながら、コンピュータもアトランティスから出ています。
また、空中からエネルギーを取り出すという永久エネルギーに注目し、空間に関する感覚を 持っていたために幾何学を発達させ、それは一部、建築術として応用されました。④
このなかの「ファイアー・ストーン」というのはよくわかりませんが、浅野さんの本に、アトランティスが消滅した直接の原因として、「恐怖のクリスタルと呼ばれるようになった大結晶体、ファイアー・ストーン」に触れている箇所があります。そのファイアー・ストーンを「間違って最大出力まで目盛りを高めてしまった結果、火山の爆発を誘発し、それが地底を揺るがして大洪水を引き起こし」てしまった、というのです。⑤ 現代社会の、原子力エネルギーのようなものを考えればいいのかもしれません。
では、このように高度の文明を発達させていたアトランティス人は、水没の際どうなったのでしょうか。浅野さんの話では、生き残った人々は、アトランティスの遺産を子孫のために残しておかねばならないと考え、一部の人たちは北アフリカの土地を選んで、エジプトにたどり着きました。中央アメリカのユカタン半島やペルーへ移った人たちもいたようです。エジプトでは、彼らは侵略者として勢力を拡大し、統治者となっていったといいます。そしてその後、紀元前三千年頃から、エジプト文明は世界史のなかに足跡を残すようになったのです。
紀元前三千年といえば、日本ではまだ縄文時代のそれも早期で、あの邪馬台国の女王・卑弥呼が初めて歴史に登場してくるのは、その後さらに三千年以上も経った二三九年からのことです。エジプトは、なぜ五千年も前にあれほどの文明をもっていたのか、現在でも解明できていない謎が多いのですが、それらの謎も、このようなアトランティス水没以後の文明の流れのなかで見ていきますと、いろいろと辻褄が合い、納得できるように思われます。
例えば、カイロ郊外のギザの三大ピラミッドは、四千五百年前頃に造られたといわれてきましたが、その配置は、天文学的に驚くほどの正確さでオリオン星座の三つ星と対応していることが学術調査で明らかにされています。三つのなかで一番大きい、いわゆる「クフ王のピラミッド」は、数学的には四つの三角面をもつ正確な投影図となっていて、ほとんど誤差のない精度で地球の北半球の四万三二〇〇分の一に相当する大きさであることもわかってきました。しかし、なぜその当時、これほどの精密な天文学や数学の計算ができたのかは、まだ謎であったのです。
この「クフ王のピラミッド」は、底辺の一辺が二三三メートル、高さは一四六・五メートルで、平均二・五トンの石灰石が二三〇万個も積み上げられています。この大きな石を一〇〇メートルを超える高さにまで、しかも頂点が正確に中心に来るように積み上げるのは、現在の建築技術でも決して容易ではありません。四千五百年前にそのような建築技術がすでにあったという事実には、当然、それまでの何千年にもおよぶ文明の発達過程を前提にしなければならなくなります。その発達過程の文明はどこにあったのでしょうか。
また例えば、ピラミッド内部のクフ王の玄室とされる部屋は、幅五・二メートル、奥行き一〇・四五メートル、高さ五・八メートルの広さですが、壁は七〇トンの石を一〇〇個、寸分の隙間もなく積み上げて造られ、天井は一枚が五〇トンもある花崗岩九枚で船底型に覆われています。この玄室の西側には花崗岩をくり抜いた蓋のない石棺がありますが、これらを綿密に調査したジャーナリストのグラハム・ハンコック氏は『神々の指紋』のなかで、「この狭い空間の中でこのような巨大な石を持ち上げて天井を造る方法は不明」だし、石棺をくり抜くには、「現在のダイヤモンドヘッドのパワードリルよりも五百倍速い速度で岩をくり抜かなければならない」が、そのような工具は発見されていない、と述べています。⑥
現在でも不可能と思えることが、なぜ、その当時可能であったのでしょうか。
これらの謎も、アトランティス文明の遺産の流れを視野に入れて考えれば、不思議ではなくなります。
スフィンクスについては、さらに大きな謎がつきまとっていました。その一つは、スフィンクスやまわりの石の壁にはっきり見られる、波状の浸食の跡についてです。私も現場で見ていますが、それが最近の地質学的調査で、石灰石に刻まれたその浸食の跡は、数百年にわたり雨に激しく打たれてできたものだということが明らかになったのです。
スフィンクスは、紀元前二千五百年頃、カフラー王によって建立されたと考えられてきました。しかし、紀元前三千年頃にエジプト王朝時代が始まってからは、ギザにはあまり雨が降っていません。この地域に大量の雨が降っていたのは、サハラ砂漠がまだサバンナであった紀元前一万年よりも前のことです。そうすると、このスフィンクスは、その頃にはすでに存在していて、激しい雨に打たれていたということになります。
巨大な岩盤を極めて高度な技術でくり抜いて造られたこのスフィンクスの存在は、もう一つの、文明の発達についての重大な問題を投げかけることになりました。ここでも、エジプト文明のさらに数千年以上も前に、いまは人類が忘れてしまっている別の高度に発達した文明が存在していたはずだ、という極めて合理的な推論が成り立つことになるのです。⑦
以上、ピラミッドとスフィンクスを中心に、想定しうるアトランティスからエジプトへの文明の流れのひとつを見てきました。冒頭で、私はアトランティスに生きていたことがある、と述べましたが、実は、エジプトでも生きていたことがある、ともいわれています。アトランティスとエジプトだけではなく、イスラエル、ペルシア、ローマ、日本、イギリスなど、いろいろな国での前世を私は聞かされてきました。私は、何度も何度も生まれ変わってきて、いまここにいるのです。そして、これは、皆さんも同じです。ここでもまた、繰り返しますが、そのいろいろな国で生きてきた記憶を、私たちはこころの奥深くに閉じこめて、いまはすっかり忘れてしまっているだけなのです。
二 私と長男の生まれ変わり
私たちは死んでも死なず、何度も生まれ変わりをくり返すものですが、皆さんのなかには、この輪廻転生を話には聞いていても、いまひとつ実感がわかない方もおられるかもしれません。ましてアトランティス時代に生きていたといわれたりすると、さらに現実味が乏しく、なにかしら絵空事のよう思えることもあるのではないでしょうか。しかし逆に、こんな時代にも生きていたということが、具体的な事例を通して納得できたら、生まれ変わりがほかならぬ自分自身の問題であることも、より強く意識されることもあろうかと思われます。そんなことを考えながら、私は、ここでもあえて、私自身といまは霊界にいる長男の、アトランティス時代からの前世を例示することにいたします。私は、つぎのようにいわれたことがありました。
あなたはアトランティス時代に科学者でした。若手の有能な科学者として始まり、薬理学の研究について進めていました。あなたはいわば国家公務員であり、アトランティスという国の公立の研究所の中にいて、ケミカルなことの究明をはかる研究チームの一員として仕事のスタートを切ったわけです。
あなたが若年の頃、実際に現場で技術者達と研究していたことは、純粋な原理や理論に関することが主でしたが、あなたが長じて昇進し、課長から部長的な職に任じられるようになってから、アトランティス末期の時代ゆえに国家的な紛争や戦争が頻発するようになり、そのことにあなたの研究所も引き込まれる羽目になりました。それで、管理的な役についていたあなたは、直接研究に従事していなかったとはいえ、あなたが管理していたあなたのもとでの研究は、そのケミカルなことを戦争の化学兵器に適用するということに方向づけられていったのです。
あなたはそのことにうすうす気づくようになりました。けれどもあなたは、それを、国家への忠誠を誓うということで、また、職を失うことを恐れたために、結果的にそれを認めてしまったのです。それで、それが実際の戦争に使われるようになって、多くの犠牲者を出すことになったわけです。あなた自身がその研究に携わっていなかったとはいえ、実際にあったことの責任の一部をあなたはとることになりました。
これは、一九九三年の十一月に、浅野さんから受けたリーディングの一部ですが、ここでいわれている「戦争の化学兵器に適用する」というのは、現代でいう生物化学兵器のようなものかもしれません。いづれにせよ、アトランティス時代の私はそれを知っていながら、国家への忠誠とか、失職を恐れて、実際に使われることを認め、多くの犠牲者を出してしまったようです。それがひとつのカルマとして残り、現世の国際的な大事件のなかで、家族を失うという結果につながっていった、とリーディングでは伝えられました。さらにこのリーディングは、つぎのように続きます。
けれども、それはすんだことです。すんだことによって、つまり結果を受けたことによって、それは清算されたのです。それ故もはや恐れる必要はありません。けれどもそれが起こったことの真意をはじめてあなたが聞くことができたということは、カルマが解けたうえに、あなたがそのようなことを聞くところにまで、あなた自身の準備が整ったということです。それだけあなたの魂が強くなり、成熟してきたからであります。
米ソの冷戦の狭間のなかで妻と長男を失ってからは、私は何年もの間、悲しみながら、苦しみながら、必死に生きる道を模索していました。生とはなにか、死とはなにか、という大きな問題を否応なく突きつけられて、私は藁にもすがる思いで、仏典や聖書を繙くようにもなりました。無明の闇にさまよっていたその頃の私については、このセミナーの最初の講演集「いのちを慈しみ明日に向かって生きる」のなかにも触れてあります。結局、そういう過程が私には必要だったのでしょう。このリーディングでいわれているように、そのような学びを経たあとで、私は「起こったことの真意をはじめて聞く」ところまで、私自身の準備が整ったのだということになるのかもしれません。
このアトランティスで一つの人生を送ったあとの私は、浅野さんのリーディングによれば、エジプトに二回ほど転生し、イスラエルやペルシアのあたりにも転生しているようです。そして、さらにいろいろな転生を重ねたあと、日本に転生して応神天皇の時代に生きていました。このときは、前回の講演集のなかでも触れておきましたように、私が日本と中国との間で「国際関係での重要な役目」についていたことになっていますが、これも、意識してはいなかったかもしれないにせよ、アトランティス時代のカルマを解消するための献身のひとつであったということになるのでしょうか。
生まれ変わりというのは、後でもまた触れますが、しばしば、人間関係の強い絆で結ばれていた人々が、新しい人生においても、同じような人間関係を選んで生まれ変わることが多いといわれています。皆さんの場合も、多分そのような生まれ変わりをしてきているはずです。私と長男との関係でも、幾度も同じように転生をくり返しながら、親子や親戚であったり、師弟であったりと、深い人間関係を保ち続けてきました。浅野さんのリーディングでは、いまは霊界にいる私の長男の生まれ変わりも、つぎのように、アトランティス時代から始まっています。
彼は、アトランティス時代に、その大陸に生きていました。精神的なことに造詣が深く、精神的な分野を科学にしようとして、その研究に励んでいました。当初は学問としてそれに打ち込んでおり、その仕事の中で、より民間の、いわゆる在野の研究者たちや実践家に出会うようになって、一つのショックを受けたことがあります。
それは、それまで自分は精神的な分野のプロであり、研究者として名を馳せつつあり、一人前であると思っていたのです。けれども、無名の民間の実践家たちの実際的な能力や活用方法においての秀でた面や、一般の大衆を惹きつける力や魅力というものにおいて、自分以上のものをそこに見たのです。それで彼は一つのショックを受けて、はたして自分は自分を自分として認識していたのだろうか、私のは単なる理論であって、生きている人のために役立っていないのではないだろうか、ということで悩みはじめたのです。
このように、私の長男は、アトランティス時代には精神的な分野の研究者として生きていましたが、学問や研究だけでは、人々を惹きつけることはできないと考えるようになりました。やはり実践が伴わないと学問も研究も活きてこないのです。長男は在野の実践家の能力を知ってショックを受け、学問一筋に生きている自分の人生とは何であるのか、と悩むようになります。リーディングはさらに、つぎのように続きます。
彼のなかにそのような精神的な動揺と不安が生じ、そして次第にそれが恐れへと進んでいったのです。それは後に転生するまで、ずっと彼のなかに残っていました。普通の人ならそこまで深刻に悩むことはなく、彼が真面目で真っ直ぐにものごとを捉え受け止める人であるためにこそ、そのような悩みを持つことになったのです。そしてそれ以降の彼は、それを解決するための輪廻転生となっていったのです。
彼は非常に純粋な人であり、魂の持ち主でした。エジプトに転生したときは、芸術方面に自分の能力を見いだし、自然の造形美を彫刻したり、あるいは絵に描いたりということに自分の天職を見いだしていました。続くギリシアの人生においては、今度は詩人として精神的なこころの美しさ豊かさを美しい詩に創造し、人々のこころを強く打つことができました。それで彼の遠い過去生の精神的な不安や自身の喪失というものが、それによって多少癒やされていったのです。
そのようなときに、キリストの弟子たちがギリシアにやってきて伝道するようになり、キリストの愛の教えに触れるようになりました。すでに彼はこころの準備ができていたので、キリストの説く無条件の愛、そして愛の力というもの、またその効果というものにふれることができたのです。それによって彼の芸術的な資質に愛が加わるようになり、彼のこころは次第に、人々への献身、そして犠牲的な行為もいとわぬ魂へと成長を遂げることができたのです。
この「犠牲的な行為もいとわぬ魂に成長」を遂げた長男の姿は、私には、それから五年後のリーディングで、長男から伝えられたメッセージの内容と重なって映ります。前回の講演集「生と死の彼方にあるもの」に書いたなかには、「お父さんと僕とは、前世において何度か、国際関係のなかで重要な役目を果たしてきた使命のパートナー同士でした。また、実際、肉の親子であったときもあり、たいそう可愛がってくれました」という長男の述懐があります。そして、「アトランティスの当時のカルマが動いて、もっと人類が魂のレベルで目覚めるように僕たち家族に働きかけだしたのです。もっとほかの人たちが目覚めるため、僕たちみんな四人が捧げられ、皆の目覚めのために尽力するように求められたのです」とも述べていました。
こうして「僕たちみんな四人が捧げられ」たのですが、娘と私の二人は現世に残りました。長男が、自分が母親と一緒に霊界へ旅立った動機について、浅野さんのリーディングは、さらに、つぎのように続いています。
そしてこの時代に、現在父親であるあなたの導きと教育があったということを非常に恩誼に感じていたために、今回の人生で、芸術や教育、ひろくは文化的な資質を育ててくれたあなたに対し、また、最終的には、キリストの愛へと導く間接的なきっかけを設けてくれた現在の父親であるあなたに対し、今度は彼がこの現代においてあなたを神の世界へと、特に真の神の愛というものをあなたに知らしめるために、キリストの犠牲的な愛の行為にでることになったわけです。
いま考えますと、長男がこのような「犠牲的な愛の行為にでること」を潜在意識のなかにもっていたことが、私にはよくわかります。そのことを示すいくつものことばがあり示唆がありました。昨年出版した『アメリカ・光と影の旅』のなかにもそのことに少し触れていますが、私は一九八三年の最後の別れの日にも、無知で鈍感であったために、そのことにはまったく気がついていませんでした。いまの私は、神の深く大きなみはからいのなかで、深い闇に差し込みはじめた一筋の光を頼りに、とぼとぼと、償いの道を歩んで行くばかりです。
三 アトランティス時代から現代へ
このアトランティス時代に生きたラムサという人がいます。彼は、現代のアメリカのJ・Zナイトという女性をチャネルにして、人類へのメッセージをいろいろと送ってきました。それはアメリカで本にまとめられてベストセラーになり、日本でも翻訳されて『真・聖なる預言』という書名で一九九五年に出版されています。このラムサは、なぜいま人類へのメッセージを送ってきているのでしょうか。それは、「人間が遠い昔に忘れてしまった遺産を、あらためて思い出してもらうため、そして、いまよりもはるかに高い視点でものごとを見ることを教え、あなたはまさに神の子で、永遠なる存在であり、神が常にあなたを愛し、守ってきてくれたことを理解してもらうためである」と彼は述べています。⑧
人間というのは、輪廻転生で生と死をくり返します。「はるかに高い視点」でいのちの実相を考えていけば、このことはよくわかります。しかしラムサの場合は、稀な例ですが、この地上界では三万五千年前に、一度の生しか生きることはなかったと言っています。このラムサのメッセージは、アトランティス時代の状況を直接伝えてくれているという点でも大変重要であると思われますので、ここでは彼自身のことばで自己を語っているところを引用してみましょう。
私はこの地上界では一度の生しか生きることはなかった。それはあなたの時間の概念でいうと、三万五千年前のことだ。アトランティア南部に位置していた最大の港湾都市オナイのスラムに暮らしていた、レムリアと呼ばれる地からやってきた巡礼の一団という、恵まれぬ人々の子として、私は無知と絶望のなかに生まれてきた。私がアトランティアに来たのは、この大陸 が崩壊し水没する前の「最後の百年間」と呼ばれていた時期のことだった。
当時、アトランティアはきわめて高い知性を持つ人々の文明で、科学の発展にも目覚ましいものがあった。それは現代科学よりもさらに高度で、たとえば「光」の原理を理解し、それをすでに使い始めていた。あなたがいまレーザーと呼んでいるものを使って、光を純粋なエネルギーに変換する方法を知っていた。光を使って移動する宇宙船さえ持っていたが、それは他の銀河系の生命とのコミュニケーションを通じて学んだ科学だった。その宇宙船はきわめて原始 的なものではあったが、そうは言ってもあなたには想像もつかない速さの移動も可能で、空中に浮かんでもいた。アトランティア人は科学と深い関わりを持っていたため、彼らは知性を崇拝していた。そうして、知性による科学がアトランティア人の宗教になっていたのである。⑨
ラムサは、これをアメリカ人女性ナイト女史の口を通して英語で語っているのですが、それを記録した英文は、美しくそして格調が高く、真理を伝える直截な力強さにあふれています。ラムサはアトランティスをアトランティアと呼んでいますが、ここでも、その当時の科学のレベルが、「現代科学よりもさらに高度」であると述べられています。
前述の浅野さんによれば、アトランティス大陸の崩壊後はオグ、アーリア、ポセイディアという三つの島が残されていました。このうち、オグ文明が後に中南米のペルーに伝えられ、アーリアは、アトランティス文明を継承してアーリア文明を興し、後のペルシアに影響を及ぼしました。残りのポセイディアの高度の文明が、エジプトに伝えられて、後に大ピラミッドやスフィンクスの建造に役立てられたということです。⑩ このピラピッドとスフィンクスの建造に役立てられたというのが事実とすれば、それはラムサがここで述べているアトランティスの高度の文明とも、辻褄が合うということになります。しかし、そのアトランティスも、高度の文明をもちながら、ほかならぬその高度の文明の故に滅んでいきました。つぎのようにです。
私が幼かった頃、世の中は荒れはて、生活は困難をきわめていた。その時点でアトランティアはすでにテクノロジーを失っていた。北部にあった科学の中枢がもうずいぶん前に破壊されていたからだ。光を使って移動する実験で、アトランティア人は、ちょうど今日の金星のように、当時の地球をすっぽりと包んでいた雲に穴をあけてしまっていた。成層圏に穴をあけたとき、大量の水が降り注ぎ、大寒波が襲ってきた。そしてレムリア大陸のほとんどと、アトランティアの北部が大海に呑み込まれてしまったのである。こうして、レムリアとアトランティアの北部の人々が南の地域に逃れてきていた。⑪
北部の科学が衰退し、テクノロジーがなくなってしまうと、南部も徐々に原始的になっていったといいます。アトランティスがすべて水中に没してしまう前の百年間は、暴君が情け容赦なく支配する野蛮国に成り下がっていました。このような暴君の非道な支配のもとでは、よそ者のレムリア人などは大地の排泄物と同じで、街をうろつく犬より劣る存在として扱われていたようです。その悲惨な状況は、ラムサ自身がつぎのように語っています。
オナイの街では、子供が虐待されたり、女が叩かれ強姦されるの目撃するのは日常茶飯事であった。アトランティア人が、ジャスミンとバラを浸した水で上等なハンカチを濡らしてそれを鼻にあてながら、道で飢えかかったレムリア人の側を通るのもよく見かけられた。私たちは臭くて不快な存在だったからだ。気体や光といったものに対する科学的理解が欠けた、魂も精神も持ちあわせていない知性のクズであり、存在にも値しないと考えられていたからだ。「知 性的な傾向」をもっていないがために、私たちは奴隷にされて畑で働かされていた。⑫
窮乏と飢餓の中で、辱めを受けた母とその結果生まれた妹とを相次いで失い、一人取り残されたラムサは、このような苦境のなかでも救ってくれようとしない神を憎みました。そして、神と一戦を交えて死のうと考えます。その時の彼はまだ一四歳の少年でした。骨と皮ばかりにやせ細り、こころに恨みと憎しみを満たした彼は、神はきっと高い山にいるのだろと考えて、地平線の彼方にそびえ立つ山を目指して何日も歩き続けます。やがて、山の頂に着いた彼は叫びました。「私は人間だ!
なのに、なぜ人としての威厳さえ与えられないのか?」 そして、神に顔を見せるように要求します。しかし、返事はありませんでした。彼の声が空しく谷間にこだまするだけです。彼は無視されたと考え、その場にしりもちをついて大声で泣き出したのです。
ラムサの運命はここから変わります。やがて神秘の女性が現れ、彼に大きな剣を授けて「この剣で自分を征服するのです」と言って消え去りました。その剣をもって山から降りたラムサは、身体のまわりに光をたたえた屈強な若者になっていました。それからの彼は、アトランティア人に戦いを挑み、オナイの街を焼き払い、穀物倉庫を開けて同胞の貧しいレムリア人に食料を分け与えました。こうして彼は、征服者になり王となっていきます。彼はまさに英雄でした。「英雄とはどんなものかおわかりだろうか。英雄とは、どん底にある社会を救い、その不条理を正そうとするが、その過程で自分も不条理をつくりだしてしまっていることに気づかない人間のことだ」とラムサは言っています。そして、神についての彼の思考が始まるのです。
確かに私は偉大な戦士だ。剣をもってすれば一瞬のうちにどんな相手でも真っ二つに裂くことができる。首を斬り、切り刻み、血の臭いを嗅ぎ、人を焼きもした。だが、いったい何のためにそんなことをしてきたのだ?太陽はそんなことに関係なく、目を見張るような美しさで沈んでいく。夜鳥はいずれにしても鳴く。何があろうとも、月は昇ってくるではないか。
私が「未知の神」について思いをめぐらせ始めたのはこの時であった。私が本当に求めてたのは、この恐ろしく荘厳で神秘的なもの、信じがたいほど遠くにあるものを理解することだけだった。それに、人間とはいったい何なのか? なぜ人間は太陽より偉大ではないのか? この地上界にこれほど大勢いて、その想像力の源泉であり、すべてを統一する力である人間が、すべての生き物の中で一番脆弱な存在であるのはなぜか? わが臣民が言うように、もし人間がそれほど重要な存在ならば、その人間が死ぬとき、なぜ太陽がその動きを止め、弔いをしてくれないのか? あるいは月が紫色にならないのか? 鳥は飛ぶのをやめないのか? 人間にはあらゆる危険が迫ってきても、すべてのものは何事もなかったように続いていく。人間は全くとるに足らない存在ではないのか? 私は、ただそれを知りたかった。⑬
この「未知なる神」というのは、レムリア人が考えていた神のことです。しかしラムサは、その神について教えてくれる師を持っていませんでした。 彼に神について教えてくれたのは、常に本当の意味での師である人生そのものでした。彼は昼から学び、夜から学びました。破壊と戦争の真っ只中にあっても、そのおびただしい数のひ弱な人間のいのちから学びました。ラムサはまた、太陽の輝きに思索をめぐらし、それが、東から現れて大空を旅し、西の空に没する姿を見守っていました。沈黙を守ったまま太陽が、霊妙な形で人間を支配していることを学びました。戦場の勇者たちがどんなに果敢に戦い続けたとしても、太陽に逆らうことはできません。日が沈めばその戦いは止むのですから。
彼は徐々に神についての理解を深めていきました。そして彼は、次のように確信していったのです。
「未知なる神」とはいったい誰なのか。それは私である。そして、夜の巣に憩う鳥たちであり、葦に宿る霜であり、朝焼け、黄昏の空だ。さらにそれは太陽であり、月であり、子供たちであり、その笑い声であり、白いなめらかな足であり、流れる水、ニンニクと革と真鍮の匂いだったのだ。それはいつでも私のすぐ目の前にあったのに、それを理解するのに長い時間がかかってしまった。「未知なる神」は、月や太陽を超えたところにあるのではなかった。それ は、私のまわりのすべてにあったのである。この見方が私の内に新たに生まれてからは、私は人生を受け入れ、自分にとって大切なものをしっかりと守り、生きて行くべき理由も見つけられるようになった。血や死や戦争の悪臭のほかにも、それ以上に価値のある存在があったのだ。それがいのちなのだ。いのちこそ、私たちが思っていたよりはるかに偉大なものであったのだ。⑭
この気づきによって、ラムサは、その後の長い年月を通じ、確かに人間こそがすべての存在のなかで最も偉大な存在だということが理解できるようになっていきます。そして、一度だけの生を終えて、高次元に昇華してから、三万数千年の時を経て、今度は地上の私たちに、自分が学び知ったいのちの尊さを伝えようとしているのです。例えば彼は、人間が死ねば灰になってそれで一生は終わると考えるのは、大いなる幻影であるにすぎないと言います。人間にとっての死とは肉体だけの死であって、肉体のうちに在り、それを操る本質の部分は、もしそれが望むならば、すぐにでもまた別の肉体に宿り、さらに生き続けていく、というのです。それをラムサは「生命は決して終わることはない。確かに身体に危害を加えることはできるであろう。首を斬ることだろうが、内臓をえぐり出すことだろうが、やろうと思えばどんな残酷なことでもやれないことはない。しかし、その肉体の中に生きるいのちは、絶対に滅ぼすことができない」と述べて、いのちの永続性を強調しました。そしてそのあとで、つぎのように私たちに語りかけています。
あなたは誰なのか? なぜいまここにいるのか? あなたの生きている目的と運命とはいったい何なのか? あなたは自分が単なる偶然の産物であり、ほんの短い時間だけこの世に生きて、つぎの瞬間には消滅するためだけのために生まれてきたと思うのだろうか?
あなたはこの地上界に何千回と生きているのだ。まるで気まぐれな風のように、戻っては去っていった。あらゆる顔や肌の色、主義主張や宗教を体験している。戦争を仕掛け、仕掛けられ、王と召使いの両方を同じように生きてきた。船乗りや船長にもなった。征服者や被征服者 にもなった。自分の歴史の理解の中にあるすべてのものにあなたはなった経験がある。それはなぜか?
感じるため、智慧を得るため、そして、あなた自身というもっとも偉大な神秘を解
き明かすためだ。⑮
四 ラムサの教え
人間の生まれ変わりについては、講演集第一集「いのちを慈しみ明日に向かって生きる」のなかですでにくわしく触れてきました。生まれ変わりは、ほとんど「証明された事実」だということも、死んでから生まれ変わるまでの期間は、最低十カ月で最高は八百年以上という調査例があることなどについても、述べてきました。この「何千回も生きて、自分の歴史の理解の中にあるすべての者にあなたはなった経験がある」というラムサのことばには、あらためて生まれ変わりの不思議を考えさせられますが、彼はこうも言っています。
あなたは自分がいったいどこからやってきたと思っているのだろうか? あなたは単にひと つの細胞から進化した細胞の集合体であるだけなのか? それなら、あなたの目の奥からじっと見つめているのは誰なのか? あなたにあなたの独自性や人格、性格、魅力を与えている本質とは何か? 人を愛し、抱擁し、希望と夢を持ち、そのうえに創造するという偉大な力まであなたに与えているのはいったい何なのか? あなたが子供の頃にすでに見せていた知性、知識、智慧はどこで積み重ねてきたものなのか? 永遠の中で見ればほんの一呼吸にしかならないいまの人生の中で、あなたはいまの自分になったと思っているのだろうか?⑯
この引用文の最後の、「永遠の中で見ればほんの一呼吸にしかならないいまの人生の中であなたはいまの自分になったと思っているのだろうか」というのは、大切なそして鋭い問いかけだと思います。ここで、そのことについて少し考えてみることにしましょう。
私たちの社会では、常識的によく、胎児は「十月十日」で生まれる、などと言ったりします。「十月十日」というのは旧暦での計算だそうですが、しかし、人間一人が十月十日で出来上がるわけでは決してないでしょう。まず、十月十日で生まれてくるようないのちの誕生の仕組みができあがるまでには、気の遠くなるような時間が必要でした。その時間をどのくらいの長さで捉えていけばよいのでしょうか。
私は、少なくとも、この地球上に生命が芽生えた三十五億年前からの時間を考えなければならないと思います。私たちの一人一人は、その三十五億年の生命進化の歴史を間違いなくDNAに刻み込んで体内にもっているはずです。しかし、その生命が芽生えるための準備期間も考慮に入れると、やはり、地球誕生の四十六億年前に溯って考えるべきなのかもしれません。
ラムサは「生命は、あなた方が何十億年とよぶ一瞬のあいだに、一連の段階を通って発達した。そして、聖なる瞬間がやってきて、あなた方は海という生命の水から陸地へ上がり、いまのようなかたちをとるようになった」と言っていますが、このように、生命はまず、海の中から生まれました。地球最古の生命の化石が一九七六年にオーストラリアで発見されていますが、これは、ストラマトライトという海中の生物からできた三十五億年前の化石です。このストラマトライトが、太陽光線に反応して酸素を放出し、新しい、酸素によって生きる生物の誕生に結びついていきました。この生命については、二十億年くらい前までさかのぼれるようです。
約十億年前には、それまでの単細胞生物から多細胞生物へと進化していきますが、すべての生物は、人間をも含めて、この時期にあらわれた生物の子孫ということになります。五億年前になりますと、爆発的な生物の進化がみられるカンブリア紀を迎えます。そして四億年前には、空気を呼吸する能力をもつ肺魚があらわれ、生命の海から陸への進出が始まりました。五千万年前には、犬に似た動物が逆に、陸から海へ帰っていったこともありましたが、これがいまのイルカやクジラの祖先です。
人間はシーラカンスという魚から進化してきたと考えられています。この魚のヒレが長い年月を経て、サルやヒトの祖先の手足になっていきました。さらに時が流れて、ヒトの祖先はオランウータンから分かれ、ゴリラとも分かれて、五百万年くらい前には、チンパンジーとも分かれます。
その頃、ヒトの祖先でもあったチンパンジーはアフリカに住んでいました。そのアフリカで、大規模な地殻変動が起こり、その当時のアフリカの森林は南北に走る大山脈によって二分されてしまいます。そして、山脈の東側では、西風と雨が山脈に遮られて、徐々に乾燥化がすすみ森林が消えていったのです。
この森林が消えてしまった東側にいたチンパンジーがヒトの祖先です。何不自由なく暮らしていた森をなくして、チンパンジーは、仕方なく食料を求めて歩き始めました。これがやがて二足歩行の猿人になります。アファール猿人と名付けられた三百万年前の骨がアフリカの東側で発見されています。
DNAの鑑定によりますと、その後もヒトの祖先は、ジャワ原人、北京原人、ネアンデルタール人といった系統とも分かれて、およそ二十万年前にアフリカから地球上に広がっていきました。そして、住み始めた環境によって、現在の白人、黒人、黄色人種などになっていったのです。
この魚から始まって、ヒトになっていった数億年分の過程は、人間の胎児が、母親の胎内の羊水のなかにいる十か月の間に、忠実にたどられていきます。この羊水は、原始の海と成分がよく似ているといわれます。魚であった名残のエラは、受精後四週間目に現れ、やがて、下あご、のど、耳の一部になっていきます。ヒレの部分も手と足に発達していきます。尻尾も四週間目に現れますが、これは六週間目から消えていきます。一言でいえば、十か月の中に、数億年分の発達過程が凝縮されて詰め込まれているのです。
生命の準備期間としての数十億年、それに魚になってからの数億年、チンパンジーと分かれてからの数百万年、これらのうちの一年が欠けても、私たちは人間として生まれることは出来ません。また、アフリカから地球上に広がっていった原人の時からでも、二十万年間の長い命の連鎖が、一度でもどこかで切れたら、私たちはこの世に存在することは出来ません。そのようにみてきますと、この世に生を受けた人間の一人一人は、一人の例外もなく、選んで選んで選び抜かれた奇跡の存在であることがわかってきます。
しかし、これも宇宙の中では米粒一つにもならないような地球に限定した見方です。私たちは確かに地球に生まれましたが、地球は生存環境のすべてではありません。さらに視野を広げてみていけば、その地球も、銀河系のなかの小さな一つの惑星に過ぎないのです。その銀河系の直径はだいたい十万光年であるといわれています。光の速さというのは秒速で三十万キロですから、その速さでも十万年かかる距離ということになります。月の光が地球に届くまでの時間はわずか一・三秒、太陽からは八・三分と比べると、銀河系がいかに広大であるかがわかります。
この銀河系の中心部はアルジとよばれる年老いた星の集まりで、その周辺部には若い星々が群がっています。その星の総数は約二千億といわれています。そして、その銀河系もまた、宇宙の中の一千億を越える銀河系の一つに過ぎません。このように見てくると、私たちのいのちの誕生を考えるのには、地球誕生の四十六億年前よりさらにずっと遡って、宇宙誕生のビッグバンまでの一五〇億年の時間を考えるべきなのでしょうか。
一五〇億年前にビッグバンで始まった宇宙は、強烈な光のもとに、時が刻み始め、猛スピードで膨張する空間に多量の物質が創成されたと考えられています。この世界のすべての存在の根元が、このエネルギーに満ち満ちた「真空」から生まれ出たのです。何も存在しない「無」の状態に詰め込まれた巨大エネルギーが爆発して、宇宙そのものが具体的な姿をとって立ち現れました。私たちが、光を懐かしく感じるのは、ビッグバンの光が私たちの存在の原点であることを、どこかに記憶しているからかもしれません。
このビッグバンは、神の光そのものとしか思えませんが、ラムサはさらにこうも言っています。
あなたは自分を創造したのは両親だと思っているのであろうか。あなたの両親は、遺伝的な意味では確かに親ではあるが、あなたを創造したのではない。より大きな真実の意味では、彼らは愛すべきあなたの同胞だ。そしてあなたは彼らと同じくらい年を重ねてきている。なぜなら、すべてのいのちは同じ瞬間に創造されたからだ。すべては偉大で崇高な思考である神が、己に思いをめぐらせ、自分を拡大して輝ける光となったときに生まれたのである。あなたの本当の親は神なのだ。すべての生命の父母原理を体現する神そのものなのだ。
あなたは自分の体が自分であると考えているであろうか。それは違う。あなたの肉体とは、あなたの真の姿である眼に見えない本質を包み込んでいるマントにすぎない。その真の姿とは、あなたの肉体のうちにある人格=自己という、感情や価値観の集合体のことだ。⑰
世間では、母親が子に向かって、「おまえを生んだのは私だ」と言うようなことも珍しくはありません。しかしラムサはここで、親は子を創造することはできないと言っています。意外な表現のようですが、しかしこれは、科学的あるいは確率論的な見方からいっても、そうであることがわかるでしょう。人間誕生の過程を考えてみれば、親は共同作業で子を産むことはできても、一人一人の子を選んで産むことは決してできないからです。
人間の誕生は、いうまでもなく、母親の卵子と父親の精子の結合によってもたらされます。数百万から選び抜かれた細胞から卵子は月に一つずつ放出されますが、その数は女性の一生のうちでわずか五百であるにすぎません。その卵子を目指して放出される精子の数は一度に三億とも四億ともいわれます。しかし、その精子がミクロの世界のなかで抜きつ抜かれつの壮絶な勝ち抜きレースを展開して、やっと勝ち残ったわずか百前後が子宮の入り口までたどり着いても、そこに目指す卵子がいるとは限らないのです。
数百万の細胞の中から選び抜かれて育った卵子が、卵管を通って子宮に移動するまでの数時間だけが受精可能で、そこで無事に卵子とたった一つの精子が結ばれる確率の低さは、ゼロに限りなく近いといってよいでしょう。つまり、一つの勝者の精子が無事卵子と結合できるまでには、おそらく数十億あるいは数百億の敗者の精子が勝ち抜きレースから脱落するわけです。この勝ち抜きレースの主役は一人一人の「子」であって、決して親ではありません。親は、この勝ち抜きレースに誰が勝とうが誰が負けようが、その選択には全く関わることができずに無力なのです。
このように親は、遺伝的には確かに親ですが、どの子を産むかを選ぶことはできません。選ぶのは、子の側でありえても、決して親ではないのです。そして、もし子の側にそのような主体的な選択の意志が認められないというのであれば、残された可能性としては、神の意志とでも考えなければならなくなります。これは科学的レベルで捉えた真理の一端に過ぎませんが、子は本当に親を選ぶのでしょうか。これについては、つぎのような霊界からの貴重な証言があります。
人はみな永遠の存在である。腕に抱かれた幼子や赤ん坊も、星々と同じく大昔から存在している。意識は永遠であり、不滅なのだ。
人は自分の人生の境遇を選択する。もしこちらの領域に来てみたなら、皆さんの世界に生まれ出る機会を切に待ち望む、数知れない仲間たちを目のあたりにするだろう。彼らは地上の喜びと豊かな環境を懐かしがり、切望している。また多くの人にとって、魂の領域自体も学ぶべきことは多いのだが、「地球学校」という意義深い領域にとってかわることはできない。
赤ん坊はすっかり成熟した完全に進化した魂であり、魂の領域では成人の姿をして見える。もし彼らの魂がこの世でさらに学ぶように駆り立てれば、彼らは、自分たちが入っていくのにふさわしい環境を検討し探す。彼らは母親を捜し、そして一種の宇宙の順番待ちのリストに登録する。家柄を慎重に調べ、適切な縁組みを探すのはわたしたちの領域にいる多くの者たちの仕事だ。そんなわけで、赤ん坊は皆さんの世界への新参者ではなく、おそらくその両親と同程度の年月を経ているのである。両親が子供から非常に多くのことを学ぶのも不思議はない。⑱
子供はこのように、自ら親を選んで生まれてきます。そして、前にも触れましたがほとんどの場合、人は自分の知っている親を選ぶといわれます。前の生で子供や親であった存在たちです。ただ、この地上界での自己表現の媒体を提供してくれるというだけの理由で、自分の知らない人を親に選ぶこともあるようです。また、自分が戻りたいときに、そのための媒体がないこともよくあって、場合によっては自分にあった化身を見つけるのに何百年と待たされることもあります。しかし、ラムサも言っているように、本当の意味で、人の母親、父親であるものは一人もいないのでしょう。すべての人間は、神という生命を分け与えられた息子であり娘だからです。つまり、私たちの誕生は「神の意志」であり、本当の親は神であることを知らねばなりません。
ラムサはさらに、子は親を選んで生まれるだけではなく、自分自身の人生をも創り上げていくと、つぎのように述べています。
あなたは、いったい誰が自分の人生を作ってきたと思っているのだろうか。自分以外の崇高なる知性、あるいは何かの偉大な力があなたの人生を支配してきたと思うだろうか。それはそうではない。本当は、あなたがしてきたこと、あなたの人となり、あなたが体験してきたこと、それらすべてはあなた自身に責任がある。無数の雄大な星を創造する力があるあなたは、自分の人生のあらゆる瞬間、すべての状況を創造してきたのである。どんな人間であるかは自分で選んできた。自分の容姿も自分で創造してきた。どういう生活をするかも、すべて自分で設計し決めてきた。それこそが神なる人に与えられた課題であり、特権なのである。⑲
これは、極めて大切な指摘ですが、私たちは、両親、生まれた祖国、生活環境なども含めて、自分の人生のすべてを選んでいるのです。同じく私たちは自分の人生の日時を選び、本当の自分を知るのに最適の過不足のない完璧なチャンスが得られるよう、人や出来事や環境を日々創造し続けています。
したがって、自分の魂が達成したい目標が何であるか理解できれば、私たちが人生の道を歩んでいくなかで、誰も不利な、あるいは不運な立場にいることはないということになります。たとえば、あるいは魂は、自分が障害のある身体で生まれたり、抑圧的な社会や厳しい政治的、経済的環境の中で生きたりして、この人生での仕事をしたいと願うかもしれません。自分が設定した目標を達成するのに必要な環境を創り出すためです。だから、物理的な意味では不利な、不運な立場に置かれているように見えることがあっても、本当は、無意識ではあるにせよ、的確で完璧な環境を自ら選んでいるということになるのだと思います。
お わ り に
大昔の人間は死をもっと身近な問題として捉え、天国や死後の生を現代よりもはるかに強く信じていたように思われます。肉体が死んだ後にもいのちは生き続けるということを、こころから信じている人がどんどん減っていったのも、ここ百年くらいのことではないでしょうか。そして、いままた人類は、環境破壊と人類滅亡のカウント・ダウンがささやかれる危機の中で、科学万能を信じ込みながら、生き続けようとしています。
実は、浅野さんによれば、現世界をリードするアメリカ合衆国は、もっともアトランティスに近いものをもっている国です。進取の精神、科学技術の発達、人種問題、エリート意識、支配したがる傾向、エゴイズム、あるいは個人主義、唯物的であること、そして、世界中に影響力をふるってきたこと、などがその特性です。アメリカは、一七八九年の建国から、せいぜい二百十余年のうちに、なんと一九万年にもおよぶアトランティスの歴史を急ぎ足でたどり直してきてしまいました。⑳ そしてそのアメリカのブッシュ政権は、昨年の「9・11テロ事件」以降、独善と独断の一国超大国主義に急速に傾斜しはじめています。
アメリカ政府は、ニューヨークのテロの犠牲者の遺族には、一人あたり平均で二億四〇〇〇万円支給すると発表しましたが、それとは極めて対照的に、アフガニスタンでアメリカ軍が誤って殺害した民間のアフガニスタン人遺族には、犠牲者一人あたり一三万円の慰謝料を支払いました。罪のない民間人が殺されたという点では同じなのに、なぜいのちの値段がアメリカとアフガニスタンで一八〇〇万倍も違うのでしょうか。その一方で、アメリカ政府は、ロシアや中国、北朝鮮、イラクなど、少なくとも七か国を核攻撃対象にしたシナリオ策定を軍部に指示して、力でアメリカの軍事力に屈服させようとしています。本稿の冒頭で取り上げた「核の時計」を表紙に掲載している米科学誌「原子力科学者会報」のスティーブン・シュオゥーツ編集発行人は、「こうした計画は危険で逆効果」とアメリカ政府を強く批判する声明を出しました。21
確かにいま私たちが生きているこの世界の生存環境は、人種や宗教の違いを超えた愛に支えられている平和で不安のない状況とは言えないようです。しかし、一方では、いまの世界のあり方に疑問を抱き、世界からこのような人間関係の極端な歪みを見直して、もっと優しさと思いやり満ちた世界にしていかねばならないと考えている人々が着実に増えてきているのも事実であろうと思われます。私たちは世紀末的な困難な状況のなかにあって、いまそのためにこそ、人間のあるべき姿は何であるかを考え、自分自身を見つめなおして、人間本来の霊性を取り戻そうとしているといってもよいのかもしれません。
私は、世界を変えていく原動力になるのは、結局はひとり一人が自分自身を知る、ということに尽きると思います。自分は誰か、なぜいま生きているのか、この生を終えたらどこへ行くのか。そういうことに思いをめぐらし、理解を深め、自分に与えられたこの世での使命とか目的が自覚できるようになれば、人間関係での差別、偏見、独善、不遜、強欲などからはおのずから遠ざかっていくことでしょう。自分を金縛りにしている物欲、金銭欲、色欲、独占欲、出世欲、権勢欲などのどろどろした汚濁からも解放されて、穏やかで安らかな生き方ができるかもしれません。
ラムサを含めて、いろいろな先人が霊界からのメッセージで伝えようとしていることは、いま私たちの置かれている生活環境が、本当は、自分を知るために、それぞれに最適であり、最善のものであるということではないでしょうか。長い長いいのちの歴史の中で、この困難に満ちた現世に生活環境を自ら選び、いま生きていることの意味は、おそらく、そのことを真に理解することではないかと思われます。
最後に、この小冊子が、これからの皆さんの人生に、少しでも道しるべとしてのお役に立つことをお祈りしながら、つぎのラムサのことばを引用して、この稿を終わりたいと思います。
あなたがいかに盲目で、真理を受け入れようとしなくても、いのちだけは永遠に持ち続ける。それが神と呼ばれるものの持つ特性だからだ。そしてその神とはあなたのことなのだ。22
注
1) 「朝日新聞」二〇〇二年二月二八日
2) 「朝日新聞」二〇〇二年三月二日
3) 「朝日新聞」二〇〇一年一二月一二日
4) 浅野信『アカシック・リーディング』たま出版、一九九七年、
一〇五~一〇七頁。
5) 浅野信、前掲書、九三頁。
6) グラハム・ハンコック『神々の指紋』下(大地舜訳)翔泳社、
一九九六年、七二~七四頁ほか。
7) グラハム・ハンコック、前掲書、一九二~一九七頁ほか。
8) ラムサ『真・聖なる預言』(川瀬勝訳)角川春樹事務所、
一九九五年、一〇頁。
9) ラムサ、前掲書、一五~一六頁。
10) 浅野信、前掲書、二二五頁。
11) ラムサ、前掲書、一六頁。
12) ラムサ、前掲書、一七頁。
13) ラムサ、前掲書、二六~二七頁。
14) ラムサ、前掲書、二九~三〇頁。
15) ラムサ、前掲書、七一頁。
16) ラムサ、前掲書、七一~七二頁。
17) ラムサ、前掲書、七二頁。
18) ジュディー・ラドン『輪廻を超えて』(片桐すみ子訳)人文書院、
一九九七年、一八~一九頁。
19) ラムサ、前掲書、七五頁。
20) 浅野信、前掲書、九三頁。
21) 「朝日新聞」二〇〇二年三月一三日。
22) ラムサ、前掲書、八二頁。
*翻訳書からの引用については、原書からの私の訳文に
替えている箇所もあります。
謝 辞
昨今の世情のなかでは、人々の生活は、うわべだけはものにあふれて豊かなように見えても、内面的には、落ち着きやゆとりが徐々に失われてきて、人々のこころは安らぎからも遠ざかっているように思えてなりません。世の中の動きに対する一抹の不安を拭いきれず、いまの暮らしぶりにも何か満ち足りないものを感じながら、人間にとっての正しい生き方をみずからに問いかけ、その答えを真摯に模索されておられる方も多いのではないでしょうか。
そのような折りに、今年も六月九日に恒例の特別講演として、武本昌三先生から「真実の自分を求めて」と題するお話をしていただくことになりました。毎年のご講演で先生は、この世に生を受けた意味と自分自身について知ることの大切さを強調されているように思われますが、今年のお話も、ご参集の皆様が、これからの実りの多い歩みのための確かな道しるべの一つにしていただくことができればと、主催者としても念願しております。
私たち、葬祭に携わっている者も、この講演会からは、いのちとは何か、生を終えてからどこへ行くのか、というような重大問題について、いろいろと学ばせていただきました。いのちの実相について理解を深め、葬祭のあるべき姿については常にこころを傾けながら、形だけの葬祭ではなく、誠心誠意のご奉仕をさせていただくことが、私たちの使命であると自覚しております。
ご講演のためにこの小冊子をおまとめ下さいました武本先生に改めて感謝申し上げますと共に、毎回、講演会に熱心にご参集いただいております皆様方にも、衷心より厚くお礼申し上げます。
二〇〇二年六月五日
株式会社 溝口祭典 代表取締役 溝 口 勝 巳
|