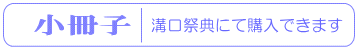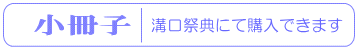【こすもすセミナー特別講演】
いのちの真実を求めて
ー生き続けて光に向かう私たちー
武 本 昌 三
人間は不滅なのです。死は無いのです。
あなた方が涙を流して嘆き悲しんでいる時、
その人はあなた方のすぐ側に立っている。
自分の存在を知らせようとして
何度も何度も叫び続けているのです。
あなた方こそ死者です。
本当の生命の実相を知らずにいるという意味で
立派な死者です。
---- シルバー・バーチの霊訓(本文二四頁)より
は じ め に
私は一九八三年夏には、アメリカのノース・カロライナ州に住んでいましたが、まったく予想も出来なかったあの九月一日の大韓航空機事件で、アメリカから帰国の途中の妻と長男が犠牲になりました。それからは何年もの間、悲嘆の日々を過ごしています。一瞬にして大切な家族を奪われ、永遠の別れになってしまったことが、ただ悲しく、そして空しく、生きていく気力も無くして絶望の淵に沈んでいました。しかし、いま考えますと、それは大きな勘違いであったように思われます。
妻と長男は、生きていました。肉体は滅びても、いのちは微塵も傷つけられることなく、元の姿のまま健やかに明るく、いまも生きています。いつまでも嘆き悲しんでいる私のそばに来て、自分たちは元気に生きているということを、一生懸命に知らせてくれようとしていたのに、死んだらすべては無であると思っていた私の耳には、何も聞こえるはずがありません。この小冊子の扉のことばのように、いのちの真実についてまったく無知であったという意味で、私こそ「死者」でした。妻と長男は立派に生きているのに、私こそ、本当は「死んでいた」のです。
その当時のことを思い出していますと、無知とは怖ろしいものだと、つくづく考えさせられます。藁にもすがる思いで、仏典や聖書を読んだりもしましたが、それでも、奪われたいのちはもう返ってはこない、という冷厳な「盤石の事実」に捉えられて、もがいても足掻いてもその事実からは抜け出ることが出来ず、仏前でお経をよみながらも、あまりの惨めさに泣きだしたこともあります。私は、なぜ、こんなにも惨めであったのでしょうか。
『歎異抄』第九段で、親鸞の弟子の唯円が、いくら極楽浄土がすばらしいところであると聞かされても、そんなにすばらしいところなら、どうして早く死んでそこへ行きたいと思えないのでしょう、と親鸞に聞く場面があります。それに対して親鸞は答えました。本当は手の舞い足のふむところも知らないほど喜ばなければならないのに、そうさせないのは煩悩のせいである。悩みや苦しみの多いこの世を去るのはいやがって、平安で幸せな極楽浄土を恋しいと思えないのは、よくよく煩悩が強いからに違いない、と。
いまの私には、この親鸞のことばがよくわかります。しかし、かつての私には、極楽浄土というのは、夢物語でしかありませんでしたから、こんなことばも何の慰めにもなりませんでした。死んでしまえば焼かれて灰になるだけだと思っていましたから、この地上か、極楽かという選択肢さえ頭にはまったくなかったのです。暗闇のなかでの呻吟は続きました。そして、そのような無明の闇から私が少しずつでも抜け出していったのは、事件後何年も経ってからでした。
やはり、このような無明の闇のなかにいるというのは、苦しいことです。そして、真実を知らないということほど自分を弱くするものはありません。そういう弱い私たちを見るに見かねて、私たちを救うために、霊界からは多くの人々が熱心に語りかけてくれているのでしょう。しかし、私たちは、それにはまったく気がついていないことが多いようです。私の場合も、長男から、(三年も経っているのに)「何時までも元気がない。お父さんは何でも出来る人ではないか」と言われたことがありましたが、霊能者のことばでそのように強く言われても、それでもまだ上の空でした。自分たちが霊界で元気に生きていることにいつまでも気がついてくれないという長男の嘆きと焦りが、その時のそのことばにはにじみ出ていたように思います。
私たちが物質世界のなかで生きている以上、物質的尺度でものを見る傾向が強いのはやむをえないことかもしれません。しかし、真理は真理です。いのちの真実は眼には見えない霊の世界にあることを、私たちは、本当の幸せのためにも知らなければならないでしょう。この真実に目覚めることがどうしても必要です。私たちは死んでも死なずに生き続けて、いのちは永遠不滅なのです。そして、霊界へ移ってからも、私たちは光に向かって気高く歩み続けます。私たちがこの世に生まれてくるのは、そのことを知るためだとさえ言ってもいいのだと思います。
よくあることですが、人生の苦しみから逃れようとして迷信にも縋ろうとするのは、寂しいことです。家族を失った嘆きのあまり、占いや新興宗教に走ったりするのも、悲しいことです。しかし、そういう人を哀れみながらも、肝心の自分自身のいのちの真実を知らないでいるのは、本当は、もっと寂しく、もっと悲しいことなのかもしれません。かつての私のように、それでは生きていることにはならないからです。生きていても、それは「死人」と同じことになるからです。
一 信じることの難しさ
遠藤周作さんは、皆さんもご存じの方が多いと思いますが、芥川賞作家で、一九九五年には文化勲章も受章しています。熱心なカトリック信者で、谷崎賞を受けた『沈黙』や読売文学賞を受けた『キリストの誕生』をはじめ、キリスト教に関する多くの著作も出されました。生涯をかけて、人間の生と死、信仰を見つめ続けた善意の人でもあります。
その遠藤さんも、しかし、イエス・キリストの復活のような奇跡は、信じていませんでした。聖書に書かれた数々の奇跡を、一生懸命に考えて説明し、彼なりの解釈をしていますが、やはり最後まで、復活は信じ切ることはできなかったようです。「死後の世界」についても、半信半疑で、その実在を信じることができないまま、一九九六年九月に、多くの読者に惜しまれながら急逝しています。
現代のような科学万能の時代では、死んだ人間のよみがえりとか、死後の世界や霊魂の存在などは、人間の「常識」からいってもあり得ないと考えて、あたまから受け付けようとしない人が沢山います。特に、科学者や知識人といわれるような人ほど、その傾向が強いと思われるのも、無理のないことかもしれません。遠藤さんのようなキリスト教徒をも含めて、教会の神父や神学者でさえ、信じられないという人は、決して珍しくはないのです。
でも、私たちは、地球の上で生きているというよりも、宇宙の真理のなかで生きています。広大な宇宙の広がりのなかでは、米粒一つにもならないようなちっぽけな地球にいて、その科学で解明できないものは存在しない、と断定していいものでしょうか。ほんとうは、科学を含めて私たちの知っていることは、真理のほんの一部にすぎないのであって、知らないことはまだまだ沢山あることを自覚する謙虚さが、特に現代の私たちには必要であるように思われます。
時代を問わず、確かに、霊の世界を信じるのは容易ではないかもしれません。そのことは、あの、イエス・キリストの弟子たちをみてもわかります。イエス・キリストは、偉大な霊能者の一人で、生前、自分が捕らえられ、十字架につけられて殺されることを弟子たちに正確に予言していました。そして、死んだあと、三日の後に甦ることも予言しています。しかし、そのイエスを敬愛する当時の弟子たちでさえ、実は、誰一人、その予言を信じてはいなかったのです。
ユダの密告でイエスが逮捕されたときには、弟子たちはみんな、イエスのように捕らえられることを恐れて、逃げ隠れていました。一番弟子のペテロでさえ、見咎められてイエスとの関わりを訊きただされると、そんな人は知らないと、三度もイエスを否認したくらいです。イエスが十字架につけられようとしても、イエスを助けようとした弟子は一人もいませんでした。結局、イエスは、弟子たちにも裏切られて死んでいったと言っても決して言いすぎではありません。
しかし、イエスは、十字架につけられたあと、予言通り三日後に甦りました。そして逃げ隠れていた弟子たちの前に現れます。弟子たちは、強い衝撃を受けたことでしょう。しかし、それでもなお、その時にその場に居なかった十二弟子の一人のトマスだけは、まだ、その話を聞いても事実を受けつけようとはせず、「私は、その手に釘あとを見、私の指をその釘あとにさし入れてみなければ、決して信じない」と言い張ったのです。(ヨハネ20・25
)
その八日後、今度はそのトマスも居るところへ、イエスはまた現れます。イエスはトマスに言いました。「あなたの指をここにつけて、私の手をみなさい。手をのばして、私の脇に差し入れてみなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい」と。トマスはことばもありません。ただ「わが主よ、わが神よ」と畏れおののくばかりです。イエスは言いました。「あなたはわたしを見たので信じたのか。見ないで信じる者は、さいわいである」。(ヨハネ20:26-29)
信じない弟子たちが信じる弟子たちに変わったのは、この復活を目の前で見てからです。疑うにも疑いようのない事実を目撃した弟子たちは、このイエスの復活のあと、劇的に変わりました。一度は師を見捨てて逃げ隠れしていた彼らが、猛然と立ち上がって結束し、熱い信仰に燃えて、多くの苦難をものともせず、罵られても、叩かれても、石を投げられても、殺されそうになっても、文字通り生命を賭して師の教えを広めていくようになったのです。逆にいえば、このイエスの復活がなければ、その後の世界宗教としてのキリスト教はなかったといっていいでしょう。
しかしそれでも、遠藤周作さんは、この復活の奇跡を信じることはできませんでした。イエスを裏切ったあの弱虫の弟子たちが、一斉に立ち上がってあらゆる困難に打ち勝ち布教に献身したのには、「なにか筆舌では言えぬ衝撃的な出来事が起こったと考えるより仕方がない」といいながらも、『イエスの生涯』のなかで、つぎのように述べています。①
なぜ弟子たちは荒唐無稽な、当時の人々も嘲笑した復活を事実だと主張し続けたのか。彼らを神秘的幻覚者だとか、集団的催眠にかかったのだときめつけるのはやさしいが、しかしそれを証拠だてるものは何ひとつない。謎はずっしりと重く我々の心にのしかかるのである。
このように遠藤さんは、復活は「荒唐無稽」であり、それなのに弟子たちが一斉に立ち上がった契機は「謎」である、と言っています。そして、復活を認めなければならないとしても、「イエスは弟子たちの信仰において甦られた」としか言いようがないであろう、と神学者・ブルトマンのことばを引用して終わっているのです。②
私は、神学者・ブルトマンや遠藤さんの「復活の謎」に迫ろうとする熱意と善意を疑うことが出来ないだけに、このような苦しい結論を出していることには、つい同情をも禁じ得ないのですが、それでも、イエス・キリストが偉大な霊能者であるという視点を欠いたままでいることの決定的な欠陥を指摘せざるをえません。これが心霊主義との受け止め方の違いです。しかも、この復活には、強力な証人がいました。かつては、キリスト教徒を弾圧していたあのパウロです。
パウロは、キリスト教徒を捕らえようとしてダマスコへ向かう途中、突然、天からの光に打たれて、「なぜ私を迫害するのか」というイエスの声を聞きました。それ以来、パウロは一八〇度転回して、熱烈なキリスト教徒に変わります。そして、弟子たちの誰よりも熱心に、実に二万キロに及ぶ三度の大伝道旅行を含めて命がけの布教を続け、最後にはローマで殉教したのです。
そのパウロが、復活を疑問視する人がいることについて、生前、キリスト教徒に宛てた書簡のなかでつぎのように述べています。
あなたがたの中のある者が、死人の復活などはないと言っているのは、どうしたことか。も しキリストが甦らなかったとしたら、私たちの宣教はむなしく、あなたがたの信仰もまたむな しい。さらに私たちは神にそむく偽証人にさえなるだろう。なぜなら私たちは神がキリストを 甦らせたと言って、神に反するあかしを立てたことになるからである。(コリント前書15・13-15)
ところが、遠藤さんも、この書簡を引用しているのです。しかし、「この絶対的な自信、動くことのない確信は何よりも私たちを圧倒してしまう。どこからこの自信と確信は生まれたのか。もし(復活が)事実でないとするならば・・・・」といい、「イエスの復活を目撃しなかった」我々は、このような「謎をふしぎに思う」と、ここでも遂に「謎」で終わってしまっているのです。③
パウロが、イエスの死後、イエスの声を聞いて回心したその当時、甦ったあとのイエスを実際に見た信徒たちは、五百人以上も居ました。そして、その目撃者たちの大多数はまだ生存している、ともパウロは前述の書簡のなかで述べています。つまり、復活の生き証人はまだ大勢いたのです。しかし、イエスのことを熱心に考えながらも、その復活を「自分で目撃する」ことが出来るはずもなかった遠藤さんは、その奇跡を最後まで信ずることはできなかったのです。
前述のように、その遠藤さんは死後の世界にも関心をもっていました。しかし、その存在には懐疑的で、やはり信じられないまま、一九九六年九月に亡くなりました。これは最近出版された女流作家・佐藤愛子さんの『わたしの遺言』に述べられていますが、遠藤さんは亡くなる半年ほど前に、親しくしていた佐藤愛子さんに「佐藤くん、君、死後の世界はあると思うか?」と、電話で訊いてきたのだそうです。
佐藤さんのことは、一昨年の講演集「生と死の彼方にあるもの」のなかでも紹介させていただきました。昭和五十年に北海道の浦河という町に山荘を建てたときから、深夜の足音、鋭いラップ音、電灯の明滅など、つぎからつぎへと起こる超常現象に見舞われ、それ以来三十年間悩み苦しんだうえで霊界の存在に行き着いた人です。だから佐藤さんは、「あると思う」とすぐ答えました。すると、遠藤さんはこう言いました。
「もしもやな、君が先に死んで、死後の世界があったら、『あった!』といいに幽霊になって出てきてくれよ。オレが先に死んだら、教えに出て来てやるから」
佐藤さんは、その時は「遠藤さんの幽霊なんて来ていらん!」と答えて、話は終わったということです。
佐藤愛子さんは、いまでも心霊の相談などで霊能者の江原啓之さんに電話をかけたりしているようです。④ 遠藤さんが亡くなった翌年の五月中旬、彼女が江原さんと電話で話をしている途中に、急に遠藤さんが現れました。
江原さんが、「あ、ちょっと・・・・待って下さい・・・・今、佐藤さんの部屋に遠藤先生が見えています」と言い出したのです。かつて浦河にいて助けを求めてきた佐藤さんに、霊能者である美輪明宏さんが、東京にいながら佐藤さんの家を的確に霊視したように、江原さんには、電話の相手の佐藤さんの部屋の様子がよく見えるのでしょう。江原さんは、「遠藤先生がこういっておられます。死後の世界はあった、こっちの世界はだいたい、君がいった通りだ・・・・」と霊界からのメッセージを伝えてくれました。
佐藤さんは、感動しました。そして『私の遺言』のなかで、つぎのように書いています。
私の身体を戦慄が走った。驚きや怖ろしさではなくそれは間違いなく感動の戦慄だった。私は思いだしたのだった。遠藤さんの生前の、あの会話を。・・・・もしオレが先に死んだら、教えに出て来てやるから・・・・・。
遠藤さんはそういった。そしてその約束を守って出てきてくれたのだ・・・・。呆然としている私の中に何ともいえない懐かしさと嬉しさがこみ上げてきた。わっと泣き出したい熱いものがたちのぼってくる。⑤
二 長男からの霊界通信
このように、佐藤愛子さんには見えなくても、霊能者の江原啓之さんの眼には、遠藤周作さんの姿がはっきり見える。そして、その遠藤さんが佐藤さんに話しかけることばも、霊能者を通じて聞くことができる。つまり、霊能者の仲介で霊界にいる人とわりあい自由に話が出来たという例は、日本でも外国でも、数え切れないほど沢山あります。私自身も、何度も経験してきましたので、このような話が特に珍しいという意識はありません。
大英心霊協会で長男と「再会」したことについては、この講演集の「生と死の実相について」のなかでも触れてきましたし、妻の誕生日には、妻が「現れて」バースディ・ケーキを切り分けてくれるように語りかけられたこともあります。毎年、六月五日の長男の誕生日には、長男といまでも文通を続けていますが、それももう、十年続きました。今回は、そのような霊界とのコミニュケーションのあり方の一つとして、二〇〇〇年六月五日の長男・潔典からの手紙を、取り上げさせていただくことにいたします。それは、つぎのように始められています。
お父さん、誕生日のお祝いの手紙をありがとう。大変うれしく、こころから感謝しています。ぼくは、いまでは生まれた時からかなり年もとって、分別もある大人になっているつもりですが、お祝いをいわれると、やはりうれしいですね。
誕生日というのは、特別の日で、なかなか忘れられません。お父さんの七十歳の誕生日のお祝いには、ぼくたちも出ていましたが、ぼくたちの存在を感じ取ってくれましたか。ぼくたちもあの席で、お父さんの誕生日をこころからお祝いしていたのです。誕生日というのは、生き ている証しの日であり、こころの成長と語り合いを通じて家族の絆が確かめられる日ですね。愛情で深く結ばれているぼくたちが、いっしょに喜び合う日でもあります。ぼくは、お父さんが大好きです。
この原文は、ロンドンで知り合った霊能者のアン・ターナーの英語で語られていますから、これは日本語に意訳されたものです。英語と日本語の言語的特性はかなり違いますので、直訳ですと、ほとんど意味を為さないことが少なくありません。意訳しても、日本語と英語の差はどうしても残るでしょう。ただ、これを訳している私は、父親として、潔典の気持ちやことばの使い方がよくわかる立場にあります。その分だけ、日本語の意訳も、本人のことばにより近いものに「戻す」ことが出来るといえるかもしれません。
ここに出てくる私の誕生日は、この手紙の一か月半前になります。娘夫婦とレストランで食事して、あとは自宅でケーキとお茶を楽しんでいたのですが、その席に、「ぼくたちもいっしょにいた」のだと、潔典は言っています。しかし、妻や長男から常に見守られているという漠然とした意識はもっていても、霊的感応については、私はかなり鈍い方なのかもしれません。「ぼくたちの存在を感じ取ってくれましたか」と言われて、せめてあのとき妻と長男のグラスぐらいは用意して、「出席」を感謝すべきであった、などと後で考えました。手紙を続けましょう。
ぼくがお父さんと、この世で最後の会話をしたときからも、長い年月が流れました。どうか、あのときの不安がっていたぼくの態度を許してください。少し甘えてお詫びいたします。考えてみるとこの十七年の間に、お父さんにもぼくにもいろんなことがありました。お互いに、多くのことを学び理解してきましたが、それらのことはしっかりと身について離れることはない でしょう。ちょっと淋しいとき、悲しいときには、ぼくたちの楽しかった日々、うれしかった 出来事などを思い出すことにしましょう。
お父さんはぼくのあの小さなおもちゃの時計をまだ持っているのですか。
ぼくはお父さん の息子であったことが本当によかったと思っています。ぼくの誇りです。ぼくたちは、生まれ るときには、好きな家族を自分の責任で、自分で選んで生まれてくるのですね。友だちなども やはり、生まれるときに、自分の責任と好みでえらんでいるのです。こういう特別の愛があることも、いまのぼくにはわかってきました。
ここに述べられている「この世の最後の会話」については、私には忘れられないつらい思い出があります。一九八三年八月、アリゾナ大学からノース・カロライナ大学へ移っていた私と長女のところへ、妻と長男が夏休みを利用して来ることになりました。急の旅行ですぐには予約が取れず、キャンセル待ちで、やっと大韓航空の切符を手に入れたのです。ノース・カロライナ州のローリーのアパートで、久しぶりに一か月の家族四人の生活を楽しんだあと、妻と長男は、アメリカ東部時間の八月三十日の朝、帰国の途につきました。ローリーの空港からフィラデルフィア経由でニューヨークへ飛び、ケネディ国際空港から、大韓航空機に乗ることになっていたのです。
私は鈍感で気がつかなかったのですが、潔典はどういうものか、この大韓航空機に乗ることを気にしていました。娘に、「お姉ちゃん、大韓航空機て大丈夫だろうか?」と二度も訊いてみたりしています。「アリゾナ大学の学生のなかには、大韓航空はいやだという人もいたけれど、大韓航空はパイロットの技術が優秀だし、大韓航空しか乗らないと言う学生もいたよ」と娘の由香利が答えますと、潔典は「助かった!」と調子外れな答え方をしていたそうです。
あとで振り返ってみますと、ローリーのアパートで潔典がベッドのうえに横になっていて、ドアの開け放たれたその部屋の前を私が通り過ぎたとき、ふと(潔典が怯えている・・・・・)と感じたこともあります。しかし、私の頭のなかでは、明るい性格の潔典と暗いイメージの「怯え」は結びつきませんでした。気の迷いだろうと、そのこともすぐ忘れてしまっていました。⑥
潔典は、フィラデルフィア空港からとニューヨークのケネディ空港から二回電話をかけてきました。二回とも、最初に由香利が受話器を取ったのですが、あとで聞いたところでは、潔典は姉に、「無事に着いて偉いだろう」と言ったそうです。たしかに、ローリーからフィラデルフィアへ飛び、ニューヨークに着いたあと、さらに国内線から国際線に移るのは、面倒には違いありません。しかし、潔典はアメリカが初めてではなかったし、英語もほとんどアメリカ人並に話せましたから、「偉いだろう」というのはいかにも変です。しかし、「最後の会話」を電話で潔典と交わしたときには、そういうことにも私はまだ気がついていませんでした。
二回目の電話で、由香利から受話器を受けとったとき、潔典は私に、ケネディ空港に無事着いて、あとは大韓航空機に乗るだけ、というようなことを言いました。私はその時初めて、潔典の言い方にしどろもどろに近いような、何か異様なものを感じたのです。「ママに代わるから、代わるから」と慌てたように言って、電話は母親に代わってしまいました。その時は、さすがに鈍感な私にも、一瞬、暗い不安のようなものがさっと頭の中をよぎりました。私は、妻とのいつもと変わらぬ穏やかな会話で電話を切ったあと、ちょっとつらいような思いをかみしめていました。
潔典は父親の私からみてもよくできた子で、私は彼を、幼い頃からほとんど叱ったことがありません。しかし、あの時は、東京へ着いたら電話で、潔典に少し強く言っておこうと思っていました。「あんなふうな話し方をすれば、お父さんは心配になるではないか」という、その時に言おうと思ったことばをいまでも覚えています。
第六感というのでしょうか、潔典は自分にこれから起ころうとしていることを、漠然としてではあっても間違いなく感じ取っていたと思います。いくら払おうとしても、その不安は拭いきれず、最後には、あのような私との会話になったのでしょう。叱られなければならないのは潔典ではなく最後まで鈍感であった私でした。私が鈍感でさえなければ、と事件のあと、長い間苦しみ続けたことをいまも忘れることが出来ません。私は、この時の潔典への手紙で、その鈍感さを詫びたのです。この返事で、その気持ちが少しでも伝わったようで救われたような気がしました。
文中の「あの小さなおもちゃの時計」というのは、潔典がなにかの付録か懸賞でもらったらしい小さな子供っぽい時計です。五百円玉よりちょっと大きいくらいのゲーム・ウオッチで、値段にすれば、おそらく千円もしないでしょう。茶目っ気のある潔典は、その時計を、自分の机の脇の電気スタンドにぶら下げていました。
事件後しばらくは辛くて部屋にも入れませんでしたが、二年くらい経ってからでしょうか、潔典の机に座っていますと、急に「タタタータタ、ターララ、ラーラ・・・・・」と、時計が鳴り出しました。私はちょっと驚いて、初めてこの「ムッシーちゃん」と名付けられた小さなおもちゃの時計が鳴ることに気づいたのです。十二時十五分に鳴り出して、十五秒ほどで終わるこのメロディーは、その後何年間も鳴り続けました。
事件後十年になる一九九三年の夏、ロンドンでアン・ターナーにこの時計のことを話しますと、彼女は「あなたに霊界のことを理解させるために、この時計は十年間鳴り続けてきたが、いまあなたは理解し始めている。それで、まもなく動くのを止めるだろう。止まっても新しくバッテリーを入れ替える必要はない。そのままにしておけばよい」と言いました。いま改めて、ビデオに録画しておいたものを見ますと、一九九四年一月六日までの記録が残っています。文字盤の人形が踊り、ちゃんとメロディーが鳴っています。普通は一年か二年で止まってしまうと思われるのに、このおもちゃの時計は、十一年以上も毎日、人形が踊って鳴り続けたことになります。
つぎに、ここで潔典のいっている「好きな家族を自分で選んで生まれる」というのは、心霊主義ではよく知られていることで、新奇ないい方ではありません。私も講演で何度か取り上げてきましたので、ここではくわしくは触れません。⑦
ただ、この場合、好きな家族というのは、必ずしも、豊かで愛情に満ちあふれた円満な家庭という意味ではないでしょう。さらに一歩進んで、愛のない厳しい逆境を自ら好んで選ぶということもあることを知っておく必要があります。ともあれ、潔典は私を父親に選んで生まれてくれました。私は、自分を選んでくれたことに対して、いまも潔典には尽きることのない感謝の気持ちを持ち続けています。
少し、説明が長くなりましたが、潔典からの手紙はさらにつぎのように続きます。
お父さん、来年、七十歳の定年を迎えることになって、おめでとう。長年、お父さんは立派 な充実した仕事を成し遂げてきました。これからも、お父さんがこころに抱いてきた夢を実現 させるためには、何年もかかります。多くの人々と会ったり、あちらこちら旅行をしたり、そ れに、本を書いたりとかで、まだまだ、することがたくさんありますね。
お父さんの書いた『生と死の彼方に』は、確かに、この霊界とそちらの世界とを結びつけてくれる本です。お父さんが書きたいと思ったことは、これからも何でも書くようにしていってください。こちらの霊界やこちらでの生活を多くの人々に知ってもらうためにも、お父さんの 知識や思いやりのあることばが必要なのです。
お父さんが書く本などで霊界についての理解が深まっていくと、そちらの世界との溝が取り除かれ、死後の世界の恐怖心とか迷信もなくなっていきます。霊界がそちらの世界からはもっと身近になって、死のもたらす悲しみや苦しみも消えていくことでしょう。死というのは、次元が違っても、隣の部屋に一歩足を踏み入れるようなものですから。心は満ち足りて平静です。
二〇〇一年の三月末で、定年退職することは私から伝えてありますから、これは、霊界からといっても、特に目新しい返事にはならないかもしれません。『生と死の彼方に』の出版についても、同様です。意地悪く言えば、別に霊能者でなくても、この程度の「返事」は仲介できると考えることもできるでしょう。ただ、このような手紙を仲介するときのアン・ターナーは、自分自身の意識と肉体から離れてしまっています。私は、そういう彼女の姿を目の前で何度も見てきましたが、霊界とのコミュニケーションに身を委ねている間は、たとえ自分の腕を切り落とされてもわからないだろう、他人の腕のようなもので、痛くもないだろう、と彼女は言っていました。
しかし、それでも霊能者の意識と肉体を媒介している以上、通信内容が霊能者本人の意識のあり方から微妙に影響を受けることはあるのではないか、と考えられないこともありません。私自身も、これが潔典の肉声でないというだけでも、信憑性が百パーセントだとはいえないと思います。これは、たとえば、宇宙のはるか彼方から送られてくる弱い雑音混じりの電波になんとか波長を合わせてメッセージを捉えようとする試みのようなものかもしれません。その時の気象条件や受信機の調子などにも影響を受けることでしょう。それだけに私の場合は、霊界からの通信はなるべく多く受けとって、比較検討しながら吟味することが、情報についての信憑性を高める一つの方法であろうと思ったりしています。
また、「死というものは、次元が違っても、隣の部屋に一歩足をふみいれるようなもの」ということばは、ほかの多くの霊界通信の内容からみても納得させられる表現です。「心は満ち足りて平静です」ということばも、潔典に関するほかのいろいろな情報とも矛盾してはいません。
お姉ちゃん(由香利)のことは決して忘れていません。お姉ちゃんは感受性が豊かで、困っ ている人々の面倒をみたり、まわりの人々とうまく歩調を合わせていく特別の才能があります。わざとらしさのない自然な調子で、人々に話しかけたり、助言を与えたりするのが上手です。大きなからだのぼくに代わって、抱きしめてやって下さい。お姉ちゃんはちょっと驚くかもしれませんが、ぼくからの愛情の表現であるとわかってくれるでしょう。ぼくの義兄になるお姉 ちゃんのご主人にも、ぼくに代わって強く握手してくれませんか。お兄さんに、あの三月の特別の記念日には、どうかおおいに楽しんで、お祝いをしてくれるようにお伝えください。こちらにいる家族のみんなも、ぼくも、お兄さんが家族の一員に加わったことを、たいへん喜んでいます。
娘の由香利は、一九九二年の十一月に結婚しましたが、このことは、私がまだイギリスに滞在中の一九九二年三月までに、大英心霊協会の複数の霊能者に予言されていました。私が帰国したあとすぐに、結婚の話がもちあがるともいわれて、そんな気配のほとんどなかった娘に、ほんとうにそんなことがあるのだろうか、とも思ったりしましたが、それも現実になりました。偶然ということばでは片づけられないこの「予言」の的確性を私は疑うことが出来ません。霊界では、この結婚についていろいろと話し合われたことなども、後に私は告げられるようになります。
「三月の特別の記念日」とは、三月二十九日の娘の誕生日を指すように思われます。それ以外には、この言葉にあたるような日はありません。それならば、「特別の記念日」のかわりに、なぜ「誕生日」ということばを使わないのか、という問題がありますが、それも、霊界とのコミュニケーションの、あるいは、霊能者の一つの限界といえるのかもしれません。ただ、霊能者はこのような個人情報は何も知らないわけですから、もし、「特別の記念日」に該当する日が全くないのであれば、その霊能者の霊界通信そのものの信憑性が問われることにもなりかねないのです。
この霊能者、アン・ターナーは、大英心霊協会で初めて会ったときに、私の前に立った潔典からのことばとして、潔典の名前や私の足の傷跡のことまで伝えてくれたことを、私は講演集「生と死の実相について」のなかでも取り上げました。こんなことは普通ではあり得ないことで、それは奇跡としかいいようがないのですが、その奇跡が私にはおこったのだ、とも書きました。実は、その「奇跡」の三日後に私はまた大英心霊協会でアン・ターナーに会っています。私はこの時、考えようによっては実に意地の悪い質問をしました。私は、必死でしたが、彼女に、「私の妻と長男が霊界へ行ったのは何年か?」と訊いてみたのです。
アン・ターナーは、ちょっと瞑想して、「一九七三年」と言ったあと、いや、「一九八三年」と言い直しました。あの大韓航空機事件が起こったのは一九八三年九月一日です。もちろん彼女は、事件と私の関わりについては何も知りません。私は驚くというよりうなだれて深く感動していました。彼女は眼をつむったまま語り続けました。「乗り物が見える、速いスピードで動いている・・・突然それが破壊された・・・・彼は混乱している・・・事態がよく理解できなかった・・・・・・」
先ほどの「特別の記念日」と同じで、この場合も、「乗り物」といって「飛行機」とは言っていません。そこまでは捉えきれていない、といってもいいと思います。しかし、これが、霊界の潔典からの情報であることは疑うことが出来ないのです。大英心霊協会では、ほかの初対面の霊能者からも、一九八三年という年は「たいへん悲しい年、号泣の年だ、泣き声が聞こえる・・・・」などといわれたこともあります。この霊能者にとっては、その程度まで捉える能力がある、と考えてもいいのかもしれません。
ここで手紙に戻りますが、ともあれ、私は、潔典に言われたとおり、彼に代わって「お兄さん」とは固い握手を交わしました。
このあと、「お母さんが、お父さんにお話ししたいというので、ここでちょっと代わります」と言って、潔典のことばは中断しました。妻がでてきて、私にいろいろと話しかけてきましたが、これは長くなりますので、ここでは省略させていただきます。最後に、潔典は、つぎのように言ってきました。
ぼくは、お父さんも知っているように、こちらでは霊界通信の勉強をしています。お父さん なら、ぼくの勉強ぶりに十点満点で何点くれますか?
お父さんの評価次第で、ぼくの勉強はますます進むようになると思いますよ。これは冗談です。ぼくが笑っているのがわかるでしょ う。でも、試しに、お父さんの評価を想念で直接ぼくに送ってみてください。
・・・・・・・アンが疲れてきました。この貴重な通信を仲介するためには彼女は大きな霊的エネルギーを消費しなければなりませんが、そのエネルギーが弱ってきたようです。だから、この辺で終わらせることにします。さよなら、お父さん。家族のみんなもお父さんに、さよならを 言っています。最後に、お父さん、ぼくのお父さんでいてくれてありがとう。お父さんのことは忘れません。
霊界では、この話し方にもみられるように、潔典はいつも明るい雰囲気に包まれているようです。大英心霊協会のほかの霊能者からも、何度も潔典が勉強に打ち込んでいる話を聞かされていますが、勉強の対象は、言語学や心理学、コミュニケーションなどと言われてきました。「あなたの息子さんは、非常に優秀な人だ。むつかしい知的な研究をしているので、私には説明しにくい。心理学のようなものであろうか、人間のこころを世代を越えて通信する方法のようなものを研究している」と言われたこともあります。
潔典は、生前の東京での学生時代には、言語学、特に音声言語学に非常に関心をもって、のめり込むように熱中していましたから、彼自身から霊界通信の勉強をしているといわれても、私には違和感はありません。ただ、この霊界通信というのは二つの異なる次元の橋渡しをするわけですから、なかなか大変であろうことは、容易に想像がつきます。⑧ その仕組みがどうなっているのか、あるいはどういう勉強が必要なのか、というようなことには興味をそそられますが、これらについては、つぎの章で改めて取り上げることにいたしましょう。
私は、父親として当然のことながら、潔典がいまどのような勉強をしているのか、強い興味があります。ですから、いろいろな霊能者に訊いてきたのですが、大英心霊協会のさらに別の霊能者からは、「彼は非常に高いI・Q(知能指数)の持ち主だ。特に音楽の才能がある。音楽を学びながら、同時に音楽を教えてもいる」とも伝えられたりしました。この手紙とは異なる捉え方になりますが、実は、この音楽の勉強も必ずしも的はずれではありません。
潔典は子供の時からバイオリンを習っていて、ギターはなかなかの名手といわれていましたし、大学に入ってからも、音楽には深く傾倒していました。アメリカ人歌手が歌う微妙な英語の発音の相違などは私にはわかりませんが、娘の話では、潔典は聞き分けられるのだそうです。ですから、潔典がいま勉強していることについては、音楽をも含めて、私にもおよその見当がつきます。もし霊能者が、医学や法律の勉強とか、生物学や工学の研究をしているなどといえば、私は不信感をもつかもしれません。
「試しに、私の評価を想念で送る」ということについては、まだまだ私の修行不足で、そのレベルには達していないことを告白しなければなりません。東京の学生時代に潔典が買った愛用のギターがあって、いまでも大切に保管していますが、潔典は霊界から、いつかはそのギターを鳴らせてみせる、と言ってきたことがあります。私はそれからは、そのギターを仏壇の横に立てかけているのですが、まだ、ギターが鳴るのを聴いたことはありません。
また、一昨年は、「試しに、想念で二つのことばを送ってみるから聞き取って欲しい」と想念を送る日と時間まで指定してきたことがあります。私も少し緊張して、指定された日時に黙想をしていましたが、その想念を受けとることは出来ませんでした。波長を合わせて霊界からの想念を受け止める力が私にはまだないということで、私は潔典に申し訳ないなどと思いながら、最近では毎日、一定時間の瞑想を続けることにしています。随分個人的な話になってしまって恐縮ですが、このへんで潔典からの手紙は終わりにしましょう。
この霊界からの手紙を、アン・ターナーは、自分の意識から離れて、激しい息づかいで時に大きく深呼吸したりしながら、独特の口調で伝えてきます。途切れ途切れになったりもしますので、一回分の手紙を仲介するのには二十分から長いときで二十五分くらいかかります。やはりかなりのエネルギーがいるからなのでしょう。終わりに近づくとだんだん声が弱くなっていくようです。この時の通信は二十分で終わりました。
三 シルバー・バーチの霊訓
潔典のような霊界で勉強中の者と違って、高級霊といわれるような人になると、霊界通信もほとんど一点の曇りも曖昧さもない明晰さで、高度で詳細な内容のものを伝えてくれています。その代表例の一人がシルバー・バーチでしょう。心霊主義の世界ではあまりにも有名で、皆さんの中にもこの名前をご存じの方が多くおられることと思います。一九二〇年代から実に五十年間にわたって、イギリスで霊界の真実を伝えるためのメッセージを送り続けました。
シルバー・バーチというのは仮の呼び名で、紀元前千年ごろ地上で生きていた人らしいのですが、訊かれても、本人は最後まで身分を明かそうとはしませんでした。「人間は名前や肩書きにこだわるからいけないのです。前世で私が王様であろうと乞食であろうと、そんなことはどうでもよろしい。私の言っていることがなるほどと納得がいったら真理として信じてください。そんなバカな、と思われたら、どうか信じないでください。それでいいのです」と答えていました。
シルバー・バーチのことばを取り次いだのは、有能な著作家、編集者として知られたモーリス・バーバネル氏でした。彼は、シルバー・バーチのことばを「霊の錬金術」として、つぎのように激賞しています。
年中ものを書く仕事をしている人間から見れば、毎週毎週ぶっつけ本番でこれほど叡智に富んだ教えを素朴な雄弁さでもって説き続けるということ自体が、すでに超人的であることを示している。誰しも単語を置き換えたり消したり、文体を書き改めたり、字引や同義語辞典と首っ引きでやっと満足のいく記事が出来上がる。ところがこの「死者」は一度もことばに窮することなく、すらすらと完璧な文章を述べていく。その一文一文に良識が溢れ、人の心を鼓舞し、精神を高揚し、気高さを感じさせるのである。⑨
しかし、シルバー・バーチですら、このように、稀代のことばの達人として霊界から語りかけるのには、霊界での長い準備と勉強が必要でした。霊の世界ではことばは使いませんから、地上へ降りてきて霊能者に乗り移った霊は、意識に浮かんだ映像、思想、アイデアを音声に変える必要があります。この音声に替える作業は、霊能者が仲介して音声にする場合と、霊体が直接、霊能者の発声器官を使って、音声を発する場合があるように思われます。潔典の手紙の場合は前者でしょう。だから、どうしても曖昧さが残ります。しかし、シルバー・バーチの場合は後者です。彼は、心霊知識の理解へ向けて指導するという使命を帯びて地上に降りるとき、いろいろな周到な準備のほか、英語の勉強もしたことを、自らつぎのように述べています。
あなた方の世界は、私にとって全く魅力のない世界でした。しかし、やらねばならない仕事があったのです。しかもその仕事が大変な仕事であることを聞かされました。まず英語を勉強しなければなりません。地上の同士を見つけ、その協力が得られるよう配慮しなければなりません。それから私の代弁者となるべき霊能者を養成し、さらにその霊能者を通じて語る真理を出来るだけ広めるための手段も講じなければなりません。それは大変な仕事ですが、私が精一杯やっておれば上方から援助の手を差し向けるとの保証を得ました。そして計画はすべて順調 に進みました。⑩
一九二〇年代にこの霊能者として選ばれたのが前述のモーリス・バーバネル氏ですが、シルバー・バーチは、氏が生まれる前から調べ上げて彼を選び、その受胎の日を待っていたといわれています。⑪ また、ここで同士というのは、当時、反骨のジャーナリストとして名を馳せ、「英国新聞界の法王」とまでいわれたハンネン・スワッハー氏でした。氏は、シルバー・バーチのための交霊会を、はじめは私的なホーム・サークルという形で開いたのですが、それが延々と半世紀も続いて、シルバー・バーチの教えは、人類の膨大な知的遺産として残ることになりました。日本でも、一九八五年から潮文社『シルバーバーチの霊訓』一~十二巻(近藤千雄訳)として、出版されています。
「語りかける霊がいかなる高級霊であっても、いかに偉大な霊であっても、その語る内容に反発を感じ理性が納得しないときは、かまわず拒絶なさるがよろしい」⑫
とくり返していたシルバー・バーチが、一旦口を開くと、「何ともいえない、堂々として威厳に満ちた、近づきがたい雰囲気が漂い始め」て、交霊会の出席者たちは、思わず感涙にむせぶこともあったといいます。⑬活字になってしまうと、そのような雰囲気は伝わりにくいのですが、ここでは、シルバー・バーチの教えのほんの一部を、再現してみましょう。
交霊会では、話が終わったあと、シルバー・バーチはどんな質問にも、明快的確に即答していましたが、ある日、「霊界についてテレビで講演することになったとすれば、どういうことを話されますか」という質問が出て、すかさず、彼はつぎのように答えました。⑭
私はまず私が地上の人たちから「死者」と呼ばれている者の一人であることを述べてから、しかし地上の数々の信仰がことごとく誤りの上に築かれていることを説明いたします。生命に死はなく、永遠なる生命力の一部であるが故に不滅であることを説きます。私は視聴者に、これまで受け継いできた偏見に基づく概念のすべてをひとまず脇へ置いて、死後存続の問題と虚心坦懐に取り組んで真実のみを求める態度を要請いたします。寛容的精神と厚意をもって臨み、一方、他人がどう述べているからということで迷わされることなく、自分みずからの判断で真理を求めるよう訴えます。そして世界中の識者の中から、いわゆる死者と話を交わした実際の体験によって死後の生命を信じるに至った人の名前を幾つか紹介します。そして私自身に関しては、私もかつて遠い昔に地上生活の寿命を割り当てられ、それを全うして、一たんべールの彼方へ去ったのち、この暗い地上へ一条の光をもたらし久しく埋もれたままの霊的真理を説くために、再び地上に戻る決心をしたことを述べます。
パラグラフにすると五つになりますが、これが切り出しの部分です。自己紹介と地上へ戻ってきた理由について述べていますが、メッセージは明らかでしょう。私はこの地上では「死者」と呼ばれるが、死んではいない。いのちは永遠で滅びることはない。それが霊的真理であり、それを伝えるために、地上に降りてきた、というのです。つぎに移りましょう。
私はその霊的真理を平易な言葉で概説し、視聴者に対して果たして私の述べたことが理性を反発させ、あるいは知性を侮辱するものであるか否かを訊いてみます。私には何一つ既得の権利を持ち合わせないことを表明します。こんなことを説いてお金をいただかねばならないわけでもなく、仕事を確保しなければならないわけでもありません。私には何一つ得るものはありません。霊界での永い永い生活を体験した末に私が知り得たことを教えに来ているだけです。聞くも聞かぬもあなた方の自由です。
人間は不滅なのです。死は無いのです。あなた方が涙を流して嘆き悲しんでいる時、その人はあなた方のすぐ側に黙って立っている・・・・・・ 黙って、というのは、あなた方が聞く耳をもたないために聞こえないことを言っているまでです。本当は自分の存在を知らせようとして何度も何度も叫び続けているのです。あなた方こそ死者です。本当の生命の実相を知らずにいるという意味で立派な死者です。神の宇宙の美が見えません。地上という極小の世界のことしか感識していません。すぐ身のまわりに雄大な生命の波が打ち寄せているのです。愛しい人たちはそこに生き続けているのです。そしてその背後には幾重にも高く界層が広がり、測り知れない遠い過去に同じ地上で生活した人々が無数に存在し、その体験から得た叡智を役立てたいと望んでいるのです。
ここで、これらがシルバー・バーチのことばであると聞かされても、テレビに映って話していると仮定されているのは、モーリス・バーバネル氏のはずですから、バーバネル氏の口からシルバー・バーチのことばが出てくることに一種の違和感を持つ人もいるかもしれません。霊能者の意識と発声器官を占有していることが理解できても、霊能者の潜在意識が影響を与えるということはないのか、と考えたりします。一般的には、霊の意識が霊能者を通じて百パーセント正確に伝えられることは非常に難しい、ともいわれています。しかし、この場合は違うようです。シルバー・バーチは、バーバネル氏を生まれる前から選び、霊界からの操作で、生まれてからもさまざまな霊能者になるための経験を積ませ、その結果、氏の潜在意識を完全に支配して、自分の考えを百パーセント述べることが出来ると言っているのです。⑮
「金銭目当てで言っているのではない、聞くも聞かぬもあなた方の自由」というのも説得力があります。世の中には、いわゆる霊感商法とか、悪霊除去とかで法外なカネをとる悪質業者が後を絶ちませんが、本来、真理を伝えるのにカネを要求することはないはずなのです。逆に言えば、法外なカネを要求するような教えや霊的治療は、真理とはかけ離れたものといえるでしょう。
一方、いくら無償の愛のこころで真理を伝えようとしても、「聞く耳をもたない」人も少なくはありません。いのちの真理を知らず、知ろうともせず、「死んだ」家族に取りすがってただ泣いてばかりしているとすれば、その人こそ本当の意味での死者である、というのもよく理解できます。「まえがき」でも述べましたように私自身がそうでした。これも、現に「死者」であるシルバー・バーチが言っているわけですから、これほど確かな「証人」はいないということになるでしょう。
見えないままでいたければ目を閉じ続けられるがよろしい。聞こえないままでいたければ耳を塞ぎ続けられるがよろしい。が、賢明なる人間は魂の窓を開き、人生を生き甲斐あるものにするために勇気づけ指導してくれる莫大な霊のカを認識することになります。あなた方は神の子なのです。その愛と叡智をもって全宇宙を創造した大霊の子供なのです。その大霊とのつながりを強化するのは、あなた方の理解力一つです。もし教会がその邪魔になるのであれば、教会をお棄てになることです。もし邪魔する人間がいれば、その人間と縁を切ることです。もし聖典が障害となっていると気がつかれれば、その聖典を棄て去ることです。
そうしてあなた一人の魂の静寂の中に引きこもることです。一切の世間的喧噪を忘れ去ることです。そして身のまわりに澎湃として存在する霊的生命の幽かな、そして霊妙なバイブレーションを感得なさることです。そうすれば人間が物的身体を超越できることを悟られるでしょう。知識に目覚めることです。理解カを開くことです。いつまでも囚人であってはなりません。 無知の牢獄から脱け出て、霊的自由の光の中で生きることです。
ここでは、大霊との繋がりに教会が邪魔になるのなら教会を捨てよ、とまで言っていますが、これは、キリスト教会が心霊主義を認めていないことを批判しているのでしょう。キリスト教徒の迫害を続けていたローマ帝国が、方針を転換してキリスト教の公認に踏み切ったのは三一三年のことで、コンスタンチヌス帝によってでした。実は、この頃まではまだ、聖職者と霊能力で教会を支えていた霊能者は共存していたのです。その両者の関係がだんだん分離していき、三二五年に異端の弾劾を審議する第一回ニカイア会議が開かれた頃には、教会から霊能者と心霊主義を追放することが決定的になったといわれています。
もともと教会では、聖職者が俗世の悩み事の相談に乗り、霊能者が天界からのお告げを伝えるというように、民衆を二重に導いていました。それが、聖職者だけが運営する教会となって、教会は次第に民衆からの尊敬を失い始め、衰退していったと、シルバー・バーチはみています。⑯この両者の違いは、イエス・キリストの奇跡の捉え方にもあらわれてきました。病人を癒した奇跡も、憑依霊を追い出した話も、イエス自身の復活も、霊能者の心霊主義ではすべて説明できることで、謎でも不思議でもありません。しかし聖職者たちは、それらが霊能力のなせるわざであり、その霊能力は本来誰にでも備わっているものだというような考え方を、認めようとはしないのです。
私は本稿一章でいくらか詳しく遠藤周作さんのことを取り上げてきました。遠藤さんのキリスト教や信仰に関する労作が、おそらく遠藤さんが意識しないままに、このキリスト教と心霊主義との乖離をよく示していると思うからです。復活は自然の法則の一つにすぎない、⑰ とする心霊主義に対して、遠藤周作さんが、復活の奇跡を最後まで「謎」としてしか捉えられなかったのも、このような教会と心霊主義との乖離が背景になっているからにほかなりません。
ともあれ、「テレビに出たら」という仮定で、シルバー・バーチは、以上の内容をよどみなく一気に語り終えました。素朴で荘厳で慈愛に満ちた彼の肉声を聞くことが出来ないのは残念ですが、その彼が、一方的な困難と負担を乗り越え、しかも何の見返りも求めず、地上に降りてきて熱心に説いたのは、私たちは死なない、死んでも生きる、いのちは永遠である、ということに尽きると思われます。その真理を私たちが素直に自分のものとして受け止めたとき、私たちははじめて彼が言う「霊的自由のなかで生きる」ことになるのでしょう。
お わ り に
山口県の萩女子短大・副学長をしておられた河村とし子さんが、何年か前に、NHKの「こころの時代」という番組で、ご自分のおばあちゃんのことを話されたことがあります。⑱
私はそれを「おばあちゃんの教え」と題して、「こもれび」に随想を載せました。つぎのような話です。
おばあちゃんは、河村さんの亡くなったご主人のお母さんです。小学校も出ていませんので一字の読み書きもできない、河村さんのことばでは「常識もない」人だったそうです。このおばあちゃんは、み仏への信仰の厚い人でしたが、六人いた息子娘たちのうち、成人してから四人までを次々に亡くしていました。
太平洋戦争の末期、東京の空襲を避けて萩市に疎開することになり、そのようなおばあちゃんとはじめて一緒に暮らすようになった河村さんは、おばあちゃんが、おそらく毎日、泣きの涙で暮らしているのだろうと思っていたそうです。ところがおばあちゃんは、少しも嘆きや悲しみが感じられない、安らかな毎日を送っていました。おばあちゃんは、「私たち浄土真宗のご門徒は、先にお浄土へ還らせていただいた愛しい子供たちとも、お念仏のなかで出おうたり話したりできるから幸せじゃのう」とよく言っていたそうです。おばあちゃんは、いのちの真実を期せずして体得していたことになるのかもしれません。
おばあちゃんの嫁であった河村さんは、熱心なキリスト教信者でした。キリスト教の家庭で育てられ、結婚するときにも、生涯クリスチャンとして過ごすことを条件としていたといいます。その河村さんは、疎開してからしばらくは、毎晩のようにおばあちゃんの部屋へキリスト教の聖書を持って押しかけ、おばあちゃんにしつこくキリスト教を勧めました。おばあちゃんは、少しもいやな顔をせず、「ああ、そうかそうか」といつも機嫌よく河村さんの話を聞いてくれたそうです。
後になって、河村さんがおばあちゃんに、「あのように毎晩押しかけられ、強引にキリスト教を勧められてさぞいやな思いをされたでしょう」と謝りますと、おばあちゃんは、「毎晩キリスト教を勧めに来る嫁じゃけど、ご縁があってうちの嫁になったんじゃから、み仏様におまかせしときゃええ、と思って少しもいやではなかったよ」と答えたそうです。そのようなおばあちゃんにいつのまにか感化されて、その河村さん自身が、キリスト教徒から仏教徒に変わり、熱心に念仏を唱えるようになりました。
おばあちゃんは、すべてのものに有り難いと感謝して拝んでいるような人でした。朝、目を覚ましても、「ああ、今日も目が見えてくださる。手が上がってくださる。足が動いてくださる。有り難いことじゃのう」と何度もひとりごとのように繰り返していたそうです。
仏教の教えには「怨憎会苦」ということばがあります。しかし、それを字で読めなくてもおばあちゃんは、「人間ちゅうもんは自分しかかわゆうないもんじゃけな、そんな者同士共に暮らさねばならんその因縁を拝みあう。それしかこの苦はのりこえられんのじゃ」と言っていました。
また、「求不得苦」ということばもあります。それもおばあちゃんは、「無いもんを欲しがらんで、有るもんを喜こばしてもらおうよのう」と達観していました。文字一つ読めないおばあちゃんは、「常識もない」どころか、誰よりも深く仏教の神髄を体現していたのです。そのうえで、人に対してはいつも穏やかに、にこにこと笑顔を絶やさず、「和顔愛語」でなかった日は一日もなかったと河村さんは述懐しています。
このようなおばあちゃんと二十三年間一緒に暮らしてきて、河村さんは、何よりも多くのことをおばあちゃんから学び、いつのまにかおばあちゃんのなかにみ仏の姿を見るようになりました。大学教授の河村さんが、一字も読み書きできない姑との出会いを、生涯で一番大きな出会いであり、「人間としての立派さでは、自分はおばあちゃんの足許にも及ばない」と深く敬愛するようになっていったということです。
日本では学歴偏重の傾向が強く、多くの人々が学歴がなければ立身出世もおぼつかないというふうに考えます。そして、大きな資産を築きあげ社会的地位が高いほど、偉い人という評価が与えられがちです。しかし、本当の人間の偉さというのは、この河村さんのおばあちゃんの例をみるまでもなく、必ずしも学歴などと相関するものではありません。おそらく、社会的地位や名誉、財産などともあまり関係がないでしょう。
学歴社会の人間を計る物差しが「地の尺度」であるとすれば、それとは別に、「天の尺度」といったようなものが厳然と存在すると思います。これは到達点の光までの距離をあらわす物差しで「光の尺度」と言い換えてもいいかもしれません。人間の偉さを計る本当の物差しは「光の尺度」であって、「地の尺度」ではないのです。私たちは、この河村さんのおばあちゃんのように「光の尺度」で偉くなるために、死んでも死なずに生き続け、輪廻転生をくり返しながら経験を積み、闇から光へ向かって一歩一歩近づいていきます。これが、いのちの真実のもつ最も重要な側面の一つではないでしょうか。
世の中には、いろいろな苦しみがあります。苦しみがあるから、それを乗り越えて手に入る楽しみがあります。人々にはさまざまな悲しみがあります。悲しみがあるから、それにうち勝ってしみじみと味わう喜びがあります。ですから、苦しみも悲しみも、本来、いいことなのです。苦しいことも悲しいことも、もともと、楽しみと喜びを知るために起こっているからです。そのことを理解し体験することによって、私たちは光に向かって一歩でも二歩でも前進できるのです。
その光に向かって歩み続けるためには、私たちは、どうしても、いのちの永遠性を理解しなければなりません。今生だけの一瞬ともいえるいのちがすべてであると考えていれば、「地の尺度」のなかで欲にまみれて、こころの安らぎや本当の幸せは掴みにくいでしょう。いのちの真実について、今日ここで述べてきたことは、きわめて単純で明快です。私たちは死んでも死なない、ということです。いのちは生き続けて永遠だということです。この単純明快な真実を、自分の理性に照らして受け容れるかどうか、それが、「光の尺度」で光へ向かって前進するか、闇へ向かって後退するかの分岐点になるのかもしれません。
注
① 遠藤周作『イエスの生涯』(新潮文庫)一九九二年、二二〇頁。
② 遠藤周作、前掲書、二一八頁。
③ 遠藤周作、前掲書、二二〇頁。
④ 佐藤さんは北海道の浦河で超常現象を経験したことがきっかけとなって、『こんなふうに死にたい』(新潮
文庫)一九九二年、を書きましたが、さらに、その本がきっかけになって霊能者の江原啓之さんと知りあ い、共著で『あの世の話』(文春文庫)二〇〇一年、を書いています。
⑤ 佐藤愛子『私の遺言』新潮社、二〇〇二年、二五七~二五八頁。
⑥ 武本昌三『疑惑の航跡』潮出版社、一九八五年、三七~四一頁などに詳述。
⑦ 武本昌三・講演集「真実の自分を求めて」二七~二八頁など。
⑧ 霊界通信は二つの全く異なる意識の次元での表現操作が必要ですが、その霊界から地上への転換の際に、 いろいろと混乱が生じがちです。そのため霊界では、精神的レベル、物的レベル、治病レベル等、あらゆ る交霊での実験と研究がなされているようです。 アン・ドゥーリー編『シルバー・バーチの霊訓』(一) 潮文社、一九八八年、九三頁。
⑨ アン・ドゥーリー編、『シルバー・バーチの霊訓』(一)潮文社、一九八八年、一二頁。
⑩ 近藤千雄・訳編『古代霊は語る』潮文社、一九八六年、一四頁。
⑪ シルバー・バーチは、モーリス・バーバネル氏が生まれてからも、霊界からいろいろと彼を霊能者にする ために指導してきました。その結果、氏の潜在意識を完全に支配し、自分の考えを百パーセント述べるこ とが出来ると言っています。近藤千雄・訳編、前掲書、一八頁。
⑫ 近藤千雄・訳編、前掲書、二八三頁。
⑬ 近藤千雄・訳編、前掲書、二四頁。
⑭ H・S・ ホームサークル編『シルバー・バーチの霊訓』(三)潮文社、一九八六年、七六~七八頁。
⑮ 近藤千雄・訳編、前掲書、一八頁。
⑯ H・S・ ホームサークル編、前掲書、九六頁。
⑰ H・S・ ホームサークル編、前掲書、八九頁。
⑱ NHK教育テレビ「信心への歩み」一九九七年五月三日(再放送)より。
謝 辞
今年も六月十五日にまた、武本昌三先生のご講演をお願いすることになりました。一九九七年以来、毎年恒例の行事になりましたが、先生のご講演は今年で七回目になります。この小冊子もこれで六冊を数えることになりました。この間は弊社三階の大ホールで、これも恒例になりはじめたハイフェッツ弦楽合奏団のクラシック演奏会が開催され、大勢の方々に癒しのひとときを楽しんでいただきましたが、その同じ会場に、また大勢のご出席者をお迎えして、貴重な学びの時間を共に持てますことを、主催者としても、たいへん有難く感謝申し上げております。
武本先生のお話をお聴きしていますと、私たちはいつも考えさせられることが少なくありません。たとえば、世の中にはいろいろと、悩みや苦しみが多いものですが、それを武本先生は、本来いいことである、と言われます。悩みや苦しみは、私たちを進歩させるために必要な教材のようなもので、それらを乗り越えたときに、悩みは消えて安らぎになり、苦しみはいつのまにか喜びに変わっていきます。そういうことを経験しながら進歩していくのが人生であって、そういう進歩を経験するために人は生まれるのだと、先生は言われるのです。今年の演題は、「いのちの真実を求めて」となっていますが、いのちとは何かという重大な命題について、またいろいろと多くのご出席の方々とともに学ばせていただきたいと思っています。
なお、講演会へのご出席は、いつも自由で無料とさせていただいていますが、武本先生のご意志で、講演料、小冊子原稿料等についても、無料でご尽力いただいておりますことをつけ加えて、改めて武本先生にこころからのお礼を申し上げたいと存じます。
二〇〇三年六月十日
株式会社 溝口祭典 代表取締役 溝 口 勝 巳
|