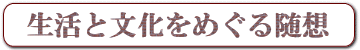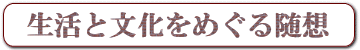|
霊界生活の実相を検証する
― 生活と文化をめぐる随想 (No.101) ―
(2015.05.01)
霊界の生活はどうなっているのか。私たちが霊界へ還った時、どのような姿でどのように生き続けていくのか。これらは私たちにとってたいへん興味ある問題ですが、それを知りたいと思っても、通常は、一部の霊能力者からの霊界通信などを除いては、現世の文献・資料からは答えを引き出していくことは出来ません。しかし、幸いにして私たちは、現代の奇跡ともいえるシルバー・バーチからの膨大な霊界の情報を手にしています。本稿では、それらのいくつかを取り上げ、その真実性を、『新樹の通信』などの優れた霊界通信によって裏付けていってみたいと思います。私自身が関わってきた数多くの霊界通信の一部も、傍証として役立つかもしれません。
まず、私たちは霊界へ移った時にどのような形体を具えるのでしょうか。肉体は脱ぎ捨てていますからもう有りませんが、霊界では霊体をまとうことになるといわれています。それでは、その霊体とはどのような体なのでしょうか。シルバー・バーチは、それを「立派な胴体と、他人と区別のつく容貌を具えた、実在の個的存在です。また他人を認識するための感覚もちゃんと具えております。霊の世界で生きて行く上で必要な霊的器官が全部そろっています」(『シルバー・バーチの霊訓 (10)』p.69)と述べています。
しかし、そのように教えられても、私たちはまだ、どうもすっきりしません。霊体とはやはり幽霊のように影の薄い存在ではないかと想像しがちです。それに対してシルバー・バーチは、念をおすように、「よく理解していただきたいのは、あなた方人間にとって物質は固体性があり実感があり、霊というと何だが影のようで実体がないかに思えるのでしょうが、私たち霊界の者にとっては霊こそ実在であり、実感があり、反対に物質の方が影のようで実体感がないということです」(『霊訓 (10)』p.70)と確言しているのです。
この霊こそ実在であり、物質の方が影であるといわれていることが、私たちの理解しなければならない第一歩であるのかもしれません。そういうことを私たちの言葉で説明するのが非常に難しいのは、何度もシルバー・バーチからも聞かされてきましたが、ここでは、少しでも具体的なイメージが持てるように、私たちにとって親しみ深い霊界の浅野新樹氏に登場してもらうことにしましょう。
昭和4年12月29日、この日は新樹氏が昭和4年2月28日に大連の満鉄病院で亡くなってから10か月が過ぎていました。お父上の浅野和三郎先生が、46回目になる新樹氏との霊界通信で、「多少前にも尋ねたことがあるのが混じるだろうが、念のためにもう一度質問に答えてもらいたい。――お前が伯父さんに呼ばれて初めて死を自覚した時には自分の体のことを考えてみたか?」と問いかけました。伯父さんというのは、和三郎先生の兄上で、心霊研究のよき理解者で協力者でもあった海軍中将・正恭氏です。新樹氏はそれに対してつぎのように丁寧に答えて、問答が続けられています。(『新樹の通信』武本昌三現代文訳 7)
答「そうですね・・・・・。あの時、僕は真っ先に自分の体はと思ったようです。するとその瞬間に体ができたように感じました。触ってみてもやはり生前そっくりの体で、特にその感じが生前と違うようなことはありませんでした。要するに、自分の体だと思えばいつでも体ができます。若い時の姿になろうと思えば、自由にその姿にもなれます。しかし僕にはどうしても老人の姿にはなれません。自分が死んだ時の姿までにしかなれないのです。」
問「その姿はいつまでも持続しているものかな?」
答「自分が持続させようと考えている間は持続します。要するに持続するかしないかはこちらの意思次第のようです。また、僕が絵を描こうとしたり、水泳でもしようとしたりすると、その瞬間に体ができ上がります。つまり外部に向かって働きかけるような時には体ができるもののように思われます。――現に、いま僕がこうしてお父さんと通信している時には、ちゃんと姿ができています・・・・・・。」
問「最初はお前が裸体の姿の時もあったようだが・・・・・・。」
答「ありました。ごく最初に気がついた時には裸体のように感じました。これは裸体だな、と思っていると、そのつぎの瞬間にはもう白衣を着ていました。僕は白衣なんかいやですから、その後は一度も着ません。くつろいだ時には普通の和服、訪問でもする時には洋服――これが僕の近頃の服装です。」
ここで新樹氏が、「触ってみてもやはり生前そっくりの体で、特にその感じが生前と違うようなことはありませんでした」と答えていますが、これが、シルバー・バーチのいう「実体感」なのでしょうか。霊体でも肉体と同じく「生前そっくりの」実体感があることになりますが、ただ、霊界は思念の世界で、こころに思うことが現実になります。だから新樹氏も、「自分の体だと思えばいつでも体ができます。若い時の姿になろうと思えば、自由にその姿にもなれます」と言っているのでしょう。しかし、その一方では、「僕にはどうしても老人の姿にはなれません。自分が死んだ時の姿までにしかなれないのです」とも述べています。やはり老人の姿というのは思念が及ばないということかもしれません。
つぎに、霊界での住宅や周辺の環境についてはどうなっているのでしょうか。シルバー・バーチによれば、私たちがこの世で見慣れている家や建物などは、基本的には劇場や図書館などを含めて、すべて霊界には存在しているようです。博物館には地上の全歴史にわたる資料が保存され、大音楽家によるコンサートはしょっちゅう開かれている。図書館の書物についていえば、地上にある本のすべての複製もあるといいます。その様子を、シルバー・バーチはこう述べています。
霊界にも庭園もあれば家もあり、湖もあれば海もあります。なぜかと言えば、もともとこちらこそが実在の世界だからです。私たちは形のない世界で暮らしているのではありません。私たちもあい変わらず人間的存在です。ただ肉体をもたないというだけです。大自然の美しさを味わうこともできます。言葉では表現できない光輝あふれる生活があります。お伝えしようにも言葉がないのです。(『霊訓 (8)』pp. 115-117)
このような「光輝あふれる生活」については、さまざまな場面でシルバー・バーチが繰り返し伝えてくれています。「花も樹木もあり、動物も小鳥もいます。その美しさの中には実際にこちらへ来ないと分からない種類のものがあります」というのもあります。「霊界の有難い点は、地上のような“生きるための必需品”を得るための苦労がいらないことです。食糧品や衣類を買う必要がありません。お金を払ってまでして家を求める必要がありません。全部そろっているのです」と述べているのもあります。(『霊訓 (10)』pp.70-71)
要するに、この地上にあるものはすべて霊界にもあるらしいのです。この世のすべての物体に対応する霊的複製品があり、新樹氏もそうしているように、生活必需品が整えられたなかで何不自由なく元気に暮らしながら、散歩をしたり、泳いでみたり、音楽や絵画なども楽しむことができるようです。もちろん自分が住む住宅に不自由することもありません。シルバー・バーチは、「霊界ではみんな自分の家を持っているのか」と訊かれた時には、つぎのように答えていました。
―― はい、持ちたいと思う者は持っております。そう望んでそれなりの努力をいたします。が、持とうと思わない者もいます。同じく家を持つにしても自分の建築の好みに合わせて工夫する者もあります。例えばあなた方のご存知ない照明方法を組み込んだりします。こうしたことはその霊の創造的才能に関わる個人的な好みの問題です。
いったん家をこしらえたら、その建築様式は純粋にその人の好みの問題となります。青空天井にしたければそうなります。好みというものは長い間の習慣によって形づくられていることを忘れてはいけません。習慣は精神的な属性であり、死後も存続します。
生涯を英国だけで送った人は当然英国風の住居の様式に慣れ親しんでおり、したがって同じような様式の家に住むことになります。そういう習性が残っているからです。やがてその習性から脱け出せば、また別の種類の住居をもつことになります。こうしたことも生活の連続性を維持するための神の賢明なる配慮なのです。ショックを防ぎ、生活をスムーズに、そして調和のあるものにしてくれています。(『霊訓(2)』pp.149-150)
それでは、具体的に、新樹氏はどのような家に住んでいるのでしょうか。それをこれから見てみることにしましょう。昭和4年12月29日、前回と同じ第46回目の通信の時に、お父上の和三郎先生が、新樹氏の住んでいる家について聞いているところがあります。浅野先生も、新樹氏が霊界でどのような生活をしているのか、気になっていました。その時の問答はつぎのとおりです。(『新樹の通信』武本昌三現代文訳 同上)
問「お前の住んでいる家は?」
答「なんでも最初、衣服の次ぎに僕が考えたのは家のことでしたよ。元来僕は洋館の方が好きですから、こちらでも洋館であってくれればいいと思いました。するとその瞬間に自分白身のいる部屋が洋風のものであることに気づきました。今でも家のことを思えば、いつも同じ洋風の建物が現われます。僕は建築にはあまり趣味はもっていませんから。もちろん立派な洋館ではありません。ちょうど僕の趣味生活にふさわしい、バラック建ての、極めてあっさりしたものです。」
問「どんな内容か、もう少し詳しく説明してくれないか?」
答「東京あたりの郊外などによく見受けるような平屋建てで、部屋は三室ほどに仕切ってあります。書斎を一番大きくとり、僕はいつもそこにいます。他の部屋はあってもなくてもかまわない。ほんのつけたしです。」
問「家具類は?」
答「ストーブも、ベッドも、また台所用具のようなものも一つもありません。人間の住宅と違って至極あっさりしたものです。僕の書斎には、自分の使用するテーブルと椅子が一脚ずつ置かれているだけです。書棚ですか……そんなものはありませんよ。こんな書物を読みたいと思えば、その書物はいつでもちゃんと備わります。絵の道具なども平生から準備しておくというようなことは全然ありません。」
問「お前の描いた絵などは?」
答「僕がこちらへ来て描いた絵の中で、傑作と思った一枚だけが保存され、現に僕の部屋に懸けてあります。装飾品はただそれきりです。花なども、花が欲しいと思うと、花瓶まで添えて、いつのまにか備わります。」
問「いまこうして通信している時に、お前はどんな衣服を着て居るのか?」
答「黒っぽい和服を着ています。袴ははいていません。まず気楽に椅子に腰をかけて、お父さんと談話を交えている気持ですね………。」
問「庭園などもついているのかい?」
答「ついていますよ。庭は割合に広々ととり、一面の芝生にしてあります。これでも自分のものだと思いますから、敷地の境界を生垣にしてあります。だいたい僕ははでなことが嫌いですから、家屋の外回りなどもねずみ色がかった、地味な色で塗ってあります。」
ここでは、着ている衣服のこと、部屋の様子や家具のこと、それに家や庭のことに至るまで、全く自由で自然な会話の中で、こまかく伝えられていることに驚嘆させられます。生垣に囲まれた割合に広々とした庭がある3室ほどの洋風の家に、黒っぽい和服を着て気楽に椅子に腰掛けている新樹氏の姿は、私たちにも眼に見えるようです。この通信を仲介しているのは、優れて霊能者の多慶子夫人で新樹氏の母上ですが、その多慶子夫人の霊眼には、新樹氏の霊界の住宅がまざまざと映っていました。その見取り図もできているといいますから驚かされます。それは浅野先生によれば、とてもあっさりした、郊外の文化住宅らしいものだったとのことでした。
この時の会話の最後に、浅野和三郎先生が、「今日は、話が大へん要領を得ているので、お前の生活状態が髣髴としてわかったように思う。――しかし、私との通信を中止すると、お前はいったいどうなるのか?」と訊いていました。それに対して新樹氏は「通信がすんでしまえば、僕の姿も、家も、庭も、何もかも一時に消えてしまって、いつものふわふわした塊り一つになります。その時は自分が今どこにいるというような観念も消えてしまいます」と答えています。
こういう状況は、私たちの理解を超えますが、これも霊界が思念の世界であることの一つの表れでしょうか。「霊界では思念は実体のある存在なのです。存在するものすべてが思念でこしらえられているのです。ですから、必要と思うものはどんなものでも手に入れることができるのです」(『霊訓 (10)』p.70)と言っているシルバー・バーチのことばなどがここでも思い出されます。必要でなくなれば、だから、なにもかも、一時に消えてしまうのでしょう。
この会話のあと、浅野先生が、「そのうちひとつ、お前のお母さんの守護霊にでも頼んで訪問してもらおうかな」と言っておられますが、新樹氏が「そんなことができるんですか」と驚いている場面があります。その訪問は実現して多慶子夫人の守護霊は新樹氏と逢うためにやってきます。しかし、ここでは、より一般的な、霊界での親しい家族や知人との再会について次に取り上げてみたいと思います。私たちはこの世で死んだあと霊界へ還っていきますが、そこでは先に死んで霊界にいる縁のある人たちと再会することになります。その再開はどのようにして行われるのでしょうか。私たちの死からその再会に至るまでの過程を、シルバー・バーチは、まず、こう述べています。
死とは物的身体から脱出して霊的身体をまとう過程のことです。少しも苦痛を伴いません。ただ、病気または何らかの異状による死にはいろいろと反応が伴うことがあります。それがもし簡単にいかない場合には霊界の医師が付き添います。そして、先に他界している縁者たちがその人の〝玉の緒″が自然に切れて肉体との分離がスムーズに行われるように世話をしているのを、すぐそばに付き添って援助します。
次に考慮しなければならないのは意識の回復の問題ですが、これは新参者各自の真理の理解度に掛かっています。死後にも生活があるという事実をまったく知らない場合、あるいは間違った来世観が染み込んでいて理解力の芽生えに時間を要する場合は、睡眠に似た休息の過程を経ることになります。
その状態は自覚が自然に芽生えるまで続きます。長くかかる場合もあれば短い場合もあります。人によって異なります。知識をたずさえた人には問題はありません。物質の世界から霊の世界へすんなりと入り、環境への順応もスピーディです。意識が回復した一瞬は歓喜の一瞬となります。なぜなら、先に他界している縁のある人たちが迎えに来てくれているからです。(『霊訓 (8)』p. 103)
かつて、あのシャーロックホームズの生みの親であるコナン・ドイルも霊界へ還った時、この霊界での再会について、「愛する者との再会ほど喜びに満ち、心を慰めてくれるものがあるでしょうか。今は亡き、父親、母親、夫、妻、兄弟、姉妹、子供と、再びこの世とあの世の障壁を越えて心を通わせられるということを知るほど、心を慰めてくれるものがあるでしょうか。それは本当のことなのです。素晴らしいことに本当なのです」(『人類へのスーパーメッセージ』p.246)と述べていました。
ただ、ここでひとつ理解しておかねばならないことは、霊界とは階層社会ですから、私たちは霊界では、それぞれの霊格にふさわしい階層に住むことになります。つまり、これまでに到達した霊的レベルが同様の人たちが集まって暮らすのです。だから現世では家族全員が一緒に暮らしていても、霊界では必ずしも一緒でないこともあり得るようです。ある時、シルバー・バーチは、熱心なスピリチュアリストのある夫人を励まして、つぎのように述べたことがありました。彼女の夫は霊的なことにまったく理解を示さず、しかも重病の床にあって、夫を救えないことで彼女は悩んでいました。
―― 一つの家族が霊界へ来ても、自動的に合流するわけではありません。家族のメンバーが自然な霊的親和性をもっている場合にのみ、それが有りえます。親和性がなければ再会はありません。意識のレベルが違うからです。
夫婦の場合であれば、身体上の結婚だけでなく魂と精神においても結ばれていなければ、霊界での再会は不可能です。再会を決定づけるのは霊的親和性です。死後しばらくは血縁によるバイブレーションが残っていますが、それには永続性がありません。
霊は物質に勝ります。霊に関わるものは死後にも残り続けますが、物質に関わるものはそのうち消えます。お子さんにそのことをよく説明してあげないといけません。なかなかうまく説明できないかも知れませんが、とにかくすべてが不変の法則によって支配されているのです。その法則の根本にあるものは愛です。愛は大霊の表現です。神、創造主、どう呼ばれても結構です。首をうなだれてはいけません。あなたはしっかりと導かれ援助をうけておられます。きっと乗り切ることができます。一瞬たりとも挫折の心配を抱いてはなりません。このたびの経験は結果的にはあなたの霊性を強化し、前途に横たわる未来において大きな豊かさをもたらしてくれる貴重な教訓を植えつけてくれることでしょう。
私は地上の同志の方に気楽な人生、何の障害もない人生をお約束することは絶対にできません。私から言えることは、障害も困難もその一つ一つが挑戦すべき目標だということです。一つ克服するごとに、あなたは霊的に成長するのです。(『霊訓 (10)』、pp. 117-118)
シルバー・バーチも言うように、人生の目的は霊性の向上にあり、私たちは悲しみや悩みや艱難辛苦を乗り越えていくことで霊性を高め、霊界の生活に備えていくことになります。その霊性の発達度によって、おのずから霊界での生活環境がきまっていくことになりますが、私たちが数多く目にする霊界での再会も、いわばそのようなスクリーニングを経て実現しているのです。そのことを理解したうえで、ここでは、霊界でのアン・ターナーと私の妻と長男との再会を取り上げてみることにしましょう。
アン・ターナーは、ロンドンで私が逢うべくして逢った霊能者で、私の書いたものの中で何度も紹介してきましたが、彼女は、イギリスのウエールズで2010年の8月22日に癌で亡くなりました。亡くなる前の入院中には、霊界の私の妻・富子と長男・潔典が何度か彼女をお見舞いに訪れています。彼女は優れた霊能力者でしたから、霊界からの訪問者を認識することができます。病室で富子と潔典と手を握り合って、彼らのお見舞いに感謝していました。(『天国からの手紙』pp.272-277) そのアン・ターナーが霊界で、私の妻と長男に「再会」した記録が私の手許にあります。
私の『天国からの手紙』が学研パブリッシングから出版されたのは、アン・ターナーが亡くなった翌年の2011年6月でした。たまたま潔典の誕生日が6月5日で、彼は霊界からこの本の出版をいろいろと支援してくれていましたから、1日早めでしたが、その誕生日に合わせて、江東区清澄公園の大正記念館で6月4日に出版記念講演会を開くことになりました。その日は、講演のあとサイン会があって、それが終わってから、編集者の方々が、近くのレストランで潔典の誕生祝の会を催してくれました。その席上で、思いがけなく、編集者の一人で霊能者の
Uさんから、潔典が霊界から送ってきた手紙を渡されたのです。かなり長い手紙で、そのなかには、アン・ターナーに触れて、つぎのように書いていました。
―― アン・ターナーはこちらに参りました。神々様のお使いになるべく、日々修行に励んでおります。ぼく達とは縁で結ばれた方です。お互いにお互いを救う境遇に絶えずあります。こちらにおいても、現世のお父さんたちをも含めて、お互いに導き助け合うことが行われているのです・・・・・・
そして、このあとに私宛のアン・ターナーからのことばも伝えられました。「アン・ターナーからお父さんへ」と潔典の但し書きがあって、そのなかでアン・ターナーはつぎのように私の妻と長男との再会について触れています。以下は、彼女のことばです。
私たちは縁があってめぐり合い、共に歩んでまいりました。私はこの縁をたいへん有難く思っています。こちらにきてキヨノリとめぐり合い、トミコさんともお会いして、思っていたとおりの方々でした。素晴らしい方々です。
私は二人にたいへんお世話になりましたが、これもショーゾー、あなたとの縁が結び付けてくれたものです。さまざまなつながりの中で、人と人が和すること、これこそあなた方が本来持つ素晴らしいものですね。いま日本は(東日本大震災で)大変な時にありますが、あなたのその苦しみの経験から得たものを用いて、多くの人々が目覚める導きができることを、心から願っております。
霊界はなかなか良い所、素敵な所ですよ、ショーゾー。あなたがいらっしゃるのを楽しみにしています。どうかお体に気をつけて、それまで多くの人びとを導く活動を続けてください。そうそう、たまにはトニー(*アンの夫君)にも連絡してあげてくださいね。私は元気でいるとお伝えください。それではまたお会いしましょう。(アン・ターナー)
以上、霊界への帰還から霊界での再会に至るまで、霊界での広範な生活のうちのごく一部を断片的に拾い上げてみました。このなかで触れている新樹氏の生活にしても、詳しい生活状況については『新樹の通信』一冊分にもまとめられていますし、私の妻や長男からの通信も、『天国からの手紙』に載せたものを含めて、何人もの霊能者から受け取ったものが、過去20年の間にかなりの量に達しています。
最近では、大空澄人氏を通じて、時折、妻・富子からの通信も届くようになりました。そのなかには、霊界での再会について、「(地上世界では)様々な問題に遭遇して理解力が深まるのです。しかしながらそこで暮らすのは一時の事です。そこでのトレーニングが終了すれば元の愛の輪のなかに帰ることが出来ます。そこでは歓呼の再会があなたを待っています」などと伝えてきているものもあります。(2015.02.22「愛の輪」より) この私の霊界での家族との再会については、潔典からも今まで何度も聞かされてきました。具体的に歓迎の準備に触れているのもあります。それらの霊界通信の数々の記録によっても、いろいろと教えられ学んできて、いまの私にとっては、霊界とは必ずしも遠い未知の世界ではありません。
これまで私は、長年の間、このような霊的真理について講演会で話したり本に書いたりしてきました。一人でも多くの方々が、私の体験や学びを踏み台にして生と死の真実に触れていかれるようになることを願望していますが、ここでは、今回もまた、大空澄人氏のご了解を得たうえで、氏のご友人の霊界からの元気なお便りを最後に引用して、この稿を終えたいと思います。「続・いのちの波動」(1015.03.04) に、「海を眺めて」と題して、大空澄人氏は、幼友達であった霊界のご友人からのお便りをこう伝えておられました。かつてのこの世での、ふる里の小豆島の海で大空澄人氏と楽しんだヨット乗りの思い出から語り始められているのが、私のような大阪湾の海辺で生まれ育ってきた者には、ことさらに印象深く思われます。
[友より]
こちらは好きなだけヨットも楽しめるよ。君がこっちに来たらまた一緒にヨットに乗ろうではないか。そっちで暮らしていた時は仕事や家族その他の事にがんじがらめに縛られていた。それが今はそういうものから解放されている。そして何でも楽しみながら学ぶことが出来る。その辺がそちらとの一番の違いかな。
僕が暮らしていた地域ではお互いが足を引っ張り合うから伸びていけない。こっちに来たらまずそういう考え方を改めないと成長できない。僕は今そういうものを改めているところだ。そこで暮らしている間に染み付いた汚れを落としているのだ。
君がこちらの世界と通じるのはこちらの人間に近いからだ。欲が少なくて人と競争したりするのを好まないから。我の強い人間はこちらとは通じにくい。地位や名誉にこだわっている者も無理だ。理屈っぽいのもダメ。問題は無我の境地になれるかどうかだと思う。
子供の頃の純粋さを失わないことが大切だと思う。純粋な人間はすぐにこちらに溶け込めるようになるよ。人を恨んだり妬んだりしている人間は自分で自分を低いところへ落としているようなものだ。勝手に沈んでいくから。でもそういう人間はこちらに来るまでそれに気が付かないのだ。
**********
生まれ育った街への尽きせぬ思い (2015.07.01)
― 生活と文化をめぐる随想 (No.102) ―
少し古い本だが、司馬遼太郎氏のエッセイ集『司馬遼太郎が考えたこと[1]』(新潮文庫、2005年)に「大阪八景」という文がある。大阪に「人に誇れるほどの景色があるだろうか」と自問して、「ずいぶん思案をかさねてえらんでみた」という。その結果、「十分に手ざわりがあるから自信をもって推せる」と、挙げているのがつぎの八つの風景である。
まず最初に、「中之島の川沿いの風景」があげられている。私もむかし中学生の頃よく歩いて知っているが、司馬氏によればこれは日本一の都市美だそうである。「世界的だ」といったイタリアの画家もいたという。その次がよく知られている「法善寺横丁」で、そのあとに「淀川の十三大橋下の水際などに生い茂っている葦の風景」が続く。司馬氏は、この葦のある風景は浪速の伝統的なもの、と書いているが、私はそれには気がついていなかった。
次が、「源聖寺坂」。「これは大阪の中央にあるとは、これまで知るひとがすくないだろう」と司馬氏が言っているが、大阪生まれの私もいままで知らなかった。坂の上からのぞむと、つい足もとにミナミの雑踏が見えるのだそうである。5番目が「生駒連峰の麓にある枚岡の夕景」。そして6番目が、「生駒山の中腹の石切から見た大阪の灯」となっている。石切の小駅から西をのぞめば、河内、摂津の平野が一望でき、陽が落ちはじめる時刻には「はるかな大阪の灯が宝石のように輝く」と述べられているが、これは私にも微かではあるが、記憶に残っているような気がする。
残りの二つが、「尻無川の渡船場」と「夜の大阪城」である。大阪城は子供の時から私は何度も訪れているし、夜には大阪駅から天王寺へ向かう電車の窓から、ライトアップされた大阪城の遠景を見たこともある。しかし、夜間に近くまで行って見たことはまだない。司馬氏は、「くっきりと夜空にうかぶこの幻想的な風景は、太閤秀吉でさえみることができなかったものだ」と美しい大阪城の夜景を八景の最後に推している。
その前に、司馬遼太郎氏が七番目に推しているのが、「尻無川の渡船場」である。私は、ここを司馬氏が大阪八景のなかに選んでいることを知ってちょっと驚きもし、うれしくも思った。この付近は、私が生まれ育って小学校3年生まで過ごしたところである。司馬氏は「尻無川」について、「どうも名前がよくない。大阪の地名は詩的ではない。京や江戸と違って古来インテリの住む町ではなかったから地名がいかにも即物的である」と述べたあと、こう続けている。
「川とはいえ、千トンぐらいの船がゆうゆうと上下し、このあたりに荷のあげおろしをする。アジア貿易の基地でもあり、この川の盛衰は、われわれの台所にじかにひびくことになる。いわば都会のふところにあるポケット港だが、存外知られていない。」
この司馬遼太郎氏の「大阪八景」が最初に載ったのは、「婦人生活」第15巻第10号誌上のようである。昭和36年(1961年)9月1日のことで、この頃、氏はその前年に『梟の城』で第42回直木賞を受賞して、産経新聞社記者を退職し作家生活に入ったばかりであった。「婦人生活」のグラビアの、おそらく写真の説明文として書かれたもののようだが、その当時の「尻無川の渡船場」の写真がどのように撮られているのか、もう50年以上も前の雑誌だから、私はまだ見過ごしたままになっている。しかし、私が子供頃に慣れ親しんだ80年前頃のそのあたりの情景は、いまでもかなり鮮明に思い出すことができるような気がする。
この尻無川の渡船場は一般には、昔も今も、「甚平渡し」と呼ばれている。このあたりは、大正時代までは昔風の川の堤になっていて、紅葉の名所であったといわれていた。川の両岸にはハゼの木が数千本植えられ、紅葉の季節には「紅葉の紅が川の面に映じて風景斜めならず」と渡船場入り口の看板に賞賛のことばが書かれているのを見たことがある。いまは川の堤が高いコンクリートの護岸壁になっているが、私の幼年時代にはまだ護岸壁も低く、子供でも簡単に壁を乗り越えて川へ降りることができた。
実は、私は5歳のころ、この川で溺れかかったことがある。お盆が過ぎたあとだから、8月の下旬であったかもしれない。「お盆流し」といったであろうか、そのあたりではお盆には、木の舟に果物や菓子をのせて川へ流す「み霊送り」の習俗があった。この木の舟は、30センチくらいの小さなものから1メートルにもなるような大きなものまで様々で、それらが尻無川から一旦海まで流されたあと、波にもまれ風に吹かれて転覆し、中身を空にしたまま、たまに、川岸へ帰ってくることがあったのである。
暑い夏の日の午後、私はたまたま、そのような舟のかなり大きめの一つが、川べりに流れ着きそうになっているのを見つけた。幼い子供にとってはこれはたいへんな宝物である。近所の2歳年長の「カズちゃん」という男の子と二人で、私は渡し場の近くの川に降り立ち、川の上に浮かんでいる材木のいかだの上に乗り移って、棒切れで何とかその木舟を引き寄せようと必死になった。すぐ近くまで来ているのだがまだ手が届かず、もう少しというところでもっと手を伸ばそうと身を乗り出し、そして、水に落ちた。
5歳の私はまだ泳ぎを知らない。私は水の中で泣き叫びながら沈んでいった。口からも鼻からも水が入ってくる。息ができずに苦しく、ばたばた手足を動かしているうちに、一度、上へ上がってきた。しかし、振りまわしている私の手は何にも触れることなく、また小さい体はぶくぶくと沈んでいく。筏の上で私が落ちたのを見た7歳のカズちゃんも、ことの重大さはわかっていたであろう。いかだの端から身を乗り出し、手で水をかきまわしながら、懸命に私を掴まえようとしていた。
そのカズちゃんの手に、もがきながら2度目に上がってきた私の手がちょっと触れた。しかし二つの手は結ばれることなく、するりと抜けて、私はまた、ぶくぶくと水の中を沈んでいった。その時の青白い水の色がまだ記憶にある。私はばたばた手足を動かしながら泣き叫ぶばかりであった。かなりの水を飲んで、ひどく苦しいがどうすることもできない。息ができない時間が長く続いて、もう限度であったろう。死が迫っていた。そして3度目、ぶくぶくと水の泡のなかでまた上へ上がっていった時に、私の手はやっと小さなカズちゃんの手をしっかりと捉えたのである。
甚平渡しからは、かつて私が溺れかかった場所はほぼ正確に特定できる。私は、それから数十年を経た後でも何度か甚平渡しを訪れていたが、その場所を眺めてはしばらく感慨にふけっていた。そんな時には、自分はなぜあの時に死ななかったのだろうと、どうしても考えてしまう。かつての私は、この場所で溺れかけて救われたことを九死に一生を得た偶然の幸運のように考えていた。しかし、おそらくそれはそうではないであろう。後に私は15歳の時にも、「九死に一生の偶然」を繰り返すことになるが、いまでは偶然というのはないことも理解するようになっている。あの時、私の手を捉えたのは7歳のカズちゃんの小さな手であったが、あれは、まぎれもなく、神の手であった。
私は、その近くの甚兵衛渡しの待合室へもよく行った。この待合室は、昔は6畳ほどの小さな木造の小屋で、壁際にはコの字型に木のベンチが据付けられていた。小屋の真ん中には大きい四角の火鉢があって、その周りには、パイプ椅子のようなものがいくつか置いてあったと思う。なかに座って渡し船が出るのを待っている人々は、朝夕の通勤時間を除いては、多くても5、6人くらいで、私が片隅に腰掛けていてもあまり邪魔にはならない。私は、ここでも、いろいろな大人たちのいろいろな世間話に聞き入ったりして、あまり退屈することはなかった。
渡し船は無料で、2、30分おきくらいの間隔で対岸へ向かう。その時間になると、私も一緒に乗り込んでいた。交替で船を操縦するおじさんたちとは、すっかり顔なじみになっているので、私はいつも、操縦室でおじさんの隣に座っていた。操縦は、前進のギヤを入れてスクリューの回転を上げるアクセルを踏む。あとはハンドルを右左にゆっくりと切っていくだけである。これならボクにもできる、と私は思っていた。往復のたびに、あまりに熱心に私がおじさんたちの操縦ぶりを見ているので、ある時一人のおじさんが、「運転してみたいのか?」と訊いてきた。それは「操縦させてくれる」という意味が含まれているように思えた。私は大きく頭を縦に振って、「ウン」と答えた。
その時の私はまだ6歳で、小学校へも上がっていない子供にお客を乗せた渡し船の操縦をさせるというのは、今ではおよそ考えられないことである。操縦しているおじさんは大阪市の職員だから、そんなことをしたら、おそらく、地方公務員法違反、操縦規則違反、任務怠慢、人命軽視等々の「罪状」がすぐにでも挙げられることであろう。でもそのおじさんは私に操縦させてくれた。それも、一度や二度ではなかった。三度や四度でもない。私は、そのおじさんの船に乗った時には全力を尽くして操縦に努め、その技量(?)が認められて、その後も長い間、出発から着船まで100メートルほどの川幅を往復しながら何十回も操縦させてもらっていたのである。
ある強い風の吹く日の昼下がり、私はたまたまその日も渡し船のハンドルを握らせてもらっていた。川幅の中ほどを過ぎると、そろそろ速度を落として着船に備えなければならない。対岸の船着場の近くまで来ると、ギヤを逆にいれ、スクリューを逆回転させて減速しながらハンドルを右に切って左舷からゆっくりと船着場に着船する。それが普通なのだが、その日は風が強すぎた。ハンドルを右に切っても、風に流されて十分に船が廻りきれないところで、船の舳先が船着場のゴムタイヤのクッションにぶつかってしまった。
停船寸前であったから、ドシンと小さな振動が起こっただけで被害はなかったが、渡し場のおじさんは、さすがに慌てて、それ以後は私に操縦させてくれなくなった。しかし私は、いまも思い出すたびにそのおじさんにはこころから感謝している。私にとっては夢のように貴重な体験で、本当に「古きよき時代」であった。その二十数年後に私は、アメリカのオレゴン州の上空を小型自家用ビーチクラフト機で飛んでいたとき、20分ほど無免許操縦させてもらったことがあるが、この二つの無免許運転は、私がいまも密かに懐かしむ「法規違反」である。
私はその翌年、家から歩いて30分ほどの北恩加島小学校へ入学した。しかし、この小学校にいたのは1年だけで、次の年の4月からは、家からより近い、歩いて20分ほどの新設の新千歳小学校へ移った。私は学校が好きで、一日も休まず、毎日楽しんで登校していたが、その頃は、勉強が好きだとか、いい成績をとらなければならないとかいうような意識はまったくなかったように思う。入学前から片仮名も平仮名も書けたし、それに道を歩いているときに目につく家々の表札や商店、道路の看板に書かれている漢字もたいていのものは読めたから、私には「サイタ、サイタ、サクラガサイタ」から始まる一年生の国語教科書は易しすぎた。
家では、2学年上の国語教科書や冒険談、偉人伝などの少年向け単行本をよく読んでいた。しかし、そんなことよりも、急に友達が増えて、休み時間や放課後などに多くの級友たちと一緒に遊べるのが何よりも楽しかった。
私の家は、甚平渡しから200メートルくらいしか離れていなかった。甚平渡しの前から川を背にしてT字型に砂利道が伸びていて、途中で左に曲がると商店街を通って北恩加島小学校へ道が続く。逆に右に曲がると小さな橋(これも「甚平」がついた甚平橋という名前であった)を渡って新千歳小学校の前に出る。当時は私の家のまわりにもふんだんに空地があったし、甚平渡しから新千歳小学校までの砂利道の両側は、ほとんどが広い原っぱになっていた。そんな空き地や原っぱで、毎日毎日、私は夢中で遊びまわっていた。学校から帰っても夕御飯までの時間に家にいた記憶はほとんどない。今では、新千歳小学校も空襲で消滅したままであり、かつての遊び場所には多くの高層アパートが立ち並んで綺麗な小公園なども見かけるだけで、もう昔の面影を偲ぶよすがはない。
私は、この尻無川のほとりで小学校3年までを過ごして、小学校4年からは、生野区の生野小学校へ移った。当時40歳であった父が、十数年鉄鋼圧延技術者として勤めていた会社を退職して独立し、生野区に自分の小さな鉄工所を持つようになったからである。家も新築の2階建てに変わった。しかし、この生野区にも1年住んだだけである。圧延技術者としての腕を買われていた父が、大手の鉄鋼会社から執拗に頼まれて、朝鮮の仁川に赴任することになった。昭和15年(1940年)の後半、父は大阪から何度も仁川への長期出張を重ねて、仁川の郊外に建てられた約1万坪の鉄鋼圧延工場に大型機械の設計と設置を終え、昭和16年(1941年)の春からは、一家で仁川に住むことになった。
仁川には5年間住んだ。太平洋戦争敗戦の翌年、1946年に引き揚げて来てからは、私はかつての生野小学校に近い府立生野中学校へ転入学した。大阪は戦災で至る所に焼け跡がひろがり、見るも無残に変わり果てていた。何よりも極端な食糧不足で、日本人の1千万人が餓死するのではないかといわれていた。多くの児童、生徒たちは昼食の弁当を持参することもできず、生野中学の授業も午前中だけの日々が続いた。私自身も栄養失調で苦しんでいた。阿倍野駅の付近や天王寺公園などで餓死者の死体をみたこともある。父も、この敗戦と引き揚げで財産のすべてを失い、やがて大阪でまた自分の鉄鋼会社を立ち上げるという再起の夢も持てない状態になっていた。困窮と苦難の日々が長く続いた後、昭和23年(1948年)夏、私が東京都立第一高等学校(現・日比谷高校)へ編入学したのをきっかけに、一家は住み慣れた大阪を離れて東京へ住むことになった。大阪での生活はその年で終わった。
それからも67年が過ぎ去り、私は現在85歳になっている。いままで何度も大阪へは「帰って」いるが、そろそろ体力的にも長距離の旅行は難しくなってきた。今年の5月下旬に、私はもう一度だけ大阪を見ておきたいと思って、2泊3日の予定で出かけることにした。出来るだけ乗り物を利用して、歩くことを少なくすれば何とかなるような気がしていた。家の近くの場所からリムジンバスで羽田へ直行し、羽田からは伊丹空港まで飛んで、空港からはリムジンバスで天王寺へ着いた。あとはタクシーと地下鉄、電車で点と点を繫ぐようにして久しぶりの大阪を見てまわった。
天王寺の近くには私の6人兄弟姉妹のうち一人残っている妹が住んでいる。妹は83歳の誕生日を迎えたばかりであった。やはり体力が衰えてあまり健康とはいえないが、甥や姪も加わって一緒に食事をし、昔の家族のビデオなどを見たりして団欒のひと時を過ごした。昨年、2014年に全面開業したばかりの「アベノハルカス」にも上ってみた。地上60階建て、高さ300mで、超高層ビルとしては日本で最も高いのだそうである。60階の展望台からはすぐ下の天王寺公園、天王寺動物園、新世界の通天閣などから遠くの生駒山に至るまで、大阪の街がよく見えた。この建物は近鉄阿倍野橋駅の上の阿倍野百貨店を改造したものだが、敗戦後のこのあたりの、うらさびれた風景をよく覚えているだけに、私はいまさらのように今昔の感に打たれた。
司馬氏が「大阪八景」に挙げていた中之島の川沿いや法善寺横丁へも行ってみた。法善寺横丁は道頓堀のすぐ近くにある。石畳の狭い路地の両側に並ぶ料亭などの古い家並はやはりなんとなく風情がある。心斎橋の大丸百貨店へも入ってみた。ここへ私が初めて一人できたのは新千歳小学校の2年生の時である。その時は、たまたま正面入り口を入ったところに本の特売コーナーが設けられていて、少年講談本の『源義経』と『楠正成』であったか、2冊を束ねたものを25銭で買った記憶がある。もう80年近く前のことになるが、その入り口付近はあまり変わっていないような気がした。念のために年配の女性店員さんに聞いてみたら、「百貨店自体は拡張や新館増築でかなり広くなっているが、この入口のあたりの構造は内装は変わっていてもほぼ戦前のまま」であるという。その優しく響く大阪訛りが心地よかった。
帰路は、大阪駅まえの阪急電車で十三駅をとおり、蛍池からモノレールで伊丹空港へ向かった。阪急電車は、昔は阪急百貨店の建物の一階が阪急梅田駅になっていて、豪華なシャンデリアのついた広大なコンコースがあった。私は、敗戦後の生野中学生の頃、そこから宝塚方面行の電車に乗り、当時十三付近にあった大阪外国語学校の別科生(夜間部)として英語を学んでいた。改札口を通ると、「サ、ン、バ、ン、セ、ン・・・・タ、カ、ラ、ズ、カ、ユ、キィ・・・・」というように若い女性の柔らかなきれいな声がスピーカーからゆっくりゆっくりと流されていた。当時は殺伐とした世相で、大阪市民はみんな食糧難で苦しんでいただけに、そのスピーカーの穏やかな透き通った声は、一服の清涼剤のように、多くの乗客のこころに優しくしみこんでいったような気がする。しかし、いまの阪急梅田駅は、1973年(昭和48年)に移転拡張工事で変わってしまった。ターミナル駅としての賑わいはあるが、もう昔の情緒はない。
この阪急電車で宝塚行に乗り十三大橋を渡ったときには、司馬遼太郎氏が「大阪八景」にあげた「十三大橋下の水際などに生い茂っている葦の風景」を思い出していた。それを見つけようと目を凝らしていたが、それらしいものが一瞬目に入っただけで、すぐに大橋を通り過ぎてしまった。伊丹空港から羽田へ向かって日航機が離陸したときには、大阪湾を横切る途中で上空から尻無川が見えるはずであったが、これも窓から見下ろして探しているうちに雲がかかってしまって見ることは出来なかった。羽田からはまたリムジンバスに乗り、私はなんとか無事に家に辿りついた。体力の衰えを見据えて、行くなら今しかないと敢行した私の大阪への2泊3日の旅は、こうして、思いのほかあっけなく終わった。
**********
32回目の「9月1日」を迎えて (2015.09.01)
― 生活と文化をめぐる随想 (No.103) ―
32年前の1983年8月31日の午後7時(日本時間9月1日午前9時)、私はアメリカのノースカロライナ州の首都ローリーの自宅で、帰国途中の妻と長男が乗った大韓航空機007便が「サハリン沖で行方不明」というテレビニュースに接しました。2、30分おきくらいに何度かそのニュースが繰り返された後、一時は、「サハリンに不時着した」というスポットニュースが流れたのですが、そのニュースも、間もなく、ソ連政府がその事実はないと否定したことが伝えられました。その時に、大韓航空の広報担当の若い女性が、テレビの取材者に答えて、「大韓航空機がサハリンに不時着していることは間違いありません。私たちは確かな筋(reliable
source)からその情報を得ているのです。乗客は全員無事です。乗員も無事です」と頬を紅潮させて、一気に言い切ったのです。ソ連政府の否定にも関わらず、彼女はその後も、二度、三度その主張を繰り返していましたが、いま振り返ってみますと、これは事件の真相を示唆する極めて重要な発言であったかもしれません。
悲嘆の底に突き落とされた私は大学の教職を中断して、その翌日、娘と共に日本へ向かいました。東京に着いてからは、遺族のために用意されたホテルに連れて行かれて、私はほとんど寝たきりのまま部屋に閉じこもっていました。長い間、新聞なども読む気力がありませんでしたから、これもかなりあとで気がついたのですが、「朝日新聞」10月9日の朝刊で、米中央情報局(CIA)の元要員であったラルフ・マギー氏がユタ州オグデンの大学で講演し、「ソ連が撃ち落とすとは思わずに、大韓航空機にスパイ飛行させた計画的行動だ。証拠は山ほどある」と言っていたことが報道されていました。それに対して、CIAのスポークスマンは、「まったく根拠がなく無責任だ」と述べたことも伝えられていましたが、このマギー氏の講演内容も、いま振り返ってみますと、事件の真相を示唆する極めて重要な発言であったかもしれません。
私は東京のホテルに閉じこもったまま一か月を過ごして、一度、アメリカへ帰りました。大学の講義に打ち込むことで、娘は大学の勉強に追われることで、なんとか起き上がるきっかけを掴もうとしていました。しかし、ノースカロライナの自宅に帰っても、ほとんど寝たきりの状態で教壇に立つこともできず、結局すべてを諦め、私は娘をつれて日本へ帰りました。11月の初めのことです。帰国後、久しぶりの札幌の自宅に住むようになりましたが、事件の後遺症からはなかなか立ち直ることは出来ませんでした。勤務先の小樽商科大学からは「自宅研修」という扱いを受け、実際に出勤するようになったのは、翌年1984年の4月からです。それ以来、授業だけは休まずにきちんと学生たちに接したつもりですが、苦しい日々が続きました。
事件そのものが極めて異常で、多くの疑惑に包まれていただけに、私は遺族の一人として真相究明を訴えていかねばなりませんでした。悲嘆の底に沈みながらも真相究明の活動を続けていくことは殆ど耐え難いほどの苦しみでしたが、黙っていることはできませんでした。その年、1984年の7月ごろから、東京でも「大韓航空機事件の真相を究明する会」の設立準備が始められ、瀬谷英行、田英夫、宇都宮徳馬、土井たか子、山川暁夫氏らが設立発起人21名を代表して、記者会見を開き、声明を発表して設立のための呼びかけを行っていました。10月20には、議事堂の近くの憲政記念館で「大韓航空機事件の真相を究明する会」の設立総会が開催され、20名の理事のうち4人が代表理事に選ばれ、私もそのうちの1人になりました。
私は個人でも真相究明を訴えるB4版の広報紙「APPEAL」を編集して、毎週、国会議員やマスコミ宛てに発送していましたが、その翌年1985年の5月には、『疑惑の航跡』(潮出版社)を発刊し、月刊誌「世界」(岩波書店)10月号に「遺族はなぜアメリカを弾劾するか」を発表して事件の真相を訴えようとしています。調べていけばいくほど、この事件はアメリカ政府の犯罪であることを、私は確信するようになっていました。1986年の4月には、私は小樽商科大学を退職して、東京の私立短大へ移りました。私にとっては、国立大学教授の地位とか名誉といったようなものは、もう何の意味ももたなくなっていました。ただ、事件の真相究明運動だけは続けて、知りえた真相の一端を世間に訴えていかねばならないと必死になっていました。東京では、毎月のように開かれていた「大韓航空機事件の真相を究明する会」の研究会に欠かさず出席していましたが、その研究成果は、後に、1988年1月発刊の『大韓航空機事件の研究』(三一書房)にまとめられています。これは編著者が私の名前になっていますが、もちろん私一人のものではありません。航空技術者、社会運動家、評論家等、会員諸氏の長年の献身的な真相究明の努力が結集された大冊です。
この本の中でも私は、明らかになったアメリカ政府の犯罪についていろいろと述べていますが、そのうちの一つに、KAL 007便がサハリンに侵入する直前の航跡データがあります。このデータでは、007便は午前3時2分に、サハリン直前でほぼ直角に右旋回し、それからやや緩やかに左旋回してサハリン上空に突入しています。それを追っているソ連機は、3時9分に「そうだ、目標は方向を変えた。・・・・・目標は当方の左方80度」などと言っていることが防衛庁公表の交信記録でも確認されていました。しかし、防衛庁はこの旋回部分のレーダーデータは公表しませんでした。公表したのは007便の右旋回と左旋回が終わった3時21分からで、その前はブランクになっていたのです。衆参両院での満場一致の真相究明の議決がありながら、時の日本政府もアメリカ政府の情報操作に加担する態度を崩していませんでした。
私たちは国会議員にも働きかけて、自衛隊が把握しているはずの稚内レーダー・データについて国会で何度も政府に質問してもらいました。それに対して当時の矢崎防衛局長は、自衛隊が捉えたのは「すでに公表したものがすべてである」と同じ答弁をくり返しました。しかし、それが嘘であることはあまりにも明白でした。すべてを公表すれば、KAL機の意図的な領空侵犯が明らかになってしまいますから、おそらく、アメリカ政府の関与が露呈することを怖れた日本政府の意向をうけて、矢崎氏は必死に嘘をつき続けたのでしょう。この点については、「真相を究明する会」の増尾由太郎氏が、「世界」1985年5月号の論文「大韓航空機事件と自衛隊」の中で多くの資料とデータをもとに、極めて明快に矢崎氏の嘘と自衛隊の情報操作の一端を「立証」しています。ある報道関係者はこの論文を読んで、「震えが止まらなかった」と卒直な感想を私に洩らしました。
この増尾論文の中で述べられているような事実が明らかになるまでには、衆議院予算委員会における大出俊議員の2月15日以降3回にわたる周到に準備された長時間の質問と追及がありました。この大出俊議員の追及により、防衛庁は1985年2月28日、はじめて、「自衛隊のレーダーによる大韓航空機の高度及び速度等」というレーダー記録を同議員に提出しました。その前に、シェミヤのレーダー記録を要請しようとして政府に拒否されていた秦豊参議院議員も、この防衛庁の資料について再度の質問主意書を提出しました。これに対し政府も5月14日、遂にこの自衛隊レーダーの内容を認める答弁書を出したのです。これで、KAL
007便のパイロットが成田管制には嘘の報告をしながら、意図的に操縦かんを握るなどしてソ連領空を左右上下に跳梁していた事実を日本政府が公式に認めたことになりました。事件後もう2年近くになっていましたから、領空侵犯の真相の一部を明らかにしても、アメリカ政府への影響は最小限度に抑えられるという判断があったからかもしれません。
それではなぜ、あの007便が500キロも航路を外れて意図的にサハリンの上空へ飛びこんでいったのでしょうか。千柄寅機長の夫人の「証言」がありますが、機長は出発前に十分に危険を意識して、その日の勤務をいやがっていたといいます。新たに生命保険もかけていました。その機長の千柄寅が、自分だけの判断で乗客・乗員269名の生命の危険を冒してまでソ連の軍事基地の上空を故意に飛ばなければならない理由はありません。考えられる理由はただ一つ、アメリカ側からの「強い要請」です。防共の最前線として、軍事力の多くをアメリカに依存せざるをえない韓国は、アメリカのそのような非情な「要請」に対しても、それを断ることができない弱い立場にありました。1978年のムルマンスク事件がその前例です。この時にもKAL機はソ連領空を侵犯してソ連機の攻撃を受け、日本人と韓国人の乗客2名が死亡し、13名が重傷を負ったうえで強制着陸させられています。007便も最悪の場合でもサハリンに強制着陸ですむとアメリカ軍部は予想していたのでしょう。悪質なのはそのアメリカ軍部ですが、おそらく千柄寅も、いやいやながらもその「要請」を受け入れざるをえなかったに違いありません。
KAL 007便の交信記録の最後は「1212デルタ」(日本音響研究所の解析では「101デルタ」)で終わっていることが、1983年10月5日に運輸省が公表した記録で明らかになっています。これは、民間航空機なら決して使うことのない「アメリカの某機関」に対する暗号といわれているものでした。このような「暗号」を最後に発していること自体が、007便の哀れな、しかし人道上決して許すことのできない、領空侵犯の役割を雄弁に物語っているといっていいでしょう。またこの暗号は、はじめに挙げた米中央情報局元要員のラルフ・マギー氏のことばにあるとおり、このKAL機の領空侵犯はアメリカ軍部が「ソ連が撃ち落とすとは思わずに、大韓航空機にスパイ飛行させた計画的行動」であったことを強く示唆するものにほかなりません。そして、事件発生時に私がテレビで聞いた大韓航空広報担当の女性の、「大韓航空機がサハリンに不時着していることは間違いありません。私たちは確かな筋からその情報を得ているのです」ということばも、この「確かな筋」、アメリカの某機関からそう伝えられていたことをつい漏らしてしまったのだと思われます。
私はアメリカ軍部の犯罪であることのゆるぎない確信のもとに、アメリカ大統領レーガン、国務長官シュルツ、国防長官ワインバーガー等に対して何度も抗議文を送り、激しい口調で彼らをののしりました。一方では、機会あるごとに、新聞、雑誌、テレビを通じて、事件の真相を訴えかけていました。しかし、ソ連の蛮行という圧倒的な大キャンペーンが広がって定着してしまったあとでは、月日の経過とともに事件は風化するだけであったかもしれません。冷や水を浴びせかけるように「もう何を言っても後の祭りだ」と放言したアメリカ政府寄りの評論家もいました。マスコミの多くは、領空侵犯の真相は「闇の中」として扱うだけで、NHKなどに出演して多くの資料を開示し熱心に説明しても、「アメリカ軍部の犯罪」に関連する部分だけはカットされてしまったりもしました。悲しみと空しさが交錯するなかで、私は「大韓航空機事件の真相を究明する会」の活動を1991年の3月まで続けて、その後、代表理事を辞任して日本を離れ、イギリスへ向かうことになったのです。
ロンドンで一人暮らしを始めてからも、私は、妻と子を奪われた悲嘆から立ち直れず、アメリカ軍部に対する強い憎しみをも抑えきれないでいました。そんななかで、客員教授としてロンドン大学に通いながら、少し落ち着いてきたころ、私は初めてシルバー・バーチの霊訓集を深く読むようになったのです。その重大性にも気づいて、自分でも原書を訳してみたりしました。大英心霊協会へ通うようになったのもそれからです。事件の真相究明運動とアメリカ政府、軍部に対する憎しみからは、なんのこころの安らぎも得られませんでしたが、私はシルバー・バーチの教えに少しずつ目を開かれ、癒されていきました。そして、年を越して1992年に入ってから、2月11日に、遂に霊界の妻と子に「再会」することができたのです。大英心霊協会で逢うべくして逢ったといえる霊能者アン・ターナーのお蔭でした。私はこころから救われ、深く安堵し、生き返ったような気持ちになりました。その後も何度も大英心霊協会を訪れ、十数人の霊能者にも会って、霊界で妻と子が生き続けている事実を確認しています。
1992年の4月に帰国してからは、熱心に霊界について学ぶようになりました。やがて、「生と死を考える」講演会を開くようになり、本も書き、2003年からはホームページ「ともしび」も開設しました。その間も続けられていた霊界の妻と子との数多くの交信も、その記録を「ともしび」や『天国からの手紙』に記載してあります。事件後20年の2003年の9月1日には、稚内宗谷岬の慰霊塔の前で行われた大韓航空機事件の犠牲者を悼む20年目の慰霊祭に私も出席しました。慰霊塔の壁には、かつて私が血を吐くような思いで原案を書いた碑文「愛と誓いを捧げる」が刻み込まれていますが、その時の私にはもう当時の絶望感も悲嘆もなくなっていました。遺族の方々が取材の記者たちに吐露している「何年経っても深い悲しみが和らぐことはありません」というようなことばが耳に入っても、私は同情しながらも聞き流していました。事件後30年の一昨年、2013年9月1日には、北海道新聞の編集委員から、「消えることのない遺族たちの悲しみについてどう思っているか」と聞かれて、私はこう答えました。
「30年経ってアメリカ政府が嘘と欺瞞でその犯罪を隠しおおせたようにみえても、広い視野でみれば、『宇宙の摂理』とでもいうべき絶対律のなかでは、誰一人、犯した罪から逃れることはできません。遺族としていつまでも嘆き悲しむというのも、犠牲者に対する供養には決してならないでしょう。長年の悲しみと苦しみを経て、私は、その宇宙の摂理のなかでの人間の生と死や自分自身をも見つめ直すようになりました。」
この事件で大きな漁夫の利を得て、危ぶまれていた大統領の再選も果たし一挙に軍拡の道を進めていたロナルド・レーガンも2004年6月に亡くなり、国防長官であったキャスパー・ワインバーガーも2006年3月に亡くなりました。タカ派のレーガン政権のなかでただ一人の穏健派といわれていた元国務長官のジョージ・シュルツだけは存命で、現在は94歳になっているようです。アメリカの情報公開法などによって、事件に深く関わっていたアメリカ軍部の「犯罪首謀者」たちの人名も明らかにされる時が何時かはくるかもしれませんが、いまの私には、彼らに対するかつての憎悪の念は殆どありません。一昨年の9月1日にも述べたように、アメリカ軍部の犯罪者たちは一時の小細工で世界の眼をくらまし重大犯罪を隠しおおせたつもりでいても、天の摂理をごまかすことは決してできないのです。彼らが犯した人道の罪に対しては、やがて寸分の過不足なく、彼ら自身が償うことになっていくはずです。
事件が起こったあの「9月1日」から32年が経って、私も85歳になりました。事件の直後は眠ってばかりしていて、目が覚めて厳しい現実に直面するのが苦しくていやでした。このまま目が覚めなければどんなに楽かと思ったりしましたが、その私が今日まで死ぬこともなく、随分長生きしたものだと思います。これも天命なのでしょうか。いまは、妻と子の霊前に静かに手を合わせながらも、私がなぜあのような苦しい目に遭わねばならなかったのかと嘆くようなことはありません。家族が大きな事故や事件に巻き込まれることもなく平穏に暮らしている人々に較べて、自分は惨めで不幸ではないかと思うこともありません。好むと好まざるとにかかわらず、自分に残された余命は僅かしかないであろうことはよく承知していますし、せめて、その残された僅かな時間だけは、安らかな気持ちで過ごしたいという思いはありますが、それでも、世間並みの辛さや苦しみがつきまとうことがあれば、最後の学びのつもりで穏やかに受け留めていくことにしたいと密かに考えているところです。
**********
大いなる力に導かれて生きる
(2015.11.01)
― 生活と文化をめぐる随想 (No.104) ―
どういうわけか苦しい、悲しいことが続いた。
幾年を経て、それが深い意味をもつことを知った。
1982年(昭和57年)2月8日(月)の早朝に発生した東京・千代田区赤坂見附のホテル・ニュージャパンの火災は、死者33名、負傷者34名を出す大惨事となった。当時、小樽商科大学に在職して札幌に住んでいた私は、この日の夕方、空路で羽田について東京に滞在していた。その翌日、フルブライト上級研究員の最終口頭試験に臨むためであった。試験会場の山王ビルは、そのホテル・ニュージャパンに隣接していた。私がかつて通っていた高校は、その裏側の丘の上にあったので、この辺の地理には私は詳しかった。久しぶりに現地を訪れた時、ホテル・ニュージャパンは前日の火災の惨状をまだそのまま残していた。黒こげになったホテルの窓のいくつかからは、宿泊客が脱出を試みたと思われるシーツを繫ぎ合わせてロープ状にしたものが何本も汚れた壁に垂れ下がったままになっていた。私は不吉な影を追い払うようにして、フルブライトの試験場に入った。
口頭試験は、フルブライト委員会のヤング事務局長を含めた3人の試験委員を前にして行なわれた。私はその頃、ドイツ・ハイデルベルグの応用言語学会機関誌「International
Review of Applied Linguistics in Language Teaching」(IRAL)に掲載されることになった「Cultural
Implications of Language Contrasts between Japanese and English」(日英語の言語比較と文化的意味)という論文を書いていて、そのコピーも審査資料の一部として委員会には提出していた。その論文を中心にしていろいろと質問され、30分ほどで口頭試験は終わった。3人の試験委員たちの反応は悪くはなかったようなので、私はもしかしたら合格するかもしれないと思った。私はその翌日、札幌へ引き返した。
フルブライトの書類審査は前年の秋から始まっていた。その時の口頭試験は予備審査を通過したあとの最終段階であったので、その合否については、まもなく通知がくると思われた。通常は最終段階の口頭試験から一か月もかからないことを私は聞いていた。しかしその年に限って、合否の通知は、1か月過ぎても、2カ月経っても来なかった。大学で教えている場合、一年も海外へ出かけるような長期出張には、当然ながら留守中の授業担当者を非常勤で手当てするなどの措置が必要になるから、少なくとも半年以上の余裕をもって申請しなければならない。5月に入って、もうこれ以上は待てないから、大学に迷惑をかけないためにも、フルブライトへは辞退の連絡をしなければならないのではないかと考え始めたころ、やっと、「上級研究員」決定の通知が届いた。後でわかったことだが、アメリカの不景気による政府の財政難で、その年に限って、予算決定が大幅に遅れたからであったらしい。
私は9月中旬に、1983年9月14日までの一年間の予定でアメリカのアリゾナ大学へ向かうことになった。妻とアリゾナ大学への編入が決まった長女が同行し、東京外国語大学在学中の長男は東京に残る予定であった。ところがその後、当時、東京・荻窪の実家に住んでいた妻の母親が胃がんに冒されていることがわかって、妻は急遽、渡米を取りやめ、看病のために東京に残ることになった。私と長女だけが渡米して、アリゾナのツーソンに住み始めた。妻の母親、山本雪香はその年は持ち越したが、翌年、1983年の2月に亡くなった。母親に付き添って看病に明け暮れていた妻は、悲しみと過労で、葬儀のあと寝込んでしまった。
長男の潔典(きよのり)は、はじめの予定では、1982年9月に私と妻が長女と渡米した後は、翌年3月からの春休みに、アリゾナへ来て家族と合流することにしていた。それが私たち家族にとっては2度目のアメリカ生活になるはずであった。1973年の暮れから1975年の初めにかけて私は文部省在外研究員としてアメリカのオレゴン州に滞在したが、その時は家族4人が一緒であった。長男と長女は、現地の小学校、中学校へ通い、夏休みにはアメリカとヨーロッパの旅を続けるなどの楽しい思い出があった。私はそれが子供たちに対する最良の教育だと思っていた。1983年の春休みに長男が来れば、またアリゾナのツーソンで家族水入らずのアメリカ生活ができることになる。私はまた子供たちに貴重な教育の機会を与えることに執着していた。しかしそれも、妻の母親の葬儀と、その後の妻の体調不良で、妻と長男の渡米は諦めなければならなかった。次のチャンスは、夏休みしかない。しかし、夏休みをアメリカで過ごすためには、私のフルブライト上級研究員の滞在期間を少なくともあと半年は延長する必要があった。
フルブライトの上級研究員の場合、通常であれば、滞在期間を延長するのはあまり困難ではない。一年後の9月以降、どこかの大学で研究を続けるか教えるかして、給与を受け取る形を整えればよいことになっていた。私は妻と長男の春休みの渡米が困難になった時点で、私の研究分野に沿うような教育・研究担当者の公募があれば応募することを考えるようになった。アメリカは大学の数も多いし、「フルブライト」にはそれなりの権威が認められていたから、私は何とかなるのではないかと思っていた。しかし、現実は予想外に厳しかった。その年に限って、アメリカの大学は、私の居たアリゾナ大学を含めて、軒並みにあまり前例のない大幅な予算削減に苦しんでいたからである。アリゾナ大学卒業生の就職も「最悪の状況」といわれていた。
その年のアメリカ社会は、大変な不況で、失業率も1930年の大恐慌以来の11パーセント近くになっていた。2パーセント台であった好景気の日本では想像もつかない深刻さであったといってよい。私が住んでいたツーソンでも、市で清掃夫を12名募集したら、750人の応募者が早朝から長蛇の列で並んだという。ある石油会社の見習い工数十人の募集には、応募者は、前日から徹夜で並んだ人を含めて3,000人にふくれあがったという新聞記事もあった。アメリカ各地の大学の教員、研究員の公募も極端に数は減っていたが、それだけに就職競争も激しかったかもしれない。
その当時、1982年の日本では、経済の高度成長を経て安定成長期にあり、バブル景気の余波はまだ続いていた。日本の自動車生産も1980年には米国を抜いて世界一になっていた。その影響を受けたアメリカの自動車産業は深刻な不況に悩み、「日本憎し」の声が全米に広がっていた。アリゾナ大学のキャンパスでも、日本製の新しい自動車一台を叩き壊して土中に埋めるというイベントが行われたりした。しかし、その一方では、社会学者エズラ・ヴォーゲルによる1979年の著書『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(Japan
as Number One: Lessons for America)が、アメリカでベストセラーになっていた。アメリカの大学でも日本語や日本文化に関する関心が高まって受講生も増える傾向にあった。だから不況の中でもこの分野での教員の公募には、僅かに期待がもてるのではないかと思われた。
そんな折に、12月中旬、カリフォルニア州モントレーのアメリカ海軍語学校から、私が所属していたアリゾナ大学言語学部に、日本語講師公募の書類が送られてきた。この学校は、後に日本文学の大家として知られるようになったドナルド・キーンさんが学んだ学校でもある。私はここの外国語教育には関心があった。軍隊は嫌いだが、この学校独特の外国語教授法の実態を知りたいと思ってきた。印欧系のなかでの外国語教育は、日本の英語教育にはあまり参考にはならない。アルタイ系ともいわれたりするが世界で孤立している日本語と印欧系の英語は、互いにきわめて異質であるから、日本語から入る英語教育で参考になるとすれば、英語から入る日本語教育である。そのような観点から、私はいくつかの論文も書いてきた。
私はアメリカ海軍語学校の教員公募に応募することにした。これが無事に通って、翌年9月からカリフォルニアへ移ることになれば、家族との再会もカリフォルニアにすればいいと考えたりもした。私は、履歴書、研究業績一覧表などと共に、要求された英文のエッセイと日本語のエッセイを新しく書いた。与えられたテーマについて、英語と日本語でそれぞれに口頭で録音テープに吹き込むという作業も済ませた。12月29日に応募書類とテープをアメリカ海軍語学校へ送った。念のために、アリゾナ大学言語学部の掲示板に貼り出されていた公募書類のうち、マサチューセッツ大学、プリンストン大学、ノースカロライナ州立大学にも、同様の応募書類を発送した。応募書類の作成で明け暮れしているうちに、何時の間にか、アリゾナの砂漠の町での1982年は過ぎていった。
翌年の1983年3月25日から3日間、サンフランシスコのヒルトンホテルで言語学会が開かれた。言語学、外国語教育の研究者が全米から集まることになっていて、アリゾナ大学からも十数人の教授、助教授、大学院学生と共に私も参加した。アリゾナのツーソン空港からロサンゼルスを経由して約1,300キロを飛んで10時過ぎにサンフランシスコに着き、学会会場のヒルトンホテルへ向かった。アメリカでは、学会は求人の場合の候補者選考の場にもなっていた。研究発表のプログラムが終わると、別室に設けられたPlacement
Service(就職斡旋)の部屋で、教員を公募している幾つかの大学が机を並べて、求職中の教員、就職を希望する大学院学生たちと面談することになっていた。学会二日目の午後、私はここでノースカロライナ州立大学のK教授に会った。K教授は私の採用に強い意欲を示していた。この時の面談でも、4月中旬には正式に決定できるだろうと言った。
アメリカ海軍語学校からもポジティブな反応が続いていた。1月下旬以降、私のパスポートとビザの写しを求めてきたり、私の1974年からのオレゴン大学客員教授時代の勤務内容についての照会があったりした。4月1日には、Notice
of Rating (資格査定通知)が届いた。アメリカ海軍語学校独特の査定で、総合点数99点、1級インストラクター(GS-7)という書類が届き、GS-7に対応する俸給表なども同封されていた。しかし、任用予定については何も触れていなかった。電話でそのことを問い合わせると、予算の決定があり次第、任用については追って知らせるというような返事であった。ここでもまた予算であった。私は滞在期間延長を在籍中の小樽商科大学へ申請するかしないかの決断を迫られていたので、少し考えて、5月末までにアメリカ海軍語学校の任用が決定されなければ、赴任することはできない、と手紙を出した。
それまでに、応募書類を出していたマサチューセッツ大学からは、1年間だけの短期任用は受け入れられないという返事があり、プリンストン大学からは、求人の対象は教授クラスではなく若手の大学講師クラスに絞っているという返事を受けていた。4月初めの時点で、滞在期間延長のための就職可能性が残されていたのは、アメリカ海軍語学校とノースカロライナ州立大学の二つだけになった。ところが、そのノースカロライナ州立大学のK教授から4月中旬に手紙がきて、任用決定が少し遅れるかもしれないといってきた。さらにその後電話がきて、遠慮がちに、フルタイムで駄目の場合、パートタイムでも教えてもらえるかと聞いてきた。やはり予算削減で苦しんでいるようであった。パートタイムで週6時間教えて、給料はフルタイムの半分になるのだという。私はパートタイムでもいいから任用を決定してくれればそれに従うと答えた。給料の多寡よりも、滞在延長手続きのためには、任命決定書を早く小樽商科大学の人事委員会に提出する必要があった。
その年のアリゾナ大学の講義は、5月初めにすべて終わって、5月6日からは期末試験であった。娘の場合は、5月12日の人類学の試験が最後で、翌日からは夏休みに入る。5月30日からは、フルブライトの年次集会が予定されていた。アメリカ全土に散らばっているフルブライト研究員たちが呼び集められ、一堂に会して総会と研究分野別の研究会に出席するのである。たまたま会場は、ノースカロライナ大学(University
of North Carolina)の所在地チャペルヒルであった。通常、各州には二つの代表的な州立大学があって、ノースカロライナ州立大学(North
Carolina State University)のほうは首都のローリーにある。私はこの年次集会に出席している間に、ローリーへ行って、ノースカロライナ州立大学のK教授にも会うことになっていた。そのノースカロライナ州立大学の任用は5月の20日を過ぎても、まだ決定の連絡はなかった。アメリカ海軍語学校のほうも、任用通知はまだ届いていなかった。私は悩みながら、滞在延長は取りやめて帰国することも考えるようになっていた。いずれにせよ、私のアリゾナでの生活はまもなく終わろうとしていた。
その頃、アリゾナ大学で私の世話役になっていたベイリー教授から、砂漠の中での朝食会に招待された。私の親しい友人で牧師のウエンガーさんが日本文化研究で博士号をとって、カリフォルニアの大学への就職が決まっていた。そのウエンガーさんや私に対する送別会のつもりであったようである。5月28日の土曜日、午前6時半に、私と娘はベイリー教授の家に着いた。ベイリー教授一家4人、ウエンガーさんの家族4人、それにアリゾナ大学で博士課程にいる日本人留学生3名を含めて、総勢13名が3台の車に分乗して砂漠へむかった。町の中心部から東へ約40分、ツーソンでは一番高いレモン山へ行く途中に、ベイリー教授の目指す場所があった。灌木の中の空き地にテーブルを組み立て、持参のコーヒー、サンドイッチ、果物などで朝食をとりながら、とりとめのないおしゃべりを楽しんだ。
朝早いうちは何とかしのげるが、日中の気温は摂氏で40度近くに上がるので、長くは居れない。一時間ほど過ぎて、そろそろ引きあげようとしていた時、近くの灌木の陰でドーンという車がぶつかったような音がした。皆でかけつけてみると、なんとそこには、朝食後その辺で遊んでいたベイリー教授の長男で15歳のショーンが、小型トラックにはねられて倒れていたのである。騒然となった。救急車を呼んでショーンを病院へ運んだが、ショーンは死んだ。私は大きなショックを受けた。フルブライトの年次集会に出なければならなかったが、旅行どころではないような気がしていた。私は鉛を飲み込んだような重い体と気持ちを引きずったまま、次の日の夜、深夜便でツーソンからフェニックスを経由してノースカロライナのローリー・ダーラム空港へ向かった。3,200キロの空の旅を私はぐったりして殆ど眠ったまま過ごした。
チャペルヒルでは会場のホテル・ヨーロッパで、5月31日の晩さん会から年次大会は始まった。世界各国から選ばれて集まっている百数十人の研究員たちは、ホテルの部屋を割り当てられ、翌日から、午前、午後、夜間の三回に分けて、いくつかの研究発表や分科会が開かれた。世界の人種問題、教育問題、経済問題、文化の違いと国際交流、世界情勢のなかのアメリカの役割、研究者、ジャーナリストの使命等々熱心な発表と討論が続いたが、私はまだ、ショーンの突然の死の後遺症が強く残っていて、会場の雰囲気になじめず上の空であった。発言するのも苦しかった。
2日目は、午前中にチャペルヒルの街とノースカロライナ大学を見学して、午後は研究会と討論、3日目も午前中はディユーク大学を見学して、午後の総会で年次大会は終わった。私はノースカロライナ州立大学のK教授に迎えられて、40キロ離れたローリーに移り、その夜はK教授の自宅で、日本食の夕食をご馳走になった。私の任命については、学内の処理はすべて終わっていて、大学財務部の予算決定を待っている段階だという。K教授は、フルブライト教授をパートタイムで来てもらうのは申し訳ないといいながら、手続きが遅れてしまっていることを何度も私に詫びた。来週にも決定は降りるはずだから、私たちのアパート探しも心がけておくとも言った。
次の日の午後、私は泊まっていたローリーのヒルトンホテルで、フルブライト年次大会に出席していた東北学院大学教授の鈴木氏とたまたま出会った。鈴木氏は図書館学の専門家でノースカロライナ州立大学図書館を午前中訪れていたという。私は鈴木さんに誘われて、午後の時間を一緒にすごした。Roleigh
Little Theaterへ行き、ミュージカル「Southern Pacific」を観た。私はミュージカルを楽しめる気分ではなかった。それよりも、隣に座っていた中年の女性のしとやかな優しい表情とちょっとひと言ふた言交わした時のことばの柔らかな温かさに、こころが和むような気がしていた。劇場を出てからは、ダウンタウンで日本風居酒屋の店を見つけて夕食をとり、その後はヒルトンホテルへ帰って、鈴木さんの部屋で深夜の12時近くまで缶ビールを何本も飲みながら話し込んだ。
少し酔いがまわってきたせいもあったかもしれない。私は苦しい胸の内を曝け出して、鈴木さんにツーソンでのショーンの死の話をした。いま滞在延長の予定が思い通りに進んでいないこともあって、延長はしないで帰国するかどうか迷っているところだと言った。その時、鈴木さんは、「実は」と、自分の息子さんの話をした。前年の春、そのショーンと同じ15歳の長男が、小児がんで亡くなったのだという。亡くなる1週間前には病院から仙台の自宅へ移っていたが、夜中に長男が声を殺して泣いている様子が病室の外へ伝わってきて悲しかったと鈴木さんは打ち明けた。9月に日本へ帰っても、位牌の前に座るのが辛いとも言った。私はここでも、彼の息子さんの死が他人事ではないような気がして、暗く沈みこんだ。ふらふらと深夜の自室に戻り、ベッドの上に倒れるようにして眠った。
ローリーからツーソンに帰ってから一週間が過ぎても、ノースカロライナ州立大学の任用通知書は届かなかった。私はやっと決心して、滞在延長は取りやめることにした。私のフルブライトの滞在期限は9月14日となっていたが、それまでに帰国することをフルブライト委員会に伝える手紙を書いた。規定による帰国旅費の支給申請書も作り、6月15日の朝、近くのポストに投函した。辛い気持ちで何もする気がおこらず、その時はそのままアパートへ引き返した。その、ほんの20分ほどの留守の間に、ノースカロライナ州立大学からの速達便が届いていた。任用通知書であった。私は呆然となった。
しばらく苦しみながら考えた後、私はノースカロライナへ赴任することにした。先ほどフルブライトへの書類を投函したばかりのポストの前で一時間以上も待って、やがて現れた郵便物集配人に事情を話し、私の手紙を取り戻したいと言った。集配人は、規則でここでは返却できないので、郵便局本局へ身分証明書を持参して受け取りに行くように、と答えた。翌日、私は言われたように郵便局の本局へ行って、フルブライト宛の書類を取り戻した。そしてアパートへ帰ってみると、今度は、アメリカ海軍語学校からの手紙が届いていた。予算措置ができて、これから任用手続きを始めるからもう少し待ってもらいたい、というのである。手続きを始めるのはいいが、それでまた少し待てといわれても、私にはもう待つ余裕はない。私は、アメリカ海軍語学校のほうは無視することにした。
7月1日、車に荷物をいっぱい積みこんで、私と娘はツーソンを後にした。アリゾナのツーソンからノースカロライナのローリーまで、直線距離は3,000キロだが、その間に、車では、ニューメキシコ、テキサス、アーカンソー、テネシー州などを通過して行かねばならない。途中、名所旧跡などに立ち寄りながら、私たちの車は3,400キロを走って、10日目の7月10日、ローリーの近くまでたどり着いた。翌日には、大学から北へ30キロほどの2LDKで90平方メートルくらいのアパートを契約した。7月12日に引っ越しをして、14日に電話がついたので、東京の留守宅へ電話した。妻の富子に、これからでもこちらへ来れるようであれば来てはどうか、と言った。(アリゾナに着いて以来のツーソンでの生活、ローリーへの旅については、拙著『アメリカ光と影の旅』第2章「忍びよる暗い影」にやや詳しく書いている)
私からの電話を受けて、東京では、ニューヨーク行きの航空券を手に入れるために八方手を尽くしたらしい。しかし急のことで、どこの航空会社の予約も取れなかった。キャンセル待ちの大韓航空の航空券でそれもソウル経由のものが8月3日になってやっと取れ、妻の富子と長男の潔典は、その二日後に慌ただしくニューヨークへ飛んできた。私と娘は、その前日にローリーを車で出発して、アメリカ時間の8月5日午後9時過ぎ、ケネディ国際空港で富子と潔典との一年ぶりの再会を果たした。
それから25日間、私たちはまた家族4人になって、かつてオレゴンに住んでいた時にそうしたように、車で東部諸州やノースカロライナ州の周辺を旅してまわった。(このことについても、拙著『アメリカ光と影の旅』第3章「うち砕かれた夢」にやや詳しく書いている)そして、8月30日の朝、思い出深いアメリカ2度目の滞在を終えて、富子と潔典は帰国の途についた。ローリー・ダーラム空港からフィラデルフィア経由でケネディ空港へ飛び、そこで大韓航空機に乗ったのである。しかし、その大韓航空007便は、遂に富子と潔典を無事に日本へ帰してはくれなかった。(事件発生以降のことは、拙著『疑惑の航跡』第1章「慟哭」などに詳述している)
いまもはっきり覚えているが、潔典は迫りくる危機を予感していたようである。帰国を2,3日後に控えた日の昼下がり、その日は外はことのほか暑く、私たちはみんな冷房の利いた家の中にひきこもっていた。私は寝室で寝転んで本を読んでいた。潔典はアパートの裏にあるひょうたん型のきれいなプールでひと泳ぎして帰ってきて、向かいの寝室にいるはずであった。静かで物音がしないので、私は潔典が勉強でもしているのかと思った。彼はこのアパートにいる間も、時々姉の机に向かってはギリシア語文法の本を読んでいた。私はお茶でも飲もうと思って立ち上がり、部屋を出ようとしてドアのところまで行った。向かい合った潔典の居る部屋は開け放たれていて、潔典がベッドの上に横になっていた。こちらを向いていた。その姿がちらっと私の眼の中に入ったのだが、その時、不意にわけもなく、一つの気配を感じたのである。(潔典が怯えている・・・・・)。なぜそう感じたのかはわからなかったが、それはまぎれもなく「怯え」であった。ただその時は、深くは意にもとめずに、その怯えはすぐ私の意識からは消えてしまった。
大体、潔典が怯えなければならない理由などあるはずがなかった。潔典の明るい性格には暗いイメージの「怯え」はおよそ結びつきそうには思われなかった。私の気の迷いに違いない。そんな私の常識が、その時の一瞬の感じを打ち消してしまったのかもしれない。そのことはそのまま忘れていたが、事件が起こった後、娘が言った言葉で、愕然として私はそれを思い出したのである。やはりローリーを出発する何日か前、「お姉ちゃん、大韓航空って大丈夫だろうか」と、潔典が言ったのだという。「アリゾナの学生の中には、大韓航空は嫌だという人もいたけれど、大韓航空はパイロットが優秀だし、大韓航空にしか乗らないという学生もいたよ」と娘が答えると、潔典は「助かった!」と叫ぶように口に出したという。「助かった」という言い方はおかしい。潔典のことばらしくもない。やはりあの子は、何かを感じ取っていたのだ。潔典の本能が、身近に迫りつつある重大な危険を、あの時、予知し始めていたのではなかったか。そう思うと、あの時の一瞬の感じが一本の鋭い針となって私の胸に突き刺さってくるのを覚えた。
富子と潔典がフィラデルフィア経由でニューヨークのケネディ空港へ向かった8月30日の午後6時半、潔典からケネディ空港に着いたという電話があった。そして午後9時、チェックインも済みこれから機内に入るという潔典からの2度目の電話があった。私が電話するように言っておいたのを守ってくれたのだが、その2度目の電話では潔典の声がなぜかしどろもどろで異常であった。私に一瞬さっと不吉の影がよぎった。潔典は慌てているような口調で、「ママに代わるから、ママに代わるから」と繰り返して電話は富子に代わったのだが、富子は普段の穏やかな口調であった。私は受話器を置いた後もしばらく、潔典のしどろもどろの声が気になってぼんやりしていた。私は、富子と潔典が東京に着いたら、電話で潔典に注意しておこうと思った。潔典はよくできた子で、私は潔典を子供の頃からほとんど叱ったことがない。しかしその時は「あのような話し方をしたらお父さんが心配になるではないか」と叱りたいような気持ちになっていた。後に私は、この自分の鈍感さにひどく罪深いものを感じさせられて苦しむことになる。
事件のあと何年も経って、私は「溺れる者は藁をも掴む」心境で仏典や聖書を学び、霊界の本を読み、霊界からのメッセージを求めて次々と数十人の霊能者と接触したりもした。そして、少しずつ霊的真理に目覚めていった。やがて霊界の富子と潔典とも「文通」できるようになり長年の悲嘆と苦しみからも抜け出していった。私はその闇の中からのたどたどしい歩みを『生と死の彼方に』第3章の「学び」以下に書いている。上にのべたケネディ空港での最後の電話についても、事件から17年を経た2000年6月5日に、ロンドンのアン・ターナーを通じて、潔典からお詫びのことばが届いた。潔典は、「ぼくがお父さんと、この世で最後の会話をしたときからも、長い年月が流れました。どうか、あのときの不安がっていたぼくの態度を許してください。少し甘えながらあらためてお詫びします」と「手紙」のなかで述べていた。
それでは、私はなぜあのような国際的な大事件に遭遇して妻と長男を失わねばならなかったのだろうか。このことについては、いままでに数多くの霊界からのメッセージや「証言」が寄せられており、今では私にとって、不思議な謎ではない。たとえば、その一つの例として、潔典は霊界からこう伝えてきたことがあった。「お父さんなら、頭も聡明で、苦しませるのは高い霊たちにとっても辛いことで、決断を要したということです。でも必ず目覚めて立ち直る人だということがわかり、一人の苦しみが何百、何千人、いや何万人の人たちの魂を目覚めさせ、同様の苦しみや悲しみのなかで沈んでいる同胞に慰みと魂の癒しをもたらすことを、その聡明さによって、やってくれるということが期待されたからです。」(1999.
6. 5)
ここで、自分のことであるのに「聡明」などのことばを書き写すのには嫌悪を感じるが、霊界からのことばには一言一句修正を加えることは出来ない。同様の「証言」は霊能者のA師を通じても幾つかあった。つぎのように言われたこともある。「・・・・・あなたが霊的なことに目覚め、価値観を正し、本当に大切なもの、すなわち、神と愛と命と心に目覚めるために、このこと(大韓航空機事件で妻と長男が亡くなること)が必要だったのです。否が応でもあなたはその方へ駆り立てられていきました。あなたは、その一連のプロセスを経ていくことで浄化され、価値観が変わり、神を求める人に作り替えられました。また、それをもって、この世の認識の暗い人たちに、大事なメッセージを体を持ったまま伝える任務に就くようにされました。」(2004.06.05)
これらの霊界からの「証言」やメッセージについては、私は『天国からの手紙』(第6章以下)や『天国の家族との対話』(第7章以下、H.Pに掲載)にも書いてきた。「世の中が偶然によって動かされることはありません。原因と結果の法則が途切れることなく繰り返されている整然とした宇宙には、偶然の入る余地はありません」と、シルバー・バーチは言っている。事件によって私が悲嘆のどん底に突き落とされたとしても、それは私にとって必要なことが必然的にもたらされたということになるのであろう。いまになって事件に至るまでの過程を逆に振り返ってみると、思い当たるようなことがいくつも出てくる。
まず、私は、フルブライトを受験して合格しなければならなかった。その決定がその年に限って異常に遅れたにも拘わらず、私はフルブライトを諦めるのではなく、受け容れてアメリカへ向かわねばならなかった。アメリカではアリゾナに一年居て帰国するのではなく、家族を呼び寄せるためにも、滞在延長をしなければならなかった。それもアメリカ海軍語学校のモントレーで教えることによってではなくて、ノースカロライナ州立大学での教職でなければならなかった。そうでなければ、それらの選択肢のうちの一つにでも私が別の選び方をしていれば、私は事件に巻き込まれることはなくなっていたはずなのである。今にして思えば、私は抗うこともできずに、ただ与えられた道を歩んできたとしか考えられない。
シルバー・バーチはこうも言っている。「一人ひとりの人生にはあらかじめ定められた型があります。静かに振り返ってみれば、何ものかによって一つの道に導かれていることを知るはずです。あなた方には分からなくても、ちゃんと神の計画が出来ているのです。定められた仕事を成就すべく、そのパターンが絶え間なく進行しています。人生の真っただ中で時としてあなた方は、いったいなぜこうなるのか、といった疑問を抱くことがあることでしょう。無理もないことです。しかし、すべてはちゃんとした計画があってのことです。天体の一分一厘の狂いのない運行をみれば分かるように、宇宙には偶然の巡り合わせとか偶然の一致とか、ひょんな出来ごとといったものは決して起きません。」―― いまの私には、こういうことばも私なりに理解できるような気がしている。確かに私は、「何ものかによって一つの道に導かれて」きた。その結果、私はあの年にあのような事件に遇った。それは私の宿命であった。そして、そのことをも含めて、私は今まで、大宇宙の大いなる力によって導かれ、生かされてきたのである。
**********
霊的真理への道に立ちはだかる壁 (2016.01.01)
― 生活と文化をめぐる随想 (No.105) ―
NHKで、むかし、「立花隆リポート 臨死体験~人は死ぬ時 何を見るのか~」という番組が放映されたことがある。1991年3月17日のNHKスペシャルである。このリポートでは、立花氏は精力的に欧米の研究者や臨死体験の経験者たちへの取材を続けているが、そのなかには、ターミナル・ケアの世界的権威といわれたキュブラー・ロス博士や臨死体験をして死後の生を確信するようになったレイモンド・ムーディー博士などもいた。その後、立花氏は『臨死体験』上、下(文芸春秋社、1994)を刊行して、一般の人々に改めて臨死体験をひろく知らしめる契機になった。さらに立花氏は、1996年には、『証言・臨死体験』(文芸春秋社)を出して、23人の比較的著名な人々の臨死体験の証言をまとめている。氏は、この本の「はじめに」のところで、こう書いている。
《「臨死体験」の取材開始からかぞえると、私がこのテーマにかかわってから、もう、あしかけ七年になる。
それほど長期にわたってこのテーマを追いつづけたのも、この問題が、人は死ぬとどうなるのか、人は死ぬとき何を体験するのかという、人の生死の根源に深く関わっており、そこに興味を持ったからである。
しかし、詳しくは『臨死体験』を読んでいただきたいが、前者の問題、すなわち死後の世界の有無とそのありように関しては、明確な答えを出すことができない。
これは本質的に不可知な問題なのである。そして、本質的に不可知な問題についてあまりに深く思いわずらうのは賢いことではない。》
立花氏は、「人が死すべき存在であることを忘れ、生と死の問題に何も思いをこらすことなく、ただその日その日を生きていくだけの人生も貧しいものだが、死後の問題に思い悩みすぎるのも、精神的に健康な人生とはいえない」とも述べている。要するに、立花氏は、臨死体験のような問題を深く掘り下げて考えていながらも、死後の世界のような「本質的に不可知な問題についてあまりに深く思いわずらうのは賢いことではない」という一貫した態度に貫かれているようである。
その立花氏は、実は、膀胱がんを患っており、一昨年(2014年)になって再発したという。そのことが契機になったのであろうか、氏は再び、死の問題に向き合うようになった。1991年のNHKスペシャルから23年を経て、今回も精力的な取材を繰り返し、その結果が、一昨年(2014年)9月14日のNHKスペシャル「臨死体験 死ぬとき心はどうなるのか」として放映された。その時の、「NHKスペシャル公式サイト」には、つぎのように同番組の内容が解説されている。
《『私』という存在は死んだらどうなるのか、死ぬとき『私』は何を見るのだろうか。20年余り前、臨死体験について徹底的に取材し考察を深めてきたジャーナリスト/評論家立花隆さん。74歳を迎え、がんや心臓の病を抱えて死を間近に感じる今、再び臨死体験の最新研究の現場を見つめ、〝死″について思索しようとしている。死の間際に一定の人が見る臨死体験。臨死体験が世界で注目され始めた1980年代以来、その解釈としては、脳内現象として科学で説明できるとする『脳内現象説』と、肉体が死んでも“魂(もしくは自我を感じる 『意識』)”が存在し続けるという『魂存在説』――これら二つの説が互いに相容れない、激しい議論が続いてきた。そうした中、立花さんは新たな臨死体験の掘り起こしをすると同時に、そもそも『意識(魂)』と呼ばれているものの正体とは何なのか、最新の脳科学・心理学・哲学にいたるまで、徹底した取材に基づいて正面から挑もうとしている。科学的に見て、死後の世界があると言える余地はどれくらいあるのか。死後の世界がないとしたら、『私(自分)』という意識(魂)はどう生まれどう消えていくのか。私たちが当たり前と思っている『私』という存在はいったい何なのか。有史以来、人類が答えを追い求め続けてきた生と死にまつわる壮大な謎――その謎に挑む立花さんの思索の旅を通じて、大震災や紛争などで多くの命が失われる今、命や『私』の存在する意味を考える。》
この番組はご覧になった方も多いであろうが大きな反響を呼んだ。おそらくNHKの全面的な支援もあって、この番組には、現代科学を代表する世界的な著名人もたくさん登場する。脳神経外科医のエベン・アレグザンダー、ノーベル生理学・医学賞受賞者で理研-MIT神経回路遺伝学研究センター長の利根川進、神経科学者のヘンリック・エーソン、精神医学者のジュリオ・トノーニ、脳神経外科医のケビン・ネルソンといったような人々である。長い取材活動を経て、番組の最後で立花氏は次のように述べた。
《結局、人間の死ということは、死と神秘と夢が隣り合わせのボーダーランドに入っていくことだ。死ぬことがそれほど怖いことじゃないことが分かった。人生の目的というのは結局、哲学者エピクロスが言った『アタラクシア(心の平安)』ということ。人間の心の平安を乱す最大のものというのは、自分の死について想念、頭を巡らせること。いい夢を見たい、見ようという、そういう気持ちで人間は死んでいくことができる。》
この立花氏の臨死体験の研究については、かつて私自身も、講演会などで何度か触れている。このホームページにも、身辺雑記No.48 に、「臨死体験と体外離脱による宇宙への旅」
(2006.12.01)などを書いてきた。しかし、臨死体験というのはあくまでも「臨死」の体験であって、死そのものの体験ではない。霊子線(シルバーコード)は切れることもなく、だからみな生き返っているのである。本当に大切なのは、シルバーコードが切れた後の問題であるが、立花氏は、これを「本質的に不可知な問題」として、ここでも考えてみようとはしなかった。おそらくスピリチュアリズムに通じている人々には、物足りなく思えたのではないか。結局、立花氏は、科学的な認証を徹底していこうとするあまり、最後まで、一種の唯物論の枠内からは決してはみ出そうとはしなかった。死後の生については、世界中で心霊主義(スピリチュアリズム)の膨大な資料や証言があるが、それらには遂に触れないで終わってしまっている。
昨年の番組の中では、立花氏は23年ぶりに、医師で臨死体験研究者であるレイモンド・ムーディー博士と再会している。ムーディー博士は自分自身が臨死体験をして以来、思索を深めて死後の世界の実在を信じるようになった。一方の立花氏は「死ねば、心も消える」と考えていて「死後の生」などは信じようとはしない。しかし、そんな立花氏に向かってムーディー博士は微笑みながら「あなたが先に死ぬか、わたしが先に死ぬかはわかりませんが、きっといつかどこかで、あなたとまた再会できると信じています」と語りかけていた。立花氏に死後の生を説いていたキュブラー・ロス博士はもう亡くなっているが、もし今度立花氏と再会していたとしたら、かつて彼女が霊的に目覚めない人々に対して述べたように、「あなたも死ねばわかりますよ」と言っていたかもしれない。
そのような立花氏に、また心霊主義の話を持ち出せば一笑に付されるのかもしれないが、かつて浅野和三郎先生が1923年に東京の本郷で創設した「心霊科学研究会」は、現在では公益財団法人日本心霊科学協会となって、いまも活発に霊的知識の普及に力を注いでいる。そのホームページを開くと、「日本心霊科学協会は、心霊の働きといわれる現象を誤りにおちいることなく、科学的に注意深く研究していこうとしております。心・精神について正しい理解が出来るようになれば、現在、私達がもっている物質中心的な考えを修正し、より適正な人生観を持つことが可能となり、私達の生活をより豊かな楽しいものにすることができると思います」というようなことばが並べられている。私はこのホームページで、立花隆氏へのつぎのようなメッセージがあることも知った。「立花隆氏へ――私たちスピリチュアリストの願い」とタイトルがつけられた公開文である。少し長いがつぎに再録しておきたい。
《私たちスピリチュアリストの本心を言うなら、特別な知的才能に恵まれた立花氏には、今後、臨死体験の探究から「心霊現象の探究」へと歩みを進めていただきたいと思っています。残された地上人生を、スピリチュアリズムの心霊現象を探究するために費やしていただきたいと願っています。
立花氏の心には、霊媒や心霊現象に対する拭いがたい不信感があることはよく知っています。恐山のイタコを前にして、半日もの時間を、その観察に当てたことも知っています。また“霊媒”と言うと、テレビや書籍で低俗な関心の対象となっている江原氏のような人物を真っ先に思い浮かべ、ますます不信感と軽蔑の思いを強くしたであろうことも推察できます。その江原氏が“スピリチュアリスト”を名乗っていることで、スピリチュアリズムへの不信感が増幅されるようになったことも承知しています。
しかし、スピリチュアリズムほど「死後の世界の探究」に真剣に取り組んできたものはありません。多くの一流の知識人がスピリチュアリズムに関わりを持ち、死後の世界の探究に人生を捧げてきました。
その一方で、江原氏のようにスピリチュアリズムを唱えながら、ニセの霊能力を売りにして人々を騙すペテン師が横行してきたことも事実です。残念なことに、ニセ霊能者と利害を共有する出版社やテレビ局が、その不正に加担してきました。さらに軽薄な知識人がニセ霊能者を持ち上げ、彼らの詐欺的行為に拍車をかけてきました。
今、売り出し中の東京大学の教授・矢作直樹氏も、そうした軽薄な知識人の一人です。立花氏は『週刊文春』(2014年10月30日号)の中で、江原氏と意気投合している矢作氏を一刀両断に切り捨てていますが、それは私たちも同じ思いです。
こうした現状にあって私たちは、日本の宝とも言うべき立花氏には、心霊現象(霊媒現象)には“ニセモノ”が圧倒的に多いけれど、スピリチュアリズムでは一流の科学者によって真摯な研究がなされ、数ある心霊現象の中から一部の本物を見いだしてきた歴史があることを知っていただきたいと思っています。恐山のイタコやテレビに出演する低俗なニセ霊能者によって判断することなく、「本物の霊媒・霊能者」について徹底して究明していただきたいと考えています。そうすれば必ずや、立花氏の知性に納得を与えるだけの実証性に富んだ事例が多くあることを確信していただけるはずです。
立花氏には、日本における“知の巨人”から「心霊研究の巨人・心霊研究の第一人者」になっていただきたい。日本のハンネン・スワッファーになっていただきたい。英国フリート街の法王と呼ばれたハンネン・スワッファーが、生涯をスピリチュアリズム普及のために捧げたように、立花氏にも、日本を代表するジャーナリストとして「死後の世界の真実を探究」するために、今後の人生を捧げていただきたいと心から願っています。》
このハンネン・スワッファー(Hannen Swaffer [1879-1962])は、いうまでもなく、英国の著名なジャーナリスト、著述家で、後に英国新聞業界の大立者といわれるようになった。英国社会主義運動の指導者としても知られている。シルバー・バーチの霊訓に接するようになってからは、熱心なスピリチュアリストに変身した。あの膨大なシルバー・バーチの霊訓は、もともとハンネン・スワッファーが主催するホームサークルから始められたものである。
また、このなかでとりあげられている『週刊文春』(2014年10月30日号)の記事では、確かに立花氏は、矢作氏を「一刀両断に切り捨てて」いる。立花氏はここでは珍しく激しい口調になっているが、これは氏の死後の問題に対する立場をよく表していると思われるので、参考までにその部分を掲げておきたい。この中で、氏は「ああいう非理性的な怪しげな世界にのめりこまないと、『死ぬのが怖くない』世界に入れないかというと、決してそうではありません」と言い切っているが、これはおそらく氏の「勇み足」であろう。氏の言い方はこうである。
《「死ぬのが怖くなくなった」といっても、「死後の世界は存在する。だから死は怖くない」と科学的な根拠もなく声高に断定する人たちもいます。最近、日本で評判を集めている東大医学部附属病院救急部の矢作直樹氏のような例です。最近彼は週刊誌で、TVの怪しげな番組に出まくって霊の世界がどうしたこうしたと語りまくる江原啓之なる現代の霊媒のごとき男と対談して「死後の世界は絶対にある」と意気投合していましたが、これが現役の東大教授かと口アングリでした。ああいう非理性的な怪しげな世界にのめりこまないと、「死ぬのが怖くない」世界に入れないかというと、決してそうではありません。ごく自然に当たり前のことを当たり前に、理性的に考えるだけで、死ぬのは怖くなくなるということをあの番組で示せたと思っています。》
この立花氏は、昨年(2015年)12月に新しく、『死はこわくない』(文芸春秋社)という本を出した。立花隆氏は1940年5月生まれだから、この出版の時には75歳になっていた。臨死体験研究、自殺や安楽死、脳死など、長い間、人の「死」をテーマに追い続けてきた氏が、この氏の人生の最終段階ともいえる時点で、いわば、「死」の探求の結果をまとめた本ということになるが、氏はこの本のなかで、「死はこわくない」と思うようになった心境をつぎのように書いている。
《私は今年75歳です。足腰は衰え、昔のように走ることも、階段を駆けあがることもできなくなりました。ついこの間も、食事中に下の歯の一部が欠けてしまい、老いの進行を強く感じました。同級生たちも次々と死んでいますし、自分より若い人も亡くなっている。自分もいずれ、それほど遠くない時期に死を迎えるにちがいないということが実感として理解できるようになりました。その結果として、生に対する執着が弱くなりつつあります。「死は怖くない」という心境に私が到達したのは、番組の取材を通じて臨死体験に関する新たな知識を得たからという理由以上に、年を取ることによって死が近しいものになってきたという事実があります。》(同書、p.10)
このように言う立花氏の現在の心境をひと言でいうと、これも昨年の番組で述べられているが、「死ぬというのは夢の世界に入っていくのに近い体験だから、いい夢を見ようという気持ちで人間は自然に死んでいくことができるんじゃないか」、ということになるようである。結局、氏のような科学信奉の唯物論的な立場では、いくら幅広く臨死体験の実態を調べ上げ、心理学や脳の研究を深めていっても、霊的真理に関してはどうしても乗り越えられない強固な壁があるようである。科学的思考のひとつの限界といってもいいであろうか。これでは、どこまで行っても、宇宙にひろがる深遠な霊的真理との接点は持つことは期待できない。
死後の世界を理解するには、当然のことながら、臨死体験よりも死後体験を知ることが何よりも重要である。立花氏は、「死後の世界の有無は本質的に不可知な問題で、それについてあまりに深く思いわずらうのは賢いことではない」というが、これは明らかに氏の思考能力の限界を示している。本当は、死後の世界のことを深く思うことをしない方が「賢いことではない」のではないか。私たちは氏と同じ時代に生きながら、「死後の世界」のことをいろいろと教えられて知っている。それを教えてくれたのは、この地上を去った数多くの霊たちである。私たちは、死とは何か、死後の生活はどうなるかというような生命の実相や霊界の生活や霊界を支配する摂理といったようなものに至るまで、さまざまな霊的知識を「死後の」霊たちから学んできた。
それらの情報が単一の霊によるものであったとすれば、その視点、観点に偏りがある可能性もある。またその教えを受け取ったのが、たった一人の人間だけであったとすれば、その人間が情報を歪曲しているという可能性も考えられないわけではない。しかし、地上の人間が霊界から受け取った教えは、実に多岐にわたっており、膨大な量にのぼっているのである。霊界から様々な教えやメッセージを送ってきたのは、最も低い境涯にいる霊から、最も高い境涯にいる霊まで、あらゆる種類の霊たちであった。また、それを受け取ったのも、世界中に散らばる、あらゆる種類の霊媒たちであった。私たちはそれらの無数の教えやメッセージから、何が真理であり、何が虚偽であるか、理性をもって慎重に検討を加えて判断することができる。それがスピリチュアリズムの立場である。
私はここで、立花氏の向こうを張って、改めて死後の世界の存在を傍証していこうとは思わない。シルバー・バーチが言っているように、いかに重大な、煌めくような霊的真理であっても、自分の理性で判断して、それが信じられないというのならば信じなければよいのである。私は自分の著作やこのホームページで、1991年にロンドンの大英心霊協会へ通うようになって以来の私の体験をできるだけ詳しく述べてきた。霊界通信の一部も載せている。シルバー・バーチの教えの原文や訳文、浅野和三郎先生の『新樹の通信』をはじめ、数多くの書籍を分類抜粋して霊的真理を学ぶための資料も掲載してきた。いまここで敢えて繰り返しておきたいのは、「死後の生」は決して「不可知な問題」ではないということだけである。
**********
「勝五郎の生まれ変わり」二つの記録 (2016.03.01)
― 生活と文化をめぐる随想 (No.106) ―
「ほどくぼ小僧」の名で親しまれている勝五郎の生まれ変わりの実録については、平田篤胤が書いた『勝五郎再生記聞』にくわしい。これは岩波文庫の『仙境異聞
勝五郎再生記』にも収められている。国学者・平田篤胤(1776~1843)は、妻に先立たれ、後妻との間に生まれた二人の子を含めて男の子を4人も亡くしていた。彼が死や死後の世界に強い関心を抱くようになったのは、おそらく、このような家族の死が要因であったに違いない。平田篤胤は、この『勝五郎再生記聞』のほかにも、人の死後、魂はどこへ行くのか、あの世はどこにあるのかを考察して、『霊能真柱』(たまのみはしら)なども書いている。
当時の八王子市中野村の勝五郎が、自分の前世は日野市程窪村(中野村からは山一つを隔てて約6キロ)の藤蔵であったと語り始めたのは、1822年(文政5年)11月のことであった。この話は、瞬く間にまわりに広がっていった。勝五郎が住んでいた中野村の領主、多門傳八郎(おかどでんはちろう)は江戸に住んでいたが、勝五郎の生まれ変わりの話が村中で大評判になり、それが江戸にまで伝わってきて、この信じがたいような話を放置できなくなったようである。1823年(文政6年)4月に勝五郎親子を呼び出して職務上の「取り調べ」を行ない、それを調書にして幕府に提出した。平田篤胤はそれを知って、多門傳八郎宅へ出向き、自分も勝五郎に会わせてくれるように頼んだのである。
平田篤胤は勝五郎親子を自分の学舎に招いて、その年(1823年)の4月22,23,25の3日間にわたって生まれ変わりの話を聞いた。勝五郎は、はじめは話をすることを嫌がっていたが、篤胤は友人の国学者・伴信友たちといっしょに、勝五郎を遊ばせながら少しずつ話を聞きとっていったという。その内容を伴信友が記録し、それを篤胤がまとめたのが『勝五郎再生記聞』である。この本は、かなりの長文であるばかりでなく、文体が古くて読みにくい。そこで、ここでは、その核心部分にあたる、伴信友が最初に勝五郎から聞き取った話の内容だけを取り上げてみたい。現代文になおして読みやすいように要約すると、つぎのようになる。
去る文政5年(1822年)11月の頃、数え年8歳の勝五郎は、田んぼのほとりで姉のふさ、兄の乙次郎と遊んでいた時、ふと兄に向って、
「兄ちゃん、兄ちゃんはうちに生まれてくる前はどこの子だったんだ?」
と訊いた。
「生まれる前のことなんてわかるわけないだろ」
と乙次郎が答えると、今度は姉に向かって、同じことを訊いた。
姉のふさが、
「どこの誰の子だったかなんて、わかるわけないじゃない」
と答えると、勝五郎は、
「それなら姉ちゃん、生まれてくる前のことは覚えていないの?」
と不思議そうな顔をした。
「じゃあ、お前は覚えてるって言うのかい?」
とふさが言うと、
「ああ、よく覚えているよ。おらは程窪村の久兵衛って子の息子で藤蔵っていったんだ。知らなかったのか」
と勝五郎は答えた。ふさは、そんな不思議な話をする勝五郎を怪しんで、
「じゃあ、その話をおっとうとおっかあに言っておくからね」
と言ったら、勝五郎はそのことを嫌がって、
「やめて、言わないで! おっとうとおっかあには言っちゃダメだ」
と急に泣きべそをかきだした。
「じゃあ、言わないでおいてあげる。だけど何か悪いことしたら、このことを言いつけてやるからね」
と、ふさは言った。
それからは姉ふさは、勝五郎と喧嘩になる度に、「いいわよ、おっとうとおっかあに言ってやるから、あのこと― 」と脅すようになった。
そんなことが何度もあったので、それに感づいた両親は不思議に思い、勝五郎が何か悪い事でもしているのかと心配になって、ふさに問いただした。
ふさは勝五郎から聞いた話の一部始終を話した。
ふさの話を聞いて驚いた両親と祖母は、勝五郎を呼び、なだめたりすかしたりして、改めて話を聞き出したのである。
勝五郎は言った。
「おら、前は程窪村の久兵衛さんって人の子だったんだ。おっかあの名前はしづさんっていった。おらが5歳の時、久兵衛さんが死んで、半四郎さんって人が新しいおっとうになって、おらを可愛がってくれた。でも次の年、おら
6歳だったんだけど、疱瘡にかかって死んじまった。その後、今のおっかあのお腹ん中に入って、もう一度生まれたんだ・・・・・」
それを聞いた両親と祖母はびっくり仰天する。しかし、百姓仕事で忙しい毎日であったので、勝五郎の話についてはそれ以上どうすることもなく、日々が過ぎて行った。
その頃、母親は4歳の妹つねにまだ乳を飲ませていたため、勝五郎は祖母つやと寝ていた。ある夜のこと、勝五郎が何か打ち明けたそうな様子なので、祖母のつやが促すと、こんな話を始めたのである。
前世のことは、4歳くらいまではみんな覚えていたけど、それからはどんどん忘れていった。でも、病気になって、死ぬはずではなかったのに薬を飲まなかったので死んだことは覚えてる。息が絶えたときはなんの苦しみもなかった。桶に入れられて、丘に埋められたのも覚えてる。地面に穴を掘って、大人たちが桶をそこにすとーんと落としたんだ。落とした時のその音もよく覚えてるよ。それでどうしてか分かんないけど、いつの間にか家に戻ってて、机の上のところにいたんだ。なにか話しかけても、誰にも聞いてもらえなかった。
すると、白髪を長く垂らして黒い着物を着たおじいちゃんがやって来て、おらをどっかに連れてった。高く登って、ひろい草原のようなところへ行ったら花がいっぱいきれいに咲いていた。その草原で遊んでいると、家のみんなの声が聞こえてた。おらのために読んでくれてる念仏の声もね。家の人が仏壇の前にあったかい餅を供えてくれたのも覚えてる。食べなかったけど、お供えから出てる湯気が甘く匂ってた。
――しばらく経ってから、あのおじいちゃんがこの家に連れてきてくれた。村への道を通ってここに来ると、おじいちゃんはこの家を指して、言ったんだ。
「さあ、生まれ変わらないといけないよ。お前はこの家に生まれるんだ。」
そう言うと、おじいちゃんはどこかへ行ってしまったんだ。
3日ほど、庭の柿の木の下にいて、それから雨戸の節穴を通って家の中に入り、かまどの横にまた3日ほどいた。そしたら、おっとうの稼ぎが少ないから、おっかあが江戸に働きに行かなきゃならねえっておっとうとおっかあが話し合っているのが聞こえた。それからしばらくして、何時の間にか、おっかあのお腹の中に入ったような気がする。お腹の上の方にいたらおっかあが辛いかなと思って、横の方に寄って行ったことも覚えてるし、生まれた時、なんの苦しみもなかったこともよく覚えてる。そのほかのことも
4、5歳の頃まではいろいろと覚えていたが、だんだん忘れちまった・・・・・
(父親の源蔵の話では、妻を江戸へ奉公に出すというのは、夜寝る時に妻と二人だけで話し合ったことで誰にも知られていないはずだという。3月に妻を奉公に出したが、懐妊したことがわかり、妻は暇をもらって家へ帰ってきた。そして10月10日に勝五郎が生まれた)
やがて勝五郎は「程窪に行きたい。程窪に行って、久兵衛さんの墓参りがしたい」と言い出すようになった。
父の源蔵は、あまりにも不思議な話だが、一度確かめてみることにした。ただ、そんなことで自分が行くのは物笑いの種になると思った源蔵は、母親(勝五郎の祖母)のつやに、勝五郎を程窪村に連れて行ってくれるよう頼んだ。
祖母のつやが勝五郎を程窪村に連れていくと、勝五郎は見知った場所のように祖母を引っ張って行き、ある家の前まで来ると「ここ、ここ」と言って、祖母を置き去りにしたまま家の中に入って行ってしまった。
続いて家に入った祖母のつやは、そこにいた人に尋ねてみた。
「この家の主はどなたですか?」
「半四郎だよ」
「奥さんのお名前は?」
「しづ、だ」
それを聞いたつやの目には急に涙が溢れてきた。勝五郎が話していたことは事実だったのである。つやは半四郎の家の人達に勝五郎の話をした。半四郎も妻のしづも大変驚き、涙を流して勝五郎を抱きしめ、
「ああ、亡くなった藤蔵が 6歳の時の顔つきとそっくりだ」と言った。
抱きかかえられながら、勝五郎は向かいの煙草屋の屋根を指さして、言った。
「あの煙草屋の屋根、前はなかったよね? あそこの木もなかった」
それは、その通りであったので、半四郎としづはますます驚き、
「ああ、やっぱりこの子は本ものの藤蔵だ」と確信の思いを強くした・・・・・・。
(平田篤胤『勝五郎再生記聞』岩波文庫、2000、pp. 367-374、現代文で要約)
以上が、伴信友が勝五郎から直接聞きだした話の要約である。これをこのように文書にしたのが、文政6年(1823年)4月29日であった。平田篤胤自身も勝五郎の機嫌をとりながら、2,3日をかけて、さらに細部に至るまでいろいろと質問し、生まれ変わりの様子を聞き出している。それに篤胤自身の詳しい注釈をつけてまとめたのが『勝五郎再生記聞』であることはすでに述べた。この本は、同年6月に江戸で出版された。
この『勝五郎再生記聞』の中には、先にちょっと触れた、勝五郎の住む中野村を治めていた地頭、多門伝八郎からの上司の御書院番頭・佐藤美濃守宛への報告書が転写されている。文政6年(1823年)4月19日付のその報告書の中で伝八郎は、勝五郎の生まれ変わりの話が評判になり他の領地から見学に来る者まで出てきたため勝五郎と父の源蔵を呼んで事情を聞いたことなどを記している。その結果、「小児勝五郎申し候通り相違これなく」、そのために、この重大な事実を捨てておくこともできず「御内々にこの段御耳打ち申し上げ置き候」と報告したのである。この生まれ変わりが興味本位の単なる噂話であれば、多門伝八郎がわざわざ上司にこのような報告をするようなこともなかったであろう。
この頃、厳密にいえば、平田篤胤と伴信友が勝五郎に会う少し前に、もう一人、勝五郎に直接会って、生まれ変わりの話を聞いていた人がいた。若桜藩(鳥取藩の支藩)の第5
代藩主であった池田定常(1767- 1833年)である。号は冠山、松平冠山とも呼ばれて文人大名として著名であった。彼は、享和2年(1802年)11月に家督を長男・定興に譲って江戸の屋敷に隠居したあとも学者や文学者と交流し、著作活動や研究に力を注いでいた。彼の著作の一つ『武蔵名所考』を編纂するために江戸近郊にも足を運んでいたとき、勝五郎のこの生まれ変わりの話が彼の耳にも入ったと思われる。
冠山には、奇しくも、勝五郎が前世について語り始めたちょうど同じ頃、文政5年(1822年)11月27日に、勝五郎の前世の藤蔵と同じように疱瘡(天然痘)にかかって6歳で亡くなった愛娘がいた。冠山51歳の時に生まれた末娘で、露姫という。悲嘆の底に沈んでいる時に、勝五郎の生まれ変わりの話を聞いて、冠山は自分の娘も生まれ変わるのであればと、強い関心を抱くようになったに違いない。ついでにつけ加えると、露姫は、生まれつき利発で信仰心が厚く、多くの人々に愛されていた。幼児ながら親を想う「遺書」なども書いており、「多くの人々から追悼を寄せられた姫」としても有名である。露姫の菩提を弔うために、冠山は集められた1600余の追悼文を29巻の巻子にまとめて浅草の浅草寺に納めた。現在も、露姫の木彫り像とともに、この29巻の追悼文は浅草寺に遺されているという。
愛娘の露姫が亡くなった年の翌年、文政6年(1823年)2月頃、冠山は、勝五郎の生まれ変わりの真偽を確かめるために当時の八王子市中野村へ出かけた。直接自分で勝五郎の家を訪れたが、当時は、大名の身分を持った者が一介の農民の家を訪れるというのは極めて珍しいことであったはずである。しかし冠山は気にかけなかった。熱心に頼んで生まれ変わりの話を聞こうとした。そして彼は、勝五郎や両親たちから聞いた話を『勝五郎再生前世話』として本にまとめたのである。この本の出版には、冠山の、わが子露姫の再生を願っての悲願が込められていたに違いない。学者としても名高い冠山が書いたものであるだけに、この著書は、江戸の文人、学者の間でも広く読まれるようになった。現在に至るまで200年近くも、長い間、語り継がれるようになった勝五郎の生まれ変わりの話には、冠山の愛娘に対するこの再生への悲願が裏打ちされているといってよい。
この冠山の『勝五郎再生前世話』の写本が、やがて、小泉八雲ことラフカディオ・ハーンにも読まれた。ハーンは、これを“The Rebirth of
Katsugoro”(勝五郎の再生)というタイトルで英文に翻訳し、随筆集『仏の畠の落穂』のなかに加えた(ハーンはこの話が自分の創作ではなくて、「日本の古い記録を訳出したもの」と書いている)。これによって、勝五郎の生まれ変わりは、ひろく欧米にも知られるようになった。その訳文の一部をつぎに取り上げていきたい。この記録の本文は、平田篤胤の『勝五郎再生記聞』と同様、直接に勝五郎から聞いたという点で、資料としては第一級といえるであろう。この二つの記録の内容は、当然、表現の些細な点を除いて同じようなものになっているが、そのハーンによる「勝五郎の再生」(平川祐弘訳『小泉八雲作品集3』河出書房新社、1977)の主要部分を抜き出すとこのようになる。(池田冠山『勝五郎再生前世話』のハーンによる訳文。読みやすいように段落をつけるなど、若干の修正を加えた)
勝五郎はこう言った。
前世のことは四歳ばかりまでは何でもよく覚えていました。しかしそれから先の事はだんだん忘れっぽくなって、いまではたいていのことは忘れてしまいました。しかしそれでも私が疱瘡で死んだことは覚えています。私は甕に入れられました。山に埋められたことを覚えています。土中に穴が掘られて、皆は甕をその穴に入れました。ぽんと落ちました。――私はいまでもその音をよく覚えています。
それからどうやったのか家に戻って来て、私の机の上にとまりました。すぐに誰か年取った人が――お祖父さんらしかったけれど――やって来て、私を連れて行きました。その人がどこの誰だか知りません。私が歩いて行った時、空気の中をまるで飛ぶように進んで行きました。その時のあたりの様子は夜でもなければ昼でもなかった。いつでもちょうどたそがれ時のようでした。熱も寒気もひもじさも覚えませんでした。私たちはずいぶん遠くへ行ったように思います。
しかしそれでもいつまでも、かすかでしたけれど、家で話している人々の声が聞こえました。それから私のために上げてくれる念仏の声も聞こえました。また家の者が仏壇に温かな牡丹餅のお供えをしてくれた時は、その湯気が香しくにおった……お祖母さんたちは亡くなった仏様たちに温かい御飯をお供えし、お坊様たちにお布施を上げることを決して忘れないけれど、こうしたことはとても功徳のあることのように思います。……その後で覚えていることといえば、そのおじいさんがどこか回り道を通ってここへ連れて来てくれたことでした。
――私たちが村の向こうの道を通ったことを覚えています。それからここへやって来ると、おじいさんはこの家を指して、「この家に入ってお生まれ」といいました。おじいさんが言うには私が死んでからもう三年が経っており、私はこの家に生まれかわるはずになっている。私のお祖母さんになるはずの人はたいへん親切だ、それだからここでお腹にはいって生まれるがいい、というのです。そう言ってから、おじいさんは行ってしまいました。私はしばらくこの家のはいり口の前の柿の木の下にたたずんでいました。
それから家の中にはいると、誰かが、家は貧乏でお父さんの稼ぎは少いから、お母さんは江戸へ奉公に出なければなるまい、と話していました。それで私は、この家にははいるまい、と思って三日間庭で様子をうかがっていました。しかし三日目になって結局お母さんは奉公に行かぬことになったので、その夜、雨戸の節穴から家の中へはいりこんだのです。それから竈の側に三日いて、それからお母さんのお腹の中へはいりこんだ。……生まれた時は何の苦しみもなかったことを覚えています。お祖母さん、お願いだから、この話はお父さんお母さんのほかは決して誰にもしないでくださいよ。
以上が冠山が聞いた勝五郎の話である。冠山は、その後の話を、こう続けている。
祖母は源蔵とその妻に勝五郎が自分に言った話を繰返した。するとその後は少年はもう気楽に自分の前世のことを自分の両親と話すようになり、よく両親に向かって、
「程窪へ行きたい。久兵衛さんのお墓詣りをしたい」
と言った。
源蔵は勝五郎が一風変った子供なので、多分あまり長生きしないのではないか、と思い、それならば程窪に本当に半四郎という人がいるのかどうかいますぐ調べた方が良い、と思ったが、しかし男である自分が〔こうした事情の下で?〕自分から調べに出向くのは軽率で出過ぎたことになると思い、自分自身出向く代りに、自分の母のつやに頼んで、その年の一月二十日に孫の勝五郎を連れて程窪まで行ってもらった。
つやは勝五郎と一緒に程窪へ行った。村にはいった時に祖母は手前の家をさして、
「この家か、あの家か」
と問うたが、勝五郎は、
「まだ先だ。もっとずっと先だ」
と言って先に立って行き、やがてとある家に着くと、
「この家だ」
と言って祖母より先にかけこんだ。それでつやもついてはいった。そして主人の名前を問うと、
「半四郎」
という答だった。妻の名前を問うと、
「しづ」
という答だった。そこで祖母はその家に前に生まれた男の子で藤蔵という子供はいたかどうかとたずねると、「いた」、という返事だった。
「しかしその子は十三年前に、六つの年で死んでしまいました」
そこでつやははじめて勝五郎の言うことが本当だと思い、思わず涙をこぼした。つやはその家の人に勝五郎が自分に語って聞かせた前世の思い出について一伍一什を物語ると、半四郎と妻もたいへん驚いて、勝五郎を抱いて涙して、藤蔵が六つで亡くなった時よりずっと可愛いい、などと言った。勝五郎は抱かれながら向かいの屋根を指して、
「前にはあの屋根はなかった」
とか、
「あの木もなかった」
とか言ったが、みなみなその通りであったから、半四郎の頭からも妻の頭からも疑念はまったく消えて、これは藤蔵の生まれ替りに相違ない、と思うようになった。
その日、つやと勝五郎とは中野村の谷津入へ帰ったが、その後、源蔵は息子を何度か半四郎の家へやり、前世の実父久兵衛の墓詣りもしたいというから、そうさせてやった。
時々勝五郎はこう言った、
「おれはののさま(註:死んだ人の霊をさす幼児語)だから、どうか大事にしてくれな」
またある時は祖母に向かってこう言った、
「おれは、十六になると死ぬけれど、御嶽さまのお教えにある通り、死ぬことは別にこわかねえや」
両親が、
「坊様になる気はないか」
とたずねると、
「坊様なんかになりたくねえや」
という返事だった。
村の人はもうその子のことを勝五郎とは呼ばず、もっぱら「程窪小僧」という綽名で言いはやすようになった。それで勝五郎は恥かしがって、人が訪ねてくると奥に引込んで姿を隠すようになった。それで誰も勝五郎と直接口をまじえることができないようになった。それで私(池田冠山)は勝五郎の祖母が私に語った通り、その話を書き記した次第である。
私は源蔵や妻やつやに、なにかとくに善行を施した覚えがあるかどうか尋ねた。源蔵とその妻は別にとくに善行を施した覚えはないと答えた。しかし祖母のつやは毎朝毎晩念仏を唱えるのが習慣で、戸口にお坊様やお遍路さんがやって来れば二文くれなかったことはないとのことだった。しかしこうした些事を除けば、とくに善行といわれそうな事はなにもしたことがないとの返事だった。(池田冠山『勝五郎再生前世話』から、ハーン、同書、pp.106-110)
ハーンが、この“The Rebirth of Katsugoro”(勝五郎の再生)を英語で紹介したことによって、勝五郎の生まれ変わりは欧米社会にもひろく知られるようになったが、その本を読んで「生まれ変わり」に大いに興味をもった一人が、ヴァージニア大学精神科の主任教授であったイアン・スティーブンソン博士(1918~2007)である。博士は、勝五郎の報告をはじめとする「生まれ変わり」の事例が世界中でいろいろと報告されているのを知り「探究されるべき何か重大なことがあるに違いない」との確信を得て、「前世の記憶とされるものによる死後生存の証拠」と題する論文を発表した。
この論文が博士の運命を大きく変え、博士は死後生存を中心とする心霊研究に専心するようになる。博士はインドなどでも調査を行った結果、1987年に最初の著書『前世を記憶する子供たち』を出版したが、このなかで取り上げられている生まれ変わりの百数十名の子供たちの名前のリストは圧巻である。(イアン・スティーブンソン『前世を記憶する子どもたち』笠原敏雄訳、日本教文社、1995、pp.392-399)
博士は、その後も東南アジアを中心に、前世の記憶を持つとされる子どもたちの事例を2300例ほども集めた。そのうちの数多くの資料は公刊されているから、日本でも容易に目を通すことができる。
しかし、このような諸外国のさまざまな事例のなかても、勝五郎の生まれ変わりの話は、その真実性において極めて傑出していると思われる。勝五郎の生まれ変わりの場合は、関係者がすべて実在し、生まれ変わりの前後の両親の名前や時間、場所もはっきり特定できるからである。このような生まれ変わりの実例が、私たちの身近な所に存在し、勝五郎の前世と今世の住んでいた家の跡やお墓などをも今でも見ることができるというのは、ほとんど奇跡的といえるような気がする。もし、人間の生まれ変わりが「事実であるかどうか」だけを問題にするのであれば、この勝五郎の生まれ変わりの事例一つだけを取り上げるだけでよいかもしれない。それだけで、生まれ変わりの真実を十分に納得できるであろう。逆に、もしその事実を否定しようとするのであれば、どのような理屈をつければそれが可能になるのかと、その方がかえって疑わしく思えたりもするのである。
(「勝五郎の生まれ変わり」に関する小文)
「寸感・短信」No.92 「江戸時代の生まれ変わりの実例」(2015.10.21)
「寸感・短信」No.95 「『勝五郎生まれ変わり調査団』について」(2015.11.18)
「寸感・短信」No.100 「高幡不動尊金剛寺を訪れる」(2016.01.13)
足るを知って生きる (2016.05.01)
― 生活と文化をめぐる随想 (No.107) ―
戦後の大阪で私は飢えに苦しんでいたことがある。その頃、私は、親しい友人の米田君の家に下宿していた。深刻な食糧不足は昭和22年(1947年)になっても続いていて、日本中では1000万人が餓死するのではないかといわれたりもしていた。米田君と私は旧制の生野中学に通っていたが、授業は午前中で打ち切られていた。昼食の弁当を持って登校できる生徒が殆どいなかったからである。私たちはおなかをすかして、ふらふらしながら朝、登校する。午前中の授業が終わったら、またふらふらして家へ帰る。家へ帰っても空腹で力がなく何もできない。ごろりと横になっているだけのことが多かった。
その当時は、食糧は配給制で、白米は1升53銭という基準価格はあったが、もちろんこれで米が割り当てられるわけではない。配給されるのは、米ではなく、黒ずんだメリケン粉やイモ粉のようなものだけであった。ただ、手を尽くせば、闇市場で米を手に入れることはできたようである。相場は1升70円、それも7月には100円、11月には150円と値上がりが続いていた。しかし、闇米を買うのは法律違反行為で、一般の市民はただ、耐えるしかなかった。この年の10月には、山口良忠判事が、「法の番人が法を破ることはできない」と言って正規の配給食糧以外のヤミ買いを買うのを拒否し続けたことで、栄養失調になり死亡している。このことは、当時の大きなニュースになった。私も米田君も栄養失調で苦しんでいた。
思い余って、ある日、私は米田君を連れて、天王寺駅からは汽車で30分ほどの、郊外の親戚の「おばさん」の家を訪れた。大阪市内とは違って、そのおばさんの家のまわりにはまだ田んぼや畑が広がっていた。いくらか食糧事情もよかったかもしれない。おばさんは、私と米田君を歓迎して、たいへんなご馳走を用意してくれていた。まず、真っ白いご飯が出た。私も米田君も、白米のご飯を前にしたのは、もう何か月ぶりかであった。牛肉のほかに、鯖かなにか、焼き魚も出された。白菜の漬物も味噌汁も食卓に並べられた。当時の大阪では、いわゆる「闇」でしか手に入らないものばかりである。おばさんは、栄養失調症で青白い顔をしている私と米田君に、「さあさあ、たくさん食べなさい」と言った。
私は目を見張ってしばらく真っ白いご飯を見つめていた。そして、おそるおそる、その一口を箸でつまんで、口へ運んだ。噛むと、ご飯のなんともいえない甘いような香りが、ぱーと口いっぱいに広がる。私はまた、ご飯だけを口に運んだ。肉や魚を食べれば、折角のそのご飯の美味しさが、消えてしまうような気がしていた。二口、三口、ご飯だけを噛んでいるうちに、涙がぽろぽろとこぼれ落ちた。なぜ涙が出るのかわからない。ただ、涙が次から次へとあふれ出てきた。私は涙と共に味わったその時のご飯の美味しさを、いまも忘れることが出来ない。それから70年を経ても、いまだにご飯は一粒残さず食べるのも、一粒残さず食べるためにご飯の量が多すぎれば食べる前に必ず減らしてもらうのも、そのとき以来の私の習慣である。
私も米田君も、その時のご馳走を、ゆっくりと、ただ黙って食べ続けた。食べることだけに一心になっていた。世の中にこれほどまでにうまいものがあるのだろうか、という思いであった。ただただ有難かった。その時の、強烈な衝撃に近い体験は、私には長く尾を引いて残った。ずっと後になって、私は、国内でも、外国でも、いわゆる「グルメ」たちがいう美食にも何度か接するようになったが、それはそれで、楽しい体験であったかもしれない。しかし、かつての、あの時の白いご飯ほど美味しいと思えたことはない。テレビなどで美食の体験を云々する自称「グルメ」たちを、うらやましいと思ったことも、いままで、一度もない。
昭和35年(1960年)の春、私は名古屋から苫小牧へ移って、室蘭工業大学に勤めるようになった。夏休みに、オートバイで遠乗りに出かけたことがある。北海道の道路は、市街地のほかはまだどこも砂利道が殆どであった。札幌から滝川を経て留萌へ向かう途中、深川の近くの一直線の砂利道を60キロくらいのスピードで走っていた時、前方の砂利道に横に溝が掘られていて、それが砂利で埋まっているだけであることに気がつかなかった。オートバイは、ざくっと溝に突っ込んで前方に向かって大きく一回転し、私は数メートル先へ投げ飛ばされた。道路に激しく叩きつけられたとき、私は意識だけははっきりしていた。しかし、強い衝撃を受けて、呼吸がピタッと止まってしまった。息を吸おうと思っても吸えない。吐こうとしても吐けない。呼吸が全くできないのである。このままでは死んでしまう。私は必死に、息を吸おうとし、吐こうと努めた。
しばらくして、やっと呻き声が少し洩れるようになった。私はその呻き声を、少しでも大きくしていこうと懸命になった。呻き声が洩れた分、息を吸い込むように必死になった。夢中になってその動作を繰り返しているうちに、やっと少しずつ呼吸できるようになった。ひどく長い時間がかかったような気がしたが、おそらく、2,3分もかかっていなかったかもしれない。体は道路に叩きつけられたままの姿勢で動けない。夏の青空が目に入っていたが、自分で自分の体を見ることもできなかった。私はやっと、右手が少し動かせるのに気がついて、右手で頭を触り、少しずつ下へずらして首から胸へ触っていった。左胸を触るとぼこん、ぼこんと窪んで、肋骨が折れていることがわかった。少なくとも3本は折れているようであった。
田舎道で近くに民家はなく、人影も見えない。そのまま5分、10分と時間が過ぎていったが、私の体は全く動かず、どうすることもできない。やがて、道路際に小学生くらいの子どもが近づいてくるのを見つけた。子どもは私が死んだと思ったのかもしれない。私は右手で手招きし、恐る恐るそばまで寄ってきた子どもに、誰か大人の人を呼んできてくれるように頼んだ。またしばらく経って、やっと近くの農家の人らしい大人が現れた。私は救急車を呼んでくれるように頼んだ。警察が来て、救急車が来て、私は深川市立病院へ運ばれた。左胸の肋骨はやはり3本折れていた。内出血も起こしていた。2週間ほど入院して、包帯で胸をぐるぐる巻いたまま、私は車に乗せられて苫小牧の家へ帰った。
いのちは取り留めたが、私はこの事故で、呼吸ができないこともあることを、身に染みて知った。私はいまでも、時に意識して、息を吸ったり、吐いてみたりすることがある。少なくとも、いまの私には、何の無理もなく、呼吸が自由にできることが、まったく当たり前であると思う気持ちはない。5歳の時に私は、大阪の尻無川で溺れかかったことがあった。その時のことをいまも鮮明に覚えているが、水中で息ができなくて、泣き叫びながらもがき続けていた。一度深く沈み、二度沈んで浮き上がってきた時にも、私の手は何もつかむことができなかったが、もう限度と思われる3度目に浮き上がってきたときに、2歳年上の友達・かずちゃんの手に初めて触れて、私は救われた。息ができることの有難さは、その時の思い出にもつながっている。
その数年後に、私は、小樽商科大学へ転任した。何かの公用で、庶務課長のSさんと当時の文部省へ出張した時、私は東京へ向かう飛行機のなかで、Sさんの奥さんが前年に肺がんで亡くなったことを知った。亡くなる前には、自由に呼吸ができなくて苦しんだそうである。病室で、Sさんが、「何かして欲しいことはないか」と訊いたら、奥さんは、「もう一度、空気を胸いっぱいに吸ってから死にたい」と答えたという。奥さんは、それから間もなく亡くなった。私はそのことばが忘れられなかった。オートバイ事故で、一時的にせよ、呼吸が止まってしまった経験があっただけに、「空気をいっぱい吸って死にたい」という
Sさんの奥さんの気持ちが痛いほどにわかるような気がしていた。自由に空気をいっぱい吸って呼吸できるということは、本当は、決して当たり前のことではなく、幸せなのである。
私は、自分で自分自身に、「右手を上げてみて」とこころの中で言って、右手をあげてみるようなことがある。同じようにして、左手も上がる。右足も、左足も動く。考えてみれば、これも決して当たり前ではないかもしれない。世の中には、手足が動かせないで不自由している人々が無数にいる。目が見える、耳が聞こえる、これも、決して当たり前でないことは、一歩外へ出て、人々の中を歩いてみればわかる。目が見えず、耳が聞こえず、ことばもしゃべれなかった三重苦のヘレン・ケラーは、かつて、「人々が若い時に、一時的に盲目になる経験を持つことができれば、大変有益ではないか。光の有難さがわかるだけではなく、人の苦しみもわかり、愛の心も広がるからである」という意味のことを述べていた。「盲目であることは、
悲しいことです。けれど、目が見えるのに見ようとしないのは、もっと悲しいことです」とも言っている。そして、その彼女は、三重苦でありながら、「私は自分の障害に感謝しています。自分を見出し、生涯の仕事に出会えたのもこの障害のおかげだからです」と、感謝の気持ちで社会福祉活動に自分の一生を捧げた。
呼吸ができて、ご飯を食べることができて、手足も動いて、目も見え、耳も聞こえる。それに、雨風を凌いで眠るための部屋があれば、それは、本当は決して当たり前ではない、たいへん幸せなことではないか。感謝しなければならないのではないか。しかし、そういうことには少しも気がつかず、考えてみようともせず、人に較べて少しでもいい生活をしたい、他人から羨ましがられるような大きな家に住みたい、地位も名誉も手に入れて満足したい、などと執拗に物欲や名誉欲を追っていくのであれば、おそらく、この世に生まれてきた意味を取り違えることになってしまうであろう。私たちは、一人一人がすべて、幸せな人生を生きる資格が生まれながらにして与えられていると思うが、それは、決して金銭欲や名誉欲の充足によってではない。むしろ、イエス・キリストの言うように、「富める者が天国へ入るのは、ラクダが針の穴を通るより難しい」(マタイ19-24)のである。
心理カウンセラーの衛藤信之氏に、『今日は心をみつめる日』(サンマーク出版、2010)という著書がある。そのなかで、衛藤氏は、こころに沁みる一つのエピソードを紹介している。ある企業のセールスマンたちの集まりに氏が講師として招かれたときに、そのなかでも一番のセールスを上げる女性と話をする機会があったらしい。その人は、見た目は「ごくふつうのおばさん」だが、周囲から母親のように慕われ、頼られながら、謙虚で少しも偉ぶるところがない人柄であったそうである。トップセールスマンの彼女は、休んでいるのを誰も見たことがないといわれるほどの熱心な働きぶりに加えて、同僚や部下の面倒もよく見、彼らの売り上げにも協力を惜しまないという評判であった。その彼女が、衛藤氏に、おだやかな笑みを浮かべながら、自分の生き方や働き方について、こう話したのである。
「私の母はよく、『一年に三日だけでもいいことがあったら、その年は最高の年だよ』といっていました。その母に育てられた私も、『生きるのは苦しいのが当たりまえ』と思って生きてきました。ですから三日いいことがあれば、残りの三百六十二日がたとえつらく苦しい日でも、私は十分、幸福だって・・・・・・」
「ですから、こうしてみなさんとおしゃべりして、おいしいものを食べられる、ただそれだけで私は幸せすぎるくらい幸せなのですよ。幸せすぎて母に申し訳ないくらいです」
「三日いいことがあれば、残りの三百六十二日がたとえつらく苦しい日でも、私は十分、幸福」というのは、なかなか言えないことばだが、衛藤氏は、それを聞いて、こう述べている。「私はいたく感動しました。何に感動したのかといえば、その人と、その人のお母さんが備えていた、幸と不幸についての知恵の深さに、です。彼女はお母さんゆずりの知恵によって、日々が大変で当たりまえ、すべてに満足できることはないと思って生きています。だから、日陰から出たときに日向の温もりがいっそう強く感じられるように、何の変化もない平凡な事柄がこのうえない幸せと感じられるのです。つまり、彼女の幸福をつくり出しているのは、「足りない中で満ち足りる」日常を味わうことの心にほかなりません。足りないことがあって当たりまえと考え、むやみに幸せを欲しがらず、ありきたりで、ささいなことにも深い喜びを見出す。そんな“賢者の知恵”が彼女に確かな幸福をもたらし、彼女のトップセールスウーマンとしての心の支えになっているのです。」(同書、p.12)
「歎異抄」による親鸞の他力信心 (2016.07.01)
― 生活と文化をめぐる随想 (No.108) ―
「歎異抄」第12条は、「経釈をよみ学せざるともがら、往生不定のよしのこと。この条、すこぶる不足言の義といいつべし。他力真実のむねをあかせるもろもろの聖教は、本願を信じ、念仏をもうさば仏になる。そのほか、なにの学問かは往生の要なるべきや」ということばで始まっている。この本は、正応3年(1290年)頃に書かれたといわれるだけに、中古文の旧仮名遣いでちょっと読みにくいが、これを、意訳して現代文にすればこうなるであろう。「尊い経典やそれについて書かれた本などを深く学ばない者は、決して浄土に往生できないだろうという人がいる。これは全く見当ちがいの意見である。本願他力について説かれたさまざまな正しい経典、書物には、阿弥陀仏の約束を信じて念仏をする者は、必ず浄土に行ける、とある。そのほかになんの学問が必要というのであろうか」。
つまり、浄土へ行けるようになるためには、経典などを深く学ぶ必要はなく、阿弥陀仏の約束を信じて念仏をするだけでいいというのである。私たちは、信心のためには、悟りを開くまでに至らなくても、まず何よりも、一生懸命に学ぶことが大切であると思いがちであるが、親鸞は、「経典を深く学ぶ必要はない」という。親鸞は、続いて、こう述べている。(以下も、主要部分は現代文に意訳して示すことにする)
「しかしそれでも納得できない人は、好きなだけ学問をして阿弥陀仏の真意を究めてみたらよい。しかしそれでも教えの本意がどうしても納得できないとしたら、それは不憫としかいいようがない。何度も言うように、文字も読めず、経典などの意味もわからない人でも、だれもができる信心の形としての易しい念仏であるから『易行』というのであり、だからこそ意義があるのだ。」
親鸞は、経典を深く学ばねばならないと思っている人は気のすむまで学問をすればよい、どうせ教えの本意などはわかるはずはない、と言いたいのであろうか。むしろ、文字も読めず、経典などの意味もわからない人のほうが、救いにあずかり易いと説いているようにもみえる。要するに親鸞は「易行」を強調している。読んで字の如く、誰にもできる易しい行為だからこそ、意味があるというのである。これに対して、学問を柱とする信仰は「難行」であり、「聖道門」である。「聖道門」というのは、一生懸命に経典などを勉強して、自分の力によって真実を悟ろうとする道である。第4条で、「聖道の慈悲というは、ものをあわれみ、かなしみ、はぐくむなり。しかれども、おもうがごとくたすけとぐること、きわめてありがたし」と述べているように、聖道門では、結局、人を救うこともできない。自分自身をも救うことはできないのであろう。それを、親鸞は、「学問を柱とするのは自力をたのむ他の宗派であって、これを『難行』という。しかしいくら学問をしても、名声や利益に拘泥したら、かえって浄土は遠のくのではないか」と述べた。
それなら親鸞自身は、経典を深く学ばなかったし、初めから易行に徹していたのであろうか。そうではない。親鸞は承安3年(1173年)に日野有範の子として生まれ、9歳の春には、関白九条兼実の弟で比叡山延暦寺の座首となった慈円を師父として得度・出家している。親鸞が13歳(1185年)の春には、平家が滅亡し、後白河法皇の院政により政治的にも宗教上でも、社会は混乱して争いが絶えないという暗い世相が背景にあった。親鸞の入った延暦寺は、最澄の興した日本仏教の根本道場であり、今日でいえば仏教学の最高学府として、数千名の僧徒が仏教学と修行に励んでいたところである。親鸞はそこで、29歳になるまでの20年間にもわたって、経典の勉学に打ち込み、自力の難行を続けていた。その自力の難行を捨てて、法然聖人の他力、易行の念仏浄土門へ廻心したのは建仁元年(1201年)のことである。親鸞は、当時の学僧としては、最も深く経典を学んだ一人であったといってよい。
第2条では、信仰に迷いを生じた信徒たちが、関東から親鸞の住んでいた京都まで、はるばると十余か国を越え、親鸞を訪ねてきたときのことを述べている。当時のことだからそれは命がけの旅であった。そのような旅を続けて目の前に現れた信徒たちに向かい、親鸞は、「あなたがたは、私が念仏以外に往生極楽への道を知っているだろうとか、いろいろと経典以外の教えにも通じているだろうとか勝手に考えているようだが、それはとんでもない誤りである。それを教わりたいというのであれば、南都や北嶺にすぐれた学僧が大勢おられるのだから、そういう人たちに会って往生の道を詳しくお聞きにたればよいのだ」と、突き放したような言い方をしている。
親鸞がここで、あえて南都(奈良の興福寺、東大寺)や北嶺(比叡山の延暦寺、三井寺)の「すぐれた学僧」に言及しているのは、実は、彼らの僧侶としての学識・実践を認め、敬意を払っているからなのではないであろう。当時の比叡山延暦寺や奈良の興福寺をはじめとする寺々には数多くの学僧がいても、仏典の真髄を把握し、仏道を真に実践できるものは極めて少ないことを親鸞は十分に知っていた。彼自身が比叡山における修業に絶望して山を下りて以来、南都、北嶺からは異端視され迫害をうけてきた苦い体験をもっている。ついには越後国へ流されもした。その親鸞が、彼らに会って往生の道を聞け、と言っているのは、おそらく精一杯の皮肉で、実際は、彼らの所へ行っても往生の道など聞けるはずがない、と言いたかったのであろう。親鸞が、学問を柱とする難行を退けているのは、こういう体験を踏まえたうえでのことであった。この第12条は、このあと、このように続く。
《この頃のように、念仏を一心に信仰する者と、それ以外の宗派の者とが議論して、「自分たちの宗派が正しい。他の宗派は劣っている」と主張しあえば、お互い敵同士にもなるし、また攻撃したり謗りあうことにもなる。これは結局、みずから真の念仏の教えを軽んずるだけのことなのだ。たとえ、他の宗派の人たちから、「念仏を称えるなど、とるに足らないつまらない者のための宗教である。教義は浅薄だし、程度が低い」などと言われても、決して争ってはならない。》
親鸞は、むしろ、他から非難され謗られても、それは当然のことで不思議ではないと、考えていた。親鸞自身が、すでに触れたように、比叡山の修行に見切りをつけ、退山してしまっている。これは比叡山の伝統と権威に逆らうことで、当時としては容易ならぬ背徳行為であった。座主の慈円からもそのために非難されていたといわれている。特に、比叡山の教義を否定するように、新しく他力の念仏を世に広めようとする行為は許しがたいと思われていたに違いない。信者たちにも、誹謗がつきまとった。放置すれば、宗派間の争いにもなっていくであろう。そのことを案じた親鸞は、争いを避けるために、誹謗されたときにはこう答えよ、とその対応の仕方にまで触れている。その細やかな配慮を、親鸞はこの第12条で、次のように示した。
《私どものように煩悩にまみれた、取るに足らない無知な人間でも、阿弥陀仏によって助けていただけると固く信じております。すぐれた方がたが念仏などくだらない教えだと思われても、私たちにとってはこれ以上素晴らしい教えはないのです。もし他にどんなにすぐれた教えがあったとしても、厳しい修行や悟りなど、自分たちには及ばないものばかりですから、とてもついてはゆけません。私たちにとっては、生死流転をくりかえすこの運命から、仏の約束によってお救いいただくことだけが希望でございます。ですから、どうぞ、お妨げにならないでください。》
親鸞が他からの非難に対してここまで気を配っているのも、当時の平安仏教からの圧力が看過できないほどに高まっていたからであった。それまでの自力聖道門の仏教がしばしば貴族仏教といわれたように、ひたすらに貴族階級を対象としてきたのに対して、法然の他力専修念仏門では、経典などを深く学ぶ必要もなく、たやすい教理でひろく老若男女の庶民までも受け入れていた。乱れた暗い世相であっただけに、阿弥陀仏の本願に身を委ねて、南無阿弥陀仏を称えさえすれば救われるという教えは、多くの大衆の心を捉え、安らぎと癒しを与えていたであろうことは想像に難くない。こうして、専修念仏教団の勢いは、燎原の火のように広がっていったのである。比叡山門の衆徒たちは、その勢いに脅威を感じ始め、元久元年(1204年)には、遂に決起集会を開いて、法然の教団に対して念仏を停止させるべく、朝廷に強訴したりした。ここで示されている親鸞の「他者」への配慮も、このような宗教的対立が背景にある。親鸞は、この前の第11条でも、すでにこう述べていた。
《読み書きもできないような人びとが熱心に念仏するさまを見て、「お前は、衆生すべてを救うという阿弥陀仏の誓願のふしぎな力を信じて念仏しているのか、それとも南無阿弥陀仏という名号の大きな力を信じて念仏しているのか。どちらなのか」などと相手を脅すようなことを言って、人を困惑させる者がいる。そのくせ、その二つの力がどんなふうに違うのか、自分の質問の意図さえ説明しようとしないのだから困ったものである。こういったことはくれぐれも気を付けて考え直さなければならない。》
親鸞は、こういう宗派の対立の中で他力の信心を説いていった。阿弥陀仏の前身の法蔵菩薩は、一大慈悲心を起こして、長い思案を重ねたうえで、称え易い名号の「南無阿弥陀仏」を創り上げ、その名号を称える人たちをすべて救済しようという誓いを立てられた。その誓願を素直に信じる者は、そのまま救われ、やがて浄土へ行けることになるのである。誓願の功徳力によるのか、名号の功徳力によるのかなどと、とやかく思いまどう必要は全くない。つまり、阿弥陀仏の誓願と功徳力を信じさえすれば、必ず名号の功徳も付随してくる。二つの功徳力は一体不二であって、別のものではないというのである。そして、その上で、念仏はあくまでも他力であることを親鸞は強調する。このことばは、次のように続く。
《阿弥陀仏は、あらゆる人びとをすべて救い、浄土に往生させようという願いのもとに、だれでも覚えることができ口にとなえやすい南無阿弥陀仏という名号を考えだしてくださった。そしてこの名号をとなえる者は、一人残らず必ず救うぞと約束なさったのだ。だからこそ、その大きな慈悲の心に身をまかせることで往生できると信じるのも、またこうして念仏できるのも、すべて阿弥陀仏のお力によるものと思いなさい。それは自力の行いではなく他力のはからいだからこそ、まっすぐに仏の約束どおり真実の浄土に生まれる道なのだ。》
私たちは阿弥陀仏の本願を信じることで浄土へ行くことができるが、その信心は、阿弥陀如来から与えられるものであって、私たち衆生が自分の力で信じとるのではないというのである。だから、信心も念仏も他力である。第8条では、それが、「念仏とは、それをとなえる者にとって、修行でもなく、善行でもない。それは自分の決意や労力によって行われる行ではないからだ。だから「非行」である。自分の力によって積まれる善でもない。だから「非善」という。念仏はひとえに、阿弥陀仏の大きな働きかけによって、おのずと発せられるものである。ゆえに自分の行う修行でもなく、またいわゆる善行とはかけはなれたものなのである」と書かれている。このように、念仏は他力の計らいで自力ではないがゆえに、読み書きができない人でも実践できる易行であると、言えるのかもしれない。親鸞は、第12条の後半で、さらに続けてこう言っている。
《他力の念仏を、信じる者も、謗る者も、もちろんいるだろう。釈尊もそのことを語られている。しかしそれを承知の上で、私たちは一筋に念仏を信じてゆくとすでに固く心に決めたのだ。また、こうも言えるだろう。釈尊の言われるとおり、今現在、私たちを謗り非難する者が確かにいるからこそ、仏が私たちをお救いくださるということばも、また間違いないのだ。かえって、念仏を信じる人ばかりで謗る人がいないほうが、不自然ではないか。かといって、必ず他人から非難されたほうがいいと言っているのではない。仏は、人から認められることも謗られることも両方とも避けられないものであると説いておられる。その上で、釈尊は、たとえ謗られても、できるだけ自分の信心に疑いを抱かないようにとおっしゃっているのだ。》
念仏を謗る人がいないほうが不自然で、「私たちを謗り非難する者が確かにいるからこそ、仏が私たちをお救いくださるということばも、また間違いないのだ」という逆説的ないい方は、第9条の表現を思い出させる。私たちが浄土へ急いで行きたいと思えないのは、私たちの煩悩のせいである、と述べているくだりである。浄土へ「いそぎまいりたきこころなきものを、ことにあわれみたまうなり。これにつけてこそいよいよ大悲大願は頼もしく、往生は決定と存じそうらえ。踊躍歓喜のこころもあり、いそぎ浄土へもまいりたくそうらわんには、煩悩のなきやらんと、あやしくそうらいなまし」とあるが、この煩悩があるからこそ、「大悲大願は頼もしく」は、「謗り非難する者が確かにいるからこそ」、「大悲大願は頼もしく」ともかけられるものであろう。「歎異抄」では、親鸞の教えをこのように伝えてきて、第12条の最後は、次のような言葉で締めくくられている。
《近年は、学問をして理論を備え、人の非難に対抗し、論破しようと身構えている人がいる。そうではなく、学問をする人は、それによってますます仏の慈悲の深さ、大きさを理解し、その誓いの意味を知るようにしなければならない。そしてもし「自分は浄土には値しない人間ではないか」と思い疑うような人に対しては、自分の知識によって、「阿弥陀仏の約束は、善悪の行いや心が清らかであるかどうかなどにかかわらない、平等、絶対のものです」と正しく説明できてこそ、はじめて学問をする者としての甲斐があろうというものだ。それにもかかわらず、たまたま何の他意もなくただ一心に阿弥陀仏を信じ念仏している者に対し、「学問をしなければ意味がない」などと脅すような言いかたをするのは、もっとも慎むべき行為であり、仏に敵対する悪魔のようなものだ。そういう者は、自分自身が他力の信心に欠けているのみならず、自分の間違いから他人をも惑わすことになる。》
この「歎異抄」では、第1条が、「すべての人びとをひとりのこらずその苦しみから救おうというのが、阿弥陀仏という仏の特別の誓願である。その大きな誓願に私たちが身をゆだねるとき、念仏せずにはいられない気持ちが起こってくる。そして『南無阿弥陀仏』が口から出て称えられる時には、私たちはすでに救われている自分に気づくのだ」と、書き出されている。これが、歎異抄全体の底流をなす信心の要諦であるといっていいであろう。しかも、この阿弥陀仏の誓願にあずかる者には、老人にも若者にも幼子にもなんの区別なく、また世間でいう善人、悪人にも関係がない。ただ一つ、ひたすら信じる心こそ大事であることが繰り返し強調されている。その上で親鸞は、第12条で、「経典などを深く学ぶ必要もない」ことさえ付け加えたのであった。
親鸞はこのように、終始、浄土へ行くためには、ひたすらに、阿弥陀仏の約束を信じて念仏をすることだけを説き続けたといってよい。そして、自分の信心については、第2章で、私はただ、念仏して仏に助けられるのだと法然上人に教えられことを信じるだけである、と述べたあと、こう言い切っている。「阿弥陀仏の本願が真実であるならば、釈尊の教えにも嘘はない。釈尊の教えが真実であるなら、善導大師のお解きになったことにも誤りはない。善導大師のお解きになったことが真実であるなら、どうして法然上人の言われることが虚言でありえようか。そしてまた、法然上人の言われることが真実であれば、この親鸞の言うことも空ごとであるはずがない。これがつまり、私の信心なのだ――
」。親鸞の信心にはこのように、一点の曇りもなかった。「たとえ法然聖人にだまされて念仏したために地獄に落ちるとしても全く後悔はしない」とまで激しく吐露している親鸞の心情には、私たちはただ、深く心を打たれるだけである。
天狗の実像についての覚え書 (2016.09.01)
― 生活と文化をめぐる随想 (No.109) ―
はじめに少し余談を付け加えておきたい。女流作家の佐藤愛子さんが自分の霊的な問題を解決するために世話になり師と仰いでいた相曽誠治という人がいた。相曽氏は、北海道の佐藤さんの山荘まで行って、山荘の怪奇な霊現象を鎮めてくれたりもした。その相曽氏は、1910年に静岡に生まれ、1999年12月31日の夜半、あと1時間で2000年が来るという時間に90歳で亡くなられたが、「普通の人」ではなかった。相曽氏を崇拝する名古屋の鶴田医師は、「あんなに無私の、清らかな魂を持った人に会ったことがない」という。柔和な眼差し、常に礼儀正しい物腰で穏やかに話し、品性の高さが感じられたというその相曽氏を、佐藤さんは「神界から来た人」と紹介している。神界から下りてきてこの世に生きていた人というのは極めて稀な例といえるが、その相曽氏が「神界から来た人」であることを知ったいきさつを、彼女は、『私の遺言』(新潮社、2002年)のなかで、つぎのように述べている。
《三か月に一度くらい、名古屋の鶴田邸で相曽氏を囲んで、日本の伝統文化の講話を聞く小さな集まりがあり、時々、私はそれに出席していた。ある日、浜松へ帰られる氏と東京へ向う私が名古屋駅のプラットフォームの待合室で電車が来るのを待っていた時、ふと私はある衝動に駆られてこう訊ねた。
「失礼ですが、先生は、神界からおいでになった方ではございませんか」
そんな唐突な問いかけに対して、氏は驚きも笑いもせず、極めて平静に頷いていわれた。
「私はことむけのみことと申します」
その口調はまるで、お故郷(おくに)はどちらですかと訊かれて「青森です」と答える人のような、まことに日常的な応答だった。
「そうでしたか」
と私はいった。やっぱり・・・・・・と心に頷いていた。「ことむけのみこと」とは多分「言向命」と書くのであろう。即ち力で従わせるのではなく、言葉をもって導くという意味であろう。私は素直にそう思った。》(同書、pp.198-199)
相曽誠治氏は、1995年(平成7年)1月17日に起こった阪神大震災を予言している。1月10日に、佐藤愛子さんへ電話で、「近々、地震が来ます。ご用心なさって下さい」と言ってきたのである。いつもの穏やかな口調であったという。「それはどこですか? 東京ですか?」と佐藤さんが訊くと、「場所は申せません。しかし必ず来ます」と相曽氏は答えた。相曽氏にはわかっていても、場所まで教えることはできなかったのであろう。「神さまはご心配になっていらっしゃいます」と付け加えた。「必ずきます」と相曽氏が言った阪神大震災は、それから1週間後に実際に起こった。
以上が余談で、ここから本題に入る。――その相曽氏は、毎年7月に富士山の山頂で神事を日帰りで行っていた。普通は、80歳半ばの人が富士山の登山・下山を日帰りで行えるというのは考えにくい。そこで佐藤さんが、相曽氏に日帰りで登山・下山できるわけを問うと、「天狗さんが助けてくれますので」と、相曽氏はきわめて当たり前のように答えて、こう続けた。「登る時はみんなで後押しをしてくれますのであっという間に山頂に行き着きます。でもその姿は人にはみえません」。そして、山頂には既に汚れていない場所が用意されていて、お供えの塩、洗米、神酒、水、海の幸、山の幸などもあっという間に整えられ、すぐに神事が始められる、のだそうである。
富士山の上空10メートルあたりに富士神界という神界があり、足利時代に肉体のまま葛城山から神仙界に入った山中照道大霊寿真というたいそう位の高い神仙がいるという。相曽氏の富士登山の時に後押しをしてくれるのは、その山中照道大霊の門人というか、眷属というか、富士山で修業している霊人で、その霊人を相曽氏は「天狗さん」と呼んでいるらしいのである。この天狗というのは私にはよくわからない。佐藤愛子さんも、「天狗というと、手に団扇を持ち、鼻が高く、顔は赤く、目はいかっていて、鞍馬山で牛若丸を鍛えたあの天狗を思う」と書いている。そして、この天狗について彼女は、相曽氏の著書などから学んで、理解していることをつぎのように書いた。
《霊界には数十、数百の区別があって、人が死ぬと四次元へ行くが、その人の生前の行動や思想、信仰などによってその人に適した霊界へ行く(これまで私が記してきた「幽界」というのが「四次元」で、「霊界」が「五次元」と思ってよいのであろう)。
五次元と一口にいっても高い階層、低い階層があり細かく分れている。低い方に印度のヨガの達人や道教の先人、修験道の行者などがおり、ここを「山人界」、あるいは「山人天狗界」というのだそうである。その山人天狗界の中にも更に次元の高低があって、高い修行者を「善玉の天狗」と呼ぶ。富士山で氏を助けるのは善玉天狗である。それに対する悪玉天狗は四次元(幽界)や三次元(人間界)よりも更に下の二次元に密着していて、山霊や動物霊などと重なる。》
(同書、pp.196-197)
80歳半ばの人間が富士登山を日帰りで行うというのは大変なことだが、「神界の人」である相曽氏はそれを毎年7月に繰り返してきた。多くの「天狗さん」たちに後押ししてもらって、あっという間に山頂に着いてしまうというから不思議である。その「天狗さん」たちは、神仙界に入った山中照道大霊の門人のような霊人たちであることも、相曽氏がこのように明らかにしている。天狗といえば、世間では一般的に、空想上の怪物と思われているが、試みに『広辞苑』で「天狗」をひくと、「深山に棲息するという想像上の怪物。人のかたちをし、顔赤く、鼻高く、翼があって神通力をもち、飛行自在で羽団扇をもつという」とある。しかし、天狗が単なる「空想上の怪物」ではなく実在することは、この相曽氏の富士山登山でもわかる。この「天狗」について、さらに、東京堂出版の『心霊研究辞典』(1990)をみてみると、そこでは次のように書かれている。
《自然霊の一種で、エンゼルや妖精類の範疇に属するものと考えられ、龍神とは異なる存在である。古来日本の逸話に登場することが多い。動的状態では,本来の姿は動物あるいは鳥類の一種のようであるが、好んで人間の様な姿を現すことが、彼らに共通の心理であるといわれている。ことに、①全身に毛が多い,②狗というような動物に似ている、③鳥のように翼がある、④口が尖っている、という特徴がある。白衣をまとった神様を想像させる姿、頭部に兜布を載せた山伏姿、手に錫杖を持った行者姿、太刀を帯びた武芸者らしい姿等々の形態をとるが、それぞれの天狗の使命や立場・階位というものが風格等に顕れるようで、修行を積んだものほど立派である。一方、幽界の天狗は感情的で、悪戯や人間を驚かせる奇抜な行為をやって喜ぶものがいる。地上のわれわれに、良い意味で、①武術の方面で能力を発揮させ指導する、②文の方に能力を発揮させる、③文武両道に才能を発揮させる、等の働きを担っているといわれている。》
ここでは、天狗は、「龍神とは異なる存在だが、自然霊の一種で、西洋でいうエンゼルや妖精類の範疇に属する存在」であるという。もちろん『広辞苑』でいうような「想像上の怪物」ではない。では、天狗たちが実在する「天狗界」のようなものがあるのだろうか。それに対しては、『心霊研究辞典』では、「霊魂界は心の境涯による世界であり,天狗界とその世界に住む霊達というものが特別に存在するわけではなく、天狗も自らの境涯で、ある者は幽界に居住し、また、向上の一途をたどると霊界へと浄化向上する。神仙界も同様に考えることができる」とある。天狗はどういう存在なのか、興味をそそられるが、幸い、この天狗については、『新樹の通信』のなかに、新樹氏自身が霊界の富士山に登山して、天狗に会う話がある。それをここで引用してみたい。
新樹氏は現世では富士山に登ったことがなかったので、霊界で守護霊とともに富士山に登ってみることにした。「僕達の選んだのは、例の吉田口で、ちょっと現界の方をのぞいてみると、北口とか、何とか刻みつけた石標があったようでした。その辺には、人間の登山者も沢山おり、中には洋服姿の人も見受けました」と新樹氏は述べている。新樹氏は洋服姿で、守護霊は白衣を裾短かにからげ、白の脚絆に白の手甲、頭には竹笠の参詣姿であった。「どうせ人間の方から、僕達の姿は見えはしないのだから、どこを通っても差し支えはない筈ですが、しかし人間と一緒では、何やら具合がわるいので、僕達は普通の登山路とは少しかけ離れた、道なき道をぐんぐん登って行きました」とも言っている。そして、天狗に会った時の模様をつぎのように伝えている。
《やがてある地点に達しますと、そこには、ごく粗末な宮らしいものが建っていました。それがどうやら、山の天狗さんの住居らしいので、守護霊さんと相談の上で、一つ訪問する事にしました。僕はお宮の前に立って拍手を打って、「こちらは富士の御山に棲われる、天狗さんのお住居ではありませんか?」と訊いてみたのです。が内部はひっそり閑として、何の音沙汰もない。
「はて、これは違ったかしら……。」僕達が小声でそんなことを言っていると、俄かにむこうの方でとてつもない大きな音がする。何かと思って、びっくりして顔を見合わせている間に、何時何所をどう入ったものか、お宮の内部には、何やらがさこそと人の気配がします。
「矢張り天狗さんが戻って来たのだな。今の大きな物音も、たしかにこの天狗さんが立てたに相違ない……。」僕はそんなことを思いながら、そっと内部をのぞいて見ると、果して一人の白髯を生やした、立派な天狗さんが、堂々と坐り込んでいました。》(『新樹の通信』「幽界人の富士登山」pp.23
私の現代文訳より)
新樹氏が訪ねたその天狗は、赤煉瓦色の服を着て、それに紫の紐がついており、下には袴のようなものを穿いていた。手には羽団扇も持っていたという。新樹氏と守護霊はドアを開けて丁寧に挨拶すると、天狗は優しそうに「まあ上れ!」と言った。このあと、天狗との会話が始まる。これも現代文訳から引用する。
《「いや、ただご挨拶だけさせていただきます。先刻はお不在のように拝見しましたが……。」
「わしは宮の内部にばかり引き籠ってはいない。或る時は樹木のてっぺんに居たり、また或る時はお山の頂上まで行ったり、これでなかなか忙しいのじゃ。」
「この宮にはたった一人でお住まいですか?」
「いや、眷族が多勢居る。わしが一つ口笛を吹けば、皆一散に集まって来る……。」
「そんな光景を、一度拝見させていただくと、大へん有り難いのですが……。」
「それはちょっと出来ん。・・・・・みな用事を帯びて他所に出ているからな。」
天狗さんは、口笛だけはどうしても吹いてくれませんでした。》(同書、p.24)
この対話はまだ続くが、この話とは別に、『新樹の通信』には新樹氏が指導霊の教えを受けながら、特定の天狗に会いに行く「天狗探検譚」というのがある。天狗には、高尚なもの、やくざなもの等、たくさんの種類があるが、この天狗は、ZKという名前で表記されている。大分年功を経ており、身体には毛が生えているという。ちょっと動物らしいところがある霊魂で、かなり歳をとっているが、時には若い風もすることがあるらしい。その天狗とどのようにして会えるかを指導霊に訊くと、「とにかく深山を目がけ、心の中でその天狗の名を念じて行けばよい」と教えられる。新樹氏は、慣れた洋服姿で、出かけた。やがて聞いた通りの山路にさしかかる。路は随分険阻だが、現世のような危なっかしい感じはない。深い谷間もあり、四辺の草木の色は鮮やかで、美しい花なども咲いており、鳥の鳴き声も聞えてくる。新樹氏は、天狗の名を心に念じつつ、気楽な登山気分で歩いて行った。そして、その後のことをこう伝えている。
《・・・・・と、はるか彼方の山の木立の中に、家が見えました。屋根が反りかえって、支那風に赤く青く彩色してあります。いつもそんな家がある訳ではないが、僕が尋ねて行くというので、急いで造ったものでしょう。どうも人が訪問してくる時に、家がないのは具合が悪いもので、僕にもそうした経験があります。多分指導役のお爺さんが、前以て通知しておいてくれたのでしょう。
門の柱などはありませんでしたが、門からかなり離れて玄関がありました。そこにはZK 閣と横に書いた額が懸っていました。書体もどうやら支那風です。そこで僕は「ご免下さい」といって案内を請いました。すると若い男が取次に出てきたが、その服装は黒い毛の繻子のような、支那風の服を着ていましたが、僕は近頃は霊眼が利くので、ちょっとそれを働かせますと、正体はやはり天狗でした。
来意を告げて取次を頼むと、やがてZKさんが出てきましたが、やはり老人の姿でした。背はかなり高く、年の頃は七十位に見えます。白い髯を生やして、ちょっと兜巾に似た面白い帽子をかぶり、支那服に似て少し袖の広い、鼠色の服を着、立派な草履を穿いております。僕は案内されるままに上り、一間に通りましたが、立派なテーブルと椅子が備えてありました。家の飾りつけなど、何れも支那好みです。庭も木石の配置など美事に出来ていました。この天狗さん、初めはどうも支那に住んでいたらしいのです。
椅子に腰をかけてから、僕は身の上をあらまし話し、今度訪問したのはほかでもなく、こちらの様子を現世に通信したいからだと申しますと、よくそんなに早く通信出来るようになったものだといって、お爺さんは大いに褒めてくれましたよ。》(同書、pp.46-47、現代文訳による)
このZKという名の天狗から、新樹氏はいろいろと天狗の生活ぶりを知ることができた。山には、薬草が沢山あるので、GDという男に色々な薬の製造法を教えていることや、木の実や何かで、葡萄酒に似たような飲み物も作っていることもわかった。ZK天狗がどんなことでも出来るというので、新樹氏が生前好きであったザボンを現世から取り寄せてもらったり、目の前の川に橋を架けたり、直径二尺もあらうという松の大木をへし折ったりする奇跡を目の前でみせてもらっている。ZK天狗が、ふだんは洞穴の中にでも住んでいて、この家は新樹氏を迎えるために造ったのであろうと思った新樹氏が、現界へ通信する必要があるから、どうかこの家を崩壊させる有様を見せて貰いたいと頼むと、それも快諾したZK天狗が、気合のようなものをかけると、赤く青く濃く彩色してある家が、だんだん淡くなり、上の方から下の方へと、自然に消えて行った、ということも新樹氏は伝えている。新樹氏は、さらに、今度は家を造るところを見せて頂きたいというと、これも天狗は快諾した。その家が造られていく状況と辞去の時の様子を、新樹氏はつぎのように述べている。
《やや暫らくすると、また気合のようなものをかけました。すると何もなかった地面の上に、これは前とは反対に、下の方から上の方へと、赤い青い色がつき始め、それがだんだん濃くなって、前の通りの立派な家が出来上がりました。その出来上った家を僕は触ってみました。僕が自分の家を触ってみた感じは、何だかカサカサしているのですが、この天狗さんの家も、同じような感じがしました。支那風のどっしりした風には見えますが……。
これでおおよその目的を達しましたから、僕は辞去することにして、天狗さんに、今度は僕の家へ来られるよう約束しました。今度は僕の方から天狗さんを煙に巻いてやりましょう。その時には佐伯さん(新樹氏の守護霊)にも来てもらうことにしましょう。》(同書、p.50、現代文訳による)
『新樹の通信』からの引用は以上で終わる。この天狗に関する記録では、江戸時代にも、もう一つ古い記録がある。平田篤胤の書いた『仙境異聞』(岩波文庫)である。文庫本のカバーページには、「文政3年、浅草観音堂の前に不意に現れた少年寅吉。幼いころ天狗に連れ去られ、そのもとで生活・修行していたという。この『異界からの帰還者』に江戸の町は沸いた。知識人らの質問に応えて寅吉のもたらす異界情報を記録した本書は、江戸後期社会の多層的な異界関心の集大成である」とある。寅吉というのは、文化三年(1806年)12月30日、年も月も日も「寅」に生まれたため、名付けられたという。この超能力少年は、「仙童寅吉」とも呼ばれて、江戸中の評判になった。
文化九年(1812年)四月、寅吉が七歳のとき、江戸上野の池之端(現・東京都台東区)、五条天神の境内で遊んでいると、奇妙な薬売りの老人に会った。老人は仕事を終えたのか、道端に並べていた薬を片付けるところだった。じっと見ていると、老人はすべてのものを小さな壺に入れ、みずからも壺のなかに姿を消して、いずこともなく飛び去っていった。寅吉は腰を抜かさんばかりに驚いた。しかし、好奇心が旺盛だったから、次の日に再び境内に行ってみると、例の老人がいた。老人は寅吉に「わしと一緒に壺に入らぬか」と誘った。寅吉は好奇心に駆られ、老人と一緒に壺に入ると、常陸国(現・茨城県)の南台丈という山へ連れていかれたという(この山は、いつの間にか岩間山→愛宕山と呼ばれ、獅子ガ鼻岩という岩が突き出ていることで知られている)。
こうして寅吉はたびたび老人に連れられ、各地へ飛行した。やがて常陸の岩間山へ飛び、その山中で諸武術、書道、祈祷術、医薬の製法、占術などを四年間にわたって修行した。その間、岩間山と家とを往復しながら、超能力を身につけていった。しかし、何度も家を留守にするので、世間では天狗にさらわれた少年ということになり、「天狗小僧寅吉」とも呼ばれたりした。その後、寅吉は文政三年(1820年)から江戸下谷長者町(現・東京都台東区)の薬種問屋長崎屋に身を寄せ、暮らすようになった。その問屋の主人の新兵衛が超能力に興味をもっていて、寅吉を招いたからである。新兵衛は自宅で、寅吉を中心にしてしばしば超能力会を開くようになったが、そこには幕府祐筆を務めた国学者屋代弘賢、その友人の国学者平田篤胤、農政学者佐藤信淵らが顔をそろえていた。
寅吉はまだ15歳の少年であった。しかし、とくに寅吉の話を聞きたがったのは、平田篤胤だった。色々話を聞くうちに、ますます「仙界」への興味をつのらせた。やがて長崎屋での研究会だけでは飽きたらず、寅吉を自分の家に招き、寅吉が訪れたという「仙界」について質問を繰り返し、文政五年(1822年)平田篤胤は、『仙界異聞〜仙童寅吉物語』を著したのである。それが、原文のまま、子安宣邦校注で刊行されたのが、岩波文庫の『仙境異聞』である。校注者の子安宣邦氏は、この本の「解説」のなかで、平田篤胤のこの本とのかかわりをつぎのように書いている。
《文政三年(一八二〇)という年の秋の末、天狗小僧寅吉は多種多様の異界の情報を身につけて、まさしく事件として江戸社会に登場した。いち早く天狗小僧出現の情報をキャッチしたのは山崎美成である。彼は自宅に寅吉をともない、天狗山人たちの住する異界の情報を聞き出すのである。そのことを知った屋代弘賢は、天狗小僧出現の報を早速平田篤胤のもとにもたらす。そして、寅吉がもたらす異界の情報は、日頃篤胤が強い関心を寄せている幽界の事情に通じるものであることを屋代は付け加えるのである。篤胤はその報に即座に反応した。たまたま来合わせていた伴信友をも誘って篤胤は早速山崎美成を訪ね、天狗小僧寅吉に面会するのである。それが篤胤と寅吉との出会いの始まりであった。篤胤の養嗣子鉄胤(かねたね)が書き抜いた『気吹舎日記』の文政三年十月一日の条に、「長崎屋へ天狗小僧を見に御出」と記されている。長崎屋とは薬種商山崎美成のことである。》(同書、pp.409-410)
やがて篤胤は、寅吉がもたらす異界の情報(異聞)を専有しようとする美成のもとから、寅吉を奪いさるようにして自分の家に連れてくる。そして少年を異界(幽界)への関心を共有する人々の強い探求的眼差しの中に置いた。篤胤を中心に、異界へのさまざまな探求的関心をもった人々は、屋代弘賢であり伴信友であり、そして佐藤信淵、国友能当であり、さらに気吹舎(篤胤門)に出入りする多くの門人たちであった。これら異界への探求的関心をもった人々が次々にはなつ質問の矢面に立たされる寅吉少年は、やがてこれら質問への見事な回答者となっていく。好奇の対象としての天狗小僧寅吉はこれらの質問への見事な回答を通して、いまや賛嘆の対象である神童あるいは仙童寅吉へと変わっていったのである。篤胤が記録したその問答は、例えば次のようなものであった。
《「問ふて云はく、人の魂の行方は、如何に成る物ぞと云ふことを、師に聞きたる事は無きか。」と篤胤が訊くと、寅吉はこう答える(現代文に訳しておく)。「人の魂は、善い魂も悪い魂も、凝り固まってしまえば、そのままの状態でいつまでも変わることはありません。なかでも悪念の凝り固まった魂は、その悪念が消えることはなく、悪魔の群れに入って、永く神の罰を受けることになります。一方、善念の固まった魂は、神の恵みを受けて、永遠に世を守る神になるのです。しかし、善念は崩れやすく、悪念は崩れにくいので、善念は生涯持ち続けなければ固まらず、悪念は少し心に思っただけで消えなくなってしまいます。だから、一分の悪念でもてば、九分の善念も水の泡となってしまうのです。》 (同書、p.176)
篤胤たちの「山人とはいかなる者か」との質問に対しては、「山人とは、まずは俗にいう天狗のこと」を指すと寅吉は答えた。その上で「山人とはこの世の人であって、事情があって山に入り、自然に山中のもので衣食をまかなえるようになった人で、30年ばかり山で生活すれば誰でもなれる」とも言っている。しかし師から「下山したときは、世間で言われている天狗と称して、山人などということは明かさないように」と忠告されたことも打ち明けた。これでは、山人(=天狗)とは、山伏のような修験者の仲間のようにも思われるが、しかし、寅吉少年の体験談には、すでに触れているように、彼らは自由に空中を飛び回っており、「一事につきて数百里を、数度空行往来する事もあり」といった話も出てくる。現世と幽界の壁をこえて生きているようで、理解は容易ではない。『仙境異聞』に300ページにわたって記録されているこのような寅吉と篤胤や学者たちとの問答は、300項目くらいもあって膨大である。ここではそれらを取り上げきれないので、天狗に関しては、このような情報と資料があるということだけで、この稿を終えておきたい。
シルバー・バーチに導かれて (2016.11.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.110 ―
1982年の夏、私は米政府のフルブライト上級研究員に選ばれてアメリカへ渡った。栄光に包まれていたはずのこの3度目の渡米は、しかし、それまでの2度のアメリカ生活の時のような夢と希望に彩られた想い出にはならなかった。全く予想もできなかったことだが、悲劇の結末で幕を閉じた。翌年の9月1日、アメリカから帰国の途上にあった妻と長男が大韓航空機事件に巻きこまれて亡くなったのである。私は、ノース・カロライナ州立大学での教職を中断して日本へ帰国した。それ以来、絶望と悲歎の淵に沈みながらも、藁をもつかむ思いで仏典に縋りつこうとした。意味がよくわからないままに、「仏説阿弥陀経」を毎日唱えたりしていた。
このお経では、西の方はるか彼方に、極楽という世界があって、そこでは阿弥陀仏が今も法を説き続けていると述べられている。その極楽というのは光り輝く壮麗な世界で、人は誰でも、阿弥陀仏の名号を唱えることによってその極楽に往生できる。そしてそのことは、東西南北上下の六法世界の数多くの諸仏によっても証明されているのだ、というようなことも書かれている。その当時の私は、霊的な真理については全く無知であった。死後の世界についても何もわかっていなかった。極楽というのは、本当にあるのか、ないのか。「人は誰でも、阿弥陀仏の名号を唱えることによって極楽に往生できる」というが、妻と長男の場合は極楽へ行けるのであろうか、と思い悩んでいた。
その頃読んでいた『歎異抄』の第9条に、親鸞の弟子の唯円が、「極楽がそんなに素晴らしいところなら、一日も早く極楽へ行きたいと思うはずなのに、そういう気持ちが起こらないのはなぜか」と疑問を呈するところがある。死を忌み嫌うのは世の常だから、これはもっともな質問であった。それに対して親鸞は、「本当は、極楽へ行くというのは天にも昇るような喜びなのだが、それをそう感じさせないのが煩悩のなせるわざである」と答えている。煩悩が邪魔をしているから、というのは理解しやすい言い方である。おそらく、それはそうであろう。親鸞はさらに、「念仏を唱えるたびに躍りあがるような喜びをおぼえ、はやく浄土へ行きたいと強く願っているというなら、むしろそのほうが、凡夫としての煩悩が欠けているのではないかと疑わしく思えるのだ」とも言った。つまり、凡夫が救われるという阿弥陀仏の本願からすれば、煩悩にまみれているからこそ極楽へ行けることになるのである。このような親鸞のことばに、当時の私は強くこころを惹きつけられていた。
一方、キリスト教では、「神を信じる者は死んでも永遠の生命を得る」という聖書の教えがある。ヨハネ書には「わたしはよみがえりであり、命である。わたしを信じる者はたとい死んでも生きる。また、生きていてわたしを信じる者は、いつまでも死なない。あなたはこれを信じるか」とある。(11:25-26) これは、兄の死を悲しんでいるベタニアのマルタに、イエスが言ったことばである。これに対してマルタは、「主よ、信じます」と答える。そしてマルタは、イエスの業によって、その兄ラザロが死から甦るのを目の前で見ることになる。死後4日も経っているマルタの兄ラザロの死体は、イエスが祈りのことばの後、「ラザロよ、出てきなさい」と大声で呼ばわると、「手足を布でまかれ、顔も顔おおいで包まれたまま」墓から出てきた。ラザロは死から甦ったのである。(11:39-44)
イエス自身も、生前から、死んだあと 3日後には甦ると弟子たちに伝えていた。そして、ゴルゴタの丘で十字架にかかった後、予言どおりに復活して、弟子たちの前に姿を現わした。しかし、一二弟子の一人のトマスは、たまたまイエスが姿を現した時には、その場に居なかった。ほかの弟子たちが、復活したイエスに会ったことを感激して伝えると、トマスは、「わたしは、その手に釘あとを見、わたしの指をその釘あとにさし入れ、またわたしの手をそのわきにさし入れてみなければ、決して信じない」と言った。復活したイエスは、しかし、また弟子たちの前に現れる。今度は、トマスもいた。イエスはトマスに言った。「あなたの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。手をのばしてわたしのわきにさし入れてみなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい」と。トマスは、もうことばもなかった。ただ畏れおののいて、「わが主よ、わが神よ」と言うのが精一杯であった。(ヨハネ20:19-29)
この奇跡を目撃して、イエスの処刑の時には一人残らず逃げ隠れしていた弱い弟子たちが、一斉に猛然と立ち上がり、鞭で打たれても石を投げられてもひるまず、身命を賭してイエスの教えを広げていくことになる。そしてこの、ガリラヤで発生したユダヤ教の一分派とでもいうべきキリスト教は、遠くローマにまで浸透して、紀元64年にはあの皇帝ネロの迫害を受けるまでになった。しかし、数々の迫害にもかかわらず、キリスト教は燎原の火のごとく広がり続けて、遂には紀元380年、当時のテオドシウス帝によりローマ帝国の国教になる。そのようなキリスト教の聖書の教えも私のこころには強く響いた。
この聖書は、イエスが2千年前に言ったことを、弟子たちが書き残したものである。2千5百年前の仏典に比べれば、現代文に訳された内容も読みやすく、わかりやすい。私はむさぼるように聖書も読んだ。しかし、それでも、聖書は2千年前の伝聞である。紀元325年のニカイア会議では、人から生まれたイエスが父なる神と同質ではありえないとするアリウス主義が異端とされてしまったりしている。その時のローマ皇帝、コンスタンチン大帝は、新約聖書の輪廻転生に関する記述を削除し、紀元553年にコンスタンチノーブルで開催された第二回宗教会議でも、輪廻転生は異端と宣言されたともいう。長い年月の間には、このように世情にあわせて聖書の内容に手が加えられ、翻訳の誤差などもあったりして、どの程度、イエスの真意が伝わっているかは疑問の点がないわけではない。結局、私は、仏典によっても聖書によっても、妻と長男の死後の行方については、釈然とした理解を得ることは、最後まで、できなかった。
事件の後遺症に苦しみながら、それでも私はその後数年の間、事件の真相究明運動に多くの時間とエネルギーを費やさねばならなかった。そのために、長年勤めていた大学も辞めて札幌から東京へ移った。東京では「真相究明の会」の代表理事の一人として究明運動に関わりながら、その間に、霊能者が数多くいるというS教団や、G教団などにも熱心に通ったりしていた。何年もの間、霊能者といわれる数十人の人たちの霊言を次から次へと聞いていたが、どの霊能者からも妻と長男の行方について納得できるような答えは、何一つ得ることはできなかった。しかし、霊的にまったく無知であった私も、そのような教団で、霊界や死後の生命などについていろいろと聞いているうちに、少しずつでも、霊的真理を受け入れられるこころの準備が整えられていったのかもしれない。
事件の真相を究明する会では、新聞、雑誌、単行本などに会員諸氏の論文が次々に発表されていた。私も『疑惑の航跡』(潮出版社、1985年)、「遺族はなぜアメリカを弾劾するか」(岩波書店「世界」1985年10月号)などを書いたほか、真相究明を訴える機関紙「APPEAL」の発行を一人で毎週続けた。1988年には、会員諸氏の研究成果をまとめて『大韓航空機事件の研究』を三一書房から刊行した。悲嘆から立ち上がれず、真相究明運動も続けなければならなかったことは私にとっては二重の苦しみであったが、避けては通れなかった。心身ともに疲れて、宗教教団による「救済」にも絶望しかけていたころ、1991年の春、私はロンドン大学客員教授としてイギリスへ向かった。
ロンドンで暮らすようになって、私はロンドン大学の行き帰りに、何度も大英心霊協会を訪れるようになった。売店でシルバー・バーチの本を買い集めて真剣に読むようになったのもその頃からである。大英心霊協会には霊能者が30人ほどいて、申し込みさえすればどの霊能者ともすぐに会えたが、私は半年以上も、その機会を先延ばしにしていた。ここは、私にとっては残された最後の「救済の場」であった。協会のミディアム達はみんなそれぞれに優れた霊能者であることは聞いていたが、もしここでも、妻と長男の行方について納得できる霊言を聞くことが出来なければ、私はもう一生、絶望から抜け出すことはできない。そのような切羽詰まった思いのなかで、一対一でミディアムと接する前に、私は霊界通信について学び、大勢が出席している公開デモンストレーションにはできるだけ参加するようにして、ミディアムの霊言に慣れていこうとしていた。
一年近く経って、そろそろ帰国の準備もしなければならなくなった頃、私は大英心霊協会の控室「リンカーンの間」でアン・ターナーと会った。その時は、アン・ターナーがミディアムであることも知らず、私はまったく偶然に会っただけだと思っていたが、後にそれは、決して偶然ではなかったことを知るようになる。霊界からの導きであった。その後の1992年2月11日は私にとって忘れられない運命の日になった。私は大英心霊協会で再びアン・ターナーに会って、彼女の卓越した霊能力により、遂に妻と長男との奇跡的な「再会」を果たしたのである。
あり得ないようなことが現実となって、私は茫然となった。目の前に立っている妻と長男は感動の面持ちだとアン・ターナーはいう。やっと意思が通じるようになって、彼らも嬉しかったことであろう。私も感動していた。彼女は、独り言を言うように、淡々と妻と長男のことばを私に伝えた。そのことばには、疑うにも疑いようのない真実の重みがあった。私はそれからも何度も彼女に会い、そのほかの何人かのミディアムとも会っているが、その度に、霊界で元気に生き続けている妻と長男の姿が、疑問の余地なく鮮明に伝えられた。それらのことについては『天国からの手紙』(学研パブリッシング、2011年)などに多く書いてきたので、ここでは繰り返さない。長年の悲しみと苦しみから初めて解放されて、私はここで生き返った。
シルバー・バーチの本の重大性も私は改めて認識するようになった。私は自分でも、その一部を和訳してみたりしている。なぜ長い間、こんな重大なことに気が付かなかったのだろうという思いがあったが、シルバー・バーチのことばの一つ一つがこころに深く沈潜していった。まず、人は死んだらどうなるのか。それまでにはわからなかった最大の疑問に、シルバー・バーチは極めて明快にこう答えている。「人間は墓場を乗りこえて生き続けます。人間も本来は霊だからです。火葬の炎さえその霊を滅ぼすことはできません。物質の世界はもとより、いえ、霊の世界の何をもってしても、内部に宿る神性、この世に生をうけることによって賦与された生命の炎を消すことはできません。」(『霊訓 (12)』p.50)また、シルバー・バーチは、つぎのようにも述べている。
「人間はあまりに永いあいだ死を生の終りと考えて、泣くこと、悲しむこと、悼むこと、嘆くことで迎えてきました。私どもはぜひとも無知――死を生の挫折、愛の終局、情愛で結ばれていた者との別れと見なす無知を取り除きたいのです。そして死とは第二の誕生であること、生の自然な過程の一つであること、人類の進化における不可欠の自然現象として神が用意したものであることを理解していただきたいのです。死ぬということは生命を失うことではなく別の生命を得ることなのです。肉体の束縛から解放されて、痛みも不自由も制約もない自由な身となって地上での善行の報いを受け、叶えられなかった望みが叶えられるより豊かな世界へ赴いた人のことを悲しむのは間違いです。」(『霊訓(3)』p.44)
シルバー・バーチはさらに、「あなた方と愛しあっている霊界の人たちは、あなた方を決して見失うことはありません。彼らは、自分たちの愛が及ぶ範囲内にとどまって、それより遠いところへ行ってしまうことはないのです」とも教えてくれているが、これは実に心強い証言である。「時には、彼らは他の誰よりもあなた方に近くいます。また時には、彼らはあなた方に働きかけようとします。あなた方から離れてしまうことはありません」ということばもある。これは、私が大英心霊協会での妻と長男との再会で、身に沁みて実感したことでもあった。
私はイギリスからの帰国後も、長年にわたって、妻と長男との「対話」を続けるようになった。その記録は数十本のテープになって今も残っている。シルバー・バーチの教えの一つ一つが、妻と長男からの霊界通信に裏付けされているようで、私にとって「死後の生」は、ますます揺るぎのない確信になっていった。妻と長男との対話を続けているうちに、私自身の数々の過去世や私が霊界へ還ったときの家族との再会、住むべき階層などについても納得して知ることができるようになった。なぜ今生の私は日本に生まれて、あのような事件に巻きこまれたのか、私と家族の使命とは何か、というようなことについても、私なりに理解できるようになった。私はそのような体験と理解を基に、度々講演会で、生と死の問題を話すようになる。2003年3月からは、ホームページ「ともしび」を立ち上げて、シルバー・バーチの教えを紹介していくようにもなった。
シルバー・バーチは、ほぼ3千年前に霊の世界へ還って行った人である。「シルバー・バーチ」は仮の名で、何度聞かれても本名は明かさなかった。「私が王であろうと乞食であろうと、そんなことはどうでもいいのです。私の申し上げることによって判断していただきたい」とのみ答えていた。3千年前に「死んだ」シルバー・バーチは、2千年前のイエスキリストよりも千年古く、2千5百年前の仏陀よりも5百年古い。そのシルバー・バーチは霊界で「少しばかり勉強して」、3千年の間に物質界からは遠く離れた高位霊となった。そして、生きることに疲れ果てているこの世の人々の魂を鼓舞し、進むべき方向を示唆するという人類救済の役目を引き受けて、わざわざこの地上へ降りてきたのである。そのお蔭で私たちはいま、シルバー・バーチの膨大な真理の教えを心ゆくまで学ぶことが出来る。
シルバー・バーチは、この世へ戻る前に自分で英語を独学し、その英語で1920年代から半世紀以上にわたってロンドンを中心に深遠な霊的真理を教え続けてきた。ミディアムとしてその仲介役を務めたのが、文筆家のモーリス・バーバネルである。シルバー・バーチは、バーバネルが1902年に生まれる前から調べ上げて彼を選び、その受胎の日を待っていたという。バーバネル自身は全く予期してはいなかったが、成人してからはシルバー・バーチのことばを伝える忠実な「声帯」の役目を果たした。そしてそれは、バーバネルが亡くなる1981年7月まで連綿と続けられて、シルバー・バーチの霊訓は人類の膨大な知的遺産として世界中に広がっているのである。
シルバー・バーチの霊訓が仏典や聖書と決定的に違うのは、その貴重な霊訓が、3千年前のシルバー・バーチによって、彼自身が学んだ現代英語で語り続けられたことである。私たちはいま、この21世紀に生きながら、その3千年前のシルバー・バーチのことばの一語一句を、バーバネル氏の声帯を通じて、自分の耳で聞くことができる。「語りかける霊がいかなる高級霊であっても、いかに偉大な霊であっても、その語る内容に反発を感じ理性が納得しないときは、かまわず拒絶なさるがよろしい」とシルバー・バーチはくり返し言っている。その彼が、一旦口を開くと、「何ともいえない、堂々として威厳に満ちた、近づきがたい雰囲気が漂い始めて」、交霊会の出席者たちは、思わず感涙にむせぶこともあったという。私も何度か講演会で、そのシルバー・バーチのことばを録音で聴衆に聞いてもらったりしたが、これはまさしく、現代の奇跡というほかはない。
日本では、シルバー・バーチの教えは、近藤千雄氏によって『シルバーバーチの霊訓』12巻となって、潮文社から出版されている。氏とは私がロンドンにいる頃から文通を始めていたが、氏がまだ和訳していないTeachings of Silver Birch, edited by A.W.Austen, については、私が和訳して全文を英和対訳のかたちで私のホームページの「霊訓原文」に公開している。シルバー・バーチの使っている英語をそのまま示しておくことも大切だと思ったからである。
この「霊訓原文」や近藤氏の訳文を含めて、シルバー・バーチの教えの主要な個所は細大漏らさず、「学びの栞」で項目別に索引できるようにしたり、「叡智の言葉」として100の短文にまとめたりもした。それらも量的にはかなりのものになっているが、何よりもまず、私が伝えなければならないのは、「人は死なない」という単純明快な真理である。本来の私たちは霊を伴った肉体ではなく、肉体を伴った霊である。霊の本性からいって、「私たちは死にたくても死ぬことはできない」と言ってもよい。私の妻と長男がいまも立派に生き続けているように、私も、近い将来、死んでも生き続けることになるだろう。この霊的真理を、「あなたも永遠の生命を生き続ける」というメッセージにして、私は、耳を傾けてくれる人には一人でも多く、伝えていきたいと思っている。
|