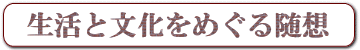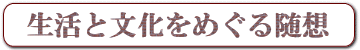|
私たちはなぜこの世に生まれてきたか (2017.01.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.111 ―
私たちは輪廻転生を繰り返しながら、霊性の向上を目指して永遠の旅を続けている。この世に生まれて、様々な人生の経験を経て死に、また生まれては、新しい経験を積み重ねて学びを深めていく。このように私たちが自分の意思によって生まれ変わりを繰り返していく場合、当然、新しく生まれ変わる場合の生活環境が、それまでに重ねてきた生活体験を基盤にして、少しでもプラスになるようなものになるのを選ぶはずである。プラスになるというのは、もちろん、少しでも悩みが少なく、楽な生活ということではない。学びのためには、厳しい過酷な環境を率先して選ぶ場合もある。このことをまず確認しておきたい。この誕生に際しての生活環境の選択をシルバー・バーチはつぎのように言っている。
《地上に生を享ける時、地上で何を為すべきかは魂自身はちゃんと自覚しております。何も知らずに誕生してくるのではありません。自分にとって必要な向上進化を促進するにはこういう環境でこういう身体に宿るのが最も効果的であると判断して、魂自らが選ぶのです。ただ、実際に肉体に宿ってしまうと、その肉体の鈍重さのために誕生前の自覚が魂の奥に潜んだまま、通常意識に上がって来ないだけの話です。》(『霊訓1』1988, p.38)
この認識は極めて重要と思われるので、もうひとつシルバー・バーチのことばを引用しておきたい。シルバー・バーチはこうも言っている。
《地上へ誕生してくる時、魂そのものは地上でどのような人生を辿るかをあらかじめ承知しております。潜在的大我の発達にとって必要な資質を身につけるうえでそのコースがいちばん効果的であることを得心して、その大我の自由意志によって選択するのです。その意味であなた方は自分がどんな人生を生きるかを承知のうえで生まれて来ているのです。その人生を生き抜き困難を克服することが内在する資質を開発し、真の自我――より大きな自分に、新たな神性を付加していくのです。》
このように、「自分がどんな人生を生きるかを承知のうえで生まれて来ている」のであれば、この世で自分の置かれた境遇を嘆いたり、他人の生活をうらやましがったりする必要はないわけである。もしそのようなことがあれば、折角自分が自分の霊性向上のために自由意思により選んできたことを、「肉体の鈍重さ」のゆえに、誕生前の自覚を意識の奥に閉じ込めてしまっていることを思い起こすべきであるかもしれない。シルバー・バーチは、この後、さらに続けて、こう付け加えた。
《その意味では "お気の毒に・・・・" などと同情する必要もなく、地上の不公平や不正に対して憤慨することもないわけです。こちらの世界は、この不公平や不正がきちんと償われる世界です。あなた方の世界は準備をする世界です。私が
"魂は知っている" と言う時、それは細かい出来ごとの一つひとつまで知り尽くしているという意味ではありません。どういうコースを辿るかを理解しているということです。その道程における体験を通して自我が目覚め悟りを開くということは、時間的要素と各種のエネルギーの相互作用の絡まった問題です。例えば予期していた悟りの段階まで到達しないことがあります。するとその埋め合わせに再び地上へ戻って来ることになります。それを何度も繰り返すことがあります。そうしているうちにようやく必要な資質を身につけて大我の一部として融合していきます。》(同書、pp.109-110)
私たちがこのように、自分の生活環境を選んで生まれてくるというのは、私たちがこの世に生きる意味を考えるうえで極めて重要である。それを認識するかしないかで、たとえば、自分の幸福感なども、大きく変わってくることがあるかもしれない。世の中には、他人の幸せを羨み、自分の不幸を嘆いている人が決して少なくはないが、本当は、シルバー・バーチがいうように、「"お気の毒に・・・・"
と同情する必要もなく、地上の不公平や不正に対して憤慨することもないわけ」である。私たちは、生まれる前にあらかじめ自分が設定していたコースを、いまこの現世で歩んでいるに過ぎない。自分で決めて選んだことを自分で嘆いたりするのは、筋の通らない話である。この生まれ変わりの真実を繰り返し説いてきた一人がラムサであった。この高位霊は、私たちが自分で環境を選んでこの地上に戻ってきたことを、こう述べている。
《あなたがここにいるのは、それがどんなところであろうと、自分がいたいからそこにいるのだ、ということを学ぶためです。叡智を学び、生の場でそれを実践するために、あなたはここにいます。この人生で(また、これから自分が望むだけ繰り返す幾度の人生でも)、あなたがここにいるのは、この幻を生き、魂が叡智という命を満たすのに必要なすべてを体験するためです。そして、この次元での体験から豊かな感情を得たとき、あなたはもはやここに戻る必要もないし、そう望むこともなくなります。そして、自分がいつここでの体験を全うしたのかを判断できるのはあなただけです。ほかに誰もいません。》(『ラムサ―真・聖なる預言』角川春樹事務所、1996、pp. 197-198)
このような私たちの生まれ変わりの真実は、シルバー・バーチやラムサのような高位霊だけではなく、現代に生きる優れた霊能者たちによっても、少なからず伝えられている。ジュディー・ラドンもその一人である。彼女は、「人は自分の人生の境遇を選択する。もしこちらの領域に来てみたなら、みなさんの世界に生まれ出る機会を切に待ち望む、数知れない仲間たちを目のあたりにすることだろう。彼らは地上の喜びと豊かな環境を懐かしがり、切望している。また多くの人にとって魂の領域自体も学ぶべきことは多いのだが、『地球学校』という意義深い領域にとってかわることはできない」と述べて、こう続けている。
《この話を聞いて衝撃を受ける人も少なからずいるにちがいない。みなさんは、「本当にそうなのだろうか」と訝しむかもしれない。これが、多くの社会の文化的枠組みの中で受け入れられている生についての考え方に反するものだからである。「赤ん坊はたまたま生まれてきただけで、みずから選択して生まれてきたわけではなかろう」。だが、これはまったくの間違いなのだ。赤ん坊はすっかり成熟した、完全に進化した魂であり、魂の領域では成人の姿をして見える。もし彼らの魂がこの世でさらに勉強するように駆り立てれば、彼らは自分たちが入っていくのにふさわしい環境を検討し、探す。彼らは母親を探し―
彼らは、すでに「妊娠している」女性を注意深く観察することがよくある― そして一種の宇宙の順番待ちのリストに登録する。家柄を慎重に調べ、適切な縁組を探すのはわたしたちの領域にいる多くの者たちの仕事だ。》(ジュディー・ラドン『輪廻を超えて』人文書院、1996、pp.18-19)
この生まれ変わりの真実を退行催眠によって証明してきた精神科医もいる。アメリカのマイアミ大学医学部精神科の教授を務めていたブライアン・ワイス博士である。博士は、アメリカでベストセラーになった『精神療法』(PHP研究所、2001年)のなかで、「偶然でもなく偶然の一致でもなく、私達は私達の家族の一員として生まれます。私達は母親が妊娠する前に、自分の環境を選び、人生の計画を立てているのです。計画を立てる時には、愛に満ちた霊的存在に助けられます。そして彼らは私達が肉体に宿り、人生計画がひもとかれてゆく間、ずっと私達を導き守ってくれます。運命とは、私達がすでに選択した人生のドラマのもう一つの名前なのです」と書いている。そして、こう続けた。
《私達は生まれる前の計画段階で、これからの人生に起こる主要な出来事や、運命の転換点を実際に見ています。そしてその証拠は、沢山存在しています。私を含めてセラピスト達が集めた、催眠状態ないし瞑想中に、または自然に、生まれる前の記憶を思い出した沢山の患者の臨床記録がそれです。私達が出会う重要な人々、ソウルメイトや魂の友人との再会、こうした出来事が起こる場所に至るまで、すべて計画されているのです。・・・・・・これはすべての人々にあてはまります。しばしば、養子や養女になった人々は、自分の人生計画は歪められてしまったのではないか、と考えます。しかし、答えは「ノー」です。養父母もまた、産みの親と同じように生まれて来る前に選ばれているのです。すべてのことには理由があり、運命の道には何一つ、偶然はありません。》(同書、pp.70-71)
世の中には、自らの境遇に不満を持ったり、人間関係に悩んだり、事件や事故に巻き込まれて悲しんだりする人々で満ち溢れているが、それらの「不幸」も、すべて、自分が生まれる前に選んだ人生コースの一部になっていることを知らなければならない。実はそれらが、自分がこの世で学ぶべき教材になっているからである。日々の悩みや苦しみ、成功や挫折等のすべてが乗り越えていくために自らが課した教材なのである。そして、ワイス博士も言っているように、「すべてのことには理由があり、運命の道には何一つ偶然はない」とすると、自分に起こっていることはすべて必要であるから起こっていることになる。必要なことだから、起こっていることは何であれ、本来、自分にとっては「良いこと」なのである。
私は、かつて、事件で妻と子を亡くして悲嘆の底に沈んでいたことがあった。立ち直るのに何年もかかったが、立ち直るきっかけを与えてくれたのも、生と死についての霊的真理であった。世の中の常識では、天真爛漫で清らかな性情の人が事故に遇うのは不条理であり、「あんないい子が」と思われている子供が早死にするのは不幸の極みである。しかし、それらも永遠の生命の霊的真理からみれば、決して不条理ではなく不幸でもない。私たちは、それが霊的成長にとって必要であれば、有徳の人でも遭うべくして事故にも遭い、幼児や若年者であっても、死ぬべき時には死ぬ。私は、長年指導を仰いできた霊能者のA師から、妻と子を亡くしたことを、「喜んでください」と言われたこともあった。
私たちは、富豪の家に生まれようと、極貧の家に生まれようと、それは永遠の生命のなかの一瞬でしかないこの世の仮の姿である。王侯貴族に生まれたものは、来世では、貧しい下男下女の生涯を体験しようとするかもしれない。非正規労働者として生活に苦労が絶えなかった人は、つぎの世では大企業の幹部としての体験を積む生涯を選ぶことになるかもしれない。それぞれが、自分の立場で、学びのために必要と思われるこの世での課題を自ら選択しながら、転生を繰り返していく。その課題は、易しいものから高度のものまで様々であろう。しかし、乗り越えられない困難はなく、克服できない悲しみもない。自分が乗り越えられない困難や悲しみの課題を、自らに課すことはないからである。それにもかかわらず、この世の生活の中で、挫折する人があれば、次の転生でまた思いを新たにしてチャレンジしていくことになるのであろう。
私は、むかしの長年悲しみ苦しんできた経験から、霊的真理を知らないことの「恐ろしさ」を身に染みて感じてきた。「知らない」というのは本当に恐ろしいことで、生きている者も死んだと思い込み、人並みの、あるいは人並み以上の恵まれた環境にあっても、不幸のどん底にあると錯覚して嘆き悲しむ。溺れる者は藁をもつかむ思いで、必死になって助けを求めたりするが、誰からも助けてもらえることはない。「守護神」は実は自分の中にいること、つまり、ほかならぬ自分が自分を救う守護神であることにはなかなか気が付かないのである。悲しみや苦しみを克服していくためには、私たちは、やはり、なぜ私たちがこの世に生まれてきたのかという原点に立ち返って、考えていく必要があるように思われる。
ここでもう一度確認しておきたいが、私たちはこの世の生活環境を自分で選んで生まれてきた。金持ちの家に生まれるのも学びのためであり、貧困家庭に生まれて生活苦に喘ぐのも、その体験が自分にとって必要だからである。成功で有頂天になることもあり、挫折して前途の希望をなくしてしまうこともあるであろう。みんな、私たちが一人一人の霊的成長のために描いてきた人生コースの一こまであり、それを現実にこの世で体験し、学び、乗り越えていくことによって、一歩一歩、神の光に近づいていく。だから、強い魂はこの世では、むしろ、波乱万丈の苦難の道を選んで生まれてくることもあるのかもしれない。私たちは、そのかつての選択を、この世への誕生の瞬間に、魂の奥深くに閉じ込めてしまっているのである。
このような、私たちがこの世に生まれてきた時の原点に立ち返って見れば、この世で生きていく上での心がまえがどうあるべきかについても、自ずから明らかになってくるように思われる。それが、本当の意味で、私たちが幸せに生きていく道を指し示してくれるであろう。そしてその道とは、この世に生まれた以上、他人を押しのけてでも大いに蓄財して、贅沢な苦労のない人生を送りたいと望むようなことでは決してないに違いない。前にも触れた霊能者のA師は、この世に生まれて、何の苦労もなく贅沢に暮らして一生を終わる人があるとすれば、それは「神に見捨てられた人」かもしれない、と笑いながら言ったことがあった。
この世で幸せに生きていく道の一つは、おそらく、物欲・金銭欲から離れて「足るを知る」ことであろうと思われる。私たちは、これまでひたすらに物質的な幸福感のみを追い求めてきた。特に21世紀に入ってからは、この追求が頂点に達したと言ってもいいかもしれない。産業や経済の発展は目覚ましく、インターネットなど科学技術の進歩は社会を一変させ、生活はますます便利で快適になってきた。私たちの周りには贅沢なものであふれ、食べ物に不自由することもなく、様々な娯楽が氾濫して人々も浮かれているように見える。このような風潮のなかで、いまでは、幸せとは金銭をたくさん持つこと、モノを好きなだけ手に入れること、と思われるようになってしまった感がある。このようにして欲望に駆り立てられた社会が精神的に健全であるはずはない。果てしなき人間の物質的欲望は人間そのものを腐敗させていく。モノはまわりにあふれているのに、こころは満たされず、人々の幸福感も、逆に、少しずつ失われてきたのではないか。
特にいまの世界では、人々の金銭欲が野放図に肥大していった結果、貧富の格差がかつてなかったほど広がってきた。国際NGO「オックスファム」によれば、世界人口のうち、2016年に最も富裕な62人の総資産は、下位36億人の総資産に匹敵するという。下位36億人の平均資産が1人でおよそ5万円であるのに対して、最も富裕な62人の平均資産はおよそ3兆円といわれているから、貧富の格差もここまでくるとほとんど犯罪的である。イエス・キリストは2千年前に、「金持ちが神の国に入るのは、駱駝が針の穴を通るよりむつかしい」(マタイ:19-24)と言ったが、現代社会では、野放しにされた金銭欲へのあくなき追及が、社会に様々な歪みをもたらすようになってきた。金持ちがカネがあるゆえに幸せであるとは決して言えないが、カネのない人は、カネがないから不幸せであると思うような傾向も、ますます強くなってきているように思える。
経済的には比較的恵まれている日本の中では、貧富の差はともかく、私たちは、当たり前のように朝、昼、夜と三度の食事をとっている。考えてみれば、いや考えてみるまでもなく、これも本当は、当たり前ではない。世界では、いまでも、およそ7億9,500万人(9人に1人)が、健康で活動的な生活を送るために必要
かつ十分な食糧を得られていないという。かつて、太平洋戦争敗戦後の日本では、食糧不足で1千万人が餓死するのではないかと言われたこともあった。私自身も大阪で餓死寸前の状態になった体験があるので、食べ物の有難さはいまも身に染みている。いまはその日本でも飽食の時代で、まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」は、日本だけでも年間約630万トンにもなっているらしい。この量は、飢餓に苦しむ上記約8億人への、世界全体の食料援助量の約2倍にもなり、しかもその捨てられている食料の半分は家庭からのものであるという。
住む場所についても、私たちは、大なり小なり、雨露をしのげる家屋に住んでいるが、これも本当は当たり前ではないであろう。国連人権委員会の報告では、世界には1億人のホームレスがいるという。いまでも、世界の約60人に1人がホームレスであるというのは、驚くべき事実といわなければならない。さらに、住む家があり、3度の食事がとれている人でも、歩けない人もおれば、目が見えない人、耳が聞こえない人も無数にいる。病気で寝たきりの人々も決して少なくはない。私たちは何よりもまず、なんとか健康に、手足を動かし、呼吸をしながら生きているだけでも有り難いと思うべきではないであろうか。
金銭やモノが多く手に入れば幸せだと思っている人が大勢いても、本来が霊的な存在である私たちは、物的な豊かさだけでは幸せにはなれないのである。本当の幸せは、むしろ金銭やモノから離れたところにある。この認識が、果てしなく強欲な富裕層のみならず、貧困層をも含めた一般庶民に至るまで広がっていくのでなければ、この世界での未来に向けての展望は開けない。経済発展至上主義に対しては、もうとっくに背を向けなければならない時機にきているのではないか。人類の繁栄をもたらしてきたといわれる資本主義が人々の欲望に対するコントロール機能を失い、国境を越えて暴威をふるうグローバル企業の増大などが、庶民の幸福感のみならず、世界の平和と安寧をも脅かし始めている現在、物から心への転換こそ、今は何よりも強く求められているように思われてならない。
その発想の転換のためには、私たちは、自分が持っていないものをさらに欲しがったり、手に入らないのを嘆いたりするよりは、すでに持っているものを数えてみることから始めるべきであるかもしれない。それらが如何に多いかに気がつけば、感謝の気持ちも湧いてくるはずである。本当は、つぎつぎに金銭やモノを欲しがるよりは、持っているものを他人に与えることを、先ず考えるべきなのであろう。他人に与えられるのは、もちろん、金銭やモノだけではない。優しさや思いやりのこころなど、無限の愛を分かち合うことが誰にでも可能である。そして、そのような愛の実践のなかでこそ、しみじみとした幸せを味わうこともできるのであろう。そして、おそらくそれが、私たちの一人一人が、生まれる前に、この人生コースで描いてきた生き方ではなかったであろうか。
私たちはなぜ生まれ変わるのか (2017.03.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.112 ―
前稿「私たちはなぜこの世に生まれてきたか」でも書いているが、私たちはこの世に生まれ、やがて死に、そしてまた、生まれ変わってくる。生命は永遠だから、死によって生命が途絶えてしまうことはないのである。この世に生まれる前にも私たちは誕生を繰り返してきたし、死をも繰り返してきた。これからも、その死と誕生を繰り返していくだろう。一体、私たちはなぜ、死と誕生を繰り返すのであろうか。本稿では、その「生まれ変わり」を中心に考えてみたい。
「生まれ変わり」でまず思い出されるのは、古代霊ラムサのことばである。ラムサは、「あなたは誰なのか? なぜいまここにいるのか? あなたの生きている目的と運命とはいったい何なのか?
あなたは自分が単なる偶然の産物であり、ほんの短い時間だけこの世に生きて、つぎの瞬間には消滅するためだけのために生まれてきたと思うのだろうか?」と問いかける。そしてつぎのように言っている。
《あなたはこの地上界に何千回と生きているのだ。まるで気まぐれな風のように、戻っては去っていった。あらゆる顔や肌の色、主義主張や宗教を体験している。戦争を仕掛け、仕掛けられ、王と召使いの両方を同じように生きてきた。船乗りや船長にもなった。征服者や被征服者にもなった。自分の歴史の理解の中にあるすべてのものにあなたはなった経験がある。それはなぜか?
感じるため、智慧を得るため、そして、あなた自身というもっとも偉大な神秘を解き明かすためだ。》(ラムサ『新・聖なる預言』川瀬勝訳、角川春樹事務所、1996、p.71)
このあと、ラムサは、「あなたは、膨大な時間の中で繰り返し繰り返し生きることを通じて、いまの自分であるすべてになってきたのだ。そしてその生の一つひとつから智慧を得て、あなたという独自の美しい存在をつくり出してきたのだ。永遠という時間のほんの一瞬の間のためだけに創造されるにしては、あなたはあまりにも美しく、あまりにもかけがえのない存在である」と続けている。(念のためにこの部分の原文をあげておくと、こうである。You
are much too priceless, you are much too beautiful to have been created
for only a moment’s siege upon the eternalness of time.)
ラムサはこのように、私たちは、一人ひとりがみんな「あまりにも美しく、あまりにもかけがえのない存在」であるというのだが、それをどれだけの人が自覚しているであろうか。私たちは、何も知らずにこの世に誕生してくるのではない。誕生の度に、さらなる霊性向上のためにはどのような環境でどのような身体に宿るのが最も効果的であるかを自ら判断して、この世に生まれてきた。ただ、実際に肉体に宿ってしまうと、その肉体の鈍重さのために誕生前の自覚が魂の奥に潜んだまま、通常意識に上がって来ないだけのことである。このこともシルバー・バーチの教えとして、前稿でも触れてきた。
しかし、ラムサからこのように、私たちは「この地上界に何千回と生きているのだ」と言われると、やはり考え込まされてしまう。私たちの魂の奥には、この何千回の生の記録が閉じ込められているのだろうか。人類の歴史のうえでも、私たち現代人と同じグループの新人類が登場したのが20万年前くらいといわれているが、ラムサはどれくらいの視野でそのなかの人間の輪廻転生を捉えているのであろうか。ラムサはこうも言っている。「あなたは何度も何度も生きる。あなたの種は永遠不滅の存在なのだ。あなたがどんなに疑念を持とうと、自分の世界を限定しようと、どれほど心配し、絶望しようとも、あなたがけっして消せないものがある。それが、生命というものだ」。つまり、生命が消せないものである以上、生まれ変わりが続き、それが「何千回」にもなるのであろうか。
ラムサ自身は、この地上界では一度しか生きることはなかった。ラムサのことばによれば、3万5千年前にアトランティア南部に位置していた最大の港湾都市オナイに暮らしていたという。彼は地上初めての征服者になり、当時の世界の4分の3を征服した。その後、自分自身であらゆるものの内にある神について深く理解し、初めてこの地上界から高次元に昇華したらしい。だから、ラムサはこの世での人生を一度体験しただけで生まれ変わっていない。そして、おそらくそれが一番理想的なあるべき姿なのであろう。人間は「完全な」存在になれば生まれ変わる必要はないからである。いわば、不完全だから完全を目指して生まれ変わる。その生まれ変わりの回数が、霊的覚醒の度合いによりゼロ回から何千回ということになるのである。その生まれ変わりの理由についても、ラムサはこう言っている。
《あなたは自分がなぜいまの自分なのかわかりますか? それはほかの役割はもうほとんど体験してきていて、今回はいまの自分を体験しているからです。なぜ飢えた子どもではなく、いまのような裕福な人間に生まれてきたのでしょうか。それはあなたが裕福な人間になりたがっていた、飢えた子どもだったことがあるからです。だからいまはそうなったのです。なぜあなたは家族を養うためにパンを焼くパン職人ではないのでしょうか。それはあなたがパンを焼いて家族を養っていたパン職人だったことがあるからです。そして今度は、パンを彼から買うほうの存在になっているのです。》(ラムサ、同書、pp.236-237)
要するに、自分の霊的進化の学びのためには、生まれ変わりを自ら選んで、富豪にも貧者にも、大会社の社長にも日雇い人夫にも、愛する者にも愛される者にも、権力者にも奴隷にもなっていくということである。このような生まれ変わりの事実は、最近数十年年来、科学の分野でも実証され始めるようになってきた。欧米の大学医学部で、「退行催眠」という精神医学の治療法が発達してきたからである。なかでもよく知られるようになったのが、アメリカのマイアミ大学医学部精神科教授の経歴をもつブライアン・ワイス博士である。博士は、自分の患者のキャサリンが、退行催眠によって過去生を明らかにしていく様子をつぎのように記録している。(ブライアン・ワイス『前世療法』、山川紘矢他訳、PHP研究所、1996、pp.232-233)
「あなたは今まで何回生まれ変わりましたか? いつも地球に生まれていますか? それとも他の場所にも生まれたのですか?」
「地球上だけではありません」と彼女は答えた。
「それはどこですか? あなたはどこへ行くのですか?」
「私はここでしなければならないことをまだすませていません。私は人生のすべてを体験しないうちは、他の場所へ進むことはできません。私はまだ終わっていません。何回も人生をくり返さなければなりません。すべての約束を果たし、すべてのカルマを返すためです」
「でもあなたは進歩しているでしょ」と私の意見を述べた。
「人はみんな進歩するものです」
「あなたは地球上に何回うまれましたか?」
「八十六回です」
「八十六回?」
「そのとおりです」
「そのすべてを覚えていますか?」
「思い出す必要があれば思い出します」
こういう調子で、ワイス博士と退行催眠で超意識の状態にあるキャサリンとの間の会話は長々と続けられている。キャサリンは、思い出した過去生での人物になって叫んだり、泣いたり、興奮して表情を変えたりするが、生まれ変わりの回数などは、彼女が「マスター」と呼んでいる守護霊に教えられているようである。時には、守護霊が彼女の代わりに答えたりもしている。これとは別に、キャサリンは、過去生のリーディングで有名な霊能占星術師・アイリス・サルツマンのところへも訪れたことがあった。ワイス博士のところで退行催眠を受けていたことは触れず、彼女はアイリス・サルツマンによっても生まれ変わりを再確認してみたかったようである。その結果もワイス博士は、つぎのように記録している。
――アイリスは手を自分ののどにもってゆき、キャサリンが前世で首をしめられたことと、またのどを切られたこともあると言った。のどを切られたのは、戦争の時で、アイリスは何世紀も前に村が炎に包まれ、破壊されている状況が見えると言った。そしてその時、キャサリンは若い男性だったと言った。
――キャサリンはかつて海軍のユニフォームを着た若い男性であった。その時、短い黒いズボンと奇妙なバックルのついた靴をはいていた。突然、アイリスは自分の左手をつかむと、そこに鋭い何かが刺さり、手に大きな傷あとを残すようなけがをしたのだと説明した。彼女は左手にズキズキとした傷みを感じるとも言った。大きな海戦があった。場所はイギリス海岸だった。さらにアイリスは航海の人生について描写した。
――パリでの短い一生があった。その時、キャサリンはまたしても少年で、貧困のうちに若くして死んだ。
――ある時は、アメリカのフロリダの南西部でアメリカインディアンの女だったこともあった。この転生では、彼女は病気をなおすヒーラーであり、はだしで歩きまわっていた。
――他の転生では、キャサリンはスペイン人で、その時は、売春婦をしていた。そして、名前はLで始まっていた。また、ずっと年上の男性と同棲していた。
――またある時は、非常に裕福で、多くの称号をもつ貴族の私生児だったこともあった。大きな屋敷の中にあるさかずきに家紋がついているのが、アイリスには見えた。その時、キャサリンはとても色が白く、先の細い長い指先をもっていた。ハープを演奏していた。結婚は親が準備したものであった。キャサリンは動物、特に馬が好きで、馬をまわりの人達よりも大切にしていた。
――モロッコの少年だった時も短い一生で若くして病気で死んでいた。ある時はハイチに生まれていて、その土地の言葉をしゃべり、魔術師の一味だった。
――大昔、エジプト人であった時は、彼女は埋葬に関わる仕事をしていた。その時、彼女は女性で頭髪を編んでいた。
――また、彼女はフランスとイタリアに何回も生まれていた。ある時はフローレンスに住み、宗教に深く関わっていた。後にスイスに移り住み、尼僧院に入った。その転生では二人の息子があった。彼女は金と金の彫刻が好きで、いつも金の十字架を身につけていた。フランスでは、冷たい牢屋の中に閉じ込められていた。
――また、ある時は赤いユニフォームを着た男性で、馬や兵隊と一緒だった。ユニフォームは赤と金色で、多分それはロシアだろうということだった。またある時は、古代エジプトにおいて、ヌビア人の奴隷だったこともあった。その時は、捕えられて牢獄に入れられた。日本の男性に生まれた時は学者で、教育に携わっていた。学校関係の仕事をして、非常に長生きをした。
――もっと近い過去生では、ドイツの兵士だった。その時は戦闘において殺されている・・・・・・。
ワイス博士は、霊能者のアイリスが、キャサリンの過去生をこのように次々と明らかにしたことについて、「私はアイリスが過去生のことをあまり詳しく描写していたので感心してしまった。キャサリンが催眠時に思い出した過去生との符合は驚くほどだった」と述べている。キャサリンが海戦で手を負傷したことや、その時着ていたものや靴のこと。スペインの夜の女であったルイザの人生、エジプトの埋葬に関わったアロンダの人生、若いヨハン、その時彼女はスチュアートの前世である人物にのどをかき切られて殺されている。それにドイツのパイロット、エリックの暗い人生等々、これらすべてのことは、キャサリンが催眠時に思い出した過去生と符合していたのである。(ブライアン・ワイス、同書、pp.246-249) そして博士は、「もちろん、このような体験が科学的に有効な実験だと言うつもりはない。条件を一定にすることは不可能だからだ。しかし、これは実際に起こったことであり、これを書き記すことは重要だと思う」と付け加えている。
この生まれ変わりについては、私自身にも数十回の記録がある。亡くなった妻と子の行方を探し求めて、何年もの間、数十人の霊能者に接触している間に、私の生まれ変わりについても度々聞くようになっていた。そのうちの二十数回分を、2011年6月刊行の『天国からの手紙』(学研パブリッシング)のなかで、編集協力者の宇田依里子さんが付表にまとめてくれている。「現家族の過去世における関係性」と題したこの付表には、アトランティス時代以降の、私と家族の生まれ変わりの模様を年代順に略記してあるが、それが数十回の記録のうちの二十数回分である。私はこの本の「あとがき」のなかで、「生まれ変わりというのは、事実であるにしてもいろいろな見方がある。この付表は、あくまでもひとつの参考例としてご覧いただければ幸いである」と、書いた。
私が数多くの霊能者と接触してきた経験からいっても、過去生を的確に捉えることのできる霊能者は決して多くはない。ロンドンで付き合っていたアン・ターナーも、過去生については「専門外」だと言っていた。逆に、優れた霊能者であるT氏のように、イスラエル、ロンドンでの私との邂逅をかなり具体的に話してくれる人もいる。なかでも私が長年教えを受けてきたA師は、過去生を読み取ることができる数少ない霊能者の一人である。そのA師によれば、私の今回のこの世での生まれ変わりは、18世紀のイギリスでの前世と深いかかわりがあるという。A師はそれを、つぎのように言った。
《あなたは、主に、ロンドン市内に暮らしていました。名前は「ジェームズ」という響きが感じられます。そのように聞こえるのですが、多分ジェームズという名前だったのでしょう。1685年、1687年ぐらいに生まれ、1760年代後半から1770年代前半まで生きていました。もちろん男性でした。学者でした。法律そのものではなかったのですが、法学と文学の方面での仕事をしている研究者でした。英国学士院と、それから、英国の宮廷に関わるアカデミー、王立のアカデミーでしょうか、そこの会員でした。実はここに入っている間に、心霊学や精神世界に関わるようになったのです。そこの会員の中に、このような霊学に興味を抱いている人が何人かいたからです。あなたは最初、軽蔑し、怪訝な顔をしてそれを外から観察していました。少しずつ興味を持ち理解するようになりましたが、自分の立場を考えて踏み込んだことはしませんでした。》 (1994. 9. 12)
私は、実は、今世の生まれ変わりが18世紀イギリスでの前世とのつながりが深いと聞いて、1994年から5年間にわたって、意図的に執拗に繰り返し、イギリスの前世のことを聞き出そうとしてきた。ほぼ一年くらいの時間をおいて聞き直したことが、どの程度一致するか、あるいはまったく符合しないか、確かめたかったからである。「ジェームズ」という名前は、毎回一致し、年代もほぼ符合している。英国学士院会員も間違いないようである。職業も法律関係でほぼ一致し、T氏も、厳格な裁判官であったと言っていた。そして、そのような前世での私が、霊的真理に関心をもちながらも、地位や評判を失うことを恐れて真理普及の使命を果たさなかったことが今世での生まれ変わりにつながっている、ということも毎回のように聞かされていた。その状況は、私の生まれ変わり以外の、大量の妻と子からの霊界通信の内容とも矛盾していない。例えば、霊界の長男・潔典からの通信でも、今生で体験した事件に関して、後につぎのように言われたことがあった。
《お父さんなら、頭も聡明で、苦しませるのは高い霊たちにとっても辛いことで、決断を要したということです。でも、必ず目覚めて立ち直る人だということがわかり、一人の苦しみが何百、何千人、いや何万人の人たちの魂を目覚めさせ、同様の苦しみや悲しみのなかで沈んでいる同胞に慰めと魂の癒しをもたらすことを、その聡明さによってやってくれるということが期待されたからです。僕は純粋だからということで、その純粋さを保持してほしいというので、早々と引き上げさせられました。あまり世俗の垢にまみれてほしくないということのようです。お父さんは僕に、仕事や勉強など、とりわけ語学の面と国際文化の領域で跡を継ぎ、活躍してほしいと期待をかけてくれていました。でも守護霊たちがが、もっとあの世のことに精通するほうへと導いていき、たいそう大きな力が働き、このような具合に流れ上、なってきました。》(1999.06.05)
1983年9月1日の大韓航空機事件で、妻と長男をなくしたことは、私の人生の最大の試練であった。長年の間、悲嘆の底に沈んでいたが、1992年2月にロンドンの大英心霊協会でアン・ターナーと出会って、私は生き返ることができた。その時は、1991年4月からの1年間のロンドン大学客員教授を終えて帰国する数週間前であったが、心霊協会の別の霊能者からは、あなたはこれから教師になると言われたことがあった。私が、実は私の職業は教師なのだと答えると、その霊能者S氏は微笑んで、「私が言っているのはそう意味ではない」と言った。私が帰国して以来、真剣になって霊的真理を学び、本や雑誌に書き、講演などもするようになることを、S氏は見通していたのかもしれない。そのことを、A師からも、つぎのように言われている。
《今回の人生ではより積極的で意欲的になってきています。当時(18世紀の前世)、あなたは守るものが余りにも多かったのです。そして、踏み込んで行くには用意が出来ていませんでした。非常に自信家で高慢なところがある人でした。今回は、非常につらい状況下で、謙虚さと信仰と素直さを学ばせられたということがありました。それだけあなたの魂が成熟し、用意が出来てきていましたので、そのような試練とテストに耐え得ると天でみなされたために、そのような出来事があなたの身の上に起こったのです。そしてあなたは非常に稀な一人として、そのテストに合格した一人です。それは、それだけあなたが今回、天からやってほしいと願われている使命を賦与されて生まれてきた人だからです。でなければ、そのようなむごいことを天は為されなかったでしょう。》
(1994. 9. 12)
私が今回、この世に生まれ変わってきた理由は、もちろん、大きなショックによって高慢な性格を直し信仰と素直さを学ぶということだけではないであろう。しかし、それらをも含めて、少しでも霊的真理に目覚め、霊性が高められることを目指して生まれてきたことには疑いを挟む余地はない。私のみならず、人々はすべて、このようにして生まれ変わるたびに少しずつ学びを深め霊性を高めていく。不完全から一歩一歩、完全へ近づいていくのである。そして遂には、生まれ変わる必要がない境地にまで達することになるのであろう。その意味でも、私たちは、一人一人が、長い霊的巡礼の途上にある旅人のようなものである。
旅を続けながら、中には足取りの早い人もあり、遅い人もある。もうすでに到達点に近い人もいれば、途中で迷ったりして遅れてしまっている人もいるであろう。つまり、霊的進化の点では、決してみんな「平等」なのではない。しかし、遅かれ早かれ、やがては到達点に達することになるという点では同じである。それを、このようにも譬えて言えるかもしれない。私たち一人ひとりは、いわばダイヤモンドの原石である。研磨が重ねられて光輝を放っているものもあれば、埃にまみれたままで光沢が顕れていないものもある。研磨次第で、それぞれの輝き方は同じではない。しかし、繰り返し磨いてさえいけば、いずれは燦然と輝くダイヤモンドであることには変わりはない。だから私たちは、その研磨のために生まれ変わりをくり返す。私たち本来の光の存在に還っていくためである。はじめに掲げたラムサのことば、「あなたはあまりにも美しく、あまりにもかけがえのない存在である」というのも、そういう私たちの霊的本性の姿を意味しているのではないであろうか。
不老不死の願望と永遠の生命 (2017.05.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.113 ―
もう8年も前のことだが、2009年10月に、私は韓国最南端に位置する済州島の西帰浦を訪れたことがある。西帰浦は、その当時でも、年間400万人以上が訪れる国際的な観光地で、リゾートとして人気が高かったが、私が行ってみたかったのは、西帰浦の正房滝の岩壁の近くにある徐福記念館であった。これは、秦の始皇帝の命により、不老長寿の妙薬を求めてここへやってきた徐福の足跡を記念した記念館である。ここには、石壁で囲まれて小公園のようにきれいに整備された敷地に、「徐福展覧館」と「徐福展示館」とに分けられた二つのかなり大きな建物がある。それらの中には、徐福が乗ってきた船や推定の航路なども大きな絵で示されていた。徐福の石像や「徐市過之」の古代文字のレプリカもあった。私はこの時の訪問を、「始皇帝が求めていた不老不死の妙薬」と題して、「寸感・短信」(2013.11.11)につぎのように書いている。
《2,200年前に広大な中国統一の偉業を成し遂げ、絶対的な権力を誇っていた秦の始皇帝でも、死ぬことは恐ろしかったのであろうか。呪術、医薬、占星術などに詳しい「方士」といわれる徐福に命じて不老不死の妙薬を捜し求めさせたことが司馬遷の『史記』にも書かれているようである。徐福は東方のはるか海上に三つの神山があり、そこには仙人が住んでいて、不老不死の妙薬も手に入ると考えていたらしい。その三つの神山の一つが、韓国最南端の済州島に聳え立つハルラ山という説がある。
徐福は、紀元前219年に大船団を率いて中国を出てから、その済州島南側の中ほどにある西帰浦にたどり着いたという。西帰浦からはハルラ山がよく見える。徐福がこの山へ登ったかどうか、大昔のことだから定かではないが、不老不死の妙薬などあるはずもないから、失望してつぎの目的地へ旅立ったに違いない。この時、徐福は、西帰浦の正房滝の岸壁に、「徐市過之」と書き込んだ。徐市というのは徐福の別名である。「西帰浦」という地名は、ここを徐福が通り過ぎて「西へ帰っていった」と伝えられることからきているという。》
徐福の船団はその後、日本へも渡ったということで、佐賀県の佐賀市、三重県の熊野市、和歌山県の新宮市、鹿児島県の串木野市、宮崎県の延岡市などのほか、山梨県の富士吉田市や東京都の八丈島にも、徐福来航の伝説は残っているようである。しかし、徐福は不老不死の妙薬を手に入れることができずに、結局、莫大な資金を無駄にしたまま、始皇帝のもとへは帰るに帰れず、姿を消してしまったらしい。「不老不死の妙薬」を待ちわびていた始皇帝も、紀元前210年、5度目の中国全土巡行の旅の途中であっけなく病没してしまった。享年50歳であったという。
絶大な権力と財力を誇っていた始皇帝でも、結局、不老不死の願いは叶わなかった。当たり前である。始皇帝に限らず、古来、数多くの帝王や権力者や大金持ちが不老不死を願望してきたが、その望みを達成できたものは、一人もいない。物質的な人間の肉体には不老不死はありえないのである。しかし、それでもこの不老不死についての願望はいまでも、多くの人々の心を捉えて離さないようである。医学の進歩でいつかはきっとそれが可能になると信じている人が今もいる。インターネットをみていると、Nさんという人からのつぎのようなブログが載っていた。
《不老不死は今世紀中に実現可能でしょうか? 私は死というのがとても怖いです。「無」というのが恐ろしく死んでも自分が死んだことすらわからない。何億年と長い時間がたっても自分は一切、何も感じることがない。記憶もその瞬間すべてがなくなり何も感じなくなると思うと「今、自分はなんの為に生きているんだろう?」と思ってしまい、人がいないところでは泣いてしまい、夜にトイレなどでは嘔吐してしまいます。
人類が死という永遠の終わり(無)を克服できる不老不死の薬を今世紀中に完成させることはできるでしょうか?不老不死になる為に、一番難しそうな問題が「脳細胞」です。生まれてから増殖しない脳細胞をどうにか増殖させたり、どこかで増殖させ、とり込んだり、そもそも脳細胞が減らないようにするなど。
今では不可能なことを実現しないといけません。たとえ、これが実現できても「私」と言う意識、感情、などを保持するのは難しいかもしれません。それでも今まで人類は不可能なことを実現し、知らないことを探求し、解明してきました。そんな人間なら不老不死の薬も作ることができるんじゃないかと自分も信じています・・・・・・》
このように死を恐れるあまり、人のいないところで泣いたり、トイレで嘔吐したりするというのは、深刻であるが、このNさんは、このあとも、「事故や殺人による身体的損傷は不老不死の薬でも無理かもしれません。それでも寿命的に不老不死になれる薬は今世紀中にできてほしいです」などと続けて、真剣に不老不死の妙薬への期待を書き綴っている。しかし、医学がさらに発達して、寿命がもっと延びることはあるだろうが、物質である肉体が不死であることは宇宙の摂理に反することで、あり得ない。秦の始皇帝も50歳で死んだし、このNさんを含めて、私たちも、遅かれ早かれ、一人の例外もなく死を迎えることになるだろう。本当は、それでいいのである。長い間、私自身が死も生もわからず苦しんできただけに、こういう言い方をするのもいささか気がひけるが、それで何も問題はない。問題なのは、死が何であるかがわからず、自分が永遠の生命をもつ霊的存在であることに気づいていないことなのである。
このような死への恐怖を抱いている人は、古来、常に絶えることはなかった。現在でも、決して少なくはない。さらにインターネットをみていると、このような死の恐怖に対して、「お悩み相談室」というようなものがあって、僧侶が回答してくれているところもあった。そのうちの一つでは、つぎのような質問と回答が載せられている。
[質問] (男性・Y)
39歳の男です。夫婦二人で子供はおりません。
2か月程前から、自分にも必ずやってくる死についての恐怖からパニックになったりし、いつでもそれが頭から離れなくなってしまい、精神をおかしくしてしまいました。私は小さな頃から死ぬ事に関して人一倍恐怖として感じていたのですが、これまではただ考えないようにできていただけだったと思います。今はいずれくるであろう避けられない自分の死の恐怖が夢の中でも襲ってくるようになってしまい、これからさきの不安などで自分自身どうして良いのかもわからない状態になってしまいました。(中略)
いろいろな死生観の本を読んだりしましたが、頭では今をしっかり生きるという必要性を理解できても、心の中の死の恐怖が勝ってしまっている状況です。仏教を勉強してみようかと思っていますが、何か少しでもアドバイスを頂けたら幸いです。
[回答] (崇興寺・釈心誓)
私も死ぬことは怖いです。 一度も経験していないので、どうなるか不安です。しかし、お釈迦様は明確にお説きくださいました。
死ぬとまた生まれる。死ぬと生まれるから「死」と「生」はくっついている。 それを「生死(しょうじ)」という。私が生まれたということは、前世の私が死んだということ。今の人生は前世の私の来世にあたるということ。
死ぬと生まれ変わります。よきものに生まれ変わるには良き因がないといけません。善い行いを積み上げていく方法もありますが、簡単な方法は他力に任せることです。阿弥陀様にいのちのことは任せておけばよいのです。任せておけば来世は必ず仏に生まれることができます。
死して去ると書いて「死去」、往って生まれるとかいて「往生」。どうせならこの人生、ご一緒に往生の人生を頂きましょう。
「精神をおかしくしてしまう」ほど死の恐怖に苦しみ、「いろいろな死生観の本を読んだり」しても、心の中では死の恐怖が勝ってしまう。そこで、仏教でも勉強してみる気になっているYさんに対して、回答者の僧侶は、このように、生まれ変わりの教えを示して、「一緒に往生の人生を頂きましょう」と答えている。死んでも決して無になってしまうのではなく、やがてまた生まれ変わるということだけでも知ることができれば、質問者は、それで少しは死の恐怖から逃れることができたであろうか。
このような仏教の教えには、私も必死に救いを求めようとした時期があった。1983年の事件で妻と長男を亡くして以来、藁をも掴む思いで「仏説阿弥陀経」などを唱えたりしてきた。西の方はるか彼方に、極楽という光り輝く壮麗な世界があって、人は誰でも、阿弥陀仏の名号を唱えることによってその極楽に往生できる。そしてそのことは、東西南北上下の六法世界の数多くの諸仏によっても証明されているのだ、という内容で、わずかながらも心を癒されているような気持ちにはなったが、それでも、死後の世界が明確に理解できたわけではない。私のような俄信者は、仏典の広大さと深さと、それから漢語の難解さを前にして、やはり、立ちすくんでしまうのである。生とは何か。死とは何か。死後の世界はあるのか、ないのか。仏典が「無上甚深微妙の法」であると教えられても、私には釈然としないものが残った。
私は聖書も真剣に読むようになった。聖書は、現代日本語訳などもひろく普及していて読み易い。そこには、「わたしはよみがえりであり、命である。わたしを信じる者はたとい死んでも生きる。また、生きていてわたしを信じる者は、いつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。」(ヨハネ 11:25-26) というようなことばもある。イエスを信じる者は「たとい死んでも生きる」。また、生きていてイエスを信じる者は、「いつまでも死なない」というのは、暗闇に光が差し込んでくるような強烈なメッセージではあったが、「あなたはこれを信じるか」といわれると、やはりちょっと立ち止まってしまう。つぎのようなことばもある。ここでは、神のみ心は、イエス信じる者が「永遠の命を得る」ことである、と教えられている。
《わたしが天から下ってきたのは、自分のこころのままを行うためではなく、わたしをつかわされたかたのみこころを行うためである。わたしをつかわされたかたのみこころは、わたしに与えて下さった者を、わたしがひとりも失わずに、終わりの日によみがえらせることである。わたしの父のみこころは、子を見て信じる者が、ことごとく永遠の命を得ることなのである。そしてわたしはその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。》 (ヨハネ6:35-40)
「イエスを信じる者が永遠の命を得る」というのはわかるようで、実感としてはどうも捉えにくい。私の場合は、それを、例えば、内村鑑三の信仰のあり方を『基督信徒のなぐさめ』などの著作で学んでいくことで、少しは理解を深めていくことはできたが、やはり、妻と子の死という過酷な現実からは抜け出すことができずに、無明の闇は続いた。生とは何か、死とは何か。私がそれを自分なりに理解し始めていくようになったのは、事件から 9年も経って、ロンドンで優れた霊能者に接するようになり、シルバー・バーチを読むようになってからである。私の場合は、むしろ、大学教授であったがゆえに、それだけ無明の闇が深かったということであろう。
やはり、何よりも大切なことは、死とは何かを理解することのようである。秦の始皇帝を持ち出すまでもなく、インターネットのNさんやYさんの恐怖に触れるまでもなく、昔も今も、死は生を脅かし続けてきた。そして私たちも、あまりにも長い間、死を生の終りと考えて、泣くこと、悲しむこと、悼むこと、嘆くことで死を迎えてきた。結局、それは死が理解できないからである。この意味では、もしかしたら、死についての無知は、死そのものよりも、もっと恐ろしいものといえるかもしれない。その無知は、私の場合もそうであったように、生きている人間をさえ死人にしてしまうからである。つぎのようなシルバー・バーチの教えを読み返していると、そんなこともしみじみと考えさせられる。
《死ぬということは肉体という牢獄に閉じ込められていた霊が自由になることです。苦しみから解き放たれて霊本来の姿に戻ることが、はたして悲劇でしょうか。天上の色彩を見、言語で説明のしようのない天上の音楽を聞けるようになることが悲劇でしょうか。痛むということを知らない身体で、一瞬のうちに世界を駈けめぐり、霊の世界の美しさを満喫できるようになることを、あなたがたは悲劇と呼ぶのですか。
地上のいかなる天才画家といえども、霊の世界の美しさの一端たりとも地上の絵具では表現できないでしょう。いかなる音楽の天才といえども、天上の音楽の施律のひと節たりとも表現できないでしょう。いかなる名文家といえども、天上の美を地上の言語で綴ることは出来ないでしょう。そのうちあなたがたもこちらの世界へ来られます。そしてその素晴らしさに驚嘆されるでしょう。》(『霊訓(4)』(p.134)
古来、人間にとって、死とは絶望にほかならず、最も忌むべきものとして遠ざけられてきた。死から距離をおき、一日でも多く死から離れていることが、殆どの人間の抱き続けてきた密かな願望であったといってよい。しかしシルバー・バーチは言う。「物的なものには、その役割を終えるべき時期というものが定められております。分解して元の成分に戻っていきます。大自然の摂理の一環として物的身体はそのパターンに従います。が、あなたそのものは存在し続けます。生き続けたくないと思っても生き続けます。自然の摂理で、あなたという霊的存在は生き続けるのです。」(『霊訓 (10)』pp. 20-21)
この、人間とは本来霊的な存在であって、肉体がいのちそのものではないことが私たちの銘記すべき最も重大な真実といえるかもしれない。私たちは、霊を伴った肉体なのではなく、肉体を伴った霊である。シルバー・バーチはそれを、こう教える。「物質はただの殻に過ぎません。霊こそ実在です。物質は霊が活力を与えているから存在しているに過ぎません。その生命源である霊が引っ込めば、物質は瓦解してチリに戻ります。が、真の自我である霊は滅びません。霊は永遠です。死ぬということはありえないのです。」(『霊訓 (11)』p. 201)
このように、シルバー・バーチは、私たちは「生き続けたくないと思っても生き続けます」といい、「死ぬということはありえないのです」と断言する。さらにシルバー・バーチは次のように「あなたは死のうにも死ねないのです」とさえ言った。「死は霊の第二の誕生です。第一の誕生は地上へ生をうけて肉体を通して表現しはじめた時です。第二の誕生はその肉体に別れを告げて霊界へおもむき、無限の進化へ向けての永遠の道を途切れることなく歩み続けはじめた時です。あなたは死のうにも死ねないのです。生命に死はないのです。」(『霊訓 (11)』pp. 201-202 )
霊界にいて、いのちの真実を一生懸命に私たちに伝えようとしているシルバー・バーチは、私たちがいつまでも死の恐怖に捉われていることが歯がゆくてならないようである。おかしみをかみ殺したような言い方で、次のように言ったこともあった。「そもそも死というのは少しも怖いものではありません。死は大いなる解放者です。死は自由をもたらしてくれます。皆さんは赤ん坊が生まれると喜びます。が、私たちの世界ではこれから地上へ生まれて行く人を泣いて見送る人が大勢いるのです。同じように、地上では人が死ぬと泣いて悲しみますが、私たちの世界ではその霊を喜んで迎えているのです。」(『霊訓 (11)』p.208) また、シルバー・バーチには、こういうことばもある。「私は自信をもって皆さんに申し上げますが、この世の中には心配することなど何一つありません。人間にとって最大の恐怖は死でしょう。それが少しも怖いものではないことを知り、生命が永遠であり、自分も永遠の存在であり、あらゆる霊的武器を備えていることを知っていながら、なぜ将来のことを心配なさるのでしょう」。(『霊訓(2)』pp.42-43)
2,200年の時差はあるにしても、もし、当時の始皇帝がこのようなことばを聞き、霊的真理を理解できたとすれば、果たして、大船団を送り出してまで怪しげな「不老不死の妙薬」を手に入れることに執着したであろうか。そして現代社会に住むNさんやYさんのような人も、書店や、インターネットで、私のような者の書いたものを含めて、求めさえすれば容易に「永遠の生命」の真実に触れることができるはずなのに、なぜ、その接点が持てないのであろうか。それにも一つの答えがある。それに触れる前に、このホームページの「メール交歓」欄の私自身の「生と死に関する質疑応答」のうちの一つを再録しておきたい。かつて、1959年生まれのSさんからつぎのようなメールが届いたことがあった。
《今年の9月下旬にシルバー・バーチの原文を探しておりまして、こちらのホームページにたどり着きました。そして先生の1983年から今に至る長い道のりを知り、『天国からの手紙』を読ませていただきました。奥様と潔典さまを突然の事故、それもありえないような空軍機による撃墜で失われたこと、先生とお嬢様の悲しみはいかばかりでしたでしょう。そしてイギリスでのミディアムとの出会いで、お二人に再会され、少しずつ心の平安をとりもどされ、霊界と人間界のつながりをホームページや著書で広く知らせていただいたことは、この時代に生きている私たちにとって大きな道しるべとなりました。
繰り返し著書を読ませていただいているうちに、私も今与えられた人生を悔いなく、やさしさと思いやりに満ちたものにしたいと心から思えるようになりました。そして先日ミディアムの方にリーディングをしていただき、10年前に亡くなった父と再会することができました。そしてご縁のあった数人の人たちからもメッセージをもらうことが出来ました。ミディアムの方に私はこれから霊的な生き方をはじめることになるでしょうと言われ、あらためてこれから新しい人生が始まることを感じております。
この半年、先生のホームページにたどり着くまでにはっきりと一本の道が引かれていた様に感じています。2月末に広島の図書館で飯田史彦氏の著書にめぐりあい、その後3年前に購入していた「シルバー・バーチの霊言」とブライアン・L・ワイス氏の著書を取り出し読み返しました。それから地元の図書館で関連した著書をむさぼるように読む日々が続きました。そんな中でどうしても繰り返しシルバー・バーチに立ち戻るのでした。そして「シルバー・バーチの霊言」を原文で読み、味わいたいと考えるようになり、ある方のブログから先生へとたどり着きました。
原文はやはりシンプルで美しい文章で、さらに感動が深まりました。その日から少しずつノートに原文と訳文を写させていただいております。先生にはホームページと著作の文章を通じてではありますが、お会いできたことを神様に心から感謝しております。しばらく迷っていたのですが、やはりそれをお伝えしておくべきかと考えメールさせていただきました。ありがとうございます。先生のこれからのご活躍と、ご健康をお祈りいたしております。》
このSさんには、当然のことながら死の恐怖はないはずである。前述のYさんに答えた僧侶の釈心誓さんのよな死に対する不安もないであろう。家族との死別の悲しみから死の意味を考えるようになったと思われるが、このメールをいただいた時点で、Sさんはすでにシルバー・バーチの著作に親しんでいた。そしてミディアムを通じて、10年前に亡くなった父上と再会したりしている。さらにシルバー・バーチの原文も読むようになった。私のホームページにたどり着くまでのそのような過程を、「はっきりと一本の道が引かれていた様に感じています」とも述べている。このメールに対して、私はつぎのように返事した。
《メールを拝見しました。私のホームページで「霊訓原文」をお読みいただいていることを厚くお礼申し上げます。
私は「霊訓原文」の冒頭で、「三千年前の古代霊であるシルバー・バーチが現代英語で私たちに語りかけているのは、奇跡としかいいようのない事実ですが、それだけに、その貴重な真理のことばを翻訳によらないで、原文のまま吟味してみることも十分に意味があることと思われます」と書きました。
ご存知のように、英語と日本語というのは互いに異質の言語で、背景にある文化も大きく異なりますから、厳密にいうと、例えば、イギリス英語の「mountain」は日本語の「山」とは違いますし、「river」も決して「川」とは同じではありません。ですから英語の原文と日本語の訳文ではどうしても多少の「誤差」が生じます。訳者によっては、その誤差の振幅もさらに増幅されたりして変わってくるわけです。
シルバー・バーチの教えは重大で貴重ですから、それだけに、誤差のない形でそれらを受けとめていくためには、やはり、シルバー・バーチの使った英語をそのままのかたちで、読んでいくほかはありません。私が「霊訓の原文」を対訳の形で取り上げてきたのも、そのような理由からですが、それをお読みいただいていることは、私にとってもたいへん有難く、うれしく思います。
私の『天国からの手紙』もお読みいただき、有難うございます。あなたのように、霊的真理を受け容れる用意が出来ている方には、こういう本も目に留まるのでしょうが、そういう方々は、確実に徐々に増えてきているとはいえ、まだまだ少数派です。これほど大切ないのちの真理に気がつかないまま、肉親の死に際して深く嘆き悲しむだけの方々が跡を絶ちませんが、一人でも多くの方が目覚めのきっかけを掴めるように、共に力を尽くしていきたいものと思います。あなたのこれからのご研鑽とご健勝をこころからお祈り申し上げます。》
この返信で、私は「霊的真理を受け容れる用意」ということばを使っている。死の恐怖から逃れようとして、インターネットで情報を探し求めていながら、それでも、シルバー・バーチに辿り着く人と辿り着かない人との差は何か。そして、霊的真理に関する情報が数多くあることを知っていても、全く信じようとはせず、確かめようともせず、初めから近づこうとはしない人がいるのは何故か。それは、その人たちにはまだ、霊的真理を受け入れる魂の用意ができていないからだ、と考えてよいであろう。霊的真理を受け入れる用意ができていなければ、生と死の真理を伝える珠玉のことばも、何の感動ももたらさず、心に響くことはない。この「霊的真理を受け入れる用意」については、シルバー・バーチが、こう言っている。
《大衆に一度に理解してもらえるような真理を説くことはできません。一人ひとりが異なった進化の段階にあり、同じ真理に対して各人各様の反応を示すものだからです。私はつねづね、神の計画は一度に大勢の人間を目覚めさせることにあるのではないことを説いてまいりました。そういうやり方では、永続性のある効果は期待できないからです。いっときの間は魔法をかけられたようにその気になっても、やがて必ず反動が生じ、群衆心理から覚めて個人としての意識がもどると、しばしば後悔の念とともに現実に目覚めるものです・・・・・・。
忘れてならないのは、真理を理解するには前もって魂に受け入れ態勢ができあがっていなければならないということです。その態勢が整わないかぎり、それは岩石に針を突きさそうとするようなもので、いくら努力しても無駄です。魂が苦しみや悲しみの体験を通じて耕されるにつれて岩石のような硬さが取れ、代わって受容性のある、求道心に富んだ従順な体質ができあがります。》(『霊訓 (7)』pp.68-69)
これは、私にとっても極めて貴重な教えであった。かつて私は、何年にもわたってS教団やG教団などに通いながら、数十人の霊能者といわれるような人々とも接触してきた。教団の霊能者たちからは、一言でも納得できる霊界の情報を掴みとろうと必死になっていたが、何一つ、真実と思える情報は引き出すことはできなかった。しかし、それでもいろいろと霊界のことを聞いたり学んだりしたことは、少しずつ、私が霊的真理を受け入れる用意を整えるのに役立っていたのかもしれない。その私は、1992年のロンドンでの奇跡的体験を経て、初めて救われ、充分に納得し、それからは、自分なりに人々に生と死の真理を伝えようとしてきた。そして25年が過ぎていった。
その間、霊的真理について、私は自分が学んだことを本に書き、何度も講演会で話し、やがてホームページも立ち上げるようになって、そのアクセス数も延べ70万回を超えた。私の述べてきたことも、少しは、愛する家族との死別の悲しみに暮れていた人々などの足元を照らす「ともしび」になってきたかもしれない。しかし、一方では、この無償の奉仕行為もすべてがスムーズに受け入れられてきたわけではなかった。死後の世界や霊界のことなどを語るのは大学教授としてはあるまじき所業であると考える人々はいまも多く、私から離れていったかつての教え子もいるし、私のまわりにも未だに理解してもらえない人々が決して少なくはない。それはそれで致し方のないことなのであろうか。魂に真理を受け入れる態勢が整わないかぎり、その霊的真理を受け入れることは「岩石に針を突きさそうとするように」困難であるというシルバー・バーチのことばは、そう遠くない将来、人生の終焉を迎えるであろういまの私には、殊更に身に染みて胸に響くのである。
イギリスでの雑草をめぐる想い出 (2017.07.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.114 ―
1991年春から一年間住んだロンドン郊外のロチェスターの家では、日本とは異なる風土の違いをいろいろと感じさせられていた。イギリスは緯度が北に偏っているせいで、冬の日照時間は少ないが、六月頃から日は一段と長くなる。夜九時になっても、庭のベンチに座って新聞が読めるほどである。これは新奇な体験であった。夏の間は、芝生の成長も早く、わが家では毎週一回、近くに住むシルビアという名のスペイン人の主婦が、庭の手入れに来てくれていた。まず、電動芝刈り機で芝生の伸びた分をきれいに刈り取る。あとは、垣根や潅木の枝を揃えたり、季節の花々を植え替えたりして三時間ほどで作業は終わる。
ある日、庭の片隅の白樺の木のまわりに雑草が茂っているのを指さして、ここも雑草を抜き取って花を植えたほうがよいという。それはよいのだが、雑草がそう簡単に抜けるものなのかと思った。日本でなら、雑草は頑固に深く根を張っていて、とても簡単に抜けるような代物ではない。シャベルで掘り下げて根ごと取り除くことになるから、雑草のあとは大きな穴になってしまう。しかし、イギリスではそうではないらしい。シルビアは雑草の全部をいとも簡単に、手で引き抜いてしまった。私はそこでまた、和辻哲郎『風土』(岩波書店)にある雑草についての記述を思い出さずにはおれなかった。
和辻哲郎は、ヨーロッパへの留学の途中、地中海を航行中の船の中で、同行の大槻教授から「ヨーロッパには雑草がない」という「驚くべき事実」を教えられる。和辻はこの時の驚きを、「それは自分にはほとんど啓示に近いものであった。自分はそこからヨーロッパ的風土の特性をつかみ始めたのである」と書いた。そして、次のように続けている。
《ヨーロッパには雑草がない。それは夏が乾燥期だということにほかならぬ。雑草とは家畜にとって栄養価値のない、しかも繁殖力のきわめて旺盛な、従って牧草を駆逐する力を持った種々の草の総称である。我々が「夏草」として知っているものはまさにこの雑草である。ところでそれが我々に「夏草」と呼ばれることによっても明らかなように、それは暑熱と湿気を条件として繁茂する。路傍、土手、空き地、河原などに五月ごろ芽を出し始め、梅雨に養われ、七月に至れば見る見るうちに数尺にものびる。それは実に根強い、頑強な、従って練兵場にでも繁茂し得る草である。耕地でも住宅地でも、もし一、二年の間放置せられるならば、たちまちこの種の雑草に占拠せられ、荒蕪地に化してしまう。しかし雑草にこの旺盛な生活力を与えるものは暑熱と湿気の結合である。すなわち梅雨とそのあとの照り込みとである。しかるに夏の乾燥はちょうど必要な時にこの湿気を与えない。従って雑草は芽生えることができない。》
ここにいう「雑草」は、しかし、おそらく「日本的な雑草」とでもコメントをつけたほうがわかりやすいかもしれない。ヨーロッパに雑草はあることはある。現にわが家の庭の片隅に茂っていた。ただ、それは日本の雑草とはまるで違うのである。和辻も、あとのほうで、「もちろん雑草が全然ないというのではない。細い、弱々しい姿の雑草が、きわめてまばらに生い育ってはいる。しかしそれらは柔らかい冬草を駆逐し得るほどに旺盛でもなく、またこの土地から牧場らしい面影を抹殺し去るほどに繁茂してもいない」と、付け加えている。ここでいう「この土地」とは、イタリアのピサとローマとの間の海岸地方である。イギリスはこれよりアルプスを越えてさらに北にあり、たとえば、ロンドンやわが家のあるロチェスターの位置は、緯度の上からいっても樺太の北部にあたる。南欧よりも当然、緯度の高い西欧のほうが風土的条件は厳しいから、雑草も一層育ちにくい。わが家の庭の雑草がすぽすぽと簡単に手で抜けたのもそのためであった。
7月になっても8月になっても、イギリスでは気温はあまり上がらない。こころみに当時の、過去30年くらいの気温の平均をとってみると、東京では最高が8月の26.7度で、最低は1月の4.7度である。その差は22度ということになる。ロンドンの場合はどうであろうか。最高は7月の16.2度とかなり低く、最低は1月の4.7度である。仮に、春、夏、秋、冬の温度差が等しいと考えると、その温度差は東京の場合、22度を4で割ればよいわけだから5.5度。これに対して、ロンドンの場合には3.1度となる。日本はよく四季の移り変わりがはっきりしているといわれるが、この数字からもそれは裏づけられていることになる。年平均気温で見ると、東京は15.3度。これに対して、ロンドンは9.5度であるにすぎない。
雨量については、イギリスでは少ない降雨量が平均化して降る傾向があるが、これも当時の平均的な数字で表してみよう。東京では6月にひとつの山があるが、最も多いのは9月で、193ミリである。年間では1,460ミリに達する。これに対してロンドンの場合には、このような降雨量の山はない。これは大きな相違点であるが、ロンドンでは雨は夏に降るというより、むしろ冬に降りやすいといってよい。一番雨がよく降るのは11月で、83ミリである。最低が夏の7月で、49ミリである。年間では759ミリで、東京の約半分ということになる。
この気温が上がらず、肝心の夏にも雨量が少ないということの意味は重大である。しかも土地は石灰質で、日本のように決して肥えてはいない。それは雑草の生育さえ阻むことになるが、同時にそれは人間の食料としての農作物の生産に極めて不適当ということにほかならない。要するにイギリスでは、他の西欧諸国と同様、穀物生産だけではとても生きていける状態ではなかった。そこで、農業生産性の低い土地をできるだけ有効に利用するための牧畜が平行して行われるようになったのである。
牧畜では、日本の夏草ほどには大きくも硬くもならない自然の野草がそのまま家畜の飼料になった。牧草類をあまり好まない豚などは、森の中に放し飼いしておけば、勝手にあちらこちら動きまわりながらドングリの実などを食べて大きくなる。日本の森林なら、背丈ほどにも伸びる下草が生い茂り、潅木がむらがって足の踏み入れようもないのだが、イギリスの森は自然のままに放置しておいても下草は成長せず、人間も家畜も自由に入って歩きまわれるのである。穀物の生産には確かに不適当であっても、家畜の飼育という点ではいろいろと条件が揃っており、極めて好都合なのがイギリスの自然であるといえよう。
日本の米食に対してヨーロッパではイギリスを含めて肉食であるのは、この風土の違いによるものであるが、これは社会的にも日本とは異なるさまざまなものの見方の違いを生み出してきた。私はイギリスでは、何度かイングランド北部のノース・ヨークシャー州にある古都ヨークを訪れたことがある。大聖堂の南に広がるヨークの町は、周囲をいまもほぼ完全に残されている城壁に囲まれて、中世の面影を色濃く残している。石畳が似合う街の通りは狭く、特に、木骨造りの家々に挟まれた路地や路地裏に入り込むと、数百年の昔にタイム・スリップしたような気持ちになる。街のあちらこちらに重厚なヴィクトリア時代の赤煉瓦の建物があるかと思うと、歴史の重みに耐えながら背の低い木造建物も健気に建っている。そのそれぞれに、しっとりとした情緒があり、時代を隔てた様々な文化の不思議な調和が感じられるのもこの街の魅力といえるのかもしれない。
ヨークの大聖堂から南へ10分ほど歩いて、ヨーク城博物館へ向かうと、途中、Shambles(シャンブル)と呼ばれている狭い通りを通る。ヨークの中でも、ほぼ完全に中世の面影を残しているところである。両側のくすんだ色調の木骨造り店舗は、一階よりも二階、二階よりも三階が道路にせり出し、軒をくっつけんばかりに建ち並んでいる。いまはすっかり観光の名所になって、美術品や土産物を扱う店などもあるが、この「繁華街」は、昔は軒並み、家畜処理業者の店が並ぶ肉屋の街であった。Shamblesというのも「屠殺場」の意味である。1930年代まではほとんど肉屋だけで占められていたらしい。
大聖堂からほど近い「繁華街」が、家畜処理業者の店で占められていたというのは、これも牧畜文化の名残で興味深い。農耕文化の伝統が生きていた昔の日本では、家畜処理業者がお寺の前の賑やかな通りに店を構えるなどということは考えられなかった。いまもその傾向は、被差別部落への陰湿な根強い差別・偏見となって尾をひいている。しかし、イギリスを含めてヨーロッパでは、家畜を処理するというのは、主食を提供するということで、なによりも重要な職業のひとつであった。日本でなら、さしずめ、米屋ということになろうか。日本人にとっては米は大切で、その大切な米を扱う業者を、日本人は決して軽蔑しなかったはずである。それと同様に、ヨーロッパでは、家畜はなによりも大切な食糧源で、それを処理する業者は、しばしば、地位と富と名誉を手に入れることさえできたのである。ヨークの大聖堂にほど近い「繁華街」に、このようなシャンブルがあったのも、そのことを示唆するものにはかならない。
ヨーロッパ諸国では、生きていくために牧畜に頼らなければならないというのは、それだけ生存条件が厳しいことを意味する。中世のころまでのヨーロッパは、慢性的な食糧不足で、住民は常に飢餓にさらされてきたといってよい。英語でforage
というのは、いまでは、「食料を探し回る」という意味になっているが、これは昔は、「盗む」と同義であった。つまり、「食料を探す」というのは「盗む」ことであったのである。ヨーロッパでは、日本にくらべて、戦争の回数がけた違いに多かったことも、これと無関係ではない。山本七平はかつて、日本最大の合戦である関ヶ原の戦いでさえ、ヨーロッパの尺度でいえば、戦争というよりは武士団のトーナメントにすぎないと言ったことがある。
このような生存条件の厳しい社会では、食料を確保し、その分配権をもつということが、権威の象徴になる。それは常に男性であって、女性ではなかった。戦乱の多い社会では女性の地位は低かった。昔アメリカに住んでいた頃、何度か感謝祭やクリスマスのディナーに招待されたことがある。そんな折に、食卓に座ってよく見ていると気がつくのだが、ナイフを持ってみんなのために七面鳥の肉を切り分けるのは、決して主婦ではない。それは常に、その家の男性家長の役割である。ウェールズの炭鉱の町を背景にして撮られた往年の名画「わが谷は緑なりき」や、ジェームズ・ディーン主演のあのアメリカ映画「ジャイアンツ」にもそのような場面がある。私は一度こころみに、主婦がナイフを持つことはないのか、と聞いてみたことがある。その時の答えでは、なぜかはわからないが、これは昔から一家のあるじ、父親がするのが習慣になっている、ということであった。これは、アメリカにもまだイギリスの伝統が残っているということである。かつて、私の「比較文化論」の講義を受けた学生の中でひと夏イギリスに滞在した一人が、次のように伝えてきたことがあった。
《私は、肉を切り分けるのは女性ではなくて一家の男性家長であることを、一度、自分の眼で確かめてみたいと思っていました。その日は、ラム肉の夕食でした。主婦のキャロルが食事の支度をしていたのですが、肉を切る段階になると、ご主人のジョンを呼んだのです。そして、ジョンが肉を切り分けました。私が、興味深そうにその様子を見ていると、そんなにおなかがすいているのか、と言われてしまいました。私は弁解して、あらためてなぜ主婦が肉を切り分けないのかと聞きますと、ジョンは、肉を切るのはその家のホストの仕事でこれは伝統的なものだ、と答えました。》
肉食の伝統をもつイギリスでは、古来、主食の肉を分け与えるということは、他のヨーロッパ諸国と同様、家族集団においても社会的集団においても、権力者の仕事であり、肉を切り分ける刀ないしはナイフは、その権威の象徴であった。英語のprinceは、語源的には、支配者とか君主、王の意味で使われてきたのだが、これはラテン語のprimus(=first)とcapere(=to take)からきたことばで、「最初の地位を取る人」であり、また「獲物の分け前を最初に取る人」の意味である。狩猟などで獲物を手に入れた時、一番いい部分はまず自分が取り、残りを家族や従者たちに分け与えたのがprinceであったのであろう。つまり、肉切り用の刀ないしはナイフを持つことは、大切な食糧分配権を手中に納めていることになる。この伝統が現代のイギリスでも、男性家長のナイフとなって続いているのである。主婦は切り取られた肉片を皿に取って、テーブルの家族や招待客にまわすことはあっても、自ら家長の権威を冒して、肉にナイフを入れることはない。
ついでに付け加えておくと、英語のfamilyということばは、ラテン語のfamilus(=servant)からきたもので、もともと権力に服する奴隷の意味であった。そして、これに対応するのがdespotで、これは「一家の主人」である。despotは、現在では弾圧的で残酷な暴君や独裁者の意味で用いられるが、このような非難の意味が込められるようになったのはフランス革命以後のことであって、本来despotとは、家を支配する人、一家の家長であった。しかし、家を支配する家長が食糧獲得の責任と分配権を一手に握っているかぎり、どうしても権威的かつ横暴になりやすい。この意味ではイギリスの家長とはまさしくdespotであって、このことばは、その権威に服従するfamilyとともに、イギリス社会の父性的特徴を表現するものとして極めて象徴的である。
このイギリス社会の父性的特徴は、たとえば、日本と対比してみるとわかりやすい。日本のように、恒常的な平和の下に農作に従事してきた環境の中では、歴史的に戦乱で明け暮れてきたイギリスなどより、女性の労働力は、はるかに重視されてきた。農耕が女性を中心に営まれた例も稀ではない。日本の農作は重労働ではないが、間断のない手作業の連続である。そのために忙しい時には猫の手も借りたいほどになり、子供たちまで動員されたりする。それゆえにこそ、女性は農作の労働力としてのみならず、働き手の生産力としても重要であった。この出産能力と農耕民族特有の多収穫への願望が結びついて、女性へのアニミズム的な信仰さえ起こり、日本では女性の地位はもともと決して低くはなかったのである。
農耕民族である日本人にとってイギリスの肉を切り分けるナイフに相当するものは、ご飯をよそう「しゃもじ」であった。しゃもじは、イギリス人におけるナイフと同じように、食糧の分配権を意味する権威の象徴であったが、しかし、それを握っていたのは男性ではなく女性であり、一家の主婦であった。かつては、日本にも「しゃもじ渡し」の儀礼が一部の地方に残っていた。主婦がやがて姑になり、年老いて嫁にしゃもじを預ければ、それは事実上、家庭の統率権を嫁に委譲したことになる。イギリスとは対照的に、日本では、女性から女性へと権威の象徴は引き継がれてきたのであった。男尊女卑とか亭主関白とかいわれる中で、次のように、イギリス人女性教師を驚かせるような例が決して稀ではないのもそのためであろう。
《日本の一部の主婦たちは、見かけよりは強いのではないでしょうか。主婦たちのすべてが忍従を強いられているわけでは決してありません。たとえば佐藤夫人はとてもいい人なのですが、ご主人を「鉄の鞭」で支配しています。彼女は、ご主人の給料を封も切らないまま受け取り、そしてご主人には毎日、お小遣いを渡しているのです。このことを彼女は、いつかコーヒーを飲みながら何気なく話してくれたのですが、私が驚いた顔をすると、「でもこれは当たり前ですよ」と彼女は言いました。》(ジョイス・マクドネル『日本人』)
亭主関白どころかこれでは女房関白であるが、ナイフとしゃもじに次ぐもうひとつの違いの例として、生計のための「財布」の問題も取り上げておきたい。夫の給料を封も切らない状態で妻が受け取り、夫はその代わりに、日々の小遣いを妻からもらうというのは、日本では少しも珍しいことではなかった。いまでこそ、給料はほとんどどこでも銀行振込になってしまったが、このような「美風」は、ついこの間まで、日本のどこででも見られた習慣である。
しかし、イギリス人にはこういう習慣はない。だから、このイギリス人女性教師も驚いているのである。要するにイギリスでは(公平のために付け加えておかなければならないが、一般に他のヨーロッパ諸国やアメリカでも)、夫は、たとえそれが無意識のものであるにせよ、妻を信用しないから、財布を妻に預けるようなことはしないのである。先に述べたナイフの例と同じく、家庭の重要なことは権力者である男性が振り、女性には任さないということで、これはおそらく、戦乱に明け暮れた歴史の中で生まれた女性蔑視の名残と見て差し支えないであろう。
このように、イギリスでは女性は伝統的に弱い立場にあり、虐げられてきた者であり、男性に属してきた存在であった。しかし、弱い立場であり、虐げられた者であるがゆえに、やがて一方では、女性はいたわらねばならぬというモラルも芽生えてくることになる。イギリスでknighthood(ナイトフッド)と呼ばれたような、中世の騎士道の精神などもそれである。現代のladies
firstはその流れを受け継いだものであって、その意味ではこのladies firstは、本来、女性尊重からきたものではなく、むしろ、女性蔑視の裏返しとして起こったものといえるのかもしれない。
ともあれ、女性には古来、時により、所により、いろいろな女性観がつきまとう。なかには、他愛のないジョークまがいのものもないわけではない。ある時、ロンドン郊外をタクシーに乗って走っている途中、急に雨が降り出したことがあった。運転手は、これだからイギリスの天気は信用できないとぼやいた。そして私に、イギリスでは信用できない三つの”W”があるのを知っているかと聞いてきた。彼は、weather(天気)、wage(賃金)をあげ、あとのひとつはwoman(女性)だと言って、にやっと笑った。
霊的真理に目覚めるまでの長い道のり (2017.09.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.115 ―
1983年9月1日の大韓航空機事件で妻と長男を亡くしてからは、私はアメリカの教職を中断して帰国し、札幌の自宅でほとんど寝たきりのようになっていた。11月下旬のある日、私はふと思いついて、妻・富子の友人の青木さんの家を訪ねた。彼女は、運命鑑定などをしている霊能者である。富子は、「私は運命鑑定などは信用しないわよ」などと言ったりしながら、時折彼女と会っては、気のおけないおしゃべりを楽しんでいた。私が富子を車で送っていったこともあるが、私自身は青木さんとは初対面であった。「もうそろそろ、お見えになる頃だと思っていました」と、私の顔を見るなり、いきなり彼女は言った。
その時の私は、「溺れる者は藁をもつかむ」心境であったかもしれない。何でもいいから、こころの支えが必要であった。青木さんはそういう私の心境もわかっていたらしい。ぽつりぽつりと語る私のことばに耳を傾けたあと、「まだこれから三年は苦しまれるでしょうね」と、私に同情を示した。彼女は事件のあと、富子と潔典(きよのり)のために二週間の供養をしてくれたのだという。そして、霊界の富子とも潔典とも話をしたとも言った。このことばは私を驚かせた。彼女は静かに語りだした。「霊感を感じましてね、精神を統一していると清らかな雰囲気に包まれて潔典さんが現われたんです。私は最初それは富子さんだと思ったのですが、よく見ると潔典さんでした……」
私は内心の動揺を抑えながら黙って開いている。(そんなことが本当にありうるのであろうか)まさか、と思う。その時の私は、霊の世界については全く無知であった。彼女は続けた。「潔典さんはですね、はじめに『有難う』とおっしゃって、それから『楽しかった』と言われました。私が、『アメリカ旅行が楽しかったのですか』と聞きますと、潔典さんは『いいえ、アメリカ旅行だけではなく、今までの生活がすべてです』と答えられました。」ここまで聞いて、私はこころのなかで思わず「あっ」と叫んでいた。これも直観である。「ありがとう……楽しかった……今まので生活がすべて……」これは潔典のことばだ。父親の私にはわかるのである。私は涙をぽろぽろと落としてしまった。
A女史の話はそれからもしばらく続いたのだが、聞いている私はもう上の空であった。あまりにも不思議な気がして、三日後にはまた彼女を訪れ、その潔典のことばをもう一度確認したりしている。その後何度か足を運んでいるうちに、富子からのことばもいろいろと開いた。「どうか、いつまでも悲しまないで下さい ――
由香利に夢を、いつも明るい希望を……」と、語りかけられたりした。「由香利」は長女の名である。私は、少しずつ聖書や仏典などを読みはじめていたが、それからは、ケネス・リング、レイモンド・ムーディ、モーリス・ローリングスの近似死体験に基づく死後の世界に関する研究書や調査報告などをひもとくようになった。その頃はまだ『シルバー・バーチの霊訓』は出版されていなかったが、市販の霊界について書かれた本を探しては、丹波哲郎のものなども含めて次々に買っていった。私にとって死後の生命は、信じるか信じないかの問題ではなかった。私が生き続けていく場合の希望を支える絶対的条件になっていた。
それからしばらくして、ある日の夕方、札幌市内の野々原と名乗る女性から電話がかかってきた。北海道大学の学生食堂に勤めていると言っていたが、私には面識がない。彼女は「昨夜、潔典さんの夢を見ました」というのである。当時はまだ、事件については、しばしばテレビや新聞に取り上げられていた。その前日も、彼女は、たまたま事件を報じているテレビで、冨子や潔典の映像を見たらしい。そして、夢の中に現れた潔典から、「ぼくの父に会ってほしい」と頼まれたのだという。テレビ局に電話して、私の電話番号を聞きだし、電話しているのだと、遠慮がちの低い声でおずおずと言った。
潔典から「ぼくの父に会ってほしい」と頼まれたというのは、ただ事ではない。私はすぐにその翌日、彼女の家へ出向いた。野々原さんは中年の寡婦で、中学生のお嬢さんと二人で暮らしている。S教団の信者で、霊界の存在や、死後の生命のことも信じているようであった。S教団では、霊能者も二百数十人もいて、霊界との交信も日常的に行われているという。事件前の私なら、そういう話ははじめから受け付けようとはせず、「夢のなかで頼まれた」などという話も一笑に付したかもしれない。しかし私は、黙って2時間ほども、真剣に彼女の話に耳を傾けた。青木さんから、霊界の潔典からの霊言を受け取ったばかりであったし、その時の私には、霊的な話を非常識だとか、荒唐無稽であると忌避するような余裕は全くなかった。野々原さんが所属しているのは、S教団の札幌支部で、本部は東京の立川にあるという。私は、札幌支部の支部長を紹介してもらって、その翌日、札幌支部へ出かけた。
円山公園に近いS教団札幌支部に着いてみると、受付に出たのは、私の小樽商科大学のかつての教え子の一人である新田君であった。新田君はちょっと驚いたような顔をした。私も、一瞬、大学教授として来るべきでない所へ来たような後ろめたさを感じたかもしれない。支部長は、菅野さんという温厚な感じの老婦人であった。私は、菅野さんの私室に迎え入れられて、ここでもまた、S教団の教えや霊界のことについて話を聞いた。菅野さんはほとんど一人で、穏やかに語り続けた。優しい人柄が伝わってくるようで、悲しみ苦しみ続けて凍り付いてしまったような私の重い心もあたたかく癒されているような気がした。菅野さんは、立川のS教団で会合があるので、その翌々日には上京するという。私は、私もS教団本部に連れて行ってくれるように頼んでみた。彼女は承諾してくれた。
菅野さんは、東京では、多摩市の永山団地に娘さんが住んでいるので、そこに泊まるという。たまたま長男の潔典が住んでいたのも永山団地であった。棟は違うが、歩いても数分の距離である。私と菅野さんは、その3日後の朝、京王線の永山駅で落ち合い、一時間ほどで立川のS教団本部に着いた。門をくぐりぬけて塀に囲まれた広い敷地の中に入ると、ちょうどすれ違うようにして、法衣を来た一人の老人が歩いてきた。それがS教団のI教主であった。信徒にとっては、教主さんは神のような存在であるらしかった。菅野さんは、教主さんの前に歩み寄って、深々と頭を下げた。そして、私のことも何か話したようである。やがて、教主さんは、少し離れて立っていた私の所へ来て、黙って手を差し伸べた。じっと私の顔を見ながら握手をしたあと、静かな足取りで立ち去っていった。菅野さんは驚いていた。教主さんから握手をされるのは大変なことのようであった。
私は菅野さんから事務局へ連れていかれて、法務主任のYさんを紹介された。それから応接室のようなところで、ずいぶん長い間、YさんからS教団や真言密教についてのお話を聞いたが、いまはほとんど覚えていない。ただ、霊界というのはあるらしかった。人は死んでも霊界で生き続けるということも、聞かされた。しかも、霊界とは荘厳華麗な世界で、そこではみんな安らぎに満ちた生活を送っているという。そのことは、私も「仏説阿弥陀経」を読んでいたので、初耳ではない。しかし、Yさんは話の途中で「私も早く死んで霊界へ行きたい」と言ったのである。このことばは、私の胸に強く響いた。本当にそう思っているのか、そう思うこともありうるのか、と何度もこころのなかで繰り返していた。
私は札幌へ帰ってからも、しばしばS教団の札幌支部へ通うようになった。霊界のことを少しでも知りたいという一心からである。しかし、霊界について関心を深めていく一方で、私にはどうしてもしなければならないことがあった。事件の真相究明である。悲嘆に暮れている中で、これは二重の苦しみであったが、遺族としては避けては通れない。つらい気持ちを抑えながら、私は事件関係の資料をひろく集めて、真実を探し求める努力を続けた。事件の翌年8月には、東京の憲政記念館で、国会議員の瀬谷英行、田英夫、宇都宮徳馬、土井たか子氏らと政治評論家の山川暁夫氏らが21名の設立発起人を代表して記者会見を開き、「声明」を発表して、「大韓航空機事件の真相を究明する会」の設立を呼び掛けた。
私は、瀬谷英行、田英夫両参議院議員、市民運動家の荒川亘氏と共に4人の代表委員の一人に選ばれて、それからは、頻繁に札幌と東京を飛行機で往復するようになった。その翌年の春には、小樽商科大学を退官して東京へ移った。私にはもう名誉とか地位・財産のようなものは何の意味もなくなっていた。東京では、「真相を究明する会」の仲間たちと熱心に研究会を重ねながら、新聞、雑誌、単行本などに会員諸氏の研究成果を発表していった。私も、「遺族はなぜアメリカを弾劾するか」(「世界」岩波書店、1985年10月号)、『疑惑の航跡』(潮出版社、1985年)をはじめ、新聞、雑誌に幾度となく書き、単独で広報紙「APPEAL」も毎週発行して真相究明を訴えていった。そして、その傍ら、立川のS教団本部に通うことをくり返した。
S教団では、毎月何回か例会の日があって、その日には、お祈りなどの宗教行事が終わると、霊能者から霊言を聞く「接心」という時間が設けられている。大広間に集まった数百名の信徒たちが、十数人のグループに分けられて輪になって座り、その中へ教団の霊能者が1人入ってくる。霊能者は、お祈りの後、輪になって座っている一人一人の前ににじり寄り、順番に霊言を伝えるという形であった。信徒たちの誰が先になるか、後になるかはわからない。教団の霊能者は二百数十人いるということであったが、そのうちの誰が輪の中に座るのかもわからない。私が最初に本部で接心を受けた時には、輪の中に瞑想して座っている私の前に、いきなり若い霊能者が寄ってきた。彼は、「あなたの内臓が弱っているが、何か苦しいことがあるのか」と訊いた。内臓が弱っているのかどうか私にはわからないが、苦しいことはある。悲しくて苦しいからここへ来ているのである。しかし、私は、事件で妻と子を亡くしていることは言わなかった。その霊能者も、私が家族を亡くしていることには気が付いていないようであった。その時の「接心」は、私の健康問題についてあれこれ言われただけで終わった。
S教団本部の「接心」で、霊能者と何度も対峙しているうちに、「身近な家族が霊界にいる」などと言われたこともあったが、それ以上、具体的に霊言で示されたことはなかった。札幌では、青木さんから、潔典や富子からの霊言をすでに聞いている。「有難う、楽しかった、アメリカ旅行だけではなく、今までの生活がすべて」などという潔典からのことばは、いかにも潔典らしいことばで、私は直感的にそれが真実の声であることを感じ取って涙を流したのだが、そのようなレベルの霊言を聞いたことは、ここの「接心」では一度もなかった。青木さんは、富子や潔典のことや事件のこともよく知っていたのに対して、事件のS教団の霊能者たちは、私のことは何も知らないという違いはあったかもしれない。私は、S教団の霊能力が高いといわれる幹部の「特別接心」というのも高い料金を払って何度も受けてみた。何年もの間、「接心」と「特別接心」を受け続けて、霊能者の前に座ったのも数十回を超えたが、結局、私は、こころから納得できるような霊言は何一つ得ることはなかった。
S教団本部の「接心」では、何も具体的なことは聞けなかったが、それでも、霊界や霊言についての教えには少しずつ慣れていったような気がする。ただ、当時の私は、事件の真相究明活動でアメリカ政府の犯罪が明らかになっていく中で、大統領のロナルド・レーガンや国防長官のキャスパー・ワインバーガーなどを激しく憎み、罵り、毎月、抗議文を送り続けたりしていて、心は暗く閉ざされていた。そのことが霊界からの霊言を受け難くしていたことはあったかもしれない。それからも、そのような状態でさらに何年か過ぎた。真相究明運動の方は、1988年に、会の研究成果として『大韓航空機事件の研究』が510ページの大冊にまとめられ三一書房から刊行された。その後、1991年春からは、私は、7年間の真相究明運動から初めて離れ、ロンドン大学客員教授として、一年の予定でイギリスへ渡った。
ロンドンでは、大学へ通う傍ら、大英心霊協会を度々訪れるようになった。大英心霊協会には優れた霊能者が沢山いることは知っていたが、しかし、はじめの半年は、それらの霊能者の前に座って一対一で霊言を受けることはしなかった。もしここでも、S教団で受けてきたような霊言の内容で終わってしまうのであれば、私はもう一生救われない。切羽詰まったような気持ちで、霊的真理の勉強を深め、霊言を受け入れる心の準備をしなければならないと思っていた。この頃にはすでに、シルバー・バーチの教えに接するようになっていた。大英心霊協会の売店でシルバー・バーチの霊訓原本をすべて買い入れて繰り返し読んだ。その重大性に気づき、自分でも一部を翻訳したりしている。
大英心霊協会では、公開デモンストレーションというのがある。霊的真理の普及のために無料で一般に公開しているものだが、私も出席して、霊言を受ける雰囲気に慣れていこうとした。そして、1992年1月30日、私は大英心霊協会で初めてミーディアム(霊能者)の前に一人で座った。ミーディアムの前に座って一対一で霊言を受けることを、大英心霊協会では“シッティング”といっていた。そのシッティングでのアン・クーパーは中年の落ち着いた感じの女性で、ちょっと祈りを捧げた後、はっきりした口調で語り始めた。霊界の富子、母、潔典、弟の耕治などがつぎつぎに私の目の前に現れているようであった。私のことは何も知らないはずの彼女が、私の家族を目の前に見ているように極めて正確に描き出していく。
潔典については、「あなたの息子は、身長5フィート8インチ(約173センチ)くらいに見える。黒い髪、美しい顔で非常に好ましい青年だ――たいへん知能が高い、私には説明し難いが、人間の心を世代を超えてコミュニケートさせる方法のようなものを研究しているらしい――あなたに強い感情を送っている、姉とは年齢があまり違わないのではないか・・・・・・」などと彼女は言った。潔典の身長は174センチである。「知能が高い」も、大学での成績は「全優」だったから間違ってはいない。姉との年利差は1年2か月だから、これも言われた通り「あまり違わない」。これらのことばは途切れ途切れに語られているので、予約していた30分の時間は瞬く間に過ぎたが、明らかに正確度の極めて高いことばの数々を受け留めて、私はこころの高揚を抑えきれずに、なかば夢見心地で、大英心霊協会を後にした。
このアン・クーパーからは、2月4日にも会って、2度目のシッティングを受けた。その日、協会の控室でたまたまアン・ターナーにも会った。その時は、彼女がミーディアムであることも知らず、私はまったく偶然に会っただけだと思っていたが、後にそれは、霊界からの導きであったことを知るようになる。2月11日には、彼女のシッティングを受けて、彼女の卓越した霊能力により、遂に妻と長男との奇跡的な「再会」を果たしたのである。彼女は、私のことを全く何も知らなかったが、私の前に霊界の長男が立っていることを伝え、感動した面持ちで自分の名を「キノーリ」、または「クノーリ」と名乗っていることを私に言った。霊界へ移ったのが1983年の事故であることも正確に指摘した。あり得ないようなことが現実となって、私は茫然となった。
堰を切ったように、私はそれから何度もアン・ターナーに会った。彼女は私を前にして、独り言を言うように、淡々と妻と長男のことばを次々と私に伝えた。それらのことばには、疑うにも疑いようのない真実の重みがあった。私は人生の大きな転換期に立っていることを実感していた。帰国前の忙しさの中で頻繁に大英心霊協会を訪れ、アン・ターナーのほかにも十数人のミーディアムからシッティングを受けた。そのほとんどのことばに私は十分に納得し、格段に高い真実の響きを感じ取っていた。長い彷徨の末に遂にここまで来て、心の底から霊界の存在も確信できるようになった。長年の悲しみと苦しみからも初めて解放され、私は生き返ることができた。
1992年3月末、日本に帰国してからもシルバー・バーチから学び、アン・ターナーからのテープによる家族との霊界通信を続けた。やがて私は、そのような霊的体験を本に書き、講演会で話すようになった。東京でも、高い霊能力をもつA師から、いろいろと霊言を聞くようになり、ホームページを開設して、シルバー・バーチの教えを伝えるようにもなった。そして今の私は、あのアメリカ滞在中に「世界史の転換点」ともいわれた大事件に巻きこまれた意味も、今生で私に課せられた使命といったようなことも、私なりに理解できるようになっている。
かつて、慟哭と絶望のなかで迎えた「9月1日」からは、今年で34年の歳月が流れた。事件直後のあの悲嘆と慟哭の日々が、遠い夢のなかの一こまのように思い出される。あの頃は、もう私の人生も終わったのだと思っていた。立ち直ることは考えられなかったし、立ち直りたいとも思わなかった。いまでは、生きるというのはどういうことか、死んでから私はどこへ行くのか、そういう切実な問題もいろいろと理解できるようになって、穏やかに残された日々を過ごしている。随分時間がかかり寄り道してしまったようだが、結局は霊界の家族からも導かれて、霊的真理に理解を深めることができたことを、私はこころから神に感謝したい気持ちである。
司馬遼太郎の大阪への想いに共感する (2017.11.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.116 ―
司馬遼太郎が書いた「大阪城公園駅」というタイトルの文章がある。昭和58年(1983年)10月1日に、JR大阪環状線「大阪城公園駅」が営業を開始した際、それを記念して、駅の改札口壁面の陶板レリーフに焼きこまれた。司馬は、この文章を草するにあたって、「私には、この地に対するやみがたき想いがある。この地とは、上町台といってもよく、大阪といってもいい。あるいはこの台地のむこうにひろがる海ともいえるし、その上にうかぶ雲ともいえる。さらにいえば、この地で営まれてきたひとびとのいのちへの愛しみともいえるかもしれない」と述べている。そして、それを、つぎのように綴り始めた。
おごそかなことに、地もまたうごく。
私どもは、思うことができる。この駅に立てば、台地のかなたに渚があったことを。
遠い光のなかで波がうちよせ、漁人が網を打ち、浜の女らが藻塩を焼いていたことども。
秋の夜、森の上の星だけが、遥かな光年のなかで思いだしている。
夏、駅舎の前の森の露草の花の青さにおどろくとき、またたきの間でも茅淳(ちぬ)の海を思いかさねてもらえまいか。ひたにこのあたりまで満ちていたことを。
目の前の台地は島根のごとくせりあがり、まわりを淡水が音をたてて流れ、大和や近江の玉砂を運び、やがては海を浅め、水が葦を飼い、葦が土砂を溜めつつ、やがては洲(しま)になりはててゆく姿は、たれの目にもうかべることができる。
これが書き出しの部分である。「おごそかなことに、地もまたうごく」から始まって、「夏、駅舎の前の森の露草の花の青さにおどろくとき、またたきの間でも茅淳(ちぬ)の海を思いかさねてもらえまいか。ひたにこのあたりまで満ちていたことを」と読み進んでいくと、その美しいことばのリズムに惹きこまれて、静かな感動が胸に広がっていく。司馬遼太郎は、1923年に現在の大阪市浪速区で生まれた。私は、その隣の大正区で1930年に生まれている。そして、司馬と同じように、私にも、「この地に対するやみがたき想い」がある。私が生まれ育ったのは、大正区の尻無川のほとりの町であったが、まわりにはふんだんに空き地が広がっていて、子どもの頃の私は、朝から夕方暗くなるまで、疲れも知らずに遊びまわっていた。夢のように楽しい日々が流れていた。
しかし、「おごそかなことに、地もまたうごく」。このあたりは、5,500年前の縄文時代には、まだ海であった。大阪城公園駅から降りると、目の前に大阪城の天守閣が聳えているが、それが南北に伸びる上町台地の北端で、かつては、台地は岬のように海へ突き出ていた。それが茅淳(ちぬ)の海である。海を隔てて、北に千里丘陵があり、東側には河内湾が生駒山地の麓まで広がっていた。西側の大阪湾も、現在の大阪城の近くまで深く抉られていた。淀川や大和川などの河川が間断なく土砂を運び続けて、16世紀後半には、河内湾は埋め尽くされ、上町台地の周辺まで湿地帯が広がる状態になったのである。司馬の文はこう続く。
目の前の台地は島根のごとくせりあがり、まわりを淡水が音をたてて流れ、大和や近江の玉砂を運び、やがては海を浅め、水が葦を飼い、葦が土砂を溜めつつ、やがては洲(しま)になりはててゆく姿は、たれの目にもうかべることができる。
八十の洲
それがいまの大阪の市街であることを、冬の日、この駅から職場へいそぐ赤いポシェットの乙女らの心にふとかすめるに違いない。創世の若さ、なんと年老いざる土(くに)であることか。
私どもは、津の国にいる。
津、水門、湊、港。私どもは、古き津の風防ぎする台上にいる。
台地は海鼠形をなし、方正にも北から南によこたわり、南端の岩盤に四天王寺が建った日のことを、炎だつ陽炎のなかで思っている。輪奐(りんかん)が海に輝いたとき、遠つ国々の船が帆をななめにして松屋町筋の白沙に近づき、この駅舎のあたりの入江のいずれかへ石の碇を沈め、内典・外典の書籍を積みおろしたにちがいない。思想の書、詩の書、工術の書。
・・・・・・もし若者が、駅舎のベンチの何番目かに腰をおろし、ひざに書物を置いて空を見あげたとき、櫂で描いたような飛行雲があらわれるとすれば、その舶が曳きつづけてきた航跡であるとおもっていいのではないか。
この「目の前の大地」とは、大阪城公園駅から見た上町台地である。まわりの淡水が土砂を運び続けて、やがて台地のまわりに「八十の洲」を造り上げた。それがいまの大阪市街であることを、「冬の日、この駅から職場へいそぐ赤いポシェットの乙女らの心にふとかすめるに違いない」と司馬はいう。「赤いポシェットの乙女ら」の語り合う柔らかな大阪方言が聞こえてくるような情景である。この上町台地の南端に、推古天皇元年(593年)、聖徳太子によって四天王寺が建てられた。崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏の間の武力闘争が起こったとき、聖徳太子は、「もしこの戦に勝利したなら、必ずや四天王を安置する寺塔を建てる」という誓願を立てたという。戦いは勝利に終わったので、その誓願によって建てられたのが「四天王寺」であると伝えられている。
この「四天王寺」が略されて、現在の「天王寺」の地名になった。天王寺駅の前には高さ300メートルの日本一といわれる高層ビル「あべのハルカス」が2014年に建てられている。私はその翌年にそこを訪れたが、その60階の展望台に北に向かって立つと、すぐ右下に四天王寺の広い境内が見える。遠く5キロ前方には大阪城も遠望できる。天王寺駅からは、その大坂城右端の大坂城公園駅まで、JR大阪環状線が走っていて、寺田町、桃谷、鶴橋、玉造、森之宮の順に5つの駅を通る。この環状線が、古代では、海岸線であったと考えてよい。岬のように南北に伸びる上町台地の東側がこの線で河内湾に面していた。大阪公園駅のあたりで上町台地は終わって、つぎの京橋から大阪駅まではすべて「茅淳の海」であった。西回りの大阪環状線は、大阪駅からは、福島、野田、大正、今宮などを通って天王寺に至るが、この広い地域も、かつてはすべて大阪湾の海であった。
その海を越えて、遠い国々からやってきた船が、「松屋町筋の白沙」に近づいてくると、四天王寺の壮大な建物も、海上からもよく見えたに違いない。大阪は、それらの船が、「内典・外典の書籍」などだけではなく、多くの物産を運んでくる物産の集積地になっていった。司馬遼太郎は、その情景を、「もし若者が、駅舎のベンチの何番目かに腰をおろし、ひざに書物を置いて空を見あげたとき、櫂で描いたような飛行雲があらわれるとすれば、その舶が曳きつづけてきた航跡であるとおもっていいのではないか」と美しく描写した。そして、こう続ける。
海鼠形の台地の北の端は、いま私どもが眺めている。
ここに西方浄土にあこがれた不思議の経典を誦する堂宇ができたとき、地は生玉荘とよばれ、坂があった。おさかとよばれた。堂宇の地は礫多く、石山とよばれていたが、ここに町屋がならんだとき、この台上にはじめてささやかな賑わいができた。
楼上から西をのぞみ、陽傾き、帰帆相次ぐころ、波のかなたの一の谷の崖に沈んでゆく夕陽の華やぎは、ひとびとに仏国土を思わせた。
堂字が去り、城ができたとき、日本の歴史は変った。
威と美を多層であらわした世界最大の木造構造物は、大航海時代の申し子というべく、その威容を海から見られるべく意識した。事実、この海域に入った南蛮船は、極東のはてに世界意識をもった文明があることを象徴として知った。
城の台上から西へ降りた低地はすでに八十洲ではなくなり、網模様のように堀川がうがたれ、大小の商家がひしめき、日本国のあらゆる商品がいったんはそこに運ばれ、市が立ち、値がさだまり、やがて諸国に散じた。この前例のない仕組みそのものが天下統一の独創から出ており、にぎわいは空前のものとなった。
この「海鼠形の台地の北の端」の「西方浄土にあこがれた不思議の経典を誦する堂宇」とは、石山本願寺のことである。大阪城が建てられる前は、ここに、石山本願寺があった。この寺のある小高い丘の北では、淀川と旧大和川が合流しており、その付近にあった渡辺津は、淀川・大和川水系や瀬戸内海の水運の拠点で、また住吉・堺や和泉・紀伊と京都や山陽方面をつなぐ陸上交通の要地でもあった。台地にそった坂に町が形成されたことから、この地は「小坂」、後に「大坂」と呼ばれたという。これが今日では、「大阪」になった。石山本願寺そのものは、天文2年(1533年)に本願寺教団の本山となって以後発展し、戦国の一大勢力となっていたが、織田信長との10年に及ぶ抗争(石山合戦)の末、天正8年(1580年)、遂に顕如が屈服して、信長に明け渡した。信長は本願寺に立て籠もった僧侶や町民たちを皆殺しにした後、この寺を焼き払ってしまっている。
信長は、このあたりの土地のことを、「凡そ日本一の境地なり」と言っていた。高台で防備の観点からも申し分なく、前述のように、海岸に面して物産の集積が容易であり、国内はもとより、中国や東南アジアなどの海外からの交易船も、瀬戸内海から入ってきて、淀川、大和川をはじめとする中小河川で京都まで行くことができたからである。その「日本一の土地」に目をつけたのが、信長の跡を継いだ豊臣秀吉であった。ここに世界最大級といわれる大阪城を建てた。その築城を契機として、大阪は大きく変わり、そして、日本の歴史も変わっていく。「城の台上から西へ降りた低地はすでに八十洲ではなくなり、網模様のように堀川がうがたれ、大小の商家がひしめき、日本国のあらゆる商品がいったんはそこに運ばれ、市が立ち、値がさだまり、やがて諸国に散じた」とあるように、大阪は、「日本一の商都」といわれて空前の賑わいをみせるようになったのである。司馬の文は、このあと、次のように続く。
台上の城には、あざやかな意志があった。台下の商権と表裏をなしつつそれを保護し、さらには海外を意識し、やがて思想なき過剰な自信が自己肥大をまねき、精神の重心が舞いあがるとともに暴発し、他国に災禍をあたえ、みずからも同じ火のなかでほろんだ。人の世にあることのかがやきと、世に在りつづけることの難さをこれほど詩的に象徴した建造物が他にあるだろうか。
つぎの政権は、篤農家のように油断なく、諸事控えめで、無理をつつしみ、この地の商権もまた前時代と同様、手あつく保護した。信じられるだろうか、二百七十年ものあいだ、この一都市が六十余州の津々浦々に商品と文化をくばりつづけたことを。
さらには、評価の街でもあった。物の目方、物の質、物の値段……多様な具象物が数字として抽象化されてゆくとき、ひとびとの心に非条理の情念が消え、人文科学としか言いようのない思想が萌芽した。さらには自然科学もこの地で芽生える一方、人の世のわりなきこと、恋のつらさ、人の情の頼もしさ、はかなさが、ことばの芸術をうみ、歌舞音曲を育て、ひとびとの心を満たした。
台上の城に、「あざやかな意志があった」というのは、もちろん豊臣秀吉のことを言っている。秀吉は、ここで天下を手中に収めた後は、二度にわたって無謀な朝鮮出兵を試みたが、志半ばで病没し、慶長20年(1615年)には、大坂夏の陣で、豊臣家は滅亡した。焼け野原になった大坂の町は、その後に天下の覇者になった徳川家康のもとで復興し、さらに発展していく。家康は、秀吉と同様、この地の商権を手あつく保護した。上町台地の西の湿地帯に広がっていった新興の町には、例えば中之島の周辺のように、日本各地の大名たちの年貢米や領内の特産物を売るための蔵屋敷が130余りも建ち並んだ。大坂は、日本中の財が集まる日本一の商都となり、江戸時代の270年もの間、日本の隅々まで、商品と文化を送り続けるようになったのである。しかし、その大坂も、嘉永6年(1853年)神奈川沖にアメリカ合衆国海軍東インド艦隊を率いる代将マシュー・ペリーの「黒船来航」以来、時代の波に翻弄されていくことになる。司馬の文は、さらに続く。
右の二世紀半、ひとびとは巨大なシャボン玉のなかにいた。
あるいは六十余州だけがべつの内圧のなかにいた。数隻の蒸気船の到来によって破れ、ただの地球の気圧と均等になったとき、暴風がおこった。
この城は、ふたたび情勢の中心となり、政府軍が籠り、淀川十三里のかなたの京の新勢力と対峙した。ついには、やぶれた。二度日の落城であり、二度ともやぶれることによって歴史が旋回した。この神秘さを感ずるとき、城はただの構造物から人格になっていると感じてもよいのではないか。
その地に居ることは、その運命とかかわる。この城が六十余州の中央に在ることで、好まざる運命をも背負わされた。薩南の暴発にそなえるために、城のまわりに火砲の製造所が置かれた。
やがて、首都を頭脳とする日本国が、十九世紀の欧州の膨張主義を妄想しはじめるともに、この場所の設備も拡大され、やがて共同妄想が業火とともに燃えおちた日、この城のまわりの鉄という鉄が熔け、人という人が鬼籍に入った。城は、三度目の業火を見た。
徳川幕府は、外国との接触を禁じて、この島国は幕末までの270年もの間、鎖国状態が続いていた。ペリーの黒船来航で、国中が太平の眠りから叩き起こされたような騒ぎになり、その翌年には、幕府が朝廷に無断で「日米和親条約」を締結したことにより、一挙に、尊王攘夷の気分が高まっていく。これが戊辰戦争の引き金になった。慶応4年(1868年)から 明治2年(1869年)にかけて、薩摩藩・長州藩・土佐藩らを中核とした新政府軍は、旧幕府勢力および奥羽越列藩同盟との間で戦争になり、大阪城もその舞台になった。徳川慶喜の大政奉還により、王政復古が実現して明治政府が樹立されたが、その後も、1877年には、鹿児島士族が西郷隆盛を擁立して新政府に対して蜂起した西南戦争が勃発している。「薩南の暴発にそなえるために、城のまわりに火砲の製造所が置かれた」というのは、明治政府軍を主導した大村益次郎が、かねてから薩摩藩の反乱を予想して火砲の準備をさせておいたことを指している。
この19世紀は、欧米列強が帝国主義を露わにして、なりふり構わず領土拡張を目指した世紀であった。東南アジアを次々に植民地化してきた欧米諸国はさらに北上する姿勢を見せており、加えて当時、徐々に勢力を伸ばしてきていた帝政ロシアが、北海道と朝鮮半島のすぐ北のサハリン、ウラジオストクまで南下してきていた。ロシアの勢力が朝鮮半島に及ぶのを防ぐため、日本は朝鮮を日本のような近代国家として自立させたうえで同盟を結ぶことを考えた。しかし、その朝鮮を長年属国としていた清国がこれを黙認するはずもなく、遂に「日清戦争」(1894〜1895年)が勃発する。日本は辛うじて勝利したが、ロシア帝国の朝鮮半島への野望は止まらなかった。
この帝政ロシアの南下を何とか抑えなければ、朝鮮どころか日本そのものもロシアに併呑されてしまいかねない。苦渋の決断で、日清戦争の10年後には、日本は日露戦争(1904‐1905年)に突入した。勝ち目のない戦争と思われていたが、奇跡的に、この戦争でも日本は勝った。しかし、この勝利に自信を得た日本帝国は、その後、欧米の「膨張主義」を妄想し始めるようになる。朝鮮を併合し、満州に進出して傀儡政権を樹立した。中国を侵略して欧米の利権と衝突し、遂には太平洋戦争へ突き進んでしまったのである。そして、日本は破滅した。大阪も、空爆で焼け野原が広がり、この大阪城のまわりも、「鉄という鉄が熔け、人という人が鬼籍に入った」のである。この敗戦で、大阪城は、「三度目の業火を見た」。
大阪城の最初の「業火」は、いうまでもなく、1615年(慶長20年)の大坂夏の陣で大坂城が落城した時である。豊臣氏の滅亡後、徳川幕府は大坂を幕府直轄領として、大坂城下の町の復興と共に、豊臣色を払拭する形で大坂城の再建にとりかかり、1629年(寛永6年)に完成させた。2度目の「業火」は、慶応4年(1868年)、旧幕府軍の鳥羽・伏見の戦いの敗北によって慶喜は船で江戸へ退却し、大坂城が新政府軍に開け渡された時である。この前後の混乱のうちに出火し、御殿や外堀四、五、七番櫓など城内の建造物のほとんどが焼失した。1928年(昭和3年)に、昭和天皇の即位記念事業として再建工事が進められた、1931年に完成している。そして3度目の「業火」が、太平洋戦争中の米軍の爆撃によるものであった。
特に終戦前日の1945年8月14日の空襲は、1トン爆弾が多数投下されて大阪城が壊滅的な被害を受けたのみならず、近隣の京橋駅も巻き添えとなり、避難していた乗客に多数の死傷者が出た。大阪城は戦後米軍に接収されていたが、1948年(昭和23年)にその接収が解除されてからは、1950年(昭和25年)から、本格的な再建作業が開始された。それが、現在の大阪城である。いま、大阪城公園駅に降り立つと、その大阪城が目の前に聳えている。この城が耐えてきた400年の有為転変の歴史に思いを馳せる時、特に私のような、子どもの時からその雄姿に親しんできた者にとっては、なにがしかの感慨を抑えることができない。司馬遼太郎は、この長文の大阪への想いを次のようなことばで結んだ。
悲しみは、この街に似合わない。
ただ、思うべきである。とくに春、この駅に立ち、風に乗る万緑の芽の香に包まれるとき、ひそかに、石垣をとりまく樹々の発しつづける多重な信号を感応すべきであろう。その感応があるかぎり、この駅に立つひとびとはすでに祝われてある。日々のいのち満ち、誤りあることが、決してない。
太平洋戦争敗戦後の大阪城周辺には一面に焼け野原が広がっていた。特にこの駅のあたりから隣り駅の「森之宮」にかけては、爆撃で破壊された軍需工場群の鉄骨の残骸がそのまま2年も3年も放置されていて、私はその情景を電車の窓から見るたびに戦争の悲惨さを味わさせられていた。戦後の極端な食糧不足のなかで、食べられる雑草の種類などを学校で教わりながら、このあたりを雑草を集めて歩き回ったこともある。今でこそ、大阪城は美しく整備され、その周辺には、ホテルや商社の高層ビルや優雅なマンションなどが林立しているが、この地には、生と死と、喜びと悲しみと、そして人間の賢さや愚かさが織りなしてきた栄枯盛衰の歴史が深く沁み込んでいる。それが、大坂城の「石垣をとりまく樹々」がひそかに発しつづける「多重な信号」なのであろう。私たちはここに立つとき、その「多重な信号」に、感応すべきなのである。それは、この土地の歴史からも学ぶということであろう。学ぶことによって人々は「祝われる」。司馬遼太郎は、自分が終生愛してやまなかったこの大阪の街とそこに生まれ命を育んできた人々への深い思いを、この最後の一行に籠めようとしていたにちがいない。
流星のように消え去った愛の人 (2018.01.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.117 ―
尾崎 秀実(おざき ほつみ、1901年(明治34年)4月29日 - 1944年(昭和19年)11月7日)は一高、東大を卒業後大学院に進み、その後、朝日新聞の記者になった。上海特派員を勤めたりしたが、1938年に退社して、第1次近衛内閣の内閣嘱託となる。同時に、近衛主催の政治勉強会「朝食会」にも参加するようになり、この関係は、第2次近衛内閣、第3次近衛内閣まで続いた。近衛文麿政権のブレーンとして、政界・言論界に重要な地位を占め、軍部とも独自の関係を持ち、日中戦争(支那事変)から太平洋戦争(大東亜戦争)開戦直前まで政治の最上層部・中枢と接触し国政に影響を与えた。その間、ソ連軍のスパイとして名高いリヒャルト・ゾルゲが主導するスパイ組織に関係し、国家の機密情報を漏らしたりしたが1941年に「ゾルゲ事件」が発覚して逮捕され、裁判の結果、巣鴨プリズンで絞首刑となった。親しい友人に犬養健、西園寺公一などがおり、ゾルゲ事件に関する著作を多く出している作家・文芸評論家の尾崎秀樹は異母弟にあたる。
この事件のことは、太平洋戦争敗戦後の日本で大きく取り上げられ、『愛情はふる星の如く』(岩波書店、現代新書)などで、一般にもひろく知られるようになった。中国問題の専門家として著名であり、近衛政権のブレーンでもあった尾崎が、なぜスパイ行為を働いたのか。当時から、いろいろと取り沙汰されていたが、それについては、一高、東大時代からの尾崎の親友であった松本慎一の手記「尾崎秀実について」(前掲書、pp.406-419)に詳しい。尾崎を逮捕した検察当局は、尾崎が共産主義に基づく信念のもとにスパイを行ったというようなことはなかなか信じようとはしなかった。信念のためではなく、よくあるような金銭の誘惑のために国家機密を漏らしたのだと考えようとした。しかし、いくら調べても尾崎は金銭的なものは誰からも何一つ受け取っていなかったことが明らかになった。松本慎一は、尾崎が国家機密を漏らした真意について次のように書いている。
《だが彼が金銭のためにではなく、その信念のゆえに、国家機密を外国人に洩したということは事実であろうか。
ある人々はこのことをも否定する。彼等は尾崎・ゾルゲ事件をもって、もっぱら近衛内閣を打倒し対米戦争を開始するための軍閥の陰謀に外ならぬと主張する。尾崎が国家機密を洩したことがあるにせよ、それは過失のためであって、彼の故意にいでたのではない。尾崎は軍閥の陰謀の憐れむべき犠牲者に過ぎない。彼は戦争を防止しようとはしていたが外国人と協力してそうしようとしていたわけではない。――これらの善良な人々はこういう風に考え、それゆえに尾崎に尊敬と同情の念とを抱いている。》 (同書、p.410)
松本は、しかし、この見解は正しくないという。この事件は、なるほど軍閥によって利用された。そして第三次近衛内閣打倒の陰謀にも巧妙に使用された。この事件の裁判が、軍閥の干渉と圧迫下に行われたのも確かである。「だが事件は軍閥がでっちあげた虚構なのではない。尾崎が国内の政治・経済ないし軍事上の秘密をゾルゲに通報したことは事実なのである。それも過失によるのではない。明らかに彼はそうしようと思って、そうしたのである」と松本は述べている。それならば、尾崎は、やはり、祖国を売ったことになるのではないか? もしそうだとすれば、われわれは彼に対して抱いている敬意と同情とを訂正しなければならないのではないか? このような当然起こりうる疑問に対して、松本は、次のように否定する。
《このような人たちに対して、私はいわねばならない。もしも祖国という語が帝国主義日本、軍国日本を指しているとすれば、たしかに尾崎は祖国を売ったに相違ない。そのような日本が滅ぶことを尾崎は願っていたし、そのためにこそ行動したのだから。だがもしも祖国の語が日本国民の圧倒的大部分である勤労大衆そのものを指しているとすれば、尾崎は断じて祖国を売りはしなかった。それどころか、彼は祖国を救うために、祖国の繁栄のために、彼の命を賭けて行動したのである。もしもわれわれが真の祖国を愛しているとすれば、われわれは彼がその祖国のために捧げた犠牲を深い感謝をもって受けとらねばならぬのである、と。》(同書、p.412)
戦争で壊滅的な打撃を受け、戦後の窮迫時代を迎えた中で中学、高校を過ごした私にとっても、この「祖国」とは何か、は深く考えさせられる問題であった。私が小学校に入学した頃には、中国を侵略し始めた日本軍による盧溝橋事件があり、やがて「支那事変」が始まった。学校では、前線の軍人へ送る慰問文に、意味も分からず中国人を侮蔑する言葉を並べ、「蒋介石の首をとってきてください」などと書かされていた。小学校5年生の時には太平洋戦争が始まった。「鬼畜米英」ということばが氾濫し、中学に入ってからは、軍事教練で、チャーチルとルーズベルトの大きな似顔絵を銃剣で突き刺す訓練が繰り返された。そして、戦争に負けると、今度は「鬼畜米英」が、「民主主義の旗頭」としてもてはやされた。そのような戦後の風潮の中で明らかにされたのが、この尾崎のスパイ事件であった。事件の真相を伝えようとする松本の文は、さらにこう続く。
《軍閥は帝国の国防は危機に陥ったがゆえに敢然蹴起する外ないと称して、満洲や支那大陸の侵略を開始した。実際は中国やソ連が外からの侵略に対し、徐々にまたは急速に、その国防を強化しつつあっただけの話で、日本が侵略を受ける心配は毛頭なかったのであるが、国民は軍閥に追随した。軍閥や官僚は日本経済は破滅の淵に瀕していると称して、大陸における強奪を開始した。日本の資本主義が窮状にあったことは事実であるが、それからの血路を戦争に求めることが、日本国民の利益に反することは、支那事変の経過を見ただけでも明らかである。この期間中に、なるほど、財閥や軍閥や、軍閥と結ぶ一部の官僚や浪人どもは、支那大陸で巨富を獲得した。アヘン成金という言葉が流行したほど、麻酔剤の密輸で儲けたものもあった。しかし国民生活は年と共に窮乏を加えたのみであった。それにもかかわらず、国民は軍閥に追随した。》(同書、p.413)
尾崎は、父が台湾総督府の後藤新平の招きを受け、台湾日日新聞社漢文部主筆として赴任したことから、生まれて間もなく台湾へ移住し、一高に入学するまでは、台北第一中学校(現台北市立建国高級中学)に在学している。大学時代までは、共産主義とは全く無縁であったという。東大卒業後は、特派員として上海に居住していたこともあり、中国問題には深い洞察と関心を持つようになった。日本の軍閥や官僚の、中国におけるこのような強奪・侵略行為をつぶさに見ていて何が正義であり、何が欺瞞であるかについても彼は正当に判断できる視座と見識を備えるようにもなった。あの当時、家を焼かれ財を失い無数の生命を犠牲にしても、それが祖国を愛する所以であると考えていた一般の庶民こそ、哀れであったというほかはない。松本は、彼の手記の中で、最後に尾崎の真意の核心に触れる。彼は、こう書いている。
《このような事態にあって、真に国民の福祉を念願する真の愛国者は、何を為すべきであったか。軍閥の戦争宣伝を粉砕し、国民に彼等の真の利益を守る途を指示し、大衆行動をもって戦争を防止することが、愛国者の常道的な進路であったろう。だがその途を歩んだ一切の進歩主義者、平和主義者が投獄せられ、全日本が軍閥官僚の専制の掌中に帰した後では、かかる進路を歩むことはできなかった。専制する軍閥官僚の支配体制そのものの内部に侵入し、これを内から突きくずすか、それとも巷に隠れ、反戦主義の影響を少しでも拡大することに満足して、時機の到来を待つか――
途は二つしかなかった。積極的で勇敢で有能なものだけが、その前者を選ぶことができた。尾崎は実にその最大の一人だったのである。》(同書、p.414)
尾崎は、このようにして、「真の愛国者」の道を選んだ。そして、1944年(昭和19年)11月7日に、国防保安法違反、軍機保護法違反、治安維持法違反により巣鴨拘置所で絞首刑に処せられたのである。処刑される前に、尾崎は事件の弁護を担当してくれた竹内金太郎弁護士宛に遺書を残している。処刑後の自分の遺体の処置、葬儀、墓などの問題や、妻と高校生の娘への気遣いを述べているほか、「大きく眼を開いてこの時代を見よ」と、このようにも書いている。
《・・・・・私の最後の言葉をもう一度繰り返したい。「大きく眼を開いてこの時代を見よ」と。真に時代を洞見するならば、もはや人を羨む必要もなく、また我が家の不幸を嘆くにも当らないであろう。時代を見、時代の理解に徹して行ってくれることは、私の心に最も近づいてくれる所以なのだ、これこそは私に対する最大の供養であると、どうぞお伝え下さい。
この私の切なる叫びが幾分でも妻子の心にとどくならば私は以て瞑します。これ以上何の喜びがありましょう。》(同書、p.397)
この尾崎が獄中から家族へ宛てて書いた書簡集『愛情はふる星の如く』は、敗戦後間もなくの日本でベストセラーになった。この本は広く読まれ続けて版を重ねた。尾崎の友人たちは、尾崎がスパイで処刑されたということで、世間の冷たい風当たりを予想していたのだが、その予想は外れた。二年たっても、三年たっても一般の人々の家族に対する好意は少しも減らなかった。思想的には全く反対の立場の人たちでさえ、暇をつくっては見舞に訪れ、何くれとなく力添えをしてくれていたという。それだけ、尾崎の手紙を読んだ人々の間では感動が広がっていたのであろう。この書簡集のなかには、尾崎が逮捕されて以来、3年目になろうとする1944年(昭和19年)10月7日に、妻の英子に対して「その記念日を祝ってほしい」と書かれた次のような手紙がある。
《・・・・・・僕が祝ってほしいと云うのは、この3年の流れ去った月日がこの僕にとってどんなに貴重な有難いものであったかを心から思うからである。この年月があったからこそ、今日僕は始めて人生の真意義を覚り、かくも静かにかつ楽しく日を送ることも出来るようになったのだ。もしもこの異常なる月日が無かったなら、僕は毎日ただ怱忙の裡にあくせくと日を送ってしまったことだろうと思う。僕の一生はもしも僕が別の道を行くならば、恐らくは社会的には高名、栄位をかち得られたことであろう。しかし人間として今日僕の立っているごとき確乎たる足場に立つことは遂に出来なかったことは明らかだ。
僕は人生の意義を知り、生命の正当なあるがままの姿に徹し、社会と、親しきものへの愛情を限りなく深めるとともにまた純化することも出来た。そこにこそ我々3人のものの永遠に生きる道をも発見し得たのだと、僕はひそかに感じている。だから僕のために祝ってくれることは、実は我々3人のものの共通なよろこびであると私は確信しているのだ。今日このことをお前たちにほんとに分らせることは無理だと思う。すべて冷暖自知あるのみだから。しかしおぼろげには分ってくれたものと思う。僕が決して無理をしたり、頑張って一人こんなことを云っているのでないということを。》(同書、pp.371-372)
尾崎はこの一か月後、11月7日に東京拘置所の絞首台で44年の生涯を閉じたのだが、彼の抱いていた透徹した死生観には心を打たれる。尾崎は、自分の死を十分に認識していたはずであるが、死刑執行日は当日にならないと知らされないから、それが一か月後に迫っていることは、彼はもちろん知らなかった。太平洋戦争も、その年の6月15日には日本軍のサイパン島守備隊3万人が全滅し、8月10日にはグアム島守備隊の1万8千人が全滅している。最高戦争指導者会議で、「戦局は重大段階」であると、徹底抗戦を打ち出していたことなども、獄中の尾崎は知らなかったであろう。尾崎が打倒を目指していた日本帝国主義はいまや崩壊に瀕していた。それを知らぬまま、この手紙を書いた10日後の手紙では、「とにかく私は社会的にはとっくに死んだ身です」といい、処刑が近いであろうことを予想して次のように続けている。
《・・・・・・満三年、既に余計に充分生き過ぎたようです。私は今、人生も自分の運命も実によくはっきりと洞見し得たようであります。生死は既に越えています。目下健康も保ち得ていますし、何よりも気力が充ち満ちておりますから、最後のことに対しても少しもお前たちは心配する必要はないことです。僕がどんなにしっかりした足どりでその場にのぞむか、ほんとは見せたいくらいです。(僕はこの手紙をほほえみながら静かに書いています。こうした断固たる言葉を使ったのは今日が始めてです。その自信は前からありましたが、大きな問題ですからよくよく見きわめた上でなくては虚勢になってはならないと思って控えていたのです。)
》(同書、p.375)
こうして、尾崎秀実は、従容として絞首台の死を受け入れていった。一高、東大以来の終生の親友であった松本慎一は、尾崎が「上は総理大臣から下は女中さんの相談相手になった」というある友人の批評を紹介しながら、「尾崎は愛情に富んだ男であった。彼は多くの優れた才能をもち、私はそれらを総合して尾崎は『偉大』と呼ぶことのできる極めて稀な人間の一人であった」と、その手記の中で述べている。そして、「尾崎は流星のごとくに現れ、流星のごとくに消え去った。だが、それは愛の星であった。この星のゆくところ、人々の胸には愛の灯が点ぜられた」と、締めくくっている。この松本の表現を借りて、私もこの小稿のタイトルを「流星の如く消え去った愛の人」とした。
シルバー・バーチのテレビ講演 (2018.03.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.118 ―
シルバー・バーチは、1920年代から半世紀にわたる交霊会で霊的真理を述べ伝えてきたが、講演という形で、特定のグループに対して、教えを説いたこともある。そのうち、国際スピリチュアリスト連盟の総会での講演、英国心霊治療家連盟の評議会員に対する講演、大英心霊協会における講演等は、このホームページの「学びの栞」(A-40)に全文を載せている。これらの講演についての質疑応答も、付け加えておいた。これらとは別に、ある日の交霊会で、「もしスピリチュアルリズムについてテレビで講演することになったらどういうことを話されますか」と質問が出されたことがあった。テレビ講演であれば、視聴者は、スピリチュアリズムについては馴染みのない一般の大衆を想定していると考えてよいであろう。それに対して、シルバー・バーチはすかさず次のように答えた。その五つのパラグラフから成る簡潔な内容をここで取り上げておきたい。(『霊訓(3)』pp76-78)
まず、最初に、シルバー・バーチはこう切り出した。
「私はまず地上の人たちから“死者”と呼ばれている者の一人であることを述べてから、しかし、地上の数々の信仰がことごとく誤りの上に築かれていることを説明致します。生命に死はなく永遠なる生命力の一部であるが故に不滅であることを説きます。私は視聴者に、これまで受け継いできた偏見に基づく概念のすべてをひとまず脇へ置いて、死後存続の問題と虚心坦懐に取り組んで真実のみを求める態度を要請いたします。寛容的精神と厚意をもって臨み、一方、他人がどう述べているからということで迷わされることなく、自分みずからの判断で真理を求めるように訴えます。そして世界中の識者の中から、いわゆる死者と話を交わした実際の体験によって死後の生命を信じるに至った人の名前を幾つか紹介します。そして私自身に関しては、私もかつて遠い昔に地上生活の寿命を割り当てられ、それを完うして、一たんベールの彼方に去ったのち、この暗い地上へ一条の光をもたらし久しく埋もれたままの霊的真理を説くために再び地上へ戻る決心をしたことを述べます。」
シルバー・バーチはほぼ三千年前にこの世の生を終えて霊界へ移った。イエスキリストよりほぼ一千年前、釈迦より五百年前ということになる。三千年前にこの世に生きたそのシルバー・バーチが、現在も霊界で生き続けて、視聴者にこのように話しかけると言っている。実際に講演する場合には、テレビに映るのは霊媒役のモーリス・バーバネルだから、霊媒の音声器官を借りてシルバー・バーチが話していることも、視聴者には事前に説明しておく必要があるかもしれない。
シルバー・バーチは、初めの間は一時、自分が米国北西部の山脈の中で暮らしていたレッドインディアンであると言っていたことがあった。しかし、その後、実は自分がその本人ではなくて、そのインディアンが地上時代に多彩な心霊能力をもっていたので、シルバー・バーチが使命を帯びて地上に降りてきた際に、その道具として参加してもらったのだと伝えている。
シルバー・バーチのような高位霊になると、波長が違い過ぎて直接この地上とコンタクトを取ることができない。それでこのインディアンも、モーリス・バーバネルとおなじように、地上の教宣のための霊媒になってもらったのであった。「私のように何千年も前に地上を去り、ある一定の霊格を具えるに至った者は、波長のまったく異なる地上圏へ下りてそのレベルで交信することは不可能となります。そのため私は地上において変圧器のような役をしてくれる者、つまりその人を通して波長を上げたり下げたりして交信を可能にしてくれる人を必要としたのです」と、シルバー・バーチは、述べている。(『霊訓 (8)』pp.10-11) このようなことも、霊界の事情に疎い視聴者には、予備知識として与えておくことも考えられる。
この講演では、自己紹介のあと、はじめに、「地上の数々の信仰がことごとく誤りの上に築かれていることを説明致します」と言っているが、この場合、まず念頭に置いているのがキリスト教であろう。キリスト教では、このように「死者」がこの世で生きている人々に向かって講演するようなことは、決して認めようとはしないからである。
また、霊界の存在を認める宗教家でも、死の関門をくぐつた信者は、すべて、言葉では尽くせないほどの喜悦に満ちた輝ける存在となって、一切の悩みと心配と不安から解放されるように説くことがある。このような宗教家の教えも、シルバー・バーチによれば、真相からほど遠く、間違いである。
死んで霊界へ来た人は、初期の段階では肉体を棄てただけで、あとは地上にいた時と少しも変わらない。個性も性格もまったくもとのままである。習性も特性も性癖も地上時代そのままに残している。利己的な人はあい変わらず利己的で、貪欲な人はあい変わらず貪欲である。無知な人はあい変わらず無知のままであり、悩みを抱いていた人はあい変わらず悩んでいる。少なくとも霊的覚醒が起きるまではそうであることを、シルバー・バーチは教えている。(『霊訓(7)』pp.24-25) だからこそ、地上にいる間の霊性向上が求められるのであろう。霊界へ還りさえすれば、誰にでも至福の生活が待っているわけではない。
このように、霊界について述べられることがあっても、霊的真理としては頭を傾げたくなるような教えも少なくはない。だから、シルバー・バーチは、「これまで受け継いできた偏見に基づく概念のすべてをひとまず脇へ置いて、死後存続の問題と虚心坦懐に取り組んで真実のみを求める態度を要請いたします」と言っているのである。
ここでシルバー・バーチが説きたい霊的真理の要諦は、「生命に死はなく永遠なる生命力の一部であるが故に不滅である」ということである。しかし、これはなかなか一般の大衆には直ちには理解し難いに違いない。そこで、シルバー・バーチは、「世界中の識者の中から、いわゆる死者と話を交わした実際の体験によって死後の生命を信じるに至った人の名前を幾つか紹介します」とも言っているのであろう。
予想されるこの場合の視聴者が西欧人であることを考えれば、この「識者」は、世界的に著名な作家のコナン・ドイル、英国第一級の化学者であるウィリアム・クルックス、ダーウィンのライバルである博物学者のアルフレッド・ウォレス、世界的な天文学者のカミーユ・フラマリオンなどをシルバー・バーチは念頭においていたかもしれない。
テレビ講演のシルバー・バーチの話は、このあと、こう続く。
「私はその霊的真理を平易な言葉で概説し、視聴者に対して果たして私の述べたことが理性を反撥させ、あるいは知性を侮辱するものであるか否か聞いてみます。私には何一つ既得の権利を持ち合わせないことを表明します。こんなことを説いてお金をいただかねばならないわけでもなく、仕事を確保しなければならないわけでもありません。私には何一つ得るものはありません。霊界での永い永い生活を体験した末に私が知り得た事を教えに来ているだけです。聞くも聞かぬもあなた方の自由です。」
シルバー・バーチの居る霊界から見れば、地上はたいして魅力ある世界ではない。地上の住民の思念が充満している大気にはおよそ崇高なものはなく、腐敗と堕落の雰囲気が大半を占めている。人間生活全体を暗い影がおおい、霊の光が届くのはほんの少数の人にかぎられている。
その地上の世界に住む人々に、霊界の物的財産が何の役にも立たず、唯一の富が霊的な豊かさである世界、生存競争も略奪も既得権力も無く、弱者が窮地に追いやられることもなく、内在する霊的能力が存分に発揮されるようになる世界のことを理解させるのは、シルバー・バーチにとっても容易なことではないであろう。
それだけに、シルバー・バーチは、自分の言うことが、もし聞く人の理性を反撥させ、あるいは知性を侮辱するのであれば、聞かないで無視してくださいというようなことも、交霊会では言ってきた。
霊界から見る地上は無知の程度がよほどひどいらしい。その無知が生み出す悪弊は見るに耐えかねるので、霊界では、霊的実在についてある程度の知識を地上に普及させることが肝要と決断された。
必要なことは、「実在としての霊」を説くということである。そのためには地上で何世紀にもわたって受け継がれてきた誤解、無知、偏見、虚偽、欺瞞、迷信---要するに人類を暗闇の中に閉じ込めてきた勢力のすべてと闘わねばならない。それを少しでも改善していくのは難事業であるが、それをシルバー・バーチは引き受けて、この地上のロンドンに降りてきたのである。
多くの困難が予想されていた。人類を邪悪の道へ誘い、迷い込ませんとする悪霊であると決めつけられるであろうとの警告も受けたりしてきた。その上、地上の人々を教化していくためには、現代英語を学び、地上世界の生活習慣を知り、文明も理解する必要がある。霊媒を探し出して、自分の意志を伝える訓練もしなければならなかった。すべては人類に対する無償奉仕のためであった。
「こんなことを説いてお金をいただかねばならないわけでもなく、仕事を確保しなければならないわけでもありません。私には何一つ得るものはありません」とシルバー・バーチはいう。「聞くも聞かぬもあなた方の自由です」と、わざわざ付け加えたりもしている。
このあと、第三パラグラフが続く。
「人間は不滅なのです。死は無いのです。あなた方が涙を流して嘆き悲しんでいる時、その人はあなた方のすぐ側に黙って立っている――黙って、というのはあなた方が聞く耳を持たないために聞こえないことを言っているまでです。本当は自分の存在を知らせようとして何度も何度も叫び続けているのです。あなた方こそ死者です。本当の生命の実相を知らずにいるという意味で立派な死者です。神の宇宙の美が見えません。地上という極小の世界のことしか感識していません。すぐ身のまわりに雄大な生命の波が打ち寄せているのです。愛しい人たちはそこに生き続けているのです。そしてその背後には幾重にも高く階層が広がり、測り知れない遠い過去に同じ地上で生活した人々が無数に存在し、その体験から得た叡智を役立てたいと望んでいるのです。」
この世の私たちは霊を伴った肉体なのではなく、肉体を伴った霊である。霊は永遠の存在であるから、死ぬことがない。これが、シルバー・バーチが一番強調している霊的真理であろう。これをここでも繰り返して、「あなた方こそ死者です。本当の生命の実相を知らずにいるという意味で立派な死者です」というシルバー・バーチのことばは痛切である。
これと同じようなことをシルバー・バーチは、「"死"というと人間は恐怖心を抱きます。が実は人間は死んではじめて真に生きることになるのです。あなたがたは自分では立派に生きているつもりでしょうが、私から見れば半ば死んでいるのも同然です。霊的な真実については死人も同然です」とも言っている。(『霊訓(4)』 p.132)
シルバー・バーチはさらに、「死ぬということは決して悲劇ではありません。今その地上で生きていることこそ悲劇です。神の庭が利己主義と強欲という名の雑草で足の踏み場もなくなっている状態こそ悲劇です」とも述べているが、このことばもしっかり噛み締めておきたい。(『霊訓(4)』p.133-134)
霊界の美しさについては、シルバー・バーチの数多くの描写がある。「地上のいかなる天才画家といえども、霊の世界の美しさの一端たりとも地上の絵具では表現できないでしょう。いかなる音楽の天才といえども、天上の音楽の施律のひと節たりとも表現できないでしょう。いかなる名文家といえども、天上の美を地上の言語で綴ることは出来ないでしょう」などと言ってきた。( 『霊訓(4)』p.134) そして、「愛しい人たちはそこに生き続けているのです」と証言しているのである。
テレビ講演の次のパラグラフは、こうである。
「見えないままでいたければ目を閉じ続けられるがよろしい。聞こえないままでいたければ耳を塞ぎ続けるがよろしい。が、賢明なる人間は魂の窓を開き、人生を生き甲斐のあるものにするために勇気づけ指導してくれる莫大な霊の力を認識することになります。あなた方は神の子なのです。その愛と叡智をもって全宇宙を創造した大霊の子供なのです。その大霊との繋がりを強化するのは、あなた方の理解力一つです。もし教会がその邪魔になるのであれば、教会をお棄てになることです。もし邪魔する人間がいれば、その人間と縁を切ることです。もし聖典が障害となっていると気がつかれれば、その聖典を棄て去ることです。」
シルバー・バーチは霊界の高位霊として、霊界の真実をありのままに伝えようとしている。その真実には、一点の曇りもない。それでも、世の中には、悩み苦しみながらも、真理を受け容れる用意ができていない人が決して少なくはない。
シルバー・バーチはおそらく歯がゆいような思いでこう問いかける。「私たちがこれまで説いてきたものを髪の毛一本ほどでも改めたり逸脱したことがあるでしょうか。
どこか私の霊訓で以前と違うところを指摘できるでしょうか。地上の事情が変わったために修正しなければならなくなった箇所が一つでもあるでしょうか。物質界での新しい発見がなされた為に、それまで私どもが絶対ですと断言してきた基本的真理を改正せざるを得なくなったところがあるでしょうか」と。そして、さらに続ける。「そんなことがあるわけがありません。自然法則を取り消したり変更したりしなければならなくなることは決してありません。生命活動に付随する環境条件の全ての可能性を認識しているからです。”生”の現象にも、あなた方のいう"死”の現象にも自然法則やその働きを改めなければならないものは絶対に生じません。私どもが説く真理には死はありません。正真正銘の真理だからです。霊的実在こそ真の実在です。だからこそ存在し続けるのです。永遠に残る叡智の宝石です。受け入れる用意のある者を導く永遠の真実です。」(『霊訓(3)』pp.39-40)
その上で、霊的真理を理解するのに邪魔になるものは、教会でも、聖典でも、人間でも、すべて縁を切って捨てよ、と述べているのである。これらのことばは強く胸に響く。
このあとが、最後の第五パラグラフである。
「そしてあなた一人の魂の静寂の中に引きこもることです。一切の世間的喧騒を忘れ去ることです。そして身のまわりに澎湃として存在する霊的生命の幽かな、そして霊妙なバイブレイションを感得なさることです。そうすれば人間が物的身体を超越できることを悟られるでしょう。知識に目覚めることで、理解力を開くことです。いつまでも囚人であってはなりません。無知の牢獄から抜け出て、霊的自由の光の中で生きることです。以上の如く私は述べるつもりです。」
ここでは、シルバー・バーチは、世間の喧騒から離れて、一人で魂の静寂の中に引きこもることを勧めている。
なぜ、一人で魂の静寂の中に引きこもるのか。それは、霊的存在として霊界からのエネルギーを受け容れるためである。私たちは、人間として完全な状態で創造されたのではない。ただ、一人の例外もなく、完全性を潜在的に宿している。その完全性を宿しながら不完全から完全へ向かって歩む。それが霊性向上への道であろう。そして、「霊的生命の幽かな、そして霊妙なバイブレイション」を感得するためにも、静寂の中で霊界との融合を図っていかなければならない。そこで、瞑想や精神統一、祈りが必要になってくるのである。
祈りとは、シルバー・バーチによれば、私たちのまわりに存在するより高いエネルギーに波長を合わせる手段である。その行為によってほんの少しの間でも肉体的活動を休止して、精神と霊とを普段より受容性に富んだ状態におくことができる。わずかな時間でも心を静かにしていると、その間に霊界からの高い波長を受け入れることができ、私たちに必要なエネルギーが流れてくる通路が用意されていくことになる。(『霊訓(1)』p.84) 「霊的生命の幽かな、そして霊妙なバイブレイション」というのも、そのような霊的エネルギーのことをいうのであろう。
そして、最後に、このテレビ講演は、「いつまでも囚人であってはなりません。無知の牢獄から抜け出て、霊的自由の光の中で生きることです」で終わることになる。
以上は、もしテレビで講演すれば、という仮定の上でシルバー・バーチが述べようとしていることで、実際にテレビ出演したとすれば、一般大衆を意識して表現も少しは変わっていくこともあるかもしれない。しかし、シルバー・バーチの言わんとするところは明らかである。人は死なない。人は霊的存在であるから、霊界から常に守られている。そのことを意識して、祈りの中で霊的エネルギーを受け容れながら、霊的自由の光の中で生きよ、ということに尽きるであろう。
たいへん有難いことに、この地上で3000年前に生きたというシルバー・バーチは、自分で学んだ現代英語でこのように私たちに語りかけてくれる。1920年代に交霊会が始まったばかりの頃は、シルバー・バーチは英語で多くを語ることができず、それもひどいアクセントだったらしい。当時の英国第一級のジャーナリストといわれたハンネン・スワッハーは、そのシルバー・バーチの英語が、「年をへるにつれて、入神させて語る回数が増えたことも手伝って英語がめきめき上達し、今日ではその素朴で流麗な英語は、私がこれまでに聞いたいかなる演説家もその右に出る者はいないほどである」と絶賛している。(『霊訓 (12)』pp. 6-7)
「文章の世界にシルバー・バーチの言葉に匹敵するものを私は知りません。眼識ある読者ならばそのインスピレーションが間違いなく高い神霊界を始源としていることを認めます。一見すると単純・素朴に思える言葉が時として途方もなく深遠なものを含んでいることがあります。その内部に秘められた意味に気づいて思わず立ち止まり、感嘆と感激に浸ることがあるのです」(『霊訓 (9)』pp.26-27)というような一読者の声もあるが、実際にその肉声を聞いた者は、その荘厳な響きに感涙にむせぶこともあったという。私たちは今日、その肉声も、サイキック・プレス編「Silver Birch Speaks」(ハート出版、2003)などのCDで聞くこともできる。これは現代の奇跡というほかはない。
実際にテレビで放映されたとすると、一般の視聴者でも、聞くべき耳があれば心して聴き、見るべき目があれば、刮目して見たにちがいないと思われるのが、このシルバー・バーチの講演であったであろう。
*(「参考資料」No.8『シルバー・バーチの教え』の中でも、この講演に触れている)
シルバー・バーチの祈りについて (2018.05.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.119 ―
はじめに、シルバー・バーチについて、少し触れておきたい。ある日の交霊会で、集まっていたレギュラー・メンバーに対して、シルバー・バーチは、自分が霊界の高級霊団から派遣され、神界の高級霊からのすべてのエネルギーとインスピレーションを得ているがゆえに、この地上での仕事には自信をもって従事していると述べた。「霊団が指図することを安心して語っていればよいのです。威力と威厳にあふれたスピリットの集団なのです。進化の道程をはるかに高く昇った光り輝く存在です。人類全体の進化の指導に当たっている、その意味での霊格の高いスピリットなのです」と、その霊団についての敬意も披歴している。そして、自分自身について、こう伝えた。
《私自身はまだまだ未熟で、けっして地上の平凡人からも遠くかけ離れた存在ではありません。私にはあなた方の悩みがよく分かります。私はこの仕事を通じて地上生活を永いあいだ味わってまいりました。あなた方お一人お一人と深くつながった生活を送り、抱えておられる悩みや苦しみに深く関わってきました。が、振り返ってみれば、何一つ克服できなかったものがないことも分かります。霊力というのは必要な条件さえ整えば地上に奇跡と思えるようなことを起こしてみせるものです。私たちは地上の存在ではありません。霊の世界の住民です。地上の仕事をするにはあなた方にその手段を提供していただかねばなりません。あなた方は私たちの手であり、私たちのからだです。あなた方が道具を提供する――そして私たちが仕事をする、ということです・・・・・・あなた方は、ついぞ、私の姿をご覧になりませんでした。この霊媒の口を使って語る声でしか私をご存知ないわけです。が、信じてください。私も物事を感じ、知り、そして愛することのできる能力を具えた、実在の人間です。こちらの世界こそ実在の世界であり、地上は実在の世界ではないのです。そのことは地上という惑星を離れるまでは理解できないことかも知れません。》(『霊訓 (9)』pp. 220-225)
このように自分について語ったあと、シルバー・バーチは、「では最後に皆さんと共に、こうして死の淵を隔てた二つの世界の者が幾多の障害を乗り越えて、霊と霊、心と心で一体に結ばれる機会を得たことに対し、神に感謝の祈りを捧げましょう」と言って、つぎのように祈りを捧げた。
《神よ、かたじけなくもあなたは私たちに御力の証を授け給い、私たちが睦み合い求め合って魂に宿れる御力を発揮することを得さしめ給いました。あなたを求めて数知れぬ御子らが無数の曲りくねった道をさ迷っております。幸いにも御心を知り得た私どもは、切望する御子らにそれを知らしめんと努力いたしております。願わくはその志を良しとされ、限りなき御手の存在を知らしめ給い、温かき御胸こそ魂の憩の場なることを知らしめ給わんことをお祈り申し上げます。では、神の御恵みの多からんことを。》(『霊訓 (9)』p. 225)
シルバー・バーチは、このように、交霊会が開かれるたびに神への祈りを繰り返している。交霊会は、凡そ半世紀の間に無数に開かれてきたから、シルバー・バーチの祈りも、それだけ無数にあることになる。そのシルバー・バーチの祈りを改めてここに取り上げてみたい。祈りというのは、私たちにとっても、決して無縁ではない。古今東西を問わず、祈りは、人々の間で日常的なありふれた行為であった。私たちは、神に祈り、仏に祈る。或いは霊界の先人たちや先祖の諸霊に祈る。太陽に祈ったり山岳の威容に祈ったりもする。祈る内容も、世界の平和と安全、人類の進歩と繁栄のようなものから、個人的な商売繁盛、家内平安、病気快癒のようなものに至るまで千差万別である。「ご成功を祈ります」とか、「ご繁栄を祈ります」、「ご健康を祈ります」等々、ほとんど挨拶ことばとしても、気軽に「祈り」を口にする。しかし、ここで改めて考えてみたい。そもそも、
祈りとは何か。私たちはなぜ祈るのであろうか。
シルバー・バーチは、祈りとは、「魂の憧憬と内省のための手段、つまり抑えがたい気持ちを外部へ向けて集中すると同時に、内部に向けて探照の光を当てる行為である」という。そして、それが「われわれのまわりに存在するより高いエネルギーに波長を合わせる手段」であるから、祈るのだと述べている。(『霊訓(7)』p.198) ちょっと難しい表現であるが、要するに、祈りによって私たちはほんの少しの間でも活動を休止して気持ちを鎮め、精神と霊とを普段より受容性に富んだ状態におくことができる。その間により高い波長を受け入れるようになり、本当に必要な霊界からの援助やエネルギーが授けられる通路を用意したことになるのである。
それでは、その祈りは、誰に向けられるべきであろうか。シルバー・バーチは、すべての祈りは、神に向けるべきであるという。「私たちの意志を神の意志と調和させることであり、神とのつながりをより緊密にすること」が祈りの本質である。(『霊訓(2)』p.169) まず、何よりも、自分自身が神に一歩でも近づくように祈る。そして、日常生活において自分と交わる人に分け隔てなく何らかの役に立つことを祈る。自分が愛着を覚える人のみに限って祈ることは、たとえ崇高な動機に発するものであっても、一種の利己主義の色あいを帯びることになるから、本来持っている祈りの力は発揮できないことになる。シルバー・バーチは、「利己的な祈りは、時間と言葉と精神的エネルギーの無駄遣いであるに過ぎません。それらには何の効力もないからです」とさえ言っている。(『霊訓(7)』pp198-199).
この、祈りが効き目があるか、ないかは、私たちにとっては無視できない関心事である。もちろん、本当の祈りとは、いわゆる「ご利益信心」ではない。自分の個人的欲望に駆られて、例えば、地位、名誉、金銭、財産を求めて祈っても、それらが叶えられるはずがないことは理解できる。そのような欲求は、本人の霊性の開発、精神的成長にとってなんのプラスにもならないからである。一方、魂のやむにやまれぬ叫び、霊的活動としての祈り、暗闇に光を求める必死の祈り、万物の背後に控える霊性との融合を求める祈り、そうした祈りに対しては、魂の内省があり、その時の魂の状態そのものがすでに神の救いの手を受け入れる態勢となっている、とシルバー・バーチはいう。(『霊訓(1)』p.170) ただし、そうした祈りでも、時にはあえて無視され、その状態のまま放っておかれることもあることを、シルバー・バーチは、こう述べている。
《こちらからあれこれと手段を講じることがかえって当人にとってプラスにならないという判断があるのです。しかし魂の奥底からの欲求、より多くの知識、より深い悟り、より強いカを求める魂の願望は、自動的に満たされるものです。つまり、その願望が霊的に一種のバイブレーションを引き起こし、そのバイブレーションによって当人の霊的成長に応じた分だけの援助が自動的に引き寄せられます。危険の中にあっての祈りであれば保護のためのエネルギーが引き寄せられ、同時に救急のための霊団が派遣されます。それは血縁関係によってつながっている霊もおれば、愛の絆によって結ばれている類魂もおります。そうした霊たちはみな自分もそうして救われた体験があるので、その要領を心得ております。》
(『霊訓(1)』pp.169-171)
つまり、真剣に祈っても、その祈りが必ずしも、叶えられるわけではない。私たちは、どうしても、この世の刹那的な狭い尺度でものごとを考えがちで、遥かに広大な大宇宙の摂理とか神のみ心には思慮が及ばない。そして、必死に祈っても願いが叶わなかった場合には、「神も仏もあるものか」と思ったりもする。例えば、内村鑑三もかつて、愛する家族の死に直面して、信仰にさえ迷いを来したことがあった。内村は必死に神に祈り、そしてその祈りは遂に聞き入れられずに、家族は苦しみながら死んでいったのである。彼は、愛する者を失って以来数か月間、祈ることさえもやめてしまった。内村は、神はなぜ自分の祈りを聴かれなかったのか、なぜ愛する者の命を奪ったのか、という深刻な疑問に悩み苦しむのである。彼はそれをつぎのように書いている。
《しかれども彼は死せざるものにして余は何時か彼と相会することを得るといえども彼の死は余にとって最大不幸なりしに相違なし、神もし神なれば何故に余の祈祷を聴かざりしや、神は自然の法則に勝つ能わざるか、或は祈祷は無為なるものなるか、或は余の祈祷に熱心足らざりしか、或は余の罪深きが故に聴かれざりしか、或は余を罰せんがためにこの不幸を余に降せしか、これ余の聞かんと欲せし所なり。》(内村鑑三『基督教徒のなぐさめ』岩波文庫、1983、p.19)
苦しみ悩み、理解し、そしてまた懐疑にぶつかる。例えば、キリスト教には数々の奇跡があったはずである。熱心な祈りによって不治の病が治った例も決して少なくはない。それならば、彼が彼の愛する者を死に至らしめたのは、彼の祈りが熱心さに欠けていたからか。もしそうなら、彼は彼の愛する者を彼の不熱心の故に見殺しにしてしまったことにさえなる。しかし、彼は必死に祈ったのである。熱心のあらん限り、祈りに祈ったのである。そして、その祈りは遂に聞き届けられなかった。これはどうしてなのか。内村はそれを突き詰めて考え続け、やがて、次のように信じるようになった。
《ああ神よ、爾は我らの有せざるものを請求せざるなり。余は余の有するだけの熱心を以て祈れり、しかして爾は余の愛する者を取り去れり。父よ、余は信ず、我らの願うことを聴かれしに依て爾を信ずるは易し、聴かれざるに依てなお一層爾に近づくは難し、後者は前者に勝りて爾より特別の恩恵を受けしものなるを、もし我の熱心にして爾の聴かざるが故に挫けんものならば爾必ず我の祈棒を聴かれしならん。》(内村鑑三、前掲書、p.22)
よく言われるように、神は私たちに乗り越えられない試練を与えることは決してない。シルバー・バーチは、「必死に父なる神の加護を求めても、そうした祈りをあえて無視して、その状態のまま放っておくことが実はその祈りに対する最高の回答である場合がよくあります。こちらからあれこれと手段を講じることがかえって当人にとってプラスにならないという判断があるのです」と述べているが、(『霊訓(1)』pp.169-171) この内村の述懐は、そのことを裏書きしている一例であるかもしれない。内村は、愛するものを失うことによって悲嘆に暮れるが、最後には、祈りを聞き届けられなかったことが、神のより深い恩寵であったことに思い至る。そして、「然り、余は万を得て一つを失わず、神も存せり、彼も存せり、国も存せり、自然も存せり、万有は余に取りては彼の失せしが故に改造せられたり」(内村鑑三、前掲書、p.28)と達観するようになった。
この内村の例でも示唆されているように、祈りの有無にかかわらず、私たちの必要なものはすべて神によって知られている。シルバー・バーチは、「大自然の摂理の働きは完璧ですから、その機構の中にあって誰一人、何一つ忘れ去られることは有りえないのです。すべての存在を包摂するように完全な摂理が行きわたっているのです。何一つ、誰一人その外にはみ出ているものはありません。あなたが神に見落とされるということは有りえないのです。どこにいても神の管理下にあり、すべてを包摂する自然の摂理の活動範囲の中にあります」と、確言している。(『霊訓 (11)』p. 115) だから、祈りが聞き届けられなかったからと言って、見捨てられたことにはならない。一生懸命に祈ったとしても、その祈る本人にとって何が一番よいかを判断できるのは神であって祈っている人ではない。結局、祈ることによって受ける援助は、その時点までに祈っている人が到達した精神的ならびに霊的発達段階に応じたものになるということであろう。
シルバー・バーチは、また、祈りとは何かを理解するにはその目的をはっきりさせなければならない、という。ただ単に願いごとを口にしたり決まり文句を繰り返すだけでは何の効果もないと断言する。それを、「テープを再生するみたいに陳腐な言葉を大気中に放送しても耳を傾ける人はいませんし、訴えるカをもった波動を起こすことも出来ません。私たちは型にはまった文句には興味はありません。その文句に誠意が込もっておらず、それを口にする人みずから、内容には無頓着であるのが普通です。永いあいだそれをロボットのように繰り返してきているからです」と言い、「真の祈りにはそれなりの効用があることは事実です。しかしいかなる精神的行為も、身をもって果たさねばならない地上的労苦の代用とはなり得ません」と付け加えている。(『霊訓(3)』p.218)
型にはまった祈りには効果がないというのは、わかるような気がするが、実際には、祈りのことばを繰り返しているうちに、だんだん型にはまった言い方のなっていくことが多いのではないか。例えば、キリスト教でいう「主の祈り」がある。イエス・キリストは、「あなた方の父なる神は、求めない先から、あなたがたに必要なものはご存じなのである」(マタイ6:8)と言っている。そしてイエスは、だから、こう祈りなさい、と祈り方をも教えているのである。聖書のなかで、イエスが祈り方を具体的に述べているのは、つぎのマタイ(6:9‐13)とルカ(11:2‐4)だけで、そこでは、同じ祈りがこう示されている。
《天にいますわれらの父よ、御名があがめられますように。御国がきますように。
みこころが天に行われるとおり、地にも行われますように。
わたしたちの日ごとの食物を、きょうもお与えください。
わたしたちに負債のある者をゆるしましたように、わたしたちの負債をもおゆるしください。
わたしたちを試みに会わせないで、悪しき者からお救いください。》
この「主の祈り」については、シルバー・バーチは、きわめて批判的である。「あのような型にはまった祈りは人類にとって何の益ももたらさないことを断言します」とまで極限している。「単なる形式的行為は、その起原においては宿っていたかも知れない潜在的な力まで奪ってしまいます。儀式の一環としては便利かも知れません。しかし人間にとっては何の益もありません」というのである。はじめの「天にいますわれらの父よ」については、「今のあなた方には、父なる神が天にましますものでないことくらいお判りになるでしょう」と、切り捨てている。「神が完全な摂理である以上、全宇宙、全生命に宿っているものだからです。この宇宙のどこを探しても完璧な法則が働いていない場所は一つとしてありません。神は地獄のどん底だけにいるものではないように、天国の一ばん高い所にだけ鎮座ましますものでもありません。大霊として宇宙全体に普遍的に存在し、宇宙の生命活動の一つひとつとなって顕現しております」とも述べている。(『霊訓(3)』p.220)
シルバー・バーチは、さらには、「”御国の来まさんことを”などと祈る必要はありません。地上天国の時代はいつかは来ます。かならず来るのです。しかしそれがいつ来るかは霊の世界と協力して働いている人たち、一日も早く招来したいと願っている人たちの努力いかんに掛かっております。そういう時代が来ることは間違いないのです。しかしそれを速めるか遅らせるかは、あなた方人間の努力いかんに掛かっているということです」と付け加えている。(『霊訓(3)』p.221)「モーゼの十戒」についても、シルバー・バーチは、「もう時代遅れです。今の時代には別の戒めが必要です」と、突き放している。
一方で、シルバー・バーチは、「知識の領域を少しでも広めようとする努力、病める人を一人でも多く治してあげたいと思う心、死別の悲しみに暮れる人をもっと慰めてあげたいと思う気持、人生に疲れた人があなたという灯台を見つけられるように一層の輝きを増したいという願い、 こうした真摯な祈りが何の反応もなく見過ごされることは絶対にありません」と、折に触れて祈りの大切さを強調している。(『霊訓 (11)』p. 112)「霊的資質を培うほど、それだけ多くの美しさと輝きと壮大さと高潔さと光沢を身につけることになります。それが魂を刺戟して、地上への誕生とともに賜わった遺産である内部の神性をますます発現したいと願う気持ちにさせるのです」と、祈りへの道を説いてもいる。そして、そのシルバー・バーチは、すでに述べたように、交霊会のたびに、高邁な珠玉のような祈りのことばを、よどみなく繰り返してきた。無数のそれらの祈りのことばが、一つとして同じでないことにも私たちは深い畏敬の念を感じずにはいられない。最後に、そのシルバー・バーチの祈りのうちの一つを、つぎに掲げて、この稿のしめくくりにしたい。
《神よ、私たちはあなたの完璧な摂理の背後に秘められた完全なる愛を説き明かさんと努力している者でございます。人類はその太古よりあなたがいかなる存在であるかを想像しながらも、その概念はいつも人間的短所と限界と制約の上に築かれてまいりました。
宇宙の生命活動を律するその霊妙な叡智を人間は幽かながら捉え、それを人間に理解できる言葉で説明せんとしてまいりました。あなたの性格を人間のすべてに共通する弱点と欠点と感情を具えた一個の人間として想像しました。気に入った者には恩寵を与え、気に入らぬ者には憤怒を浴びせる人間味むき出しの神を想像いたしました。その後の進化に伴って人間の知識も進歩いたしましたが、この大宇宙を創造した究極の存在について想像したものは真のあなたの姿には遠く及びません。
無限なる存在を有限なる言葉で表現することは所詮いかなる人間にも不可能なのでございます。あなたの尊厳の神性、あなたの愛と叡智の永遠性は、五つの感覚のみの物質の世界に閉じ込められた人間には真実の理解は不可能なのでございます。
そこで幸にして実在の別の側面を体験させていただいた私たちは、あなたが定められた摂理の存在を説いているところです。すべてを包含し、すべてを律する法則、不変不朽の法則、無数の生命現象に満ちた宇宙における活動を一つとして見逃すことのない法則、すべての自然現象を律する法則、人間生活のすべてを経綸する摂理に目を向けさせようと致しているところでございます。
一宗一派に偏った神の概念を棄て、宇宙がいかなる法則によって支配されているかを理解することによって、そこに連続性と秩序とリズムと調和と完全なバランスの観念が生まれてまいります。一人一人が無限なる組織の中の一部であり、自分一個の生命活動もあなたのご計画の中に組み入れられていることを自覚いたします。
私たちの仕事は人間の霊に宿されているところの、人生に輝きを与えるはずの資質、いまだに未知の分野でありながら莫大な可能性に満ち、その活用によって人間生活に豊かさと生き甲斐、壮厳さと気高さ、人生観を一変させてしまう広大なビジョンと精神的飛躍を与えるところの魂の秘奥を明かすことにあります。
それこそ人間を永遠なるものとつなぐものであり、それこそあなたがお授けくださった神聖なる属性であり、それを開発することが少しでもあなたに近づき、存在の意義を成就し、あなたの遺産を相続することになるものと信じるのでございます。
かくのごとく私たちは人間の霊的成長を促す分野に携わる者です。そこが人間がこれまで最も無知であった分野だからでございます。その無知の暗闇を払いのけることによって初めてあなたの真理の光が人類の水先案内となりうるのです。闇の存在はことごとく消え去り、あなたの御子たちは、あなたの意図されたとおりに自由に堂々と、神性を宿す者に相応しい生き方に立ち帰ることでございましょう。
ここに、ひたすらに人類のためをのみ願うあなたの僕インディアンの祈りを捧げ奉ります。》 (『霊訓(2)』pp.212‐214)
シルバー・バーチとは誰か (2018.07.01)
― 生活と文化をめぐる随想 No.120 ―
シルバー・バーチは3千年前に死んで霊界へ移ったといわれる高位霊である。3千年の間に、いろいろと修行を続けながら、霊的の界層を一段また一段と上っていった。界層といっても、一つ一つが仕切られているわけではない。霊的な程度の差があり、それぞれの段階にはその環境条件にふさわしい者が存在するということである。「霊的に向上進化すると、それまでの界層を後にして次の一段と高い界層へ溶け込んでいきます。それは階段が限りなく続く長い長い一本の梯子のようなものです」と、シルバー・バーチは言っている。(『シルバー・バーチの霊訓(3)』潮文社、1986、p.153 ― 以下、『霊訓』と略記する)
霊界から見るとこの地上世界は、あまり魅力ある世界ではないようである。地上の住民から発せられる思念が充満している大気にはおよそ崇高なものは見られず、腐敗と堕落の雰囲気が大半を占めている。人間生活全体を暗い影がおおい、霊の光が届くのはほんの少数の人に限られているらしい。これに対して霊界は、真の生きる喜びにあふれて全てが光り輝く色彩豊かな世界である。(『霊訓(2)』p.158) そこでは、経済問題は存在せず、お金には何の値値もなく、物的財産も何の役にも立たない。生存競争も略奪も既得権力も無く、弱者が窮地に追いやられることもない。霊的な豊かさだけが唯一の富とされる世界で、一人ひとりはあるがままの姿をさらけだして生きていくことになる。(『霊訓(3)』pp.153‐154)
そういう霊界に、何百年、あるいは何千年も生きていると、物質界から遠く離れていき、やがて、物質界には二度と接触する気持が起きなくなる段階に至るという。しかし、そういうなかで、シルバー・バーチには、この地上で、人生に迷い、生きることに疲れ果てている人類に進むべき方向を示唆し、魂を鼓舞するための使命が霊界の上層部から示された。それは、さまざまな妨害や迫害が予想された大事業であることはわかっていたが、シルバー・バーチはその使命を引き受けてこの地上に戻ってきたのであった。1920年代のことである。
そのシルバー・バーチがイギリスのロンドンで霊界からの使命を遂行するために、まず第一にやらねばならなかったのは、霊媒を探すことであった。シルバー・バーチが霊媒として使ったのは、文筆家でジャーナリストのモーリス・バーバネルである。シルバー・バーチは、彼を胎児のときから選び、生まれてからは、霊媒になるべく導いていったのだという。そのバーバネルは、ロンドンで育って18歳の頃には、様々な講演会へ出かけて反論することを目的とするクラブの一員となっていた。講演者の主張が何であれ、それに反論することで弁舌の腕を磨いていくのである。そのうちに、バーバネルは、初めてスピリチュアリズムに接するようになる。
ある時、数人の友人たちがバーバネルを交霊会なるものに招待したことがあった。バーバネルにとって初めてのことで、彼は大真面目で出席した。ところがそれが終ってから、その「交霊会」は、彼をからかうための悪ふざけであったことがわかった。仕組まれたトリックだったのである。たとえ冗談とは言え、十代のバーバネルは非常に不愉快な思いをさせられ、それからは「スピリチュアリズム」に対し、むしろ反感を抱くようにさえなっていた。そのようなバーバネルを、友人や同僚たちは、スピリチュアリズムに対する反論者として、押し立てるようになった。スピリチュアリズム関連の講演会や交霊会に出かけて行っては、その「欺瞞」を明かそうとしていたのである。しかし、その彼も、やがて、スピリチュアリズムの真実に目覚めていく。その経過を、後にバーバネル自身がこう語っている。少し長いが、以下に引用する。
《ある夜、これといって名の知れた講演者のいない日があった。そこでヘンリー・サンダースという青年がしゃべることになった。彼はスピリチュアリズムについて、彼自身の体験に基づいて話をした。終わると私の同僚が私の方を向いて、例によって反論するよう合図を送った。
ところが、自分でも不思議なのだが、つい最近ニセの交霊会で不愉快な思いをさせられたばかりなのに、その日の私はなぜか反論する気がせず、こうした問題にはそれなりの体験がなくてはならないと述べ、従ってそれをまったく持ち合わせない私の意見では価値がないと思う、と言った。これには出席者一同、驚いたようだった。当然のことながら、その夜は白熱した議論のないまま散会した。
終わるとサンダース氏が私に近づいて来て、“調査研究の体験のない人間には意見を述べる資格はないとのご意見は、あれは本気でおっしゃったのでしょうか。もしも本気でおっしゃったのなら、ご自分でスピリチュアリズムを勉強なさる用意がおありですか”と尋ねた。
“ええ”私はついそう返事をしてしまった。しかし“結論を出すまで六カ月の期間がいると思います”と付け加えた。日記をめくってみると、その六カ月が終わる日付がちゃんと記入してある。もっとも、それから半世紀たった今もなお研究中だが……。
そのことがきっかけで、サンダース氏は私を近くで開かれているホームサークルへ招待してくれた。定められた日時に、私は、当時婚約中で現在妻となっているシルビアを伴って出席した。行ってみると、ひどくむさ苦しいところで、集まっているのはユダヤ人ばかりだった。若い者も老人もいる。あまり好感はもてなかったが、まじめな集会であることは確かだった。
霊媒はブロースタインという中年の女性だった。その女性が入神状態に入り、その口を借りていろんな国籍の霊がしゃべるのだと聞いていた。そして事実そういう現象が起きた。が、私には何の感慨もなかった。少なくとも私の見るかぎりでは、彼女の口を借りてしゃべっているのが“死者”である、ということを得心させる証拠は何一つ見当たらなかった。》(『霊訓 (10)』pp. 215‐217)
おそらく霊界のシルバー・バーチは、このようなバーバネルの動向を具に見ていたであろう。霊媒に不信感を持たせる経験も必要であったのかもしれない。そして、このあと転機が訪れる。バーバネルは、それをこう続けている。
《しかし私には六カ月間勉強するという約束がある。そこで再び同じ交霊会に出席して、同じような現象を見た。ところが会が始まって間もなく、退屈からか疲労からか、私はうっかり“居眠り”をしてしまった。目を覚ますと私はあわてて非礼を詫びた。ところが驚いたことに、“居眠り”をしている間、私がレッドインディアンになっていたことを聞かされた。
それが私の最初の霊媒的入神だった。何をしゃべったかは自分にはまったく分からない。が、聞いたところでは、シルバー・バーチと名乗る霊が、ハスキーでノドの奥から出るような声で、少しだけしゃべったという。その後現在に至るまで、大勢の方々に聞いていただいている。地味ながら人の心に訴える(と皆さんが言って下さる)響きとは似ても似つかぬものだったらしい。
しかし、そのことがきっかけで、私を霊媒とするホームサークルができた。シルバー・バーチも、回を重ねるごとに私の身体のコントロールがうまくなっていった。コントロールするということは、シルバー・バーチの個性と私の個性とが融合することであるが、それがピッタリうまく行くようになるまでには、何段階もの意識上の変化を体験した。始めのうち私は入神状態にあまり好感を抱かなかった。それは多分に、私の身体を使っての言動が私自身に分からないのは不当だ、という生意気な考えのせいであったろう。》(『霊訓 (10)』pp. 217‐218)
こうして、モーリス・バーバネルを霊媒とするシルバー・バーチの地上世界における教化活動が始められるようになった。それに非常な関心を示すようになったのが、当時のイギリスの著名なジャーナリストであり、「新聞界の法皇」といわれていたハンネン・スワッハーである。彼は1924年に初めてシルバー・バーチの霊言に触れて以来、その熱心な信奉者になっていた。霊媒のバーバネルも、その頃、『サイキック・ニューズ』紙の編集長であった。スワッハーは、これほどの霊訓をひとにぎりの人間しか聞けないのは勿体ないから、バーバネルに、シルバー・バーチのことばを彼が編集する『サイキック・ニューズ』紙に連載するように勧めたのである。バーバネルは、反対した。自分が編集している新聞に自分の霊現象の記事を載せるのはまずい、という理由からである。しかし、ずいぶん議論したあげくに、編集長のバーバネルが霊媒であることを公表しないことを条件に、いわば匿名で、シルバー・バーチの霊訓を『サイキック・ニューズ』紙に連載することになった。
この連載にあたっては、もう一つ問題があった。現在シルバー・バーチと呼んでいる支配霊は、当初は別のニック・ネームで呼ばれていて、それは公的な場で使用するには不適当なので、支配霊自身に何かいい呼び名を考えてもらわねばならなくなった。そこで選ばれたのが「シルバー・バーチ」(Silver
Birch)という名前だった。不思議なことに、そう決まった翌朝、バーバネルの事務所にスコットランドから氏名も住所もない一通の封書が届いた。開けてみると銀色の樺の木(シルバー・バーチ)
の絵はがきが入っていたという。こうして、その後半世紀にも及ぶ、長いシルバー・バーチの交霊会が続けられることになったのである。それを、バーバネルは、こう書いている。
《その頃から私の交霊会は、「ハンネン・スワッハー・ホームサークル」と呼ばれるようになり、スワッハー亡きあと今なおそう呼ばれているが、同時にその会での霊言が『サイキック・ニューズ』紙に毎週定期的に掲載されるようになった。当然のことながら、霊媒は一体誰かという詮索がしきりに為されたが、かなりの期間秘密にされていた。しかし顔の広いスワッハーが次々と著名人を招待するので、私はいつまでも隠し通せるものではないと観念し、ある日を期して、ついに事実を公表する記事を掲載したのだった。》(『霊訓 (10)』p. 220)
シルバー・バーチは、この地上で布教活動を行うためには、このモーリス・バーバネルを霊媒として使っていくことに習熟していくほか、英語を学び、生活習慣や現代文明も理解していく必要があった。シルバー・バーチは、「私はあなた方の言語、あなた方の習性、あなた方の慣習を永い年月をかけて勉強しました。それは私たちの世界ではごく当り前の生活原理である"協調″の一環です。言わば互譲精神を実践したまでです」と言っている。(『霊訓(3)』p.211) このシルバー・バーチの英語については、ハンネン・スワッハーも、「当時はシルバー・バーチは多くを語ることができず、それもひどいアクセントだった。それが年をへるにつれて、入神させて語る回数が増えたことも手伝って英語がめきめき上達し、今日ではその素朴で流麗な英語は、私がこれまでに聞いたいかなる演説家もその右に出る者はいないほどである」と称賛している。(『霊訓 (12)』p. 6) そのスワッハーは、交霊会についても、つぎのように述べている。
《シルバー・バーチを支配霊とする私のホームサークルは、毎週金曜日の夜に開かれる。その霊言は定期的にサイキックニュ-ズ紙に掲載される。その版権が私のホームサークルに所属するのは、サークルとしての私用を目的としてのことではなく、これを世界中に広めるためである。今ではシルバー・バーチは地上のいかなる説教者よりも多くのフアンをもつに至っている。あらゆる国、あらゆる民族、あらゆる肌色の人種の人々に敬愛されている。
しかし実を言うと、いったん活字になってしまうと、シルバー・バーチの言葉もその崇高さ、その温かさ、その威厳に満ちた雰囲気の片鱗しか伝えることができない。交霊会の出席者は思わず感涙にむせぶことすらあるのである。シルバー・バーチがどんなに謙虚にしゃべっても、高貴にして偉大なる霊の前にいることをひしひしと感じる。決して人を諌めない。そして絶対に人の悪口を言わない。
・・・・・・もっともシルバー・バーチは理屈をこね回すだけの議論には耳を貸さない。人間は何らかの仕事をするためにこの地上へ来ているのだということを繰り返し説き、宗教とは
“人のために自分を役立てること” と単純明快に定義する。そして、お粗末とはいえわれわれは、今この地上にあって戦争に終止符を打ち飢餓を食い止め、神の恩寵が世界中にふんだんに行きわたる時代を招来するための、霊の道具であることを力説する。
“われわれが忠誠を捧げるのは一つの教義でもなく一冊の書物でもなく一個の教会でもなく、生命の大霊とその永遠不変の摂理である” ― これがシルバー・バーチの終始一貫して変わらぬ基本姿勢である。》(『霊訓 (12)』pp. 8‐10)
このようにして、シルバー・バーチの教えが多くの人々に感動を与えるようになり、その令名が世界に広がっていくにつれ、シルバー・バーチとは誰か、ということが人々の大きな関心事になっていった。シルバー・バーチは、はじめはインディアンであるとされていたが、それは、シルバー・バーチの霊格が高すぎるために、この地上との波長を合わせるための中継として一人のインデイアンの幽体を使用していたからであった。しかし、本当はインディアンではない。そのことについては、シルバー・バーチも、こう語ったことがある。
《私は実はインディアンではありません。あるインディアンの幽体を使用しているだけです。それは、そのインディアンが地上時代に多彩な心霊能力をもっていたからで、私がこのたびの使命にたずさわるように要請された際に、その道具として参加してもらったわけです。私自身の地上生活はこのインディアンよりはるかに古い時代にさかのぼります。
このインディアンも、バーバネルが私の霊媒であるのとまったく同じ意味において私の霊媒なのです。私のように何千年も前に地上を去り、ある一定の霊格を具えるに至った者は、波長のまったく異なる地上圏へ下りてそのレベルで交信することは不可能となります。そのため私は地上において変圧器のような役をしてくれる者、つまりその人を通して波長を上げたり下げたりして交信を可能にしてくれる人を必要としたのです。》(『霊訓 (8)』pp.10)
この「シルバー・バーチ」という名前については、同様のことをシルバー・バーチがつぎのように語ったこともあった。ここでも、シルバー・バーチというのはかつて地上に住んだインディアンの名前で、自分はそのシルバー・バーチではないと答えて、この地上での使命についても言及している。
《私の名はシルバーバ-チではありません。これは私がバイブレーションを下げて地上世界とコンタクトすることを可能にしてくれる一種の変圧器の役目をしている、かつて地上でインディアンだった霊の名前です。いずれにせよ名前はどうでもよいことです。私に関するかぎり名前は何の価値もありません。これまで一度も地上時代の名を明かしたことはありません。地上時代の私はインディアンではありません。このインディアンよりはるかに古い時代の、別の民族の者です。霊的進化の末に二度と地上世界へ生身に宿って戻ってくる必要のない段階にまで到達いたしました。霊界の上層部には〝神庁″とでも呼ぶべきものが存在します。それに所属するのは格別に進化を遂げた霊、高級神霊です。その仕事は立案された創造進化の計画を円満に進展させることです。その神庁からこの私にお呼びが掛かり、これまでの進化で私が得たものを一時お預けにして、可能なかぎり地上圏に近づき、その高級神霊たちのメッセンジャーとして働いてくれないかとの要請を受けたのです。私の役目はその指導霊たちの教えを取り次ぎ、一人でも多くの受け入れる用意のできた人間にお届けすることです。私は喜んでその要請をお引き受けしました。それが半世紀近くにもわたってたずさわってきた私の使命だったのです。》(『霊訓 (12)』pp. 234‐235)
それでは、地上でのシルバー・バーチは、誰であったか。すでに触れられているように、交霊会では何度かその実名を訊かれたことがあったが、シルバー・バーチは、「私は人物には関心がないのです。私がこの霊媒とは別個の存在であることだけ分かっていただければ、私が地上で誰であったかはもはや申し上げる必要はないと思います」と答えて最後まで明かさなかった。「私の地上の名前などはどうでもいいことです。私の言っていることがなるほどと納得できれば受け入れて下さい。そんなばかなと思われるのなら信じないでください。それでよろしいのです」などとも言っていたことはよく知られている。また、つぎのように述べたこともあった。
《私は何一つややこしいことは申し上げておりません。難解な教理を説いているわけではありません。自然の摂理がこうなっていて、こういう具合に働くのですと申し上げているだけです。そして私はつねに理性に訴えております。そうした摂理の本当の理解は、それを聞かれた方がなるほどという認識が生まれた時にはじめて得られるのです。何がなんでも信じなさいという態度は私たちの取るところではありません。
霊界からのメッセージが届けられて、その霊がいかに立派そうな名をなのっていようと、もしもその言っていることにあなたの理性が反撥し知性が侮辱されているように思われた時は、遠慮なく拒否しなさいと申し上げております。理性によって協力が得られないとしたら、それは指導霊としての資格がないということです。》(『霊訓 (8)』pp.17‐18)
このような、名前よりも説いていることばの内容が重要なのだというシルバー・バーチの主張は、数多くの交霊会で何度も繰り返されてきた。ある時の交霊会で、また、アメリカ人のメンバーから、シルバー・バーチが地上に住んでいたころのの名前を訊かれた時にも、つぎのように答えている。
《かりに私が地上でファラオ(古代エジプトの王)だったと申し上げたところで、何にもならないでしょう。それは地上だけに通用して、霊の世界には通用しない地上的栄光を頂戴することにしかなりません。私たちの世界では地上でどんな肩書き、どんな財産をもっていたかは問題にされません。要はその人生で何を為したかです。
私たちは魂そのものを裁くのです。財産や地位ではありません。魂こそ大切なのです。地上では間違ったことが優先されております。あなた方のお国(アメリカ)では黄金の仔牛(旧約聖書に出てくる黄金の偶像で富の象徴)の崇拝の方が神への信仰心をしのいでおります。圧倒的多数の人間が神よりもマモン(富の神)を崇めております。それが今日のアメリカの数々の問題、困難、争いごとの原因となっております。
私がもしもアリマタヤのヨセフだったとかバプテスマのヨハネだったとか申し上げたら、私の威信が少しでも増すのでしょうか。それともイロコワ族の酋長だったとでも申し上げればご満足いただけるのでしょうか。》(『霊訓 (8)』pp.12‐13)
こうして、地上時代の名前が明かされないまま、1920年代から始まり、1981年に霊媒バーバネルが亡くなるまで、延々50年以上にわたって続けられてきたシルバー・バーチの布教活動は、世界中にひろがって、日本でも近藤千雄氏の翻訳による全12巻の『シルバー・バーチの霊訓』が刊行された。この12巻目の『霊訓』は、総集編だが、その「訳者あとがき」のなかで、近藤氏はこう書いている。
《洋の東西を問わず〝霊言″と名のつくものは数多く存在する。が、シルバー・バーチ(と名のる霊)ほど気取らず、何のてらいもなく、格好もつけず、親しみぶかく語りかけながら、しかも威厳を失わず、そして最後まで自分の地上時代の名前も地位も国家も明かさなかった霊を私は他に知らない。
私は今でも、ふと、一体シルバー・バーチのどこがいいのだろう、と自問することがある。そして、これといって取り立てて挙げられるものがないのに、実際に霊言を読みあるいはカセットを聞くと何とも言えない魅力を覚え、知らぬ間に読み耽り、聞き耽り、いつしか体に熱いものが込み上げてきて涙が頬をつたう。スワッハーも〝序文″の中で述べているが、シルバー・バーチに語りかけられると、姿はバーバネルなのに、思わず感涙にむせぶ者が多かったという。》(『霊訓 (12)』p. 240)
この近藤氏の12巻には含まれていないA.W.Austen編集のTeachings of Silver Birch については、私も英和対訳の形で「霊訓の原文」としてこのホームページで取り上げてきた。その訳文の冒頭にも触れたように、3千年前の古代霊であるシルバー・バーチが現代英語で私たちに語りかけているのは、奇跡としかいいようのない事実であるが、それだけに、その貴重な真理のことばを翻訳によらないで、原文のまま吟味してみることも十分に意味があることと思われたからである。最後に、そのようなシルバー・バーチの珠玉のことばの一つを付け加えて、この稿の締めくくりにしたい。
《組織的宗教は数多く存在しますが、地上の人間にその自我を見出させ、生命の根源である神性を発現させるような理想に沿って生きる、その指針を提供することはできませんでした。何よりもまず“霊性”が日常生活の中で顕著とならないといけません。皆さんの住んでおられる地上というところは、とても暗い世界です。騒乱と暴力沙汰が絶えず、貪欲と妬みに満ちております。大霊の代りに富の神が崇められております。今なお間違った偶像が崇拝の対象とされています。
すでに地上にもたらされている証拠を理性的に判断なされば、生命は本質が霊的なものであるが故に、肉体に死が訪れても決して滅びることはありえないことを得心なさるはずです。物質はただの殻に過ぎません。霊こそ実在です。物質は霊が活力を与えているから存在しているに過ぎません。その生命源である霊が引っ込めは、物質は瓦解してチリに戻ります。が、真の自我である霊は滅びません。霊は永遠です。死ぬということはありえないのです。
死は霊の第二の誕生です。第一の誕生は地上へ生をうけて肉体を通して表現しはじめた時です。第二の誕生はその肉体に別れを告げて霊界へおもむき、無限の進化へ向けての永遠の道を途切れることなく歩み続けはじめた時です。
あなたは死のうにも死ねないのです。生命に死はないのです。不滅の個霊としてのあなたはその肉体の死後も生き続け、あなたという個的存在を構成しているものはすべて存続するという事実を立証するだけの証拠は、すでに揃っております。死後も立派に意識があり、自覚があり、記憶があり、理性を働かせ愛を表現する力が具わっています。愛は神性の一つなのです。
愛はその最高の形においては神々しさを帯びたものとなります。そして、生命と同じく、不滅です。》(『霊訓 (11)』pp. 201‐202)
|