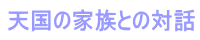
1.『天国の家族との対話』の連載を始めるにあたって
私が『天国からの手紙』の最終章を書き始めた頃、2011年の3月11日にあの東日本大震災が起こりました。この本は、大震災の余波がまだ色濃く残っているなかで、6月に学研パブリッシングから出版されました。それから1年後の2012年6月には、定期検査で私に大腸がんが見つかり、その後の検査で腹部動脈瘤があることもわかりました。6月の末からは、しばらく手術のための入退院を繰り返しています。その頃、私は、それまでに霊的真理を求めて私が辿ってきた足跡をまとめて、新しく
『天国の家族との対話』 を書いていました。講演や小冊子やこのホームページにばらばらに書いたり話したりしてきたものを一冊にしておきたいと思ったからでした。
この『天国の家族との対話』の原稿は出来上がっていますが、まだ未公刊で、これからどこかの出版社で出版されるかどうかも決っていません。このホームページも、そろそろ終わりに近づいてきていると思っていますので、この際、この原稿をホームページの締めくくりの一環として、毎週一回の予定で連載させていただくことにしました。『天国からの手紙』の姉妹編のような形になりますが、関心のある方はご一読いただきたく存じます。なお、原稿は、製本した場合の形にして縦書きで 325ページになります。この連載に際しても、書き加えたりする場合の検索の便を考えて該当部分のページをつけておくことにしました。下記の目次に従って、本文は6月27日から載せていく予定です。(2014.06.20)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
2. 『天国の家族との対話』 本文 (目次)
天国の家族との対話
―生き続けているいのちの確かな証し―
武 本 昌 三 著
いまは亡き愛しい家族の
在りし日の面影を追い求めながら
深い悲嘆の淵に沈んでおられる遺族の方々に
こころを込めてこの一書を捧げる
目 次
はじめに
第一部 無知の闇から真実の光へ
第一章 天国は本当にあるのか
『仏説阿弥陀経』を読む
無知のなかで迷い悩みながら
第二章 なぜ極楽へすぐ行きたいと思えないのか
『歎異抄』に見出した一筋の光
親鸞の信心に教えられる
それでも信じ難いいのちの真理
アメリカ人は死後の世界を信じているか
第三章 霊界から届いた初めてのことば
夢の中で生き続けている妻と子
初めて霊能者を訪ねる
夢に現われた潔典からの伝言
第四章 死後の世界を信じることの難しさ
イエスの復活を信じられなかった弟子たち
復活の奇跡に苦慮した作家の足跡
霊界から届けられた死後の世界の証言
第五章 実証され始めた人の生まれ変わり
退行催眠による生まれ変わりの証明
人は自ら選んで生まれ変わる
ワイス博士の生まれ変わりの証言
第六章 生き続けている妻と長男の命を確認する
真理を受け容れる心の準備
初めてのシッティング
アン・ターナーによる霊言
疑うことのできない霊言の真実
第七章 霊界から送られてきた妻と子からの便り
潔典が誕生日に思い出を語る
この通信はどの程度に正確か
霊界で潔典は何を学んでいるか
第八章 私は何故この世に生まれてあの事件に遭ったか
もう一つのルートによる霊界通信
私がこの世に生まれてきた目的
家族四人が引き裂かれた理由
霊界から長男に導かれて
第九章 東日本大震災後の霊界からの便り
富子と潔典は今どのように生きているか
大震災の犠牲者に霊界ではどう対応したか
アン・ターナーの死とその後の消息
第十章 生と死の次元を越えた父と子の対話
八十年前に実現していた奇跡の通信
通信の相手の確認を求めて
この世での思い出から始まる対話
霊界の生活環境はこの世とどう違うか
第十一章 シルバー・バーチの真理の教え
古代霊からの珠玉のことば
シルバー・バーチの講演
シルバー・バーチの教え
第二部 悲しみの声に応える
一.光へ向かって歩んでいくために(1〜18)
=メールの交換:二〇〇四年七月〜二〇一〇年六月=
1 希望から確信に変わっていく幸せ(来信)
―霊的真実を知ることの素晴らしさ (返信)
2 天国の赤ちゃんからの素敵なニュースを(来信)
―真理を知って安らかに生きていくことの大切さを(返信)
3 障害を負って生まれてきた子に感謝(来信)
―愛し子をしっかりと胸に抱いて歩む(返信)
4 霊界の「富子せんせい」と仲良しの美樹(来信)
―霊界の美樹ちゃんと祈りのなかで対話を(返信)
5 人を恨まないでいることの救い(来信)
―春の野の草花のように素直で美しく(返信)
6 シルバー・バーチの教えにたどり着いて(来信)
―さまざまな試練を前向きに受けとめていく(返信)
7 眼から鱗が落ちるような真理を知る(来信)
―どん底の悲しみこそ天から与えられた恵み (返信)
8 この世に生まれてきた意味を考え続けて (来信)
―無知から逃れるための長い歳月 (返信)
9 母の眼を見たかった霊界の幼児 (来信)
―ひたむきな母親の愛にこころ打たれて (返信)
10 天国にいる父からの大切なプレゼント (来信)
―永遠に変わることのない霊的真理について学ぶ (返信)
11 神様からいただいた光り輝く最後の二年間 (来信)
―神様との約束を立派に果たした稀有の魂 (返信)
12 避けては通れない生と死の問題について考える (来信)
―極めて明確に答えられている生と死の真実 (返信)
13 天国の愛し子と共に歩んで行くために (来信)
―「不幸」はしばしば真の意味での幸福 (返信)
14 魂の響きに寄せて海の彼方から (来信)
―この世に生かされて生きていることの実感 (返信)
15 母の旅立ちで得た真理を学ぶチャンス (来信)
―明るく幸せであることで親孝行を (返信)
16 愛し子の大きな置き土産 (来信)
―霊的真理だけが癒やせる死別の悲しみ (返信)
17 愛する娘の死の意味を求めて (来信)
―繰り返し教えられている生と死の真実 (返信)
18 人を赦すことについてロンドンで考える (来信)
―いつのまにか消えてしまった恨みと憎しみ (返信)
二.光へ向かって歩んでいくために(19〜36)
=メールの交換:二〇一一年二月〜二〇一二年二月=
19 流産した子供たちと対話する (来信)
― 流産しても霊界で生き続けている生命 (返信)
20 スピリチュアルな世界に触れて拡がる意識 (来信)
―誰にでも押しつけてはならない霊的真理 (返信)
21 守護霊との二人三脚で霊的摂理の普及を (来信)
―妥協することはできない真理への道 (返信)
22『天国からの手紙』を一気に読み終える (来信)
―これからも着実に真理探究の道を (返信)
23 一人で逝ってしまった息子を案じて (来信)
―霊的真実を知ることで癒される悲しみ (返信)
24『天国からの手紙』 を読み少し救われました (来信)
―大震災で被災された奥様やお子さん達のためにも (返信)
25『天国からの手紙』を読んで確信に近い気持ち (来信)
―求め続けなければならない霊的真理 (返信)
26『天国からの手紙』に込められた力強いメッセージ (来信)
―いのちの真理を伝えていくための小さな貢献を (返信)
27 十一歳で亡くなった愛し子への感謝の気持ち (来信)
―愛する家族のいのちを取り戻すために (返信)
28 霊界と地上界とを結ぶ通路としての役割 (来信)
―霊界の家族に対する一番の供養とは (返信)
29 シルバー・バーチの「霊訓原文」に辿り着いて (来信)
― 一人でも多くの方々の目覚めのために (返信)
30 二十歳で突然亡くなった長男の行方を捜し求めて (来信)
―霊界のご長男と安らかなこころの対話を (返信)
31 何度も『天国からの手紙』を読んで (来信)
―真理を知るための確かな歩みを続けて (返信)
32 長男を失った悲しみをまた吐き出して (来信)
―決して絶望ではない死の真実を知る (返信)
33 心の支えとなっている『天国からの手紙』 (来信)
―真実の言葉によって涙が拭い去られることを (返信)
34 道しるべになった『天国からの手紙』 (来信)
―熱意さえあれば誰でも掴める命の真実(返信)
35 何度もこのホームページを開いて学ぶ (来信)
―光への道を共に歩んでいくために (返信)
36 最愛の夫が生き続けていることを実感するために (来信)
―永遠のいのちの真実を学び続ける (返信)
おわりに
**********
3. 『天国の家族との対話』 はじめに
はじめに
私は、かつて、北海道の札幌に長年住んでいて、小樽商科大学で教鞭をとっていました。
私には、アメリカで暮らした経験が三度あります。
一度目は留学生としてでした。太平洋岸のオレゴン州のユジーンという街に州立のオレゴン大学がありますが、そこに二年近く滞在して大学院を修了しました。それが一九五九年のことです。
帰国してからは大学で教えるようになったのです。
二度目のアメリカ生活は、それから一四年後になります。
一九七三年の暮れから一九七五年の春にかけて、私は文部省の在外研究員としてアメリカへ渡り、母校のオレゴン大学で客員教授を勤めました。
その時には、妻と中学一年の長女、小学校五年の長男が一緒でした。子どもたち二人は、現地の学校へ通い、夏休みには家族四人でアメリカ一周旅行をしたり、ヨーロッパを車でまわったりして、大変思い出深い一年を過ごしました。
三度目は、それから八年後です。
一九八二年になって、私はフルブライト上級研究員に選ばれ、今度はアリゾナ大学で客員教授を勤めました。
アリゾナ大学の留学生となった長女と二人で、大学のあるツーソンという町に住んでいましたが、その時は、妻と東京外国語大学の学生であった長男は東京に残りました。
この三度目のアメリカ生活で、私たち家族は、全く予想もできなかった国際的な大事件に巻き込まれることになります。
その翌年、一九八三年の夏に、私は東部のノース・カロライナ大学に移り、長女もその大学に編入学して、首都のローリーという町に住んでいました。そこへ、夏休みを利用して、東京から妻と長男がやってきて、私たち親子四人は、久しぶりに家族水入らずの生活を送りました。
いろいろとノース・カロライナやバージニアの各地を旅行したりして、楽しい一か月を過ごしましたが、妻と長男は、この夏休みを終えて帰国するときに、あの大韓航空〇〇七便に乗ってしまったのです。妻と長男は、九月一日未明、日本を目前にしたサハリンの海上に散らされました。
私は、大学で教壇に立つこともできなくなり、教職を中断して長女と一緒に帰国してからは、寝たきりの病人のような状態になりました。
起きていることだけでも苦しくて、私は昼も夜もただ眠り続けました。
眠ってさえいれば、悲しみからは一時的にでも逃避することができます。だから、目を覚ますことを恐れました。
目を覚まして過酷な現実に直面すると、悲しみよりも痛みが全身を突き抜けます。私はもうろうとした精神状態のなかでうつらうつらしながら、目を覚まして正気に戻ると、また慌てて眠ろうとしていました。
その当時のことを思い出しますと、いまこうして、こころ穏やかに生きていることが不思議なような気がいたします。その頃は、妻や長男のことを話そうとしても、声がでなかったこともありました。
のちに私は、『疑惑の航跡』(潮出版社)という本のなかで、この極限状態の自分を書くことになりますが、それをここでくり返すつもりはありません。
ただ、こういう悲嘆の極限状態から、長い年月を経て、私は少しずつ、本当に少しずつ、生とは何か、死とは何かを、考え、学び、掴み始めていったのです。
今度書いたこの本のタイトルは、『天国の家族との対話』としました。
死んでこの世にいなくなった家族と、本当に対話ができるのかと思われる方がおられるかもしれません。というよりも、おそらく世間の大半の人々が、そんなことはあり得ないと思い込んでいるでしょう。
しかし、その対話は可能です。
迷信を退け、妄言に惑わされず、信憑性に欠けるものは慎重に排除しながら、ひたむきに真実を求めていけば、愛する家族と確かな対話をすることは、決して不可能ではありません。
長い苦しみと迷いの年月を経て、私が辿ってきたこのような対話への道筋の一端も、どうか、この本の中から読み取っていただきたいと思います。
第一部では、私が無知の闇のなかで悲嘆に暮れていた何年かを経て、霊界の家族が生き続けていることを確認するまでを、書いてみました。
そして、第二部では、愛する家族との死別の悲しみに暮れている多くの遺族の方々からのメールとそれに対する私の応答をとりあげています。
死別の苦しみを救えるのは、いのちの真実を知ることだけだと思いますが、人は死なない、愛する家族はいまも生き続けているという峻厳な真実を、これらのメールの交換で少しでもお伝えできれば、望外のしあわせです。
武本昌三『天国の家族との対話』 ―生き続けているいのちの確かな証し― (pp.12-15)
4. (第1章 天国は本当にあるのか) (2014.06.27)
第一部 無知の闇から真実の光へ
第一章 天国は本当にあるのか
『仏説阿弥陀経』を読む
事件が起こる前までの私は、宗教とか霊界とかには、全くといってよいほど縁のない無知な人間でした。
家には仏壇があって、浄土真宗の法名で父や母の位牌がありますが、浄土真宗のこともほかの宗派のことも殆ど何も知りませんでした。
その私が、いつの頃からか、毎朝お経をとなえるようになりました。お経のことは何も分からず、それでも毎朝お経をとなえていました。
お経をとなえていると、自然に涙が出てきます。
お経のことは何もわからないわけですから、お経が有り難くて涙が出るのではありません。ただ悲しくて涙が出るのです。あまりにも自分が惨めでつい泣いてしまうのです。
しかし、それでもほかに為すすべもなく、毎日お経を読んでいました。
浄土真宗のお経の中に、「仏説阿弥陀経」というのがあります。
お釈迦様が大勢の弟子たちを前にして、西の方はるか彼方に、極楽という世界があることを教えているお話です。「仏説」というのは、文字通り、仏様のお説きになった、という意味です。
「如是我聞一時仏在舎衛国・・・」という書き出しで、「ある時尊き師である釈尊は、千二百五十人もの多くの修行者とともに舎衛国の祇園精舎に滞在しておられた。その時に釈尊は、長老の舎利弗に言われた」というふうにこのお経は始まります。
その後に続くのが、釈尊御自身のことばです。
その内容をいまのことばでごく簡単にわかりやすくまとめますと、だいたい次のようになると思います。
ここから西方の十万億の仏の国を過ぎたところに、極楽という名の世界がある。その世界には、限りない命と光をもった阿弥陀仏が住んでおり、いま現に教えを説いておられる。
その世界に住む者たちには、体の苦しみも心の悩みもなく、ただ幸せがあるだけだ。その世界には、七重の石垣、七重の並木があり、それらは、金、銀、水晶等の宝石で飾られている。また、宝石から出来ている池があり、池の底には一面の金の砂が敷き詰められている。階段の上には御殿があって、七種類の宝石で飾られ、池の中には、車の車輪ほどもある大きい蓮の花が美しく咲いている。
その世界では、常にすぐれた音楽が演奏されている。大地は黄金でできていて、昼、夜に三度ずつ、曼陀羅の花が降ってくる。白鳥、クジャク、オウム等、色とりどりの美しい鳥たちも、昼、夜に三度ずつ、優しい声で鳴く。そよ風が気持ちよく吹き渡り、宝石で飾られた並木を揺り動かして、美しい音が流れている。その美しい音は、あたかも百千種類の音楽を同時に演奏しているようである。
これは極楽の描写ですが、そこでは「体の苦しみも心の悩みもなく、ただ幸せがあるだけ」というのは、話しに聞いていたような気がしていました。
それでも、金、銀、水晶等の宝石で飾られている石垣や並木というのは想像もつきません。宝石で出来ている池もそうですし、黄金でできている大地や、七種類の宝石で飾られている御殿などというのも、お伽話の世界のように思われます。
しかし、釈尊は決していい加減な気持ちでこんなことを言っているのではないようです。この釈尊のことばは、さらにこう続きます。
生きている者は、わたしの教えを聞くならば、この世界に生まれたいと願いをたてるべきである。わたしがいま、阿弥陀仏のすぐれた徳をたたえているように、東西南北上下の世界でも、数多くの仏たちがおられて、それぞれの国で、三千大千世界を長い舌で覆い、教えが真実であることを証明しながら、こういわれているのだ。
「世の生ける者たちよ、そなたたちは今こそこの阿弥陀仏のすぐれた徳をたたえ、すべての仏によって護られているこのお経の教えを信じなさい」と。
このなかの「三千大千世界を長い舌で覆い」というのは、釈尊の説法が嘘ではないことを示す言い方です。
釈尊の三十二ある身体的徳著の一つで、その舌の大きいことは、顔面を覆うほどであるといわれます。舌が鼻を覆えば、その説くことばに偽りがないと考える風習がインドではあったのです。
私は、このお経のなかで、「これは嘘ではない、本当のことなのだ」と何度も何度もくり返して述べられていることばに、わずかながらも心を癒されているような気持ちになることがありました。
無知のなかで迷い悩みながら
それでも、「はるか西の彼方に極楽がある。これは嘘ではない」と言われても、つい「本当だろうか?」と思ってしまいます。
地球は球形で一回りすると約四万キロです。今は飛行機で割合簡単に地球を一周できますから、日本から飛んで西へ西へと行けば、またもとの場所、つまり日本に戻ってきてしまいます。
極楽はどこにあるのでしょうか。
地球の上ではなくて、それは、西の空のかなたにあるのだ、と言われても、そこには無限の大空が宇宙の果てまで広がっているだけです。
極楽とはその空の彼方にあるのでしょうか。
それこそ何か、雲を掴むような話で、どうも実感が湧かないような気がしてくるのです。
結局、極楽などというものは一種の気休めであるに過ぎない。人間というのは、他の生き物のすべてがそうであるように、死んだらそれでおしまいで、あとは灰になるだけだ、というように考える人が少なくないのも致し方のないことかもしれません。
実際、人間が死んで葬儀が終われば、火葬場に運ばれて目の前で灰になっていくわけですから、「死んだらそれで終わりだ」という言い方には、それなりに、説得力があるようにも思われます。
そのような「迷い」に対して、むかし、空海は次のように述べました。
生まれ、生まれ、生まれ、生まれて
生の始めに暗く、
死に、死に、死に、死んで
死の終わりに冥し。
これは 『秘蔵宝鑰』という本に残されている空海(弘法大師)のことばです。
人間は生まれては死に、死んでは生まれて、何度も何度も輪廻転生をくり返すものだが、いったい何度生まれ変わったら、この生と死の真理が理解できるようになるのだろうという、空海の嘆きが伝わってくるようなことばです。
空海は、よく知られているように、平安時代の高僧で、七七四年に生まれて、八三五年に亡くなっています。
自分の死ぬ日時を、三月二一日の寅の刻(午前三時〜五時)と予言し、弟子たちに「嘆くなかれ」と戒めつつ、予言通りに死んでいきました。
この空海の死んでいく場面は映画にもなっていますが、死ぬ前の十日あまりは五穀を断ち、自ら体を浄めて宇宙の大日如来のもとへ帰っていくことになっています。
私たちはどうも見える世界だけがすべてに思えて、見えない世界のことについては関心が及ばないのかもしれません。
自分の目で見えるものは信じられるが、見えないものはなかなか信じようとはしないのです。
生の始めも、死の終わりも、実は心の目で見ることがでなければ、理解できないことを空海は教えようとしていたのでしょう。
大切なのは、目に見えるものではなくて、目には見えないもののようです。
般若心経には、「照見五蘊皆空度一切苦厄」とありますが、ここでも、すべてのものの実体は「空」、つまり、見えないもので、見えるもの「色」は、実は仮の姿でしかないことをいっているのだと思います。
しかし、当時の私には、そういうことも何もわかっていませんでした。
武本昌三『天国の家族との対話』 ―生き続けているいのちの確かな証し― (pp.16-22)
5. (第2章 なぜ極楽へすぐ行きたいと思えないのか) (2014.07.04)
第二章 なぜ極楽へすぐ行きたいと思えないのか
『歎異抄』に見出した一筋の光
私は、妻と長男がいなくなってしまったことが、どうしても承服できませんでした。
妻と長男が死んだということはどういうことか。そもそも、いのちとは何か。私たちはいったいどこから来たのか。そして、死とは何か。生を終えてからはどこへ行くのか。
いやでもそれらの問題に向き合わざるをえなかったのです。
いくら考えてもよくわかりません。しかし、考えるのをやめることは出来ません。
わからないなりに、悩みつつ、苦しみつつ、考えていくうちに、ふと、無明の闇に差し込むかすかな光を感じることがありました。それが、たとえば、『歎異抄』第五段のような文に出会ったようなときです。
父母というのは、自分の父母だけが父母なのではない。人間は何度も何度も生まれ変わるから、生きとし生けるものは、みんないつかの世で、父母であり兄弟であった。だから、親鸞は、念仏を唱える場合でも、現世の自分の父母だけに対する孝養のつもりでとなえたことは一度もない、というのです。
人間のいのちというのは、いま生きている間がすべてで、死んだらそれが最後だと思っているのと、いのちは永遠に続いて、人間は繰り返し生まれ変わるのだというのでは、大変な違いです。
そして、いのちが永遠に続くというのが本当であれば、それは、大きな救いです。
しかも、死んだ後は、極楽とか浄土へと移り住むことになり、その極楽・浄土が光に包まれた壮麗な歓喜の世界であるとするならば、死ぬことは悲しみではなくて、喜びでなくてはなりません。早く死んで極楽へ行きたいと思うようになっても決して不思議ではないのです。
そこでまた考えてしまうのですが、本当に、そんな霊界とか極楽・浄土はあるのでしょうか。
この素朴な疑問についても、『歎異抄』の中では触れられている箇所があります。
『歎異抄』の第九段では、弟子の唯円が、親鸞に、
「いくら念仏をとなえていても、どうも天に舞い地に踊るというような全身の喜びが感じられません。それに、真実の楽園であるはずの浄土へも、早く行きたいという気持ちが起こらないのはどうしてでしょう」と、率直に聞いたのです。
親鸞もそれに対して率直に答えました。
「実は私もそのことを不思議に思っていたのだが、そなたも同じであったか」と。
そして、つぎのように自分の考えを述べています。
はるか遠い昔から今日に至るまで、生死を繰り返してきたこの迷いの世界は捨てがたく、まだ見たこともない極楽浄土は恋しくないというのは、本当によくよく煩悩は強いものにちがいない。けれども、いくら名残惜しいと思っても、この世との縁が切れ、静かに生命の灯が消える時は、あの浄土へ行かざるをえなくなる。仏は、急いで浄土へ行きたいと思うことの出来ない者をことのほか憐れんで下さっているのだ。そうであればなおさら、大慈大悲の仏の本願が頼もしく、往生は間違いないと信じられる。逆にもし、天に舞い地に踊る喜びがあり、急いで浄土へ行きたいというのであれば、その人には煩悩はないのであろうかと、かえってうたがわしく思われてしまうのだ。
私は、こういう文章に少しずつ、目を開いていくようになりました。
いま、自分が住んでいるこの苦しみの多い、迷いの世界に執着して、あれほどすばらしい極楽・浄土へもすぐに行きたいと思わないのは、それほど人間のもっている煩悩が強いからだ、というような言い方にも、それなりに少しずつ、理解できるような気がしてきたのです。
むかし私が見たある外国映画につぎのような一つのシーンがありました。
ヨーロッパのどこかの監獄で、一人の囚人が、三〇年も四〇年も独房に閉じこめられてよぼよぼの老人になってしまいます。
老人は、独房の高い小さな天窓から差し込む光を仰いでは、監獄の外の自由へのあこがれを募らせていました。
第二次世界大戦の末期だったでしょうか、その監獄もある日、激しい空爆を受けて、高い塀も頑丈な建物も崩れ落ちてしまいます。
その独房の老人は生き延びて、瓦礫のなかから這い出してきました。そして、よろよろと外へ向かって歩き始めます。
しばらく歩いて振り返りますが、誰も追ってくる様子もありません。
目の前には、広々とした野原が広がっています。それは、老人が長い年月あこがれてきた自由の世界のはずでした。
老人は、また少しよろよろと歩き続けます。
しかし、そこで立ち止まってしまうのです。
やがて老人は、またよろよろと、崩れ落ちた監獄へ帰って行きました。
自由が束縛されても、孤独の苦しみがあっても、あまりにも長い年月それに慣らされてしまいますと、もうそこから抜け出すことさえ不安になってしまいます。
浄土・極楽がいかに壮麗ですばらしいところであると聞かされても、唯円が疑問に思ったように、煩悩の世界に慣れきってしまうと、「急いで行きたい」と思われないのも、無理ではないのかもしれません。
しかし、それでは、この煩悩の世界に生きている限り、安心立命の境地に達するのは難しいということになってしまうのでしょうか。
親鸞の信心に教えられる
信心というのは、ここで問題になってくるのだと思います。
また親鸞に戻って、今度は、親鸞自身の信仰のありようをみてみることにしましょう。
かつて親鸞は、常陸の国(いまの茨城県)を中心に、下総、下野、武蔵などの関東諸国に、他力本願の念仏を説いてまわっていたことがありました。
その後親鸞は、一二三五年、六十三歳の頃、関東を去って京都に帰っていったのですが、残された関東の信徒たちの間には、やがて信仰に対する考え方の違いから正統派と異義派に分かれて対立するようになっていきます。
そこで、信心に迷いを来した人たちが、あらためて親鸞から直接に教えを受けるため、常陸の国から東海道十余か国をはるばると越えて、京都へ向かったのです。
東海道といっても、鎌倉時代のことですから、江戸時代の東海道五十三次などよりよほど不便で、危険も多かったにちがいありません。
その命がけの旅をしてやってきた信徒たちを前にして、親鸞は、
「あなた方は、私が念仏以外に往生極楽への道を知っているだろうとか、いろいろと経典以外の教えにも通じているだろうとか勝手に考えているようだが、それはとんでもない誤りである」と切り出しました。
そしてその後で、親鸞は率直に、しかし強いことばで、自分自身の入信のいきさつをこう告白するのです。
私はただ、念仏をとなえて阿弥陀仏に助けていただくだけだと、法然上人に教えていただいたことを信じるのみである。そのほかはなにもない。念仏をとなえれば本当に浄土に行けるのか、それとも地獄に堕ちるのか、そんなこともどうでもよい。かりに、法然上人に騙されて、念仏したあげくに地獄に堕ちたとしても、私は決して後悔はしないであろう。
これはずいぶん思い切った言い方だと思います。
関東からはるばる命がけの旅を続けてやってきた信徒たちは、いま固唾をのんで親鸞の顔を見守っています。
この緊迫した雰囲気の中で、親鸞は、赤裸々な自分自身の姿をさらけ出して、信念を披瀝しなければなりませんでした。
しかしこれは、まかり間違えば師としての信を失いかねず、仏道の教えにも疑問を抱かせることにもなりかねないことばです。
そのようなことばを、確固たる信仰の証として信徒のこころに直裁にしみこませていったのは、おそらく親鸞のその時の気迫であったにちがいありません。
親鸞はさらに続けます。
阿弥陀仏の本願が真実であるならば、釈尊の教えにも嘘はない。釈尊の教えが真実であるなら、善導大師のお説きになったことにも誤りはない。善導大師のお説きになったことが真実であるなら、どうして、法然上人の言われることが虚言でありえようか。そしてまた、法然上人の言われることが真実であれば、この親鸞の言うことも空言であるはずがない。これがつまり、私の信心なのだ。この上は、念仏を信じようが、捨てようが、それはあなた方の勝手である。
これが、信仰とはこういうものだと、親鸞が血を吐くようなことばで述べたまごころからの告白でした。
それでも信じ難いいのちの真理
しかし、その親鸞から、歎異抄などで極楽浄土へ行きたいとは思えない理由をあれほどわかりやすく説明されても、なかなか霊界のことなどを信じようとはしない人が世のなかには数多くいます。
しかも、科学者や知識人といわれる人々ほど、その傾向が強くみられるようです。私も学者・研究者の一人として例外ではありませんでした。
なぜ、それはそうなるのでしょうか。このことを少しここで考えてみましょう。
大般涅槃経のなかに、つぎのような「盲人と象」のたとえ話があります。
昔、ひとりの王があって、多くの盲人を集め、象に触れさせて、象とはどんなものであるかを、めいめいに言わせたことがある。象の牙に触れた者は、象は大きな人参のようなものであるといい、耳に触れた者は、扇のようなものであるといい、鼻に触れた者は、杵のようなものであるといい、足に触れた者は、臼のようなものであるといい、尾に触れた者は、縄のようなものであると答えた。ひとりとして象そのものをとらえ得た者はなかった。
これは、大変わかりやすいたとえ話です。牙に触れたり、耳に触れたり、鼻に触れたりしていますが、それだけでは、象の実像にせまることは出来ません。
しかし、例えば、耳に触れている盲人Aは、自分が確かに象に触っているわけですから、象とは、扇のようなものだと固く信じて疑わないでしょう。
同様に、尾に触れた盲人Bは、実際に手に触れた感触で、縄のようなものだと思っているわけですから、その判断の正しさには盤石の自信を持つかもしれません。
この場合、盲人AもBも、彼らの立場では確かに正しいのです。しかし、それらはあくまでも象の一部であって、象の実像からは遠く、結局、彼らの見方は間違いであることになってしまいます。部分としては確かに正しいのですが、しかし、間違っているのです。
この象の実像を、仮に「真理」と置き換えて考えてみることにしましょう。
その真理を捉えるのには、どういう見方をすればよいでしょうか。少なくとも、視野を広げなければならないことがわかります。
象の実像を捉えるためには、牙や耳や鼻だけに触れて、それだけで結論を出してしまうのではなく、一人の盲人が、足や尻尾や大きなおなかまでできるだけ多くの場所を触ってみて、そのうえで、全体像を組み立てれば、かなり実像、つまり「真理」に近づくことができるはずです。
つまり、象=牙、象=耳、象=鼻ではなくて、象=(牙+耳+鼻+尾+・・・・・)ということになります。
真理の探究というのは、学問の目的であり、学者の本分でもあるわけですが、しかし、往々にして、学者は対象を深く見つめているうちに視野が狭くなって、小さな自分の専門領域に閉じこもりがちです。
広大な宇宙の中では米粒ひとつほどの大きさにもならないちっぽけな地球の上で、科学で説明できないものは真理ではない、と広言しているような科学者がいるとすれば、ちょっと滑稽な気がしないでもありません。
盲人と象のたとえでは、象の尻尾だけを繰り返し触り続け、毛の数や成分までも知り尽くして、それで象のことについては何でも知っている権威であると錯覚してしまうようなものです。
そして、本当に象の全体が見える人から、象というのはもっと巨大で、鼻も頭も足もある複雑な存在だと聞いても、そんなものは迷信だと一笑に付すことになるのでしょう。
アメリカ人は死後の世界を信じているか
さまざま見方があることを知るために、ここでもう一つ、アメリカでの調査にも触れておきたいと思います。
ジョージア大学のエドワード・ラーソン氏らが実施したアンケートによると、最先端の研究に携わる米国科学者の約四〇パーセントが、神や死後の世界を信じているそうです。
歴史学者のラーソン氏らは、「米国科学者名簿」から数学、生物学、物理、天文学の計千人を無作為で抽出し、約六百人から回答を得ました。
それによりますと、「神を信じる」が三九パーセント、「死後の世界を信じる」が三八パーセントにのぼりました。
同じアンケートは、一九一六年にも実施されていて、その時は、神、死後の世界は、それぞれ、四二パーセントと五一パーセントの科学者が信じている、という結果でした。八〇年間で、信じる科学者の傾向はあまり変わっていないということです。(「朝日新聞」1997.4.4)
このような調査は、かつて、一九七六年に世論調査のギャラップ社が、アメリカ国民全体を対象に実施したことがあります。
その時のデータでは、「神の存在を信じる」は九四パーセント、「死後の生を信じる」は六九パーセントというようにかなり高い数字を示していました。
この全体調査に比べると、科学者の場合は確かに、神の存在、死後の生とも、懐疑的に見ている人が多いといえるでしょう。
ここで思い出されるのは、エリザベス・キューブラー・ロスのことばです。
彼女は、アメリカのシカゴ大学の精神医学部教授を勤め、末期ガン患者をどのように看護するかというターミナル・ケアの世界的な権威として有名です。皆さんの中にもご存じの方が多いことでしょう。
キュブラー・ロス博士自身も臨死体験をしていますが、それとは別に、彼女が医者として患者の治療に当たっている間に、患者の臨死体験の例を二万件も集めました。
人間は死んでも死なない、死というものはないのだ、ということを人々に説いてまわるのが自分の使命だと、感じていたからだということです。
しかし、やがて、彼女は悟ります。人間のいのちは永遠であって、本来、死というものはないのだということは、聞く耳を持った人なら彼女の話を聞かなくてもわかっている。しかしその一方で、その事実を信じない人たちには、二万はおろか百万の実例を示しても、臨死体験などというものは脳のなかの酸素欠乏が生み出した幻想にすぎない、と言い張るに違いないのです。
そういうことを知るようになって彼女は、臨死体験の例を集めて「死後の生」を証明しようとする努力を二万件でやめてしまいました。
彼女は、少し自嘲気味に、自分の著書『死ぬ瞬間と臨死体験』のなかで言っています。
「わかろうとしない人が信じてくれなくても、もうそんなことはどうでもよいのです。どうせ彼らだって、死ねばわかることですから。」(読売新聞社刊、1997, 129頁)
*日本人の死生観の調査については、随想集(75) 「私達がなるべく早いうちに知っておくべきこと」のなかで、
「朝日新聞」が2010年11月4日に実施した全国世論調査の結果を紹介しています。
武本昌三『天国の家族との対話』 ―生き続けているいのちの確かな証し― (pp.23-35)
6. (第3章 霊界から届いた初めてのことば) (2014.07.11)
第三章 霊界から届いた初めてのことば
夢の中で生き続けている妻と子
私は事件で長女と一緒に帰国してからは、「遺族会」がおかれたホテルの自室にほとんど閉じこもったまま横になっていました。
一か月ほどの後、一度アメリカへ引き返し、講義に打ち込むことで何とか立ち直ろうとしたことがあります。しかし、ノースカロライナの自宅でも事件の後遺症から立ち直ることが出来ず、結局、アメリカ生活を打ち切って日本へ帰りました。
小樽商科大学で認められていた海外出張の期間はその翌年の3月末になっていましたので、帰国後は新学年が始まるまで、自宅研修という形になりました。
札幌の自宅では、それからも寝たきりのような毎日を過していました。
その頃、うつらうつらしながら、私はよく夢を見ました。
―― 場所ははっきりしないのですが、古い体育館のような建物の中に一家四人でいました。
中は暑くて、長く居たので富子と潔典が疲れた様子です。二人をどこかで休ませなければなりません。
外へ出てみると涼しそうな裏庭のようなところに、椅子が二つ三つ置いてありました。
それを見つけて、そこへ富子と潔典を両脇にかかえるようにして連れ出し、休ませました。
由香利は一人、屋内に待たせてあります。
私は今度は由香利を連れ出すために屋内へとって返しましたが、由香利は一人残されて、迷い児になったみたいにおろおろしながら少し泣いていました。
「ホラ、ゆかちゃん、ちゃんと連れに帰ってきたでしょう」
そう言って由香利をなだめながら富子と潔典のところへ連れて行きました。富子は両手を差し出して由香利を抱きかかえました。その時の由香利はなぜかおカッパ頭の幼児の姿でした。幼児の由香利を抱きかかえている富子とその隣に座っている潔典の姿を私は見つめ続けていました。
―― やはり暑い夏の一日、家の中に私と富子がいて、遊びに来ていたらしい高円寺の姉夫婦も傍にいました。由香利と潔典はそれぞれ二階の自分の部屋にいる様子です。
富子は時々そうするように、片手を首のうしろにまわして凝ったところを指でおさえつけていました。
私は富子に、
「ぼくが揉んでやろう」と言いました。
富子をうしろ向きに坐らせて、一生懸命に両肩を揉み始めました。私の顔から汗がしたたり落ちます。それでも揉むのをやめませんでした。
(揉んでやらねばいかん。疲れても揉むのをやめてはいかん)
と、私はこころの中でつぶやきながら、いつまでも富子の肩を揉み続けていました――。
富子と潔典が無事であって、ちゃんと生きていて、以前のように親子四人元気に揃っていることを確認して大よろこびする。
しかし、それはぬかよろこびで、夢であったことも何度かありました。
―― 潔典が元気よく歩きながら、並んで歩いている由香利に何やら笑いながら語りかけています。どこかの町の、広い並木路の坂を上っているところでした。
前方には広い眺望がひろがっています。団地のような風景であったかもしれません。*
私は潔典と由香利のあとを数歩はなれて、富子と肩を並べています。親子四人、いつものままの姿で、変わっているところはどこもありません。
私は今度もまた夢でないかと疑いました。
しかし、いくら見直しても本当のことのようです。潔典はあんなに元気に手を振って歩いているし、私の横には確かに富子がいます。
今度こそは夢ではない、大丈夫だ。これは現実なのだと私は思いました。
その 「現実」に甘えて、私は富子に話しかけました。
「こういう風に四人で歩いたことが何度もあるのに、今までみんなそれが夢であったものだから、今度もこれが夢であったということになればひどく辛いんだよ……」
私はそう言って、富子の肩にもたれかかるようにして泣き出してしまいました。
そこで目が覚めました。
夢でした。
*[後記] この2年後、私は大学を退職して東京の多摩市に移り住んでいましたが、ある日、ワープロを買おうと思って多摩センター駅近くの道を歩いていました。多摩ニュータウン通りというのがあって、そこから駅の少し手前の道を左折すると、広い並木道になっています。なぜか人通りはほとんどなく、前方には白いコンクリート建築の棟がいくつか遠望できました。その地点まで来て、私は思わず「あっ」と小さな声をあげました。それは、この時の夢に出てきた情景と全く同じであった気がしたからです。心霊現象でいうデジャ・ビュ(既視体験)であったかもしれません。
初めて霊能者を訪ねる
その頃、一九八三年の十一月下旬のある日、私は、ふと妻の友人に霊能者の青木耀子さんという方がおられたことを思い出して、青木さんの自宅を訪れました。
私自身は青木さんとは初対面でしたが、その時の私は「溺れる者は藁をも掴む」思いでした。
青木さんは、私の顔を見るなり、「もうそろそろお見えになる頃と思っていました」と、いきなり言われました。
彼女は、事件のあと、私の妻・富子と長男・潔典(きよのり)のために二週間の供養をして下さったのだそうです。そして、霊界の富子と潔典とも話しをした、と切り出されたのです。
「話しをした?」 私は内心の激しい動揺を懸命に抑えながら、黙って聞いていました。青木さんはつぎのように言われました。
「霊感を感じましてね、精神を統一していると清らかな雰囲気に包まれて潔典さんが現れたんです。私は最初、それは富子さんだと思ったのですが、よく見ると、潔典さんでした・・・・・」
私は極度に緊張しながら、一瞬、(そんなことが本当にありうるのだろうか)と思いましたが、ただ黙って聞き続けました。彼女はさらに、こう続けました。
「潔典さんはですね、はじめに『ありがとう』とおっしゃって、それから『楽しかった』と言われました。私が、『アメリカ旅行が楽しかったのですか』と聞きますと、潔典さんは『いいえ、アメリカ旅行だけではなくて、今までの生活がすべてです』と答えられました」
ここまで聞いて、私は思わず、こころのなかで「あっ」と叫んでいました。
直感で父親の私にはわかるのです。
「ありがとう・・・・・楽しかった・・・・・今までの生活がすべて・・・・・」 これは潔典のことばだと直感でわかった瞬間、涙がぽろぽろとこぼれました。
霊界のことなど何も知らなかった私は、あまりにも不思議な気がして、三日後にはまた青木さんを訪れ、潔典のことばを確認したりしました。
そして、その後何度か足を運んでいるうちに、妻の富子からも、
「どうか、いつまでも悲しまないでください・・・・・由香利に夢を、いつも明るい希望を・・・・・」と告げられたりしました。由香利というのは、長女の名前です。
このことがあってから、私はさらに真剣に、霊界や死後の世界についての本を読み始めるようになりました。
夢に現われた潔典からの伝言
それからしばらく経ったある夜、電話がかかってきました。北海道大学の学生食堂に勤めているNさんという女性からでした。
私はかつて北海道大学でも兼任で教えていましたが、もちろんNさんとは面識はありません。
彼女は、少し遠慮がちに、その前日、潔典の夢を見たのだと切り出しました。夢の中で、潔典から「父に会って欲しい」と頼まれたのだと彼女はいうのです。
事件のことや私のことは、よく新聞やテレビに出たりしていましたから、彼女が私と潔典のことを知っていても不思議ではありません。
潔典の夢を見たのも、たまたま、その前の日にテレビに映っていた潔典の写真を見たあとだったそうです。放送局に電話して、私の電話番号を聞きだし、電話しているのだと言っていました。
私に会って欲しいと潔典に言われたというのは、私にとってはただ事ではありませんでした。
「そんなことは信じられない」と一笑にふしてしまうような「余裕」は、私にはまったくありません。
とにかく私は、すぐに会いに行きました。
彼女は、潔典が元気でいること、霊界で母親も一緒に安らかに暮らしていることを、私に伝えて欲しい、と夢の中で自分に頼んだのだと何度か繰り返しました。あまりにその夢がリアルであったので、捨てておけなかったとも言いました。
見ず知らずの彼女が、なぜそんな時にそんな夢を見るのか、「霊界」とはなにか、私にはまだ、どうもよくわかりません。
私はいろいろと彼女に尋ねました。これが、彼女の所属していた宗教団体「S教団」に私がつながりをもちはじめるようになったきっかけです。
妻の友人の青木さんから、潔典のことばを聞かされて以来、私は霊界に強い関心を抱き始めるようになっていました。
少しでも、何でも、霊界に関することは知りたいと思っていました。
S教団では、霊界の存在が当たり前になっていて、霊界からの霊言を伝えてくれる霊能者も三百人くらいいるというのです。
私はそれを聞いてすぐに、札幌支部長のKさんに会い、たまたま、Kさんがその翌日には上京して、都内のS教団本部に行くというので、私も頼んで同行させてもらいました。
S教団では、接心修行と呼ばれる集会があります。
小さなグループにわかれて円陣をつくり、その中に霊能者が座ります。その霊能者から、一人一人が短い霊言を聞くというやり方で、集会は進められます。
私は、東京でも、札幌でも、何度も、いろいろな霊能者から「接心修行」で霊言を受けました。
S教団の幹部から霊言を受ける「特別接心」というのもありました。人数が制限されているので、申し込んで霊言をうけるまでにはかなり時間がかかりますが、これも何度も受けています。
妻や長男についての具体的な内容の霊言は、なにひとつ聞くことは出来ませんでしたが、それでも私は、そのような霊言を聞く修行も大切であろうと考え、機会さえあれば、霊言を聞くことにしていました。
妻と長男に対する供養の仕方もわからない私でしたから、そのような「接心修行」からでも、なにかを掴んでいかなければならないという思いが強くあったのです。
武本昌三『天国の家族との対話』 ―生き続けているいのちの確かな証し― (pp.36-40)
7. (第4章 死後の世界を信じることの難しさ) (2014.07.18)
第四章 死後の世界を信じることの難しさ
イエスの復活を信じられなかった弟子たち
霊界というのは本当にあるのか、人は死んでもあの世で生き続けるのか。
この重大な問題について、確信的な答えを見つけ出すことは、やはり、なかなか容易ではないようです。私の場合も、ずいぶん長い時間がかかりました。
私は、自分なりに聖書を学んでいたとき、遠藤周作さんの本も、いろいろと読んでいたことがあります。
遠藤周作さんは、皆さんもご存じの方が多いと思いますが、芥川賞作家で、一九九五年には文化勲章も受章しています。
熱心なカトリック信者で、谷崎賞を受けた『沈黙』や読売文学賞を受けた『キリストの誕生』をはじめ、キリスト教に関する多くの著作も出されました。
生涯をかけて、人間の生と死、信仰を見つめ続けた善意の人でもあります。
その遠藤さんも、しかし、イエス・キリストの復活のような奇跡は、信じていませんでした。
聖書に書かれた数々の奇跡を、一生懸命に考えて説明し、彼なりの解釈をしていますが、やはり最後まで、復活は信じ切ることはできなかったようです。
「死後の世界」についても、半信半疑で、その実在を信じることができないまま、一九九六年九月に、多くの読者に惜しまれながら急逝しています。
現代のような科学万能の時代では、死んだ人間のよみがえりとか、死後の世界や霊魂の存在などは、人間の「常識」からいってもあり得ないと考えて、あたまから受け付けようとしない人が沢山います。
すでにみてきたように、科学者や知識人といわれるような人ほど、その傾向が強いと思われるのも、無理のないことかもしれません。
遠藤さんのようなキリスト教徒をも含めて、教会の神父や神学者でさえ、信じられないという人は、決して珍しくはないのです。
でも、私たちは、地球の上で生きているというよりも、宇宙の真理のなかで生きています。
広大な宇宙の広がりのなかでは、米粒一つにもならないようなちっぽけな地球にいて、その科学で解明できないものは存在しない、と断定していいものでしょうか。
ほんとうは、科学を含めて私たちの知っていることは、真理のほんの一部にすぎないのであって、知らないことはまだまだ沢山あることを自覚する謙虚さが、特に現代の私たちには必要であるように思われます。
時代を問わず、確かに、霊の世界を信じるのは容易ではないかもしれません。そのことは、あのイエスの弟子たちをみてもわかります。
イエスは、偉大な霊能者の一人で、生前、自分が捕らえられ、十字架につけられて殺されることを弟子たちに正確に予言していました。そして、死んだあと、三日の後に甦ることも予言しています。
しかし、そのイエスを敬愛する当時の弟子たちでさえ、実は、誰一人、その予言を信じてはいなかったのです。
ユダの密告でイエスが逮捕されたときには、弟子たちはみんな、イエスのように捕らえられることを恐れて、逃げ隠れていました。
一番弟子のペテロでさえ、見咎められてイエスとの関わりを訊きただされると、そんな人は知らないと、三度もイエスを否認したくらいです。
イエスが十字架につけられようとしても、イエスを助けようとした弟子は一人もいませんでした。結局、イエスは、弟子たちにも裏切られて死んでいったと言っても決して言いすぎではありません。
しかし、イエスは、十字架につけられたあと、予言通り三日後に甦りました。そして逃げ隠れていた弟子たちの前に現れます。
弟子たちは、怖れ慄き、強い衝撃を受けたことでしょう。
しかし、それでもなお、その時にその場に居なかった十二弟子の一人のトマスだけは、まだ、その話を聞いても事実を受けつけようとはせず、
「私は、その手に釘あとを見、私の指をその釘あとにさし入れてみなければ、決して信じない」と言い張ったのです。(ヨハネ20・25 )
ところが、その八日後、今度はそのトマスも居るところへイエスはまた現れます。
イエスはトマスに言いました。
「あなたの指をここにつけて、私の手をみなさい。手をのばして、私の脇に差し入れてみなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい」と。
トマスはことばもありません。ただ「わが主よ、わが神よ」と言ってひれ伏すばかりです。
イエスは言いました。「あなたはわたしを見たので信じたのか。見ないで信じる者は、さいわいである」。(ヨハネ20:26-29)
信じない弟子たちが信じる弟子たちに変わったのは、この復活を目の前で見てからです。
疑うにも疑いようのない事実を目撃した弟子たちは、このイエスの復活のあと、劇的に変わりました。
一度は師を見捨てて逃げ隠れしていた彼らが、猛然と立ち上がって結束し、熱い信仰に燃えて、多くの苦難をものともせず、罵られても、叩かれても、石を投げられても、殺されそうになっても、文字通り生命を賭して師の教えを広めていくようになったのです。
逆にいえば、このイエスの復活がなければ、その後の世界宗教としてのキリスト教はなかったといっていいかもしれません。
復活の奇跡に苦慮した作家の足跡
遠藤周作さんは、しかし、それでもこの復活の奇跡を信じることはできませんでした。
イエスを裏切ったあの弱虫の弟子たちが、一斉に立ち上がってあらゆる困難に打ち勝ち布教に献身したのには、「なにか筆舌では言えぬ衝撃的な出来事が起こったと考えるより仕方がない」といいながらも、『イエスの生涯』(新潮文庫、1992年、220頁) のなかで、つぎのように述べています。
なぜ弟子たちは荒唐無稽な、当時の人々も嘲笑した復活を事実だと主張し続けたのか。彼らを神秘的幻覚者だとか、集団的催眠にかかったのだときめつけるのはやさしいが、しかしそれを証拠だてるものは何ひとつない。謎はずっしりと重く我々の心にのしかかるのである。
このように遠藤さんは、復活は「荒唐無稽」であり、それなのに弟子たちが一斉に立ち上がった契機は「謎」である、と言っています。
そして、復活を認めなければならないとしても、「イエスは弟子たちの信仰において甦られた」としか言いようがないであろう、と神学者・ブルトマンのことばを引用して終わっているのです。(前掲書、218頁)
私は、神学者・ブルトマンや遠藤さんの「復活の謎」に迫ろうとする熱意と善意を疑うことはできません。
それだけに、このような苦しい結論を出していることには、つい同情をも禁じ得ないのですが、それでも、イエス・キリストが偉大な霊能者であるという視点を欠いたままでいることの決定的な欠陥を指摘せざるをえません。
これが心霊主義との受け止め方との違いです。
しかも、この復活には、強力な証人がいました。かつてはキリスト教徒を弾圧していたあのパウロです。
パウロは、キリスト教徒を捕らえようとしてダマスコへ向かう途中、突然、天からの光に打たれて、「なぜ私を迫害するのか」というイエスの声を聞きました。
それ以来、パウロは一八〇度転回して、熱烈なキリスト教徒に変わります。
そして、弟子たちの誰よりも熱心に、実に二万キロに及ぶ三度の大伝道旅行を含めて命がけの布教を続け、最後にはローマで殉教したのです。
そのパウロが、復活を疑問視する人がいることについて、生前、キリスト教徒に宛てた書簡のなかでつぎのように述べています。
あなたがたの中のある者が、死人の復活などはないと言っているのは、どうしたことか。もしキリストが甦らなかったとしたら、私たちの宣教はむなしく、あなたがたの信仰もまたむなしい。さらに私たちは神にそむく偽証人にさえなるだろう。なぜなら私たちは神がキリストを甦らせたと言って、神に反するあかしを立てたことになるからである。(コリント前書15・13-15)
ところが、遠藤さんも、この書簡を引用しているのです。
しかし彼は、「この絶対的な自信、動くことのない確信は何よりも私たちを圧倒してしまう。どこからこの自信と確信は生まれたのか。もし(復活が)事実でないとするならば・・・・」といい、「イエスの復活を目撃しなかった」我々は、このような「謎をふしぎに思う」と、ここでも遂に「謎」で終わらせてしまっているのです。(遠藤、前掲書、220頁)
パウロが、イエスの死後、イエスの声を聞いて回心したその当時、甦ったあとのイエスを実際に見た信徒たちは、五百人以上も居ました。そして、その目撃者たちの大多数はまだ生存している、ともパウロは前述の書簡のなかで述べています。
つまり、復活の生き証人はまだ大勢いたのです。
しかし、イエスのことを熱心に考えながらも、その復活を「自分で目撃する」ことが出来るはずもなかった遠藤さんは、その奇跡を最後まで信ずることはできなかったのです。
霊界から届けられて死後の世界の証言
その遠藤さんも、死後の世界には強い関心をもっていました。
ただ、その存在には懐疑的で、やはり信じられないまま、一九九六年九月に亡くなりました。
これは女流作家・佐藤愛子さんの『私の遺言』(新潮社、2002年)に述べられていますが、遠藤さんは亡くなる半年ほど前に、親しくしていた佐藤愛子さんに、
「佐藤くん、君、死後の世界はあると思うか?」と、電話で訊いてきたのだそうです。
佐藤さんは、昭和五十年に北海道の浦河という町に山荘を建てたときから、深夜の足音、鋭いラップ音、電灯の明滅など、つぎからつぎへと起こる超常現象に見舞われ、それ以来三十年間悩み苦しんだうえで霊界存在の確信に行き着いた人です。
だから佐藤さんは、「あると思う」とすぐ答えました。
すると、遠藤さんはこう言いました。
「もしもやな、君が先に死んで、死後の世界があったら、『あった!』といいに幽霊になって出てきてくれよ。オレが先に死んだら、教えに出て来てやるから」
佐藤さんは、その時は「遠藤さんの幽霊なんて来ていらん!」と答えて、話は終わったということです。
佐藤愛子さんは、いまでも心霊の相談などで霊能者の江原啓之さんに電話をかけたりしているようですが、遠藤さんが亡くなった翌年の五月中旬、彼女が江原さんと電話で話をしている途中に、急に遠藤さんが現れました。
江原さんが、
「あ、ちょっと・・・・待って下さい・・・・今、佐藤さんの部屋に遠藤先生が見えています」と言い出したのです。
かつて浦河にいて助けを求めてきた佐藤さんに、霊能者である美輪明宏さんが、東京にいながら佐藤さんの家を的確に霊視したように、江原さんには、電話の相手の佐藤さんの部屋の様子がよく見えるのでしょう。
江原さんは、
「遠藤先生がこういっておられます。死後の世界はあった、こっちの世界はだいたい、君がいった通りだ・・・・」と霊界からのメッセージを伝えてくれました。
佐藤さんは、感動しました。そして『私の遺言』(257-258頁)のなかで、つぎのように書いています。
私の身体を戦慄が走った。驚きや怖ろしさではなくそれは間違いなく感動の戦慄だった。私は思いだしたのだった。遠藤さんの生前の、あの会話を。・・・・もしオレが先に死んだら、教えに出て来てやるから・・・・・。
遠藤さんはそういった。そしてその約束を守って出てきてくれたのだ・・・・。呆然としている私の中に何ともいえない懐かしさと嬉しさがこみ上げてきた。わっと泣き出したい熱いものがたちのぼってくる。
武本昌三『天国の家族との対話』 ―生き続けているいのちの確かな証し― (pp.41-50)
8. (第5章 実証され始めた人の生まれ変わり) (2014.07.25)
第五章 実証され始めた人の生まれ変わり
退行催眠による生まれ変わりの証明
親鸞は、「一切の有情は、みなもて世々生々の父母兄弟なり」と言って、人の生まれ変わりの姿を説きました。
この生まれ変わりを表したものには、浄土真宗だけではなく、それ以外のいくつかの宗派によっても唱えられている礼拝文にも出てきます。
「人身は受け難し、今すでに受く。仏法聴き難し、今すでに聴く。この身今生に向かって度せずんば、更にいずれの生に向かってかこの身を度せん」ということばは、なじみの方も多いのではないでしょうか。
これも、空海の、「生まれ、生まれ、生まれ、生まれて・・・・・」と基本的には同じで、何度生まれ変わればいのちの真実がわかるようになるのか、いまの人生で真実を掴むべきだと、無明の闇から抜け出すことを教えているのだと思います。
かつての私のように、長い間何もわからず、無知無明のままに悲しみ苦しみ続けてきた者には、この礼拝文は、このようにも聞こえました。
「人間のいのちは永遠で、死んでも死なない、また生まれ変わるのである。それが真実であることを仏法が教えている。それなのにおまえがいまこれを知ろうとしないのであれば、いったいいつになったらこの真実を知るのか。この真実を知ろうとしないで、何故いつまでもいつまでも悩み苦しむのか・・・・・・」と。
この人の生まれ変わりが、科学の分野でも実証され始めたのは、最近数十年来のことです。欧米の大学医学部で、「退行催眠」という精神医学の治療法が発達してきたからでした。
催眠というと、私たちは何となくトリックや奇術めいたものを連想してしまいますが、欧米の大学医学部で行われているのは、そういうものではありません。医術としての催眠です。
訓練を受けた医師の誘導によって、患者が心身をリラックスさせ、意識をある一点に集中させると、意識の奥に潜んでいた過去を思い出すことができます。それによって、過去に受けたこころの傷などを探ろうというものです。
ただし、過去生にまで遡るためにはかなり高度な催眠技術が必要で、この治療法が、欧米でもひろく一般化されているわけではありません。
そのなかで、ヨーロッパの九つの大学の学位を持つイギリスのアレクサンダー・キャノン博士は、この退行催眠の研究者としては先駆者の一人です。
被験者一、三八二人を紀元前何世紀というはるか昔まで退行させたという記録を持っています。そのキャノン博士も、初めのころは生まれ変わりを信じようとはしていませんでした。
一九五〇年に出した自分の著書の中で、博士はつぎのように述べていることを、後述のホイットン博士が『輪廻転生』(人文書院、1989年)で紹介しています。
何年もの間、生まれ変わりの説は、私にとって悪夢であり、それに反駁しようとできるかぎりのことをした。トランス状態で語られる光景はたわごとではないかと、被験者たちと議論さえした。あれから年月を経たが、どの被験者も信じていることがまちまちなのにもかかわらず、つぎからつぎへと私に同じような話しをするのである。現在までに一千件をはるかに越える事例を調査してきて、私は生まれ変わりの存在を認めざるをえなかった。(93頁)
このキャノン博士は、一九七〇年代から一九八〇年代にかけて、何千人もの患者を退行催眠により治療してきましたが、その業績の上にさらに研究を積み重ねてきたのが、カナダのトロント大学医学部の精神科主任教授を務めるジョエル・L・ホイットン博士です。
ホイットン博士は、十四歳ころから催眠家としての腕前を発揮してきました。二十代になってから、彼は次第に人間の生まれ変わりに関心を持つようになり、催眠技法に磨きをかけていったといわれています。
深い催眠状態に入れる人たちは人口の四〜一〇パーセントくらいいるようです。
それらの人々がみな同じように、指図に従って誕生前の前世に戻れる、ということを発見したのは、彼がトロント大学の精神科主任教授になった頃でした。
「前世に戻ってください。・・・・・さあ、あなたは誰で、どこにいますか」
こう博士が言うと、催眠状態の被験者は、自分に関する別の時代、別の場所でのエピソードを詳しく話し始め、その時の自分の姿を再び演じてみることさえありました。(同書17頁)
このような催眠下の被験者を通じて、ホイットン博士は人間の生まれ変わりの理由を明らかにしていきました。
簡単にいえば、それは魂の修行をするために自ら選んで、この世に生まれてくるということです。
人間は、いろいろと自分の修行に適した計画をたてて生まれてきますが、なかにはその計画が充分でない魂もあるようです。
それを催眠下の被験者が博士に告げるときには、必ず不安そうな表情になります。一方、はっきりした計画を持った魂は、その計画が困難に満ちたものであっても、淡々としてそれを博士に語るそうです。
そして、計画が決定されれば、あとはまた、生を受けてこの地上の肉体に戻ることになります。
つまり、人間の誕生は、この世での修行への出発であり、死とはまさにあの世への帰郷で、修行の苦しみから解放されて憩いの期間に戻ることにほかなりません。
死とは、だから、本当は悲しむべきことではないのでしょう。
逆に、修行とはいえ、時間と空間のない自由なあの世から、肉体をまとって物質界の拘束を受けるこの世に生まれることは一種の苦痛であるにちがいありません。
そのために、またこの世に生まれることに消極的な魂も少なくない、といわれています。
人は自ら選んで生まれ変わる
一体今まで私たちは何回くらいこうして生まれ変わっているのでしょうか。私自身も、いろいろな前世で、意欲を持って生まれたり、消極的な生まれ方をしたこともあったはずです。
私は霊能力はありませんから自分ではわかりませんが、自分の過去生について何度かは聞かされてきました。『天国からの手紙』には、アトランティス以来の私の生まれ変わりの模様をかなり具体的に一覧表にしたものもあります。
ホイットン博士の被験者の場合、死んでから次に生まれ変わるまで最低一〇か月、最も長いものでは八〇〇年以上だそうです。
平均的には四〇年ほどになりますが、その数値は、過去数百年の間に確実に縮まってきました。
昔の世界では大きな地球上の変化はなく、今日ほど生まれ変わりの誘因が見られませんでした。現代では、地球上の変革が相次いで、この世での新しい体験を待ち望んできた魂たちを誘い込むため、生まれ変わりの頻度が増えてきているようです。
それが、世界の人口の急激な増加につながっているのだといわれています。
ホイットン博士は、このような人間の生まれ変わりありようを、自らの長年の研究と退行催眠による実証をとおして、つぎのように述べました。
一番重要なのは、今回の人生で私たちがおかれた境遇は、決して偶然にもたらされたものではないということである。私たちは、この世においては、あの世で出生前に自ら選んだことを体現しているのである。私たち自身が、あの世で肉体を持たない状態の時に決定したことによって、今回の人生が決まる。そして、どのような潜在意識で人生を生きていくかによって、いわゆる運、不運も決められるのである。(同書115頁)
もっとも、この人の生まれ変わりについては、死後の生命と同様、様々な異論、反論がないわけではありません。日本でも長い間、低迷状態を続けてきました。
アメリカでもそれは同じです。
それが、アメリカでは、一九八〇年代くらいから少しずつ状況が変わってきました。
たとえば、アメリカの映画女優シャーリー・マクレーンが、一九八三年に、自らの霊的体験を『Out on a Limb』(邦訳『アウト・オン・ア・リム』)という本に書きましたが、これは全米で三百万部を越す大ベストセラーになりました。
その結果、全米で輪廻転生を信じる人が、一九八一年のギャラップ調査では二三パーセントであったのに対して、この本が出てからは、その割合が三五〜四〇パーセントに跳ね上がったといいます。(ワイス『前世療法』山川訳、PHP、1991、271頁)
人間は本当に死んでも生き続けるのでしょうか。そして、生まれ変わりはあるのでしょうか。
その真偽を探るために、ジョージア大学教授のロバート・アルメダー博士は、死後の生命についての肯定論者と否定論者の主張を客観的に分析し検討する作業を続けてきました。
その結論はどうだったでしょうか。
一九九二年に博士は『死後の世界』(笠原敏男訳、TBSブリタニカ)を書いて、その検討結果をつぎのように述べています。
私たちは現在、人類史上はじめて、人間の死後生存信仰の事実性を裏づける、きわめて有力な経験的証拠を手にしています。このことが、哲学や倫理学における今後の考察に対して持つ意味は、きわめて大きいといえます。
人間が死後にも生存を続けるという考え方は、誰にでも認められる証拠によって事実であることが証明できるばかりか、誰にでも再現できる証拠によって、事実であることが、すでに証明されているのです。(189頁)
このように、死後の生が「証明された事実」であっても、それでもそれを受け付けようとしない人には、やはり押しつけてはならないのでしょう。
キュブラー・ロス博士も言っているように「死んだらどうせわかること」だからです。
ワイス博士の生まれ変わりの証言
ホイットン博士に引き続き、ここではもう一人、退行催眠研究者について触れておきたいと思います。
アメリカのマイアミ大学医学部教授であったブライアン・L・ワイス博士です。
一九八八年に『Many Lives, Many Masters』と題して、退行催眠の実例を紹介する本を出版しましたが、これも二百万部のベストセラーになり、霊的知識の普及に大きな役割を果たしました。
これは日本では、『前世療法』というタイトルで山川紘矢さんご夫妻によって翻訳されて出版されています。
この本の原題のなかの「マスター」とは、日本では一般に指導霊とか守護霊といわれています。
私たち一人一人を保護し、魂の成長の助言や指導を行ってくれているいわば私たちの「恩師」です。
恩師は当然、私たちのことはすみからすみまで何でも知っているので、退行催眠の時など、超意識下で恩師からのメッセージを受けることがあります。ワイス博士は、そのような自らの体験をこの本にまとめました。
その序文のなかで、博士はこう書いています。
私がこの本を書いたのは、心霊の分野、特に生まれる前や死んでから後の魂の体験に関する研究に、少しでも貢献するためである。これから読者の方々がお読みになるものは、一字一句、本当のことである。私は何一つつけ加えていない。(同書、九頁)
このワイス博士は、やや長めの金髪で魅力的なキャサリンという神経症の患者を退行催眠によって治療していました。
キャサリンは、水を怖がり、暗闇を怖がり、飛行機を怖がり、そして何よりも死をひどく恐れていたそうです。それらの原因を退行催眠によって治療していく過程が、本の中では時間を追って詳細に書き記されています。
しかしここでは、そのキャサリンが、退行催眠の治療を受けている最中に、指導霊からワイス博士宛のメッセージを伝えた部分だけを取り上げてみることにしましょう。
ワイス博士の前で長椅子に横になり、深い催眠状態に入っているキャサリンが急にこう言い出したのです。
あなたのお父様がここにいます。あなたの小さな息子さんもいます。アブロムという名前を言えば、あなたはわかるはずだと、あなたのお父様は言っています。お嬢さんの名前はお父様からとったそうですね。また、彼は心臓の病気で死んだのです。息子さんの心臓も大変でした。心臓が鳥の心臓のように、逆さになっていたのです。息子さんは愛の心が深く、あなたのために犠牲的な役割を果たしたのです。彼の魂は非常に進化した魂なのです。・・・・・彼の死は、両親のカルマの負債を返しました。さらに、あなたに、医学の分野にも限界があること、その範囲は非常に限られたものであることを、彼は教えたかったのです。(56頁)
これを聞いたワイス博士は、びっくり仰天します。
「今、一九八二年、私の薄暗い静かな診療室で、隠されていた秘密の真実が、耳を聾する瀧の如く、私の上に降り注いでいた」と博士は書いています。
正確を期するために、このあとも、博士自身のことばでその驚きを再現してみましょう。
鳥肌が立つ思いだった。こうした情報をキャサリンが知っているはずがなかった。どこかで調べることができるようなことでもなかった。父のヘブライ名、一千万人に一人という心臓の欠陥のために死んだ息子のこと、私の医学に対する不信感、父の死、娘の命名のいきさつ、どれもあまりにも個人的なプライバシーに関することばかりだった。しかも、どれも正確だった。 ・・・・・もし、彼女がこんな事実を明らかにできるのであれば、他にどんなことがわかるのだろうか?私はもっと知りたかった。
「誰?」。私はあわてて言った。「誰がそこにいるのですか?誰がこんなことをあなたに教えてくれるのですか?」
「マスター達です」と彼女は小声で言った。
「マスターの精霊達が私に教えてくれます。彼らは私が肉体を持って、八六回生まれていると言っています」(59頁)
この時以降、自分の人生はすっかり変わってしまった、とワイス博士は言っています。
神の手が差し伸べられて、彼の人生のコースを変えてしまったのです。
それまでは、注意深く批判的に一定の距離を置いて読んでいた沢山の霊界に関する本の内容が、すべて納得できました。彼は、亡くなった父も息子も「生きている」ことを知りました。
「私は事実を掌握したのだ。証拠を得たのだった」と博士は結んでいます。
しかし、人生が修業の場であるとすると、ワイス博士の息子さんの場合もそうですが、なぜ幼くして死んでしまうということが起こるのでしょうか。
それは、若くしてこの世を去る人々は、すでにこの世での目的を果たしてしまったためか、あるいは、若くして亡くなること自体が、その人や家族にとって大きな意味を持ちうるからなのだそうです。
福島大学助教授の時に『生きがいの創造』(PHP、1996年)を書いた飯田史彦さんは、
「その人たちには、それ以上生きながらえて、成長する必要がありません。なぜなら、自分たちの死が、両親の成長を早める材料になっているからです」という指導霊からの教えを引用して、つぎのように述べています。
もちろん、亡くなった直後に自分の役割を思い出しますから、若くして亡くなった魂も、自分の死を後悔することはありません。むしろ、「自分が死ぬことによって両親や家族の精神的成長を早める」という役割を果たしたことに大いに納得し、両親をあの世から激励するのです。親にとって、子供の死ほど精神的に成長できる貴重な試練は、ほかにないためです。
しかも、決して永遠の別れではなく、いつかこの世を去ったときに、必ず再会することができます。これらの仕組みを、さまざまな根拠のある科学的知識として知らせることによって、「死別の悲しみ」という、抜け道のない暗やみの中にとどまりもがいている方々を、どれだけ救うことができるでしょうか。(153頁)
この「決して永遠の別れではなく、必ず再会できる」ことは、知る人ぞ知るで、霊界通信などでは当たり前の「常識」になっているようです。
私も、あの世へ行けば、妻や長男とも再会できることを知っています。その時には、長男からも、二一歳の若さで霊界へ移った理由を改めて聞かされることになるのかもしれません。
もうひとつ、若死にしなくても、精神病や肉体的障害などをもつことの本当の意味はなんでしょうか。
ワイス博士は、「重い精神病や肉体的障害などのように、深刻な問題を持つことは、進歩のしるしである。こうした重荷を負うことを選んだ人は、たいへん強い魂の持ち主だ。なぜなら、もっとも大きな成長の機会が与えられるからである」と述べています。
そして、「普通の人生を学校での一年間だとすれば、このような大変な人生は、大学院の一年間に相当します。安楽な人生、つまり休息の時は、普通は、それほど意味を持っていないのです」とさえ言い切っているのです。(『前世療法(2)』217頁)
武本昌三『天国の家族との対話』 ―生き続けているいのちの確かな証し― (pp.51-64)
9. (第6章 生き続けている妻と長男の命を確認する) (2014.08.01)
第六章 生き続けている妻と長男の命を確認する
真理を受け容れる心の準備
一九九一年四月から私は、ロンドン大学の客員教授としてイギリスに渡り、ロンドン郊外のロチェスターという町に住んでいました。
ロンドンでは、私は大学へ通うかたわら、折をみては、大英心霊協会を訪れていました。
大英心霊協会というのは、一八七二年の創設以来、イギリスの作家コナン・ドイルや著名な物理学者オリバー・ロッジなど、多数の名士によって支えられてきた世界的に有名な心霊研究の殿堂です。
『霊訓』で知られる古代霊・シルバー・バーチに目を向けはじめたのもこの頃からです。
大英心霊協会には心霊関係の書籍コーナーもあって、私はこのシルバー・バーチのほかに、コナン・ドイルの心霊研究に関する著作などにも親しんでいました。
しかし、大英心霊協会に通いながらも、シッティング(霊能者の前に一対一で座って霊界からの通信を受ける)にはなかなか踏み切ることはできませんでした。
日本では、何年もの間 S 教団や T教団などに通い、多くの霊能者と称する人たちから何十回も霊言を聞いてきましたが、それらが霊界からの妻や長男からであるという確信を掴むことは最後まで何一つ出来ませんでした。
ただ、霊界から通信を受け取るということは、それが事実なら大変なことに違いありません。その「大変なこと」が簡単に起こらないのは、私のような霊界について無知の者にとっては、当たり前ではないかとも考えていました。
コナン・ドイルやシルバー・バーチの本で、まず一生懸命に霊界のことを学ばなければならないと思っていたのもそのためです。
それに、私が日本で接してきた霊能者たちは、霊界に意識を通わせている間は、ほとんどみんな、グググ・・・と喉をつまらせているような、独特の発声をしていました。
大英心霊協会でもイギリス人の霊能者たちは、英語でそのような独特の話し方をするのかもしれません。
そのために、私は、霊能者の前に一対一で座る前に、そのような霊言を英語で聞くことにも慣れておかねばならないと考えていたのです。
自分なりに霊界について学び、十分に心の準備をしたうえで、大英心霊協会の霊能者の前に座る。それでも、妻や子について確信できることが何も掴めなければ、もう私には希望は残されず、いつまでも救われないことになります。
大英心霊協会の霊能者に会うというのは、ですから、私にとっては最後の賭けのようなものでした。
それだけに、その最後の賭けでも失望する結果になることを怖れて、私は切羽詰まったような気持ちになっていたのです。
大英心霊協会では、私はまず、何度か霊界通信の公開デモンストレーションに参加してみました。霊的真理を普及させていくというのは営利事業であってはなりませんから、この種の行事はすべて無料です。
一九九二年の一月中旬、ある時の公開デモンストレーションで、私は数十人の参会者に交じって、気持ちを静めて座っていました。
その時の霊能者S氏は、気軽に演壇に立って、「普通の」英語でたんたんと語り始めました。
霊界や霊界通信などについて、当たり前のことを当たり前に話している感じでしたが、私はそのことばを一言も聞き漏らすまいとして、全神経を集中していました。
S 氏は導入部の話は短く切り上げて、いきなり中央の私の斜め前に座っていた若い女性に問いかけました。それからの問答は次のように続きました。
――あなたのおばあさんはいま霊界にいますね。
「はい」
――あなたはピアノの練習を続けていますね。ピアニスト志望ですか。
「はい」
――おばあさんもピアニストでしたね。おばあさんはあなたをとても可愛がっていました。あなたがピアノを練習しているのを、おばあさんは、いつも傍から見ていますよ。
「・・・・・・・・」
ここでは、若い女性は何も言わずに、不思議な感じに打たれているようでした。彼女もこのような霊能者の前で話を聞くのも初めてだったのでしょうか。どうしてそんなことがわかるのだろうと、戸惑っている雰囲気が伝わってきます。
その次にS 氏が言いました。
――おばあさんのお名前はメアリーですね、自分はメアリーだと言っています・・・・・」
それを聞いた途端に、その若い女性はわっと声をあげて泣き出しました。大勢の聴衆のなかで所かまわずといった感じです。
S氏の言ったことが本当であることをその泣き声が物語っていました。
会場はシーンと、水を打ったように静まり返りました。
私にとっても、これは新鮮な驚きの体験でした。それまで、霊能者が初対面の見知らぬ相手を前にして、霊界にいる家族の名前まで言い当てるというようなことがあるとは、その時の私には想像することもできなかったのです。
初めてのシッティング
その後、一月三十日、私はイギリスへ来て初めてミーディアム(霊媒)とのシッティング(ミーディアムが面談者に関係する霊と交信すること)を予約しました。
三十分コースで料金は千五百円くらいです。ミーディアムの交通費などを考えれば、ほとんど奉仕活動に近いといえるでしょう。病気の治療の場合のヒーリング・コースでは、無料でした。
予約した時間に、私は大英心霊協会の一室で、アン・クーパーという名前の霊媒の前に座りました。
私は彼女が霊能者である以外にどういう人かまったく知りませんでした。たまたま、その人の時間が空いていたので、予約しただけです。
固くなっている私の前で、彼女はちょっとお祈りを捧げた後、はっきりした口調で語りはじめました。霊言の訛りのようなものはありませんでした。
時折の彼女からの問いには、私は、緊張して答えました。
その主な部分をありのままに再現すると、次のようになります。
――二人のレディーが現われています。一人はまだ若く、もう一人は老人です。若いレディーは、親しげにすぐあなたのそばに立っています。美しい人ですね。あなたの妹さんですか?
「いいえ、霊界に妹はいません。私の妻でしょう。どのように見えますか?」
――髪は黒く……(というように顔の表情を説明して)、特に化粧してはいないようですが、美しい人です。控えめな態度で、洋服を着ています。もう一人は、あなたのお母さんです。昔風の服を着ています。
――二人の若い男性が出てきました。あなたは霊界に二人の息子さんがいるのですか?
「いいえ、息子はひとりだけです。その息子が霊界にいます。あとは娘が一人います」
――それでは、もうひとりの男性は近親者の誰かですね。
――あなたの息子さんは、身長五フィート八インチ(約百七十三センチ)くらいに見えます。黒い髪、美しい顔です。非常に好ましい青年です。
――あなたの息子さんは、何か忙しく仕事をしているようです。あっ、図書館が見えてきました。彼は図書館を指差して、「研究をしている」と言っています。
「どのような勉強をしているのですか?」
――あなたの息子さんは、たいへん知能が高いですね。難しい知的な研究で、私には説明しにくいです。心理学のようなものでしょうか。人間のこころを世代を超えて伝達させる方法のようなものを研究しているようです。霊界の上層部の人々からの指導を受けて、「やらなければならない仕事がたくさんある」と言っています。
「私がいま、ここにいるのを彼は知っていますか?」
――もちろん、知っています。あなたに強い愛情を送っています。姉さんとは、年齢があまり違わないようですね?
「そうです、一年と少しの差しかありません」
――息子さんの後ろから、お祖父さんが出てきました。息子さんもそうですが、お祖父さんも強力な霊的エネルギーを持っているようです。二人は霊界で活躍していて、祖父と孫というよりは同僚のようなところもありますね。霊的レベルの高い人たちで、こういう人たちの話を紹介できるのは、ミーディアムとしてはたいへん光栄です。
――広い大きな居間のなかに、ハスの花が浮かんでいる大きな円形の鉢があって、あなたの息子さんが、そのなかからマグノリアに似た花を一本抜いて、いまあなたに手渡ししています。非常にあたたかい家庭的な雰囲気です。こういう雰囲気を伝えられるのは、私もうれしいです・・・・・・。
このような通信レベルでの霊言を聞いたのは、私にとっては初めてのことです。日本でいろいろな霊能者から聞いてきた「霊言」とは、内容の正確さでも具体性でも、まったく違っていました。
このなかの「近親者の誰か」というのは、多分、弟のことのようです。
四十代であった弟は、倒産した会社を再建させるのに苦労していましたが、私が渡英する直前、一九九一年の二月に、心不全で急逝しました。
このシッティングでは、断片的ではありますが、富子と潔典のことなどが、かなり正確に語られています。
例えば、潔典の身長は実際には百七十四センチですから、五フィート八インチ(百七十三センチ)は間違ってはいません。心が純粋で明るく、誰からも好かれる優しい性格でした。大学の成績も入学以来ほとんど全部「優」でしたから、語られた容貌、性格、知的資質も、ほぼその通りといってよいでしょう。
父や母、弟のことなども、言われていることに違和感はありませんでした。
私が子どもの時から誰よりも偉いと思い続けていた父が、強力な霊的エネルギーを持っていてレベルが高く、潔典と同じように霊界で活躍しているというのにも、十分に納得できました。
途切れ途切れに語られていたので、三十分の時間は瞬く間に過ぎ去りましたが、明らかに正確度の極めて高いことばの数々を受けとめて、私はこころの高揚を抑えきれずに、半ば、夢見心地で、大英心霊協会を後にしました。
アン・ターナーによる霊言
この後は、私は矢継ぎ早に大英心霊協会でシッティングを受けるようになりました。
一日に2回受けたこともあります。登録された20人ほどの霊能者のスケジュールに空いている時間があれば、私は片っ端から申し込みをしていきました。
そして、ついに、その大英心霊協会で、こころに思い続けていた妻と長男に「再会」することができたのです。
この「再会」は、その時の私にとってゆるぎのない確信でした。
一九九二年二月十一日のことで、それまでの迷いと悲しみから抜け出したこの日のことは、私にとっては忘れられない記念の日になっています。
札幌の青木耀子さんの霊言以来、S教団やT 教団などで何十回となく霊能者に向かい合ってきて、半ば信じ、半ば疑い、そして苦しみ悩み、結局何もつかめないでいた状態がロンドンへ来てからも続いていました。
それが、疑うにも疑いようのない明白な形で事実を突き付けられて、私は体が震えるほど深く感動し、重苦しく漂っていた疑いの靄もすっと消えて、こころからの安堵感を覚えたのです。
その日、二月十一日の長男の潔典と妻との「再会」は、私にとっては重大な出来事でした。
全く予想もできなかった奇跡でした。
その「再会」の様子を、私は強い感動と感謝の気持ちのなかで、すぐに東京にいた長女へ知らせましたが、その時の手紙に、私は次のように書きました。
これはもちろん、全く公開を予想していませんでしたので、私ごとの羅列になってしまいますが、ありのままをお伝えするために、あえてそのまま、一部を引用させていただきます。
二月十一日の耕治叔父さんの命日には、札幌では英子叔母さんの親戚の人たちが十人くらい集まってくれたらしい。有り難いことだと思っている。お父さんもこちらで、日本時間に合わせてお供えをし、こちらの十一日には、ロンドンの大英心霊協会へ行った。いままで何度も、大勢のなかでの公開実験に参加して、お父さん自身が霊界からの通信を受ける場合の準備をしてきたが、近頃は、一人で霊能者の前に座って、一対一で直接話を聴くようになっている。
十一日は耕治叔父さんの命日でもあるので、かねてから、この日を予約していた。霊能者は、まずママと潔典が霊界にいることを見抜いた。それから、「あなたの弟さんも霊界にいますね」と言った。その霊能者アン・ターナーによれば、霊界でも耕治叔父さんの「記念日」にお父さんが大英心霊協会に来て神妙に座っているというので、みんなが集まっていたらしい。耕治叔父さんは、すぐに出てきて、お父さんの横に立っていたようだ。そして、潔典が出てきた。潔典はお父さんの前に立って、非常に感動している様子だと、アン・ターナーが言っていた。
ここでアン・ターナーが出てきますが、彼女とは会うべくして会ったことを、かなり後で私は知るようになります。彼女の指導霊は中国の古代霊だそうですが、霊界の潔典がその指導霊に頼んで、二人を引き合わせもらったというのです。
その当時は彼女もロチェスターに住んでいました。それも私の家から歩いて10分ほどの近くです。
彼女とはそれから何度も会うようになりますが、初めのうちは、意識して、私は彼女には家族のことを極力何も伝えないようにしていました。
この手紙は、こう続きます。
お父さんは、この霊能者のアン・ターナーに大英心霊協会で初めて会って、その前に黙って座っているだけで、アン・ターナーはお父さんのことは何も知らない。日本から来ていることも、事件のことも、家族のことも、彼女には一切言っていない。アン・ターナーは、「あなたの前に立っているのはあなたの息子さんで、身長は五フィート・八インチ(一七三センチ)ぐらい、聡明な顔つきに見える」と言う。潔典の身長はそのくらいだろう。
しかし、それだけではまだよくわからないから、お父さんは黙っていた。アン・ターナーは、また言った。「息子さんが、自分の名前は、キュオーニとかクヨーニだと名乗っている」。そして、何度か、「キューオーニ、キヨーニ、クヨーニ」と独り言を言うようにつぶやいた。
お父さんは、はっとした。これは潔典だ。潔典に違いない。ほかの名前ならこのように聞こえるはずがない。しかし、それでも念のために次のように聞いた。
「それは英語の名前か?」
「そうではない、外国語の発音で私にはよくわからないが、そのように聞き取れるのだ」
潔典(きよのり)という発音は、たしかに日本語になれていない英米人には聞き取りにくい。これを一度聞いて、正確にくり返すことの出来る英米人はほとんどいないだろう。そこでお父さんは、思い切って聞いてみた。
「その発音は、『キ・ヨ・ノ・リ』とは違うか?」
彼女は答えた。
「そうだ、キヨノリだ。キヨノリと言っている」
長男の潔典の名前をこのように言われたことは、私にとっては重大なことでした。私は、娘にはあまり強い刺激にならぬように注意しながら、なるべく感情を込めずに淡々とこの手紙を書いたつもりなのですが、実際には、私の心の中は激しく揺れ動いていました。
事件後、長い年月、何年も何年も苦しみ続けてきて、いま初めて、一つの大きな山を越えようとしている。そのような思いが激しくこころを揺さぶっていたのです。
疑うことのできない霊言の真実
この手紙はまだ続きます。もう少し、引用させていただきます。
・・・・また、アン・ターナーはつぎのようにも言った。
「息子さんは、あなたの左足に scar(傷跡)があると言っている」
お父さんは、このへんでかなり緊張していた。言っていることはよくわかっていたが、左足には傷跡はない。だから「私の左足には傷跡はない」と、率直に答えた。なぜそんなことを言うのだろうと、不審にも思った。
しかし、アン・ターナーは怯まなかった。「それは古い傷跡で、もう消えかかっているのかもしれない。必ずあるはずだから探して見よ」と言う。いくらそう言われても、自分のことは自分が一番よく知っている。無いものは無い、とお父さんは思った。そこでちょっと失望して、その日の面接は終わった。
本人の私が傷跡はないと言っているのに、アン・ターナーは必ずあるはずだから探して見よと言うのです。アン・ターナーはいつもこういう調子で、霊言については確信を持って伝えていました。
あてずっぽうで言っているのであれば、当の本人の否定にあえば少しはたじろぐはずですが、彼女にはまったくそういう様子はありませんでした。
この場合は、私が勘違いしていたのです。手紙で私は、こう続けています。
そのあと、家へ帰るためにヴィクトリア駅の方へゆっくり歩きながら、突然、はっとして立ち止まってしまった。アン・ターナーの「scar」ということばで、お父さんはつい、刃物の傷跡のようなものを連想してしまったのだが、やけどの跡も「scar」ではないか。
それならお父さんには、子供の時に、湯たんぽでやけどした傷跡が大きくいまもはっきりと残っている。それを知っている者は、潔典を含めて家族しかいない。ただひとつ、違っているのは、そのやけどの傷跡は、左足ではなく、右足だ。しかしこれも、前に立っていた潔典からは、お父さんの右足は、左足になる。
潔典は、やはりあの時、お父さんの前に立っていた。自分の名前を告げ、お父さんの足の傷跡を言い当てることで、それが間違いなく潔典であることを一生懸命にお父さんに訴えようとしていたのだ、深い感動を顔に表しながら。お父さんがやっとここまで来てくれたことを、そして、潔典やママが「本当にまだ生きている」のだということをお父さんが理解し始めたのが嬉しかったのだろう。
事件後まだ札幌にいたとき、青木さんを通じての霊言で、潔典から「いつまでも元気がない・・・・お父さんは何でも出来る人ではないか」と言われたことがある。そのお父さんがやっといま、少しずつ立ち直ってきた。何よりも、潔典やママが元気で生きていることがわかって、あのように潔典やママたちの前に座るようになった。これからは、もっともっと「対話」ができるようになる。だから、潔典は感動していたのであろう。お父さんも感動していた。
私のことは何も知らない初対面のイギリス人から、ひとことも私や家族のことは話していないのに、妻や長男が霊界にいて、長男の名前から私の足の傷跡のことまで告げられる、というようなことは、普通ではあり得ないことでしょう。
そんなことがあれば、それは奇跡としか思えませんが、その「奇跡」が現実に私に起こったのです。
その後、潔典とは、何度か「会い」、二月二十四日の妻の誕生日には、妻とも「会い」ました。
そして、日本へ帰国してからも、毎年六月五日の潔典の誕生日に、アン・ターナーを通じて、潔典と文通も続けてきました。
次章で取り上げるのは、そのうちの一つです。
武本昌三『天国の家族との対話』 ―生き続けているいのちの確かな証し― (pp.65-71)
|