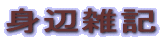
アジア大陸最西端の地 (身辺雑記 24)

ヨーロッパ側のトプカプ宮殿テラスから
ボスポラス海峡を隔てて見たアジア側。
(2004.12.04) 筆者撮影
トルコ共和国の国土は、アジアとヨーロッパの二つの大陸にまたがり、広さは、日本の約
2.1倍の78万平方キロです。東西に約 1,600キロ、南北に約 650キロ広がっていて、その97パーセントがアジアに、残りの3パーセントがヨーロッパに位置しています。このアジアとヨーロッパの二大陸をまたいでいる特異性をもっともよく表しているのが、「アジアとヨーロッパの架け橋」といわれるトルコ最大の都市イスタンブールでしょう。
イスタンブールは、長さ約 30キロのボスポラス海峡でアジア側とヨーロッパ側に分かれてしまっています。この二つの大陸を結んでいるのが、南側のボスポラス大橋と北側のファティフ・メフメット大橋(通称第二ボスポラス大橋)で、この二つの橋が文字通りの「アジアとヨーロッパを結ぶ架け橋」です。人々は、この二つの橋を渡り、あるいはフェリーに乗って、アジアとヨーロッパを行き来しています。
私が初めてイスタンブールを訪れたのは、1997年の春のことでしたが、観光の名所になっているヨーロッパ側東端のトプカプ宮殿のテラスから、目の前のボスポラス海峡を隔てて対岸のアジア側を眺めたときには、ひとしおの感慨を禁じ得ませんでした。日本はアジア大陸のほぼ東端に位置していますから、そのアジア大陸が、日本から始まり、中国、パキスタン、イランなどの国々を経てここで終わっていることを目の前で確認することが、やはり、なにか意味があるような気がしていたのです。
今年の一月、私はたまたま日本最西端の地を訪れていました。石垣島からさらに西へ130キロ離れた与那国島です。その与那国島西端の西崎(イリザキ)が日本最西端の地で、そこには最西端であることを示す碑も建てられています。北緯24度27分、東経122度56分です。しかし、イスタンブールでは確かにアジア大陸が終わっていますが、アジア大陸の最西端ではありません。トルコの地図をみてもわかるように、北の黒海からボスポラス海峡を通ってマルマラ海に抜けると、その南側にはさらにトルコの大地が西へ広がっています。
ボスポラス海峡が黒海とマルマラ海を結んでいるように、マルマラ海の西端では、またアジアとヨーロッパの両大陸が接近してきて、ダーダネル海峡になり、それを抜けると、エーゲ海にでることになります。ちょうとそのあたりには、あのトロイ戦争で有名なトロイの町がありますが、このあたりがアジア大陸の最西端ということになるでしょう。小さな島がまわりに点在していて正確な位置は分かりませんが、大体北緯40度、東経26度あたりです。今度の旅行では、私はその辺もバスで通りました。
今度は、成田からイスタンブールに直行して、一泊してからは夜行の寝台列車でまず首都のアンカラへ行き、そこからはバスで南下して、パムッカレへ向かいました。そのあたりのトルコ中北部では、たまに通る市街地を除くと寒々とした荒れ地がどこまでも広がっているという感じです。やせ細ったポプラが枯れ木のようにところどころで立っているぐらいで、遠くに見える山々はうっすらと雪をかぶっています。何時間も走り続けて、コンヤから西へ折れても、そのような風景は続いていました。やっとエフェソスあたりまで来てエーゲ海が見え隠れするようになる頃から、車窓から見える景色は変わり始めます。緑が目立つようになり、松やオリーブなどのほか、イチジク、オレンジ、桃、ミカンなどの果樹も増えてきて、ところどころ、きれいなホテルや家々が並んだ保養地なども目に入るようになります。
イスタンブールを出て東へ向かい、広大なトルコの大地の西半分を一回りする形で南に折れ西に向かってまたイスタンブールへ帰る。このようなルートで2000キロ近くを走り、トロイまで来て古代の遺跡のなかに立ちますと、西方にエーゲ海が視野に入ってきます。そこがアジア大陸の最西端です(正確には、「ほぼ最西端」といわねばなりませんが)。
このトロイから少し北上すると道はダーダネル海峡にぶつかり、バスは海峡のアジア側を進んで行きました。そのエーゲ海からダーダネル海峡沿いのうすい紫がかったような風景と、その風景のなかでアジア大陸の最西端を走っているのだという感慨が今の私には、忘れ難い思い出の一こまになりそうです。今年、2004年の1月には日本の最西端の地を訪れ、12月にはたまたま、アジア最西端の地を通り抜けたという感傷めいた気持ちも、少しはあるからかもしれません。
(2004.12.15)

長崎県五島列島の「ルルドの水」 (身辺雑記 23)

五島列島・福江島の井持浦教会にある
日本最初の「ルルドの水」。泉水はこの
マリア像の右下から流れ出ている。
(2004.11.16) 筆者撮影
フランス南部のピレネー山脈の麓にルルド(Lourdes)という町があります。いまでは人口も1万5千になり、「ルルドの聖水」で世界的に有名になっていますが、かつては山間の小さな寒村のひとつにすぎませんでした。1844年1月7日、この村の貧しい農家の長女として、ベルナデッタ・スービルー(Bernadette Soubirous) が生まれて、やがて、この子がこの山里の村を大きく変えていくことになります。
1858年2月11日、ベルナデッタが14歳の時、ポー川のほとりにあるマッサビエール洞窟の近くで、彼女が薪拾いをしていると、聖母マリアが現れました。ベルナデッタのまわりに突然風が吹き渡り、ふと顔を上げてみると目の前に白衣の聖母マリアが十字を切ってお祈りしている姿が見えたというのです。聖母マリアは、その後も繰り返し少女の前に現れて、その回数は最初の時のを含めて18回にもなったといいます。
9回目に現れたのはその年の2月25日のことでした。この時には聖母マリアは、洞窟の方を示して、「泉から出てきた水を飲んで顔を洗いなさい」とベルナデッタに告げたそうです。ベルナデッタは、洞窟へ行ってみましたが泉はありません。そこで、示された場所を右の手で掘り出しますと、小さな窪みができて、その底から泥水がにじみ出てきました。彼女は、その水を飲もうとしますが、濁っている泥水なので飲めそうもないのです。捨ててしまいました。2、3度同じようにしたあと、4度目に、やっと手ですくった水を飲み干しました。
ところが、その日のうちから、この小さな窪みにはこんこんときれいな水が湧き出してきたのです。その3日後、たまたま目を患っていた人がその聖母マリアから告げられた水のことを聞いて、その水で顔を洗ってみますと、忽ち目の病はなおってしまったということもありました。その話は村中にひろがり、人々はその水を持ち帰って、病気の人に飲ませるようになります。飲んだ人はみんな、病気が治っていったそうです。はじめは半信半疑であった教会の神父たちも、病人がその水をのんで治っていく様子を現実につぎつぎにまのあたりにするようになっては、その奇跡を認めざるを得ません。噂は噂を呼んで、大騒ぎになりました。それがルルドの奇跡が知られるようになった始まりです。
その後もこのルルドの泉は、現在に至るまで140年以上にもわたって涸れることなく湧き続け、いまでは、年間500万人もの巡礼者が訪れるカトリックの聖地になっています。いろいろな病気を持った人が、このルルドの水を飲んで、いまもつぎつぎに治っているという不思議な水で、「神の水」としてひろく崇められているようです。1927年には「ルルド国際医学会」も設立され、世界30か国の5000人以上の医師が名を連ねて、ルルドの水のもたらす効果についての研究を続けている、ともいわれています。化学分析をしてみても、このルルドの水には、普通の水にはない活性水素が多量に含まれていることがわかっていますが、おそらく、奇跡がもたらされる要因はそれだけではないのでしょう。
ベルナデッタは、「ルルドの聖水」で一躍有名になりましたが、世間の喧噪を逃れるように尼僧院の学校の寄宿生になって、外界から遮断された生活を送るようになりました。そして、1866年からは修道院に入って12年間の祈りの生活を送ったあと、35歳で亡くなっています。しかし、奇跡は、このあとでも起こりました。
死後30年経って、何かお告げでもあったのでしょうか、ベルナデッタの墓を掘り返してみると、彼女の遺体は、少しの腐敗も硬直もなく、皮膚もバラ色で、まるで生きているようであったというのです。当時のことですから防腐剤が注入されていたわけでもなく、ミイラにするときのような人為的な技術が施されていたわけでもありません。それなのになぜ、遺体が生きたままのような状態であり続けてきたのか。これも本当に不思議です。奇跡としかいいようがありません。今もベルナデッタの遺体は、少しも朽ちることなく、パリ郊外のサン・ジルダール修道院に安置されています。私はまだこの修道院を訪れたことはありませんが、写真で見ても、その輝いているような寝姿は、とても遺体とは思えず、まるで生きている人が眠っているだけのように見えます。
このベルナデッタの前に聖母マリアが現れたという事実は、ローマ法王によっても公式に認められ、1933年には、彼女は聖人の一人に加えられました。これにより、ベルナデッタと「ルルドの聖水」の奇跡は、いっそう広く、世界中のカトリック信者の間に知れ渡って、厚い信仰の対象になっていきました。そしてその傾向は、日本でも例外ではありません。
日本では、明治維新から5年後の1873年にキリシタン禁制が解かれたあと、特に長崎の五島列島では、各地につぎつぎに教会が建てられていきました。その全五島の宣教司牧にあたったのが、フランス人のアルベルト・ペルー神父でした。彼は、故国のルルドの洞窟をこの日本の五島列島にも作ることを計画し、その場所を、下五島の福江島玉之浦に定めて全五島の信者たちに協力を呼びかけたのです。
その呼びかけに応じて、五島の津々浦々から、教会建造のための石が運び込まれ、信者たちの奉仕によって、1899年に完成したのが井持浦教会です。ペルー神父は、はるばるとフランスからルルドの聖母像を求めて、それを、この井持浦教会の左奥にある洞窟に収め、さらに、本場のルルドの霊水を取り寄せて、井持浦教会の洞窟横の泉水に注ぎ込みました。こうしてできたのが、日本最初の井持浦教会ルルドです。
この教会は、五島列島南端の福江島の南西にあります。東京から行くとすると、長崎空港まで飛行機で飛び、それからフェリーで、約3時間、快速艇で1時間半の航海で福江島に着きます。福江港は島の東側ですから、井持浦教会は島のちょうど反対側になります。直線距離にしますと福江港から約25キロしかありませんが、屈折の多い山道を通ったりしますから、バスでたっぷり1時間半は揺られなければなりません。島のはずれまで来て、本土の最西端が東シナ海にのめり込んでいるあたりにあるのがこの教会です。
この九州の長崎の西の果てに連なる五島列島だけで、50あまりの教会がありますが、そのなかにルルドを持っている教会は、この井持浦教会のほかにも、水の浦、三井楽、浜脇、奈留、鯛ノ浦、曽根などがあって十箇所ほどになります。しかし、そのなかでも、井持浦教会ルルドは、日本本土最西端の遠隔の地にあるにもかかわらず、日本最初のルルドということで、特に強い信者の信仰を集めているようです。フランスのルルドへお詣りするかわりにこのルルドを訪れて、霊水によりお恵みを戴いたという人も少なくはないと聞きました。あのベルナデッタの奇跡は、この日本でも、井持浦教会などのルルドを通して、こうしていまも、多くの人々に恩恵を与え続けているのです。
(2004.12.01)

もう一人の「阿倍仲麻呂」 (身辺雑記 22)

西安の興慶宮公園内に建てられてい
る阿倍仲麻呂記念碑。李白が彼の死を
悼んで詠んだ「哭晃衛詩」などが刻み込
まれている。 筆者撮影(2001.04.13)
私の手許には、2001年4月に中国の古都・西安を訪れたときにもらった「通関文牒」というのがあります。西安は昔の長安で、古来、シルクロードの起点としても有名でした。龍の透かしの入ったA4判くらいの用紙に「有朋遠来 光臨西安・・・・・・:嘉賓尽歓 謹具関牒 永思永念」などと美しい古代漢字が墨書されていて、末尾には古城長安役人の大きな公印が押してあります。長安城に入場することを許可し歓迎するという、いわば、古代のパスポートのコピーといっていいでしょう。
観光行事の特別の企画があって、この二つ折りの、厚い布表紙で装丁された「パスポート」を渡され、私は、何人かの同行の旅人たちとともに、長安上の南門から入城しました。通路には、赤いカーペットが敷き詰められて、門の両側には、古代のしきたりのままに、門番の守備兵、礼装した役人、それに美しく着飾った官女たちが、ずらりと並んで出迎えています。私は、かつて日本から遣唐使としてここを訪れた阿倍仲麻呂たちも、このようにしてこの城門をくぐっていったのだろうか、などと想像しながら、少し面はゆい気がしていました。
むかし、長安には、紀元前11世紀から10世紀初頭まで、2千年にわたって、漢や唐など多くの王朝がここに都をおいてきました。それと同時にこの都は、秦の始皇帝、前漢の武帝、唐の太宗、武則天、唐の玄宗と楊貴妃など、歴史上の英雄やヒロインたちを多く輩出しています。このうちの玄宗の治世下に、阿倍仲麻呂は第8次遣唐使団の一員として、ここへ来ました。その頃の長安は、おそらく、世界第一の文化都市で、周囲14キロの城壁の内部には、世界中からの外交官僚、学者、僧侶、商人たちが賑やかに行き来していたことでしょう。仲麻呂たちが着いたのは、唐の開元5年(717年)のことで、その時彼はまだ、19歳の若者でした。
長安に来てからの阿倍仲麻呂は、ここでは最高の学府であった「太学」で学び、超難関の科挙進士科の試験に合格してしまいます。それからは、玄宗皇帝の信任も厚く、当時の唐という大帝国の高級官吏として、出世を重ねていきました。こうして、いつのまにか在唐36年にもなった阿倍仲麻呂は、753年の冬、第10次遣唐使団の帰国に際して、唐側の使節として、日本へ同行することになったのです。36年ぶりの日本を、彼はどんなにか懐かしんだことでしょう。「天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも」という有名な望郷の歌は、長安から揚州に下り、船出をする長江南岸の黄泗浦(いまの江蘇省鹿苑)で詠んだといわれています。
阿倍仲麻呂は、しかし、この故郷の「三笠の山にかかる月」を見ることはできませんでした。帰国途中の4隻の船団は、阿児奈波島(沖縄本島)に到着後、北の奄美に向かう途中暴風雨に遭遇してしまうのです。そのうち、阿倍仲麻呂が大使の藤原清河と乗った第1船だけは、遠く南のベトナムまで押し流されてしまいました。そこから、阿倍仲麻呂と藤原清河は、幾多の困難を乗り越えながら奇跡的に生き延びて、755年6月、またもとの長安にたどり着きます。長安の人々はさぞ驚いたことでしょう。阿倍仲麻呂が親しくしていた友人で詩人の李白なども、遭難の知らせを聞いた時には、「晃郷(仲麻呂の唐での名前)の行を哭す」という追悼の七言絶句を作っていたくらいでしたから。阿倍仲麻呂は、その後、安南節度使などのベトナム・ハノイ鎮守の最高長官に任じられたりしましたが、日本へは遂に帰ることなく、72歳のときに長安で亡くなりました。
阿倍仲麻呂については、このように、日本と中国の両方の資料で比較的よく知られていますが、この間、西安で、阿倍仲麻呂と同期で遣唐使の一員として唐の都・長安に渡り、その地で36歳で亡くなった日本人留学生の墓誌が発見されたというニュースが大きく報じられました(「朝日新聞」04.10.11など)。中国古代の墓誌というのは、有力者が亡くなったときに、名前や役職、家族などの情報を石に刻み、墓に収めたものだといわれています。その、新しく発見された墓誌の銘文には、専門家の抄訳によりますと、つぎのように書かれているそうです。
姓は井、字(あざな)は真成、国は日本と号す。生まれつき優秀で、国命で遠く唐にやってきて、一生懸命努力した。学問を修め、正式な官僚として朝廷に仕え、活躍ぶりは抜きんでていた。ところが思わぬことに、急に病気になり開元22年の1月に官舎で亡くなった。36歳だった。皇帝は大変残念に思い、特別な扱いで埋葬することにした。尚衣奉御の位を贈った。2月4日に万年県の川のほとりに埋葬した。体はこの地に埋葬されたが、魂は故郷に帰るにちがいない。
玄宗皇帝が外国からの留学生の死を惜しんで、わざわざ官位を追贈するなどということは、非常に異例なことであったにちがいありません。それだけに、この「井真成」という留学生は、よほど優秀な人であったのでしょう。阿倍仲麻呂と切磋琢磨しながら勉学に勤しみ、仲麻呂と同じように、超難関の科挙の試験にも合格していたのかもしれません。当然、阿倍仲麻呂も彼のことはよく知っていたはずですが、そのようなことを示す文書は何も残っていないのが残念です。
この銘文によりますと、彼の死亡したのは開元22年で、これは西暦では734年ということになります。当時の日本の留学生たちは、いつ来るかわからない次の遣唐使船を待ちわびながら勉学や職務に励んでいたと思われます。しかし、記録を調べてみますと、井真成が死亡したときには、たまたま、733年に日本から来た遣唐使船団がまだ唐に残っていて、734年の秋には、そのうちの一隻が日本へ帰ることになっていました。井真成はその年の1月に病気で死ぬことがなければ、留学の十分な成果を携えて、その第1船で帰国できたのかもしれなかったのです。そのように考えてきますと、故郷に錦を飾るのを目前にした彼の無念さが、1270年の時を超えて、ひしひしと胸に伝わってくるような気がいたします。
(2004.11.17)

尾崎秀実氏の淡々とした最後 (身辺雑記 21)
10月17日の「朝日新聞」に、あのゾルゲ事件で死刑に処せられたドイツ人新聞記者リヒアルト・ゾルゲと尾崎秀実の処刑記録が、神田の古書店で見つかったことが大きく報道されました。見出しは、「ゾルゲ・尾崎、淡々と最後」とあります。(文中、敬称略)
これは、連合国軍総司令部が作成したゾルゲ事件の調査報告書で、国防保安法違反などの罪名が列記されたあとに、処刑の宣告と死刑執行の様子が記録された書類です。ゾルゲについては、「静かに教誨師始メ職員ニ対シ『皆様御親切有難フ』ヲ繰リ返シツツ何等取リ乱シタル態度無ク刑場ニ進ミ」などと書かれ、尾崎秀実のところでは、「香ヲ焼キ閉目シツツ心ヨリ敬礼ヲナシ終リニ職員ニ謝礼シ取乱シタル態度無ク刑場ニ入リ南無阿弥陀仏ヲ二唱シ」などと書かれていた、と伝えています。二人の、大悟に徹した最後を垣間見るようで、粛然とした気持ちにさせられます。
尾崎秀実は、まだ覚えておられる方も多いと思いますが、元朝日新聞記者で、第二次世界大戦のさなか東京で逮捕されたときには、第一次近衛内閣嘱託として、中国問題に鋭い筆を振るっていました。獄中で書かれた『愛情はふる星のごとく』は、敗戦後の日本でベストセラーになりましたが、そのなかに、1944年10月7日付けで妻に宛てて書いたつぎのような手紙があります。尾崎秀実はこの一か月後、11月7日に東京拘置所の絞首台で44年の生涯を閉じました。
今月の15日は、私が家を離れて丁度3年になる。17日の我が家の紀念日は、一つ特に私のために祝ってほしいと思う。楊子にも指令を発してほしい。お前もさぞかし感慨の多いことであろう。僕が祝ってほしいと云うのは、この3年の流れ去った月日がこの僕にとってどんなに貴重な有難いものであったかを心から思うからである。この年月があったからこそ、今日僕は始めて人生の真意義を覚り、かくも静かにかつ楽しく日を送ることも出来るようなったのだ。もしもこの異常なる月日が無かったなら、僕は毎日ただ怱忙の裡にあくせくと日を送ってしまったことだろうと思う。僕の一生はもしも僕が別の道を行くならば、恐らくは社会的には高名、栄位をかち得られたことであろう。しかし人間として今日僕の立っているごとき確乎たる足場に立つことは 遂に出来なかったことは明らかだ。
僕は人生の意義を知り、生命の正当なあるがままの姿に徹し、社会と、親しきものへの愛情を限りなく深めるとともにまた純化することも出来た。そこにこそ我々3人のものの永遠に生きる道をも発見し得たのだと、僕はひそかに感じている。だから僕のために祝ってくれることは、実は我々3人のものの共通なよろこびであると私は確信しているのだ。今日このことをお前たちにほんとに分らせることは無理だと思う。すべて冷暖自知あるのみだから。しかしおぼろげには分ってくれたものと思う。僕が決して無理をしたり頑張って、一人こんなことを云っているのでないということを。(尾崎秀実『愛情はふる星のごとく』岩波現代文庫、2003年、pp.371-372)
文中の「わが家の記念日」とは、死刑が確定して自分のいのちが断たれることになった事態を意味しています。「人生の意義を知り、生命の正当なあるがままの姿に徹し」というのは、いのちの何であるかを意識の深いところで感得することができた、ということでしょう。古来、高僧や人生の修行者たちが、難行苦行を重ねたりして会得するいのちの真理を、尾崎秀実は、獄中の死を前にした絶体絶命の境地の中で、確固として自分のものにしていきました。ですからこの文は、「永遠に生きる道をも発見し得たのだ」と続けられているのだと思われます。
この本には、このほかにも、獄中での深い思索を通じて死の恐怖を乗り越え、死を安らかに受け容れる覚悟ができていることを冷静に伝えている手紙などがあります。そういう手紙では、自分の悟りの心境を、決して虚勢を張って言っているのではないことをつけ加えたりしていますが、その手紙の通り、尾崎秀実は、「取り乱したる態度はなく」、「南無阿弥陀仏」と2度唱えながら、聖者のように淡々として死んでいったことが、この資料でも明らかにされたことになります。
私は、ここに引用した手紙を「学びの栞」(B)-10 でも取り上げてきました。そして、その文には、当時は「国賊」とか「売国奴」とまで言われて日本中の非難の的となった尾崎秀実の真実の姿と事件の背景を少しでも正しく理解するために、尾崎秀実の一高時代からの親友であった松本慎一の文も、一部抜粋してつけ加えてあります。敗戦まではあれほどまでに声高に叫ばれていた「鬼畜米英」が、一夜明けると、一変して「民主主義の旗頭」として崇められていったあの異様な風潮のなかで、真の愛国者とは誰であるかを、深く考えさせられる一文です。併せて、是非ご一読いただければと思います。
(2004.11.01)

タイ・クワイ川の「戦場に架ける橋」 (身辺雑記 20)

クワイ川に架けられた現在の鉄橋。かつ
てはこの鉄道の右端がビルマまで通じて
いた。 (2004.10.08) 筆者撮影。
10月のはじめから一週間ほど、商社の駐在員として義弟が滞在しているタイのバンコクを訪れてきました。バンコクへの訪問はこれが3度目です。はじめて訪れたのは、1975年の春で、もう30年近く前のことになります。その頃のバンコクは、街並みのすべてが雑然としていて、いかにも貧しいという印象を受けました。デパートのようなところへ入ってみても、戦後間もない頃の日本のように商品の量も乏しく、旅行者の目から見ると購買欲をそそられるような物はあまりありません。家庭用品売り場では、質の悪いアルミの鋳物鍋が並べられたりしていました。それでも女店員たちは物腰が柔らかく、優しく、歩くときもゆっくりです。語尾を伸ばすようなふんわりしたタイ語の抑揚ものんびりと響いて、貧しさの中にも屈託のない明るさが感じられました。
そのバンコクは、1992年の春に再訪したときには、見違えるように変わってしまっていました。高層ビルが林立する繁華街は、忙しく動きまわる人混みで活気に満ちて、東京の繁華街の賑わいとあまり変わりません。ありとあらゆる商品が店先にあふれ、道路を走る自家用車の数も急にふえて、タイの大きな経済成長を如実に示していました。ホテルのロビーで、携帯電話で話しているタイ人らしい人を見かけましたが、これが私が外国で見た初めての携帯電話です。日本企業の進出も著しく、デパートの伊勢丹やスーパーのヤオハンなども大きな店を構えていたようです。私は少し戸惑いながら、バンコクの近代化の喧噪から逃れて、アユタヤなどの遺跡めぐりをしました。椰子の葉が茂り、水を湛えた田圃が広がる緑の濃いのんびりとした田園風景に接して、やっとタイが実感できたように、ほっと一息つける感じがしたものです。
今回は、はじめて、バスでバンコクから北西へ約130キロのカンチャナブリへ行ってみました。あのアレク・ギネス主演の映画「戦場に架ける橋」で一躍有名になり、アジア諸国のみならず、欧米からも多くの人々が訪れている観光の名所です。クワイ川へ行ってみますと、百数十メートルほどの水量豊かな川に真っ黒な鉄橋が架かっていて、その中を真っ直ぐに一本の鉄道がビルマ側に伸びています。この場所に、日本軍は、木材や竹材を使ってあの映画に出てくるような橋を建てたのですが、それは、戦争の末期に連合軍の爆撃で破壊されてしまいました。ですから、これは戦後架け直された鉄橋で、いまでは、かつての「戦場に架ける橋」の2代目として、歴史的遺産になっています。
第二次世界大戦中、海上からの補給路を絶たれていた日本軍は、ビルマ戦線への補給路を確保するために、タイからビルマへ通じる415キロの泰緬鉄道を1年3か月の突貫工事で完成させました。この工事の最大の難関であったのがクワイ川に架ける橋でした。この難工事を強行するために動員されたのは、タイ側から鉄道9連隊、ビルマ側からは鉄道5連隊、これに、国鉄作業員3,000人、タイ、マレーシアからの労働者約10万人、さらに、シンガポールから、イギリス、オランダ、オーストラリアの白人捕虜73,502人が加えられたといいます。
この橋を架けたあたりは、世界でも有数の多雨地域で、当時は、一度豪雨に見舞われると、十数メートルにおよぶ水位の変化がみられたそうです。そのほか、補給物資の欠乏、栄養失調、マラリア、それにコレラの発生などもあって、橋の建造は困難を極め、完成までには数多くの犠牲者を出してしまいました。連合軍側の発表では、コレラによる死者560人、マラリア、栄養失調などによって10,500人、その他を合わせると死者の総数は24,490人になったとされています。そして、それに倍する数多くの労働者も犠牲になりました。日本人の死亡者も約1,000人にのぼったといわれていますが、現地ではいまも、この橋の突貫工事を「悪魔の日本軍」の所業として、連合軍やアジア労働者の犠牲の大きさだけが語り継がれているようです。
カンチャナブリの町外れに、セーンシュートー通りに面して、広大な連合軍共同墓地
(Kanchanaburi War Cemetery) があります。日本軍の捕虜としてここへ連れてこられ、「戦場に架ける橋」の建造中に死亡した、イギリス、オランダ、オーストラリア、アメリカなどの軍人6,982人の墓が、よく手入れされた芝生の間に整然と並べられています。暑い陽差しのなかを、私は、ゆっくりと墓地の一角を歩いてみました。四角い平面の墓標には、十字架と埋葬者の国章、氏名、年齢、出身地などが刻まれています。ほとんどが20代、30代の若さで亡くなっていますが、特に20代の犠牲者が多いのには粛然とさせられる思いでした。
クワイ川の近くには、この橋の突貫工事が完成した後に日本軍が建立した「戦没者慰霊塔」も残されています。そこには、「泰緬鉄道建設中に不幸にして病に倒れた南方各国の労務者および俘虜のためにこの碑を建て、恭しくその霊を慰む。昭和19年2月、日本軍鉄道隊」とあり、石碑のまわりの壁には、タイ語、マレーシア語、中国語、英語で同じ文章が刻み込まれていました。戦争遂行のためとはいえ、あまりにも多くの犠牲者を出してしまったことに、当時の日本軍のこころある人々も、胸が潰れる思いであったことでしょう。この文字を眺めている私も、切ない気持ちにさせられていました。この慰霊塔は、「タイ国日本人会」が管理し、毎年3月には、タイ在住の日本人が集まって、ここで欠かさず、慰霊祭を行っているそうです。
(2004.10.15)

40年来の友との別れ (身辺雑記 19)
去る9月13日、私の親しい友人であったWさんが、北海道の小樽市で亡くなりました。71歳でした。Wさんは、40年ほど前に私が室蘭工業大学に勤めていた頃の同僚で、その後、私が小樽商科大学へ移ったあと、Wさんも小樽商科大学へ転任してきて、それからも30年以上の長い付き合いになります。Wさんは文化人類学の専攻で、日本民族学会の会長なども務めました。私の知るもっとも優秀な学者の一人ですが、その優しい人柄は、学生たちのみならず、まわりの多くの人々からも慕われていました。
Wさんの病名は、筋萎縮性側索硬化症という難病で、普通 ALS と略称されています。この病気では、視覚や聴覚、痛みなどの五感が正常のまま、運動神経だけが徐々に麻痺していきます。最後には、呼吸もできなくなりますから、その段階では、気管を切開して人工呼吸器をつけなければなりません。しかしWさんは、人工呼吸器をつけることはしないことを選択し、かねてから家族にもそのことを伝えていたということです。
昨年の1月末に、小樽のお宅へ私がお見舞いに行ったときには、Wさんは、まだ少し歩くことができました。奥さんの介添えで、コーヒーをスプーンで飲み、そのあと、ワインも私に出してくれて、自分でも少しスプーンで口にしたのです。疲れると、ちょっと寝室に引き上げて10分ほど休んでは、また居間へ出てきて私と話をします。それを何回か繰り返して、結局、3時間ほどもおしゃべりをしました。Wさんの希望で、そのとき私と二人で並んで撮った写真も、いま残っています。
8月末に、またお見舞いに行ったときには、もう居間でお話しすることはできませんでした。寝室に寝たままで、時折痰がつまったりすると、奥さんが病室に持ち込んだ器械で除去しなければなりません。自分で処理することはできなくなっていて、見ていても辛い気持ちでした。
ALSは、もう100年以上も前からその存在が知られていながら、いまだに病気の原因は解明されていません。そのために、有効な治療法もなかなか見出せないのだそうです。40代から60代の男性に多く、発症率は女性の2倍といわれています。人口10万人について2~3人の割合で発症し、日本全体では5千人近くの患者がいることになります。
治療法もなく回復の希望が持てない状況のなかで、生きていくのはたいへん辛いことですが、まわりの人たちも優しく見守る以外にはどうすることもできません。私もただ、東京からほとんど毎週、「少しでも回復していかれますようにこころからお祈りしています」とメールを送り続けるだけでした。そして、「なんとか、人間が本来持っている自己治癒能力を発揮されて、この病気に打ち勝ち、今度は東京へ来ていただいていっしょにワインを飲めるようになることを夢見ています」というようなことも書き送ったりしていました。
私からのメールに対して、数回に一度くらいは、Wさんからも返事のメールが届いていました。たいていは、札幌に住んで銀行に勤めているご長男がお見舞いに来たときに、Wさんのことばを代筆していたようです。9月6日に、毎週出しているメールを送信しますと、そのメールに対しては、珍しくその日のうちに、「いつも有り難うございます」という件名でWさんの口述のメールが返ってきました。
そのメールには、「私のほうは芳しくなく、呼吸のトラブルが起こったりしていますが、先生のメールを見て気を取り直して頑張ろうと努力しています。とりあえず、ご親切なメールのお礼を申し上げます」と書かれていました。それが、Wさんからの最後のメールになりました。つぎの週の9月12日の朝、またメールを送ったときには、そのメールにはWさんからの返事はもうもらえないことを、私は知る由もありませんでした。Wさんは、その日の午後、呼吸困難になって亡くなりました。
Wさんはカトリックの信者で、葬儀は、小樽カトリック富岡教会で行われました。教会の信者のほかに、私にとっても懐かしい小樽商科大学の教職員や卒業生たちも大勢出席して、厳粛で、カトリックらしい清々しさが感じられる葬儀になりました。Wさんは、ALS
を発症する前後から、熱心にこの教会へ礼拝に訪れていたようです。運動神経が麻痺して歩けなくなってからも、車椅子に座って、礼拝は続けられました。そして、9月14日の通夜のときの神父のお話しでは、長い間神から離れていたことへの赦しを願って、お祈りを捧げていたこともあったそうです。
つぎの日は告別式で、私が弔辞を読みました。そのなかで私は、あふれるような感慨をこめて、「先生は、いま、神に召されて天国へ移られましたが、天国ではもう
ALS による束縛はありません。呼吸困難で苦しまれることも、もうありません」と述べました。そして、「開放された完全な自由のなかで、どうか、のびのびと、学問にスポーツに、先生の類い希な才能を十分に発揮していってください」と続けました。私にはまだ、その時の40年来の友への惜別の思いが、薄らぐことなくいまも残っています。
(2004.10.01)

マハトマ・ガンジーのことば (身辺雑記 18)
もう十二、三年前のことになりますが、イギリスに一年ほど住んだあと、帰国の途中インドに立ち寄り、数日間、デリーを中心に歩きまわったことがありました。デリーは、1911年以降、イギリス領インド帝国の首都になったところで、それまでは、東インドの大都会カルカッタが首都でした。首都がデリーに移されてからは、イギリスが街の南部に計画都市ニューデリーを建設し、それが、1947年のインドの独立後は、新しいインドの首都になって現在に至っています。そして、このイギリスからのインド独立を導いたのが、「独立の父」として崇められているマハトマ・ガンジーでした。「マハトマ」とは、サンスクリット語で「偉大な魂」という意味だそうです。
鉄道のニューデリー駅から東に約3キロくらいのところに、ヤムナー川を背にして、「ラージ・ガート」と呼ばれるガンジーを記念した聖跡があります。インドが独立して間もない1948年1月30日、ヒンドゥー極右のテロリストによってピストルで射殺されたガンジーは、その翌日、この場所で火葬にふされました。遺骨はヒンドゥー教の慣習に従って川に流されましたから、ここには遺骨はありません。ですから墓ではないのですが、墓所同様に、インド各地から、ガンジーの遺徳を慕う多くの人々が集まり、「独立の父」への敬意をあらわしているのです。
聖跡は緑の芝生が広がる広場になっていて、その中央に大きな四角い黒大理石の記念石が置かれています。その記念石の正面に刻み込まれているのは、ただ一言、ガンジーが射たれたときに口にしたといわれることば
"He Ram"「おお、神よ!」だけです。多くのインド人たちは、靴を脱いで裸足になり、黙って恭しくお祈りをしながら、そのまわりをまわっていました。
私の記憶では、たしか、この聖跡の一角に石碑があって、そこにヒンドゥー語と英語で、「自分のまわりにいる貧しい人々のなかで一番貧しい人に、まず救いの手を差し伸べよ」といった意味のガンジーのことばが書かれていたと思います。このことばは、その後も長い間、わたしのこころのなかに余韻を残していました。いまも私は、ガンジーと聞けば、きまってこのことばを思い出します。
ガンジーはそのことばを、自分自身が身をもって実践した人でした。世の中の不平等や偏見をなくすための愛の行為として、自分の持っているものを持っていない人々に与えることを説き、ものや財産を持たないことの本当の意味での幸せを、ひろく訴えつづけました。ラージ・ガートのすぐ近くにあるガンジー記念博物館には、彼が最後に身につけていた質素な白布が、血にまみれたまま残されていますが、その質素な白布は、生涯を愛と平和の実践者として捧げた人のほとんど唯一の所有物として、いまも、見る人には感動を呼び起こしているようです。
1982年にイギリスとインドの合作映画「ガンジー」が作られましたが、覚えておられる方も多いのではないでしょうか。ベン・キングスレー主演のこの映画は、多くのアカデミー賞に輝いた名画として、世界中にひろく知られています。ガンジーはインドの民衆と力を合わせて、徹底した非暴力主義を貫きとおしながら、イギリスからインドの完全な独立と自治を取り戻していきますが、私はつい最近、その偉大なガンジーの足跡をビデオで見直して、新たな感動を抑えきれませんでした。
しかし、独立といっても、インドは単独で独立したわけではなく、ガンジーの意に反して、ヒンドゥー教のインドとイスラム教のパキスタンという分離した形での独立になってしまいました。そして、独立後も、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒との間では激しい内紛が続くことになります。宗教観の対立や憎悪がいかに根が深いものか、しみじみと考えさせられる情景です。ガンジーも悲しかったのでしょう。死を覚悟した断食によって、両者の和解を訴えようとします。映画のなかでも、そのことを取り上げた、つぎのような場面があります。
断食しているガンジーのところへ、ヒンドゥー教徒たちがやってきて、「約束します。戦いは止めます」と和解を誓います。その時に、足取り荒く一人の男が入ってきて、ガンジーにパンを投げつけ、「さあ、食べろ。オレは地獄行きだが、あんたを助けたい」と言います。その男は、イスラム教徒に自分の子供を殺され、仕返しに、イスラム教徒の子供を壁にたたきつけて殺したというのです。ガンジーには断食で死んで欲しくないが、イスラム教徒は絶対に許せない、ということでしょうか。その男にガンジーは、静かに諭しました。「地獄から抜け出る道がある。子供を拾うのだ、母親と父親を殺された子を。」そう言って「これくらいの子がいいな」と弱々しい手を差し伸べ、幼時の背丈を示そうとします。
そう言われても男は、まだ険しい顔つきのままでした。その男にガンジーは続けて言います。「・・・・・自分の子として育てるのだ。ただし、イスラム教徒の子だよ、イスラム教徒として育てるのだ。」男は、黙って立ち去ろうとします。しかし、そのガンジーのことばには、あきらかに衝撃を受けていました。ヒンドゥー教徒の自分が憎むべきイスラム教徒の孤児を拾って、しかも、イスラム教徒として育てよとは。出て行こうとしていた男は、立ち止まってしまいました。感動が顔に走ります。やがて、彼はよろよろとガンジーのところへ引き返し、ひざまずいて、泣き崩れていきました。映画の一場面ですが、これがガンジーの愛であったのでしょう。このガンジーのことばも、いまでは、私には忘れられないことばになりました。
(2004.09.14)

21年の歳月 (身辺雑記 17)
1983年9月1日にアメリカから帰国の途中、サハリンの沖に母親と共に散っていった長男の潔典(きよのり)は、事件当時、21歳でした。今日は21年目の命日にあたります。あれから、その時の潔典の年齢と同じ21年の歳月が流れて、彼がこの世に生き続けていれば、いまは42歳になっていることになります。21年の歳月をしみじみと振り返りながら、あの潔典がいまこの世に生きていればどういう環境の中にいるだろうと、ふと考えることがあります。
潔典は、言語学者になるという強い志望と意欲をもっていて、東京外国語大学の英文科に入学してからは、のめりこむように言語学と取り組んでいました。入学以来、彼が集めた百数十冊の和洋の言語学書のほかに、定期購読していた英文週刊誌「TIME」と大修館の月刊誌
「言語」が、2年分いまもそっくり彼の書棚に残っていますが、このうち、特に「言語」のほうは、「こんないい雑誌はない」と学友にも勧めたりしながら、すみからすみまで熟読していました。
大学では、英語とフランス語を履修し、そのほかに、ドイツ語とロシア語も学んでいたようです。あの事件の時は3年生になっていて、アメリカの私のところへ来た夏休みには、ギリシア語文法の本を読んだりしていました。父親の私からみても、語学には
私などよりはるかに勝れた才能を持っていたと思われますし、世界史なども好きで不得手な学科はあまりありませんでしたから、2年生の成績も
"ストレートA" (全優)であったようです。「勉強するのが楽しくて仕方がないようにみえる」と潔典の親しい友人が言っているのを聞いたこともありました。事件の後、潔典が所属していた音声学のゼミ担当の竹林滋教授が、「武本君は私のゼミで一番優秀な学生だったので、がっかりしました。あのままいけば、外語と東大の大学院は両方合格するのは間違いないのに」と言っておられたと、T
教授からのお手紙をいただいて、その時は悲しさが一層つのるばかりであったことも、いま思い出すことができます。
事件に巻きこまれて状況は大きく変わってしまいましたが、実は、潔典をアメリカへ呼び寄せようとしたのは、1983年の夏休みの間ではなく、春休みでした。その頃はまだ、アリゾナ大学にいた私は、制度の違いで日本の大学の春休みの間も開講しているアリゾナ大学で、言語学の講義に潔典を出席させようとしていました。私は、将来アメリカにも留学するであろうと考えていた潔典のために、知りあいの言語学教授に頼んで、潔典が聴講することの了解もとりつけていたのです。しかし、その計画は、東京に住んでいた母方の祖母の死亡と、看病疲れで体調を崩していた母親への彼の思いやりで、実現されませんでした。それで、アメリカへ来たのは、私がノース・カロライナ大学へ転出した直後の夏休みになってしまったのです。
いまから考えますと、つぎからつぎへとそうなっていくように導いていた「運命の手」があって、潔典は、そのあとにくる「父親の覚醒のために自らも犠牲になる事態」についても、深い意識の底で、なんとなく感じ取っていたように思われます。私は鈍感で気がつかなかったのですが、後から振り返ってみますと、そのことを示唆する潔典のいくつものことばがあり、状況がありました。1999年に潔典から届けられた霊界からのメッセージでは、そのことを裏書きするように、「お父さんなら頭も聡明で、苦しませるのは高い霊たちにとっても辛いことで、決断を要したということです」と霊界の計らいについて述べ、そのあとで、「でも、必ず目覚めて立ち直る人だということがわかり、一人の苦しみが何百、何千人、いや何万人の人たちの魂を目覚めさせることが期待されて」母親と共に自分が事件に巻き込まれることになったと、続けています。
潔典はいま、霊界でも、好きであった音楽を引き続き学んだり教えたりしながら、一生懸命に「異次元間コミュニケーション」などの研究に打ち込んでいるようです。彼は、当初私が予想していたようなアメリカの大学に留学するかわりに、霊界へ留学したのだということになるのかもしれません。少し遠く離れて、ちょっと寂しい気がしないでもありませんが、母親ともよく会っているようですし、元気で幸せな生活ぶりを定期的に伝えて来てくれますので、いまでは、私も安心して、霊界での成長ぶりを見守ることができるようになりました。その意味では、私自身の21年も、潔典がこの世に生きていた間と、潔典が霊界へ行ってからでは、大きく変わったということになるのでしょう。
事件後の何年かは、すべてを失ったと思いこんでしまって、希望も生きる意欲もなくし、絶望の淵に沈んでいましたが、いまは、失ったものは何一つないことを、私なりによく理解しているつもりです。それに、なによりも、霊界で潔典も母親といっしょに、こころ安らかに生き続けていることを知ることができたのは、大きな救いです。霊界の高遠な深い計らいについても、それを十分に納得して受け容れられますし、文字通りいのちを賭けて私の目覚めのきっかけを与えてくれた妻の富子と潔典には、かつての自分の無知を詫びながらも、こころから感謝するようにもなっています。この21年という歳月は、私の生涯にとっても、人生の大きな転換をもたらせたという意味で、きわめて貴重な21年になりました。
(2004.09.01)

時の流れが止まっていたかのように (身辺雑記 16)

(左から)潔典のラジオ、ゲームウオッチ、
最後の写真を撮ったカメラ (日付窓には
正確に今日の日付が表示されている)
[ 2004.08.16 ]
長男の潔典(きよのり)は、1981年4月に東京外国語大学英文科に入学してからは、札幌から上京して、多摩市永山のアパートに住んでいました。大韓航空機事件に巻き込まれた1983年の夏も、このアパートから母親と一緒に、当時アメリカにいた私のところへ出発して、ついにこのアパートには帰ることはありませんでした。
このアパートの潔典の勉強部屋に、潔典がなにかの付録か懸賞でもらったらしい子供っぽい時計が残されていました。五百円玉よりちょっと大きいくらいのゲーム・ウオッチで、値段にすれば、おそらく千円もしないでしょう。茶目っ気のある潔典は、その時計を、自分の机の脇の電気スタンドにぶら下げていました。
事件後しばらくは辛くて部屋にも入れませんでしたが、二年くらい経ってからでしょうか、ぼんやり潔典の机に座っていますと、急に「タタタータタ、ターララ、ラーラ・・・・・」と、時計が鳴り出しました。私はちょっと驚いて、初めてこの「ムッシーちゃん」と名付けられた小さなおもちゃの時計が鳴ることに気づいたのです。十二時十五分に鳴り出して、十五秒ほどで終わるこのメロディーは、その後何年間も鳴り続けました。鳴り続けるだけでなく、画面の人形が可愛らしく踊るのです。それだけ、電池の消耗も大きいはずですが、私は、いつまでも鳴り続け、踊り続けるこの時計の「異常」に気がついて、7, 8年目くらいからは、ときどきビデオで時計の時間を音と映像とともに記録するようになりました。
事件後十年になる一九九三年の夏、ロンドンでアン・ターナーにこの時計のことを話しますと、彼女は「あなたに霊界のことを理解させるために、この時計は十年間鳴り続けてきたが、いまあなたは理解し始めている。それで、まもなく動くのを止めるだろう。止まっても新しくバッテリーを入れ替える必要はない。そのままにしておけばよい」と言いました。いま改めて、ビデオに録画しておいたものを見ますと、一九九四年一月六日までの記録が残っています。文字盤の人形が踊り、ちゃんとメロディーが鳴っています。普通は一年か二年で止まってしまうと思われるのに、このおもちゃの時計は、十一年以上も毎日、画面の人形が踊って鳴り続けたことになります。
昨年は、事件後20周年で、稚内での慰霊祭に参加し、札幌の自宅では、長年そのままになっていた妻や長男の遺品などの整理を始めました。長男の潔典の部屋には、高校時代まで使っていた机が元のままの状態でおいてあります。はじめて引き出しを開けてみたら、小さなトランジスタ・ラジオがひとつ出てきました。大学に入ってからは、性能のいい別のラジオを使っていましたから、このトランジスタ・ラジオは、おそらく、22年以上もこの引き出しのなかで眠り続けたことになります。私は、自分のラジオを5年くらい放置して、なかの電池が腐食で流れ出したことがあったのを思い出したものですから、電池だけは抜き出しておこうと思ったのです。その時、なにげなくスイッチを入れてみたら、ラジオから大きな音響で音楽が流れ出して、びっくりしました。いまでもこのラジオは、電池は入れ替えていないのに、22年以上も前と同じように、普通に鳴り続けます。
1982年に、フルブライト上級研究員として、アリゾナ大学へ行くとき、私はコンパクトなコニカ製のカメラを持っていきました。翌年の夏に、当時留学生としてアリゾナ大学に在学していた娘と二人でノース・カロライナ大学へ移ったとき、そこへ、東京からやってきた妻と長男が合流して、家族4人でいろいろなところを旅行しましたが、そのおりおりの写真を撮ったのもこのコニカのカメラです。大韓航空機に乗るためにニューヨークへ向かう妻と長男を見送って、ノース・カロライナのローリー・ダーラム空港で二人の最後の写真を撮ったあとは、このカメラは使ったことはありません。
20年以上前の当時は、まだカメラはほとんど手動式でしたが、日付を写し込む部分だけは、電池を使っていました。先日、私はそのことを思い出して、しまいこんであったそのコニカのカメラを取り出してみたのです。1981年に買って、もう23年にもなるそのカメラの日付は、閏年の誤差も自動修正して正確に、正しい日付を示していました。念のために、その後何年かして購入したたペンタックスとミノルタの一眼レフカメラをみてみますと、いづれも、10年もたっていないのに、日付機能は電池切れで、消えてしまっています。
潔典のおもちゃの時計が11年以上も、画面の人形が踊り、鳴り続けたというのは、アン・ターナーに言われるまでもなく、とても偶然とは思えませんが、潔典のラジオが22年以上たったいまも放送を送り続け、潔典たちの最後の写真を収めたカメラは、その日付が23年たったいまも正常に表示されている、というのもちょっと不思議な気がします。これらもまた、単なる偶然ではないのかもしれません。
(2004.08.16)

旅先で重なる偶然 (身辺雑記 15)

九寨溝の池(2004.07.01)筆者撮影
先月末からの中国四川省黄龍への7日間の旅は、阪急交通社主宰のツアーでした。こういう中国奥地への旅になると、なんといってもツアーに参加するのが便利です。一人で行けないことはないのですが、おそらく、一人では費用は2倍から3倍はかかりますし、同じコースをたどるにしても、日数も、おそらく、2倍以上はかかってしまうでしょう。
このツアーの参加者は、27名で、一人で参加というのは私だけでした。夫婦で参加したり、女性の友人同士というのが多かったようで、おそらく、平均年齢は60歳くらいだったかもしれません。なかには80歳は超えていると思われるようなおばあさんもいて、娘さんらしい人が付き添っていました。私は、阪急交通社のツアーに参加するのは初めてだったのですが、こういうツアーでは、お互いにプライバシーを尊重するからでしょうか、いっしょに行動していても、名前以外の個人的なことはよくわかりませんし、聞いたりもしないようです。私も、旅の途中で外国人のグループといっしょになって、英語が話せることぐらいはわかってしまいましたが、はじめのうちは、口数の少ない一人参加の変わった人くらいに思われていたかもしれません。
成田から3時間半で北京に着き、そこからさらに乗り継いで、私たちの乗った中華航空機は3時間ほどのフライトの後、四川盆地の中心都市・成都に着きました。成都は『三国志』で知られる劉備玄徳の蜀の都があったところです。劉備玄徳は、彼に仕えた名軍師・諸葛孔明とともに、いまも、特にこの地の人々からは深く敬慕されていて、二人をともに祀った武候祠は、この古都の重要な名所になっています。私たちは、ここで一泊して、翌朝、飛行機で、黄龍への出入り口である九寨溝へ向かうことになっていました。
翌日は、朝6時にホテルを出て、空港には7時前に着きました。ところが、九寨溝空港一帯の天候不良のためとかで、7時40分の出発時間は遅れる予定だというのです。そのうち、成都の空港付近でもかなりの雨が降り、雷も鳴ったりしていましたから、私たちは、空港の待合室で、天候の回復を待ち続けるだけでした。添乗員の
Oさんは、1時間くらいは待たされるかもしれない、といっていましたが、しかし、2時間たっても、3時間たっても、出発する気配はまったくありません。成都から九寨溝までは、45分のフライトで、8時半にはもう着いているはずでしたが、とうとう正午になり、午後1時も過ぎて、空港の待合室で、中華航空が用意してくれた発泡スチロールの容器に入った遅い昼食の弁当を食べることになってしまったのです。
九寨溝の空港は山岳地帯にあって、標高3,000メートルくらいの高所にありますから、天候に左右されやすいのはわかるような気もしましたが、それにしても中華航空の対応は、官僚主義で「慎重すぎる」ように思われてなりませんでした。結局、14時間も待たされて、九寨溝のホテルに着いたのは、真夜中です。予定では、その日は、午前中に九寨溝のホテルに着いて、午後は、「高地順応のため」ホテルで休養することになっていましたが、それが、思いがけぬ大幅な遅延で、私がホテルのベッドに横になったのは、午前1時をまわってしまってからです。
それでも、このホテルでの休養の予定を1日とってあったお陰で、その休養の1日がつぶれたほかは、その後のスケジュールは少しハードでしたが予定通り進みました。この旅行の目玉であった旅行3日目の8時間かけての九寨溝観光と4日目の4時間歩いての黄龍観光が、天候にも恵まれて、無事終わったのです。黄龍の観光が終わって、九寨溝空港発午後7時45分の飛行機で成都へ戻ることになっていましたが、この時もまた、飛行機の出発は3時間も遅れて、成都到着は真夜中になってしまいました。しかし、ツアー参加の皆さんは、黄龍と九寨溝の素晴らしい景観を、ともかくも見ることができたという満足感で、あまり、飛行機遅延の苦情を言うこともなかったようです。添乗員の Oさんも、参加者からは、九寨溝と黄龍観光の感動の声を聞いたりして、ほっとしていた様子でした。
その時の、成都へ向かう機中では、添乗員の Oさんと、たまたま席が隣同士になりました。Oさんは、まだ20歳代の女性ですが、参加者に対する気配りも細やかで、なかなか頼りがいのある添乗員です。雑談のなかで、私が、「あなたは中国への添乗が多いのですか」と聞きますと、彼女は、「いいえ、私は東欧やドイツへ行くことが多いのです」と言いました。「東欧やドイツに興味があるのですか」と私がまた聞きますと、彼女は、「実は、私はチェコのプラハに3年ほど留学していて、ドイツへも、プラハから行ったり来たりしていました」という答えでした。だから、チェコ語のほかに、ドイツ語も少ししゃべれるのだそうです。
チェコ語といえば、私の大学時代の同級生の千野栄一君が日本におけるチェコ語の権威で、彼も、学生時代に何年か、プラハに留学していました。言語学会の重鎮で和光大学の学長を最後に亡くなくなりましたが、いまでも、言語学やチェコ語を学んでいる人で、彼の名を知らない者はいないでしょう。それで私は、「千野栄一を知っていますか」と聞きますと、今度は彼女が驚いたように、どうして私が彼のことを知っているのか、と聞き返されました。彼女は、千野君の奥さんであったズデンスカのこともよく知っていて、何度も千野君の家にも遊びに行ったことがあるということでした。
5日目は、成都からバスで2時間ほどの世界遺産・楽山大仏を見学し、午後は、そこからバスで30分ほどの峨嵋山(がびさん)へ向かいました。峨嵋山というのは、中国仏教の四大聖地のひとつで、海抜3,099メートルの金頂とよばれる高峰には、臥雲尼寺などの名刹があります。その日の宿泊ホテル・峨嵋山大酒店の夕食の席で、27名のツアー参加者が三つの円卓に分かれて座りました。私の座ったテーブルでは、左隣が、東京駅から歩いても10分のところに住んでいるという50歳代くらいに見える
A さん夫妻、私の右隣が、年齢はその時にわかったのですが、参加者では最高齢の81歳のおばあさんと娘さん、そして、私と向かい合うように、二組の老夫婦が座っていて、左側に昭和5年生まれで、私と同じ年であることがわかった
Bさんと奥さん、右側には、大正14年生まれで79歳の Cさんと奥さん、という顔ぶれでした。
Aさんの、東京駅の近くに住んでいるので、あまり歩くことがない、というのが話のきっかけであったように思います。その代わり、北海道の余市へ商用の果物の仕入れなどでよく出かけるので、運動不足を解消するため、小樽のカントリー・クラブでゴルフをするのを楽しみにしている、と言ったのです。それを聞いた81歳のおばあさんが、「実は私は小樽の出身で、実家は小樽の曹洞宗のお寺なんですよ」と言って、いろいろと昔の小樽の話などを始めました。すると、その話に耳を傾けていた79歳の
Cさんが、「私も札幌に何年も住んでいたことがあって、小樽のことはよく知っています」と切り出しました。「三井鉱山の札幌支店長をしていて・・・」と言いますと、隣にすわっていた
Bさんが驚いて、「三井鉱山ですか、実は私も」と先輩、後輩の名乗りをあげたのです。Bさんの場合は、主に東京や京阪神の支店長などを務めて、宅地開発などを担当していたということです。
小樽、札幌、余市、三井鉱山などで、話が盛り上がりました。Aさんの奥さんまでが、むかし学生の頃、北海道にあこがれて何度も札幌へ行ったし小樽もよく知っているとうち明けたのです。それにつられて、おばあさんも、小樽の「館」という喫茶店のコーヒーがとてもおいしかったことなど、女学生時代の青春の思い出を語りはじめたりします。急に一座の親密度が増したようで、みんなもそれぞれに北海道の思い出などを語り出しました。そこで、Cさんが、むかし札幌に住んでいた頃、北海道の港湾設備を充実させるためのヨーロッパ使節団の一員となったことがある、と言い出したのです。「その時の視察団の団長が、あとで学長になられた小樽商科大学の伊藤森右衛門教授で・・・」というのを聞いて、今度は私が驚きました。
伊藤森右衛門教授というのは経済学者で、何年か前に亡くなりましたが小樽商科大学では私が親しくしていた同僚でした。彼の名前がこんなところで出てくるとは思いもよらなかったことで、私も、ついそのことを口に出しますと、C さんも驚いたように、「実は、家内の父親も昔の小樽高商時代の卒業生です」と言ったのです。「袖振り合うも他生の縁」といいますが、私を含めてテーブルを囲んだ9人が、みんなそれぞれに、何らかの糸で結ばれているような感じです。その日の夕食のテーブルは三つのうちの私たちのテーブルだけが、最後までにぎやかな余韻を残して、81歳のおばあさんは、こんないい思い出ができて本当によかった、と嬉しそうに何度もくり返していました。
(2004.08.01)

神の泉・黄龍 (身辺雑記 14)

黄龍・五彩池の一部(2004,7,2)筆者撮影
中国四川省北部の黄龍は、中国では、そしておそらく世界でも、もっとも美しい風景のひとつとして有名です。その3,400にのぼる美しく神秘な池は、地元の人々には、神の住む聖域と考えられていて、その自然景観は世界遺産としても登録されています。先月末、私は、その黄龍を訪れるため、成田を発って、北京経由で成都へ飛び、それから黄龍への出入り口である九寨溝の小さな飛行場に降り立ちました。
黄龍は、この九寨溝から130キロのところにあります。途中、急峻な曲がりくねった路を登っていったりしますので、バスでたっぷり3時間はかかります。しかし、この九寨溝の飛行場は、昨年オープンしたばかりで、この飛行場ができる前までは、黄龍へ行くのには成都から、バスで13時間もかかったのだそうです。そのせいか、九寨溝に飛行場ができてからは、観光客の数は、外国からの観光客を含めて、大幅に増加するようになりました。
黄龍の広大な風致地区に入りますと、まず目に入るのが、迎賓池です。この池の周辺だけでも、大小360の池があるのだそうですが、何よりも不思議なのはその水の色です。透き通るような青さで、小さなさざ波がたつと、きらきらと宝石が輝いているように見えます。水温は7度。カルシウム分が強いので、水中には魚や昆虫はいません。このあたりで、標高は3,200メートルありますから、夏でも日によってはかなり気温も下がり、私も厚手のセーターの用意をしていました。
迎賓池を通り過ぎますと、蓮台飛瀑、盆景池、明鏡倒映池、争艶彩池、などが続いて、やがて接仙橋にさしかかります。この辺まで来ると、標高は3,400メートルくらいありますし、ずっと上り坂ばかりですから、歩き続けるのも楽ではありません。人々は、時々腰を下ろして持参の酸素吸入器から酸素を吸って、呼吸を整えたりしています。一番上の五彩池まで全長3.5キロメートルを普通、2時間から2時間半をかけて登っていくのですが、気分が悪くなるようなことがあれば、ここから引き返すように注意をうけていました。
自然環境を保護するために、路はほとんど厚板が敷き詰められた歩道になっていて、観光客は、その上をゆっくり歩いて上がっていきます。歩道のまわりにはさらに、玉翠彩池、映月彩池などが展開していって、やがて、五彩池に着くことになります。やっとたどり着いて、目の前に開けたこの五彩池を見ると、人々はみな一様に感動するようです。この類い希な情景をどのように表現したらいいのでしょうか。その美しさは、ただ「筆舌に尽くしがたい」というほかはありません。
シルバー・バーチは霊界の美しさを、「地上のいかなる天才画家といえども、霊の世界の美しさの一端たりとも地上の絵の具では表現できないでしょう。いかなる名文家といえども、天上の美を地上の言語で綴ることはできないでしょう」(『霊訓-4-』)と述べていますが、あるいは、その霊界の美しさに近いのが、この黄龍の風景といえるのかもしれない、と思ったりしました。
五彩池の、五色の透き通るような色を湛えたそれぞれの池の水の上に風が吹き渡りますと、小さなさざ波がたって、きらきらと虹のような色彩の変化をみせていきます。たえず色合いは微妙に移り変わっていくようで、宝石をちりばめたような、とでも形容すればよいのでしょうか、息をのむ美しさです。地元の人々が「神の泉」と称えて信仰の対象にしているのもよくわかるような気がしました。
五彩池は文字通り、それぞれの池の水が、緑、青、黄、白、黒の五色に見えることから付けられた名前ですが、なぜ、このように色が変わってくるのか、よくわかっていないということです。黄龍の神様の弟子にあたる仙人が5人いて、それぞれの池に住みながら5色の色彩を放っているという伝説があるようですが、科学的な調査の結論もまだ出せないでいるのだそうです。
黄龍のまわりには、5,000メートル級の山々が取り囲んでいますが、そのなかの最高峰が、5,588メートルの雪宝頂という山です。その名のように、頂上は一年中、雪に覆われています。この山の中の、動物の骨などが永年堆積されてできた石灰質の地層が、やがて石灰岩になり、その中をしみ通っていった水がカルシウムを含んだ伏流水となって麓に湧き出てきたのが黄龍の泉だといわれています。
このカルシウム分を含んだ水は、水中の枯れ葉や小枝をまわりに押し流し、それらを水中のカルシウム分が固めていったのが池を取り巻く壁になっていったといいます。その壁が出来上がっていくのは一年間に高さ3ミリ程度だそうですから、1メートルの壁が出来上がるのには、300年から400年の歳月を要することになります。この黄龍も、年々少しずつ姿を変えているわけで、あと数百年もすると、またいまとは違った神秘な美しさをみせることになるのかもしれません。
(2004.07.16)

霊魂の実在を信じない人たち (身辺雑記 13)
女流作家の佐藤愛子さんが新潮文庫で出した『こんなふうに死にたい』という本があります。これは、小説家の彼女が霊に関する彼女の実体験をまとめた本ですが、佐藤さんもはじめのうちは、霊魂の存在などは全く信じてはいませんでした。佐藤さんは、「私がこれから語ることを、おそらく読者の大半はナンセンスだというだろう。なぜなら現代に生きる大部分の人は、目に見るもの、耳に聞こえるもの、科学的に分析実証できるものしか信じないからだ。かつての私もその一人であった」とこの本の中で書き出しています。
彼女は、長い霊体験のなかで悩んだり苦しんだりしながら、だんだん霊について理解を 深めるようになっていきました。そして、その彼女を導いたのが「優れた霊能力者」といわれる美輪明宏さんです。この佐藤さんと美輪さんとの霊体験にまつわる話は、私の講演集(第4集)にも触れてきましたが、美輪さんは、この佐藤さんの本の最後に「霊を受け入れる柔和質直な心」という一文を載せています。美輪さんには霊がはっきり見えるわけですから、「霊なんかあるわけがない」と広言する人などは、殊更に傲慢にみえるのかもしれません。実は、そのような人は、ものごとをよく知っているつもりの、科学者、医者、学者、知識人といわれる人たちのなかに多いといわれているのですが、美輪さんは、それらの人たちこそ無知で蒙昧であると、次のように強いことばで批判しています。
通常の医者や科学者は、超常現象や己の無知なる部分を認めれば沽券にかかわる、それらを否定することこそ立派な科学者で常識ある人間だと思いこんでいる。この姿こそ小心翼々とした哀れむべき根性である。頑迷ということは愚か者だということである。「超常現象なんてあるわけはありません」とそれに対する勉強も研究もせず何の知識もない癖に頭から否定してかかるのが傲慢なる愚者の発言であり、「この世の中には自分が知らない事はまだまだ山の様にあります。私には知識も経験も無いのでわかりません」と発言する人が聡明で謙虚な人なのである。(同書:p.153)
美輪さんに言われるまでもなく、私たちが見えない霊の世界を理解し信じるのは容易ではありませんが、だからといって、はじめから迷信と決めつけ、知ろうともせず勉強もしないのは傲慢ということになるのでしょう。しかし、それにしても、ものごとをよく知っているはずの科学者や、知識人、文化人といわれるような人々に、なぜ霊の世界を信じようとしない傾向が強いのでしょうか。知らないことを認めるのは沽券に関わる、というのはわかるとしても、それだけではなく、学者や知識人に特有のものの見方が絡んでくるように思われますが、それを改めてここで考えてみることにしましょう。
仏典の大般涅槃経のなかに、つぎのような「盲人と象」の譬え話があります。
昔、ひとりの王があって、多くの盲人を集め、象に触れさせて、象とはどんなものであるかを、めいめいに言わせたことがある。象の牙に触れた者は、象は大きな人参のようなものであるといい、耳に触れた者は、扇のようなものであるといい、鼻に触れた者は、杵のようなものであるといい、足に触れた者は、臼のようなものであるといい、尾に触れた者は、縄のようなものであると答えた。ひとりとして象そのものをとらえ得た者はなかった。
これは、大変わかりやすい譬え話です。牙に触れたり、耳に触れたり、鼻に触れたりしていますが、それだけでは、象の実像にせまることは出来ません。しかし、例えば、耳に触れている盲人Aは、自分が確かに象に触っているわけですから、象とは、扇のようなものだと固く信じて疑わないでしょう。同様に、尾に触れた盲人Bは、実際に手に触れた感触で、縄のようなものだと思っているわけですから、その判断の正しさには盤石の自信を持つかもしれません。この場合、盲人AもBも、彼らの立場では確かに正しいのです。しかし、それらはあくまでも象の一部であって、象の実像からは遠く、結局、彼らの見方は間違いであることになってしまいます。部分としては確かに正しいのですが、しかし、間違っているのです。
この象の実像を、仮に「真理」と置き換えて考えてみることにしましょう。その真理を捉えるのには、どういう見方をすればよいでしょうか。少なくとも、視野を広げなければならないことがわかります。象の実像を捉えるためには、牙や耳や鼻だけに触れて、それだけで結論を出してしまうのではなく、一人の盲人が、足や尻尾や大きなおなかまでできるだけ多くの場所を触ってみて、そのうえで、全体像を組み立てれば、かなり実像、つまり「真理」に近づくことができるはずです。つまり、象=牙、象=耳、象=鼻ではなくて、象=(牙+耳+鼻+尾+・・・・・)ということになります。
真理の探究というのは、学問の目的であり、学問というのは、本来、視野を広げることであるはずなのですが、しかし、往々にして学者は、対象を深く掘り下げて見続けているうちに視野を広げることを怠って、狭い自分の専門領域に閉じこもりがちになります。それに、ほとんど不可避的に、科学で立証できるものだけが真理であると信じ込まされてきました。広大な宇宙の中では米粒ひとつほどの大きさにもならないちっぽけな地球の上で、科学で説明できないものは真理ではない、というのは、ちょっと滑稽な気がしないでもありません。盲人と象のたとえでは、象の尻尾だけを繰り返し繰り返し触り続け、尻尾の感触から形状、毛の組成から数まで知り尽くして、それで象のことは何でも知っている権威であると錯覚してしまうようなものです。そして、本当に象の全体が見える人から、象というのはもっと複雑で、目も鼻も足も牙もある巨大な存在だと聞かされても、象のことは自分が一番よく知っていると固く信じていますから、そんなものは迷信だと一笑に付すことになるのでしょう。
霊は目には見えませんから、わからなければわからないでも致し方ないのですが、わからないのにそんなものはあるはずがないと決めつけている人は、いつまでも霊の事実を理解できるようにはなりませんし、霊が見える人の話にも聞く耳をもちません。霊の存在などはあたまから否定することが、学者や知識人であることの資格でもあるかのように考えている人々も決して珍しくはないようです。せめて、美輪さんのいうように、「この世の中には自分が知らない事はまだまだ山の様にあります。私には知識も経験も無いのでわかりません」と考える聡明さと謙虚さをもつことはできないものでしょうか。
(2004.07.01)

熊野詣でと浄土へのあこがれ (身辺雑記 12)

青岸渡寺と三重塔、那智大社は
この左側にある。奥に見えるのが
那智の滝。(2004.06.08)筆者撮影
紀州・和歌山の熊野三山というのは、よく知られているように、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の三社を合わせた総称です。この熊野三山に通じる熊野古道は、古来、人々のこころをとらえた信仰の道として、上皇や貴族から、武士や庶民に至るまで、多くの人々が訪れ、その数の多かったことから「蟻の熊野詣で」などともいわれてきました。
この熊野三山が日本国内に広く名を知られるようになったのは、平安中期から鎌倉時代にかけてで、上皇や法王が競うようにお詣りを始めた、いわゆる「熊野御幸」がきっかけになっていたようです。延喜7年(907年)に、宇多法王が最初に参詣してから、最後の亀山上皇までの375年間に、歴代上皇の熊野御幸は100回にも及んでいます。速玉大社へ行ってみますと、その境内には、これらの熊野御幸の記念碑が建っていて、上皇たちの熊野詣での回数が記されていますが、白河上皇が12回、鳥羽上皇が23回で、後白河上皇に至っては33回を記録しています。そのあとの後鳥羽上皇も29回で 飛び抜けて多いのですが、それでも上皇は、まだ30回に達していないのは信仰が足りないからだと、嘆いていたと伝えられています。
この後鳥羽上皇は、建仁元年(1201年)10月5日に、4度目の熊野詣でに旅立っていますが、この旅の様子は、随行した歌人の藤原定家の『後鳥羽院熊野御幸記』に詳しく残されていて、これは、当時の旅事情を知る貴重な資料となっています。専門家の解説などによりますと、京都から往復で22日もかけ、総行程600キロメートルにおよぶ苦難の旅であったようです。定家も、この熊野詣では気が重かったのでしょうか、『後鳥羽院熊野御幸記』のあちらこちらには、定家の愚痴混じりのため息が聞こえてくるといいます。定家にとってだけではなく、いかにこの熊野詣でがたいへんな旅であったか、それは、いまも残る熊野古道をちょっと歩いてみただけでも、よくわかりますが、それなのに、なぜこれほどまでに多くの人々は熊野詣でに執心していたのでしょうか。
田辺から東に進んで山中にはいると、中辺路とよばれる古道が本宮にまで続いていますが、細い道の両側は、深い緑の鬱蒼とした森林です。「語り部」と呼ばれるガイドさんに案内してもらいながら、足許に気をつけ、一歩一歩足を運んでいますと、梅雨のはじめで蒸し暑いはずなのに、私は、つめたい一種の霊気のようなものを感じさせられていました。ふと気がつくと、途中の苔むした岩肌のそばに立て札があって、「熊野ではこの山や森が神様仏様です・・・・」と書かれています。この立て札のとおり、熊野は昔から修験者でしられる山岳信仰の霊場でした。それに、のちの浄土思想が重なって、熊野一帯が阿弥陀如来や観音菩薩が住まわれる浄土と考えられるようになっていきました。古来、熊野は、神仏のふところに抱かれて浄土をかいま見ることのできる、信仰の聖地であったのです。
熊野那智大社の近くには飛滝神社という大社の別院がありますが、この神社には鳥居があるだけで本殿はありません。実は、鳥居の後ろの那智の滝そのものが、ご神体なのです。人々は、この滝に向かって手を合わせ、祈りを捧げます。この滝は、熊野では日本一と呼称されていますが、高さ133メートルで、決して日本一高いわけではありません。日本一美しく、尊いという意味でしょう。滝の背後には鬱蒼とした原始林が生い茂り、暖地性の植物を中心に300種に及ぶ植物の宝庫にもなっています。連綿と生き続けて、朽ち果てても種子を残してまた新しい生命が育っていく、濃い緑の豊かな植生です。その濃い緑のなかを、地から天へ、天から地へと循環する水を豊富に集めていつまでも流れ落ちる滝。それぞれにこの大自然のなかで、いのちの再生と永遠を示唆しているかのようにみられます。この緑と水が、いかにも熊野らしい峻厳な雰囲気を醸し出していて、「熊野では山や森が神様仏様です」ということばが素直に納得させられるような、聖域となっていました。
熊野那智大社は、南向きの朱塗りの拝殿があって、その後ろに、熊野権現造りの社殿が並んでいます。ここにお詣りすると、無病息災、延命長寿などに御利益があるのだそうです。那智大社のみならず、熊野三山のどこへお詣りしても格別の御利益があると信じられてきたからこそ、多くの人々は、険しい道をものともせず、この熊野に惹きつけられてきたのでしょう。古道を歩いていたときに、私が、「語り部」のガイドさんにこの熊野詣での御利益のことを聞いてみたところ、中年の優しい顔つきをしたこの女性は、大きな御利益があることを固く信じていて、いまでも、何か困ったこと、悩み事があると、お詣りに出かけるのだと言っていました。
この那智大社のすぐ隣にあるのが、青岸渡寺で、これも、西国三十三か所第一番札所として、熊野詣での多くの人々を惹きつけてきました。この寺はインドから熊野浦に漂着したと伝えられている裸形上人によって開かれた古刹で、「青岸に渡る」をいう名前は、浄土への指向を表しているようで興味深く思われます。同じ裸形上人によって開かれた、那智川下流の補陀洛山寺(ふだらくさんじ)の「ふだらく」は、サンスクリット語で観音浄土を意味する「ポタラカ」からきているといいます。この補陀洛山寺も、極楽往生のための「補陀洛渡海」と称する水葬の儀式でも知られてきました。この熊野の土地と深く結びついているこのような葬送の儀式について、熊野出身の芥川賞作家・中上健次は、『浮島』のなかで、つぎのように書いています。
「ひょっとすると、こうも言えるかもしれない。那智の青岸渡寺と大社は鳥葬、海辺にある補陀洛山寺は水葬、新宮の神倉は鳥葬、王子、阿須賀、速玉は水葬の、死体が集まるところだった。死体の魂を呼び、鎮めるところだった。その町は、死んだ者の魂と生きている者の魂の、行き交うところであった」
このように、熊野に結びついた葬送のあり方を並べ立てると、死のイメージが強く出てしまうようにも思われますが、死と生が行き交うところ、つまり、死がどこか遠いところにあるのではなくて、生のそばの身近なところにあることが大切なのでしょう。「くまの」とは、「隈る野」(くまるの)のことで、あの世とこの世の接点と考えられてきました。現代では、生と死を峻別し、死の国を遠くにイメージしがちですが、死は生の継続であり、生は死の継続であるというように、本来、生と死は断絶していなのかもしれません。そういう意味では、熊野は死者の地であると同時に、再生を経た生者の地でもあって、古来、多くの人々は、浄土思想の中で、よりよき再生への願望を共有しながら、この熊野詣でに励んでいたようにも思われます。
(2004.06.16)

託卵するカッコウの哀しみ (身辺雑記 11)
カッコウは託卵という習性があることでよく知られています。自分は「子育て」をせず、ほかの鳥の巣に自分の卵を産みつけてしまいます。その鳥に自分の卵を抱かせて孵らせ、育てさせるのです。その託卵の様子をテレビで見たことがありますが、ほんとうに不思議な習性です。
私がテレビで見たのは、カッコウがオオヨシキリに託卵する様子でした。オオヨシキリが自分の巣の中に卵を幾つか産んで抱き温めているのを、カッコウが少し離れた木のなかに隠れてじっと見守っています。オオヨシキリは卵を温めているわけですから、なかなか巣を離れようとはしません。それを、カッコウは、おそらく飲まず食わずでじっと見続けているのです。それだけでも、たいへんな忍耐と根気が必要です。
どれくらいの間見続けていたのか、テレビの映像ではよくわからなかったのですが、やがて、なにかの拍子に、オオヨシキリがちょっと巣を離れますと、その瞬間に、カッコウはさっと、オオヨシキリの巣の中へ飛び込んでいきました。そこで不思議な早業をみせます。間髪を入れずに、そこにあったオオヨシキリの卵を一つ呑み込んでしまうと、今度は、自分の卵を一つ産み落とすのです。これで、巣の中の卵の数は増えたことになりませんから、オオヨシキリが戻ってきても、カッコウの卵が一つ混ざっていることに気がつかないようです。オオヨシキリは、それまでどおり、卵を温め続けてやがて雛が孵ることになります。
不思議なことに、卵から孵る最初の雛は、オオヨシキリの雛ではなくて、あとから産み落とされたカッコウの雛のほうです。いつでも、一日か二日、カッコウの卵のほうがオオヨシキリの卵より先に孵ります。なぜそうなるのかはわかりません。ともかく、先に孵るのはかならずカッコウの卵だそうです。しかも、そればかりではありません。もっと不思議な、恐るべき光景がそのあとに続くのです。
雛が孵ったら、雛は餌をねだるようになります。オオヨシキリの卵はまだ孵っていませんが、親鳥は、時折、餌を探し求めて巣を離れなければなりません。ところが、そのオオヨシキリの親鳥が巣を離れるとすぐに、孵ったばかりのカッコウの雛は、まわりにある幾つかのオオヨシキリの卵を巣から押し出して、下へ落としてしまおうとするのです。
孵ったばかりの雛が、自分のからだの大きさとあまり違わないようなオオヨシキリの卵を、背中に乗せて、一つずつ必死になって押しはじめ、巣の外へ落としてしまいます。驚くべきことに、そのカッコウの雛の背中は、そのような作業のためなのでしょうか、卵を乗せやすいように、くぼんでさえいます。カッコウの雛が、ハアハアと息をつきながら、ひとつ、またひとつと、懸命にオオヨシキリの卵をその背中のくぼみに乗せて、巣の外へ押し出している姿は、実に不思議な光景というほかはありません。
理屈からいうと、オオヨシキリの親が運んでくる餌を独り占めするためには、自分だけが生きて、ほかのオオヨシキリの卵は孵らないほうがいいのはわかります。しかし、そのために、孵ったばかりの雛がまわりの卵を巣の外へ押し出してしまうという知恵は、いったい、どこからくるのでしょうか。そして、孵ったばかりのカッコウの雛がほかの卵を押し出しやすいように背中にくぼみをつけた体型をしているというのは、いったい、どのように説明できるのでしょうか。しかも、カッコウの雛のその背中のくぼみは、まわりの卵を押し出すという作業が終わってしまう数日後には、なくなってしまって普通の体型に戻るという、テレビの解説を聞いたりすると、ほんとうに不思議で、人智を超えた大きな力といったようなものをつい頭に思い描いたりもしてしまいます。
ところで、カッコウのこの託卵は、種の維持・存続という視点からみると、けっして、効率のよい習性とはいえないようです。ほかの鳥の巣を狙って自分の卵を産み落とすのには、たいへんな忍耐と機敏さが必要ですし、相手の鳥も、自分の不利益になるような、そのような行為を易々と容認するはずもありませんから、カッコウは自分の卵を危険にさらす大きなリスクを背負うことになると考えてもいいでしょう。せっかく託卵しても、下手をすると相手の鳥に気づかれて、自分の卵を食べられてしまったり、巣から落とされてしまったりするかもしれません。そんなリスクを冒すくらいなら、はじめから自分で巣を作って、自分で自分の卵を温めた方がはるかに楽なようにも思えるのです。それでも託卵しようとするのは、カッコウがよほど怠けものでずるいからでしょうか。
それが、どうも、そうではないようなのです。カッコウの親鳥の生態についてのある研究によりますと、カッコウとかホトトギスのような鳥の仲間は、ほかの鳥に比べて進化が遅れていて、自分の体の体温調節がよく出来ないのだそうです。そのために、体温はどうしても外気温に左右されやすくなってしまいます。つまり、昼はあたたかくても夜は冷たくなり、この特性が、一定の温度の維持を必要とする卵の孵化には向いていないというのです。そうすると、カッコウも、できれば自分の卵は自分で温めて、自分の力で子育てをしたいはずなのに、それが出来ないから、仕方なく、リスクを冒して、他の鳥の巣へ侵入していることになります。
自分で自分の子を育てられないというのは、どれほどつらく哀しいことでしょうか。それでも絶望せずに、なんとか、子を育てる方策を探ろうとするのは、いのちを持つものの本能的な反応です。カッコウの場合は、長い進化の歴史を経て、それが託卵という形で遺伝子DNAのなかに刻み込まれていったと考えられるでしょう。オオヨシキリなどの他の鳥を欺き、自分の卵を生かすために他の鳥の卵を突き落としても、カッコウとしては、それを悪いことと考える余裕はありません。そうする以外の生き方が出来ず、カッコウはカッコウなりに必死になってがんばっているのです。
こういう風にみてくると、カッコウのあの身勝手で非情な託卵も、また違った目で捉えられるように思われます。これは人間の場合も同じですが、人の姿を、外面だけで、それも行動の一面からみるだけでは、なかなか本当の姿は捉えられないものです。違った角度から見れば、当然、違って見えてきます。欠点が美点になることさえ珍しくはないでしょう。そういうものの見方の違いも、私たちは、このカッコウの託卵から考えてみることもできるかもしれません。
(2004.06.01)

『夜と霧』新版からの三つの断章 (身辺雑記 10)
私は、身辺雑記(05) で「雪のなかのアウシュビッツ」を書きましたが、あのなかで触れた『夜と霧』(霜山徳爾訳)は1947年の旧版を準拠にして、1961年にみすず書房から刊行されたものです。この本は、著者のフランクルによって、1977年に新版が出され、それをもとにドイツ文学翻訳者の池田香代子さんが改訳した『夜と霧』(新版)が、同じくみすず書房から2002年11月に出版されています。池田さんによりますと、旧版と新版では、かなりの異同があったということですが、私は、翻訳文の違いに関心もあって、新版のほうも読み比べてみました。私が、「雪のなかのアウシュビッツ」のなかで、最後に引用した文(愛についての認識)は、池田さんの新版では、つぎのようになっています。
《雪に足を取られ、氷に滑り、しょっちゅう支え支えられながら、何キロもの道のりをこけつまろびつ、やっとの思いで進んでいくあいだ、もはや言葉はひとことも交わされなかった。だがこのとき、わたしたちにはわかっていた。ひとりひとりが伴侶に思いを馳せているのだということが。
わたしはときおり空を仰いだ。星の輝きが薄れ、分厚い黒雲の向こうに朝焼けが始まっていた。今この瞬間、わたしの心はある人の面影に占められていた。精神がこれほどいきいきと面影を想像するとは、以前のごくまっとうな生活では思いもよらなかった。わたしは妻と語っているような気がした。妻が答えるのが聞こえ、微笑むのが見えた。まなざしでうながし、励ますのが見えた。妻がここにいようがいまいが、その微笑みは、たった今昇ってきた太陽よりも明るくわたしを照らした。
そのとき、ある思いがわたしを貫いた。何人もの思想家がその生涯の果てにたどり着いた真実、何人もの詩人がうたいあげた真実が、生まれてはじめて骨身にしみたのだ。愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだ、という真実。今わたしは、人間が詩や思想や信仰をつうじて表明すべきこととしてきた、究極にして最高のことの意味を会得した。愛により、愛のなかへと救われること! 人は、この世にもはやなにも残されていなくても、心の奥底で愛する人の面影に思いをこらせば、ほんのいっときにせよ至福の境地になれるということを、わたしは理解したのだ。
収容所に入れられ、なにかをして自己実現する道を断たれるという、思いつくかぎりでもっとも悲惨な状況、できるのはただこの耐えがたい苦痛に耐えることしかない状況にあっても、人は内に秘めた愛する人のまなざしや愛する人の面影を精神力で呼び出すことにより、満たされることができるのだ。わたしは生まれてはじめて、たちどころに理解した。天使は永久の栄光をかぎりない愛のまなざしにとらえているがゆえに至福である、という言葉の意味を・・・・・。》 (pp.60-61)
この新版のなかでも、旧版訳者の霜山徳爾氏は、一文を寄せていました。そのなかで、氏は、「あの愚かしい太平洋戦争の絶望的な砲火硝煙の戦場体験を持つ者は、今や70歳代の終わりから 私のように80歳前半までの老残の人間のみである。どうしても骨っぽい、ごつごつした文体になってしまう」と書いています。そして、「新訳者の平和な時代に生きてきた優しい心は、流麗な文章になるであろう」と池田さんの訳文に期待感を表しています。戦争の愚かしさを身をもって体験した霜山氏の心情がにじみ出ているような文です。
確かに新版は読みやすくはなっていますが、ここでは、そのなかから、あと二つ、こころを打たれた場面を抜き書きしておきたいと思います。はじめの文は、被収容者の美に対する感覚について述べたものです。人間が、あれほどまでのぎりぎりの極限状況にまで追い込まれますと、美を意識するこころの余裕もなくなり、感覚の麻痺状態が続くようにも思えるのですが、実際は、むしろ逆で、彼らの場合は、鋭敏にとぎすまされた感覚で、自然の美しさを全身で味わっていたように思われます。つぎのようにです。
《被収容者の内面が深まると、たまに芸術や自然に接することが強烈な経験となった。この経験は、世界やしんそこ恐怖すべき状況を忘れさせてあまりあるはど圧倒的だった。
とうてい信じられない光景だろうが、わたしたちは、アウシュヴィッツからバイエルン地方にある収容所に向かう護送車の鉄格子の隙間から、頂きが今まさに夕焼けの茜色に照り映えているザルツブルクの山並みを見上げて、顔を輝かせ、うっとりとしていた。わたしたちは、現実には生に終止符を打たれた人間だったのに---あるいはだからこそ---何年ものあいだ目にできなかった美しい自然に魅了されたのだ。
また収容所で、作業中にだれかが、そばで苦役にあえいでいる仲間に、たまたま目にしたすばらしい情景に注意をうながすこともあった。たとえば、秘密の巨大地下軍需工場を建設していたバイエルンの森で、今まさに沈んでいく夕日の光が、そびえる木立のあいだから射しこむさまが、まるでデユーラーの有名な水彩画のようだったりしたときなどだ。
あるいはまた、ある夕べ、わたしたちが労働で死ぬほど疲れて、スープの椀を手に、居住棟のむき出しの土の床にへたりこんでいたときに、突然、仲間がとびこんで、疲れていようが寒かろうが、とにかく点呼場に出てこい、と急きたてた。太陽が沈んでいくさまを見逃させまいという、ただそれだけのために。
そしてわたしたちは、暗く燃えあがる雲におおわれた西の空をながめ、地平線いっぱいに、くろがね色から血のように輝く赤まで、この世のものとも思えない色合いでたえずさまざまに幻想的な形を変えていく雲をながめた。その下には、それとは対照的に、収容所の殺伐とした灰色の棟の群れとぬかるんだ点呼場が広がり、水たまりは燃えるような天空を映していた。
わたしたちは数分間、言葉もなく心を奪われていたが、だれかが言った。
「世界はどうしてこんなに美しいんだ!」 》 (pp.64-66)
著者のフランクルは、餓死寸前の状態の中で重労働に従事させられていましたが、医者であったために、幸運な偶然があって、のちに収容所内の医務室勤務となります。彼の両親も、妻も、二人の子どもも収容所内でいのちを断たれて、結果的には彼一人が生き残ることになりました。つぎは、彼が医務室で死んでいったある女性患者の記録です。死を前にして内面性を深めていった彼女が、「こんなにひどい目にあわせた」運命に感謝している姿には、こころを打たれます。
《この若い女性は、自分が数日のうちに死ぬことを悟っていた。なのに、じつに晴れやかだった。
「運命に感謝しています。だって、わたしをこんなにひどい目にあわせてくれたんですもの」
彼女はこのとおりにわたしに言った。
「以前、なに不自由なく暮らしていたとき、わたしはすっかり甘やかされて、精神がどうこうなんて、まじめに考えたことがありませんでした」
その彼女が、最期の数日、内面性をどんどん深めていったのだ。
「あの木が、ひとりぼっちのわたしの、たったひとりのお友だちなんです」
彼女はそう言って、病棟の窓を指さした。外ではマロニエの木が、いままさに花の盛りを迎えていた。板敷きの病床の高さにかがむと、病棟の小さな窓からは、花房をふたつつけた緑の枝が見えた。
「あの木とよくおしゃべりをするんです」
わたしは当惑した。彼女の言葉をどう解釈したらいいのか、わからなかった。讒妄(せんもう)状態で、ときどき幻覚におちいるのだろうか。それでわたしは、木もなにかいうんですか、とたずねた。そうだという。ではなんと? それにたいして、彼女はこう答えたのだ。
「木はこういうんです。わたしはここにいるよ、わたしは、ここに、いるよ、わたしは命、永遠の命だって・・・・・」
》 (pp.116-117)
(2004.05.16)

障害を乗り越えていく人 (身辺雑記 09)
重度障害者の星野富弘さんのことは、いまでは、花の詩画集などでよく知られるようになりました。私のアパートの部屋にも、娘が毎年贈ってくれる星野さんのカレンダーがかけられています。美しい花の絵に、美しい詩のことばが添えられて、これが口に加えた筆で描かれたとはとても思えないほどですが、どの絵にも、星野さんの気持ちがそのまま伝わってくるようなあたたかさを感じさせられます。
私は、教壇に立っていた頃、学生たちに発想の転換を考える資料の一つとして、何度か、星野さんのビデオを使ったことがありました。星野さんは、怪我をしたあと、クリスチャンになって結婚しますが、その時のナレーター・樫山文枝さんは、「何気なく見えるこの結婚式の裏にひそむ、深い意味をお考えいただければ幸いでございます」と言っていました。その星野さんは、結婚式の時に、色紙に「わたしはあなたのみおしえをよろこんでいます。苦しみに会ったことは、わたしにとってしあわせでした」と書いています。「あれほどの苦しみにあったことが幸せとは」と、私たちはつい考えてしまいますが、これは、深くこころに残ることばです。
星野さんは、詩画集『かぎりなくやさしい花々』のなかで、「わたしが元気だったころ、からだの不自由な人を見れば、かわいそうだとか、気味がわるいとさえ思ったことが、ずいぶんありました」と自らのことを述懐しています。そして、つぎのように、続けています。
しかし、自分が車椅子にのるようになって、はじめてわかったことなのですが、からだが不自由な自分を、不幸だとも、いやだとも思わないのです。
けがをして、一、二年は、からだのことでなやんだり、くるしんだりしました。でも、うけた傷は、いつまでもひらきっぱなしではなかったのです。傷をなおすために、そこには新しい力が自然とあたえられ、傷あとはのこりますが、そこには、まえよりもつよいものがもりあがって、おおってくれます。からだには傷をうけ、たしかに不自由ですが、心はいつまでも不自由ではないのです。不自由と不幸は、むすびやすい性質をもっていますが、まったく、べつのものだったのです。
そして、「不自由な人を見て、すぐに不幸ときめつけてしまったのは、わたしの心のまずしさでした」とその述懐を結んでいました。
そういえば、あの『五体不満足』の乙武洋匡君も、「障害は不便です。だけど、不幸ではありません」と、同じようなことを言っていたのを思い出します。乙武君の場合は、先天性四肢切断というやはり重い障害ですが、彼は、それを、単なる身体的特徴としか考えていませんでした。「ボクには、人に負けないものがある。それは、手足がないこと」といっていたぐらいですから、乙武君は、はじめから障害の苦しみとは無縁の人であったのかもしれません。『五体不満足』のあとがきには、彼は、つぎのように書きました。
ボクは、五体不満足な子として生まれた。不満足どころか、五体のうち四体までがない。そう考えると、ボクは最低条件すら満たすことのできなかった、親不孝な息子ということになる。
だが、その見方も正しくはないようだ。両親は、ボクが障害者として生まれたことで、嘆き悲しむようなこともなかったし、どんな子を育てるにしても苦労はつきものと、意にも介さない様子だった。何より、ボク自身が毎日の生活を楽しんでいる。多くの友人に囲まれ、車椅子とともに飛び歩くいまの生活に何ひとつ不満はない。
つい最近では、韓国でベストセラーになった『チソン、愛してるよ』が日本語に翻訳されて、テレビなどでも話題になりました。「チソン」というのは、ソウルの梨花女子大学で幼児教育を専攻していた人で、学生の頃は、「女優のように美しい」と言われた美貌の持ち主でした。その彼女が、二〇〇〇年の七月、兄と一緒に自動車で帰宅の途中、交通事故にあい、全身の五十五パーセントが黒焦げになるほどの大火傷を負ってしまいます。かつぎ込まれた病院では、医者は彼女を一目見るなり、「生きる望みはない。生きても人間の姿には戻らない」と言ったのだそうです。
チソンさんは、何度も皮膚の移植を繰り返しながら、奇跡的に回復に向かいました。そして、入院七か月で一応退院することになります。そのあとは、通院とリハビリの長い生活が続きましたが、あるいは、肉体的な苦しみよりも、精神的な苦しみとの闘いの日々であったかもしれません。みるも無惨に変わってしまった自分の顔を見て、「お兄ちゃん、わたしを殺して。こんなになって、生きていけないわ」と言ったこともあります。「率直にいって、あなたは醜いです」とこころないことばをホームページに書き込まれたりして、傷ついたこともあったようです。
本の中には、「女優のように美しい」と言われた頃の写真と、事故後の大きく変わってしまった写真も載せられていましたが、この厳しい現実を受け容れることは、彼女にとってもたいへん困難なことであったにちがいありません。しかしそれでも、チソンさんは、だんだんと自分を取り戻し、キリスト教への深い信仰に支えられて、見事にこころの変身をも遂げていきました。それを本の中で、彼女は、こう書いています。
よい大学を出てよい夫に出会い、人からうらやまれるように生きるのが祝福だと考えたころもありました。顔がきれいなのがすべてだと思っていたときもありました。しかし本当の祝福はそんなものではありませんでした。わたしの体の障害が、これまで耐えてきた苦痛と痛みがそれを教えてくれました。本当に重要で永遠に存在するものは目に見えるものではないことを悟ったのです。体が普通でなく不自由であるからといって萎縮する必要はありません。人生が終わりだとあきらめる必要もありません。障害者は決して劣った存在ではありません。わたしはむしろ、優越感を持ってもいいような祝福された人間だと思っています。神さまのかぎりない関心と細心の配慮そして果てることのない愛を経験することができた神さまのVIPなのですから。
彼女は、リハビリを続けながら、苦痛のなかでも、やっと、ひとりでスプーンをもつことが出来るようになったことに感謝します。ドアのノブを掴んで、自分でドアを開けられるようになったことにも感謝し、喜びを感じるようになっていきます。そして、この本の「エピローグ:私はいま幸せです」にはつぎのように書きました。
苦難は祝福です。つらく苦しい時間を過ごし、それを克服するときに与えられる宝物があります。苦難を通じてしか学ぶことのできない、持つことのできないその果実がどれほど貴いものか……わたしはそれを理解しています。
誰かがわたしにこう質問しました。「昔の姿に、事故の前の自分に戻してくれると言われたらどうする?」と。バカだと言われるかもしれませんが……わたしの答えは「戻りたくない」です。
「戻りたくない」理由は、外見の点数は下がっても、心の点数がぐんと上がったからだそうです。その彼女が、自らの「変身」を確認し、それを納得させるために鏡に向かう場面は、感動的といえるかもしれません。昔の美貌の片鱗もないいまの見慣れぬ自分の顔を鏡に映して、手を振り挨拶をするのです。「こんにちは、イ・チソン」。すると、鏡の中の新しいチソンも挨拶を返してきました。「チソン、愛してるよ」。
(2004.05.01)

スイスという国 (身辺雑記 08)

レマン湖畔のヴヴェイ付近から眺めたアルプス
の山々。 2004.04.08 (筆者撮影)
スイスは面積が4万1千平方キロで、日本の九州よりやや大きめの広さですが、総人口は7百万人を少し上まわる程度です。よく知られているように、国土の6割をアルプスが占める山岳国家で、最高峰はモンテ・ローザの4、634メートルです。マッター・ホルン(4、478メートル)、ユング・フラウ(4、158メートル)などがそれに続いています。アルプス山脈全体の最高峰は、モン・ブランの4、807メートルですが、これはイタリア・フランス国境にあって、スイス領土には含まれていません。
私が家族4人で最初にスイスを訪れたのは、もう30年も前の1974年夏のことでした。その当時は、アメリカのオレゴン州に住んでいましたが、夏休みに、カナダのバンクーバーからロンドンへ飛んで、しばらく過ごした後、オランダのアムステルダムへ行きました。そこからレンタカーで、ドイツ、オーストリアを経て、インスブルックから南下をはじめたのです。ここでは、アルプスを越えればイタリアです。当時はまだイタリアも貧しく、国境を越えたところで、外国人観光客を増やすための、ガソリン割引切符などをもらったことを覚えています。
イタリアでは、ローマまで南下し、そのあとは北上して、ミラノの北部のコモ湖付近からはじめてスイスに入りました。このあたりは、ティチーノ地方と呼ばれて、イタリア領土の中にスイス領土が袋がぶら下がったように入り込んだ形になっています。ルガーノを通りさらに北上すると、やがて、アルプス山脈中のサン・ゴッタルダ峠にさしかかります。
この峠は、13世紀以来、地中海世界から北ヨーロッパを結ぶ最も重要な交易ルートとして注目されてきました。峠の北側を支配していたのは、オーストリアのハプスブルグ家でしたが、彼らが派遣した代官の圧政に抵抗して、あの、ウイリアム・テルの物語も生まれました。権威に従わないウイリアム・テルは捕らえられて、自分の子供の頭の上にリンゴを置き、それを射落とせば許したやるといわれます。ウイリアム・テルは、そのリンゴを見事に射落としたのですが、代官は約束を守らず、さらに難題をふっかけていきます。こうしたハプスブルグ家の横暴に対する民衆の反抗運動が、結局は、スイスの独立国家への道を拓くことになっていきました。私は、その物語の舞台になったあたりを運転しながら、くねくねと曲がった狭い峠道を、通り抜けていきました。ところどころで開けた緑の斜面には、のんびりと、牛の群が首に付けたカウ・ベルをカランカランと鳴らしていました。
いまでは、このサン・ゴッタルダ峠の下には全長15キロに及ぶトンネルが開通していて、高速道路も「ウイリアム・テル特急」などと名付けられた鉄道列車も、瞬く間にアルプス山脈を通り抜けてしまうようです。何年か前に、イタリアのミラノから西へ向かって、バスで、アルプスの反対側のフランスへ出たことがありましたが、その時も、モン・ブランの下に掘られたトンネルで、一気に、アルプスを通り抜けてしまいました。あの、カウ・ベルの鳴る、サン・ゴッタルダ峠のくねくね道を思い出すと、ちょっと味気ない気もしないではありません。交通が便利になったのはいいのですが、このようなトンネルによってスイスを通過するヨーロッパ諸国のトラックの数が1997年に百万台を突破してからも増加の一途をたどり、いまや、深刻な公害問題を引き起こしているようです。
サン・ゴッタルダ峠を越えますと、フィーアヴァルトシュテットという名の大きな湖が眼前に広がってきます。長い名前ですが、通称ルチェルン湖と呼ばれている美しい湖です。スイス最大の湖はレマン湖で、大きさは582平方キロありますから、日本最大の琵琶湖を一回り小さくしたくらいです。スイスでいわれる五大湖は、レマン湖のつぎに、ボーデン湖、ヌーシャテル湖、マッジョーレ湖と続きます。そのあとにくるのがルチェルン湖で、大きさは、レマン湖の5分の1くらいでしょうか。
私は、1974年以来、スイスへは何回か行っていますが、この間は、ジュネーブからレマン湖の北側の湖畔に沿って、ヴヴェイ、モントルーなどの景勝地へと続く湖畔の道をバスでドライブしてきました。青く澄んだ湖面は、雪を頂いたアルプスの山々の影を映して、こころが吸い込まれるような美しさです。このような風景に惹かれたからでしょうか、あの喜劇王・チャールズ・チャップリンも、ヴヴェイの高台のブドウ畑の中に、別荘を建てて住んでいたようです。湖畔には、チャップリンの銅像も建っていました。
バス旅行は、何日かをかけてスイス北端に近いチューリッヒまで続きましたが、その途中で通ったのがルチェルン湖です。その近くには、いまも中世の面影を留めている美しいルチェルンの街があります。ここでは、あのヨーロッパで一番古い木造橋といわれるカペル橋が、観光の名所となっています。かつて、私たち家族4人も、この橋を渡り、旧市街の時計屋の一軒を尋ねて、長男は念願の時計を自分で貯めた50ドル相当のスイスフランで買ったことがありました。残念ながら、1994年には火事でこの橋の半分以上が消失してしまいましたが、世界中から再建のための募金が集まって、すっかり元通りに修復されたということです。
このカペル橋から北側のホープ教会を通り越してさらに3百メートルほど歩いたところに、有名な「瀕死のライオン」記念碑があります。デンマークの彫刻家トルバルセンのデザインによる石像で、これは、フランスの傭兵となって戦死したスイス人兵士の慰霊碑として建てられました。
スイスは、いまでこそ観光立国で、世界中から観光客を集めて、国民の生活も豊かですが、少なくとも19世紀以前は、ヨーロッパではもっとも貧しい国の一つとして、人々は生活苦に喘いでいました。山も湖も生活の足しにはならず、全国平均標高が1、350メートルの生活環境の中では、農業生産性も決して高くはなかったのです。人々は、山ばかりの自然の厳しさを嘆いていたかもしれません。食べていけなくなった人々は、外国の傭兵として国外へ出ていきました。スイス人は堅実で辛抱強く、困難にも耐えることになれています。それに、国内では、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語と四つの言語が話されていることからも想像できるように、スイス人はことばの上でも、外国で不自由することはあまりありません。そんなことから、スイス人傭兵は、貧しいスイスの最大の「輸出品目」として、周辺の国々から歓迎されていたのです。
あの、フランスのルイ16世も、スイス傭兵を側に置いて、身辺の警護にあたらせていました。フランス革命が起こって、ルイ16世の家族が危険にさらされたとき、パリのチュイルリー王宮で、スイス傭兵は、王の家族を守るために最後まで戦って全滅しています。その786人におよぶ傭兵の死を悼んで建立されたのがこの石像「瀕死のライオン」です。スイスが長い苦難の歴史を経て永世中立の道を宣言しているのも、このような悲しい傭兵の悲劇とも無関係ではないでしょう。今日では、このスイス人傭兵の名残は、ローマのバチカン宮殿の警備兵として残されているだけです。
しかし、貧しかったスイスも、1760年代にイギリスで始まり、1830年代以降ヨーロッパ諸国へ波及していった産業革命に大きく影響されることになります。生活が豊かになり、スイスの美しく壮大な自然美に目を向けはじめた諸外国の人々が、イギリス人、フランス人を筆頭にして、つぎつぎにアルプスを訪れはじめたのです。
スイス人は、それまで自分たちが無用の長物のように考えてきたアルプスの山々を中心とする雄大な自然が、大きな収入源になることにはじめて気がつきました。スイス国内の産業革命も手伝って、生活もだんだんとよくなっていきます。やがて、スイスは、ヨーロッパの、というよりは、世界の観光地として不動の地位を占めることになりました。いまでは、誰よりも熱心にこのアルプスの自然を愛し、守ろうとしているのも、地元のスイス人といっていいかもしれません。
(2004.04.16)

「雪山偈」と「いろは歌」 (身辺雑記 07)
仏典の「涅槃経第十三」に次のような話があります。
むかし、ヒマラヤの山中に雪山童子(せっせんどうじ)と呼ばれていた若い修行者がいました。その雪山童子は、衆生を救うための法を求めて、いろいろと難行苦行を続けていましたが、その修行の姿を、天からじっと帝釈天がみていました。
帝釈天というのは、東京でも柴又の帝釈天で有名ですが、もともとは、インド最古の聖典『リグ・ヴェーダ』に出てくる英雄神です。その当時からインドでは、悟りを開こうとする求道者は数多くいました。しかし、固い意志で、難行苦行に最後まで耐え抜き、悟りに至る人はほとんどいません。帝釈天は、雪山童子もまた、そのような意志の弱い修行者のひとりではないかと思ったのです。そして、雪山童子の苦行が本物かどうか、試してみようとしました。
まず、帝釈天は、恐ろしい形相の羅刹に姿を変えました。羅刹というのは、インドの食人鬼です。人の生肉を食べ、生き血をすすります。その羅刹となって天上から雪山まで降りてきた帝釈天は、雪山童子の近くまで来ると、過去生の仏が説いた教えを詩句にして、その前半を、声高らかに唱えました。
諸行無常 (作られたものはすべて無常である)
是生滅法 (生じては滅することを本性とする)
これを聞いた雪山童子は、深い喜びに包まれます。これこそが長い間求めてきた真理のことばだ、とすぐわかりました。ただ、これだけでは意味が十分ではない。まだあるはずで、どうしてもこの後の句も聞きたい、と思ったのです。けれども、そこにいたのは恐ろしい形相の羅刹だけでした。よもやとは思ったのですが、雪山童子は、思い切って羅刹に尋ねました。
「いまのことばは、過去、現在、未来の三世にわたる仏の教えで、真理のことばです。この続きがあるはずですが、ご存じでしたら是非教えてください」
羅刹は答えました。「私は幾日も食べ物が手に入らず、飢えている。お前の体を食べさせてくれるというのなら、教えてやってもよい」
雪山童子は、しばらく考えて、静かに答えました。「わかりました。残りのことばを聞くことができたら、私の体はあなたに差し上げましょう。私の体は、たとえ天寿を全うしたとしても、どうせ獣か鳥に食われるだけです。それに、食われたからといって、なんの報いもあるわけではありません。それならば、悟りの道を求めるために、この体は捨てることにいたします」
それを聞いた羅刹は、雪山童子の固い決意に迷いがないのを見届けると、やがて、居ずまいを正して、ゆっくりと、後半のことばを唱えました。
生滅滅己 (生滅するものがなくなり)
寂滅為楽 (静まっていることが安らぎである)
こう説いてから、羅刹は、約束通り、雪山童子の体をくれるようにと詰め寄りました。
雪山童子は、覚悟の上のことですから、体を捨てるのにはなんのためらいもありませんでした。ただ、後世の人々のために残しておきたいと考えて、このことばを、まわりの岩や木に書き留めました。そして、近くの高い木に登ると、一気に地上へと身を投げたのです。
その瞬間、雪山童子の体がまだ地上に着かないうちに、羅刹はさっと帝釈天の姿に戻り、空中で、雪山童子の体を受け止めてしまいます。そして、恭しく地上に降ろし、雪山童子にひれ伏して礼拝しました。実は、この雪山童子が、お釈迦様の前世の姿であったということです。
この雪山童子が羅刹から聞いた真実のことばは、雪山にちなんで仏教では、「雪山偈」(せっせんげ)とよんでいるようです。偈というのは、仏の教えや、徳を称えたりするときのことばを詩句の形であらわしたものです。
この話は、仏典がインドから中国や朝鮮を経て伝わってきた後、やがて日本文学の中にもとりいれられ、さらに、それが太平洋戦争中の小学国語読本でも、六年生用の巻十二に「修行者と羅刹」というタイトルで取り上げられてきました。私が小学生の時にこれを教室で習ったのは、考えてみますともう
62年も前の昭和 17年(1942年) のことになりますが、この話は妙に印象深く、幼いこころに染みこんでいったことをいまでも覚えています。
ただ、私が、教わったときには、この「雪山偈」のところは、日本語に置き換えられて、「いろは歌」になっていました。その意味を、一生懸命に暗記したりしたことが、昨日のことのように思い出されます。調べてみますと、八王子の中央図書館に複製があるということなので、出かけていって、資料室でこの古い教科書に対面してきました。巻十二に、たしかに、「第十七
修行者と羅刹」があります。懐かしい気がしました。子供に返ったような気持ちになって読み返してみましたが、つぎのような文です。新仮名遣いになおして、全文をうつしてみます。
「色はにほヘど散りぬるを、
我が世たれぞ常ならむ。」
どこからか聞えて来る尊い言葉。美しい声。
所は雪山の山の中である。長い間の難行苦行に、身も心も疲れきつた一人の修行者が、ふと此の言葉に耳を傾けた。
言知れぬ喜びが、彼の胸に湧上つて来た。病人が良薬を得、渇者が清冷な水を得たのにも増して大きな喜びであつた。
「今のは仏の御声でなかったろうか。」
と、彼は考えた。しかし、「花は咲いても忽ち散り、人は生まれてもやがて死ね。無常は生ある者のまぬかれない運命であるという意味の今の言葉だけでは、まだ十分でない。若しあれが仏の御言葉であれば、其の後に何か続く言葉がなくてはならない。彼には、そういう風に思われて来た。
修行者は、座を立ってあたりを見廻したが、仏の御姿も人影もない。ただ、ふとそば近く、恐ろしい悪魔の姿をした羅刹のいるのに気がついた。
「此の羅刹の声であったろうか。」
そう思いながら、修行者は、じっと其の物すごい形相を見つめた。
「まさか、此の無知じゃけんな羅刹の言葉とは思えない。」
と、一度は否定してみたが、
「いやいや、彼とても、昔の御仏に教を聞かなかったとは限らない。よし、相手は羅刹にもせよ、悪魔にもせよ、仏の御言葉とあれば聞かねばならぬ。」
修行者はこう考えて、静かに羅刹に問いかけた。
「一体、お前は誰に今の言葉を教えられたのか。思うに仏の言葉であろう。それも前半分で、まだ後の半分があるに違いない。前半分を聞いてさえ私は喜びにたえないが、どうか残りを聞かせて、私に悟りを開かせてくれ。」
すると、羅刹はとぼけたように、
「わしは、何も知りませんよ、行者さん。わしは腹がへっております。あんまりへったので、つい、うわ言が出たかも知れないが、わしには何も覚えがないのです。」
と答えた。
修行者は、一そうけんそんな心で言った。
「私はお前の弟子になろう。終生の弟子になろう。どうか残りを教えて頂きたい。」
羅刹は首を振った。
「だめだ、行者さん。お前は自分のことばっかり考えて、人の腹のへっていることを考えてくれない。」
「一体、お前は何をたべるのか。」
「びつくリしちゃいけませんよ。わしのたべ物というのはね、行者さん、人間の生肉、それからのみ物というのが人間の生き血さ。」と言うそばから、さも食いしんぼうらしく、羅刹は舌なめずりをした。
しかし、修行者は少しも驚かなかった。
「よろしい。あの言葉の残りを聞こう。そうしたら、私の体をお前にやってもよい。」
「えっ。たった二文句ですよ。二文句と、行者さんの体と取りかえてもよいというのですかい。」
修行者は、どこまでも真剣であった。
「どうせ死ぬべきこの体を捨てて、永久の命を得ようというのだ。何で此の身が惜しかろう。」
こう言いながら、彼は其の身に着けている鹿の皮を取って、それを地上に敷いた。
「さあ、これへお座り下さい。謹んで仏の御言葉を承りましょう。」
羅刹は座に着いて、おもむろに口を開いた。あの恐ろしい形相から、どうしてこんな声が出るかと思われる程美しい声である。
「有為の奥山今日越えて、
浅き夢見じ酔ひもせず。」
と歌うように言い終わると、
「たつたこれだけですがね、行者さん。でも、お約束だから、そろそろごちそうになりましょうかな。」と言って、ぎょろりと目を光らせた。
修行者は、うっとりとして此の言葉を聞き、それをくりかえし口に唱えた。すると、「生死を超越してしまえば、もう浅はかな夢も迷いもない。そこにほんとうの悟りの境地がある。」という深い意味が、彼にはっきりと浮かんだ。心は喜びで一ぱいになった。
此の喜びをあまねく世に分って、人間を救わねばならぬと、彼は気づいた。彼は、あたりの石といわず、木の幹といわず、今の言葉を書きつけた。
色はにほえど散りぬるを、
我が世たれぞ常ならむ。
有為の奥山今日越えて、
浅き夢見じ、酔ひもせず。
書き終わると、彼は手近にある木に登った。其のてっぺんから身を投じて、今や羅刹の餌食になろうというのである。
木は枝や葉を震わせながら、修行者の心に感動するかのように見えた。修行者は、
「一言半句の教のために、此の身を捨てる我を見よ。」
と高らかに言って、ひらりと樹上から飛んだ。
とたんに妙なる楽の音が起こって、朗らかに天井に響き渡った。と見れば、あの恐ろしい羅刹は、忽ち端厳な帝釈天の姿となって、修行者を空中に捧げ、そうして恭しく地上に安置した。
諸の尊者、多くの天人たちが現れて、修行者の足下にひれ伏しながら、心から礼拝した。 此の修行者こそ、ただ一すぢに道を求めて止まなかったありし日のお釈迦様であった。
ここであらわれてくる「いろは歌」は、空海が「雪山偈」を日本語に訳したものであると、長い間考えられてきました。しかし、いろいろ検証されてきた結果、いまではそれは否定されて、空海以後の平安中期から世に広まっていったとされています。訳者はまだわかっていません。
日本語への翻訳にあたっては、和音の異なる四十七文字をすべて一度だけ使って重複させずに、七五調四句にまとめているというのは、実に驚くべき技巧です。しかもそれで、深遠な「雪山偈」の意味を移しているとすると、もう神業というほかはありません。
私たちが日常何気なく口にしている「イロハニホヘト・・・」には、このように、インドの「雪山偈」以来の、深い意味がこめられていることになります。
(2004.04.01)

極限状況のなかの二人の母親のことば (身辺雑記 06)
神戸市須磨区で児童連続殺傷事件が起こったのは1997年の3月のことでした。小学生の女児2人が連続して通り魔に襲われ、1人は鈍器で頭を殴られて死亡、もう1人は刃物で腹部を刺されて重傷を負わされました。
この事件はさらにエスカレートします。その後、5月には、切断された子供の頭部が、市内の中学校の正門前で発見されたのです。「酒鬼薔薇聖斗」の名で「ボクは殺しが愉快でたまらない」などと書かれた犯行声明が出されるなど、その異常さが世間を驚かせました。6月には、遂に犯人が逮捕されましたが、それが14歳の少年であったことが、また大きな衝撃を与えて、多くの人々のこころにも、深い傷跡を残したように思います。
その少年を収容した関東医療少年院では、その非行の重大さを考え、医療系と教育系のスタッフで特別チームを組んで、少年に、罪を償う意識や、生命を尊重する心を育て、社会復帰に向けた適応力を高めていくように補導していったようです。その結果、本人が、被害者や遺族に対して強い謝罪の気持ちを持てるようになったとして、同少年院は、先日、法務省に仮退院を申請したことがひろく報道されました。事件の時14歳であった少年は、7年経ったいまでは、21歳の青年になっています。
仮退院申請をつたえる新聞各紙には、この事件で殺害された当時11歳の土師淳と10歳の山下彩花さんのお二人のお父さんとお母さんの談話が載せられていました。そしたまた、加害者である男性の両親の長文の手記も載せられていました。自分の子供がこのような事件の被害者になったら、親はどういう気持ちがするものでしょうか。問うことさえはばかられますが、この極限状況のなかで、彩花さんの母親の山下京子さんは、仮退院申請を聞いて、つぎのように述べています。
私たち遺族に対する謝罪も、もう二度と人を傷つけず、悪戦苦闘しながらもいばらの道を生き抜いていくしかない、と私は考えています。悪戦苦闘といっても制裁を加えるためだけの「苦しめ!」とはニュアンスが違います。
現実社会は決して甘くはありません。そして、平凡な日々ばかりの人生ではないでしょう。それでも、人間を、生きることを、放棄しないでほしい。それこそが私たち遺族の「痛み」を共有することになるのです。
なぜなら、私たちも悪戦苦闘しながら自分の道を歩いているのですから。
彩花さんを失った母親の京子さんは、事件直後は悲嘆の底に沈みながら、おそらく激しく犯人を憎んでいたことでしょう。しかし、事件から半年後、ある瞬間に転機が訪れます。自宅でぼんやり夜の月を眺めていたときに、ふと、彩花さんが話しかけてきたような気がしたのだそうです。「お母さん、もう人を憎まないでいいよ」と。
それでも、母親としての憎しみや悲しみは消えることはなかったでしょう。しかし、新しい気持ちが京子さんに芽生えてきました。「彩花が教えてくれたことはいのちの大切さ。どの人のいのちも、かけがえもなく大切だということ。彼の中が、99パーセントの悪でも、残り1パーセントは善と信じたい」と、このように述べている母親の京子さんのここころのなかでは、なにかが少しずつ変わりはじめてきたように思われます。
もう一つの極限状況のなかにいるのは、加害者のお母さんです。お父さんの書いたものとは別に、長い手記を載せていますが、つぎは、その一部です。
当時は何が何だかわからないままに毎日が目まぐるしく過ぎていきました。頭がおかしくなるかもしれない。でも、かえっておかしくなった方が、何もわからなくて楽かもしれないなとも思いました。
それからは、毎日おびえた生活をしてきました。何度も死にたいと思いましたが、もし、私たちが死ねば、被害者の方々、ご遺族の怒りや悲しみを受け止めるのは、長男以外になくなる。何よりも、どうしてこのような事件が起きたのか、真相を究明する妨げにもなる、それこそ、もう一つの罪かもしれない。生きながらえて、悲しみや怒りを受け止めなければならないと思いました・・・・・・・
これも、私たちには、重く、深くひびくことばです。生涯をかけても償いきれない重い罪を、親が子と共に背負っていこうとするこの決意は、あるいはわが子が極刑を受けるよりも苦しい選択であるのかもしれません。親が担いでいく十字架はこれほどまでに重いものでなければならないのであろうかと、つい考え込んでしまいます。それに、このような事件が起きた背景には、殺戮ゲームや残虐行為などの映像が野放しにされている環境があり、モノとカネの基準がはばを利かして、こころをどこかへ置き忘れてしまったような大人の社会の風潮があることも無視することはできないのです。いまでもなお、未成年者がかかわる残虐な殺人事件などが、あとを断たないところをみると、この事件も、起こるべくして起こったとは言えないでしょうか。
それにしても、この母親の悲しさ、人間の哀れさ。そして、本当はいのちは一つであるのに、という思い。極限状況のなかにあるお二人の母親のことばには、いろいろと考えさせられる教えが含まれているように思えてなりません。
(2004.03.16)

雪のなかのアウシュビッツにて (身辺雑記 05)

アウシュビッツ収容所の入り口
「労働は自由をもたらす」のドイツ語
が見える。筆者撮影(2004.02.29)
もう40年以上もまえのことになりますが、『夜と霧』というタイトルでアウシュビッツ強制収容所の体験記録が出版されて、大きな反響を呼び起こしたことがありました。著者の V. E. フランクルは、かつては少壮の精神医学者として属目され、美しい妻と二人の子供とともにウイーンで平和に暮らしていました。しかし、この平和は、ナチス・ドイツのオーストリア併合以来、破れてしまうことになります。彼はユダヤ人だったからです。
「夜と霧」というタイトルの由来は、1941年12月6日に出されたヒットラーの特別命令に基づいているようです。ナチス・ドイツに反抗する非ドイツ国民を、夜ひそかに逮捕して強制収容所へ送り、その安否や居所は家族親戚にも知らせないとするもので、これが隠語で「夜と霧の命令」といわれていました。後にこの命令の原則は拡大され、対象も広がって、ユダヤ人のほか、何の罪もないポーランド人やジプシーなども含まれるようになっていったのです。
ユダヤ人であるというただそれだけの理由で、著者のフランクルも家族とともに逮捕され、あのアウシュビッツの強制収容所に送り込まれました。そしてそこで、彼の妻や子供達、両親までもが、ガス室で殺されたり餓死したりしました。生き延びたのは、彼だけでした。彼だけが、奇跡的に死を免れて、学者としての冷静な筆致で、凄惨な収容所の記録を残したのです。その記録が日本でも和訳されて、タイトルも『夜と霧』とつけられました。霜山徳爾訳で、みすず書房から刊行されたのが1961年です。多くのショッキングな写真なども収められていますが、この本には、はじめに、出版社の序として、つぎのようなことが書かれています。
1931年の日本の満州侵略に始まる現代史の潮流を省みるとき、人間であることを恥じずにはおられないような二つの出来事の印象が強烈である。それは戦争との関連において起った事件ではあるが、戦争そのものにおいてではなく、むしろ国家の内政と国民性とにより深いつながりがあると思われる。さらに根本的には人間性の本質についての深刻な反省を強いるものである。
第一には1937年に起った南京事件であって、これは日本の軍隊が南京占領後、無辜の市民に対して掠奪・放火・拷問・強姦などの結果、約20万人と推定される殺人を行った。これは当時の目撃者や医師・教授・牧師たちによる国際委員会によって報告書が作製されており、さらに極東国際軍事裁判においても広汎に資料が蒐集されたが、手近かには林語堂「嵐の中の木の葉」やエドガー・スノー「アジアの戦争」などの中にもヴィヴィッドに描写されている。
第二には1940年より1945年に至るナチズム哲学の具体的表現ともいうべき強制収容所の組織的集団虐殺である。これは原始的衝動とか一時性の興奮によるものでなく、むしろ冷静慎重な計算に基づく組織・能率・計画がナチズムの国家権力の手足となって、その悪魔的な非人間性をいかんなく発揮した。「近代的マスプロ工業が、人間を垂直に歩く動物から一キログラムの灰にしてしまう事業に動員された」(スノー)。アウシュビッツ収容所だけで、三百万の人命が絶たれ、総計すれば六百万に達するといわれる。
いまだ人類の歴史において、かくの如き悪の組織化は存在しなかった。その規模においてかくも周到厖大な結末を示したものもなかった。かくてこれは、人類史において画期的な事件として永久に人間の記憶に残るであろうことは疑えない。
事件とこの本のことは、長い間、私の頭の片隅に重苦しく留まっていました。そして、今年の2月末には、私自身が、クラクフ郊外のアウシュビッツにいて、あの「労働は自由をもたらす」とドイツ語で書かれ鉄の門をくぐったのです。春とはいえ、ポーランドはまだ冬の寒さです。アウシュビッツのあたりも一面に
10センチほどの雪で覆われ、ちらちらと雪が舞う広大な収容所跡には、訪れてくる人も疎らでした。
アウシュビッツ収容所は、設立された1940年当時は、1階建てが14棟と2階建てが6棟の計20棟であったようです。それが、1942年までには、囚人の労働力を使って、1階建てはすべて2階になり、新しく8棟がつけ加えられて、28棟になりました。そこへ最も多いときで28,000人の囚人がつめこまれ、さらに増大する囚人は、第2、第3の収容所建設で「処理」されていったようです。
現在では収容所全体がポーランドの国立博物館として開放されていて、ナチス・ドイツの暴虐と狂気のあとが、あちらこちらの建物の中で見られます。ある部屋には、厖大な量の髪の毛がうずたかく積まれていました。収容所に入れられると、男女ともみんな髪の毛を切られ、入れ墨をされたりして、番号だけで呼ばれる存在にされてしまいます。そこに積まれていたのはその人たちの髪の毛の一部で、それでも、2
トンもあるということでした。切られた髪の毛は、ドイツの紡績工場に送られ、そこで布に織られて、防寒服や敷物にされたのだそうです。そのようにして作られた布地のサンプルも展示されていました。
私は、ガス室にも入ってみました。ここではドイツ兵たちは、人々をまず地下の脱衣室に入れ、シャワーを浴びさせるためと騙して、裸のまま隣のシャワー室にみせかけた210平方メートルほどの部屋まで歩かせました。その「シャワー室」の天井には、水が出たことのないシャワーが取り付けられています。そこへ一回に200人くらいの人々を押し込め、部屋に施錠して、天井の穴から「チクロンB」という毒ガスを注ぎ込んだのです。中に入れられた人たちは、15分から20分で死んでいったといいます。
ガス室のほか、死体を燃やすための焼却炉、拷問室、生体実験室、銃殺の壁、集団絞首台、それに、餓死牢、90センチ×90センチの狭い一角に4人を詰め込んだ「立ち牢」などもありました。人間がここまで残酷になりうるのだということを目の前の証拠でふんだんにみせつけられて、歩きまわっているうちにだんだん気分が重くなっていきます。
冬のようにどんよりとした陰鬱な天気で、雪の舞う寒さであったことがむしろアウシュビッツにはふさわしかったのでしょう。少なくとも、うららかな春の陽差しの中でなかったことが、かえってよかったような気がしました。
ついこの間見てきたばかりのこのようなアウシュビッツ収容所の情景は、いまも頭のなかに生々しく残っていますが、そのなかで、明日ともしれぬ死の不安と隣り合わせで過酷な労働に駆り出されていた『夜と霧』の著者が、当時すでに死んでいたはずの妻と交わすつぎのような「対話」がよみがえってきます。愛についての認識の場面です。それは、暗闇に微かに差し込んでくる光のように、絶望のただ中にあっても失われることのない僅かな、しかし確かな救いとして、読むひとのこころに強く訴えかけてくるように思われてなりません。
・・・・・・そしてそれから、われわれが何キロメートルも雪の中をわたったり、凍った場所を滑ったり、何度も互いに支えあったり、転んだり、ひっくり返ったりしながら、よろめき進んでいる間、もはや何の言葉も語られなかった。しかしわれわれはその時各々が、その妻のことを考えているのを知っていた。時々私は空を見上げた。そこでは星の光が薄れて暗い雲の後から朝焼けが始まっていた。そして私の精神は、それが以前の正常な生活では決して知らなかった驚くべき生き生きとした想像の中でつくり上げた面影によっで満たされていたのである。私は妻と語った。私は彼女が答えるのを聞き、彼女が微笑するのを見る。私は彼女の励まし勇気づける限差しを見るーーそしてたとえそこにいなくてもーー彼女の眼差しは、今や昇りつつある太陽よりももっと私を照らすのであった。その時私の身をふるわし私を貫いた考えは、多くの思想家が叡智の極みとしてその生涯から生み出し、多くの詩人がそれについて歌ったあの真理を、生れて始めてつくづくと味わったということであった。すなわち愛は結局人間の実存が高く翔り得る最後のものであり、最高のものであるという真理である。私は今や、人間の詩と思想とそして信仰とが表現すべき究極の極みであるものの意味を把握したのであった。愛による、そして愛の中の被造物の救いーーこれである。たとえもはやこの地上に何も残っていなくても、人間はーー瞬間でもあれーー愛する人間の像に心の底深く身を捧げることによって浄福になり得るのだということが私に判ったのである。収容所という、考え得る限りの最も悲惨な外的状態、また自らを形成するための何の活動もできず、ただできることと言えばこの上ないその苦悩に耐えることだけであるような状態ーーこのような状態においても人間は愛する眼差しの中に、彼が自分の中にもっている愛する人間の精神的な像を想像して、自らを充たすことができるのである。天使は無限の栄光を絶えず愛しつつ観て浄福である、と言われていることの意味を私は生れて始めて理解し得たのであった。
『夜と霧』pp.123-124
(2004.03.05)

与那国島への旅 (身辺雑記 04)

与那国島西崎の「日本国最西端の
地」の碑 筆者撮影 (2004.01.07)
北海道へ行って、電車で稚内駅に着くと、駅の外壁には「日本最北端」とあって、「北緯45度22分44秒」書かれているのが目に入ります。しかし、本当の最北端は、その駅からさらに北西の宗谷岬まで足を伸ばしたところにあります。そこには、オホーツク海を背景に、三角形に尖った「日本最北端の地」の碑が建てられていて、「北緯45度31分22秒」とあり、これが文字通りの日本最北端の地です。
日本人の多くは、これも農耕民族であったことの名残でしょうか、「北」に対しては寒さと結びついた暗いイメージを抱きやすく、かつては北海道も長い間、「文化果つる最果ての国」のように思われてきました。
しかし、世界地図の上で、この北緯45度31分の線をどこまでも西へ伸ばしていくと、ちょうどアルプス山脈の中の最高峰、4,807メートルのモン・ブランあたりにたどり着きます。ヨーロッパというのは、本来は西欧のことで、これはアルプスとピレネー山脈を南端の障壁として北に広がる地域を指していました。すると、どういうことになるでしょうか。日本の最北端は、ヨーロッパの最南端ということになるのです。
たとえば、フランスのパリは北緯48度58分で、サハリンの中部に位置していますし、ロンドンなら、さらに北へ進んで北緯51度28分ですから、これは、サハリンでもはるか北部ということになってしまいます。実際には暖流の影響などで、緯度ほどには気温が低くはありませんが、それでも、このような地理的条件の相違は、ヨーロッパと日本の文化を比較する場合、見落とすことのできないポイントの一つとして重要です。
日本の最北端でもヨーロッパでは最南端ということになりますと、その日本の最南端はどのような位置になるでしょうか。私は、奄美大島と沖縄までは行ったことがありますが、国内での旅の南端はそこまでです。それで、今年の一月のはじめ、日本最南端の島々へ出かけてみることにしました。
東京からまず、南西へ約2,100キロ飛んで亜熱帯の石垣島へ着きました。気温は東京では10度であったのが、23度に上がっています。「日本最南端のリゾート、北緯24度以上にちりばめられた南の楽園」というのがこのあたりの八重山諸島のキャッチフレーズで、そのなかの周囲130キロの石垣島は、八重山エリアの80パーセントの人口が集中する行政と経済の中心の島です。
日本最南端の地を示す碑は、この石垣島から西南へ約56キロの波照間島にあります。周囲はわずか14.
8キロ、人口600人余の小さな島です。しかし、距離的に稚内から一番遠いのは、石垣島から西へ130キロ離れた与那国島で、そこは、日本最西端ということになります。私は、その一番遠い与那国島を目指して、1日2便だけの小さな飛行機に乗り込みました。そこまで行くと、台湾がすぐ近くで、111キロ離れているだけですから、快晴の日には肉眼でもよく見えるのだそうです。
与那国島は、周囲25キロほどの小さな島です。人口もわずか1,800人くらいと聞きました。こういう小さな島では、観光バスもなく、タクシーが自由に使えるわけでもありません。私は、空港の案内所で紹介された小さなホテルに連れて行ってもらい、そこからレンタカーで自分でまわることにしました。
この島は、断崖絶壁に囲まれた絶海の孤島といわれたりもしてきましたが、珊瑚礁の海はあくまでも青く、時々車を停めて、海風に吹かれながら岩肌に砕ける白い波をぼんやり眺めていると、こころが洗われるような気がしました。大自然の中に一人でとけ込んでいくような感じです。
観光客もほとんどなく、車を走らせていても、すれ違う車もあまりありません。私は、やがて、島の西の端の西崎(イリザキ)に車を停めて、「日本最西端の碑」の前に一人で立ちました。北緯24度27分00秒、東経122度56分04秒、これがこの最西端の位置です。最北端の稚内からは、約3,500キロ離れていることになります。
西崎の西を「イリ」というのは、この地方の方言です。西表島を「イリオモテジマ」というのもそうで、「日の入り」の「イリ」からきているようです。島の反対側の「東崎」は「アガリザキ」といわれていました。これも「日の上がり」からきているようです。
私は、北海道には長年住んでいましたので、日本の最北端には何度か行ったことがあります。今度は初めて、弓状に湾曲した日本列島の最西端に立ってみて、なんとなく、あの平知盛の「見るべきほどの事は見つ」という最後のことばを思い出していました。
(2004.02.16)

自律神経失調症に悩む妹への手紙 (身辺雑記 03)
先日、手紙をもらったが、それをまた読み返しながらこれを書いている。お前の自律神経失調症などの病気の回復に役に立つ本当の治療薬とはなんだろうかと、そんなことを考えながら、思いつくままを伝えておきたい。
お前も私も、あのお父さんとお母さんを両親に選んで生まれてきた。私は、毎日、仏壇のお位牌に向かって、お父さんとお母さんに、私の両親であってくれたことを感謝している。お前も私も、あのお父さんとお母さんを選んできた理由があった。少しは、人並み以上に苦労することも知っていた。それを望んで、そのうえで、お父さんとお母さんの子になることを選んで生まれてきた。私自身は、その選択をしたことに満足している。いい選択であったと、生まれてくる前の自分をほめてやりたいくらいだ。
お前も私も、子供の時、お前は怪我で、私は病気で、普通なら死ぬはずのところを、お父さんに助けられた。お父さんはそういう人だった。お父さんの子でなかったら、お前も私もあの時死んでいて、いまこうして生きていることもないだろう。私は時々そのことを思い出すと涙が出そうになる。親の愛情というのは、そういうものだろうが、お父さんの愛情は人並み外れて強く深かった。苦しい生活のなかでも、死にものぐるいで子供たちを守ってきた。そういうお父さんだから、お前も私も、お父さんを選んで生まれてきたのかもしれない。私は、そのようなお父さんに、そして、そのお父さんを支えて、気丈に子供たちに深い愛情を注いでくれたお母さんにも、心から感謝している。だから、いまでも毎朝、お父さんやお母さんに手を合わせて「有り難う」とお礼を言い続けている。
両親を自ら選んできたように、私は、人並み以上の悲しみや苦しみを経験することを選んできたようだ。しかし、それもいま思えば、いいことであった。いまの一生が無駄ではなかったことを、生きる意味があることを、文字通り、いのちを懸けて気づかせてくれた富子や潔典に、こころから感謝している。人間の経験することで、偶然に起こることは一つもないのであろう。すべては、必然に起こり、必要だから起こる。だから、起こることはすべて、いいことなのだろう。悪いことはひとつもない。それがわからないと、自分には悪いことばかり起こると思いこんで、つい、自分の「不運」を嘆いたりする。しかし、その不運を直せるのは、「幸運」でも、沢山のカネでも、高い社会的地位でも、安定した就職でもない。すべて起こっていることは自分にとっていいことだという真実を「知る」ことだけだ。
お前は、愛情深いお父さんを選び、優しいお母さんを選び、そして、平凡でない生活環境をも選んで、予定通り、いろいろな人生経験を重ねてきた。いい夫にも恵まれ、いい子供たちにも恵まれた。しかし、いくらいろいろと経験し、いい夫に恵まれ、いい子供たちに恵まれても、その人生経験の意義がわからないと、本当の意味で幸せになることはないのかもしれない。人間というのは、いつでも高望みするものだ。そして、カネというのは、いつでも足りないものだ。お前が世間一般並に、F男(妹の長男)に新しく
いい就職口が見つかれば安心できるような気がしているのはわかるが、本当に大切なことは、おそらく、そういうことではないだろう。
世の中の大勢の人々が信じている「幸せ」が、本当の幸せとはかぎらない。むしろ、不幸を幸せと勘違いしていることの方が多いのかもしれない。カネが沢山あるから幸せなのではない。全くないのも困るであろうが、カネがないことによって無一物の人間本来の自由のなかから人生の意義を理解しはじめ、幸せの境地に至るということもある。だから、古来、聖賢といわれるような人は、世俗的な、カネとか財産とか名誉などから遠ざかろうとしてきた。私は、あまりカネはないが、住む家もあり、食事に事欠くこともなく、一人暮らしをしながら健康で不自由のない生活を送っている。有り難いことだと思っている。いまの私の状態を、霊界のお父さんやお母さんは、多分、安心して見ていてくれているだろう。
もし、私が惨めなあばら家に住んで、毎日の生活にも窮乏しているようなことがあれば、それは親不孝になる。霊界からはこちらが丸見えだから、お父さんもお母さんも辛い思いをするだろう。富子や潔典も嘆くにちがいない。だから、私は窮乏生活はしないし、貧乏にはならない。しかし、本当は、豊かさとは、本来、カネが多いとか少ないとか、住んでいる家が大きいとか小さいとかの物質的な尺度にはほとんど関係がないから、世間でいう貧富の違いなどは、あまり問題ではない。お父さんやお母さんが安心して喜んでくれるのは、私が物質的にではなく、精神的に豊かであることだろう。その意味では、私は、カネはあまりなくても、いまも豊かだし、死ぬまで豊かであり続けたいと思っている。
お前は、F男がリストラとかで大学講師の定職を失い、再就職できないでいることを嘆いているが、それはわからないわけではない。しかし、就職口がないのと仕事がないのとでは、同じではない。仕事はいくらでもある。私は自分の体力さえ許せば、たとえば、街頭で靴磨きをしたり、駅の公衆便所の掃除係をしたりするのは、少しもいやではないが、世間の人たちはしばしば、収入の多い少ないで、就職を判断する。外面的な体裁だけで、職業のえり好みをする。それは、おそらく、こころが豊かでないからだろう。
カネがあっても、財産を沢山持っていても、それよりも、カネがあればあるほど、財産を持てば持つほど、こころが貧しくなることが多いものだが、そういうことがわからないうちは、つい、世間の常識に流されてしまいがちになる。大きく目を見開いてよく見てみよう。仕事はいくらでもあるはずだ。特に貧しい人を助ける仕事はいくらでもある。また、カネがなくとも、人々にこころの優しさを与えることはいくらでもできる。しかし、人々は何をするにしても代償として出来るだけ沢山のカネを欲しいと思うから、そういう人たちには、仕事がなかなか見つからないだけではないだろうか。
苦しみには意味がある。病気にも意味があるだろう。それを乗り越えることで、苦しみは楽しみに変わり、病気でさえ喜びになる。私が教材で使っていたビデオに、「癌になって有り難う」
というのがある。癌になって喜び、感謝しているのだ。最初はやはり苦しむのだろう。何で自分が癌になったのか、嘆くのであろう。暗い絶望的な顔つきになる。当然、そのままでは治らない。高いカネをつぎ込んで、名医にかかれば安心できるというものでもない。癌になって、苦しんで悩んで泣いて、絶体絶命の心境のなかではじめて、自分の考え方の誤りに気がつくのだ。そして、顔色が一度に明るくなる。人間本来が持っている自然治癒力が、強烈な力を発揮して、治らないはずの癌でも治っていく。もちろん、それでも治らない場合もあるだろう。その時には、おだやかに、まわりのすべての人たちに感謝しながら死んでいく。
敢えて言えば、お前の病気の半分以上は、お前の考え方の未熟さによるといってもいいだろう。半分というのは、まだ少ないかもしれない。おそらく、病気の70パーセント以上は、すべて人間のこころの持ち方、もっといえば、心得違いからくるような気がする。私は決して、いい加減なことをいっているつもりはないし、世間の多くの人々が心得違いをして苦しんでいるなかで、お前だけがよくないと言っているわけでもない。しかし、もう一度、考えてみよう。お前は、お父さん、お母さんを選び、生きていく上でより多くの課題を背負うことを選び、最後には病気をすることも選んできた。それは、悪いことではない。ただし、その意味がわからず、自分を不幸だと思いこんで、嘆いたりしているのでは、それは、悪いことになる。その場合のみ、それは不幸で悪いことになるだろう。
お前ももう70年生きてきた。お前は、この70年でどういうことを学んできたのだろうか。もしお前がまだ、自分で自分のいまの環境を選んできたことの意味がわかっていないとすれば、そうであれば、いまの生活は苦しいだろうと思う。それなら、いまからでも学んでいくべきなのだ。学ぶといっても、べつに難しいことではない。お前は、まず、一人で生きているのではない。お前は、お父さんにいのちを救われたように、まわりの多くの人々に生かされてきた。だから、まず、そのことに感謝することから始めよう。
Mさん(妹の亡夫)は、純粋で誠実な人柄であったが、生前は、この世間でもてはやされることも名を挙げることもなかった。しかし、それは重要ではない。人間的に優れた気質を持ち純粋さと温かさを保ち続けていたことが重要だ。それをお前は感謝して学ぶべきだ。3人の優秀な子供たちにも感謝すべきだ。子供たちはみんな立派に大学教育を終え、これからも、それぞれの経験を積みながら学んでいく。
F男の失業も例外ではない。失業が悪いわけではないだろう。失業からも学ぶことは多い。学ばないことがよくないのだ。そのことを
F男もやがて理解していってくれることを祈っている。
病気になって、なかなかよくならず、そのうえ F男の失業問題を抱え込んだのでは、辛いことであろうと思う。しかし、気持ちを持ちかえて、まず、素直に、いま生かされていることに感謝しよう。それから、家族に、まわりの人間に感謝していこう。病気にも、気づきのきっかけを与えてくれるということで、「有り難う」
を言おう。お前が、純真な幼児のように素直な気持ちで、まわりのすべてに、こころから「有り難う」
と言えるようになったとき、お前の顔は、確実に明るく晴れやかに変わっている。そして、病気は、多分、半分以上は治ってしまっているだろう。
私のホーム・ページの「学びの栞」のなかには、「人はなぜ病気になるのか」や「苦労が多いのはいいことである」など、多くの引用文が含まれている。こういうのを読んでもらえれば、いろいろと考えていくうえでの参考資料として役に立つのではないかと思うが、それができなくても、べつに難しいことではない。「生かされている」
ことの認識から始めて、感謝する生活を続けよう。それは、間違いなく、お前のこころの悩みを癒す「特効薬」になっていくはずだ。それだけを伝えておいて、この手紙を終わることにしたい。先日、お前の銀行口座に少しばかりのカネを振り込んでおいた。これは、決して「特効薬」ではないのだが、なんらかの役に立ててもらえば有り難い。
(2004.02.01)

ガラスの壁 (身辺雑記 02)
今年の正月は、3日に高幡不動尊金剛寺へお詣りに行きました。大勢の人混みの中で不動堂に上がって不動明王像の前に座っていますと、管主の代理のようなお坊さんが出てきて、びっしりと詰めかけていた人々を前にして、つぎのような話をしてくれました。
小さい魚は大きい魚の餌となって食われるものですが、ある実験で、大きな水槽の中に透明なガラスで壁をつくり、二つに仕切った片方に何匹かのナマズを泳がし、他方には小魚を沢山入れておいたのだそうです。ナマズは、しばらくしておなかがすいてきますと、小魚を食べようとして追いかけます。ところが、小魚はガラスの壁に仕切られた向こう側にいますから、小魚を追いかけるたびに、こつんこつんとガラスの壁にぶつかって、小魚を食べることができません。そういう状態が長く続いて、それに慣れてしまいますと、もう小魚は食べられないものと思いこんでしまうのでしょうか、ガラスの壁を取り外して、本当に小魚を食べられるようにしてやっても、ナマズは小魚を食べようとはせず、空腹のまま、ついには餓死してしまうというのです。
もう一つの実験は、ノミについてです。ノミはあの小さい体で、高さ20センチ、距離では35センチも跳べるのだそうです。そのノミの何匹かを高さ10センチくらいのガラスコップに入れ、それにガラスで、ふたをしてしまいます。つまり、ガラスの壁を天井に作ってしまうのです。ノミは逃げだそうとして、飛び跳ねるのですが、高さ10センチのところでガラスの壁に突き当たり、何度試みても、コップの外へは出ることが出来ません。
そして、やがてその状況に慣れてきますと、いつのまにか、20センチ跳べるはずのノミも10センチしか跳ばなくなります。ですから、しばらくしてガラスのふたを取り除いてしまっても、もうノミは、そのガラスのコップからは逃げ出すことは出来なくなるということです。
食べれば食べられるのに食べないで死んでいく。20センチも跳べるのに、跳べないと思いこんで、10センチのコップのなかから出ることができない。このように、勘違いで自分の能力を発揮できないまま、ついに一生を終えてしまうのは、もちろん、実験でのナマズやノミだけではありません。これは、私たち人間の場合にもいえるのではないでしょうか。
大切なことは、勘違いさせられる状況におかれても、それは、ガラスの壁のせいであり、ガラスの壁さえ取り除かれれば、本来の能力は、少しも損なわれることなく発揮できると知ることです。つまり、作られた状況の変化だけでは、本来備わっている能力が失われることはありません。能力を失ってしまうのは、自分自身が、状況の変化の理由がわからないままに、それを肯定し、その作られた「現実」を事実として受け容れてしまったときだけです。
考えてみますと、私たちは、実に多くの「作られた状況」や、「ガラスの壁」に取り囲まれているような気がします。それらが「虚」であり「実」ではないことが理解できないと、私たちもまた、自己の尊厳性を見失い、劣等感にさいなまれて、不幸を甘受することになりかねません。いつのまにか、美しいものでも醜いと思い、喜ぶべきことをも悲しみ、豊かであるのに貧しいと、大きな勘違いをしてしまうこともあるのではないでしょうか。
「ガラスの壁」の実験で示されたような錯覚と無知が、私たちの見る眼も曇らせていることがあるとすれば、私たちの本当の意味での人間らしい幸せな生き方は、なによりもまず、私たちのまわりの、このような多くの「ガラスの壁」を一枚一枚取り外していくことにある、あるいは、それしかない、といってもいいのでしょう。
金剛寺の不動堂で聞いた話は、ナマズとノミの実験のところだけで、そのあとは、ざわざわした人混みの中でよく聞き取れませんでした。しかし、おそらくあのお坊さんも、本来人間は、よかれ悪しかれ、「思った通りになる存在」であることの大切な真実を、ナマズとノミの話で、私たちに伝えようとしていたのかもしれません。
(2004.01.16)

イラク戦争について ―M氏からの手紙― (身辺雑記 01)
2003年から2004年へ・・・・・日本の「戦力なき軍隊」が米・英占領軍の一翼を担って、イラクに展開することになる正に「戦中」(第三次世界大戦)の年・・・・・・・
① 米・ソによる対立と相互依存体制の時代にはよく見えなかったナマの世界がソ連がソ連崩壊後の米・欧による対立と相互依存の体制の時代に入ったことによって、第二次世界大戦後の支配のカラクリがよく見える時代に入りました。
② 「落ち目」のアメリカ帝国の「あせり」と背中合わせの「おごり」が(予想通り)アフガニスタンとイラクの「泥沼」の中で立往生しています。イラクで占領軍に対しておこなわれている攻撃はイラク民衆によるゲリラ戦であって「テロ」ではありません。
③ ゲリラ戦における勝者とは「アリが象を倒す」の図を、政治と軍事の両面で現実のものにする能力を持つ者だということが、まるで「教科書」の通りに私達の茶の間の「テレビ」にまで登場するようになりました。
④ 父ブッシュ氏とベーカー氏らのコンビは、占領軍が他民族の国土を占領し続ける事の困難さを予見するだけの能力を持っていましたから、いわゆる「湾岸戦争」では常に敵の射程圏外で闘い、敵を内懐に入れる愚をさけました。
⑤ 息子ブッシュ氏とチェイニー氏らは「経済面の世界支配力」の著しい低下を「軍事面の世界支配力」の圧倒的優位によって、強引にはねかえそうとしているかに見えますが、そのやり方の無理がかえって、その帝国としての「総合的世界支配力」の衰えを早めるでしょう。
⑥ 世界が今、まさに死なんとしている帝国に対してなすべきことは、この帝国の最大の製造業である軍需産業を安楽死させるための、あらゆる智恵を、注意深く、かつ大胆に全地球的規模で協力しあって動員し、その最後屁による世界の被害を最小限に抑え込む工夫をすることでしょう。
⑦ 無名の民衆がテレビとインターネット、携帯電話などの情報系グッズを持つようになった時代に、世界最大の「大量破壊兵器」所有国の軍隊が、あるかなきかが定かでない程度の世界最小の「大量破壊兵器」の所有国をつかまえて「大量破壊兵器」を持っているからお前はけしからぬとのおかしないいがかりをつけて武力で占領し、さんざん利用したパナマのノリエガ将軍を国際法を無視し逮捕したのと同じく、対イラン戦争ではさんざん利用したイラクのフセイン大統領を逮捕し、そこにかいらい政権を作ろうとしている。そして当然のことながら、その国の、まともな人間たちのゲリラ的抵抗を受けている。この実に分かりやすい‘現実’を前にして、この国のジャーナリスト、軍事評論家、アホな政治家どもが「アメリカが間違っていることは間違いないが、アメリカに恩を売っておいた方が、アメリカに守ってもらえるからナラズ者国家の金正日のミサイルが日本にむけられているのに対抗して、日米ナラズ者同盟を強化して日本の国益を守ることも現実の政治選択としては、いたしかたない正しい選択である」といった風な議論を手をかえ、品をかえて、恥ずかしげもなく繰り返しています。
⑧ 私も、もしかりにブッシュ君の政策を支持する以外に、私の家族、友人、知己の生命と安全を守る手段が何もないのであれば、その選択がいかに、恥多きものであろうとも、いかに男子として屈辱的なものであろうとも、韓信のマタクグリをあえて厭うものではありません。だが、
(1)「ブッシュ君の利益」と「大多数の米国民の利益」とは同じものでしょうか?どうもそうではなさそうです。
(2)米英ブロックという、第二次世界大戦の「勝ち組」に乗り損ねたという、「歴史の教訓」を金科玉条のようにして、「昔のモノサシ」を「未来」に押し当てるタイプの思考停止型の、一知半解のアホどもが現実主義者のようにふるまっているが、この連中には5元連立方程式で応用問題を解く志も能力もないようです。
(3)仏、独、露、中らがそれぞれの短期、中期、長期の「利益」を念頭におきつつ、ゆるやかな「非米」グループを形成しはじめている。「反米」に踏み切るには、今のアメリカは強すぎる。しかし、唯一の超大国アメリカが当時の覇権国イギリスから、徐々にその覇権を奪い取っていったように、「ドル」から「ユーロ」へ徐々に覇権が移行しつつある。賢明なる「非米」グループは、決して「反米」の旗をふることなしに、熟柿作戦をとるでしょう。
(4)その時、アジアはどう動くのか。イスラム圏の国々はどう動くのか。
(5)米英以外の大多数の国や地域がブッシュ君の政権に対しては、「面従腹背」のスタンスを徐々に大胆にとりはじめる可能性があります。
(6)日本がイラクに軍隊を送ることは、逆説的に言えば良いことかもしれません。予見する能力のない政治家や国民にとって、実物教育以外には、その愚見を改める契機はないでしょう。大義なき占領軍が、その国の国民の抵抗を受けるのは自然なことではないでしょうか。
(2004.01.04)
|