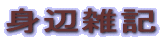
内村鑑三の来世観 (身辺雑記 55)
内村鑑三が著した『キリスト教問答』(講談社文庫、1981)のなかに、来世はあるのかないのかを論じたところがあります。内村は、噛んで含めるように、死後には来世があることを諄々と説くのですが、それに対して、質問者は「しかしながら人類全体が来世の存在を要求する理由は彼らの無学によるのではありませんか。いわゆる未来観念なるものは知識の増進とともに消滅するものではありませんか」と尋ねました。内村はこう答えます。
「日本人にして少しく近世の教育を受けた者は、たいてい貴下の仰せられるようなことを申します。しかしながら私はそうは信じません。来世存在の希望は野蛮人のみの希望ではありません。しかのみならず、この観念もまた他の観念と同じく、知識の進歩と同時に進歩するものであります」
これに対して、質問者はさらに次のように反論しました。「しかし、それは何人にも迷信の元素が多少のこっているからではありませんか。迷信の元素がまったく知識の光明によって取り去られた後に、初めて来世観を要求するの必要がなくなるのではありませんか」
内村はちょっと皮肉交じりに答えます。「ずいぶん深いご観察であります。来世の希望を堅くいだいて死んだニュートンも、ファラデーも、ワーズワースも、グラッドストンも、彼らの心の中に存する迷信を脱却しえずして、来世を希望したとのご疑問であります。そうしてかかる希望をいだかれない貴下ご自身は、新知識の光明によって、かかる「迷信」を全然脱却されたのだと申さるるのでありましょう。それはずいぶん大胆なるご断定であります」
知識や教養を身につけていけば、来世があるなどいう「迷信」などには囚われなくなるものだと考えがちな一般の根強い傾向は、いまもほとんど変っていないといえるでしょう。ここに名をあげられた4名は、いうまでもなく、いづれも深い教養をもった最高の知識人ですが、このうち、グラッドストンはヴィクトリア女王の下に、4回まで大英帝国の総理大臣を務めた大政治家でした。そのグラッドストンにとっても、来世の存在は、「インド帝国を保存しアフリカ大陸を経営するにまさるの大問題」であった、と内村は述べています。しかし、別にグラッドストンでなくとも、いまの私たちにとっても、「来世の存在」がもつ重大な意味に気がつけば、おそらく生涯最大の大問題というふうに考えるようになるのかもしれません。
来世の存在を固く信じて死んでいったグラッドストンの臨終のことばは、Our
Father (われらの父よ)であったそうです。大政治家として、60余年間、世界を震動せしめたグラッドストンのくちびるは、「天にいますわれらの父よ」と神の名を呼んで閉ざされました。「じつに偉大ではありませんか」と、内村は惜しみなく賞賛のことばを並べています。そして、そのあとで、内村は、自分自身の来世存在に対する信仰についての思い出を、次のように、続けています。
* * * * *
私はグラツドストンの死状(しにざま)を聞いて、私の先師、故シーリー先生のことを思い出さざるを得ません。
ご承知かも知れませんが、彼は十余年間、米国アマスト大学の総長でありまして、日本人にして彼の薫陶にあずかった者は私のほかにも幾人もあります。私は目にグラッドストンを見たことはありませんが、しかしシーリー先生に接して、グラツドストンとはこういう質の人であろうと、たびたび思いました。学者で、実務家で、信仰家で、その円満なること、とうてい日本などにおいては見ることのできない人物であります。
私は一夜、少しく先生に求むるところがありまして、突然先生の書斎に侵入いたしました。先生はその時あたかもある書を読んでおられましたが、いつになく喜んで私を迎えられ、その読みつつありし書を卓上に置かれ、金ぶちの眼鏡を取りはずして、そのちりを払われ、静かに私の言わんと欲するところを聞かれ、後は話頭を現世の事より神と来世の事とに転ぜられ、書斎の壁の上に掛けてありし一老婦人の絵画を指さされ、小児のような余念なき口調にて言われました。
「内村君よ、あれは私の妻であります。彼女は二年前に私どもを逝りまして、今は天国にありて私どもを待っております」と。
言い終わって先生の温顔を仰ぎ見ますれば、眼鏡の中なる先生の大なる眼球はいっぱいに涙をもってひたされたのを見ました。私はじつにその時ほど明白に来世の実在を証明されたことはありません。先生の大知識をもってして、かくもありありと、墓のかなたにうるわしき国のあるのを認められしのを見まして、私は自己の小なる頭脳をもって、たびたびその存在について疑いをいだいたことを深く心に恥じました。
私は今日まで幾度となく来世存在の信仰をあざける人に出会いました。しかしながら、その人はみな人物からいっても、学識からいっても、シーリー先生に遠く及ばない人たちでありました。先生の言われしこととて、かならずしも一から十まで真理であるとはいえません。しかしながら、かかる人物がかかる確信をいだいておったことを思いまして、私の来世存在に関する信仰はひじょうに強められます。
* * * * *
これは、内村鑑三の「来世存在」信仰について述べた一部ですが、ひるがえって、いまの私たちは、来世の存在をどのように受け止めているでしょうか。本当に有難いことに、私たちは、素直に霊的真理に心を向けることさえすれば、熱心に、一生懸命に、何の代償も求めず、深く広い人類愛から私たちに語りかけてくれている霊界の高位霊からの「来世存在」の教えに、いくらでも接することができます。たとえば、シルバー・バーチの膨大な量の霊訓のなかのつぎの一言だけをとりあげてみても、そこには、私たちにとっては何よりも重大な「生涯最大の問題」が、極めて具体的に、かつ明確に、証言されているといえるのではないでしょうか。
・・・・・墓の向うにも生活があるのです。あなた方が “死んだ” と思っている人たちは今もずっと生き続けているのです。しかも、地上へ戻ってくることもできるのです。げんに戻ってきているのです。しかし、それだけで終わってはいけません。死後にも生活があるということはどういうことを意味するのか。どういう具合に生き続けるのか。その死後の生活は地上生活によってどういう影響を受けるのか。二つの世界の間にはいかなる因果関係があるのか。死の関門を通過したあと、どういう体験をしているのか。地上時代に口にしたり行ったり心に思ったりしたことが役に立っているのか、それとも障害となっているのか。こうしたことを知らなくてはいけません。
また、死後、地上に伝えるべき教訓としていかなることを学んでいるのか。物的所有物のすベてを残していったあとに一体なにが残っているのか。死後の存続という事実は宗教に、科学に、政治に、経済に、芸術に、国際関係に、はては人種差別問題にいかなる影響を及ぼすのか、といったことも考えなくてはいけません。そうなのです。そうした分野のすべてに影響を及ぼすことなのです。なぜなら、新しい知識は、永いあいだ人類を悩ませてきた古い問題に新たな照明を当ててくれるからです。(『霊訓(7)』pp.27-28)
(2007年12月1日)

長く生き過ぎた人びとの哀しみ (身辺雑記 54)
晩年から死後にかけて「戦中派天才老人」などと呼ばれた作家の山田風太郎は、1922年1月4日に兵庫県で生まれた。この山田風太郎には、「人間臨終図巻(上・下)」などの多数の著作のほかに、かつて朝日新聞紙上に書き続けた「あと千回の晩飯」というエッセイがある。1994年11月10日には、このエッセイのなかで彼は、「生き過ぎて」と題して、つぎのように書いた。
《長生きは一応おめでたいことになっているが、モノには限度ということがある。
古今亭志ん生は八十一のとき、こんなことをいった。
「やんなっちゃうね、どうしようかと思っちゃう。ほんとに。ここまでくると、どこまで生きりゃいいんだって、いいたくなっちゃう。ねえ、つまんないもう。いつもそう、なんかあると、ああ面倒くせえ、はやく参っちめいてえなって」
志ん生は八十三歳で死んだ。
志賀直哉はまだそれほど衰えないときに「不老長寿という。不老で長寿ならいいが、老醜をさらしての長生きはいやだね」といった。
八十四のときこんなことをいった。
「ここがわるい、ここが痛むというのでなしに、衰えて― このごろしみじみ老苦というものを味わわされているんだ」
と嘆き、テレビドラマを指さして、見ていても筋なんかさっぱりわからない。
「老いぼれて、気力が全くなくなって― そればかりでなく、アタマがおかしい、ヘンなんだよ」
と、いった。
志賀直哉はそれから八十八歳まで生きた。
武者小路実篤は八十九のときこんな文章を書いた。
「人間にはいろいろな人がいる。その内には実にいい人がいる。立派に生きた人、立派に生きられない人もいた。しかし人間には立派に生きた人もいるが、中々生きられない人もいた。人間は皆、立派に生きられるだけ生きたいものと思う。この世には立派に生きた人、立派に生きられなかった人がいる。皆立派に生きてもらいたい。皆立派に生きて、この世に立派に生きられる人は、立派に生きられるだけ生きてもらいたく思う。皆人間らしく立派に生きてもらいたい」
一回転ごとに針がもとにもどるレコードのようなもので、果てしがない。
こういう状態で、武者小路実篤は九十歳で死んだ。》
1899年生まれの川端康成は、日本人として初めてのノーベル文学賞を1968年に受賞したが、その時彼は69歳であった。年齢的には「生き過ぎて」からはほど遠い若さである。しかし、その頃すでに、彼は死への逃避欲のようなものを強く持っていたのかもしれない。瀬戸内寂聴にであったか、「飛行機に乗るたびに落ちてくれないかといつも思うよ」などと語ったことが伝えられている。その川端康成は、1972年にガス自殺した。73歳であった。
73歳といえば、山田風太郎がこのエッセイを書いたのが、73歳になろうとする直前のことである。彼は5歳の時に父を亡くし、母も彼が14歳の時に肺炎で亡くなっている。両親を早くして失った寂しさのあまり、中学時代には三度も停学処分を受けるような荒れた生活が続いた。このような彼の生い立ちが、彼の死生観に大きく影響したであろうことは想像に難くない。
山田風太郎は、このエッセイを「あと千回の晩飯」としたが、その彼は、2001年7月28日に79歳で死んだ。生前に、自ら定めた戒名は「風々院風々風々居士」である。命日の7月28日は、奇しくも師の江戸川乱歩の命日でもあった。八王子市にある川上霊園の墓地には、「風の墓」とのみ刻まれた墓碑が建っているという。(文中敬称略)
(2007年11月1日)

開かれている極楽浄土への道 (身辺雑記 53)
「佛説阿弥陀経」というのは、お釈迦様が大勢の弟子たちを前にして、西の方はるか彼方に、極楽という世界があることを教えているお経です。漢語で書かれたものを日本語読みしているわけですから分かりにくいのですが、浄土真宗のお葬式の席などで、このお経が唱えられているのを、何度も耳にされている方も多いのではないでしょうか。
このお経の中では、「その極楽に住む者たちには、体の苦しみも心の悩みもなく、ただ幸せがあるだけだ。その世界には、七重の石垣、七重の並木があり、それらは、金、銀、水晶等の宝石で飾られている。また、宝石から出来ている池があり、池の底には一面の金の砂が敷き詰められている・・・・・」などと、光り輝く壮麗な極楽の描写が延々と続きます。
そして、その後で、人は誰でも、阿弥陀仏の名号を唱えることによってその極楽に往生できる。そしてそのことは、東西南北上下の六法世界の数多くの諸仏によっても証言されているのだ、とも述べられています。さらには、「これは嘘ではない、本当のことなのだ」と何度もくり返して付け加えられてもいるのです。これを、私たちは、どう受け留めていけばいいのでしょうか。
もし本当に、極楽浄土がそんなに素晴らしいところであるのなら、死ぬということは悲しみではなく大きな喜びになるはずです。それなら、なぜ私たちは、早く死んで、その極楽浄土へ行きたいとは思えないのでしょうか。
たまたま、『歎異抄』第九段では、親鸞の弟子の唯円が、同じような疑問をもっていたことが記されています。いくら極楽浄土がすばらしいところであると聞かされても、早くそこへ行きたいとは思えないのは何故でしょうか、と親鸞に訊いたのです。
それに対して親鸞は答えました。本当は手の舞い足のふむところも知らないほど喜ばなければならないのに、そうさせないのは煩悩のせいである。悩みや苦しみの多いこの世を去るのはいやがって、平安で幸せな極楽浄土を恋しいと思えないのは、よくよく煩悩が強いからに違いない、と。
この親鸞の答え方はよくわかります。五濁悪世の煩悩の世界にどっぷりと浸かっていても、それも「住めば都」ということになるのでしょう。しかも、一般には、死ぬということが最大の不幸であると固く信じ込まれていますから、このような極楽浄土の素晴らしさを聞いても、やはり、俄かには信じがたいと思われるのも無理ではないのかもしれません。
しかし、いまでは、極楽浄土の壮麗さを裏付けるすぐれた真理の書も、その気にさえなれば容易に手に入りますから、死後の世界の実状を理解するのも、そんなに難しいことではなくなりました。そのうちの一つが、『シルバー・バーチの霊訓』(潮文社刊十二巻)です。そこでは、例えばその第四巻に、次のように述べられているところがあります。
《あなたがたはまだ霊の世界のよろこびを知りません。肉体の牢獄から解放され、痛みも苦しみもない、行きたいと思えばどこへでも行ける、考えたことがすぐに形をもって眼前に現われる、追求したいことにいくらでも専念できる、お金の心配がない、こうした世界は地上の生活の中には譬えるものが見当たらないのです。その楽しさは、あなたがたにはわかっていただけません。
肉体に閉じ込められた者には美しさの本当の姿を見ることが出来ません。霊の世界の光、色、景色、木々、小鳥、小川、渓流、山、花、こうしたものがいかに美しいか、あなたがたはご存知ない。そして、なお、死を恐れる・・・・・》
これは、「仏説阿弥陀経」に描かれた極楽浄土の姿そのものですが、霊界から見ると、それでも「なお死を恐れる」私たちの無明ぶりが歯がゆくてならないようです。
そのような私たちに、シルバー・バーチは、人間の本質は実は霊であって、「人間は死んではじめて真に生きることになるのです」と、つぎのようにも諭しています。
《真の自我である霊は滅びません。霊は永遠です。死ぬということはありえないのです。
死は霊の第二の誕生です。第一の誕生は地上へ生をうけて肉体を通して表現しはじめた時です。第二の誕生はその肉体に別れを告げて霊界へおもむき、無限の進化へ向けての永遠の道を途切れることなく歩み始めた時です。あなたは死のうにも死ねないのです。生命に死はないのです・・・・・》
しかしそれでも、このように聞かされても、私たちが自分のいのちについて、なかなか安心立命の境地に達することができないとすれば、それはやはり、親鸞が言うように、五濁悪世での私たちの「よくよく強い煩悩」のせいであるということになるのかもしれません。
(2007年10月1日)

宿命のノース・カロライナへの道 (身辺雑記 52)
私が6年前に書いた『アメリカ・光と影の旅』の第5章「懐かしく哀しいアメリカ」のなかに、カリフォルニア州モントレーにあるアメリカ合衆国海軍外国語学校にふれたくだりがある。
アメリカ合衆国海軍外国語学校というのは、語学の才能のあるアメリカ軍将校などを情報要員として全米から集め、世界各国語の特訓をしているところである。日本文学者のドナルド・キーン博士も、かつてはここの日本語科の学生であった。日本語のように難しいと思われている言語でも、ここでは、二年間で、読み・書き・話す・聞く、の四技能をほぼ完璧にマスターさせることで知られている。私はむかし、アメリカのアリゾナ州に住んでいたころ、その外国語学校の講師公募に応募したことがあった。そのいきさつを、私はこの本の中でつぎのように書いている。
一九八二年の秋、このモントレーの海軍外国語学校から、私がいたアリゾナ大学言語学部に、日本語講師公募の書類が送られてきた。私はここの外国語教育には関心があった。軍隊は嫌いだが、この学校独特の外国語教授法のノウハウだけは知りたいと思っていた。
日本の「外国語としての英語」教育では、従来からよく、アメリカやヨーロッパでの語学教育が参考にされることがある。しかし、印欧系言語は互いに親戚関係にあって発音や構文も似通っているから、印欧系のなかでの外国語教育は、日本の英語教育にはあまり参考にならない。アルタイ系ともいわれたりするが世界で孤立している日本語と印欧系の英語は、互いに極めて異質である。だから、日本語から入る英語教育で参考になるとすれば、英語から入る日本語教育である。そのような観点から、私はいくつか論文も書いている。
私は応募することにした。フルブライト客員教授としてのアリゾナ大学での最初の一年の任期が終われば、半年くらいなら海軍外国語学校で、教壇に立ってもいいと考えていた。「フルブライト」の肩書きは、アメリカの大学でもそれなりのプレスティージがある。応募すれば、割合簡単に決まるのではないかと思ったりもした。
ところが、簡単ではなかった。フルブライトの肩書きには関係なく、経歴や業績、語学教育経験などのこまかい書類審査が続いたあと、日本語と英語の論文をそれぞれ送るようにといってきた。それをクリアすると、今度は、日本語と英語のスピーキングのテストである。「いま、あなたが居る自分の部屋の様子を、初めに日本語で、次には英語でそれぞれ詳しく、五分間ずつかけて説明して下さい」などというものであった。それをテープに吹き込んで送るのである。
三段階の審査には、いつもかなりの時間がかかっているようであった。やがて、日本語の「A級インストラクター」の認定証書とともに、任用手続きにはしばらく時間がかかるという手紙が届いた。そのあとはなしのつぶてである。その状態でかなり長く、何週間も待たされているうちに、別に書類を出しておいたノース・カロライナ州立大学への赴任が決まってしまった。
一九八三年七月一日の朝、私は、ノース・カロライナ州立大学への編入学生となった娘を伴い、車にいっぱいの荷物を積み込んで、アリゾナを離れた。ツーソンから三千五百キロ離れたノース・カロライナのローリーに向かって出発したのである・・・・・・・
このモントレーの海軍外国語学校で、あの時、任用手続きになぜあれほど時間がかかってしまったのか、よくわからない。はじめはurgent need(緊急に必要)などと言っていたのに不思議であった。後日、海軍外国語学校の日本語科で教えている講師に、直接手紙を出して聞いてみたことがあったが、どうやら、予定されていた空席が生じなかったのが原因であったらしい。講師陣と事務局との意志の疎通も欠けていたようである。しかし、いま考えてみると、モントレーへの道は始めから私には閉ざされていた。私は、行くべくしてノース・カロライナへ行ったのである。
当時のアメリカは、バブルで沸き返っていた日本とは違って大変な不況であった。大学の予算なども軒並みに大幅な削減を余儀なくされていた。だから、ノース・カロライナ州立大学での教職もすんなり決まったわけではない。期待していた海軍外国語学校からの任用通知は来ず、ノース・カロライナ州立大学からの通知も予想を超えて遅れていた段階で、私はこれ以上は待てないと判断した。日本の在籍大学に対する海外出張期間延長の申請期限が迫っていたのである。私は帰国を決意して、帰国のための手続き書類をフルブライト委員会へ宛てて送った。
しかし、その書類をアパートの近くのポストに投函して帰宅すると、そのちょっとの留守の間に、ノース・カロライナ州立大学からの招聘状が速達で届いていた。私は呆然とした。しばらく考え込んだあと、結局、郵便局へ出向いて、投函したフルブライト委員会宛の書類を取り戻した。これも、いま考えると、私が小さな自分の意思で、ノース・カロライナへの道を自ら閉ざすことは許されなかったということであろうか。
もともと私は、ノース・カロライナへ行くようなことは、念頭にはなかった。首都のローリーについてもよく知らなかった。その年の春に、たまたまローリーでフルブライト研究員の年次大会があって、私もアリゾナから参加したのがローリーとノース・カロライナ州立大学へ足を踏み入れた最初である。3日間の滞在を終えて、空路アリゾナのツーソンへ帰っていったときにも、数か月後にこのローリーに再びやってきて住むことになろうとは、まったく思ってもいなかった。それが、その年の夏には、私はローリーへ転居し、妻の富子と長男の潔典に渡米を促していたのである。
[一九八三年八月一日の日記]
朝九時(日本時間午後一〇時)過ぎに潔典に電話する。意外にも五日の航空券がまだとれていないという。三日になればわかるということで、もう一度、三日に電話することにしたが、ここでもまた、最後のきわどいところで待たされることになった。
すべてが裏目に出ている感じだ。あまり無理をしてはいけないのかもしれない・・・・・
急に予定をたてたので、どこの航空会社の航空券もなかなかとれず、やっとソウル経由で、しかも空席待ちの大韓航空のチケットで富子と潔典がニューヨークに着いたのは八月五日の午後九時過ぎであった。それからしばらくノース・カロライナ州ローリーの自宅で親子四人水入らずの生活を過ごし、再び、富子と潔典がこのニューヨークから日本への帰国の途についたのが、八月三〇日の夜である。しかし、二人を乗せた大韓航空007便は、遂に日本へ着くことはなかった。
この富子と潔典が乗った大韓航空機は、アンカレッジを経由した後、ソウルへ向かったのだが、ロサンゼルス発でソウル行きの大韓航空機も同じようにアンカレッジを経由して、15分後に、007便の後を追うようにして飛んでいる。しかし、007便は、大きく航路を逸脱してソ連領内を侵犯して撃墜され、ロサンゼルス発の大韓航空機015便は、正規のルートを飛んで、無事にソウルに着陸した。
潔典は、はじめから九月一日には日本へ帰る予定をたてていたようだから、もし仮に、私がノース・カロライナ州立大学へ行かず、カリフォルニアのモントレーの海軍外国語学校へ行っていたとすれば、そしてまた仮に、往復の航空機が同じように大韓航空機であったとすれば、富子と潔典は、ニューヨーク発の007便の代わりに、ロサンゼルス発の015便に乗っていた可能性もあり得たのかもしれない。
しかし、いまではわかるような気がするのだが、おそらく、そういう風には天から定められてはいなかった。私は悲劇に巻き込まれなければならなかったのであろう。ノース・カロライナへの道へ進んだことは、決して単なる偶然ではなく、私の宿命であったに違いない。すでにそのことを潔典は、潜在意識では間違いなく感知していたように思われる。それを暗示するような潔典の常とは異なる気配があり、これから起こるべきことを示唆するようないくつものことばがあった。鈍感であった私がその時には気がつかなかっただけである。
あれから二十四年経ったいまも、私は、そのことを考えるたびに、粛然として襟を正したい気持ちに駆られる。
(2007年8月1日)

山村幸夫さんの奇跡の足跡 (身辺雑記 51)
山村幸夫さんには2冊の著書がある。『神からのギフト』と『与え尽くしの愛』である。いずれも、山村幸夫「神からのギフト」出版会から発行された非売品で、いわば私家版である。しかし、「知る人ぞ知る」で、この2冊の本は、スピリチュアリズムの世界では、『シルバー・バーチの霊訓』の実践版として読む人々に深い感動と希望を与え、真理のことばが持つ清冽な光彩を放ち続けている。
山村幸夫さんとはどういう人か。あるいは、どういう人であったか。これらの著書に記載されたプロフィールによれば、山村さんは1962年に宮崎県で生まれた。東海大学卒業後、1987年に渡米して1990年より心霊治療を中心とした霊的活動を始めている。アメリカのロサンゼルスを拠点にして、アメリカ各地のほか、諸外国、日本などでも心霊治療の奉仕活動を精力的に行い、多くの人々に霊的な真理を広めていった。その山村さんは、2001年の11月頃から体調を崩し、半年間の闘病生活の末、2002年5月28日、ロサンゼルスの治療院としていた自室で亡くなった。39歳の若さであった。
これは痛恨の極みであるが、山村さんが何度も来日し、東京や横浜のほか日本各地で無料の公開治療や、勉強会をしていたのに私はそのことを知らなかった。私は、だから、生前の山村さんにはお会いしたこともない。ただ、いまは、上記の2冊の著書を通じて、山村さんが文字通り輝かしい「与え尽くしの愛」を実践して流星のように宇宙に消えていったその生涯を知り、深い敬意だけではなく、限りないなつかしさと親しみの気持ちをも抑えることができないでいる。
私は、この4月で77歳になっているから、山村さんよりも年齢だけは30年以上も年上であるが、山村幸夫さんを私の慕わしい先生の一人と思っている。ここでも、こころをこめて「山村先生」と呼びたいところであるが、そうしないでいるのは、山村さんが「先生」と呼ばれることを好まないことを知っているからである。患者たちからも絶大な信頼と尊敬を受けていたようだが、けっして偉ぶることもなく、誰に対してもひたすらに奉仕に徹していた。訪れてくる患者には「どうなさいました?」と優しく問いかけ、「ニコッと満面に人懐っこい笑みをたたえ」ながら、その眼差しには、「大丈夫ですよ」という感じの深い慈愛があふれ出ていた、とこの本の中でもその人となりが紹介されている。
心霊治療家としての山村さんは、末期がんの患者などを含めて、近代医学で見放された数々の難病患者を何百人、何千人と治していく奇跡を見せてきた。しかし、その治療費は一銭も取らなかった。治療は誰に対しても常に無料であった。この事実の持つ重い意味を私たちはけっして看過してはならないであろう。治療費を無料にしながら、それでいてあれだけ広範囲な奉仕活動ができたのは、すべて、患者たちからの感謝の気持ちがこもった善意の寄付による。真理を知り無償の愛の行為に献身する者には、霊界からの巨大な霊力が援護してくれることを身をもって証明して見せてくれたのが、山村幸夫さんであった。私は、『神からのギフト』と『与え尽くしの愛』に示された山村さんの奇跡の足跡を辿りながら、いまさらの如く、宇宙の摂理と霊力の偉大さをまざまざと見せ付けられる思いがして、深く畏敬の念に打たれるのである。
この2冊の本の出版は、山村さんの奇跡の足跡をひろく知ってもらうために、「神からのギフト」出版会を組織した黒木昭征氏の献身と努力に負っている。通常なら、これだけの大部の印刷・製本を内税・送料込みで1500円というような廉価にして希望者に配布するのは、採算的にみて困難なはずであるが、それを黒木氏が可能にしているのも単なる偶然ではないのかもしれない。真理は真理であるがゆえに、必然的に霊力を得て広がっていくものだからである。私は、先日、何部かをプレゼント用に注文した折に黒木氏にも手紙を出して、山村さんへの橋渡しをしてくださっていることに対する丁重なお礼を申しあげた。
この黒木氏の、こころを打つことばが『与え尽くしの愛』の「編者あとがき」にもある。私はそのことばを辿りなおしていると、どういうわけか、いまも涙がひとりでにあふれ出てくる。つぎのようなことばである。
・・・・・最後に、山村幸夫さんのご両親へ心からの哀悼の意を表します。そして、彼の偉大なる魂を讃えて頂きたく、この『与え尽くしの愛』を謹んで捧げます。
霊的な活動にはまったく縁のない親御さんから眺めたら、先立って行った親不孝な息子と感じるかも知れませんが、あなた様方の幸夫さんは、この本の中のように、神から授かった霊力と与え尽くしの愛で、悩める多くの人々を癒されました。ヒーラーとしての生涯を全うされました。その素晴らしい奮闘の人生を褒めて頂きたく存じます・・・・・。
(2007年6月1日)
*この『神からのギフト』と『与え尽くしの愛』は直接下記へ申し込めば入手できます。
山村幸夫「神からのギフト」出版会
〒223-0058 横浜市港北区新吉田東7-24-8
TEL / FAX 045-546-1032

生き神の住むクマリの館 (身辺雑記50)

「クマリの館」 この2階の中央の窓
が開かれて、あどけなさの残る少
女の生き神が顔を見せた。
筆者撮影 (2007.01.18)
ネパールのカトマンドゥの見所の一つがダルバール広場である。ダルバールというのはネパール語で「宮廷」の意味だそうだが、旧王国時代には、ここは王宮前の広場としてカトマンドゥ王国の中心部であった。広場の中央には17世紀末に建てられたシバ寺院がひときわ高く聳え立ち、その周辺にはシバ・バールヴァティー寺院やカスタマンダフという古色蒼然とした寺院なども建ち並んで、辺り一体が中世の雰囲気を漂わせている。このダルバール広場の南側に、生き神が住んでいるという「クマリの館」がある。
生き神「クマリ」とは、実はあどけない少女なのだが、ドウルガーや昔のネパール王国の守護神であるタレジュ女神の化身として、ヒンドゥー教徒が9割を占めるという国民全体から広く崇められている存在である。今年1月のヒマラヤ旅行でカトマンドゥを訪れた時に、この生き神を見ることが出来るかもしれないというので、ツアーの仲間たちと、クマリの館を訪れてみた。
門をくぐって館に入ると、古いレンガ造りの3階建てが小さな中庭を囲んでコの字形に建てられている。中庭も百坪くらいであろうか、そんなに広くはない。2階、3階の窓枠には見事な木彫りが施されていて、なにか由緒ありげな雰囲気である。生き神クマリは、この2階の窓から顔を見せるということであった。ヨーロッパからの観光客らしい一団と一緒になって、4時の定時に窓が開かれるのではないかと待っていたが、その時は、結局、クマリは顔を見せなかった。
クマリは、家柄の正しい幼女たちの中から選ばれるのだそうだが、その選考には、容姿や品性、知能だけではなく、神にふさわしい聖性があるかどうかが大切な基準になるという。選ばれたあとは、両親の元から引き離され、付き添いの老女や僧侶から神としての振舞い方を教え込まれる。それが、本人が初潮を迎えるまで続けられるのである。毎年9月に行われるインドラ・ジャトラの大祭には、クマリは3日間の山車巡行の主役となり、前方を見つめたまま身動き一つしない姿勢で人びとの前に現れる。国王でさえひざまずかせるクマリだが、年若い少女には神としての振る舞いを維持し続けるのもなかなか大変のように思われる。
そのクマリを見ることが出来ずに、一旦はダルバール広場に出てしばらく自由時間となったのだが、それが終わって帰る途中、現地ガイドのリルさんは、もう一度、クマリの館へ行ってみようという。私たちがクマリを見ることが出来なかったことをすまなく思っていたらしい。今度は、中に入ったのは私たちのツアーの17名だけであった。中庭に立ったリルさんは、2階に向かってネパール語でなにか大声で呼びかけ始めた。やがて窓の一つが開き、長いひげの老人が顔を出した。クマリの付き添いの一人であろう。その老人にリルさんは、一生懸命に訴え続けた。
中庭には、「クマリの写真撮影は厳禁する」と書かれた掲示があって、その側には、クマリに捧げる基金箱なども置かれている。どうやら、リルさんは、みんなで寄付をするから、クマリに出て来てもらいたい、というようなことを言っていたらしい。やがて、2階の中央の窓が開いて、ついにクマリが顔を見せた。少し厚化粧の感じで、唇は赤く、頭には冠をつけている。まだあどけなさの残るふっくらした顔つきの少女である。私たちは、ネパール風にうやうやしく礼拝して、一瞬の対面が終わると、それぞれが何がしかのお金を基金箱へ入れた。
(2007.04.05)

白く輝く神々の座 ヒマラヤ山脈 (身辺雑記49)

南西方向から見たエベレスト(8,850メートル)
小型機のコックピットから筆者撮影 [07.1.18]
北米大陸のロッキー山脈やヨーロッパのアルプス山脈はいろいろな地点から何度か見てきました。しかし、ヒマラヤ山脈はまだ見たことがありません。そのなかの世界最高峰・エベレストはアメリカのボストン科学博物館の研究チームが1999年に行った測定により、いまは、8850メートルということになっていますが、私には、現地で一度その威容をこの目で見てみたいという願望がくすぶっていました。70歳代も後半に入るとだんだんと海外旅行も億劫になってきます。それでも、心残りのないようにと、一月の中旬、思い切ってH
交通社のツアーに参加することにしました。
成田で一緒になったグループは添乗員を除いて17名でした。男性9名で女性は8名です。グループのうちの最高齢は男性のSさんで、82歳。80歳まで現役で歯科医をしていたそうですが、若い時には、陸軍士官学校で鍛えられたからということで、「お陰さまで至って健康です」と言っていました。やはり、一度、ヒマラヤを見たいという願望を持っていたようです。その願いを知っていた娘さん夫婦が、優しい顔つきの20歳くらいの長女と3人で、おじいちゃんを招待して同行することになったのだそうです。「三世代の家族で旅行できて幸せですね」と、私は、私自身の1歳8ヶ月になったばかりの双子の孫娘を思い出しながら、Sさんに語りかけたりしていました。
成田を午後5時過ぎに離陸したタイ航空機は、約7時間でタイのバンコクに着きました。時差は2時間で、タイ時間の午後10時過ぎです。そこでホテルに一泊することになっていました。ホテルへのバスのなかで、現地ガイドが、「皆さん、バンコクは何度目ですか?」と聞き始めました。「初めての人は手を挙げてみてください?」と言われても、誰も手を挙げません。「2度目の人は?」でも、誰もいません。3度目から手が挙がり始めて、どうやら、大半の人が4回、5回と来ているようです。あとでわかったのですが、このグループの人たちは、ほとんどが海外旅行の「ベテラン」で、多い人で50数回100カ国以上、少ない人でも、10数回の海外旅行を経験しているようでした。
翌朝、10時45分バンコク発のタイ航空機でネパールのカトマンズへ向かいました。飛行時間は3時間半くらいです。ちょっとややこしいのは、時差が1時間15分で、修正が1時間単位の世界時計では、自動修正はできません。こういう時差の設定もあることを私は初めて知りました。カトマンズ空港に着いたのは、現地時間で午後1時ごろです。入国手続きが終わってから、一時間半ほど、旧王宮のあるダルバール広場や二、三の寺院をまわったあと、悪路をバスに揺られて東へ約30キロのナガルコットへ向かいました。ナガルコットは、標高約2100メートルの丘にあって、ヒマラヤの展望台といわれているところです。泊まるところもホテルというより山小屋ふうで、道が狭くて、バスも近くまで行くことができません。バスを降りてから10分ほど歩いて夕闇が迫る「山小屋」にたどり着きました。
このナガルコットの丘の上には、ホテルが30軒ほどありますが、みんな、ヒマラヤを見るために建てられたような造りで、ホテルに居ながらにして、壮大な山脈の景観が楽しめることになっています。東の方角にはエベレスト、正面には、ランタン・ジュガール、西には、マナスルからアンナプルナまで、はっきり見通せるはずでした。朝早く、日の出と共に、刻々と色を変え、輝きを増していくというヒマラヤの美しさを堪能するために、私たちも、翌朝は、6時に起きて、ホテルの屋上で日の出を待ったのです。
しかし、期待は裏切られました。屋上へ上がったとたん、これは駄目だと思いました。濃い霧が一面に立ち込めているのです。何も見えませんでした。「昨日はよく見えていたのに」とホテルの従業員も残念そうに言います。大体、ネパールの冬(12月から2月)は乾季で、ヒマラヤを見るのにはこの時期が最もいいといわれているのですが、やはり運が悪かったのかもしれません。諦めて、私たちはしばらく霧の中を付近を散策したあと、再びバスでカトマンズへ戻り、そこから、小さなプロペラ機で、ポカラへ飛びました。湖とヒマラヤの展望で知られるポカラは、カトマンズから西へ200キロの場所にあります。飛行中に雲の上から、ほんのひと時ですが、初めて白く輝くマナスルの山容を、遠望することが出来ました。
ポカラについて、簡易舗装の、それもかなり傷んだままの悪路を20分ほど走り、ノウダラの尾根と呼ばれるヒマラヤの展望台のような場所へ行きました。そこからは、マナスルやアンナプルナの荘厳な山並みが目の前に広がっているという触れ込みです。しかし、そこでも期待は裏切られました。霧が深く立ち込めていて何も見えません。尾根の上では、チベット人女性たちが、ヒマラヤの写真などのほか、手製の首飾りや数珠や革の財布などのみやげ物をしつこく売り込みにきます。片言の日本語を話し、なかには、かなり上手に英語を話す人もいます。「今日はヒマラヤは見えないけれど、明日の朝はホテルからでもきっとよく見える。私たちには分かるのだ」というようなことを言っていました。地元の人が言っているのだから、その通りかもしれない、と私はかすかに翌日に期待をつないでいました。
翌朝は、早朝の5時半にホテルを出て、チョーレパタンへ向かいました。フェワ湖南側の丘陵で、標高1113メートルのその頂上には、“World
Peace Pagoda”の名で知られる日本山妙法寺があります。その広い境内からのヒマラヤの景観が絶景だというのです。バスで約30分走り、道が狭くなってからはバスを降りて、懐中電灯で足元を照らしながら登り道を一時間近くも歩き続け、やっとその妙法寺にたどり着きました。そこで日の出を待ち、朝日に輝くヒマラヤの山々の威容を見ようとしていたのです。しかし、結局その日も駄目でした。ほとんど何も見えません。辛うじて、マチャプチャレ(6993メートル)とアンナプルナⅢ(7555メートル)のかすかな稜線が目に入ったくらいです。不運続きで、さすがに帰りの足取りも重くなりました。
その日は、ポカラの町の観光をしたあと、フェア湖でボートに乗ったりもしたのですが、湖に影を映す荘厳なヒマラヤの山並みはついに見ることが出来ませんでした。ポカラの同じホテルに連泊し、2日目も、早朝に起きだして、今度はもう一つのヒマラヤ観光の名所、標高1592メートルのサランコットの丘へ向かいました。交通社から渡された日程表には、「サランコット・ハイキング、霊峰マチャプチャレやアンナプルナの感動的な絶景をお楽しみください」などと書かれています。しかし、この最後の「感動的な絶景を楽しむ」チャンスも、霧で駄目になりました。私たちの今度のツアーは、珍しく、各地のどの展望台からも、ついに一度もヒマラヤの山々を見ることなく終わってしまったのです。ポカラからカトマンズへ帰る小型機も、霧で離着陸できないからということで、何時間も遅れて、カトマンズにたどり着きました。
成田を出発して6日目、明日の帰国を前にして、私たちはその日の朝の「ヒマラヤ遊覧飛行」に最後の望みを賭けていました。ホテルのロビーに
6時に集合して空港へ向かうことになっていたのですが、現地ガイドのソルさんが空港へ電話してみたところ、視界が悪くて飛べる状態ではないという返事です。一旦部屋に帰って、霧が晴れるのを待ちました。10時ごろになって、少し霧が晴れてきたというので、期待しながら空港へ行ってみました。1500メートルの視界が必要なのに、まだ600メートルの視界なので、もう少し待ってくれるようにと、と言われ、結局、12時近くになって、やっと、遊覧飛行の小型機は私たちのグループを含めて20人の乗客で離陸したのです。
小型機は北東へ向かって高度を上げていきます。すぐに雲の上に出て、15分も飛ぶと、左側の窓からは壮大なヒマラヤ山脈が白い雪を頂いて連綿と続いているのが目に入ってきました。7~8000メートルの山々ですから、さすがに高さが違います。日本でも、飛行機から富士山の遠景を何度が見たことはありますが、ヒマラヤの山々は高さが3776メートルの富士山の二倍もありますから、山脈全体が雲の上にそっくり浮いているような感じです。ネパール人のスチュワデスが「あの左の方に見えるのがマナスル(8163メートル)です。正面に見えるのがランタン・リルン(7234メートル)です・・・・」と次々に山の名前を教えてくれました。山々の頂が白く輝いて荘厳な美しさです。近づいていくにつれて、乗客からは感嘆の声があがりはじめました。そして、まもなく8850メートルのエベレストの偉容も視界に入ってきました。
ヒマラヤ山脈は、インド・チベット間に東西に連なる長さ2550キロ、幅220キロにおよぶ大山脈ですから、全体を一望することは出来ません。飛行機で一時間近く周辺を飛びまわっても、マナスルからエベレストあたりの中央部を見ることが出来るだけです。私は、小さな木の葉のような小型機に揺られながら、この白く輝く「神々の座」を吸い込まれるように眺めていました。1億年前には広い海であったのが、7000万年前にはインド亜大陸がアジア大陸にぶつかり、じりじりと大陸を押し上げていく。そして、2500万年前から1000万年前にかけて、かつての海の底が、このような大山脈になった―。まさに、「神の座」にふさわしい壮大なドラマの、今の一こまを見ているのだという感慨が沸き起こってくるのです。
ヒマラヤ山脈に近づいてからは、乗客は一人ひとり交代でコックピットに招き入れられ、コックピットのなかから、目の前に広がる大パノラマを写真に収めることができました。雲の上を飛び続ける小型機のすぐ前には、白く、美しく、神々しく、ヒマラヤの高峻な山々が広がり、そのなかには、エベレストが磐石の重みと威厳を見せながら頭角をあらわしています。この一瞬の感動を味わうために参加したツアーが、これで報われたような気がしました。おそらく、ほかの同行者の皆さんも同じ思いであったことでしょう。ネパールに来てヒマラヤを見ることが出来ないというそれまでの不運続きににもかかわらず、6日目にやっと手にしたその幸運に感謝しながら、私たちは、何の不満もなく、翌日、帰国の途につきました。
(2007.02.01)
|
