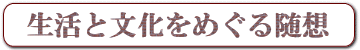
No,1〜No,10
溝口祭典「こすもす倶楽部」会報紙『木洩れ陽』連載
|
自分の足で歩く ー生活と文化をめぐる随想(1)ー 1998.5 日本では親の子供に対する過保護がよく問題になります。大学生になっても、あるいは就職して給料をもらうようになっても、子供は親と同居を続け、母親が食事から洗濯、掃除に至るまですべて面倒を見るというのは、日本では別に珍しいことではありません。しかし、欧米では、これはかなり珍しい部類に入ります。 たとえば、一般にアメリカでは、子供は高校を出れば親元から離れて自立し始めます。大学に入っても、できるだけ学費や生活費は自分で稼ごうとします。就職しても母親に食事や洗濯で世話になるというようなことは、おそらく皆無であるといってもよいでしょう。 私はアメリカには何度か住んだことがあります。住んでいるとそういう違いがよくわかるのですが、そのような違いを最初に強く意識したのは、もう、四〇年も前のアメリカ留学の時でした。 私は、秋の新学期からオレゴン大学大学院に入学することになっていて、それまで、カリフォルニア大学バークレイ本校で夏期講座に出席していました。 インターナショナル・ハウスという大きな寄宿舎の六階でフランツ・シモンという UCLA(ロサンゼルス分校)の学生と一か月半同室でしたが、彼は猛烈な勉強家でした。がっちりした体格で、旺盛なエネルギーを一心に勉強に注ぎ込み、寸暇を惜しんで教科書に取り組んでいます。授業から帰ってきたら、三〇分ほど運動して、それから勉強を始め、明け方の二時頃まで机に向かっていました。睡眠も五時間くらいしかとっていなかったかもしれません。私はいつも先に寝ていました。 ある日、食堂で夕食の後ちょっと雑談していた時に、フランツは、夏休み前半の一か月半はロサンゼルスで線路工夫のアルバイトをしたが、仕事がきつくて大変だったと言いながら、私に豆だらけの両手を見せてくれたことがあります。私が、なぜ線路工夫などをやったのか、と聞きますと、彼は当たり前ではないかというような顔をして、短く"money" と答えました。 鉄道の線路工夫というのは、重労働であるだけに賃金がほかのアルバイトより倍も高く、要するにお金がほしかったから線路工夫を選んだというのです。彼は、バークレイ本校での夏期講座の授業料も、そのアルバイトで稼いだお金で払った、と言いました。 当時の日本では、まだアルバイトというのはどこか貧しく、暗い響きがありましたから、私はフランツからそれを聞いたとき、自然に彼のことを貧しい苦学生なのだと思いこみました。親が貧しくて、子供の授業料も払えないのだと勝手に想像してしまったのです。しかし、それはそうではありませんでした。 お互いに夏期講座を無事に終了し、別れの日が近づいてきた頃、フランツが、自宅がサン・フランシスコの郊外にあるので、ロサンゼルスへ帰る前に、私を夕食に招待したいと言ってくれました。私は彼の運転する古い自動車に乗って彼の家へ向かいました。彼は一人息子です。父親はオランダ系のアメリカ人で、母親はドイツ人だそうですが、私はその両親に会うまでは、子供の授業料も払えない「貧しい親」というイメージを抱き続けていました。 一時間近く走って、やがてフランツの家に着きました。場所がどの辺であったかは忘れましたが、サン・フランシスコの郊外に小高い丘があって、その麓の一隅に鉄格子の門があります。そこを通り抜けて、アスファルトのアプローチを駆け上り、着いたところが堂々とした邸宅でそれがフランツの家でした。その小高い丘全体が邸宅の敷地になっていて、英語でいうマンションです。フランツの父親はもともと外科医で、サン・フランシスコにある大病院の院長であることも、その時はじめて耳にしました。 優しさとはなにか ー生活と文化をめぐる随想(2)ー 1998.7 むかし、「キタキツネ物語」という映画がありました。ごらんになった方もおられることと思います。 冬のオホーツクのブリザードが荒れ狂って去ったある朝、流氷を渡って精悍な雄キツネのフレップが姿をあらわします。フレップは果てしなくひろがる雪原の上で、ほかの雄キツネと闘い、美しい雌キツネのレイラを獲得しました。この映画は、こうして結ばれたキツネ夫婦と、春に生まれた5匹の子供たちとの「別れ」を中心展開するドラマでした。 眼の見えない子ギツネのチニタは、草原に迷いでて死に、母親のレイラも、子供たちの飢えを満たすための食料探しで罠にかかって死にました。そしてやがて、立派に成長した子ギツネたちと父親キツネとの間に別れの時がやってくるのです。それは、このドラマのクライマックスでもあるのですが、父親キツネのフレップは、子ギツネたちと凄絶な死闘を繰り返し、一匹一匹を確実に荒れ野の彼方へ追い払うことによって、子別れを遂行して見せたのでした。 子供はいつまでも親の庇護のもとに、親の愛情を期待して生きていくわけにはいきません。時が至ればいつか別れて、独力で自分の食料を手に入れなくてはならなくなります。これはまさしく自然の摂理であって、その厳しい試練に耐えられなければ死ぬほかはないのです。だからこそ、このように厳しい子別れは、すべての動物にとって種の保存のための本能であるといってもよいのでしょう。 本来、人間の場合でも、これが例外でありうるはずはありません。例えば古代スパルタでは、処世の術として、子供に他人のものを盗むことを教えました。盗んで捕まるようなことがあれば、捕まるような下手な盗み方をしたということで罰せられました。子別れとは結局、子供を自立させるためのしつけですから、これも子別れの一つの形式といえるかもしれません。 中世までのヨーロッパでも、略奪と戦闘能力を持つことが、生きていくための必須条件でした。強いものが弱いものを倒し、奪うことによって生存が確保できた厳しい世界であったからです。当然、子供のしつけも、そのような闘争と略奪と無関係ではなかったといえるでしょう。 このヨーロッパの弱肉強食の原理は、近代的ヒューマニズムの粉飾をほどこした現代の欧米人の生活の中にも、現実感覚として鮮やかに波打っていると考えられます。子別れのための厳しいしつけの伝統は、だから今日でも、ヨーロッパやアメリカでは、連綿と受け継がれて、ゆらぐことがないのです。 前回の本欄で取り上げたのもその一例です。あのフランツは、大邸宅に住む大病院の院長という資産家の息子でありながら、鉄道の線路工夫までして自分の授業料を稼いでいました。 これと対照的なのが、恵まれた環境に守られてきた日本人の場合です。日本人が育ってきた環境には、ヨーロッパ的な意味での生存競争の厳しさは、かってもなかったし、今もありません。日本は古来、豊かな自然と高い食料生産性に支えられて、基本的には、きわめて住み易い「豊葦原の瑞穂の国」であったのです。それが、日本独特の家族的な人間関係の中で寛容と互恕の精神を生み、そしてそれが、欧米にはみられない甘えの下地を醸成していく結果になりました。 言い換えれば、日本人の世界観には、生に対する切迫した緊張感も深刻な不安もないのが普通です。いわば、生存が前提とされた生き方の問題があるだけで、そこに一つの楽天的な余裕があります。 子供は大きくなったら苦労することになってかわいそうだから、子供のうちだけは甘えさせるというのも、この余裕のなせるわざでしょう。そしてこの「余裕」が、長い年月を経ていつの間にか、諸外国に例をみないほどの親の過保護になって、日本人の親子関係をきわめて特異なものにしているといえるのかもしれません。 あるテレビ番組で、この親子問題をとりあげているのがありました。ひとりの母親が、子供が言うことを聞いてくれないで困る、という相談を持ちかけました。子供に強く言うと、「そんなことを言うのなら、ボク、大学へ行ってやらないよ」と言い返すというのです。司会者が、それで、あなたはどう対応するのですか、と聞きますと、その母親は、「私、ただ、悲しくて泣くだけです」と答えていました。 日本文化には、諸外国にない優れた美点がいくつもありますが、いまはそれらの良質の部分が少しずつ失われていっているような気がします。子供に対するしつけも、その中にはいるかもしれません。 むかしと違っていまは、小学校でも、超自己中心的な児童が多すぎて、教員も大変なんだそうです。その嘆きをこの間(六月一〇日)の「朝日新聞」が特集していました。 例えば、ある小学校一年生の女の子がおもらしをした話。担任がその子を保健室につれていき、養護教諭が自宅に連絡しました。 「すぐに着替えを持って伺います」と言って母親はすぐやってきたので、養護教諭はほっとしたといいます。しかし、しばらくして様子が変なのでふとみると、目を疑う光景が飛び込んできたのだそうです。母親も子供と一緒になって泣きながら、二人ベッドの上で抱き合っていたのだというのです。 また例えば、わが子の万引きに気がついていながら、注意しない母親の話。教師が母親に「お子さんとちゃんと話をして、お店に謝りに行って弁償すべきですよ」と言うと、その母親はこう答えたそうです。 「でも、それじゃあ、子供とけんかになっちゃうじゃないですか」 この間、私自身もつぎのような体験をしました。 あるカメラ屋のカウンターの前で、写真を受け取るために並んでいると、すぐ近くで、五,六歳くらいの女の子が、天井からぶら下げられていた大きな風船を、飛び上がっては激しく叩いていたのです。私はやめさせるつもりで、優しく頭をなでました。するとその女の子は、「なにするんだよ!」と、怒鳴り返してきたのです。そしてなおも、飛び上がっては風船を叩きつづけていました。 私はわが耳を疑いました。こんな小さな女の子が、そんなものの言い方をするはずはない。おそらく私の聞き間違えであろう。私はそれを確かめたい気持ちもあって、また軽く頭をなでたのです。女の子はいっそう声を張り上げて、「なにするんだよ!」と私にくってかかってきました。私は一瞬呆然として、背筋が寒くなるような気がしました。 若い父親は、それを見ても、別に注意しようとも止めようともしなかったのです。いまでもよく言われることですが、やはり、子供のしつけは、欧米のほうが一般にかなり厳しいといってよいと思います。いろいろと本で読んだり、私自身も見聞きしてきましたが、そのしつけの厳しさの最初の思い出は、むかし、私がアメリカで留学生活を送っていた頃のことです。 私が、西海岸のオレゴン大学で学んでいる間、私を学校の休みのときなどによく自宅へ招待してくれていたバイアリーさんという若い医者がいました。美しくしとやかな奥さんと、ボブという三歳の男の子がいました。街外れの広い家の敷地には、小川が流れて、子馬なども飼っていたようです。自家用のセスナ機も持っていて、一度、大学の上空を飛びながら、私にも操縦させてくれたことがあります。 ある年の感謝祭の休みに、私はバイアリーさんの友人の家での夕食に招待されました。私はまずバイアリーさんの家へ行って、そこからバイアリーさん夫妻の車で一緒に出ようとしたのです。三歳のボブは、その時に来てもらっていた女子高校生のベイビー・シッターと留守番です。女子高校生に抱かれて、見送りに玄関先まで出てきました。 奥さんがボブの頬にキスをして、車に乗り込もうとすると、幼いボブは心細くなったのでしょうか、急に泣き出しました。奥さんは一度引き返してボブをなだめたので泣くのを止めたのですが、母親が離れていこうとするとまた泣き出しました。その時です。車から降りて、無言のままつかつかとボブに近寄っていったバイアリーさんは、いきなり泣いているボブに激しく平手打ちを食わせたのです。温厚なバイアリーさんにしては信じられないような一瞬の出来事でした。 三歳のボブは、「ウッ」と息を詰まらせたまま、泣くのを止めてしまいました。アメリカ人の父親の、しつけの厳しさを目の前でまざまざと見せつけられて、私は深い感銘を受けました。 忘れられない一言 ー生活と文化をめぐる随想(3)ー 1998.9 同じひとつの仕事をしていても、それがひどく辛くて疲れることもあれば、逆に、あまり疲れず楽に感じられることもあります。つまり、自分の気持ち次第で、その仕事が、辛くもなり楽にもなるのです。私がそのことを初めて身にしみて感じさせられたのは、もう四〇年も前のアメリカ留学中のことでした。 無我夢中で勉学に追われていたオレゴン大学での一年が過ぎて、最初の夏休みに、私は四千五百キロをドライブしてアメリカ大陸を横断し、東海岸へ向かいました。日本では当時、個人の海外渡航などはまだ一切認められてはいませんでした。日本へ帰ったらもう二度とアメリカへは来れないような気がしていましたから、どうしても、ニューヨークを見ておきたかったのです。しかし、奨学金で旅費までは出してくれません。私は友人の世話で、ニュージャージーのリゾートホテルのレストランで、一カ月半アルバイトをすることにしました。 ホテルは豪華で、すぐ前には大西洋の大海原が広がっていました。週末などには、すぐ隣のニューヨークなどから大勢の人々が休養にやって来ます。私はアルバイトの女子学生とペアーを組んで、レストランのいくつかのテーブルを受け持ち、ウェイターとして忙しく働きました。しかし、まだ、ウェイターに徹しきることは出来なかったのでしょう。主任のトムは、何かにつけて口うるさく小言を言い続けました。 小言を言われながら働くのは辛いし、それにひどく疲れます。その時の私は、まだ日本的な甘えから抜け切れていませんでした。「エリート留学生」のはずの私が、こんな仕事で小言をいわれながら働いているのを親が知ったら何と言うだろう、と思ったりもしました。私は三週間ばかりで、とうとうその仕事を途中で投げ出してオレゴンに帰り、夏休み後半の夏期講座に出ることを考え始めたのです。 そう決心して、明日はトムにそのことを告げようと考えていた日の夕方、たまたま、別のところでアルバイトをしていたエール大学の韓国人留学生パクさんに会いました。品のよい物静かな彼の人柄に惹かれながら、私は彼の前でも仕事の話をして、「もういやだからやめる」とつい弱音を吐いてしまいました。パクさんは黙って私の話を聞き終わったあと、ひとこと静かに、「でも、あなたは殺されるわけではないのでしょう?」と言ったのです。私はそのひとことにはっとして、一瞬全身に電流が流れたような衝撃を受けました。 その当時のアメリカ留学というのは、勉強も生活も背水の陣で、ちょっと大げさに言えば、間違いなく命がけでした。しかし、殺されるわけではありません。私のアルバイトにしても、考えてみれば日本のアルバイトより時給でおそらく十数倍は高く、しかもホテルの従業員として出される無料の食事も、ミルク、ジュース、卵、パン、肉類がほとんど飲み放題食べ放題なのです。当時の貧しかった日本では考えられないほどの豊かさでした。仕事も確かに忙しいのですが、疲労困憊して倒れてしまうようなものでは決してありません。考え直してみれば、結構楽なのです。 私は、決心を翻して、アルバイトを最後まで続けることにしました。仕事の合間の小休憩の時間も惜しみ、床を拭いたり、窓ガラスも磨いたりして、くるくると独楽ネズミのように動き続けました。仕事はもう嫌ではなくなっていました。不思議なことに、ほとんど疲れも感じませんでした。一生懸命に働いて、終わったら、シャワーを浴びて海岸に出ます。大西洋の風が実に爽やかでした。 鬼のように思っていたトムは、急に小言を言わなくなりました。最後の日、給料の小切手を私に手渡しながら、彼は、「ショーゾー、君はよくやった」と、笑顔を見せながら初めて私をほめてくれました。 厳しさから学ぶ ー生活と文化をめぐる随想(4)ー 1998.11 アメリカの大学生はよく勉強します。週日は、朝から深夜まで、わき目もふらずに机に向かっているのが普通です。何年か前の調査では、自宅や図書館で一日に勉強する時間は、日本の大学生が平均で一・八時間であるのに対し、アメリカの大学生は七・六時間で、実に四倍以上も多く日本の大学生より勉強している結果がでていました。(「朝日」'90・7・14) 彼らはこのように、猛烈に勉強するから、週末にはしばしば羽目を外して遊びます。猛烈に勉強するためには遊ぶことも必要なのです。これは一生懸命働くためには休養が必要なのと同じで、私は、この遊ぶことや休養の大切さも、アメリカでの留学で学びました。 どんなに宿題などに追われて時間が惜しくても、週末には勉強から離れ、気分転換をはかりました。アメリカの大学での競争は激しく、それだけに、焦って勉強ばかりしていたら、おそらく、ノイローゼになったり、体をこわしてしまったりしたことでしょう。 生活もいわば背水の陣で、留学中の勉強は決して楽ではありませんでしたが、特に、大学院の最終試験は苦しい試練でした。必死になって勉強し、終わった時には自室のベッドの上で、「終わった、終わった・・・」と何度も叫びながら、転げまわりました。 私の場合は結局、当初の予定より少し早く、一年九か月で大学院を終え、船でシアトル、バンクーバーを経由して帰国することになりました。一九五九年の三月のことです。 シアトルには、留学の途上、船で一緒であったY君がいました。彼は三重県四日市の石油会社社長の息子でした。いかにも坊ちゃんという感じで、船室の中でも、恋人の写真を飾ってにやけていました。船がロサンゼルスに着き、一緒にハリウッドを見てまわった後は別れて、それ以来会っていませんでした。 彼は、ワシントン大学で経営学を学んでいましたが、生活には随分苦労したようです。下宿代を安くあげるために住み込みで働いたこともあります。しかし、女主人の下着まで洗濯させられたといって、そこを飛び出しました。レストランで深夜の掃除係をしていた時には、巨大なモップで床を拭こうとしても、小男の自分のほうが押し返されてしまう、というような便りをくれたりしました。 そのY君が、帰国を間近に控えた私に手紙で、シアトルを通る時には、是非自分のところへ寄ってほしいと、いってきたのです。私は、にやけたイメージの彼に会うのはあまり気が進みませんでしたが、言われるままに彼のところへ行きました。そして私は、別人のようにすっかり変わったY君の姿にひどく驚きました。かっての世間知らずの坊ちゃんの面影はどこにもありませんでした。堂々と落ち着いて優しく、体つきも一まわりも二まわりも大きく見えました。 彼は私にしみじみと言いました。「大学院を終えて日本に帰れる君がうらやましい。ぼくはまだ、一、二年はかかりそうだし、無事に卒業できるかどうかもわからない。でも、アメリカに来てよかったと思っている。ぼくは日本に帰ってももう怖いものはない。乞食をしてでも生きていける。そう四日市の両親に伝えてほしい」と。 太平洋を二週間で渡って、私の乗った船は横浜に着きました。その当時の日本ではまだ、横浜から東京へ電話するのにも、電話局の交換を通さねばならず、三〇分も待たされたりしていました。 強烈な逆のカルチャー・ショックが治まりかけた頃、私は機会を作って四日市のY君の家を訪ねました。ご両親の前で、Y君のことを話し、彼の「乞食をしてでも生きていける」ということばを伝えると、Y君のお父さんは大きくうなずき、じっと耳を傾けていたお母さんは、ぽろぽろと、大粒の涙をこぼしました。 男尊女卑とレディー・ファースト ー生活と文化をめぐる随想(5)ー 1999.1 私がアメリカに住んでいた頃、何度か感謝祭やクリスマスのディナーに招待を受けたことがあります。そのような折りに、食卓に座ってよく見ていると気がつくのですが、ナイフを持ってみんなのために七面鳥の肉を切り分けてくれるのは、決して主婦ではありません。それは常に、その家の男性家長の役割です。ジェームス・ディーン主演のあのアメリカ映画「ジャイアンツ」にもそのような場面があります。 これはイギリスでも同じです。イギリスも、もともと肉食の国ですから、他のヨーロッパ諸国と同様、古来、主食の肉を分け与えるということは、権力者である家長の仕事でした。そして、その肉を切り分けるナイフは、大切な食料分配権を握っていることを示す権威の象徴であったのです。英語の「ファミリー」とは、もともと権力者の家長に服従する奴隷の意味で、これはイギリス社会の父性的特徴をよくあらわしています。 日本の社会はこれとは反対で、母性的特徴を持っているといえるでしょう。恒常的な平和のうちに稲作文化が育てられてきた環境のなかでは、歴史的に戦乱で明け暮れしてきたイギリスなどより、女性の労働力がはるかに重視されてきました。農耕が女性を中心に営まれてきた例も希ではありません。 日本の農作は、重労働ではありませんが、間断のない手作業の連続です。忙しいときには猫の手も借りたいほどになり、子供たちまで動員されたりします。それゆえにこそ日本の女性は、農作の労働力としてのみならず、働き手の生産力としても重要視されてきたのです。 農耕民族である日本人にとって、イギリスの肉を切り分けるナイフに相当するものはご飯をよそう「しゃもじ」でした。しゃもじは、イギリス人におけるナイフと同じように、食料の分配権を意味する権威の象徴でしたが、しかし、それを握っていたのは男性ではなく女性であり、一家の主婦であったのです。 いまも一部に残る「しゃもじ渡し」の儀礼にみられるように、主婦がやがて姑になり、年老いて嫁にしゃもじを預ければ、それは事実上、家庭の統率権を嫁に移譲したことになります。イギリスとは対照的に、日本では、女性から女性へと権威の象徴は引き継がれてきたのでした。男尊女卑とか亭主関白とかいわれてきたなかで、つぎのように、イギリス人女性を驚かせるような例が決して少なくないのもそのためでしょう。 日本の一部の主婦たちは、見かけよりは強いのではないでしょうか。主婦たちのすべてが忍従を強いられているわけでは決してありません。たとえば佐藤夫人はとても いい人ですが、ご主人を「鉄の鞭」で支配しています。彼女は、ご主人の給料袋を封も切らないまま受け取り、そしてご主人には 毎日、お小遣いを渡しているのです。このことを彼女はいつかコーヒーを飲みながら 何気なく話してくれたのですが、私が驚いた顔をすると、「でもこれは当たり前ですよ」と彼女は言いました。 (ジョイス・マ クドネル『日本人』より) なぜ、このイギリス人女性は驚くのでしょうか。要するにイギリスでは(そして一般にアメリカや西欧諸国でも)、先に述べたナイフの例と同じように、大切な財産は権力者である男性が握り、女性には任せないということで、これはおそらく、長い戦乱の歴史の中で生まれた女性蔑視の名残とみてよいでしょう。 イギリスでは、女性は伝統的に弱い立場にあり、虐げられ、男性に従属してきた存在でした。しかし、それがゆえに、やがて一方では、女性はいたわらねばならないというモラルも芽生えてくることになります。 実は、いまではよく耳にする「レディー・ファースト」も、そのモラルの流れをうけついだもので、本来、女性尊重からきたものではなく、むしろ、女性蔑視の裏返しとしておこったものといってよいのかもしれません。 私たちは星の子 ー生活と文化をめぐる随想(6)ー 1999.3 私たちの社会では、常識的によく、胎児は「十月十日」で生まれる、などと言ったりします。しかし、「十月十日」で人間一人ができあがるわけでは決してないでしょう。十月十日で生まれてくるようないのちの誕生の仕組みが創りあげられるまでには、気の遠くなるような長い時間が必要でした。その時間をどのくらいの長さで捉えていけばよいでしょうか。 少なくとも、この地球上に生命が芽生えた三五億年前からの時間を考えなければならないと思います。私たちの一人一人は、その三五億年の生命進化の歴史をDNAに刻み込んで、確かに、体内にもっているはずです。しかし、その生命が芽生えるための準備期間も考慮に入れると、やはり、地球誕生の四六億年前に溯って考えるべきなのかもしれません。 さらに、もっと視野を広げてみていけば、その地球も、銀河系のなかの小さな一つの惑星に過ぎないのです。その銀河系の直径はだいたい一〇万光年であるといわれています。つまり、一秒間に三〇万キロ走る光のスピードで測っても、一〇万年かかる広さということです。 この銀河系の中心部は、アルジとよばれる年老いた星の集まりで、その周辺部には若い星々が群がっています。それらの星の総数は約二千億にもなるようです。そして、その銀河系もまた、全宇宙の中の一千億を越える銀河系の一つに過ぎません。このように見てくると、私たちのいのちの誕生を考えるのには、地球誕生の四六億年前よりさらにずっと遡って、宇宙誕生のビッグバンまでの一五〇億年の時間を考えるべきなのでしょうか。 一五〇億年前にビッグバンで始まった宇宙は、強烈な光のもとに、時が刻み始め、猛スピードで膨張する空間に多量の物質が創成されたと考えられています。そのガス状の原子の海から、大小さまざまな星が次々と生まれてきました。百億年ほど経って生まれた私たちの地球もその一つです。 生命科学者の柳沢桂子氏によると、こうして生まれた地球も、そして炭素を主体とした元素で構成されている私たちの肉体も、ともに星の輝きの産物なのです。私たちは、体に鉄分が足りない、と言ったりしますが、炭素も酸素も、鉄もアルミも、私たち周辺の水素以外のすべての元素は、もともと、星の輝きのなかで形成されてきました。 つまり、元素のレベルで見れば、私たちはかって星として輝いていたし、その輝きがあったからこそ、現在の私たちの存在へとつながってきたことになります。まさに、私たちは「星の子」なのです。 夜空に星を見上げるとき、自然のうちに故郷を思い起こしたりするのは、私たちがかっては星であった記憶が、魂のどこかに刷り込まれているからなのかもしれません。 ついこの間、一月の末に、国立天文台がハワイのマウナケア山頂に建設していた世界最大といわれる口径八・二メートルの大型光学望遠鏡「すばる」が、宇宙に向けての観測を開始しました。このすばるの活動目的は、宇宙の始まりの頃、銀河がどのようにして創られてきたかを調べることと、太陽系のほかの惑星のなかに生命の痕跡を探すことであるといわれています。 宇宙のなかの星の生や死は、私たちの生や死の問題とも無関係ではないので、これらの観測の結果によっては、私たちの宇宙観、生命観が根底から変わってしまうようなこともあるかもしれません。 いままでも、天文学の進歩は、人類の世界観を大きく変えてきました。私たちの住む地球の表面は平らだと思っていたら、丸かった。地球が宇宙の中心だと思っていたら、実は太陽のまわりを回っていた。その太陽も、あとでわかったことは銀河系の片隅の平凡な星の一つで、しかも、その銀河系も、宇宙に無数にある銀河の一つに過ぎなかった、というようにです。 私は、この宇宙の探索が、星の生と死の永続的な繰り返しを明らかにしてきたように、やがて私たちのいのちの永遠性をも証明してくれるようになることを、こころ密かに期待し続けています。 障害は不幸ではない ー生活と文化をめぐる随想(7)ー 1999.5 「障害は不便です。しかし、不幸ではありません」。これは三重苦の聖女といわれたヘレン・ケラー(一八八〇〜一九六八)のことばです。 ヘレン・ケラーは、よく知られているように、盲・聾・唖の三重苦を克服して、講演と著述で世界中の身体障害者福祉運動に一生を捧げた社会事業家でした。 彼女はアメリカのアラバマ州で生まれましたが、二歳の時の猩紅熱による高熱で、目、耳、口が不自由になりました。七歳からパーキンス盲学校のサリバン先生から読み書きの特殊訓練を受け始めたのですが、その感動的な教育の様子は、「奇跡の人」という映画で、日本でも広く紹介されましたから、ご存じの方も多いことと思います。 ヘレン・ケラーは一九〇四年に、ラドクリフ女子大学を優等で卒業しましたが、その時には、「耳が聞こえず、目が見えなくとも、魂が不滅である以上、それらの障害は私の人生になんら致命的なものではないということを、私は喜ばしい思いで確信したのです」と書き残しています。 そして後に彼女は、健常者のために「誰でも若いうちの一時期に、もし視力や聴力を失う経験をもつことができたら、それはむしろ、幸せなことです」とも言いました。 私たちは、目は見えて当たり前、耳も聞こえて当たり前、しゃべることもできて当たり前と思っていますから、目が見えなくなったり、耳が聞こえなかったりすれば、本当に大変で、絶望感に打ちのめされてしまうかもしれません。その上しゃべることもできないとなれば、もう生きていく意欲さえなくしてしまうことでしょう。しかし、それをヘレン・ケラーは「不便ではあっても、不幸ではない」と言い切っているのです。 こういうことばをよく考えていきますと、どうも、幸福とはしばしば不幸の別名であり、不幸とはしばしば幸福であることの錯覚ではないかとさえ思われることがあります。人が幸福か不幸かということは、結局はその人自身のこころの持ち方の問題で、決して、富でも地位でも名誉でもなく、いわゆる「五体満足」でもないのでしょう。 重度障害者としては、日本でも、首から下が麻痺してしまった星野富弘さんのことが、よく知られています。口に絵筆をくわえて描く美しい花の絵は、「花の詩画集」としてNHKテレビで放映されたり、本やカレンダーになってひろく親しまれてきました。 その星野さんは、クリスチャンになって結婚しますが、その時に、参会者に贈った色紙には、 わたしは あなたのみおしえを 喜んでいます 苦しみに会ったことは わたしにとって しあわせでした と書いていました。 最近では、乙武洋匡君という昭和五一年生まれの明るく元気な若者が、話題になっています。手足のない胴体だけの彼の書いた『五体不満足』という本がベストセラーになり、もう三百万部近くも売れているようです。 乙武君は、自分の体に劣等感を持つどころか、自分に手足のないことを、誰にも負けない、ほかとは違う自分の長所だと、思っているようです。そして、「多くの人が健常者として生まれてくるなか、どうしてボクは身体に障害を持って生まれてきたのだろう。そこには、きっと何か意味があるのではないだろうか」と自問自答した彼は、「障害者にはできないことがある一方、障害者にしかできないこともあるはずだ」と考えて、福祉活動に乗り出していきます。 この健康で手足のない若者には、何の暗さもじめじめしたところもなく、彼の姿はいつも明るい光のなかで輝いているようです。 彼は本の中で世間の障害者を励まして、次のようにも書きました。 日本中、いや、世界中を見渡したところで、自分とまったく同じ人間などいるわけがない。たった一人しかいない人間であれば、その人にしかできないことがあって当然なのだ。そうであるなら、ボクらは、もっと自分自身を大切にして、誇りをもたなければならない。 瞬間と永遠 ー生活と文化をめぐる随想(8)ー 1999.7 私たちはこの世に生をうけて、数十年から長くても百年くらいで死んでいきます。日本人の現在の平均寿命は、厚生省の発表によると、男性が七七・八九歳、女性が八三・八二歳で、いずれも世界最高だそうです。確かに日本人は長生きするようになりましたが、世界最高だからこの平均寿命は長いのでしょうか、それとも人間の寿命としては、まだまだ短いのでしょうか。これは、ものの見方によってどちらにも変わります。 人間の寿命を最高でも百年くらいと限定して考えれば、間違いなく、七七歳よりも八三歳のほうが長く、百歳まで生きれば、二〇歳で亡くなった人より五倍も長生きしたということになります。しかし、生命が永遠であるとすれば、二〇歳であろうが百歳であろうが、一瞬であることに変わりはなく、その差は限りなくゼロに近いといえるでしょう。 こころみに、ここで視野を大きく宇宙にまで広げて、外から私たちの住んでいる地球を眺めてみましょう。私たちの地球は、巨大なようであっても、宇宙からの視野で見れば、その存在は銀河系の中のごく小さな惑星にすぎません。 その銀河系の直径は、だいたい一〇万光年、つまり、一秒間に三〇万キロ走る光の速さで測っても一〇万年かかるという広さです。中心部はアルジとよばれる年老いた星の集まりで、その周辺部には若い星々が群がっています。その星の総数は約二千億個です。そして、この銀河系もまた、全宇宙の中の一千億を超える銀河系の中の一つにすぎません。 このように見ていくと、地球というのは、宇宙の中では、本当に小さい一つのけし粒のような極小の存在です。極大であったはずの地球も、極小に変わってしまいます。 その地球が誕生したのは、およそ四六億年前のことですが、兄弟の火星や金星とちがって、地球には海ができ、大気には酸素があり、そして生命に満ちあふれるようになりました。この生命の誕生については、実はまだよくわかっていませんが、地球最古の生命の化石が、オーストラリア北部のノース・ポールというところで一九七六年に発見されています。ストラマトライトという海中の生物からできた三五億年前の化石です。 このストラマトライトが太陽光線に反応して酸素を放出し、それが、新しい、酸素によって生きる生物の誕生に結びついていきました。この新しいタイプの生命については、現在のところ二〇億年くらい前までさかのぼれるようです。 四六億年前の地球の誕生そのものが奇跡でしたが、その上で現在生きている私たち自身は、この酸素によって生きる生物の誕生以来、さらに多くの気の遠くなるような奇跡の連続のうえで、生をうけました。その生は、この地上では長くても百年くらいのものかもしれません。しかし、人間の生命誕生の過程を科学的な分析が明らかにしているように、その一つ一つの生には、少なくとも二〇億年分のDNA遺伝子情報が組み込まれていることも、紛れもない事実です。 これほど長い時間をかけて創り出された私たちの生命が、たかだか百年の視野だけに限定して捉えられるものでしょうか。 生命誕生の長い歴史の中では、私たちは明確に、瞬間を生きていることになります。しかし、その瞬間は永遠の中の瞬間です。永遠があるから瞬間があります。瞬間があるから永遠があります。そして、視点によっては、瞬間とは永遠にほかなりません。 私たちの人体は、六〇兆の細胞から成り、それ自体が小宇宙の広大さをもっていますが、宇宙の中のけし粒ほどの地球の中のさらに小さな「極小」であることも事実です。つまり、私たち自身も極大でもあるが極小でもある。また、瞬間を生きているが、それは永遠を生きているということにもなるのです。 このような見方では、たとえば、私たちの身のまわりの幸せとは、案外、不幸のことで、不幸とは実は幸せのことである、というような逆説も成り立ちうるのでしょう。そして、自分の視野を転換できず、真実を見ることができないことが本当の不幸ではないか、というようなことも考えられるようになります。 大切なことは真実を知ることですが、仏教のみならず、キリスト教やイスラム教など世界の主要な宗教はすべて、人間のいのちは永遠であることを、繰り返し教え示しています。そのような生命の真実を知るためにも、「瞬間は永遠である」というような発想の転換が、私たちにはどうしても必要なのかもしれません。 人類はみな兄弟 ー生活と文化をめぐる随想(9)ー 1999.9 仏教には輪廻転生の思想があって、たとえば親鸞は、『歎異抄』のなかでつぎのように言っています。 父母というのは、自分の父母だけが父母なのではない。人間は何度も何度も生まれ変わるから、生きとし生けるものは、みんないつかの世で、父母であり兄弟であった。だから自分は、念仏をとなえる場合でも、現世の自分の父母だけに対する孝養のつもりでとなえたことは一度もない。 同じようなことは、キリスト教の聖書の中でも、度々述べられています。たとえば、ある時、イエスが大勢の人々に囲まれて座っていると、そこへ、イエスの母と兄弟たちがやってきます。群衆の一人が、「あなたの母上と兄弟たちが外であなたを尋ねておられます」と言うと、イエスは、「私の母、私の兄弟とは誰のことか」と問い返し、まわりに座っている人々を見まわして、「ここに私の母、私の兄弟がいる。神のみこころを行う者は誰でも、私の兄弟、また姉弟、また母なのである」と答えました。(マルコ伝・三章) ここでは、「神のみこころを行う者」という制約がつけられていますが、これは、「真実を知る者」というように捉えると、わかり易いかもしれません。つまり、人間というのは、誰でもみな父母であり、兄弟であるというのが「真実である」ということです。 この真実を理解するのは、そう難しいことではありません。それを、数字を基にして考えてみましょう。 いま私がここにいるのは、私に父と母の二人の親がいたからです。その父と母がいたのは、父にも母にもそれぞれ二人ずつの親がいたからです。このようなつながりを長い年月たどっていき、一世代を三〇年として計算すると、どうなっていくでしょうか。 一〇世代前(三〇〇年前)で、二親の数は、二、〇四八人になります。二〇世代前(六〇〇年前)では、二、〇九七、一五二人となり、もう少し遡って二四世代前(七二〇年前)になると、二親の数は、三千三百五〇万人を超えてしまいます。日本の江戸時代の人口は、二千六百万から二千七百万人といわれていますから、その江戸時代の人口をはるかに超え、さらに、二六世代前(七八〇年前)になると、二親の数は一億三千四百万以上になり、現在の日本の総人口をさえ、超えてしまう結果になります。 もちろん、実際には、人口は過去に向かって縮小し、逆に、未来に向かっては時代が経つにつれて増えていくのが普通ですから、このような親の数の増加は、現実にはありえません。これはどう解釈すればよいのでしょうか。この矛盾を説明できる合理的な根拠は、「人類みな兄弟」だけです。人間というのは、数が増えても、実はそれぞれが同じ大家族の一員であり、みんなが兄弟であることにならざるをえません。 それでは人間は一体、どういう道筋を通って現在の大家族になってきたのでしょうか。その科学的な探求は、近年大きく進歩してきました。類人猿などの化石による研究によって、約五百万年前にチンパンジーと分かれて独自の進化を遂げてきた私たち共通の祖先のイメージもだんだん明らかになってきましたし、彼らが、地球上に広がっていった足跡も、集団遺伝学のDNA鑑定などで、かなり明確にたどることができるようになりました。 たとえば、日本人の祖先はどういう人たちであったかもわかります。現在の日本人のDNA鑑定で明らかにされたところによると、中国・韓国系が最も多くて五一パーセント、次いで多いの沖縄系で一六・一パーセント、そのあとアイヌ系の八・一パーセントが続いて、それ以外の二一パーセントを除くと、日本人固有のDNAを持っている人の割合は、わずか四・八パーセントにすぎないことが判明しました。(NHK「遺伝子・DNA」) つまり、現在の日本人の二人に一人は、中国・韓国系で、「人類みな兄弟」という大家族のなかでも、中国・韓国人はもっとも身近な血縁ということになります。そのような真実を知れば、地球上に恣意的な国境線を引き、人種差別をすることの愚かしさもよくわかってきます。白が黒を差別するのもおかしいことですが、黄色が黄色を差別するのは、ほとんど、自分で自分を差別するのと同じことになってしまうからです。 親鸞やイエス・キリストのことばをまつまでもなく、このような「人類みな兄弟」の真実を理解していくことは、これからの世界の中で平和に共存共栄していくための不可欠の要件であると言ってよいのかもしれません。 アメリカのバブルのなかで ー生活と文化をめぐる随想(10)ー 1999.11 私は、今年の夏一か月をカリフォルニアで過ごしました。今度行ったのは、ロサンゼルスから南東へ約四十五キロのディズニーランドの近くです。ヴィッキーとヴァレリーという母親と娘の二人暮らしの家にホームステイしました。 ヴィッキーは六十二歳になりますが、毎日朝六時頃家を出て夕方六時頃に帰るまで、家政婦として忙しく働いています。娘のヴァレリーは三十六歳で、家から車で十五分くらいの所にある個人医院の受付事務をしています。 家はヴィッキーの亡くなったご主人が買ったもので、百坪ほどの土地に4LDKの平屋建てです。リビングルームと食堂で三十畳くらいあって、トイレ(浴室つき)は二つ、それにほとんどどの家もそうですが車庫も二台分ついています。築後三十年くらいで、売れば二十五万ドル(約二千七百万円)くらいではないかと、ヴィッキーは言っていました。 だいたいこの程度の家が、その辺では平均的な家といってよいかもしれません。 東京などとは違って、ロサンゼルス周辺の町では、住宅はまだ一戸建てが多く、価格も東京周辺に比べるとおそらく三分の一前後と思われます。しかしそれでも、いまアメリカは空前の好景気で、住宅もかなり値上がりしてこの価格なのだそうです。 近くの町に、私の知り合いの若夫婦の家があって、こちらは五年前に十九万ドルで買った新築の家が、いまでは少なくとも四割くらいは値上がりしていると言っていました。ニューヨークでもマンションの平均価格は過去一年間だけでも二割ほど値上がりし、地方のデンバーなどでも、五年前に二十一万ドル(約二千三百万円)だった住宅が今では三十六万ドル(約四千万円)になっているという話も聞きました。日本もバブルがはじけるまでは、土地も家も毎年のように値上がりしていましたが、いまアメリカは、ちょうどそのバブル経済の絶頂期にあります。 ごく大まかにいって、日本ではバブルがはじけて以来、株価は半分くらいに下がりましたが、アメリカはその間に逆に二倍も上がりました。アメリカはいま空前の株式ブームで、この株価上昇分が消費を押し上げ、大邸宅、高級ヨット、宝石類が人気を集めているほか、たとえば、自動車の売上も過去最高の勢いで伸びて、年間千六百十万台を越える勢いだといわれています。 この好況で、アメリカのトップ経営者の平均年収は、九十年の約百八十万ドル(約二億円)から九十八年の約千六十万ドル(約十一億八千万円)にまでなったそうです。一方、製造業の従業員の年収は、この間、約二万三千ドル(約二百五十万円)から約二万九千ドル(約三百二十五万円)へ二十八パーセント増えただけで、貧富の格差を大きく広げたのが、アメリカのバブルの特徴です。 私のホームステイ先のヴィッキー親子なども、家の資産価値が値上がりしているほかは、あまりバブルの「恩恵」は受けていない様子でした。彼らは、好景気で浮かれている人々の姿をまわりに見聞きしながらも、昔ながらのアメリカ庶民のつつましやかな暮らしぶりを堅実に守り続けているようです。 娘のヴァレリーが、三十六歳にもなって母親と同居しているのは、アメリカでは珍しいほうなのですが、そのヴァレリーが、郵便局職員で同年のラスティーと婚約することになりました。婚約の式があって、私もそれに参加したのです。しかし、婚約の式といっても、みんなで一緒に簡単な夕食を食べただけでした。 ある日の夕方、仕事を終えた半袖開襟シャツ姿のラスティーが、半ズボンで運動靴を履いた六十代の父親を連れて現れました。母親は何年か前に亡くなったそうです。この二人にヴィッキー親子と私を加えて、五人で食卓を囲みました。 彼らはみんな熱心なクリスチャンです。食事前の祈りを捧げて、やがてラスティーがちょっと改まった口調で結婚申し込みの言葉を述べ、それに対してヴァレリーが、「喜んでお受けします」と答えます。あとは、ラスティーの父親とヴィッキーから一言ずつお祝いのことばがあり、「証人」の私も一言述べて、それでめでたく「式」は終わりました。費用は食事を含めても三〇ドルはかからなかったでしょう。 バブルがいつ崩壊するか、資産家たちがみな戦々恐々としているなかで、ヴァレリーはいま、来年春三百人を招待して教会で結婚式をあげるのに、全費用約八千ドル(約九十万円)でやりくりする算段をしているそうです。 No,1〜No,10へ No,11〜No,20へ No,21〜No,30へ No,31〜No,40へ No,41〜No,50へ |