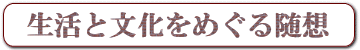
No,41〜No,50
溝口祭典「こすもす倶楽部」会報紙『木洩れ陽』連載
長生きすることの意味 ―生活と文化をめぐる随想(50)― (2006.07.01) いまから約二千二百年前、中国・秦の始皇帝が、斉の国出身の徐福に命じて、不老不死の秘薬を探しに行かせたことが、中国の歴史書『史記』に記されています。 徐福は、往復三十年分の諸経費にあたる金銀財宝を準備し、衣・食・住の専門家などを含めた三千人を引き連れ、八十五隻の大船団を組んで遥かに遠い東海の国へ出かけたのですが、結局は、不老不死の秘薬をもって本国へ戻ることはありませんでした。始皇帝は、死ぬ間際まで、徐福の帰りを待ち侘びていたといいます。いつまでも生きていたいという「永遠の生命」への願望は、始皇帝の権力と財力をもってしても、叶えられませんでした。 不老はともかくとして、不死については、別に王者や権力者でなくても、多くの人々が、できればそうありたいと、ひそかに抱いている根強い願望といってもよいでしょう。もし、「不死の妙薬」と称するようなものが本当に現れたとしたら、家や財産をすべて売り払っても、その妙薬を手に入れたいと思う人が続出することになるのかもしれません。 むかし、私がまだ大学生であった頃、知人の実業家のMさんという人が癌で亡くなった話を、母から聞いたことがありました。かなりの資産をもっていた人でしたが、東京の病院で、余命いくばくもないと言われたとき、Mさんは、病床から手を伸ばして主治医の腕をしっかり掴み、自分の財産を全部差し上げるから、なんとかいのちを救って欲しい、と頼んだというのです。死は、それほどまでに怖ろしく、避けて通りたいものであり、人間が「死ぬ存在」であることがわかっていても、その訪れが一日でも遅くなることを切望するのが普通です。 しかし、人間は本来は霊的な存在ですから、霊的な観点からみると、長生きの意味も捉え直さなければならなくなります。年齢の数が少しでも多くなるのが大切なのではなくて、本当に大切なのは、私たちが生きているうちに、どの程度まで霊的に成長していけるか、ということになるからです。それを霊界の高位霊シルバー・バーチが、つぎのように教えてくれています。(『シルバー・バーチの霊訓』10、潮文社、62-63頁) 《肉体が地上で永らえる年数を長びかせることは神の計画の中にはありません。リンゴが熟すると木から落ちるように、霊に備えができると肉体が滅びるということでよいのです。ですから、寿命というものは忘れることです。長生きをすること自体は大切ではありません。地上生活のいちばん肝心な目的は、霊が地上を去ったのちの霊界生活をスタートする上で役に立つ生活、教育、体験を積むことです。もし必要な体験を積んでいなければ、それはちょうど学校へ通いながら何の教育も身につけずに卒業して、その後の大人の生活に対応できないのと同じです。》 このように「長生きをすること自体は大切ではない」と述べられているのは、霊的な生命の永遠性を理解すると、当然のこととして納得できるように思われます。シルバー・バーチの教えでは、地上的存在には不滅はありえず、物的なものには、その役割を終えるべき時期というものが定められています。大自然の摂理の一環として、私たちの物的身体もまた例外ではありません。その摂理のパターンに従って、肉体は朽ちていくだけなのです。 しかし、肉体と違って、本当の生命は滅びることがありません。「あなたそのものは存在し続けます。生き続けたくないと思っても生き続けます」というのです。そして、こうも伝えられています。「そもそも人間は死んでから霊となるのではなくて、もともと霊であるものが地上へ肉体をまとって誕生し、その束の間の生活のためではなく、霊界という本来の住処へ戻ってからの生活のために備えた発達と開発をするのですから、死後も生き続けて当り前なのです。」(前掲書、20-21頁) 世界保健機関 (WHO) が今年の四月に発表した「世界保健報告06年版」では、日本人の平均寿命は男性が七八・六歳、女性が八五・六歳です。男女平均では八二歳を少し超えて、世界一の長寿国とされています。しかし、その一方では、自殺者が年間三万人を超えるという深刻な問題も起こっています。人口十万人あたり二五・二人という高い比率です。 長寿国で幸せであるはずなのに、これほど多くの自殺者を出して、近頃の日本の社会では心の貧しさが露わになってきました。どうしたら私たちは、このモノが溢れて金銭欲が横行する風潮のなかで霊的成長に関心をもち、優しさと思いやりを周りの弱い人々に向けられることになるのでしょうか。私たちが自分は誰かを知り命の本質に目覚めて、本来の心の豊さを取り戻していかなければならない時期は、もう来ているのにと思えてなりません。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 念ずれば花ひらく ―生活と文化をめぐる随想(49)― (2006.05.01) 「祈り」は最古の医療ともいわれますが、病気治療に「祈り」は本当に効果があるのでしょうか。それを実際に研究してきたアメリカでの実例が「朝日新聞」に載っていました。(二〇〇六・四・一) その研究は、ペンシルベニア州のジョン・テンプルトン財団が資金提供して、今回は六回目であったそうです。アメリカで心臓手術を受けた約千八百人を対象に、患者を知らない人に祈ってもらって、手術の結果への影響が調べられました。そして、「今回の厳格な研究では、効果は確認されなかった」とする声名が発表されたのです。過去の研究では、第三者の祈りが治癒に効果を与える可能性が指摘されていたといいます。 AP通信によりますと、今回の研究では、患者とは関係のないボランティアが「手術が成功して早く回復し、合併症が起きないように」と祈ったのだそうです。手術の成功については、祈りの効果はみられなかった。逆に、祈りが行われていることを知っていた患者の五九パーセントが三〇日以内に合併症を起こしたのに対し、知らなかった患者は、五二パーセントと、祈りの「マイナス効果」さえ見られた、と伝えられています。 祈りというのは、本来、霊的行為で、私たちのまわりに存在するより高い霊的エネルギーに心をこめて波長を合わせる手段であるといっていいでしょう。ですから、この研究の結果の、マイナス効果があるかないかも論外で、霊力を試してみようとするような「機械的な」祈りには、もともとなんの効果もないことを示しているのではないでしょうか。 霊界から多くの叡智のことばを伝えてくれているシルバー・バーチは、かつて、祈りの効用について、次のように述べたことがありました。 (祈りが聞き届けられるかどうかは)祈りの動機と祈る人の霊格によります。ご承知のとおり宇宙はすみからすみまで法則によって支配されており、偶然とか奇跡とかは絶対に起こりません。もしもその祈りが利己心から発したものであれば、それはそのままその人の霊格を示すもので、そんな人の祈りで病気が治るものでないことはいうまでもありません。ですが、自分を忘れ、ひたすら救ってあげたいという真情から出たものであれば、それはその人の霊格が高いことを意味し、それほどの人の祈りは高級神霊界にも届きますし、自動的に治療効果を生む条件を作り出す力も具わっています。要するに祈る人の霊格によって決まることです。(『シルバー・バーチの霊訓(6)』潮文社、一九八六年、四六頁) このように、利己的でない真の意味での祈りには必ずそれなりの効果があると考えていいでしょう。詩人の坂村真民氏には、その祈りの効果を詠ったつぎのような詩があります。 念ずれば 花ひらく 苦しいとき 母がいつも口にしていた このことばを わたしはいつのころからか となえるようになった そうしてそのたび わたしの花がふしぎと ひとつひとつ ひらいていった 坂村氏は、この詩で信仰の大切さを説いているのですが、もちろんこれも、念じさえすれば花開くというのではないでしょう。坂村氏は、信仰というのは要するに「疑うな」ということであると、「疑えば花開かず、信心清浄なれば、仏を見たてまつる」という仏典「大蔵経」の解説書「十住昆婆沙論」のことばを引用していました。 坂村氏によれば、現代人の不幸は、科学万能の現代社会の病理のなかで、人間と自然が乖離してしまっていることである、といいます。すべての生きものと共存することを忘れ、自然のいのちにも気がつかず、「念ずれば花ひらく」と聞いても、心ない人は、「そんなばかなことがあるものか」と、頭から受けつけようとはしません。学校の教師が生徒に、「そんなのは迷信にきまっている。お前そんなにいうなら、ここで念じてみよ、花が開くか?」などと椰楡したりもするのだそうです。教育テレビの番組で見た坂村氏は、「それでは花は開きませんわな」と嘆いていました。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 心に抱く思念の力 ー生活と文化をめぐる随想(48)ー (2006.03.01) 私たちが頭の中で何を考えていようが、それは目には見えませんから、まわりの人にはわかりません。しかし、こころのなかで思っていること、思念には、力があるということを私たちは知っておく必要があるでしょう。 戦後まもなくの頃、「リーダーズ・ダイジェスト」日本語版のなかで、アメリカ南部で起きたある裁判の記事を読んだことがあります。食料品店かどこかで、黒人男性からじろじろ見られて、その視線が体にまつわりついたという白人女性が、その黒人男性を訴え、男性は、婦女陵辱罪で有罪にされたというのです。当時中学生であった私は、じろじろ見ただけで有罪というのは、黒人蔑視の人種差別ではないかと、憤りを感じたことを覚えています。 その後、聖書のマタイ伝のなかに、「だれでも情欲をいだいて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである」(5-28)というイエスのことばを見つけた時、あの時のアメリカ南部の裁判で、黒人が有罪にされたのは、この聖書のことばが根拠になっていたのかもしれないと思いました。もちろん、白人男性が黒人女性をじろじろ見たとしても、おそらく同じような裁判沙汰にはならなかったでしょうから、あの時の有罪判決は、理不尽な人種差別であったことは間違いないでしょう。 それからさらに歳月が流れて、その後の私は、思念は、実は、強い力をもっていることを教えられてきました。「思念は思念の世界においては実在そのものです。が、地上においてはそれを物質でくるまないと存在が感識されないのです。肉体による束縛をまったく受けない霊界では、思念は物質よりはるかに実感があります」とシルバー・バーチは『霊訓7』(潮文社)で述べています。 冒頭の例のように、「情欲を抱いて女を見る」のは決していいことではありませんが、同様に、この地上世界では、嫉妬心や恨みなどで誰かを憎んで、「殺してやりたい」と頭の中で思ったとしても、それがあからさまな行動となって表れない以上、少なくとも法的には罪に問われることはありません。しかし、本来の私たちは霊的な存在で、このような「殺してやりたい」という思いは強い力をもっていますから、目には見えなくても、毒素のように、相手に降りそそぐと考えていいでしょう。そして問題は、その「毒素」が、それを吐き出した本人にもはね返ってくることです。 たとえば、怒りに任せて人を殴りつけたとしても、その怒りは決して収まりません。かえってその怒りは増幅されたかたちで返ってきて、自分自身を余計に苦しめることになるようなものです。シルバー・バーチは、「嫉妬心、貪欲、恨み、憎しみといった邪念を、精神的次元で捉らえた場合、身体的行為よりも大きな悪影響を及ぼします。思い切り人をぶん殴ることによって相手に与える身体的な痛みよりも、その行為にいたらせた邪念が当人の霊と精神に及ぼす悪影響の方がはるかに強烈です」と述べています。(『霊訓6』潮文社) 小林正観『22世紀への伝言』(弘園社、二〇〇五年)のなかにも、この思念の力を示す興味深い例がとりあげられていました。 南太平洋のある国に、未開の部族がいて、いまでも石器時代のままの生活をしているのだそうです。当然、鉄製の道具などはなく、鋸も斧も持っていません。ジャングルを縦横に駆け巡る彼らにとって、通行の邪魔になる大木があるとしたらどうするでしょうか。何人もの人間で囲まねばならないほどの大木です。彼らの持っている道具といえば、石斧や槍、弓といったもので、それらの道具では直径何メートルもある大木は切り倒すことはできません。しかし、彼らはちゃんとその木を倒し、道を作るというのです。 どのように木を倒すかといいますと、部族総出でその木を囲み、来る日も来る日もその木に向かって罵倒し続けるのです。「邪魔だ」「お前など死んでしまえ」などと怒鳴り続けると、一〜二週間で葉が枯れ始め、一か月もすると、どうーと木が倒れてしまいます。「昔の話ではなく、現在も実際に行われている方法だそうです」と、この著者は述べています。 ことばは思念ですから、この例も思念の力をよく示しているといえますが、一か月もこのような罵詈雑言を吐き続ければ、生きている大木だけではなく、当然、部族側にもそのことばの持つ毒素が跳ね返ってくることになります。木を倒す正当な動機があるにせよ、このような部族では、おそらく不和や争いが多く、人々も短命であると思えてなりません。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 地上に宝を蓄えてはならない ー生活と文化をめぐる随想(47)ー (2006.01.01) 近頃はいろいろな面で社会的な或いは道徳的な荒廃が目立ってきていますが、そのうちの一つが、度の過ぎた金銭欲の横行でしょう。株の買占め事件で話題になったある I T企業社長の若者が、「カネで買えないものなどあるはずがない」と豪語しているのを見てちょっと驚いたりしましたが、いまの世の中では、そのような大きな思い違いも、あまり違和感もなく受け入れられているのかもしれません。 最近では、建築業界での耐震強度の偽装事件が社会的な大問題になりました。「他社に負けないためのコストダウン」と称して、利益を得るためには設計段階での徹底したコスト削減が不可欠であるとし、結果的に、数多くのマンションやホテルで違法の欠陥建築を生み出してしまったわけです。金銭的な利益のためには、地震時の建物倒壊の危険や人命尊重を考えることなどは二の次三の次で、全く省みられなかったことになります。 みずほ証券がジェイコム株で誤った注文を大量に出してしまった問題もありました。その機に乗じて、欧州系金融機関の UBSグループが約百二十億円の利益を得るなど、結果的にはみずほ証券の損失は、約四百億円にもなったといわれています。政治家たちから「東証のシステムトラブルに乗じた火事場泥棒だ」などと批判されたこともあったからでしょうか、巨利を得た証券会社などからは、何らかの形でその利益金を返還しようとする動きも出てきているようです。一応「合法的」に取得したつもりではあっても、やはりそれは行きすぎであったと認識し始めたのでしょう。 それにしても、この凄まじいまでの金銭争奪戦には、こころが寒々と冷え込んでしまう思いがします。なかには、個人投資家で、この誤発注に乗じて五億円とか二十億円とかを手にした二十歳代の若者たちもいたということですから、他人事ながら、やはり、少し心配になります。うらやましいと思う人もいるかもしれません。しかし、これは彼らのためには、本当の意味で、決して幸せなことではないでしょう。 聖書のマタイ伝(6-19)に、「あなたがたは自分のために、虫が食い、さびがつき、また、盗人が押し入って盗み出すような地上に、宝をたくわえてはならない」ということばがあります。宝は、地上ではなく、天に蓄えることを教え諭しているのです。五億円であろうが、二十億円であろうが、或いは、百二十億円であろうが、それは人のため世のために還元するのでなければ、天には蓄えることの出来ない「ごみ」「がらくた」のようなものでしかないのでしょう。 私たちは、自分名義の土地や家や預金通帳の残高が、確かな自分の財産だと考えがちです。しかし、この競争社会の中で自分が手に入れたもの、或いは、他人から与えられたものが財産ではなくて、自分が他人に与えたものこそが、おそらく、本当の財産なのでしょう。与えるものは、金銭とは限りません。また、金銭も多い方がいいとは限りません。優しさ、思いやり、あたたかい言葉、人のために尽くすこと、それらの人に与えてきたものの総量が、自分が天に蓄えることの出来る朽ちることのない財産であろうと思います。 私たちは、この地上に生まれてきてやがて「死んで」いきますが、それでいのちが終わりと考えるのであれば、いくら「ごみ」「がらくた」であっても、金銭にしがみつくのはわからないわけではありません。しかし、私たちが永遠のいのちの中で、その一瞬を、私たちの魂を磨くためにいまこの地上に生きているという認識に立つと、ものの見方は大きく変わってきます。そのことを、霊界からの教えをまとめた『霊訓(6)』(潮文社・一九八六年)のなかで、シルバー・バーチはつぎのように述べています。(一七九頁) 《物的存在物はいつかは朽ち果て、地球を構成するチリの中に吸収されてしまいます。ということは物的野心、欲望、富の蓄積は何の意味もないということです。一方あなたという存在は死後も霊的存在として存続します。あなたにとっての本当の富はその本性の中に蓄積されたものであり、あなたの価値はそれ以上のものでもなく、それ以下のものでもありません。そのことこそ地上生活において学ぶべき教訓であり、そのことを学んだ人は真の自分を見出したという意味において賢明なる人間であり、自分を見出したということは神を見出したということになりましょう。》 金銭的な欲望が渦巻く中で、その渦に呑みこまれて休む間もなくあくせくと走りまわり、自分自身をも見失ってしまうというのは悲しいことです。一度立ち止まって、豊かさとは何かを静かに考え直してみることも、いまの世では、大切なことなのかもしれません。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 コナン・ドイルの霊界からのメッセージ ー生活と文化をめぐる随想(46)ー (2005.11.01) コナン・ドイルは、よく知られているように、イギリスの推理作家で、あの名探偵の象徴ともいうべきシャーロック・ホームズの創作者です。推理小説というジャンルに初めて手を染めたのはエドガー・アラン・ポーであるといわれていますが、それを確立させたのがコナン・ドイルでした。彼が打ち立てた推理小説のスタイルは、アガサー・クリスティをはじめとする以後の作家にも受け継がれ、今日に至っています。 コナン・ドイルは一八五九年五月二日にエディンバラに生まれ、エディンバラ大学の医学部で学びました。一九八二年にポーツマスで医師を開業したのですが、患者が少なく暇であったことが、小説の執筆に力を入れるきっかけになったといわれています。しかし彼には、もう一つ、熱心な心霊研究家としての顔がありました。晩年には文字どおり文筆家としての栄光に満ちた経歴さえ投げ捨て、数多くの国々へ講演旅行に出かけたり、論文を書いたりして、心霊思想の普及のために献身しました。彼は一九三〇年七月七日に七十一才でこの世を去りましたが、死亡後も霊界で生き続けていることを、霊媒を通じての通信で証言を行ったりしています。 一八八二年に医学生としての課程を終えた頃のコナン・ドイルは、他の若い医者と同じく、肉体や生命に関しては確信に満ちた唯物主義的概念を抱いていました。そして、人間は死んだら土に帰っていくだけだと考え、死後も生き続けるなどということは、全く信じてはいなかったのです。 その彼は、一八八六年頃、偶然、『エドマンズ判事の回想録』という本を手に入れます。著者のエドマンズ氏は、当時、ニューヨーク州最高裁判所の判事で、高い人望を得ていましたが、同時に心霊現象の解明に意欲を燃やしていた心霊研究家でもありました。 彼は当初、心霊現象をトリックとみなして、それを暴く目的で交霊会に参加したようです。しかし、どのように考えても真実としか思えない現象を体験させられて、その真相解明に乗り出したのが心霊思想に深入りするきっかけとなりました。ところが、判事という職業柄、世間の眼はやがて批判的になり、「エドマンズ判事は、裁判の判決のことまで霊能者にお伺いをたてている」というような噂まで広がるようになって、結局、彼は法曹界から身を引きます。その後は、自由な立場で心霊思想の普及に努めたという人物です。 そのエドマンズ氏の本の中に、亡くなった夫人が交霊会に出てきて、エドマンズ氏と語り合うということが長期間にわたって続いたという話が紹介されていました。その内容は実に細かく具体的で、コナン・ドイルは大いに興味をもつようになります。 その後、コナン・ドイルは、心霊関係の本を片っ端から読み始めるようになりました。そして、実に多くの学者、特に科学界で権威をもった人たちが、霊と肉体とは別個の存在であり、死後にも存在し続けることを完全に信じ切っていることを知って驚ろかされます。たとえば、英国第一級の化学者であるウイリアム・クルックス、ダーウインのライバルである博物学者のアルフレッド・ウオレス、世界的な天文学者のカミユ・フラマリオンなどといったそうそうたる学者たちでした。 コナン・ドイルは一八九一年にロンドンの当時の心霊研究協会に入会します。それからは、協会が所有する調査研究の報告書を次から次へと読んでいきました。このようにして、小説家のコナン・ドイルは、やがて、熱心な心霊研究者として、心霊思想の普及に余生のすべてを捧げるようになっていったのです。 彼が、死後も霊界から送ってきたメッセージは日本でも翻訳され、『コナン・ドイル 人類へのスーパーメッセージ』(講談社)として一九九四年に出版されました。そのなかで彼は、「私は言葉に表すことができないほど美しい霊界にいます。この現実を地上にいる私の友人たちに伝えることが私の最大の願望です」と言って、多くの証言を書き綴っています。「死んだ」と思い込んでいる愛する家族も、決して死んではいない。霊界では元気に生き続けている。だから、霊界の家族とも接触しようと思えばお互いに連絡をとることさえできるのだと、つぎのようにも述べています。 愛する者との再会ほど喜びに満ち、こころを慰めてくれるものがあるでしょうか。いまは亡き父、母、夫、妻、兄弟、姉妹、子供と再びこの世とあの世との壁を越えてこころを通わせられるということを知るほど、こころからの喜びがあるでしょうか。それは本当のことなのです。素晴らしいことに本当のことなのです。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 「悪人」だからこそ救われる ー生活と文化をめぐる随想(45)ー (2005.09.01) 『歎異抄』に出てくる親鸞の悪人正機説はよく知られていますが、この「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」の「悪人」をめぐっては、いろいろの受け取り方がされているようです。「善人でさえ往生できるのだから、悪人が往生できないことがあろうか」というのですから、世間の常識とは逆のようで、ちょっとわかりにくいかもしれません。 その『歎異抄』の第十三章には、次のような話があります。 あるとき親鸞聖人が弟子の唯円に、「おまえは私の言うことを信じるか」と訊いたことがありました。唯円は、「もちろんでございます」と答えます。すると、「そうか、それなら私のこれから言うことに決して背かないか」と重ねて訊きなおした上で、「それでは、どうか、人を千人殺してくれ。そうしたらおまえは必ず往生することができる」と言ったのです。 唯円はさぞ驚いたことでしょう。たじたじとなって、「聖人の仰せですが、私のような人間には、千人はおろか一人だって殺すことができるとは思いません」と答えました。それを聞いた親鸞は、「それではどうしていまおまえは私の言うことに決して背かないと言ったのか」と問い返して、こう言いました。「これでおまえもわかるであろう。人間が心にまかせて善でも悪でもできるのならば、往生のために千人殺せと私が言ったら、おまえはすぐに千人殺すことができるはずではないか。しかしおまえが一人すら殺すことができないのは、おまえの中に、殺すべき因縁が備わっていないからなのだ。」 「因縁が備わっていないから殺さないだけだ」ということばには深く考えさせられますが、親鸞は「自分の心がよくて殺さないのではない。また、殺すまいと思っても百人も千人も殺すことさえあるのだ」とも言いました。 親鸞はこのように、人間というのは誰にでも悪を犯す可能性があり、そのような悪の可能性を秘めた人間を救済するのが阿弥陀仏の慈悲であると説いてきました。この阿弥陀仏の慈悲が「他力」ということでしょう。因縁に支配されている弱い人間は、「自力」では自分を救うことができませんから、「他力」によってのみ救われるということで、この意味でも他力念仏というのは、この悪を犯す可能性を秘めた弱い人間であることの自覚のうえに成り立っているといえるかもしれません。 親鸞は、自分がそのような弱い人間であることを強く意識していました。第二章のなかには、親鸞自身の「いづれの行(ぎょう)もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定(いちじょう)のすみかぞかし」という告白があります。第三章にも、「煩悩具足のわれらは、いずれの行にても生死をはなるることあるべからざる」とあります。これが親鸞のいう「悪人」で、親鸞は自分自身を含めて、そういう自覚を持った人を「悪人」といっているのです。 自ら善行に励み、自力で極楽往生できると思っている人が「悪人」に対する「善人」ですが、こういう人には、ひたすら阿弥陀佛に縋ろうとする気持ちが強くはないかもしれません。しかし、そういう「善人」であっても、自力の心を入れ替えて、阿弥陀佛に縋れば、極楽浄土へ行くことができるようになるというのです。それが善人の往生です。 自力というのは、このように、あくまでも弱い人間の力です。たとえば、私たちがこの世で、いくら他人に同情し、気の毒に思うようなことがあっても、私たちの力だけでは助けおおせるものではありません。そういう「慈悲」は所詮中途半端なのです。ですから、親鸞は、中途半端な慈悲の自力ではなく、徹底した大慈悲心、つまり阿弥陀仏による他力のみが衆生を救えるのだ、と考えていました。善人であっても自力のこころを入れ替えて、阿弥陀仏に縋らなければならない、というのも、自力の狭い限界を諭しているのでしょう。 これに対して、「悪人」というのは、前述のように、悪を犯す可能性を秘め、さまざまな欲望に翻弄されながら、修行によってもこの苦悩の世界から逃れられないでいる人々のことです。しかし、阿弥陀佛の本当の願いは、むしろ、このような「悪人」を成仏させることにあったはずでした。だから、自分ではなにも善行を行うことがなくても、ひたすら「他力」に縋ろうとする「悪人」のほうが、かえって、阿弥陀佛の救いに値する人々ということになる、と親鸞は教えているのです。 弱い、罪深い悪人の自覚を持つ親鸞は、阿弥陀仏の大慈悲、言い換えれば、宇宙にあまねく漲る人類救済の巨大エネルギーの存在を確信して、念仏により、そのエネルギーに連なっていくことを、一生懸命に説いてきたということになるのかもしれません。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 親を選んで生まれてくる子供たち ー生活と文化をめぐる随想(44)ー (2005.07,01) 旧約聖書(伝道11・5)に「あなたは身ごもった女の胎のなかで、どうして霊が骨に入るかを知らない。そのように、あなたは、すべての事をなされる神のわざを知らない」ということばがあります。これは人間にとって極めて大切な、いのちと神についての教えです。 いのちについては、私たちは、赤ちゃんが生まれますと、「生命の誕生」というふうに考えます。しかし、正確には、赤ちゃんの体が生命ではありません。本来、生命は肉体とは別にあって、それが妊娠のときに体に入り込んでいくと教えられています。つまり、肉体に霊が入って、いのちをもった人間になり、霊が出ていけば、霊のない肉体「死人」になるということです。 それでは、霊であるいのちは、肉体にいつ入っていくのでしょうか。これは、「霊的視力」をもっている人のことばに頼るほかはないのですが、たとえば、シルバー・バーチは「精子と卵子が合体して、ミニチュアの形にせよ、霊が機能するための媒体を提供したとき」(『霊訓(四)』潮文社、'86・53頁)と言っています。また、「幸福の科学」の大川隆法氏は、それをはっきりと、「妊娠後、満九週目に入ったとき」と断言しています。「満九週目になると、確実に魂が体内に宿ります。その日時も特定できます」と氏は言い、「胎児の魂が入る」状況を、氏は何度も目撃した、とも述べています(『永遠の生命の世界』幸福の科学出版、'04・165頁)。 科学では解明できない難しい問題ですが、冒頭の旧約聖書のことばは、あなたはそういういのちのあり方も知らないように、神が全知全能でこの宇宙のすべてを支配していることも知らない、といっているのです。これは別の見方をすれば、それらの霊的真実を学びなさいと諭されているのではないでしょうか。 霊魂の存在というのは、よくいわれますが、これも、人間の体に霊魂が付属しているのではなくて、霊魂に人間の体が付属していると考えなければならないでしょう。あくまでも霊魂が主体であって、肉体は従属的な存在なのです。そして、その霊魂がいのちであって、肉体がいのちではありません。ですから、肉体が滅びても、いのちである霊魂は永遠に生き続けます。霊魂には死はないのです。 大切なことは、この霊魂が肉体に宿るとき、意識的にその相手の肉体を選ぶ、つまり、親や生活環境を選ぶということです。このような問題を理解していくのには、ほとんど霊界からの証言だけが頼りですが、たとえば、シルバー・バーチは、つぎように述べています。 《地上に生を享ける時、地上で何を為すべきかは魂自身はちゃんと自覚しております。何も知らずに誕生してくるのではありません。自分にとって必要な向上進化を促進するにはこういう環境でこういう身体に宿るのが最も効果的であると判断して、魂自らが選ぶのです。ただ、実際に肉体に宿ってしまうと、その肉体の鈍重さのために誕生前の自覚が魂の奥に潜んだまま、通常意識に上がって来ないだけの話です。》(『霊訓 (一)』潮文社、'88・38頁) シルバー・バーチは、さらに、つぎのようにも言っています。これは、輪廻転生の一端をも示している重要な真実といっていいかもしれません。 《霊界にはすでに地上生活を体験した人間が大勢います。その中にはもう一度地上へ行って果たさねばならない責任、やり直さなければならない用事、達成しなければならない仕事といったものを抱えている者が沢山います。そして、その目的のためのチャンスを与えてくれる最適の身体を求めているのです。》 (『霊訓(四)』63頁) このように、子供たちは、それぞれに親を選んで生まれてきます。この場合、「最適の身体」というのは、生活に何の不自由もないお金持ちの親ということではないでしょう。おそらくその逆で、いろいろと苦難や悲しみを経験し、それらを克服して喜びや心の安らぎを掴み取っていくことなど、様々な修行を積むことができる環境ということなのです。 私たちの世界で、人々が毎日あくせくと必死に求めようとしている地位や財産や権威などは、霊界では何の価値もありません。そんなものは肉体が滅びると同時に消えてなくなるだけなのです。本当に価値があるのは、人のこころの優しさや他人に対する思いやりでしょう。博愛と献身から生まれる他人への善行こそ、その人の霊性を高め、魂に消えることのない栄光を刻み込んでいきます。それが本当の意味でのその人の財産です。そのような資質を身に着けていくために、修練の場として「最適の」親を選んで生まれてくるというのが、霊界から教えられている真実です。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 宇宙のなかで生き続けるいのち ー生活と文化をめぐる随想(43)ー 2005.05.01 世界には各地にいろいろと歴史的遺産が残っていて、現在私たちは、それらの遺跡をこの目で見ることができます。たとえば、イタリアのローマでは、二千年前のフォロ・ロマーノを見ることができますし、エジプトのギザでは、四千年以上も前のピラミッドやスフィンクスを目の前にすることができます。しかし、二千年前のローマ人たちが動きまわっている姿や、四千年以上も前のエジプト人がピラミッドやスフィンクスを作り上げている状況などは、見ることができません。 当たり前のことを言っているようですが、これは何故でしょうか。それは、私たちがこの小さな同じ地球上で、イタリアやエジプトにあまりにも近い所にいるからです。 仮に、私たちが宇宙に飛び出して、二千光年かなたの星からこの地球を眺めるとするとどうでしょうか。それだけ離れていても見える望遠鏡があると仮定すると、その望遠鏡には、ローマ人たちが、いま、生きて動きまわっている姿が見えます。四千光年離れた星からは、ピラミッドの建造などで働かされているエジプト人の姿が、いま、見えるはずです。逆に、それらの星からは、現代の私たちの姿は、まだ、見ることができません。 音の速さというのは、一秒間に約三三〇メートルですから、たとえば、三三〇メートル離れたところで杭を打っている音は、ちょうど一秒後に私たちの耳に聞こえてきます。しかし光は毎秒約三〇万キロの速さで進みますから、一秒間では、地球を七・五回も廻ってしまいます。この光速で計ると、太陽から地球までの距離は「約八分」です。つまり、私たちが見ている太陽は、常に八分前の太陽であって、いまこの瞬間の太陽ではありません。 昨年の一二月一日、アメリカの宇宙望遠鏡科学研究所は、これまで見つかった中ではもっとも幼い赤ちゃん銀河の画像を公表しました。ハッブル宇宙望遠鏡で撮影したもので、その写真には、「たった五億歳の赤ちゃん銀河」とキャプションがつけられていました。広大無辺の宇宙では、五億歳でも、「たった五億歳の赤ちゃん」なのです。 これとは対照的に、日本の国立天文台と東京大学のチームが、今年の二月に、最古・最遠の銀河団を発見したという発表がありました(「朝日」2・18)。このチームは、二〇〇二年以来、ハワイに設置した高性能のすばる望遠鏡で調べた結果、五百個を超える銀河が見つかり、そのうちの六個は、地球から約一二七億光年離れて、直径三百万光年という「狭い」範囲に固まっていたというのです。 宇宙自体の年齢は、現在、一三七億歳とするのが有力な説になっているようですから、これは、宇宙誕生後の約一〇億年後の姿を捉えたということで、したがって、もっとも古い銀河ということになるようです。それにしても、地球から光の速さで約一二七億年かかる距離にあるというのは、気が遠くなるような宇宙の彼方です。そして、この場合も当然のことながら、私たちは、この銀河の約一二七億年前の実像を見ているわけで、二〇〇五年現在の姿を見ているわけではありません。 このように、宇宙はあまりにも広すぎて、しばしば、私たちの関心も及ばなくなってしまいがちですが、しかし実は、この宇宙が私たちのいのちのふる里といっていいのだと思います。宇宙の永い歴史を通じて宇宙で作り上げられてきた無数の星々の素材である原子が、はるばると一三七億年の旅をしてきて、いま私たちのいのちを支えている体の素材となっているからです。 私は、かつて学生たちに、あなた方は地球という星の子で、二〇年やそこらでいまの自分になっているのではない。いのちの誕生は、地球生成の四六億年と不可分であるとすれば、自分の年齢は、少なくとも四六億年プラス二〇年と考えたほうがいい、というようなことを言ったことがありました。しかし、広大な宇宙の中では、この地球もほんの米粒一つのような小さな存在になってしまいます。やはり私たちは、地球の子であるよりは、宇宙の子と言ったほうがいいのかもしれません。 そのように考えていきますと、次のような、霊界の高位霊シルバー・バーチのことばも、少しは身近に響いてくるように思われます。 《人間の多くの悩みが絶えないのは、無意識のうちに物質の世界にのみ生きていると思い込んでいるからです。本当はあなた方と私とは同じ宇宙の中に存在するのです。霊界と地上とが水も漏らさぬように区別されているのではありません。互いに融合し合い調和し合っています。死ぬということは物的身体による認識をやめて霊的身体によって魂の別の側面を表現しはじめるということに過ぎません。》 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 早く行きたいとは思えない極楽浄土 ー生活と文化をめぐる随想(42)ー 2005.03.01 むかし、私が思いがけない家族の死に直面して嘆き悲しんでいたときに、毎日のように仏壇に向かって、「仏説阿弥陀経」を唱えていたことがありました。これは、お釈迦様が大勢の弟子たちを前にして、西の方はるか彼方に、極楽という世界があることを教えているお経です。そのお経には、極楽浄土の様子がつぎのように詳しく描かれています。 |