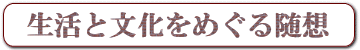
No,11〜No,20
溝口祭典「こすもす倶楽部」会報紙『木洩れ陽』連載
|
奪われてもほほえむ ー生活と文化をめぐる随想(11)ー 2000.1 「奪われてもほほえんでいる者は、盗人からいくらかでも取り戻す。けれども、奪われて嘆き悲しんでばかりいる者は、自分で自分を傷つけ、奪われ損をするだけだ」。これは、シェイクスピアの作品『オセロ』のなかに出てくることばです。 才色兼備のデズデモーナが黒人の将軍オセロを愛するようになり、結婚の意志を固めたとき、自慢の娘をオセロの策略で奪い取られると勘違いしたデズデモーナの父親が、ベニス公に訴え出ました。ベニス公は、デズデモーナの意志を確認した上で、父親に諭して言ったのがこのことばです。 「娘を奪われる」としたら穏やかではありませんが、このことばを、たとえば、恋を「奪われる」失恋の場合に置き換えて考えてみましょう。失恋の苦しみは耐え難く、しばしば自分の命さえ縮めたりしますが、しかし、どんなにもがいても苦しんでも失われたものは返ってきません。その場合、もしたった一つ、救われる道があるとすれば、それはやはり、静かにほほえんでいることのようです。 ほほえむことができたとき、人間は確実に成長して、「奪われた」経験が逆に、大きな恵みとなり、苦しみはうそのように消えて、こころは穏やかに優しくなれるのでしょう。 人間関係ばかりでなく、モノや金銭を奪われるというような場合にも、こういうことばは、少しは気持ちを安らかにしてくれることがあるかもしれません。私にもいままでに何度か、そのような経験があります。 むかし、私の父が癌で亡くなる前、病院の個室の枕の下あたりに、札束の封筒を入れておいたことがあります。体が動けなくなることを予想していた父が、病院の費用や見舞いにくる子供たちに小遣いを与えたりするのに用意していたお金でした。そのお金は、父が亡くなったときには気が動転していて、病室に置き忘れてしまいました。あとで気がついたので「後の祭り」です。でも、そのお金は誰かが有効に使ってくれたはずだと考え、あまり損をしたという気にはなりませんでした。 ちょっと情けない話もあります。電車の中でスリに財布を抜き取られたことが二度ほどあるのです。二度とも、スリの手口があまりにも見事で、私はほとほと感心し、スリを憎むような気持ちがおこりませんでした。海外で十分注意していたつもりなのに、カメラバッグをこれも見事な手口で盗まれたこともあります。 これらは、結果的にはスリや泥棒を援助していることにもなるわけで、自分のだらしなさを反省しなければならないのですが、私はそれでも、高い授業料を払ってスリや泥棒に人生の「特別指導」をしてもらったような気持ちがしないでもありません。 このような私の経験から言っても、この「盗まれてもほほえむ」というのは、なかなか効き目のあることばのようです。しかし、まだその上のことばもあるのです。イエス・キリストは、旅の途中で弟子の一人が衣を盗まれて嘆いているときに、「盗まれるような物になんの価値があるのか。泥棒を捜し出して残りの物も与えなさい」と諭しました。このような広く大きな愛のことばには、ただ粛然として頭を下げるほかはありません。 でも世の中には、こういう小さなモノの「損失」だけではなく、様々な形の大きい「損失」も無数にあります。私にも、父が長年にわたって営々として築き上げてきた事業を、私の代になって倒産させてしまったということがありました。これはやはり大きな痛手でした。「ほほえむ」どころではなく、しばらくは後遺症が残りましたが、しかしそれもやがて薄らぎ、いまではあれはあれで「よかった」のだと、思えるようになりました。 結局、自分に起こるいろいろなことは、決して偶然ではなく、すべて必然なのかもしれません。そして、それらは同時に、必要だから起こったのであり、かつ起こったことは最善である、という気がどこかでしています。 いまアメリカのアリゾナで病床にあるエリザベス・キュブラー・ロス博士は、死んでいく人を愛のこころで看取っていくターミナル・ケアの世界的権威として有名です。人間の生と死について数多くの本を書いてきましたが、そのなかに次のようなことばがあります。 人が人生で直面するありとあらゆる困難、苦難、悪夢、喪失などを、多くの人はいまだに呪いだとか神の下した罰だとか、何か否定的なものと考えています。でも、本当は自分の身に起こることで否定的なことは一つもありません。あなたが経験する試練、苦難、喪失など、あなたが、もしこれほどの苦しみだと知っていたら、とても生きる気にはなれなかっただろう、というようなことはすべて、実は、あなたへの神からの贈り物なのです。 与えることの幸せ ー生活と文化をめぐる随想(12)ー 2000.3 シェイクスピアーの『オセロ』のなかには、「貧乏でも足ることを知っている者は大金持ちも同然ですが、いくら大金持ちでも、貧乏になりはしないかと恐れている者は、その心は貧しい冬枯れです」ということばがあります。世間ではよく、金持ちは豊かであると考えがちですが、金持ちと豊かであることは必ずしも同じではないようです。むしろ、逆のほうが多いのかもしれません。 聖書の「マタイ伝」につぎのような話があります。ある金持ちの青年が、イエスに近づいて、「永遠の生命を得るにはどうしたらいいでしょうか」と尋ねました。その青年にイエスは言います。「もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝をもつようになるであろう」と。金持ちの青年は、そんなことはとても実行できないと考えて、悲しみながら立ち去りました。 その時にイエスが弟子たちに言ったのが、あの有名なラクダと針の穴の喩えです。イエスは、「富んでいる者が天国に入るのは難しい」と言った後、「富んでいる者が神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっとやさしい」と、金持ちが幸せになりにくいことを強調したのです。 この「すべてを与える」というイエスの教えを実行するのは確かに容易ではなく、誰にでもできることではないでしょう。しかし、そういう人がいないわけではありません。例えば、イタリアのアシジの聖フランシスコがそうでした。豊かな商人の子でしたが、財産をすべて投げ捨て、清貧と謙遜のなかで神の愛を説き続けました。フランシスコ会、クララ修道女会を創立し、世界中のキリスト教社会に大きな影響を与えました。 「与えられるよりも、与えるほうが幸せ」とはよくいわれることばです。聖フランシスコの例を持ち出すまでもなく、おそらくこれは、与えることが本当の意味での豊かさと幸せをもたらすからでしょう。こういうふうにみてきますと、人の財産とは、本当は預金の残高や不動産のようなものではなくて、他人に与えてきたものの総量ではないかと考えることもできます。 この場合、与えるものはお金ばかりではありません。また、そのお金も、必ずしも多い方がいいというわけではないでしょう。貧者の百円は、しばしば富者の一万円にも勝るからです。 貧しい人、力の弱い人たちにどれだけ思いやりや優しさを与えてきたか、温かいことばやほほえみを与えてきたか。そういうことが多ければ多いほど、それが財産で、その人は本当の意味で豊かで、幸せなのでしょう。 お手本は、例えば、マザー・テレサです。 「私は安いサリーを二つ持っているだけです。テレビもラジオも持っていません。休みもありません。貧しい人たちと一緒になるためです。貧しさこそ真の自由です」。そう言いながら、彼女は、貧民や孤児、ハンセン氏病患者たちへの奉仕に自分の生涯を捧げて、一九九七年九月五日に八十七歳で亡くなりました。 マザー・テレサは日本へも講演で来たことがあります。その時に、ある財界人が彼女に多額のお金を渡そうとしたそうです。彼女は「私は寄付を貰いに日本へ来たのではありません。あなたは忙しすぎてこころを貧しくしていませんか」と答えました。そしてまた、つぎのようにも言いました。「日本はインドのことよりも、日本の中の貧しい人々への配慮を優先すべきです。愛はまず手近なところから始まります」。 貧困はインドのカルカッタのスラム街だけにあるのではない。ニューヨークにも東京にもある。パンの一切れに飢えていなくても、食べ物の飢え以上に、すさまじい愛情の飢えに苦しんでいる人が沢山いる、というのが彼女の言い分でした。 太平洋戦争で負けて、貧乏のどん底から立ち上がってきた日本人は、半世紀にわたって、ひたすらに物質的な豊かさを求め続けてきました。お金が何倍にも増え、欲しいものが沢山買えるようになることが幸せだと思い続けてきたのです。 しかし、世界の経済大国にまでのし上がった日本でいま、私たちは、物質的な豊かさが必ずしも本当の幸せとは結びつかず、むしろ、家庭や社会のあり方を歪め、こころの荒廃をもたらすという逆説を、史上初めて、日常の生活の中で痛切に体験させられています。 足ることを知る豊かさ、与えることを知るよろこびーー私たちはいま、そのような、本当の意味での幸せを考える時期に来ているのかもしれません。 ベルギーの金持ちの粗食 ー生活と文化をめぐる随想(13)ー 2000.5 今年の三月、二年ぶりにベルギーを訪れて、ブリュッセル市内のほか、近郊のゲント、ブルージュ、アントワープなどの古都を廻ってきました。案内してくれたのは、徳島出身の安原久雄さんという七十二歳の元公務員です。 アントワープでは、ノートルダム寺院に掲げられたルーベンスの二枚の大作「キリストの昇架」と「キリストの降架」が有名で、日本でも『フランダースの犬』の物語で広く知られるようになりました。ゲントには、その絵を観るためだけに世界中の絵画ファンが集まってくるといわれるファン・エイクの「ヘントの祭壇画」などがあります。また、ブルージュも「天井のない美術館」といわれるほど、街中至る所に芸術品があふれています。 安原さんは西洋美術に詳しく、こういうところで、それぞれの絵がもつ深い意味合いなどを、ほかの誰よりも丁寧に解説してもらえたのは幸運でした。しかし、私にとってそれに劣らず興味深かったのは、バスの中で、あるいは一緒に歩きまわりながら、安原さんから聞いたヨーロッパの金持ちの食事の話です。 ドイツの小説家トマス・マンに『ブッテンブローク家の人々』という自伝的長編小説があります。これは、四代にわたる金持ち一家が没落していく様を内面から描いた傑作ですが、安原さんは、その没落のメカニズムは食生活にあると言います。 大体、一代目の創業者というのは、貧困から身を起こし、卓抜なアイデアと刻苦精勤によって財産を築き上げていきますが、食事は至って簡素であるのが普通です。しかも、よく咀嚼して唾液を出さなければ喉を通らないような堅いものを食べているのが特徴だそうです。 二代目になると、創業者のお陰でゆとりができ、食生活も少しは贅沢になりますが、まだ初代の苦労を知っているだけに、粗食と質素が大切な家訓のように守られています。 しかし、三代目となると、もう創業者の苦労はほとんど知らないし、遊んで暮らしても不自由しないような有り余る財産があるので、食生活はがらりと変わってしまうのです。 堅いものは食べなくなり、スープ、コンソメ、ポタージュ、クリームなどの流動物や柔らかいケーキ、果物、アルコール飲料等々が毎日の食事になります。ほとんど歯で噛む必要はなくなりますが、同時に、健康に大切な唾液も出ることはなくなってしまいます。 悪循環はまだ続きます。間食が多く、空腹で食卓に向かうということがないので、人工的に食欲をもりあげようとして、どぎついソース類を多用することになります。味が強くなると、それだけ喉が渇き飲み物が多くなります。こうして、知らず知らずのうちに健康のバランスは崩れ、体は抵抗力を失って蒲柳の体質になっていくのです。 さらに、この生理的弱体化は精神的弱体化につながっていきます。道楽遊芸にしか興味をもてなくなり、無気力で意志も弱く、いつのまにか、先代が築いた富も持ちこたえられなくなって没落していくというのです。 本当の金持ちというのは、だから、いつでも粗食なのだと安原さんは言います。たとえば、ベルギーの金持ちは、パンひとつとっても念入りに自分で焼いて、市販のものを買うようなことはしないそうです。 どのように念入りかといいますと、まず、材料の小麦は無農薬のものしか使いません。製粉は人任せにせず、精白しないで玄麦を石臼でひき、塩はフランスまで行って自然塩を買い、水は近くの森の中の泉の水を汲みます。ふくらし粉のような化学薬品は使用せず、自然なビール酵母菌を使い、焼くのは暖炉の横に特別に作ってある石造りのパン焼き場で焼き、燃料は、電気やガスではなく薪です。 野菜なども農薬など撒布しませんから虫の食ったものばかりですが、本来、虫でさえ食わないようなものを人間が食べることのほうが間違っているのだと考えます。防腐剤の入った加工食品などは論外で、当然腐るべきものが腐らない「異常」食品など、決して体に取り入れようとはしません。そこまで徹底しているのが本当の金持ちで、そういう金持ちだけが、家を潰さないで何代でも続くのだと、安原さんは言っていました。 実は安原さん自身も、肉や卵は口に入れず、人工調味料は一切使わず、お米も玄米だけしか食べていません。白米というのは、玄米から自然の栄養分をわざわざそぎ取って「残り滓」にしたようなもので、そんなものをなぜ食べなければならないのか、というわけです。 安原さんは、これまでの七十二年間ずっと健康で、一度も病気になったことはなく、薬も一度ものんだことがないそうです。 イギリス人の肉食と動物愛護 ー生活と文化をめぐる随想(14)ー 2000.7 何年か前、私はロンドンの北西約一六〇キロのところにあるアプトンという小さな町の郊外でひと夏を過ごしたことがありました。 泊まったのは、ディビットと奥さんのクリスティーナの二人だけの家でしたが、敷地は、縦横ほぼ二〇〇メートルもあって、約四ヘクタールの広さです。 最初にこの家を訪れた日、クリスティーナは、六寝室の家の中を隅々まで見せてくれたあと、私を敷地の一角にある五〇メートル四方くらいの羊の放牧場に案内してくれました。その中には羊が十一頭いましたが、しかし、夫妻はここで牧畜業を営んでいるわけではありません。 ご主人のディビットは六十二歳で、近くの町のコンピュータ関係の会社で管理職を勤めていました。羊を飼っているのはいわば彼らの趣味です。奥さんのクリスティーナは五十五、六歳くらいだったでしょうか、日焼けして健康そのものという感じで、羊の世話ももっぱら彼女の役目でした。 その彼女が、羊の放牧場の前で、十一頭のうちの三頭を指さし、これと、これと、あれは、明日解体業者に渡して食肉にするのだと、何げなく言ったのです。私は一瞬緊張しました。指さされた三頭の羊たちは、明日の運命も知らぬげに、のんびり草を食んでいました。 要するに、動物の解体も牧畜文化の一つであることは私もよく知っており、一瞬緊張はしたものの、あまり気にも留めないでその時は聞き流したのでしたが、それから五日ほど経って、なんと、その羊の肉の一部がラム・ステーキとなって夕食のテーブルに現れたのです。 夕方、いつものように裏庭のテラスのテーブルで、ディビットとその日のおしゃべりをしながらビールを飲んでいると、やがてクリスティーナがワゴンにステーキの皿をのせて運んできました。おいしそうな匂いが流れてきて、「今日はステーキか、ご馳走だな」と私は思いました。その時にクリスティーナは、「これはラムで、先日あなたにお見せしたあの羊の肉ですよ」と言ったのです。 業者に頼んで解体してもらった羊は、毛皮をはぎ取られ、バラバラに切断されて戻され、冷凍庫に入っています。そのうちの一部が、その日の夕食になったわけです。 クリスティーナは、バラバラにされた肉片でも、その大きさや形などで、大体どの羊のものかわかると言います。にわかに、はじめた見た日の三頭の羊の姿が目の前に浮かんできました。私は小一時間も飲み続けていたビールの酔いも一度にさめる思いで、たじたじとなりました。 ディビットもそうですが、クリスティーナも動物が好きで、殺された三頭をも含めて、羊たちを大切にし可愛がっていたのは事実です。「ひもじい思いもさせなかったし、ここでのんびり育って幸せな一生だったと思うわ」と彼女は言いました。 そんな時に、そんなに可愛がっていた羊をなぜ殺すのか、と問うのは愚問です。そこはイギリスで、日本人の稲作文化的発想は通用しません。 イギリス人を含めてヨーロッパ人は、古来、風土的な厳しい制約のなかで、生存のためには家畜に大きく依存しなければなりませんでした。そして、それは食料としての家畜の解体にも慣れるということを意味しています。 問題は、家畜が日本人のもっとも身近な動物蛋白源である魚介類とは違って、生物学的には人間と同じ哺乳類であるということです。そういう家畜の解体に慣れてくると、ヨーロッパ人の血に対する感覚も、血を忌み嫌う日本人とは大きくかけ離れたものにならざるをえません。たとえば、ヨーロッパの町の肉屋さんの店頭で、あるいはスーパーマーケットのガラスケースのなかに、羊や豚の頭が血の付いた眼をむき出しにしたまま並べられているのも、ごくありふれた光景といえるでしょう。 日本人はしばしば、「欧米人は血の滴るビフテキを食べながら動物愛護の精神を説く」と、彼らの残酷を非難したりします。しかし彼らは、血の滴るビフテキを「食べながら」ではなく「食べるから」動物愛護の精神を説くのです。これは、基本的には、稲作文化の日本人が、お米を「食べるから」お米を大切に守り育てるのと同じです。 稲作文化の日本では、家畜の解体を業とする人たちは、昔から極端な差別を受けてきましたが、これも、文化が違えば逆になります。ヨーロッパでは、牧畜文化を支えるそういう人たちこそ、しばしば、社会から尊敬され、地位と名誉と財産を手に入れてきたのです。 おばあちゃんの教え ー生活と文化をめぐる随想(15)ー 2000.9 山口県の萩女子短大・副学長をしておられた河村とし子さんが、何年か前に、NHKの「こころの時代」という番組で、ご自分のおばあちゃんのことを話されたことがあります。 おばあちゃんは、河村さんの亡くなったご主人のお母さんです。小学校も出ていませんので一字の読み書きもできない、河村さんのことばでは「常識もない」人だったそうです。このおばあちゃんは、み仏への信仰の厚い人でしたが、六人いた息子娘たちのうち、成人してから四人までを次々に亡くしていました。 太平洋戦争の末期、東京の空襲を避けて萩市に疎開することになり、そのようなおばああちゃんとはじめて一緒に暮らすようになった河村さんは、おばあちゃんが、おそらく毎日、泣きの涙で暮らしているのだろうと思っていたそうです。ところがおばあちゃんは、少しも嘆きや悲しみが感じられない、安らかな毎日を送っていました。おばあちゃんは、「私たち浄土真宗のご門徒は、先にお浄土へ還らせていただいた愛しい子供たちとも、お念仏のなかで出おうたり話したりできるから幸せじゃのう」とよく言っていたそうです。 おばあちゃんの嫁であった河村さんは、熱心なキリスト教信者でした。キリスト教の家庭で育てられ、結婚するときにも、生涯クリスチャンとして過ごすことを条件としていたといいます。その河村さんは、疎開してからしばらくは、毎晩のようにおばあちゃんの部屋へキリスト教の聖書を持って押しかけ、おばあちゃんにしつこくキリスト教を勧めました。おばあちゃんは、少しもいやな顔をせず、「ああ、そうかそうか」といつも機嫌よく河村さんの話を聞いてくれたそうです。 後になって、河村さんがおばあちゃんに、「あのように毎晩押しかけられ、強引にキリスト教を勧められてさぞいやな思いをされたでしょう」と謝りますと、おばあちゃんは、「毎晩キリスト教を勧めに来る嫁じゃけど、ご縁があってうちの嫁になったんじゃから、み仏様におまかせしときゃええ、と思って少しもいやではなかったよ」と答えたそうです。 そのようなおばあちゃんにいつのまにか感化されて、その河村さん自身が、キリスト教徒から仏教徒に変わり、熱心に念仏を唱えるようになりました。 おばあちゃんは、すべてのものに有り難いと感謝して拝んでいるような人でした。朝、目を覚ましても、「ああ、今日も目が見えてくださる。手が上がってくださる。足が動いてくださる。有り難いことじゃのう」と何度もひとりごとのように繰り返していたそうです。 仏教の教えには「怨憎会苦」ということばがあります。しかし、それを字で読めなくてもおばあちゃんは、「人間ちゅうもんは自分しかかわゆうないもんじゃけな、そんな者同士共に暮らさねばならんその因縁を拝みあう。それしかこの苦はのりこえられんのじゃ」と言っていました。 また、「求不得苦」ということばもあります。それもおばあちゃんは、「無いもんを欲しがらんで、有るもんを喜こばしてもらおうよのう」と達観していました。文字一つ読めないおばあちゃんは、「常識もない」どころか、期せずして仏教の神髄を文字通り体得していたのでしょう。そのうえで、人に対してはいつも穏やかに、にこにこと笑顔を絶やさず、「和顔愛語」でなかった日は一日もなかったと河村さんは述懐しています。 このようなおばあちゃんと二十三年間一緒に暮らしてきて、河村さんは、何よりも多くのことをおばあちゃんから学び、いつのまにかおばあちゃんのなかにみ仏の姿を見るようになりました。大学教授の河村さんが、一字も読み書きできない姑との出会いを、生涯で一番大きな出会いであり、「人間としての立派さでは、自分はおばあちゃんの足許にも及ばない」と深く敬愛するようになっていきました。 日本では一般に、学歴偏重の傾向が強く、学歴がなければ立身出世もおぼつかないというふうに考えられがちです。しかし、本当の人間の偉さというのは、この河村さんのおばあちゃんの例をみるまでもなく、必ずしも学歴などと相関するものではないのでしょう。 学歴社会の人間を計る物差しが「地の尺度」であるとすれば、「天の尺度」といったようなものも考えたほうがいいのかもしれません。人間として偉いかどうかを計るのは、本当は、天の尺度によってでなければならないと思うのですが、カネやモノが中心の競争原理が強く支配するいまの日本の社会では、そういうこともなかなかわかりにくくなってきているようです。 見えないものを見る ー生活と文化をめぐる随想(16)ー 2000.11 霊魂は存在するか、しないか。立命館大学・国際平和ミュージアム館長の安斎育郎さんが仏教各派に照会したら、いろいろな宗派から返事が返ってきました。それによりますと、「霊は存在しない」(仏光寺・浄土真宗)から、「霊は実体を持った存在」(金剛峰寺・真言宗、延暦寺・天台宗)まで、大きな差がありました。同じ真言宗系の寺院でも、「霊は実体を持った存在」、「霊は観念であって実体ではない」、「霊は存在しない」など多様性が見られたそうです。(「朝日」'00.9.13) この結果について、安斎さんは、「結局、霊に関する見解は多様で、十三宗百四十派を超えるといわれる日本の仏教では、どの宗派のどの僧侶に出会うかによって、霊に関する理解に大きな差が生じることが示された」と述べています。そして、「たたり」についても、「あるはずがない」から「人間は前世における業の報いを受けて生きる」まで宗派の見解がいろいろと分かれていることを紹介した後、「仏教界はこの混乱をどう見るか?」と、締めくくっています。 霊魂は目には見えませんから、その存在を知るということは、なかなかむつかしいことのようです。仏教界でさえ混乱しているといわれるのも、無理ではないのかもしれません。 新潮文庫に、佐藤愛子さんの『こんなふうに死にたい』という本があります。これは小説家の彼女の霊に関する実体験をまとめたものですが、佐藤さんも初めは、霊魂の存在など全く信じてはいませんでした。彼女は、「私がこれから語ることを、おそらく読者の大半はナンセンスだというだろう。なぜなら現代に生きる大部分の人は、目に見えるもの、耳に聞こえるもの、科学的に分析実証できるものしか信じないからだ。かっての私もその一人であった」とこの本の中で書いています。 佐藤さんは、たまたま訪れた北海道の片田舎で、気に入った土地を見つけてそこに別荘を建てました。ところがその家で、次から次へと霊現象が起こりはじめたのです。思いあまった佐藤さんは、ある日ついに美輪明宏さんに電話をかけて救いを求めます。美輪さんは歌手、俳優として有名ですが、実は大変優れた霊能者だと聞いていたからでした。 美輪さんは東京にいても、霊視によって、佐藤さんのその北海道の別荘や周辺の景色などが手に取るようにわかりました。その後、東京でもしばしば美輪さんに会った佐藤さんは、美輪さんから、先祖の霊についてのみならず、自分自身の前世の霊についてもいろいろと聞かされるようになります。 佐藤さんの前世では、アイヌの女酋長だったことがあるそうです。その女酋長の名前もわかりました。そこで佐藤さんが調べてみると、その女酋長が戦いに敗れて命を落とした場所と北海道の彼女の別荘地とのつながりなどがわかりはじめてきたのです。 長い霊体験との関わりを通じて、佐藤さんは、だんだん霊について理解を深めるようになっていきました。「私は成仏できずにさまよう霊が存在することを、様々な体験で信じるようになっている。たとえ死に際が安らかであったとしても、死後にさまよう霊のあることも知っている」と語るようになりました。そして、「まっすぐ霊界へ行くことが出来なければ、私は死に変わり生き変わり輪廻転生をくり返す覚悟を決めるだろう」と、最後に述べています。 この本には、佐藤さんに高い霊能力を示してきた美輪明宏さんの「霊を受け入れる柔和質直な心」という文も載せられています。美輪さんには霊がはっきり見えるわけですから、「霊なんかあるわけがない」と広言する人などは、殊更に愚鈍に思えるのかもしれません。実は、そのような人は、物事をよく知っているつもりの、科学者、医者、学者、文化人・知識人といわれる人たちのなかに多いのですが、美輪さんは、それらの人たちこそ無知で蒙昧であると、次のように非難しています。 通常の医者や科学者は、超常現象や己の無知なる部分を認めれば沽券にかかわる、それらを否定することこそ立派な科学者で常識ある人間だと思いこんでいる。この姿こそ小心翼々とした哀れむべき根性である。頑迷ということは愚か者だということである。「超常現象なんてあるわけはありません」とそれに対する勉強も研究もせず何の知識もない癖に頭から否定してかかるのが傲慢なる愚者の発言であり、「この世の中には自分が知らない事はまだまだ山の様にあります。私には知識も経験も無いのでわかりません」と発言する人が聡明で謙虚な人なのである。 生まれることの奇跡 ー生活と文化をめぐる随想(17)ー 2001.1 人間はサルから進化してきたというのは、よく知られていますから、人はみな尻尾の名残を持っていたと言われても、あまり違和感はないかもしれません。しかし、「あなたは昔、魚でした。だから胎児の時にはエラの名残を持っていました」と言われると、ちょっと信じがたいと思われる人も多いことでしょう。しかし、これは本当のことです。いまでは生まれる前の胎児の映像で、そのエラの名残を確認することも出来ます。 赤ちゃんは妊娠十か月で生まれることになっていますが、十か月の時間をかければ人間が一人できあがるわけでは決してありません。妊娠十か月で生まれるようになるためには、その前に、気の遠くなるような長い準備期間が必要でした。私はそれを、少なくとも地球誕生以来の、四十六億年の時間で捉えなければならないと考えています。 生命はまず、海の中から生まれました。地球最古の生命の化石が一九七六年にオーストラリアで発見されていますが、これは、ストラマトライトという海中の生物からできた三十五億年前の化石です。このストラマトライトが、太陽光線に反応して酸素を放出し、新しい、酸素によって生きる生物の誕生に結びついていきました。この生命については、二十億年くらい前までさかのぼれるようです。 約十億年前には、それまでの単細胞生物から多細胞生物へと進化していきますが、すべての生物は、人間をも含めて、この時期にあらわれた生物の子孫ということになります。五億年前になりますと、爆発的な生物の進化がみられるカンブリア紀を迎えます。そして四億年前には、空気を呼吸する能力をもつ肺魚があらわれ、生命の海から陸への進出が始まりました。五千万年前には、犬に似た動物が逆に、陸から海へ帰っていったこともありましたが、これがいまのイルカやクジラの祖先です。 人間はシーラカンスという魚から進化してきたと考えられています。この魚のヒレが長い年月を経て、サルやヒトの祖先の手足になっていきました。さらに時が流れて、ヒトの祖先はオランウータンから分かれ、ゴリラとも分かれて、五百万年くらい前には、チンパンジーとも分かれます。 その頃、ヒトの祖先でもあったチンパンジーはアフリカに住んでいました。そのアフリカで、大規模な地殻変動が起こり、その当時のアフリカの森林は南北に走る大山脈によって二分されてしまいます。そして、山脈の東側では、西風と雨が山脈に遮られて、徐々に乾燥化がすすみ森林が消えていったのです。 この森林が消えてしまった東側にいたチンパンジーがヒトの祖先です。何不自由なく暮らしていた森をなくして、チンパンジーは、仕方なく食料を求めて歩き始めました。これがやがて二足歩行の猿人になります。アファール猿人と名付けられた三百万年前の骨がアフリカの東側で発見されています。 DNAの鑑定によりますと、その後もヒトの祖先は、ジャワ原人、北京原人、ネアンデルタール人といった系統とも分かれて、およそ二十万年前にアフリカから地球上に広がっていきました。そして、住み始めた環境によって、現在の白人、黒人、黄色人種などになっていったのです。 この魚から始まって、ヒトになっていった数億年分の過程は、人間の胎児が、母親の胎内の羊水のなかにいる十か月の間に、忠実にたどられていきます。この羊水は、原始の海と成分がよく似ているといわれます。魚であった名残のエラは、受精後四週間目に現れ、やがて、下あご、のど、耳の一部になっていきます。ヒレの部分も手と足に発達していきます。尻尾も四週間目に現れますが、これは六週間目から消えていきます。一言でいえば、十か月の中に、数億年分の発達過程が凝縮されて詰め込まれているのです。 生命の準備期間としての数十億年、それに魚になってからの数億年、チンパンジーと分かれてからの数百万年、これらのうちの一年が欠けても、私たちは人間として生まれることは出来ません。また、アフリカから地球上に広がっていった原人の時からでも、二十万年間の長い命の連鎖が、一度でもどこかで切れたら、私たちはこの世に存在することは出来ません。そのようにみてきますと、この世に生を受けた人間の一人一人は、一人の例外もなく、選んで選んで選び抜かれた奇跡の存在であることがわかってきます。 私たちはなぜ、このような奇跡の生を受けてきたのでしょうか。その意味をまず理解することが、あるいは、私たちが生きていく上での最も大切な課題なのかもしれません。 人それぞれに生きる ー生活と文化をめぐる随想(18)ー 2001.3 幼稚園に通っているような小さな子でも、例えば、絵本一冊を全部暗記してしまうようなことは、そんなに珍しいことではありません。そういう子は、なにか「特別に頭のいい子」のように思われがちですが、これは、実は、うまく誘導して子供にやる気を起こさせれば、どの子にもできる潜在能力の一つです。 むかし、ある事業経営者から、自分の幼稚園の娘が吹き込んだ英語のテープを是非聞いてみて欲しいと、言われたことがあります。そのテープは、クリスマスにちなんだイエス・キリストの物語を五分くらいの英語でまとめたもので、なかなか上手な話しぶりでした。 親からみれば、自分の子が天才児のように思えたのでしょう。私からも、そのようなほめ言葉を期待していたのかもしれません。私は、「きれいな英語ですね」と素直に賞賛のことばを述べたことを覚えていますが、これも実は、うまく教えれば、どの子にも出来る潜在能力の一つです。 人間にはもともと言語能力がありますから、ことばでまとまったお話をするということは、それが日本語であれ、英語であれ、少し訓練すれば、誰でも出来ることです。そして、このような言語能力は、本来人間に備わっている数多くの潜在能力の一つの例にすぎません。 ある種の運動能力なども、人間の持つ潜在能力の一つです。例えば、生後間もない赤ちゃんを、プールの中へ沈めたらどうなるでしょうか。大人でさえ泳げない人がいるのに、赤ちゃんをプールへ沈めるなんてとんでもない、と思われるでしょうが、現実には、どんな赤ちゃんでも、平気で水中を泳ぎます。 少しは水を飲み込んでも、気管には決して水が入らないように、気管の入り口は自然にふさがれます。自分で体を持ち上げる力はありませんから、ときどき水から顔を出させて呼吸をさせる必要はありますが、水中では平気で、手足を動かして泳ぎます。このような能力は生後半年ほども続くようです。 このような、本来人間が誰でも持っている潜在能力の集積は、想像以上に巨大なもので、その意味では人間は例外なく誰でも、天才であるといっても決して過言ではありません。ただ、ほとんどの人々はそのことに気がつかず、自分の持つ潜在能力の数パーセントも使わないまま、この世を終えていくのだといわれています。 こういうことを知るためにも、教育は大切ですが、少し気になるのは、日本語の「教育」にはどうも、能力を与えるために「教えて育くむ」というような語感があることです。これに対して英語やドイツ語の教育にあたることば(educateやerziehen)には、もともと持っている才能を「引き出す」「導き出す」という意味をもっています。このように、誰でもはじめから持っている能力を「引き出す」のが本当の意味での教育なのでしょう。そして、もっとも効率よくこの能力を引き出すためには、何よりも、自分には巨大な潜在能力があることを知らなければなりません。 ただ、世の中では往々にして、学校の成績や金儲けの上手下手だけで人の能力を判断しがちです。それらも、人間の能力には違いありませんが、しかし、ごく一部の能力であるにすぎません。それに、そのごく一部の能力を発揮することが、人間として一番立派で幸せなことだとは決していえないのです。 アリの社会を観察していますと、よく働くアリと、普通に働くアリと、全く働かないアリの三種類に分けられるのだそうです。そして、その割合は、六対三対一になるといいます。つまり、アリの社会では、いつでも全く働かないアリが一〇匹に一匹は必ずいるということです。人間の目には、このような働かないアリは、どうしようもない「無能な怠け者」というふうに映るかもしれません。しかし、実はそうではないのです。 このアリの社会から、試みに、その全く働かないアリを、取り除いてみます。すると、残されたアリたちは、また、よく働くアリと普通に働くアリと全く働かないアリの、六対三対一に分かれて、アリの社会を再構成していくのです。全く働かないから「無能な怠け者」なのではなくて、そのアリも、アリの社会では、なくてはならない必要な存在であることがわかってきます。 人間の社会でも、本来、無能で必要ではない存在というのはないのでしょう。私たちの一人一人が、それぞれに目的を持って生まれ、生きる意味があるから生きているのです。その意味をそれぞれが持つ巨大な潜在能力を活かして自分で「引き出して」いくのが、この世で生をうけた私たちに与えられている最も大切な課題の一つなのかもしれません。 謝らない欧米の文化 ー生活と文化をめぐる随想(19)ー 2001.5 日本では、なにか失敗をしたり、他人に迷惑をかけたりしたらすぐ謝るのが当たり前で、それが美徳と考えられています。しかし実は、それは世界に通用する美徳ではありません。 例えば、本田勝一さんは『極限の民族』のなかで、皿を割ったような過失に対しても、アラビア人なら決して謝らないと述べて、つぎのようにつけ加えています。 世界の主な国で、皿を割って直ちにあやまる習性があるところは、まことに少ない。「私の責任です」などといってしまうお人好しは、まずほとんどいない。日本とアラビアを両極とすると、ヨーロッパ諸国は真ん中よりもずっとアラビア寄りである。隣の中国でさえ、皿を割ってすぐあやまる例なんぞ絶無に近い。ただしヨーロッパでは、自分が弁償するほどの事件になりそうもないささいなこと(体にさわった、ゲップをした、など)である限り「すみません」を日本人よりも軽くいう。この謝罪は、ベドウィンの「親切」のように、単なる習慣である。 ・・・探検歴の最も豊富な日本人の一人、中尾佐助教授に、帰国してからこの話をすると、教授は言ったーー「日本こそ、世界の最後の秘境かもしれないね」。 では、ヨーロッパ人はなぜ謝らないのでしょうか。それはおそらく、彼らが日本人とは違って、簡単には他人の価値観を受け入れないという態度と関係があるように思われます。 厳しい自然の中で国境を接しあったヨーロッパの歴史は、生存と自己主張のための対立が絶え間なく続いた抗争の歴史でもありました。一旦他人の価値観を受け入れるということは、それを全面的に被征服者の立場で受け入れるほかはなく、それに、安易に自分の非を認めて謝るようなことがあれば、自分の存在の抹殺にもつながりかねない厳しい生存環境が常に背後にはあったのです。ヨーロッパ人が一般に、日常生活のこまごまとした部分においてさえ、極めて自己主張が強いといわれるのもそのためでしょう。 これは、ヨーロッパの伝統と価値観を受け継いでいるアメリカでも同じです。彼らも、この「自分が弁償するほどの事件」になると、めったに謝ろうとはしません。例えば、かって、自動車事故に関する意識の違いが日米で調査されたことがあります。 その調査では、「もし事故にあうとしたら主にどのような原因だと思うか?」に対する回答として、「自分自身のミス」という答えが、米国の10%に対して、日本は45%でした。そして、「他人のミス」と答えたのは日本の14%に対して、米国では74%もありました。日本人が自分のミスだと考える傾向が強いのにくらべて、アメリカ人は圧倒的に自分の非を認めず、相手方の責任にしたがる傾向が強いことがここにもよく示されています。(拙著『英語教育のなかの比較文化論』参照) 実は私も、長年のアメリカ生活の中で、一度だけ事故を起こしたことがあります。田舎道の狭い四つ角で、私が一時停止のサインを見落とし、そこへ左から猛スピードで突っ込んできた車と接触事故を起こしてしまったのです。相手は明らかにスピード違反ですが、しかし、非は一時停止を怠った私にあります。でも、私は謝りませんでした。謝りたくても謝れないのです。事故を起こしても「謝らないで、あとは保険会社に任せよ」と保険証書にも注意書きがついているのを無視することが出来ずに、苦しい思いをしました。 日本にはまだ謝る文化がありますが、世界では、欧米を含めた多くの国々で謝らない文化がむしろ支配的です。足を踏んだくらいではすぐ謝るかもしれませんが、小さなことでも、スーパーでレジの計算を間違えたというような責任問題になると、もう謝ろうとはしないのがほとんどといってよいでしょう。 この文化認識の違いを端的に浮かび上がらせたのが、例えば、昨年夏以来、アメリカで問題になっているブリジストンタイヤの子会社の二千万本にも達するといわれるタイヤのリコール問題です。原因がまだ特定されていないうちから、最高経営責任者の小野正敏氏はアメリカ議会の証言で、まず謝罪のことばを述べました。しかし、それがかえって「原因を知っていて隠していた」と、反発を呼び、一気に苦境に立たされることになりました。 逆に、今年の二月に発生した実習船えひめ丸のアメリカ原潜による沈没事故では、責任が明白であるのにワドル艦長がなかなか謝罪しようとせず、「日米謝罪摩擦」といわれたりして、対立が長く尾を引く結果になりました。 習慣とものの見方の違い ー生活と文化をめぐる随想(20)ー 2001.7 欧米では、よく知られているように、家に入るときに靴を脱ぐ習慣はありません。ベッドで寝るとき以外は、ほとんどいつも靴を履いたままといってよいでしょう。しかし、日本人は、欧米に住むようになっても、室内で靴を履いたままではどうも落ち着きませんから、入り口のドアのあたりでスリッパに履き替えたりします。かっての私も、そうでした。 でも、この室内では靴を脱ぐという習慣のある国は、世界ではかなり少数派のようです。それだけに、日本に来ている留学生などが日本人の家庭に招待されたようなとき、最初はちょっとまごつくようなことも珍しくはありません。私の知人のOさんが、いつか、こんな話をしてくれたことがありました。 来日したばかりのアメリカ人留学生を二人、Oさんが自宅に招待した時のことです。玄関のチャイムが鳴ったので、奥さんがドアを開けますと、なんとそこには、靴をそれぞれ両手にぶら下げ裸足になった二人が立っていたというのです。「靴を脱ぐのが少し早すぎたな」と、大笑いになったと言っていました。 この、家の中では靴を脱ぐ習慣があるのは、お隣の韓国でも同じですが、中国へ行くとこの習慣はなく、家の中でも靴を脱がないのが普通のようです。何カ月か前に、中国に暮らして六年になるというSさんという女性が、つぎのような話を朝日新聞に書いていました。 私の不在中、夫が夜中に高熱を出して往 診に来てもらった。地元の救急病院から駆 けつけた若い看護婦さんはスリッパをすす めても靴を脱ぎたくないと、断固拒否した。 そう言われても、土足で寝室に入られるの も困る。靴を脱ぐ脱がないの押し問答の末、玄関先にいすを持っていっての診察という ことで折り合いがついた。(01・2・4) 結局、彼女のご主人は、玄関でおしりを出して注射を打たれたというのですが、彼女があとで中国人の友人にその話をしたら、その友人の分析はこうでした。中国人女性にとって、親しくない男性の前で靴を脱ぎ素足を見せるのは、大げさに言えば服を脱ぐような感覚になるというのです。そして、中年の彼女でさえ、「男性と二人っきりの時は私も靴を脱ぎたくない」と言ったそうです。 その後、私も何度か中国へ行ったときに、このような習慣の違いをいろいろと見聞きしました。たとえば、食事の習慣の違いがあります。日本では、ご飯もみそ汁も、お椀をもちあげて口に入れますが、これはかなり独特で、この習慣は中国にはありません。お茶を飲む茶碗以外は、すべてテーブルにおいたまま、箸やスプーンを使います。これは韓国も同じで、欧米型といってよいでしょう。 ちょっと気をつけなければならないのは、中国人から食事に招待されたような場合、出された料理は全部食べてしまわないで少し残す、ということです。日本では食事を残すと失礼になるかもしれませんが、中国では逆に、全部食べてしまうと、「まだ足りない」の意味に取られてしまいます。「こんなに沢山は食べられません」と料理を食べ残すのが招待主のメンツを立てるエチケットのようです。 これは本で読んだのですが、中国人に贈り物をするときには、時計や傘、扇子は忌み嫌われるので避けなければならないとありました。時計は中国語で「鐘」といって、終わりの「終」と発音が同じため、そして、傘と扇子も別れを意味する「散」と発音が似ているからだといいます。日本でもたとえば、数字の四は、「死」が連想されるので、病院の入院病棟などで四号室を避けたりするのと同じような発想です。 また、中国語では、自動車は「汽車」といいます。日本語の汽車は、中国語では「火車」で、これは、火を燃やして蒸気を出しながら走る車ですから、何となくわかるような気がします。しかし、自動車がなぜ「汽車」になるのか、私はその発想が面白くて、何人かの中国人に聞いてみたりしました。 日本語の自動車は英語のauto(=自から)+ mobile(=動く)と発想は同じですが、これはおそらく、英語を直訳して「自動車」という語が作られたといってよいでしょう。テレビが出てきたとき、日本語では「電映」とでも名付けるのかなと思っていましたら、これもほとんど英語そのままの、「テレビ」で落ち着きました。中国語では「電視」です。 自動車については、中国語でガソリンのことを「気油」といい、その気油で走るから「汽車」だと言ってくれた人がいましたが、それが一番正しいのかもしれません。漢字では先輩の国が、その漢字もこのように、いろいろと日本とは違った発想で使っているのは、文化比較の観点からも、興味深く思えます。 No,1〜No,10へ No,11〜No,20へ No,21〜No,30へ No,31〜No,40へ No,41〜No,50へ |