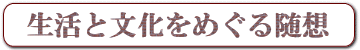
No,21~No,30
溝口祭典「こすもす倶楽部」会報紙『木洩れ陽』連載
|
古い伝統の中で生きる人たち ー生活と文化をめぐる随想(21)ー 2001.9 日本とイギリスは、島国という点では同じですが、文化や生活習慣には多くの違いがあります。私はいつもイギリスへ行くたびに、その違いをいろいろと実感させられます。 この間、久しぶりに、二週間ほど一人旅をしてきました。イギリスのヴァージン・アトランティック機で行ったのですが、乗っていたのは大半が日本人で、機内では日本人の客室乗務員が何人もいて日本語でサービスしていますし、食事も寿司や幕の内弁当が出されたりします。昔と違っていまでは、多くの観光客が国内旅行の延長のような感覚で、気軽に海外へ出られるようになりました。それはいいことですが、気をつけなければならないのは、日本の文化や生活習慣などは海外では通用しないことが少なくないということです。 例えば、飛行機がロンドンのヒースロー空港に着いて、空港内の長い動く歩道で移動している日本人を見ていますと、ほとんどの人たちは左側に立っています。しかしイギリスでは右側に立って、左側は追い越していく人たちのために空けておくのが普通なのです。これはロンドンの地下鉄のエスカレータなどでも同じです。 近年になって、東京などの地下鉄のエスカレータも、長いものが増えてきました。私は初めの頃、エスカレータの上で歩く時には、左右どちらを通ることになるのだろうと、関心をもってみていましたが、いまでは左に立って、急ぐ人は右側を通り過ぎていくのが当たり前になってきました。車の左側通行などはイギリスにならって制度化してきたと思われるのに、エスカレータの歩き方の場合は、イギリスとは逆の習慣が定着したわけです。 このような習慣の違いのほかに、イギリス人はどうも、時間の長さや古さに対する感覚が日本人とは違うように思えてなりません。 ロンドンの地下鉄の車両は、ここ数年でかなりきれいになりましたが、日本から初めて行った人には、小さくてちょっと貧弱に見えるようです。車両の幅も狭く、左右の座席の列の間の通路にも一人ずつ一列に立てるだけです。一両に乗れるのはせいぜい八十人くらいでしょう。東京などの地下鉄車両のほうが、ずっと大型で新しく近代的です。 ただ、このロンドンの地下鉄が初めて開通したのは、いまから百三十八年も前の一八六三年であったというのには驚ろかされます。日本では一八六〇年に井伊直弼が駕籠に乗って登城の途中に暗殺された「桜田門外の変」が起こっていますが、当時はまだ人力車のようなものもなく、駕籠や馬の時代でした。日本で地下鉄が開通したのは一九二七年(昭和二年)になってからのことで、上野・浅草間の二・二㌔が初めてです。 夏目漱石がロンドンに留学していたのは、一九〇〇年(明治三十三年)ですが、漱石の住んでいた下宿の近くには、地下鉄ノーザン線のクラップハム・コモン駅がありました。この駅は、建設以来改築されてはおらず、いまも漱石が乗り降りした百年前のままです。 私がロンドンに住んでいた十年前には、地下鉄レスター・スクエア駅のエスカレータは、人が乗る台座の部分がまだ木製でした。いまでは鉄製に変わっていますが、イギリス人はどうも古いものに愛着をもち、なかなか新しくはしないようなところがあります。あのロンドン名物のタクシーなどもそうで、昔もいまも古いオースチンの箱型のままです。日本のタクシーのように、ドアを自動で開ける装置をつけることなども、彼らは決して考えようとはしないようです。 私は今度の旅で、ロンドン北西一七〇㌔ほどのアプトンという町を久しぶりに訪れました。そこに住む知人のディビッド夫妻の家は築後二百年くらいですが、これは特に古いほうではありません。まわりには三百年くらいの家もいくつかありますし、町の中心には、一六〇一年に建てられた小さなレストランが、いまも営業を続けています。日本ではあの、天下分け目の「関ヶ原の戦」が一六〇〇年ですから、この小さな木造の建物は、その頃から四百年の歳月に耐えてきたことになります。 私の友人の一人に、ケンブリッジ大学出身のエリックがいます。ケンブリッジ大学は、創立が一二世紀にまで遡りますから、八百年以上の歴史があり、大学のあちらこちらには鮮やかな緑の美しい芝生がひろがっています。彼の話では、むかし、彼のいたカレッジにアメリカの大学からの視察団がやってきて、どのようにしたらこのように美しい芝生が育つのか、と庭師に聞いたのだそうです。庭師は、「別にむつかしいことではありません。私たちはただ三百年間、丁寧に手入れを続けてきただけです」と答えた、ということです。 ヨーロッパの肉食文化と十字軍的思想 ー生活と文化をめぐる随想(22)ー 2001.11 古来、ヨーロッパでは、厳しい風土的な条件のなかで農業生産性は極めて低く、人々が生きていくためには、大きく家畜に依存せざるをえませんでした。ヨーロッパの肉食文化というのは、ですから、生存環境の厳しさと切り離して考えることはできません。 しかし、生きていくために家畜に頼るということは、動物の処理にも慣れるということでした。問題は、家畜が魚介類などとは違って、生物学的には、人間と同じ哺乳類であるということです。人間と同じく、殺せば大量に赤い血が流れ出します。そういう家畜の処理に慣れるということは、ヨーロッパ人の血に対する感覚が、血を忌み嫌う日本人とは大きく違ったものにならざるをえません。 しかもこの場合、家畜を処理して血を見たり血の匂いをかぐのは、専門の業者や一家の主人だけではなく、主婦や子供たちも例外ではありませんでした。冬に入る前には、ヨーロッパでは、家族全員が協力して豚を処理し、塩漬け豚を作っていましたが、それが冬を越すための文字通りのいのち綱だったのです。 それだけにヨーロッパ人は、家畜を殺すことを残酷だと考えていては神経がもちません。彼らには、動物を処理しても残酷とは感じないですむような論理がどうしても必要でした。彼らはその論理を、聖書に求めました。聖書の「創世記」には、「地のすべてのけもの、空のすべての鳥、海のすべての魚はあなた方の食物となるであろう」と書かれています。 この人間と動物との明確な断絶の論理によって、ヨーロッパ人は、人間以下のものを殺すことには残酷を感じないですむことになりました。殺す場合の思いやりとしては、できるだけ苦痛を与えないように、一気に殺すことだけです。しかし、ここでひとつ注目しておかねばならないことは、彼らのいう「人間」とは決して人類一般ではなく、キリスト教徒である自分たちヨーロッパ人だけに限定して考えていた傾向があったということです。 この「傾向」のなかでは、異教徒は「人間」ではないし、有色人種も「人間」のなかには入りません。そのように彼らは、人間と動物を断絶させたのと同じ論理で、人間の中でも、キリスト教徒のヨーロッパ人とそれ以外の人間とを断絶させてしまったのです。その一つの例が、十一世紀から十七世紀後半まで、七回にわたってくり返された十字軍の遠征でした。 異教徒は人間ではないと割り切った十字軍遠征兵士の残虐さは、目に余るものがありました。勝利が確定してからも、和平協定を破って、無抵抗の非戦闘員、婦女子、子供に対してまで、殺戮、略奪、暴行の限りを尽くしたりしましたが、このようなことを伝えるヨーロッパ側の記録には、良心のひとかけらもみられないことが、橋口倫介『十字軍』(岩波文庫)などに述べられています。 また、中南米に渡ったヨーロッパの植民者たちが、あまりにも多くのインディアン達を殺すので、その反動を恐れたローマ法王が、「インディアンも人間である」と改めて宣言したという信じがたいような話も伝わっています。スペインの司教ラス・カサスは、一五五二年に書いた『インディアスの破壊についての簡潔な報告』(岩波文庫)のなかで、「この四〇年間にキリスト教徒たちの暴虐的で極悪無慙な所業のために男女、子供合わせて一二〇〇万人以上の人が殺されたのはまったく確かなことである」と書きました。 このような「傾向」は遠い昔だけのことではありません。かって、第二次世界大戦中のビルマで英軍の捕虜になった経験がある京都大学教授の会田雄次さんは、英軍兵舎で使役に服していた経験を、中公新書『アーロン収容所』の中でつぎのように述べています。 その日、私は部屋に入り掃除をしようとして驚いた。一人の女が全裸で鏡の前に立って髪をすいていたからである。ドアの音にふり向いたが、日本兵と知ると、そのまま何事もないように髪をくしけずり始めた。入ってきたのがもし白人だったら、女達は金切り声をあげて大騒ぎになったことと思われる。しかし、日本人だったので、彼女らは全くその存在を無視していたのである。彼女たちからすれば、植民地人や有色人はあきらかに「人間」ではないのである。 それは家畜にも等しいものだから、それに対し人間に対するような感覚を持つ必要はないのだ。 これらの例は、もちろん、キリスト教の真の教えと相容れないものですが、ヨーロッパの肉食文化には、一面ではこのような誤った傾向がつきまとっていたことを、時には私たちも、思い起こす必要があるかもしれません。 世界のなかの飢餓と飽食 ー生活と文化をめぐる随想(23)ー 2002.1 年輩の方はよくご存じだと思いますが、敗戦後の日本では、特に大都会で、人々は飢餓に苦しんでいました。一人一日二合一勺の米穀配給量も、遅配、欠配は常態化し、一九四六年六月の「共同通信」の調査では、東京都民で、米のご飯を一日一度しか食べられない人が、七一パーセント、米は無いのでまったく食べられない人は、一五パーセントであると、伝えられています。 この戦後日本の飢餓状況は、私も大阪にいて体験しました。私はまだ旧制中学の生徒でしたが、半年くらい、米粒一つ食べられなかった記憶があります。配給の黒ずんだ小麦粉を水でこねて作ったすいとんを、食べるというより飲んで、飢えをしのいでいました。昼食の弁当をもって登校できる生徒はほとんどいないので、学校の授業も午前中だけで、午後は、ふらふらと歩いて家に帰ると、横になって体を休めるという毎日でした。 その頃、戦勝国のなかでもアメリカは、ひとり漁夫の利を占めて、かつてない繁栄を謳歌していました。焼け跡の残る街の中を颯爽と歩きまわるアメリカ進駐軍の兵隊の姿は、貧しくみすぼらしいまわりの日本人の姿とは、際だった対照をみせていましたし、たまに、バラック建ての映画館で見たりするアメリカ社会の、ものにあふれたきらびやかな豊かさには、ただ一方的に圧倒されていました。 アメリカの学校では、水道の蛇口をひねると牛乳が出るそうだ、とか、食堂では何でも好きなだけとって食べればいいことになっている、とか、後年、私自身もアメリカで体験することになるカフェテリアの様子などが、その頃の私たちには、まったく夢の世界のように語り合われたものです。私たちが食べるものもなく栄養失調になってやせ細っているというのに、世の中はどうしてこんなに不公平なんだろう、と何度も思ったことを覚えています。 それから半世紀を経て、日本も経済大国になり、アメリカと同じように、ものがあふれ、食べ物もあふれて、食べ残したものを、平気で捨てるようにもなってきました。 現在、世界で大量に食べ残すのは、アメリカと日本ですが、その量は、アメリカが四三六〇万トン、日本が一六〇〇万トンにもなっているようです。そして、そのようなアメリカや日本を、いま世界で飢えに苦しんでいる八億三千万人の人々が、怨嗟まじりの羨望の目で見ています。しかし、一旦、飽食に慣れきってしまいますと、私たちも、そういう飢餓状態の人々のことには、つい無関心になってしまいがちです。 実は、世界で八億を超える人々が飢えているのは、世界の食糧が不足しているからではありません。現在の世界の穀物生産量は一八・七億トンですが、これに対して、世界の年間必要量は、推定で九億トンですから、世界には必要量の倍以上の食料があるのです。牛や豚、鶏などの家畜飼料用としての六・六億トンを加えても、まだ世界の食糧は余る計算になります。(「朝日」'01・12・12) 食料が余っているはずなのに八億人以上が飢えるのは、食料を捨てるほど買う人がいる一方で、まったく買えない人がいるという、富の極端な偏在がその原因です。世界中のたった六パーセントの人が全世界の六〇パーセントの富を独占しているといわれますが、残りの四〇パーセントの富が九四パーセントの人々に割り当てられる場合にもこの配分のアンバランスはおこりますから、たとえば、戦火が続くアフガニスタンだけをとってみても、人口一六〇〇万人のうち、六〇〇万人もが飢餓にさらされるということになります。 おそらく、昨年の「9・11」テロ事件を直視する場合にも、その背景にあるこの飢餓と富の偏在の問題を無視することはできないでしょう。作家の辺見庸氏は、それを「朝日」で、つぎのように述べています。 オサマ・ビンラディン氏の背後にあるのは、数千の武装集団だけではなく、おそらく億を超えるであろう貧者たちの米国に対するすさまじい怨念である。一方で、ブッシュ大統領が背負っているのは、同時多発テロへの復讐心ばかりでなく、富者たちの途方もない傲慢である。('01・10・09) 統計の上では、もし私たちの上に屋根があり寝る場所があり、さらに着る服があって冷蔵庫にも食料があるのであれば、それだけで私たちは世界の七五パーセントの人より恵まれていることになるのだそうです。日本の家庭で一年間に食べ残して捨てている食料は、アフガンの人々が食べる三年分の穀物の量と同じになるというようなことも、時には私たちも考えてみる必要があるのかもしれません。 ジャンヌ・ダルクの奇跡 ー生活と文化をめぐる随想(24)ー 2002.3 フランスのパリから北西約一二〇キロ、セーヌ川下流の河畔にルーアンという古い街があります。中世を偲ばせる多くの歴史的記念物があり、なかでも、一三世紀に建造されて以来、フランスでも最も美しいゴシック建築の一つであるといわれるノートルダム大寺院は、印象派画家モネの連作のモデルとなったことでも有名です。 そのノートルダム大寺院から西へ延びる「大時計通り」は、ルーアンで一番の繁華街で、途中には道をまたぐアーチの上に、一四世紀以来の金色に輝く大時計が一本針で時を告げています。そこから五分も歩くと、右側に開けてくるのが旧市場広場です。 いまも、その広場には、野菜や果物の屋台などが雑然と並んでいますが、そのすぐ向こうには、高さが二〇メートルはあるでしょうか、ひときわ高い銀色の角柱の上に十字架がくっきりと浮かび上がっています。あの奇跡の少女ジャンヌ・ダルクの処刑の跡です。ジャンヌ・ダルクは、ここで、一四三一年五月二八日朝、異端の嫌疑をかけられ、多くの群衆が見ている前で、火あぶりにされました。 その現場に立ちますと、日本にいる間、遠い外国の昔の話として頭の片隅にあった知識の断片が、にわかに現実味を帯びた史実として、強く迫ってくるのを感じます。それは、ありふれた伝説だとか風聞などではなくて、ジャンヌ・ダルクという奇跡の少女が、確かにここにいて、ここで死んだという事実のもつ重みです。 一五世紀の初め、フランスは国王シャルル六世が死んだ時、イギリスの支配下におかれていました。しかし、イギリスの国王ヘンリ五世も、ほぼ同じ時期に死去し、生後間もないヘンリ六世が即位して、イギリス・フランス両国の王ということになったのです。 フランスはもとよりこれを認めようとせず、シャルル六世の末息子のシャルルが王位を奪い返そうと反旗をひるがえします。フランスの特に北部で、イギリス軍とフランス軍との間の激戦が繰り広げられました。そしてその戦局の焦点となったのが、一四二九年の「オレルアンの戦い」でした。 圧倒的に優勢なイギリス軍を前にして、国家存亡の危機にさらされていたその時のシャルルのところへあらわれたのが、ロレーヌ生まれの一七歳の農村娘ジャンヌ・ダルクでした。「祖国フランスを救え」という神の啓示を受けて来たというジャンヌに対して、当然いろいろとその啓示についての疑惑や審問が投げかけられましたが、シャルルは神の啓示に賭けてみる気になったのでしょうか、結局、彼女に戦闘指揮をまかせることになります。 その結果、戦争のことなど何も知らないはずのこの少女の率いるフランス軍が、奇跡的にイギリス軍の築いた砦を落とし、ついにイギリス軍は、オレルアンから撤退しました。そしてシャルルは、ランスでシャルル七世として戴冠式をあげることができたのです。ジャンヌの言っていた神の啓示は成就しました。 しかしその後、ジャンヌには、王の側近の嫉妬、部下の裏切り、イギリス軍への売り渡しというような不幸が続きます。その翌年には捕らえられ、イギリス王家のルーアン代官により、このルーアンの広場で、異端として火あぶりの刑に処せられてしまいます。異端の汚名がそそがれたのは一四五五年になってからで、それから四六五年後の一九二〇年には、ヴァチカン法王庁によって、ジャンヌは聖女に列せられました。 このジャンヌ・ダルクが、実在の人物であり、彼女の示した奇跡も史実であることは、疑うことができません。そして、このような奇跡についての話は、フランスでもあちらこちらの教会に、少なからず残されています。有名な「ルルドの奇跡」もそのひとつです。 フランスの南西部、ピレネー山脈のほとりにあるルルドという風光明媚な小さな町で、奇跡が起こりました。一八五八年二月一一日から七月一六日までの間に、この町の貧しい少女ベルナデッタの前に一八回も聖母マリアがあらわれたのです。そして、その場所から奇跡的な病気治療の霊泉が湧き出るようになりました。これが世界的に有名になった「ルルドの水」で、いまでは、霊泉のある洞窟の上に美しい大聖堂が建てられ、世界各地から年々、二〇〇万人をこえる巡礼者が集まるといわれています。 奇跡が実は奇跡ではなく、単なるつくり話にすぎないのであれば、このような社会現象には説明がつけられません。ジャンヌ・ダルクのもたらした「神の啓示」の奇跡も、もしそれがなければフランスの独立もなく、歴史は変わっていたことになってしまうでしょう。 ファラオの夢の跡 ー生活と文化をめぐる随想(25)ー 2002.5 エジプトを南北に縦断するナイル川の上空を、カイロから南に向かって飛んでいますと、ヨーロッパやアジアでは見られない特異な光景が眼下に広がっているのが目に入ります。 果てしなく続く一面の白い砂漠の上に、縦に一本、緑の帯が伸びているだけなのです。その緑の帯の周辺だけが、エジプトでは農業が可能で人が住めるところです。ナイル川の西側も東側も、紅海を隔てたシナイ半島も、ほとんど全土が砂漠ですから、砂漠地帯はエジプト国土の九五パーセントにもなります。 ナイル川は、アフリカ大陸中央部のルアンダ地方に端を発し、スーダンやエチオピアからも水を集めてエジプトを南から北へ貫き、地中海に流れ込んでいます。長さは延々と六六九〇キロもある世界第一の大河です。 このナイル川は、有史以来、毎年六月から十月にかけて定期的に増水氾濫をくり返し、肥沃な沖積土が川の周辺に豊かな農作物を育ててきました。特にカイロから地中海にかけてのナイル川は、幾筋にも川が分かれて、デルタ地帯の大沃野となっています。 あの紀元前三千年からのエジプトの古代文明は、このナイル川の水の恵みに支えられて生まれました。ルクソールやアスワン、アブ・シンベルなどに散在する信じられないほど壮大で重厚な大神殿や、葬祭殿、王侯墳墓などには、ただ圧倒されるばかりですが、それにしても、どうしてこれほどまでに高度の文明が、四千年も五千年も前に、花開いていたのか、不思議に思われてなりません。 五千年前といえば、日本ではまだ縄文時代の早期で、あの邪馬台国の女王・卑弥呼が初めて歴史に登場してくるのは、その後三千年以上も経った三世紀になってからです。人類の文明は、その発達過程でなぜこれほど大きな地域的アンバランスを示すのか、カイロ郊外のギザのピラミッドやスフィンクスを眺めていても、そのような疑問を強く感じました。 ギザの三大ピラミッドは、四千五百年前頃に造られたといわれていますが、そのなかで一番大きいのがいわゆる「クフ王のピラミッド」です。底辺の一辺が二三三メートル、高さは一四六・五メートルで、平均二・五トンの石灰石が二三〇万個も積み上げられています。この大きな石を一〇〇メートルを超える高さにまで、しかも頂点が正確に中心に来るように運び上げた方法を含めて、駆使された極めて高度の建造技術の数々は、いまだに解明できない謎として残されているようです。 例えば、ピラミッド内部のクフ王の玄室とされる部屋は、幅五・二メートル、奥行き一〇・四五メートル、高さ五・八メートルの広さですが、壁は七〇トンの石を一〇〇個、寸分の隙間もなく積み上げて造られ、天井は一枚が五〇トンもある花崗岩九枚で船底型に覆われています。 この玄室の西側には花崗岩をくり抜いた蓋のない石棺がありますが、これらを綿密に調査したジャーナリストのグラハム・ハンコック氏は『神々の指紋』のなかで、「この狭い空間の中でこのような巨大な石を持ち上げて天井を造る方法は不明」だし、石棺をくり抜くには、「現在のダイヤモンドヘッドのパワードリルよりも五百倍速い速度で岩をくり抜かなければならない」がそのような工具は発見されていない、と述べています。 スフィンクスについては、さらに大きな謎があるようです。その一つは、スフィンクスやまわりの石の壁には、波状の浸食の跡が見られますが、それは石灰石が数百年にわたり雨に激しく打たれてできたものだということが地質学的調査で明らかになったことです。 スフィンクスは、紀元前二千五百年頃、カフラー王によって建立されたと考えられてきました。しかし、紀元前三千年頃にエジプト王朝時代が始まってからは、ギザにはあまり雨が降っていません。この地域に大量の雨が降っていたのは、サハラ砂漠がまだサバンナであった紀元前一万年よりも前のことです。そうすると、このスフィンクスは、その頃にはすでにここにあって、激しい雨に打たれていたことになります。 巨大な岩盤を極めて高度な技術でくり抜いて造られたこのスフィンクスの存在は、もう一つの、文明の発達についての重大な問題を投げかけることになりました。日本の縄文時代にすでに花開いていたエジプト文明のさらに数千年以上も前に、いまは人類が忘れてしまっている別の高度に発達した文明が存在していたはずだという極めて合理的な推論です。 エジプトのピラミッドやスフィンクスは、実はファラオの夢の跡ではなくて、地球規模の天変地異などの何らかの原因で滅びた高度の文明が、エジプトに残した確かな足跡であるという見方も、できるのかもしれません。 見えない世界を知る ー生活と文化をめぐる随想(26)ー 2002.7 佐藤愛子さんは、一九六九年に『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞した女流作家としてよく知られています。一昨年の二〇〇〇年には、父の作家・佐藤紅緑氏や異母兄の詩人・サトウハチロー氏をはじめ、佐藤家の人々の凄絶な生の姿を描いた大河小説『血脈』で、菊池寛賞を受けました。 本紙第二十八号の「見えないものを見る」のなかでも触れていますが、佐藤さんは五十歳になった頃、たまたま訪れた北海道の浦河という町の丘の上で、その土地が気に入り、衝動的に別荘を建ててしまいました。 ところがその家で、いわゆる心霊現象が次から次へと起こりはじめます。その現象は、東京の自宅でも起こり、旅先のホテルなどにもつきまとって、佐藤さんは深く悩むようになります。 思いあまった佐藤さんは、すぐれた霊能者でもある美輪明宏さんに救いを求めました。美輪さんは、霊視によって、佐藤さんがかつて浦河のその別荘のある土地で、アイヌの女酋長であった前世の姿を見抜きました。その時の佐藤さんは、口のまわりに入れ墨があり、馬に乗って部下を従えていたということです。 その丘の上は、むかしアイヌの集落があったところで、佐藤さんの別荘は、アイヌが神様を祀っていた場所にあたっていました。その場所を中心に、アイヌたちが平和に暮らしていたところへ、和人がやってきて、罪のないアイヌたちを皆殺しにしてしまったようです。女酋長であった佐藤さんも、戦いに敗れてそこでいのちを落としました。佐藤さんに起こった数々の心霊現象は、その場所に帰ってきた彼女に、かつてのアイヌたちの怨念を思い出させようとしたのかもしれません。 佐藤さんは、否応なしに、死後の世界や心霊について学ばざるをえないようになりました。その心霊と取り組んできた彼女の経験は、『こんなふうに死にたい』という本になって一九八七年に新潮社から出版され、その後、新潮文庫のなかにも取り入れられています。 この話にはまだつづきがあります。 『こんなふうに死にたい』の本が出た後、それを読んだからといって、佐藤さんの前に「忽然と」あらわれた人がいました。名古屋の小児科医で東洋医学の研究者でもある鶴田光敏氏です。この鶴田氏の登場で、佐藤さんは自分の「行き詰まっていた人生は開かれていった」と述べています。この鶴田氏との出会いがきっかけとなって、彼女は霊能者の江原啓之氏を紹介され、のちに江原氏との共著『あの世の話』が青春出版社と文芸春秋(文庫版)から出版されることになります。 実は、佐藤さんと鶴田氏は、前世で不思議な因縁で結ばれていました。それをこの本の中で、佐藤さんはつぎのように語っています。 美輪さんがある日、鶴田さんと私を前にして霊視して、大きな川のほとりを敗残の武士がよろよろと歩いていく。と向こうに一軒の家があって、その中の囲炉裏に向かって老婆が坐っている。背筋をすっと伸ばして端然と坐っている。この老婆が佐藤さんの前世で、敗残の武士が鶴田先生だと言うんです。 鶴田武士が空腹でよろよろしながら、家の中に入っていくと、老婆から一椀のお粥を貰い礼を言って立ち去るーーこういう因縁が私と鶴田先生の前世であったと言うんです。 これを聞いている霊能者の江原氏は、「佐藤先生と鶴田先生は深い絆で結ばれているなと思っておりました。前世の縁が今世にまでつながり助け合っているのですね。ご恩返しなんですね」と述べています。 佐藤さんの不思議な話はまだ続きます。 その後、鶴田武士は川上だか川下だかで切腹したというんですけどね。おどろいたことには鶴田先生、おへその下に、切腹の痕のような一文字の傷があるんです。見せてもらいましたけど、それは生まれたときからだそうですよ。 かつての佐藤愛子さんは、死後の世界のようなものは、全く信じていませんでした。「魂? そんなものは迷信だ」と述べたりしていました。浦河で心霊現象にあって以来、一転して、熱心に心霊を学び始めるようになった佐藤さんは、「その後の二十五年間は、その心霊現象の理解のためにあったといっても過言ではない」と言い、いまでは苦悩からも解放されて、つぎのように述懐しています。 神仏のことにまるで関心をもたなかった私が、これがきっかけとなって、人生観も価値観も変わってきました。いままで度重なるつらい経験もしてきたけれど、私にとっては有難いことだったと思うようになっています。 輪廻転生を信ずる人たち ー生活と文化をめぐる随想(27)ー 2002.9 シャーリー・マクレーンはアメリカの演技派女優として有名で、日本でもよく知られています。一九八四年には「愛と追憶の日々」で、アカデミー主演女優賞も獲得しました。 その彼女が書いた本に『アウト・オン・ア・リム』(邦訳・地湧社)というのがあります。原題の『Out on a Limb』というのは、梢の果実(真実)を手に入れるためには、危険を冒しても枝先まで行かなければならない、という意味です。 この本の中には、彼女が、アイルランドの友人の話を書いているくだりがあります。その友人が日本へ行って京都の町を歩いていたとき、ある骨董品店の店先に古い鎧兜が飾ってあるのが目に入り、強い衝撃を受けます。彼は、自分がその鎧のかつての持ち主であることを「知って」いたからでした。それを見つめているうちに、その鎧を身につけて戦っていた戦場のことなども生き生きと思い出し、そこで武士として戦死した日本の前世での記憶を取り戻したというのです。 このような見聞を重ねて、精神世界への理解を深めていったシャーリー・マクレーンは、「輪廻転生をくり返して人類の魂が進化していく、という考え方は欧米社会では新しい時代の主要な考え方になりつつあるのを私は知った」と述べるようになります。そして、この本の邦訳にあたっては、「日本の読者の皆様へ」という一文に、つぎのようなことばもつけ加えました。 私たちの人生に起きてくる悲劇的な事件でさえ、確かな理由があって起こっているのです。それは、私たち一人ひとりの成長のために必要だから起こっているということなのです。もし自分の人生は、自分の内なる神を経験するためのものだと常に忘れないでいるならば、私たちの人生は輝きに満ち、一見悲劇に思えることも、実は悲劇ではないとわかるでしょう。 この本がアメリカで出版されたのは、一九八三年ですが、これは三百万部を突破する大ベストセラーとなりました。一九八一年のギャラップ調査では、アメリカ人で輪廻転生を信じている人は二三パーセントであったのに、このシャーリー・マクレーンの本が出てからは、輪廻転生を受け入れる人は、三五~四〇パーセントになったともいわれています。 その五年後の一九八八年には、輪廻転生を取り上げたもう一冊の本が、アメリカで二百万部を超える大ベストセラーになりました。『Many Lives, Many Masters』という本です。著者は、ブライアン・L・ワイス博士で、エール大学医学部を卒業後、ピッツバーグ大学医学部教授やマイアミ大学付属病院の精神科主席教授を勤めてきたという精神科医です。 この本の序文の中で博士は、「私がこの本を書いたのは、心霊の分野、特に生まれる前や死んでから後の魂に関する研究に、少しでも貢献するためである。これから読者の方々がお読みになるものは、一字一句、本当のことである。私は何一つつけ加えていない」と述べて、死後の生の具体例を示しています。この本は、世界の二十か国のことばで翻訳され、日本語版も一九九一年に『前世療法』(PHP研究所)というタイトルで出版されて、ひろく読まれるようになりました。 このあと博士は、『前世療法2』を書き、さらに『魂の伴侶』を出しました。そして昨年(二〇〇一年)、四冊目の本が『魂の療法』というタイトルでPHP研究所から出版されています。この本の中では、あの自動車事故で亡くなられたイギリスのダイアナ妃にまつわるエピソードも紹介されています。 一九九七年八月二十二日、マイアミにいたワイス博士のところへ、ロンドンのダイアナ妃の居城であるケンジントン宮殿から電話がかかってきたのだそうです。ダイアナ妃の個人秘書が、「ダイアナ妃は、あなたの『魂の伴侶』を愛読されています」と切り出しました。そして「この本のおかげで、彼女は非常になぐさめられ、心が穏やかになりました。彼女はあなたにお目にかかりたいと言っております。近い将来、イギリスに旅行される予定はおありですか」と聞いてきました。 ワイス博士が、特に渡英の予定はない旨答えますと、秘書は「いま彼女は休暇中ですが、イギリスに戻ったら、また連絡させていただきます」と言って電話を切ったということです。ダイアナ妃は、八月三十一日、イギリスへ帰る直前に、パリのトンネル内での事故で亡くなられましたから、二人の間の連絡はこれで途絶えました。しかし、ダイアナ妃が、死を前にした最後の日々に『魂の伴侶』を愛読していたというのは、これも決して偶然ではなく、大きな意味があったのかもしれません。 はるばると旅をしてきたことば ー生活と文化をめぐる随想(28)ー 2002.11 録画テープのことを「ヴィデオ」といいますが、これはもちろん英語の"video"からとって「日本語」にしたことばです。しかし、その英語の「ヴィデオ」は、もともとは「私は見る」という意味のラテン語でした。 ラテン語を先祖にすることばには、直系の子孫であるイタリア語のほかに、フランス語、スペイン語、ポルトガル語などがありますが、この「私が見る」という意味のラテン語は、たとえば、いまのイタリア語では「ヴィドウ」("vedo")となり、スペイン語では「ヴィオウ」("veo")となっています。 さらに、スラブ系のロシア語でも、この「私は見る」は「ビィジュウ」で、よく似ています。また、古代インドの知恵の聖典「ヴェーダ」も、この「見る」と無関係ではありません。古代では、「見る」ということが「知る」ことであって、「ヴェーダ」は「見るための書」でもあったわけです。 ヨーロッパのほとんどの言語は、実は、これらのラテン系、スラブ系、インド系のほか、英語、ドイツ語などのゲルマン系、ケルト系、ギリシア系などを包含した一大ファミリーに属していて、それらは総称して「インド・ヨーロッパ語族」とよばれています。つまり、これらのことばを話している人々は、太古の昔は、みんな同じひとつのことばを話していた、いわば、親戚同士ということになります。 日本語は、このファミリーとは関連がなく、別の系統の言語です。文法は朝鮮語とよく似ていますし、発音はポリネシア系といわれたりしますが、まだ、正確なルーツはわかっていません。ただ、古代インド語のサンスクリット語がヨーロッパへ渡って、現代英語に確かな痕跡を残しているように、仏教の伝来を通じて、現代の日本語にも、いくつかの鮮明な足跡を残している、とはいえるでしょう。 たとえば、サンスクリット語の「アクァ」(水)ということばがありますが、これはいまの英語でも「水」を意味することばです。「アクァリアム」(水族館)、「アクァダクト」(水道、水道橋)、「アクァラング」(潜水具)などと日常英語のなかで使われています。 日本語のなかにも、この「アクァ」はあります。皆さんのなかにも使っておられる方がおられるのではないでしょうか。仏壇にお供えする水を「アクァ」といいますが、国語辞典には、これは「閼伽」と表示されています。 このことばは、仏教伝来とともにインドからはるかに遠く、日本にまで旅をしてきたことばのひとつなのです。 阿弥陀仏の「アミダ」も、インドから日本へ渡ってきたことばです。これは、英語では、「ア・ミータ」(a-meter)でした。「ミータ」は日本語では「メーター」といったりしますが、たとえば「ガス・メーター」というように、「メーター」は量を計るものです。「ア・ミータ」の「ア」は英語では、否定を意味します。ですから、「ア・ミータ」は「量を計ること・が出来ないもの」ということになります。浄土宗では、これを「計ることの出来ない無限の寿命をもつもの=無量寿」と名付けました。つまり、阿弥陀仏とは無量寿仏という言い方と同じなのです。 曹洞宗では、布施行として、他人に対する思いやりのこころをもつことや、困っている人に救いの手をさしのべることを特に大切な徳目にしているようです。そして、それを「何よりもまずダーナから」と教えています。「ダーナ」もサンスクリット語からきたことばで、このように、もともとは他人に対する施しや布施を意味していました。 やがて日本では、これは、お寺や僧侶に寄進するパトロンのことを意味する「ダンナ」(檀那)になりました。「檀那」は「檀家」といったりもします。なお、この「檀那」は、家を支えるパトロンとか、恩恵を与えてくれる有難い人という意味で、既婚の男子、特に夫や主筋の相手に対する一種の敬称となってきました。それが、いまも世間でよく使われている「旦那」です。 お釈迦様は約二千五百年前にインドに生まれ、三十五歳のときに、ブッダガヤーの菩提樹の下で悟りをひらかれました。その教えは、西北インド全域にひろがったあと、中央アジアを経て、紀元前後には、中国にも伝えられていきました。その中国仏教は、三七二年に朝鮮半島の高句麗に、ついで、三八四年には南部の百済にまで浸透していきます。百済から海を越えて、日本にまで仏教が伝来したのは、五三八年のことです。 お釈迦様の教えを伝えることばは、このようにして、インドから山を越え野を越え砂漠を越えて海をも渡り、はるばると旅を続けて、いまもこうして、日本に息づいているのです。 袖すり合うも他生の縁 ー生活と文化をめぐる随想(29)ー 2003.1 「袖すり合うも他生の縁」は、いろはかるた(京都式)に出ていることわざです。「袖すり合う」は、「袖振り合う」とも「袖触れ合う」ともいわれて、いまでもよく、人々の間で、使い続けられているようです。 ただ、「他生の縁」は、「多少の縁」と勘違いされていることが少なくありません。実は、私も長い間、「多少の縁」と思い違いをしていました。むかし、あるお寺の法話のなかで、それが「他生の縁」であって、「多生の縁」ともいったりすることを教えられて、はっと気がついたことがあります。「他生」は、現世からみた前世のことで、「多生」は、何度も生まれ変わることを意味します。 つまり、道行く知らない人と袖が触れ合うようなことがあれば、それも「多少は」縁があることになる、というのではなくて、このことわざは、どんなに小さな出来事も、ちょっとした人間関係も決して偶然には起こらず、前世からの因縁によっておこるものだ、という深い真理を伝えているのです。「一樹の蔭一河の流れも他生の縁」という類句もあります。このように、日本でも、人間の生まれ変わりの思想は、ふだん使われていることわざのなかにも、さりげなく含まれて、連綿と生き続けてきました。 本紙三十八号の「見えない世界を知る」のなかで述べた小説家の佐藤愛子さんと名古屋の小児科医師・鶴田光敏氏との出会いも、この「袖すり合うも他生の縁」の一つの好例かもしれません。前世では、敗残の武士であった鶴田氏は、空腹でよろよろしながら一軒の家に入っていきます。そこには佐藤さんの前世の姿である老婆が囲炉裏端に端然と座っていました。鶴田武士は、一椀のお粥を老婆からもらい、礼を言って立ち去ったあと、川のほとりで切腹をして果てたのでした。その鶴田武士は、今生では、佐藤さんの本『こんなふうに死にたい』を読んだあと、「忽然と」佐藤さんの前に姿を現し、佐藤さんの「生き詰まっていた人生」を導いていって、前世でのご恩返しをしたのです。 こういう前世からの因縁が明らかにされるには、やはりすぐれた霊能者の助力が必要ですが、私の知人のTさんも、そのような霊能者の一人です。Tさんによれば、彼は、キリスト時代のイスラエルと、中世のイギリスで私に会ったことがあるというのです。 イスラエルでのTさんは、小間物を積んだロバの手綱を引きながら、エルサレムの街で行商をしていたそうです。当時のその街は隅々まで歩いて知っていましたので、今生で、何年か前に初めてエルサレムへ行ったとき、古い道筋や遺跡の場所を次から次へと思い出して、案内のガイドを驚かせたといいます。 私は、そのエルサレムでは城壁の中の役所にいて、厳格な法務官のような存在として知られていたそうです。パウロがはじめはそうであったように、ユダヤ教の伝統を重んじ、律法を絶対視する立場をとっていました。そのために、庶民の間の背徳行為に目を光らせていたばかりでなく、当時のキリスト教徒たちに対しても、容赦のない迫害者であったのかもしれません。霊能者ではない私自身は知る由もないのですが、Tさんは、私のそのような姿をよく覚えているというのです。 別の霊能者のSさんは、前世で私とエジプトで会ったときの話をしてくれたことがありましたが、もちろん私には、そのような邂逅の意識は全くありません。しかし、いろいろとこういう話を聞いていますと、「袖すり合うも他生の縁」で、私が今生で会っている人たちは、本当はこのように、みんなどこかの前世で会ったことがある人たちばかりなのだろうと、いまでは思えるようになりました。 そのことを直截に示している文章が、日本の代表的な古典のひとつである『歎異抄』のなかにもあります。これは、親鸞のことばを弟子の唯円がまとめたものですが、その第五段には、次のように書かれています。 父母というのは、自分の父母だけが父母なのではない。人間は何度も何度も生まれ変わるから、生きとし生けるものは、みんないつかの世で父母であり兄弟姉妹であった。だから、私(親鸞)は念仏を唱える場合でも、現世の自分の父母だけに孝養を尽くすつもりで唱えたことは一度もない。 この親鸞のことばと「袖すり合うも他生の縁」ということわざは、深いところで結ばれています。私たちはつい、いまの人生だけがすべてであると信じ込み、他人の親も自分の親で、他人の子も自分の子だというふうには、なかなか考えられませんが、人生の真実に目覚める光明への道は、その壁を乗り越えたところに開かれているように思えてなりません。 見るべきほどの事は見つ ー生活と文化をめぐる随想(30)ー 2003.3 祇園精舎の鐘の声、諸行無常のひびきあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことわりをあらわす。 これは、十三世紀初頭に、語り物文芸として成立したとされる『平家物語』の、有名な冒頭の一句です。 祇園精舎は、むかしインド中部にあった舎衛国の長者・須達多が、お釈迦様に帰依して寄進した僧院で、そこには、鐘を吊り下げた無常堂がありました。精舎で修行を積んでいた僧が病気で死ぬときには、その無常堂の鐘が自然に鳴り出して死の恐怖を取り除き、極楽へ導いていったといわれています。 また、「沙羅双樹の花の色」というのは、お釈迦様が跋堤河のほとりで涅槃に入られたとき、その床の四隅に立っていた沙羅の双樹が、それぞれに合体して一本の樹となってお釈迦様を覆い、枯れ死んで白色に変じたという故事を意味しています。お釈迦様の説話のなかに仏教の基本理念である無常観を巧みに織り込んだ名句ですが、この無常観がそのまま、『平家物語』には底流として、一貫して流れているといってよいでしょう。冒頭の句は、さらに次のように続けられます。 おごれる人も久しからず、只春の夜の夢のごとし。 たけき者も遂にはほろびぬ。偏に風の前の塵に同じ。 そして、おごり高ぶって滅んでいった人々の例を、中国、日本のなかからいくつか列挙していったあと、「ごく近くの例では、平清盛という人のおごり高ぶりよう、横暴な振る舞いのようすは、目に余るものがある」というふうに作者は述べて、この物語は始まるのです。 この平家一門の栄華の蔭で、不満と反感を募らせていた地方の武士たちの期待に呼応して、伊豆にいた源頼朝が挙兵するのは、清盛の死の直前のことでした。その知らせを聞いて激怒した清盛は、「すべて望みは叶って思い残すことはないが、頼朝の首を見ないのだけが残念だ。私が死んでも供養などしなくてよい。頼朝の首を墓前に供えることだけが供養だ」と言い残して死んでいきました。 しかし、清盛の怨念も空しく、平家は、木曽義仲に追われて都を落ち、さらに、一一八四年からの一ノ谷・屋島の合戦では、源義経に敗れてしまいます。そして遂に一一八五年、壇ノ浦の海戦で全滅しました。そのとき三十三歳であった、清盛の四男・知盛は、船中を掃き清めて、「見るべきほどの事は見つ、今は自害せん」と、鎧を二重に着たうえで海中に身を投じたと『平家物語』は伝えています。 知盛は、清盛の正室・時子を母としていたので、わずか八歳で官職につき、順調に栄達の道をのぼりつめていました。一番上の兄で、深く仏法に帰依し温厚実直の人とされる重盛が、四十二歳で病死したあとは、次男の宗盛が跡を継いだのですが、この宗盛は、物語では、極端な臆病者として描かれています。 壇ノ浦の海戦でも、知盛の妹・徳子が生んだまだ幼い安徳天皇をはじめ、一族郎党がまわりで次々と自らいのちを絶つていくなかで、宗盛だけは死のうとはしません。その見苦しさをみかねた配下の武士たちに、とうとう海へ突き落とされてしまいます。しかし、泳ぎの達者な宗盛は沈むこともなく、泳ぎ回っているうちに源氏の兵に生け捕りになってしまうのです。そのような兄のふがいない様子も、死ぬ前の知盛は見ていたかもしれません。 宗盛と違って、知盛は平家の軍勢を支えていた武勇の将軍でしたが、その知盛にも、一ノ谷の敗戦のときの悲しい経験がありました。あの鵯越で有名な義経の奇襲を受けて逃げていくときに、自分の子供の知章が身代わりになって討ち死にしてしまったのです。いざというときには、自分の子供でさえ見殺しにした自分のいのちへの執着と利己心を恥じて、知盛は涙を流した、と伝えられています。 平家の一門は、この壇ノ浦の海戦で捕らえられた者も生き残って逃げた者も、やがてすべて源氏によって殺され、平家の血筋は絶えてしまいました。一一六七年に清盛が五十歳で太政大臣になって栄華の絶頂をきわめてから、わずか二十年後のことです。 「見るべきほどの事は見つ」と言って死んでいった知盛は、あのとき、何を見たというのでしょうか。敗軍の将として、一族の最後を見届けた、ということだけではないはずです。彼は、自分の一族が滅びるにしても興るにしても、それは人間の力の及ばない運命に左右されるものと、 固く信じていました。 その彼が見たものは、戦乱に明け暮れていた末法の世の中で、人間が繰り広げていた悲喜劇・喜怒哀楽の一切であったでしょう。そしてやはり、それらを支配している大きな運命の力と天の摂理であったのかもしれません。 No,1~No,10へ No,11~No,20へ No,21~No,30へ No,31~No,40へ No,41~No,50へ |