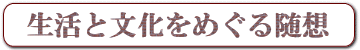
No,31〜No,40
溝口祭典「こすもす倶楽部」会報紙『木洩れ陽』連載
|
イエス・キリストの復活 ー生活と文化をめぐる随想(31)ー 2003.5 イエス・キリストは、エルサレムのゴルゴタの丘で十字架につけられました。その死亡日時は、聖書によっても不明で、紀元30年4月7日という説もありますが、イエス誕生の日時と同様、確定されてはいません。 その時、イエスの処刑の場には、イエスの弟子たちはほとんど誰もいませんでした。一番弟子のペテロをも含めて、誰一人イエスを助けようともせず、イエスとの関わり合いから罪に問われることを恐れて、逃げ隠れていたのです。イエスは、弟子たちからも裏切られて死んでいったといってもいいでしょう。 イエスは、生きているときから、この日の来ることを弟子たちに告げていました。そして、死んだ後、3日後によみがえることも予言していました。しかし弟子たちは、このよみがえりも信じていなかったようです。 隠れていたペテロ自身も、イエスの墓が空になっていることを聞いて、それを確かめるために、一度は走って墓まで行きました。墓の中まで入り込んで、遺体を包んでいた亜麻布だけしかそこには残されていないのを見たのですが、「ことの次第を不思議に思いながら帰っていった」(ルカ24・12)だけです。 しかし、甦ったイエスは、エルサレムで、ほんとうに弟子たちの前に現れました。それでも、その時にその場に居なかった十二弟子の一人のトマスだけは、まだ、その話を聞いても受けつけようとはせず、 「私は、その手に釘あとを見、私の指をその釘あとにさし入れてみなければ、決して信じない」(ヨハネ20・25 )と言い張ったのです。 その8日後、今度はそのトマスも居るところへ、イエスはまた現れます。イエスはトマスに言いました。「あなたの指をここにつけて、私の手をみなさい。手をのばして、私の脇に差し入れてみなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい」。(ヨハネ20・26-29) トマスはただ、『わが主よ、わが神よ」と言いながら懼れ慄くだけでした。 このイエスの復活のあと、イエスの弟子たちは、劇的に変わりました。一度は師を見捨てて逃げ隠れしていた彼らは、猛然と立ち上がって結束し、熱い信仰に燃えて、多くの苦難をものともせず、叩かれても、石を投げられても、殺されそうになっても、師イエスの教えを異邦人の間にも伝えていこうとします。 イエスの処刑が紀元30年とすると、そのあと紀元64年にはもう、あの歴史に残る皇帝ネロのキリスト教徒迫害が起こっています。キリスト教は、イエスの死後わずか34年で、遠く離れた帝国の首都ローマにまで浸透し、ネロの大弾圧の対象となるほどまでに大きく成長していったのです。イエス復活の奇跡のなせる業である、というほかはないでしょう。 しかし、このイエスの復活の奇跡は、いまでもなかなか信じられていないようです。よみがえりというのは、現代の科学では説明がつきませんから、科学者や知識人といわれるような人ほど、信じようとはしないのかもしれません。広大な宇宙のなかでは米粒一つにもならないようなちっぽけな地球の上で、「科学万能」を思いこんでいる人は、ちょっとこっけいな気もしますが、それでも、神学者やキリスト教徒でさえ、この復活は信じられないという人が決して珍しくはないのです。 たとえば、作家の遠藤周作さんは、熱心なカトリックで、生前にはキリスト教に関する著作も多く残されていますが、その彼でも、目に見える形での復活には疑問を持っていました。イエスを裏切ったあの弱い弟子たちが、一斉に立ち上がってあらゆる困難に打ち勝ち布教に献身したのには、「なにか筆舌では言えぬ衝撃的な出来事が起こったと考えるより仕方がない」といいながらも、『イエスの生涯』のなかで、つぎのように述べています。 なぜ弟子たちは荒唐無稽な、当時の人々も嘲笑した復活を事実だと主張し続けたのか。彼らを神秘的幻覚者だとか、集団的催眠にかかったのだときめつけるのはやさしいが、しかしそれを証拠だてるものは何ひとつない。謎はずっしりと重く我々の心にのしかかるのである。 そして、「イエスは弟子たちの信仰において甦られた」としか言いようがないであろう、とある神学者のことばを引用しています。 当然のことながら、といってもよいのでしょうか、遠藤さんは「死後の世界」の実在についても懐疑的でした。しかし、その彼もまた、1996年9月に死亡したあとは、確実に変わっていったようです。霊界からのメッセージで、遠藤さん自身が「死後の世界」があることを明るく伝えてきているからです。 そのことについては、次の稿で、また改めて取り上げてみることにいたしましょう。 生き続けるいのち ー生活と文化をめぐる随想(32)ー 2003.7 イエスは、十字架につけられたあと、予言通り三日後に甦りました。この甦りを契機にして、弟子たちは劇的に変わります。一度は師を見捨てて逃げていた彼らが、初めて信仰に深く目覚めて一斉に立ち上がり、文字通り生命を賭して師の教えを広めていくようになったのです。逆にいえば、このイエスの復活がなければ、その後の世界宗教としてのキリスト教はなかったといってもいいでしょう。 その一方で、「復活」や「甦り」などは、人間の常識からいってもあり得るはずがない、という否定や批判も、常につきまとってきました。キリスト教徒や神学者のなかでも、信じられないと言う人が、いまでも珍しくはありません。前稿で取り上げた作家で熱心なカトリックの遠藤周作さんもその一人でした。 しかし、この復活には、強力な証人がいます。かっては、キリスト教徒を弾圧していたパウロです。パウロは、キリスト教徒を捕らえようとしてダマスコへ向かう途中、突然、天からの光に打たれて、「なぜ私を迫害するのか」というイエスの声を聞きました。それ以来、パウロは一八〇度転回して、熱烈なキリスト教徒となり、命がけの布教を続けて最後にはローマで殉教したと伝えられています。 そのパウロが、復活を疑問視するひとがいることについて、キリスト教徒に宛てた書簡のなかでつぎのように述べています。 もしキリストが甦らなかったとしたら、 私たちの宣教はむなしく、あなたがたの信仰もまたむなしい。さらに、私たちは神にそむく偽証人にさえなるだろう。なぜなら、私たちは神がキリストを甦らせたと言って、神に反するあかしを立てたことになるからである。(コリント前書15・13-15) 遠藤さんも、この書簡を引用して、「この絶対的な自信、動くことのない確信は何よりも私たちを圧倒してしまう。どこからこの自信と確信は生まれたのか。もし(復活が)事実でないとするならば・・・・」というのですが、「謎はずっしりと重く我々の心にのしかかるのである」と「謎」で終わってしまっています。 パウロが、イエスの死後、イエスの声を聞いて回心したその当時、甦ったあとのイエスを見た信徒たちは、五百人以上も居ました。そして、その目撃者たちの大多数はまだ生存している、ともパウロは前述の書簡のなかで述べています。つまり、復活の生き証人はまだ大勢いたのです。しかし、イエスのことを熱心に考えながらも、「復活を目撃できなかった」遠藤さんは、その奇跡を最後まで信じてはいませんでした。 その遠藤さんは死後の世界にも関心をもっていましたが、やはり信じられず、懐疑的であったようです。彼は、一九九六年九月に亡くなりました。その半年ほど前に、親しくしていた女流作家の佐藤愛子さんに「佐藤くん、君、死後の世界はあると思うか?」と、電話で訊いてきたのだそうです。 佐藤さんのことは、この随想でも何度か取り上げてきましたが、何年も悩み苦しんだうえで霊界の存在に行き着いた人ですから、「あると思う」とすぐ答ました。すると、遠藤さんはこう言いました。 「もしもやな、君が先に死んで、死後の世界があったら、『あった!』といいに幽霊になって出てきてくれよ。オレが先に死んだら、教えに出て来てやるから」 佐藤さんは、その時は「遠藤さんの幽霊なんて来ていらん!」と答えて、話は終わったということです。 佐藤さんは、いまでも心霊の相談などで霊能者の江原啓之さんに電話をかけたりしているといいます。遠藤さんが亡くなった翌年の五月中旬、彼女が江原さんと電話で話をしている途中に、急に遠藤さんが現れました。 江原さんが、「あ、ちょっと・・・・・待って下さい・・・・今、佐藤さんの部屋に遠藤先生が見えています」と言い出したあと、「遠藤先生がこういっておられます。死後の世界はあった、こっちの世界はだいたい、君がいった通りだ・・・・」と霊界からのメッセージを伝えてくれたのです。 佐藤さんは、感動しました。そして『私の遺言』のなかで、つぎのように書いています。 私の身体を戦慄が走った。驚きや怖ろしさではなくそれは間違いなく感動の戦慄だった。私は思いだしたのだった。遠藤さんの生前の、あの会話を。もしオレが先に死んだら、教えに出て来てやるから・・・・・。 遠藤さんはそういった。そしてその約束を守って出てきてくれたのだ・・・・。呆然としている私の中に何ともいえない懐かしさと嬉しさがこみ上げてきた。わっと泣き出したい熱いものがたちのぼってくる。 アンコール・ワットへの旅 ー生活と文化をめぐる随想(33)ー 2003.9
今年の七月中旬、カンボジアのアンコール・ワットへの旅に出かけました。世界文化遺産として知られるアンコール・ワットは、十二世紀前半、当時のクメール王国のスールヤヴァルマン二世によって造営されたものです。 当時のクメール王国は、インドシナ半島の大部分とマレー半島の一部までを領土としていた東南アジア唯一の大帝国で、このスールヤヴァルマン二世は、王は死後には神と一体化するという思想のもとに王権を神格化し、自分が死後に住む地上の楽園として、この壮大な寺院群を造り上げたといわれています。 成田を発って六時間後、ヴェトナムのホーチミン市(旧サイゴン)で乗り換えたターボジェット機は、北西へ十分ほど飛んでカンボジア領空に入りました。やがてメコン川の上空を通過して、間もなく眼下に広がり始めるのが、東南アジア最大のトンレサップ湖です。雨期の面積は琵琶湖の二十一倍ほどにもなり、年間三十万トン以上の三百種類に及ぶ淡水魚の漁獲量があって、カンボジア国民の主要な蛋白をまかなう「命の湖」でもあります。 その湖の北端に近いところに、アンコール・ワットなどの遺跡群の町、シェムリアップがあります。私たちの乗った飛行機は、四十分ほどの飛行の後、その町外れにひろがるのどかな田園風景の中の小さな飛行場に着陸しました。少し車を走らせると、外国人観光客用のホテルやレストランの建築や改造が目立つようになりますが、全体としては、貧しく雑然とした田舎の小さな街という感じで、街中で交通信号機もまだ二つしかありません。 アンコール・ワットは、街の中心部からバスで北へ二十分ほどのところにありますが、実は、いまから百三十年前にフランス人博物学者アンリ・ムオにより再発見されるまでは、そのあたりはすっかり密林に覆われ、遺跡群はすべて、その奥深くに眠り続けていました。 繁栄を誇っていたクメール王国は、一三五三年以降、二度にわたるシャム(タイ)との大戦争に破れ、それからは急速に衰えていきます。一四三一年頃には、遂にアンコール王都は陥落し、人々は南部の地方に逃れて、その後には、長い年月が経つうちに、深い密林が覆い茂るようになっていったのです。 遺跡群のひとつ、タ・プローム寺院へ行ってみると、密林に覆われていた名残がそのまま残されていました。一一八六年に仏教寺院として建てられたこの石の建造物には、ガジュマルの大木が何本も覆い被さっていて、巨大な鳥の足が寺院を踏みつぶしているようにも見えます。ここだけは、自然の脅威を示すために、わざと修復の手を加えないで、再発見当時の姿のまま、残してあるのだそうです。 アンコール・ワットは南北千三百メートル、東西千五百メートルの堀で囲まれた敷地内にあります。砂岩とレンガを積み上げて作られたこの巨大な建造物は、ヒンドゥー教のヴィシュヌ神に捧げられた寺院であると同時に、王が死後に住む楽園という意味では、王の墳墓でもありました。 その中に聳える中央祠堂はいわば世界の中心で、神々が住むメール山(須弥山)を象徴し、周囲の回廊は雄大なヒマラヤ連峰を、環壕は無限の大洋を意味しているといわれます。 石を敷き詰めた西参道からこの中央祠堂まで歩いていくには、階段を上って最初のテラスに着き、さらに進むと、回廊つきの西塔門への次の階段を上ることになります。この階段を上りきったところで、塔門の中央部の縦型の開口部のなかに、中央祠堂の五つの塔が前へ進むにつれて徐々にその全容を現すという、意図された空間構成になっています。 それからさらに、西塔門テラスへの急な階段があり、壁面が見事なレリーフのギャラリーになっている第一回廊を抜けて、やっと中央祠堂の下まで行くと、目の前には上ることを拒否するような急勾配の最後の階段が立ちはだかるという構図です。「須弥山」へたどり着くのは、決して楽ではありませんでした。 なにしろ、気温三四度、湿度八五パーセントの熱帯モンスーン気候ですから、着ているTシャツもすぐ汗でびっしょりになります。アンコール・ワットを含めて、三日間歩きまわって鑑賞した遺跡群は感動的でしたが、このひどい蒸し暑さは、少し体にこたえました。 カンボジアはまだまだ貧しい国で、政府職員や警察官などの月給も、二十〜三十ドルくらいといわれています。遺跡の周辺では、地雷で両足をなくした少女が物乞いをしていたり、多くの物売りの中には、まだ五歳くらいの小さな女の子が裸足で絵はがきを売っていたりもしています。その人たちに小銭を手渡す度に、なにか空しく辛い気持ちになっていたのも、この旅の思い出の一齣になりました。 闇夜のバルト海にて ー生活と文化をめぐる随想(34)ー 2003.11
去る九月二八日の夕方、私は北欧スウェーデンのストックホルムから、フィンランドのヘルシンキへ向かう三万五千トンのフェリー・ガブリエラ号に乗っていました。六階の海側の個室の窓から見えていたバルト海は、曇天で六時頃には真っ暗になって、どこまでも深い闇がひろがっていただけです。 船内のレストランでヴァイキング料理の夕食をすませて、八時半頃部屋へ戻っていた私は、翌日の忙しい行程に備えて、一〇時すぎにはもうベッドに横になっていました。 まだ時差ぼけから抜けていなかったからでしょうか、夜中に私はふと目を覚まし、時計を見ると午前零時です。三万五千トンの巨体は船底の方で鈍いエンジン音を響かせているだけで、船はほとんど波で揺れることもなく、粛々と進んでいるようです。私はカーテンを開けて、夜のバルト海に目を向けてみました。 私は、船旅は好きなほうで、一九五七年にアメリカ留学で二週間かかって太平洋を船で渡って以来、船室から夜の海を眺めるという経験は、海外でも日本でも少なくはありません。船室の窓から、月夜の美しい海原を眺めたことは何度もありますし、曇り空で、真っ暗闇の海を航行しているときには、全く何も見えないこともよく知っています。しかし、その夜の場合は、様子が違っていました。 曇天の暗い海上の遠くの方で、赤い光が、すーと流れ星のように流れていくのが見えたのです。よく見ると、それは水平に、そして、左右に素早く動いていて、流れ星でないことはすぐわかりました。しかも、それが、三本の線になったり、四本、五本の線に増えたりするのです。みんな、鮮明に赤く光っています。私はその不思議な光景に、眼を凝らして、何とかその正体を見極めようとしました。 それらの赤い光は、それが素早く飛んでいるから赤い線に見えたのですが、船から遠く、おそらく百メートルも二百メートルも離れていたように思えます。ずっと見続けていますと、たまに船のそばまで近づいてくる光があって、船の近くでは、船の灯りを受けたからなのでしょうか、一瞬、白く見え、そして羽ばたいていたような気がしました。それで、私は、遠くの赤く光る物体も、鳥ではないだろうかと推測したのです。 しかし、赤色に光って飛ぶ鳥などというものは、常識で考えても、とてもあり得るとは思えません。蛍や、洞窟の中でかすかに光る苔などは、私も見たことがありますが、鳥の類が光るはずがない、と何度も思いました。 真夜中の真っ暗闇の海の上ですから、もし物体が光るとすれば、それは船からの光を反射している、と考えられないことはありません。しかし、その可能性もなかったようです。 「光の明るさは距離の二乗に反比例する」ことも私の頭の片隅にはあって、何度も暗い海を眺めまわしたのですが、真夜中の船から漏れている明かりは、船のすぐそばの波の動きをわずかに捉えているだけです。五〇メートルや百メートルの、あるいは二百メートルもあるような遠方の空中の物体に届くはずがないこともすぐわかったのです。 あまりに不思議なので、私は、幻覚でも見ているのではないかと何度も思ったりしましたが、何度見直しても、やはり間違いはありません。赤い光は、断続的に、しかし、何度も何度も暗い夜空に赤い線を引きながら、左右に速い速度で直線的に飛んでいました。 いつまでも見ているわけにもいかず、眠らないでいると、旅行中の予定にも差し支えてきます。私はいったんは寝ることにしましたが、目覚ましを三時にセットして、三時に起きあがり、もう一度、窓の外を眺めました。再度、確認しておこうと思ったからです。外は相変わらず、漆黒の闇でした。そしてやはり、赤い光を発する物体が、左右に速い速度で飛んでいました。ちょうど流れ星が横に流れているような感じで、鮮明に目に映ります。 おそらく、高感度のフィルムでカメラのシャッターを開放にして、あのときの窓の外へ向けていたら、フィルムには何本も赤い線が間違いなく写っていたことと思われます。しかし、私の持っていたのは普通の小さなデジタル・カメラだけで、そのような記録を残すことは出来ませんでした。いま、私の頭に残っているのは、あの赤いいくつもの鮮明な光の線と、そして、それが決して幻覚ではなかったという、ゆるぎない確信だけです。 なかなか信じてもらえないような話を書くのは難しいのですが、科学万能と思われている現代でも、人間にはまだまだ未知のことが沢山あります。その一例を、改めて私は、闇夜のバルト海上を飛ぶ赤い光という現象で、教え示されたような気がしてなりません。 美容整形と臓器移植 ー生活と文化をめぐる随想(35)ー 2004.1 この間、かつての教え子であったまだ二〇歳代の若い女性数人と会ったとき、雑談のなかで、美容整形手術をどう思うかと、訊かれました。彼女たちの友人の誰かが、そのような手術を受けて「綺麗になった」というようなことでしたが、私はちょっと考えて、やはり賛成できない、と答えました。 事故などで失われた肉体的機能をもとのように修復、復元するための形成外科手術はまだわかりますが、肉体的に健康で何の不自由もないのに、「美しさを追求する」ということだけで自分の身体に手術のメスを入れるというのは、どう考えても行き過ぎのような気がしてなりません。第一、それで本当に、美しくなれるのでしょうか。 ちょっと気になって、インターネットで見てみますと、美容整形を受けに来る若い女性は、ほとんど「玉の輿」指向で、「美しさ」を手に入れて、理想の相手と結婚するための道具と考える、というようなことが書かれていました。「道具」とはおだやかでありませんが、それほど、美しくなりたいという願望は、特に若い女性の場合、強いといえるのかもしれません。 もちろん、女性であれ、男性であれ、美しくなることへの願望を持つことは非難されるべきではないでしょう。むしろ、いいことだと断言しても差し支えないと思います。ただ、その美への追求が、きわめて人工的な美容整形によって、ということになると、不可避的に、人間とはなにか、というような根元的な問題がからんでくるように思えるのです。 おそらく、美容整形でうまくいった場合、そして、手術を受けた本人が、「より美しくなった」と満足している場合には、それなりに一定の効果があることは否定できないでしょう。人前に出るのを億劫がっていた人が、積極的に人と付き合い、自信をもって仕事にも取り組むというようなこともあるでしょう。人間は本来、自分が思った通りになる存在ですから、それでプラス思考が強くなれば、それなりに、すべての面で、潜んでいた多くの能力が発揮されることにもなります。 しかし、人間にはもっと大切なことがあります。生まれては死に、死んでは生まれて輪廻転生をくり返しながら、それぞれの生で、その時の自分の学びのうえで、一番ふさわしい親を選び、環境を選んで私たちは生まれてきました。いまの自分がどのような人間として生まれたか、それも自分が選んで決めたことで、そこに、この世を生きていくうえでの大切な意味が隠されているのです。 人間はせいぜい生きても百年くらいで、それで死んだら灰になっておしまい、という考え方では、いのちの実相は見えてこないでしょう。永遠の生命の中で、いまそのなかの一瞬を、この世で修行のために生きていることが理解できれば、美容整形は、実は自分自身に対する背信行為で、魂の輝きも、それだけ曇ってしまうということも自明になる筈です。イエスは、「富んでいる者が神の国に入るのは、駱駝が針の穴を通るより難しい」と言いましたが、これはそのまま、美容整形の願望者にも当てはまるように思えてなりません。 臓器移植も、人間の身体に人工を加えるという点では同じですが、この場合は、どうでしょうか。いまは医学も発達して、摘出された心臓や腎臓を他人に移植することも可能になり、その恩恵を受けて生き永らえることができる人々も、世界中で増えてきました。 この臓器移植の場合は、これによって人間のいのちが救われるという崇高な目的がありますから、おのずから区別して考えられなければならないでしょう。これに異を唱える人もあまりいないかもしれません。しかし、永遠のいのちの観点からみると、やはりその是非について、考えてみる必要はありそうです。たとえば、世界でひろく知られている高位霊のシルバー・バーチは、動機が立派であることを認めても、臓器移植には賛成できないと述べて、つぎのように続けています。 《そもそも死というのは少しも怖いものではありません。死は大いなる解放者です。死は自由をもたらしてくれるのです。皆さんは赤ん坊が生まれると喜びます。が、その時、私たちの世界では大勢の者がこれから地上に生まれていく人を泣いて見送っているのです。同じように地上では人が死ぬと泣いて悲しみますが、私たちの世界ではその霊を喜んで迎えているのです。なぜならば、死の訪れは地上生活が果たすべき目的を果たし終えて、次の世界が提供してくれる莫大な豊かさと美しさを味わう用意がその霊にそなわったことを意味するからです。》(『シルバー・バーチは語る』近藤千雄訳、ハート出版、2003年、21〜23頁) 心に響く「アメイジング・グレイス」 ー生活と文化をめぐる随想(36)ー 2004.3 「アメイジング・グレイス」の歌は、日本でも多くの人々が耳にしているのではないでしょうか。歌の名前を知らなくても、このメロディーを聞けば、「ああ、あれか」と気がつかれるかもしれません。さだ・まさしの「風に向かって立つライオン」でも、最後のハミングにこのメロディーが使われています。 このメロディーは、もともと、スコットランドに古くから伝わっていました。そのメロディーに、イギリス中部のオールニー教会のジョン・ニュートンという牧師が、次のような意味の歌詞をつけたのです。それが「アメイジング・グレイス」です。四節ありますが、そのうちの一節だけを和訳してみましょう。 神のみ恵みは なんと優しく胸を打つことか、 私のような惨めな人でなしでも お救いくださった。 生きる道を間違え盲目であった私も、 今は目が開かれて神を崇めている。 作詞者のジョン・ニュートンは、一七二五年にイギリスの貧しい家庭に生まれました。学校にも通えず、若くして、父親のつてで船乗りになります。イギリスの商品を西アフリカまで運び、その商品と引き換えに、奴隷を連れて帰るという仕事をしていました。無神論者で船乗りをしている間は、放蕩の限りをつくしていたようです。後に彼は、「私はかつて悪魔に仕える者の一人であった。もしもすべてが私の思うがままになっていたら、世界は破滅していただろう。大酒飲みや女遊びをする者など、かつての私に比べれば可愛いものだ」などと、述懐していたくらいです。 そのジョン・ニュートンの乗っていた奴隷船が、あるとき、大西洋の真ん中で猛烈な嵐に見舞われて沈没しそうになります。彼はその時、思わず「神よ助けたまえ」と必死になって祈りました。 神をまったく信じていなかったのに、なぜ神に救いを求めたのか。彼はそれを神の啓示として受けとめました。九死に一生を得た彼は、やがて、奴隷貿易から手を引き、今度は奴隷貿易廃止の運動を始めます。そして最後には牧師になって、熱心に神の教えを説くようになっていったのです。 彼は、ほかにも讃美歌をいくつか書いていますが、この「アメイジング・グレイス」には自分の劇的な体験を重ね合わせて、特別の深い思いを込めていたに違いありません。「私のような惨めな人でなしでもお救いくださった」と書きながら、彼のこころは感動で震えていたのではないでしょうか。 これは、キリスト教会で讃美歌として歌われているほか、スコットランド民謡として、いまでは欧米でひろく親しまれるようになりました。東京でも、私はこのメロディーを聞く度に、こころが洗われるような気がします。 むかし私は、ロンドンに着いたばかりで家探しをしていた頃、カンタベリーの民宿で朝食を取っていたとき、急にこの歌がラジオから流れ出したことがありました。私はなぜかその時、「ああ、イギリスへ来たんだなあ」と妙に感慨にふけっていたのを思い出します。 その後私は、この歌をロンドンの街の中や、ラドローという小さな古い町を歩きまわっているときなどに耳にしたり、私の住んでいたロチェスターの街でも、何度か聞いたりしました。そして、聞くたびにいつも、なにがしかの感動を覚えなかったことはありません。 大学の夏休み中のことです。ロンドンをバスで出発して、ウェイクフィールドに一泊したあと、スコットランドへ入りました。それからエディンバラをかすめて北上し、小さな名もない寒村で昼食をとっていました。 その古いレストランの前は綺麗に手入れされた芝生になっていて、そのむこうに民芸品を売っている店が一軒見えていました。その入り口付近で、キルトをはき、バグパイプを口にくわえた老人がスコットランド民謡を演奏していたのです。まわりはスコットランドの田舎らしい侘びしい雰囲気です。その中での鄙びた老人の姿は、まわりの風景によく溶け込んでいるような気がしました。 私がレストランを出て、その老人のほうへ近づいていったそのとき、急に曲目が変わって、「アメイジング・グレイス」が流れ始めました。緩やかに哀調を帯びて漂うその旋律は、こころに深く染みこんで、私は体が小刻みに震えるほどの感動を覚えました。哀しみの歴史を秘めたスコットランドの小さな寒村の、バグパイプの老人の、これが「アメイジング・グレイス」 の歌なのだろうと、その時しみじみと思ったことがいまも忘れられません。 コルベ神父の愛の奇跡 ー生活と文化をめぐる随想(37)ー 2004.5
マクシミリアノ・コルベ神父は一八九四年一月八日にポーランドに生まれました。ローマのグレゴリアン大学と聖ボナベンツラ神学大学で哲学と神学を学び、一九二七年にはポーランドで聖母の騎士修道院を創設しています。一九三〇年に来日し、一九三六年にポーランドへ帰国するまで、六年間、長崎で布教に務めていたこともあります。 このコルベ神父が帰国して間もなく、ヒトラーのドイツ軍がポーランドに侵攻し、一九三九年九月に第二次世界大戦が始まりました。ポーランドを占領したドイツ軍は、自分たちに反感をもつ一般の民衆のみならず、社会の指導的立場にある多くのポーランド人にも弾圧の手を広げて、一九四一年二月にはコルベ神父も、あの悪名高いアウシュビッツの強制収容所へ送り込まれてしまったのです。 その年の七月末、ここで、コルベ神父が収容されていた第一四号獄舎から、一人の逃亡者が出てしまいました。収容されていた人々は、恐怖で身震いしたことでしょう。収容所長フリッチの警告があって、もし逃亡者が一人出たら、罰として、同じ獄舎に収容されている者のうち、一〇名が餓死刑に処せられることになっていたからです。 逃亡者が出た日の翌朝、点呼の時、他の獄舎の人々は解散を命じられましたが、第一四号獄舎の人々はその場に残されました。彼らは炎天下に何時間も立たされたあと、やがて所長のフリッチがあらわれて、囚人たちの顔を見ながら、一人また一人と指名していきました。そして一〇名の餓死による処刑者が決まったのです。 指名された人たちはどのような気持ちであったでしょうか。あまりの残酷無慈悲に神をも呪ったかもしれません。残された記録と証言によりますと、そのなかの一人は、突然、「ああ、妻と子供が可哀想だ。もう一度会いたい!」と泣き叫びはじめたのだそうです。しかし、冷酷なフリッチは、うむを云わさず彼らの靴を脱がせ、はだしのまま餓死刑の監房のある第一三獄舎の方へ追い立てようとしました。 そのときです。まったく誰もが予期しなかったことが起こりました。一人の囚人が、あっけにとられる仲間たちをかきわけて、前へ進み出てきたのです。コルベ神父でした。頭を少し傾け、目を大きく見開いて、フリッチの前に立ちました。 慌てふためいて拳銃に手をかけたフリッチの前で、コルベ神父は、笑みさへもふくめながら、「私をあの人の代わりに死なせて下さい」と、落ち着き払って言いました。コルベ神父は静かに続けます。「私は年寄りで、なにもできません。生きていてもたいして役に立ちませんから、あの人の代わりに死なせて下さい。あの人には妻子があります。」 しばらくは沈黙が続いたそうです。フリッチが事態を呑み込むのには時間がかかったのでしょう。ただ、そのときの彼には、「否」と答える力はありませんでした。しゃがれた声で許可を与えた後は、黙り込んでしまったのです。この許可によって、先程の嘆き悲しんでいた男、フランシスコ・ガイオンチェックは元の列に戻り、コルべ神父は餓死刑の監房へと消えて行きました。 餓死室では、一〇人が一緒に閉じこめられて、食べ物も水も一切与えられません。収容者の一人で、死体運搬の役目を命じられていたボルゴヴィオクという生き残りの証人がいましたが、その彼の話によれば、他の人々の死体はすべて、ひきつった無惨な顔をしていたのに、コルベ神父の顔は、清潔で輝いているように見えたといいます。 アウシュビッツ収容所は、いまではポーランドの国立博物館として一般に公開され、このコルベ神父が入れられた六畳間ほどの鉄格子の部屋も見ることができます。薄暗い廊下を通ってこの鉄格子の前に立ちますと、なかには十字架と花模様で飾られた大きなローソクが立てられていて、その左右には二本のローソクと花輪が供えられていました。その前には、ポーランド語と英語の説明版があって、「逃亡者が出て集団責任を負わされた囚人たちが餓死刑を執行された部屋。仲間の囚人の身代わりとなったコルベ神父もここで死んだ」と書かれています。 イエス・キリストは、「友のために生命を捨てるより大きな愛はない」といいましたが、コルベ神父は、文字通りにそれを実践しました。それも、もっとも耐え難いと思われる餓死刑によってです。この「愛の奇跡」に対して、一九八二年十月十日、ローマ法王ヨハネ・パウロ二世は、「カトリック聖人」の尊称を贈って、コルベ神父を称えました。 修行者と羅刹 ー生活と文化をめぐる随想(38)ー 2004.7 むかし、ヒマラヤの雪山にひとりの若い修行者がいました。雪山で修行に励んでいたので雪山童子と呼ばれていました。その雪山童子は、衆生を救うための法を求めて、いろいろと難行苦行を続けていましたが、その修行の姿を、天からじっと眺めていた神がいました。帝釈天です。 帝釈天は、東京でも柴又の帝釈天で有名ですが、もともとは、インドの聖典にあらわれる最大の神です。インドでは、悟りを開こうとする求道者は数多くいました。しかし、固い志で、難行苦行に最後まで耐えて、悟りに至る人はほとんどいません。帝釈天は、雪山童子の難行苦行は本物だろうかと、試してみようとします。 まず、帝釈天は、みるも恐ろしい羅刹に姿を変えました。羅刹というのは、インドの鬼で、人を食べるといいます。羅刹となって天上から雪山へ下りてきた帝釈天は、雪山童子の近くまで来ると、過去生の仏が説いた教えを詩句にして、その前半を、声高らかに唱えました。 諸行無常 是生滅法 (作られたものはすべて無常である。生じては滅することを本性とする) これを聞いた雪山童子は、深い喜びに包まれます。のどが渇ききっているときに、冷水にありついたような心地でした。これこそが真理のことばだ、どうしても、この後の句も聞きたいと思ったのです。けれども、そこにいたのは恐ろしい形相の羅刹だけでした。よもやとは思ったのですが、雪山童子は、羅刹に尋ねました。 「いまのことばは、過去、現在、未来の三世にわたる仏の教えで、真理のことばです。この続きがあるはずですが、ご存じでしたら是非教えてください」 羅刹は答えました。「私は幾日も食べ物が手に入らず、飢えて渇いている。人肉を食べたいし、人の生き血も飲みたい。お前の体をくれるというのなら、教えてやろう」 雪山童子は、しばらく考えて、静かに答えました。「わかりました。残りのことばを聞くことができたら、私の体はあなたに差し上げましょう。私の体は、たとえ天寿を全うしたとしても、どうせ獣か鳥に食われるだけです。それに、食われたからといって、なんの報いもあるわけではありません。それならば、悟りの道を求めるために、この体は捨てることにいたします」 それを聞いた羅刹は、雪山童子の固い決意に迷いがないのを見届けると、やがて、居ずまいを正して、ゆっくりと、後半のことばを唱えました。羅刹とは思えない美しい声です。 生滅滅己 寂滅為楽 (生滅するものがなくなり、静まっていることが安らぎである) こう説いてから、羅刹は、約束通り、雪山童子の体をくれるようにと詰め寄りました。 雪山童子は、覚悟の上のことですから、体を捨てるのにはなんのためらいもありません。ただ、後世の人々のためにと、このことばを、まわりの岩や木に書き留めると、近くの高い木に登り、地上へと身を投げたのです。 その瞬間、雪山童子の体がまだ地上に着かないうちに、羅刹はさっと帝釈天の姿に戻り、空中で、雪山童子の体を受け止めてしまいます。そして、恭しく地上に降ろし、雪山童子にひれ伏して礼拝しました。この雪山童子が、実は、お釈迦様の前世の姿であると、仏典の「涅槃経第十三」は伝えています。 この話は、日本文学の中にもとりいれられ、戦前の文部省・小学国語読本では、巻十二に「修行者と羅刹」というタイトルで載っています。この雪山童子の聞いた真実のことばは、雪山にちなんで「雪山偈」とよばれていますが、私が、もう六十年も前の、小学校六年生の時に習ったときには、これはつぎのように、「いろは歌」になっていました。 色は匂へど散りぬるを 我が世誰ぞ常ならむ 有為の奥山今日越えて 浅き夢見じ酔ひもせず このいろは歌の登場は、平安中期になってからのようです。和音の異なる四十七文字をすべて一度だけ使って雪山偈を和訳したもので、空海の訳といわれたりしましたが、それは、いまでは否定されています。いったい誰が訳したのでしょうか、その神業のような翻訳の巧みさには驚かされます。私たちが日常何気なく口にしている「イロハニホヘト・・・」には、このようなインドの雪山偈以来の、深い意味と歴史が秘められているのです。 ガリラヤ湖で起こった奇跡 ー生活と文化をめぐる随想(39)ー 2004.9 最近、高い霊能力をもっておられる T さんとお会いしたときに、「エルサレムのポンテオ・ピラトの官邸跡へ行かれたことがありますか」 と聞かれました。ポンテオ・ピラトというのは、紀元二七年から三六年にかけてユダヤを統治していたローマの総督です。イエス・キリストはユダの裏切りによって捕らえられたあと、そのピラトの官邸に連れてこられて、審問の末に死刑の宣告を受けました。T さんの問に、私が「いいえ、ありません。イスラエルへもまだ行ったことはないのです」 と答えますと、T さんは、「一度行かれるといいと思います。何か感じられるかもしれません」 と言われました。 私は、いままでも何度か、T さんが、前世でのイスラエルやイギリスで私と会っていることを聞かされていました。T さんによりますと、私は、イエス・キリストが捕らえられた当時、ローマの法務官としてピラトの官邸に居ました。イエスのこともよく知っていたはずだから、その現場に立てば、何かを思い出すかもしれないと言っておられるのです。 イスラエルに生きていた時の T さんは、小間物を商っていて、ロバ二頭に乗せた雑貨類を、イスラエルの街のなかで売って歩いていたそうです。一頭は自分が引き、もう一頭は若い使用人に引かせていました。いま、T さんは、二〇人ほどの社員をかかえたコンピュータ会社の社長で、映画のプロデューサーなどもしておられますが、その現在の社員の一人の N さんが、そのときの二頭目のロバを引いていた若い使用人であったといいます。 いまから十数年前、東京でエルサレムへの「巡礼団」が組織され、三〇人ほどの参加者に混じって、T さんも、今生では初めて、エルサレムの地を踏まれました。T さんは、二千年前の前世では、エルサレムの街は小間物屋として街の隅々まで歩きまわって熟知していましたから、その時の旅では、現地の人しか知らないような古い小路なども、次々に思い出して、人々を驚かせたということです。 むかしの T さんは、イエスのガリラヤ湖畔での説教も、小間物を売りに街へ行った帰りなどに立ち寄って、何度も熱心に耳を傾けたことがあるそうです。十数年前の旅では、そのイエスの説教の地を訪ねて、ガリラヤ湖を船で渡る経験もされました。その前日の夜、ホテルの自室で、T さんは、初めて自動書記の体験をされることになります。ひとりでに手が動いて、たった三〇秒ほどの間に、つぎのような啓示が伝えられたということです。 《汝、心静かにして我を思え。我は常に汝と共にあり、汝、我と同じにして我を助けん。汝、我と共に事をおこして我と共に戦わん。全ての民を助けんと、汝、我と共に行かん。我と汝とは不離一体なり。戦いは辛く耐え難きものなり。しかし汝、我を信じ、神を信じ、すべてを包括せし者。艱難辛苦に出会うとも、我、汝と共に常に歩まん。汝、悩むとき道を失いしとき、心静かにして我に祈れ。おのずと道は開かれ、その道は光の道なり。汝に不可能なく、汝、祝福される者なり。汝、一なる者にして、神なり。》 次の日の天候は荒れ模様で、ガリラヤ湖を横断する船も、高い波に翻弄されていたそうです。日本からの巡礼団を含めた六〇人ほどの乗客は、みんな立っておられず、船内の椅子に座っていても、肘掛けや背もたれにしがみついていました。「イエスはこういう荒れた湖をなだめて小舟で渡って行ったんだよね」 と誰かが言ったそうです。そこで T さんは誰もいない甲板へ出て、大きく十字をきりながら、「波よ静まれ、天よ晴れよ」 と叫んだのです。そして奇跡が起こりました。 走っている船の上の空が割れ、船はちょうどスポットライトを浴びているように、光の線に包まれて、前後左右の激しい揺れも急に収まってしまいました。まわりの湖は荒れたままだったのに、船だけは大きな力で支えられて誘導されているように、静かな航海を続けて、岸辺にたどり着いたということです。 荒唐無稽な話のように聞こえるかもしれませんが、その船には、やはり日本から同行した I さんが乗っていました。I さんも、イエス・キリストの時代には、ローマに生きていましたが、イエスの教えを聞くために、いわば国禁を冒しながら、はるばるとエルサレムへ命がけの旅をしたといわれる人です。その I さんが私に言いました。「あれは、本当に不思議な体験でした。あれほど船が揺れて、乗客はみんな青い顔で不安がっていたのに、急に船の上に光が射し込んできて、走っていても全く揺れなくなってしまったのです。」 「天の摂理」に気づかない人たち ー生活と文化をめぐる随想(40)ー 2004.11 この間「朝日新聞(9・13)」に、東京で一人暮らしをしている或る女子学生が、物干し竿を買ったときの「失敗談」を書いていました。 竿売りの車が来て、「竿ヤア、竿竹ェー。一本四百円からございまーす」というので、車を覗くと、中年の夫婦らしい二人がいました。女子学生が、「四百円のでいいわ」と言いますと、「いや、あいにく今日は在庫がないんです」と男性のほうが答えます。すると、女性のほうが、「お父さん、これがいいよ、これ持っていってあげな」と素早く、一本の竹竿を渡したのだそうです。女子学生は、その竹竿の値段を聞く間もありませんでした。 アパートのベランダまで持っていってくれて、古いのと取り替えると、男性から「ハイ、四千円です。消費税はまけとくから」と言われます。女子学生は勢いに負けてしまって今更いやとも言えず、仕方なく、四千円も払ってしまいました。それからも時々竿売りがきて、「一本四百円から・・・・」と拡声器で流しているのを聞くと、思わず「それはウソですよ」と叫びたくなる、と彼女は述べています。 実は、私も今年の夏に、札幌の自宅で、似たような目に遭っていました。私の場合は網戸です。 その日は日曜日で、私は庭に出て植木の手入れをしていました。塀の近くまで、拡声器の女性のテープの声が響いて、竿竹の販売と網戸の修理をする、と言っています。私はふと、ベランダの網戸の片隅が破れているのを思い出しました。日曜日もこうして働いている小さな業者のためにもなることだし、この際、修理してもらおうかな、と思ったのです。 車をとめてみますと、出てきたのはがっしりした体格の中年の男性で、目つきがよくないというか、険しいのです。「これは、いかんな」と私は内心思いながら、用心して、現場で「この網戸一枚を張り替えたいのですがいくらですか」と聞いてみました。男性は、「一メートルで千九百円です」と答えました。網戸は二メートルくらいですから、それなら四千円前後ですむことになります。私は、張り替えてくれるように頼みました。 一旦網戸を外してしまうと、男性は、いろいろと言ってきます。まず、この網戸の大きさは規格外だと言い出しました。私は、この辺の家もみんなこれと同じで、規格外ではない、とはっきり答えました。網戸の縁のモヘアを取り替えたほうがいいとか、二、三枚なら安くするなどと言っていましたが、「必要はない」と、これもはっきり断りました。ただ一つ私が注文を付けたのは、黒い色の網をつけようとしていたので、もとの網戸のように、白い色にして欲しいと言っただけです。 男性は黙って網を張り、ベランダに網戸を取り付け、そして、張り替え料一万円を請求してきました。私が、一メートル千九百円であるはずなのに、なぜ一万円になるのかと聞きますと、千九百円は黒い網の値段で、白い網は三千九百円だというのです。それに、ゴムの取り替え、手数料を含めたら、一万円でも安いのだと、開き直りの姿勢です。「ああ、これはダメだ」と私は思いました。 一万円は惜しくはありませんが、そういう詐欺まがいの行為は決して利益にはならず、損をするだけだということを、この「貴重な」機会にわからせてあげられないのは、やはり残念です。人から奪うのではなく、人に与えることが、本当の利益につながっていくということを、こういう人たちに、なんとか知ってもらうことはできないものでしょうか。 この宇宙には、「天の摂理」ともいうべきものが厳然と支配していて、時空を超え、寸分の狂いもなく完全無欠に、私たちの上に働きかけていると思います。奪ったものは必ず奪われていきますし、与えたものは、いつかは間違いなく返ってきます。ですから、奪う行為にも、与える行為にも、私たちは自分で責任をもたなければならないのでしょう。よかれ悪しかれ、蒔いた種を刈り取るのは必ず自分自身だからです。 最近は日本でも、空き巣、ひったくり、強盗殺人などが目に見えて増えてきました。「援助交際」とか「オレオレ詐欺」だとか、銀行が設置したATMを器械ごと盗んでいくというような、一昔前までは考えられない破廉恥で手の込んだ犯罪も、しばしばニュースに取り上げられるようになってきています。 愛を、優しさを、人に与えようとしなければ、人からも与えられることはない。そのことに気がつかないこころの貧しさが、カネで満たされると錯覚して人からカネを奪っても、そのカネは決して身につくことはなく、結局はまた、人から奪われていく。こういう単純明快な道理を、この社会では、もっと深く考えていく必要があるのかもしれません。 No,1〜No,10へ No,11〜No,20へ No,21〜No,30へ No,31〜No,40へ No,41〜No,50へ |
||||||


