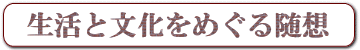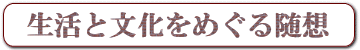|
�@�@�@�@�@���������������A�����J�����̑z���o�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (96)�\�@ �@�@ �@�@
(2014.07.01)
�������߂ăA�����J�̒n�̂́A1957�N�̉Ă̂��Ƃł������B�I���S����w��w�@�̋���w���Ƃ��Ăł���B�܂���ʂ̎���ɂ��C�O�n�q�Ȃǂ͋�����Ă��Ȃ���������ŁA�A�����J�̐�������Ȃǂ��悭�킩���Ă��Ȃ������B�ܗ������̂܂܉��l����і�C�^�̗��M�ۂɕ֏悳���Ă�����āA�����m���T�Ԃ������ĉ��f�����B���M�ۂ�16,000�g���Ń^���J�[�ł������B�A�����J�͐Ζ��̗A�o���ŁA�����m�푈�̔s���A���{�͂��̃A�����J����̐Ζ��A�����ĊJ���Ă����̂ł���B
�@���M�ۂ́A8��12���̒��A���T���[���X�����֎O�\�L���قǂ̃T���E�y�h���u���ɒ������B�傫�ȃW�������~�����̃g�����N��X�[�c�P�[�X�Ȃǐ��̉ו����A�^�N�V�[�̉^�]��ɂȂ�Ƃ��ςݍ���ł�����āA�܂����j�I���E�X�e�[�V�������������B�����ŁA�ċx�ݒ��̉Ċ��u���ɏo�Ȃ���͂��̃J���t�H���j�A��w�o�[�N���C�Z�ɓS���ւƂ��ĉו��𑗂�g�y�ɂȂ������ƁA�n���E�b�h�̃z�e���ōŏ��̖���߂������B
�@�����Ȃ�C���痤�ɏオ���ăA�����J�̊X�ɓ��荞�݁A�S�g�ɗ��т�V�����[�̂悤�ɃA�����J�����̐�����āA����ȃJ���`���[�E�V���b�N�ł������B���͉f��ł����������Ƃ̂Ȃ������n���E�b�h�̊X���������Ă��������ɔ��Ă������A�����̂��߂ɂقƂ�Ljꐇ���ł��Ȃ������B�������L���X�H���̓����A�����玟�ւƃW�F�b�g�@���v�킹��悤�ȃe�[���t�B����������^��p�Ԃ��ʂ�B�����ɂ͏d���ȍ\���́A���{�Ƃ͒i�Ⴂ�ɂ���т₩�ȑ����̓X������A�˂Ă���B�V���[�E�B���h�[�ɂ͉₩�ȏ��i�̐��X�����ӂ�Ă����B���������ƓX�ɓ���ƁA��ʂɃJ�[�y�b�g���~���l�߂��Ă��āA�c�[���Ɠ���������B�A�����J�̖L�����̓����ł���B���́u�L�����̓����v�͂ǂ��֍s���Ă����܂Ƃ��āA�z�e���ł����̓����̒��ŁA���͂܂�Ƃ��������𖾂������̂ł���B
�@�n���E�b�h�̕t�߂ɂ́A���Ƃ��p�T�f�i�̂悤�ȍ����Z��n�������āA�n�E�X���C�h���ق��Ă���悤�ȉƂ��������͂Ȃ��B�f��o�D�̍��ȓ@��Q�̑O���ό��o�X�Œʂ�߂��Ȃ���A���̃n�E�X���C�h�̋���������250�`300�h�����炢�ƕ������ꂽ���ɂ́A�v�킸���ߑ����o�����ɂȂ����B���w����O�̎��́A�D�y�Ō������Z�̋��������Ă����B����30�~�A���[������40�~���炢�ŁA�����̐V���w�Ǘ���330�~�̎���ł���B���̌����́A1���~�ɖ����Ȃ������B���̓����̃h���Ɋ��Z����ƁA����͖�25�h���ŁA�A�����J�̃n�E�X���C�h�̋�����10����1�ɂ����Ȃ�Ȃ������̂ł���B
�@���̍��A�~�ƃh���̊��Z���͌���ł͈ꉞ�A�P�h��360�~�Ƃ������ƂɂȂ��Ă����B�������A����Ńh����������킯�ł͂Ȃ��B���{�́A���̕n���̂ǂ�ꂩ�����Ə����������オ��n�߂������ŁA���{���{���A���p�Ɩf�ՖړI�ȊO�ɂ̓h���̔��������F�߂Ȃ������B�ǂ����Ă��h�����~������A�f�ՊW�̉�ЂȂǂ�ʂ��āA��̂�����u�Ńh���v����ɓ���邵���Ȃ������̂����A���̌������͂P�h��450�`480�~�������B����ł́A���̋�����20�h��������Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��B
�@���̓����̃A�����J�l�́A���M�ƌւ�ɖ����Ă����悤�ȋC������B�����폟���ł���Ȃ���A�푈�ō��y���r�炳��A�o�ϓI�ɂ��敾���Ă������[���b�p�����ɑ��āA�ЂƂ�A�����J�͂�������̗����߂āA�ɉh��搉̂��Ă����B���T���[���X�������ł��������A�X�̂������܂����A�ǂ��ƂȂ������Ƃ�Ɨ��������āA�����������X�܂ōs���n���Ă����B���킴�킵���s���̈Â��e�͂ǂ��ɂ��Ȃ������B���T���[���X�̗�����Ɍ�������n�C�E�F�C�̉��]�́A���̍��̊G�t���ɂ悭�o�ꂵ�āA�l�H���̋ɒv�̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�@�J���t�H���j�A��w�o�[�N���C�Z�ł̎v���o������B�T���̑������ɁA�T���t�����V�X�R�֏o������Ƃ��ɂ́A���̓����͂܂������Ă����I�[�N�����h�x�C�E�u���b�W��n��d�Ԃɏ���Ă����B���͖�ɂȂ�ƃI�����W�F�̃����v�̌��̃g���l���ɂȂ�B�C�̏�ɒ������̉e�𗎂Ƃ��Č��z�I�Ŏ��ɔ������B���̃g���l����ʂ�Ȃ���A�u�����A����͖��ł͂Ȃ����v�Ǝ��͉��x���v�����B
�@�H����I���S����w�ֈڂ��Ă���́A�L�����p�X�̔������ɂ������ł��ꂽ�B�w�����̎����̑����猩����Ő��̗̍L��ȂЂ낪��́A���Ŕ�ꂽ�̂��₳�����J����Ă��ꂽ�B�L�����p�X���o�ĊՐÂȏZ��X���U�����Ă���ƁA�_���̂�傤�̉Ԃ��U���ĕ��������F�̉Ԃ��O�~�ɂȂ����肵�Ă���B�����Ƃ�Ǝ���C���܂��̐F���������܂�ɔ������āA���͑O�ɐi�߂��A���̏�ɂ��Ⴊ�݂���ł��܂������Ƃ��������B�u�����Ƃ�Ƃ��ė����������������v�A����͌܁Z�N��̃A�����J�ł́A���Ȃ��Ƃ����̂܂��ł͂ǂ��ł�����ꂽ���ʂ̏�i�ł������Ƃ����Ă悢�B�����̓��{�́A�s��Ŏ��M�Ɛ����b���r�����A�n���̂Ȃ��ł������Ȃ��獑�y�Č���͍����Ă����B���̓��{�̈Â��̎c�鐢�������Ƃɂ��Ă��������ɁA���̓��ɂ́A���̃A�����J�̔��������A�悯���ɋ�����ۂÂ����Ă����̂�������Ȃ��B
�@���̃A�����J���傫�ȏՌ������̂́A1957�N10��4���A�\�A���l�ލŏ��̐l�H�q���u�X�v�[�g�j�N1���v��ł��グ���Ƃ��ł���B���������炩�I���S����w�̐����Ɋ���n�߂����ł������B�X�v�[�g�j�N�́A������96��12�b�Œn�����������O���ɏ�����B���i�͕��ɒǂ��ăe���r������]�T���Ȃ��A�����J�l�w�����A���̓�����́A�[���̃e���r�j���[�X�̑O�ɓB�t���ɂȂ����B���̃X�v�[�g�j�N�̏d�ʂ�83,4�L���ŁA�A�����J���ł��グ��\�肵�Ă����l�H�q����8�{���̏d���ł���B���̋�����������ɐ��f���e���Ƃ���ƁA�\�A�̓A�����J���j�U���ł��邱�ƂɂȂ�B���̗⌵�Ȏ�����O�ɁA�A�����J�l�̎��M�ƗD�z���͂�����ɗh�炢�ŁA�u�\�A�ɒǂ����ǂ��z���v���A�A�����J���{�ً̋}�ۑ�ƂȂ����B
�@����Ƀ\�A�́A������11��3���A�S�d��508�L���̃X�v�[�g�j�N2���Ƀ��C�J����ςݍ���őł��グ�ɐ��������B�A�����J���{�͘T�������B���̑哝�̃A�C�[���n�E�A�[�́A���̂��ƁA�ً}�ɑS�Č����̃e���r�������s���A�A�����J�̉F���v��𑣐i���邽�߂ɉȊw�E�Z�p�Ɋւ���哝�̌ږ��݂��A���h�ȓ��̋@�\����������A�Ɣ��\�����肵�Ă���B���̉e���ŁA�I���S����w�ł��A���V�A��̗��C�w�����}�ɑ����A���̂�����������āA���{��⒆����Ȃǂ̑��̊O�����I��������̂̐��������݂Ɍ��������肵���B
�@���̐l�H�q���ł��グ�ɂ��[���ȏՌ������A�����J�́A���̌�̃\�A�Ƃ�����ȉF���J�������̖��A1962�N10���ɂ́A�S�ʊj�푈�u���́u�L���[�o��@�v��h�����ĉ������B�����āA1969�N7��20���ɂ́A�������F���D�u�A�|��11���v�ɂ��l�ޏ��̌��ʒ����𐬌��������B�A�[���X�g�����O�D���ƃI���h������s�m���A���ʂɐ������𗧂Ă��̂��e���r��ʂŊm�F�����A�����J�l�̊�тƊ������ǂ�قǑ傫���������͑z���ɓ�Ȃ��B�A�����J�l�͂܂��A�傫�Ȏ��M�����߂����̂ł���B�����A�A�����J���{�́A���̌���\�A�ɗD�ʂɗ����߂̌R���g���̓���˂��i�݁A����ɑ��ă\�A���܂��A���Y��`�̊����Ƃ��āA�A�����J�ɑR����R�����͂�グ�Ă������B
�@���̎��R��`�w�c�Ƌ��Y��`�w�c�Ƃ����Η��̂Ȃ��ŁA�A�����J���{�́A�x�g�i���푈�ւ̉�������[�߂Ă����B�����āA���̃x�g�i���푈�ւ̉���́A�A�����J�Љ�Ɍo�ϓI�ɂ��ϗ��I�ɂ��A�[���ȑŌ���^���A�`���I�ȃA�����J�l�̉��l�ς�傫���h�邪���錋�ʂɂȂ����B
�@1973�N12���̃N���X�}�X�E�C�u�B���͓�x���̒����؍݂̂��߁A�H�c���̓��q�@�ŃA�����J���������B���x�́A�����ȍ݊O�������Ƃ��Ăł���B���c��`���J�`�����̂�1978�N5���ŁA�����͂܂��A�H�c���g���Ă����̂ł���B�܂��A�C�O���s�͂��܂قǐ���ł͂Ȃ������B�Ζ���̏��M���ȑ�w�ł��A���{���̋����Ƃ��ĊC�O�֏o�鏉�߂Ă̕����Ȕ��߂ŁA�����ɂ���݂ɂȂ�ƌ���ꂽ�肵���B���ƌ������������s�@�����{�q����g��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ȒʒB������������ł���B
�@���̕�Z�̃I���S���B���W�[���̃I���S����w��1�N�ԉ߂������ƂɂȂ��āA���͍Ȃƒ��w��N�̒����A���w�Z�ܔN�̒��j�̉Ƒ��l�l�ŁA�A�q���n�߂�����̃W�����{�@�ɏ�荞�B�S�����\���[�g���A�S���Z�\���[�g���̃{�[�C���O���l���^�@�́A�܂��n���C��ڎw�����B�ō��Ŏl�S��\�l�����鋐��ȋq���ɁA��q�͎��������܂߂Ă������O�\�l���炢�������Ȃ��B�قƂ�Ǒ݂����Ԃł���B�u�������Ȃ��ł��ˁv�ƃp�[�T�[�Ɏ��������ƁA�u��C���^��ł���悤�Ȃ��̂ł��v�Ƌ�����Ԃ��Ă����B
�@���̍��A���{�݂̂Ȃ炸�A�قƂ�ǂ̉��ď����́A�I�C���V���b�N�Ɍ������h��Ă����B���̔N10��6���̑�l�������푈�̖u�������������ɁA�A���u�����͐Ζ���헪�I����Ƃ��āA�Ζ������̍팸�v���W�J���n�߂�����ł���B����܂ŁA�����Ζ����̂悤�Ɏg���Ă���������i�����́A���̐Ζ��헪�ɑ傫�ȑŌ������B���Ɏ����̏��Ȃ����{�ł̓C���t���ɔ��Ԃ�������A�����̓c�����t�̌o�ω^�c���ɂ߂č���ȏɒǂ�������B�s���ɂ���ꂽ�Q�O�̃g�C���b�g�E�y�[�p�[���܂Ȃǂ̔�����ߑ������N������������Ă���B�A�����J�ł��A�R���s���̂��߂ɍ������̑��q���Ђ��啝�Ȍ��ւɓ��ݐ�A�j���[���[�N�s�́A�Ԃ̓s�S��������֎~�����B�J���t�H���j�A�ł��A�K�\�����X�^���h�ł��ł����R�ɃK�\���������Ԃł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@�I�C���V���b�N�̍Œ��ɂ���������ł��낤���A�n���C���烍�T���[���X�ɒ����āA�����܂�����s���̕��͋C�́A�ǂ������ʂ������Ă����B�n���E�b�h�Ȃǂ̖L�����̍���͌��݂ł��������A�X�̂������܂����Ȃ�ƂȂ����킴��Ƃ��ė����������Ȃ��A���́u�����Ƃ�Ƃ����������v�́A�����ǂ��ɂ��������Ȃ������B�����A�T���t�����V�X�R�֔�сA�����ł�����؍݂��āA���W�[���̋�`�ɒ������̂́A��A���̂�����[��ł���B
�@�I���S����w�ł́A���m�j�S���̃t�@���R�l�����������̐��b���Ƃ������ƂɂȂ��Ă����B�������̌��ւƔN���̍��G�ŁA�����̕ւ̗\���Ȃ��������Ƃ��T���t�����V�X�R����d�b�Ő������āA���W�[����`�ւ̓��������m�点��ƁA�u�����ɋ�`�܂ł̃K�\��������ɓ���Ƃ����̂ł����v�ƁA�����͖��Ȃ��Ƃ������B���͂��̎��������k���Ǝv�����̂����A�����ł͂Ȃ����Ƃ͂��Ƃł킩�����B�I���S���ł́A�J���t�H���j�A���Ζ�������������[���ŁA���̌㎄���g���A��w�֒ʂ��Ԃ̃K�\��������ɓ����̂ɁA���т��ђ��܂��Â���������N���o���āA�K�\�����X�^���h�̑O�ɕ��ԉH�ڂɂȂ����̂ł���B
�@���̂Ƃ��̃t�@���R�l�������́A�������A�����Ƀx���c�ɏ���Č}���ɗ��Ă��ꂽ�B���́A�Ƒ����Љ�A�������[��ɂȂ��Ă��܂����s��ۂ�l�т��B��w�ŗp�ӂ��Ă���Ă����h�ɂɓ���葱���͎��ԊO�ŏo���Ȃ������̂ŁA�Ƃ肠�����߂��̃z�e���ֈē����Ă�������B�ו����z�e���̕����ɉ^�э���ł���āA�������A���Ă������Ƃ��A�����ł������ɋ���̏��̉������ꂽ�B���v���݂�Ƃ��傤�Ǘ뎞�ł������B�������Ƒ��̃��W�[���ł̐����͂͂��炸���A��㎵�l�N���t���ƂƂ��Ɏn�܂邱�ƂɂȂ����B
�@���̗��w���ォ��\�ܔN���o�āA�I���S���̐��������A�����J�Љ���z���ȏ�ɕς���Ă��܂��Ă����B���M�ƌւ�ɖ����������̈��芴�̂悤�Ȃ��̂����̂܂ɂ������Ă��܂��Ă���B�l�X�̖�Ɋ��ɑ���s�����萶���A�Љ�ɑ���s�����T�ς��n�߂Ă����B�@�����ł́A���Ƃ��A�������ݏo�����_��ł���B���܁Z�N�ォ��Z�Z�N��ɂ����Ă̓��{�ł��A�h�W���E��_�J�A�z�^���Ȃǂ��}���Ɏp�������Ă����āA�y��̉������[�������Ă���B�����͂���ł��A�l�X�̖ڂ́A�l�̐����ɒ��ڊւ�鐅���a�ȂǂɒD���Ă��āA�����S�ʂɂ܂ł͊S���y�Ȃ������B
�@�������A�A�����J�ł́A���Z��N�ɏ�����Ƃ̃��[�`�F���E�J�[�\�����w���ق̏t�x�Ŕ_���̎��̂��������Ĉȗ��A���������Љ�I�ȑ���ɂȂ��Ă����B����܂łƂ��납�܂킸�܂���Ă���DDT�Ȃǂ̗L�@���f�n�_���Ő��̋����L�@�����܂��A�����ɂ́A������v�����E���Ă������łȂ��A�l�̖��܂ł��������Ă��邱�Ƃ�m�炳��āA�l�X�͜��R�Ƃ����̂ł���B
�@�~�V�V�b�s��ʼn����ɂ�鐅���_�f�̌��R�̂��߁A�������S���P�ʂŎ���ł����Ƃ����s�C���ȃj���[�X���`�����ĊԂ��Ȃ����ł���B���̂ق��ɂ��A�j�����ɂ�鎀�̊D�A�T���h�}�C�h���̖��Ȃǂ������������ɁA�_���̖��͓��ɏ����ɑ傫�ȕs����^�����B���̃A�����J�̎Љ�ł́u�l�Ԃ͕�̑ٓ��ɏh�����Ƃ�����N�V���Ď��ʂ܂ŁA���낵�����w��i�̎����̉��ɂ���v�ƃ��[�`�G���E�J�[�\���͏����Ă���B�A�����J���{�͍����̖�ɋ}���ɂЂ낪�����s���������邱�Ƃ��o�����A1970�N�ɕĊ��ی�ǁiEPA�j�������đΉ��ɏ��o�����B���̊������̖��́A���̌���A�Ԃ̔r�C�K�X�����␅������������˔\�R��A���ː��n�t�̊C�m�������ɂ܂ŋK�͂��L���āA���܂��l�X�̋��̒��ɏd�ꂵ������ł���Ƃ����Ă悢�B
�@�Љ�ɑ���s���ł́A���Ƃ��A�l�퍷�ʂ̖�肪����B�������w���Ƃ��ăA�����J�ɂ������ɂ͂܂��A�암�ł͌��R�ƁA���l���ʂ��s���Ă����B���ܔ��N�̉ċx�݂ɁA�嗤���ʼn��f���ăj���[���[�N�֍s���A��������o�X�œ쉺���ăA�g�����^�֒������Ƃ��ɂ́A�o�X�̑ҍ��������l�p�ƍ��l�p�ɕ������Ă����B�uWHITE
ONLY�v�Ə����ꂽ���l�p�̑ҍ����́A�L�X�Ƃ��Đ����ŁA�N�[���[�������ė������B�������A���l�p�̑ҍ����́A���ꂵ���������ŃN�[���[���Ȃ����ꂵ�������B�A�W�A�l�͎��l�p�ɓ��邱�ƂɂȂ��Ă�������A�������߂����v�������Ȃ�����K�Ȏ��l�p�̎����ŗ��̔����x�߂Ă����L��������B���̍��ɂ��̃��g�����b�N�������N�������B
�@�A�[�J���\�[�B���g�����b�N�s�̃Z���g�������Z�ŁA��l�̍��l�V�������A�w�Z�ɓ��낤�@�@�Ƃ����B���̂Ƃ��ɁA���l�̓��Z���������Ƃ���Q�O�Ǝ�낤�Ƃ���Q�W�̊ԂŏՓ˂��N���@��A���҂��o�������ɂ܂Ŕ��W�����̂ł���B���l�Ɣ��l�̋��w���֎~����암���B�̖@���́A���łɃA�����J�A�M�ō��ٔ��������@�ᔽ�̔��f�������Ă����B���l�^���w���҂����́A�������ɑ哝�̃A�C�[���n�E�A�[�ɕی��v�����A���l�V���������́A�O�S�\�l�̋���̌x���̂��Ƃɂ悤�₭�o�Z���ʂ������B
�@�������ŁA���͎��܂����킯�ł͂Ȃ��B���l�������Ȏs�������Ђ낭�F�߂���悤�ɂȂ�܂łɂ́A���̌�����]�Ȑ܂̒������̂��v�����B���Z���N�̎l���ɂ́A���l�A����^���w���҂̃}�[�e�B���E���[�T�[�E�L���O�q�t���A�e�l�V�[�B�����t�B�X�ō��l���|�J���҂����̃X�g���C�L���x�����A���l�e�����X�g�ɏe�Ō�����Ď��S���Ă���B���̈ÎE�ɓ{�������l�����́A�����t�B�X���͂��߁A�{�X�g���A�j���[���[�N�ȂǃA�����J�e�n�Ŗ\�����N�������B���Ɏ�s���V���g���ł́A�\���̋K�͂��g�債�āA���R�����l��l���o�����Ē����ɓ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̂悤�Ȑl�퍷�ʂ��߂���Ύ�́A���̓�x�ڂ̃A�����J�؍ݒ��ɂ������邱�ƂȂ������āA�A�����J�Љ�ɔZ���A�e�𓊂������Ă����̂ł���B
�@�������A��͂艽�����A�����J�Љ���Â����傫���c�߂Ă������̂́A�A�����J�R�ɂ��x�g�i���푈�ւ̉���ł������B���Z�l�N�����A�x�g�i���ł�����g���L���p�������N�������B���̌��̓���A�A�����J���{�̓g���L���p�̌��C��ŃA�����J�쒀�́u�}�[�h�b�N�X�v���A�k�x�g�i���������O�ǂɂ�鋛���U���������A�������ĂP�ǂ������A����2�ǂ���ꂩ��͍̊ڋ@�ɂ���Č��ނ����A�Ɣ��\�����B���̑哝�̃W�����\���́A�����ɖk�x�g�i���ւ̕����𖽗߂���B�����Ĕނ́A�A�����J�㉺���@�Ɂu�g���L���p���c�āv��������āA����A�W�A�ɂ������̌R���s���̌�����v�������B�������[�h������オ���Ă����c��́A��@�c����l�������������ŁA���̑哝�̂̕��͍s�g����������ƔF�߂Ă��܂����B
�@�������A�A�����J�����ł͂Ȃ��ɂ���A���{��R�͂����ΉR�����B���ƂɂȂ��Ă킩�������Ƃ����A1968�N�̃A�����J��@�O���ψ���̒����ŁA�g���L���p�����́A�A�����J�R���푈���g�傷�邽�߂ɖژ_�ł��������ł��邱�Ƃ����������B�A�����J�R�́A�Z�l�N������A��x�g�i���R���g���Ėk�x�g�i�������́u34A�v�Ə̂���B�����𑱂��Ă���A�}�[�h�b�N�X�́A���C��ł͂Ȃ��k�x�g�i���̊C���ŃX�p�C���������Ă����̂ł���B�����ɏI���͂��ł������x�g�i���푈�ւ̉�����A����Ɛ[�݂ɂ͂܂��Ă����̂��݂āA�A�����J�����ɂ����타�[�h���Y���n�߂��B���̂悤�ȂȂ��ŁA�ł肾�����A�����J���{�́A���Z�ܔN�ɖk�����J�n�A�A�����J���O�ǂ����ї����������@���A�����\���e�ƃ��P�b�g�e�Ŗk�x�g�i���̃h���z�C�ɂ���R���{�݂��U������B�x�g�i���푈�͈�C�Ɋg�債���B
�@���̖k���J�n�ɂ������ăA�����J���{�́A�u��x�g�i���������������A���̓��̖����A��x�g�i���������ɂ���u���[�N�̃A�����J�R��n���P���������Ƃɑ���ł���v�Ɣ��\�����B������������A�S���̌����ɂ����Ȃ��������Ƃ��A���ƂɂȂ��Ă킩��B�k���́A�O�N�㌎�̃z���C�g�n�E�X�ł̐헪��c�ł��łɌ��肳��Ă����B�A�����J���{�́A�k���ɂ���Ėk�x�g�i���ɑŌ���^����Ɠ����ɓ�x�g�i���R�̎m�C�����߁A�A�����J�y�[�X�ł̘a�����ɖk�x�g�i������������o���A�Ƃ����V�i���I��`���Ă����̂ł���B
�@�������A�k�x�g�i���Ɖ������́A�A�����J�ɑ���O��R���錾�����B���\�̉�������ƃA�����J���܂߂����������̍����̖�ɍL���锽�타�[�h���A�����炭�ނ��͂Â��Ă����ł��낤�B�k�������ł͌��ʂɌ��E������Ƃ݂��A�����J���{�́A�k������w�g�傷�����Ő퓬�����̑��h�����߁A���N�����ɂ́A�x�g�i�������̃A�����J�R�������ܐ�l����\�ܐ�l�ɑ��₵���B
�@�A�����J�����̔��타�[�h�͈�w�L���Z�����Ă����悤�ɂȂ����B�Z���N�l���\�ܓ��Ƀj���[���[�N�A�T���t�����V�X�R�Ŏn�܂�������W��́A�\����\����Ƀs�[�N�ɒB�����B�ȗ��A���̓��́A�u10�E21���۔���f�[�v�Ƃ��ċL�O���ׂ����ƂȂ����B���̂悤�ȃx�g�i���푈�ɂ�鎞��s�����ł��g�߂Ɋ�������Ă����̂́A�����܂ł��Ȃ��A�푈�ɂ��肾����n�߂��x�r�[�E�u�[������̎�҂����ł���B���̎�҂������W�߂ĊJ���ꂽ���Z��N�����̃E�b�h�X�g�b�N�E�R���T�[�g�́A��O�̋K�͂ɖc��オ�����B�j���[���[�N�k����S�\�L���̉��ɂ��Ă�ꂽ���_��ɂ́A�ܖ��l�Ɨ\�z����Ă������O���l�\���l�ɂ��B�����̂ł���B
�@�A�����J�̐N�����́A�E�b�h�X�g�b�N�𐢑�̘A�т̏ے��Ƃ��A������E�b�h�X�g�b�N�E�W�F�l���[�V�����ƌĂB�ނ�͌����̎Љ�V�X�e���̎��������ۂ��A�A�����J�̌����������Ɏ��������̑z�肷��Љ�ւƕω������Ă��������l����悤�ɂȂ����B����ł͖��������҂�ɗ��p����A���̕\�������R�z���ɂȂ��Ă����B�]���̃A�����J�Љ�̉��l�ς��傫���h�炬�n�߂��̂͂��̂����肩��Ƃ����Ă悢�B
�@���̂��ƁA�\�ꌎ�\�O������́A�A�����J�e�n�Ōv�S���l�ȏオ����f�����s���A�\�ܓ��ɂ͎�s���V���g���ł̔���W��ɁA�S�������\�ܖ��l���W�܂����B��s�ɂ��ꂾ���̃f���Q���҂��W�܂����̂́A�A�����J�j�㏉�߂Ă̂��Ƃł���B�������s��ꂽ�A�j���[���[�N�s���I�ł́A�x�g�i��������f�����W�����E�����[�[����������Ƃ����u�ԋ��킹�v���������B�������A���_�̔��ɂ��������A���̑哝�̃j�N�\���́A�k�������Ɩk�x�g�i���S�`�p�̋@�����������s�����B����ł����ɏ����Ƃ��o�����A���̌�A�A�����J�R�͏��X�Ɏ��ł��Ă����̂ł���B
�@��㎵�O�N�ꌎ�̂�����u�p������v�Ɏ���܂łɃA�����J���x�g�i���ɒ��������͖��O�S���h���ŁA���҂͎l���Z��l�A�d�y���҂͎O�\���O��l�𐔂����B��x�g�i���R���̎����҂́A���ɎO�S���l�ȏ�ɂ̂ڂ��Ă���B�������A���̃p��������A�����㔽�ÂƉ����Ă�������A�푈�̎S���́A���̂��Ƃ���ɓ�N���܂���������̂ł���B
�@���E��̑卑�Ǝ������Ă����A�����J���A����A�W�A�̏����k�x�g�i���Ƃ̐푈�ɑS�͂𓊓����Ă����ĂȂ������B�A�����J�����̂�����̒��ɐ[�����Ղ��c���āA���ǂ́A�k�x�g�i���ɕ������B����ŎЉ�ς��Ȃ��͂��͂Ȃ������B��㎵�l�N�̈ꌎ�������n�܂�����x�ڂ̒����؍݂�ʂ��āA���́A���Ƃ��邲�Ƃɂ��̕ω��ɋC�Â�����邱�ƂɂȂ����̂ł���B�X�̕��͋C�ɂ����Ă̗����������������͂Ȃ��Ȃ�A�Љ���̖��邳�ɂ��Ȃ肪�����Ă����悤�Ɏv�����̂́A�I�C���V���b�N�̐[�����̂��߂����ł͂Ȃ������B
�@���M�Ɗ��C�������n�߂��A�����J�Љ�̂Ȃ��ŁA�ǂ��ł���������悤�ɁA�������̑؍ݒ��ɂ́A�j�N�\���̃E�H�[�^�[�Q�[�g�����Ƃ����̂��������B����͈�㎵��N�Z���A���V���g���̃E�H�[�^�[�Q�[�g�E�r���̃K�[�h�}�����A���r�����ɂ��閯��}�S���{���N�����悤�Ƃ����ܐl�̒j������ߕ₵���̂��n�܂�ł���B���傤�ǃj�N�\�����哝�̂̍đI��ڎw���đI���^����W�J���Ă����Ƃ��ł������B���̍đI�ψ���N�������ƊW���邱�Ƃ͂����ɘI�������B
�@�����͂��炭�̊ԐÂ��ɐ��ڂ��A�j�N�\���͏\�ꌎ�ɑ哝�̂ɍđI���ꂽ�B���̊ԃj�N�\���ƕ⍲���̃n���h�}����A�[���b�N�}���́A�đI�ψ���Ɋւ��鋋���̎x������ŋ��̂��܂����A��@�ȑI����t�A����}�ɑ���I���W�Q�̉�������Ȃǂ��B�����悤�Ƃ����B�����̂��Ƃ����V���g���|�X�g���L�҂Ȃǂ̎����Ȏ�ޒ����Ŏ����玟�ւƖ��炩�ɂȂ��āA�����͈�C�ɑ哝�̂̃X�L�����_���ւƔ��W�����B�j�N�\���́A�ꕔ�̕�������������ƂŎ����͒m��Ȃ������A�ƉR�������������A�₪�ĉB������Ȃ��Ȃ�A���ɔ��������A�哝�̂����C����H�ڂɂȂ����̂ł���B���E�̑哝�̂��C���̓r���Ŏ��C����̂̓A�����J�j�㏉�߂Ă̂��Ƃł������B���̎����ɂ��哝�̂̈АM�͌���Ȃ��ቺ�������A���낤���āA�A�����J�����`�ƃW���[�i���Y���̌��S���𐢊E�ɏؖ����錋�ʂƂȂ����B
�@���̓��W�[���̑�w�h�ɂɗ��������Ĉȗ��A�e���r�j���[�X�ŁA�������̎��������グ���Ă���̂����Ă����B����͕����ʂ�A�������������������ł������B���{�ł͂��̎�̔ƍ߂ł��A��A��J��������₪�ĒNjy�̎�����߂��A�����̂ق����ɖO���ĖY��Ă����B���ꂪ�A�����J�ł́A�����Ă����������Ƃ͂Ȃ������B���̖������X�ɑ���������A�������������ł����Ɏ��J�����̊ԑ������̂ł���B
�@���������B���̓����͉Ƒ��Ƌ��Ƀ��V���g���B�̃X�{�P�B���ɂ����B��w�����w�Z���ċx�݂ɓ������Z�����{����A�������l�l�Ƒ��́A�Â���^�V�{���[�Ƀe���g��Q�܂Ȃǂ̃L�����v�p�i�ƁA�āA���A�R���Ȃǂ�ςݍ���ŃA�����J����̗��ɏo�Ă����B�I���S������쉺���A�J���t�H���j�A����i�H�𓌂ɂƂ��đ嗤�����f�����B���C�݂ɒ����Ă���́A���V���g��D�EC�A�{���e�B���A�A�j���[���[�N�A�{�X�g�����̓s�s���o�ăJ�i�_�̃����g���I�[���֔����A���̂��Ɛ��Ɍ������āA�~�V�K���B����E�B�X�R���V���A�~�l�\�^�A�m�[�X�E�_�R�^�A�����^�i�B�܂ŁA������Ƒ傰���Ɍ����Ζ������̗��𑱂��Ă����B�I���S���̃��W�[�����o�Ă��łɎl�\���A�ꖜ����L���𑖂��Ă��āA���������ɂ̓X�{�P�B���̍L��ȃL�����v��ň�x�݂��Ă����̂ł���B�j�N�\���̎��C�����͂����ŕ������B�L�����v��̕Ћ��ł͎�҂̈�c���傫�Ȋ������グ���B�߂��̃e���g�̉A�ł́A���N�̏������ЂƂ�܂𗬂��Ă����B
�@�X�{�P�B���ł͖������₩��Ă����B���̎l�N�O�̑�㖜���ɂ����܂��܉Ƒ��l�l�ŖK��Ă������A����́A����̓���҂��O�\���l�ɂ��Ȃ����肵�āu�҂����A��ꂽ�A�����Ȃ������v�����ł������B���̃X�{�P�B���̃A�����J����������ł́A����̓���҂͓l�ɂ������Ȃ������B�L�����̂Ȃ����������ƍD���Ȃ��̂��D���Ȃ������邱�Ƃ��o�����B�{���A�����Ƃ͂����������̂ł��낤�B�������A�哝�̂̃X�L�����_�������C�Ƃ����������}�������Ƃ̖������́A�ǂ��ƂȂ���������C������Ă���悤�ȋC�������B
�@��㔪��N�̏H�A���̓t���u���C�g�㋉�������Ƃ��āA�A���]�i�B�̍����̂Ȃ��̊X�c�[�\���ʼn߂����Ă���B�O�x�ڂ̒����؍݂ł������B���̎��́A�ꑫ��ɃA���]�i��w�̕ғ����ɂȂ��Ă��������Ɠ�l�����̐����ł������B�ȂƓ����̑�w�֒ʂ��Ă������j�́A�����̉ƂɎc���Ă����B
�@�c�[�\���́A�A���]�i�B�ł̓t�F�j�b�N�X�Ɏ������̓s�s�ł���B���͂ɂ́A�T���^�E���[�A�J�^���[�i�A�����R���A�E�G�b�g�X�g�[�����̎R�n���A�Ȃ��Ă��āA�����͂�������A�┧��I�o�����������������̓Â��R���قƂ�ǂł���B�������ŗL���ȍ����̊X�����A���܂ł͐l�������\�ܖ����ăn�C�e�N�Y�Ƃŋ}�������Ă���B�����Z��ł��������ł��A�_�z�ƂƊό�����ȎY�ƂŁA�L���ȊX�Ƃ��Ēm���Ă����B�Ȃɂ���A��N�̂����O�S�\�������V�ŁA���x���N���ϓ�\�܃p�[�Z���g���炢�����Ȃ��B����Ȑl�H�_���ɉ��ΔR�����ӂ�Ɏg���Ċ������u����������A���V�C�܂����ł͂Ȃ��ɂ߂Č����̂悢�_�ƌo�c���\�ɂȂ�B�I�����W�A�O���[�v�t���[�c�A�X�C�J�A���������̉ʕ����A���{�̉��i�̎O���̈ꂩ��ܕ��̈ꂭ�炢�̈����ł������B
�@�������A��͂萶�����͌����������B�����u�t���u���C�g�v�̑I�l�̍ۂɁA�z����]���A���]�i��w�ɂ������R�̈�́A�����̂Ȃ��ł̐����̌������Ă݂�����������ł������B��r�����̕��̂��߂ɂ��L�v�ł���B�����āA�c�[�\���ł́A�\�z�ʂ�̌��������������҂��Ă����B
�@�A�����J�ł́A�����܂����{�ɂ���ԂɁA�^�C���m�[���������������āA�呛�����Ă����B�^�C���m�[���Ƃ����̂́A�A�����J�ōł��L���g���Ă�����ɍ܂̖��O�ł���B�h���b�O�E�X�g�A�[�Ŕ����Ă��邻�̒��ɍ܂ɁA�N�����_�J�����������āA�A�����J�e�n�Ŏ��l�̎��S�҂��ł��B����҂��ʂɑ_������ʎE�l�����ɂȂ��鋰�|�̂Ȃ��ŁA�S�Ă��p�j�b�N��ԂɂȂ����B�t���u���C�g�ψ����������ɁA�A�����J�ɒ����Ă��A�^�C���m�[����Ȃ��悤�ɂƂ̒��ӂ̎莆���͂����B
�@���T���[���X�œ���߂����ăc�[�\���ɒ��������̖�A������Ă����Ă��ꂽ�A�p�[�g�̋߂��ŁA��K�͂ȕ߂���̑������������B�w���R�v�^�[������s�Ő��Ȃ���A�T�[�`���C�g�Œn����Ƃ炵�Ă���B�p�g�J�[�̃T�C�������苿���A�������̏e�����������B���̐�����ɂ́A��͂�߂��ŁA�Z�̏��̎q�����҂��ɎE�Q����Ă���B�n�捷�͂�����邪�A�u�A�����J�͂܂���i�ƈ����Ȃ��Ă���ȁv�Ǝ��͎v�����B
�@�A���]�i��w�ł́A����w���̎������̑O�ɘL�����͂���Ń^�C�v���C�^�[��R�s�[�@�������ꂽ�@�펺���������B�R�s�[�@�͑傫���ē��P�Ɏ����^�тł��Ȃ��̂ł��̂܂܂����A�^�C�v���C�^�[�͂��ׂĊ��ȃ{���g�Ŋ��ɌŒ肳��Ă���B�ƍ߂��������Ƃ�@���Ɏ����Ă����B�����A�����R�s�[�@���g���Ă��钋�x�݂̊ԂɁA�ڂ̑O�̎������œ���������B�O�l���������E�������܂��܉����̗p���ň�l�����Ȃ��Ȃ���������Ƃ������ɁA���������̃{���g�ɌŒ肳��Ă��Ȃ��d���^�C�v���C�^�[����䓐�܂ꂽ�̂ł���B�������͘L���̉��܂�����p�ɂ����āA����ȑ傫�Ȃ��̂𔒒����X�Ɠ��ނ��߂ɂ́A��قǂ̋Z�ʂ�����B�����S���C�����Ȃ��������A�����Ȃ�����A���̋Z�ʂ̌������Ɋ��������B
�@���̖������Ƃ̋A��ɁA��w���ɂ���X�ǂ֊�����B�؎���A�J�E���^�[�̉��̃e�[�u���̏�Ŏ莆�ɓ\�낤�Ƃ��Ă�����A������������ł��Ă��̐؎���͂�͂�Ɣ�����B���̐؎���E���Ă��Ƃ̃e�[�u���ɖ߂�ƁA�莆�̉��ɒu�������z�͂����Ȃ��Ȃ��Ă����B��u�̌��ł������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��A���̃A���]�i�A���邢�́A�A�����J�Ȃ̂ł���B
�@���Ɩ��̏Z��ł����A�p�[�g�̕����͕S�������[�g���قǂ�2LDK�ŁA�����͂Ȃ����������܂�V�����͂Ȃ������B�钆�ɋN���đ䏊�̓d�C������ƁA�S�L�u���������Ɠ����Ă������Ƃ�����B�����ʂ�悤�ȏ����Ȃ��炾�ŁA����͋����قǑf�����B�ς��Əu�Ԃɏ����Ă��܂��悤�Ȋ����ł���B��͂荻���̃S�L�u���ł���B�{������悤�ȑ傫�Ȃ��炾�ł������������Ă���悤�ȓ��{�̃S�L�u���Ƃ͑傫�ȈႢ�ł���B�ւł������̎ւ͂����Ă����炾���������A����ł��ďP���Έ�u�ɂ��ċ������|���悤�Ȗғł������Ă���B���ꂪ�����̐������ł���B���炾���傫���ݏd�ȓ����ł���A�H���̏��Ȃ������ł͐����Ă������Ƃ��o���Ȃ��B
�@�����A�F�l�̈�l�ɁA���܂̃A�p�[�g�̓S�L�u�����o�Ă��₾�A�ƌ�������A�ނ͕��C�Ȋ�����āA�^�����`�������Ă��ĕ����̂Ȃ��ɕ��������ɂ��Ă��������Ƃ����B�^�����`�����Ƃ����̂́A�傫�ȓŃO���ł���B�ŃO�������l�Ԃ͂��܂��ɃS�L�u����H�ׂĂ����̂������ł���B���́A������ɂł��o�Ă���悤�Ȃ��̕s�C���ȓŃO���̎p��z�����邾���ł��w�������Ȃ����B�����̊X�Ő����Ă����̂ɂ́A�ׂ��_�o�ł͂����Ȃ��B�j���̂悤�ȑ����_�o���K�v�Ȃ̂ł���B
�@�łƂ����A���̌�A�J���t�H���j�A���n�ɂ��鍻���ۗ̕{�n�p�[���E�X�v�����O�X�֍s�������ɂ��A�����Ă����g���x���b�W�̃z�e���̂܂��ɁA�I���A���_�̊������炬��ƏƂ���鑾�z�̉��ŁA����Ԃ̉Ԃ������ς��ɍ炩���Ă����B������A�A���]�i�̍����̖œł������Ă���͂��ł���B�^�U�̂قǂ͖��炩�ł͂Ȃ����A�c�[�\���ł��̃I���A���_�̎}���o�[�x�L���[�̋�����Ɏg���āA���l������ƕ��������Ƃ��������B
�@�c�[�\���ɂ���A���̃p�[���E�X�v�����O�X�ɂ���A�����̂Ȃ��̊X�Ƃ����̂́A���R�A����߂Đl�H�I�ł���B�{���A�l�Ԃ��Z�ݓ�s�т̍����Ȃ̂�����A�����ŊX���Ă����̂ɂ͂�قǑ傫�Ȑl�H�̎�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA������\�ɂ����̂��A�����J�̖L�x�ȐΖ������ł���B���̂��Ƃ́A�����Ƃ��납�獻���̂Ȃ��̊X����]���Ă݂�Ƃ悭�킩���Ă���B
�@�p�[���E�X�v�����O�X�̒��S������k�֎O�L���قǑ���ƁA�}�s�Ȋ�R�̎R���܂œo���P�[�u���J�[������B�I�[�X�g���A�̃P�[�u���J�[����Ђ̋Z�p�����ŁA1963�N9���ɏv�H�����B���\�l���̑�^�P�[�u���J�[���A���Z�S���[�g���̎R���X�e�[�V�����܂ŁA�قƂ�ǐ����ɋ߂��悤�ȋ}�p�x�œo���Ă����B���͎l�\�x�̏����ł��A�R���ł͓�\�܁A�Z�x�̗������ł���B�W�]������˂����X�g�����ł��炭�x��ŃR�[�q�[�����ށB���������Ƃ���ň��ރR�[�q�[�͂��܂��B
�@�R������̓p�[���E�X�v�����O�X�̊X�̑S�i���������茩�n����B���͂͏\�L�����炢�ɂȂ邾�낤���B�����̂Ȃ��Ɍ�Ղ̖ڂ̂悤�ɐ��R�Ƃ����X�̕��т��`������A�����ɂ�Ⓑ���L�тĂ���B�����X�̐F�ƁA���͂̍����̔��Ƃ̃R���g���X�g���ۂ����Ă��āA�����ɂ������̂Ȃ��̊X�Ƃ��������ł���B�����A�邱�̎R������X�������낹�A���̍��Ɣ��̃R���g���X�g�́A���ƈł̃R���g���X�g�ɂȂ��Ĉ�w�̍ۂ������ΏƂ�������ł��낤�B�ł̂Ȃ��ɂۂ�����ƕ����Ԍ��̌̂悤�Ȃ��̂ŁA�������������i�ł���ɈႢ�Ȃ��B�������A�l���Ă݂�ƁA����͎��Ɂu�낤���������v�ł�����B
�@�×��A�����́A�X�т��J�����Ƃ���n�܂����B�X�т̔��̂��������x���A�����āA���̂��ׂ��X�т����ׂĎ������Ƃ��A�����͖łт��B�G�W�v�g�A�M���V�A�A���[�}���̒n���C���݂ɉh�������������ׂĂ����ł���B�n���C���݂ő���������������́A�A���v�X���z���ă��[���b�p�̐X�т�j�n�߂��B�����Ēz���グ��ꂽ���[���b�p�������A�₪�ă��[���b�p�̐X�т����O�ꂵ���j��ɓ����Ă����O�ɁA������~�����̂��A�����J�̍L��ȐX�тł���B
�@���[���b�p���A�����̑�J������ɐX�т��|���Ă������悤�ɁA�A�����J�͏\�����I�����J��ɓ����ĐX�т��|���Ă������B�������A�\�����I�ɂȂ��ăC�M���X�̎Y�Ɗv�����N����ƁA���̗]�g���ăA�����J�̐X�ю��������X�ɍz�������Ɏ���đ�����悤�ɂȂ�B�ꔪ�܋�N�ɂ́A�y���V���o�j�A�B�ŁA���E�ɐ�삯�ĐΖ��̎��˂��@���A�ߑ�I�ȐΖ��Y�Ƃ̖��J���ƂȂ����B
�@��\���I�ɂȂ�ƁA�K�\�����@�ւ�f�B�[�[���@�ւȂǁA�Ζ���R���Ƃ�����R�@�ւ̔��B�ɔ����A�Ζ��͂�����Y�Ƃ̍ł��d�v�ȓ��͌��ƂȂ��Ă����B�A�����J�͐Ζ���ɂ��Đ��E�����[�h���A���E��̖L�������֎�����悤�ɂȂ����B�c�[�\����p�[���E�X�v�����O�X�̂悤�ȍ����̒��̊X�����グ��ꂽ�̂��A���̃A�����J�̖L���ȐΖ����������������炱���ł���B
�@�A���]�i�̍����̂Ȃ��ɁA�S���l�H�I�ɑ���ꂽ�T���E�V�e�B�̊X������B��s�@���猩��ƁA�L�����l�ɑ傫�ȃJ�^�c���������Ⴊ�݂���ł���悤�Ȉٗl�ȕ��i�ł���B�X�̒��S�����瓯�S�~��ɏZ��X�������ĊX�H�����A�����A���̊Ԃɒr��v�[����S���t��Ȃǂ��_�݂��Ă���B�Z�����������s���R���Ȃ��悤�ɁA�����H�����Z�������ׂċ@�B�Ɉˑ����A�����̋@�B���t���ɉ^�]�𑱂��ďZ���̐������x���Ă���B�ꌩ�A�֗��ʼn��K�Ɍ����邪�A�������A��U�d�C���~�܂�Ζ����ꂽ��A�����͂��̂܂܋���Ȑl�Ԃ̕��Ɖ����Ă��܂��ł��낤�B���̃p�[���E�X�v�����O�X���͓����ł���B�@�B���Ƃ܂�A�l�Ԃ͐����Ă����Ȃ��B�c�[�\���������ł���B�����āA���Ƃ��ƍ����ł������J���t�H���j�A�̑����̊X���A���T���[���X���܂߂āA��O�ł͂Ȃ��B
�@�v���Ύ������߂ďZ�ނ悤�ɂȂ���1957�N����̃A�����J�́A���̂悤�ɔ��������ł������B���͂��̃A�����J�ŁA�������̗��s�����Ėk�����ցA�����瓌�ւƁA�����炭�n��������z���邭�炢�̐����L���̑��Ղ��c���Ă����B�����āA���̃A�����J���A�N���o�閈�ɔ������ƖL�����̉e����߂āA�l�X�̍K����������������Ă����悤�ȋC�����Ă����B1957�N����26�N���o�āA3�x�ڂ̒����؍݂𒆒f���ċA������1983�N�����̃A�����J�́A�����Ɋ������܂ꂽ�h���L�������邩��ł��낤���A���̎��ɂ́A�W���Ă��낢����̘O�t�̂悤�ɁA�D�F�ɂ����X�X�̂������܂��������A�v���o�����悤�ȋC������B
�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@�@���̐����炠�̐��֊҂�Ƃ�
�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (95)�\�@ �@�@�@�@ �@�@
(2014.05.01)
�@���āA�u�����V���v���A���{�l�̎����ςɂ��Ă̑S�����_���������{�������Ƃ�����܂�(2010.11.04)�B����ɂ��Ắw���z�x�i75�j�u���B���Ȃ�ׂ����������ɒm���Ă����ׂ����Ɓv�ɂ����ڂ����Љ�Ă���܂����A���̑�R�̎��⍀�ڂ̂Ȃ��ɂ́A�u���Ȃ��́A���̐��Ƃ͈Ⴄ����̐��E��w���̐��x������Ǝv���܂����B�w���̐��x�͂Ȃ��Ǝv���܂����v�Ƃ����̂�����܂����B����ɑ��āA�u����Ǝv���v��49�p�[�Z���g�ŁA�u�Ȃ��Ǝv���v��43�p�[�Z���g�ł����B�ق�2�l��1�l�̊����ŁA�l�͎���ł����̐��֍s���A�ƍl���Ă��邱�Ƃ�������܂��B���̌X���́A�����炭�A���܂����܂�ς���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@���̎���Ɋ֘A���āA�u���̐�������Ǝv���v�Ɠ�����49�p�[�Z���g�̐l�������Ă���u���̐��v�̃C���[�W��q�˂Ă��鍀�ڂ�����܂����B���̌��ʂ́A�i��=16�p�[�Z���g�A����14�p�[�Z���g�A���܂�ς��=33�p�[�Z���g�A�₷�炬��29�p�[�Z���g�A�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B���܂�ς�肪33�p�[�Z���g�ň�ԑ����̂́A���ꂪ���t�Ƃ��Ă�����I�Ɏ��ɂ��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�����ł��傤���B�������A�u���̐��v������ƍl���Ă��Ă��A���̃C���[�W���u���v�ł���Ƃ��Ă���l��14�p�[�Z���g����Ƃ������Ƃ́A��͂�A�܂��A�u���̐��v�ɂ��Ă̗������s�m���ŗh�ꓮ���Ă��邱�Ƃ������Ă���悤�ł��B
�@�{���Ɂu���̐��v�͂���̂��A�Ȃ��̂��B�ނ������́A�����ōȂƒ��j��S�����ĔߒV�ɒ��݂Ȃ�����A�����̂悤�Ɂu��������Ɍo�v��ǂ�ł������Ƃ�����܂����B����́A���߉ޗl���吨�̒�q������O�ɂ��āA���̕��͂邩�ޕ��ɁA�Ɋy�Ƃ������E�����邱�Ƃ������Ă��邨�o�ł��B���̋Ɋy�Ƃ����̂͌���P���s��Ȑ��E�ŁA�l�͒N�ł��A����ɕ��̖����������邱�Ƃɂ���Ă��̋Ɋy�ɉ����ł���B�����Ă��̂��Ƃ́A������k�㉺�̘Z�@���E�̐������̏����ɂ���Ă��ؖ�����Ă���̂��A�Ƃ����悤�ȓ��e�ɂȂ��Ă��܂��B���́A���̂��o�̂Ȃ��ŁA�u����͉R�ł͂Ȃ��A�{���̂��ƂȂ̂��v�Ɖ��x�����x������Ԃ��ďq�ׂ��Ă��邱�ƂɁA�킸���Ȃ�����S�������Ă���悤�ȋC�����ɂȂ��Ă��܂����B
�@���܂Ȃ�A�w�V���o�[��o�[�`�̗�P�x������ł��n�ǂ���A���̂悤�ȏ����I�Ȓi�K����Ȃ��z���Ă�����Ǝv���܂����A����Ɂu���̐��v�̑��݂��ؖ�������̂Ƃ��ẮA���ڂ��̐��ƌ�M����u��E�ʐM�v�Ȃǂ��������܂��B���܂܂Ŏ��́A20�N�قǂ̊ԁA���\�l�̗�\�҂ɂ���āA��E�̍ȂⒷ�j�Ɛ������́u�ʐM�v�����݂Ă��܂����B���̈ꕔ�́A�{�ɂ������A�z�[���y�[�W�ɂ����J���Ă��܂������A���܂̎��ɂ́A���̐��͂��邩�A�Ȃ����̋^��͑S������܂���B�����ɍȂƒ��j���u���̐��v�Ō��C�ɐ��������Ă��邱�Ƃ��A�M����Ƃ������A�悭�m���Ă��܂��̂ŁA������Ƒ���S������ĔߒV�ɕ��Ă���悤�ȕ��X�ɂ́A��l�ł������u���̐��v�̐^����m���Ă������������Ƃ��������v��������܂��B
�@���܂����̃z�[���y�[�W�ɂ́A�w�V���̒ʐM�x�̌��㕶��T�ڂ��Ă��܂����A���̂Ȃ��ɁA���a�O�Y�搶�����̐����炠�̐��֊҂�ꂽ���̏��A���q���̐V��������E����ڎ����Ȃ�����Ă���u�ʐM�v������܂��i���̕����́A5�����{�ɑS�����ڂ���\��ł��j�B���̒ʐM�̂͂��߂ɐV�����́A�u�l�͋ߍ��K���ɁA�쎋�������悤�ɂȂ�܂��āA���̗ՏI�̖͗l���A�_�l�ɂ��肢���Č����Ă��炢�܂����B�l�͎����̗ՏI�����邱�Ƃ��o���Ȃ���������A��x���l�̗ՏI���������ƁA����v���Ă��܂������A���ꂪ�}�炸�����̗ՏI�����邱�ƂɂȂ����̂ł��v�Əq�ׂĂ��܂��B���̐��Ŏ������́A�Ƒ��̗ՏI�̎p�����邱�Ƃ͂���܂����A�����V�����́A���̐����猩�Ă������Ă���Ă���킯�ŁA����͎������ɂƂ��Ă��ɂ߂ċM�d�ȁA�H�L�́u�ʐM�v�Ƃ�����ł��傤�B
�@�����Ƃ��A�V�����́A�ՏI�ɍۂ��Ă̘a�O�Y�搶�̗l�q���A���܂��ɂ��Ȃ������ŁA�{���ɗՏI���}���Ă���̂��A������������_�l�̌����݈Ⴂ�ł͂Ȃ����Ǝv�����肵���悤�ł��B�����ŁA�_�l�ɕ����Ă݂܂��ƁA�u������Ŏ�삵�Ă��邩�炻�������邾�����v�Ɠ������܂��B�V�������A����ł��a�O�Y�搶�����ʂƂ͂ǂ����Ă��v�����A���Ƃ�����悤�ɉ��x���_�l�ɂ��肢���Ă݂܂����A����͊������܂���ł����B�u�N�ɂ����܂��ׂ��������莀���ׂ���������܂��B�����������ׂ��������Ă���A���Ƃ�����ڐA�ɂ���Ă����̓��̂�n��ɉi�炦�����邱�Ƃ͂ł��܂���v�ƃV���o�[��o�[�`�͌����Ă��܂����A���̎��̘a�O�Y�搶���A�厩�R�̐����̐ۗ��ɂ��̂܂]���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B
�@�v�����Ȃ��A�V�����͂��炭�Êς�����ق�����܂���ł����B�������邤���ɁA��������ׂ��キ�Ȃ��Ă����悤�Ɋ����n�߂܂��B���̐��ŗՏI���}���悤�Ƃ��镃��́A���̂悤�Ȃ��Ƃ܂ŁA��E����͌�����悤�ł��B���ɂȂ��Ă����a�O�Y�搶�͂₪�ċN���オ�낤�Ƃ��܂��B�a�O�Y�搶�ɕt���Y���Ă����Z�̐������i���E�C�R�����j���A��������āA�V�����̌Z�̏��ǎ��ɕ����N�������܂����B���̌�H�̗��E���n�܂�܂����A���̗l�q���E���猩�Ă���V�����́A�u�����N���オ��ƁA�H�̂͑��̕������̕��ւƗ���n�߂܂����B�H�̂Ɠ��̂Ƃ́A�����̕R�Ōq�����Ă��܂����`�̕R����ԑ����A���ɂ��R������܂��B�E���o���Ƃ��������ƁA���͔����ۂ��悤�Ȓ����𒅂Ă���܂����v�ƕ��Ă��܂��B
�@���̂��痣�ꂽ�H�̂́A���炭�����̓��̂̏�ɁA�����悤�Ȏp�ŕ����Ă��܂����B�����ĊԂ��Ȃ����̂ƗH�̂Ƃ��q���ł����R���ՂՂƐؒf����čs���܂��B������u�ʂ̏������v�Ƃ����錻�ۂł��B���ꂪ�{���̐l�̎��ŁA���̋ʂ̏�����Ă��܂��A�l�͂�����x�Ƒh�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�Վ��̌��ȂǂŁA�u�O�r�̐��n�낤�Ƃ��Ĉ����Ԃ����v�Ƃ����悤�Șb������܂����A����͋ʂ̏����܂���Ă��Ȃ��ŁA�����瑧�𐁂��Ԃ��Ƃ������Ƃ�����Ƃ������Ƃł��傤�B�V�����́A���̋ʂ̏�����Ă������l�ȏ��A�u�`�̂���Ԑ�ŁA�������A�����̕R���Ō�ł����B�R�̐F�͔��ł����A�����D�F�������Ă���܂��B�����Ĕ����o���H�̂́A���������������F�ł��v�Ƃ����悤�Ɍ��߂Ă��܂����B
�@�������Ęa�O�Y�搶�́A���a12�N2��3���ɁA63�ł��̐����炠�̐��ւƊ҂��Ă�����܂����B���́u���̐��v�Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȑ��E�Ȃ̂ł��傤���B����ɂ��Ắw�V���̒ʐM�x�������݂Ă��ɂ߂ċ�̓I�ɂ������ڂ����`�����Ă��܂����A�V���o�[��o�[�`����E�̗l�q���A�u��E�ɂ��뉀������ΉƂ�����A������ΊC������܂��B�Ȃ����ƌ����A���Ƃ��Ƃ����炱�������݂̐��E������ł��B�������͌`�̂Ȃ����E�ŕ�炵�Ă���̂ł͂���܂���B�������������ς�炸�l�ԓI���݂ł��B�������̂������Ȃ��Ƃ��������ł��B�厩�R�̔������𖡂키���Ƃ��ł��܂��B���t�ł͕\���ł��Ȃ����P���ӂ�鐶��������܂��v�ȂǂƁA�܂ɐG��āA�l�X�ɋ����Ă���Ă��܂��B
�@���܂��܁A�����܂ŏ����Ă����Ƃ���ŁA�S���v�������Ȃ��A���̐�����̎莆�����܂����B�X�ǂ��瑬�B�ւ���ʓ͂����̂ł��B�D�ꂽ��\�҂�
E. U. �����2�N�Ԃ�̂��ւ�ł����B����ɂ́A�u�搶�͂ǂ��Ȃ����Ă��邩�Ƃ����Ǝv���Ă����������A�����قǖ������܂����B���̌�A�߈˂Ƃ����`�Ō��T���炲�K������������܂����B���b�Z�[�W�����a���肢�����܂����̂ŁA���X���\���グ�܂��v�Ə�����Ă��܂����B�����āA��E�̒��j�E���T�i����̂�j�����A4�ł̗p��5�����̎莆����������Ă��܂����B���͍���84�̒a�������}���܂������A�Ȃ�Ƃ����C�Ɉ�l��炵�𑱂��Ă��܂��B�ł����T�ɂ́A���̂��Ƃ���͂�C������̂悤�ł��B�u��������̗̑͂������Ă��Ă���̂ŁA���ꂳ��ƈꏏ�ɑ�ϐS�z���Ă��܂��v�ȂǂƁA���̌��N���C�����Ĕނ�Ȃ�̒�ĂȂǂ����Ă���Ă��܂��B�����āA���̂��Ƃ̈ꕔ�ɂ́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂ��Ă��܂����B
�@�\�\��������A�܂��Ȃ����̐�����邱�ƂɂȂ�ł��傤���A���̎��͖l�����́A�_�X�l�̂��g���Ƃ��āA����Ȃ�v���Ɍ��������ƂɂȂ�܂��B�l�͂��̂��Ƃ��ւ�ɁA�܂��y���݂Ɏv���Ă��܂��B
�@�h�������ł͂���܂������A���ɂ�������ɂƂ��ẮA��ނȂ����̏C�Ƃł����B���̂��Ƃ��ǂ̂悤�ȈӖ������̂��A�܂��Ȃ�����������m��悤�ɂȂ�܂������B�V�E�̉c�݂͐[���f���炵���A����ɋ����ꊴ�ӂ���邱�ƂƎv���܂��B�y���݂ɂ��Ă��Ă��������B
�@�l�����͗։��]�����J��Ԃ��A�����܂ŒH�蒅���܂������A�܂��܂����ɂ͍��̐�����K�v�Ƃ�����X�ň��Ă��܂��B�l�����͂��̕��X����ł��~��Ȃ���Ȃ�܂���B����̐����͂��̂悤�Ȃ��̂ɂȂ�ƁA�_�X�l�ɂ��������Ă��܂��B�܂�A�_�X�l�̉��œ��������ɂȂ��Ă����ł��B
�@�c���ꂽ�l���́A�ł炸�ɂ����炩�ȋC�����ʼn߂��Ă��������B�����Ă��鐢�͎v���ʂ�ɂȂ�ʂ��Ƃ���ŋC��J���₦�ʂ��ƂƎv���܂����A����Ƃč��̏C�Ƃł���A���ꂼ��̕��̍��̃��x���ł�����A�v�����Ȃ����ƂƗ������Ă���܂��B
�@��������A���ׂĂ͌��̌��ɗ����҂���̂ł����āA�Ȃ��S�z�͗v��܂���B�ǂ������S���Đ_�̂��ɕ�����Ă��������B���̐��́A�f���炵�����̐��E�ł��B�{���̍��̂ӂ邳�Ƃł�������B
�@���̐�����̋v���Ԃ�̎莆�ŁA���������t���������ق����킩��Ղ��Ȃ镔��������܂����A���̌㔼�̈ꕔ�������ǂ���ɏC���������Ȃ�����̂悤�ɂȂ�܂��B���́A���N�̑咰����Ɠ���ᎂ̎�p���o���������Ƃ��A�C���������͓w�߂ĉ��₩�ɂ������Ă��܂����B�������A�ꂵ�݂��Ȃ��Ȃ����킯�ł͂���܂���B�v�킸�u�l���̍ŏI�i�K�ŁA�܂�����Ȑh�����Ƃ����z���Ă����˂Ȃ�Ȃ��̂ł����v�Ƒi�������悤�ȋC�����邱�Ƃ�����܂��B��͂肱�̐��́u�ܑ������v�ŁA�����Ă������͏C�s�̂��߂̋��ނɂ͎������Ȃ��̂ł��傤�B��E�̌��T��������͂��������u���ށv�Ǝ��g��ł��鎄�̗l�q�Ȃǂ��悭�����Ă���悤�ŁA���ꂪ����̎莆�ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B�����܂��A���̐�����̗D�����፷���Ǝv�����Ɏx�����Ă��邱�Ƃɂ����납�犴�ӂ��Ȃ���A���̐����炠�̐��֊҂�Ƃ��ɔ����āA�C�����𐮂��Ă����˂Ȃ�Ȃ��悤�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@�������ߑ����Ă����������̂�
�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (94)�\�@ �@�@�@�@ �@
(2014.03.01)
�@1992�N�̏t�A�C�M���X����A���������́A�܂������s�̉i�R�c�n�ɏZ�ނ悤�ɂȂ����B���j�̌��T���A�����O�����w���w�ȗ��A�D�y����㋞���āA1983�N�ẴA�����J�ĖK�܂�2�N�ԏZ��ł����A�p�[�g�ł���B���̃����h������̋A����܂��Ȃ��A���̃A�p�[�g�̗X�֎ɁA�ꖇ�̏����ȁu�V���o�[��o�[�`������v����ē��̃`���V�������Ă���̂��������B�ׂ̒c�n�ɏZ��M���̘A���悪������Ă���̂��݂āA���͂����ɓd�b�������AM���ɉ�ɍs�����B���ꂪ�AM���Ƃ̕t�������̎n�܂�ł������B
�@���͂��̑O�N�̃C�M���X�؍ݒ��A����Ɓw�V���o�[��o�[�`�̗�P�x�̏d�傳�ɋC�����Ă����B�V���o�[��o�[�`�̌�������������ɓ���āA���̈ꕔ�������ł��|���肵�Ă���B�u��P�V���[�Y�v�|��҂̋ߓ���Y���Ƃ��莆�̂���������悤�ɂȂ��Ă����B����́A���낢��ƍ��܂ł������Ă������A���͂��̃C�M���X�؍ݒ��ɁA��p�S�싦��̐��l�̃~�[�f�B�A���ɉ�A�\����̃V�b�e�B���O�i���O���Ȃ��Ƀ~�[�f�B�A�����ʒk�҂ɊW�����ƌ�M���邱�Ɓj���Ă��Ă���B���͐l�Ԃ̎��㑶���ɂ��āA�������Ă��������ɊԈႢ�͂Ȃ����A�{���ɖ{���Ȃ̂����A���x�����x���m�F�����������Ŏ���̐����ւ̊m�M�����߂Ă����B���߂ė�E�̐^���̈�[�ɂ��G��邱�Ƃ��ł��āA�n�p�̑O�ƌ�ł́A��I�^���ɂ������鎄�̑ԓx�́A180�x�ς���Ă����B�i�R��M���Ɖ�����̂́A����Ȏ��ł������B
�@�u�V���o�[��o�[�`������v�𗧂��グ�悤�Ƃ��Ă���M���́A����Ō��z���w�Ⴂ���z�Ƃł���B�w���̍�����A���_���E�ɋ����������A���T�Ȃǂ������Ă����悤�ł���B�V���o�[��o�[�`�⍑���O�̗�\�ҁA��I���ɂ��ڂ��������B����M���Ƃ͂����ɐe�����Ȃ����B�������A�u�V���o�[��o�[�`�̌�����v���������킯�ł͂Ȃ��B�ق��ɉ����]�҂����Ȃ���������ł���BM���Ɠ�l�����Ō�����𑱂��Ă��悩�����̂����A���ǁA������̔����͗���Ă��܂����B���̑���ɁAM���ɗU���ĎQ������悤�ɂȂ����̂��AA�t�́u����������v�ł���B����1992�N�Ĉȍ~�AM�����ԂŃs�b�N�A�b�v����1���ԂقǑ���A�����̂悤�ɓ�l�ō������s��A�t�̎����6��ԂŊJ����Ă������l�����́u����������v�ɒʂ��悤�ɂȂ����B
�@����A�t����\�҂Ƃ��Ă̊������n�߂��̂�1983�N�ł���B���������ŁA�Ȃƒ��j��S�����������N�ł������B���̌�A�t��1987�N�ɃA�����J�̃��@�[�W�j�A�֓n���āA�|�[���E�\�������̒�q�ƂȂ�A���Ă��������Ȃ��烊�[�f�B���O���w�ƕ����B�����āA1992�N5���A�|�[����\��������6�x�ڂɗ��������ہAA�t�֏ے��I�Ȃ�����Ń��[�f�B���O�\�͂��`����ꂽ�B���܂��܁A����M���Ɓu����������v�ɒʂ��悤�ɂȂ������ł���B���̃��[�f�B���O�Ƃ́A�ґz��Ԃɓ����āA��E�ƌ�M���ł������\�͂ŗ�E�̋L�^�ɂɏ�����Ă�����e��ǂ݉������Ƃł���Ƃ����Ă���B�������A���̓����͂܂��AA�t�̂��̂悤�ȗ�\�͂́A�Љ�I�ɍL���m���Ă͂��Ȃ������B
�@���́A���̑O�N�A1991�N�̏t�Ƀ����h����w�֕��C����O�ɂ��A���{�Ő������̗�\�҂Ƃ�����l�X�ɉ���Ă����B������s�v�c�Ȉ����ɓ�����Ēʂ��悤�ɂȂ���������S���c�ɂ́A200�l����Ƃ������\�҂������B�W��J����邽�тɏ����ȃO���[�v�ɕ�����āA���̓��̗�\�҂ƈ�Έ�őΖʂ��邱�ƂɂȂ��Ă����B�Ζʂ����\�҂͖����l�ł͂Ȃ���������AS���c�����ł����\�l�̗�\�҂���쌾���Ă������ƂɂȂ�B���ɂ́A�����������A�����Ԃ��҂�����ď�Ȃ̗�\�҂�������쌾�����Ƃ��������B
�@���͓M���҂��m�����͂ގv���ŁA��E�̍Ȃƒ��j�ɂ��Ă̏��������ł��A�ꌾ�ł��ł��͂����Ƃ��ĕK���ɂȂ��Ă����B�������A���N�����Ă��[���ł���悤�ȏ��͉����͂߂Ȃ������B���̂ق��́A��\�҂�����Ƃ������c�ւ����x�������^���Ƃ����邪�A���ʂ͓����ł������B�����Ȃƒ��j�Ƃ̌�M�ŁA���߂Ă����납��[���ł���悤�ɂȂ����̂́A�����h���̑�p�S�싦��֍s���Ă���ł���B����܂ł́A���N���̊ԁA�ꂵ�݂Ȃ��疳���̈łɒ���ł������ƂɂȂ�B
�@���̐��N�́A���v���Ίm���ɒ����������A�������A������Ƃ����āA���̂悤�ȗ�\�ґ���̕s�т̑̌��𐔑����d�˂Ă������Ƃ��A���ɂƂ��Ă͖��ʂł������Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B����܂ł̎��́A��I�^������͑S���������E�Ő����Ă����B���̂悤�Ȏ��ɂƂ��ẮA���X�̕s�т̑̌������̖ڊo�߂̂��߂ɂ͕K�v�ł������Ƃ������Ƃł��낤�B��\�҂Ə̂���l�X�͓��{�ɂ��O���ɂ������ɂ��邪�A��E�Ɩ{���Ɍ�M�o�����\�͂̕ێ��҂͋ɂ߂ċH�ł���B�َ����̉Ƒ��ƌ�M����Ƃ����̂́A��͂�l�q���z������ςȂ��ƂŁA�唼�́u���ʂ́v��\�҂̗͂̓���y�ԂƂ���ł͂Ȃ��B
�@����ŁA��E�ʐM�̂��߂ɂ́A����𒇉���\�҂̗�\�͂̂ق��ɁA�����炭���̒ʐM����鑤�̍��̏������K�v�ł���B������M�\�͂܂ł͎��ĂȂ��u���ʂ́v��\�҂Ɛ������ڐG���Ă������Ƃ��A�����₪�āA�ɂ߂ċH�ȗD�ꂽ��\�҂Əo��A�^���̗쌾���~�߂�悤�ɂȂ邽�߂̏����ɂ͖𗧂��Ă�����������Ȃ��B�C�M���X�ł́A���̂悤�ɂ��ăA����^�[�i�[�Ɖ�ׂ����ĉ�����B�����āA���{�ł��AA�t�ւƓ�����Ă������BA�t�́A���̒m�����ł́A�ɂ߂ċH�ȁA�����炭���{�L���̗D�ꂽ��\�҂ł���B
�@���͂���A�t����A���l���̃O���[�v�Ń��n�l�`�̐����u�`����悤�ɂȂ��Ă���A�N���1983�N11��29���ɁA���߂ă��[�f�B���O���Ă���B�����ăA�g�����e�B�X���ォ��̐��܂�ς��̑傫�ȗ����������ꂽ�肵���B����ȗ��A���N�P��A���ɂ�2��A��x����������A�t����A���[�f�B���O�������Ă���B�����h���̑�p�S�싦��ւ����N�̂悤�ɉċx�݂ɏo�����āA�A����^�[�i�[�⑼�̗�\�҂����̃V�b�e�B���O���Ă�������A��E�ʐM�Ɋւ���e�[�v�ނ́A�����h���Ɠ����̂��̂���ƌy��100�{���Ă���B���̂����̈ꕔ�́A��E�ʐM�ɊS�����l�X�̂��߂̎Q�l�����Ƃ��ăz�[���y�[�W�ɂ����J���A�{�ɂ������Ă����B
�@2011�N6���Ɋw���p�u���b�V���O����o�ł��ꂽ�w�V������̎莆�x�́A���̂悤�ȗ�E�ʐM�̋L�^���܂Ƃ߂����̂ŁA�u������Ƒ��Ƃ�18�N�Ԃ̗�E�ʐM�v�Ƃ����T�u�^�C�g�������Ă���B18�N�ԂƂ����̂́A1992�N�̃C�M���X�؍ݒ�����n�܂��āA���̖{�̏o�ł̑O�N2010�N�܂ł̊��Ԃł���B���Ǝv���Ă����Ȃƒ��j�́A��E�ŗ��h�ɐ����Â��Ă����B���̐^�����^�����ɂ��^�����Ȃ��`�Ŏ��X�ɂ������āA1983�N�̎����ȗ��A�ߒV���甲���o�邱�Ƃ��o���Ȃ����������A���߂ċ~���A�S�̒ꂩ����g���A�_�Ɋ��ӂ���悤�ɂȂ��Ă����18�N�ł������B
�@���͂���18�N�ԁA���N�A�����ƃ����h���ŁA��E�̍Ȃƒ��j�̋ߋ���q�ˁA���̐��Ƃ͈Ⴄ�����Ԃ��m�炳��A���j����I�ɐi�����Ă����l�q�Ȃǂ̕��Ă����B���傤�ǃA�����J�Ɠ��{�ŗ���ĕ�炵�Ă������̂悤�ɁA���������Ƃ���ɍȂƒ��j�����C�ɕ�炵�Ă��邱�Ƃɏ����̋^���������Ȃ��Ȃ����B�Ȃ����������A���̂悤�Ȏ����Ɋ������܂�A���͂��̂悤�ɗ��ꗣ��ŏZ�ނ悤�ɂȂ������A���̗��R���������āA���͔[�����Ă���B���ė�I�ɂ͑S�����m�ł�������������Ɨ�I�ɖڊo�߂āA�����N���A�w�Ԃׂ����Ƃ͊w�сA�l�X�ɓ`����ׂ����Ƃ͎��Ȃ�ɓ`���悤�Ƃ��Ă����B�����č��ł́A�����ł̎g�����قډʂ����I������A�t���猾����悤�ɂȂ��Ă���B��E�ł́A�ȂⒷ�j�������A���̊��}�������i�߂Ă���炵���B���́w�V������̎莆�x�ɂ́A�����������Ƃɂ��G��āA�I�͂ɂ́A���̂悤�ɏ������B
�@�l�͎��ʂƁA�Ă���ĊD�ɂȂ��Ė��ɋA����ƍl����̂́A���m�ł���B������Ƒ����S���Ȃ��āA���������ĉ���Ƃ��b���������Ƃ��ł��Ȃ��ƒQ���߂��ނ̂́A�ԈႢ�ł���B���́A�x�q�ƌ��T���؍q��@�����Ŏ����Ĉȗ��A�����N���A���̖��m�ƊԈႢ�̂Ȃ��Ő����Ă����B�����Ă��܂ł́A���m�ł��邱�ƁA�Q���߂��ނ��Ƃ̊ԈႢ�̋��낵�����A�ɂ��قǂɎv���m�炳��Ă���B
�@�l�͎��ȂȂ��B�Ƃ������A���ʂ��Ƃ��ł��Ȃ��B������Ƒ�������ł͂��Ȃ��B���܂������Â��Ă���B�b�������Ȃ����Ƃ������ĂȂ��B�����A���̂��Ƃ�m�炸�ɁA���炷�ׂĂ͏I������ƒ��߂āA������Ƒ����݂�����Y�p�̔ޕ��։��������A�b���������Ƃ͂��Ȃ��l�������A���т��������܂��ɂ͂��邾���ł���B
�@�m���ɁA���̎p�͖ڂ̑O�ɂ͌����Ȃ���������Ȃ��B�������A�����i���ɉ�Ȃ��A�ƂȂ��v�����ނ̂��B�b���������Ƃ��ł��Ȃ��ƁA�N�������������̂��B�u����Łv���܂����̂�����A�{���ɂ�������Ƃ��b���������Ƃ��ł��Ȃ��̂��B����������Ŋm���߂��̂��B
�@���܂ł́A���́A����悤�Ȏv�����}���āA�����₢�����邱�Ƃ��ł���B�E�E�E�E�E�E�E
�@�����ȗ��̒������̂���A�ƂڂƂڂƕ��������Ă��邤���ɁA���̊Ԃɏ����Ă��������q�A�G���A�{�̌��e���E�ʐM�Ȃǂ̋L�^�͂��̂܂ɂ��A�����ȗʂɒB���Ă���B��E�ʐM�ɂ��Ă��A������������A���̂悤��18�N�Ԃ������Ă����L�^�́A���܂�Ⴊ�Ȃ���������Ȃ��B���܂��ɁA�w�V������̎莆�x�ɂ́A�ҏW����`���Ă��ꂽ�F�c�˗��q���A�c��ȗ�E�ʐM�̋L�^�����āu���Ƒ��̉ߋ����ɂ�����W���v�Ƃ����u�t�\�v�쐬���Ă���Ă���B�����ł����ł́A�A�g�����e�B�X���ォ�猻��Ɏ���܂ŁA���E�̗l�X�ȍ��ŁA����Ƒ����ǂ̂悤�ɐ��܂�ς���Ă��������ꗗ���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B������A�������܂��̂Ȃ����ƂŁA���܂�ς��𗝉����邽�߂̈ꏕ�ɂȂ�Ǝv�����A�t�ɁA��E�ʐM��ᔻ���邽�߂́u���������v�Ƃ��Ďg���Ă��������Ă��A���ʂł͂Ȃ���������Ȃ��B
�@�@�����炭�A���̂悤�Ȏ��̗�E�ʐM�̋L�^���A������Ƒ��������ĔߒV�ɕ��Ă���l�X�̑������Ƃ炷�������ȁu�Ƃ����v�ɂȂ��Ă����ł��낤���Ƃ����҂��Ă���B���Ǝv���Ă����l����E�Ō��C�ɐ��������Ă��邱�Ƃ�m�邱�ƂقǑ傫�Ȋ�т����邾�낤���B����ł�����ł́A��I�^���ȂǂƂ������̂���ь������Ďt���悤�Ƃ��Ȃ��l�X�������ď��Ȃ��͂Ȃ����Ƃ����͂悭���m���Ă���B���邢�́A��I�^�����e��鏀�����o���Ă��Ȃ��l����������ł��낤�B���������l�����ɂ��A�^���Ɏ���ЂƂ̃A�v���[�`�Ƃ��āA���_��ᔻ�̂��߂̈�ǂ��A���͂܂����肢���Ă݂����C�����ĂȂ�Ȃ��B���͂����A���Ԃ̑����̐l�X�ɁA���Ă̎��̂悤�ȗ�I�^������O�ꂽ���m�ƔߒV�̓O�܂Ȃ��悤�ɂƁA�肢������݂̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�l�ދ����̂��߂̖����ւ̓W�] �\ EU����AU��
�@�@�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (93)�\�@ �@�@ �@�@
(2014.01.01)
�@�l�ނ݂͂Ȍ݂��ɌZ��ł���B������L���X�g���Ȃǂ��܂߂āA�×��A���܂��܂ȏ@���̂Ȃ��ł���l�ɋ������Ă������̒P���Ȑ^���́A�������A�����ɂ͂Ȃ��Ȃ��^�ɗ�������邱�Ƃ�����B���̈�̏؍����A21���I�̌��݂ł��A���E�e�n�Ő헐���₦�Ȃ����Ƃł��낤�B���E���ŁA�E��������D���������A���ς�炸���s���Ă���̂��A�u�l�ނ݂͂ȌZ��v���A�قƂ�Nj�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B���������A�ǂ�����A���̐^�����l�X�̂�����ɟ��݂Ă������ƂɂȂ�̂ł��낤���B�A�����J�̐��_�Ȉ�u���C�A���E���C�X�́A���鎞�̑ލs�Ö��̂Ȃ��ŁA�u�Ռ��I�ł������킩��₷���C���[�W�v�ɂ���āA���́u�l�ނ݂ȌZ��v�̐^�����͂����茩����ꂽ�A�Ƃ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�܂��A�����Ȏl�p���X�ň�t�̑�C���������܂����B�l�p���X�͈�ЂƂʌŁA���݂��̊Ԃɂ͂͂�����Ƃ������E������܂��B����ł��A�݂�ȓ������肻���Ȑ��ɕ�����ł��܂����B�����ɐ����g�����Ȃ�A�l�p���X�͗n���܂����B�݂�Ȑ��Ȃ̂ł��B�ǂ̎l�p���X���A�C�̒��̑��̎l�p���X�ƂȂ����Ă��܂����B�����ĔM������ɉ������A���͕������n�߁A�����C�ɕς��܂����B�Ԃ��Ȃ��S���������Ȃ��A�ڂɂ������Ȃ������C�ɂȂ�܂����B�ł��A�����C�́A���Đ����������́A�l�p���X���������̂��܂�ł��܂��B�X�A���A�����C�̊Ԃ̗B��̈Ⴂ�́A���q�̐U���G�l���M�[�����Ȃ̂ł��B�l�Ԃ͎������g���A�l�p���X�̂悤�ɁA�����I�ɕ����������̂ƍl���Ă��܂��B���������́A���B�݂͂Ȃ��݂��ɂȂ��荇���Ă���A�������̂Ȃ̂ł��B�i�w���̗Ö@�x(�R��h��E����q��) PHP�������A2001�N�Ap.320�j
�@���́u�l�ނ݂͂ȌZ��v�́A�g�߂ɂ���ȒP�Ȑ����̏�ł��l���邱�Ƃ��o����B���Ƃ��A�����������ɂ���̂́A���ɕ��ƕ�̓�l�̐e����������ł���B���̕��ƕꂪ�����̂́A���ɂ���ɂ����ꂼ���l���̐e����������ł���B���̂悤�ȂȂ�����N�����ǂ��Ă����A�ꐢ���30�N�Ƃ��Čv�Z����ƁA�ǂ��Ȃ��Ă����ł��낤���B
10����O�i300 �N�O�j�ŁA��e�̐��́A2,048�l�ɂȂ�B20 ����O�i600�N�O�j�ł́A2,097,152�l�ƂȂ�A���������k����24����O�i720�N�O�j�ɂȂ�ƁA��e�̐��́A3��3�S50���l���Ă��܂��B���{�̍]�ˎ���̐l���́A2��6�S������2��7�S���l�Ƃ����Ă��邩��A���̍]�ˎ���̐l�����͂邩�ɒ����A����ɁA26����O�i780�N�O�j�ɂȂ�ƁA��e�̐���1��3��4�S���ȏ�ɂȂ�A���݂̓��{�̑��l���������A�y�������Ă��܂����ʂɂȂ�B
�@�������A���ۂɂ́A�l���͉ߋ��Ɍ������ďk�����A�t�ɁA�����Ɍ������Ă͎��オ�o�ɂ�đ����Ă����̂����ʂ�����A���̂悤�Ȑe�̐��̑����́A�����ɂ͂��肦�Ȃ��B����͂ǂ����߂���悢���B���̖���������ł��鍇���I�ȍ����́A�u�l�ނ݂ȌZ��v�����ł���B�l�ԂƂ����̂́A���������Ă��A���͂��ꂼ�ꂪ������Ƒ��̈���ł���A�݂�Ȃ��Z��ł��邱�ƂɂȂ炴������Ȃ��B
�@���̒P���Ȑ^������邱�Ƃ́A���̂悤�ɁA�ƂĂ��ȒP�Ȃ悤�Ɏv����B�������A�����I�ȔϔY�ɂ܂݂ꂽ�S�ɂƂ��āA���̐^���g�Ŋ����Ă����̂́A�����ĊȒP�ł͂Ȃ��B������܂��A��I�^���̈�ŁA�����͗�E�֕����Ă͂��߂Ă����납��[�����邱�ƂɂȂ�̂ł��낤���B���āA�R�i����h�C�����A��E�֊҂��Ă���̒ʐM�ŁA�u��E�ɂ��鎄�����́A���ɂ��̐^���𗝉�����Ɏ���A�F���̓��E�������ӂ̋C�����ŐM�����A���̈����������A�ꏏ�Ɉ��炩�ɐ������Ă���̂ł��v�Əq�ׂĂ���B�����āA�u�l�X�ƍ��X�̂������̓��E���̕K�v���������ōĂы����������Ǝv���܂��v�ƁA���̂悤�ɓ`���Ă����B
�@��������E���ȊO�̐������ȂǂƂ������̂́A���E�����ނׂ����̑I�����Ƃ��ĊJ����Ă͂��Ȃ��̂ł��B���݁A���E�̍��X�͋^�f�Ƌ��|�S�̒��ő��݂��Ă��܂��B�N�����낤�Ƃ����A���݂�������Ă��܂��B�r�W�l�X�̐��E�ł́A��l��l�������̕����O���m�ۂ��悤�Ƃ��āA���E�Ɛ���Ă��܂��B���̂悤�Ȑ������́A�l�Ԃ��ǂ��ɓ����Ă����̂ł��傤���B����ł��Ȃ���A�i���I�Ȕɉh�ł��Ȃ����Ƃ͊m���ł��B����ǂ��납�A����������܂ňꐶ�����z�������Ă������̂��ׂĂ̕���ɂȂ��邱�Ƃł��傤�B�i�A�C���@���E�N�b�N�� �w�R�i���E�h�C�� �l�ނւ̃X�[�p�[���b�Z�[�W�x�������A�u�k�ЁA1994�N�App.279-280�j
�@�V���o�[��o�[�`���A���́u�l�ނ݂ȌZ��v�ɂ��ẮA���肩�����A���낢��Əq�ׂĂ���B���ǁA����ꂪ�{���ɕK�v�Ƃ��Ă���̂́A�@���̍������Ȃ��P���Ȑ^����m�邱�Ƃ����ł���B�����āA���̐^���Ƃ́A�u�l�ނ͂��݂������݂��̈ꕔ�ł��邱�ƁA�����Ĕ��̐F�̈Ⴂ�̓����ɂ͂��ׂĂ����т��鋤�ʂ̗�I���J������Ƃ������Ɓv�ł���ƁA�����Ă���B�����l�Ԃ��A�݂��ɍ��ʂ������A���݂����̐��ɋC�����Ă��Ȃ�����A������������E����~��Ă��āA���̎����������Ă���̂��A�ƌ��������Ƃ�����B���������ɁA���̂悤�ȕ\���ŋ������Ă���B
�@�l�C���E�A�����A��d�A���e�\�\�����������_�����l���̊�{�ł���A�������b�Ƃ��Ȃ�������^�̕��a�͂��蓾�܂���B���Ă�҂���������҂ɕ����^���邱�Ƃɂ���Č݂��ɕ�d�������A�r�݂����A�������������Ɓ\�\���̒P���Ȑ^���͌J��Ԃ��J��Ԃ��������Ȃ���Ȃ�܂���B������l�Ƃ��Ă̓��퐶���ɂ����āA�����Ƃ��Ă̐����ɂ����āA�����č��ƂƂ��Ă݂̍���̒��ɂ����Ď��H����҂����A�l�ԂƂ��Ă̖{���̐����������Ă��邱�ƂɂȂ�\�\���ꂾ���͒f���ł��܂��B�i�u�w�т̞xA�v52-b�j
�@�l�Ԃ̗��j�������ƐU��Ԃ��Ă݂Ă��A��ɒ�������ߑ�ɂ����āA�������̍��X�ŁA�n���̍�����̎�̌Q�Y�����Ȃǂ���A�����ɒ����̓��ꍑ�Ƃւ̓����Ɍ��������������ł����B�C�^�����A�X�y�C���A�t�����X�A�h�C�c�A�I�[�X�g���A�Ȃǂ̃��[���b�p�e���������ł��������A�A�W�A�ł��A�L��Ȓ������܂߂āA�؍������{����O�ł͂Ȃ��B����A�W�A��C���h�ȂǁA���[���b�p�̐A���n�ɂ��ꂽ���X���A�Ɨ�����20���I�ɂ܂ʼn��т����A�������ƂƂ��Ă̈ӎ��͍��߂��Ă����Ƃ����Ă������낤�B�������A�푈�͉����̏ꍇ���Ȃ��Ȃ�Ȃ������B�ނ���A���Ă͂ǂ��ł����킪��ł��������̂��A�K�͂̑傫�ȍ��ƊԂ̑ΊO�푈�Ɏ���đ�����悤�ɂȂ��āA���̎S�Ђ������x�I�ɑ傫���Ȃ��Ă������B�u�l�ނ݂͂ȌZ��v�Ƃ́A�t�̕����ɐi��ł����悤�ɂ��v����B
�@���́A���Ƃ��̂��̂ɂ���̂�������Ȃ��B���Ƃ́A�ǂ̂悤�ȍ��Ƃł���A��Ɏ����̗��v���ŗD��ɍl���A���v����낤�Ƃ���B���v�����Ƃ����̂́A�ǂ̍��Ƃł����R�̂��ƂŁA�ǂ̍����������Ď����̍��v����邱�ƂɈق������邱�Ƃ͂Ȃ��A����͎��㖽�߂ł�����B�������A���̍��v�Ƃ͂����������ł��낤���B�����̗��v����邽�߂ɂ́A�����͋]���ɂ��Ă���ނ����Ȃ��Ƃ������̃G�S�ł͂Ȃ��̂��B������A���ꂼ��̍��Ƃ����v���咣���Ă����A���Ƃ̃G�S���Ԃ��肠���āA���R�̂��ƂȂ���A�����ŏՓ˂��N����B���݂̐��E�ł̍��ە����Ƃ����̂��A��Ȃ菬�Ȃ�A���̍��Ƃ̃G�S���X���Ԃ��荇���Ă���p�ł���ɉ߂��Ȃ��B�����āA���̏�Ԃ������Ă�������A�����������O�̂��Ƃł��邪�A�l�ނ��������Ă����W�]�͊J���邱�Ƃ͂Ȃ��B�����́A���܂ł́A���̍��Ƃ̘g���Ă������Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@��̊�]�́A���[���b�p�Ō`�����ꂽ EU�iEuropean Union���[���b�p�A���j�ł���B�t�����X�ƃh�C�c�Ȃǂ����ݍ����Ă����G�����m�◘�Q���Η����鍑�X�����܂߂āA���Ƃ�����̋����̂����グ���Ă����B���[���b�p���ʒʉ݂́u���[���v��S��ɗ��ʂ����āA�����I�ɂ͍��ۓI�Ȑ����������������Ƃ��Ă���B���������A1967�N�̔������́A�x���M�[�A���h�C�c�A�t�����X�A�C�^�����A���N�Z���u���O�A�I�����_��6�����ł��������A1973�N�ɂ́A�f���}�[�N�A�A�C�������h�A�C�M���X��3�����������A2004�N�ɂ́A�L�v���X�A�`�F�R�A�n���K���[�A�|�[�����h�Ȃǂ̓�������10���������������B���̌���������͑��������āA���N2013�N�ɉ��������N���A�`�A���܂߂�ƁA���݂̉�����������28�����ɂ��Ȃ�B
�@�������AEU���ł�������Ƃ����āA����ŕ������Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ����낤�B���[���b�p�A�������ł��A�o�ϊi���≿�l�ς̈Ⴂ�Ȃǂ��܂߂āA���ꂩ������z���Ă����˂Ȃ�Ȃ��ǂ������������͂������Ă���B���܂��܂Ȑ��x�I�Ȓ�������j������̈Ⴂ�ɑ��鑊�ݗ���������ɐ[�߂Ă������Ƃ��K�v�ł���B�������A���̂��̂̍��Ƃ̃G�S���z���āA���ӂ̍��X�Ƃ̋�����}���Ă����ׂɂ́A���̃��[���b�p�A���́A���炩�ɉ���I�ŗL���ȑ�������ݎn�߂Ă���Ƃ����ׂ��ł���B�����͂�������K���A�A�W�A�ɂ����Ă͂߂āA�Ƃ肠�����A�����A�؍��A���{�𒆊j�ɂ���AU�iAsian
Union�A�W�A�A���j���l���Ă������Ƃ͏o���Ȃ����̂ł��낤���B
�@���[���b�p�����̓L���X�g�������ł���Ƃ�����悤�ɁA���[���b�p�ł́A�×��AChristendom �i�L���X�g�����E�j�Ƃ������ʂ̐��_�I��Ղ��������B���̃L���X�g�����E�̊�Ղ����[���b�p�A���̏d�v�Ȏx���ɂȂ��Ă���̂͌���ւ��Ȃ��B���܂ł́A����ɁA���̃L���X�g�����E�̊�ՂɁA�g���R�Ȃǂ̃C�X�������̍������e����邩�ǂ�������������Ă���B���l�ɁA�����A�؍��A���{�ɂ��A���ʂ̐��_�I��Ղ�����B���������ƕ����A�̏@���I�A�����I�w�i�ł���B���ꂼ��ɁA���̉e���x�͓����ł͂Ȃ����A�����̐��_�I�A�����I��Ղ̏�ɗ����āA�����̂�ڎw���Ă������Ƃ́A�����ĕs�\�ł͂Ȃ��͂��ł���B���ƊԂ̕������Ȃ����Ă������Ƃɂ��Ȃ���A�l�ނ̋����̂��߂̕��������������Ƃɂ��Ȃ�B���݂̒����Ƃ̊Ԃ̐�t�����̗̗L����؍��Ƃ̊Ԃ̒|���̏����̖��ȂǁA���̂���������̕����Ɍ������Ă����̂ł͂Ȃ��ł��낤���B
�@������A�����A�؍��A���{�ɂ́A�l��I�Ȕw�i���l�����ŁA�ߔN�̏W�c��`�w��DNA�Ӓ�Ȃǂ����m�ɂ��Ă����d�v�Ȏw�W������B ���Ƃ��A���݂̓��{�l��DNA�Ӓ�Ŗ��炩�ɂ��ꂽ�Ƃ���ɂ��ƁA�����E�؍��n���ł�������51�p�[�Z���g�A�����ő����͉̂���n��16.1�p�[�Z���g�A���̂��ƃA�C�k�n��8.1�p�[�Z���g�������āA����ȊO��21�p�[�Z���g�������ƁA���{�l�ŗL��DNA�������Ă���l�̊����́A�킸��4.8�p�[�Z���g�ɂ����Ȃ����Ƃ��������Ă���B�i�m�g�j�X�x�V�����u��`�q�E�c�m�`�v�B�u���{�l�̃��[�c��T��v1999.5.4�j �܂�A���݂̓��{�l��2�l��1�l�́A�����E�؍��n�ŁA�u�l�ނ݂ȌZ��v�Ƃ�����Ƒ��̂Ȃ��ł��A���{�l�ɂƂ��āA�����E�؍��l�͂����Ƃ��g�߂Ȍ����ł��邱�Ƃ��������Ă���B
�@���m�̔@���A���łɓ���A�W�A�ł́A����A�W�A�����A���iAssociation of South-East Asian Nations�j�������āA����A�W�A10�����̌o�ρA�Љ�A�����A���S�ۏ�A�����Ɋւ���n�拦�͋@�\�Ƃ��ĉe���͂������n�߂Ă���B1967�N�Ƀ^�C�A�t�B���b�s���A�}���[�V�A�A�V���K�|�[���A�C���h�l�V�A�ȂǁA������`��5�����Ŕ������Ĉȗ��A1995�N�ɂ́A�x�g�i�����Y�}�ɂ���}�ƍق������x�g�i���Љ��`���a�������}�������悤�ɂȂ����B���̌�A�R�������̃~�����}�[��x�g�i���̉e���͂̋������I�X��J���{�W�A���������ʼn����������Ƃɂ��A���݂ł�10�����̋����̂ɂȂ����̂ł���B���̂悤�Ȑ����������͏d���~�߂Ă����˂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B�����͎Љ��`���Ŋ؍���36�x���Ŗk���N�ƑΛ����Ă���Ȃǂ́A���낢��ȍ������ɂ��Ă��A��͂�A�����́A�����́u�A�W�A�A���v�Ƃ��������̂̑n�݂��A�����P�ɁA��͂��ȋ�_�Ƃ��ĕЕt����ׂ��ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B
�@�A�����J�嗤�ł��A���Ƃ��u�A�����J�A���v���ł���Ƃ����悤�ɁA���̂悤�ȍ��Ƃ��z���������̂��n����ɍL���邱�Ƃɂ���āA�������ł��A���ƃG�S���痣��āA�����̂̒��Ԃ��v�����S���L���A���Ȃ��痘���ւƐ��_�I�u�i���v�𐋂��Ă����B���̂��Ƃ��A�����炭�A���ꂩ��̐l�ދ������l���Ă������߂ɂ́A�������Ȃ��X�e�b�v�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����B
�@�O�f�̃R�i����h�C�����w�E�����u���E�̍��X�͋^�f�Ƌ��|�S�̒��ő��݁v���Ă���́A���܂��ς���Ă��Ȃ��B�ނ���A�������Ă���悤�ɂ����݂���B�l�ނ��K���ɓ����Ă����͂��ł��������{��`�̐��E�̒��ŁA�l�X�͕����I�E���K�I�~�]���ʂĂ��Ȃ���点�āA���E�������̂��A�אl�Ɠ����A�n����̌o�ϓI�i�������ĂȂ��قǂɍL���Ă����B���̂悤�Ȑ��������A�����ɕ��a�Ɖi���I�Ȕɉh�������炷�͂��͂Ȃ��B�����͕K���s���l���āA���{��`������ł��낤�B����ꂪ�������Ă����铹�͂����炭������A�u�l�ނ݂ȌZ��v�̌��_�ɗ����Ԃ邱�Ƃł���B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A���Ԃ��������Ă��A���Ƃ̘g���z�����u�����́v�𐢊E�e�n�ɑn�肠���A���ƃG�S�ɐU��܂킳��邱�ƂȂ��A���Ȃ��������̂�������L�߂Ă������Ƃ��A�l�ނ̖����ւ̓W�]��Ă������ƂɂȂ�K�{�̏����ł���Ǝv���ĂȂ�Ȃ��̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@�����������a�ɋ������Ă������߂�
�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (92)�\�@ �@�@�@ (2013.11.01)
�@���ē̃I���j�o�X�f��w���x�̂Ȃ��̑�8�b�́u���Ԃ̂��鑺�v�ƂȂ��Ă���B�����ɂ͂��̐��̂��̂Ƃ͎v���Ȃ��قǔ������삪����Ă��āA���́A���̉f��������Ƃ��A����Ȃɔ������삪�{���ɂ���̂��낤���A�Ǝv�����肵���B�����ԁA���̐����x���Ă݂����Ǝv���Ă������A����ƌ���ɑ����^�Ԃ��Ƃ��ł����̂́A2012�N��1���̂��Ƃł���B�i�u������Z�M�vNo.19�Ɏʐ^�j
�@���́u���Ԃ̂��鑺�v�̎B�e����͒��쌧�E���ܖ�̖������i��낸������j�������i���ł���j�̍����n�_�t�߂ł���B�u���Ԃ̂��鑺�v�������ŎB�e���ꂽ�̂́A1989�N5���̂��Ƃł������B5���̂��̕ӂ�̕��i�́A��ӂ̑��Ԃ�X�̗��������A���̗���������炭�����𑝂��āA���̂Ȃ��ɂ́A���̉f��ɏo�Ă���悤�ȑ�ʂ̐����������ɂȂт��Ă���l�q��������̂ł��낤�B�����́A�����s����1���ɂ��X�Ƃ��Ă������A���̗���͂�͂�5���قǂɂ́A�����͂Ȃ������B
�@�f��́u���Ԃ̂��鑺�v�́A��������̂��ŁA���Ԃ̊̈���C�����Ă���103�̘V�l�ɁA�������߂ĖK�˂Ă�����҂��b��������Ƃ��납��n�܂�B���̑��ɂ͓d�C�͂Ȃ��B���ԏ����̃����v�����āA��҂��u��͈Â��͂Ȃ��ł����v�ƕ����ƁA�V�l�́u�Â��̂��邾�B��܂Œ��̂悤�ɖ��邭�Ă͍���B���������Ȃ��悤�Ȗ��邢��͂��₾�ˁv�Ɠ�����B���̑��ł́A�c���̍k��ɂ�����n���g���āA�k�^�@��g���N�^�[�Ȃǂ��Ȃ������B�u�R���ɂ͉����g���Ă����ł����v�Ǝ�҂������ƁA�u�����ɁA�d���g���Ă���B�����Ă����͉̂����������A�͂�����邩��A�����ɂ�����āA�d�Ɏg���Ă���B���̃t���������R���ɂȂ�v�ƘV�l�͓�����B�����ĘV�l�͂������ƓƂ茾�̂悤�ɑ������B
�@�@�\�\�������͎��R�̕�炵�����������Ǝv���Ă���B�ߍ��̐l�Ԃ́A�������������R�̈ꕔ���Ƃ������Ƃ�Y��Ă���B���R�������Ă̐l�ԂȂ̂ɁA���̎��R�𗐖\�ɂ�������܂킵�āA�����Ƃ������̂��o����Ǝv���Ă���B���Ɋw�҂ɂ́A���͂����̂�������Ȃ����A���R�̐[���S�������ς蕪����Ȃ����̂������̂ō���B���������A���́A�l�Ԃ��K���ɂ���Ƃ������̂��ꐶ�����������ē��ӂɂȂ��Ă���B�܂��A���������ƂɁA�命���̐l�Ԃ����́A���̔�������Ղ̂悤�Ɏv���A�L����āA���̑O�Ɋz�����B�����āA���̂��߂Ɏ��R��������B���܂̐l�Ԃ���ԑ�Ȃ��̂́A������C�₫�ꂢ�Ȑ��A��������o����Ȃ̂ɁA����͉��������A�r�����A��C�␅�͐l�Ԃ̐S�܂ʼn����Ă��܂�������
�@�f��ł́A�����Ő�̌���������A�ɂ��₩�ȓJ����ۂ̉����������n�߂�B����ɋC�����āA��҂́u���Ղ肪�����ł����v�Ɛu���B�V�l�͓������B�\�\����A����͑�������B���������̓w���Ȋ�����邪�A�{���A�����͂߂ł������̂���B�悭�����āA�悭�����āA�u����J����v�ƌ����Ď��ʂ̂́A�߂ł���������@���̑����́A����103�̘V�l�̏����̐l��99�ŖS���Ȃ����̂ŁA�����Łu���j���v�����Ă���̂��Ƃ����B�����āA�V�l�����̓��₩�Ȃ��j���́u����v�ɎQ�����邽�߂ɏo������Ƃ���ŁA���̍�i�͏I����Ă���B
�@����́A�����܂ł����V�ē̍�i�u���v�̈ꕔ�ł����āA����Љ�Ƃ͂������ꂽ�u���J�v�Љ�́A���ꂱ��������̂悤�Ɏv���邩������Ȃ��B�������A���́A���̂悤�ɂ��Č��㕶�����痣�ꂽ�Ƃ���ŁA���������̐��������Ă���u���J�l�v�Ƃ����Ă���l�������A���E���̂����炱����ɍ��ł�����B���Ƃ��Γ�ău���W���̃A�}�]���̐X�̒��ɂ̓��m�}�~�������āA���̎���ɔ������A�X�̏�������߂��̐�̋���H�ׂĎ��������̐��������Ă���B������u�����l�v�������A�X���J���A��ɋ��̌@�̐���𗬂����肵�āA�ނ�̐������������Ă�������݂������Ă���̂ł���B
�@���㕶�����痣��ďZ��ł���̂́A�u���J�l�v����ł͂Ȃ��B����̃A�����J�̃y���V���x�j�A�B�ɏZ��ł���L���X�g���k�̈�c�������ł���B�A�[�~�b�V���ƌĂ�邱�̈�c�́A18���I�Ƀ��[���b�p����ڏZ���Ă��Ĉȗ��A�ږ������̃L���X�g���k�Ƃ��Ă̌����������K�������܂�����āA�u���Ԃ̑��v���̂܂܂́A���������̐����𑗂��Ă���B�d�C�A�K�X�A�����Ƃ��������̂͂Ȃ��A�e���r�����@�Ȃǂ��Ȃ��A�����Ԃ�k�^�@�Ȃǂ̋@�B���g��Ȃ��B���Ԃ𗘗p���A�n�Ԃ𑖂点�A�ƒ{�ƂƂ��ɐ����A�q�������̋�������̓Ǝ��̊w�Z�ōs���Ă���B�������́A�d�C�������Ԃ��Ȃ��ƕ����������ŁA����ł͂����������s�ւł��낤�ƍl�����������A���̂悤�Ȕނ�́A�ґ���ł����ɉʂ����ĕs�K�Ȃ̂ł��낤���B
�@���̃A�[�~�b�V���̊w�Z�ŁA�A�����J�ł悭�N����e���ˎ������N���������Ƃ�����B2006�N10��2���̂��ƂŁA���̎��ӂɏZ��32�̒j���w�Z�ɐN�����āA��������������̕Ћ��ɏW�߂āA5�l���ˎE���A6�l�ɏd�y�������킹���̂ł���B�j�͏e�𗐎˂������ƁA���������E�����B���̒j���Ȃ��A�[�~�b�V���̊w�Z��I�̂��͖��炩�ł͂Ȃ����A�����c�������������̏،�����A���˂̏����炩�ɂ��ꂽ�B�����`���������̃A�����J�̃��f�B�A�́A�u���̎q�̋����ׂ��E�C�v�Ƃ��u���߂̐[���͗�������v�ȂǂƑ傫�����B
�@�܂��A�]���҂̂Ȃ��ōŔN���ł�����13�̃}���A���E�t�B�b�V���[����ł���B�����Ɏc���ꂽ10�l�̏�����e�^�҂�������ƕ����������A�ޏ��́u���������Ăق��̎q�͉�����Ă��������v�ƌ����Đi�ݏo���B������}���A������̖��ŁA�a�@�ňӎ�������11�̃o�[�r�[���b���Ă���B���̃o�[�r�[������A�u���̎��͎����v�ƌ������B�}���A������͌�����Ď��S���A�o�[�r�[����͌��ɏd�������B�S���Ȃ������ɂ́A�}���A������̂ق��A12�A8��2�l��7�̏������܂܂�Ă����B
�@�e�^�҂̉Ƒ��́A�A�[�~�b�V���̈���ł͂Ȃ����̂́A�����n��ɏZ��ł����炵���B���ꂾ���ɁA���ꂾ���̑傫�ȎE�������������N�������e�^�҂̉Ƒ������́A�g�̒u�������Ȃ��v���ł������낤�B�Ƃ��낪�A�A�[�~�b�V���̐l�����́A���̉Ƒ��������̖邩��K�˂Ď͂���\�����A��������ׂ̂��Ƃ����̂ł���B�⑰�̈ꕔ�͗e�^�҂̉Ƒ����q�ǂ��̑��V�ɏ������Ƃ����`�����Ă���B�A�����J�̓L���X�g���̐���ȍ��ł��邪�A���̂悤�ȃL���X�g���k�̎p�́A�����Ĉ�ʓI�ł͂Ȃ��B�ߒQ�ɂ���钆�ɂ��\�͂����Ǝ͂��ŕ�ݍ��ރA�[�~�b�V���̐l�тƂ̐������́A�L���X�g���Љ�̂Ȃ��̐M�̂�����ɂ��A�傫�ȗ������������Ƃɂ��Ȃ����B
�@�A�[�~�b�V���̐l���������������`�̌���I�ȕ�炵��ނ���̂́A�L���X�g���k�Ƃ��āA���m������������d�邩��ł��낤�B�N���u�_�ƕx�ƂɌ��ˎd���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v����ł���B�e�̉��s�ɏے������悤�ȁu�́v��M��A�����J�Љ�̂Ȃ��ŁA��̖\�͂�r���鐶�������т����Ƃ���̂́A�����ɐ����̈��̋�������낤�Ƃ��邩��ł���ɈႢ�Ȃ��B�u���ꂩ���E�̖j��łȂ�A�ق��̖j�����ނ���v�ƃC�G�X�͋������B
�@�����āA�ނ炪�A����̐��E�ւ̋����M�������Ă���̂��A�C�G�X�̋����𐳂�����������A���R�̋A���ł���Ƃ�����B�{���̃C�G�X�̋����Ƃ́A�l�Ԃ���I���݂ł���A��ł��邩�炱���i���ł���Ƃ����^���𒆐S�ɐ��������̂ł͂Ȃ������ł��낤���B���́A�ނ���A�����L���X�g���k�ł���Ȃ���A�����́A�L���X�g���k�łȂ��Ă��A�����k�Ȃǂ����܂߂āA�u���߂̐[���͗�������v�Ƌ����Ă��鑤�ɂ���̂�����������Ȃ��B���㕶���Љ�̌o�ϔ��W�����`�A���m�ƃJ�l�ւ̖O���Ȃ��Nj��́A�l�X�̍K���������点��ǂ��납�A�l�X�̕��a�ȕ�炵��j�A�S�̈ł�[�߂Ă���悤�Ɏv����B���āA�V���o�[��o�[�`�́A���̂悤�Ɍ������B
�@�s�n��l�ނ͓����������A���I���Ȏ�`���×~�Ƌ��~�̏��n�ɑ�������A���ꂪ�푈�Ɩ\�͂Ƒ����݂�ł���܂��B��̗D�ʐ���F�����A�l�Ԃ����̂�������������ł��邱�Ƃɓ��S�������\ ������������ׂĂ̐l�Ԃ��_�̕���ł���A����̂ɐl�ނ݂͂ȌZ��ł���o���ł���A�_�Ƃ���Ƃ������Ƒ��ł��邱�Ƃɗ��������������A���̎��͂��߂Đ푈���\�͂������݂������Ȃ邱�Ƃł��傤�B�����Ĉ��ƈ���݂Ǝ��߂Ɗ��e�Ƌ����ƒ��a�ƕ��a���x�z���邱�Ƃł��傤�B�t�i�w�V���o�[��o�[�`�̗�P (11)�x p.54�j
�@���́u���I���Ȏ�`���×~�Ƌ��~�̏��n�ɑ�������v�Ă���́A���܂̃A�����J�Љ�̈ꕔ�̕x�҂̊Ԃœ��Ɍ����ł���B�����̍��x�̔��B�́A�ނ�Ɂu���Z�H�w�v�Ƃ������ٕ�����J�������A���x�̐��w�ƃR���s���[�^�Z�p����g���āA�������܂ܔ���ȗ��v�ݏo���d�g�݂����グ�Ă���B����10�N�ȏ���O����A���E�̂Ȃ���1�p�[�Z���g�̕x�T�҂����E�����Y�z��40�p�[�Z���g��ۗL���A���10�p�[�Z���g�̕x�T�w�ł́A���̐�L����85�p�[�Z���g�ɒB����Ƃ����Ă������A���̋ɒ[�ȕx�̃A���o�����X�́A���܂͂����ƍL�����Ă���ł��낤�B�����āA����ɂ��ꂩ����A�N�X�L���葱����C�z�ł���B
�@�������A���̈ꕔ�̕x�T�w�́u���I���Ȏ�`���×~�Ƌ��~�v�͎Љ�̋��e�͈͂̌��E�ɋ߂Â��Ă���Ƃ�����ł��낤�B���邢�́A���łɌ��E���Ă��܂��Ă��邱�Ƃɐl�X���܂��C�����Ȃ������Ȃ̂�������Ȃ��B����10��13����NHK�X�y�V�����ł́A�����̌o�ς̍����������ݏo���Ă����n�x�̊i���̑���ɐl���̔��������܂��Ă���̂�}���邽�߁A���{���@���𗘗p���n�߂����Ƃ��A�`�����Ă����B���Ă͒e���̑Ώۂł�������F�߁A�u���l�ւ̎v�����v��u�����ɂƂ���Ȃ��S�v���d��ŁA�l���̕s�����������������Ƃ��Ă���̂ł���B�L���X�g�������e���āA���F����̂ق��u�ƒ닳��v�������āA���܂܂�600���l���炢�ł������M�҂��A�ŋ߂ł�1���l�ɂ��B���Ă���炵���B�u�q����`�v�ł͐l�Ԃ͍K���ɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��A�����̐l�X�������������n�߂�悤�ɂȂ��Ă����Ƃ������B�i�u��������(2)�v�j
�@���̕n�x�̊i���̑���ɕs�������l�X�̏́A�A�����J�̏ꍇ�A�����A�����Ɛ[���ł���B���āA�x�g�i���푈�ɔ������҂������W�߂ĊJ���ꂽ1969�N8���̃E�b�h�X�g�b�N�E�R���T�[�g�́A��O�̋K�͂ɖc��オ���Ē��O��40���l�ɂ��B�����B���̂��ƁA11��13������́A�A�����J�e�n�Ōv100���l�ȏオ����f�����s���A15���ɂ͎�s���V���g���ł̔���W��ɁA�S������25���l���W�܂����B��s�ɂ��ꂾ���̃f���Q���҂��W�܂����̂́A�A�����J�j�㏉�߂Ă̂��Ƃł���B����^���ɔM�S�Ȃ̂̓A�����J�Љ�̎�҂ł���n���w�ł���B���܃A�����J�ł͂��̕n���w�̐l�X���A�Љ�̋ɒ[�ȕn�x�̊i���ɋꂵ�ݔY�܂���Ă���B������Ƃ������������ŁA���x�́A����^���̎����������ƍL�͈͂ɁA�n���w�̐l�X���Љ�̕s������i���ė����オ���Ă����̂ł͂Ȃ����B���ɂ͂��̓����A���܂艓���ł͂Ȃ��悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B
�@����E����A�A�����J�Ɍނ��钴�卑�Ƃ��ČN�Ղ����\�r�G�g�A�M�́A1991�N��12��25���ɕ����B1917�N11��7���̃��V�A�v���ȗ��A74�N��̂��Ƃł���B����́A�Љ��`�̌��E��I�悵�����̂ɂق��Ȃ�Ȃ����A�������A������Ƃ����Ď��{��`���������̂��Ƃ����ؖ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ނ���A���̂悤�Ɂu���I���Ȏ�`���×~�v�ɂ܂݂ꂽ�܂܂ł́A�₪�Ď��{��`���s���l��͂��ł���B�����Łu�q����`�v�ւ̔��Ȃ����܂��Ă���悤�ɁA���m�Ƌ��K�ւ̖O���Ȃ��Nj����A�������������čK���ɂ�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����F�������E���ɍL�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B���Ԃ͂������Ă��A�u�l�ނ݂͂ȌZ��v�ł��邱�Ƃɖڊo�߁A�ݏ��Ɨ����̐��_�Ŋi���̂Ȃ��Љ�������ɖڎw���Ă����ȊO�ɂ́A�������̖����͂Ȃ��̂ł���B
�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@��������������������
�@�@��؍q��@��������30�N�����炦���@�@
�@�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (91)�\�@ �@�@�@�@
(2013.09.01)
�@���N�A�u9��1���v���߂Â��Ă���ƁA���܂��Č��T�i����̂�j�̓����O�����w����̐e���������F�l�����l�l����d�b���������Ă���B���N���������Ă����B���T�ƕ�e�̗�O�ɉԂ������āA���Ⓑ���̉Ƒ������ƐH�������ɂ���ł����킹�̂��߂ł���B�������@���������Ă�����N�������āA���́u�Âԉ�v�́A�����̔N�̑��V�ȗ��A�r��邱�ƂȂ������Ă����B�u�\�N��́v�Ƃ������A���́u��́v��3��J��Ԃ���Ă��邱�ƂɂȂ�B�����̂Ƃ��Ɍ��T�Ɠ�����21�ΑO��ł������ނ�����܂ł�50���z���Ă���B���m�����Ƃ��đ�w�ŋ����Ă���s�N���͂��߁A�O�ȓ��w�E�B�Y�_���p�a���T�x�̕ҏW�ψ��Ȃǂ����߂�悤�ɂȂ����x�N�ȂǁA���ꂼ��ɎЉ�̊e����̑����Ŋ��Ă���l�����ł���B�����āA���̎�53�ł���������83�ɂȂ����B�����g���A�����ȗ��́A�Í��̐�]�Ɣ߂��݂���[�����g�Ɗ��ӂւ̑傫�ȕω����A����30�N�̊Ԃ̐S�̔N�ւɍ��ݍ���ł����Ƃ����邩������Ȃ��B
���́u���E�j�̓]���_�v�Ƃ���ꂽ��؍q��@�������N�������̂́A���傤��30�N�O��1983�N9��1���i���{���ԁj�ł������B���͂��̓����́A�m�[�X�E�J�����C�i�B����w�̋q�����������Ă����B������w�̗��w���ł����������Ɠ�l�����̗[�H���Ƃ��āA���̌�Еt�������Ă������ł���B�ߌ�7���̃e���r�ŁA�O���̖�Ƀj���[���[�N�𗣗�����KAL007�ւ��s���s���Ƃ����j���[�X���J��Ԃ��ė���n�߂��B����KAL007�ւɂ́A�ȥ�x�q�ƒ��j����T������Ă����B�ċx��4�T�Ԃ��Ƒ��l�l�����炸�ʼn߂����āA�A���̓r���������̂ł���B���ƒ����́A��u�ɂ��ĔߒV�̂ǂ��ɓ˂����Ƃ��ꂽ�B
�@�K���ɂȂ��ăe���r�Ɠd�b�ɂ�������Ă��邤���ɁA�ߌ�10���߂��ɂ́ACBS �e���r�̔ԑg���ꎞ���f����āA�uKAL �@�̓T�n�����ɕs���������͗l���Ɓv�Ɠ`�����B����͓��{�ł��j���[�X�œ`����ꂽ�炵���B�����̎��̎o��A�x�q�̖�����̍��ۓd�b�Łu�T�n�����ɕs�������āA��q�͑S�������v��m�点�Ă����B���͗܂����ڂ��āu�����v����B�������A���̃j���[�X�͂��̌�A�[��̓������炩�����ė����x�q�̒킩��̓d�b�Ŕے肳�ꂽ�B���{�̊O���Ȃ̖₢���킹�ɑ��āA�\�A���{���A�u�T�n�����ɖ��ԋ@���s�������������͂Ȃ��v�ƒʍ����Ă����Ƃ����̂ł���B�n��ɂ��Ȃ���Ηm��ɗ����邵���Ȃ��B����͊m���ɂȂ����B���ƒ����́A�܂��ޗ��̒�ɓ˂����Ƃ���Ă��܂����B�߂��݂Ƌꂵ�݂ňӎ����N�O�Ƃ���Ȃ��ŁA�������́A���̗����A���{���������B
�@���{�A���Ă�����A���͂قƂ�ǐQ������ɂȂ��Ă����B�ڂ��o�܂��ƁA�Ȃƒ��j�����Ȃ��Ȃ��������ɑς���Ȃ������B��x�A�A�����J�֖߂��āA���̓m�[�X�E�J�����C�i�B����w�ł̍u�`�𑱂��邱�ƂŁA�����͖Z�����w�Ƃɒǂ��邱�ƂŁA�Ȃ�Ƃ��������낤�Ƃ��Ă݂����A�ł��Ȃ������B�������́A���ׂĂ���߁A���{�A�������B�D�y�̎���ŁA�܂��A�Q������̂悤�ȏ�Ԃ��������B�x�q�ƌ��T������Ă�����s�@���\�A�̐퓬�@�Ɍ��Ă��ꂽ�Ƃ����̂́A���������ǂ��������ƂȂ̂��B�������́A�ڂ��o�܂��x���ɂ��̖₢��˂������Ȃ���A����ɓ�����̂��Ђ�����ɔ����悤�Ƃ��Ă����B���ɂ͂��́u�����v��^���ʂ���Ƃ߂�C�͂͂Ȃ������B�����Ƃ͗V����������̐��E�������肠���A���̒��ɓ������ނ��Ƃɂ���āA�h�����Đ����Ȃ��炦�Ă����̂ł���B���͐����邱�Ƃɐ�]���Ă����B�O�r�ɂ͂Ȃ�̊�]�����ĂȂ������B
�@���N(1984�N) ��4������A���M���ȑ�w�֕��A���ċ��d�ɗ��悤�ɂȂ������A�ꂵ�����X���������B�������A�ǂ�Ȃɋꂵ���Ă��A���ɂ͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�����������B�x�q�ƌ��T����������{�ɂ��Ďc���Ă������Ƃł���B
���T�͓����O�����w�̎l�N���ɂȂ��Ă���͂��ł������B���̗��N�̏t�ɂ͑��ƂŁA�F�l�B�Ƃ�����Ȃ�ɂȂ��Ă��܂�����A�{�����̂Ȃ�A�����Ȃ��Ă���ł͒x���B�����������ɖ{�����ꂸ�A����̐��E�ɐg���������܂܂ł́A�����v�̍b�㐫���A�������e�̈���Ƃ����悤�Ȑ������̒��������߂��肷��B���͂�������ȏ�x�q�ƌ��T�ɑ��āu�߁v���d�˂邱�Ƃ͏o���Ȃ��Ƃ����悤�Ȑ؉H�l�����C���ŁA��悤�ɂ��āA�Ǔ��̏��̕ҏW�Ɏ��g�ݎn�߂��B���N�قǂ������āA1984�N11���ɏ㈲�����w�ȂƎq�̐������Ɂx�i�k�s�o�Łj�́u���Ƃ����v�Ɏ��́A���̈ꕔ�����̂悤�ɏ������B
�@�s�����̖{���܂ƂߏI�����Ɏc���ɓ����āA���̑S�g��˂������Ă����̂́A�����܂�������̋��ł���B�������������n�܂�A�����I������Ƃ����̂��B���̖��ɂ��������������́A���ɂƂ��Ă̂��ׂĂ����Ȃ�ꂽ���Ƃł́A�����Ƃ̎n�܂���Ȃ��A�I�����Ȃ��B����͈̂ˑR�Ƃ��čL���Ƃ����u���v�̐��E�̂Ђ낪�肾���ł���B���͂��ꂩ����܂��A�����Ɖ���̐��E�̒����s�����藈���肳�܂悢�Ȃ���A�ɂ������Ȃ��]����Đ��I�ɂȂ��ł������ƂɂȂ�̂ł��낤����������t
�@���́u�ɂ������Ȃ��]����Đ��I�ɂȂ��ł����v�Ȃ��ŁA���ɂ͈⑰�Ƃ��Ăǂ����Ă��ʂ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��ӔC���������B�����̐^�������ł���B���܂�ɂ��s���ŗ��s�s�Ȏ����ł����������ɁA�����Q���Ă���ł��邱�Ƃ͋�����Ȃ������B��������l�ł��A�^�������ɗ����オ��˂Ȃ�Ȃ������B�ߒV�ɕ��Ȃ���������ɂ��Ē��ׂĂ����͓̂�d�̋ꂵ�݂ł��������A��������1���N��1984�N8��30����9��1���ɂ́A�u�k�C���V���v�Ɂu�����Ȃ��^�f�v (��j�i���j���������B����ȗ��A���́A�����̓A�����J�R���̖d���ɂ����̂ł��邱�Ƃ��A�@��邲�ƂɐV����G���ɏ����đi���n�߂��B�}�X�R�~�⍑��c���Ȃǂ֑i���邽�߂ɁAB4�ł̍L�uAPPEAL�v�T��l�Ŕ��s����悤�ɂ��Ȃ����B
�@���̗��N�A1985�N�ɂ́A���́u�⑰�͂Ȃ��A�����J��e�N���邩�v�i��g���X�u���E�v1985�N10�����j���������B���̂Ȃ��ŁA���́AKAL007�ւ��̈ӂɍq�H����E���A�T�n�������t�߂ł͉E����A������3��t�C�[�g���̍��x�ύX�܂œƒf�ōs���Ă����������A���J�����B���{�̖h�q�����Ђ��B���ɂ��Ă������̒t�����[�_�[�̋L�^���A�`�L�Q�c�@�c�����ēx�̎����ӏ����o���āA���{���{�ɔF�߂������̂ł���B���{���{�́A��������ɂ́u�^�������v���v�ʼn���������̋c��������Ȃ���A�����炭�A�A�����J���{�̖d�������炩�ɂȂ�̂�|��āA�I�n�A�^�����B�����ɂ܂���Ă����B�������ɏo�ł����w�^�f�̍q�Ձx�i���o�ŎЁA1985�N�j�́u�����v�̏͂̂Ȃ��ł́A���́A���������Ă���B
�@�s�^���͂͂��߂���킩���Ă����B�����A������A�����܂߂��A�����J���{�����Ђ�����ɉB���Ă��������ɂ����Ȃ��������
�@�������́A����ƃA�����J���{�́u�ƍ߁v�ɂ��Ċm�M�����߂Ă������B
�@����1���́u�R�c�̓��v�ɂ́A��؍q���\�A�ɑ���R�c�d��̂ق��A���[�K�����ɂ��R�c�d���ł��͂��߂��B�R�c�̎莆�������A���V���g���̃z���C�g�E�n�E�X�֑���͂��߂��B
�@��������ȁA���ǂ남�ǂ낵�����̂ɑ��Ă��奂̕��ł��邩������Ȃ��B
�@�������A���͕x�q�̕v�ł���A���T�̕��ł���B
�@�x�q�̕v�Ƃ��āA���ꂩ������炩�ɂ��ׂ����Ƃ͐l���Ɛ��`�̂��߂ɖ��炩�ɂ��A���T�̕��Ƃ��āA�i���Ă����ׂ����Ƃ͐��E�̗ǐS�ɑi���Ă������Ƃ���ł��낤�B
�@���ꂪ�A�����c�������́A���ʂ��Ƃ��ł��Ȃ��ł��鎄�́A���߂Ă��́A�ȂƎq�ɕ����郌�N�C�G���ł���B�t
�@���́A�����̗��N�ɓ����ɐݗ����ꂽ�u��؍q��@�����̐^�������������v�̒���c�⌤����̂��߂ɁA�D�y���瓌���֖����̂悤�ɔ�s�@�ʼn�������悤�ɂȂ��Ă����B1986�N�̏t�ɂ͏��M���ȑ�w�����E���ē����̏��q�Z��ֈڂ����B�n�ʂ▼�_�̂悤�Ȃ��̂ɂ́A�������̊S���������Ȃ������B�u���������v�ł́A����c���A�Љ�^���ƁA�q��@�Z�p�ҁA�]�_�ƂȂǂ��܂��܂ȐE��̉���̕��X���M�S�Ɍ��������𑱂��āA1988�N1���ɂ͑���́w��؍q��@�����̌����x�i�O�ꏑ�[�j���o�ł����B���̖{�ł́A���O�̌������Ȃǂ̕��ͥ�Љ�Ȃǂɉ����āA�A�����J�̌R���Ə��g�D���A�\�A�̓d�g�T�m�\�͂�h��Ԑ���T�����邽�߂ɁA007�ւ̋@���ɋ������ăT�n�������ɐN�����������Ƃ������^���鍪����l�X�Ȏ�����،��Ŏ����Ă���B���N9��1���ɂ́A������ق�O�@�c����قȂǂŁA�L�҉���J���Đ����\���邱�Ƃ����Ă����B�����āA���́u�^�������������v�̊������A���́A1991�N�t�ɁA�����h����w�q�������Ƃ��ăC�M���X�֍s���܂ő������B
�@�����ȗ��A���ł�8�N���o�߂��Ă������A�߂��݂̌��ǂ͂܂��[���c���Ă����B�^�����������̖T��A���T�����ǂ݁A�����ł́A��\�҂�200�l������Ƃ���
S ���c�ɂ����Ȃ�p�ɂɒʂ����肵�Ă����B�߂��݂����z���邽�߂̉�����͂����Ƃ��ĕK���ɈÒ��͍������Ă������A���ǁA�����͂߂��A�S�̈��炬�������Ȃ������B�����h���ł����̏�Ԃ͂��炭�������B���͂��̕s����Ȋ��]�̐S�����A���{�S��Ȋw����̋@�֎��u�S�쌤���v�i1992�N1�����j�Ɂu�F��ւ̓��v�Ƃ����^�C�g���ŏ������B��̊�]�́A���̍�����A�V���o�[��o�[�`�̖{���n�ǂ���悤�ɂȂ������Ƃł���B���̏�����Ă��邱�Ƃ̏d�傳�ɋC�Â��Ĉꕔ�������ł��a���肵�Ă��邤���ɁA�w��P�x�̖|��ҁE�ߓ���Y���Ƃ����ʂ���悤�ɂȂ����B
�@�₪�āA1992�N1���̔����߂��āA���낻��A���̏������n�߂˂Ȃ�Ȃ��Ȃ������A���͂悤�₭��p�S�싦��֒ʂ��悤�ɂȂ����B�����ʼn�����͂߂Ȃ���A���͎��ʂ܂ŋ~���Ȃ��Ƃ����؉H�l�����C�����ł������B���̓X�s���`���A���Y���̖{��ǂ݁A�f�����X�g���[�V�����ɎQ�����Ă�����̏����𐮂�����ŁA��\�҂̑O�ɍ���悤�ɂȂ����B������1992�N2��11���A���͗�\�҂̃A����^�[�i�[�ɉ���āA�傫�ȓ]�@���}�����̂ł���B���͂��̕x�q�ƌ��T�������Ă��邱�Ƃ��m�M�����B�ޏ��ɂ͓�x�A�O�x����Ċm�F�������ԈႢ�͂Ȃ������B��Ղ��N�������Ƃ��������悤���Ȃ������B���́u��Ձv�ɂ��Ă͂��낢��Ə����Ă����̂ł����ł͐G��Ȃ����A���͒��N�̔ߒV�Ɛ�]���珉�߂ĉ������A�Â����̕������S�����悤�Ȗ��邢�C�����ɂȂ����̂ł���B���܂ɂ��Ďv���A���͍s���ׂ����ă����h���֍s���A��ׂ����ăA����^�[�i�[�ɉ�����Ƃ������Ƃł��낤�B
�@4���ɋA�����āA���͑�؍q��@�����u�⑰��v�̉������ɉ�����B�݂�Ȏ��Ɠ��l�ɁA���̎����ʼnƑ���S�����ĔߒV�ɕ��Ă����l�����ł���B�݂�Ȃ͎��̕\��̕ω��ɋ�������������Ȃ��B�������A�]���҂́u����ł͂��Ȃ��v�̂��ƔM�S�ɐ������̘b�ɂ́A��͂蔼�M���^�ł������悤�ł���B���̌���d�b�Řb���A���������̂𑗂葱�����肵�����A��͂�A�Ȃ��Ȃ��킩���Ă��炦�Ȃ������B�M����ׂ����Ƃł��M�����Ȃ��Ƃ����̂͒v�����̂Ȃ����Ƃł���B��I�Ȑ^���������ɂ́A���̗p�ӂ��ł��Ă�����Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��낤���B���͂���A�u�^�����v����u�^���鑤�v�ɂ܂�������A���̂悤�ɂ��Đ����n�߂����͂Ƃ̐S���I�ȃM���b�v�́A�₪�Đg�̂܂��̉Ƒ���e�����F�l�����ɂ��y��ł�������������Ȃ��B��w�̌Â������q�̉��l�����A�����痣��Ă������B
�@���������͋��܂Ȃ������B�����Ă��������Ƃł͂Ȃ������B���̓����h���ł̊m�M������ɕ⋭���Ă������߂ɁA���ꂩ������N�̂悤�Ƀ����h���̑�p�S�싦��֒ʂ����B�A����^�[�i�[�Ƃ����x����A���{�ł��A��\�҂�A
�t��ʂ��ĕx�q�ƌ��T����̒ʐM�����悤�ɂȂ����B�ނ炪��E�Ō��C�ɐ��������Ă��邱�Ƃւ̊m�M�́A�h�炮���Ƃ͂Ȃ������B���͂��̂��Ƃ������q��{�ɏ����A�u����Řb�����B2003�N3������́A�z�[���y�[�W�u�Ƃ����сv���J�݂��āA���j���������Ăقږ����A��I�^���𒆐S�Ɍ��e�������A���J���n�߂��B���̎��_�ŁA�����シ�ł�20�N���o�߂��Ă����B�����h���̑�p�S�싦��ŁA�u���Ȃ��͗�I�ȋ��t�ɂȂ�v�ƌ���ꂽ���Ƃ����������A�����͂��ꂪ�ꕔ�ł������ɂȂ����̂�������Ȃ��B
�@���̔N�A2003�N��9��1���ɂ́A����20���N�̈ԗ�Ղ��t���E�@�J���́u�F��̓��v�̑O�ōs���A�����Q���B�ߋ����x���̈ԗ�Ղł́A�߂��݂ɑς����˂Ď���œ|�ꂻ���ɂȂ������Ƃ����������A20���N�̎��̎��ɂ́A�����A���Ă̔߂��݂͂Ȃ������B���N�ɂ킽���Đ^�������^�������Ȃ���A�A�����J�哝�̃��[�K���⍑�������̃V�����c�A���h�����̃��C���o�[�K�[�Ȃǂ֍R�c�d���莆����œ��������Ă��������������݂��A���̊Ԃɂ������Ă����B�ԗ�Ղł̋L�҉�ň⑰�������A�قƂ�Ljٌ������ɁA�u���N�o���Ă��߂��݂͏����邱�Ƃ�����܂���v�Ɠ����Ă���̂��A���͖ق��ĕ��������Ă����B
�@����Ɍ���������āA���N�A2011�N6���ɁA���́w�V������̎莆�x�i�w���p�u���b�V���O�j���o�ł����B����܂ő����Ă����A��E�̕x�q�⌉�T�Ƃ�18�N�Ԃɂ킽���E�ʐM�����J�������̂ł���B����͎��ɂƂ��Ă�������ƕs�v�c�Ȗ{�ł������B�{�̏o�łɂ́A�ʏ�A�o�ł����܂�܂ł���ς����A���܂��Ă�����A�C���A�Z���Ȃǂ��܂��܂Ȗʓ|�����܂Ƃ����̂����A���̖{�̏ꍇ�́A�o�ł̘b���������܂�Ă���A���ׂĂ��X���[�Y�ɐi�B�u���ԂɈ�����{�܂ŏo���オ���Ă��܂����悤�Ȋ����ł���B6��5���ɍ]���搴���뉀�̑吳�L�O�قŏo�ŋL�O�u������J�Â��ꂽ�B�T�C����Ȃǂ����߂Čo�������B���̓��͌��T��49��ڂ̒a�����ɓ������Ă����̂ŁA�ҏW�W�҂̕��X�����̓��̖�ɂ́A�߂��̃��X�g�����Œa���j�̉���J���Ă��ꂽ�B��E����̏��ł́A���낢��ƌ��T�����̖{�̏o�łɊւ��A�������Ă���Ă����炵���B
�@�����Ď��́A��N�̑咰����ƕ�������ᎂ̎�p���o�����āA���N�͂܂��A�u9��1���v���}���悤�Ƃ��Ă���B����Ŏ��́A�����タ�傤��30�N�����тĂ������ƂɂȂ�B���N�ɂ킽���đ����Ă����x�q�ƌ��T�̈�i�����⏈�����A���̊Ԃɂ悤�₭�A�قƂ�ǂ��ׂĂ��I����Ă���B�ߗނ̑唼�́A�~�����}�[�̔��L�����v�Ȃǂ֑���A�x�q�̓��{���w�W�̑����̂������S���́A���̗m���ƈꏏ�ɁA�C�O�̑�w�}���ق֊����B�A�����J�̏o�g��w���܂߂ĕ̂��߂ɂƍl���Ă����c�̂�l�ɑ����t����ʂ�I�����B�ǑP���{�̂���ŁA�C���h�ƃl�p�[���̕n�����_�Ƃ̓�l�̗c���̗{�������葱���Ă������A�\���N�̊ԂɁA��l�Ƃ����C�ɐ������ė��h�ȑ�l�ɂȂ����B���N�̏t�ɂ́A�u���{���T�̋L�^�v�i�����Ǝʐ^�̃t�@�C���j���쐬���āA�����̐^�������ɂ��Ă̎��̒���⎑���Ƌ��ɁA�����O�����w�̕����قɏ������Ă�������B30��ڂ́u9��1���v���}����ɂ������āA���ɂ́A�⑰�Ƃ��Ă���ׂ����Ƃ͂��Ă����A�Ƃ����W�����S������B
�@���N�́u9��1���v�ɂ́A�k�C���V�����A��؍q��@����30���N�Ƃ������ƂŁA���W�L�����ڂ���\��ł���炵���B�����̋]���҂̈⑰�Ŗk�C���ݏZ�҂͎������ł������̂ŁA���̐V���ɂ́A�����ȗ��A�Ƒ��̂��Ƃ����낢��Ǝ��グ���Ă����B�������x���A���ʂɐ^�������̌��e���Ă����B�������������̂��̂́A30�N���o�āA�A�����J�̖d�������ɖ���݂ɏo�Ȃ��܂܂ŕ���������B�u����ł͈⑰�����̔߂��݂������邱�Ƃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����ɂ��Ăǂ��v���Ă��邩�v�ƐV���̕ҏW�ψ��ɕ�����āA���͂����������B
�@�u30�N�o���ăA�����J���{���R�Ƌ\�Ԃł��̔ƍ߂��B�����������悤�ɂ݂��Ă��A�L������ł݂�A�w�F���̐ۗ��x�Ƃł������ׂ���Η��̂Ȃ��ł́A�N��l�A�Ƃ����߂��瓦��邱�Ƃ͂ł��܂���B�⑰�Ƃ��Ă��܂ł��Q���߂��ނƂ����̂��A�]���҂ɑ��鋟�{�ɂ͌����ĂȂ�Ȃ��ł��傤�B
�@���N�̔߂��݂Ƌꂵ�݂��o�āA���́A���̉F���̐ۗ��̂Ȃ��ł̐l�Ԃ̐��Ǝ��⎩�����g�������ߒ����悤�ɂȂ�܂����B�v
�@���͂��܁A���݂��݂Ƃ���30�N��U��Ԃ�B�l���Ă݂�A�悭�����́A���̐�]�̕����甲���o�����Ƃ��ł������̂ł���B���̑�؍q��@�����ŕx�q�ƌ��T�������ĔߒV�̂ǂ��ɓ˂����Ƃ��ꂽ�͕̂�����Ȃ������ł��邪�A���܂ł͂�����u���ꂽ�ߌ��v�ł͂Ȃ��āA�ނ���u�V�̔z���v�ł��邱�Ƃ��A�m��悤�ɂȂ��Ă����B���Ǝv���Ă����x�q�ƌ��T�����C�ɐ����Ă��邱�Ƃ��킩�����ȏ�A�߂��݂ɕ��闝�R�͉����Ȃ��B�߂������A�ނ�Ɖ�邱�Ƃɂ����������̋^���͂Ȃ��B���ׂĂ��������ƒQ���Ă������A�{���́A���������Ă͂��Ȃ������B���܂́A�����A���ӂ�����݂̂ł���B
�@������������ʼn߂������Ă���������܂ł�30�N�́A�m���ɔg���ɖ����Ă����B�������܂߂ėl�X�Ȋ�{���y�̐U���̌������̌������������A���ׂĂ͋N����ׂ����ċN���������ƂŁA�����ĈӖ����Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�����̈����A���ɂƂ��Ă͎����̍����ڊo�ߐ������Ă������߂ɕK�v�Ȋw�тł������B���܂̎��͂��̂��Ƃ𗝉����[�����āA�����뉸�₩�ɂ��̐��������Ă�����ł��낤���Ƃ��A�L�����ƂƎv���Ă���B���̎�����30�N�́A���̈Ӗ��ł��A���ɂƂ��Ă͍Ō�̑傫�Ȑߖڂ̔N�ł���B�����Ă܂��A���́u�X��1���v�̒����̓��́A���܂ł͑�Ȋw�т̓��ł���A���ӂ����߂��F��̓��ɂ��Ȃ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@��E���猩����Đ������@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (90)�\�@
(2013.07.01)
�@

����̒��A���N�ɂȂ��ĂT��ڂɊJ�Ԃ�����̉�
�̈�B���ꂪ18�ڂɂȂ�B2013.06.30.�u����
�ɏo������O�ɎB�e�B�ߌ�P���ɋA������ɂ͂���
���ڂ�ł����B
�@���̃A�p�[�g�̃x�����_�̃T�{�e���́A���N���A�����̉Ԃ𐔎��Ԃ����J�����Ă����̂����A��N�Ɍ����āA�咰����ƕ�������ᎂ̓�̕a�C�̌����A���@�A��p�Ƀ^�C�~���O�����킹��悤�ɁA7����̊J�Ԃ��J��Ԃ����B���́A��N10��29���A���̃z�[���y�[�W�́u�����E�Z�M�v���ŁA�u�O�x�ڂ̓��@�̓��̒��ɊJ�����T�{�e���̉ԁv�Ƒ肵�āA���̂悤�ɏ����Ă���B
�@�s�{���Ɂu�v�������Ȃ���x�ڂ̉Ԃ��J�������T�{�e���v���ڂ����̂́A���N�i2012�N�j��7��20���ł����B�u��N�Ɉ�������Ԃ��J�����Ă��Ȃ��������̃T�{�e�����A���N�Ɍ����āA��x�ڂ̉Ԃ��J�����邱�ƂɂȂ낤�Ƃ́A������ƐM�����Ȃ��悤�ȋC�����Ă��܂����v�Ƃ��̎����͏����Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���́A���̃T�{�e���̉Ԃ́A���N�͂��ꂩ��������玟�ւƊJ�Ԃ𑱂��āA10��12���A�Ō�̓��@�̓��̒��A���̂悤�Ɏ���ڂ̉Ԃ��J�����Ď����������Ă���܂����B�i�����ł͎ʐ^�͏ȗ��j
�@���̃T�{�e���̍��N�̊J�Ԃ̈��ڂ�6��14���ŁA���̗�������咰����̌��f���āA�����������ł���������܂����B���ڂ̊J�Ԃ��O�q��7��19���ŁA����̐؏���p���đމ@���Ă��������̂��Ƃł��B�Ƃ��낪�A���̃T�{�e���́A���̌���A�O��ځE8��13���A�l��ځE8��20���A�܉�ځE8��24���A�Z��ځE9��23���A�����āA10��12���ɂ͎���ڂ����̂悤�ɊJ�Ԃ����̂ł��B�ʐ^�ɂ���ĉ��߂Ă��ꂼ��̊J�Ԃ̓��̑O����m���߂Č��܂��ƁA�މ@��Ɠ��@�O�̈�A�̌�����f�f�ŁA�d�v�Ȑߖڂ̓��ɓ������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�@�N�Ɉ���J�Ԃ��Ă��Ȃ��������̃T�{�e�����A�Ȃ����N�Ɍ����Ď�����ԊJ�����̂��A���������T�{�e���Ɍ��炸�ԂƂ����̂́A����ȂɔN�ɉ�����J�����̂Ȃ̂��A���ɂ͂悭�킩��܂���B�����A���N�����͎��̂��̃T�{�e���́A6��15���̑咰����̔�������A10��12���̕�������ᎂ̎�p�̂��߂̓��@�Ɏ���܂ŁA����̎��̕a�C�̌o�܂ɕt���Y���悤�ɁA�Ԃ��J�����Ă����Ƃ����܂�����Ȃ��������������̖ڂ̑O�ɂ���܂��B�l���Ă݂܂��ƁA���̑傫�Ȏ�p�̑O������A�����Ȃ�̕s�����|����Ȃ����₩�ɉ߂��Ă��ꂽ�̂��A���̏����̔������Ԃɂ���Ă�������Ă������炩������܂���B�t
�@���̃T�{�e�����A��N�A7����̊J�Ԃ��J��Ԃ����Ƃɂ͉����Ӗ�������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă������́A���N�͂��̃T�{�e�����ǂ������炫��������̂��A�����������Č�����Ă����B�܂��A��N�̂悤�ɁA�N���A�����̉Ԃ��J�������Ԃɖ߂�̂��A�������茩����߂Ă��������Ǝv���Ă����B�������A��͂荡�N���A�ŏ��̊J�Ԃُ͈�ł������B���̏�6��1���́u�����E�Z�M�v���ŁA���́A�u���N�͔��̉Ԃ��J���������̃T�{�e���v�Ƃ����^�C�g���ŁA�����L���Ă���B
�@�s���N6�����{�Ɉ���A�����̉Ԃ��J�����Ă����x�����_�̃T�{�e�����A��N�͎��̓��މ@�ɍ��킹��悤�ɁA7����J�Ԃ��܂����B6��14������10��12���ɂ����Ăł��B����ŁA���N�͂ǂ̂悤�ȍ炫��������̂��A�����������Č�����Ă����Ƃ���A5��21���̖�A�����Q�̂����l���ʐ^�i�����ł͏ȗ��j�̂悤�ɉԂ��J�����܂����B
�@��ɊJ�����Ԃ́A���ɂȂ��ėz�ɓ�����܂��Ɛ����Ԃł��ڂ�ł��܂��܂��B���̎ʐ^�̉Ԃ́A5��22���̒�����ɂ͂��ڂ�ŁA����Ɏc��̎l���Q���Ԃ��J�����܂����B���N�́A5��21���̖邩��22���̗[���܂łɁA���̉Ԃ���x�ɊJ�������ƂɂȂ�܂��B���܂܂ŁA��ȏ�̉Ԃ���x�ɊJ�������Ƃ͂���܂���̂ŁA���N�͂ǂ����Ă��̂悤�ȊJ����������̂��A������ƕs�v�c�Ȋ��������Ă��܂��B
�@�ʐ^�̒������ɏ������Q��������܂����A�����Q�͗������[�����ɉB��Ă�����̂��܂߂Ĕ��������܂��B�����炭�����́A�₪�ĉԂ��J������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���������Ȃ�A���N�́A���̉Ԃ��J������̂�������ƂɂȂ�܂��B����́A���܂܂łɂ͂Ȃ��������Ƃł����\���͂��肻���ł��B�������A���̌���A�܂��J�Ԃ��������ǂ����͍��̂Ƃ���͂킩��܂���B���ꂩ�炵�炭������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�t
�@����6��1���ɏ����������́A8���Q�́A6��16���ɂP�ցA6��19���ɂV�ւƉԂ��J�������B����ō��N�́A���܂܂ł̂Ƃ���A�S�{�S�{1�{�V��16�@�Ƃ����悤�ɁA�l��ɂ킯��16�̉Ԃ��J�Ԃ������ƂɂȂ�B���̕��������Ă���6��30���ɂ́A���̂����ɂ���ɓ�̉Ԃ��J���āi�����̎ʐ^�j�A�悭����ƁA�܂��A����Q���L�юn�߂Ă���B�����炭�����1�T�Ԍキ�炢�ɂ͉Ԃ��J��������̂Ǝv����B��������ƁA���N�́A���ł�19�̉Ԃ��Z��ɕ����āA�J�����ƂɂȂ�悤�ł���B���̌���A����ɊJ�Ԃ��������ǂ����́A���܂͂܂��킩��Ȃ��B
�@�J��Ԃ��ďq�ׂĂ���悤�ɁA��N�͑�P��ڂ̊J�Ԃ�6��14���̑咰���f���n�߂�O���ŁA��7��ڂ̊J�Ԃ���������ᎂ̎�p�œ��@������A10��12���̒��ł���������A4�����ɂ킽���ĊJ�Ԃ𑱂������ƂɂȂ�B�������x�ɉԂ��J���̂́A���܂��Ĉ����ł������B����ɑ��āA���N�́A��x�ɂS����V�Ɏ���܂ł̊J�Ԃ��A���ł�4��A����ɍ��x�̓�ƈ�̊J�Ԃ�������āA6��̉ɂȂ����B�������A�܂��ŏ��̊J�Ԃ���P�����������o���Ă��Ȃ��B��N�́A�J�Ԃ̉́u�ُ�v���ڗ��������A���N�͉����邱�ƂȂ���A�J�Ԃ̉Ԃ̐��́u�ُ�v���J��L�����Ă���̂ł���B���ُ̈�̈Ӗ����m�肽���āA���́A�U���U���A�W���Q���m�F�ł������_�ŁA��\�҂Ƃ��č�����A�t�ɕ����Ă݂��BA�t�͂����������B
�@�s�u�V�v�͐����̐i���̒i�K��\�킵�Ă��܂��B���悢��I�ȓ����́u�V�v�ŕ\�킳��܂��B���Ȃ������̐��ŕa�C�ɂȂ����̂ŁA�x�q����⌉�T������͂��߁A���Ȃ��ƌq���肪����A���Ȃ��������납��v����E�̑��݂������A���̐����琶���͂𑗂��Ă��Ă����̂ł��B���̂��ߋ����قǑ�R�A���đ����ɍ炢�Ă��܂����B���̐����͂̂��A�ł��Ȃ��͎�p�����܂������A���������̂ł��B
�@�����Ă��̗�E����̎x���́A���܂ł������č��N���炫�n�߂Ă��܂��B���̐��Ƃ��̐��Ƃٖ̋��ȊW���������܂��B���Ȃ����g�A��E�ɑ啪�߂Â�����܂��B���ꂩ��܂��܂��A��E�̕��͋C���I���݂����̗Ս݊�����������悤�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B��E�Ƃ��ٖ��ɂȂ��Ă����A���X�ɂ��̐��ւƈڍs���Ă������Ƃł��傤�B���̐��̑��̐g�ӂ̐����⏈���Ȃǂ��A���������Ă����Ă��������B�t
�@A�t����̓��������̂悤�Ȃ��̂ɂȂ�ł��낤���Ƃ͂�����x�͗\�z���Ă������A����ł��A7��́u�V�v�̐����̈Ӗ��́A���ɂƂ��Ă͏����ł���A�V�N�ł������B���̎��́u��E����̎x���v�ɂ��ẮA���ɂ͏\���ɔ[���ł���C������B���������A���́A��E����Ȃ̕x�q�Ⓑ�j�̌��T��������Ă���Ă��邱�Ƃ́A���Ȃ苭���ӎ����ĉ߂����Ă����B�������ӂ̋F��𑱂��Ă��邵�A����̐����̂Ȃ��ŁA���܂��ܑ��������ꋫ����}�ɋ~���o���ꂽ�肷��悤�Ȃ��Ƃ�����ƁA���͎v�킸�u�L��v�ƌ��ɏo�����肷�邱�Ƃ�����BA�t��������悤�ɁA�ނ炪���̐�����u�����́v�𑗂��Ă��āA���̂��A�Ŏ�p�����܂��������Ƃ����̂��A�����炭���̂Ƃ���ł��낤�B�������A���̔ނ炪�����Ă���Ă��������͂��A���̂悤�ȃT�{�e���̉Ԃ̊J�ԂƂ��������I�Ȍ`�ł�������Ă������Ƃɂ́A�v���y�Ȃ������B
�@���̕x�q�ƌ��T����E���獷���L�ׂĂ���Ă����u�����́v�ɂ��ẮA���āA�A���E�^�[�i�[���A�x����̎�p�ŃC�M���X�̃T�E�X�E�E�G�[���Y�̕a�@�ɓ��@���Ă������ɂ��A�ޏ����g�̎莆�Œm�炳�ꂽ���Ƃ��������B2009�N3��1���́u�g�ӎG�L63�v�Ɏ��́A�u��E���獷���L�ׂ�������̎�v�Ƃ����^�C�g���ŁA��E����x�q�ƌ��T���������ɔޏ���K�ꂽ���̂��Ƃ������Ă���B�A���E�^�[�i�[�͗D�ꂽ��\�҂ł���������A���ӂ̋C�����Ŕޏ��̂��Ƃ�K��Ă����x�q�ƌ��T�̑��݂��ӎ��ł����̂ł���B����͎����ɂ킽�邪�A�M�d�ȋL�^�ł��邩������Ȃ��̂ŁA�����̂Ȃ�����A���̊j�S�����������Ă��ɍĘ^���Ă��������B�܂��A�ŏ��́u��Ձv�͂��̂悤�ɋN�������B
�@�s��N�i2008�N�j�̂W���T���A���̏W���������ː����Â��邽�߂ɁA�w�肳�ꂽ�T�E�X�E�E�G�[���Y�̕��ː����a�@���A�A���E�^�[�i�[�͕v�N�̃g�j�[�ɔ����ĖK�ꂽ�B���܂��܁A�W���T���́A�ނ�̌����L�O���ł��������B�\��͌ߑO11���ł��������A10���O�ɂ͂����a�@�ɒ������炵���B�A���E�^�[�i�[�͂��Ȃ�ْ����Ă����Ƃ����B�ҍ����ɗאڂ��鏬���ȃR�[�q�[�E�V���b�v�ŁA�v�N�Ƃ��������݂Ȃ���f�@�̎��Ԃ�҂��Ƃɂ����B
�@���̃R�[�q�[�E�V���b�v�̕Ћ��ɂ́A200�`300�����炢�̌Ö{����ׂ����I�������āA���̔�����́A�����̂��߂Ɋ�t����邱�ƂɂȂ��Ă���B���������ݏI������v�N�̃g�j�[���A�����オ���āA���̏��I�̑O�łӂƈ���̖{�����グ���B���ꂪ��؍q��@������������R.W.
Johnson�́w���āx�ł������B�A���E�^�[�i�[�́A���́u���R�v�ɂ��Ƃ������قǁA�Ђǂ��������炵���B�킴�킴���̖{�̎ʐ^���B���đ����Ă����B�����āA���̋������A���̂悤�ɏ������B
�@�@--- for the one and only book that Tony picked up was called �gShoot-down�h
by R W Johnson which told the story of the last flight of KAL 007. We took
this as the first sign that Tomiko and Kiyonori were with us, telling me
that I was in the right place at the right time.
�@�v�N�̃g�j�[����\�҂ł��邪�A���͔ނɂ͉Ƒ��̂��Ƃ͉����b���Ă��Ȃ��B�������A���̂Ƃ��͉�������������Ă����̂�������Ȃ��B�A���E�^�[�i�[�ɂ��A�����̂��Ƃ͎�����͂قƂ�lj����b���Ă��Ȃ����A�ޏ��͗�E�ɂ��鎄�̍ȂⒷ�j�Ƃ́A���x����b�����Ă���̂ŁA���������ł͂Ȃ��A�x�q�ƌ��T�̂��Ƃ́A���ꂼ��̗e�e���琫�i�A�l�ƂȂ���܂߂āA�n�m���Ă���Ƃ����Ă悢���낤�B�v�Ȃ́A���̎��A�x�q�ƌ��T���A���̏�ɗ��Ă��邱�Ƃ��@�m���āA��x�ɋْ���s����������Ƃ����B�t
�@���ꂪ�ŏ��̋ɂ߂ċH�ȁu���R�v�ł���B��͂�A�u��Ձv�ƌĂ�ł����ł��낤�B���̃W�����\���̖{�͎��������Ă��邪�A���̈��p���ɂ������Ă���悤�ɁA���͔ނɂ�������̃A����^�[�i�[�ɂ��A�����̂��Ƃ͂قƂ�lj����b���Ă��Ȃ��B�ނ�ɐ���ς�^���Ȃ����߂Ɏ��́A�������܂߂����̐��ł̍Ȃ�q�̏��́A�ӎ��I�ɔނ�ɂ͒m�点�Ȃ��悤�ɂ��Ă����B
�@�₪�ăA����^�[�i�[���f�@���ɌĂ�āA���̕a�@�ł̍ŏ��̐f�@�����Ƃ��ɁA���́u��Ձv���N�������B���̏�ɗ��Ă����x�q�ƌ��T�̓A���̎�����肵�߂āA�ޏ����܂��A�Ԃ߂Ă���Ă����Ƃ����̂ł���B�A�������u���Ă���Ԃɖڂ���Ă������ɂ��A�x�q�ƌ��T�̑��݂͗�I�Ȍ��ƂȂ��Ĕޏ��ɕt���Y���Ă����B������\�͂������Ă����ޏ������炱���A���̂��Ƃ��킩�����̂ł��낤�B�ޏ��̎莆�ɂ́A���̎��̏��A����ɋ�̓I�ɂ����������Ă���B
�@�sWe were so elated unbelievably, all our nerves and tension simply fell
away, and after being called in for my treatment I felt their presence,
holding my hand, surrounding me with love and healing, reassuring and comforting
me. As I closed my eyes during the treatment their spiritual light was
blinking.
�@Whoever donated the book was without knowing it, being inspired by spirit
to leave it at the Radiotherapy Department, this was done in advance showing
that spirit knew before we did that we were going to be there on that day
5th of August, 2008. We give thanks to spirit for their loving intervention
into our lives every day.
�@��E�ł́A���ׂĂ����ʂ��ŁA8��5���ɃA�������̕��ː����a�@�ɗ��邱�Ƃ��A�A��������ɒm���Ă����A�Ƃ����̂ł��邪�A����͂����炭�A���̒ʂ�ł��낤�B�����A�A���́A8��5���ɂ��̕a�@�ŁA�ŏ��̏W���������ː����Â��邱�ƂɂȂ�Ǝv���Ă����B�������A����́A�����ł͂Ȃ������B���̓��̐f�@�́A�E�̔x����̑傫����ʒu�����߂Ċm���߁A���x�̕��ː��𐳊m�ɂ���ɏƎ˂��邽�߂̗\���I�Ȑf�@�ł������炵���B�菇�����Ɛ����Ɋւ��̂ŁA���̗\���I���u�ɂ́A���̌�̐f�@���܂߂ĉ��T�Ԃ����������B�����āA����ƁA�ŏ��̕��ː����Ǝ˂���������܂����B�����9��1���ł������B������A��؍q��@�����̋N���������Ɠ������ł���B
�@2008�N9��1��---�B���̓��ɂ́A���́A�k�C���E�t���́u�F��̓��v�̑O�ōs�Ȃ�ꂽ������25���N�̈ԗ�ՂɎQ�����Ă����B�����̈Ⴂ�͂��邪�A����9��1���ɁA�A���E�^�[�i�[�́A�����̃��X�N�������ĂȂ��Ƃ͂����Ȃ��ŏ��̋��͂ȕ��ː����Â��J�n���Ă����̂ł���B�ʂ̎莆�ŁA�ޏ��́A���́u���R�v�̈�v���A�����`���Ă����B
�@So when you our dear friend was attending that very special�@25 year ceremony,
the memorial service at Wakkanai, I was having my very first Radiotherapy
session. I knew your wife Tomiko and son Kiyonori were administering their
healing to me without a doubt! I thank them with all my heart!!!
�@���̓����A�x�q�ƌ��T�́A���ː����Î��ɉ������A���E�^�[�i�[�̂��ɂ��āA�����̎�������L�ׂĂ����Ƃ����̂ł���B�s�v�c�Ƃ����Εs�v�c�ł��邪�A�ޏ��ɂ͂��ꂪ�킩��̂ł��낤�B�A���E�^�[�i�[�́A������A���̐��Ő��������Ă��閳�m�Ŋ���Ȏ����~���o���̂ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă��ꂽ�B�x�q�ƌ��T���A���̔ޏ��ɂ́A���Ɠ��l�ɁA���͎��ȏ�ɁA�[�����`�������Ă���͂��ł���B�ނ�͔ނ�Ȃ�ɁA�����ł��A�ޏ��ւ̐��ӂ��������������̂�������Ȃ��B�t
�@�A����^�[�i�[�̔x���Â̎��ɁA���̂悤�ɂ��Ĕޏ����������Ă����x�q�ƌ��T���A���̌�4�N���o�āA�����g���咰����ƕ�������ᎂ̎�p���邱�ƂɂȂ����Ƃ��ɂ��A�I�n�A���̂��Ō�����Ă��Ă��ꂽ���Ƃ́A�������R�ł������낤�B�ŏ��̎�p�̑O���ɂ́A�V�̑��̉ēގq���A�u�����������A������ĂˁA�����悤���̂ڂ��v�ƁA�������̊G��`���ē͂��Ă��ꂽ���A������������A���̎q�ɂ����Ԃ点���̂��A�ނ�ł�������������Ȃ��B��N���́A�u���̗c��7�̎q��������̕Ћ��ŁA�ǂ̂悤�ɂ��āu���z�������v�Ƃ������z��a���������̂��A������ƕs�v�c�ȋC������v�Ə��������i[������Z�M]�u���̐��Ƃ��̐��̋��Ԃŗh�ꓮ�����̂��v2012.08.03�j�A���܂ł͎��͂��̂��Ƃ��悭�����ł���悤�ȋC�����Ă���B�����A���̓A����^�[�i�[�̂悤�ȗ�\�͂͂Ȃ��̂ŁA����������Ɋ������͂͂Ȃ������B���̓݊��Ȏ��ɑ��āA�x�����_�̃T�{�e�����A��N�����N���A�u�ُ�ȁv�炫�������邱�ƂŁA�ނ�̖����́u�����́v�������Ă���Ă������ƂɂȂ�̂ł��낤�B
�@�������āA��N�̓��̎�p�����т����́A���N��4����83�ɂȂ����B���낻���E�֊҂鏀�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����@�ɂȂ��Ă��邪�A���̎��́A�u���ꂩ��܂��܂��A��E�̕��͋C���I���݂����̗Ս݊�����������悤�ɂȂ�v��A�t�͂����B���́A����łӂƋC�������̂����A���Ă���I�ȁu�����̌��v��������ꂽ���Ƃ��������B���Ȃ�O�ɂȂ邪�A���̐��z�W�iNo.34�j�ɁA�u�Ŗ�̃o���g�C�ɂāv�Ƃ��������ڂ������Ƃ������i2003�N11��1���j�B���̍��A����73�ł������B
�@���̐��z�ł́A���́A�u����X��28���̗[���A���͖k���X�E�F�[�f���̃X�g�b�N�z��������A�t�B�������h�̃w���V���L�������O���ܐ�g���̃t�F���[�E�K�u���G�����ɏ���Ă��܂����B�Z�K�̊C���̌��̑����猩���Ă����o���g�C�́A�ܓV�ŘZ�����ɂ͐^���ÂɂȂ��āA�ǂ��܂ł��[���ł��Ђ낪���Ă��������ł��v�ƁA�����o���Ă���B�����āA���̖�A�܂�����Ȃ��u��Ձv�ɑ��������̂ł���B���̕����́A�����ł���B
�@�s�����̖Z�����s���ɔ����āA���͌ߌ�10���߂��ɂ͂����x�b�h�ɉ��ɂȂ��Ă��܂������A���傤�ǖ钆��12���Ɏ��͂ӂƖڂ��o�܂��A�D���̃J�[�e�����J���āA��̃o���g�C�ɖڂ������Ă݂܂����B���̎��ɕs�v�c�Ȍ��i����ɔ�э���ł����̂ł��B�D���牓���A�����炭�S���[�g������S���[�g�������ꂽ�C��ɁA���̂悤�Ɍ����镨�̂��Ԃ�����Ȃ���A�����ɁA�����č��E�ɁA�O�{�A�l�{�A�ܖ{�̐��ɂȂ��āA�f�������ł��܂����B�t
�@���́A���̖��̐^���Èł̊C���Ԃ�����Ȃ�����ł������̂��Ȃ�ł��������A�����Ԃ킩��Ȃ������B�O�̂��߂ɁA�R�Ȓ��ތ������ւ��₢���킹���肵�����A�钆�ɐԂ������Ĕ�Ԓ��Ȃǂ�����͂����Ȃ������B���̂܂��̎҂������A���̘b���Ă����Ď�荇���Ă���Ȃ������B�������A���N���o���Ă����߂��ꂸ�ɁA���́A�u���z�i79�j�v�ŁA���̖��ɂ��čĂю��グ�Ă����i�u�Ŗ�̃o���g�C�Ō����Ԃ���s���̂̐^���v�j�B2011�N8��1���̂��ƂŁA����81�ɂȂ��Ă����B���̂Ƃ��́A�������������������Ă���B
�@�s���́A80�N���鐶�U�ŁA��x�A�O�x�A��ՓI�ɖ����~��ꂽ��A�W�R�ƋP���ݕ��̎p�Ɍ����ꂽ�肵�����Ƃ��܂߂āA���Ȃ��炸���낢��ƋM�d�ȑ̌������Ă��܂����B���܂ł́A�����̑̌��͉��ł��������A�Ȃ��A���̂悤�ȑ̌��������̂����A���̂قƂ�ǑS���ɂ��Ď����Ȃ�ɗ������[�����邱�Ƃ��ł��܂��B�������A���̃o���g�C�ł̑̌��ɂ��ẮA���͂�����l���Ă��킩��܂���ł����B�ŋ߂ł́A���̑̌������́A���ɍŊ��܂ŁA�킩��Ȃ��܂܂��̐������邱�ƂɂȂ�̂��낤���A�ƍl�����肵�Ă��܂����B�t
�@�����āA���̂Ƃ�����͂�v���]���āA��\�҂�A�t�ɂ��̖��������o���Ă݂��̂ł���B���͉��Ƃ��m�肽����S��A�t���v������̂����A�������AA�t�ɂƂ��ẮA�ʂɓ��ł��s�v�c�ł��Ȃ������悤�ł���B���̎���A�t�́A�ґz��Ԃ̂Ȃ��ł�ǂ݂Ȃ��A���̂悤�ɓ����Ă��ꂽ�B
�@�s���Ȃ����o���g�C�Ō����̂́A�l�Ԃ̗�ł͂Ȃ��A�����������A���ɊC�n�̐����������̐����̋C�ł��B�܂��A���Ȃ��̐S������ł��āA���������z���A�B�ώ����Ă��Ă����̂ł��B�����ł͖��䖲���Ō����ɑΉ����Ă����̂ł����A���������������������Ă���ȏ�ɒB�ς��Đ��S���ɂȂ����̂ŁA�]�v���Ȃ��ɂ͖ڗ����Č������̂ł��B�n���͐����ɖ������ӂ�Ă��āA�����͌���P���Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ɍ������̂ł��B���Ȃ��͐����ɂ��āA�����ŋꂵ���̌����Ȃ��ĉ���܂����B���ʂɂ͓����������Ƃł����B���ꂪ���Ȃ��ɍ����ŗ^����ꂽ���蕨�ł��B�t
�@���ẮA���̎�����75����78���炢�Ɖ��x�������Ă����B�������̂���ł������A����܂ł̍u����ł��A�u�������͂��̍��Ɏ��ʂ��낤�v�ƌ��������Ƃ�����B�������A���͎��ȂȂ������B���v���A���̃o���g�C�ł̑̌��̂���ɂ́A���̈�̋������z���悤�Ƃ��Ă������ƂɂȂ�B�K�������������������Ƃ͎v���Ă��Ȃ����A���̂��̐��ł̎g���́A���̍��́A�܂��I����Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��낤���B
�@�����āA��N�̓x�����_�̃T�{�e����7����Ԃ��J�����Ă��钆�ŁA���͓��މ@���J��Ԃ��A�������тĂ����B�����ł��A��E���猩����Đ�������Ă����̂ł���BA�t�ɂ��A���̋���86�ΑO��ɂȂ�悤�����A���ɂƂ��Ă͂��܂�83�����łɏ\���ɒ����ł���B���x���܂��A���́u���v���z�������Ƃ͎v��Ȃ��B����ׂ��قǂ̂��Ƃ͌��Ă������A�����m��C�������������킹�Ă������ł���B1983�N�̎����ȗ��A���N��30�N�A���́A�ꂵ�ݔY�݁A�ߒV�ƜԚL�̂Ȃ��ŁA�������A���N���������āA�F���̐ۗ��Ƃł������ׂ����̂����Ȃ�Ɋw�сA�͂ݎ���Ă����B���Ƃ͂����A���̉F���̐ۗ��̈�[���A��l�ł������́A�u��鏀���v���ł��Ă�����X�ɁA�`���Ă����g�����ʂ����Ă��������Ɗ肤�����ł���B������܂ŁA���������뉸�₩�ɁA�����āA�F��Ɗ��ӂ̋C������Y�ꂸ�Ɂ\�\�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@�@������Ƃ������Ƃ͎E���Ƃ�������
�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (89)�\�@
(2013.05.01)
�@���̃C�M���X�ł̐e�����F�l�Ƀf�C�r�b�h������B�`�F���g�i���ɋ߂��Z�o����̂قƂ�ɐ�͂��肻���ȍL��ȕ~�n�ɁA���z���S�N���炢�o���Ă���傫�ȉƂ������āA�����ɉ�����̃N���X�e�B�[�i�Ɠ�l�ŏZ��ł���B�\���N�O�A�ŏ��ɂ��̉Ƃ�K�ꂽ���A�Z�Q���̉Ƃ̒������X�܂Ō����Ă��ꂽ���ƁA������̃N���X�e�B�[�i�́A����~�n�̈�p�ɂ���O�Z���[�g���l�����炢�̗r�̕��q��ֈē����Ă��ꂽ�B���̒��ɂ͗r���\�ꓪ�قǂ����B�������v�Ȃ͂����Ŗq�{�Ƃ��c��ł���킯�ł͂Ȃ��B
�@����l�̃f�C���B�c�g�͓����Z�\�˂��炢�ŁA�ԂŎO�\���قǂ̃`�F���g�i���ɂ���R���s���[�^�W�̉�Ђɋ߂�Ǘ��E�ł������B�r�������Ă���̂́A����Δނ�̎��v�����˂���ł������B������̃N���X�e�B�[�i�͌\�܁A�Z�˂��炢�ł������낤���A���Ă����Č��N���̂��̂̏���v�Ƃ����������ŁA�r�̐��b�͂����ς�ޏ��̖�ڂł������B���̔ޏ������̎��A�\�ꓪ�̂����O�����w�����A����ƁA����ƁA����́A�����j�E��֑����āA�H���ɂ���̂��ƁA���C�Ȃ��������̂ł���B���͈�u�ْ������B���̎��̑O�ŁA�w�����ꂽ����ȎO���̗r�����́A�����̉^�����m��ʂ��ɁA�̂�т�Ƒ���H��ł����B
�@���́A���̍��A�O�T�ԋ߂����f�C���B�c�g�ƃN���X�e�B�[�i�̉Ƃɑ؍݂��Ă����̂����A�N���X�e�B�[�i����O���̗r�����̂��Ƃ��Čܓ��قnjo�������A�Ȃ�ƁA�[�H�̃e�[�u���ɂ��̗r�̓��̈ꕔ�������E�X�e�[�L�ƂȂ��Č��ꂽ�̂ł���B�[���A�����̂悤�ɗ���̃p�e�B�I�Ńf�C���B�c�g�Ƃ��̓��̏o�����Ȃǂ�������ׂ肵�Ȃ���r�[��������ł���ƁA�₪�ăN���X�e�B�[�i�����S���ɃX�e�[�L�̎M���̂��ĉ^��ł����B�����������ȓ������H��̏�ɗ��ꂽ�B�u�����̓X�e�[�L���A���y�����ȁv�Ǝ��͎v�����B���̎��ɃN���X�e�B�[�i���A�u����̓����ŁA������Ȃ��Ɍ��������̗r�̓��ł���v�ƌ������̂ł���B
�@�Ǝ҂ɗ���œj�E���Ă�������r�́A�є���͂�����A�o���o���ɐؒf����Ė߂���A�Ⓚ�ɂɓ����Ă����B���̂����̈ꕔ���A���̓��̗[�H�ɂȂ����킯�ł���B�N���X�e�B�[�i�́A�o���o���ɂ��ꂽ���Ђł����Ă��A���̑傫����`�ȂǂŁA���������ǂ̗r�̂��̂����킩��Ƃ����B������ƁA�ɂ킩�ɁA���߂Č������̎O���̗r�̎p���ڂ̑O�ɕ�����ł����B���͏��ꎞ�Ԃ����ݑ����Ă����r�[���̐�������x�ɂ��߂�v���ŁA���������ƂȂ����B
�@�f�C���B�c�g�����������A�N���X�e�B�[�i���������D���ŁA�������邵�n�������Ă���B�r�������E���ꂽ�O�����܂߂āA��ɂ��ĉ������Ă����͎̂����ł���B�u�Ђ������v���������Ȃ��������A�����ł̂�т����čK���Ȉꐶ�������Ǝv����v�Ɣޏ��͌������B���͖ق��ĕ����Ă���B����Ȏ��ɁA����Ȃɉ������Ă����r���Ȃ��E���̂��A�Ɩ₤�̂͋��ł���B�����̓C�M���X�Ȃ̂��B�N���X�e�B�[�i�̂��Ƃ��A�q�{�������炭����L�̔��z�ŁA����͈�앶���̓`���������{�l�ɂ͂킩��ɂ����B
�@�C�M���X�l���܂߂ă��[���b�p�l�́A�×��A���y�I�Ȍ���������A�����̂��߂ɂ͉ƒ{�ɑ傫���ˑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����������`���Ɏx�����Ă���B�������A�����Ă������߂ɉƒ{�ɗ���Ƃ������Ƃ́A�����̓j�E�ɂ������Ƃ������Ƃł��������B���́A�ƒ{�����{�l�̂����Ƃ��g�߂ȓ����`�����ł��鋛��ނȂǂƈ���āA�����w�I�ɂ͐l�ԂƓ����M���ނł��邱�Ƃł���B�l�ԂƓ������A�E���ΐԂ�������ʂɗ���o��B���������ƒ{�̓j�E�Ɋ����Ƃ������Ƃ́A���[���b�p�l�̌��ɑ��銴�o���A�������������{�l�Ƃ͑傫���������ꂽ���̂ɂȂ炴������Ȃ��B
�@�������A���ẮA�ƒ{���E���Č��������茌�̓������������̂́A���̋Ǝ҂��Ƃ̎�l���������ł͂Ȃ��A��w��q�������������ł������B�܂�C�M���X�l���܂߂ă��[���b�p�l�́A�Ƒ�����݂ʼnƒ{�̎��̂⌌�����邱�ƂɊ���Ă���̂ł����āA���̓`���͌��݂ł��A���[���b�p�̉ƒ뗿���̒��Ɏc���Ă���Ƃ����Ă悢�B���Ƃ��A�C�M���X��t�����X�̊X�̓����̓X���ŁA���邢�̓X�[�p�[�}�[�P�b�g�̃K���X�P�[�X�̒��ɁA�r��̓������̂����ڂ��ނ��o���ɂ����܂܂ŕ��ׂ��Ă���̂��A��������ӂꂽ���i�Ȃ̂ł���B
�@���{�l�͂����A�u���Đl�͌��̓H��r�t�e�L��H�ׂȂ��瓮������̐��_������v�Ɣނ�̎c�������B�������ނ�́A���̓H��r�t�e�L���u�H�ׂȂ���v�ł͂Ȃ��A�u�H�ׂ邩��v��������̐��_������̂ł���B����́A��{�I�ɂ́A��앶���̓��{�l���A���Ă�H�ׂ邩�炨�Ă��ɂ���̂Ɠ������Ƃł���B�N���X�e�B�[�i���r��H�ׂ邩��A���̗r��厖�ɂ��Ĉ�Ă��B���̉������Ă����r���E���͎̂c���Ȃ̂ł͂Ȃ��B�����A�E�����߂̎v�����Ƃ��ẮA�ł��邾����ɂ�^���Ȃ��悤�ɁA�ꋓ�ɑ��̍����Ƃ߂Ă�邱�Ƃł���B�C�M���X�l�̖ڂ��猩��ƁA������A���{�l���������܂܂ŐH�ׂ�u�������v�Ȃǂ́A�t�ɁA�����ɑ���ɂ߂Ďc���Ȏd�ł��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@����ɂ��ẮA��q��w�̃s�[�^�[�~�����[�h���A���ď��������{������_���镶�̒��Ɏ��̂悤�Ȃ��̂�����B
�@�s���̂��ƂɊւ��ẮA��l�̃C�M���X�l�Ƃ��āA���{�l�̎c���ȐH�ו��ɂ��Ĉꌾ�R�c���Ă��������C������B�������������̂́A�O���l�ɑ��Ăł͂Ȃ����ɑ��ĈӐ}�I�ɉ����Ă���ꂵ�݂ɂ��Ăł���B���{�ɂ́A�h�g�̈��Łu�������v�Ƃ�������̂�����B���́u�������v�ɑ�������p��͂Ȃ��B�܂��A�l����H�ׂ�u�L���j�o���Y���v������ɋ߂��ł��낤���B
�@�������l���Ă݂�A���̃L���j�o���Y���ł��A�ؐl�͐l�Ԃ�H�ׂ�Ƃ��ɂ́A���Ȃ��Ƃ��ς���Ă����肷��̂ł����āA�������܂܂̐l�ԂŐH�ׂ邱�Ƃ͕��ʂ��Ȃ��B�Ƃ��낪���{�l�́A�܂��ɂ�������킢�����ȋ��ɑ��Ă���̂ł���B���̂܂܂ł���ǂ��납�A�����Ă܂������Ă���̂ɁA�h�g�̂悤�ɔ��������ĐH�ׂ�̂ł���B�t�@�i�w�C�M���X�Ɠ��{�x�j
�@�l�H���l��ł����l�Ԃ�H���Ƃ��ɂ́A�ς���Ă����肵�Đ��̂܂܂ł͐H�ׂȂ��̂ɁA���{�l���������܂ܐ荏�݁A�܂������Ă���̂��h�g�ɂ��ĐH�ׂ�͎̂c�����A�Ƃ����킯�ł��邪�A���̂悤�Ȍ������ɂ͂���Ȃ�̐����͂�����悤�Ɍ�����B�C�M���X�l�̍l����c���́A���{�l�̎c���Ƃ͈Ⴄ�̂ł���B
�@�h�g�Ƃ����̂́A�L�x�ŐV�N�ȋ��ƁA�H�����̐����ȓ��{�l�̔��ӎ������ݏo�������{�Ɠ��̒����@���Ǝv�����A�u�������v�Ƃ́A����A���̎h�g�̐V�N���Ɛ��������Ɍ��܂ŒNj����āA���ɂ������q�̑O�ɒ������̂ł��낤�B������A����ނ����炱���́u�������v�ł���B�M�������̓��ł��h�g�ɂł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�������A���́u�������v�͂��蓾�Ȃ��B��ʂɓ��{�l�́A����ނȂ�܂������A�M��������ڂ̑O�ŎE���悤�Ȃ��Ƃɑ��鋑�┽���́A�C�M���X�l�ȂǂƂ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�ɋ����̂����ʂ�����ł���B
�@�����Řb�������O�ɖ߂����B�N���X�e�B�[�i�̃����E�X�e�[�L���ڂ̑O�ɒu���ꂽ�̂ł������B���͏��������낢���B�������A���͂�͂肻�̃X�e�[�L��H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��B�H�ׂ��B�p���ŏ��߂ăG�X�J���S��H�ׂ����̂悤�ɁA������Ƃ������̐�ւ����K�v�ł������B�u���܂����H�v�ƕ����ꂽ����A�d���Ȃ��A�u���܂��v�Ɠ������B
�@���ꂩ���A�O���o�������A���H�ŐH���֍s���ƁA�N���X�e�B�[�i��������ƊO���猺�ւ����Ă݂�Ƃ����B�s���Ă݂�ƁA���ւ̃h�A�̏㕔���E�ɂ��Ă���Ԓ����艺���邽�߂̓S�̃A�[���ɁA��e����C�ƎR������H�A��̂Ƃ�����Ŕ����ĂԂ牺�����Ă���B�߂��̔_�Ƃ̐l�����ł��Ƃ߂����̂������������Ă��ꂽ�̂��Ƃ����B�O���̖�͂��܂��܁A�����v�Ȃ��`�F���g�i���̓��{�����X�֘A��o���ė���ł������̂ŁA�����֒u���Ă������̂ł���B�A�肪�x�������̂ŁA���������C�����Ȃ������B���A�d�b���������Ă��āA�ނ�����߂Ēm�����炵���B
�@��e�ƎR���Ƃ͂����A���̂悤�Ȏp������̂͋C�����̂������̂ł͂Ȃ��B�V��������Ŕ����ĂԂ牺�����Ă���̂�����̂́A���ɂ����܂��R�͂Ȃ����A����������̈Ⴂ�Ȃ̂ł��낤�B���{�ł���Ȃ��Ƃ���������A���������ǂ���ł͂Ȃ��B�����炭�C���������Ă��܂��ɂ������Ȃ��B��e�̖є������A�R���̖т��ނ������肷�邾���ł����┽��������B�������A�N���X�e�B�[�i�͊��ł����B���ɎR���͂��܂��̂��ƌ����āA�������ł������B
�@�����̑n���L�i9�F2-3�j�ɂ́A�u�n�̂��ׂĂ̏b�A��̂��ׂĂ̒��A�n�ɔ������ׂĂ̂��́A�C�̂��ׂĂ̋��͋��ꂨ�̂̂��āA���Ȃ������̎x�z�ɕ����A���ׂĐ����ē������̂͂��Ȃ����̐H���ƂȂ�ł��낤�v�Ƃ������Ƃ�����B�L���X�g���ł́A�_�����̂悤�ɓ������E���ĐH�ׂ邱�Ƃ������Ă���ƍl����B������A���[���b�p�ł́A�L���X�g���k�����͈��S���ē������E���A�����H�ׂĂ���̂ł���B�t�ɁA�������E���ĐH�ׂ邱�Ƃ��c�����Ƃ��ĔF�߂��Ȃ������Ȃ�A�C�M���X�l���܂߂ă��[���b�p�l�͐����Ă������Ƃ��ł��Ȃ������B
�@���́u�������E���Đ�����v�����l���́A�O���[�o�����̉e�����āA����̓��{�ł����Ȃ�[���Z�����Ă��Ă���悤�ł���B��O�̓��{�ł́A�������`�����Ƃ��ẮA�j���g�����炢�Ȃ�܂������A������u�l���v�̓����͂��܂�H�ׂȂ������B�M��������H�ׂȂ��Ă��A���i�̈�������ނ��L�x�ɂ���������ł���B���y�I�����ɂ��b�܂�āA�_�Ɛ��Y�������{�ł͊i�i�ɍ����B����Ă̍��ނ�H�ׁA��ނ̑������V�N�ȋ���ނŁA���[���b�p�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ����炢�A�����̈ێ����e�Ղł������B���y�̎O���̓R�n�ł���Ȃ���A�l�����x���ɂ߂č����̂́A���̒[�I�Ȃ�����ł���B
�@�@�������A���̓��{�l�̐H�����́A���A���{���L���ɂȂ�ɂ�đ傫���ς���Ă����B����A�H�����̉��ĉ����i��ł����̂ł���B�����A���i�������āA����A�r�Ȃǂ́A���܂ł͌����č����ȐH�i�ł͂Ȃ��Ȃ����B�ނ���A�]���̓��{�̋���ނ����P���I�ɂ���ɓ���₷���Ȃ��Ă���B���{�́u�ĐH�����v���e�𔖂߂āA���Ắu���H�����v�ɋ߂Â�����悤�ł���B�������A���{�ł́A�u�E���Đ����Ă���v���o�͔����B�C�M���X�̃N���X�e�B�[�i�����̏ꍇ�́A�����ł͎�������Ă��Ȃ��܂ł��A���́u�E���Đ����Ă���v�Ƃ������o�͐@������Ȃ��ł��낤�B�������A���{�ł́A���H���Ȃ���������̂��̂��̂��Ƃ܂ł͎v�����y�Ȃ��B
�@���Ƃ��ƁA�����̓���H�ׂ�Ƃ����̂́A�R����삯�����āA���̓����������ŁA�����͒��ԂƋ��͂��āA�d���߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������͂��ł���B�d���߂������́A���ɂ܂݂�Ȃ���A��������������ʼn�̂��ĐH���ɂ���B�������d���߂��Ȃ���A�����������Q���邾���ł���B�ۂ����ł��u�����邽�߂ɎE���v�Ƃ������o�����������Ă����ɂ������Ȃ��B�������A��앶���ł́A���ɂ��̕K�v���Ȃ������B������A�����ԁA�č��Ɩ�Ƌ���ނɊ���e����ł����H�����Ɍォ����H�������Ă��Ă��A����͋���ނƓ����悤�ɁA�X�[�p�[�Ȃǂ֍s���āA���ꂢ�ɐ蕪�����ĕ���ꂽ���Ђ��������o���Ĕ������߂邾���ł���B���ꂪ�����̎��̂ł���Ƃ������o�͂Ȃ��B�u���́v�ł͋C����������A�����v���������Ȃ��ł��낤�B
�@���{�ɂ͕����̎E�������`���I�Ɏc���Ă��āA�������E�����Ƃɂ��ẮA�������۔���������B�������A�������́A�����𑼐l�ɎE�����āA���̎��̂�H�ׂĂ���̂ł���B�����ŎE���Ă��Ȃ�����߂��Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��B�ނ���A���̂悤�Ȗ����o�́A�E����铮��������݂�A�����ŎE���Ă���҂����������čߐ[���Ƃ����邩������Ȃ��B����ɁA������O�ł��邪�A����ނ��������ł���B���푽�l�̋������낢��ȊL�ނ��A���ꂼ��ɂ݂�Ȑ����������Ă���B�������E���̂͂����Ȃ����A����ނȂ�E���Ă������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��͂��ł���B
�@���߂čl���Ă݂�ƁA����A�l����܂ł��Ȃ��A�������́A�E���Ɩ��W�ł͐����Ă����Ȃ��B���ɁA�ꕔ�̑m���������������Ă����悤�ɁA�����⋛��ނ�����čؐH��`�ɓO�����Ƃ��Ă��A���́A���ނ��Ȃǂ̐A�����܂��A�݂Ȑ����ł���B���ꂼ��ɂ��̂��������Đ��܂�A�������Ă����B������H�ׂ邱�Ƃɂ���āA�������͎��������̖����q���ł���B�H�ׂȂ���Ύ������͎��ʁB�܂�A�������́A�������A�����E�����Ƃɂ���Ă̂݁A������������������Ă���B������Ƃ������Ƃ́A�E���Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�@�������������Ɉӎ����������������Ă����A�����́A���{���܂߂āA���E�̕x�T���Ŗ��ɂ���Ă����ʂ̐H���̐H�c����������A�����ł����������邫�������ɂȂ邩������Ȃ��B������D���Ă����āA���̎����ɂ����C�������A�H���C�Ŏc������A�̂Ă��肷��Ƃ������Ƃ́A��͂肩�Ȃ�ߐ[�����Ƃł���B�E����鑤���炷��A�H�ׂ����Ȃ��Ŏ̂Ă邭�炢�Ȃ�n�߂���E���Ȃ��łق����A�Ƃ��������Ƃ���ł��낤�B
�@��������������A�����E���Ă���̂́A�H���邽�߂����ł͂Ȃ��B�Ƃ�Ƌ�⎆�Ȃǂ́A�̎��̂ł��邵�A�v�C���є�Ȃǂ����Ƃ͓����̐g�̂̈ꕔ�ł���B���Ă���m����V���c�ނȂǂ��A�قƂ�Ǔ�����A���̂��̂���D�����Ƃɂ���č���Ă���B�u�l�Ԃ́A�ӎ��I�������͒��ړI�ȎE���ɂ�����炸�Ƃ��A���̐����̋]�����Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ������v�Ȃ̂ł���B�i�����G�Y�w���w���p�Ɍ��镧���̐����ρx�jNHK�o�ŁA2013�j
�@���ꂾ���ɁA�s�E��������낤�Ƃ��镧���k�́A�^���ł������قǁA���́u�E���Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��v�����ɐ[���Y�ݔ����Ă����B�������̃`�x�b�g�ł́A�l�Ԃ����炻�̎��̂ɗ^����u�����v�̏K�����L���s���Ă��邪�A����́A�����Ă��邤���͑��̐������]���ɂ��Ă����̂�����A���点�߂Đg�̂��炢�͒��Ɏ{�������Ƃ�������́u�z�{�s�v�̐��_�ł���B���������I�ɖ��J�̏K���Ƃ��đނ�����́A�����ɂ��[���ȋF��̎p�����邱�Ƃ��A�l���Ă݂�ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@�@�u�ʎ�S�o�v�̗l�X�ȉ��߂��߂�����
�@�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (88)�\�@
(2013.03.01)
�@�V���[���[�E�}�N���[���w�A�E�g�E�I���E�A�E�����x�̓��{��łɁA�u���{�̓ǎ҂̊F�l�ցv�Ƒ肵�������ipp.2-3�j�����邪�A���̂Ȃ��ŁA���҂̃V���[���[�E�}�N���[�������̂悤�ɏ����Ă���Ƃ��낪����B
�@���܂łɎ����w�ł��d�v�Ȃ��Ƃ́A���̐��Ɍ����Ȃǂق�Ƃ��͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�������������Ƃ��Č��Ă�����̂͂��ׂāA��������������ǂ��Ƃ邩�Ƃ����F���̖�肾�Ƃ킩�����̂ł��B�l�����ǂ̂悤�ɔF�����Ă��邩�A���̔F���̂��������������ׂĂȂ̂ł��B����������A�������̐l���͎������̌��Ă��鐢�E���̂��̂ɂ���Č��܂�̂ł͂Ȃ��A�������ǂ̂悤�ɐ��E�����Ă��邩�ɂ���Č��܂�̂ł��B
�@�����炱���A���̐����ǂ��F�����Ă��邩����ŁA�O�����Ŏ��葽���l���́A�������l��l�ЂƂ�̐������ɂ������Ă���Ɣޏ��͂����̂ł��邪�A���̌������͂킩��Ղ��A�����͂�����B���Ƃ��A�����u���̐��v�ł����Ă��A���̑��������͐l�ɂ���Č����ē����ł͂Ȃ��B��������čK�������ς��Ɗ�����l�����Ă��A���̓������̂Ȃ��ŁA�S�߂ŕs�K�̂ǂ��ł���ƒQ���l�����邩������Ȃ��B�܂�A�K�������ς��́u�����v������̂ł͂Ȃ����A�S�߂ŕs�K�ȁu�����v������̂ł��Ȃ��B�������ǂ̂悤�ɔF�����邩�ɂ���āA�K�A�s�K�͕������̂ł���B
�@���̌����̑��������A�����ЂƂʂ̗�ōl���Ă݂悤�B���́A�p��Ɠ��{��Ƃ̈Ⴂ���������ꍇ�ɁA�u�p��Ō���v���E�Ɓu���{��Ō���v���E�͓����ł͂Ȃ��A�ƌ������肷��B���̂����ĔF������͖̂ڂ̍�p�ł��邩��A���ʁA�������́u�ڂŌ���v�ƍl���邪�A�ڂ͂���J�����ł��������Y����ɂ����Ȃ��B�����Y�ɉf�����f����F�����邽�߂ɂ́A�u����͎R���v�Ƃ����悤�ɁA���̉f�����������͂܂����{��ŕ��͉�͂��������ŁA������]�֑���˂Ȃ�Ȃ��B���̌���͂���t�B�����ŁA��]���ʐ^�ł���B
�@�p��Ɠ��{��Ƃ́A����w�I�ɂ͍\����̑傫�ȍ������邩��A�u����͎R���v�ƁuThat is a mountain.�v�́A�����ɂ����Γ����ł͂Ȃ��B�s�芥���̗L�������ł͂Ȃ��u�R�v���̂��̂��umountain�v�Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�B�܂��A�u��v�́uriver�v�Ƃ܂���������ł͂Ȃ����A�u���v���uwater�v�Ƃ͈Ӗ����e����v���Ȃ��B�u�^���v�Ȃǂ��A���{�ł͍r�ꋶ���ЊQ�̃C���[�W���������A�ufloods�v�ɂȂ�ƁA�C�M���X�ł͂����Ή��₩�ȏt�̕������ɂȂ�B�������́A�����Y�Ɏʂ����f�������ꂼ�������t�B�����ɏĂ��t���āA���������ʐ^�����ꂼ��́u�����v�Ƃ��ĔF�����邪�A���́u�����v�͏�ɁA����ɂ���ĈقȂ�A�����͐l�ɂ���Ă��قȂ����肵�āA�q�ϓI�A���ՓI�Ȏ�����\�킵�Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł���B�i�ْ��w�p�ꋳ��̂Ȃ��̔�r�����_�x�Q�Ɓj
�@�����̂��Ƃ́A������ƍl����킩�邱�ƂŁA����ȏ�ڐ�����͖̂{�e�̎�|�ł͂Ȃ��B�q�ϓI�ȁu�����v�͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂��̂悤�ȗ�ɂ���Ă��e�Ղɗ����ł��邪�A�������A�ʎ�S�o�ɂȂ�Ƃ��ꂾ���ł͂��܂Ȃ��B�ʎ�S�o�ł́A���̂��݂�Ώۂ����̂̂Ȃ��u��v�ł���Ƃ��Ă���݂̂Ȃ炸�A���Ă����̂̔F���⊴�o�����ׂāu��v�ł���Ƃ����̂ł���B����͂��̎�����u�Ȃ��v�Ƃ����̂�����A����͂Ȃ��Ȃ��킩��ɂ����B�u�����v�̑�����������Ɉ�i�Ɛ[�������Ă����˂Ȃ炸�A�������̏펯�����[�����@�͂��K�v�ɂȂ��Ă���B
�@�ʎ�S�o�́A�u�ώ��ݕ�F�s�[�ʎ�g���������ƌ����]�F��x��؋��v�Ŏn�܂��Ă���B���̊ώ��ݕ�F�Ƃ����̂́A�ω���F�̂��Ƃł���B�ω���F���A�[�ʎ�g�������s�����܂������A���]�͊F��Ȃ�Əƌ����āA��̋���x�����܂���v�ƁA�����ł͈ꉞ��ނ��Ƃ͂ł���B�u�ω��l���[�����̒q�d�ɂ���ĕ��̍��֍s�����Ƃ�^���ɏC�s���Ă������ɁA���ׂĂ͖���ŏ�Ɉڂ�ς���Ă������Ƃ����ɂ߂��āA���̂ɂ�����邱�Ƃ��琶����ꂵ�݂�Г�����ׂď��z���邱�Ƃ��ł����v�Ƃ�������ׂ����̈Ӗ����Ȃ�Ƃ��͂ނ��Ƃ͂ł���B���������́A�u���]�F��v�ł���B�u���]�v�Ƃ́A�l�Ԃ̓��̂Ɛ��_���܂̏W�܂�ɕ����Ď��������̂ŁA�l�Ԃ̓��̂��܂߂āA�����p�A�\�ۍ�p�A�ӎv��p�A�F����p�Ȃǂ��Ӗ�����Ƃ����B����炪���ׂāu��v���Ƃ����̂ł���B
�@����ł́A�u��v�Ƃ͉����B����͕����̐^����\�킷���t�ŁA���ꂪ�킩��Ε����̋��`�̑S�����𖾂��ꂽ�悤�Ȃ��́A�ȂǂƂ����邾�������āA����߂ē���ł���B�ꌹ���猾���u��v��
[sunya �V���[�j��] ���炫�Ă��āA�Œ�I���̂̂Ȃ����ƁA���̐��������Ă��邱�ƁA����ł��邱�ƂȂǂ��Ӗ����Ă���Ƃ����B�ߑ㐔�w�����W�����̂́A�C���h�l�ɂ��[���̔��������������炾�Ƃ����邪�A���ꂪ�u�V���[�j���v�ł���B�������A�ʎ�S�o�ł����u��v�͂������u�[���v�ł͂Ȃ��B�����Ȃ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�@�����ɂ���������Ȃ��Ƃ������Ƃł���炵���B��������ƁA�u���]�F��v�Ƃ́A�����̊����p�A�\�ۍ�p�A�ӎv��p�A�F����p�Ȃǂ̂��ׂĂ��ڂ낢�ς���Ă������̂����炱������Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B�������A���̒��x�̗����ł́A�������́A�ƂĂ��u�x��؋��v�Ƃ͂����Ȃ��B
�@������݂ɁA���̕��������낢��Ȋw�ҁA�����ҁA����҂��ǂ̂悤�ɖĂ��邩���݂Ă݂悤�B�������E�I���`�w�ʎ�S�o�E�����ʎ�o�x�i��g�����j�ł́A�u���݂�����̂ɂ͌܂̍\���v�f������Ƃ݂���߂��B�������A����i�����҂ɂ��Đ��Ȃ�ω��j�́A�����̍\���v�f���A���̖{�����炢���ƁA���̂̂Ȃ����̂ł���v�ƌ��������̂ł������A�ƂȂ��Ă���B���Џ@�v�w������ �ʎ�S�o�x�i�����ܐV���j�ł́A�u�������̑̂�_��p�͑S�Ď������������A����͂���Ή��N�ɂ����閳��Ȃ錻�ۂȂ̂��v�ƌ��ɂ߂��āA�Ɩ�Ă���B����j�q���́u�S��ʎ�S�o�v�Ɩ��������w�����Ď��ʒq�d�x�i���w���j�ł́A�i���Ȃ�ω��́j�u�F���ɑ��݂�����̂ɂ͌܂̗v�f�����邱�ƂɋC�Â��܂����B�����̍\���v�f�͎��̂������Ȃ��̂ł��v�Ƃ���B���ׂĂ�����ŕς���Ă������̂ł���A���N�ɂ���ċN�����Ă��邾���̌��ۂ��A�u���̂̂Ȃ��v�Ƃ��u�����������Ȃ��v�Ƃ��Ƃ����������ŕ\�����Ă���悤�ł���B
�@�����ɖڂ̑O�Ɍ����āu����v���̂�ے肵�āA�ʎ�S�o�ł͂���͎��́u��v�ł�����̂́u�Ȃ��v�̂��Ƌ�����B����Ȃ�A�u����v�Ɗm�F���Ă��鍪���ɂȂ��Ă��鎄�����̌܊���o����ے肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u����v�̂ɉ��́u�Ȃ��v�̂��B���̎��̂��u�Ȃ��v�Ƃ����̂́A�����ɂ���������u�Ȃ��v�̌��ӂ��ƒm���Ă��A����͕��}�Ȏ������̎v�l���邱�Ƃŗ�������̂͂���߂ē���B������ł��낤�A�ʎ�S�o�ł́A���̂��ƁA�u�F�s�ً�@��s�ِF�v�Ɓu��v�̐����������B�킴�킴�u�F������v�u���F�v�u��z�s�������@���v�Ƃ��������āA����ɁA����Ŋ܂߂�悤�ɁA�u�ɗ��q�@�����@������v�Ɓu��v�̉���������Ă����̂ł���B
�@���̕����́A�ʎ�S�o�݂̂Ȃ炸�A�������̂��̂̊j�S�Ƃ����Ă��邾���ɁA���낢��ȉ����������A���܂��܂ɉ��߂���Ă���B�����̌��㕶����������݂Ă݂�ƁA���̂悤�ɂȂ��Ă���B
�@�����́u��v�ɂق��Ȃ炸�A�u��v�������ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B���������Ȃ킿�u��v�ł���A�u��v�����Ȃ킿�����ł���܂��B��������A�m������A�ӗ~������A���f�����肷�鐸�_�̂͂��炫���A������������u��v�Ȃ̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�{�����E�����ǕF�w�F������̌����x�i���{�o�ϐV���Ёj
�@���̐��ɂ����ẮA�����I���ۂɂ͎��̂��Ȃ��̂ł���A���̂��Ȃ����炱���A�����I���ۂł��肤��̂ł���B
�@���̂��Ȃ��Ƃ����Ă��A����͕����I���ۂ𗣂�Ă͂��Ȃ��B�܂��A�����I���ۂ́A���̂��Ȃ����Ƃ𗣂�ĕ����I���ۂł���̂ł͂Ȃ��B
�@���̂悤�ɂ��āA���悻�����I���ۂƂ������̂́A���ׂāA���̂��Ȃ����Ƃł���B���悻���̂��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����I���ۂȂ̂ł���B
�@����Ɠ����悤�ɁA���o���A�\�ۂ��A�ӎv���A�m�����A���ׂĎ��̂��Ȃ��̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������E�I���`�w�ʎ�S�o�E�����ʎ�o�x�i��g���Ɂj
�@���悻�����I���ۂƂ������̂́A���ׂĎ����������Ȃ��̂ł���A�t�Ɏ������Ȃ����N���邩�炱�������I���ۂ����藧�B�i�l�Ԃ̊�Ɋώ@�ł��镨���I���ۂł���Ƃ����̂́A�����������ƂȂ̂ł���B�j
�@�����悤�ɁA���o���\�ۍ�p���A�ӎu���A�ӎ��E���ӎ����܂߂��ǂ�ȔF�����C���ꂶ�����Ɏ����͂Ȃ��A���N�̂����ɖ���ɐ��ł��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Џ@�v�w������ �ʎ�S�o�x�i�����ܐV���j
�@�����̍\���v�f�i�܂̗v�f�j�͎��̂������Ȃ��̂ł�
�@�`�̂�����̂͌`���Ȃ�
�@�`�̂Ȃ����̂͌`������̂ł�
�@���o�A�\�ہA�ӎv�A�m����
�@���ׂĎ��̂��Ȃ��̂ł�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����j�q�w�����Ď��ʒq�d�x�i���w�فj
�@���́w�����Ď��ʒq�d�x�ɂ́A���{���w�����҂ō�Ƃł����郊�[�r�p�Y���̉p������Ă���B�p��ł��̔ʎ�S�o���ǂ̒��x�ɂ܂ŕ\���ł��邩���݂Ă݂邽�߂ɁA���̕����̉p������Ɍf���Ă��������B���[�r���͂����Ă���B
�@�@Form is none other than emptiness, emptiness is none other than form.
�@ Form�\�@it is, in fact, emptiness.
�@ Emptiness�\�@it is, in fact, form.
�@ To sense, to imagine, to will, to conceive �\ they too are all like
this.
�p��̓T���X�N���b�g�Ɠ����n���ꂾ����A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă��A�����ł͉��̖��ɂ������Ȃ��B�u��v���uemptiness�v�Ƃ����Ă��قƂ�Ǘ����ł��������Ȃ��B��͂�A���{��ɂ���A�p��ɂ���A�|��͂̌��E�݂̂Ȃ炸�A����̌��E������������������Ȃ��̂ł���B����̌��E�������ł��₤���߂ɂ́A���낢��Ɖ���Ɋ��ʂ��Ă����ق��͂Ȃ��ł��낤�B�����G�Y�w���w�E���p�Ɍ��镧���̐����ρx�iNHK���W�I�e�L�X�g�A2013�j�̂Ȃ��ɂ́u�ʎ�S�o�̓N�w�Ə@���v�Ƃ�����͂����邪�A�����ł́u��v�ɂ��āA���̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B����͂����炩�킩��Ղ��B
�@��Ƃ́A������A����̊��o�ɂ���đ�����ꂽ�������E���A��ΓI�łȂ����Ƃ������B���䂪�l�̊��o�ƁA���̐ςݏd�˂ł���L���ɂ���Č`�����ꂽ���̂Ƃ���A���̍����͂���ӂ�ł���B�L���Ȃǂ͔]�̏�Q�ŊȒP�Ɏ����Ă��܂��B
�@�w�ʎ�S�o�x�͂����B�u�F�͂��Ȃ킿�����Ȃ�i�F������j�v�ƁB�킽���̌��Ă��鐢�E�͋�ł���B��̑̓��ɂ���āA�����ւ̎�����f����A���̋��|��ꂩ��E����B���ꂪ�w�ʎ�S�o�x�̋~�ς̋����ł���B
�@����ɁA�w�ʎ�S�o�x�́u��͂��Ȃ킿����F�Ȃ�i���F�j�v�Ƒ�����B���Ȃ⌻���͋�ł��邪�A��ł��邩�炱�������ł���Ɛ����Ă���B���E�͋�ł���Ƃ��Ă��A�����͂��̋�̒��ɐ�����ȊO�ɂȂ��B�^����ꂽ���E�̒��Ŏ������̂āA����������t������B�������l����ϋɓI�ɑ����鏊�Ȃł���B�ipp.36-37�j
�@�������A�����܂ł݂Ă��Ă��A�܂��u��v�̈Ӗ��͌����s������Ă���Ƃ͂����Ȃ��ł��낤�B�w�ʎ�S�o�x�ł́A����Ɂu�s���s�Ł@�s�C�s��@�s���s��������v�Ɓu��v�̐����������B���̕ӂ܂ł���ƁA���̂悤�ɁA�O����Ɠ��{��̖|����o�����Ă����҂ɂƂ��ẮA�|��̉\���Ƃ����ꂻ�̂��̂̌��E�Ȃǂɂ��Ă��l�����܂��ꂽ�肷��B���T���������Y�⌺���O�����̂����ꂽ�|��ɂ����̂ł��邱�Ƃ͂킩�邪�A�|��ɂ͌덷�������̂ł���B�܂������������̓��Ď��ŕ\�킳����Ȃ���������Ȃǂ�����ł��낤�B�����瑽���̌����҂́A�����ɋ߂��T���X�N���b�g��ɑk���Đ^�ӂɔ��낤�Ƃ���B
�@�������A�Ñ�C���h�̍��x�ɒ��ۓI�Ȏv�z�������Ő��m�Ɉڂ����Ƃ͂ł��Ȃ����A����ɂ������{��ɒ����A���̌덷�͈�i�Ɗg�傷��B����́A���̋t���l���Ă݂Ă��킩�邱�Ƃł���B�Ⴆ�A���{��ł����u��сv�u���сv�������̓��Ď��ŕ\�킹�A�ǂꂭ�炢���ӂ��`��邾�낤���B����ɂ��̓��Ď��̊������T���X�N���b�g��ɖ��Ƃ��Ă��A�u��сv�u���сv�̊܈ӂ��ǂ��܂ŗ����ł���悤�ɂȂ邩�A�傢�ɋ^��ł���ƌ��킴������Ȃ��B���������u�G�O�v�̂悤�Ȃ��̂�����Ă���ƁA�w�ʎ�S�o�x�́u�s���s�Ł@�s�C�s��@�s���s��������v�ȉ��̈Ӗ���H���Ă����̂ɂ��A�����Η����~�܂��Ă��܂����肷��B
�@���Ƃ��A�u���������������s�T�����V�������V���s�v�ł���B���̂Ȃ��́u�������s�v��u���V���s�v�͂ǂ̂悤�ɑ����Ă��������̂��낤���B�V�䖞�w���R��ʎ�S�o�x�ł́A�����̂Ƃ���́A�u���҂ƌ��ҁA��҂ƘV�l�A����ȑ��ΓI�Ȃ��̂��A�Ȃ��A�ƍl���Ă悢�̂���v�ƂȂ��Ă��邪�A����͂�����ƒZ���ɉ߂���悤�ȋC������B����j�q���̂́A������͂킩��Ղ��B�w�����Ď��ʒq�d�x�ł́A���̂悤�ɖ�Ă���B
�@�^���ɑ��鐳�����m�b���Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ȃ�
�@���ꂪ�s����Ƃ������Ƃ�����܂���
�@�������Ȃ��@�������Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ�����܂���
�@����́u��v�̐S�����l��
�@������������
�@�������Ȃ��Ƃ��Ƃ��Ȃ��S�ł����邩��ł�
�@�������Ă��Ɂ@�V�����Ȃ��@�����Ȃ�
�@�V���Ǝ����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ƃ����S�Ɏ���̂ł�
�@�V���Ǝ������ۂɂ����Ă�
�@���������邱�Ƃ��Ȃ��̂ł�
�@�܂��ߑR�Ƃ��Ȃ��Ƃ�������邪�A�����̂Ƃ���́A�����G�F�w�}���ʎ�S�o�x�i�u�k�ЁA1983�j�̉���ɗ��邱�Ƃɂ��悤�B�����ɂ́A�����q�ׂ��Ă���B�ipp.46-47�j
�@�u�����v���Ȃ��Ƃ����̂́A�l�͐��܂�Ȃ���ɒm�b�������Ă���̂��Ƃ������ƂŁA�l�ԉߐM�ɂȂ���܂��B
�@�܂��A�u�����v���s���邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂ł́A���ɐl�Ԃ͖��m����ʂ��o���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��āA�~�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�@�����ł́A�u�����v�Ɓu�������s���邱�Ɓv�̗�����ے肵�āA�l�Ԃ́A���Ɩ����̒��Ԃɂ����ēw�͂�����̂ŁA�u���Ƃ������v�ɂ�������Ă��Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@�u�T���v�́A�u�����v�Ɓu�V���v�̊Ԃ͗������A����������l�������Ƃ������Ƃł��B
�@�l�Ԃ́u�����v�ɂ͂��܂��āu�V���v�ňꐶ����������킯�ł����A�u�V���v�Ƃ����Ă��A���̊Ⴉ�猩��ΌŒ肵�������ł͂Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�u�V���v���Ȃ��ƂȂ�����A���̐��ɂ��킢���̂͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ƃ����Ă���̂ł��B
�@�܂��A�u�V���v����ʂ��o�����Ƃ��ł��Ȃ�����Ƃ����āA�Ⴂ�Ƃ�����u�V���v�����߂Ă��邾���ł͎Ⴓ�������Ƃ��ł��܂���B
�@�Ⴂ�Ƃ��ɂ́A�Ⴓ�����Ȃ���A�Ȃ��u�V���v��\�����Đ�����Ȃ�A�Ⴓ�Ɋ��ӂ��Ȃ���V�l�ɂ��������̂�����悢���������ł���ł��傤�B
�@����͌����Ĕے�̂��߂̔ے�łȂ��A��d�ے���J��Ԃ����Ƃɂ���ēO��I�Ȑl���̍m��I�ȑԓx�������Ă���ƍl����ׂ����Ǝv���܂��B
�@���̂悤�ɁA�������͗^����ꂽ������o�����āA���t�̈Ӗ��ׂāA������ǂ肵�������Ŕʎ�S�o��������̂ł��邪�A���̖{���𗝉�����̂ɂ͂��̂悤�Ȍ��t�ɗ���A�v���[�`����Q�ɂȂ邱�Ƃ�����̂�������Ȃ��B���Ƃ��Ə@���I�ȋ����Ƃ����̂́A�܂�܂���u������̂Ƃ����`���������āA�N�X�Ə����Ă��邤���ɓ��łƂ������A�̑S�̂ŗ������Ă������̂Ƃ���ꂽ�肷��B�w�ʎ�S�o�x�ł��A�u����[�ā[����[�ā[�́[��[����[�ā[�v�Ŏn�܂�Ō�̐^���Ƃ����镔���Ȃǂ����ɂ����ł����āA�_�����Ă��邩��|��͂����A�����̂܂����邱�ƂɂȂ��Ă���B���ċ�C���A�u�^���͕s�v�c�Ȃ�A���u����Ζ�����������v�Əq�ׂ��B�u�s�v�c�v�Ƃ͕�����Ř_���I�Ȏv�l�������E�������A�u���u�v�Ƃ͐S�̒��ɊϔO���āA�����o���ď����邱�Ƃ������B����ɂ��A�������Ȃ킿�S�g�̖��������������Ƌ�C�͂����̂ł���B�i�����G�N�A�O�f���j
�@�ނ����A���������h���ɏZ��ł����Ƃ��A���s�̂����Ŋw�Ƃ����C�M���X�l�̓��āA�u�����̉�v�Ƃ����̂��J���Ă����B���B�N�g���A�w�̗���ɂ��邻�̉��Ɏ����s���Ă݂����Ƃ�����B�����ł́A���{��̔����ł�ޔʎ�S�o�����̂܂܃��[�}���ɂ��āA������A���{��͂قƂ�ǒm��Ȃ��Ǝv���鐔�\�l�̃C�M���X�l���A��Ăɐ����o���ď����Ă����B���[�}���́A�����̂悤�ȕ\�ӕ����ƈ���ĉ����L���ɂ����Ȃ�����A���̈Ӗ��������Ȃ��B���{�l���J�^�J�i�ŏ����ꂽ�ʎ�S�o�����ł����Ԃɋ߂��B�������A��̐����ł́A�ʎ�S�o���̂��̂��u�^���̂��Ƃv�ł����āA���ꂾ���ɁA���̂��ƂΎ��̂ɃG�l���M�[���������Ă���B������A����������邱�ƂɈӋ`�͂���̂��A�Ƃ������Ƃł������B���܂ł͎��́A���ꂪ�w�ʎ�S�o�x�ւ̖{���̃A�v���[�`�ł�������������Ȃ��A�Ǝv�����肵�Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@�@�F���̔ޕ��̒m�I�����̂ւ̃��b�Z�[�W
�@�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (87)�\�@
(2013.01.01)
����35�N�ȏ���O�̂��ƂɂȂ邪�A�F���T���@���H�C�W���[1����1977�N9��5���ɁA���H�C�W���[2�������N8��20���ɑł��グ��ꂽ�B2���̂ق���1�������ł��グ�����������̂́A1���̃V�X�e���s�ǂɂ��ł��グ��16���ԉ������ꂽ���߂ł���B���̂悤�ɁA1977�N�ɓ�̉F���T���@���قړ����ɑł��グ��ꂽ�̂́A1970�N��㔼����1980�N��ɂ����Ėؐ��A�y���A�V�����A�C�����Ƃ������O�f���������悤�ȕ����ɕ��Ԃ��߁A�F���T���@��ł��グ��^�C�~���O�Ƃ��Ă͍œK�̔N�ł���������Ƃ����Ă���B���̋@�������A���̂悤�ȏ����̉��Ɏ��ɑł��グ����̂ɂ́A175�N��܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ������Ƃ������Ă����B
�@�����[���̂́A�����̓�̉F���T���@�ɂ́A�A�����J�q��F��(NASA) ���A�n���O�m�I�����ɑ���l�ނ���̃��b�Z�[�W��ύڂ��Ă������Ƃł���B�����̏Z��ł���n�����Љ�悤�Ƃ�����̂ŁA����́A�u�n���̉��v�iThe
sounds of Earth�j�Ƃ����^�C�g���̋����b�L���ꂽ�������R�[�h�ɂȂ��Ă����B�d�q�I�ɏ������ꂽ���̃��R�[�h�̓��e�ɂ́A115���̉摜�Ɣg�A���A���A����~�ȂǓ����̖����Ȃǂ̑����̎��R���̂ق��A���{�̎ڔ��ȂǁA�l�X�ȕ����⎞��̉��y�Ȃǂ��܂܂�Ă����B���̃��R�[�h���F���֑���o���ɂ������āA1977�N6��16���A�����̃J�[�^�[�哝�̂͂��̂悤�Ȍ����R�����g���o���Ă���B
�@��X�͉F���Ɍ����ă��b�Z�[�W�𑗂����B��͂ɂ�2,000�����̐�������A�������̐��ɂ͐������Z�݁A�F�����s�̋Z�p�����������������݂��邾�낤�B�����������̕����̈���{�C�W���[�����A���R�[�h�̓��e�𗝉����邱�Ƃ��ł���A��X�̃��b�Z�[�W������Ă���邾�낤�B��X�͂��̓��ɂ��A���ݒ��ʂ��Ă���ۑ���������A��͕����̈���ƂȂ邱�Ƃ����҂���B���̃��R�[�h�ł͉�X�̊�]�A��X�̌��ӁA��X�̗F�D���A�L��ňؕ|���ׂ��F���Ɍ������Ď�����Ă���E�E�E�E
�@���̃R�����g�́A�������W���[�N�ł͂Ȃ��B�F���ɂ́A�n����̐l�ނ̂悤�ȁA���邢�͂���ȏ�̒m���������������̂����݂���B�����35�N�O�ł����A�����P�Ȃ鐄��ł͂Ȃ��āA�u�Ȋw�I�ȁv�����Ƃ��Đ��E�̉Ȋw�҂���������e����Ă����B������A�A�����J�哝�̂��A�^���ȑԓx�ł��̂悤�Ȍ����R�����g���o�����̂ł���B�����āA�T���@�̃��R�[�h�̂Ȃ��ɂ́A�n���O�����ɑ���ގ��g�̈��A���A���{��⒆����A�؍��ꓙ���܂ޒn�����55��ނ̌���ɂ��Ċ܂܂�Ă����B�����ł́A�����q�ׂ��Ă���B
�@����͏����ȁA�������E����̃v���[���g�ŁA��X�̉��A�Ȋw�A�摜�A���y�A�l���A��������\�������̂ł��B�������̎�����A�{�L�^�����͐������сA�F����̌��ɓ͂����ƂŁA�F����̑z���̒��ɍĂю��������S�邱�Ƃ��ł���K���ł��B
�@�@�@--�A�����J���O���哝�� �W�~�[�E�J�[�^�[
�@���̓�̒T���@�ɂ́A�܂��A�n�����\���āA���ۘA�����������̃N���g�E���@���g�n�C�����ɂ�鈥�A�����ڂ���Ă����B���܂��܁A���̎苖�ɂ́A���̂Ƃ��A���@���g�n�C�������I�[�X�g�����A�a��̉p��ŏq�ׂĂ��镔���̘^���e�[�v�����邪�A���̓��e�͂��̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@�n����̂P�S�V�J���ɂ��g�D���ꂽ���ۘA���̎����������n�����\���Ă����A�\���グ�܂��B
�@�����̉F���T���̖ړI�́A���a�ƗF�D�A�����đ��ݗ����ł���܂��B�����͌����ȋC�����Ɗ�]�������āA�F���ւ̑����ݏo���܂����E�E�E�E�E
�@�����̃��H�C�W���[�P����2���́A���݂ł��F���ʼnғ����Ă���B���H�C�W���[�P����2011�N8��8�����݂ő��z�����177��km���ꂽ�Ƃ���z�Ƃ̑��Α��x��b����17.06km�Ŕ�s���ł���A�n������ł������ɂ���l�H���̂ƂȂ��Ă���B�����܂ʼn����Ȃ�ƁA�n���Ƃ̒ʐM�̂��߂̓d�g�͕Г������ł���13���ԗv����Ƃ����B
����A���H�C�W���[2����2011�N8�����݂ő��z�����144��km���ꂽ�Ƃ���z�Ƃ̑��Α��x�E�b����15.46km�Ŕ�s���ł���A�{�C�W���[1���Ƃ��̌�ɑł��グ��ꂽ�p�C�I�j�A10���Ɏ����Œn�����牓���Ƃ���ɂ���B
�@���̂悤�ɁA���łɂR�T�N�ȏ���O����A�F���̔ޕ��ɂ͒m�I�����̂����݂���Ƃ����O��̂��ƂɁA�F���Ɍ������āA�n������̃��b�Z�[�W�M���Ă����B����ɑ��锽���͂܂��Ȃ��B�������A������Ƃ����āA���ꂪ�n���O�����Ȃ���̂͑��݂��Ȃ��̂��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����A���܂�ɂ��F���͍L��Ȃ̂ŁA�����̎����݂̒ʐM��i�ł̓��b�Z�[�W�𑗂�͂��邱�Ƃ������ėe�Ղł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��낤�B���Ƃ��A���H�C�W���[�P���A2���Ƃ����݂͑��z�n�̒[�߂��܂ōs���Ă��邪�A�������瑾�z�n�𗣂�āA���ɑ��z�n�ɍł��߂��P���n�ł���P���^�E���X���A���t�@�����������Ƃ��Ă��A��������܂łɂ͖�8���N������̂��Ƃ����B
�@���܂�ɂ��L��ȉF���ł̃R�~���j�P�[�V�����́A��͂�e�Ղł͂Ȃ��B�����A������A�F������̐M���Ǝv������̂�n������M�����L�^������BNHK�ŕ��f���ꂽ�u�F���ɐ��������߂āv�iBS 2012.12.27�j�ɂ��ƁA����́A���H�C�W���[���ł��グ��ꂽ1977�N�ɁA�A�����J�̓d�g�]��������M�������̂ŁA��ʂɁuWow�M���v�ƌĂ�Ă���炵���B���ꂪ�A�F������̗B��̐M���Ƃ���Ă�����̂ŁA���̎��g���ɍ��킹�Ă��̌���^���Ɏ�M�����݂�ꂽ���ĂѐM����߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�������A���E�̓V���ϑ��҂����͒��߂Ă���킯�ł͂Ȃ��B���H�C�W���[1����2���ɐςݍ��܂�Ă��錴�q�͓d�r�̎����́A1����2020�N�ȍ~�A2����2030�N�ȍ~�ɐs����\��Ƃ�������A�܂����炭�́A���̃��H�C�W���[1����2���ɂ��F���̒m�I�����̂Ƃ̃R���^�N�g�̉\���������ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����킯�ł͂Ȃ��̂ł���B
�@���̂悤�ȉF���̒m�I�����̂Ƃ̐ڐG��z�肵�āA�V���w��̍��ۘA���Ƃ������ׂ��u���ۓV���A���v���u�n���O�m�I�����̔�����̊����Ɋւ��鏔�����ɂ��Ă̐錾�v�Ƃ������̂��o���Ă���炵���B������A�����NHK�̔ԑg�ŏЉ��Ă������A���̋L�^�ɂ��ƁA���̂����̑����Ƒ�O���ɂ́A���̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ă���B
�@��1��
�@�n���O�m�I�����ƍl������M�����̔����҂́A���\���s���O�ɁA���ꂪ���R���ۂ܂��͐l�דI�Ȍ��ۂɂ����̂ł͂Ȃ��A�n���O�m�I�����̑��݂ł��邱�Ƃ��m�F����w�͂�����B�ؖ��ł��Ȃ������ꍇ�́A���m�Ȍ��ۂ̔����Ƃ��Č��J���s�Ȃ��Ă��悢�B
�@��3��
�@���������炩�ɒn���O�m�I�����̐M���ł���؋��ƔF�肳��W�҂ɒʒm���ꂽ��A�����҂͍��ۓV���w�A���̓V���d���ǂ�ʂ��Đ��E���̊ϑ��҂ɘA������B�܂����A���������ɒʒm����B�����ɔ����҂́A���ۓI�Ȋ֘A�@�ւɐv���ɒʒm���A�f�[�^�������B
�@���̂悤�Ȓn���O�m�I�����̂̒T���Ƃ͕ʂɁA���Ƃ��A2011�N11��26���ɑł��グ��ꂽ�ΐ��T���@�u�L�����I�V�e�B�v�̉ΐ���ł̒T�������ڂ����B���̃L�����I�V�e�B�́A����܂ŁA�ΐ��ō̏W�����y���̂Ȃ����琶���̌��ɂȂ�L�@���̈�N�������^�������Ă��邪�A���̒T�������͂��܂��p�����čs���Ă���B���l�̒T�������́A�ؐ��̉q���u�G�E���p�v��A�y���̉q���u�G���P���h�X�v�A�u�^�C�^���v�Ȃǂł��s���Ă��邩��A�����Ԑl�ނɂƂ��ē�ł������n���O�̐����ƒm�I�����̂ɂ��Ă��A�_��̃��F�[���͉Ȋw�I�ɂ���������������Ă������ƂɂȂ�̂�������Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA�n��̎��_����ł͂Ȃ��F���̎��_����݂�A���̒n���O�����ƒm�I�����̂Ƃ́A�ǂ̂悤�ɑ�������ł��낤���B�Q�[���[�E�Y�[�J�t�́A�n�[�o�[�h��w���Ƃ̉Ȋw�҂ŁA�l�ނ̐i���ƍ��Ɋւ��钘��ŗL���ł��邪�A�ނ̏������w���Ƃ̑Θb�x�̂Ȃ��ł́A�m�I�����̂́A�����̋�͂̒��ɖ����ɑ��݂��Ă���ƁA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�l�Ԃ̍������i�����������̌`�Ԃ͂������݂���B�I�����͕����ǂ��薳���ɂ���B�����͖����̋�͂̂Ȃ��ɑ��݂��Ă���B�����ɖ������f���̐��́A���S���A���≽�\���ɂ��y��ł���B�����A�����Ȉӎ��������Ă���f���͂ЂƂ��Ȃ��B�������l�Ԃɂ悭�����`�Ԃ̐��������݂���A�܂������قȂ����`�Ԃ̐��������݂��邪�A�Ƃɂ���������f���ɁA���������ӎ��Ƃ��ė������鐶�������݂��Ă���̂ł���B�i�w���Ƃ̑Θb�x��{�v���A�T���}�[�N�o�ŁA2003�App.197-198�j
�@���̂悤�ɔނ́A�����́u�����̋�͂̂Ȃ��ɑ��݂��Ă���v�Ƃ����B������f���Ɂu���������ӎ��Ƃ��ė������鐶���v�����݂��Ă���Ƃ���������Ă���B�������A�n��̎������́A���̑��݂����Ȃ��Ƃ��u�Ȋw�I�ɂ́v�܂��m�F���邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��B���H�C�W���[�ȊO�ɂ��A����ɑ����̒T���@���F���ɑ��荞��ł��A�n�ォ��̃��b�Z�[�W�������ɓ͂�����̂��m�F�ł���܂łɂ́A��̂ǂꂭ�炢�̎��Ԃ�������̂ł��낤���B�Q�[���[�E�Y�[�J�t�́A���̓_�ɂ��āA��ʓI�ɂ͎������́u�L��ȉF���ɖڂ��������Ƃ��ł����A�����ɐ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̉F���̂Ȃ��ɂق��̐����ȂǑ��݂���͂����Ȃ��Ƃ����M�O�ŁA�Â�ł܂��Ă��邽�߂ɂł���v�Əq�ׂ����ƂŁA���̂悤�ɂ����킦�Ă���B
�@�i�������́j����Ńn�b�L���ƌ��āA�m���߂Ȃ�������A�����M���傤�Ƃ��Ȃ��̂��B���̂��߁A�ق��̋�͌n�ɏZ�ސ����̌Q�A�������̌Z�킽���́A���܂��ɉB�ꂽ�܂܂ł���B�����Ă��̏�Ԃ́A�u�����͑��݂��邷�ׂĂł���A���݂��邷�ׂĂɏ[�����Ă���v�Ƃ������ƁA���Ȃ킿�u���݂���̂͐����݂̂ł���v�Ƃ������Ƃ��A�����������܉Ȋw�ƌĂ�ł�����̂̒��S�����ƂȂ�Ƃ��܂łÂ����Ƃ��낤�B
�@�������A���̂Ƃ��͕K���K���B���̂Ƃ��������́A���̕����w���X�^�[�g�����邱�ƂɂȂ�B���̂Ƃ����玄�����́A�����ɂ��āA����ł�����̂ł͂Ȃ������Ă�����̂��������Č�������悤�ɂȂ�B�l�Ԃ⓮���̎��̂���U���邱�Ƃɂ���Đ����̐_����������������ȂǂƂ͂��Ȃ��Ȃ�B���̂悤�ȍs�ׂ́A���̓����A����߂Č��n�I�Ȋw�K�@���ƌ��Ȃ����悤�ɂȂ邾�낤�B�Ȃ��Ȃ�A���̂̂Ȃ��ɂ͈ӎ������݂��Ă��Ȃ�����ł���B�i�w���Ƃ̑Θb�x��{�v���A�T���}�[�N�o�ŁA2003�App.205-206�j
�@���̂悤�ɏq�ׂĂ���Q�[���[�E�Y�[�J�t�́A�l�ނ̐i���ƍ��̖������������āA�v��450�����̃x�X�g�Z���[���L�^���Ă���Ȋw�҂ł���B���̐l���A�u�����͑��݂��邷�ׂĂł���A���݂��邷�ׂĂɏ[�����Ă���v�Ȃǂƌ����Ă���̂ł���B�Y�[�J�t��m��Ȃ��ŁA���̂悤�Ȍ��t�ɐڂ���l�́A���邢�́A�����̌��t���A��E����̌[���ł��邩�̂悤�ȍ��o������������Ȃ��B�����ō��x�́A��E����̎��_�ł́A�F���̐����͂ǂ̂悤�ɑ������Ă��邩���݂Ă݂邱�Ƃɂ������B�V���o�[��o�[�`�́A���Ĉ������̏��ҋq����A�u���Ɍ����鐯�́A�����̕��̂ł��傤���A����Ƃ����������݂���̂ł��傤���v�Ɛu���ꂽ���Ƃ�����B����ɑ��ăV���o�[��o�[�`�́A�����������B
�@�F���ɂ͍ō��E�̓V�g�I���݂���A�ӎ����悤�₭���ł�����x�̍Œ�̍��ɂ�����܂ł́A���܂��܂Ȉӎ��I�i�K�ɂ��鐶���������ɑ��݂��܂��B�ӎ��I�������n�������Ɍ����Ă���Ǝv���Ă͂Ȃ�܂���B�n���͐�������Ȃ����݂���V�̂̂����́A��������ɂ����܂���B�����Ȃ�b�q�����F���̑�삪�A�����Ȃ�F���ɂ����Ė����Ȃ�ӎ��I�i�K�ɂ��閳���̐����ɖ����̐����̏��^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��͂�������܂���B�L�@�I�����̑��݂���V�͖̂����ɂ���܂��B�������A���̐����͕K���������Ȃ�������������Ă���`�̂��Ƃ�킯�ł͂���܂���B�ȏ�̐��������Ƃ��Ă͐���t�ł��B�i�w�V���o�[�E�o�[�`�̗�P�i6�j�x�i�ߓ���Y��j�����ЁA1986�Ap.170�j
�@���̃V���o�[��o�[�`�́A�������Y�[�J�t�Ƃ͈���āA���̒n��̐l�ł͂Ȃ��B�ق��Ȃ�ʁu�F���̒m�I�����́v�̈�l�ł���A�����ł��u��C���O���痈�������v�Ǝ����̂��Ƃ���k�߂����Č����Ă���B���������̒m���́A�^�����Ȃ��A�n��̐l�Ԃ��͂͂邩�ɍ����B���̃V���o�[��o�[�`���A�u�L�@�I�����̑��݂���V�͖̂����Ɂv����Ƃ����B�������A���̐����͕K�����������������̒n��Ō�����Ă���`�̂��Ƃ�킯�ł͂Ȃ��ƒf���Ă���B���̂����ŁA�V���o�[��o�[�`�́A�F���͂�������ł��̒��ɖ����̐����������鐶���̏ꂪ����A�Ƃ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�F���͂�������ŁA���̒��ɖ����̐����̏ꂪ����܂��B�����͈�ł��B��������ɂ͖����̐i���̒i�K������Ƃ������Ƃł��B����������I������������悤�Ƃ���ƌ���̕s���R���������͂�����܂��B�Ƃ͌����A���̂������Ȃ��s�K�ȋL�����g�p��������A���ʓI�ɂ͐^�������܂��`�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����͈�ł��B�F���͈�ł��B���E���Ƃ������̂͑��݂��܂���B�����Ƃ������̂͂���܂���B����ōs�����l�����ς炸�������̉F���Ő��������Ă���̂ł��B�����n��Ƃ͈قȂ�o�C�u���[�V�����̐��E�A�قȂ�ӎ��̒i�K�Ő������Ă���Ƃ��������ł��B����A���Ȃ��̖ڂɂ͌����Ȃ��Ă������n��ɂ���ƍl���Ă��悢�̂ł��B����͂��傤�ǁA���Ȃ����������ł͋C�Â��Ȃ��Ă��A���Ɠ�����E�ɂ���ƍl���Ă��悢�̂Ɠ����ł��B�i�w�V���o�[�E�o�[�`�̗�P (12)�x�ߓ���Y��ҁA�����ЁA1988�App.32-33�j
�@�L��ȉF���̍L����̂Ȃ��ł́A�ė���ɂ��Ȃ�Ȃ��悤�Ȃ����ۂ��Ȓn���ł����Ă��A�F���̈ꕔ�ł��邱�Ƃɂ͕ς��͂Ȃ��B�����ɂ���ẮA�n�����F���ɗn������ł����č��ꂷ��悤�ɁA�n�㐢�E�Ɨ�E���ӑR��̂ƂȂ��Ă����悤�ȏ��l������B�n��ł̓��H�C�W���[1����2����ł��グ��35�N�ȏ���O����A���̍L��ȉF���ɑ��݂���͂��̒m�I�����̂ւ̃��b�Z�[�W�𑗂邱�Ƃ�S�����Ă����B����͎����ł���B�����Ĉ���ł́A�V���o�[��o�[�`�̂悤�ɁA�u�m�I�����́v�Ƃ��āA�F�����炷�łɖc��ȃ��b�Z�[�W��n���ɓ͂������Ă�������������B���̓�̎����́A�₪�ğӑR��̂ƂȂ�A�����ɂ��Ă̈�̎����A��̐^���ƂȂ��āA�������̑O�ɑĂ������ƂɂȂ�̂�������Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@�Ñ���{�ɂ����鍑�ی𗬂Ǝ��̑O��
�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z(86)�\
���E�j�̖{��N�\�Ȃǂ��J���āA�Ñ�̐��E�����Ă݂�ƁA�G�W�v�g�A�M���V�A�A�����Ȃǂ̗��j��5��N�قǂ܂ők���̂ɑ��āA���{�̗��j�ők���̂́A��������2��N�قǂł���B�������2��N�O�ɂ́A���{�Ƃ�������̂̍��͂܂��Ȃ������B���{�ɂ͂��悻1��2��N�O����ꕶ�����������Ă�����A2��3�S�N�O������퐶�������N�����Ă������Ƃ́A�e�n�̈�ՂȂǂ���킩���Ă��邪�A�I��1�`2���I���̓��{�ɂ́A�`�l�̏������e�n�ɕ������Ă����ƍl�����邾���ł���B���̍��̓��{�ɂ́A�܂��������Ȃ��������A�L�^�ł��ǂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@����ɑ��āA�����ł͂��łɁA�I���O1��6�S�N�̟u�̎��ォ��b�������Ŏ�v�ȍ������L�^���n�߂Ă���B���̍b�������͌n���I�ȕ����ŁA���̌�̒����ł̊����̔��W�̊�b�ƂȂ����B�I���O202�N�ɂ͑O���̎���ɓ���A���c����7��ڂ̕��邪�I���O136�N�Ɂu�܌o���m�v�������āA���E���E�ՁE��E�t�H�̂T���T����ɋ������锎�m�̐��x��������Ă���B���̎̍��������_�@�ɂ��āA�͎���ɐ����Ƌ���̊�{�ɂȂ�A���̉e���͂́A�����݂̂Ȃ炸�A���̌�A���N�A���{�ɂ��y��ł����悤�ɂȂ����B
�@�I���O108�N�A����̉����R�́A�����̉q�����N��łڂ��A���鍑�́A���݂̗ɔJ�ȁA�g�яȂ̓쓌�����܂߂����N�����Ɋy�Q�A���p�A�ՓԁA�^�Ԃ̎l�S�������Ċ��̒����n�Ƃ����B���̌�A���N�l�S�́A�y�Q���c���݂̂ƂȂ������A���̊y�Q�S��ʂ��āA���N��������{�ɑ����̒��������������炳��邱�ƂɂȂ�B�y�Q�S�Ƃ����̂́A���݂̃\�E�����܂ލL�͈͂Ȉ�тł���B
�@���j�Ƃ̎i�n�J���A���̕���Ɏ���܂ł̒����I�v�̗��j��S130���ɂ܂Ƃ߂āw�j�L�x�������グ���̂́A�I���O97�N���ł���B�ނ͎��M�ɂ�����A�n�c��̕����Ȃǂɂ��j���̐���ɋ�J�����Ƃ����邪�A�ËL�^�ȊO�ɁA���g�̌����▯�Ԃ̌�蕔�Ȃǂ����p���Ă���B2��N�O�̏��ł���Ȃ���A�S���ɗ���Ă����z�����l�Ԋώ@�Ɣᔻ���_�A����ɐ��ʂɕx�ޏ��q���A���̗��j���ɍ������w�I���l�����^�����邱�ƂɂȂ����B
�@���̍��A���N�ł́A�v�]�����������Ă���B�����āA�I���O37�N���ɂ́A�������������ꂽ�B���̌�A�I��21�N���ɕv�]���ɐN�U���Đ��͂��L���Ă����������́A�ɓ��A�ɐ��ւ̐N�U���J��Ԃ��A���鍑�̒��N�x�z�͌�ނ��Ă������B�����͌㊿�̌�����̎���ŁA�����ŁA�I��57�N�A���j�N�\�ł͏��߂āA���{�Ɋւ���L�q���o�ꂷ��B�u�`�l�A���v���A�������������v�Ƃ����̂�����ł���B���鍑�ł́A�I���O��A���{�ɘ`�l���S���܂�̏W�c�ɕ�����ďZ��ł���Ƃ̏��͓��Ă����B������́A���̎����v���Ă����`�l�̎̎g�߂��������A�`�l�̎�`�̓z���i�Ȃ����j���ƔF�߂āA�u���ϓz�����v�̋����^�����B���ꂪ��ɍ]�ˎ���ɂȂ��ĕ������̎u��œy�����甭�����ꂽ����ł���B
�@���̍��̓��{�́A�퐶����̒����������ɂ�����A�_�k�Љ���W�̈�r�����ǂ��Ă����B���ꌧ�̋g�샖����Ղɑ�\������^�̊��W���⒩�N�n�̎R��̐��i��тт����n���W�����e�n�Ő���ɒz����A�S���̕������ʂɐ��Y�����悤�ɂȂ��āA�n��W�c�̊Ԃ̐헐���p�ɂɋN����悤�ɂȂ��Ă����B���̂����̈�c���A�㊿�֎g�߂𑗂��ē��v�����̂��A�����̌��Ђɂ���돂�����߂����̂ł������ƍl�����Ă���B
�@�������A107�N�ɂ́A�`�̖ʓy���̉��E�����i�������傤�j���h�������Ə̂���ʂ̎g�ߒc���A�㊿�̓s�A���z�Ɍ����āA�����̈���ɓz��160�l�����サ���Ƃ����L�^������B147�N����189�N�܂ł́u�`���̓����v�ƋL�����N�\�����邩��A���{�̓�����Ԃ́A���̌�����������Ă����̂ł��낤�B�����āA���̌�ɓo�ꂵ�Ă���̂��A���̏����E�ږ�Ăł���B239�N�Ɂu�הn�䍑�̔ږ�āA鰂Ɍ��g�v�ƋL�^�Ɏc����Ă���B�����̋L�^�́A���ׂĒ�������̊����ɂ����̂ł���B
�@���́A���̂悤�ɁA�Ñ�̓��{�𒆍��ƒ��N�Ƃ̊W�̂Ȃ��Ō��Ă������Ƃ��Ă���̂́A���ƒ��j�̌��T���A�Ñ���{�̑O���Œ�������N�Ƃ̌𗬂ɐ[���ւ���Ă����ƁA���x�������Ă�������ł���B�D�ꂽ��\�҂�A�t�ɂ��A���́A�Ñ���{�ɁA��x�قǐ��܂ꂽ���ƂɂȂ��Ă���B�ŏ��́A�����炭�A���̔ږ�Ă������Ă��������܂߂āA2���I����3���I�ɂ����Ă̌Õ������̎���ŁA���̎��́A5���I����6���I�ɂ����ẮA�������q�������Ă�������ł���B����敪�ŁA��̌덷�����邩������Ȃ����A�����̂�����̎�����A�����Ƃ́A�����āA����ȏ�ɒ��N�����Ƃ̌𗬂�����ɍs�Ȃ��Ă��āA���̔w�i�̉��ɁA�u�`���̕S�]�ɕ�����Ă��������v�͎���ɁA��a�Ƃ�����̍��ƌ`�ԂɎ��ʂ���Ă������ƍl������̂ł���B�܂��A����A�t���璷�j���T����̃��b�Z�[�W�����̂悤�ɓ`����ꂽ���Ƃ��������B
�@��������Ɩl�Ƃ́A�O���ɂ����ĉ��x���A���ۊW�̂Ȃ��ŏd�v�Ȗ�ڂ��ʂ����Ă����g���̃p�[�g�i�[���m�ł����B�܂��A���ہA���̐e�q�ł��������Ƃ�����A���������������Ă���܂����B�g���̃p�[�g�i�[�ł������Ƃ��͂��낢��Ə��������Ă���A���������������Ă���܂����B�Ñォ��ߑ�ɂ����āA���x�����݂��i�ʂȊW�����сA���ɍ��ۊW�ɂ����ē�̍��ƍ��̊Ԃ̒������Ȃǂ߂���A�w��̐��E�ł��A����w�̕���ł��A���݂��ɐ��������������܂����B�i1999.06.05�j
�@����3�N��ɓ`����ꂽ�̂́A���̂悤�ȃ��b�Z�[�W�ł���B
�@�I���S���I�̍��́A���{�ɐ����Ă��܂����B�Õ�����ł��B���N�����Ƃ̍s���������������ł��B���{�Ɗ؍��̊ԂŎg�߂��s�������Ă��܂����B����Ɋւ��d�������Ă��܂����B�����̎d�������Ă��܂����B�������A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�l�Ԑ��ɕx�ނ��߁A�ЂƂ̐��b�����Ă����Ă����Ƃ����̂����ۂ̂Ƃ���ł��B���ɐl���I�Ȗʂ̋����l�ł����B�`���I�Ȑl�ł͂���܂���ł����B�������A���ې����ɂ����閵�����m��A�Y��ł��܂����B�ꕔ�ʖ�����˂Ă��܂����B��̍��̊Ԃ̌𗬂̂Ȃ��ł̂��邢�l�����̓����ɂƂĂ��Y�݂܂����B����𗘗p���悤�Ƃ������x�����Ƃ���l�����ɂ��Ăł��B�i2002.06.05�j
�@�����āA����ɂ���3�N��ɂ́A���̂悤�ɂ������Ă���B
�@�I��3���I������4���I�ɂ����Ă̓��{�̌Õ�����ɂ́A�����Ƃ̍����ɑ����A���N�����Ƃ̌𗬂��n�܂�܂����B�ށi���T�j�͂��̂Ƃ��m�b�҂ł����B�����̐��E�������ŁA�����ǂ̂悤�ɂ�����悢�̂��A������l���A���̑�𗧂Ă�l�ł����B�����Œ��ځA�����⒩�N�����ɏo�������Ƃ͂Ȃ������̂ł����A�o�����s����������{�l�ł������蒩�N�̐l�Ȃǂɑ��āA�K�v�Ȃ��Ƃ��w�������苳������A���v������肵�܂����B
�@���Ȃ��́A���ڂ̎d���͂��̂��Ƃł͂Ȃ������̂ł����A���Ȃ��̎d���̈ꕔ�Ƃ��āA���̂��ƂɊւ��Ċē��̃|�X�g��^�����Ă��܂����B���Ȃ��ɍŏI�ӔC������܂����B���ׂĂɂ����Ă̍ŏI�ӔC�҂ł͂���܂���ł������A���镔���ɂ����ẮA���Ȃ��͍ŏI�ӔC�҂ł����B�������A�ނ͂�����ƁA�I�m�ɍs���Ă��ꂽ�̂ŁA���Ȃ��͍ŏI�ӔC���Ƃ����Ă��A���������J��������f��ւ����肷�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ă��݂܂����B���Ȃ����g�A�����́A�w�҂ł����B�����̐��E�ł��铌�A�W�A�Ɋւ��ďڂ����A�ׂ������Ƃ܂Œm���Ă��܂����B���邢�͔c�����Ă��܂����B���̂��ߏd����������Ă����̂ł��B(2005.08.31)
�@�����A����A�t�ɂ�鎄�ƌ��T�̑O���������ł���Ƃ���A�Ñ�l�Ƃ��Ă̎��ƌ��T���ւ���������A���N�����A���{��n���I��ՂƂ��鑊�݂̌𗬂́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������B���̃C���[�W��a���o�����ƂɊS��������������Ȃ��̂ł��邪�A���̏ꍇ�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�����炭�A�ߑ㍑�Ƃ��������Ĉȗ��̍��ی𗬂Ƃ́u���ہv�̊T�O���u�𗬁v�̎��Ԃ������ē����ł͂Ȃ��ł��낤�Ƃ������Ƃł���B
�@���ɌÑ�ɂ����ẮA�����̓��{���̗��H����������Ă��Ȃ��ňړ��������ėe�ՂłȂ��̂ɑ��āA���N�����Ƃ̌𗬂́A��������C�������D�ł��n���n�C�E�G�C�ɂȂ��āA�ނ���A���݂Ɉړ����Ղ��W�ɂ��������Ƃ����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B���{�ƒ����Ƃ̌𗬂͊y�Q�S���o�R����ꍇ�������ẮA�m���ɖ������ŁA���̌�ɑ����A���@�g�⌭���g�Ȃǂ��A�����Α���đ����̐l���������Ă���B�����̊Ӑ^�����{�ɗ���̂ɂT�s���A753�N�A6��ڂɂ悤�₭�������ɒH����Ă���B�������A���{�ƒ��N�����̊Ԃł́A�������x���ł��ړ��͍���ł͂Ȃ��A�o���������R�ŁA���̂��Ƃ��A�����̕��y�ɂ��傫�ȈӖ��������Ă����B��Ƃ̏��{�����́w�Ñ�j�I�x�̂Ȃ��ŁA�쒩�N�Ɩk����B�͂ނ��듯�ꐶ�����ł���Ƃ��Ă��邭�炢�ł���B�ނ́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u�킽���͎O���I�ɂ͓쒩�N�̈�p���k����B���`�̖��������Z���A���n��͓��ꕶ���Ɛ������ł������Ǝv���B�쒩�N�ɖk��B�̘`�킪�ړ����ĐA���n���������̂ł��Ȃ���A���̋t�ł��Ȃ������B������҂̌�ʂ͂��������A���Ƃ��Ƃ͗��n��ɈȑO����Z��ł����̂ł����āA������₷�������Ɠ쒩�N�Ɠ��{�Ɓw�`��̍��x������݂��Ă����̂ł���B�v�i1982�N�A���{�����o�ŋ���A33�Łj
�@���́A�u�쒩�N�Ɠ��{�Ɓw�`��̍��x������݂��Ă����v�Ƃ����̂́A�ǂ̂悤�ȏł��낤���B���Ȃ��Ƃ��A�ߑ㍑�ƂƂ��Ă̓��{�Ɗ؍��̊Ԃœ��{�l�Ɗ؍��l�����ی𗬂���Ƃ����̂Ƃ́A���Ȃ�l��������Ă����͂��ł���B�����ł́A���߂ČÑ�̓��{�ɐ����Ă����l�X���ǂ̂悤�Ȑl�X�ł������������݂Ă����K�v������Ǝv����B�܂��A�ږ�Ď��ォ��S�]�̏����ɕ�����āA���{�̊e�n�ł��荇�����J��Ԃ��Ă��������܂��͎Ƃ́A��̂ǂ̂悤�Ȑl�����ł��������B����ɂ��Ă̏��{�����̐����́A�����ł���B
�@�i�ނ�́j�ނ���V�c�Ƃ̑c�悪�쒩�N������{�ɓn�����āA��a�~�n�Ɋ��荞��ł���ȑO����̍ݒn�̐��͂Ƃ��ċ��Z���Ă������̂ƍl������B�������������������Ȃ�푰�ł��邩�Ƃ������Ƃ͂͂����肵�܂��A�ސ��ł����Ȃ�A�����炭����ȑO������{�ɈڏZ���Ă������N�l����̂ł͂Ȃ������낤���Ǝv���܂��B���N����̓n���͂������̔g�ɂȂ��Ă��邪�A�����܂��Ɍ����āA�����Ƒ����Ƃ킯��ƁA�����͖퐶����̑����i�O�O�Z�Z�N�j�A�����͖퐶����̔ӊ��i��O�Z�Z�N�j�ŁA���̌Õ�������������̂́A���̑����̓n���l����ł������Ǝv���܂��B�i�O�f���A79�Łj
�@�����ł́A���{�̌Õ���������グ�������҂��A���N��������̓n���l����̂ł������Ƃ����̂ł��邪�A�����A�����ł���Ƃ���ƁA���̌�̒��N�����Ƃ̌𗬂��A�����炭�A���N��������̓n���l�����̎���ł͂Ȃ��������Ƃ������ƂɂȂ�B����ł͒��N��������͈�̂ǂꂭ�炢�̋K�͂œn�����Ă����̂ł��낤���B
�@���s�ɂ��鍑�ۓ��{���������Z���^�[�̏����a�Y�����R���s���[�^���g���Čv�Z�������ʂł́A�Ñ㒩�N�����Ɠ��{�̐l�ԏW�c�̓����́A���N����������{�ɑ��v��S���l���炢�̐l�������Ă��邾�낤�Ƃ����B�i�����V���Еҁw���{�Ñ�j�̓�x1992�N�A34�Łj�@�܂��A�Â��w�g���S�j�x�Ȃǂɂ́A�u��a�̔@���͎����㊿�l�i����ЂƁj�̍��A�R��͎�����`�i�͂��j�̍��v�Ə�����Ă����āA����ɂ��A���݂̓ޗnj��⋞�s�{�Ȃǂ̏Z���́A�唼���n���l�ł������Ƃ������Ƃ�������������Ă���B�i���B���w���{�Ñ�j�ƒ��N�x�i�u�k�Њw�p���ɁA1999�N�A69�Łj
�@����͏��������ɓ��邱�ƂɂȂ邩������Ȃ����A����̓��{�l�̒��̂��̂悤�ȓn���l�̍��Ղ����Ȋw�I�Ő��m�ɒT����@�Ƃ��ẮADNA�Ӓ�ɂ����̂�����B���Đ_�ސ쌧�t�R���̍�������������w�@��w��DNA�����҂̕����m���A����̓��{�l�̃��[�c��T�鎎�݂Ƃ��āA���{�l�̃~�g�R���h���ADNA�����ӂ̊O���Ɣ�r�������ʂ��ANHK�X�y�V�����u��`�q�v��O�W�ŕ��f�������Ƃ��������i2000.01.02�j�B
�@����ɂ��ƁA�{�B�̓��{�l�������Ă���~�g�R���h���A��DNA�^�C�v�́A�����̑����ق����炠����ƁA�����l�ɑ����^�C�v��25.8�p�[�Z���g�A�؍��l�ɑ����^�C�v��24.2�p�[�Z���g�A���ꌧ�l�ɑ����^�C�v��16.1�p�[�Z���g�A�A�C�k�ɑ����^�C�v��8.1�p�[�Z���g�ȂǂƂȂ��Ă���A���{�l�ŗL�̃^�C�v��4.8�p�[�Z���g�ł���ɂ����Ȃ��B�܂�A������{�l�̓�l�Ɉ�l�́A�����I�ɂ͒����n�Ȃ����͊؍��n�ł���Ƃ������ƂɂȂ�B����͖ܘ_�A�Ñ���{�ɂ�����n���l�̑�ʗ����Ɩ��W�ł͂Ȃ��ł��낤�B���{�����́A���̂悤�ȓ��{�l�̃��[�c�ɂ��Ă͔ޓƎ��̐��������ĂĂ��邪�A����͂��̂悤�Ȃ��̂ł���B�������������̂܂܈��p���Ă݂悤�B
�@�������������{�l�Ȃ���̂��ǂ��������̂��܂����m�łȂ��̂ł����A�����Ă���悤�ɁA�C���h�l�V�A�A�|���l�V�A�A�C���h�V�i�A�����̓���A���N�����A���邢�͒��N�������o�R���Ă����Ƃ���́A�����Ɩk�A�W�A�̖����A�����������̂̍����ł������ł��傤�B�����ɒn���I�W���璩�N�l�̓n��������ɑ����Ă����B���{�ł̍����̌J��Ԃ��ɂ���āA������u�`��v�����ꂽ�Ǝv���܂����A���������l���̑��B�����̂܂ܐ��͂ƂȂ��āA���Ƃ��Ώo�_�n���ɂ��A�O�g�n���ɂ��A�k���n���ɂ��A����ɋg���A�R��A��a�A�I�ɁA����������ɂ��L����A���ꂼ��W�c�������Ă����Ǝv���܂��B�����Ȃ�Ό��n���������́A���邢�͕������ƓI�Ȃ��̂����X�ɂ������B���ꂪ�n���ʂɃu���b�N���`�����A�o�_�Ƃ��g�����Ƃ���a���Ƃ������悤�ȂƂ���ɁA�A�����͑̂Ȃ���̂������Ă������Ǝv���܂��B���������̕������ƓI�ȃu���b�N�́A���݂̊Ԃɋٖ��ȘA���͂Ȃ��A�����I�ȋ��͊W���Ȃ������B������[�Y�ȊW�������Ǝv���܂��B�����ɍc���̑c��ƂȂ��������̓n���l�W�c����a�ɓ��荞��ł����̂ł����A���̍ۂ��A���̃��[�Y�ȘA���̂́A��v���ĐV���������L�͂Ȑ��͒c�̂ɒ�R���邱�Ƃ��Ȃ������B�����ő�a�����������̓n���l�ɂ���Đ�̂���A���ꂪ����Ɋe�n���ɐN�����Ă������̂��Ǝv���܂��B�i�O�f���A79�|80�Łj
�@���{�����́A�����ō]��g�v���̋R�n�������������o���Ă���B�]����͓쒩�N����̓n�����͂��k����B�ɂ��āA�����ŕS�N���炢���āw�Î��L�x�w���{���I�x�������Ƃ���̐��_�V�c�ƂȂ�A���ꂩ�牞�_�V�c�Ƃ��ĉ͓��ɏ㗤���A�����Łu�����v�𗧂āA�̂��ɑ�a���͂��z������Ƃ����̂ł���B����ɑ��āA���{�����́A�n�����͖͂k����B�ɂ͏㗤�����A���_�V�c�Ƃ��Ă����ɉ͓������a�~�n�ɓ������ƍl���Ă���悤�ł���B������ɂ���A�ږ�Ă̎��ォ����{�ŕS�]�̏W�c�ɕ�����đ������J��Ԃ��Ă������̎����̑唼���A���N��������̓n���l�ł���Ƃ������Ƃ͒��ڂɒl���邱�Ƃł���B��Ƃł́A���������A���̌Ñ���{�́u�n���l�v�ɂ��āA�w������{�j�x�i���m���@�A1988�N�j�̂Ȃ��ŁA���̂悤�ɓƎ��̍l�@���s�Ȃ��Ă���B
�@���{�̌��Z���̓A�C�k�l���̃R���|�b�N���l���̂Ƃ��낢��ɉ]���Ă��邪�A�L�ˎ���̏Z���͂Ƃɂ����Ƃ��āA�}�]�����k�N�܂œ쉺���Ĉȗ��A�܂��Z���S�N���炢�O����A���N����̎����I�ȁA�܂��͑����ɗ�����ꂽ�Ƒ��I�ȈڏZ�҂͗����Ƃ��ĂÂ��A�ނ�͊L�ːl��ƈ���đ����̕����������Ă��������A���I�ɂ�������Z����ǂ��z�����x�̗D�ʂ��߂����̂Ǝv����B�i202�Łj
�@���̂悤�ɁA�Ñ���{�ł͂܂����{�����Ƃ��Ă͂܂Ƃ܂��Ă��炸�A�����̏����ɕ�����đ������J��Ԃ��Ă����Õ����ォ��A���N����̈ڏZ�҂������Ƃ��đ����Ă����Ƃ���Ȃ�A����͓��R�A���{�̏Z���̍\���ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��Ă������͂��ł���B�������A�ނ�́A�u�����̕����v�������Ă��āA��Z�������Љ�I�ɗD�ʂɗ��悤�ɂȂ��Ă������B���̂��Ƃ��Ӗ����邱�Ƃ́A�����ĉߏ��]���ł��Ȃ��B�������́A����ɂ������q�ׂĂ���B
�@�܂�V�c�Ƃ̑c�_�̍ŏ��̒蒅�n�_����^�J�}�K�������{�̂ǂ��ɓ��邩�B������l����O�ɁA���łɂ���ȑO�ɓ��{�̊e�n�ɑ����̕}�]�����̐V���l���̂̈ڏZ���������Ƃ������ƁA�y�ѓ����͂܂����{�Ƃ������̊m�����Ȃ���������ނ�͓��{�l�ł��Ȃ���Ε}�]�l�ł��Ȃ��A���炭�P�ɑ����ɓ������ꂽ�������Ƃ��Ċe�n�Ƀe���f���o���o���ɐ������Ă��������Ƃ��l���Ă����K�v������B�i�O�f���A202�Łj
�@���̂悤�ȌÑ���{�̎Љ�I�w�i���l���Ȃ���A�����ł܂��A���̑O���ɂ��Ă�A�t�̂��Ƃ����グ�Ă݂邱�Ƃɂ���BA�t�̂��Ƃ��ꎚ��傻�̂܂܍Č�����Ƃ��̂悤�ɂȂ�B
�@�i���Ȃ��̑O���ɂ́j�I��3���I����4���I�ɂ����Ă̌Õ����オ����܂����B�_�{�c�@���牞�_�V�c�ɂ����Ă̎���ł��B���̎����Ȃ��͒��N�����Ő����Ă��܂����B���A���������c���������悤�ł��B���Ə����āu�����v�Ɠǂ݂܂��B��ɋ���ʂŐl�X�̐������������シ��悤�Ɍv�炤��ڂł��B���̖�ڂ��ē��{�ɂ���ė��܂����B�����A���̏ꍇ�A���N�����̕ꍑ�ŁA���Ȃ��͌��C����Ŏ��_�������Ă������Ȃ��Ƃ��낪�������̂ŁA�����������߂Ƃ��ē��{�Ƃ����O�n�Ɉڂ��ꂽ�̂ł��B�Ƒ��s���Ă̂��Ƃł����B(2011.06.07)
�@�܂��A�I��3���I����4���I�ɂ����Ă̌Õ�����͂킩�邪�A���ꂪ�A�u�_�{�c�@���牞�_�V�c�ɂ����Ă̎���v�ƌ����Ă��A����͓��{�̒����W�����m������ȑO�̍��������̎���ł����āA�u�_�{�c�@�v�Ƃ��u���_�V�c�v�Ƃ����̂́A��ɂȂ��āw�Î��L�x��w���{���I�x�ɂ���Ĝ��ӓI�ɑn�肠����ꂽ���̂ł������Ƃ����Ă悢�ł��낤�B����I�ȈӖ��ł́u�V�c�v�Ƃ����̂́A�܂����̍��͑��݂��Ă��Ȃ������B�ނ�͂����炭�������������̓����̍����̈ꕔ�ł������ɂ������Ȃ��B�Ƃ�����A���������Ă����Ƃ����钩�N�����ł́A�����A�S�ρA�V���̎O������ł��������A���̂����̂ǂ̍��Ɏ������܂ꂽ�̂��͂킩��Ȃ��B���́u����ʂŐl�X�̐������������シ��悤�Ɍv�炤��ځv�������Ă����Ƃ���A�����炭��l�̂悤�ȑ��݂ŁA���ꂪ���C����Ȑ��i�̂䂦�ɁA���{�֍��J���ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���̌�́A���������B
�@���{�ɗ��Ă���A���Ȃ��͋��J�𖡂킢�Ȃ���A�����A��i���ł��������{�̂Ȃ��ŁA���Ƃ╶���������`���܂����B���̉��ŁA������ɐ��܂�ς��܂����B���x�́A�I���U���I�̍��̔���ł��B���x�͓��{�l�ɂȂ��Đ��܂�ς��܂����B���{�̒n�ŁB�����Ē��N�����⒆���Ƃ̉˂����ƂȂ�A���{�l�ɍ��ۓI�Ȏ�����������܂����B�����A��ォ��ޗǂɂ����Ă̒n�����_�ł������̂ŁA�����ł����̒n�ɒa�����܂����B(2011.06.07)
�@���N��������Ƒ��ƈꏏ�ɓ��{�֍��J���ꂽ���́A���x�͂U���I�̓��{�ɐ��܂�ς���āA�u���ی𗬁v�ɐs�͂��邱�ƂɂȂ����悤�ł���B���́u���ی𗬁v�Ɋւ���Ă����Ƃ����̂́AA�t���牽�x���J��Ԃ���Ă��邩��A���̂悤�Ȏ������������̂�������Ȃ��B�����āA���̎��̉Ƒ��ɂ́A���T���܂܂�Ă����悤�ł���B���̏ɂ��ẮA���̑O�N�ɂ��A���̂悤�ɏq�ׂ��Ă����B
�@���{�̔���ɂ����܂�ς��܂����B���{�����N�����⒆���ƍ�����ɍs���悤�ɂȂ������ł��B�����̌𗬂ɂ��Ȃ��͈�������Ă��܂����B�������A�������[���ł��Ȃ����Ƃ͖�ڂł��s���܂���ł����B�C����l�ł����B�������A�{���ɏd�v�Ȃ��Ƃ��Ǝv�����Ƃ��́A�ނ��뗦�悵�čs���l�ł����B����w�̊��������Ȃ��Ă���O���ɋ����������Ă��āA�����⒩�N�����̐l�X�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������킷���Ƃ��o���܂����B���̂��߁A�C�O����̑�g��g�҂ɑ��āA�v�l�ȂǂƃR�~���j�P�[�V����������茈�߂��s���ۂɁA���Ȃ��͋��߂��܂����B(2010.08.17)
�@�����ōēx�A���ڂ��Ă��������̂����A�Ñ�ł͒��N�Ɠ��{�̊Ԃ��u�Ă�C�́A��ǂƂȂ��Ă����킯�ł͂Ȃ��A�ނ���u�n�C�E�G�C�v�Ƃ��Đl�X�̑D�ɂ��ړ���e�Ղɂ��Ă����B�{���̒��N�ł́A���{�̏��������ɂ�鑈���ȏ�ɁA����s����ɂ�鑈���������Ă�������A���Z�̒n�����߂đ�ʂ̈ڏZ�҂������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�������ނ�́A���{�ɒ����Ă�����L�͈͂ɍL�����āA�����������ɏq�ׂ�悤�ɁA�����炭�u�ߗׂ̎x�z�I�n�ʁv�ɂ��ꍇ�����������悤�ł���B�O���̎������̂悤�ȗ���ɏ���Ă�����l�ł�������������Ȃ��B�������͂����B
�@������ނ��n�֊C�����琣�˓��C�ɂ͂����āA���������̓��X���B�l���{�B�ɓy�������̂��X�ɑ��������ł��낤���A�ꕔ�͒��肩�玭�����{��Ƌ�B���ꏄ���ēy���̒n��T���A�܂��͎l�����ꏄ������A�I�ɔ������������A�������{�֏㗤������A�X�ɉ����ɓ�������֓��A���B�̖k�ӂɂ܂ň��Z�̒n�����Ƃ߂��������������ł��낤�B�����Ĕނ�͌��Z���ɂȂ������������Ă����̂ŁA�܂��Ȃ��ߗׂ̎x�z�I�n�ʂɂ��ꍇ�����Ȃ��Ȃ������Ǝv����B�i�O�f���A202-203�Łj
�@���̂悤�ɁA�Ñ���{�̊e�n�̎x�z�w�ł���⍋���̑唼���A���N�o�R�̓n���l�ł���Ƃ���A���̌�̓��{�ŁA�ނ炪���X�ɓ��{�̒��������Ɏ��ʂ���Ă����ߒ��ɂ����Ă��A���邢�́A����I�Ȓ����������m�����ꂽ����A���N�����̍����ƕS�ςƐV���̐��͑��������{�ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ����ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���������̒��Ŕނ�́A���ꂼ��ɁA�����n�A�S�όn�A�V���n�ƂȂ��Đ��͂��ێ����Ă������ƂɂȂ����ł��낤�B���ꂪ�A���{�̌Ñ�j�̔w�i�ɂ���傫�Ȓ����ɂȂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�������q�̑剻�̉��V�͂��̂悤�Ȕw�i�̒��ōs�Ȃ�ꂽ��吭�����v�ł������B
�@�u���n���n�̍����I�̐������e���̑c���₻�̕����ɂ������荑���̓���͂̂��߂Ȃ��B����ꂷ��ŒZ�����́A���̂�����̌n���̎����ɑ��Ă������I�ɕ�ق��Ȃ��ő勭���̑啶���ɂ����ɂ܂�����̂͂Ȃ��v�ƍ������͏q�ׂĂ��邪�A���̑剻�̉��V�ɂ���āA���{�̒������{�͎���ɖ{�i�I�Ɋm������Ă������B�����āA�ޗǕ������̂���ɂȂ��ď��߂āA�G���̌n���̖��������{�l�Ƃ��ē��ꂳ���Ɏ������̂ł���B
�@�������́A�u���q�̌n���͍����̖ŖS�Ƌ��ɂ��邢�͖S�т������m��Ȃ����A�Ƃ��������{����̋@�^�݂��������{�ŏ��̂܂��ő�̑吭���Ƃ́A�������q�ł������v�Ɛ������q�̑剻�̉��V�̋Ɛт��̂�����ŁA����ł��c�����h���ɂ��āA���̂悤�Ɏw�E���Ă���B
�@�������Ė����I�ȎG���Ȍn���͏��ł������A����͕ʂ̌`�Ŏc�������̂�����B���ꂪ���X�~�R�g�≽�X�V�c�A���X�e���̎q���Ƃ����n���ł���B�����╽�Ƃ̌n���̔w�i�ɂ������̌Ñ�ɂ����̂ڂ��ē��{�j�̓䂪����悤�Ɏv����B�����A���a�A�F���Ƃ����悤�ȕ������̓V�q��c�Ƃ��邱�Ƃ܂ł̓n�b�L�����Ă��邪�A���̕������̓V�q�Ɏ���܂ł̑�̂����ł���A��ł���B�r�����䂾�B�i�O�f���A204�Łj
�@���̂悤�ɁA�Ñ���{�̗��j�ɂ͕����ɏ����ꂽ�L�^���Ȃ������ɑ����̓䂪�܂܂�Ă���B�����āA���̋��O�̗��j����ł́A���N�⒆����N�����Ă������߂̓��{�D�ʂ̐_�b��c���j�ςŖ��߂Ă������B���R�̂��ƂȂ���A���{�������A���N�ɂ���ׂĐ����I�ɂ��A�����I�ɂ���i���ł����������͕�����ꂽ�B���A�W�A�ł̓��{�̑��݂��̂����ނ̂Ȃ��c���Ƃ��Ĕ������A���̊�b�ɂȂ�����a��������łɂQ�C�R���I�ɂ͊m�����Ă����Ƃ��Ă����̂ł���B���݂̗��j����ł��A�Ñ�̓��{�ɂ��ẮA�_�b����̘b���������Ă͂��邪�A���ɒ��N�⒆���Ƃ̊W�ŁA�c���j�ς̎c�悪�@������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@���̗��j����̕Ό��Ɉ�𓊂����̂��A�ق��Ȃ�ʌ��V�c�̔����ł���B1984�N9���A�؍��̓����̑S�l���哝�̂����{��K�₵���ہA9��6���̋{���ӎ`��œV�c���炪�q�ׂ����Ƃ̂Ȃ��ɁA���̂悤�ȕ������������B
�@�ڂ݂�A�M���Ɖ䂪���Ƃ́A��ߑѐ��̗��ł���A���̊Ԃɂ́A�Â����l�X�ȕ���ɂ����Ė��ڂȌ𗬂��s���ĎQ��܂����B�䂪���́A�M���Ƃ̌𗬂ɂ���đ����̂��Ƃ��w�т܂����B�Ⴆ�A�I���Z�A�����I�̉䂪���̍��ƌ`���̎���ɂ́A�����̋M���l���n�����A�䂪���l�ɑ��A�w��A�����A�Z�p�����������Ƃ����d�v�Ȏ���������܂��B�i�����j�ɂ킽��A�����͐[���אl�W�ɂ������̂ł���܂�������
�@�����œV�c���A�u�I���Z�A�����I�̉䂪���̍��ƌ`���̎���ɂ́v�Əq�ׂĂ���̂́A�ɂ߂ďd�v�ł���B���̍��ƌ`���̎���ɂ��ẮA���j�w�A�l�Êw�̊w��ł������������Ē�܂��Ă��炸�A�����w�Z�̋��ȏ��Ȃǂł����ʂ́A�I���l���I�i350�N���j�Ƃ���Ă����B�T�䍂�F��O�㎟�j�E�ь����Y�҂́u���E�j�N�\�v�i�g��O���فA1989�N�j���ɂ������L�^����Ă���B������A�V�c��200�N����300�N�x�点���̂ł���B�V�c�̂��Ƃ́A���Ƃ��A���{�̍ō����x���̐l�����ɂ���āA���낢��ƌ������ꂽ�����ł̔����ł������ł��낤�B���ꂾ���ɁA���̔����́A���{�̗��j����̏�ł��傫���C���𔗂���̂ɂȂ����B
�@���Ƃ��A��Ƃ̋��B���́A�w���{�Ñ�j�ƒ��N�x�i�u�k�Њw�p���ɁA1985�N�j�̂Ȃ��ŁA������A�}����j����̕ҏW�ɂ�鍂�Z���ȏ��w�ڐ� ���{�j�x�́u���N�����ւ̐i�o�v�Ƃ��������ɂ����ĉs���ᔻ���Ă��邪�A���̋��ȏ��ɐ����Ă���͎̂��̂悤�ȋL�q�ł���B�i291�Łj
�@��a����͎l���I�㔼����ܐ��I���߂ɂ����āA�������Y�Z�p��S�������l�����邽�߂ɒ��N�����ɐi�o���A�܂������ƌQ�̂܂܂̏�Ԃł����������암�̕ي؏��������̐��͉��ɂ����߂��B���ꂪ�C�߂ł���B��a����͂���ɕS�ρE�V�����������A�����Ƃ�������B
�@���̋��ȏ��̋L�q�͖��炩�Ɏj������͂ݏo�Ă��Ă��������B�V�c�̂��Ƃɂ��A�u�l���I�㔼����ܐ��I���߁v�ɂ́A�܂����{�ɂ͓��ꍑ�Ƃ��������Ă��炸�A�ي؏��������̐��͉��ɂ����߂���͂����Ȃ������B���B���́A�u�ي؏����v���̂��̂��ԈႢ�ŁA�u�l���I�㔼�v�ɂ́A�������́u�ي؏����v�Ȃ���̂͑��݂��Ă��Ȃ������ƒf�肷��B�����āA�V�c�̂��Ƃ̂Ȃ��ŁA�u�����̋M���l���n�����A�䂪���l�ɑ��A�w��A�����A�Z�p�����������Ƃ����d�v�Ȏ���������܂��v�ɂ��Ă��A�u�������v�Ƃ���̂́A�^���ł��Ȃ��Ƃ����B���{�ɂ���Ă����n���l�͐V�V�n�����߂Ď��R�ɂ���Ă����̂ł����āA�u������v���߂ɂ���Ă����̂ł͂Ȃ��A�Ƃ����̂����B���̎咣�ł��邪�A����́A���̌܌o���m�̔h���Ȃǂ��O�Ƃ��āA�{�e�ł���܂ł݂Ă������Ƃ�����A�����͂�����Ƃ�����ł��낤�B
�@�O�f�́u���E�j�N�\�v�ł́A�u513�N���ɕS�ς����{�Ɍ܌o���m�𑗂�v�ƋL�^����Ă��邪�A����́A�`���ɂƂ肠�����O���̕���́u�܌o���m�v�̐��x�����łɕS�ςł͒蒅���Ă��āA���ꂪ���{�ɑ���ꂽ�Ƃ������Ƃł��낤�B�������A���̏ꍇ�����{�ł͂܂����ꐭ���͎�������Ă��Ȃ������B��a���������Ɍ����Ă̊�b�ł߂��i�߂��Ă���i�K�ŕS�ς����x�̐����ɏ��͂����Ƃ������Ƃł���B������A�u���N������{�ցv�Ƃ������o�ł͂Ȃ��A�����炭���Ԃ́A�S�ϐl�����{�ɓn���Ă��������̕S�ϐl�̂��߂ɁA�Ƃ����F�������Z���̂ł͂Ȃ��������B�u�����암�̕ي؏��������̐��͉��ɂ����߂��B���ꂪ�C�߂ł���v�Ə�����Ă��邻�́u�C�߁v���A�O���̂Ȃ��ŏ�������������̗̓y�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��āA���Ƃ��炠���������̐��͂����߂����J��[�߂��Ƃ����悤�ɑ�����ׂ���������Ȃ��B
�@�����ł�����x�悭�A���N�����⒆������̓n���l�̓�����U��Ԃ��Ă݂����B���̖��J�̓��{���C����悭�������L���ŕ�炵�悢�Ƃ����āA���ɖڂƕ@�̒��N��������͈�Ƃ�ꑰ���܂Ƃ߂Ĉڂ�Z�ގ҂���������r��邱�ƂȂ��Â��Ă����B�����āA�\�N�A�S�N�Ƃ������ɁA���̓��̓삩��k�̉ʂĂ܂ŁA�R���ɂ��ÁX�Y�X�ɂ��A�ނ炪�Z�݂��A����ɕ邵�ɂ����Ȃ����̂ł���B�����ŐV�������肱��A�����̍k�n���Ђ낰�邽�߂ɁA�������N��悤�ɂȂ����B
�@���������������^���ɂȂ�ƁA��Ƒ���A�ꕔ���̗͂ł͎����̈��Z�̕ۏႪ������Ȃ�����A����ɑ傫�Ȓc�������ԕK�v���N���Ă���B���̂悤�Ȓc���̍Ō�̂��̂Ƃ��Č`���Ƃ�̂́A���̓����ֈڏZ�O�̍��Ђɂ���邱�Ƃł���B��O����ɈڏZ���ďZ�݈Ղ����Ɉ��Z�̒n�����Ƃ߂Ă������Z���������A���߂ĈڏZ�O�̍��ЂŒc������K�v���N�����̂ł���B���̌��ʂƂ��āA�e�c�����Ƃɋ��͂Ȏ�̂��K�v�ƂȂ����B�����Ċe�X�̎�̂͒��������𑈂����߂ɁA�e�X�̒n���̕����I�Ȓc������ۂƂ���K�v�����������A�{���̐��͂ƌ��ԕK�v���������B�����炭���̂悤�Ȏ���A���̋��ȏ��ł́u��a���삪���N�����ɐi�o���A�܂������ƌQ�̂܂܂̏�Ԃł����������암�̕ي؏��������̐��͉��ɂ����߂���A�S�ρE�V�����������A�����Ƃ�������v�A�ƕ�������Ă��܂��Ă���̂ł��낤�B
�@�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�I���l���I�㔼����ܐ��I���߂ɂ����ẮA�܂��u��a����v�Ȃ���̂͐������Ă��Ȃ������B�������A���̂��Ƃ������̓��{�ƒ��N�����⒆���Ƃ́u���ی𗬁v��W�������Ƃɂ͌����ĂȂ�Ȃ��B�ނ���A���{�e�n�Ɋ������鍋�����R���ɋ��菟���Ē����W����ڎw���Ă������߂ɂ́A�����̐�i���ł��钩�N�⒆���Ƃ̌��т����������K�v�ł������Ƃ����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B���̂悤�Ȕw�i�̒��ŁA�Ñ���{�ɂ����鎄�̑O���́A���̂悤�ɂ�������Ă���B
�@��l�Ƃ���g�ł����B���ƍ��A�����Ɩ����Ƃ̊Ԃ₵����A����������悤�Ɍv�������A���邢�͕����⋳��A�Ƃ��ɋZ�p�̖ʂŌ݂��̍����������A�ɉh���邽�߂ɗ͂�s�����܂����B�Ñ�̓��{�̑�a����̎���ɂ́A���N�����Ɠ��{�Ƃ̊Ԃō������n�܂�A���N�����̂ق�����Z�p�╶�����A���l�ƂȂ����l�����������炵�Ă��Ă��܂��B���̂���̎���A��l�͓��{�ƒ��N�����Ƃ̊ԂŁA�݂��ɗL�v�ƂȂ�悤�ɁA�܂��o�����X���Ƃ��悤�ɁA�v�炢�܂����B����������́A�Ȃ��Ȃ�������Ƃł��������̂ł��B�I���S���I����T���I�ɂ����Ă̍��ł��B�_�{�c�@���炻�̑��q�̉��_�V�c�ɂ����Ă̎���ł��B�i2000.06.03�j
�@�Ñ���{�ł̑O�����펯�I�Ȍ���p��ŏq�ׂ���ƁA�ǂ����Ă�����敪�Ȃǂ̂����}������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�����ɏo�Ă���u��a����v�̂ق��ɁA���N��������́u�A���l�v�Ƃ����\���������炭���Ԃɂ�����Ȃ��B���������A���̍��̒��N�����Ɠ��{�Ƃ̌𗬂ł́A�������̓n���l�͂����Ă��A�ނ�́u�A���l�v�ł͂��肦�Ȃ��B�������A�I���S���I����T���I�ɂ����Ă̍��A�u���ی𗬁v������ł������Ƃ������Ƃ͗����ł��邵�A���ƌ��T�����̂悤�Ɂu���ی𗬁v�ɐs�����Ă����Ƃ����̂��A���łɋL�ڂ��Ă������̂��܂߂āA���x��A�t�ɂ���ē`�����Ă��邩��A����������Ĕے肷�邱�Ƃ��Ȃ��ł��낤�B����A�t�ɂ�鎄�ƌ��T�Ƃ̑O���́A�Ȃ����̂悤�ɑ����B
�@�����̂ق��Ƃ̍������n�܂��Ă��܂����B���Ȃ��͎�ɒ����̂ق��Ƃ̊Ԃł̍��ی𗬂Ƃ������ƂŖ�ڂ�����܂����B�ނ̕��́A���N�����Ƃ̊ւ��ŐӔC������܂����B�����̐��E�Ƃ����A���{�ɂƂ��Ē����⒩�N�����ł����B���Ȃ��͒����Ƃ̍����̂ق��ŖZ�����A�ӔC���d�������̂ŁA�قƂ�ǂ�����ɖZ�E����Ă��܂����B���N�����Ƃ̍����͂Ȃ��Ȃ���������͂��ł��āA�ނ͂ƂĂ���ςł����B���Ȃ��͉��ƂȂ��C�ɂ͂Ȃ��Ă�������ǂ��A�����̂ق��ł�������킳��āA�Ȃ��Ȃ��ӎ���ނ̂ق��Ɍ����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B
�@ ���Ȃ��͔ނ��܂߂āA���l�����\�l���̋K�͂́A���ی𗬂ɖ�ڂ̂����g��O�����̂悤�Ȑl�����̂܂Ƃߖ��A�܂���Ė��̐e�Ƃ�������ɂ���܂����B�ނ��܂߂ĉ��\�l���̎g�߂Ŕh�������҂����̈琬�ҁA�܂��w���҂������̂ł��B���{�ΊC�O�ł̌𗬂̔h������̂��Ȃ��͌����ߓI���݂ł����B�ނ̂��Ƃ́A���ڂ̑��q�ł͂Ȃ������悤�ł����A�ƂĂ��L�]�ł���ƌ��Ȃ��A�ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂����B���N�����Ƃ̍������n�܂����̂ŁA�ƂĂ�����͓��{�ɂƂ��Ă��d�傾�Ǝv���A�L�\�ŏ����L�]������Ă����ނ�������ɐU������邱�ƂƂȂ�܂����B�i2000.06.03�j
�@�Ñ���{�ɂ����鎄�ƌ��T�̑O���́A���̂悤�ɑ哯���ق̓��e�̂��̂��J��Ԃ��`�����Ă����B�����āA�Ō�ɓ`����ꂽ�̂��A���̂悤�ȓ��e�ł���B������A����܂łɓ`�����Ă������̓��e�ƂقƂ�Ǖς��͂Ȃ��A����_�C�W�F�X�g�ł̂悤�Ȍ`�ɂȂ����BA�t�́A�����̋L�^���F���̃A�J�V�b�N����R�[�h����ǂݎ���Ă���Ƃ����邪�A���̂��߂ɁA���x�ǂݎ���Ă������悤�ȓ��e�ɂȂ�̂͂���Γ�����O�ŁA�������}�ȗ�\�͂�����A�t�����炱���ׂ�����Z�Ƃ����ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�̂̒��N�����⒆���ƁA��x�قǐ��܂�ς��̂Ȃ��ŁA���Ȃ��͂�����肪����܂����B��x�ڂ́A���{�̌Õ�����A���m�V�c�����{�����߂Ă������ł��B���Ȃ��͊w��̑��w���[���A�m�b�҂Ƃ��č�����������߂�ہA�Ă�q�˂��邱�Ƃ����x������܂����B�ӂ���́A���{�����ŋ���̔C�ɓ������Ă��܂����B
�@���̓����A���T����́A�w�p�I�Ȍ����ɏ]�����n�߂Ă��܂����B���{�����ێЉ�Ƃ��āA�m�����邽�߂ɓ��{�̍����̋��烌�x�����グ�邱�Ƃ��ނ̔O��ł����B���Ȃ��͂��̂悤�Ȕނ𗊂������v���A���҂��āA�t���Ƃ��āA�܂����e�Ƃ��Ďv�������Ă��܂����B�����āA���ۂɂ����Ă����Ă��܂����B
�@��x�ڂ̐l���́A����ł��B���ÓV�c�����{�̍������߁A�������q���ږ�ɓ������Ă�������ł��B���Ȃ��͊ē҂ł����B�����̒����⒩�N�����Ƃ̕����𗬂ɂ����Ďg�߂�h������ہA���Ȃ������߂�����v������肵�Ă��܂����B���̎��ɂ����T���T�ɂ��āA�O�����̈�l�Ƃ��Ĉ琬����A��x�قǁA���N�����ɔh������܂����B���̂悤�ɂ��Ȃ����e�q�́A�w��Ǝg���̗����Ő[���ւ���Ă����̂ł��B(2012.06.06)
�@�I���R�A�S���I�̍��Ƃ͈���āA6���I����7���I�ɂ����Ă̔���ɂȂ�ƁA���ی𗬂̃C���[�W�����Ȃ�͂����肵�Ă���B�܂���a����̊�b���ł܂����A���ÓV�c�̎��A�������q������̌��@�g��h�����Ă���B����͓��{���ɂ͋L�^���Ȃ����A�w�@���x�ɂ����600�N�̂��Ƃł��������Ƃ��m�F����Ă���B�����đ���̌��@�g���h�����ꂽ�̂�607�N�ŁA���̎��͏��얅�q����g�ł������B�u���o�Â鏈�̓V�q�A������v���鏈�̓V�q�ɒv���v�Ƃ����A�w�L�т����V�����Ƃ̋C�����ƍ��g���̟��ލ������g���čs�������Ƃł��m���Ă���B
�@���̌��@�g�͂��̗��N608�N�ɂ��h������A���̌�A�������q��622�N�ɖS���Ȃ��Ă�����A630�N�ɍ��x�͌����g�̂������ŁA�����c�L���g�Ƃ��Ĉ����p����Ă������ƂɂȂ����B���̂����肩��A���w���E���������A���w�m�E�앣�����ȂǁA�����̖��O���o�Ă���悤�ɂȂ�BA�t�̂����邱�Ƃ����̂܂~�߂�A���ƌ��T�́A�������q�����߁A�����̗��w���A���w�m�����Ƃ��A�����炭�A�ɂ߂ċ߂�����ɋ����݂̂Ȃ炸�A���ی𗬂Ƃ����E���ɐ[���ւ���Ă����Ƃ����Ӗ��ł́A�قƂ�ǐg���̂悤�Ȑe�����W�ɂ������Ƃ����Ă����̂�������Ȃ��B
�@�@(2012.11.01)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@�@�@�e�a�̑��͐M�̋����ɂ���
�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z(85)�\
�@�e�a�̎t�̖@�R��12���I�O������13���I�̏��ߍ��̐l�ŁA�e�a���͎l�\����N��ł����B���@�̐��ɐl�X���~����ɂ́A�O�����ق��ɂ͂Ȃ��Ɛ����āA�킪���ɏ�y�@��n�߂��c�t�ł��B���Ƃ��Ɣ�b�R�ɂ����Ē��N�C�s�ɗ�݁A��b�R�̍���ɂȂ邱�Ƃ����҂���Ă����قǂ̊w���L���ȏG�˂ł������A���O�̔敾�����Ԃ�ɖڂ������悤�Ƃ͂����A�M���̂��߂ɂ̂ݕ�d���Č������v��}�铖���̕����ɂ͐[���^��������n�߂�悤�ɂȂ�܂��B���̖@�R���A�����̑P����t�́w���o�a�x��ǂ�ł��āA���̂Ȃ��́u��S�ɂ����ς爢��ɂ̖�����O���邱�Ƃɂ���ď�y�ɉ����ł���v�Ƃ������ƂɐG�����ꂽ�̂��A�@�R�̉�S�̎n�܂�ł������Ƃ����Ă��܂��B
�@���̂悤�ɁA�@�R�́A�����̌o�T����P����t�̂Ђƌ��ɐG��āA����ɕ��Ƃ������ɏo��A����܂łɊw���Ƃ̂��ׂĂ𓊂��ł��Ĉ���ɕ��ɋA�˂���悤�ɂȂ�܂������A�����̕����̂�����ɋ^�������Ă����e�a���܂��A���̖@�R�̎v�z�Ƌ����ɋ����䂩��Ă����܂��B�₪�āA����܂ł̔�b�R�ł̊w���C�s�̂��ׂĂ𓊂��ł��āA�g���ɂ������@�R�̑����ɒʂ��悤�ɂȂ�A��q�����F�߂��܂��B�e�a�́A�V�Q�҂ł��N�����M�S�Ő^���Ȗ@�R�̐M�S�̗����҂ł������A���̂悤�Ȑe�a�́A���͔O���̐M�S�̐[�����}�b���w�V�ُ��x��\�����ɂ��c����Ă��܂��B
�@�����ł́A�e�a�Ƒ��̒�q�����̊ԂŁA�M�S�ɂ��ċc�_���ꂽ���Ƃ��q�ׂ��Ă��܂��B�����͂܂��P�M�Ƃ������O�ł������e�a���A�P�M�̐M�S���t���̖@�R��l�̐M�S�������ł���ƌ��������Ƃ���A���̒�q�������猃�����������̂ł��B�@�R�ɂ����ẮA�M�S���܂��u���́v�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł����A���̐M�S�����͂ł���Ƃ������ߕ��́A�O���ɖڊo�߂��@�R�̍��킽���̊Ԃł��A���܂�e�Ղł͂Ȃ������悤�ł��B
�@���̕����́A���Ƃ��g��p���́w�e�a�x�i�u�k�ЁA1993�N�j�ɂ́A�@�R�̍��킽�����M�S�̐��ɂ��āA���낢��Ƌc�_���Ă����ʂƂ��āA���グ���Ă��܂��B�u��X�́A�ЂƂ�����y�ɐ�����Ƃ������z�������Ă���B����ǁA�}�v�̌�X�Ǝt�̏�l�i�@�R�j�Ƃ́A�M�S�̐����ǂ����Ă��Ⴄ�͂��ł��B����́A���ɂȂ�����t�̏�l�̂悤�ȐS���ɂȂ��āA�^�̈��S�������邾�낤���ƍl�������Ȃ�v�ƁA���鍂�킪�����āA�����ނ�ɂƂ��Ă͐V�Q�҂ł������e�a�ɁA�u�������ł��A�P�M��V�v�ƈӌ������߂܂����B����ɑ��āA�Ⴋ���̑P�M�i�e�a�j�́A����������̂ł��B
�@�u������\���܂ł��Ȃ����ƂƎ��͎v���B�ЂƂ��ё��͐M�S�̂����Ƃ��������Ă���A���́A����Ȗ��ɍ����܂Ŗ��������Ƃ͂���܂���B���̂����́A�t�̏�l�̐M�S���A���͂ɂ���Ď��Ƃ���̂��́B�ǂ��ɂ��̗��҂ɂ�����������܂��傤�B�ہA�t�ƒ�q�݂̂ł͂Ȃ��A���͖�̐M�S�́A���ׂĈ�ł����āA�Ⴂ�������Ă͂Ȃ�ʂƎv���̂ł��B�v
�@�Ⴋ���̐e�a�́A�@�R��l�ɂ���ׂ���A�w����l�i�̏�Ŏ����͏�l�̑����ɂ��y�Ȃ����A�������A�M�S�ɂ��ẮA�������ƌ�������܂����B�������A���̐e�a�̂��Ƃɂ́A�܂��݂̂�Ȃ͙G�z�Ƒ����Ĕ[�����܂���ł����B�����ŁA�ꓯ�́A�t�̖@�R�̑O�ɏo�āA�t���������̓��������߂��̂ł��B����ɑ��āA�g��p���͂��̖{�̂Ȃ��ŁA�t�̖@�R�ɂ�����点�Ă��܂��B�ipp.402-403�j
�@�u�l�ɂ��A�M�S�ɈႢ������Ɗς�̂́A���͂̐M�S�̂��Ƃ������̂���B�q�d�Ƃ��A�g���Ƃ��A�j���̍��Ƃ��A�����������̂����{�ɂ��čl���邩��A�M�S���܂��A�q�d�A�����Ȃǂɂ���āA���̂�����̂ƍl�����Ă���B�\
�������A�O����̑��͂̐M�S�Ƃ������̂́A�P���̖}�v�A�݂ȓ������A���̂�����苋���M�S�ł����āA�݂�����̒q�d�⋫���̗͂Ɉ˂��Ă��݂Ƃ�M�S�ł͂Ȃ��̂ł�����B�\�䂦�ɁA�@�R���M�S���A�P�M���M�S���ς�͂Ȃ��͂��B�M�S�ɕς肠��ƍl���Ă��킷���X�́A���̖@�R���Q���y�ւ́A����Ƃ肨���Ă��A������X�Q�苋�����Ƃ͂��̂��܂��Ɂc�c�B�悤�������Ǎl���Ă݂�ꂢ�B��������Ƃ��J��Ԃ��悤�ł����邪�A�������ǂ����ł��\�����B�O���͐�Α��͂̋����ł���Ƃ������Ƃ��v
�ŋ߂ł́A�ܖ؊��V������w�e�a�x�i�u�k�ЁA2010�N�j���o���Ă��܂����A�����ł́A���̐M�S�̈Ⴂ�ɂ��āA�@�R���e�a�ɐq�˂邩�����ɂȂ��Ă��܂��B�@�R�́A�u���@�ɂ��āA���l�Ƃނ�݂ɖ@�_���������킹��̂́A�悭�Ȃ��B�������A���ԓ��m�łӂ���̋^���^���Ɍ�荇�����Ƃ͑厖�ł��낤�B�����ōŌ�ɂЂƂA�����Ă��������v�ƌ��������ƂŁA�ЂƑ�����āA�����₩�Ȍ����Őe�a�i�����ł́A�͉��Ƃ������O�ɂȂ��Ă��܂��j�ɐq�˂�̂ł��B
�@�u�킽���͓��X�˂ɔO�������ɂƂȂ��ĕ�炵�Ă���B���̖@�R�̔O���ƁA���Ȃ����ƂȂ���O���Ƃ́A�͂����Ă������Ƃ��낪����ł��낤���B����Ƃ������O���Ƃ��āA�ς��Ƃ��낪�Ȃ��̂��B�ǂ�����v�@����ɑ��āA�͉��͂��炭�l�������ƁA�u�����O���ł������܂��傤�B���������ς��Ƃ���͂Ȃ��Ǝv���܂��v�Ɠ����܂����B���̓����́A�܂��ɂ��鍂�킽���ɂ́A�t�̖@�R��`�����邱�Ƃ̂悤�Ɏ���܂����B���̗l�q���A���̖{�w�e�a�x�i���j������p����ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B
�@�u�Ȃ�Ɓ\�@�v
�@�@�{��̐����������B�����͕���͂Ă��Ƃ�������ɐO���䂪�߁A����ӂ��Ă���B
�@�u���y�[�́A���͉̔��̈ӌ����ǂ��v���H�v
�@�@�R���������B�����͌����ɓ������B
�@�u�Ƃ�ł��Ȃ��v��������ł������܂��B���_����C������܂���v
�@�u�悭�A���̂悤�Ȃ��Ƃ��v
�@�ƁA���Ř@�����̂̂悤�ȚX�萺���������B
�@�u�䖝���A��������܂ł���v
�@�����Ȃ�Ƃт��������@��̌����A�ł��̂悤�ɔ͉��̊��A�ł����B
�@�u��߂�A�@��v
�@�@�R�̐����������Ђт����B�����قǂ܂ł̂����₩�Ȑ��Ƃ͂܂������������A���̕��ғ��̂悤�Ȗ쑾�����������B
�@�u�킽���̔O�����A�͉��̔O�����A�����Ę@��⓹���̔O�����A�����ɂ����܂邷�ׂĂ̐l�тƂ̔O�����A���ׂĂݕ��Ƃ̂����ɂ���Ă��܂��O������B����ɔ@�����炽�܂�����O���ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�����v���A���̖@�R�[����̔O�����A���Ȃ������̔O�����A�܂����������O���ł��낤�B�͉��Ƃ��A�悤�������B���傤���炻�Ȃ����A���̖@�R�̒��Ԃ̈�l�Ƃ��@�ċg���Ɍ}���悤�B�v�ipp.61-62�j
�@���̂悤�ɐe�a�́A�Ⴂ�������瑼�͔O���̈Ӗ���[���������Ă��܂������A���ꂾ���[���A�@�R�̐l���Ƌ����ɌX�|���Ă����Ƃ������Ƃł��傤���B���ꂩ�玞���o�āA�@�R���������ēƎ��̓�����݂͂��߂��e�a�̐M�S�ɂ��āA�w�V�ُ��x�̑����ɂ́A���̂悤�Ȃ��Ƃ�����܂��B
�@�u��ɔ@���̖{�肪�^���ł���Ȃ�A�ߑ��̋����������ĉR�ł͂Ȃ��B�ߑ��̋������^���ł���̂Ȃ�A�P����t�̂������ɂȂ������Ƃ������ł���͂��͂Ȃ��B�P����t�̂������ɂȂ������Ƃ��^���ł���̂Ȃ�A�ǂ����Ė@�R��l�̂����邱�Ƃɂ܂₩�������낤���B�����āA���̖@�R��l�̂����邱�Ƃ��^���ł���̂Ȃ�A���̐e�a�������Ă��邱�Ƃ������ċł͂Ȃ��̂ł��v
�@����́A�M�S�ɖ���������n�߂��M�҂������e�a��K�˂Ă��āA�O���ȊO�ɂȂɂ��Ɋy��y�։����ł�������̂ł͂Ȃ����Ɩ���āA�e�a�����������Ƃł��B�����ł͐e�a�́A�u���͂����A�t�̖@�R�́A�O�����̂��Ĉ���ɕ��̂������ɂ�������Ƃ������Ƃ����̂܂܋^�����Ȃ��M���ĔO�����̂��Ă��邾���Ȃ̂ł��B���̂ق��ɂ͉����Ȃ��B�����A�@�R��l�ɂ��܂���āA�O�����̂����������ɒn���ɑ���Ƃ��Ă��A���炳�����͂��܂���v�Ƃ܂ŏq�ׂāA�����M�S����l���Ă��܂��B
�@����ł́A�e�a������قǂ܂łɋ������悤�ɂȂ������͂̐M�S�́A���͂Ƃ͂ǂ̂悤�ɈႤ�̂ł��傤���B�Ⴆ�A���ܖڂ̑O�ł킪�q���r�̐��ɗ����ēM�ꎀ�ɂ����ɂȂ��Ă���Ƃ��܂��B�u���́v�Ƃ����̂́A�r�̂Ȃ���e�̂悤�Ȃ��̂ŁA������߂�����������ł��A��������L�ׂĂ킪�q���~�����Ƃ��ł��܂���B�~�����߂ɂ́A�킪�q����������ƒ͂ނ��Ƃ̂ł��鈢��ɕ��̖����ɑ傫�Șr���K�v�ŁA�u���́v�Ƃ́A���̘r�ɗ��邱�Ƃł��傤�B����A�l�̗͂ƕ��̗͂̈Ⴂ�ł��B���̈Ⴂ���A�w�V�ُ��x�̑�l���ł͂��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@���������A���̐��ŁA��������ꂾ�A���������Ǝv���Ă��A�Ȃ��Ȃ��A�����Ƃ���������̂��ׂĂ���������������̂ł͂Ȃ��B���͂ł́A�l�Ԃ̗͂ɂ͌��肪���邩��A���������Ƃ����C�����������Ă����r���[�ŏI����Ă��܂��B����ɑ��āA�u���́v�ł́A���̐��ɂ���Ԃ́A�O�����̂��Ĉ���ɔ@���̖����̗͂ɂ�����A���̂����I����Ă���́A���ɂ��Ȃ��厜��߂̂�������āA�v�������ɁA������l�X���~�����Ƃ��ł���̂ł���B
�@�����āA���̈���ɔ@���̖����̗͂ɂ����邽�߂̔O�����A���͂��O�ꂵ�Ă����A�u�O���͍s�҂̂��߂ɔ�s�E��P�Ȃ�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����́A�w�V�ُ��x�攪���̂��Ƃł����A�O�������ďC�s��ς�ł����Ă��A����́A�������C�s���Ă���̂ł͂Ȃ��A����ɕ��̗͂ŏC�s�������Ă���̂�����A�s�ł͂Ȃ��A�܂��s�ł���Ƃ����̂ł��B�܂��A�O�������邱�Ƃɂ���đP���ׂ��Ă������ł��A���́A���̔O���͈���ɕ����瓭���������ď������Ă���킯������A�����̑P�ł͂Ȃ��A�܂�A��P�ł���Ƃ����̂ł��B���̂悤�ɁA���͂ł͂Ȃ����͂�O�ꂵ�ċ������Ă���̂��A�e�a�̎v�z�ł���Ƃ����Ă����ł��傤�B
�@��Z���́A�u�e�a�͒�q��l�����������ӂ�Ӂv�������ł��B�����̗͂ŔO��������������悤�ɂ����̂ł���A���̐l�������̒�q�Ƃ����Ă������̂�������Ȃ����A���ׂĈ���ɕ��̓����ɂ���ĔO���ɖڊo�߂Ă����l���A�����̒�q�ȂǂƂ����̂͂Ƃ�ł��Ȃ����Ƃł���B������A�e�a�͒�q�͈�l�������Ă��Ȃ��A�Ƃ����Ă���̂ł��B���̑�Z���ɂ́A�u�@����肽�܂�肽��M�S�v�Ƃ������Ƃ�����܂����A�M�S�ł����A�����������̈Ӑ}�ŐM�S���Ă���̂ł͂Ȃ��A���́A���̐M�S�͔@������^�����Ă���̂��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@���̑��͂̋����ł́A��\�O���̂悤�ɁA�킩��Ղ��������܂��B�����ł́A���̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B
�@���鎞�A�B�~�́u���Ȃ��́A���̌������Ƃ��^���Ȃ������邩�v�Ɛe�a�������āA�u�͂��v�Ɠ����܂��B�e�a�͏d�˂āA�u����Ȃ�K���A���̌����Ƃ���ɂ��邩�v�Ɛu���Ă��܂����̂ŁA�u���̒ʂ�ɂ������܂��v�ƕԎ������܂����B����Ɛe�a�́A�u����Ȃ�A�l���l�E���Ă���Ȃ����B��������A�K���~������Ă��炦�邪�v�ƁA�v�������Ȃ����Ƃ������o�����̂ł��B�������̗B�~���A�u�����Ƃł͂������܂����A���̗͂ł́A��l�͂��납�A��l�����ĎE�������ɂ͂���܂���v�Ɠ����܂����B�����ŁA�e�a�͌����܂��B
�@����Ȃ�A�Ȃ��e�a�̂����Ƃ���ɂ���ƌ������̂��B����ł��킩��ł��낤�B�������v���̂܂܂ɏo����̂Ȃ�A�~���ɂ������邽�߂ɐ�l�E���悤�ɂ���ꂽ��E���ł��낤�B�������A�����ɂ͈�l�ł��E���Ƃ��Ȃ�����E���Ȃ������ŁA�E���Ȃ��̂́A�Ȃɂ������̐S���P�ł��邩��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�܂��A���̔��ɁA�E���C���S���Ȃ��Ă��A�S�l�A��l���E���Ă��܂����Ƃ��A�Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��̂��B
�@�����̍s�Ȃ����Ƃ́A������̗ǂ����������Ō��߂���̂ł͂Ȃ��B����ɕ��̕s�v�c�Ȍ����̗͂ɂ���Č��߂��Ă���̂Ɏ������͋C���t���Ă��Ȃ��������Ƃ������͂̋������A�����ł��e�a�͓`���Ă���̂ł��B�w�V�ُ��x�͒��Õ��̋����������̂����ɕ����p�ꂪ�����ǂ݂Â炢�ʂ�����܂����A����ł��A���̂悤�ɗv�_���E���Č��Ă���ƁA�����́u��ɂ̐���s�v�c�ɂ������܂��点�āA�������Ƃ���Ȃ�ƐM���ĔO���܂�����Ƃ�������������̂�����Ƃ��A���Ȃ͂��ێ�s�̗̂��v�ɂ��Â����߂��܂��Ȃ�v��u��ɂ̖{��ɂ͘V���P���̐l������ꂸ�B�����M�S���悤�Ƃ��Ƃ���ׂ��v���w�V�ُ��x�̑S���ɗ���镚���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�悭�����ł���悤�ȋC�����܂��B
�@(2012.09.01)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@�@�C�M���X�ɂ�����O���ւ̉���
�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z(84)�\�@

�@���`�F�X�^�[�̒��S�X�ɂ���u�������Â̊فv
�@����1�N�ԏZ��ł����ԁA�U���̓r���悭���̑O��
�@�ʂ�A���̌��������x���ʐ^�Ɏ��߂Ă����B
�@�߂��ɂ́A���B�N�g���A������1837�N��18�ő��ʂ�
�@�钼�O�ɔ��܂����Ƃ��������ȃz�e�����c����Ă���B
�@����1991�N�t�����N�ԏZ��ł������`�F�X�^�[�̊X�́A�����h���̃��B�N�g���A�w����P���g���ɏ���āA�J���^�x���[�������r���ɂ���B�����h���ɒ���������̂���A��T�Ԃ��炢�́A�����h����w�ŗp�ӂ��Ă���Ă�����p�����قɋ߂��h�ɂɔ��܂��Ă����B���̊ԂɁA�����̊w�������T���Ă����Ă��ꂽ��w�t�߂̃A�p�[�g������ē����Ă��ꂽ�B�s���Ă݂�ƁA�ʋɕ֗��Ȃ̂͂����̂����A�܂��͐Α���̍�����������ŁA�ǂ�������ɂ͋C�ɓ���Ȃ��B�����l�܂�悤�ȋC�������B���͍x�O�֏o�����āA�����ő{�����Ƃɂ����B�����ŁA�����^�J�[�ŃJ���^�x���[�܂ŏo�����āA���̋A�r�A����������̂��u���j�̊X�v�Ƃ����郍�`�F�X�^�[�ł������B
�@������܂�Ƃ����X�̒��S���ɂ͏�ǂɈ͂܂ꂽ�Ï邪����A�C�M���X��2�ԖڂɌÂ��Ƃ������`�F�X�^�[�吹���������藧�B���̑O�������̊X�ʂ���v�킹��悤�Ȓ��S�X�n�C�E�X�g���[�g�ŁA�̖̂ʉe�����Ɏc���Ă���B���̊X�̗l�q�́A���̃C�M���X�̑�\�I�ȏ����ƁE�`���[���Y��f�B�P���Y�i1812-1870�j�����x�ƂȂ���i�Ɏ��グ�A�ʂ�⌚����X�̕ǂȂǂɁA���̍�i���������ł��͂ߍ��܂�Ă����B���́A���̎�̂���Â��X������܂��Ȃ���A�Ȃ�ƂȂ����������v�������Ă����B�ǂ����ɉ�����������������B���͉��̖������Ȃ������ɏZ�ނ��ƂɌ��߂āA����2�A3����ɂ́A���O��́A�ՐÂȏZ��X�̂Ȃ��̈ꌬ�Ƃ��肽�B
�@���̉Ƃ́A���{�ł����RLDK�ŁA�����͌Â��̂����S�قǂ�����������Ő��̒낪��蕿�ł������B�ł���ΐ��̂��镗�i���Ɩ]��ł������A�Ƃ̂��ɂ̓��h�E�G�C�Ƃ����L���삪�Â��ɗ���Ă���B������2�A3���ȓ��ɋ���Ɩ�ǂƎO�̐H���G�ݓX������A���̂����̈�́A�X�̉��������ȗX�ǂɂȂ��Ă���B5���ȓ��̋����ɂ́A���w�Z�ƁA�����ƁA������̎G�ݓX������A�C�M���X�����̃p�u���A�����Ƃ������̂��ꌬ�������B�Ƃ���S���[�g�����炢�̂Ƃ���Ƀo�X�₪����A�������炠��2�K���Ẵo�X�ɏ��ƁA10���قǂŁA�X�̒��S����ʂ��ă��`�F�X�^�[�w�ɒ����B�������烔�B�N�g���A�w�܂œd�ԂŖ�35���A�����Œn���S�ɏ�芷���āA�����h����w�̂���s�J�f���[���̃��b�Z���E�X�N�G�A�[�w�܂ł�20���قǂ̋����ł������B
�@���̃��`�F�X�^�[�̉Ƃ�������Ă�15���قǂ̂Ƃ���ɁA������f�B�P���Y�̍�i�ɏo�Ă��邪�A�s�̏d�v�j�Ղ̂ЂƂł��鉤�����Â̊فiRestoration
House�j���������B�G���U�x�X���l����3�K���ă����K����̃}���V�����ł���B1649�N�ɁA�s���[���^���v���ō����`���[���Y�ꐢ�����Y���ꂽ���A�⎙�Œ��j�̃`���[���Y�́A�嗤�ɖS�����Ă����B���̔ނ��A�����āA�����Ƀ`���[���Y�Ƃ��đ��ʂ��邽�߂Ƀh�[�o�[���烍���h���������r���A���`�F�X�^�[�ɗ�������ďh�������̂����̊قł���B1660�N5��28���̂��Ƃł������B
�@���`�F�X�^�[�s���炩�犽�}���Ĉ��������ʼn߂������`���[���Y�́A���̗����A���̊ق��A�u�������Â̊فv�Ɩ��Â���A�ƌ����c���āA�����h���֔n�Ԃ�i�߂��B����ł��̖�������ꂽ���Ƃ��A���̊ق̖�̂��ɓ��łō��ݍ��܂�Ă���B���̓��A5��29���̃����h���ł́A�ނ͑吨�̎s����������}���A�z���C�g�z�[���ɓ������B���̃z���C�g�z�[���́A�A�ނ̕��̃`���[���Y�ꐢ�����Y���ꂽ�ꏊ�ł�����B�����ŁA�ނ̓`���[���Y�Ƃ��ĉ����ɂ����Ƃ��錾����A�������Â����������B����5��29���́A�ނ�30�̒a�����ł��������B
�@�`���[���Y�́A��ϗ��ȓI�ŋ��y�I�Ȉ�ʂ������āA���e�������Ă����`�����A�]���̐��_�Ɍ����Ă����Ƃ����Ă���B�������A����ł́A���҂Ƃ��Ă̕i�ʂ�����A�c��ƑΗ�����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��A�`�������ď�������Ƃ����悤�Ȑ����I�ȍˊo�͂������炵���B�`���[���Y�̍ɑ��ɂȂ����̂́A�ނ��嗤�ɖS�����ɂ����ŏ]���Ă����G�h���[�h�E�n�C�h�A��̃N�������h�����ł���B���̍ɑ��̑������Ɛl���������̐l�X�̐M���āA�������Â��O���ɏ��̂ɗ͂��������Ƃ����Ă���B
�@���̃`���[���Y�̎{���Œ��ڂ���邱�Ƃ̈�́A1662�N7���ɁA�V�����w�⌤����ڎw���w�p�c�̂ɓ������^���ă��[�����E�\�T�G�e�B�i��������j�����������Ƃł���B����́A1626�N�ɖS���Ȃ����t�����V�X�E�x�[�R���������w��̑�v�V�����H����`�ɂȂ����B1640�N�ォ��A�I�b�N�X�t�H�[�h����h���̃O���V������J���b�W�ȂǂŁA�����Ɗώ@���d������V�����w��̂������͍�����O���[�v�������Ă������A����炪���̉�������ݗ��̔w�i�ɂȂ��Ă���B�����̉���ɂ́A���z�ƂŃZ���g�E�|�[�����@�̍Č��Œm���Ă���N���X�g�t�@�[�E������Ȋw�҂̃��o�[�g�E�{�C���Ȃǂ�����A�ˁA1672�ɂ́A�����w�҂̃j���[�g��������ɑI��A��������́A17���I�̉Ȋw�v���ɑ傫�Ȗ������ʂ������B
�@���̍��̃����h���̗��j�ɂ́A��̑傫�Ȏ������������B���̈�́A1665�N�̉u�a�̑嗬�s�ŁA������́A���̗��N�̑�ł���B1665�N��6���Ƀ����h���̃h���[���E���C������N�������u�a�͉Ă̊ԁA�҈Ђ�U�邢�A1349�N�̃y�X�g�̑嗬�s�ȗ��A�ő�̗��s�a�ɂȂ����B�a���͓��肳��Ă��Ȃ��悤�����A��͂�y�X�g�ł������炵���B�����̃����h���̐l���́A30�`40���Ɛ��肳��邪�A���̂�����7�`10���l���]���ɂȂ����Ƃ����B���̗��N�̑�ł́A�v�b�f�B���O�E���C������9��2���ɏo���ĎO���ԔR�������A�V�e�B�[�̑唼���Ă��s������1��3��̖��Ƃ��D���ɋA�����i����o�u��w�p���Љ�j�k��l�x����o�ʼn�A1971�A261�Łj�B�Z���g�E�|�[�����@���͂��߁A���j�I�������̑��������̉ЂŔ�Q���A�Â������h���̊X���݂́A���̂Ƃ��ȗ��p�������Ă��܂�����������B
�@�ȏ�A�������`�F�X�^�[�ɏZ��ł������댩���ꂽ�u�������Â̊فv�Ƃ���ɂ܂��C�M���X��17���I�㔼����̐����I�A�Љ�I��̊T���������Ƃ݂Ă������A���́A�O���ł̎��́A���̂悤�Ȕw�i�̂Ȃ��ŁA�����h�����ӂŐ��܂ꂽ���ƂɂȂ��Ă���B�u1675�N����80�N�ɂ����Đ��܂�Ă���A�����炭1678�N���܂ꂭ�炢�ł��傤�B1754�N���炢�܂Ő����Ă����l�ł��B����w�҂ł���A���܂ł��������l�ފw�ɋ߂����Ƃ��������Ă��܂����B���͌���w�ł��B���݂̐E�Ƃ́A���̂����ŋ߂̃C�M���X�ł̐E�Ƃ̑����ł���܂��v�ƁAA�t���炢��ꂽ���Ƃ��������i1994�N1���j�B
�@������́A��������ׂĂ��̂܂܁A�M������ł���킯�ł͂Ȃ��B���̂悤�ȑO���ɂ��Ă̔��f�ɂ́A���낢��Ɠ�����������āA�����ɏ��ꂽ��\�҂ł������덷���������Ȃ����Ƃ����R�l���Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B�Ȃɂ���A�c��ȉF���̋L�^�ɂ̒����̈ꕔ��S��œǂݎ�낤�Ƃ����̂ł��邩��A�قƂ�ǐl�ԋZ�ł͂Ȃ��B�덷���o�Ȃ��ق����s�v�c�Ȃ̂ł���B�����A���̑O�N��11���ɂ́A�����C�M���X�Ő����Ă����̂́A�u1700�N�㔼����A1800�N�㏉���ɂ����āv�ł������Ƃ����Ă����B����ł�100�N����Ă��邱�ƂɂȂ邪�A����́A�����炭�u17���I������18���I�����v�̌����ԈႢ�ł��邱�Ƃ��A���̌�̌�����������e�Ղɐ����ł����B
�@�������A����ł��A�����̎��̒��߂̑O�����C�M���X�ł���A���̊ւ��̒��Ō������Ă����Ƃ�����ƁA�������̃C�M���X�̑O�����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������A�S��������������Ȃ��B���͉��x���A���N���ɂ킽���Ă��̃C�M���X�ł̑O���ɂ��ĕ�������Ă����̂����A�����ŔO�̂��߂ɁA����ȊO�ɂ����Ă������N��܂ꂽ�ꏊ�����������Ă݂�ƁA���̂悤�ɂȂ�B�i�J�b�R���͌���ꂽ�N���j
�@�u1685�N����i1687�N���炢�ł��傤���j�ɐ��܂�1760�N��㔼����1770�N��O���܂Ő����Ă��܂����B�v�u���Z�n�̓����h���s���ł���A�����h���s�̒��S�X�ł͂Ȃ��A���x�O���̂Ƃ���A�k�����ł��B�v�u���`�F�X�^�[�Ƃ����Ƃ�����A���Ȃ����m���ɐe���݂��o�����Ƃ���ł���A�ꎞ�Z��ł������Ƃ̂������n��ł��B��������ɁA�����h���s���ɕ�炵�Ă��܂����B�v�i1994�N9���j
�@�u��ԍŋ߂̐l���̓C�M���X�ł��B17���I����18���I�ɂ����Ăł��B�v�i1996�N�P���j
�@�u��̓I�ȂƂ����ǂނ̂͂ƂĂ�����̂ł��B����ł��ł��邾���ǂ߂�悤�Ɏ��݂邱�Ƃɂ��܂��B����1686�N�A���邢��1676�N�A74�N�A���̂�����̂悤�ɑ�������̂ł��B����1786�N�Ƃ��ł͂Ȃ��ł��悤�B���Ԃ�1686�N��������10�N�O��܂��̐��܂�̂悤�ɑ������܂��B�v�i1997�N6���j
�@ �u����1670�`80�N��ɐ��܂�Ă��܂��B1686�N�A���邢��76�N�A���̂�����̂悤�ł��B���邢��1678�N��������܂���B�v�u���Ȃ��́A�����h���̍x�O�Ő��܂�܂����B�����h���̍x�O�A�����h���̒��S����x�O�����ē쐼�̕��p�ŁA�����h���̂ǐ^����130�L���쐼���̂�����Ƃ����悤�ɑ�������̂ł����A���̂�����Ő��܂�܂����B�v�i1998�N6���j
�@�����𑍍����čl����ƁA��͂�A�u1675�N�`1680�N�ɐ��܂�Ă���v�Ǝ~�߂�̂������炭�Ó��ł���悤�Ɏv����B���̓����́A�`���[���Y�͂܂��Ⴍ���݂ł������B���́A1993�N11���ɁAA�t����A�u���Ȃ��̓C�M���X�̉��ƂƑ����Ȃ��肪����ƌn�ɐ��܂�A�C�M���X�̉�������̃����o�[�ł����B�t�����V�X�E�x��R���ɂ��Ă̌�������ɂ��Ă��܂����v�ƌ����Ă���B����͂���ɁA�u����ŁA�t�����X�v���A�A�����J�̓Ɨ��錾�Ɋւ���v�����Ɋւ��悤�ɂȂ�A�A�����J�Ƃ����V�����\���̂���V�V�n�ւƓn��v�悪�v���W�F�N�g�Ƃ��Đi�s���A���Ȃ������̗F�l�A�m�l�̊��l���́A�s�����^���Ƃ��ĐV�V�n�ւƈڂ��Ă������킯�ł��v�Ƒ�����ꂽ�B
�@���̂����A�u�C�M���X�̉��ƂƑ����Ȃ��肪����ƌn�ɐ��܂ꂽ�v���Ƃɂ��ẮA�������ꂪ�����ł������Ƃ���A���ɂƂ��ă`���[���Y�́A���邢�́A�����͐g�߂ȑ��݂ł��������ƂɂȂ�̂ł��낤���B�������A��������A�u��������̃����o�[�ł������v���Ƃɂ��ẮA���̌���A���N���ɂ킽���ĉ��x���J��Ԃ���Ă��邩��A������̂ق��͐M�ߐ��������͍����Ƃ�����̂�������Ȃ��B
�@���̓����̎��̖��O�́AA�t�ɂ��A�u���o�[�m�E�W�F�[���Y�E�n���v�g���v�Ƃ������悤�Ȗ��O�ł������炵���B�u�����̂��Ȃ��́A���������ʂ��Ă���A�����҂Ƃ��āA���邢�͊w�҂Ƃ��Ċ��Ă��܂����̂ŁA�����h���̐}���ق⎑�����֍s���Ē��ׂ�A���O���c���Ă���\��������܂��v�Ƌ����Ă���Ă���B(1994�N 1��)
�@���̔��N��ɂ́A���łɏq�ׂ��悤�ɁAA�t����A���`�F�X�^�[�Ɂu�ꎞ�Z��ł����v���Ɓv��`�����A�����āA���̎��̖��O�́u�W�F�[���Y�v�Ƃ�����������������A�Ƃ�����ꂽ�B���̑O���ŁA���`�F�X�^�[���o�Ă����̂́A���ꂪ���߂Ăł���B���O�́u�W�F�[���Y�v�́A�����ł��J��Ԃ���Ă���B�����āA���̑O���ł̎��́A�u�w�҂ł����B�@�����̂��̂ł͂Ȃ������̂ł����A�@�w�ƕ��w�̕��ʂł̎d�������Ă��錤���҂ł����B�p���w�m�@�ƁA���ꂩ��A�p���̋{��Ɋւ��A�J�f�~�[�A�����̃A�J�f�~�[�ł��傤���A�����̉���ł����v�ƁA�����悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂ��Ă���B����ɂ����ł́A������I�m����g�ɂ��邱�Ƃɏ��ɓI�ł��������Ƃ��A���̂悤�ɍ�����ꂽ�B
�@�u���͂����i�����A�J�f�~�[�j�ɓ����Ă���ԂɁA�S��w��_���E�Ɋւ��悤�ɂȂ����̂ł��B�����̉���̒��ɁA���̂悤�ȗ�w�ɋ���������Ă���l�����l����������ł��B���Ȃ��͍ŏ��A�y�̂��A���b�Ȋ�����Ă�����O����ώ@���Ă��܂����B������������������������悤�ɂȂ�܂������A�����̗�����l���ē��ݍ����Ƃ͂��܂���ł����B�p���w�m�@�≤���A�J�f�~�[�̉�����X�g�̂Ȃ��ŁA1680�N�ォ��1760�N�ギ�炢�܂łɐ������u�W�F�[���Y�v���邢�́u���R�u�v�Ƃ��������O�̐l�ŁA���ܕ`�ʂ����悤�Ȑl������������邩������܂���B�v(1994�N 9��)
�@���łɕt�������Ă����ƁAA�t����́A�C�M���X�ł̑O���ł̎��̕�ɂ��Ă��A�����܂��ȕ\���ł͂��邪���̂悤�ɒm�炳��Ă���B
�@�u����́A����͂������������h�����痣�ꂽ�Ƃ���ŁA�����h���̉������̃G���A�̂Ȃ��ŁA3�Ԗڂ���4�Ԗڂ��炢�Ɉʒu����A�m���Ă����n�ł��B�����h���̎s�������������悭�m���Ă����n�̒��ŁA��ԖځA��ԖځA�O�ԖڂƗ��Ă����āA3�`4�ԁA4�`5�Ԗڂ��炢�̕�n�ł��B���O�͏o�Ă��Ă��܂���B3�Ԗڂ���5�`6�Ԗڂ��炢�́A�m���Ă����n�ł��B�����A��������̕�ƕ���ł��܂��B�����̂��Ȃ��̂�������ł��B�v(1998�N6��)
�@�u���Ȃ��̂���̈ʒu�ł��������h������k�����̂ق�2�A30�L�������A���邢��3�A40�L�������A�����h���̒��S�n����k����3�A40�L���̒n�_�̕�n�̂���Ƃ���A30�̂���50�́A���邢��100�̂��炢�̂���̋K�͂̂Ƃ���ɂ���悤�Ɋ������܂��B(1999�N 6��)
�@���́A1991�N�̏t���烍�`�F�X�^�[�ɏZ�ނ悤�ɂȂ�A��\�҂̃A����^�[�i�[�ƒm�荇�������Ƃ��A�����ĒP�Ȃ���R�ł͂Ȃ��������Ƃ��A���܂ł͂悭�������Ă���B�������A���̃C�M���X�̑O�����A���̂��ƂƉ��炩�̌`�Ō��т��̂��ǂ����́u�������Â̊فv�ɂ܂����j���܂߂āA�܂��悭������Ȃ��BA�t�Ɠ��l�A�A����^�[�i�[���A�����O���ňꎞ���`�F�X�^�[�ɏZ��ł����Ƃ͌����Ă������A�����������ꂽ���`�F�X�^�[�Ƃ́u�ړ_�v�͂��ꂾ���ł���B�p���w�m�@�≤������̉�����X�g�ׂ���A�����̕�������h���ߍx�̕��ŒT�����肷��قǂ̃G�l���M�[�����Ԃ��Ȃ�����A�C�M���X�ɂ����鎄�̑O���̒T���́A��������ȏ�͐i�ނ��Ƃ͂Ȃ���������Ȃ��B
�@�@(2012.06.01)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@�@�@�@�E�H���^�[�E���[���[�̔g������̐��U
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z(83)�\�@
�@��؍q��@��������������1983�N�̉Ăɂ́A�������Ƒ��S�l�́A1973�N�ȗ��A��x�ڂ̃A�����J�����𑗂��Ă����B�m�[�X�E�J�����C�i�B�̎�s���[���[�ɏZ��ł������A���̃��[���[�Ƃ������O�́A�C�M���X�̌R�l�A�C�m�T���ƁA��b�A���l�Ƃ������ʂȊ�������Ă����E�H���^�[�E���[���[(Walter
Raleigh) ����Ƃ������̂ł���B�ނ́A�G���U�x�X�ꐢ�̒��������āA1584�N�ɂ̓i�C�g�݂̏̍���^�����Ă����B�ʂ���݂ɍ����ȃ}���g���L���ď�����ʂ����Ƃ����`���͗L���ł���B
���̑O�N�A1982�N�̉Ă���́A���Ɩ��̓A���]�i�B�c�[�\���ɏZ�ނ悤�ɂȂ��Ă����B���̒��̃A���]�i��w�ɖ��͗��w���Ƃ��āA���̓t���u���C�g�q�������Ƃ��ď������Ă����B�Đ��{�̃t���u���C�g����Ő��E������I�ꂽ�������A�q�������̓A�����J�e�n�̑�w�ɕ��U���Ă������A�N�Ɉ��A�S������ӏ��ɏW�܂��āA�����W��ɎQ�����邱�ƂɂȂ��Ă���B���̔N�x�̌����W��́A���N��1983�N�t�A�m�[�X�E�J�����C�i�B�̎�s���[���[�̃m�[�X�E�J�����C�i��w�ɁA�S���\�l���W�܂��čs�Ȃ�ꂽ�B���̓c�[�\�������H3���Ԃ���Ń��[���[�ɒ��������A���ꂪ�A�������[���[�ɑ��ݓ��ꂽ�ŏ��ł���B
�@3���Ԃ̌����W��ɏo�Ȃ��Ă���ԂɁA���́A���[���[�̃z�e���ŁA���k��w���痈�Ă���S�����ƈ�ӌ�荇�������Ƃ��������B���ł��Y����Ȃ��̂́A���̎��AS��������A���̐��N�O�ɁA���w���ł��������j���K���ŖS�������b�������Ƃł���B�]�����������Ȃ����Ƃ�m���Ă���S�����̒��j�́A���܁A�a���Ő����E���ċ����Ă����Ƃ����B���������Ă���A���̎��̎��̒��j�Ƃقړ����N���ɂȂ�͂��ł������B���͘b���Ȃ���AS�����̔߂����v���ɐ[����������A���̐�������ɂ́A�����g���ق��Ȃ�ʂ��̃��[���[�ɏZ�ނ悤�ɂȂ��āA���̌��ʁA���j�����ł͂Ȃ��Ȃ����S�������ƂɂȂ낤�Ƃ́A�z�������ł��Ȃ������B
�@���̒��̖��O�̂��ƂɂȂ����E�H���^�[�E���[���[�́A�G���U�x�X�����̒����āA�C�M���X�ł͂����Ƃ������A1584�N����V�嗤�������Ă̒T�����𑗂荞��ł���B���N��1585�N�ɂ́A���߂Ă̈ڏZ���c���C�M���X����o���������B�ނ�́A�吼�m�̊댯�ȍr�C�����z���āA���݂̃m�[�X�E�J�����C�i�̃��A�m�[�N���ɏ㗤�������A���Z���̃C���f�B�A�������Ɛ܂荇���������A��Z����ɂ͎���Ȃ������B���̌�A1586�N�ɂ��A87�N�ɂ��ڏZ�����݂�ꂽ���A�������Ȃ������B���ǒ�Z�ɂ͎��s���āA�ڏZ���͑S�ł����B
�@�ނ炪�Ȃ��S�ł��Ă��܂����̂��ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B�c����Ă����̂͗����ɍ��܂ꂽ�C���f�B�A���̖��O�����ł���B�C���f�B�A�������Ƌ������Ă������Ƃ��ł����ɎE���ꂽ�̂�������Ȃ��B���́A1983�N�̎����̒��O�ɂ́A�Ƒ��l�l�ŁA���̃��A�m�[�N���̈ڏZ�̌����K��Ă��邪�A���̐Ւn�͂��܂��j�ՂƂ��ĕۑ�����Ă���B�ނ炪�������������Ă�����A�A�����J�A����ꍆ�̉h�_���ɂȂ����ƂɂȂ�A�E�H���^�[�E���[���[�̖����͂܂��܂����܂��Ă����ł��낤�B���������̉h�_�́A���̌��1607�N�́A�W�����E�X�~�X�D���ɂ��W�F�C���X�^�E���̐A���ɒD���邱�ƂɂȂ����B
�@���A�m�[�N���ɂ�����ŏ��̐A���ɂ͎��s�������A�ނ͐A���v��̋��͂Ȑ��i�҂ł��葱�����B�㑱�̐A���n�ւ̓����J�������̑傫�Ȍ��т��̂����āA���[���[�̏B�c��c�����̑O�ɂ́A�E�H���^�[�E���[���[�̑傫�ȓ��������Ă��Ă���B���́A�Ƒ��A��ʼn��x�����̂����������Ă���B���[���[�̓����̑O�ŎB�����ʐ^���ǂ����Ɏc���Ă���͂��ł���B
�@�A�����J�̐B�����ƂɎ��s�������ƁA1591�N�ɁA���[���[�͖����ɏ����t���̏����ł������G���U�x�X�E�X���b�N���[�g���ƌ��������B���N�ɂȂ��Ă��̖����̌��������o����ƁA���{���������̓��[���[�������h�����̘S�ɗH���A�G���U�x�X���{�삩����ق���悤�ɖ������B���̎��ɂ͊Ԃ��Ȃ��A�ߕ����ꂽ�̂����A1603�N�̃W�F�[���Y�̎��ɂȂ��āA���x�͉A�d�̂��ǂ�13�N�Ԃ������h�����ɗH����Ă��܂����B�`���Ƃł����Ɏ����U���ɒ��������l�ł��������ނ́A���̍����ő咘�w���E���j�x�������グ���B
�@���̌�ނ́A��ՓI�Ƀ����h��������o����������A��ăI���m�R�여��ɉ�������T�����ׂ��h�������2�x�ڂ̒T�������w�����邱�ƂɂȂ�B�Ƃ��낪�T���̓r���A���[���[�̕����B���A�X�y�C���̓��A�n�ŗ��D���s���X�y�C���l�Ƃ̐퓬�ɂȂ��Ă��܂����B���S�����X�y�C����g���A�W�F�[���Y�ꐢ�Ƀ��[���[�����Y�ɂ���悤���߂��B�X�y�C���Ƃ̊W���������ꂽ�����́A���̗v����F�߁A���[���[��1618�N10��18���A���Ɏa��Y�ɏ�����ꂽ�B���[���[�͎a����s������������ꂽ���A�u����͌���ł��邪�A���ׂĂ̕a��������̂ł���v�Ƃ����Ō�̂��Ƃ��c�����Ƃ����B
�@�ނ̖��������A�����J�̒��ɂ��ďZ��ł������Ƃ��ẮA���̂悤�Ȕg�p����̐��U�𑗂������[���[�̍Ō�̔ߌ��ɁA���������̊���̓�����}���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B��Ɏ��́A�����ȗ�\�҂�A�t����A�O����1678�N���ɃC�M���X�ɐ��܂�A���̐B���v��̐��i�ɐϋɓI�Ɍg����Ă����A�ƕ�������Ĉ����߂������̂������邱�ƂɂȂ�B1678�N���Ƃ����A�W�F�C���X�^�E���́A���łɊ�b���ł܂��Ċg�唭�W���������͂��ł���B����A�k���̃}�T�`���[�Z�b�c�ł��A1620�N�Ƀ��C�t�����[���œ��������V���k�����̈�c���v���}�X�̊X��z���n�߂�50�N���o�߂��Ă���B�C�M���X�̐A���n���A���̍��ɂ̓j���[�C���O�����h����J�����C�i�Ɏ���܂œ��C�݈�тɍL�����Ă����B
�@���́A���̓��C�݈�т��Ƒ��ƈꏏ�̍Ō�̗��s�ŎԂő���܂���Ă���B�}�T�`���[�Z�b�c�ɂ��s�������A�W�F�C���X�^�E���̈�Ղ����܂Ȃ��������B��������[���[�ɏZ��ł�������ł��邪�A�������A�͂��߂́A���͂��̃��[���[�ɍs�������čs�����킯�ł͂Ȃ������B�A���]�i�̃c�[�\���ɂ���A���]�i��w�ň�N���߂�������A��N�ڂɂ̓T���t�����V�X�R�ֈڂ��ċ��E�ɂ������Ǝv���Ă����̂ɁA�ǂ������킯���A�s�{�ӂȂ��烍�[���[�ɂ����j�ڂɂȂ��Ă��܂����̂ł���B���܍l����ƁA�R����傫�ȗ͂ɉg�������Ă����悤�ȋC������B�����āA���́A1983�N�̂��̎����Ɋ������܂�邱�ƂɂȂ����B
�@�O���ł̎����A��\�҂�A�t�ɂɌ���ꂽ�悤�ɁA����1600�N��㔼�ɃC�M���X�ɐ��܂�Ă��āA�A�����J�ւ̐B���v��𐄐i���Ă����Ƃ���A�������̃E�H���^�[�E���[���[�̐B�����Ƃɂ��Ă͏\���Ɉӎ����Ă��āA���̂��Ƃ��p���҂Ƃ��Ĕނɐe���݂������Ă����̂�������Ȃ��B�����āA�����A�t�̘b�ł́A�����܂��E�H���^�[�E���[���[�̂悤�ɁA�C�M���X�����Ƃ͂Ȃ�炩�̊ւ��������Đ����Ă����B�u���[���[�v�Ƃ��������A�����Z��ł������̖���ʂ��āA���̐��U�ɑ傫�ȈӖ��������ƂɂȂ��������ɁA���ɂ̓E�H���^�[�E���[���[���A�Ȃ�ƂȂ������O���́A�����̐l���Ƃ͎v���Ȃ��̂ł���B
�@�@(2012.04.01)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@�@�@�@�l�ގj�̂Ȃ��̕����̔��B�Ǝ��R�j��
�@�@�@�@�@�@�@�@�\�����ƕ������߂��鐏�z (82)�\�@
�@�g���R�̃G�[�Q�̂قƂ�ɃG�t�F�\�X�Ƃ����Ñ�s�s�̈�Ղ�����܂��B�I���O2���I�ɁA���a�����[�}�̎x�z���ɓ���A�Ñネ�[�}�鍑�̓��n���C���Ղ̒��S�ƂȂ��ĉh���Ă����`�p�s�s�ł����B�����ɂ��G�y�\�̖��ŏo�Ă��܂��B���āA�G�W�v�g�̏����E�N���I�p�g���́A���a�����[�}�����̌��͎҂ł������}�[�N�E�A���g�j�[�ƁA���̊X�ɑ؍݂��Ă������Ƃł��m���Ă��܂��B
�@���܂��A�A���e�~�X�_�a�̈�Ղ��͂��߁A�A���L�T���h���A�A�x���K���̐}���قƕ���œ����̐��E�O��}���ق̈�Ƃ����Ă����Z���V�E�X�}���ق̐Ւn��A5���l�����e�ł����Ƃ����~�`������A�قڂ��̌`�𗯂߂Ďc���Ă��܂��B�ނ����A������x�قǁA�N���I�p�g�����ʂ����͂��̑嗝�̓���ʂ�A�����̈�Ղ����Ă܂�������Ƃ�����܂����B��Ղ̋K�͂₻�̌������̑s�킳������A���N�O�ɂ��łɂ��̂悤�ȓs�s���������Ƃ́A������ƐM�����Ȃ��v���ł����B���{�ł́A�܂��A���j�ɔږ�Ă��o�ꂷ�鐔�S�N���O�̂��Ƃł��B
�@ �������A���̃G�t�F�\�X���A�I������́A�ɉh�̊�Ղł������`�p�����X�ɏk������Ă����悤�ɂȂ�܂��B�G�t�F�\�X�̊X�̔w��ɂ�������̎R���痬��o�����y�����`�p�ɑ͐ς��n�߂�����ł����B���̌����́A�X�т̔��̂ɂ���܂��B�G�t�F�\�X�̊X���g�債�Ă����ɂ�āA���ӂ̐X�т͎��X�ɔ��̂���Ă����܂����B�J���~�邽�тɕې��͂���������n���A�Ō�ɂ͕\�y�������������āA���ɂ͍`���y���Ŗ��ߐs������A�Z���̐������x����_�앨�̐��Y���ł��Ȃ��Ȃ����̂ł��B�����I�ɓ���ƁA�l�X�͏Z�߂Ȃ��Ȃ�A�}���ɊX�͐��ނ��āA���ɂ́A�p�ЂɂȂ��Ă��܂��܂����B
���̃G�t�F�\�X�̐��ނ́A�Ñ�M���V�A�A���[�}�����̐��ނ̂�������������Ă��܂��B�܂�A�����̔��B�́A��ɁA�X�т̔j��Ƃ����㏞���Ă��܂����B�X�т̔j������ӂɊg�U�����Ă������Ƃɂ���Ă̂݁A�����͂��̔��W���ێ��ł����̂ł��B�j�����ĐX�т��Ȃ��Ȃ������_�ŁA�l�X�͂��̐�����Ղ������A�V���ȐX�т����߂Ĉړ�����������܂���ł����B���̂悤�ɂ��āA�A�e�l�A�X�p���^�A�J���^�S�A���[�}���A�n���C�̏��s�s�����ނ������Ƃ́A�l�X�́A���x�́A�A���v�X�R�����z���āA�L��ȃ��[���b�p�̑�X�т�ڎw�����ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A���[���b�p�̑�J������̎n�܂�ł����B
�@ ���[���b�p�ł́A�Ⴆ�p���́A���S�N�O�ɁA�Z�[�k�͔ȂɃm�[�g���_�����@�����āA���̂܂��ɐl�X�������ȑ�������ďZ�ނ悤�ɂȂ����̂��X�̎n�܂�ł��B�܂��A�X�т̂��ċ�������āA���̂܂��ɐl�X���Z�ޑ������A����ɑ��̎��ӂ̐X�т̂��āA�_�앨����Ă邽�߂̔������܂��B�l���������Ă���ƁA�X�є��͈̂̔͂͂���ɁA�傫���L�����Ă����܂��B���̂悤�ɂ��āA�s�s���ӂ̐X�є��͉̂ʂĂ��Ȃ��L�����Ă����܂����B���ꂪ�A�����h����x�������ȂǁA���[���b�p�̏��s�s���ł��������Ă��������^�Ƃ����Ă悢�ł��傤�B
�@�e���Y�͔Ȃ̃Z���g�E�|�[�����@����L�����������h���Ȃǂ́A���[���b�p�ł��ł��X�єj�i�X�ŁA���܂ł͐X�іʐς͂킸���ɋ�p�[�Z���g�ɉ߂��Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B�x�������Ȃǂ́A�\�����I�ɖw�ǂ̐X�т��蕥���āA���̔��Ȃ���A�A�т��n�߂��̂����܂̐X�тł��B���[���b�p�������܂��A�X�т̔j��̏�ɒz���ꂽ�����ł����B���̐X�т̔j�A�s�s�̖c���œO��I�ɐi�߂���O�ɁA���[���b�p���~�����̂��A�\�܁`�\�Z���I�̑�q�C������o�āA�\�����I����{�i������A�����J�嗤�ւ̐i�o�ł��B
�@�\�I���܂Ń��[���b�p�ł́A����n�Ȃǂɂ��{�͂̂ق��́A���Ԃƕ��Ԃɂ�鎩�R�G�l���M�[�̗��p�͍L���s�Ȃ��Ă��܂����B���ꂪ�A�\�l�`�\�ܐ��I�ɂȂ�ƁA�������ݏグ���萻���ɗ��p�����肷��ق��ɁA�r�[���̏����A�����A�����A���v�A���ށA���S�Ȃǂ̑����ʂ̎Y�Ƃ��������铮�͂Ƃ��ĉ��p����A�Љ�̐��Y�����̊g��������炵�܂��B���̗���́A�\�����I�㔼�ɁA���C�@�ւ����������܂ő����܂����B�����āA�ΒY�A�Ζ��Ȃǂ̉��ΔR���̎���ɓ���܂��B�X�ю�������Ղɂ��Ă����l�ނ̕������A���x�́A���ΔR������Ղɂ��ĉ����I�ɑ傫�����B���邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�����Ԃ̔��B�Ԃ�́A���̓T�^�I�Ȉ��ł��B�ꔪ���Z�`��Z�N��ɂ͎����Ԃ̊J�����������i�݁A���Z���N�ɂ́A�A�����J�Ńw�����[�E�t�H�[�h��T�^�t�H�[�h�̑�ʐ��Y���n�߂܂����B����T�^�́A��\���N�܂łɐ�ܕS���������A����Z�N��Ȃ��̃j���[���[�N�ł́A�����X�p�ɎԂ����ӂ�Ă��܂��B�����m�푈�ŕ��������{�ł́A���l�Z�N��㔼�ɓ����Ă��A�Ԃǂ���ł͂���܂���ł������A�\�N��㔼�ɂȂ��āA�悤�₭�g���^�̎Ԃ����܂�A�M�������܂�Ȃ��������H�Ɏp��������悤�ɂȂ�܂����B
�@���̍��A�����N����܋�N�ɂ����āA���͗��w���Ƃ��ăA�����J�ɂ��܂����B���{�ł͂܂��A�����̍x�O�ł����H�ܑ͕�����Ă��Ȃ������̂ɁA�ŏ��Ɍ������T���[���X�̊X�ɂ́A�������R���N���[�g�̍������H���c���ɑ���A����ȍ��˃n�C�E�G�C���傫���Q�������Ă���l�q�Ȃǂ��������G�t���ɂȂ��Ă��܂����B�s�����̉H�̂悤�Ƀe�[����L������^�Ԃ�������A�K�\�����������ł��Ĉ����A��w�ł͊w���p�̍L�����ԏꂪ���邱�Ƃł���������܂����B�A�����J�ł͂����X�тɈˑ����邱�Ƃ����A���ΔR���Ɠd�C�ɂ���āA�����̔��B�͂���ɂǂ��܂ł������Ă����悤�Ɏv���܂����B
�@��㎵�O�N�����㎵�ܔN�ɂ����āA���͕����ȍ݊O�������Ƃ��āA��x�ڂŏ\�l�N�Ԃ�̃A�����J������̌����܂����B���̍��A���x�������̓��{�݂̂Ȃ炸�A�w��ǂ̉��ď����́A�I�C���V���b�N�Ɍ������h��Ă��܂����B�A�����J���������O�̏\���Z���̑�l�������푈�̖u�������������ɁA�A���u�����͐Ζ���헪�I����Ƃ��āA�Ζ������̍팸�v���W�J���n�߂��̂ł��B���{�ł��g�C���b�g�y�[�p�[���̂ɂ����A�����s���������肵�܂����B
�@���Ă̐Ζ��A�o���ł������A�����J�́A���łɗA�����ɂȂ��Ă��āA�K�\�����X�^���h�ł́A�������R�ɃK�\�������������Ԃł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���T���[���X�̊X�ł́A���łɌ�ʏa���n�܂�A�������������̎Ԃ̌�ʗʂ��ɘa���邽�߂̓��H�̊g���H����������Ƃ���ōs�Ȃ��Ă��܂����B�������B�̏ے��̂悤�ł��������̔����������������H�̍��˃��[�v���A�l�X�͂����a��\�z���āA���肵���\��Ō���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�G�R�Ƃ��ė����������Ȃ������X�̕��͋C�̂Ȃ��ŁA���܂ł͓��{�ł�������O�ɂȂ�܂������A�Z�������͈��������������Ĉ��ނ悤�ɂȂ��Ă��邱�ƂɂЂǂ����납����܂����B
�@���̓����A�A�����J�ł́A������Ƃ̃��[�`�F���E�J�[�\�������Z��N�Ɂw���ق̏t�x�ŃA�����J���ɍL����_���̎��Ԃ��������Ĉȗ��A���������Љ�I�ȑ���ɂȂ��Ă��܂����B����܂ŁA�Ƃ��납�܂킸�T����Ă���DDT�Ȃǂ̗L�@���f�n�_���Ő��̋����L�@���܂��A�����ɂ́A������v�����E���Ă������łȂ��A�l�̖��܂ŋ�������Ă��邱�Ƃ�m�炳��āA�l�X�͜��R�Ƃ����̂ł��B�L��ɂЂ낪��A�����J�̑�n���A������Ƃ���ŁA�����Ɣj��ɔ�����Ă�����Ԃ��A�j�㏉�߂āA�A�����J�����̑O�ɖ�������Ă����܂����B
�@�암�̃~�V�V�b�s��ł��A�����ɂ�鐅���_�f���R�̂��ߋ������S���C�P�ʂŎ���ł�������A�j�����ɂ�鎀�̊D��T���h�}�C�h���̖�肪���o���đ���ɂȂ��Ă��܂����B�����̔��B�́A���Z��N�ɐl�ނ����߂Č��ʂɗ�������܂łɂȂ�܂������A���̈���ł́A�X�т̔��݂̂̂Ȃ炸�A���R�j��Ɛl�S�̍r�p���A�L�͈͂ɂ����������ɐi��ł����̂ł��B���{�ł��A���O�N�����甭�����������a�Ȃǂ̌��Q�a���[���ȉe����^�������āA�_���␅�̉����ȂǁA���N���x��āA�A�����J�̌��ǂ��悤�ɎЉ���ɂȂ��Ă����܂����B
�@���̊ԂɁA�ˑ�ȗʂ̉��ΔR���̏���́A�[���ȑ�C�������䂫�N�����A��_���Y�f�̑���ɂ��n���̉��g�������E�K�͂ł̑���ɂȂ��Ă��܂����B��\�ꐢ�I�̔��ɂ́A�n���̕��ϋC�����O�x�㏸���āA�k�đ嗤�̒��S����A�����A���V�A�̍��q�n�т̐������R�O�`�T�O�p�[�Z���g�������A�����̒n�悾���ł��A�H�Ɛ��Y���Q�O�p�[�Z���g����������Ƃ����Ȋw�҂̗\�z������܂����B�����ďo�Ă����̂��A���q�͔��d�ł������̂ł��B���q�͔��d�͌��q���e�Ɠ����ŁA�l�ނ������߂Ă͂����Ȃ��u�p���h���̔��v�ł����B�������A���q�͂́u���a���p�v�Ƃ����Â��L���b�`�t���[�Y�ɖ��킳��āA�l�X�͂�����e��Ă��܂����B�����āA�������́A���܁A��N�R���̕����̌������̂�̌����Ă��܂��B
�@ �����Ԃ̘b�ɖ߂�܂��ƁA���̌������̂��܂߂���N�̑�k�Ђ�A�^�C�̍^���Ȃǂ̉e���ŁA��N�x�̓��{�̍����V�Ԕ̔��䐔�͑O�N�x���P�T�D�P�p�[�Z���g���̂S�Q�P���Q�Q�O�䂾���������ł��B����A�A�����J�̐V�Ԕ̔��䐔�́A�O�N�x���P�O�p�[�Z���g���̖�P�A�Q�W�O����ɂȂ�܂����B����ɑ��āA�ŋߑ䓪�������������́A��N�̂P�`�P�P�������ŁA���łɂP�A�U�W�P����ŁA�������O�N�A���Ő��E��̎����Ԏs��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�i�u�����v2012.01.05-06�j�@����́A�����ׂ������Ԃ̐��Y�䐔�̑����Ԃ�ł����A������������́A�������B�̐��ʂƂ��Ď�����ŏ^���Ă������̂ł��傤���B
�@���݁A���{��A�����J���܂߂āA���E�̎�v���́A��O�Ȃ��A�����ԑ䐔�̉ߏ�ɂ���ʏa��A��C�������䂫�N�����Ă��܂��B���ꂪ����ɒ����̑�n�ɂ��L�����Ă������ƂɂȂ�܂��B�C���h�Ⓦ��A�W�A�����ł��A�X�т����X�ɔ��̂���Ă�������ŁA�����Ԃ̐��Y�ƗA���͋}���ɑ��������Ă��܂��B���́A���̂悤�Ȏ����Ԃ̗Ⴞ�����Ƃ��Ă݂Ă��A�����������R���̍Đ��y�[�X���͂邩�ɏ��鑬�x�ŁA���R��j�����Ă��邱�Ƃł��B����A�r�㍑�̐l�X�̐����������オ���Ă����A���͂���ɐ[���ɂȂ��Ă����܂��B�V�O���l�̐��E�l�����A���ׂĐ�i�����݂̐���������悤�ɂȂ�A�����n������芪�����R���̕��ה\�͂��A����ɑς���Ȃ��Ȃ�̂͒N�̊Ⴉ�猩�Ă����炩�ł��B
�@���R�j��Ƒ�C�����A����Ɍ������̂ɂ����ǂ̖��B���{�ɏZ�ގ������̑O�ɂ́A�����{�̍Đ��̂ق��ɁA���܁A�����̓�̑傫�Ȗ�肪�����͂������Ă��܂��B������ǂ������Ă����悢�̂ł��傤���B�`�F���m�u�C����X���[�}�C�����̎��̂̎��́A�܂��Ί݂̉Ύ��ł������A���x�͓��{�̕����ł��B���̂��N����������ŁA�[���Ȕ�Q�͂܂�����������������܂���B���S�_�b�����������Ƃ���A�����p�~�̐��_���₩�ɍ��܂���݂��A��ɂ���ă}�X�R�~���A����ɒǏ]����悤�ɂȂ�܂����B�J���Ă��܂����p���h���̔��́A�Ȃ�Ƃ��Ăł��܂����Ȃ���Ȃ�܂���B����͂��̒ʂ�ł��B
�@�������A���ꂾ���ł͒n���͋~���Ȃ��ł��傤�B������p�~���Ă�����Η͔��d�ŕ₦�A���ΔR����R�₵�����邱�Ƃɂ���C����������Ɋg�傷�邱�Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�܂���B�������A�n��Ɍ��肳��Ă��錴���̔�Q�����A�n���K�͂ōL�����Ă����C�����̔�Q�̂ق����ނ���[���ŁA�r��ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�����܂ŗ��āA�}�ɁA���͂⑾�z���Ȃǂ̎��R�G�l���M�[�̗��p�����i�����悤�ɂȂ�܂������A���R�j��̃X�s�[�h�𗎂Ƃ��ɂ́A�܂��܂�����������ł��B�n�����̊�@�I�ȏ́A�܂�������������ɂ͌������Ă��Ȃ��̂ł��B
�@�n�����a�����Ă���46���N�A700���N�O�Ƀ`���p���W�[�Ǝ}�����ꂵ�āA���l�A���l�A���l���o�Č��݂̐l�ނ̑c�悪�A�t���J�ɏo�������̂�20���N�O�A���̃A�t���J���o�đS���E�֊g�U���n�߂��̂�6���N�O�A�����āA���̎��͕X�͊��̐^���Œ��ŁA2���l���炢�����������̑c��́A�H�Ɠ�Ő���l�ɂ܂Ō������Ă����Ƃ����Ă��܂��B���̎��̑c�悽���̋Q����~�����̂����̖_�����H���č����������ŁA����ɂ���ē����������܂Ŕ����悤�ɂȂ�A�����鏬������߂炦�ĐH�ׂ���悤�ɂȂ�܂����B�����炭�A���ꂪ�l�ނ̍ŏ��̕����̗���ł������ł��傤�B���̐l�ނ��A�n���̗��j����݂�ق�̈�u�̂����ɁA�����Ƃ����ԂɁA���܂�70���ɑ����āA����̍���ȕ����̋��Ђɔ�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�������́A���̕����̋}���Ȕ��B�ɂ��A���m�ɂ��ӂꂽ�O�H�̐��������Ȃ���A���̂܂ɂ��A�l�Ԃ��A�n����̂Q�O�O����̐����̂��̂��Ƌ������A���R�̂Ȃ��Ő�������Ă��鑶�݂ł��邱�Ƃ�Y��Ă��܂��Ă���̂�������܂���B����̐�i�����̐l�Ԃ́A��N�O�̐l�Ԃ��P�N�ԂŎg���G�l���M�[���A����������ŏ�������Ă���Ƃ����܂��B�������A����قǂ̗B��Ƒ��I�ȘQ��𑱂��Ȃ���A�ǂꂾ���̐l�X���A�����뉸�₩�ȁA�K���Ŗ������肽�����𑗂��Ă���ł��傤���B���{�����ł��A�Ȃ��A���N�R���l���鎩�E�҂��o�Ă���̂ł��傤���B�������́A���܁A��l�ЂƂ肪�A�l�ԂƂ��Ă̐��������̂��̂��s������Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B
�@�@ (2012.02.01)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@�@�@�@�@�@�@���������邱�Ƃɂ��čl����
�@�@�@�@�@�@�@�@�\ �����ƕ������߂��鐏�z (81) �\
�@�ܖ؊��V���́A���؏܍�ƂƂ��Ē����ł����A�w�e�a�x�A�w�@�@�x�Ȃǂ̒��삪����ق��ANHK�́u21���I�����ւ̗��v�ɏo������ȂǁA�����ɂ��Ă��[���S�������Ă��܂��B�ŋ߁A���́w���́x(�u�k�ЁA1998�N)�Ƃ����{��ǂ�ł��܂��ƁA���̂Ȃ��Ɂu�����͂͂����ĈӖ��̂��邱�ƂȂ̂��v�Ƃ����^�C�g���̈ꕶ������A�����ɂ͂��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B
�@�s���{�̒j���̕��ώ����͎��\�����炢�ł��傤���B����͐��E�Ɋ����钷�������{�̕��ώ����ł�����A���E�S�̂��Ђ�����߂čl����ƁA�Z�\�N�ȏ㐶����Ƃ����̂́A�s���R���l�H�I�ɐl���������Ă���A�Ȃɂ����R�̐ۗ��Ƃ������̂ƃY���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����܂��B�t
�@���̖{���o����Ă������13�N�o���Ă��܂�����A���̓��{�l�j���̕��ώ���77�Ƃ����̂́A�C�����čl����K�v������܂��B���N(2011�N)��WHO(���E�ی��@�\)�̃f�[�^�ł́A���{�l�̕��ώ����́A�j����80�A������86�ł��B�j�����ςł�83�ŁA����͐��E��̂悤�ł��B���łɒ��ׂĂ݂܂��ƁA���E�̕��ώ����́A�j����66�A������71�A�j�����ς�68�ŁA���̂����A�ł����ώ������Z���̂̓}���E�C��47�ŁA���{��36���������Ă��܂��B
�@�ܖ؎���1932�N���܂�ł�����A�����2�ΔN���ł��B������������̂͋t�Z���Đ����܂��ƁA�����炭66�ΑO��ŁA���łɂ��̍����玁�́A60�N�ȏ㐶����Ƃ����̂́u�s���R�v�ŁA�u���R�̐ۗ��Ƃ������̂ƃY���Ă���̂ł͂Ȃ����v�ƍl���Ă������ƂɂȂ�܂��B���̖{�ł́A���͂���ɁA���̂悤�ɂ��q�ׂĂ��܂��B
�@�s�u�m���v�Ƃ������t������܂��B���邱�Ƃ�m��\�B
�@�K���������͂���������̐����ő̌����Ă���Ƃ͎v���܂��A�N���o�邲�ƂɎ��Ƃ��ڂƂ��A���̑��������̊튯�������Ă䂫�A�l�Ԃ͂��̕ӂŎd�����I���ċ����Ă�����A�Ƃ����Ăт���������͂��ł��B���ꂪ�̂ł����l���\�N�ŁA����l�̏ꍇ�͂���ɏ\�v���X���ĘZ�\�Ƃ����̂��A�����Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@����ȏ㐶���悤�Ƃ���̂́A�Ӗ����Ȃ��ƌ����܂����A���ɕs���R�ŁA�����ʂȂ��Ƃ����Ă���悤�ȋC�����܂��B�t
�@����͐����v�������������ŁA����l�Ƃ��Ă�60�Έȏ㐶���悤�Ƃ���̂́u���ɕs���R�ŁA�����ʂȂ��Ɓv�Ƃ���̂ɂ́A������ƍl�����܂���Ă��܂��܂��B�ܖ؎��͂���79�̂͂��ŁA����81�ł��B���܂̌ܖ؎��́A�u���ʂȂ��Ƃ����Ă���v�v��������ɋ��߂Ă���̂ł��傤���B���̏ꍇ�́A�u60�Έȏ㐶���悤�Ƃ����v�Ƃ��������A��������Ă����Ƃ����v���ł����A����ł����̊Ԃɂ������������������ƂɂȂ��Ă��܂��āA���Ȃ��Ƃ�����́A�u���R�ł͂Ȃ��v�Ǝ��˂Ȃ�Ȃ��̂�������܂���B����ɂ��Ă��ܖ؎��́A�Ȃ����̂悤�Ȍ���������̂ł��傤���B�������̂悤�ɍl����̂ɂ́A���̂悤�ȔF��������悤�ł��B
�@�s�l�Ԃ́A�n����̔M�щJ�т�Ђ��ς������|���āA�u���C���[�̌{���ʐ��Y���A���̋�����A�ŋ߂ł͗r�����̉a�ɂ��邱�Ƃ܂ł���Ă���B��������āA���̐����̖������̂������k�������Ă���B����ł��āA�l�Ԃ���������܂ł̕��ώ������͂邩�ɏ����ĉ������Ă���B����Ȃ��Ƃ�������邾�낤���A�Ɛ^���ɍl���Ă��܂��̂ł��B
�@�l�Ԃ̉����Ƃ������Ƃ��A�͂����ĈӖ��̂��邱�ƂȂ̂��A���������ƂȂ̂��Ƃ����^�₪�����Ƃ���܂��B�t
�@����́A�S�����̒ʂ�ŁA�����A���̎��̔F���Ɉق����������͂���܂���B���݂܂Ől�Ԃ͒n���K�͂Ŏ��R��j�����Ă��܂������A����́A�l�ԈȊO�̓��A���̖����̂��̂���D�����邱�Ƃł�����܂����B�����āA���̈���ł́A�u���C���[�̌{�݂̂Ȃ炸�A�_�Y���⋛��ނɎ���܂ŁA��ʂ̂��̂���l�H�I�ɑ��₷���Ƃɖ�N�ƂȂ��Ă��܂��B�l�Ԃ��l�ԈȊO�̂��̂���O��I�ɋ]���ɂ��A�����ė��p���āA���̏�Ől�Ԃ̉������d���Ă���Ƃ�����A��͂�A���R�̐ۗ�����݂Ă��A����͍s���߂��ł���Ƃ����ق��͂���܂���B
�@�ܖ؎��̉������^�⎋����l�����ɂ́A���̌l�I�ȑ̌����w�i�ɂ���悤�ł��B�u���̉Ƒ��́A��e���S���Ȃ����̂��l�\��A���e���\�Z�ŁA��͕Е����c������ɖS���Ȃ��āA������l�̒�͎l�\��B�����玩���������Z�\���͂邩�ɉ߂��Đ����Ă��邱�Ǝ��̂��s�v�c�v�ł������ƁA���͏����Ă��܂��B�������77�܂Ő����܂������A����59�ŖS���Ȃ�܂����B����ɁA�����ŖS���Ȃ����͍̂Ȃ�47�Œ��j��21�̎��ł�����A���܂̎��́A60�ǂ��납�A��e��77���������Ă��܂������ƂɂȂ�܂��B���͂��Ă͐�]�̕��ɐ[������ŁA�����Ă����ӗ~�����قƂ�ǎ����Ă������Ƃ�����܂�������A���ꂾ���ɁA�ܖ؎��Ɠ����悤�ɁA���ܐ����Ă��邱�Ǝ��̂��A�s�v�c�Ɏv���邱�Ƃ��Ȃ��ł͂���܂���B
�@�ł�����A�ܖ؎����A�u���ł��Ȃ���Έݒ�ᇂł��Ȃ������̉����v�����炭�����Ă��A�a�@�֍s���Č������悤�Ƃ͂����A�u���ꂪ�咰�K���ł�������A�����|���[�v�ł����Ă��A����͂���ō\��Ȃ���������������Ŏ��ʂ悤�Ȃ��Ƃ������Ă��A����͂���Ŏd�����Ȃ��Ɗo�債���̂ł��v�Ƃ������ɏ����Ă���̂́A���ɂ���R�Ȃ��~�߂��܂��B�����A���̌�ŁA�ܖ؎����A�u���܂�Ă��邱�Ƃɂ��ẮA�I���ł����ɐ��܂�Ă���킯�ł�����A���ʂƂ����炢�́A�����őI���������B�����ł���������̂��I�������A�Ȃ�䂫�C�����ЂƂ̑I���ł��B�����g�́A���܂�呛�����Ď��ɂ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��v�Ə����Ă���Ƃ���ł́A�܂�������ƍl���������܂����B
�@�呛�����Ȃ��Ŏ���ł����̂��A�m���Ɉ�̑I���ł�����A����͕�����܂��B�������A���̂Ȃ��́A�u�I���ł����ɐ��܂�Ă���킯�ł�����v�ɂ́A��͂�^�╄������������܂���B���́A�Ƃ�����莄�����́A���������܂������\���Ɂu�I�����āv���̐��ɐ����邱�Ƃ��w��Œm���Ă��邩��ł��B�t�ɁA���ʂƂ��ɂ́A��C��X�F�[�f���{���O�̂悤�ȍ�����\�͎҂͕ʂƂ��āA�ʏ�́A�������ʂ̂��A�ǂ̂悤�Ɏ��ʂ̂��͕�����܂���A�{���̈Ӗ��ł̑I���͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂��B
�@�Ⴆ�A���[�e�������N�́w�����x�̒��ŁA�����̍��֍s�����`���`���ƃ~�`�����A���̗��N�A�`���`���ƃ~�`���̒�Ƃ��Đ��܂�Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���u��l�̎q�v�ɉ��ʂ�����܂��B����͂������A���Ƃ��b�ɉ߂��܂��A��E�̃R�i����h�C���ɂ��A���̏́u��ςȐ^���v���������Ă���̂������ł��B�i�u���z�W�v65�Q�Ɓj
�@���̎q�́A�`���`���ƃ~�`���̒�ɂȂ邱�Ƃ��u�I�����āv����̂ł����A���̐��֍s���Ƃ��ɂ́A�u���悤�����M�v�Ɓu�S���P�v�Ɓu�͂����v�̎O�̕a�C�������Đ��܂�邱�ƂɂȂ�܂��B�����āA���̎q�́A���܂ꂽ�セ�̎O�̕a�C�������ėc�����Ď��ʂ��Ƃ��m���Ă��܂��B�������A����͗�E�ɂ���Ԃ̂��ƂŁA��U�A���܂�ĕ����̐��E�ɓ����Ă��܂��܂��ƁA���̑I���̎����͍��̉��[���ɂ��܂����܂�Ă��܂��āA���̎q�����ʂƂ��ɂ́A�Ȃ�����ȕa�C�ŗc���܂���ł����̂��A�����v���o���Ȃ��ł��傤�B
�@�������������̂��ƂŁA���߂Đl�̎��ʎ��@���l���Ă݂܂��ƁA�{���́A�ܖ؎��̂悤�ɁA�a�@�֍s�������s���܂����A����͖{���I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��悤�ȋC�����܂����A�c���̂Ƃ��Ɏ���ł��A60���Ă܂������Ă��Ă��A����́A���������̐��ɐ��܂�Ă���O�Ɂu�I�������v�쐫����̂��߂̃X�P�W���[���ɑg�ݍ��܂�Ă���̂�������܂���B�͂����Đ^���͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B
�@���̂悤�Ȃ��̂��̐^���ɍł������̂́A��͂��E����̍��x�̏��ł����A���ă����h���̌���ŎQ���҂̈�l���A�V���o�[�E�o�[�`�Ɂu���S�Ȑ�����������������l�Ԃ�150�܂ł͐�������̂ł͂���܂��v�Ǝ��₵�����Ƃ�����܂��B����ɑ��āA�V���o�[�E�o�[�`�͂��������Ă��܂����B
�@�s���̓I�N��Ɨ�I���n�x�Ƃ��������Ă͂����܂���B��Ȃ͔̂N��̐��ł͂Ȃ��A���̂�ʂ��Ĉꎞ�I�Ɍ������Ă����̐����E���W�E�J���̒��x�ł��B
�@���̂��n��ʼni�炦��N���т����邱�Ƃ͐_�̌v��̒��ɂ͂���܂���B�����S���n����Ɩ��痎����悤�ɁA��ɔ������ł���Ɠ��̂��łт�Ƃ������Ƃł悢�̂ł��B�ł�����A�����Ƃ������͖̂Y��邱�Ƃł��B�����������邱�Ǝ��̂͑�ł͂���܂���B�t
�i�u�w�т̞xA�v57-i�j
�@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�������A�ܖ؎��̂����u�呛�������Ȃ��Ŏ��ʁv�I���͂ł���ł��傤�B�������A�ǂ̂悤�ȕa�C�ŁA�������ʂƂ������Ƃɂ��ẮA�`���`���ƃ~�`���̒�̂悤�ɁA���̕������E�ɋ���Ԃ͂��đI���������Ƃ��v���o���Ȃ��̂����ʂŁA����́A�_���̔��f�ɂ��C������ق��͂���܂���B�ܖ؎��̏��������̖{�̃^�C�g���́w���́x�ł����A���͂Ƃ́A�v����ɁA�_���̗͂��낤�Ǝv���܂��B�����Ă���Ԃ͐���t�����ɐ����āA���̌�̂��Ƃ͈��S���Đ_���ɂ��ׂĂ��ς˂�Ƃ����u���ͣ�I���z�ŁA�u�������v���C�y�ɑ����Ă��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@ (2011.12.01)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
No,1�`No,10��
No,11�`No,20��
No,21�`No,30��
No,31�`No,40��
No,41�`No,50��
No,51�`No,57��
No,58�`No,80��
|