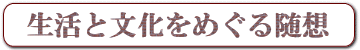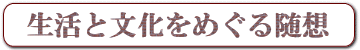|
霊界生活の実相を検証する
― 生活と文化をめぐる随想 (No.101) ―
(2015.05.01)
霊界の生活はどうなっているのか。私たちが霊界へ還った時、どのような姿でどのように生き続けていくのか。これらは私たちにとってたいへん興味ある問題ですが、それを知りたいと思っても、通常は、一部の霊能力者からの霊界通信などを除いては、現世の文献・資料からは答えを引き出していくことは出来ません。しかし、幸いにして私たちは、現代の奇跡ともいえるシルバー・バーチからの膨大な霊界の情報を手にしています。本稿では、それらのいくつかを取り上げ、その真実性を、『新樹の通信』などの優れた霊界通信によって裏付けていってみたいと思います。私自身が関わってきた数多くの霊界通信の一部も、傍証として役立つかもしれません。
まず、私たちは霊界へ移った時にどのような形体を具えるのでしょうか。肉体は脱ぎ捨てていますからもう有りませんが、霊界では霊体をまとうことになるといわれています。それでは、その霊体とはどのような体なのでしょうか。シルバー・バーチは、それを「立派な胴体と、他人と区別のつく容貌を具えた、実在の個的存在です。また他人を認識するための感覚もちゃんと具えております。霊の世界で生きて行く上で必要な霊的器官が全部そろっています」(『シルバー・バーチの霊訓 (10)』p.69)と述べています。
しかし、そのように教えられても、私たちはまだ、どうもすっきりしません。霊体とはやはり幽霊のように影の薄い存在ではないかと想像しがちです。それに対してシルバー・バーチは、念をおすように、「よく理解していただきたいのは、あなた方人間にとって物質は固体性があり実感があり、霊というと何だが影のようで実体がないかに思えるのでしょうが、私たち霊界の者にとっては霊こそ実在であり、実感があり、反対に物質の方が影のようで実体感がないということです」(『霊訓 (10)』p.70)と確言しているのです。
この霊こそ実在であり、物質の方が影であるといわれていることが、私たちの理解しなければならない第一歩であるのかもしれません。そういうことを私たちの言葉で説明するのが非常に難しいのは、何度もシルバー・バーチからも聞かされてきましたが、ここでは、少しでも具体的なイメージが持てるように、私たちにとって親しみ深い霊界の浅野新樹氏に登場してもらうことにしましょう。
昭和4年12月29日、この日は新樹氏が昭和4年2月28日に大連の満鉄病院で亡くなってから10か月が過ぎていました。お父上の浅野和三郎先生が、46回目になる新樹氏との霊界通信で、「多少前にも尋ねたことがあるのが混じるだろうが、念のためにもう一度質問に答えてもらいたい。――お前が伯父さんに呼ばれて初めて死を自覚した時には自分の体のことを考えてみたか?」と問いかけました。伯父さんというのは、和三郎先生の兄上で、心霊研究のよき理解者で協力者でもあった海軍中将・正恭氏です。新樹氏はそれに対してつぎのように丁寧に答えて、問答が続けられています。(『新樹の通信』武本昌三現代文訳 7)
答「そうですね・・・・・。あの時、僕は真っ先に自分の体はと思ったようです。するとその瞬間に体ができたように感じました。触ってみてもやはり生前そっくりの体で、特にその感じが生前と違うようなことはありませんでした。要するに、自分の体だと思えばいつでも体ができます。若い時の姿になろうと思えば、自由にその姿にもなれます。しかし僕にはどうしても老人の姿にはなれません。自分が死んだ時の姿までにしかなれないのです。」
問「その姿はいつまでも持続しているものかな?」
答「自分が持続させようと考えている間は持続します。要するに持続するかしないかはこちらの意思次第のようです。また、僕が絵を描こうとしたり、水泳でもしようとしたりすると、その瞬間に体ができ上がります。つまり外部に向かって働きかけるような時には体ができるもののように思われます。――現に、いま僕がこうしてお父さんと通信している時には、ちゃんと姿ができています・・・・・・。」
問「最初はお前が裸体の姿の時もあったようだが・・・・・・。」
答「ありました。ごく最初に気がついた時には裸体のように感じました。これは裸体だな、と思っていると、そのつぎの瞬間にはもう白衣を着ていました。僕は白衣なんかいやですから、その後は一度も着ません。くつろいだ時には普通の和服、訪問でもする時には洋服――これが僕の近頃の服装です。」
ここで新樹氏が、「触ってみてもやはり生前そっくりの体で、特にその感じが生前と違うようなことはありませんでした」と答えていますが、これが、シルバー・バーチのいう「実体感」なのでしょうか。霊体でも肉体と同じく「生前そっくりの」実体感があることになりますが、ただ、霊界は思念の世界で、こころに思うことが現実になります。だから新樹氏も、「自分の体だと思えばいつでも体ができます。若い時の姿になろうと思えば、自由にその姿にもなれます」と言っているのでしょう。しかし、その一方では、「僕にはどうしても老人の姿にはなれません。自分が死んだ時の姿までにしかなれないのです」とも述べています。やはり老人の姿というのは思念が及ばないということかもしれません。
つぎに、霊界での住宅や周辺の環境についてはどうなっているのでしょうか。シルバー・バーチによれば、私たちがこの世で見慣れている家や建物などは、基本的には劇場や図書館などを含めて、すべて霊界には存在しているようです。博物館には地上の全歴史にわたる資料が保存され、大音楽家によるコンサートはしょっちゅう開かれている。図書館の書物についていえば、地上にある本のすべての複製もあるといいます。その様子を、シルバー・バーチはこう述べています。
霊界にも庭園もあれば家もあり、湖もあれば海もあります。なぜかと言えば、もともとこちらこそが実在の世界だからです。私たちは形のない世界で暮らしているのではありません。私たちもあい変わらず人間的存在です。ただ肉体をもたないというだけです。大自然の美しさを味わうこともできます。言葉では表現できない光輝あふれる生活があります。お伝えしようにも言葉がないのです。(『霊訓 (8)』pp. 115-117)
このような「光輝あふれる生活」については、さまざまな場面でシルバー・バーチが繰り返し伝えてくれています。「花も樹木もあり、動物も小鳥もいます。その美しさの中には実際にこちらへ来ないと分からない種類のものがあります」というのもあります。「霊界の有難い点は、地上のような“生きるための必需品”を得るための苦労がいらないことです。食糧品や衣類を買う必要がありません。お金を払ってまでして家を求める必要がありません。全部そろっているのです」と述べているのもあります。(『霊訓 (10)』pp.70-71)
要するに、この地上にあるものはすべて霊界にもあるらしいのです。この世のすべての物体に対応する霊的複製品があり、新樹氏もそうしているように、生活必需品が整えられたなかで何不自由なく元気に暮らしながら、散歩をしたり、泳いでみたり、音楽や絵画なども楽しむことができるようです。もちろん自分が住む住宅に不自由することもありません。シルバー・バーチは、「霊界ではみんな自分の家を持っているのか」と訊かれた時には、つぎのように答えていました。
―― はい、持ちたいと思う者は持っております。そう望んでそれなりの努力をいたします。が、持とうと思わない者もいます。同じく家を持つにしても自分の建築の好みに合わせて工夫する者もあります。例えばあなた方のご存知ない照明方法を組み込んだりします。こうしたことはその霊の創造的才能に関わる個人的な好みの問題です。
いったん家をこしらえたら、その建築様式は純粋にその人の好みの問題となります。青空天井にしたければそうなります。好みというものは長い間の習慣によって形づくられていることを忘れてはいけません。習慣は精神的な属性であり、死後も存続します。
生涯を英国だけで送った人は当然英国風の住居の様式に慣れ親しんでおり、したがって同じような様式の家に住むことになります。そういう習性が残っているからです。やがてその習性から脱け出せば、また別の種類の住居をもつことになります。こうしたことも生活の連続性を維持するための神の賢明なる配慮なのです。ショックを防ぎ、生活をスムーズに、そして調和のあるものにしてくれています。(『霊訓(2)』pp.149-150)
それでは、具体的に、新樹氏はどのような家に住んでいるのでしょうか。それをこれから見てみることにしましょう。昭和4年12月29日、前回と同じ第46回目の通信の時に、お父上の和三郎先生が、新樹氏の住んでいる家について聞いているところがあります。浅野先生も、新樹氏が霊界でどのような生活をしているのか、気になっていました。その時の問答はつぎのとおりです。(『新樹の通信』武本昌三現代文訳 同上)
問「お前の住んでいる家は?」
答「なんでも最初、衣服の次ぎに僕が考えたのは家のことでしたよ。元来僕は洋館の方が好きですから、こちらでも洋館であってくれればいいと思いました。するとその瞬間に自分白身のいる部屋が洋風のものであることに気づきました。今でも家のことを思えば、いつも同じ洋風の建物が現われます。僕は建築にはあまり趣味はもっていませんから。もちろん立派な洋館ではありません。ちょうど僕の趣味生活にふさわしい、バラック建ての、極めてあっさりしたものです。」
問「どんな内容か、もう少し詳しく説明してくれないか?」
答「東京あたりの郊外などによく見受けるような平屋建てで、部屋は三室ほどに仕切ってあります。書斎を一番大きくとり、僕はいつもそこにいます。他の部屋はあってもなくてもかまわない。ほんのつけたしです。」
問「家具類は?」
答「ストーブも、ベッドも、また台所用具のようなものも一つもありません。人間の住宅と違って至極あっさりしたものです。僕の書斎には、自分の使用するテーブルと椅子が一脚ずつ置かれているだけです。書棚ですか……そんなものはありませんよ。こんな書物を読みたいと思えば、その書物はいつでもちゃんと備わります。絵の道具なども平生から準備しておくというようなことは全然ありません。」
問「お前の描いた絵などは?」
答「僕がこちらへ来て描いた絵の中で、傑作と思った一枚だけが保存され、現に僕の部屋に懸けてあります。装飾品はただそれきりです。花なども、花が欲しいと思うと、花瓶まで添えて、いつのまにか備わります。」
問「いまこうして通信している時に、お前はどんな衣服を着て居るのか?」
答「黒っぽい和服を着ています。袴ははいていません。まず気楽に椅子に腰をかけて、お父さんと談話を交えている気持ですね………。」
問「庭園などもついているのかい?」
答「ついていますよ。庭は割合に広々ととり、一面の芝生にしてあります。これでも自分のものだと思いますから、敷地の境界を生垣にしてあります。だいたい僕ははでなことが嫌いですから、家屋の外回りなどもねずみ色がかった、地味な色で塗ってあります。」
ここでは、着ている衣服のこと、部屋の様子や家具のこと、それに家や庭のことに至るまで、全く自由で自然な会話の中で、こまかく伝えられていることに驚嘆させられます。生垣に囲まれた割合に広々とした庭がある3室ほどの洋風の家に、黒っぽい和服を着て気楽に椅子に腰掛けている新樹氏の姿は、私たちにも眼に見えるようです。この通信を仲介しているのは、優れて霊能者の多慶子夫人で新樹氏の母上ですが、その多慶子夫人の霊眼には、新樹氏の霊界の住宅がまざまざと映っていました。その見取り図もできているといいますから驚かされます。それは浅野先生によれば、とてもあっさりした、郊外の文化住宅らしいものだったとのことでした。
この時の会話の最後に、浅野和三郎先生が、「今日は、話が大へん要領を得ているので、お前の生活状態が髣髴としてわかったように思う。――しかし、私との通信を中止すると、お前はいったいどうなるのか?」と訊いていました。それに対して新樹氏は「通信がすんでしまえば、僕の姿も、家も、庭も、何もかも一時に消えてしまって、いつものふわふわした塊り一つになります。その時は自分が今どこにいるというような観念も消えてしまいます」と答えています。
こういう状況は、私たちの理解を超えますが、これも霊界が思念の世界であることの一つの表れでしょうか。「霊界では思念は実体のある存在なのです。存在するものすべてが思念でこしらえられているのです。ですから、必要と思うものはどんなものでも手に入れることができるのです」(『霊訓 (10)』p.70)と言っているシルバー・バーチのことばなどがここでも思い出されます。必要でなくなれば、だから、なにもかも、一時に消えてしまうのでしょう。
この会話のあと、浅野先生が、「そのうちひとつ、お前のお母さんの守護霊にでも頼んで訪問してもらおうかな」と言っておられますが、新樹氏が「そんなことができるんですか」と驚いている場面があります。その訪問は実現して多慶子夫人の守護霊は新樹氏と逢うためにやってきます。しかし、ここでは、より一般的な、霊界での親しい家族や知人との再会について次に取り上げてみたいと思います。私たちはこの世で死んだあと霊界へ還っていきますが、そこでは先に死んで霊界にいる縁のある人たちと再会することになります。その再開はどのようにして行われるのでしょうか。私たちの死からその再会に至るまでの過程を、シルバー・バーチは、まず、こう述べています。
死とは物的身体から脱出して霊的身体をまとう過程のことです。少しも苦痛を伴いません。ただ、病気または何らかの異状による死にはいろいろと反応が伴うことがあります。それがもし簡単にいかない場合には霊界の医師が付き添います。そして、先に他界している縁者たちがその人の〝玉の緒″が自然に切れて肉体との分離がスムーズに行われるように世話をしているのを、すぐそばに付き添って援助します。
次に考慮しなければならないのは意識の回復の問題ですが、これは新参者各自の真理の理解度に掛かっています。死後にも生活があるという事実をまったく知らない場合、あるいは間違った来世観が染み込んでいて理解力の芽生えに時間を要する場合は、睡眠に似た休息の過程を経ることになります。
その状態は自覚が自然に芽生えるまで続きます。長くかかる場合もあれば短い場合もあります。人によって異なります。知識をたずさえた人には問題はありません。物質の世界から霊の世界へすんなりと入り、環境への順応もスピーディです。意識が回復した一瞬は歓喜の一瞬となります。なぜなら、先に他界している縁のある人たちが迎えに来てくれているからです。(『霊訓 (8)』p. 103)
かつて、あのシャーロックホームズの生みの親であるコナン・ドイルも霊界へ還った時、この霊界での再会について、「愛する者との再会ほど喜びに満ち、心を慰めてくれるものがあるでしょうか。今は亡き、父親、母親、夫、妻、兄弟、姉妹、子供と、再びこの世とあの世の障壁を越えて心を通わせられるということを知るほど、心を慰めてくれるものがあるでしょうか。それは本当のことなのです。素晴らしいことに本当なのです」(『人類へのスーパーメッセージ』p.246)と述べていました。
ただ、ここでひとつ理解しておかねばならないことは、霊界とは階層社会ですから、私たちは霊界では、それぞれの霊格にふさわしい階層に住むことになります。つまり、これまでに到達した霊的レベルが同様の人たちが集まって暮らすのです。だから現世では家族全員が一緒に暮らしていても、霊界では必ずしも一緒でないこともあり得るようです。ある時、シルバー・バーチは、熱心なスピリチュアリストのある夫人を励まして、つぎのように述べたことがありました。彼女の夫は霊的なことにまったく理解を示さず、しかも重病の床にあって、夫を救えないことで彼女は悩んでいました。
―― 一つの家族が霊界へ来ても、自動的に合流するわけではありません。家族のメンバーが自然な霊的親和性をもっている場合にのみ、それが有りえます。親和性がなければ再会はありません。意識のレベルが違うからです。
夫婦の場合であれば、身体上の結婚だけでなく魂と精神においても結ばれていなければ、霊界での再会は不可能です。再会を決定づけるのは霊的親和性です。死後しばらくは血縁によるバイブレーションが残っていますが、それには永続性がありません。
霊は物質に勝ります。霊に関わるものは死後にも残り続けますが、物質に関わるものはそのうち消えます。お子さんにそのことをよく説明してあげないといけません。なかなかうまく説明できないかも知れませんが、とにかくすべてが不変の法則によって支配されているのです。その法則の根本にあるものは愛です。愛は大霊の表現です。神、創造主、どう呼ばれても結構です。首をうなだれてはいけません。あなたはしっかりと導かれ援助をうけておられます。きっと乗り切ることができます。一瞬たりとも挫折の心配を抱いてはなりません。このたびの経験は結果的にはあなたの霊性を強化し、前途に横たわる未来において大きな豊かさをもたらしてくれる貴重な教訓を植えつけてくれることでしょう。
私は地上の同志の方に気楽な人生、何の障害もない人生をお約束することは絶対にできません。私から言えることは、障害も困難もその一つ一つが挑戦すべき目標だということです。一つ克服するごとに、あなたは霊的に成長するのです。(『霊訓 (10)』、pp. 117-118)
シルバー・バーチも言うように、人生の目的は霊性の向上にあり、私たちは悲しみや悩みや艱難辛苦を乗り越えていくことで霊性を高め、霊界の生活に備えていくことになります。その霊性の発達度によって、おのずから霊界での生活環境がきまっていくことになりますが、私たちが数多く目にする霊界での再会も、いわばそのようなスクリーニングを経て実現しているのです。そのことを理解したうえで、ここでは、霊界でのアン・ターナーと私の妻と長男との再会を取り上げてみることにしましょう。
アン・ターナーは、ロンドンで私が逢うべくして逢った霊能者で、私の書いたものの中で何度も紹介してきましたが、彼女は、イギリスのウエールズで2010年の8月22日に癌で亡くなりました。亡くなる前の入院中には、霊界の私の妻・富子と長男・潔典が何度か彼女をお見舞いに訪れています。彼女は優れた霊能力者でしたから、霊界からの訪問者を認識することができます。病室で富子と潔典と手を握り合って、彼らのお見舞いに感謝していました。(『天国からの手紙』pp.272-277) そのアン・ターナーが霊界で、私の妻と長男に「再会」した記録が私の手許にあります。
私の『天国からの手紙』が学研パブリッシングから出版されたのは、アン・ターナーが亡くなった翌年の2011年6月でした。たまたま潔典の誕生日が6月5日で、彼は霊界からこの本の出版をいろいろと支援してくれていましたから、1日早めでしたが、その誕生日に合わせて、江東区清澄公園の大正記念館で6月4日に出版記念講演会を開くことになりました。その日は、講演のあとサイン会があって、それが終わってから、編集者の方々が、近くのレストランで潔典の誕生祝の会を催してくれました。その席上で、思いがけなく、編集者の一人で霊能者の
Uさんから、潔典が霊界から送ってきた手紙を渡されたのです。かなり長い手紙で、そのなかには、アン・ターナーに触れて、つぎのように書いていました。
―― アン・ターナーはこちらに参りました。神々様のお使いになるべく、日々修行に励んでおります。ぼく達とは縁で結ばれた方です。お互いにお互いを救う境遇に絶えずあります。こちらにおいても、現世のお父さんたちをも含めて、お互いに導き助け合うことが行われているのです・・・・・・
そして、このあとに私宛のアン・ターナーからのことばも伝えられました。「アン・ターナーからお父さんへ」と潔典の但し書きがあって、そのなかでアン・ターナーはつぎのように私の妻と長男との再会について触れています。以下は、彼女のことばです。
私たちは縁があってめぐり合い、共に歩んでまいりました。私はこの縁をたいへん有難く思っています。こちらにきてキヨノリとめぐり合い、トミコさんともお会いして、思っていたとおりの方々でした。素晴らしい方々です。
私は二人にたいへんお世話になりましたが、これもショーゾー、あなたとの縁が結び付けてくれたものです。さまざまなつながりの中で、人と人が和すること、これこそあなた方が本来持つ素晴らしいものですね。いま日本は(東日本大震災で)大変な時にありますが、あなたのその苦しみの経験から得たものを用いて、多くの人々が目覚める導きができることを、心から願っております。
霊界はなかなか良い所、素敵な所ですよ、ショーゾー。あなたがいらっしゃるのを楽しみにしています。どうかお体に気をつけて、それまで多くの人びとを導く活動を続けてください。そうそう、たまにはトニー(*アンの夫君)にも連絡してあげてくださいね。私は元気でいるとお伝えください。それではまたお会いしましょう。(アン・ターナー)
以上、霊界への帰還から霊界での再会に至るまで、霊界での広範な生活のうちのごく一部を断片的に拾い上げてみました。このなかで触れている新樹氏の生活にしても、詳しい生活状況については『新樹の通信』一冊分にもまとめられていますし、私の妻や長男からの通信も、『天国からの手紙』に載せたものを含めて、何人もの霊能者から受け取ったものが、過去20年の間にかなりの量に達しています。
最近では、大空澄人氏を通じて、時折、妻・富子からの通信も届くようになりました。そのなかには、霊界での再会について、「(地上世界では)様々な問題に遭遇して理解力が深まるのです。しかしながらそこで暮らすのは一時の事です。そこでのトレーニングが終了すれば元の愛の輪のなかに帰ることが出来ます。そこでは歓呼の再会があなたを待っています」などと伝えてきているものもあります。(2015.02.22「愛の輪」より) この私の霊界での家族との再会については、潔典からも今まで何度も聞かされてきました。具体的に歓迎の準備に触れているのもあります。それらの霊界通信の数々の記録によっても、いろいろと教えられ学んできて、いまの私にとっては、霊界とは必ずしも遠い未知の世界ではありません。
これまで私は、長年の間、このような霊的真理について講演会で話したり本に書いたりしてきました。一人でも多くの方々が、私の体験や学びを踏み台にして生と死の真実に触れていかれるようになることを願望していますが、ここでは、今回もまた、大空澄人氏のご了解を得たうえで、氏のご友人の霊界からの元気なお便りを最後に引用して、この稿を終えたいと思います。「続・いのちの波動」(1015.03.04) に、「海を眺めて」と題して、大空澄人氏は、幼友達であった霊界のご友人からのお便りをこう伝えておられました。かつてのこの世での、ふる里の小豆島の海で大空澄人氏と楽しんだヨット乗りの思い出から語り始められているのが、私のような大阪湾の海辺で生まれ育ってきた者には、ことさらに印象深く思われます。
[友より]
こちらは好きなだけヨットも楽しめるよ。君がこっちに来たらまた一緒にヨットに乗ろうではないか。そっちで暮らしていた時は仕事や家族その他の事にがんじがらめに縛られていた。それが今はそういうものから解放されている。そして何でも楽しみながら学ぶことが出来る。その辺がそちらとの一番の違いかな。
僕が暮らしていた地域ではお互いが足を引っ張り合うから伸びていけない。こっちに来たらまずそういう考え方を改めないと成長できない。僕は今そういうものを改めているところだ。そこで暮らしている間に染み付いた汚れを落としているのだ。
君がこちらの世界と通じるのはこちらの人間に近いからだ。欲が少なくて人と競争したりするのを好まないから。我の強い人間はこちらとは通じにくい。地位や名誉にこだわっている者も無理だ。理屈っぽいのもダメ。問題は無我の境地になれるかどうかだと思う。
子供の頃の純粋さを失わないことが大切だと思う。純粋な人間はすぐにこちらに溶け込めるようになるよ。人を恨んだり妬んだりしている人間は自分で自分を低いところへ落としているようなものだ。勝手に沈んでいくから。でもそういう人間はこちらに来るまでそれに気が付かないのだ。
長寿と短命をどう受け留めるか
―生活と文化をめぐる随想 (100)―
(2015.03.01)
司馬遼太郎『宗教と日本人』(文春文庫)には、司馬氏が吉田松陰の文才を褒めて、つぎのような文章を紹介しているところがあります。幕末に安政の大獄(1858-1859)がありましたが、そのなかで吉田松陰は 30歳の若さで斬罪されています。処刑を知った松蔭は、江戸の小伝馬上町の牢獄で、その二日前から門下生たちに宛てた遺書を書き始めて、処刑前日に長文の「留魂録」を書き上げました。司馬氏が取り上げているのはそのうちの一部です。このような文です。
〈今日死を決するの安心は四時の順環に於て得る所あり。蓋し彼の禾稼を見るに、春種し、夏苗し、秋苅り、冬蔵す。秋冬に至れば人皆其の歳功の成るを悦び、酒を造り醴を為り、村野歓声あり。末だ曾て西成に臨んで歳功の終るを哀しむものを聞かず。吾れ行年三十、一事成ることなくして死して禾稼の末だ秀でず実らざるに似たれば惜しむべきに似たり。然れども義卿の身を以て云へば、是れ亦秀実の時なり、何ぞ必ずしも哀しまん。何となれば人寿は定りなし、禾稼の必ず四時を経る如きに非ず。十歳にして死する者は十歳中自ら四時あり。二十は自ら二十の四時あり。三十は自ら三十の四時あり。五十、百は自ら五十、百の四時あり。十歳を以て短しとするは蟪蛄をして霊椿たらしめんと欲するなり。百歳を以て長しとするは霊椿をして蟪蛄たらしめんと欲するなり。斉しく命に達せずとす。〉
いまではこういう文章も読むのが難しくなりましたが、このなかの「義卿の身を以て」の「義卿」は松陰の字(あざな)です。そのほか、おもな単語を広辞苑などで調べますと、「禾稼」は穀物、穀類のこと。「禾」はイネ科の植物の穂で、「稼」はみのりを表わす、とあります。「醴」は甘酒、白酒類。「蟪蛄」は夏蝉のことで、短命の例えとして使われます。「霊椿」は長寿の木と考えていいでしょう。この文を現代文風に分かり易く書き直してみますと、次のようになるかと思われます。
〈今日、私が死を目前にして平静な心でいるのは、春夏秋冬の四季の循環を考えるからである。つまり、農事をみると、春に種を撒き、夏に苗を植え、秋に刈り取り、冬にそれを貯蔵する。秋・冬になると農民たちはその年の労働による収穫を喜び、酒や甘酒を造っては村々に歓声が満ち溢れるものだ。この収穫期を迎えてその年の労働が終わったのを悲しむ者がいるとは聞いたことがない。
私は30歳で一生を終わろうとしている。いまだ一つも成し遂げたことはなく、このまま死ぬのは、これまでの働きによって育てた穀物が花を咲かせず、実をつけなかったことに似ているから、惜しむべきかもしれない。だが、私自身について考えれば、やはりこれが花咲き実りを迎えた時なのである。なぜなら、人の寿命には定まりがない。農事が必ず四季をめぐって営まれるようなものではないのだ。
しかし、人間にもそれにふさわしい春夏秋冬はあるといえるだろう。10歳にして死ぬものには、その10歳の中におのずから四季がある。20歳にはおのずから20歳の四季が、30歳にはおのずから30歳の四季が、そして、50、100歳にもおのずから50、100歳の四季がある。10歳をもって短いというのは、短命の夏蝉の短い命を長生の霊木の命に取り替えようと願うようなものだ。100歳をもって長いというのは、長生の霊木の命を夏蝉の短い命に変えようとするようなもので、いずれも天寿に達するということにはならない。〉
司馬氏のいうように、これは30歳の文章とは思えないほどの名文ですが、私は、その名文よりも、松陰がこのなかで、「10歳をもって短いということにはならない」、「100歳をもって長いということはできない」といっていることばに惹きつけられていました。おそらく10歳も、100歳も、それぞれがその人の天寿なのでしょう。松陰にとっては、30歳が天寿でした。この「留魂録」の文は、いろいろな文献に残されていますので調べてみますと、この後、こう続けられています。ここでは、松本三之介『吉田松陰』(中央公論社、1955、p.366)の訳文を、そのまま引用してみましょう。
〈私は30才、四季はすでに備わっており、また花咲き実は結んでいる。それが実のよく熟していないもみ殻なのか成熟した米粒なのかは、私の知るところではない。もし同志のなかでこの私の心あるところを憐れんで、私の志を受け継いでくれる人があれば、それは撒かれた種子が絶えないで、穀物が年から年へと実っていくのと変りはないことになろう。同志の人びとよ、どうかこのことをよく考えてほしい。〉
吉田松陰はこのような遺書を残して 30歳の若さで刑場の露と消えていきました。その最後の「撒かれた種子」のことばは、期せずして、聖書ヨハネ伝(12:24)の、「一粒の麦、地に落ちて死なずにあらばただ一つにてあらん。もし死なば、多くの実を結ぶべし」を思い起こさせます。実際、松陰の死は、貴重な多くの実を結びました。あの幕末の動乱の時代に、師を慕う弟子たちの魂を奮い立たせ、日本の国家体制さえも大きく動かして、明治維新へと導く礎を築きあげていくことになりました。
ところで、刑死といえば、太平洋戦争末期の、あの尾崎秀美のことも思い出されます。当時、日本の軍閥は、国防を強化するためと称して、満洲や中国大陸への侵略に乗り出していました。日本経済は破滅の淵に瀕しているといって国民を欺きながら、大陸における資源も強奪し始めています。一高、東大を出て朝日新聞の記者になった尾崎は、上海にいてそのような軍部の実態を知り深く憂えていました。やがて中国問題の専門家として、当時の第一次近衛内閣の嘱託になった尾崎は、そのような軍閥の暴走を内部から食い止めようとします。そして、あのゾルゲ事件が起きました。尾崎は、国防保安法違反などの罪名で、1944年11月7日に東京拘置所の絞首台で処刑されました。44歳でした。
その尾崎秀実が獄中で書いた『愛情はふる星のごとく』は、敗戦後の日本でベストセラーになりました。そのなかに、1944年10月7日付けで妻に宛てて書いたつぎのような手紙があります。死ぬことが決まって、処刑の一か月前に書かれた手紙です。このなかで、尾崎は、「今月の15日は、私が家を離れて丁度
3年になる。17日の我が家の紀念日は、一つ特に私のために祝ってほしいと思う」と書き出しています。この「わが家の記念日」とは、死刑が確定して自分のいのちが断たれることになった事態を意味しています。そのあと、尾崎はこう書いています。
〈僕が祝ってほしいと云うのは、この 3年の流れ去った月日がこの僕にとってどんなに貴重な有難いものであったかを心から思うからである。この年月があったからこそ、今日僕は始めて人生の真意義を覚り、かくも静かにかつ楽しく日を送ることも出来るようなったのだ。もしもこの異常なる月日が無かったなら、僕は毎日ただ怱忙の裡にあくせくと日を送ってしまったことだろうと思う。僕の一生はもしも僕が別の道を行くならば、恐らくは社会的には高名、栄位をかち得られたことであろう。しかし人間として今日僕の立っているごとき確乎たる足場に立つことは遂に出来なかったことは明らかだ。〉(尾崎秀実『愛情はふる星のごとく』 岩波現代文庫、2003年、p.371)
尾崎はここで、獄中の 3年があったからこそ、「始めて人生の真意義を覚り、かくも静かにかつ楽しく日を送ることも出来るようなった」と書いています。別の道を進んでおれば、「おそらく社会的には高名、栄誉をかち得られた」であろうが、しかし、それでは現在のこの心境には達しなかったはずだとも書いています。生きることの意味を深く考えさせられる文章です。この手紙は、さらに次のように続きます。
〈僕は人生の意義を知り、生命の正当なあるがままの姿に徹し、社会と、親しきものへの愛情を限りなく深めるとともにまた純化することも出来た。そこにこそ我々3人のものの永遠に生きる道をも発見し得たのだと、僕はひそかに感じている。だから僕のために祝ってくれることは、実は我々3人のものの共通なよろこびであると私は確信しているのだ。今日このことをお前たちにほんとに分らせることは無理だと思う。すべて冷暖自知あるのみだから。しかしおぼろげには分ってくれたものと思う。僕が決して無理をしたり頑張って、一人こんなことを云っているのでないということを。〉(尾崎、同書 p.372)
このなかで、「人生の意義を知り、生命の正当なあるがままの姿に徹し」といっているのは、いのちの何であるかを意識の深いところで感得することができた、ということでしょう。古来、高僧や人生の修行者たちが、難行苦行を重ねたりして会得するいのちの真理を、尾崎秀実は、獄中の死を前にした絶体絶命の境地の中で、確固として自分のものにしていきました。ですからこの文は、「永遠に生きる道をも発見し得たのだ」と続けられているのだと思われます。
この本には、このほかにも、獄中での深い思索を通じて死の恐怖を乗り越え、死を安らかに受け容れる覚悟ができていることを冷静に伝えている多くの手紙があります。そういう手紙では、自分の悟りの心境を、決して虚勢を張って言っているのではないことをつけ加えたりしていますが、その手紙の通り、尾崎秀実は、「取り乱したる態度はなく」、「南無阿弥陀仏」と
2度唱えながら、聖者のように淡々として死んでいったことが、その後に発見された処刑記録によって明らかにされました。(「朝日」2004.10.17)
私は、ここに引用した手紙を「学びの栞 B」(10-a) にも載せておきました。そして、その文には、当時は「国賊」とか「売国奴」とまで言われて日本中の非難の的となった尾崎秀実の真実の姿と事件の背景を少しでも正しく理解するために、尾崎秀実の一高時代からの親友であった松本慎一の文も、一部抜粋してつけ加えてあります。敗戦まではあれほどまでに声高に叫ばれていた「鬼畜米英」が、一夜明けると、一変して「民主主義の旗頭」として崇められていったあの異様な風潮のなかで、真の愛国者とは誰であるかを、深く考えさせられる一文だと思います。
私がこのような人間の死に方について改めて深く考えさせられるようになったのは、1983年にあの大韓航空機事件で妻と長男を亡くしてからでした。悲嘆の底に突き落とされて、溺れる者が藁にもすがる思いで、いろいろな本を読んでいきましたが、そのなかに、内村鑑三
『基督信徒のなぐさめ』(岩波書店、1983年)があります。その本の第一章「愛するものの失せし時」では、内村は、愛児を亡くした悲しみを次のように書いていました。
〈生命は愛なれば愛するものの失せしは余自身の失せしなり、この完全最美たる造花、その幾回となく余の心をして絶大無限の思想界に逍遥せしめし千万の不滅燈を以て照らされたる蒼穹も、その春来るごとに余に永遠希望の雅歌を歌いくれし比翼を有する森林の親友も、その菊花香しき頃巍巍として千秋に聳え常に余に愛国の清を喚起せし芙蓉の山も、余が愛するものの失せてより、星は光りを失いて夜暗く、鶯は哀歌を弾じて心を傷ましむ、富嶽も今は余のものならで、かつて異郷に在りし時、モナドナックの倒扇形を見、コトバキシの高さを望みし時、わが故郷たらざりしがゆえにその美と厳とは反て、孤独悲哀の情を喚起せしごとく、この世は今は異郷と変じ、余はなお今世の人なれどもすでにこの世に属せざるものとなれり。〉(p.16)
古い文体で、愛児を失った悲しみがこのように綿々と記されています。伝わってくるのは、「生きてはいても、死んだも同然の身になってしまった」という深い嘆きでしょうか。この時の内村は、死ぬこと自体には、「この世は、いつかは去るべきものなれば今これを失うも三十年の後に失うも大差なかるべし」と、自分自身のいのちをも見つめて、一応の達観を示していました。それでも彼を最も苦しめたのは、愛児がなぜ短命で死ななければならなかったかということでした。愛児は、愛のためには自分を忘れて身を捧げる純白なこころの持ち主で、それでいて、一日も心痛のない日はなく、生まれてから短命で死ぬまで、不幸艱難が続きました。死ぬ時には非常な苦痛をさえ味わっています。聖書には、この世は神を敬う者のために造られた、とあるのに、この最も神を慕っていた者が最もわずかにこの世を楽しんで死んでいったのはなぜか、と思い悩むのです。神はないのかと迷い、しばらくはお祈りさえしなくなりました。
かつての私は、このような内村の文章にも深くこころを打たれていました。世間ではまだ幼い子が亡くなったような時、よく、「どうしてあんなにいい子が・・・・・」と言ったりします。最も神に愛されているはずの純真無垢の子が早死にしてしまうようなことは、どう考えても理不尽で、やはり「神も仏もないのか」と思ってしまいます。人によっては、何も悪いことをした覚えはないのになぜこんな不幸に遭わねばならないのかと訴えたい気持ちにもなるでしょう。自分が死ぬのを受け入れることができても、子供に死なれるのは耐えがたい苦しみです。内村も、「神はないのか」と苦しみ悩みました。愛児が「なぜ短命で死ななければならなかったのか」と悲痛な心情を吐露してもいます。
その内村は、それらの苦しみをどう乗り越えていったのでしょうか。「神はないのか」という深刻な疑問については、内村はこの本のなかで、「もし神なしとせば真理なし、真理なしとせば宇宙を支える法則なし、法則なしとせば我も宇宙も存在すべき理なし」と書いています。そして、「ゆえに我自身の存在する限りは、この天この地の我目前に存する限りは、余は神なしと信ずる能(あた)わず」と結論づけました。それでは、その神は、なぜ愛児を取り去るという「大試練」を与えたのでしょうか。内村が辿り着いた結論はこうです。
〈ああ神よ、爾は我らの有せざるものを請求せざるなり、余は余の有するだけの熱心を以て祈れり、しかして爾は余の愛する者を取り去れり、父よ、余は信ず、我等の願うことを聴かれしに依て爾を信ずるは易し、聴かれざるに依てなお一層爾に近づくは難し、後者は前者に勝りて爾より特別の恩恵を受けしものなるを、もし我の熱心にして爾の聴かざるが故に挫けんものならば爾必ず我の祈祷を聴かれしならん。〉 (p.22)
つまり、神は決して、罰として艱難を下すことはない。このような大試練に彼が耐え得ることを知っているがゆえに、神は彼の願いを聞き届けなかったのです。彼の祈りが不熟心であったからではなく、むしろ十分に熱心であったが故に、神はこの苦痛を彼に与えました。愛児の死は、そのような彼に与えられた選ばれたものに対する恩寵でさえあるのでしょう。熱心なキリスト教徒としては、あるいは当然の帰結であったかもしれませんが、ここまで信仰が深められれば、あとは、感謝と喜びがあるだけです。それを内村は、「然り余は万を得て一つを失わず、神も存せり、彼も存せり、国も存せり、自然も存せり、万有は余に取りては彼の失せしが故に改造せられたり」と書きました。そして、最後を感動的なつぎのような文章で締めくくっています。
〈余の得し所これに止まらず、余は天国と縁を結べり、余は天国ちょう親戚を得たり、余もまた何時かこの涙の里を去り、余の勤務を終えてのち永き眠りに就かん時、余は無知の異郷に赴くにあらざれば、彼がかつてこの世に存せし時彼に会して余の労苦を語り終日の疲労を忘れんと、業務もその苦と辛とを失い、喜悦をもって家に急ぎしごとく、残余のこの世の戦いも相見ん時を楽みによく戦い終えしのち心嬉しく逝かんのみ。〉(p.28)
前に触れたように、1983年の事件以来、私自身も嘆き苦しみながら、長い間、生と死の問題に心を囚われていました。キリスト教徒ではありませんが真剣に聖書に向き合うようになり、仏教徒ともいえない私が、毎日仏典を唱えるようになっていました。しかし、仏典はいくら熱心に読もうとしてもよく理解できません。聖書も、読んで感動することがあっても、なかなか、内村のように「万を得て一つを失わず」という心境にはなれませんでした。尾崎秀実が獄中の絶体絶命の境地のなかで「永遠に生きる道をも発見し得た」ことについても、その意味がよくわかっていなかったかもしれません。
その私が変わってきたのは、やはり、スピリチュアリズムに接するようになってからのことです。具体的には、1991年の4月からロンドンに住むようになってからで、もう事件から
8年も経っていました。私はロンドン大学へ通う傍らシルバー・バーチを読み始め、その重大さに気づいて大英心霊協会へも頻繁に行くようになりました。その一年間の滞在を経て、私は初めて、生命は永遠であるという真実に目覚め、それまでぐずぐずと引きずっていた事件後の深刻な後遺症から救われたのです。
それまでは、長男がなぜ 21歳という若さで亡くならねばならなかったのか、と私は随分苦しみ続けていました。しかし、いのちが永遠であることがわかれば、苦しみはおのずから消えていきます。人生がこの世だけのものであるとすると、長生きしてもせいぜい100年であって、多くは80年、90年で死んでいきます。この短い一生のなかで、たとえば、21年と80年を比べれば、その差は極めて大きく、その大きな差は、そのまま深い絶望的な悲しみの差となって跳ね返ってくることになります。内村のいうように、「この世は、いつかは去るべきものなれば今これを失うも三十年の後に失うも大差なかるべし」という心境にもなかなかなれないでしょう。しかし、永遠のいのちからみれば、その途中の、60年や80年の差は、決して大差ではありません。小差でさえないでしょう。松陰のように、「十歳を以て短しとするは蟪蛄をして霊椿たらしめんと欲するなり。百歳を以て長しとするは霊椿をして蟪蛄たらしめんと欲するなり。斉しく命に達せずとす」などと考えるまでもなく、その差は限りなく零に近いのです。
しかし、このいのちの真理はすぐ身近にありながら、なかなか理解されにくいのが実状です。シルバー・バーチも、「光が与えられるのに、何故人びとは闇を求めようとするのでしょうか。知識を得ることができるのに、何故無知のままでいたがるのでしょうか」と嘆いていますが、見る目と聞く耳があれば、そして、素直に求め続けさえすれば、それは誰にでも手に入れることができます。決して手の届かない遠く高いところにあるのではありません。さらにそれは、この世で多くの人びとが血眼になって手に入れたがる莫大な財産や高い地位名誉などにくらべても、はるかに勝る不滅の価値があるといえるでしょう。何よりも恐ろしいと思われている死の恐怖から解放されます。愛する者の死を悲しむこともなくなります。幼くして死ぬことへの捉え方もまったく変わってしまうかもしれません。
しかも、繰り返すようですが、その貴重な真理を手に入れるためには特に難行苦行する必要はないのです。金銭も要らないでしょう。必要なのは、汚れのない素直な心と、ものごとを正しく判断できる人間の理性であろうと思われます。私は私なりに、その真理へ至る道への判断資料を数多く、このホームページにも載せてきました。例えば、このなかの「霊界通信」だけを取り上げてみても、『新樹の通信』が伝えているのは殆ど現代の奇跡ともいえる内容で、永遠の生命を証明する第一級の資料であろうと思います。ほかにも、「リンク集」で紹介している大空澄人氏の貴重な霊界通信もあります。本稿にとっても重い比重を持つ「若くして世を去ることの意味」についても、氏の「いのちの波動」(2007.10.26)をクリックするだけで、つぎのように明快な真理のことばを読むこともできます。
〈早く世を去るもの達の共通点は霊的にレベルが高くすでに過去多くの事を学んでいるのでそれ以上この世では学ぶ必要がないということである。顕在意識の上では本人も気付かないが潜在意識のレベルではすでに十分に学び多くを知っているのである。好人物で皆から慕われる、人のために尽くせるような人物は早死にすることが多いがそれはそういう理由からである。親より早く死ぬというような場合、実はその者は親よりも霊格が高く自らの死をもって親に霊的覚醒を促すことになっている場合がある。〉
大空澄人氏は医師であるとともに、すぐれた霊能者で、霊界におられるご自分のご両親や友人たちとも、親しく対話できる稀有の能力を持っておられます。東日本大震災の際には、霊界で救助活動をしていた私の妻からの通信も、伝えてくださったことがありました。ここでは、氏のご了解を得て、もう一つ、ホームページ
「続 いのちの波動」から、「幽界の友より」(2014.12.20)を転載させていただきます。大空澄人氏のふる里・小豆島で親しかったご友人が霊界からつぎのように伝えてきたことがありました。
〈―― 君がいてくれてよかった。本当に助かる。こうして妻に思いを届けることが出来る。生きていた時にもっと君とそういう話をしておけばよかったと思う。今僕は何一つ不自由な事はない。気の合う人達に囲まれているから。
今、高校の工事が進んでいるようだね。それも時の流れやな。高校が出来てこの地域が潤うようになればいい。僕も総代を勤めて地域の為に働くことが出来て良かった。足跡を残せたかな。
やっぱり君と一緒にヨットに乗ったり大阪で泊まりに行って飲んだりしたことが一番楽しい思い出になっているよ。あの頃が人生で一番楽しかったな。お互いに若かったし勢いがあったからな。
今は酒を毎日飲みたいとは思わない。誰かと付き合って飲むくらいだな。自分から飲もうとは思わない。
こっちでは乗り物は必要がない。車も要らない。金は一切かからないから金の心配をしなくていい。そしてしんどい作業もしなくてもいいから体が疲れることがない。寝ようとしてもすぐに起きてしまう。今までのように眠くならない。とにかく僕は今、幸せに暮らしている。そっちにいた時より余程楽しい。
死んだ者(実際は死んでいないけど)が墓や寺にいるなどあり得ない話だ。アホらしくて笑ってしまうよ。そっちの者こそ窮屈な所に閉じ込められているのに皆、それがわからないのだ。
最初は自分が死んだと分かってこれは困ったことになったと思ったけど、こちらで暮らすうちにそんな思いは消えてしまった。とにかく一杯やることがあって忙しい。落語や漫談など芸達者な人達が一杯いるから面白い。退屈するという事がない。
長生きなんかしなくて良かったよ。次第に不自由になる自分の体を抱えて毎日生活するのはしんどい事だ。そっちではやりたいことがあってもなかなか出来ないだろう。それで諦めてしまうのだ。こっちではやりたいと思ったら簡単にそこにアクセス出来る。そこが全然違う所だ。そっちの者は本当に不自由なところで生活しているのだけど少しもそれがわからない・・・・・。〉
冒頭で、ご友人は、「君がいてくれてよかった。本当に助かる」と大空澄人氏への感謝のことばを述べておられますが、氏へ感謝しているのはもちろんこのご友人だけではないでしょう。私を含めて、氏のホームページの多くの読者たちが、「本当に助かる」とこころから有難く思っているのです。私たちに霊能力がなくても、氏のお蔭で、こうして、霊界から見たこの世の姿を、鏡に映しだすように見ることができます。これだけでも極めて貴重な情報ですが、「死んだ者が墓や寺にいるなどあり得ない話だ。アホらしくて笑ってしまうよ」
と言っておられるのには、思わず、笑いを誘われます。そして、いま霊界で幸せに暮らしているという氏のご友人の、「そっちにいた時より余程楽しい」、「長生きなんかしなくて良かったよ」という末尾のことばは、私のように、すでに十分に「長寿」の領域に入り込んでしまっている者には、殊更に強く胸に響いてくるように思えてなりません。
**********
『歎異抄』から学ぶ他力本願の信心
―生活と文化をめぐる随想 (99)―
(2015.01.01)
かつて親鸞は、常陸の国(現在の茨城県)を中心に下総、下野、武蔵などの関東諸国に他力本願の念仏を説いてまわっていたことがあった。それから、一二三五年、親鸞は六三歳の頃、関東を去って京都に帰ったのだが、残された関東の信徒たちの間には、やがて信仰に対する考え方の相違から正統派と異義派との対立がおこるようになる。そしてその対立は年をおって激しくなっていった。そこで、信心に迷いを来した人たちが、あらためて親鸞から直接教えを受けようとして、関東の常陸の国から東海道十余ヵ国
(常陸、下総、武蔵、相模、伊豆、駿河、遠江、三河、尾張、伊勢、近江、山城) をはるばると歩き続けて、京都へやってきたのである。
東海道といっても、鎌倉時代であったから、徒歩での長い道のりは、江戸時代の東海道五十三次などよりよほど不便で危険も多かったにちがいない。その命がけの旅をしてきた信徒たちを前にして、親鸞が述べたことばが『歎異抄』の第二条である。親鸞はつぎのように言った。(私訳)
「あなたがたは、私が念仏以外に往生極楽への道を知っているだろうとか、いろいろと経典以外の教えにも通じているだろうとか勝手に考えているようだが、それはとんでもない誤りである。それを教わりたいというのであれば、奈良や比叡山にすぐれた学僧が大勢おられるのだから、そういう人たちに会って往生の道を詳しくお聞きになればよいのだ」。
親鸞が、ここで、南都 (奈良の興福寺、東大寺) や北嶺 (比叡山の延暦寺、三井寺) の「すぐれた学僧」に言及しているのは、本当は、彼らの僧侶としての学識や実践を認め、敬意を払っていたからではないであろう。当時の比叡山延暦寺や奈良の興福寺をはじめとする寺々には数多くの学僧がいても、仏典の真髄を把握し、仏道を真に実践できるものは極めて少ないことを親鸞は十分に知っていた。彼自身が比叡山における修業に見切りをつけ、山を下りてしまっている。それ以来、南都、北嶺からは異端視され迫害をうけてきたし、ついには越後国へ流されるという苦い経験も持っていた。その親鸞が、彼らに会って往生の道を聞け、と言っているのは、おそらく精一杯の皮肉で、実際は、彼らに聞いても往生の道など聞けるはずがない、と言いたかったに違いない。それでは極楽往生のためにはどうすればいいというのであろうか。
親鸞は続けて言った。
「私は、ただ念仏をとなえて阿弥陀仏に助けていただくだけだと、法然上人に教えていただいたことを信じるのみである。そのほかは何もない。念仏をとなえれば、本当に浄土に行けるのか、それとも地獄に落ちるのか、そんなこともどうでもよい。かりに、法然上人に騙されて、念仏したあげくに地獄に落ちたとしても、私は決して後悔はしないであろう」。
これは、随分思いきった表現である。関東からはるばる命がけの旅を続けてやってきた信徒たちは、いま目の前で固唾をのんで親鸞の顔を見守っている。その緊迫した雰囲気のなかで、真剣な信徒たちの眼差しを前にした親鸞は、赤裸々な自分自身の姿をさらけ出して、信念を披瀝しなければならなかった。しかしこれは、まかり間違えば師としての信を失いかねず、仏道の教えにも疑問を抱かせることにもなりかねないことばである。信徒たちもそれだけでは納得できなかったであろう。親鸞はさらに続けた。
「そのわけは、念仏よりほかの修業を励んで悟りを開けるはずであったのが、念仏に打ち込んだために地獄に落ちたというのなら、その時は師に騙された、という後悔もあるかもしれない。しかし、私はどのような修業もできない身だから、どうせ私には地獄がはじめから定められた行き場所なのだ」と。そして、最後をつぎのように結んだ。
「阿弥陀仏の本願が真実であるならば、釈尊の教えにも嘘はない。釈尊の教えが真実であるなら、善導大師のお解きになったことにも誤りはない。善導大師のお解きになったことが真実であるなら、どうして法然上人の言われることが虚言でありえようか。そしてまた、法然上人の言われることが真実であれば、この親鸞の言うことも空ごとであるはずがない。これがつまり、私の信心なのだ。この上は、念仏を信じようが、捨てようが、それはあなたがたの勝手である」。信仰とはこういうものだと、親鸞が血を吐くようなことばで述べた真心からの告白であった。
阿弥陀仏というのは「本師本仏」といわれるように、浄土真宗の捉えかたでは無数に存在する仏の中でも最高の仏である。その阿弥陀仏が誓願をたてられた。私たち凡人は、すべて、有れば有るで苦しみ、無ければ無いで苦しむ。四苦八苦の世界の中で苦より離れられない私たちを何とか救い出したい、絶対の幸せの境地を与えてやがてはみんなを極楽浄土へ導きたいという誓願である。仏説無量寿経には、その誓願は48もあったことが記されているが、その18番目には、「人々が心から信じて私の建立した仏国土に生まれることを願い、せめて10回でも念仏してそれで生まれることが出来なかったならば、私は自分だけが仏になるようなことはしない」という強い決意なども含まれている。
誓願とは本願ともいうが、親鸞にとっては、その阿弥陀仏の本願を信じることが救いそのものであった。そして、それを覚知できるのが念仏であり、その覚知がさらに、死後の浄土往生への確約を意味することになる。つまり、私たちが救われるのは阿弥陀仏を一心に念ずることによってである。その釈尊以来の教えに基づく念仏を信じようが捨てようが、「それはあなた方の勝手である」と親鸞は述べたのである。信徒たちはおそらくその親鸞の気迫に打たれたことであろう。そしてその気迫が、信徒たちのこころに親鸞のことばを深く沁みこませていったに違いない。
親鸞は、この仏の慈悲によってのみ私たちが救われることを強調した。私たちがこの世で、苦しみ悩んでいる多くの人々をいくら可哀そうだとか憐れだとか思ってみても、自力ではなかなか救うことは出来ない。弱い自力ではその慈悲心はどうしても中途半端に終わってしまう。だから阿弥陀仏の本願力である念仏によって、父母兄弟、あるいは衆生すべてを救うべきで、それこそが大慈悲心であると第4条でも述べられている。これが親鸞のいう他力本願である。他力本願というのは、したがって、時に世間で誤解されるように、他人の力に頼るというような安易な意味ではない。阿弥陀仏の本願力そのものをいっているのである。
この他力本願の思想は、第5条にもあらわされている。親鸞はここでは、はじめに「私は父母への孝養のために念仏を唱えたことは一度もない」と述べた。これは実に新鮮に響くことばで、私はこのことばに初めて接したときにはしばらく釘付けになった。父母というのは自分の父母だけが父母なのではない。生きとし生けるものは、みんないつかの世で、父母であり兄弟であったからだと親鸞はいう。輪廻転生をつよく打ち出しているのである。そして次のようなことばが続く。
「念仏が自力の善であるならば、わたしの念仏の功徳を回向して父母を助けることもできるであろう。しかし、よく考えてみると、自分の力による念仏ではないのだから、自力で助けようというような考え方は捨てて早く阿弥陀仏の本願に目覚めることだ。その上で、念仏することによって、阿弥陀仏の自由自在の救済の力で、父母兄弟らの縁につながる人々をはじめ、この輪廻の世界に苦しんでいる多くの衆生を救っていくことができる」
つまり、念仏とは他力本願の念仏でなければならない。他力本願の念仏によって初めて私たちは救われ、極楽浄土に導かれていくことになる。そうであれば、私たちは一心に念仏するべきである。そして、そのときの私たちは、救われる喜びと浄土への希望に満ち溢れているのが道理である。それはそうなるはずであろう。しかしそれがわかっていても、なかなかそのようにならないのはなぜか。おそらくこれは誰でも抱く疑問である。親鸞の下で他力本願を学んできた唯円でさえも、そう思った。そして親鸞に尋ねたのである。そのことが第9条にはこう述べられている。
「念仏を唱えても、どうも飛びたつほどの喜びを感じることは出来ません。また、早く浄土へ行きたいという気持ちにもなれないのはどうしてでしょうか」と唯円が親鸞に尋ねた。それに対して親鸞は言った。「それは私も不思議に思っていたことだが、そなたも同じであったか。しかし、よくよく考えてみれば、手の舞い足の踏むところも知らないほどに喜ばねばならないのに喜ばないでいるのだから、いよいよもって阿弥陀仏の救いにあずかることは間違いないと考えるべきである」
しかし、これだけでは、なぜ「喜ばない」ことが「阿弥陀仏の救いにあずかる」ことになるのか、まだよく理解できないかもしれない。この親鸞のことばは、こう続く。「本当は喜ぶはずのものを、その気持ちを抑えて喜ばせないようにしているのは、私たちの煩悩のなせる業である。ところが阿弥陀仏は、このことをはじめから見抜かれていて、私たちのことを『煩悩具足の凡夫』、罪深い性をもつ身、といわれたのだから阿弥陀仏の本願はこのような私たちのためであったことがわかって、ますます頼もしく思われるのだ」
阿弥陀仏の本願はわかり易いようでわかりにくいところがある。「だからますます頼もしく思われる」といわれても、少し考え込んでしまうかもしれない。その道理をいま親鸞は、弟子に向かって熱心に伝えようとしている。唯円はたしかに親鸞の弟子なのだが、親鸞にとってはただの弟子ではなく、ともに阿弥陀仏の弟子であるという自覚があった。それは、「親鸞は弟子一人ももたずそうろう」と第六条に述べられていることからも窺い知ることができる。阿弥陀仏の弟子としては絶体平等であると考えている親鸞の唯円に対する答え方は、謙虚でやさしい。親鸞は続いてこのように答える。
「よくよく考えてみると、天に舞い、地に踊るほどの喜ぶべきことを喜ばないでいるからこそ、むしろ往生は間違いないと思ってよい。喜びを抑えて喜ばせないようにしているのが、煩悩のせいなのだ。阿弥陀仏は、はじめからそのことをよく知っておられたからこそ、私たちのことを『煩悩をもった凡夫』と言っておられるのであり、それ故にこそ、他力の悲願はこのような私たち凡夫のためのものであったと、私たちも納得して安心することができるのだ。それから、浄土に急いで行きたいと思わない一方で、一寸した病気にかかってもすぐ死ぬのではないか、と心細くなるのも煩悩のせいである」。
ここで「煩悩」が繰り返し出てくる。私たちは「煩悩をもった凡夫」であり、その煩悩が、喜ぶべきことをも喜べないようにしているのだという。しかも、そのことは阿弥陀仏も見通された上で衆生救済の本願を立てたのだから、その本願はなおさら真実のものとして納得できるのだともいう。親鸞は、さらに続けて言った。
「はるか遠い昔から今日に至るまで、生死を繰り返してきたこの迷いの世界は捨て難く、まだ見たこともない極楽浄土は恋しくないというのは、本当によくよく煩悩は強いものにちがいない。けれどもいくら名残惜しいと思っても、この世との縁が切れ、静かに生命の灯が消える時は、あの浄土へ行かざるをえなくなる。阿弥陀仏は、急いで浄土へ行きたいと思うことのできないものを、ことのほか憐れんで下さっているのだ。そうあってみればなおさら、大慈大悲の仏の本願が頼もしく、往生は間違いないと信じられる。逆にもし、天に舞い地に踊る喜びがあり、急いで浄土にも行きたいということであれば、その人には煩悩はないのであろうかと、かえって疑わしくなってしまうのだ」。
親鸞の「よくよく煩悩は強いものにちがいない」ということばは、私たちの胸に強く響く。煩悩が私たちを盲目にする。煩悩が善悪の判断をも狂わす。有り難いものでも有り難く感じさせないのである。しかも、私たちはその煩悩にすっぽりと埋まってしまっているから、煩悩の虜になっていることにさえ気がつかない。そして、煩悩の世界がすべてで、そこから離れることがむしろ不安になったりする。「煩悩をもった凡夫」が「極楽浄土へ急いで行きたいと思えない」のも、いわば、当然のことであるかもしれない。ここで思い出されるのが、かつて私が学生時代に見た外国映画の一つの場面である。これは、他のところでも触れているが、次のようなシーンがあった。
ヨーロッパのどこかの監獄で、政治犯であったろうか、一人の囚人が30年も40年も独房に閉じこめられてよぼよぼの老人になってしまう。老人は、独房の高い小さな天窓から差し込む光を仰いでは、監獄の外の自由へのあこがれを募らせていた。
第二次世界大戦の末期で、その監獄もある日、激しい空爆を受けて、高い塀も頑丈な建物も崩れ落ちてしまった。その独房の老人は生き延びて、瓦礫のなかから這い出してくる。そして、よろよろと外へ向かって歩き始める。しばらく歩いて振り返るが、誰も追ってくる様子はない。目の前には、広々とした野原が広がっている。それは、老人が長い年月あこがれてきた自由の世界のはずであった。老人は、また少しよろよろと歩き続ける。しかし、そこで立ち止まってしまうのである。やがて老人は、またよろよろと、崩れ落ちた監獄へ帰って行った・・・・・
自由が束縛されても、孤独の苦しみがあっても、あまりにも長い年月それに慣らされてしまうと、もうそこから抜け出すことさえ不安になってしまう。浄土・極楽がいかに壮麗ですばらしいところであると聞かされても、煩悩の世界に慣れきってしまうと、唯円が疑問に思ったように、「急いで行きたい」と思われないのも、無理ではないかもしれない。しかし、それでは、この煩悩の世界に生きている限り、安心立命の境地に達するのは難しいということになってしまうのであろうか。そこで、親鸞が説き続けたように、ひたすらに阿弥陀仏に縋る他力本願の信心が大切になってくるのであろう。「私は、ただ念仏をとなえて阿弥陀仏に助けていただくだけだと法然上人に教えていただいたことを信じるのみである。そのほかは何もない」と言った親鸞の言葉を、私たちも改めて噛み締めておきたいものである。
**********
思い出の中に生き続ける穴熊の物語
―生活と文化をめぐる随想 (98)―
(2014.11.01)
もう2年前になるが、私に大腸がんが見つかって手術を受けた時、「寸感・短信」欄に「この世とあの世の狭間で揺れ動くいのち」(2012.08.03) を書いた。そのなかで私は、当時小学校一年生であった双子の孫が、私の入院のことを母親から聞かされて二人とも泣き出したことに触れている。私はそれを病室で聞いた時にはしんみりした気持ちになった。「もうこの辺であの世へ行くことになっても少しも不自然ではない」などと思ってはいたが、その時の文にはつぎのように付け加えている。
《私の孫は、この二人だけである。祖父の病気や死亡を体験させるのも、人生の大切な学習の一つだが、私にもう少し時間が与えられるのであれば、この孫たちに、病気や死についても、明るく乗り越えていけるような話をしておきたいというささやかな願望までは、捨て切れていない。》
それから、大腸がんの手術とそのときに見つかった動脈瘤の手術とを無事に乗り越えて、2年が経過した。いまでも手術後の経過観察で3ヶ月に一度、通院して検査を受けているが、大腸がんの転移や再発はなく、動脈瘤も落ち着いているようである。そして、今年の10月からは、それまでの長年の一人暮らしを解消して、娘夫婦の家に同居するようになった。いまでは、孫の二人とも毎日顔を合わせる生活が続いている。
先日、その孫のうちの一人、K子が、自室で書類整理をしている私のところへやって来て、授業でいま習っているところを読むから聞いて欲しいと言った。私は書類整理の手を休めて、聞いてみることにした。K子は私の傍に座り、教育出版の「小学国語3上」を手に持って元気に読み出した。タイトルは「わすれられないおくりもの」となっている。作者はスーザン・バーレイという女流作家で、小川仁央訳と書かれている。その話はつぎのように始まっていた。
《あなぐまは、かしこくて、いつもみんなにたよりにされています。こまっている友だちは、だれでも、きっと助けてあげるのです。それに、大へん年をとっていて、知らないことはないというぐらい、もの知りでした。あなぐまは、自分の年だと、死ぬのがそう遠くはないことも、知っていました。》
これはその年をとった穴熊の物語りであるらしい。私はふんふんと頷きながらK子が読むのを聞いているのだが、その物知りで優しい穴熊が、「自分の年だと、死ぬのがそう遠くはないことも、知っていました」と述べられているのに気を惹かれた。近く死ぬであろうことを予見している穴熊の話がどう展開されていくのか、急に興味をそそられる気がしてきた。K子はつぎのように読み続けた。
《あなぐまは、死ぬことをおそれてはいません。死んで体がなくなっても、心はのこることを知っていたからです。だから、前のように体がいうことをきかなくなっても、くよくよしたりしませんでした。ただ、あとにのこしていく友だちのことが気がかりで、自分がいつか長いトンネルの向こうに行ってしまっても、あまり悲しまないようにと、言っていました。》
K子のやや早口の朗読を聴きながら、私は自然に気持ちが引き締まっていった。句読点のところでちょっと間をおきながら、もう一度そこの所をゆっくりと読んでくれるようにとK子に言った。K子が読み直したあと、私も読んで聞かせた。――そこでは、穴熊は死ぬことを恐れていない。死んで体がなくなっても心は残る、と書かれている。だから、体がいうことをきかなくなっても穴熊はくよくよしない。ただ、後に残していく友達のことが気がかりである・・・・・と続いて、「自分が長いトンネルの向こうに行ってしまってもあまり悲しまないように」ということまで言っている。易しい表現だが、これらは人間の生と死の問題についても極めて重要なことばの数々である。子供向けの物語だから「霊魂」とか「霊体」ということばこそ使ってはいないが、これはスピリチュアリズムそのものではないか、と私は思ったりした。しかし、余計な注釈はいらない。私はまた、ふんふんと頷きながら、次の文章を読むK子の声に耳を傾けた。
《ある日のこと、あなぐまは、もぐらとかえるのかけっこを見に、おかに登りました。その日は、とくに年をとったような気がしました。あと一度だけでも、みんなといっしょに走れたらと思いましたが、あなぐまの足では、もう無理なことです。それでも、友だちの楽しそうな様子をながめているうちに、自分も幸せな気持ちになりました。》
モグラと蛙のかけっこを見ようとして丘に登った穴熊は、目の前で元気に走っている彼らの姿を眺めながら、改めて自分の老いを思い知らされる。「あと一度だけでも、みんなといっしょに走れたら」という思いはいまの私にもよくわかる。そうは思っても、そんなことが出来るはずもなく、穴熊は、特に年をとったような気がするだけである。しかし、ここでは、その穴熊はいたずらに自分の老いを嘆くのではない。モグラや蛙の楽しそうな様子を眺めているうちに、自分も幸せな気持ちになるのである。ここでも、わざわざ「隣人愛」だとか「人類みな兄弟」のような注釈を付け加える必要はないであろう。ただ、穴熊は、心優しい性格の持ち主でもあった。
夜になって、自分の家に帰ってきた穴熊は、月に「おやすみ」を言って、カーテンをしめる。それから、地下の部屋にゆっくりと下りていく。そこでは、暖炉が暖かく燃えていた。穴熊は、その部屋で夕ご飯を食べ、それが終わると机に向かって手紙を書く・・・・・というように物語りは進んでいく。その手紙は、いままで親しくしてきた仲間や友人たちへの最後の手紙であった。いわば穴熊の遺書である。しかし、悲壮な気持ちでそれを書いているのではない。穴熊の心は穏やかで平静のようである。その後、揺り椅子を暖炉の傍に引き寄せて静かに揺らしているうちに、穴熊はぐっすりと眠ってしまい、そして、「ふしぎな、でも、すばらしいゆめ」を見ることになる。K子はそれを、こう読んでいった。
《おどろいたことに、あなぐまは走っているのです。目の前には、どこまでもつづく長いトンネル。足はしっかりとして力強く、もう、つえもいりません。体はすばやく動くし、トンネルを行けば行くほど、どんどん速く走れます。とうとう、ふっと地面からうき上がったような気がしました。まるで、体が、なくなってしまったようなのです。あなぐまは、すっかり自由になったと感じました。》
暖炉の前で眠り込んだ穴熊は、夢の中では元気に走っているのである。かつての若い頃の姿そのままに、長いトンネルのなかを力強い足取りで、どんどん速く走っている。年をとって走る力もなかったはずなのに、杖も必要なく、すばやく動いている自分の体に、穴熊はちょっと驚いていたかもしれない。やがて、ふっと地面から浮き上がったような気がして、穴熊はすっかり自由になったと感じる。穴熊は、実はこのとき、このようにしてこの世からあの世の世界へ移って行ったのである。
籠から解き放たれた一羽の小鳥のように、老いた肉体の束縛から解放された穴熊は、新しい光明の世界のなかで若さを取り戻して自由自在の生活を満喫できるようになった。しかし、そのことは穴熊の仲間や友人たちにはわからない。次の日の朝、家の入り口のドアは閉ざされたままで、いつものように穴熊が家から出てくることはなかった。仲間や友人たちは穴熊がみんなの前に姿を現わさなかったので心配して、穴熊の家へ集まってきた。その後の話は、こう続く。
《きつねが、悲しい知らせをつたえました。あなぐまが死んでしまったのです。そして、あなぐまの手紙を、みんなに読んでくれました。
長いトンネルの
向こうに行くよ
さようなら
あなぐまより
森のみんなは、あなぐまをとてもあいしていましたから、悲しまない者はいませんでした。なかでも、もぐらは、やりきれないほど悲しくなりました。
ベッドの中で、もぐらは、あなぐまのことばかり考えていました。なみだは、あとからあとからほおをつたい、毛布をぐっしょりぬらします。》
この世からあの世へ移るということは、あの世では喜びであることがわかっていても、やはり、この世では悲しみである。それを否定することは出来ない。スピリチュアリズムの理解があってさえ、この悲しみを乗り越えることはなかなか容易ではないであろう。愛する家族や仲間たちとの別れは、いつでも、どこでも、耐え難く辛いのが世の常である。この物語でも、その悲しみはつぎのように描かれていた。
《その夜、雪がふりました。冬が始ったのです。これからの寒いきせつ、みんなをあたたかく守ってくれる家の上にも、雪はふりつもりました。雪は地上をすっかりおおいました。けれども、心の中の悲しみを、おおいかくしてはくれません。
あなぐまは、いつでも、そばにいてくれたのに――みんなは、今どうしていいか、とほうにくれていたのです。あなぐまは、悲しまないようにと言っていましたが、それは、とてもむずかしいことでした。》
その愛する者との別れをどう理解していくか。私たちならそれをどう乗り越えて立ち直っていくか。ここでも述べられているように、それは「とても難しいこと」である。それに、この物語を読んでいる小学校3年生は、まだ9歳前後でしかない。その頃の子供たちに、自分の問題として、これを考えさせていくのはやはりどこか無理があるような気がする。決して簡単ではないであろう。私は、折に触れ、こんな時にはシルバー・バーチならどのような言い方をするだろうかと思うことがあるが、この場合には適例を見出せない。ただ、シルバー・バーチは、11歳で父親と妹を亡くしたジョンという少年に、かつて次のように述べたことがある。
《ジョン君に知ってほしいことは、もうわかっているでしょうけれど、妹とお父さんはいつもそばにいてくれているということです。これはまだまだ知らない人が多い大切な秘密です。いつもいっしょにいてくれているのです。ジョン君を愛し力になってあげたいと思っているからです。このことを人に話しても信じてくれませんよね? みんな目に見えないものは存在しないと思っているからです。このことを理解しないために地上では多くの悲しみが生じております。理解すれば “死” を悲しまなくなります。死ぬことは悲劇ではないからです。あとに残された家族にとっては悲劇となることがありますが、死んだ本人にとっては少しも悲しいことではありません。新しい世界への誕生なのです。まったく新しい生活の場へ向上して行くことなのです。ジョン君もそのことをよく理解してくださいね。》 (『霊訓6』pp.71-72)
これは、11歳の少年に対するシルバー・バーチのあたたかい思いやりの気持ちが直截に伝わってくることばである。この物語りでも、穴熊は、悲しまないようにと言い残している。物語の作者は、穴熊がこれからも生き続けて、何時もみんなと一緒にいるのだと言わせることも考えたかも知れない。それを作者は、さりげなく、穴熊がみんなの思い出のなかで生き続けているという形で伝えようとする。――冬の間、悲しみの時が流れて、やがて春になった。雪が融けて外に出られるようになると、みんなは互いに行き来しては、穴熊の思い出を語り合うようになるのである。穴熊はみんなに多くの優しい思い出を残していた。
たとえば、モグラは鋏の使い方が上手で、一枚の紙から手を繋いだモグラを切り抜くことが出来る。それは穴熊が教えてくれたものであった。蛙はスケートを穴熊から習った時、自分が一人で立派にすべれるようになるまで、穴熊はずっと優しく傍についていてくれたことを覚えている。狐は子供のころに穴熊からネクタイの結び方を教えてもらって以来、今ではどんな結び方でも上手に出来る。ウサギの奥さんは、料理上手で村中の評判だが、それも最初に教えてくれたのは穴熊であった。このように、みんなの誰にも、なにかしら、穴熊の思い出があって、穴熊は、一人一人に、「別れたあとでも宝物となるような、ちえやくふうをのこしてくれた」のである。そして、この物語の最後の締めくくりになる。その部分を、K子はこう読んで聞かせてくれた。
《最後の雪が消えたころ、あなぐまがのこしてくれたもののゆたかさで、みんなの悲しみも、消えていました。あなぐまの話が出るたびに、だれかがいつも、楽しい思い出を、話すことができるようになったのです。
あるあたたかい春の日に、もぐらは、いつかかえるとかけっこをしたおかに登りました。もぐらは、あなぐまががのこしてくれた、おくりもののお礼が言いたくなりました。
「ありがとう、あなぐまさん。」
もぐらは、なんだか、そばであなぐまが、聞いていてくれるような気がしました。
そうですね――きっとあなぐまに――聞こえたにちがいありませんよね。》
この穴熊の物語はこれで終わっている。孫のK子はここまで、時々息を大きく吸い込みながらよどみなく読んだ。――私は改めて考える。こんなことはそれまで一度もなかったのに、K子が、なぜこの物語を読むのを私に聞いて欲しいと言ってきたのか。それはわからない。9歳の子に別に深い考えがあってそうしたのではないはずであるが、ただ、私には有難かった。この小文の冒頭で私は、「私にもう少し時間が与えられるのであれば、この孫たちに、病気や死についても、明るく乗り越えていけるような話をしておきたいというささやかな願望までは捨て切れていない」と書いていたことに触れた。その私が、期せずして、孫のほうから、このような穴熊の話を教えられることになった。私は、折をみて、K子に、そしてもう一人の孫のM子にも、またこの物語りを読んでくれるようにと頼むことになるかもしれない。
**********
イギリスのバス旅行の想い出
―生活と文化をめぐる随想 (97)―
(2014.09.01)
イギリスでは、観光バスによる旅行が盛んである。一泊、二泊の小旅行から、一週間、二週間の休暇旅行に至るまで、気軽に観光バスを利用して旅行に出かける。どこへ行ってもよく見かける旅行案内業者の店の中の棚には、いろいろな方面への旅行パンフレットが所狭しとばかり並べられ、店内のカウンターには、若者から、家族連れ、老夫婦、あるいは車椅子の身体障害者に至るまで、旅行の相談や予約で訪れる人たちがあとを絶たない。
イギリスは、その正式の国名(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)が示すように、グレイト・プリティン島とアイルランド島の北部六分の一からなり、総体約二四万四千平方キロの広さである。日本の面積は約三六万八千平方キロだから、日本の約三分の二である。グレィト・ブリティン島だけを取り上げれば、これは日本の本州とほぼ同じ大ききで、イギリス全体の八八パーセントにあたる。このあまり広くはない国土に、道路網が非常によく発達していることが、なによりも観光バス旅行を盛んにしている大きな要因であると思われる。
このグレイト・プリティン島は、イングランド、ウェールズ、スコットランドの三地方に大別できるが、その大部分が、日本と違って、平坦な地形であるといってよい。この平坦な地形の上を、ロンドンからの高速道路が縦横に遠くまで伸びて、長距離の旅行も割合楽にできる。しかも、高速料金などを取られることもない。すべて無料である。
イギリスでは高速道路はほとんど片道三車線で広く、渋滞もあまりない。たとえばロンドンからM1号で北へ向かってLeeds(リーズ)までの約三二〇キロは、途中で一、二度小休止をしても、予定通り四時間で着く。東京一名古屋間の距離はこれとほぼ同じだが、道路の幅も狭く、渋滞もしばしばで、なかなか四時間では着かない。それに高速料金だけでも、往復で一万五千円も取られるのである。
イギリスで観光バスの旅行が盛んなのは、もちろん道路事情だけによるものではない。おそらくホテルの宿泊代が安いことにもよるであろう。もっとも、一般の旅行でよく使われるのは、三ツ星クラスで、四ツ星クラスは少ないほうである。それでも、日本の国内旅行のホテルや旅館の宿泊料に比べると、ずいぶん安いような気がする。そのために、旅行費用もあまり高くならない。
たとえば、行き先やシーズンにもよるが、私がイギリスに住んでいた1991年当時で、一般的な国内旅行が、二泊三日で一〇〇ポンド前後、四泊五日で一二〇~一五〇ポンド、六泊七日で一七〇~二四〇ポンドくらいであったろうか。一ポンド約二二〇円で換算しても、一週間の旅行が、ホテル、食事、観光込みで五万円程度だから、日本に比べれば、やはり安いといえるであろう。2014年の現在では、多少旅行費用は値上がりしているかもしれないが、ポンドは約175円になっているから、さらに安くなっている感じである。
私も、イギリス在住中は、この「安い」観光バス旅行によく便乗した。観光バスの運営会社は、ナショナル、シェアリングズ、ウォレス・アーノルドなどが代表的なもので、これらの会社は、イギリス国内旅行のみならず、ドーバー海峡をフェリーで渡って、ヨーロッパ各地にも毎日数多くの観光バスを送り込んでいる。観光バスに乗り込むまでの手順もよくできていて、ロンドンから離れた場所から参加しても、あまり迷ったりすることはない。では、どのようにすればよいか。かつて私が参加した六泊七日のスコットランド旅行を例にとって、述べてみよう。
その旅行は、シェアリングズの7-Day Holiday, Panoramic Highlands というもので、八月初旬の日曜日に出発して、土曜日に帰る行程だった。夏の最盛期であったから、費用もこの種の旅行では一番高くて、二四〇ポンド。まずこれを、私の住んでいた町、ロチェスターのエイジェントで予約し、確認を取って代金を払い込む。
次に、どの旅行会社も、イギリス全土にはりめぐらせた数百か所の集合地点(local joining point)を確保している。その集合地点の一覧表は、旅行パンフレットに記載されているので、当日は、指定された時間に、自分の住所から最寄りの集合地点で待っていると、シェアリングズのバスがやって来てピックアップしてくれる。私の場合は、家がロチェスターで、カンタベリーとロンドンの中ほどにあるから、家に近いチャタムのバス・ターミナル二番乗り場で、八時四十五分にバスに乗り込んだ。ただし、このバスは、そのままスコットランドへ向かうのではない。
途中でも何か所かの集合地点で、旅行客を拾い上げてバスは西北へ走り続け、ロンドンを取り巻いている高速環状線M25(London Orbital)に入る。そこから大きな曲線を描いて、初めは北へ、やがて西へと走り、Potters
Bar(ポターズ・バー)を通り越したあたりで、ロンドソ市街の中心部から上がってきた高速道路M1と交差する。その場所South Mimms(サウス・ミムズ) に、観光バス専用の広大なバス・ターミナルがあって、そこがバスの乗り換え地点(interchange
point)になっているのである。ロチェスターからは、一時間半くらいかかった。
サウス・ミムズでは、イギリス各地から旅行客を集めてやって来た数十台のバスが、一旦旅行客を降ろし、今度は目的地ごとに並べ替えられて、旅行客は自分の目的地行きのバスに乗り換えるのである。サウス・ミムズのスコットランド行きのバスは何番であるかは、サウス・ミムズに着くまでの車内でもアナウンスされるし、着いてからも、ずらりと並んだバスの前に一覧表で示されているから、まごつくことはない。指定された番号のバスへ行ってみたら、Scotland-Panoramic
Highlands とフロントガラスの上に大きく行き先と旅行名が書いてあった。
しかし、行き先がロンドンとは逆方向の場合はどうするか。私も何度か、この観光バスでドーバー海峡を越え、ヨーロッパ各地を訪れたが、その場合は、このサウス・ミムズへ行く必要はない。そこで行き先別に編成し直されたバスがドーバーへ向かう途中に、先ほどのチャタムの集合地点へ寄ってくれるのである。集合時間もゆっくりでよい。たいてい十一時から十二時頃であった。
さて、私たちのスコットランド行きのバスは、サウス・ミムズから高速道路M1に乗って、一路北上を続けた。一、二時間おきに、途中のサービスエリアで休憩をとる。高速道路のサービスエリアには、レストランやファース・トフードの店、ゲームコーナーやトイレなどの設備があって、どこでも同じようなものである。グラナダ、ウエルカム・ブレイク、ブルー・ボアなど三つの系統の会社で運営されていて、中にはホテルを併設しているのもある。新聞、雑誌、書籍、CD、音楽テープなどのほか、水、ジュース、サンドウィッチ、果物、キャンディなど、なんでも置いているコンビニェンス・ストア並みの売店が、日本よりは目につきやすいくらいであろうか。
その日は、サウス・ミムズから三〇〇キロほど走って、ウェイクフィールドに夕方着いた。その夜のホテルはSwallow Hotel で、三ツ星である。感じのよい清潔な部屋であった。パンフレットの紹介では、All
rooms with private facilities, television and tea / coffee making amenities.
Restaurant with panoramic windows. (全室、専用テレビ、湯沸かし器等付き。展望レストランあり)などと書かれている。七時頃から夕食が始まり、みんなでテーブルを囲むと、同行の人々の様子がよくわかり始めて興味深かった。
四〇人ほどの乗客はほとんどがイギリス人で、外国人らしいのは私とオーストラリアから来た中年の夫婦を含めて三人しかいない。アメリカ人がグループで旅行するような場合に比べるとイギリス人のグループはやはり少し物静かな感じがするが、それでも和気藹藹とした雰囲気で、話しかけるとすぐに明るい声が返ってくる。同じバスに乗っている同じ仲間だという意識が強いのかもしれない。たとえば、私のように一人で旅行に加わっている外国人であっても、決して、仲間外れにされるようなことはなかった。
二日目は、ホテルの食堂でみんなで一緒に朝食をとったあと、九時過ぎにウェイクフィールドを出発した。Yorkshire Dales (ヨークシャー・デイル)国立公園の周辺をかすめてM6 に入り、やがてスコットランドとの「国境」を越える。さらに北上を続けてM74 に入った。やがてグラスゴーに到着する。グラスゴーは雨であった。古いくすんだ煉瓦の建物が雨で濡れて、夏なのに冷たい感じがする。
途中、トイレ休憩や昼食の時間をとったりしたので、この辺まで来るのに五時間近くかかったであろうか。すでに三五〇キロも走ってきた計算になるが、あまりハードなスケジュールという感じはない。バスは常時、八〇キロから一〇〇キロくらいのスピードで走っているが、道路がよく、順調に走れるためもあって、あまり疲れないのである。
午後二時過ぎに雨のグラスゴーをあとにして、A82で北上を続ける。やがて前方右側に大きな湖が見えてくる。全長約四〇キロ、幅は広いところで八キロ、三日月状に南北に伸びるスコットランドの湖の中では最大のLoch
Lomond (ロモンド湖)である。ここでちょっとボートに乗ってみる。水は透き通り、魚が泳いでいる姿まで見える。仙人や妖精がいまでも棲んでいるという噂まであって、イギリスでも一番美しい湖といわれている。この広大なロモンド湖の左岸を通り、さらに一時間ほど北上して、私たちのバスは、悲劇の谷として知られる
Glencoe(グレンコー)の寒村を通り抜けた。
このような旅行では、バスが現地に着いて観光する場合、しばしば、現地のガイドが乗り込んできて、道案内をしながらいろいろとマイクで説明してくれる。しかし、途中の風景や、史跡や、要所などの説明は、ドライバーの役割である。このグレンコーでは、ドライバーのトムはハンドルを握りながら、運転席のマイクを通して、次のような悲劇のあらましを話してくれた。
一六九二年二月十三日、このグレンコーで、スコットランドの歴史に名高い「グレンコー虐殺事件」が起こった。一六八八年の名誉革命で、ウィリアム三世は、もともとスコットランドの王家の出であったスチュワート朝のジェームズ二世を追い出し、自ら王位に就いた。そのあと、スコットランドの部族たちの反抗が続くのに業を煮やしたウィリアム三世は、彼らに、反抗を止めて服従を誓う誓約書を一六九一年末までに出すように布告を出した。そして、この期限までに誓約書を提出しない者に対しては、一揆と見なして厳罰に処する、と宣言したのである。
スコットランドのすべての部族は、この布告に従わざるを得なかった。期限を守って誓約書を提出した。しかし、このグレンコーに住んでいたMacDonald(マクドナルド)一族だけは、部族内の意見をまとめるのに時間がかかってしまったためか、年末の提出期限ぎりぎりになって役所へ赴く結果になった。しかし、運悪く役人が不在であったため、提出は翌年にずれ込み、一月六日になってしまった。それを咎めて、ウィリアムの家臣Duncunson(ダンカンサン)が、グレンコーのマクドナルド一族の村を襲い、住民約一五〇人を、老人から婦女子に至るまで、ことごとく無差別に殺戮してしまったのである。
Glencoe の “glen” とは「谷」のことで、このあたりはいまも、“The Weeping Glen” (嘆きの谷)と呼ばれている。私たちのバスが通った時は、曇天で雲が低くたれこめ、まわりの山や谷の線も暗くくすんでいた。それだけに、トムの話はことさらに身に沁みて、車内にはしばらくは静寂が続いた。いつも思うことだが、こういう過去の悲劇の存在を無視しては、いまのイギリスの社会や文化も、おそらく、よくは見えてこない。
グレンコーの虐殺事件などを経て、やがてスコットランドは、一七〇七年には遂にイングランドに併合され、「大ブリティン連合王国」が成立することになる。しかし、このようなイングランドとの反目の歴史は、なにもスコットランドに限ったものではない。アイルランドもそうであるし、ウェールズも例外ではない。冒頭でも触れた、イギリス連合王国の変則的な国名(The
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)にも、そのようなイギリスの歴史の厳しさが反映されている。
アイルランドもウェールズも、もともと、カトリックを信ずるケルト族の国であり、「侵略者」の子孫であるAnglo-Saxon(アングロ・サクソン)民族とは敵対関係にあった。 ウェールズについていえば、一二八四年にイングランドのエドワード一世に征服されてからは、イングランドのいわば属国であった。その後、一五六三年に、イングランドに正式に併合されたが、現在でも、ウェールズへ行くと、道路の標識やテレビ放送などで、ウェールズ語が英語と併用されていて、ウェールズ独自の文化を残す努力が続けられている。
一方、アイルランドのほうは、イングランドとの対立関係が解消されることなく残った。イングランドのこの島を支配しようとする試みは十二世紀頃から始まる。クロムウェルの清教徒革命(一六四九年)で、プロテスタントがイングランドの支配権を握ると、その勢いをかってアイルランドへ侵入し、人口が半減するほどの皆殺しで島を屈服させた。以来アイルランド人は、被征服者としての塗炭の苦しみを味わいながら、イングランドのために一方的に奉仕させられてきたのである。
ようやく解放と独立を勝ち取ったのが一九二一年であったが、イングランドからの植民者が住み着いた北アイルランドだけが、独立に背を向け、イングランドに残った。しかし、ここのプロテスタントは一〇〇万人、原住民たるカトリックは五〇万人で、過去の力関係をそのままに、現在もなお、流血の惨事があとを絶たないでいる。
一九九七年五月の総選挙で一八年ぶりに政権についた労働党のブレア首相は、スコットランドとウェールズの地方分権を思い切って認める方向に転換した。これも、このような歴史的背景を持った「ケルト民族意識」を専重して、政治の安泰を計ろうとしたものであった。九月に、住民投票が行われ、その結果、スコットランドもウェールズも、それぞれの議会を設けて大幅な権限を持つ「地方政府」を誕生させることになったが、振り返って見れば、この “The Weeping Glen” の悲劇も、そのようなケルト民族意識高揚のための、礎のひとつであったということになるのかもしれない。
グレンコーの暗さと、悲劇の痛ましさに思いを馳せているうちに、少し横道にそれてしまったが、私の乗った観光バスは、まだ北に向かって走り続けていた。イングランドでは見かけない山らしい山が、次から次へと現れては消える。やがて、長大なLoch
Linnhe(リニ湖)の東岸を一時間足らず走って、バスはとうとう、夕闇が迫るFort William(フォート・ウィリアム)にたどり着いた。グラスゴーからの距離は一五〇キロ足らずだから、その日一日で、約五〇〇キロも走ったことになる。湖の近くの白壁の美しいMercury
Hotel に入る。ここも三ツ星だが、部屋は清潔で快適であった。
明くる日の朝、三階の部屋で目を覚まして窓のカーテンを開けると、空はよく晴れて、目の前にはリニ湖の水面がきらきらと光りながらはるか遠くまで広がっている。すばらしい景観であった。スコットランドはまさに湖の国である。冷たく澄んだ水の美しさと静かなたたずまいが、見る人の気持ちに安らぎを与える。
このホテルのあるフォート・ウィリアムというのは、湖に沿って開けた細長い小さな町である。端から端まで歩いても二〇分くらいしかかからない。一六五五年に「粗暴な野蛮人」、つまり、当時のイングランド人からみたスコットランド人、を制圧するために、ここに土の砦が築かれたのが町の始まりである。その後、ウィリアム三世が石の砦に造り直してから、フォート・ウィリアムの名がつけられた。文字通り、ウィリアムの砦である。その石の砦は、鉄道建設の際の工事で取り壊されていまはないが、名前だけは残った。これも、イングランドとスコットランドの対立を示すひとつの象徴であるのかもしれない。
午前中は自由時間で、バスの仲間たちはそれぞれ町へ出かけて、博物館をのぞいたり、特産の毛織物を物色したりしていた。さすがに北の果てで、真夏なのに、通りを歩いていても薄ら寒いくらいである。緯度は北緯五七度に近いから、日本の位置で見れば、北海道の北端をはるかに通り越え、サハリンの北端のなお少し上ということになる。
午後は、観光バスで周辺の景勝の地として知られるGlenfinnan(グレンフィナン)やLoch Shiel(シール湖)などを見てまわった。この辺はスコットランドでも特に、美しい湖と「高い」山々で知られているが、町の三キロ東には、イギリスの最高峰
Ben Nevis(ベン・ネヴィス)山が聳えている。ただし、最高峰といっても、高さは一、三四四メートルである。富士山に比べても三分の一しかない。しかし、イングランドのなだらかな山々、というより丘の連なりを見慣れてきた限には、スコットランドにはいかにも日本でいう「山々」があるという感じがする。
イングランドでは、大部分が日本とは違って、平坦なひと続きの平野が広がっている。北部にはPennine Chain(ペンニン山脈)があるが、そのうちもっとも高いCross
Fell(クロス・フエル)でさえ、八九三メートルだから、あとの山も高さはしれている。Cambrian Mountains(カンブリア山地)の湖水地方は、例外的に高い山が多いところであるが、その中の
Scafell Pike(スカフェル山)が九七七メートルで、これが文字通り、イングランド地域の最高峰なのである。
フォート・ウィリアムズに二泊して、次の日の朝、私たちはさらに北へ向かった。A82を北東に進むと一時間足らずでFort Augustus(フォート・オーガスタス)の町に着く。あのNessie(ネッシー)で知られるLoch
Ness(ネス湖)が始まるのは、ここからである。ネス湖は約四五キロ細長く北東に伸びて、終わったところにInverness(インバネス)の町がある。この町も、ネッシーのおかげで、一躍スコットランドでも指折りの観光地になった。
ネス湖の左岸をしばらく走って、途中で西に進路を変え、A87に入る。Loch Duich, Loch Carronなど、大小さまざまな湖の側を通って、景勝地Torridon(トリドン)の山や谷を見た。A832で北西から、北へ、それから東へと半円を描くようにして、Loch
Maree, Gair Loch, Loch Ewe, Loch Broom など、次々に通り過ぎていく湖を眺めながら、夕方、Ulapool(アラプール)にたどり着いた。
朝からの走行距離は二五〇キロを越えていただろうか。ここまで来ると、スコットランドでもほとんど最北端に近い。コーンウォールの最西端、Land’s
Endへ行った時には、南の明るさがあったが、ここには北の暗さがある。あたり一面に、どことなく重く、冷気が漂っているような心細い、侘しい感じに私はとらわれていた。
ホテルはここもMercury Hotel であった。フォート・ウィリアムズのMercury Hotel と同系列のホテルなのであろう。私たちは、まずホテルのロビーに入って、ドライバーのトムがチェックインの手続をしてくれている間、座って待っていた。その時に、ちょっとした手違いが明らかになった。トムが部屋の鍵を持って私たちのところへ来たのだが、ホテルのミスで、私ともう一人、イギリス人の女性の部屋の予約を見落としていたのである。
ホテル側は急いで部屋のやりくりをして、結局、私はホテルの特別室、イギリス人女性のほうは、ホテルの支配人の自宅の客室、ということで鍵を手渡された。その間二〇分くらい。バスの仲間たちは、自分たちの部屋の鍵はもらっていながら、全員、自分たちの部屋へは行こうとせず、そのまま私たちと一緒に待ち続けた。これも、イギリス人の仲間意識からくるエチケットなのであろうか。私はちょっと感動した。
翌日は、アラプール付近の漁港や湖、旅行客相手の特産品センターなどを見てまわって、Mercury Hotel にもう一泊する。旅行はすでに五日が過ぎていた。毎日のように湖と湖の間の、冷たい北の最果ての大地を走りまわっていると、厳しい自然の美しきに感動するこころとは裏腹に、なにか賑やかなもの、あたたかいもの、雑踏のようなものにさえ、ふと一種の懐かしさが感じられたりもする。
旅行六日目の朝、九時頃アラプールを出る。ほとんどイギリスの最北端まで来て、初めて進路を南へ転じた。一時間余でインバネスに着く。ネス湖の南端を通って北上し、半円を描いた上で、今度は北端を通って南下することになる。
インバネスの名は、日本でも明治時代に輸入された「袖無し外套」で知られているが、もともと、Inverness とはケルト系のゲーリック語 Ionar にネス湖の -nessがついたもので、ネス河の河口の町[mouth of the (river) Ness]という意味である。ネス湖から流れている河がネス河で、この意味でもインバネスは、ネス湖と直接につながっている。
インバネスでは、町をひとまわりしたあと、スコットランド特産のtartan(タータン)織物工場を見学した。このタータンは、スコットランド部族の伝統の紋様や色が先祖から代々受け継がれていて、種々様々である。だいたい、狩猟などの時に身につけるのが緑系で、晴れの式典やフォーマルなパーティなどでは赤系が用いられるらしい。売場では、このタータンを使ったキルトやスカーフ、帽子などが並べられていて、本場であるだけに値段も安い。私もバスの仲間たちと一緒にのんびりと買い物のひとときを楽しんだ。
十一時頃インバネスからA9に入ると一路エディンバラまでの二五〇キロを南下した。A道路といってもこの辺ではほとんど高速道路並みに走りやすい。イングランドとは違って周囲には「険しい」山々が現れては消えていく。その山々の線の谷間を縫うようにして、緩やかなカーブを描きながら、私たちのバスは走りに走った。
途中で昼食の休憩を取ったりして一四五二年までスコットランドの首都であったPerth(パース)まで来ると、そこからはA9は高速道路M90に変わる。エディンバラに着いたのは午後四時頃である。ここでは現地ガイドが乗り込み一時間だけの慌ただしい市内観光をした。ちょうど、名物のエディンバラ国際フェスティバルが始まっていて、街は観光客であふれていた。オペラなどの演劇や、ジャズ、クラシックなどの音楽を始め、バレー、ダンス、サーカスなども含めて、国境を越えた芸術が三週間にわたって多くの人々を惹きつけるのである。
私たちは、エディンバラでのおきまりの観光ルートを、急ぎ足でまわった。まず、Castle Hill (キャッスル・ヒル)と呼ばれる坂道を上って城門をくぐり、エディンバラ城の中へ入って行く。城は巨大な岩山の上の高いところに築かれた天然の要塞で、甲胃や武具で飾られた城の内部の部屋なども見ることができる。スコットランドの王冠、王笏、剣など王位継承のシンボルとなった品々を展示した
Crown Room(王冠の間)などもある。
しかし、ここでなによりも惹きつけられるのは、城の内部よりも外部の、城壁から見下ろすエディンバラ市街の風景の美しさであろう。私はエディンバラへ行く度に、この城壁からの写真を撮っていた。特に北側のニュータウンのあたりは、整然とした線の街路樹に沿って重厚な建物が左右対称に並び、沈んだ煉瓦色がよく周囲と調和している。この市街地の美しさがヨーロッパ随一といわれたりするのも、あながち誇張ではないかもしれない。
城門の前のキャッスル・ヒルを逆に降って行くと、通りの名はLawn Market(ローン・マーケット)に変わり、それがハイ・ストリートへ続く。土産物屋なども増えてきて、街はだんだんと賑やかになっていくが、左側の一角に、Brodie’s
Close(ブロディーズ・クロース)と呼ばれる建物がある。ここは、観光ガイドが必ず立ち止まって、いちだんと声を張り上げ説明を加える場所である。
BrodieというのはDeacon Brodie(ディーコン・ブロディー)がフルネームで、実在した人物である。豊かな商人であった。商業組合の長でもあったが、その彼は夜になると盗賊に変身し、追いつめられると殺人さえ辞さなかった。あのエディンバラ生まれの詩人・小説家
Robert Louis Stevenson(ロバート・ルイス・スティーブンソン)が一八八六年に出版したThe Strange Case of
Dr. Jekyll and Mr. Hyde(『ジキル博士とハイド氏』)は、この人物がモデルになったといわれている。
このハイ・ストリートから道はCanongate(キヤノンゲイト)に続いて、その突き当たりが The Palace of Holyroodhouse(ホリルード宮殿)である。現在のエリザベス女王が来た時に宿泊する現役の宮殿で、一般にも公開されているが、この時には時間がなくて中へは入れなかった。外から見ただけで私たちはバスでエディンバラ城の北東にあるCalton Hill(カールトン・ヒル)へ向かった。
その途中、住宅街を通って、五階建てのアパートの前まで来た時、たまたまその入口を入ろうとしている老女のうしろ姿が見えた。バスに同乗していたガイドは、急に声を張り上げて、「皆さん見えますか、あれが『ジキル博士とハイド氏』を書いた小説家スティーブンソンの娘さんです」と言った。そのアパートに独りで住んでいるらしいのである。冗談を言っているのかな、と思ったが、つい確かめるのを怠ってしまった。その真偽はいまもわからない。
カールトン・ヒルはホリルード宮殿からはそう遠くはない。一本道の坂を登りつめると急に展望が開けて小高い丘の上に出る。まずネルソン記念塔が目につく。ギリシア風の建物がポツンポツンと建っている。その中で、ナポレオン戦争の戦死者記念館だというアテネのパルテノン神殿を模したような建物が未完成のままで残されている。屋根もないし大理石の柱も足りない。建造途中で予算が足りなくなり、そのまま放置されたのである。これは中途半端の記念館ということで、かえって有名になった。
しかし、ここからの、市街地の眺めはすばらしい。エディンバラ城からの景観と双壁をなすといってよいだろう。ちょうど、夕暮れ前の淡い光を斜めに浴びて、エディンバラの街が少し輪郭をぼかしたように、目の前に沈みこんでいる。その静かでくすんだたたずまいは幻想的な感じさえして、いつまで見ていても飽きない。いつか、冬にここへ来て、寒風に吹かれながら街を眺めたことがあったが、冬空は、厳しい歴史の重みに耐えてきたこのエディンバラの街によく似合うと思った。しかし、夕暮れ近くの柔らかな日差しの中では、夏空もまた、平和で穏やかないまのこの街には、よく似合うといえるのかもしれない。
エディンバラを五時過ぎに出た私たちのバスはA1 に乗り、一七〇キロを一気に南下して、七時半にはもうNewcastle upon Tyne(ニューキャッスル・アポン・タイン)に着いた。ここのNorthumbrian
Hotel が六日目の最後のホテルである。みんなで賑やかにおしゃべりしながらちょっと遅いthree course の夕食を楽しむ。日本でなら、家族や友人同士のグループで固まってしまって、他人との会話はなかなかはずみにくいものだが、イギリスではあまりそういうことはない。彼らは、他人同士の会話に慣れていて、それが話題を広げ、こころを通わせて食事を楽しくしているのである。
その翌日もまた、九時頃ホテルを出た。観光はすべて終わって、あとは帰るだけである。ニューキャッスル・アポン・タインからロンドンまでは、約四六〇キロ。A1とM1を乗り継いでほとんど一直線に南下する。道路がよいせいもあって、バスの振動も少なく、あまり疲れることもない。これも日本とは違う点かもしれないが、座ったまま眠っている人もほとんどいない。あの食堂での会話と同じように、みんな和やかに近くの人同士でおしゃべりを楽しんでいる。
バスの走行スピードは常時九〇~一〇〇キロ。渋滞はほとんどないから、走行時間はロンドンまで五時間ですむはずである。途中、グラナダなどのサービスエリアでゆっくり昼食をとったり、何度かCoffee Break、トイレ休憩を取ったりしながら、午後四時ちょっと前にはまた、あのロンドンでのinterchange point であるサウス・ミムズに無事たどり着いた。
観光バスの乗客たちがここで降り、レストランやコーヒー・ショップで休んでいる間に、イギリス各地、あるいはヨーロッパ各国からの旅行を終えて帰ってきた数十台のバスが続々と集結し始める。到着したバスは、今度は乗客の出発地
local point別に並べ替えられて、乗客を自宅から最寄りの集合地点まで送り届ける。ちょうど出発の時と逆のやり方で、人々はイギリス各地に散って行くのである。
私は、午後四時に着いてから四〇分ほど休んで、指定されたカンタベリー方面行きのバスに乗り込んだ。チャタムのlocal point で降ろしてもらって、ロチェスターの自宅に帰り着いたのが午後七時頃であったろうか。一週間の間、スコットランドの北の端まで足を延ばしていろいろと歩きまわり、バスの仲間たちとも親しく交わりながら楽しく見聞を広めることができた。このようなバス旅行を私は何度か繰り返したが、それらは、そこで触れた人々の笑顔や優しさとともに、私にとってはいまでも、忘れがたい大切な想い出になっている。
**********
懐かしく哀しいアメリカ生活の想い出
―生活と文化をめぐる随想 (96)―
(2014.07.01)
私が初めてアメリカの地を踏んだのは、1957年の夏のことであった。オレゴン大学大学院の給費留学生としてである。まだ一般の私費による海外渡航などは許されていなかった時代で、アメリカの生活事情などもよくわかっていなかった。五里霧中のまま横浜から飯野海運の隆邦丸に便乗させてもらって、太平洋を二週間かかって横断した。隆邦丸は16,000トンでタンカーであった。当時のアメリカは石油の輸出国で、太平洋戦争の敗戦後、日本はこのアメリカからの石油輸入を再開していたのである。
隆邦丸は、8月12日の朝、ロサンゼルスから南へ三十キロほどのサン・ペドロ埠頭に着いた。大きなジュラルミン製のトランクやスーツケースなど数個の荷物を、タクシーの運転手になんとか積み込んでもらって、まずユニオン・ステーションへ向かった。そこで、夏休み中の夏期講座に出席するはずのカリフォルニア大学バークレイ校に鉄道便として荷物を送り身軽になったあと、ハリウッドのホテルで最初の夜を過ごした。
いきなり海から陸に上がってアメリカの街に入り込み、全身に浴びるシャワーのようにアメリカ文化の洗礼を受けて、強烈なカルチャー・ショックであった。私は映画でしか見たことのなかったハリウッドの街を夢中で歩き回ってくたくたに疲れていたが、興奮のためにほとんど一睡もできなかった。美しく広い街路樹の道を、次から次へとジェット機を思わせるようなテールフィンをつけた大型乗用車が通る。両側には重厚な構えの、日本とは段違いにきらびやかな多くの店が軒を連ねている。ショーウィンドーには華やかな商品の数々があふれていた。おずおずと店に入ると、一面にカーペットが敷き詰められていて、ツーンと匂いがする。アメリカの豊かさの匂いである。その「豊かさの匂い」はどこへ行ってもつきまとって、ホテルでもその匂いの中で、私はまんじりともせず一夜を明かしたのである。
ハリウッドの付近には、たとえばパサデナのような高級住宅地があって、ハウスメイドを雇っているような家も珍しくはない。映画俳優の豪華な邸宅群の前を観光バスで通り過ぎながら、そのハウスメイドの給料が月に250~300ドルくらいと聞かされた時には、思わずため息が出そうになった。留学する前の私は、札幌で公立高校の教員をしていた。そばが30円、ラーメンが40円くらいで、毎月の新聞購読料も330円の時代である。私の月給は、1万円に満たなかった。その当時のドルに換算すると、それは約25ドルで、アメリカのハウスメイドの給料の10分の1にしかならなかったのである。
その頃、円とドルの換算率は公定では一応、1ドル360円ということになっていた。しかし、それでドルが買えるわけではない。日本は、戦後の貧困のどん底からやっと少しずつ這い上がり始めた時期で、日本政府も、公用と貿易目的以外にはドルの買い入れを認めていなかった。どうしてもドルが欲しければ、貿易関係の会社などを通じて、若干のいわゆる「闇ドル」を手に入れるしかなかったのだが、その交換率は1ドル450~480円もした。これでは、私の給料は20ドルちょっとにしかならない。
その当時のアメリカ人は、自信と誇りに満ちていたような気がする。同じ戦勝国でありながら、戦争で国土が荒らされ、経済的にも疲弊していたヨーロッパ諸国に対して、ひとりアメリカはいわば漁父の利を占めて、繁栄を謳歌していた。ロサンゼルスもそうであったが、街のたたずまいが、どことなくしっとりと落ち着いて、清潔さが隅々まで行き渡っていた。ざわざわした不安の暗い影はどこにもなかった。ロサンゼルスの螺旋状に交差するハイウェイの遠望は、その頃の絵葉書によく登場して、人工美の極致のように思われた。
カリフォルニア大学バークレイ校での思い出もある。広大なキャンパスに隣接する寄宿舎での食事は、牛肉や卵や果物などもふんだんに食べられて、日本では想像もできないような豊かさであった。週末の息抜きに、サンフランシスコへ出かけるときには、その当時はまだ走っていたオークランドベイ・ブリッジを渡る電車に乗っていた。橋は夜になるとオレンジ色のランプの光のトンネルになる。海の上に長い光の影を落として幻想的で実に美しい。光のトンネルを通りながら、「ああ、これは夢ではないか」と私は何度か思った。
秋からオレゴン大学へ移ってからは、キャンパスの美しさにこころを打たれた。学生寮の自室の窓から見える芝生の緑の広大なひろがりは、勉強で疲れた体をやさしく労わってくれた。キャンパスを出て閑静な住宅街を散歩していると、垣根のれんぎょうの花が散って歩道が黄色の花の絨毯になったりしている。しっとりと湿り気を含んだその色合いがあまりに美しくて、私は前に進めず、その場にしゃがみこんでしまったこともあった。「しっとりとして落ち着いた美しさ」、それは五〇年代のアメリカでは、少なくとも私のまわりではどこでも見られた普通の情景であったといってよい。当時の日本は、敗戦で自信と生き甲斐を喪失し、貧困のなかであえぎながら国土再建を模索していた。その日本の暗さの残る世相をあとにしてきただけに、私の頭には、このアメリカの美しさが、よけいに強く印象づけられていたのかもしれない。
そのアメリカが大きな衝撃を受けたのは、1957年10月4日、ソ連が人類最初の人工衛星「スプートニク1号」を打ち上げたときである。私がいくらかオレゴン大学の生活に慣れ始めた頃であった。スプートニクは、無事に96分12秒で地球を一周する軌道に乗った。普段は勉強に追われてテレビを見る余裕もないアメリカ人学生も、この日ばかりは、夕方のテレビニュースの前に釘付けになった。このスプートニクの重量は83,4キロで、アメリカが打ち上げを予定していた人工衛星の8倍もの重さである。この金属球がかりに水素爆弾だとすると、ソ連はアメリカを核攻撃できることになる。この冷厳な事実を前に、アメリカ人の自信と優越感はいっぺんに揺らいで、「ソ連に追いつき追い越せ」が、アメリカ政府の緊急課題となった。
さらにソ連は、翌月の11月3日、全重量508キロのスプートニク2号にライカ犬を積み込んで打ち上げに成功した。アメリカ政府は狼狽した。時の大統領アイゼンハウアーは、そのあと、緊急に全米向けのテレビ放送を行い、アメリカの宇宙計画を促進するために科学・技術に関する大統領顧問を設け、国防省内の機構を強化する、と発表したりしている。この影響で、オレゴン大学でも、ロシア語の履修学生が急に増え、そのあおりをくって、日本語や中国語などの他の外国語を選択するものの数が軒並みに減少したりした。
この人工衛星打ち上げによる深刻な衝撃を受けたアメリカは、その後のソ連との熾烈な宇宙開発競争の末、1962年10月には、全面核戦争勃発の「キューバ危機」を辛うじて回避する。そして、1969年7月20日には、月着陸宇宙船「アポロ11号」による人類初の月面着陸を成功させた。アームストロング船長とオルドリン飛行士が、月面に星条旗を立てたのをテレビ画面で確認したアメリカ人の喜びと感動がどれほど大きかったかは想像に難くない。アメリカ人はまた、大きな自信を取り戻したのである。だが、アメリカ政府は、その後もソ連に優位に立つための軍備拡張の道を突き進み、それに対してソ連もまた、共産主義の旗頭として、アメリカに対抗する軍事勢力を盛り上げていった。
この自由主義陣営と共産主義陣営という対立のなかで、アメリカ政府は、ベトナム戦争への介入をも深めていく。そして、このベトナム戦争への介入は、アメリカ社会に経済的にも倫理的にも、深刻な打撃を与え、伝統的なアメリカ人の価値観を大きく揺るがせる結果になった。
1973年12月のクリスマス・イブ。私は二度日の長期滞在のため、羽田発の日航機でアメリカへ向かった。今度は、文部省在外研究員としてである。成田空港が開港したのは1978年5月で、当時はまだ、羽田を使っていたのである。まだ、海外旅行はいまほど盛んではなかった。勤務先の小樽商科大学でも、教養部の教授として海外へ出る初めての文部省発令で、同僚にも励みになると言われたりした。国家公務員だから飛行機も日本航空を使わなければならない。そんな通達があった時代である。
私の母校のオレゴン州ユジーンのオレゴン大学で1年間過ごすことになって、私は妻と中学一年の長女、小学校五年の長男の家族四人で、就航し始めたばかりのジャンボ機に乗り込んだ。全長七十メートル、全幅六十メートルのボーイング七四七型機は、まずハワイを目指した。最高で四百九十人も乗れる巨大な客室に、乗客は私たちを含めてたった三十人くらいしかいない。ほとんど貸し切り状態である。「随分少ないですね」とパーサーに私が言うと、「空気を運んでいるようなものです」と苦笑いが返ってきた。
その頃、日本のみならず、ほとんどの欧米諸国は、オイルショックに激しく揺れていた。その年10月6日の第四次中東戦争の勃発をきっかけに、アラブ諸国は石油を戦略的武器として、石油供給の削減計画を展開し始めたからである。それまで、安い石油を湯水のように使ってきた西側先進諸国は、この石油戦略に大きな打撃を受けた。特に資源の少ない日本ではインフレに拍車がかかり、当時の田中内閣の経済運営を極めて困難な状況に追いやった。不安にかられた群衆のトイレット・ペーパーや洗剤などの買い占め騒ぎが起こったりもしている。アメリカでも、燃料不足のために国内線の大手航空会社が大幅な減便に踏み切り、ニューヨーク市は、車の都心乗り入れを禁止した。カリフォルニアでも、ガソリンスタンドでいつでも自由にガソリンを買える状態ではなくなっていた。
オイルショックの最中にあったからであろうか、ハワイからロサンゼルスに着いて、歩きまわった市内の雰囲気は、どこか精彩を欠いていた。ハリウッドなどの豊かさの香りは健在であったが、街のたたずまいがなんとなくざわざわとして落ち着きがなく、あの「しっとりとした美しさ」は、もうどこにも感じられなかった。二日後、サンフランシスコへ飛び、そこでも二日滞在して、ユジーンの空港に着いたのは、大晦日のそれも深夜である。
オレゴン大学では、東洋史担当のファルコネリ教授が私の世話役ということになっていた。国内線の減便と年末の混雑で、日中の便の予約が取れなかったことをサンフランシスコから電話で説明して、ユジーン空港への到着時問を知らせると、「無事に空港までのガソリンが手に入るといいのですが」と、教授は妙なことを言う。私はその時それを冗談だと思ったのだが、そうではないことはあとでわかった。オレゴンでは、カリフォルニアより石油事情がいっそう深刻で、その後私自身も、大学へ通う車のガソリンを手に入れるのに、たびたび朝まだ暗いうちから起き出して、ガソリンスタンドの前に並ぶ羽目になったのである。
そのときのファルコネリ教授は、しかし、無事にベンツに乗って迎えに来てくれた。私は、家族を紹介し、到着が深夜になってしまった不手際を詫びた。大学で用意してくれていた宿舎に入る手続きは時間外で出来なかったので、とりあえず近くのホテルへ案内してもらった。荷物をホテルの部屋に運び込んでくれて、教授が帰っていったとき、遠くでかすかに教会の鐘の音が流れた。時計をみるとちょうど零時であった。私たち家族のユジーンでの生活ははからずも、一九七四年の黎明とともに始まることになった。
私の留学時代から十五年を経て、オレゴンの生活環境もアメリカ社会も想像以上に変わってしまっていた。自信と誇りに満ちた生活の安定感のようなものがいつのまにか消えてしまっている。人々の問に環境に対する不安が芽生え、社会に対する不満も鬱積し始めていた。 環境問題では、たとえば、環境汚染を生み出した農薬である。一九五〇年代から六〇年代にかけての日本でも、ドジョウやメダカ、ホタルなどが急速に姿を消していって、土壌の汚染が深刻化している。当時はそれでも、人々の目は、人の生死に直接関わる水俣病などに奪われていて、環境問題全般にまでは関心が及ばなかった。
しかし、アメリカでは、一九六二年に女流作家のレーチェル・カーソンが『沈黙の春』で農薬汚染の実体を告発して以来、環境汚染が社会的な大問題になっていた。それまでところかまわずまかれていたDDTなどの有機塩素系農薬や毒性の強い有機リン剤が、現実には、小鳥や益虫を殺しているばかりでなく、人の命までも脅かしていることを知らされて、人々は愕然としたのである。
ミシシッピ川で汚染による水中酸素の欠乏のため、魚が数百万単位で死んでいくという不気味なニュースが伝えられて間もない頃である。そのほかにも、核実験による死の灰、サリドマイド児の問題などがあっただけに、農薬汚染の問題は特に女性に大きな不安を与えた。このアメリカの社会では「人間は母の胎内に宿ったときから年老いて死ぬまで、恐ろしい化学薬品の呪縛の下にある」とレーチエル・カーソンは書いている。アメリカ政府は国民の問に急速にひろがった不安感を無視することが出来ず、1970年に米環境保護局(EPA)を発足させて対応に乗り出した。この環境汚染の問題は、その後も、車の排気ガス汚染や水質汚染から放射能漏れ、放射性溶液の海洋汚染等にまで規模を広げて、いまも人々の胸の中に重苦しく淀んでいるといってよい。
社会に対する不満では、たとえば、人種差別の問題がある。私が留学生としてアメリカにいた頃にはまだ、南部では公然と、黒人差別が行われていた。一九五八年の夏休みに、大陸を車で横断してニューヨークへ行き、そこからバスで南下してアトランタへ着いたときには、バスの待合室が白人用と黒人用に分けられていた。「WHITE
ONLY」と書かれた白人用の待合室は、広々として清潔で、クーラーが利いて涼しい。しかし、黒人用の待合室は、狭苦しい小部屋でクーラーもなく暑苦しかった。アジア人は白人用に入ることになっていたから、私も後ろめたい思いをしながら快適な白人用の室内で旅の疲れを休めていた記憶がある。その頃にあのリトルロック事件が起こった。
アーカンソー州リトルロック市のセントラル高校で、九人の黒人新入生が、学校に入ろうとした。そのときに、黒人の入校を拒もうとする群衆と守ろうとする群集の間で衝突が起こり、死者を出す騒動にまで発展したのである。黒人と白人の共学を禁止する南部諸州の法律は、すでにアメリカ連邦最高裁判所が憲法違反の判断を下していた。黒人運動指導者たちは、ただちに大統領アイゼンハウアーに保護を要請し、黒人新入生たちは、三百五十人の空挺部隊の警備のもとにようやく登校を果たした。
もちろんこれで、問題は収まったわけではない。黒人が正当な市民権をひろく認められるようになるまでには、その後も紆余曲折の長い道のりを要した。一九六八年の四月には、黒人、解放運動指導者のマーティン・ルーサー・キング牧師が、テネシー州メンフィスで黒人清掃労働者たちのストライキを支援中、白人テロリストに銃で撃たれて死亡している。この暗殺に怒った黒人たちは、メンフィスをはじめ、ボストン、ニューヨークなどアメリカ各地で暴動を起こした。特に首都ワシントンでは、暴動の規模が拡大して、陸軍部隊四千人が出動して鎮圧に当たらなければならなかった。このような人種差別をめぐる火種は、私の二度目のアメリカ滞在中にも消えることなく続いて、アメリカ社会に濃い陰影を投げかけていたのである。
しかし、やはり何よりもアメリカ社会を暗くし大きく歪めていったのは、アメリカ軍によるベトナム戦争への介入であった。一九六四年八月、ベトナムでいわゆるトンキン湾事件が起こった。この月の二日、アメリカ政府はトンキン湾の公海上でアメリカ駆逐艦「マードックス」が、北ベトナム哨戒艇三隻による魚雷攻撃を受けたが、反撃して1隻を撃沈、他の2隻も空母からの艦載機によって撃退した、と発表した。時の大統領ジョンソンは、直ちに北ベトナムへの報復爆撃を命令する。そして彼は、アメリカ上下両院に「トンキン湾決議案」を上程して、東南アジアにおける一切の軍事行動の権限を要請した。愛国ムードが盛り上がっていた議会は、上院議員二人が反対しただけで、この大統領の武力行使をあっさりと認めてしまった。
しかし、アメリカだけではないにせよ、政府や軍はしばしば嘘をつく。あとになってわかったことだが、1968年のアメリカ上院外交委員会の調査で、トンキン湾事件は、アメリカ軍が戦争を拡大するために目論んだでっちあげであることが判明した。アメリカ軍は、六四年二月頃から、南ベトナム軍を使って北ベトナム挑発の「34A」と称する隠密作戦を続けており、マードックスは、公海上ではなく北ベトナム領海内でスパイ活動をしていたのである。すぐに終わるはずであったベトナム戦争への介入が、だんだんと深みにはまっていくのをみて、アメリカ国内にも反戦ムードが漂い始めた。そのようななかで、焦りだしたアメリカ政府は、一九六五年二月に北爆を開始、アメリカ空母三隻から飛び立った爆撃機が、高性能爆弾とロケット弾で北ベトナムのドンホイにある軍事施設を攻撃する。ベトナム戦争は一気に拡大した。
この北爆開始にあたってアメリカ政府は、「南ベトナム民族解放戦線が、その日の未明、南ベトナム中央部にあるブレークのアメリカ軍基地を襲撃したことに対する報復である」と発表した。しかしこれも、全くの口実にすぎなかったことが、あとになってわかる。北爆は、前年九月のホワイトハウスでの戦略会議ですでに決定されていた。アメリカ政府は、北爆によって北ベトナムに打撃を与えると同時に南ベトナム軍の士気を高め、アメリカペースでの和平交渉に北ベトナムを引きずり出す、というシナリオを描いていたのである。
しかし、北ベトナムと解放戦線は、アメリカに対する徹底抗戦を宣言した。中ソの援助増大とアメリカを含めた西側諸国の国民の間に広がる反戦ムードも、おそらく彼らを力づけていたであろう。北爆だけでは効果に限界があるとみたアメリカ政府は、北爆を一層拡大する一方で戦闘部隊の増派を決め、同年七月には、ベトナム駐留のアメリカ軍を七万五千人から十二万五千人に増やした。
アメリカ国内の反戦ムードは一層広く浸透していくようになった。六七年四月十五日にニューヨーク、サンフランシスコで始まった反戦集会は、十月二十一日にピークに達した。以来、この日は、「10・21国際反戦デー」として記念すべき日となった。このようなベトナム戦争による時代不安を最も身近に感じ取っていたのは、いうまでもなく、戦争にかりだされ始めたベビー・ブーム世代の若者たちである。その若者たちを集めて開かれた一九六九年八月のウッドストック・コンサートは、空前の規模に膨れ上がった。ニューヨーク北西約百十キロの会場にあてられた酪農場には、五万人と予想されていた聴衆が四十万人にも達したのである。
アメリカの青年たちは、ウッドストックを世代の連帯の象徴とし、自らをウッドストック・ジェネレーションと呼んだ。彼らは現実の社会システムの呪縛を拒否し、アメリカの現実をいかに自分たちの想定する社会へと変化させていくかを考えるようになった。一方では麻薬がおおっぴらに乱用され、性の表現も自由奔放になっていく。従来のアメリカ社会の価値観が大きく揺らぎ始めたのはこのあたりからといってよい。
このあと、十一月十三日からは、アメリカ各地で計百万人以上が反戦デモを行い、十五日には首都ワシントンでの反戦集会に、全国から二十五万人が集まった。首都にこれだけのデモ参加者が集まったのは、アメリカ史上初めてのことである。同じ頃行われたニューヨーク市長選では、ベトナム反戦を掲げたジョン・リンゼーが勝利するという「番狂わせ」もあった。しかし、世論の反対にも屈せず、時の大統領ニクソンは、北爆強化と北ベトナム全港湾の機雷封鎖を強行した。それでも遂に勝つことが出来ず、その後、アメリカ軍は徐々に自滅していくのである。
一九七三年一月のいわゆる「パリ協定」に至るまでにアメリカがベトナムに注ぎ込んだ戦費は約千三百億ドルで、死者は四万六千人、重軽傷者は三十万三千人を数えた。南ベトナム軍民の死傷者は、実に三百万人以上にのぼっている。しかも、このパリ協定も、事実上反古と化していたから、戦争の惨劇は、このあとさらに二年あまりも続いたのである。
世界一の大国と自負していたアメリカが、東南アジアの小国北ベトナムとの戦争に全力を投入しても勝てなかった。アメリカ国民のこころの中に深い傷跡を残して、結局は、北ベトナムに負けた。これで社会が変わらないはずはなかった。一九七四年の一月一日から始まった二度目の長期滞在を通して、私は、ことあるごとにその変化に気づかされることになったのである。街の雰囲気にもかつての落ち着いた美しさはなくなり、社会生活の明るさにも翳りが見えてきたように思えたのは、オイルショックの深刻さのためだけではなかった。
自信と活気を失い始めたアメリカ社会のなかで、追い打ちをかけるように、私たちの滞在中には、ニクソンのウォーターゲート事件というのもあった。これは一九七二年六月、ワシントンのウォーターゲート・ビルのガードマンが、同ビル内にある民主党全国本部へ侵入しようとした五人の男たちを逮補したのが始まりである。ちょうどニクソンが大統領の再選を目指して選挙運動を展開していたときであった。この再選委員会が侵入事件と関係することはすぐに露見した。
事件はしばらくの間静かに推移し、ニクソンは十一月に大統領に再選された。その間ニクソンと補佐官のハルドマンやアーリックマンは、再選委員会に関する給料の支払いや税金のごまかし、違法な選挙寄付、民主党に対する選挙妨害の汚い手口などを隠蔽しようとした。それらのことがワシントンポスト紙記者などの周到な取材調査で次から次へと明らかになって、事件は一気に大統領のスキャンダルへと発展した。ニクソンは、一部の部下がやったことで自分は知らなかった、と嘘をつき続けたが、やがて隠しきれなくなり、遂に八月八日、大統領を辞任する羽目になったのである。現職の大統領が任期の途中で辞任するのはアメリカ史上初めてのことであった。この事件により大統領の威信は限りなく低下したが、かろうじて、アメリカ民主主義とジャーナリズムの健全さを世界に証明する結果となった。
私はユジーンの大学宿舎に落ち着いて以来、テレビニュースで、毎日この事件が取り上げられているのを見てきた。それは文字通り、来る日も来る日も毎日であった。日本ではこの種の犯罪でも、一、二カ月もすればやがて追及の手もゆるめられ、国民のほうも報道に飽きて忘れていく。それがアメリカでは、決してそういうことはなかった。この毎日執拗に続けられる報道が、私が見ただけでも実に七カ月もの間続いたのである。
八月八日。この日私は家族と共にワシントン州のスボケィンにいた。大学も小学校も夏休みに入った六月下旬から、私たち四人家族は、古い大型シボレーにテントや寝袋などのキャンプ用品と、米、水、燃料などを積み込んでアメリカ一周の旅に出ていた。オレゴンから南下し、カリフォルニアから進路を東にとって大陸を横断した。東海岸に着いてからは、ワシントンD・C、ボルティモア、ニューヨーク、ボストン等の都市を経てカナダのモントリオールへ抜け、そのあと西に向かって、ミシガン州からウィスコンシン、ミネソタ、ノース・ダコタ、モンタナ州まで、ちょっと大げさに言えば命がけの旅を続けていた。オレゴンのユジーンを出てすでに四十日、一万八千キロを走ってきて、八月八日にはスボケィンの広大なキャンプ場で一休みしていたのである。ニクソンの辞任演説はそこで聞いた。キャンプ場の片隅では若者の一団が大きな歓声を上げた。近くのテントの陰では、中年の女性がひとり涙を流していた。
スボケィンでは万博が開かれていた。その四年前の大阪万博にもたまたま家族四人で訪れていたが、それは、一日の入場者が三十万人にもなったりして「待った、疲れた、見られなかった」万博であった。このスポケィンのアメリカ万国博覧会では、一日の入場者は二万人にも満たなかった。広い会場のなかをゆっくりと好きなものを好きなだけ見ることが出来た。本来、万博とはそういうものであろう。しかし、大統領のスキャンダルが辞任という結末を迎えたあとの万博会場は、どことなく湿った空気が流れているような気がした。
一九八二年の秋、私はフルブライト上級研究員として、アリゾナ州の砂漠のなかの街ツーソンで過ごしている。三度目の長期滞在であった。この時は、一足先にアリゾナ大学の編入生になっていた長女と二人だけの生活であった。妻と東京の大学へ通っていた長男は、東京の家に残っていた。
ツーソンは、アリゾナ州ではフェニックスに次ぐ第二の都市である。周囲には、サンタ・リ夕、カタリーナ、リンコン、ウエットストーン等の山系が連なっていて、それらはいずれも、岩肌を露出したごつごつした感じの禿げ山がほとんどである。西部劇で有名な砂漠の街だが、いまでは人口も七十五万を超えてハイテク産業で急成長している。私が住んでいた当時でも、農鉱業と観光が主な産業で、豊かな街として知られていた。なにしろ、一年のうち三百五十日が晴天で、湿度も年平均二十五パーセントくらいしかない。巨大な人工農園に化石燃料をふんだんに使って潅水装置を完備すれば、お天気まかせではない極めて効率のよい農業経営が可能になる。オレンジ、グレープフルーツ、スイカ、メロン等の果物も、日本の価格の三分の一から五分の一くらいの安さであった。
しかし、やはり生活環境は厳しかった。私が「フルブライト」の選考の際に、配属希望をアリゾナ大学にした理由の一つは、砂漠のなかでの生活体験をしてみたかったからであった。比較文化の勉強のためにも有益である。そして、ツーソンでは、予想通りの厳しい生活環境が待っていた。
アメリカでは、私がまだ日本にいる間に、タイレノール事件が発生して、大騒ぎしていた。タイレノールというのは、アメリカで最も広く使われている鎮痛剤の名前である。ドラッグ・ストアーで売られているその鎮痛剤に、誰かが青酸カリを混入して、アメリカ各地で七人の死亡者がでた。消費者を無差別に狙った大量殺人事件につながる恐怖のなかで、全米がパニック状態になった。フルブライト委員会からも私宛に、アメリカに着いても、タイレノールを決して買うことのないようにと注意の手紙が届いた。
ロサンゼルスで二日過ごしてツーソンに着いた日の夜、娘が借りておいてくれたアパートの近くで、大規模な捕りもの騒ぎがあった。ヘリコプターが低空飛行で旋回しながら、サーチライトで地上を照らしている。パトカーのサイレンが鳴り響き、何発かの銃声も聞いた。その数日後には、やはり近くで、六歳の女の子が何者かに殺害されている。地域差はもちろんあるが、「アメリカはまた一段と悪くなっているな」と私は思った。
アリゾナ大学では、言語学部の事務室の前に廊下をはさんでタイプライターやコピー機がおかれた機器室があった。コピー機は大きくて筒単に持ち運びできないのでそのままだが、タイプライターはすべて頑丈なボルトで机に固定されている。犯罪が多いことを如実に示していた。事実、私がコピー機を使っている昼休みの間に、目の前の事務室で盗難があった。三人いた事務職員がたまたま何かの用事で一人もいなくなったちょっとした隙に、事務室内のボルトに固定されていない電動タイプライターが一台盗まれたのである。事務室は廊下の奥まった一角にあって、あんな大きなものを白昼堂々と盗むためには、よほどの技量がいる。私も近くにいて全く気がつかなかったが、驚きながらも、その技量の見事さに感服した。
私の娘が授業の帰りに、大学内にある郵便局へ寄った。切手を買い、カウンターの横のテーブルの上で手紙に貼ろうとしていたら、風が吹き込んできてその切手をはらはらと飛ばした。その切手を拾いあげてもとのテーブルに戻ると、手紙の横に置いた財布はもうなくなっていた。一瞬の隙でも見せてはならないのが、このアリゾナ、あるいは、アメリカなのである。
私と娘の住んでいたアパートの部屋は百平方メートルほどの2LDKで、狭くはなかったがあまり新しくはなかった。夜中に起きて台所の電気をつけると、ゴキブリがさっと逃げていくことがある。透き通るような小さなからだで、動作は驚くほど素早い。ぱっと瞬間に消えてしまうような感じである。やはり砂漠のゴキブリである。倍もあるような大きなからだでもぞもぞ歩いている日本のゴキブリとは大きな違いである。蛇でも砂漠の蛇はたいていからだが小さく、それでいて獲物を襲えば一瞬にして牛をも倒すような猛毒を持っている。それが砂漠の生き物である。からだが大きく鈍重な動きであれば、食料の少ない砂漠では生きていくことが出来ない。
私が、友人の一人に、いまのアパートはゴキブリが出ていやだ、と言ったら、彼は平気な顔をして、タランチュラを買ってきて部屋のなかに放し飼いにしておけばいいという。タランチュラというのは、大きな毒グモである。毒グモだが人間をかむことはなくゴキブリを食べてくれるのだそうである。私は、怪奇小説にでも出てくるようなその不気味な毒グモの姿を想像するだけでも背筋が寒くなった。砂漠の街で生きていくのには、細い神経ではもたない。針金のような太い神経が必要なのである。
毒といえば、ツーソンの家々のまわりには、真夏の強い太陽の光の中で、オリアンダがハイビスカスに似た白や赤の花をいっぱいに咲かせていた。これも、アリゾナの砂漠特有の木で毒をもっているはずである。真偽のほどは明らかではないが、ツーソンでこのオリアンダの枝をバーベキューの串代わりに使って、死んだ人がいると聞いたこともある。その後、カリフォルニア奥地にある砂漠の保養地パーム・スプリングスへ行った時にも、泊っていたトラベロッジのホテルのまわりに、この花をみかけた。ぎらぎらと照りつける太陽の下で、白や赤の花をいっぱいにつけていた。それは花の可憐な優しさというものとは全く無縁の異様な乾いた美しさであった。暑熱に対抗するするかのように、人工の造花のような逞しさをむき出しにしている。
ツーソンにせよ、このパーム・スプリングスにせよ、砂漠のなかの街というのは、当然、きわめて人工的で、むしろこの造花のようなオリアンダがよく似合うのかもしれない。本来、人間が住み難い不毛の砂漠なのだから、そこで街を造っていくのにはよほど大きな人工の手を加えなければならない。そして、それを可能にしたのがアメリカの豊富な石油資源であった。そのことは、高いところから砂漠のなかの街を一望してみるとよくわかってくる。
パーム・スプリングスの中心部から北へ三キロほど走ると、急峻な岩山の山頂まで登れるケーブルカーがある。オーストリアのケーブルカー専門会社の技術援助で、1963年9月に竣工した。八十人乗りの大型ケーブルカーが、二千六百メートルの山頂ステーションまで、ほとんど垂直に近いような急角度で登っていく。下は四十度の暑さでも、山頂では二十五、六度の涼しさである。展望台を兼ねたレストランでしばらく休んでコーヒーを飲む。こういうところで飲むコーヒーはうまい。
山頂からはパーム・スプリングスの街の全景がそっくり見渡せる。周囲は十キロくらいになるだろうか。広漠とひろがる砂漠のなかにその中の一部だけが碁盤の目のように整然とした街の並びが形成され、東西にやや長く伸びている。黒ずんだ街の色と、周囲の砂漠の白とのコントラストが際だっていて、いかにも砂漠のなかの街という感じである。もし、夜この山頂から街を見下ろせば、この黒と白のコントラストは、光と闇のコントラストになって一層の際だった対照を見せるであろう。闇のなかにぽっかりと浮かぶ光の湖のようなもので、さぞ美しい光景であるに違いない。しかし、考えてみると、それは実に「危うい美しさ」でもある。
古来、文明は、森林を切り開くことから始まった。森林の伐採が文明を支え、そして、伐採すべき森林をすべて失ったとき、文明は滅びた。エジプト、ギリシア、ローマ等の地中海沿岸に栄えた文明もすべてそうである。地中海沿岸で足場を失った文明は、アルプスを越えてヨーロッパの森林を破壊し始めた。そして築き上げられたヨーロッパ文明が、やがてヨーロッパの森林をも徹底した破壊に導いていく前に、それを救ったのがアメリカの広大な森林である。
ヨーロッパが、中世の大開墾時代に森林を切り倒していったように、アメリカは十七世紀から大開拓時代に入って森林を切り倒していった。しかし、十八世紀になってイギリスの産業革命が起こると、その余波を受けてアメリカの森林資源も徐々に鉱物資源に取って代わられるようになる。一八五九年には、ペンシルバニア州で、世界に先駆けて石油採取井戸が掘られ、近代的な石油産業の幕開けとなった。
二十世紀になると、ガソリン機関やディーゼル機関など、石油を燃料とする内燃機関の発達に伴い、石油はあらゆる産業の最も重要な動力源となっていく。アメリカは石油を武器にして世界をリードし、世界一の豊かさを誇示するようになった。ツーソンやパーム・スプリングスのような砂漠の中の街が作り上げられたのも、このアメリカの豊かな石油資源があったからこそである。
アリゾナの砂漠のなかに、全く人工的に造られたサン・シティの街がある。飛行機から見ると、広い砂浜に大きなカタツムリがしゃがみこんでいるような異様な風景である。街の中心部から同心円状に住宅街が造られて街路樹が植えられ、その間に池やプールやゴルフ場なども点在している。住民が少しも不自由しないように、水も食料も住居もすべて機械に依存し、それらの機械がフルに運転を続けて住民の生活を支えている。一見、便利で快適に見えるが、しかし、一旦電気が止まり石油が切れたら、ここはそのまま巨大な人間の墓場と化してしまうであろう。このパーム・スプリングスも状況は同じである。機械がとまれば、人間は生きていけない。ツーソンもそうである。そして、もともと砂漠であったカリフォルニアの多くの街も、ロサンゼルスを含めて、例外ではない。
思えば私が初めて住むようになった1957年からのアメリカは、夢のように美しい国であった。私はそのアメリカで、数多くの旅行をして北から南へ、西から東へと、おそらく地球一周を越えるくらいの数万キロの足跡を残してきた。そして、そのアメリカが、年を経る毎に美しさと豊かさの影を潜めて、人々の幸せからも遠ざかっていくような気がしていた。特に、1957年から26年を経て、3度目の長期滞在を中断して帰国した1983年当時のアメリカは、高度文明の翳りと社会体制の行き詰まりさえも危惧させるようになっていた。事件に巻き込まれた辛い記憶もあるからであろうか、今の私には、その頃のアメリカの街々のたたずまいが、あのニューヨークなども含めて、淡くてもろい砂上の楼閣のように、セピア色にくすんで思い出されるような気がする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
No,1~No,10へ
No,11~No,20へ
No,21~No,30へ
No,31~No,40へ
No,41~No,50へ
No,51~No,57へ
No,58~No,80へ
|