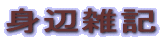
思い出の新千歳町を離れて (身辺雑記75)
= 生かされてきた私のいのち (5) =
奈良の生駒山山腹に不動明王坐像を本尊とした宝山寺というお寺がある。「生駒聖天さん」と呼ばれて関西ではひろく親しまれている名刹である。私は、小学校に入る前から、毎年、元旦には父に連れられて、この宝山寺へ初詣に出かけるのが慣わしになっていた。昭和15年(1940年)の元旦にも訪れている。
正月というのは、子供心には限りなく楽しく、「もういくつ寝たらお正月・・・・・」と本当に指折り数えて待っていたものである。大晦日になると、その楽しみの期待は頂点に達して、布団にもぐりこんでもなかなか寝付けない。それでも、初詣に出かけるために、朝2時過ぎに起こされると、私は飛び起きて、正月用のよそ行きの服を着る。そして、普段は履くことのない革靴を履いて、父と二人で3時には家を出る。それだけでも、このうえもなく嬉しかった。
暗い道を市電通りまで出て、初詣用の市電で「上六」と呼ばれていた上本町6丁目まで行く。そこで、近鉄奈良線に乗り換えるのだが、いつも駅は大変な人出で、私ははぐれることのないように必死に父の手に縋って歩いた。やっと電車に乗り込んで、30分ほどで生駒で降りると、あとは果てしなく続くように思われた石段をひたすらに上っていくのである。お寺の境内まで辿りつくのに、ここでも30分以上はかかっていたかもしれない。
私は知らなかったが、当時すでに生駒の鳥居前から宝山寺までは、日本では最初といわれるケーブルカーが走っていた。延長距離948メートル、高低差146メートルの宝山寺線で、大正7年の8月29日から運行が始まっている。しかし、元旦はものすごい数の人出だから、ケーブルカーに乗ろうと思えば、おそらく、何時間も待たされたのかもしれない。私は、ケーブルカーのことは知らず、西も東もわからず、人ごみにもまれながら、ただ、父に必死にしがみついて歩いていた。
宝山寺の境内に入ると、本堂のうしろに般若窟という切り立った巌山がそそり立っているのが見えてくる。「般若窟」の名は、役の行者(えんのぎょうじゃ)として知られている役君小角(えのきみおづぬ)が、この場所に般若経を納めたところから名付けられた。いまはこの般若窟を背景に、いかにも仙人らしい雰囲気を漂わせている役の行者の等身大の像が境内を見下ろしている。役の行者は、『続日本紀』にも記録が残されている実在の人物で、卓越した超能力者であり呪術者であった。舒明6年(634年)1月に、大和国葛城山麓の茅原の里(現在の御所市)で産声をあげたといわれているから、もう1300年以上も前の人物である。
役の行者は、若い頃より金剛葛城の山々で修練を積み、そのあと大峰山系、箕面、生駒山系などでも修行して、最高の法力である孔雀明王の術を会得したという。「孔雀明王の術」といってもそれがどういうものか、ちょっと想像もつかないが、『日本書記』には、中大兄皇子の母皇極天皇が、斉明天皇として再び即位された年(655年)の記録に、「大空の中に龍に乗れる者あり、かたち唐人に似たり。青き油笠を着て葛城の嶺より馳せて胆駒山(いこまやま)に隠る。午の時にいたりて住吉の松のいただきの上より西に向い馳せ去りぬ」とあるそうだから、空を自由に飛ぶことも出来たのであろう。
事実、空を飛んだ話は、いろいろな形で言い伝えられてきた。後には、光格天皇より「神変大菩薩」の称号も受けている。全く人間離れをした能力の持ち主であったが、役の行者は、そのような法力によって多くの庶民の悩みや苦しみを救ってきたともいわれている。そのことが、その当時もいまも、多くの人々から、親しまれ敬われている所以なのかもしれない。
この役の行者が、宝山寺の般若窟で修行したという故事によって、宝山寺の開祖とされているのだが、その後もここは修験道の聖地として、数多くの修験者を惹きつけてきた。寛保元年(1741年)に寺社奉行に提出された「記録写し」には、唐へ渡る前の弘法大師(774〜835)も、ここで修行したことがあると記されているらしい。
しかし、この宝山寺へ初詣を続けていた頃の幼い私には、そういうことは、もちろん、何も分かってはいなかった。ただ、この初詣は、幼い私にとっては「待ちに待った正月」を迎えたことを意味していたから、そのことだけでもうれしく、幸せであった。父は信心深かったが、数多くの初詣のための神社、仏閣があるなかで、なぜこの宝山寺を選んで熱心に参詣を続けていたのかも、いまとなっては、知るすべもない。
初詣を終えて、新千歳町へ帰ってくるころには、もう8時近くになっていただろうか。昔は、1月1日にも学校で新年の式典があった。市電を降りて、家へ寄っていく時間はなかったので、私はそのまま、父と別れて新千歳小学校へ行った。左胸には、赤い房飾りをつけていた。級長のしるしである。青が副級長で、私の胸には、いつも赤か青の房飾りがあった。学校では、講堂に集められて、君が代を歌い、教育勅語を聞く。教室では、紅白の饅頭をもらって、それが終われば一目散に家へ帰る。それからが、正月の天国の時間になった。
私は、時おり思うことがあるが、子どもの頃の正月はなぜあれほどに楽しかったのであろう。大人になっていくにつれて、いろいろなことを覚えていくが、その反面、あの楽しみを感じる子どもの能力は、失われていくのかもしれない。私は、正月の時間は、一分でも十分でも、惜しいような気がしていた。繁華街の映画館はだいたいどこも満員になるのだが、映画などで時間をとられるのは、もったいないことだと思っていた。
お年玉をもらって、ご馳走を食べて家を飛び出すと、私は、夕方まで無我夢中で過ごした。家から、北恩加島小学校へ行く途中に、北恩加島町の商店街がある。かなり広く、十数メートルはあったと思われる道幅の両側に様々な店が並び、それが五百メートルくらいも続いていた。お好み焼きや、たこ焼き、いか焼き、綿菓子、駄菓子などの屋台なども所狭しと並んでいる。文房具店のショーウインドーに、どういうものか、本物そっくりの拳銃が飾ってあって、一円五十銭という高い値札がついている。それを矯めつ眇めつ見ているだけでも、すぐ30分くらいは過ぎてしまうのであった。
正月3か日はあっという間に過ぎてしまって、もとの生活に戻っても、私は毎日外で遊びまわっていた。昼食の時間になると一度家に帰るが、そのほかは、ほとんど家にはいたことがない。小学校の3年生になっていたから、たまに、宿題なども出されることがあったが、そんな時には、大急ぎで宿題を片付けて、すぐまた家を飛び出す。父の工場、甚兵衛渡しの待合室、川沿いの材木置き場や川の前の広大な原っぱなど、遊び場所には少しも不自由しなかった。
父は、月に二回ほど日曜日が休みであった。その日だけは、私は何処にも行かずに父にくっついていた。父が和服に着替えると、それが外出の合図である。私は父の和服の袖を片手で掴んで、放さなかった。たいていは、甚兵衛渡しから船で対岸に渡り、そこからバスで、九条新道の繁華街に出る。そこで食堂に入り食事をして、映画を見て帰るというのが父と私の外出のパターンであった。いま考えると、胃が弱くて寝込むことの多かった母の世話などすべてを姉たちに任せて、いつも私一人が、父にくっついて楽しんでいたのはやはり不公平で、すまない気がする。
しかし、この九条新道行きは、何時までも続かなかった。昭和十五年(1940年)の三月、父は長年勤めていた伸鉄会社を退社し、生野区の田島に自分の小さな鉄工場をもつことになったからである。父は自分が得意とする鉄工技術を生かして、いつかは伸鉄、圧延工場を経営することを考えていたと思うが、それには、巨額の資金が必要になる。それまでのつなぎに、鉄工場を経営して独立を目指したのであろう。それが四十歳になったばかりの父の経営計画であった。
家も広々とした新築の二階家へ引っ越した。真新しい木の香りが実に新鮮であった。学校も、新千歳尋常小学校は三年生までで、四月からは、生野尋常小学校へ転校して四年生になった。このときの新居の住所は、生野区の田島四丁目で、いまでも特定できる。今里筋とよばれる広い道路に面していて、この道路は、いまは交通量の多い中央分離帯を設けた幹線道路になっているが、私が住んだ頃は、滅多に自動車も通らず、昼間でも閑散としていた。今も同じ場所にある生野小学校へは歩いて十分の距離である。私は、勇んで学校へ通い始めたが、ここでは予想に反して、初めての、特異な経験をすることになった。
この生野小学校で私が入れられた四年生のクラスの担任は、Sという四十歳くらいの男性であったが、明らかに精神障害をもっていたのである。これは、今も昔もあまり変わらないが、小学校では、担任がほぼ全科目を受け持って指導する。しかし、S担任は、何も教えようとはしなかった。教室の隅に自分の机を置いて座り、墨をすっては筆で新聞紙の上に字を書きながら、時々、思い出したようにくすくす笑っていた。それが、下校時まで続くのである。授業時間は全部、自習であった。
何故こういう事態がまかりとおっていたのか。いまでは考えられないことだが、むかしは、学校に対してものを言う風潮はあまりなかった。おそらく、校長も気がつかなかったのであろう。もしかしたら、他の教員たちも見てみぬ振りをしていたのかもしれない。子供たちは遊び盛りである。私もそうであったが、おとなしく自習などするはずもなく、教室では好き勝手に遊びごとをしたり、あるいは、教室を抜け出しては運動場の片隅で遊びまわっていた。S担任は、教室内ががらんとしていても、気に留めるふうでもなかった。
この全く勉強を教えられない異常な状況は、四月の新学期から、十二月末の二学期の終わりまで続いた。私は転校してきたばかりで、はじめのうちは呆然としていたが、そのうち、「自習時間」を活用して、算盤の練習と模型飛行機作りに熱中するようになった。
学校の近くに、評判のよい算盤教室があって、巧みな指導法で多くの子供たちを集めていた。私も友達に誘われて行ってみたのだが、夕方から始まるその教室は、数十人の子供たちであふれていた。六級から始まって一級までのクラスに、技量によってふるいわけられ、一級になると、子どもの目には、神業のように思える計算能力を発揮する。私は、生野小学校四年生の自習の時間には、教室の後ろのほうに座って熱心に算盤の練習に努め、夕方には算盤教室へ通って、徐々に序列を上げていった。その年の暮れには、いつの間にか、一級に登り詰めていた。
しかし、その算盤よりも、もっと楽しく熱中していたのは、模型飛行機作りである。私は小さいときから工作が好きであった。おそらく、手先も人一倍器用であったかもしれない。朝、登校して、算盤ばかりを「自習」して、下校すると、一目散に、家から十分ほどのところにあった模型飛行機の店へ行く。その店の奥には、作業場があって、たいてい店のご主人が模型飛行機作りに専念していた。店は奥さん任せである。
十畳ほどの作業場には、天井や壁に、大きいのから小さなものまで、ご主人が作ったさまざまな模型飛行機が飾られていた。寸分の狂いもなく作られたそれらの模型飛行機は、見ているだけでもわくわくするくらいで、実に見事な出来栄えであった。私は、頻繁に出入りしているうちに作業場へ入ることも許され、たまには、ご主人の作業の手伝いもした。また、時には、ご主人のお供をして、出来上がった模型飛行機のテスト飛行にでかけることもあった。
店から少し歩くと、おそらく今の百済駅前あたりであったろうか、その頃はまだ、広大な原っぱが広がっていた。そこで、模型飛行機を飛ばす。ご主人の飛行機はどれもすばらしくよく飛んだ。一生懸命に追っかけて、それを拾って帰るのは私の役目である。至福の時間であった。私の作った模型飛行機も、よく飛ぶようになって、時々、ご主人からも出来栄えをほめられたりしていた。
私が算盤と模型飛行機に夢中になっているうちに、戦時下の世相は厳しさを増しつつあった。四月にはガソリン不足のため、タクシーの深夜営業は禁止されていたが、それが八月になると、「国民生活新体制要綱」が発表されて、自動車の使用は厳しく制限されるようになった。食堂やレストランなどでは米食が禁止され、映画館の営業時間制限、遊覧旅行の制限など、要するに、贅沢、享楽はすべて厳禁ということになった。九月に入ると、日本軍の北部インドシナ進駐がはじまり、二十七日には、日独伊三国同盟がベルリンで調印されてしまった。第二次世界大戦での日本の破局の始まりである。
十月に大政翼賛会が発足して、戦時体制が強化されていくなかで、十一月十日から十四日まで「紀元二千六百年記念式典」が日本各地で大々的に行なわれた。神武天皇即位後二千六百年になるというこじつけであったが、それは『日本書紀』の研究でも史実とはいえないとする津田左右吉の著書なども発禁処分にしたうえでのことであった。言論統制を強めていくかたわら、政府は、なりふりかまわぬ国威発揚のための宣伝に努めた。昼酒も、この五日間だけは許可された。
私の家のまわりでも、賑やかに提灯行列が行なわれて、久しぶりに華やいだ雰囲気を味わった。美しく飾られた花電車も走った。その時の歌、「金鵄輝く日本の、栄えある光身に受けて、今こそ祝えこの朝、紀元は二千六百年」は、いまもよく覚えている。しかし、物資不足や物価上昇に苦しめられていた一般庶民は、この祝典歌をタバコの値上げにもじって、「《金鵄》上がって十五銭、栄えある《光》三十銭」と陰で歌って鬱憤を晴らしていた。永井荷風の『断腸亭日乗』(十一月十六日)には、その頃の政治体制を揶揄して、「今回の新政治も田舎者の作り出せしものと思えばさして驚くにも及ばず。フランス革命または明治維新の変などとは全く性質と品致を異にするものなり」とある。
(2011.03.01)

戦時色が強まっていく社会の中で (身辺雑記74)
= 生かされてきた私のいのち (4) =
私が大阪市大正区の北恩加島尋常高等小学校に在学したのは1年だけである。昭和13年(1938年)4月からは、住んでいた町内に新設された新千歳尋常小学校へ移った。私の手許には、「右者本校ニ於テ尋常小学校第一学年ノ課程ヲ修業セシコトヲ証ス」と書かれた北恩加島小学校長名の修業証書が残っているが、これが私が手にした最初の証書である。この証書と、印刷されたばかりの学校新聞をもらって、級友たちと別れた。その学校新聞には、私の作文「運動会の日」が載せられていた。私の文章が活字になったのは、これが最初であった。
新千歳小学校は、家から歩いて15分くらいの電車通りにある。新築の校舎だから、机も椅子も教室も、すべたが新しくて綺麗であった。ここで私は2年イ組に編入された。担任はいまもよく覚えているが、西川
始という名の女の先生である。女学校を出たばかりで、代用教員であったように思う。昔は、女学校を出るだけでもなかなか大変であったから、私たちはみな西川先生を偉い人だと思っていた。西川先生は、紫の袴をはいて颯爽と歩きまわり、教室では大きな声で熱心に私たちを教えた。
もう70年以上も前のことになるが、このときのクラスメイトの一人の名前を鮮明に覚えている。稲見一良という。一良は「イツラ」と読んだ。お父さんは陸軍中尉で出征中であった。一人っ子の稲見君はお母さんと二人で留守を守っていた。一度彼の家に遊びに行ったことがあったが、玄関には「英語教授」と書かれた看板がかかっていた。お母さんは、その頃としては珍しく、自宅で英語を教えていたのである。
この稲見君は、作文がうまかった。よく書けた作文は、授業のなかで西川先生がクラスのみんなに読んで聞かせるのであるが、そのなかには、ほとんどいつも、稲見君と私の作文があった。西川先生は、ある時には稲見君の作文を先に、また、ある時には、私の作文を先に読んだりしていた。いつのまにか、稲見君も私も、互いにライバル意識のようなものを持つようになっていたかもしれない。
学期ごとに、級長と副級長が担任によって任命されていたが、それも、稲見君と私が、ほとんど交互に、級長と副級長を独占していた。2学年の終わりには、学年に一人与えられる大正区教育会長からの表彰状と銀の賞牌は、私がもらったが、稲見君はそれをひそかに期待していたらしい。彼の残念がっていた顔つきがいまも記憶に残っている。
その当時、級長をしていて一つ、分かったことがあった。小学校の授業料は無料だが、父兄会費というのを毎月納めることになっていた。1口10銭で、1口から10口まで、自由に選んで申し込む。その父兄が書いた申込書を私がみんなから集めて、先生に提出することになっていたのである。その時、みんなの申し込みの口数がわかったのだが、大半が、1口の10銭であった。なかに2口の者が何人かいた。3口の者は1人であった。私だけが10口の1円だった。
私はなぜ自分だけが1円なのかわからなかった。1円といえば子どもにとっては大金である。3円で子どもの自転車が一台買えた。2年上のマーちゃんなら、お父さんが大阪ペイントの社長でお金持ちであったから、10口であったかもしれない。しかし、私の父の場合は、まだ若い一介の社員で、小さな借家住まいである。有能な鉄鋼技術者として会社から一目置かれて給料も高かったかもしれないが、1円はいかにも多すぎるようにその時の私には思えた。私は父の書いた申込書の、10口1円を、3口30銭に自分で勝手に直して提出した。だが、それはすぐばれてしまった。
その翌月、父兄会費を納める袋に1円が入っているのを見て、私は3口にして申し込んだことを白状せざるを得なかった。3口でも、クラスでは一番大きい金額であることなども言ったかもしれない。父は大声で私を叱った。私は改めて、西川先生に訂正を申し出て10口にしてもらい、それからは、毎月1円ずつ納めていった。
父は終生、私を命がけで愛してくれていた。私がほしいものは、言えば必ず買ってくれた。学校からも、時には、児童向きの本などが推薦されることがある。値段が高くて、クラスの誰もが敬遠しても、父は私に申し込ませた。私は父がものを大切にし、自分は決して無駄使いしないことをよく知っていた。しかし、私のためには、大工道具から万年筆、ハーモニカなど、なんでも買ってくれた。私はいつのまにか、ものをほしがることを止めるようになっていった。言えば必ず買ってもらえることを知っているだけで、私はこころ豊かで満ち足りていた。
ちょっと脱線したが、ここでまた、稲見君のことに話を戻そう。私は、新千歳小学校には2年いただけで、稲見君とは3年生の最後に別れて以来、長い間、互いに連絡は途絶えていた。何年か前にふとインターネットで調べて、初めて、彼が放送作家、小説家として、その才能を期待されていたことを知ったのである。迂闊であった。彼は、10年間の闘病生活の末、1994年2月24日に肝臓がんで亡くなったらしい。63歳であった。「ウイキベディア」では、稲見君のことを、つぎのように紹介している。
《記録映画のマネージメントを務める傍ら、1968年文芸誌の新人賞に入選、しかし多忙のため作家活動に専念しなかった。1985年肝臓がんの手術を受けるが全摘ができないと分かると、生きた証として小説家活動に打ち込むと周囲に宣言し、1989年『ダブルオー・バック』にて本格的に小説家デビュー。1991年『ダック・コール』にて数々の賞を受賞し期待されるも、1994年、わずか9冊を残して癌のため没した。》
あの新千歳小学校でクラスメイトであった稲見君のこのような壮絶な生き方を垣間見て、私も粛然とさせられた。昭和一桁生まれというのは、戦中、戦後を経て苦難の多い人生を歩んできた人が少なくないのだが、そのためか、何十年前の古い友人となると、その消息を掴むのは難しい。70年前の友人の詳細をここまで辿れるのは、私の場合は、稲見君一人だけである。
新千歳小学校の2年生になった昭和13年(1938年)には、日中戦争がますます激化していた。前年の暮れには、南京陥落の祝賀行事が日本全国で盛大に行われていたが、その裏では日本軍による住民大虐殺があったことなどは、知る由もなかった。虐殺された中国人の数は、一説には30万人ともいわれるが、この蛮行は、中国民衆の反日感情を一層高める結果になった。中国軍はその後も頑強に抵抗を続けて、日中戦争は長期化の様相を見せ始めていたのである。
国内では4月に国家総動員法が公布され、そのあと、物資統制令も施行されて、戦時色が強まっていった。灯火管制や防空訓練も行なわれるようになった。小学校でも、作文の時間には、戦地の軍人のための慰問袋に入れる手紙をよく書かされるようになった。そんな折に私たちが書いた、或いは書かされたのは、ここに記すのは憚れるような中国人罵倒のことばである。社会の風潮が大人たちの中国蔑視を強め、それが何も知らない子ども達にも歪んだ影を落としていた。
しかし、日中戦争というのは、子供たちにとっては、あくまでも遠い外国での戦争であった。私たちは社会が窮屈さを増していく中で、そんなことにはあまり影響されずに、元気に遊びまわった。特に私にとっては、学校くらい面白いところはなかった。授業の間だけは神妙におとなしくしていても、休み時間になると教室を飛び出し、クラスの子供たちと思う存分遊びまわれる楽しみを満喫していた。日曜日に学校が休みなのが気に入らなかった。家のまわりでは、男の子たちの中で私が一番チビであったから、遊び相手が限られる。日曜日でも学校があればいいのにと、よく思っていた。
私は体が丈夫で、走るのもクラスで一番速かった。相撲も得意であった。夏休みになると、町内会では子供たちの相撲大会を開催していたが、私は何回か、5人抜きの賞をもらっている。相手が同じ2年生なら、問題なく勝てる。相手が3年生でも勝つほうが多かった。私はいまでも相撲で勝つ時の感覚を覚えているが、相手とがっぷり四つに組んだら、もうそれで、「勝てた」と思う。四つに組んだあと、両手でぐいと相手を引き寄せ、腰投げで投げるのである。
ずっと後になって、戦後の東京で日比谷高校(その当時はまだ、東京都立第一高等学校といっていた)の2年生のとき、体操の時間に相撲の勝ち抜き競争をやらされたことがあった。クラスを半分に分けて、砂場の両側に対峙する。背の低いほうから順番に一人ずつ出て、勝ったほうは残り負けたほうは入れ替わる。私は12人を勝ち抜く記録を作った。それも、13人目で負けたのではない。相手がいなくなってしまったのである。
これは、私が強かったからというより、相手側がみんな弱すぎたからであったかもしれない。全国から集まってきて秀才といわれた生徒たちも、相撲のような体力の勝負では勝手がちがったのであろう。この相撲だけではなく、何事でも、勝つと思ってやれば勝つ。私はいまだにそう考えるくせがあるが、これは、子どもの頃の相撲の経験から来ているように思う。ともあれ、新千歳小学校時代の私は、走っても勝ち、跳んでも勝ち、鉄棒の懸垂の回数でも、群を抜いて勝っていた。頑健な体に恵まれ、私は疲れを知らずに、学校でも、学校から帰ってからも、歩きまわり走りまわっていた。
それでも、水泳はまだできなかった。5歳の頃に溺れかかった経験はあっても、水は嫌いであったわけではない。私は、近くの銭湯へ行くたびに、人のいないときを見計らって、比較的大きかった湯船の端から端まで、顔を湯につけたまま泳いでみたり、もぐったりした。それを、往復で繰り返したりして、私は、顔をつけたままなら、10メートルは進めることを確信するようになっていた。水泳を練習したかったが、近くにはプールはなかった。しかし、その代わりに絶好の泳ぎ場があった。大阪湾の海である。
家主のカズちゃんの家は、大阪湾に停泊する汽船に、水を供給する仕事をしていた。家の前の尻無川には、カズちゃんの家の水船とよばれる500トンくらいの舟が常に係留されている。電話で注文を受ければ、カズちゃんのお父さんが、この水船で出動するのである。夏の暑い日などには、近所の数人の年上の子供たちと、私もよく、この水船に乗り込んだ。
カズちゃんのお父さんは、赤ら顔で、漁師のような感じの無口な人であった。近所の子供たちが、何人船に乗っても、まったく気にもかけていないふうであった。黙って船を出し、黙って仕事をして、黙って帰ってくる。船の上ではしゃいでいる子供たちにも、ほとんど声をかけることはなかった。水船には、船の周りの柵や手すりのようなものはない。大きな四角の水のタンクが海に浮かんでいるようなもので、甲板の四辺は、いきなり海に落ち込んでいる。子供たちにとっては、決して安全ではなかった。
その水船は、尻無川の河口から海へ出て、やがて大きな汽船に近づき、横付けになる。太いホースが汽船の水槽の受け容れ口に接続され、給水が始まると、それからが、子供たちの天国であった。少なくともその時の私にはそう思われた。汽船に接舷している水船の反対側には、ひろびろとした青い水が遠くまで広がっている。銭湯の湯船とはわけが違うのである。波も立っていて、風も吹いている本物の海であった。甲板の上から、その海へ子供たちはつぎつぎに跳びこんでいく。最年少でまだ泳ぎのできない私も、臆せずに跳びこんでいた。足からどぼんと落ちていくのは、少しも怖くはなかった。
ただ、顔を水につけたままで泳げる距離は10メートルである。10メートル進んだら、顔を上げて息をしなければならない。そこで、何も手に掴めるものがなければ、息を吸った後、もう一度、顔をつけてまた10メートルを泳ぐ。だから、水船からあまり離れないで泳ぐことになるのだが、それでも私はあまり、不自由を感じなかった。カズちゃんのお父さんも、私が、十分に泳げるものと思っていたのかもしれない。
1時間ほども夢中で「泳いで」いる間に、水船は水道水をどんどん吐き出していって、高く浮き上がっていく。甲板から垂らしたロープを伝って上へ昇るのが、ちょっと面倒であった記憶がある。おそらく、いまなら、こんな「危ない遊び」を許さない親は多いだろうし、柵も手すりもない甲板のうえで子供たちを遊ばせてくれるカズちゃんのお父さんのような人もいないであろう。どちらがいいか、と問うのは難しい。ただ一ついえることは、このような思い出をもてたことは、私にとっては大変な贅沢であり、しあわせであった。
昭和14年(1939年)に入ると、戦時体制の引き締めがさらに強くなり、2月には、国民精神総動員強化策として、金属回収や隣組制度の強化などが行なわれるようになった。鉄製のポスト、ベンチ、街灯、広告塔などは、撤去回収され、家庭でも、火鉢、灰皿などの鉄製品はすべて供出させられた。作家の永井荷風は、持ち物の煙管の口金の金までとりあげられそうになり、6月30日に、浅草へのみちすがら吾妻橋の上から、川へ投げ捨てた、などと、『断腸亭日乗』に記している。4月には、米穀配給統制法なども公布され、米も自由には買えないようになる日が近づいていた。そして、9月1日、ヨーロッパでは、ドイツが遂にポーランド侵攻を開始した。第二次世界大戦の始まりであった。
この年の冬、新千歳町の我が家では、大きな出来事があった。私の姉の玉枝が、夜中に高熱を出したのである。父は、医学的知識に明るかった。尋常ではないと判断して、大正区では比較的大きな境川病院へ入院させた。しかし、三日たっても四日たっても、熱は下がらなかった。五日目に父は、院長に会い、退院させると伝えた。院長は正気ではないと怒った。しかし父は、頑として怯まなかった。病院はあんたのものだが、これは私の娘だ、と言ったそうである。母と二人で姉を抱きかかえて、タクシーに乗せ、大阪赤十字病院へ向かった。
赤十字病院では、姉を診察のあと、すぐに手術室へ入れて手術を始めた。眉の上に小さな穴を明け、頭蓋骨内部にたまっていた膿を取り出した。手術がもう一日遅れていれば、完全に手遅れであったらしい。姉の玉枝は、1か月ほどの入院で、無事に退院することができた。その2年前の秋江の場合のように、玉枝はこうして、父のお陰で命を取り留めたのである。
玉枝は、私より2歳上だが、小さい頃から聡明で性格が明るく、家のまわりのみんなからも好かれていた。その頃、病弱で寝込んでいることの多かった母に代わって、ほとんどの家事を、まだ子どもの玉枝がこなしていた。父もこの玉枝を頼りにしていたようである。私は時折、もし玉枝が男として生まれていたら、私に代わってもっとまともな大学教授になっていたのではないか、と思うことがある。そして、おそらく私は、後になって展開される父の事業の後を継がされていた。しかし、天は、玉枝に平安な生涯を与えなかった。長じて資産家の息子に見初められて結婚したが、彼は商才はあっても他人に対する愛に欠けていた。姉は不幸な日々を健気に生き抜き、60歳で亡くなった。再生不良性貧血が病名であった。
私は、姉の玉枝のようにこころ優しく、勝れた素質を持った人間が、なぜ不幸な生涯を送らねばならなかったのか、と長い間、思い続けてきた。しかし、いまでは分かるような気がするのだが、姉は、多分、この世では、そのような逆境に生きることを学ぶために生まれてきたのである。私と同じように、同じ父と母を選び、この世に生きて学ぶべきことを学び、そして、いまはまた、天性の明るさで輝きながら、霊界で安らかに暮らしているはずである。あの昭和14年の冬に、11歳の玉枝が生き残ったのも、生まれる前から計画していた逆境の学びが、まだ終わっていなかったからであったに違いない。
(2011.01.01)

大阪の尻無川のほとりで (身辺雑記73)
= 生かされてきた私のいのち (3) =
私は学校が好きであった。というよりも、好奇心がいっぱいで、子どもが大勢集まる学校というところへ早く行ってみたくて仕方がなかった。私の誕生日は4月20日で、「遅生まれ」である。21日早く生まれていれば、一年早く学校へ行けるのに、と駄々をこねたこともあったらしい。勉強したいという意識があったわけではない。ただ、面白く遊べるところ、と勝手に思い込んでいた。当時はまだ、幼稚園のようなものはその周辺にはなかったから、初めての、集団の遊び場と考えていた学校へ行けるようになる日が、ひたすらに待ち遠しかった。
近所の男の子の中では、私が一番小さかった。よく一緒に遊んだ家主の家のカズちゃんも、私より2歳年上である。ほかにも小学校5年から上の男の子が3人ほどいたが、彼らはみんな私から見るとオトナで、遊び相手ではなかった。私は長男だが、上には二人の姉がいた。下には妹二人とまだ赤ん坊であった弟がいたが、姉や妹たちと家で遊んだりした記憶はほとんどない。私は、朝ごはんが終わると、すぐ外へ飛び出し、昼になると食事にちょっと家へ帰って、あとは夕方まで、外で遊びまわっていた。
家から少し離れたたところに、大阪ペイントという会社があって、甚平渡しから川に背を向けて5分ほど歩くと、右側に敷地千坪ほどの会社の塀が見えてくる。その会社に隣接して、五百木さんという社長の大きな家があった。その社長の子が私たちがマーちゃんと呼んでいた、私より一歳上の五百木マコト君である。「マコト」がどういう漢字であったかは覚えていないが、苗字の「五百木」は、どうしてこれで「イオキ」と読むのだろうと、不思議に思ったりしたのでいまも忘れていない。
マーちゃんの家はお金持ちで、遊びに行くのにも少し敷居が高かったが、それでも、4,
5歳のころから私はかなり頻繁に遊びに行った。お目当ては絵本であった。当時は、「講談社の絵本」というのがあって、小さな子どもにとっては、ちょっと高価で贅沢な読み物であった。低学年用の『桃太郎』、『かぐや姫』、『かちかち山』、『牛若丸』といったものから、少しレベルが上の、『源為朝』、『木村重成』、『イソップ物語』、『ガリバー旅行記』、『ロビンソン漂流記』等々に至るまで、2,
3百冊くらいは出ていたであろうか。それがマーちゃんの家では、ほかの多くの本に混じって百冊以上も揃っていたように思う。わが家にも少しは本があったが、マーちゃんの家の蔵書の比ではなかった。
私は、マーちゃんが学校へ行くようになってからは、帰る頃を見計らって遊びにいったのだが、マーちゃんはいつも快く迎えてくれた。色白の内気な子で、遊び友達もほかにはあまりいなかったように思う。私はマーちゃんと二人で、たいていはおとなしく本を読んでいた。私は字を読むのを何処でどのように覚えたのかよく思い出せないのだが、学校へ行く前から、「講談社の絵本」はほとんど読むことができた。それから、たいていの道路の看板や、家々の表札の漢字などもなんとか読むことができた。もしかしたら、このマーちゃんの家が、私の最初の「学校」であったのかもしれない。
そのマーちゃんも近くのカズちゃんも、学校へ行ってしまっている間は、私は一人で動き回っていた。甚平渡しから「関東炊き屋さん」の前を通り、川に対してT字型に伸びている砂利道は、大阪ペイントの会社がある辺りまできて、そこから左右に分かれ、左へ折れた道は、北恩加島町(きたおかじまちょう)の商店街へ通じている。川からその辺までの道の左側は、広大な野原になっていて、遊び場所には事欠かなかった。私たちが「相撲取り草」と呼んでいた雑草などが一面に生え、至るところでバッタやコオロギが跳ねている。時には、子どもたちの戦争ごっこの格好の舞台にもなった。尻無川とその前面のこの広大な野原も、多くのいい思い出を与えられたという意味で、私にとっては学校の一部で、校庭のようなものであった。
私は、甚兵衛渡しの待合室へもよく行った。この待合室は、6畳ほどの木造の小屋で、壁際にはコの字型に木のベンチが据付けられている。小屋の真ん中には大きい四角の火鉢があって、その周りにも、パイプ椅子のようなものがいくつか置いてあったように思う。なかに座って渡し船が出るのを待っているのは、朝夕の通勤時間を除いては、多くても5,
6人くらいで、私が片隅に腰掛けていても、あまり邪魔にはならない。私は、ここでも、いろいろな大人たちのいろいろな世間話に聞き入ったりして、あまり退屈することはなかった。大人たちは、幼児の私のそばで、時にはきわどい大人の話をする。そばに小さい子が一人いても、どうせ分からないと思っているふうであった。
渡し船は無料で、2, 30分おきくらいの間隔で出る。その時間になると、いつも私は一緒に乗り込んだ。交替で船を操縦する二人のおじさんたちとは、すっかり顔なじみになっているので、私はいつも、船前方の操舵室のおじさんの隣に座らせてもらっていた。操縦は、前進のギヤを入れて、スクリューの回転を上げるアクセルを踏む。あとはハンドルを右左に切っていくだけである。これならボクにもできる、と私は思っていた。往復のたびごとに、あまりに熱心に私がおじさん達の操縦ぶりを見ているので、ある日、おじさん達の一人が、「運転してみたいのか?」と訊いた。私は大きく頭を縦に振って、「ウン」と答えた。
小学校へも上がっていない子供に、お客を乗せた渡し船の操縦を任せるというのは、今では、およそ考えられない無謀行為である。操縦しているおじさんは大阪市の職員だから、そんなことをしたら、地方公務員法違反、操縦規則違反、任務怠慢、人命軽視等々の「罪状」が、すぐにでも挙げられることになる。でもおじさんは私に操縦させてくれた。それも、一度や二度ではなかった。三度や四度でもない。私は、全力を尽くして操縦に努め、その技量(?)が認められて、その後も長い間、出発から着船まで、何十回も渡し船を操縦させてもらっていた。
ある強い風の吹く日の昼下がり、私はたまたまその日も、渡し船のハンドルを握っていた。川幅の中ほどを過ぎると、そろそろ速度を落として、着船に備えなければならない。対岸の船着場の近くまで来ると、ギヤを逆にいれ、スクリューを逆回転させて減速しながらハンドルを右に切って左舷からゆっくりと船着場に着船する。それが普通なのだが、その日は、風が強すぎた。ハンドルを右に切っても、風に流されて十分に船が廻りきれないところで、船の舳先が船着場のゴムタイヤのクッションにぶつかったのである。
停船寸前だったから、ドシンと振動が起こっただけで被害はなかったが、渡し船のおじさんは、さすがに慌てて、それ以後は私に操縦させてくれることはなかった。しかし私は、そのおじさんにはいまも感謝している。私にとっては、「古きよき時代」の貴重な経験であった。その二十数年後に私は、アメリカのオレゴン州の空を、小型自家用飛行機で20分ほど無免許操縦させてもらったことがあったが、この二つの無免許運転は、私がいまも密かに懐かしむ「法規違反」である。
昭和12年の春、私は待ち焦がれていた小学校へ入った。北恩加島小学校で、家からは甚兵衛渡しの前の道をマーちゃんの家の前を通り、北恩加島町の商店街を通り抜けて、子どもの足で30分近くかかる。新しい教科書の匂いやランドセルの皮の匂いが新鮮でうれしく、別世界に入り込んだような気がしていた。教室では先生の話を熱心に聞いていたが、しかし、勉強したという記憶はあまりない。「サイタ、サイタ、サクラガサイタ」で始まる小学読本は、私には幼稚すぎたが、しかし、退屈した記憶もない。それよりも、新しい環境で、急に遊び友達もふえ、行動範囲も広がって、毎日が夢のように楽しかった。
この一年生の時の級友のなかでは、ひとりだけ、永井君という名前を覚えている。北恩加島小学校の正門の前には文房具屋さんがあったが、その右隣の何軒目かが永井君の家で、一度、2,
3人の級友とその家へ遊びにいったことがある。永井君にはそのとき3年生であった兄さんがいて、秀才であったらしい。部屋の壁に永井君の兄さんの名前の入った大きな表彰状の額がかけてあって、永井君のお母さんはそれが自慢であったようである。毎年、区内の各小学校を代表して学年で一人、学業優秀なものに大正区の教育会長から贈られるもので、賞状のほかに「表彰」と刻まれた銀のメダルもついてくる。永井君のお母さんは、「あんたたちもこんな賞状をもらうようになりなさいよ」と、チビッ子の私たちを激励した。
勉強ができるとか、できないとか、そんなことはその頃の私には全く関心外であった。学業成績というものがあるらしいと知ったのもそのときが初めてである。永井君の名前を覚えているのも、多分、この彼の兄さんの表彰状とお母さんのことばのせいであろう。その二年後、その時には私たち新千歳町に住所があるものは新設の新千歳小学校へ移っていたが、そこでその表彰状は、思いがけなく、天からでも降ってきたもののように、私にも与えられた。父は喜び、母は感動していたが、この頃から、いやおうなく、私にも、勉強とか成績とか競争とかの意識が芽生え始めていったように思う。
一年生の頃の私には家で机に向かって勉強したという記憶は全くない。勉強は学校にいる間だけするものだと思っていた。勉強より私には好きなことがあった。工作である。木刀、舟、ゴム鉄砲などなど、私は多くの木製玩具を自分で作っていた。父の会社の裏側には、大阪湾の海水が打ち寄せている一角があって、そこへいくと、夥しい数の木片、瓶、缶などが漂流ごみに混じって打ち上げられている。どういうものか、輪ゴムなどもいくらでもほしいだけ見つけることが出来た。私にとっては宝の山のようなもので、私はしばしばそこへ行っては、必要な木片を物色し、輪ゴムなども拾って、工作材料にしていた。何日もかけて20〜30センチくらいのボートをいろいろと作り、スクリューだけは買ってきて、ゴム動力で動くように取り付ける。それらを近くの水溜りへ持って行って、水の上を走らせる。そのような遊びに夢中になったりしていた。
工作は、だから、好きであり、得意であった。北恩加島小学校の一年生の夏休みに、初めて工作の宿題が出されて、私は一生懸命に木製の引き出しつきの本立てを作った。サンド・ペーパーで磨き上げて、市販のものに比べても見劣りしない出来栄えだと自分では思っていたが、秋の学内展覧会でそれは展示されなかった。二、三の展示された級友たちの作品が、私の目から見ても稚拙な出来上がりで、なぜこんなものが、と不思議であったが、私はまだ、そんなことで不平の感情をもつことは知らなかった。小さな子どもでも、好きで一生懸命に作れば、大人にも劣らない作品ができあがることもあることを、おそらく、その時の担任の先生は知らなかったのであろう。
多分その頃、私が夏休み後の2学期で、また楽しく学校へ通っていたある日に、我が家では、大変な事故が起こった。二つ年下の妹の秋江が、家の路地から出たところの道端で近くの女の子たちと遊んでいた時、たまたま、そこへやってきたタクシーがUターンするために後退してきて、妹を左の後輪で轢いてしまったのである。妹は左の側頭部に深い傷を負って、ほとんど即死に近い状態で倒れていたらしい。タクシーの運転手は、その様子を見て怖くなったのであろうか、そのまま走り去ってしまった。滅多に起こることのない大事故がすぐそばで起こって、近所の人たちも総出で、大騒ぎになったようである。
私はそのとき、まだ学校から帰っていなかった。後で聞いた話によると、知らせ受けた父が急いで会社から帰ってきて、とりあえず一人で、毛布にくるんだ秋江を抱いたまま電車道のほうへ走っていこうとしたらしい。その時、事故の現場でたまたま道路を測量していた測量士が、轢いたまま走り去ったタクシーのナンバーをメモして父に渡してくれていた。電車道は、尻無川に並行して走っている大通りで、走って行っても15分はかかる。しかし、そこまで行かなければ病院へ行くためのタクシーは拾えなかった。救急車などはまだない時代で、家主の伊藤さんの電話を使って、タクシーを呼ぶというようなことも、その頃はまだできなかった。
やっと電車道まで出て見つけたタクシーで、父は大阪大学の付属病院へ向かった。瀕死の重傷を負って意識も失っている小さな体を抱きしめながら、父はさぞ辛い思いであったにちがいない。一生懸命に祈り続けるほかはなかったであろう。その父が、ふと、運転席の上に掲げられた車のナンバーを見ると、なんと、そのナンバーは、つい先ほど測量士から渡されたメモのナンバーと一致していたのである。一度は事故現場から走り去ったものの、それとなく様子をみようとして、また現場付近へ引き返そうとしていたのかもしれない。それにしても、自分が轢いた子を客にして乗せるとは、どのような天の配剤であろうか。父は、運転手に「あんたがこの子を轢いたのか」と訊いた。運転手は、ただ、「すんまへん」と謝るばかりであったらしい。
付属病院に着いた父は、すぐに秋江を外科医に診てもらったが、外科医は、黙って首を横に振ったという。傷が深すぎて、手術は無理である。手術したとしてもおそらく一日ももたないだろうから、そのままにしておいたほうがよい、というようなことであったらしい。しかし父は、断固として手術をお願いした。こういうときの父は、執念の鬼のようになるのを私は知っている。この父の執念によって、その後、私のすぐ上の姉の玉枝も私自身も、奇跡的にいのちを救われることになるのである。
秋江がすぐに手術室へ入れられた後、父からの伊藤さんの家の呼び出し電話で連絡を受け、母と姉の一人が病院へ向かった。私が病院へ一人で向かったのは、その翌朝である。家では、もう一人の姉が、秋江の下の妹と弟の面倒をみながら留守番をしていた。付属病院の病室では、前日に手術を終えた秋江が、頭をぐるぐる包帯で巻かれて、昏々と眠っている。枕元には、悲痛な顔つきの父と、もともと胃が弱くて寝込むことの多かった母が、青白い顔をして、涙を流していた。寝台の足もとには、秋江の晴れ着も用意されていた。担当医から、一日ももたないだろうと言われていたので、その時には着せ替えるためのものであった。
一日はなんとか持ちこたえた。二日目もなんとか無事に過ぎた。三日目になると、もしかしたら乗り越えられるかもしれないと、みんなが希望を持ち始めた。4日が過ぎ、5日が過ぎてついに一週間を越え、さらに二週間を生き延びた。幼い秋江のいのちは途切れることなく続き、徐々に、少しずつ、少しずつ、回復の道を辿り始めた。
(2010.11.01)

霊界で潔典はどのように生きているか (身辺雑記72)
あの大韓航空機事件が起こったのは、1983年9月1日の早朝でした。今日は、そのKAL
007便でアメリカから帰国途中であった長男の潔典が、母親と共に霊界へ移った日で、二人の27回目の「命日」にあたります。私にとって、かつては慟哭と悲嘆の日であったこの9月1日も、長い年月を経て、いまでは、こころ穏やかな感謝の気持ちで迎えられるようになりました。深い悲しみと絶望があったとはいえ、結局はこの事件を契機にして、人のいのちは永遠で、一分一厘の狂いもない大宇宙の摂理の中で生かされているという真理を、身に染みて知ることができるようになったことは、大きな安らぎであり、幸せであると思っています。
潔典は、事件当時は、東京外国語大学英米語学科の2年生でした。言語学の勉強に強い情熱を持ち、好きな音楽やスポーツにも全力で打ち込んでいた彼にとっては、大学生活は夢のように楽しい日々であったようです。成績もすべて優で、多くのよき師、よき友にも恵まれてしあわせでした。その頃から親しかった学友のうち4名の方々が、毎年、欠かさず、いまでも、この時期には花束をもって我が家を訪れてくださっています。社会的にそれぞれ重要な立場で立派に活躍しておられる方々に、これまでも、霊界にいわば「留学」している潔典の消息をお伝えしてきましたが、今年は、その「留学先」での潔典の最近の成長ぶりをまとめて、この4人の学友の方々にも、みていただくことにしました。
私が無明の深い闇のなかからどうにか抜け出すことが出来るようになったのは、先日、8月22日に亡くなられたイギリス人の優れた霊能者アン・ターナーのお陰でした。1年間のロンドン滞在を終え、1992年の春に帰国してからも、私は、アン・ターナーを通じて、定期的に、霊界にいる富子と潔典に手紙を送り、返事をもらっていました。そしてそれと同時に、東京でも、別のルートで、霊界通信を毎年のように繰り返してきました。18年に及ぶその通信記録は、相当な量に達しています。その一部は、このホームページの「霊界からのメッセージ」にも収録してきました。
その数多くの霊界通信から取捨選択するのは、あまり容易ではありませんが、ここでは、東京ルートの1996年以降の潔典の霊界での消息を中心に、その10回分だけを経年順に取り上げてまとめてみることにしました。霊界での潔典は、初めの頃は少し不安定なところもありましたが、この頃からは、落ち着きを取り戻し、また、好きな言語学や音楽などの勉強に、熱心に取り組んでいくようになったようです。
これらの通信内容は、霊能者が語っているのをテープに吹き込んだもので、そのまま文章に直しますと、一人称と三人称が混在したりして、当然少しはぎこちないところもでてきます。しかし、読み易いように修正を加えることはできませんので、一字一句、語り伝えられたとおりに転載してあります。ただ、全体を少しでも短くするために、いくつかのパラグラフは、私の独断でカットしました。カッコ内の日付は、その通信が行なわれた日を表しています。
私は冒頭で、「人のいのちは永遠で、一分一厘の狂いもない大宇宙の摂理のなかで生かされている」と、書きました。この富子と潔典の記念の日「9月1日」に、以下の「通信文」が、これからお会いする
4人の学友の方々をはじめ、富子と潔典を直接あるいは間接に知る多くの方々にも、この真理のことばを受け止めていただく一つの小さなきっかけになってくれれば、とこころから念じています。また、世間の常識では、あり得ないと思われているこのような通信文を、私が敢えてまとめて、多くの方々に読んでいただこうとすることの意味も、あるいはご理解いただけるかもしれないと、ひそかに、ささやかな期待をも持ち続けています。
* * * * *
[通信文]
1. 霊界でも熱心に学び続ける (1996. 06. 03.)
(しばらく同調します。)(いま捜しています。)以前とは違う領域に行っています。非常に繊細な魂の持ち主です。今の彼の状態は悪いようには感ぜられません。まずは安心してください。彼の魂を探索中ですが、悪いものは伝わってきていません。何かひとりで黙々と取り組んでいます。まわりにはあまり、ほかの存在たちはいません。少し離れたところには、ほかの存在たちもいます。彼の間近にはあまりほかの存在はうかがえません。彼自身は何かに向かって一生懸命に取り組んでいる最中です。勉強しているような感じです。何かに一生懸命に向かって取り組んでいるということで、一見するとキャンバスに向かって絵を描いているという格好です。あるいは、机に向かって何か本を読んだり書き物をしている・・・そういうふうにも捉えられます。
一生懸命学んでいる最中なのでしょう。生前、学んでいたことの残りをいまこちらに来て、つまり霊界に来ても、続けようという意気ごみです。何か地上にいたときの続きのようです。しかし、つらいようではなく、とにかく一生懸命に学んでいる最中というところです。あまりまわりの動きには気づいていません。多少切迫した感じは受けるのですが、悲痛な感じはしません。苦しそうでもありません。ただ単純に、一生懸命励んでいるというのが伝わってきています。
自分の学びで精一杯というところです。その意味ではまわりは見えていません。まわりを見ようともしません。もっともこのようなあり方は、こちらの霊界では別段不思議なことではなく、珍しいことではないのです。よくこのように一生懸命、生前の中断したことにこちらに来ても励んで、没頭している魂は幾体も見うけられるのです。学びの領域に彼はいます。学んでいる内容は、語学のようでもあり、また絵を描いているようでもある。あるいは、歴史とか文化を学んでいるのでしょうか。どうやら、学びの対象は一種類ではなさそうです。いろいろ一生懸命に学んだりおさらいしたりして、励んでいます。
活気が伝わってきます。とにかく一生懸命、無我夢中というふうです。それであまりほかに関心や意識が向いていません。家族の人達に対しても、あまり意識は向いていません。自分の学びの中断したことに対しての多少の焦りから、懸命に自分のやり残している学習に取り組んでいるところだからです。それでも、彼の母親が見守ってくれています。もちろんあなたの奥様です。守護霊のように彼を見守っています。あたたかい慈愛のこころで包んでくれています。それがためか、安心して励んでいられるのでしょう。
それで、彼の前方上方部に彼の母親の生きた波動や、そのこころがうかがえます。こちらに来ても母親としての自覚が強いのです。そして、息子の地上での中座してしまった学習の残りの部分を成し遂げさせようと見守っている最中です。それで安心して、あなたの息子さんのほうもその下で励んでいるという、そんな状況です。
あなたの奥様のほうは、大きくひろがった意識で、とらわれもさほどありません。息子さんのほうは相変わらず若々しく、生前のころの20代前半のような若さや活力をいまだに保持しています。34才とかという感じではありません。むしろ、20代前半、22
〜3歳というくらいの年齢を感じさせます。それだけ、引き継いで、生前のやり残した学習を完成させようと無我夢中なのです。
ただそれでも念頭に、父親であるあなたのことは、想っています。忘れたわけではありません。念頭にはあなたのことがあり、支えになっています。それで、彼の中での位置付けとしては、自分の前、前方上方に守護霊的に慈しみの母親がいて、翼の蔭で彼が黙々として学んでいるということ、そして、彼の脳裏にはあなたのことがあり、彼の頭上、後方部にあなたがいるという、そういった位置付け、あるいは関係としてとらえられます。彼にとっての父親と母親の、彼の中での位置付けです。
あなたのことはとても慕い、尊敬し、信頼しています。それで、父親であるあなた自身がこの地上で残されて大丈夫なのかな、とか、そういったふうに案じているふうには見えません。なぜならあなたのことを信頼しきっており、尊敬しているので、地上に残されていてあなたが大丈夫なのかな、などと息子の立場として案じるということはありそうもないことだからです。むしろ自分が、父親からどう見られているか、あなたが霊界に来られたときに自分がどうなのか、というふうに意識が向いているということです。
よほど生前、父親であるあなたからの期待や愛を感じていたのでしょう。とても真面目な子です。あまり早くあなたがこちらに来られると困る、と言っています。いずれ会うことになるでしょう。
2. 新しい環境のなかで (1997.06.04.)
十数年も経ちますと、あの世での過ごし方も分かってくるものです。最初は戸惑いがちでした。戸惑いながらのスタートとなったのです。みな大体、あの世に行くとそのようなのです。私の場合も、暗中模索といったところからのスタートとなったのです。最近ではよく分かってきました。みんなが助けてくれるものだし、自分でもいろんな事情に少しずつですが精通し、迷いや苦悶も消えてきました。自分ではまだまだだと感じているのですが、結構こちらの世界では、スムーズに次の境界へ進んでいけそうだというのです。そういった話を聞くにつれ、自分でも少しづつですが自信がついてきました。
こちらでは、家族同士よりも同類のもの同土が、寄り集っています。もちろん同類のなかには、かつて家族や同族の親類であった者たちも含まれてはいます。けれども基本的な単位としては、家族としてよりも似た者同士として、寄り集っているのです。私は比較的早く、地上界から離れることができました。純粋さを保つようにという要請からです。何よりもそのことで自分の家族、お父さんや兄弟たちを精神的な世界へと導くようにという要請が強く出てきたことに基づくのです。私のように早くに取り去られる者の場合、親がかなり精神的に成長が遂げられるということが狙いとして強いものなのです。私は世にいた間のお母さんとは、いまは少しばかり離れ離れになりかかっています。それでも、時々は落ち合うことが出来、淋しくはなく、また不自由もしていません。
私は、心配する気持ちや不安はいまはあまりなく、だんだんひとつの団体に向かい始めています。世を離れてから、冥界でオリエンテーションのような期間を数年過ごし、今は正式な霊界に向かって進んでいます。完全に子供のとき他界した者と大人が普通に他界した者の場合とのちょうど中間に位置していたため、こちらの世界では私の扱いには最初困った様子でした。過渡的な状態だったからです。大人扱いか子供扱いか、だいぶん霊界の住民たちも思案にくれていた様子でした。私は、純粋だというふうに認められ、子供の中に入れられることになったのです。それだけ特典もあって、大目に見られ、私は恵まれていたというふうに受け止められます。
しばらくは母がついてくれていて、私を守ってもくれまた慰めてもくれたものです。私がだんだん霊界のことを知るにつれ、また母親も一方いろんな学びが進んできたので、それぞれの道を歩もうということになってきたのはごく最近からのことです。それでもつながりはあるもので、先程お伝えしましたとおり、時々は会うことを許されており、いわば連携のようなものが図られているから安心して下さい。こちらの世界では、会おうと思えばすぐ思い浮かべただけで会えるものなのです。空間の隔たりというのはなく、強いてあるとするならそれは意識の隔たりだけなのです。遠いという場合、意識がお互いに疎遠だということなのです。近いという距離感は非常にこころが通いあって親密で抵抗がないということなのです。意識の実感がこちらの領域では物差しとなっています。
こちらの世界では意識の実感のようなものが、すべての尺度の基準になっているのです。特に最近はそのようなことを学んでいます。自分が早く変われば、時間がそれだけ早く経過したというふうに感じます。自分が完全に完成して本来の自分になりきれば、変化がなくなりまた変化も不要になります。それがどうやら時間を超えたということで、変化しない完成しきった、それが永遠のいのちということのようでした。そこに向けて、素直で素朴なこころをますます培うようにトレーニングを受けている最中です。そのためには正直で内面と外面を一致調和させるということが求められてきています。
地上でのことは、まだ少し気にはかかっております。愛着もまだ少しあるのです。しかし、自分が地上にいたときほどは心配ないことが分かってきています。まだ、思いは残っています。でも不安は嘘のように消えています。それはいろんな宇宙の秩序や仕組みが指導霊から説明されて、私も学び始めたことによります。私は進歩は早いほうのようで、苦しくはありません。比較的上位のレベルの霊界で修行に励んでおります。
4人の家族はお互いに、意識の深いところでつながりを今でも保っており、こころを通わすことができています。私のことやお母さんのことを思い浮かべれば私もそれに感応し、テレパシーで伝えることができるのです。それはやはりつながっていることに基づくのです。はっきりと声として聞こえなかったり、話した内容をはっきり捉えられない場合でも、何かニュアンスのようなもので感じられると思います。私のほうではもっとはっきり、お父さんたちのことは捉えられています。ほぼ、14年が経過しました。あとまた14年くらいで、こちらの世界で会えるかもしれません。その時は、私のほうが霊界では先輩ですので、いろいろとお役にたてると思います。お母さんも元気で頑張っているようです。
苦しんでいる者たちもこちらの世界では多いのですが、私たちは事故に見舞われたとはいえ、さほど苦しむことなく、一緒に飛行機ごとこちらの世界にまとめて移されました。あまりにもそれが急だったので、苦しむことなく移されました。もともとあまりお母さんも私も、執着はないほうですので、ふっきれるのも早いほうでした。それに比べて残されたお父さんたちのほうが苦しんでいます。この世にいてもあの世にいても、あまり違いはありません。いづれまた数年後に会えることになっています。時間はすぐ経ちます。神様によくお祈りして、お互いのこころをあたためあうことを望んでいます。
こちらの世界に来てからは私が先輩ですが、すぐお父さんに追い抜かれると思います。お父さんが生きている間に進歩を遂げて、善き業を日頃の生活の場で行ってくだされば、お父さんにこちらに来てから導いてほしいのです。そしたら家族共々、キリスト様のみ顔を仰ぎ見ることができ、魂が救われることが期待できるからです。職業としてばかりでなく、日頃ふだんの生活の中で隣人に何を為したかが大事だと、よくよく聞かされました。「もっとも小さき者に対して為したことは私に為したことである」と神はおっしゃられる方だからです。文句なくキリスト様を通して、神のことばが伝えられたのです。
ときどき私やお母さんのことを思い浮かべてくだされば、喜びこの上ありません。お互いのこころの通い合いの中で絆も保たれ、さらに深まるでしょう。
3. 人々の目覚めのために (1999. 06. 05.)
僕は死んですぐ、霊界に行きました。といっても、すぐに、正式の霊界へ赴けたわけではありません。まず、黄泉の国といって、中間段階を経て行ったのです。そこで待機させられていました。どのくらいだったかは定かではありません。ただ、随分と長かったのは、いまでも覚えています。
特に苦しんだことはありません。むしろ、肉体から解放されて、自由を感じることが出来ました。神様が居られるということを、あとでだんだんと、わからせられました。二人か三人の守護者達がついてくれていて、いろいろと教えてくれたりして、導いてくれているのです。最初はよく誰だかわかりませんでした。守護者たちのことです。でもなにか覚えているという感じは最初から自分のなかにはありました。なじみがあるような気がしたのです。けれど、誰だかはわかりませんでした。
肉体を離れてから自由を感じました。特に痛烈な打撃とか痛みは伴いませんでした。肉体から魂を分離させたときのことです。お母さんと僕とはとても縁が強く、一方、お父さんとお姉さんとは縁が強く、お互いに対照的に位置しています。お互いに向かい合っているような関係にあるのです。
あの世というのがあるのは、聞いていましたが、本当にあるということがわかり、安心できました。ひとつの扉を通っていくようなものです。ひとつの部屋といまひとつの部屋とがあります。二つの領域のことです。扉が間にはあります。そこからいまひとつの領域へ移行できるのです。あの世からこの世、この世からあの世、いずれの場合も同じです。ただこの世のほうが粗雑な世界で、重い感じがします。ちょうど鎧を身にまとって戦士として戦に赴くようなのがこの世です。それに対して、鎧を脱ぎ、家庭のなかで憩い安らぎ、自分の本心に帰れるのがあの世です。もちろん鎧というのは肉体の喩えです。そのぐらいあの世に来てみると、肉体の重たげなことがわかったのです。それ故、あの世に行って苦しんだり悲しむということはこの世にいる間想像していたほどのものはありません。最初は悲しかったり辛かったりというよりも、戸惑いを覚えました。この世に残っている人たちのほうが悲しむことがわかりました。
あの世であるここに来てから、あの世側からはあまり寂しくはありません。何故というに、この世のことが見通せて、死んでも生きていることがわかったし、引き離されたというわけでもなく、いまでも身近に居るからです。それで、引き裂かれたという気はしません。だから、寂しくはありません。肉体をまとっていると鈍くなるので、引き離された感じになり、寂しかったり悲しみます。あの世とこの世とで、ご縁のある四つの魂が二つの領域で、縁ある二組でペアーをなし、向き合って暮らし続けています。別の世界に行ったわけではありません。いまでも一緒です。ただ次元が違うだけです。
お母さんと僕とには、守護者がついてくれています。同様に、お父さんとお姉さんには僕たち二人が守護者です。守護者というのは、縁のある魂のなかで先輩格のことです。この世の年齢とは異なり、あの世や神様のことに精通している者たちが先輩ということになります。
お母さんと僕とはとても縁が強く、一対をなしています。同じように、お父さんとお姉さんとは対をなし、とても縁があります。それでこの二人同士は引き裂かれません。多少、この世やあの世の都合や事情によって、もう一人が結婚したり、多少、別に居をかまえたりなどしたりしても、完全な別れは体験しないように考慮されています。でも、二人と二人との間は、このように、別な次元に分けられました。あの世とこの世の二つの領域を股に掛けてバランスをとるようにということでした。また、お父さんを目覚めさせ、導くために高い霊が動かれ、このようなことを起こされました。
お父さんなら、頭も聡明で、苦しませるのは高い霊たちにとっても辛いことで、決断を要したということです。でも、必ず目覚めて立ち直る人だということがわかり、一人の苦しみが何百、何千人、いや何万人の人たちの魂を目覚めさせ、同様の苦しみや悲しみのなかで沈んでいる同胞に慰めと魂の癒しをもたらすことを、その聡明さによってやってくれるということが期待されたからです。僕は純粋だからということで、その純粋さを保持してほしいというので、早々と引き上げさせられました。あまり世俗の垢にまみれてほしくないということのようです。
お父さんは僕に、仕事や勉強など、とりわけ語学の面と国際文化の領域で跡を継ぎ、活躍してほしいと期待をかけてくれていました。でも守護霊たちがが、もっとあの世のことに精通するほうへと導いていき、たいそう大きな力が働き、このような具合に流れ上、なってきました。
お父さんと僕とは、前世において何度か、国際関係のなかで重要な役目を果たしてきた使命のパートナー同士でした。また、実際、肉の親子であったこともあり、たいそう可愛がってくれました。使命のパートナーであったときはいろいろと助言をしてくれ、教え導いたり守ってくれました。古代から近代にかけて、何度かお互い格別な関係を結び、特に国際関係において二つの国と国の間の調整役などを務めたり、学問の世界でも、言語学の分野でも、お互いに切磋琢磨しあいました。
いまの時代、それをまたやろうと思っていたのですが、切迫していることがあり、霊界にも異変があるなどして、大きなカルマや意向がはたらき、僕たち家族に大きな力が介入してきました。アトランティスの当時のカルマが動いて、もっと人類が魂のレベルで目覚めるように僕たち家族に働きかけだしたのです。特に僕たちが前世で罪を犯したとか、いけないことをしたから苦しまねばならないということではなかったのです。もっとほかの人たちが目覚めるため、私たち、僕たちみんな四人が捧げられ、皆の目覚めのために尽力するように求められたのです。自分の場合は、純潔を魂の領域で保つようにということで、新しい守護者になるよういま訓練をうけているところです。
4. 叙情的なこころの優しさ (2001. 06. 06.)
ちょうど昨日は、39回目の誕生日にあたっていました。この世での直前の前世の誕生日とか、あるいは命日とかいうのは、やはり生命のリズムにおけるひとつの印になっているのがわかります。それで日本でも昔から、そのようなときにお祭りとかそれに準ずることを執り行ってきているのです。あなたのリーディングということで、毎年ここに来られています。それは無意味なものではありません。今はちょうど周期の上で、ちょうど変わり目にさしかかってきているのがわかります。それは例えば、天候をみてもあらわれていますし、また、媒体となるものの体調にもあらわれたとおりです。いまはややあの世で不安定な状態にあるからです。でもいい方に向かいつつある節目なのです。むしろここのところ、落ち込んでいたということであり、ちょうどまた今日ぐらいから持ち直し、あの世で元気を徐々に盛り返していく感じがします。
もともと彼は、影響を受けやすいたちです。とても繊細で鋭敏な人です。確かにそのまま生きていれば、語学の方面で活躍できる人になれていました。前世でも語学とかあるいは文芸の方面で活躍していた魂なのです。彼の場合前世では、語学や文章の面で卓越していたのと、ほかには経済や金融の方面で一見識をもっていたときもありますし、また、なかなかアイデアの人であったときもあり、工学、技術の方面で才能を発揮したときもありました。また、趣味として、楽器を、おもに弦楽器でしたが、奏でて、そして声もとても美しくきれいで、歌うことも出来た人でした。叙情的な詩や文章も好み、自分でも綴ったことがあった人なのです。それで今あの世でも、かなり創作活動に燃えてきているところです。
非常に論理的で緻密な科学の頭脳と、同時に一方、叙情的なこころ優しい機微を感じさせる面とを併せ持った人であることがわかります。閃きがあるということでは直感型の人です。音楽と数学の才能、そして、文章と語学の才能が特に秀でています。そのようなきびきびした面をいま捉えています。ちょうど昨日から今日にかけてが、また一つの節目になってきており、この半年ぐらいはやや動揺して落ち込んでいましたが、ちょうど今ぐらいから、持ち直し始めてきているのがわかります。そのような意味では、このリーディングの働きかけが一つの浄化となり、彼自身また元気になってくるので、それが当然のことながらこの世のつながりが強い人たち、家族をはじめ魂の上でご縁のある人たちにも今後及んでくるに違いありません。
何れにせよ、今回のリーディングが一つのきっかけとなって浄化が起き、彼自身また、父親であったあなたの力をいただいて活発に動き出そうとしているところです。ある意味で、リーディングをする時点で繋がり、父親と息子との間でまたこころのエネルギーの交換が為されたということがわかります。それであなたの意志が彼のほうに及んで、また元気になってやる気が出ているのが見られます。そのへんのところは以心伝心がちゃんと働いています。相互に影響を及ぼしあうわけですが、父親と息子という関係の場合、お二人の場合ですが、おもにあなたから彼にという方向の働きかけの影響が主流です。あなたが彼のものを受信するというよりも、そのような関係性にあるのです。そのため、リーディングということで、いってみれば取り次ぎ役を任じられ、それが始まる頃にそっとあなたの思いが彼のほうに届いて、彼は大分元気になりました。
しかしその直前には、同調を始めると彼のものがまず媒体のほうに及んできました。しかしある程度、人間関係の心理といいますのは、こころの面といいますのは、相手に伝えると楽になるということがあるわけです。自分のものをうち明けたり、思ったことをぶつけたり、感情をあらわにしたり、などで、そうすると本人はそれで楽になります。それに対して受けとった側がそれを受けます。しかしそこで解消していくことが起きるということです。そのようなエネルギーの交換が今回かなり起きました。この6カ月ぐらいは彼はけっこう沈んで元気がなかったのです。しかしまたあなたの思いがこれを機に伝わって、張りきりだしています。また彼は別の前世では、園芸とか庭作りなどに興味を持っていたときがあり、なかなか純朴な魂の、素直な青年だったときもありました。
5. 指導者としての修行 (2003. 06. 05.)
大分凛々しく立派になってきました。霊界においてもちゃんと成長し、順調に神のもと、育成されてきているのがわかります。もちろん、この世における肉体の成長とか年齢のようなものではありません。それでも内面の実質としては、ちゃんと成長し続けていくのです。そのことが彼のことによっても、確認することが出来ます。
魂はもうすっかり癒され、全体として雄々しさ、たくましさが伝わってきます。頼もしい感じがします。威風堂々とした感じさえあります。しかし、あまり話しません。内なる自信と信頼に富みます。そのような落ち着きがあります。それで、ことばで伝えてこなくても、こちらを安心させてくれるのです。あまりまわりに人などの存在は感じられません。自立しています。霊界のなかでは比較的自由に各人が動ける境遇に位置しています。最近までは、生前のお母さんといっしょでしたが、いまではお互いの了承のもと、自由に行動するようになってきています。といっても、母と息子の関係が絶たれたわけではありません。いつでも会おうと思えばいまでも会えます。実際、ときどき会っています。不便なことはありません。すっと目の前に現れ、落ちあえます。
いづれ霊界で彼は指導者になることでしょう。指導霊のようなスピリットになる養成あるいは訓練を受け始めているところです。当面は生まれ変わらないでしょう。こころとこころとのコミュニケーションの指導に主に当たるようになるでしょう。正直言って、地上での肉体をまとった生活は向いていませんでした。地上でそのまま生きれば、それなりに大成し、活躍したことでしょう。でも彼には、それよりも霊界における任務のほうが適っています。彼はいま満足して微笑んでいます。ちょうど地上の朝に対応する時間帯が霊界でめぐってくると、光のほうに向かってひざまずき、手を合わせて礼拝しています。敬虔深さがあるのです。ちゃんと敬うべきところを敬い、立てるところは立てているのがわかります。それも指導者の条件のうちにあるのです。
生前、地上では四人家族の一員でした。ただ訳あって、二人ずつにさせられました。偶然ではなく、母と息子、一方、父親と娘、この二人ずつが特に繋がりが強かったことになります。四人家族として縁は強かったほうなのですが、とりわけこの二人ずつがもともと緊密でご縁が深かったので、そのようにおのずとなりました。その意味で、この二人ずつは一心同体であるのを感じさせてくれます。別にカルマがあってそのようになったのではありません。神の愛のもと、さらなる成長と浄化のために起きたことです。
地上に留められた父親であるあなたは、最近のヨーロッパの前世のとき、また遡れば、ギリシア・ローマ文明期の前世のときにも、霊界の存在や、人間の本質は霊であることを知っていながら、世間の体裁やポジションを考えて、自分の内なる信念と理解を控えました。カルマといえばそれがカルマです。しかし、いわゆるカルマそのものではありません。今生においても、それをあらためて確信する、つまり霊界があること、人間の本質は霊であることを再確認するとともに、それを自分の痛みと悲しみとを通して、実感しつつ成長を遂げ、そのことを救いを求めている方々に洗礼する、自分としては公言する、そのような行動にでることで、前世で控えたことにバランスを取らせるようなはからいが起きたのです。あなたはほぼそれを立派に、この20年間でやり遂げました。ほぼやり遂げたといえるでしょう。
さて、以上述べられたことは、一般論ではなく、これもまた、息子さんから伝えるようにと委託された内容なのです。このようなことをお父さんに伝えて欲しいとのことです。彼の思いと意向とを汲んで代わってお伝えしました。そのようなことまで配慮できる余裕が彼のなかには生じてきています。そもそも、霊界に帰っていった者よりも地上に留めおかれた者のほうが、辛さと悲しみが大きいものでした。そういうものです。霊界に早く帰っていった二人よりも、置き去りにされた二人のほうが、はるかに辛い思いを体験しました。それが霊界に早めに帰った息子さんが、いまのように元気でたくましく、頼もしささえ感じて立派に霊界で生きて存在していることの説明になっているはずです。別に、地上に残してきた家族の二人に対する思いが少ない、小さいからではなく、霊界に向かっていったというのは、前向きであり、先のことに向かって行動に移したことなのですから、あまり辛さや悲しみはなかったのです。
霊界は内面の世界です。この世では外側から、物事でも、人でも、自分自身のことでも見ます。しかし、霊界に来てみると、すべてはあべこべの世界に最初は思われます。内面がそのまま曝露されて、地上の作られたものは通用しない世界です。しかし、しばらくすると霊界のほうが正しく、地上は作られた世界、いわば虚偽の世界であることが判明してくるのです。建前は通用せず、本音や本性が露わになります。しかし、それに気づけば楽になり、その生き方が身につけばなかなか過ごしやすい領域です。彼はもともとそのような純朴で、素直で、正直なところがあり、つくる人ではなかったので、霊界向きでした。
6. 清冽な波動を放つ (2004. 06. 05.)
物静かで、静寂さが伝わってきています。落ち着いていてゆったりと過ごしています。まわりは平和で、静かなたたずまいです。時々ひとりで瞑想をしています。大分自信がでてきました。物腰は柔らかで、こころは安定し、自信に満ちあふれてきています。最近は活力に富み、後輩の指導にあたりはじめました。霊たちの指導にあたっています。あの世で教師としての認定を受け、一体一体が確信をもって歩むべき道をしっかりと歩み通すように指導にあたっています。
もう、この世にいたときのしがらみや他界していたときの不安定さからは完全に脱却しています。もともと早いほうだったのですが、いまはとても元気がよく、清冽な感じが伝わってきます。はきはきして清らかです。あの世で生命について、こころの持ち方について、また、創造性について、霊たちを指導しています。たいていは数十体を相手に、それらの存在として向き合って、てきぱきと指示をされています。なかなか神々しく、生き生きしています。てきぱきとして、はきはきして、活力に富むというのが、見た感じから伝わってくる印象です。
教えているとき以外は、ひとり退いて、静かに神といのちについて瞑想していたり、あるいは、自由自在に飛行し、飛び回っていたりします。時々は、この世にいたときの母親と落ち合って、必要最小限のやりとりを交わします。いつもいつもいっしょにいるわけではありません。高位の存在に彼は昇格しました。この世に生きていたときに世俗的なことに染まらなかったので、あの世に移ってからももたつかず、浄化のプロセスも比較的たやすく、すんなりと通過していきました。また、根が優しかったので、慈愛のこころがあの世で呼び覚まされました。いまはそのうえに、彼本来の賢さや活発さが表に現れてきて、感情と理性、愛と叡智が一体となって、彼の個性が生命として十分に発露されています。
霊たちを指導しているといっても、おしゃべりではありません。よけいなことはしゃべっていません。むしろ静かです。必要なことだけをてきぱきと手際よく、また歯切れよく、快活な感じに伝えています。生き生きして快活というのが印象的で、大きいのです。また、爽やかさも感じさせてくれます。霊界でも随分上の方にいます。芸術的な感性に富み、ことばの才能がみられます。しかし、ことばの一人歩きはしていません。しっかりと生命に根を下ろして、まごころから真実を伝えています。また、音楽の才能もみられます。歌とも詩とも捉えられる叙情的な香りを放ちながら、叡智をもって霊たちに働きかけています。
ちょっと見ると指揮者のようで、指揮棒を皆の前で振るって、交響楽団がそこにあるかのようです。そのような感じなのです。それによって、その場ばかりでなく、その周辺にも、やんわりと平和と静寂の波動が伝播していくのがみられます。そのような意味で、芸術家としての感性が十分に伝わってくるのです。たんに教えたり説教しているという感じではないのです。ハーモニーを造りだしています。それによって霊界に調和と均衡をもたらし、また、浄化する働きもしています。清らかな、あたたかい波動をまわりにもたらしています。たしかに指導霊の一体になったのですが、しかし、指導霊という感じではなく、むしろ、導きの天使という感じです。
生前のお父さんに対しては、感謝と喜びを伝えてきています。自分が十分にあの世で浄められ、癒され、さらには昇格して、この世に留まっていた以上のすばらしいお役を授かり、とてもよい働きをするようになれたからです。もともとこの世に生き続けていても、濁りに染まることはほとんどなかったことでしょう。ただたんに、年齢が若いうちにあの世に取り去られたからばかりではなく、生来のその特性からしても、この世にいたのであっても、あまり俗化して俗物になったことはなかったでしょう。なぜ早めに還ったかといいますと、この世は重く、汚れに満ちあふれており、彼が生き続けるには適していない場だったからです。
彼はとても繊細で、ただ、弱いという意味ではありません、むしろ、そのまま生き続けると、損なわれかねる、惜しいので取り去られました。もっと積極的な意味合いとしては、この世に留まって使命を遂行するよりも、あの世で、霊たちのためになれること、また、霊界全般に対してもよい働きかけが出来ることがわかったからです。あの世を通して、この世をもサポートできます。彼は、この世よりもあの世むきです。あの世でのほうが良さが保持され、また、その特質が遺憾なく発揮されます。この世には、適していません。それで、おのずと、一つの事故がきっかけになって、その通りのことが起きました。
彼はいまたいへん凛々しく、すっとした感じで、清冽な波動を放っています。凛々しくて、きりりとしています。日本でいえば菩薩です。そして表情は柔和で、慈愛の波動を、叡智を含む慈愛の波動をこの世にまで及ぼしています。寡黙です。多くは語りません。しかし、柔和で、あたたかく優しい波動がこちらにも及んできています。父親のあなたには、こころで有難く感じ、微笑んでいます。また、彼があの世で偉くなったといっても、謙虚で、生前の父親のあなたを、たいへん尊敬しています。感謝と尊敬が無言のうちに、波動として伝わってきています。十分感じ取ってください。
7. 堂々と自信にあふれて (2005.08.31.)
ほかの霊たちの前に立っています。そして、指導に当たっています。すでに霊界での生活にも慣れ、本来の彼の特性が生かされるように、尊く大切なお役をあてがわれて、その任につくようになりました。見たところ、はきはきして明るく、活発です。また、優しくて、他の霊たちを思いやり、ケア−もできています。
堂々として、確信と自信にも満ちあふれている様子です。明るくて軽快な波動をまわりに放っているため、他の霊たちにとって、それが慰めや目覚め、あるいは浄化の役に立っています。それぞれの霊が清められ慰められ態勢が整ってきたのを見計らって、それぞれ行き先を指し示し、そこへ向かうように促したり、激励もしています。あるいは、最終的なすべての霊に共通する究極のゴールであるいのちの本源を指差して、最終的にはあそこに行くんですよ、と教えたり、諭してもいます。
彼にはこの世、地上での物理的な生活は辛く、ふさわしくないものでした。苦労したり、世の汚れに染まっていったり、あるいは、あきらめて妥協したりするのは似つかわしくないことでした。そのため、純粋でよいものを保持したまま、世の汚れに染まったり、折り合いをつけたりするようになってしまう前に、引き上げさせられました。生前の名前のように、「潔」(きよ)らかな魂の持ち主です。また、生きるうえでの法則や宇宙の摂理などにも精通しています。生きる規範、あるいは、人生の規範などについて知恵が働きます。それも生前の名前に表れています。「典」(のり)というほうです。
いまあの世では、生きる規範やいのちの法則について、教え諭しているところです。特に他の霊たちの魂を癒したり慰めたり清めたりする上で、効力を発揮しています。とても爽やかで、癒したり浄化する作用があります。それとともに一人ひとりが自分に目覚めて、あの世で本当の霊になっていくことが出来ます。そのような役目を果たすようになり始めています。
また、時々はそれ以外の役目も、別の領域に行って果たすこともあります。迷子になったり道から外れかかっている霊に注意したり、教え諭したりです。また、ともに瞑想に入ったり、お祈りの仕方を教えたりもするときがあります。
生前の父親であるあなたとしては、この世に普通に留まって、主に語学の分野で出世街道を歩むことが願いでした。それも可能だったのですが、神様とその許に集っている守護霊たちの判断で、むしろ早くに引き上げさせ、彼を守り、あの世で清らかなまま、その任に当たらせたほうがよいという決定が下されたのです。カルマによるものではありません。多くの場合、事故死を遂げた者たちは、執着が残り、あの世に行って苦しんで、救われていません。しかし、彼の場合はほとんどそのような経過を経ることなく、すっと、よい霊界へ向かいました。しかし、当分は、守られ、あの世について教育されたり、いわば、使命のための研修期間を過ごしていたのです。
最初は、控えめで、おとなしくしていました。しかしここ最近は、自信が出て、積極的にその任に当たるようになって活躍しています。他の指導霊や天使たちとも連携をとって、それぞれの役目を果たしています。
もともと、この世での生まれ変わりが少なく、あまりこの世向きではない魂です。父親のあなたには生命の尊さや、人生において本当に大切なことについて、身をもって教え示すために、その長男として転生したのです。それは神の摂理に基づくことでした。もちろん、前世で縁があったからです。しかし、今世ではずっとこの世に留まって、跡取りのような人生を歩む計画ではありませんでした。むしろ、頑固なあなたに大事なことを伝えるために、その長男として出てきました。一番大事なこと、大切なものとは、いのちと愛です。そして、それこそが神なのです。そのことを身をもって示し、いのちは途絶えることなく永遠であるのと同様、愛も永遠で変わることがない、もっともこの宇宙で尊いものであることを、あなたに示そうとしたのです。それは、彼自身の願いであるとともに、彼を通して、もっと上位のご意思がそれをあなたになさりました。
彼はいま、朗らかで、心が晴れ晴れとして爽やかです。自分でも安心して、爽やかさが伝わってきています。あなたに対しては、「有難うございます。よく耐えてくださいました。もうじきお会いしましょう。こちらで待っています。他界する時期は自分でもわかるでしょう。僕も分かっていました。」そのようなことが伝わってきています。
「この世で寿命が与えられている限りは、この世でのいのちを大切にしてください。」
そのような思いも併せて伝えられてきています。彼はもう完全に苦境を抜け出て、悟りの心境に入っています。他の霊たちに対する思いやりに満ちています。それは、背後の神様のお心を体現しているからです。
8. 平和の大使として (2007.06.05.)
心が平静で、とても澄み切っています。まわりは平安に包まれています。「平和の大使」として霊界で認められるようになりました。少し前までは、活発に他の霊たちを必要に応じて指導したり育成していたのですが、最近は「平和の大使」として任じられたために、あまり活発な動きはせず、霊界に平安と安全をもたらすために自らも鎮まって、その存在の在りかたでまわりを支えたり、包むようになっています。
本来の在り様になり始めたのです。すなわち、もともとの彼の持つ属性なり特質にふさわしい在りかたとお役が与えられたということです。それはちょうど、仏陀が平安と寂静ともよばれる静寂の境地を体現し、地上にその波動をもたらしたことと似通っています。あるいは、主の前世の一つであられた平和の王子、メルキベデクが地上にもたらせた波動と似通っています。もちろんメルキベデクが最終的にイエスとよばれる人物として出てきた時に最大限にそれがなされました。
霊界においても、平安と安全をもたらす役目の者が必要なのです。そのようなお役を授かった者が何体かおられます。たいていは天使です。そもそも彼は、地上での重たくて汚い世俗的な波動には似つかわしくなく、それがために21歳で娑婆世界から取り去られたのです。古来から、清らかな心を持つ詩人や文学者、音楽家や宗教者などには早くから他界する者がいるのも、単なる逃避的なことが原因であったり本人の意思が弱いからだけではありません。純粋なるがゆえにこの地上では生き続けられないのです。また、その純粋さを神が、保つために、見過ごしにされず引き上げられます。取り去られます。そうでないと、無理に本人は地上に合わせ、汚れていってしまいかねないからです。
ひろくは人間の大半が、子供から大人になる時にそれが起きてしまっています。それゆえにこそ主は「幼子のようになりなさい、幼子のようになれば天国に帰れます」とおっしゃられたのです。そのように言い得る主ご自身が、清らかな心の持ち主だったからです。だからそれがわかるし、言い得たのです。そして実際、主もそのまた従兄弟の洗礼者ヨハネも、30台前半で地上から去って行かれました。
潔典さんは、そのお名前にも表れているように、清らかな規範を備えています。そのために、それ以上地上に居ると彼自身が汚れてしまいかねませんでした。なぜなら彼は、それ以上居たら、地上に合わせ始めただろうからです。それを人は、大人になったとか、分別がついたなどと言います。しかし、仏陀がなぜ分別を好ましくないと捉え、無分別を説いたか、です。それはやはり、仏陀自身が、きれいな魂の持ち主だったからです。そのため仏教では、世間とは正反対に、分別がつくことをよろしくないとみなし、無分別の境地を説きすすめるのです。
潔典さんは、そのまま21歳以降も地上に居ると、彼自身、素直で謙虚なので、地上に合わせ始めたことでしょう。21歳といえば7の倍数です。7×3で、ちょうど区切りのよい年数を地上で送りました。それで十分だったのです。たしかに地上にそのまま留まれば、地上でも有能振りを発揮して、言語学の大家になっていたことでしょう。あるいは外交官になっていたかもしれません。しかしそこまでの任務は、今生において与えられていませんでした。むしろ父親を導き、教育し、いのちの大切さと永遠性とを身を以って知らしめるために自ら去っていくことが重大な任務として与えられていたのです。
それを、もっと彼は、つまり潔典さんは、父親のあなたに伝えたかったのです。また、彼を通して背後の高位の霊的存在方は、あなたに伝えようとしました。それが多大の犠牲と苦悩を伴うことになりました。それを経ないことには最も得がたい賜物をいただくことは起き難いのです。
あなたはそのような危険を冒して、今日にまで生き延びさせられているのも、背後の高位の存在方のお陰です。そうでもないと、あなたは今日までとても生き延びれなかったことでしょう。単にあなたが強い人だからということではありません。まして、地上での生きることへの執着心が強いからではないのです。逆に、あなた自身は、むしろ、早く地上から、また自分の肉体から去っていき、あの世で自分の息子や妻に会いたがっていたくらいです。
人間は身を以って体験しないと、また、追い詰められないと、本当には悟って大切な資質を身に着けることは起き難いのです。そのような大切な資質が「枝の先端に生っている実」で例えられます。そして、それは確かにあなたの身に起きたことです。その意味であなたの愛する息子さんは、いまほっとしているところです。やっと霊的に同列に、あなたは自分の息子と向き合えるところにまで成長してきました。
彼は清らかで、天的な存在なのです。そのため地上で天使の輝きと賢さを現し出しましたが、地上の任務は似つかわしくなく、過酷すぎました。それが予感された時点で、還っていくことになりました。彼は苦しまずに肉体から離れました。なぜ飛行機事故だったのでしょう。それは、彼が地上的な存在でなかったからです。それ故、地上でいのちを落とすことにはならず、空中を飛行する物体からそのまま天へと還っていくことが起きたのです。地上に飛行機が激突してその衝撃でいのちを落としたのではありません。その前に覚悟を定め、失神していました。そのため空中で体から離れ始めていました。それによって肉体的に苦しまずに、すっと、早々と、天へと向かって行けたのです。
彼はいま、平安そのものです。天使の一体となって、静かに天界を巡ったり静かに回想して、温かく優しい波動を天界から霊界全体に送り届けています。この世の父親であるあなたと、今でも親密に繋がっています。21年間の共にある生活をときに回想して懐かしみ、また、あなたに感謝しています。また、父親のあなたをこころから尊敬しています。ことばにならない慕う気持ちと、憧れと、尊敬心が無言のうちに波動としてあなたに伝わってきています。その波動が、これまであなたを支え導いて、今日のあなたがあるのです。
9. 美しく清らかに輝く (2009.06.06.)
潔典さんは、父親のあなたのことをとても尊敬しています。あなたが父親であったことに、誇りを持っています。今でもあの世で、そのことをはっきり覚えています。あなたのことは忘れていません。むしろ確信すら抱いています。その確信は時が経つにつれて、しっかりしたものになりつつあります。
生前、潔典さんは父親のあなたを目標として生きていました。もしそのまま生きていたとしたなら、外交官、たとえば外務次官などになっていたかもしれません。大学の先生になるよりは、多くの人たちのために国際的に飛び回って、世界の架け橋になることを彼は選んだことでしょう。それでも、父親のあなたのことは自分の目標であり、理想とするべき存在として心に抱いて生き続けたことでしょう。
前世では、文学や音楽を好んだり、また翻訳をしたりしていたことがありました。しかし今世では実務的な方面に、潔典さんは生き続けていたなら、自分を向けていったことでしょう。いずれにせよ語学を活かし、多くの人に理解をもたらせたり安堵感を与え、世界の架け橋となったはずです。
霊界へ早めに還り、霊界において自分の夢を実現させています。霊界において、異なった層の間で行き来しながら、霊界をひとつに結ぶことを行なっているのです。
霊界にも、いくつかの国に相当するものがあります。霊界ではテレパシーで通ずるのですが、それでも、異なった層にいる霊たちの間では、コミュニケーションが容易ではありません。思い方や思いの種類が霊によってそれぞれまちまちなので、テレパシーといってもそれほど実際は簡単ではないのです。彼はそのような間に入って、お互いに理解し行き来ができるように取り計らっています。また、一人ひとりを指導し、時にはカウンセリングに応じながら、異なったところにいる霊たちのことを理解し考慮しながら、自分自身の成長を遂げ、より立派な魂になるように見てあげているのです。
彼は教育者であり、指導者の一人です。懇切丁寧にやさしく一人ひとりに相対し、導きつつあります。たいていは霊たちが座っていて、彼は立って指導しています。彼は活発型で多くの霊たちと向かい合い、清らかで美しく輝いています。身体はやや細身であり、若さを保持しています。それでも年齢を経るごとに風格が備わり、誠実味を帯びてきているので、単に若くて純粋ということではなく、少しずつ落ち着き、円熟味を増しているところです。
霊界では霊たちが単に年とっていくのではありません。その時の意識状態や、あるいは疲労の度合いなどや行なったことが、外見に投影されて出てくるのです。この世で老けていくというようなことはあの世ではありません。もしそれに近いことがあるとするならば、疲労や倦怠感が老けたような状態を霊にあの世ではもたらします。元気でエネルギーに満ちていれば若く、希望があれば輝いており、意図が良ければ美しいのです。彼は小気味よく、よい光を放って、朗らかに応対しています。
霊格は、もし9段階に分けるとするならば、7段目から8段目に向かいつつあります。上の下から上の中に向かいつつあるところです。ちょうど学校の偏差値と似たように、非常に低いレベルと非常に高いレベルとは数が少なく、山の形をしていて、中くらいのレベルに数多く集中しているのです。この世でも、あの世でも、凡人のように普通程度の霊が集まっているものです。
最近はアンバランスがこの世でもあの世でも生じており、あまりよろしくない霊たちの数が膨らんできています。きれいな山型の波に異変が生じてきているのです。それをなくするためにも彼はあの世で、一生懸命、霊たちに関わっています。清らかで無心になって、人のため霊のために関わっています。また時に、自分で鎮まりながら、自分を感じ内省し、調整しています。より高い霊に、時に向き合い、自分を同調させて、神様から来るエネルギーをいただいて取り入れて調整もしています。
食べたり飲んだりすることはほとんど無くなりました。ちょうど 「仙人は霞を食って生きている」
といわれるように、霊気をチャクラで吸い込むことで、住むようになっているのです。あの世に行っても普通の霊たちは、食べ物や飲み物が必要です。この世でその習慣が身についているからです。そのような霊にとって、子孫がご供養をしてくれることは、またとない機会になっています。しかし、ある程度以上に高くなると、ご供物は必要なくなります。
父親のあなたに対しては、信じて安心しています。再会できる時が近づいてきているので、彼も自分を備えているところです。
10. 生まれ変わる必要がない霊格に (2010.06.04.)
霊界において、教師の役目を果たしています。霊たちに対して、生きる心得や、生命とは何か、いのちの尊厳とはどのようなことか、霊界に来て何をしなければならないのか、次に人間として物理領域に生まれるに際してどんな心がけをもたねばならないのか、などを教えています。時に、霊界の構造や仕組みに関しても説明します。
霊界入りを果たした霊たちに対して、生前の行いや、心の持ち方について回顧し、反省することも手伝っています。つまり、潔典さんは霊界で指導霊になっているのです。以前にも増して積極的で、活き活きと指導に当たっています。ある場合は、霊界でのコミュニケーションの仕方について物理領域での様々な言語との関連で、霊界ではテレパシーとして通ずることを教えています。霊界では、純粋さと正直さと誠実さが特に求められることなどを強調しています。
潔典さん自身は、他の霊に教える以外の自分の時間帯において、精神統一をしたり、心の念の使い方で工夫し、さらに自分を浄めたり、愛と命の本源の御光に浴し、波長合わせをしたりして静かに過ごしています。霊界の修行の多くが、以前のことの回想と告白懺悔、そして精神統一にあります。
潔典さんの修行は、大分進んでいます。9段階で分けるならば、上の下から上の中という、7段目から8段目まで来ようとしているところです。そこまで行くと、一般には人間として生まれてこなくなります。生まれてくる必要がなくなるからです。ただ、父親であったあなたをはじめ、縁のある者たちとの繋がりで、必要とあらば来世また一緒に出てくることが十分あります。その時は来世において、まわりの手本となり、まわりを整え、人間の在り方や生き方を身をもって示し、多くの人たちに希望と自信をもたらせていくことになるでしょう。
このように、普通にみれば生まれ変わる必要のないところまで来ていますが、縁のある者たちとの関連で来世に出てくることが起こり得ます。本人もそれを予感していて、少しずつ、内省に備え始めてもいるのです。
父親のあなたに対して伝えたいことは、霊界で再会した時、自分の息子に対し誇りを感じられるように今から準備し、お父さんを歓待したい、十分な尊重と敬意を持って迎え入れたい、そのために霊界で状況を整えておきたい。それが父親であった人に対する礼儀であり、また感謝のしるしである、このように自分の中で心得て、あなたを迎え入れようとしています。そのこころづもりを伝えたがっています。
あなたに対しては、ただただ感謝と、父親であるということへの誇り、また、惜しむらくは(親子関係が)短い期間であったこと、その分、霊界では十分にもてなして共に過ごし、交流をはかりたい旨、伝えたがっています。生前、父親の恩義に報いられなかったため、霊界に来てその分、霊界では自分が先輩になったので、いろいろと霊界のことを教え、何よりも優遇させてくださいという思いがあります。それが潔典さんにできる父親に対する恩義だと本人は捉えています。
つまり、どのように礼に報い、恩返しをするかについて検討しているのです。そして、あなたが霊界に入ってくるのを、ただ待つのではなく、自分が霊界で輝いており、活躍して多くの良いものをまわりに与えつつある姿を、今のうちから定期的に、あたかも実況中継のように伝えたい意向があるのです。それは、本人ばかりでなく、関連の指導霊や天使も同様に思っているため、それがあなたの心に伝わり、たとえばリーディングの機会をあなたが活用して、潔典さんやまわりの指導霊のその意向が、このような形で毎年、実現してきていることもあるのです。
ただあなたが知りたかったり、思いが残っているということだけではありません。それ以前にまず、潔典さんやかかわりのある指導霊が、潔典さんがあの世で輝いて活躍していることを是非いまのうちから、父親のあなたに伝えたいし、伝える必要がある、それがあなたが天寿を全うする上で必要だということなのです。それによって、あなたが地上に留まりつつ、確かに霊界があり、神様をはじめとする高位の霊的存在がおられることを深く認識し、前世の時の懐疑的な面を払拭する願いがあります。
あなたは最近の前世において、密かに霊界や霊的存在を認め、関心を寄せていたものの、自分の立場を失うことを懼れて、またまわりから怪訝にみられることを回避したくて、このようなことには一切触れなかったのです。たとえ話題が出たときも、笑って話題を逸らしたものでした。そのときのあなたが取った態度がカルマとなって、生まれ変わった今世で、あなたは自分が学者のうちから霊的なことを認め、活動するように仕向けられたのです。また、それによって学者である立場が生かされ、多くの人たちがこのような霊的世界とその働きがあることを、あなたが学者であることで、あなたの話すこのようなことが信じられるようにする狙いがあるのです。
あなたは前世の時に自分が取った態度が好ましくないことがあることを悟り、そのために生まれ変わった今世では、そのことに対して素直になって行動を起こしました。そのために、潔典さんというあなたにとって縁のある魂が早くに霊界に行って、霊界の存在とその様子をあなたに知らせ、あなたがこの世に留まって、それを多くの人に伝え啓蒙することを、あなたは後半生の役目として引き受けたのです。
あなたがそのカルマを果たすために、あなたの縁のある潔典さんが、早くにあの世に迎えられました。それによって前世のあなたのカルマを果たさせるように、彼が霊界で導いたのです。あなたはその通り、後半生をこうして生きているのです。このように、あなたは学者であったことを妨げにせず、それを上手に用いて多くの人たちを説得し、霊界や霊的存在のあることを現に伝えつつあります。カルマを果たし使命を遂行することは、縁のある者たちとのチームプレーで為されることがあるという、よき実例となっています。
(2010.09.01)

初めて死について考えたころのこと (身辺雑記71)
= 生かされてきた私のいのち (2) =
尻無川の「甚兵衛渡し」の名前は、この渡船場の前にあった「甚兵衛の小屋」と呼ばれた休み茶屋からきているらしい。この茶屋は、「蛤小屋」とも呼ばれていた。海に近いこのあたりでは、むかしは、シジミやハマグリが沢山取れて、「蛤小屋」で出すシジミ、ハマグリが名物になっていたという。私の幼時の頃から親しんだ「関東炊き屋さん」は、おそらくこの「甚兵衛の小屋」の跡を継いだものと思われる。
この「関東炊き屋さん」の主は、人のよい中年のおばさんで寡婦であった。名前は覚えていない。娘さんと二人で店をきりまわしていたが、その娘さんは今から考えると15歳くらいだったろうか。ときどき、痩せて背の高いおじさんも顔をみせていたが、娘さんは、この人のことを、「おっちゃん」と呼んでいた。沖縄からやってきて、店の手伝いをしていたのだが、いつのまにか同居するようになったようである。おばさんと娘さんとおっちゃんは、3人で店から歩いて10分ほどの、北恩加島町に住んでいた。そこから毎朝、店へやってきて、工場への通勤者や渡し舟の乗客などを相手に店を開き、夜には、店を閉じて自宅へ帰るのである。
店を閉じて家へ帰るときには、大きなセパード犬を店の中に残して、広い出入り口の何枚かの板戸には、端から端まで太い鎖がまわされていた。朝の早い時間に、まだ板戸がしまっているのを見て、一度いたずらで、鎖をバンバンと板戸に打ち当てたことがある。中ではセパード犬が激しく吠え立てた。いつもは怖くて近くへも寄れないのだが、絶対に安全であると思い込んでいたから、そのことで、あさはかな幼児の優越感のようなものに動かされていたのかもしれない。
その店の出入り口の端には、長い木の腰掛が二つ三つ置いてあった。客がいないときなどには、私はちゃっかりその腰掛に座って、ちょっとの間、遊んだりすることもある。ある日の午後、私は、ちょこちょこと走っていって、その腰掛の一つに飛び乗ろうとした。ところが、あのセパード犬が、あいにくその腰掛の下の奥のほうで昼寝をしていたのである。自分に向かってくる向こう見ずの子供を犬は容赦しなかった。私はいきなり左足をがぶっと噛まれて、悲鳴をあげ泣き出した。おばさんが慌てて飛び出してきて、私を抱きかかえて中に入り、ヨードチンキかなんかで傷の手当をしてくれた。私も泣き止んで、この件は、それで終わりである。
むかしのことで、犬にかまれたくらいで大騒ぎはしなかったし、狂犬病の予防注射のことなども問題にしなかった。私も、家に帰ってからも、多分、心配をかけてはいけないと思ったからであろう、母にも家族の誰にも、犬に噛まれたことは黙っていた。ただ、子供心にも、体に傷がついたのだから、それだけでも寿命に影響があるはずだと考えた。たいした傷ではない。しかし、これで三日くらいは、早く死ぬことになるに違いないと思いつめた。そのことがひどく悲しくて、私は布団の中に入って、声を殺して泣いた。
夏に、溺れて死にそうになったときには、水中で泣き叫んだだけで、引っ張りあげられ後では死の恐怖がつきまとうことはなかった。それなのに、このとき、「三日くらいは・・・・・」と悲しみ悩んだことはよく覚えていて、いまでは、なぜあの時、ああいう風に考えたのだろう、と自分でもおかしいのだが、これが、5歳から6歳くらいのころの私が、死についての怖れを感じた最初の記憶である。
幼児のころの私は、毎日、朝から夕方まで、ほとんど家を出て遊びまわっていた。父の勤めるS伸鉄会社は自宅からは遠くなかったので、私はよく、その会社の中の父の工場へも「遊びに」行った。父の工場は、会社の圧延部門である。そこでは、炉のなかで真っ赤に熱せられた鉄の塊(インゴット)を、細い鉄棒に加工していた。大きなローラーが並んでいる圧延機械の前にクレーンで運ばれたインゴットが、大きな直径のものから小さな直系のものに至るまで、いくつかのローラーを通るたびに細くなっていく。現場では、末端のローラー付近で、真っ赤に熱せられた鉄の線がくねくねと曲がって這い回っているような感じだから、危険で、部外者が立ち入れるところではない。私は、できるだけ機械から離れて、遠回りしながら工場の奥にある父の作業事務室へ行くことにしていた。
向学心に燃えていながら、貧しくて上級の学校へ進めなかった少年時代の父は、働きながら懸命に独学を続けて、鉄鋼圧延機械の構造や設計に精通していた。そのころはまだ40歳にもなっていなかったはずだが、会社からも一目おかれていたようである。待遇は主任でも、圧延工場の運用と20人ほどの工員の人事・監督なども任されていた。* 父の作業事務室の窓からは、灼熱の鉄を操っている現場の仕事ぶりがよく見えた。4畳半くらいの狭い部屋の真ん中に大きな四角の火鉢があって、そのまわりに椅子が三つ四つ置いてある。片隅には父の机があった。父は現場に出ていることのほうが多かったが、そんな時にも私はひとりで中に入り、椅子の上にちょこんと腰掛けて、機械が大きな鉄の塊を押しつぶしていく様子を見ていた。そんな光景を見るのが好きで、私はひとりでいても、いつまでも見ていて飽きなかった。
ある冬の日の昼近く、私はまた工場へ行って、父の作業事務室へ入った。その日は父が中に居て、髪をぼさぼさにした中年のおじさんが火鉢を挟んで父の前に座っていた。父は、お茶を注いだり、火鉢で焼いた焼き芋をそのおじさんにすすめたりしながら、いろいろと世間話のようなおしゃべりをしている。話の内容は私にはよくわからなかった。おじさんは、うなだれながらただ黙って父の話を聞いている。私が部屋に入ってから15分ぐらいたって、そのおじさんは何度も頭を下げながら部屋を出て行った。父と二人になって、「あの人、だれ?」と私は聞いた。「あれはね、ドロボーさんだよ」と父は答えた。
工場の入り口の、道路を挟んだ反対側の資材置き場には、いろいろな鉄鋼資材や製品の原料となる鉄のインゴットがいくつかの山になって積み重ねられていた。そこには会社専用の船着場があって、尻無川を船で運んできた原料や資材が、そこで下ろされるのである。そのおじさんは、前日の夜に小さな舟でその船着場に漕ぎ寄せて、資材のいくらかを舟で運び去ろうとしたらしい。運悪く会社の警備員に捕まってしまって、父の前に連れてこられたのである。
考えてみると、捕まってからすでに数時間以上はたっているはずであったが、その間、このおじさんがどうしていたのかは知らない。ただ、父は、そのおじさんを警察に突き出すことはしなかった。私が行ったときには、一緒にお茶をのみ、焼き芋を食べながら、父は諄々と諭していたのであろう。最後には、いくらかのお金を持たせて帰らせた。この記憶のせいか、私にはいまでも、泥棒というのは悪い人というより、気の毒な人というイメージが強い。ただ、その時の幼なかった私にはまだ、生活の苦しさとか、犯罪というようなことは、何もわかっていなかった。盗みという社会の暗い面にじかに触れたのは、おそらくそのときが初めてである。
暗い記憶では、こういうこともあった。ある日の夕方、甚兵衛渡しの近くで誰かと喧嘩したらしい若い人が酒に酔ってわめきちらしながら、川に飛び込んだのである。渡し場の近くには、何人か人がいたので、みんなで苦労して、その人を川から救い上げた。そのあたりから私も目撃したのだが、その人は、手がつけられないほど暴れていた。暴れながら怒鳴っていたが、「死んでも一銭くらいはもうかる」といっているのが耳に入った。私は、どうして、そういうことになるのか、死んでも本当に一銭くらいはもうかるものなのか、と不思議に思った記憶がある。びしょびしょに濡れながら怒り狂っていたその人の姿が怖くなって、私はすぐそこを離れたが、その後、その人はまた川へ飛び込んだらしい。
また、こういうこともあった。私たちの借家の同じならびに、二階建ての家が2軒あって、そのうちの一軒の2階に間借りしていた「大人の人」がいた。それがどういう人だったのか、まったく記憶にないのだが、ある日の夕方、私が遊びから家へ帰ってくる途中、その人が、私服の屈強な刑事らしい人に連れていかれるところに出会った。ふと見ると、手錠がはめられている。その異様な姿に私がたじたじとなると、刑事らしい人は、ちらと鋭い目を私に向けた。窃盗犯なのか、あるいは思想犯なのか、幼かった私には知る由もなかったが、こういうことでも、社会には暗い一面があることを、小さな頭に植えつけられていったようである。
これらの記憶は、多分、1935年(昭和10年)秋から翌年の春にかけてのもので、私は5歳から6歳になろうとしていた。今から考えると、ちょうどその頃、1936年(昭和11年)2月26日に、あの「2・26事件」が起こっている。その日の朝、珍しく大雪に見舞われた首都・東京で、皇道派の陸軍青年将校らに率いられた1400人の兵がクーデターを決行した。ロンドン軍縮条約で軍備の制約を受け、日本の国防に危機を感じていた青年将校らは、政党、官僚、財閥の腐敗を一掃して、昭和維新を断行しようとしたのである。この決起は、戒厳令発布と、天皇の勅令で押しつぶされてしまったが、これは、その後の軍部の政治権力掌握への道を大きく開く契機となった。
この「2・26事件」前後の何日間は、東京の中心部でもただならぬ慌しい雰囲気であったようである。その雰囲気の中で、2月24日、九段の靖国神社にほど近い家でひとりの女の子が生まれた。軍服などの生地卸し問屋の店を構えていた山本家の長女である。生まれてからしばらくの間は、産婆さんが通ってくるのにも、買い物でお手伝いさんたちが外出するのにも、兵たちの警備の網を何度もくぐり抜けなければならず、なかなか大変であったらしい。このとき生まれた女の子が富子である。靖国神社の境内を遊び場にしながら元気に育って、25年の後に私の妻となった。
大阪の尻無川のほとりで6歳になろうとしていた私が、少しずつものごころがつき、人間の痛みや悲しみの片鱗にも触れはじめていたときに、600キロ離れた東京の九段では、軍靴の足音が響くような周囲の混乱の中で富子が産声をあげていた。そして、これも今思えば、二人はそれぞれに紆余曲折を経て異なった道を歩みながらも、時が至れば、結ばれるべくして結ばれている。繰り返しになるが、偶然というのはないのである。しかし、その当時の大阪での幼い私には、家のまわりの狭い空間だけが自分の世界のすべてで、そこからはみ出た外の世界のことや、二十年、三十年の未来に起こることなどについては、当然のことながら、何の思いも及ばなかった。
*会社の名前は千歳伸鉄株式会社といった。昭和十四年六月十五日付けの「皆勤賞」「特賞」などの賞状がいまも残っている。
(2010.07.01)

生かされてきた私のいのち (身辺雑記70)

現在の「甚兵衛渡し」。対岸は港区。昔は、この川の
堤は、紅葉の名所であった。川の両岸にはハゼの木
が数千本植えられ、紅葉の季節には「紅葉の紅が川
の面に映じて風景斜めならず」と渡船場入り口の看
板に書かれている。私の幼年時代には、この対岸に
は一面に原っぱが広がっているだけでコンクリートの
護岸壁もなかった。私が溺れかかったのは、この手
前の桟橋から約50メートル左寄りの水面である。
[2009.10.21. 筆者撮影]
大阪市の大正区と港区との間を南西に流れる尻無川というのがある。淀川水系の下流のひとつで現在の地図では、北恩加島町の西側の南端まで流れてきて大阪内港に注いでいるが、かつては、この北恩加島町の下には新千歳町があった。尻無川は新千歳町まで下ってきて、そこから大阪湾に流れ込んでいたのである。このあたりには、昭和の初期から大きな鉄工場や造船所があった。そのために、太平洋戦争末期には、米軍の猛爆を受けて壊滅的な打撃を受け、いまでは、海になって、大阪内港の下に沈んでしまっている。
私は、この尻無川のほとりの北恩加島町で、父・泰三、母・真子の長男として生まれた。1930年4月で、今からちょうど80年前である。当時、父の勤め先は新千歳町の鉄工会社で、鉄鋼を棒や線状に加工する圧延工場の主任であった。おそらく、勤務先に近いということからであったろう、私が生まれてから間もなく、新千歳町の会社の近くへ引っ越した。引っ越した先の家は、いまも残る「甚兵衛渡し」という名の舟の発着場から歩いて5分足らずの海側に向かったところにあった。もし私の記憶が正しければ、新千歳町20番地である。しかし、そこも、もう今は、ない。
当時、甚兵衛渡しの前には、私たちが、「関東炊き屋」さんとよんでいた食べ物を売る店があった。いまでいう、おでんのほかに、饅頭、餅、菓子、果物類も売っていた。その店から、川の左側の道を50メートルほど海側へ向かったところに、伊藤さんという資産家の大きな家があった。水舟とよばれていた500トンくらいの木造船を持っていて、家の前の道を挟んだ川岸の専用船着場にその船は係留されていた。当時はまだ珍しかった電話で注文をとり、船に水をいっぱい積み込んで、大阪湾に停泊する大型汽船などに給水していた。
伊藤さんの家の右隣には、「めしや」と看板をかけた食堂があった。ご飯におかずをつけた定食のようなもののほかに、うどんなども食べられる。風邪をひくと、熱いうどんに頓服薬をつけて持ってきてくれたりした。この頓服薬つきのうどんが、風邪のときの医者代わりであった。この「めしや」の角を左折すると、そこが細長い路地になっていて、大阪によく見られる長屋が6軒ほど軒を連ねていた。これらも伊藤さんの持ち家である。引越し先は、その長屋の奥から2軒目であった。居室は4.5畳と8畳の2部屋だけで、玄関の横には4.5畳くらいの台所がついている。その一部は土間になっていて、水道はあったがガスは当時まだ普及していなかったから、ご飯は竈に薪をくべて炊き、魚を焼いたり湯を沸かしたりするのには七輪を使っていた。この、至って庶民的な、小さな借家から私の幼時の記憶は始まっている。
幼時の記憶といっても、2歳くらいからの、断片的な、それもおぼろげなものにすぎないが、その中でも、いまも特に強く残っている記憶は、1934年9月21日の室戸台風である。その時、私は4歳5ヶ月になっていた。戦後の枕崎台風、伊勢湾台風と並んで、この台風は昭和の三大台風といわれている。はじめに、高知県室戸岬付近に午前5時ごろ上陸したことから、室戸台風と呼ばれるようになった。いまでは記録により、台風の爪あとも明らかになっているが、この台風は、同日、午前8時には、大阪と神戸の間に再上陸している。潮位が高かったことと、最大瞬間風速60メートルという強風により、4メートルを越える高潮が発生した。そして、死者2,702人、不明者334人、負傷者14,994人を数える被害者を出した。
その日の朝、私たちの家族は、ほかの長屋の住人たちと、すぐ近くの家主である伊藤さんの家の二階に避難した。水が海のほうから道路の上を広がり初めて床上浸水になる直前、腰まで水に浸かりながら、伊藤さんの家まで歩いたが、そのときの冷たい水の感触を私は今もよく覚えている。伊藤さんの家の二階には30人くらいも集まっていただろうか。みんな心配そうに、ぼそぼそと話し合ったり、ラジオに耳を傾けたりしていた。水位はどんどん上昇してきて、やがて、一階の全部を飲み込んでしまいそうな勢いになった。強烈な風の音が断続的に響き渡って、大きな家全体がぐらぐらと揺れる。わが家の隣家のおばあさんが風呂敷に包んで持ってきたお位牌を部屋の隅に並べて、「ナムアミダブツ、ナムアミダブツ」と繰り返していた。この「ナムアミダブツ」と、誰かに抱かれて窓越しに見せてもらった光景が、海のような水の広がりだけであったことも、鮮明に記憶に残っている。
しかし、台風の恐怖心はあまりなかった。家族を含めた大勢の人たちの間では、幼いだけに、なにかしら安心感があった。一階の屋根近くまできていた水が、「二階までくると家が持ち上げられて危険だ」と言っていた誰か、大人の声を覚えているが、幼児の頭では、そんな危険も理解できなかったからかもしれない。そんなことよりも、台風が過ぎ去った後の、周辺の光景は忘れられなかった。あたり一面が泥だらけで、大きな船が道路に乗り上げていた。水が引いた空き地のところどころでは、水溜りで魚が跳ねたりしている。どういうものか、麦の葉模様の反物が、おびただしくあたりに散乱していて、それらは拾ってもかまわないようだった。通常では全くありえない情景で、すべてがもの珍しく、興味深く、幼時の私は、目を見張るようにして、あちらこちら歩きまわった。
このような幼時の私の思い出は、月日の経過とともに密度を増していくが、それらはほとんど、楽しい思い出に満ちている。だが、それから一年、私が5歳になってからの夏、今から考えると、私は生死に関わる重大な体験をすることになる。尻無川に落ちて溺れかかったのである。
家主の伊藤さんの家には、私より2歳年長の男の子で「カズちゃん」がいた。お盆が過ぎた頃だから、8月のの下旬であったかもしれない。カズちゃんと私は、連れ立って、家の前の尻無川へでかけた。お盆の終わりには、木の舟に果物や菓子をのせて川へ流すみ霊送りの習俗がある。この木の舟は、30センチくらいの小さなものから1メートルにもなるような大きなものまで様々で、それらが尻無川から一旦海まで流されたあと、波にもまれ風に吹かれて、たまに、川岸へ帰ってくることがある。そのような舟を見つけて持ち帰ろうというのである。うまくいけば大変な「収穫」になるはずであった。
川岸の一部には、多くの原木が筏に組まれて繋ぎ止めてある。その筏の上に乗って一番端まで来たところでカズちゃんと私は、根気よく空っぽになった舟が流れ着くのを待っていた。いまなら、大人の監視の目がうるさく、とてもそんなまねは出来ないに違いない。しかしその頃は、周りに人々がいることもあまりなく、親たちも、子どもたちの遊びにはほとんど干渉しないのが当たり前であった。その日は、晴天で暑かった。それでも1時間ほどは待ち続けたであろうか。やっと、遠くからかなり大きな木の舟が近づいてきた。すぐ目の前に来てからは、カズちゃんと私は、棒切れで水を叩きながら、なんとかその舟を引き寄せようと必死になった。私は小さな手を力いっぱいに伸ばした。それでも届かないので、もっと手を伸ばそうと身を乗り出し、そして、水に落ちた。
私は水の中で泣き叫びながら沈んでいった。口からも鼻からも水が入ってきて苦しい。息ができずにばたばた手足を動かしているうちに、一度、上へ上がってきた。しかし、振り回している私の手は何にも触れることなく、また小さい体はぶくぶくと沈んでいった。筏の上で、私が落ちたのを見た7歳のカズちゃんも、ことの重大さはわかったであろう。手で水をかきまわしながら、懸命に私を掴まえようとしていた。そのカズちゃんの手に、もがきながら2度目に上がってきた私の手がちょっと触れた。しかし、二つの手は結ばれることなく、するりと抜けて、私はまた、ぶくぶくと水の中を沈んでいった。青白い水のなかで私はばたばた手足を動かしながら泣き叫んでいる。かなりの水を飲んで、苦しい。もうあれが限度であったろう。死が迫っていた。そして3度目、ぶくぶくとまた上へ上がっていった時に、私の手ははじめてカズちゃんの手をしっかりと捉えたのである。
昨年の秋、私は十数年ぶりに、この尻無川の甚兵衛渡しへ行ってみた。いまではこのあたりの川岸にも高いコンクリートの壁が連なり、渡し場へ通ずる広い道路には高層アパートが建っていたりして、昔の面影はほとんどない。しかし、尻無川自体は、同じ場所を昔も今も同じように流れているはずだから、甚兵衛渡しからは、かつて私が溺れかかった場所は、ほぼ正確に特定できる。私は、その場所を眺めながら、しばらく思いにふけった。かつては、私は、この場所で溺れかかっても救われたことを九死に一生を得た偶然の幸運のように考えていた。しかし、おそらくそれはそうではないであろう。後に私は15歳の時にも、「九死に一生の偶然」を繰り返すことになるが、もともと偶然というのはないのである。あの時、私の手を捉えた7歳のカズちゃんの手は、まぎれもなくそれは、神の手であった。
(2010.05.01)

単純明快な霊的真理 (身辺雑記69)
シルバー・バーチの教えは、近藤千雄訳『シルバー・バーチの霊訓』(潮文社刊)12巻を見てもわかるように量的にも厖大であるが、もちろん大切なのは、量だけではない。私たちのこころを打つのは、その質の高さと深さであり、そのことばの持つ意味の重大さである。私は何度か折に触れて述べてきたが、私にとってそれらは、何ものにも代えがたい「無上甚深微妙の法」となった。私はいままでの生涯で、話者自身が語ったことばをそのまま活字にしたもので、これに比肩できる文章がほかにあることを知らない。
この『霊訓』は12巻もあって確かに厖大であるが、実は、シルバー・バーチが述べている霊的真理そのものは決して複雑多岐にわたるものではない。むしろ、極めて単純明快ないくつかがあるだけでである。ただ、私たちがあまりにもその霊的真理から遠い存在であるために、なかなかそれに近づいていくのが容易ではなく、そのために、シルバー・バーチは、いろいろと表現を変え比喩をまじえたりしながら、なんとか私たちに理解させようとしてきた。それが、『霊訓』12巻となって、いま私たちの手の届くところにおかれているのである。しかし、この12巻を全部読まなければシルバー・バーチのいう霊的真理が、たとえそのおぼろげな輪郭だけであるにせよ、理解できないというものではないであろう。
繰り返すがシルバー・バーチの霊的真理は単純明快なのである。そして、おそらく、その一番大切な核心のひとつは、この地上に生きている私たちのすべては、霊を伴った肉体ではなく、肉体を伴った霊であるということであろう。本来霊である私たちは、霊であるがゆえに永遠の存在であり、この世での死も霊界で生きることにほかならない。住む世界が変わっても、私たちのいのちは決して滅びることはなく、永遠に霊性の向上を目指しながら、神の摂理のなかで生きつづけていく。これだけの極めて単純で明快な霊的真理を地上の人間に教えるために、シルバー・バーチは半世紀にわたって、私たちに無償の奉仕を飽くこともなく続けてきた。
この霊的真理を、試みに、シルバー・バーチの厖大なことばのなかから、敢えていくつかに集約したら、何を選んだらいいであろうか。それをここで考えてみることにしたい。過去数年間、ほとんどすべてのシルバー・バーチのことばを「学びの栞」(A)
に分類してきて、このような作業をするのもそんなに困難ではない。キーワードは、神と霊と死の三つである。そのなかから、誰にとっても関心が高いはずの死についての真理から始めることにしよう。こう述べられている箇所がある。
《"生″を正しい視野で捉えていただきたい。その中で "死″が果たしている役割を理解していただきたいと思います。人間はあまりに永いあいだ死を生の終りと考えて、泣くこと、悲しむこと、悼むこと、嘆くことで迎えてきました。私どもはぜひとも無知----死を生の挫折、愛の終局、情愛で結ばれていた者との別れと見なす無知を取り除きたいのです。そして死とは第二の誕生であること、生の自然な過程の一つであること、人類の進化における不可欠の自然現象として神が用意したものであることを理解していただきたいのです。死ぬということは生命を失うことではなく別の生命を得ることなのです。肉体の束縛から解放されて、痛みも不自由も制約もない自由な身となって地上での善行の報いを受け、叶えられなかった望みが叶えられるより豊かな世界へ赴いた人のことを悲しむのは間違いです。》「学びの栞」(A) [2-f]
死を「悲しむのは間違い」といわれても、死について、これだけで納得して安心立命できる人は少ないかもしれない。それに、世の中に生きていく上では、死のほかにも、いろいろと自分のこと、家族のこと、あるいは、社会のことなど心配事が絶えずつきまとう。生活上の不安もあり、予期しない不幸に襲われたりもする。しかし、死の真理は霊の真理であり、生の真理でもある。死を理解すれば、何の心配もなく生きていけるはずのこの世の「処世術」についても、シルバー・バーチは次のように言及する。
《人間にとって最大の恐怖は死でしょう。それが少しも怖いものではないことを知り、生命が永遠の存在であり、自分も永遠の存在であり、あらゆる霊的武器を備えていることを知っていながら、なぜ将来のことを心配なさるのでしょう。不幸の訪れの心配は、その不幸そのものより大きいものです。その心配の念が現実の不幸より害を及ぼしております。》「学びの栞」(A) [2-zm]
心配や不安にとりつかれることに慣れてしまっている私たちは、実は、そのような不完全な存在だからこの世に生まれてきた。完全な存在ならこの世に生まれてくることはなかった。私たちはそれぞれに弱点を持ち、欠点を持つからこそ、この世に生まれて、霊性向上のための経験や学習を重ねていく。しかし、そのためにも、私たちは、さまざまな困難辛苦を経験し乗り越えていかねばならない。逆に言うと、困難辛苦を経験しなければ、学習の効果が期待できない。困難辛苦は、だから、学校で与えられている課題のようなもので、決して「悪いこと」ではないのである。ここで、シルバー・バーチの霊の真理のことばに出会う。
《地上的環境の中に置かれている以上あなた方は、地上ならではのさまざまな条件が生み出す幸福の絶頂と不幸のドン底、いわゆる人生の浮き沈みというものに直面しないわけにはまいりません。
しかし、そこにこそ皆さんが地上に生を受けた意味があるのです。つまりそうしたさまざまな浮き沈みの体験が皆さんの霊、真実の自我に潜在する資質を顕現させることになるのです。困難と逆境とに遭遇してはじめて発揮されるものなのです。
・・・・・人間の一人一人に神の計画があるのです。偶然の事故、偶然のチャンス、偶然の一致というものはありません。すべてが大自然の摂理によって動いており、そこには奇跡も摂理への干渉も有り得ません。摂理そのものが完璧にできあがっているのです。なぜなら完全な叡智によって生み出されているからです。》「学びの栞」(A) [56-i]
世の中には、本当は、偶然や奇跡というものはなく、すべては大自然の摂理によって動いているという教えは、実に新鮮に響く。そして、これが真理であれば、実際には、この世でしばしば話題にされるような個人的、社会的不公平というものはないことになる。不公平がないのであれば、どんなことであれ、他人をうらやむ必要も全くない。それにもかかわらず人生が不公平に思えるのは、大自然の、あるいは、神の摂理を理解できないからであると、シルバー・バーチはここでは、神についての真理を教える。
《時として人生が不公平に思えることがあります。ある人は苦労も苦痛も心配もない人生を送り、ある人は光を求めながら生涯を暗闇の中を生きているように思えることがあります。しかしその見方は事実の反面しか見ておりません。まだまだ未知の要素があることに気づいておりません。私はあなた方に比べればはるかに永い年月を生き、宇宙の摂理の働き具合をはるかに多く見てまいりましたが、私はその摂理に絶対的な敬意を表します。神の摂理がその通りに働かなかった例を一つとして知らないからです。》「学びの栞」(A) [48-h]
シルバー・バーチが、ここばかりではなく、いろいろなところで何度も、宇宙の摂理の働きを見て、「絶対的な敬意を表します」と述べているのは、私たちも十分にこころに留めておくべきであろう。宇宙の摂理とは神のことである。自分を知ることとは、つまり、神を知ることなのだが、その神を知ることの大切さも、私たちは忘れてはならないであろう。私たちはもともと神の子であって、神との縁を切ることはできない。だから、私たちは、できるだけ、「神との融合を保つことを怠ってはならない」というシルバー・バーチのことばを最後に付け加えておきたい。
《地球は完全な状態で創造されたのではありません。個々の人間も完全な状態で創造されたのではありません。完全性を潜在的に宿しているということです。その潜在的完全性が神からの霊的遺産であり、これを開発することが個人の責務ということです。それには自由意志を行使する余地が与えられています。善か悪か、利己主義か無私か、慈悲か残酷か、その選択はあなたの自由ということです。ただし忘れてならないのは、どちらの方向へ進もうと、神との縁は絶対に切れないということです。神の力とエネルギーと援助を呼び込む手段は常に用意されています。しかしそのためには時には魂の奥の間に引きこもり、その静寂の中でできるだけ神との融合を保つことを怠ってはなりません。》「学びの栞」(A) [58-b]
(2010.03.01)

こころに響く救いのことば (身辺雑記68)
このホームページの「学びの栞」Aでは、シルバー・バーチのことばを 80 の項目に分類して取り上げてきた。はじめのうちは、シルバー・バーチのことばのうちの大切な部分と思われるところだけを拾い上げていくつもりで始めたのだが、すぐに、それは不適切であることに気がついた。ことばの一つ一つが、それぞれに大切で、それぞれに真実の重みを伝えていて、取捨選択などできるようなものではなかったからである。結局、潮文社発行の『シルバー・バーチの霊訓』12巻を、ほとんど全文、転写するような形になった。そして、それもまもなく終わろうとしている。
「学びの栞」Bは、私の目の届く範囲内での種々の書籍から、シルバー・バーチのことばの内容と対応するものを抜き出し、同じように、できるだけ
80 の項目に分類していこうとするものである。これによって、シルバー・バーチがいっていることを、ラムサは例外としても、この地上の人びとはどのようにいっているかを、比較検討してみることもできる。このような場合、普通は、A
の信憑性を補強するために、或いは、その内容を補足説明するために、B を配置するということになるのであろうが、この
A と B の間には、その「真実の重み」に大きな格差があることを考えないわけにはいかない。それは、シルバー・バーチがどのような霊であるかを知れば、当然のこととも思えるのだが、シルバー・バーチのことばの前では、この世の多くの覚者、賢人のことばも、影が薄いとさえ感じられてならないのである。
しかし、ここで、シルバー・バーチがどのような霊であるかを、改めて詮索する必要はないであろう。シルバー・バーチ自身も、かつて、地上時代での身元を訊かれて、「私は荒野に呼ばわる声です。神の使徒以外の何者でもありません。私が誰であるかということが一体何の意味があるのでしょう。私がどの程度の霊であるかは私のやっていることで判断していただきたい。私の言葉が、私の誠意が、私の判断が、要するにあなたがた人間世界における私の仕事が暗闇に迷える人々の心の灯となり慰めとなったら、それだけで私はしあわせなのです」と答えている。シルバー・バーチのいうように、大切なことは、彼自身の誠意であり、ことばであろう。その彼自身のことばを、私たちは、いまも原文の英語で、一字一句、少しも憶測や誤差のない形で、読んでいくことができる。
「文は人なり」というが、私たちは、シルバー・バーチの語ったことばを、それを忠実に再現した文章によって、シルバー・バーチが誰であるかを知り、そのことばの真実性にこころを打たれる。ある読者は、シルバー・バーチの文章について、「文章の世界にシルバーバーチの言葉に匹敵するものを私は知りません。眼識ある読者ならばそのインスピレーションが間違いなく高い神霊界を始源としていることを認めます。一見すると単純・素朴に思える言葉が時として途方もなく深遠なものを含んでいることがあります。その内部に秘められた意味に気づいて思わず立ち止まり、感嘆と感激に浸ることがあるのです」と述べているが、このような感嘆と感激を覚えるものは、無論、この読者一人ではない。このシルバー・バーチのことばの真実性と重大さは、読めばわかるのである。
私たちは、お経をよむときに、よく、「人身受け難し、いますでに受く。仏法聞き難し、いますでに聞く」というように、礼讃文を唱える。そして、「無上甚深微妙の法は、百千万劫にも遭遇うこと難し」とも続ける。「百千万劫」の「劫」とは、古代インドにおける最長の時間の単位で、たとえば、巨大な岩山を薄い白布で百年に一度さっと払う。それを続けて大岩石がすっかりなくなってしまうまでの時間が一劫である。それが、さらに百千万回も繰り返されるような、殆ど無限永久の時間がかかっても、なかなか聞くことができないのが、「無上甚深微妙の法」である。ところが、それを礼讃文では、「我今見聞し受持することを得たり」と唱えるのである。これは、私には、わかりにくい。
私自身は、例えば、「般若心経」を、何百回、何千回もとなえてきたが、いまだによくわからない。「何百回、何千回ととなえてやっとわかった」といって、「般若心経」を和訳した作家もいるが、そのような和訳を読んでも理解できない。救われる思いをすることはない。だいたい、お経そのものは釈尊が書いたものではないし、すべて釈尊のいったことばのまた聞きである。しかもまた聞きしたものの漢訳である。それを日本語でいわば「棒読み」しているのである。おそらく「よくわからない」のは私だけではないであろう。そのお経が、いくら「無上甚深微妙の法」であると聞かされても、私のような者にはその有難さが実感できるはずもない。しかし、シルバー・バーチのことばは違う。その有難さは、私にも身に染みてわかるのである。私にとっては、シルバー・バーチのことばこそが、「無上甚深微妙の法」といってよい。このホームページでも、繰り返してこれからも、学んでいかなければならないと思っている所以である。
(2010.01.01)
|
